2011年05月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
今は亡きジャーナリスト筑紫哲也を思う
阪神大震災のとき、私は相模原の工房で仕事をしていた。1月の震災以来、工房の行き帰りで震災の被害、とくに死亡者の数字を毎日更新をしていた。 連日、被害の拡大や亡くなられた方々の数字をことさら報道する、マスコミのありようを、当時TBSのニュースキャスターだった筑紫哲也は、そんなことでいいのかと、テレビの前で問いかけていた。 ジャーナリズムが持つ役割は、もっと違ったところにあるのではないかという、メッセージだったように思う。もし、彼が今生きていれば、この大震災にどういう切り口で立ち向かっただろうかと思う。 大手の報道機関が、現地に行かず報道していることや、来るまで行けないところは取材の対象にしていないなど、聞き及ぶが、現地に立たずに何が分かるのだろうかと思う。 おそらく、筑紫哲也は現地で取材しただろうし、東電、政府、御用学者のもたれあいを厳しく批判したのではないかと、思う。 人はその人ごとに、やれることがあると思う。とても長い支援と、長期にわたって関心を切らさないことが、大事だと思う。その意味で筑紫哲也をとりわけ思うのだ。
2011.05.29
コメント(0)
-
選べない時
阪神大震災の時は、和歌山に帰省するコースで阪神高速のルートを、間違えて西宮まで行き、行き過ぎに気がついて、いったん降りて、乗りなおした。 だから、1月にこの震災が起きた時、高速道路がテレビに映し出された時、「あそこだ!!」と分かった。 昨年は夏に福島の家内の実家に帰省する時、常磐道から東北道を通って行ったのだが、今回の震災の被害があったところのそばを通っていったのだと、実感した。 何か不可思議な縁を感じてしまう。結果が分かれば、あの時と思うが、事前に知ることはできない。自分に何ができるだろうかと考えることが多い。来月、被災された方々に陶器の器を持っていく友人の手伝いで福島に行くことになった。少しは役に立てるだろうか。
2011.05.24
コメント(0)
-

ローテーブルの仕様
このローテーブルは車の整備をしている、工場の事務所に置かれています。金属の椅子が置かれているのだが、今4脚製作中でいずれ、お目にかけることができると思います。 テーブルは幅が450mm、長さが1000mm、厚みは35mm。樹種はビャクシンを使っている。ヒノキ科ビャクシン属、香木でとてもいい香りがする。1枚板を使っていて、木味が面白い。木肌はこんな濃い色を、している。 足もとはタモを使っている。ここに4人の方が座ることもあると、考えて支柱はあえて下のほうは、中のほうに入れるデザインにした。こういう形で組むには、それぞれ型板を作り、ホゾ穴を斜めに開けるためには治具が必要だった。できてしまうと何てことなく、できているようだが、ここまでの形にするには、いろいろな工夫が必要だった。 まあ、それが面白いんですけどね。
2011.05.23
コメント(0)
-

ローテーブルを納品してきました
今日、かねて、ご依頼いただいていたお客様のところへ、ローテーブルを納品してきました。アームチェアー4脚とのセットなのだが、まずテーブルをというところです。 自分の工房はそう広くないので、なかなかいいポジションで撮影できなかったのですが、今日は心置きなく撮影。 どうでしょうか?、この位置からだと分かりにくいのですが、甲板の下には1本太い受けを通していて、そこに2本横にすり桟を組んでいる。 直線で組んでいるところは、ほとんどないという、ちょっと手がこんだ作りになっている。家具そのものは大きくはないのだが、おおらかさと生命感を出したいと考えて製作をしました。 さてさて、早く椅子を作りあげねば!!
2011.05.21
コメント(0)
-
バッテン
今、原発事故のことで、技術者とはということに関心があって、柳田邦男さんが書かれた「零式戦闘機」を読んでいる。 そのなかに、機体のラインをひくのに「バッテン」という檜の角材を、使ったという記述がある。製図で曲線を描くとき、雲形定規というのをつかうこともあるが、飛行機のラインをひくのには、この「バッテン」でなくてはならないとある。 実は、私も家具の椅子やテーブルのラインをひくとき、檜の角材を使っている。これは以前お世話になった方から、船の設計をするとき、このバッテンを使ってラインをひくと教えられてから、使うようになった。 このしなりが流麗なラインを、示すことができるというわけだ。 今は、パソコンのキャドなどを使って、いとも簡単に曲線がひけるのだろうが、私はこのバッテンを使って、鉛筆でラインをひくことが好きだし、自分のなかに、しっかりとした形を記憶することができる。 やはり、消しゴムで消したり、なんども描くことで、納得できる形ができるように思う。
2011.05.18
コメント(0)
-

ローテーブル調整完了
いよいよローテーブルが完成間じかになってきた。この画像は携帯で撮ったので、ちよいとうまくないが、甲板の調整、脚の調整、そして、組み付けまで完了した。 残るは塗装だけ、土曜日に納品予定。お客様から納得するまでやってといわれて、ほぼ1年が過ぎた。これだけ待ってくれるお客様はそうはいない。 以前やはり、急がなくていいよといわれて、のんびりやっていたら、私が生きているうちにやってねと言われてあせって作り納品したことがあるが、それ以来である。 この後は、椅子を4脚、今までのデザインでなく、このローテーブル用に新しくデザインしたもの。このオーダーが済めば今のところ、注文はない。今は安いことに価値がある世の中なので、そう多くは望めないなあと覚悟している。 でも作るのは大好きなので、今後はクラフトフェアにむけて、新作を作るつもり。
2011.05.17
コメント(0)
-
政治家は小粒になったか
司馬遼太郎氏著作の「坂の上の雲」に明治に海軍を創設した山本権兵衛のことが、でている。 まだ40代という若さで海軍を設計し、実行したが、その影には西郷従道という後ろ盾がいて、はじめて可能になったという。実施にあたっては山本に一切をまかせ、最後の責任は西郷がとるという形であったという。 しかるに、今この大震災の復興、原発事故の対応、そういう体制がとられているか、とられていないと思う。 人が動くことが容易にできる体制がとれないでいる。明治の頃と比べて生活も多様化し、シンプルでなくなっていることもあるだろう。外国との関係も複雑多岐になっている。 でも、この状況を打開できるのは今生きているわたし達しか、いない。その意味において、政治家・官僚は、現地を見るべきでしょうし、単に見るだけでなく、そこで働くことをする政治家・官僚もいていいと思う。 もちろん、本人は動かないで大局をみながらマネージメントをする役割の人がいなくてはならない。後世になって評価される政治家は現れるのだろうか。 納豆は小粒がいいが、政治家は大きいひとがいいなああ~
2011.05.15
コメント(0)
-
映画「オーケストラ」
つたやで映画「オーケストラ」のソフトを借りてきて,鑑賞する。 ソ連のブレジネフ政権下でボリショイのオーケストラの指揮者をしていたが、ユダヤ人の楽団員をかばった罪で、その地位を奪われた主人公が、パリのある劇場から自分が掃除夫として勤務している楽団にオファーがあったことから、この物語は始まる。 30年、指揮者としての地位を奪われ、アルコール依存症になり、鬱屈した人生を変えたいと思ったことから、元の楽団員に呼びかけ、衣装や楽器やそろえ、そこは映画なので、そうまくいくのかなという展開もあるのだが、ユダヤ人の商い上手のエピソードもまじえながら、話は進んでいく。 主人公の再生と、もう一方で追放され収容所で悲惨な最期をむかえたユダヤ人音楽家夫婦の忘れ形見が主人公と出会うことから、自分の人生を取り戻すストーリーも合わさっていくことで、より物語が深みを増している。 いよいよパリの劇場での演奏会が始まったが、まったくリハーサルなしの演奏なものだから、はじめは観客から失笑がもれるほどのできだったのが、演奏するにつれ息があってきて、中盤からは人をひきつけていく。 演奏が終わると、総立ちのアンコール。映画と分かっていてもジンとする。 自分がやりたいことは、いくつになってもあきらめちゃいかんということですかね。
2011.05.14
コメント(0)
-
食中毒ユッケと赤信号
一見何の関係もない関係にみえるかな。 しかし、ルールを守るということでは同じことだ。私は焼肉やさんには、かつて友人が行くのでついて何度か行ったことはあるが、家族で焼肉やさんにいったことはないので、最近の様子は知らない 肉を生で食べたいとは思わないが、店で出しているメニューであれば、誰も食中毒になるとは思わないだろう。生で出す場合はトリミングというのを施すのがルールだという。 横断歩道も赤は渡らないというのがルール。しかし、朝早く通勤のために駅にいくと、駅近かのところではまず赤で待つ人はいない。 が、わたしは渡らない。何故ならルールだから。これを守らない人は、車で走行するとき、やはり信号を守らないと私は思っている。 その傾向が交通事故につながると思う。今のご時世、そうしたルールを守るという暗黙の了解が希薄になってしまっていることで、こわいことになっているように思う。
2011.05.13
コメント(0)
-
幕藩体制のほうが良かったかも
江戸末期、黒船の日本襲来で坂本竜馬らの活動で、外国に負けないように、日本を近代国家にするべく幕藩体制をやめて中央集権国家に衣替えをして、地方の力をそぐ方向に舵を切ったように思う。 その結果はどうか、自治という部分では、およそかつての力は無くなってしまったように見える。 今回の大震災でも、中央でリードしようとしているが、実情の把握、今後の見通し、いずれをとっても後手に回っている。 幕藩体制のときなら、フットワークももっと違うかも、と考えるのは私だけかな。
2011.05.12
コメント(0)
-
救命胴衣はどうかな
震災以来、いろんなことを考えている。今回の震災では地震そのものよりも、津波で命を落とされた方が多い。確か、愛知のほうだったかと思うが、輪中というのがあって、水害の多い地域で、そのときのために家の軒下に船を装備している地域があったと思う。 だから、津波の多い地域では救命胴衣を標準装備として確保したらどうだろうか。少し調べてみたが、時間の経過で繊維が劣化するようなので、何年かおきに更新していくようにしたらいいと思う。 また、救命胴衣をしていて、落命されるのは低体温での衰弱によるそうだ。でも溺死からは免れるようなので、津波と聞いたらすぐ救命胴衣を着る!! 震災のことを今後どうしたらいいのか、私なりにいろいろ考えてみている。
2011.05.11
コメント(0)
-
もったいない!!
今日、玄米の精米にいきつけのコイン精米に行ってきた。なんと、床に精米が終わった白米がそうねえ~2合くらいかな、ぶちまけられていた。 シチューエーションとして、考えられることは精米が終わったあと、袋にいれるのだが、口にきちんとあてられていなかった。 その袋に穴があいていた。 まあいろいろ推定はできるが、しかし、もったいない。家じゃあ、ご飯を食べるとき、一粒でも残さぬよう子供たちに言い聞かせて食べていたので、今では私のほうが、注意されるぐらいになっている。 「ご飯を残すと、目がつぶれるよ!」 震災にあわれた方々を思えば、実にもったいない。いつか自分もその境遇になるかもしれないんだもの。心がけが大事だと思うね。
2011.05.09
コメント(0)
-

人は時代を選べないなあ
5月の連休で、家内の実家に行き、いつも庭先から見える吾妻小富士を撮影。いつもはこのきれいな山を見ると、福島に来たなあと感じるひと時だったが、今年は3・11があったので、格別の想いがある。 実家も壁に割れがあったり、して震災とは無縁ではなかった。周りをみると、屋根の瓦が落ちた家が結構ある。 ホームセンターに充填用のパテを買いに行ったが、ホームセンターそのものも壁が一部落ちたり、電灯が落ちたりと被害を受けていた。 放射能の計測値が毎日報道されているせいか、いつもより人出が少ないように感じた。 自分が生きている時代にこんな大きな震災に遭遇するとは・・・・ 亡くなられた人に哀悼の意を表すとともに、生きている人間はその命を大事にしないといけないと改めて思う。
2011.05.08
コメント(0)
-

木工三昧-2
オーダーいただいているローテーブルの仕上げの追い込み。木端・木口の鉋かけ、サンディング、甲板の鉋かけなど素地調整をする。 脚はタモ、甲板はビャクシンを使っている。ビャクシンは入り皮があったり、木目がねじれていて鉋をかけるのも難しい。西岡常一さんの本を読んだとき、その木のもつ様子を活かすことが大事とあった。ただただきれいにするだけでは駄目で、その魅力を見つけること。 一部えぐれているところがあるが、そこは埋め木をしないであえてそのままにしたがお客様はなんと仰るだろうか。 明日、塗装の前段階まで仕上げる予定。妥協しないで今自分でできることをきちんとするつもり。
2011.05.07
コメント(0)
-
what's JAZZ
今日は、知人の方からお誘いを受けてジャズの演奏会に行ってきました。ジャズへの招待 vol.21懐かしのスイング・ジャズ特集演奏者はクラリネット清水万紀夫 ピアノ神村晃司 ベース秋元公彰 ドラムス奥田”スインギー英人。曲目はスターダスト、あなたの思い出、特別急行便、私の青空など、最後にグッバイ、気がきいてるよね。大学時代にジャズが好きな友人がいて、よくレコードで聞かせてもらっていたが、自分は貧乏暇なしでレコードも買えず、せいぜいラジオで聞くぐらいであったが、今日はよかった。生で演奏を聴いたのは初めて、心地よくいい時間を過ごせた。今度は9月に演奏会があるとのこと、またぜひ行きたいと思う。 こんなゆとりのある日を持つこともいいもんだね。
2011.05.06
コメント(0)
-
判断力
今、古書店で購入した新書で「判断力」という本を読んでいる。戦後、日本は政・官・財の鉄のトライアングルでやってきたと書かれている。そして、お互いにもたれあって何かあってもお互いに責任をとるということをせずにやってきた。バブルがはじけて銀行が大量に不良債権を抱えたときも、私たちの税金である国費を投入して生き延びさせた。 この時の政治家が責任をとりますという言い方をしていない。また、郵政民営化で日本の隅々までサービスはやりますといいながら、実は閉鎖された郵便局もあると聞く。 このことで、当時の担当大臣が責任をとるということは一切言っていない。 このもたれあいが、戦後の高度経済成長を支えてきたともいえるらしいが、このたびの東北大震災では、人災の色が極めて強くお互いにもたれあって、逃げることはできないだろう。東電の社長が謝罪行脚をされているが、本来ならば政・官も同行して謝罪するべきだろうと思う。 原発で電気関係がすべてアウトになった時、的確な判断力をもっていれば、ここまで事態を悪くすることはなかったのではないか。この事態を考えることはあってはならないことと、逃げていたからではないかと、思えるのだが。
2011.05.05
コメント(0)
-
福島の春、梨の花
吾妻山の麓にかみさんの実家がある。周りには梨や桃、りんごの果樹園が多い。 今は桃や梨の花が満開。時がたてば農家の方のご苦労があって立派な果物ができることだろう。 この果物が原発事故の風評被害で食べられないなんてことがないように、切に願う。
2011.05.04
コメント(0)
-
東北道を走る
3日、朝7時から中央道国立府中インターから入り、ほぼ12時間かかって福島市のかみさんの実家に到着。 東北道のあちこちに大震災の傷あとがまだ残っていた。多くの段差を修復したあとや、ひび割れ、道路と外界との仕切り壁もいくつか落下したままのところもあった。 よくこんな短期間で使えるようにされたと思う。道がつながらないと、復興は始まらない。
2011.05.03
コメント(0)
-
葛尾村からのはがき
葛尾村で工房を主宰されている友人の木工作家さんに葉書を出した。 原発事故をうけて政府が決めた計画避難によって6月までには避難という報道を見たので、どういう対応をされるにせよ、退避しなければいけないということならば私に何かお手伝いできることがあればと思い、葉書を出したのだが、郵便事業株式会社より下のような付箋がついて戻ってきた。 『福島原子力発電所の事故に伴い、配達先の地域に避難指示等が発令され、または、受取人様の現在の避難先が不明であること等により、お届けすることができませんでしたので、お返しします。大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いもうしあげます。』 6月ならばまだ時間の余裕があるので、友人に届くかと思っていたのだが、せんないことであった。 事態はそこまで切迫しているのだと改めて認識をした。
2011.05.02
コメント(0)
-
私が子供頃の電力事情
私が子供頃、そう昭和30年代。その頃はテレビはなく、ラジオでそれもずっとつけていたわけではなく、大相撲の番組を聴いていたくらいかな。照明は裸電球、それもそんなに明るくなかった。 台所ではコンロは朝顔形のプロパンガスコンロ、冷蔵庫はなかった。釜もなくて鍋でご飯を炊いていたと思う。電気釜が家にきたのは30年代後半。借りていた家には井戸があって美味しい水だった。そこで冷やしたスイカは美味しかったなあ。 もちろんエアコンもない。これは今でも我が家では使ってはいないが。風呂は薪でわかしていたし。考えれば本当に電気の力を使っていなかったように思う。 あるときから、それは多分高度経済成長と関係があると思うが、国民が電気を大量に使う生活にシフトする方向を国が目指したからだと思う。 生活の質をどうするかはそれぞれの人にまかされている。それを選択するのは自分自身だと思うよね。
2011.05.01
コメント(0)
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
-
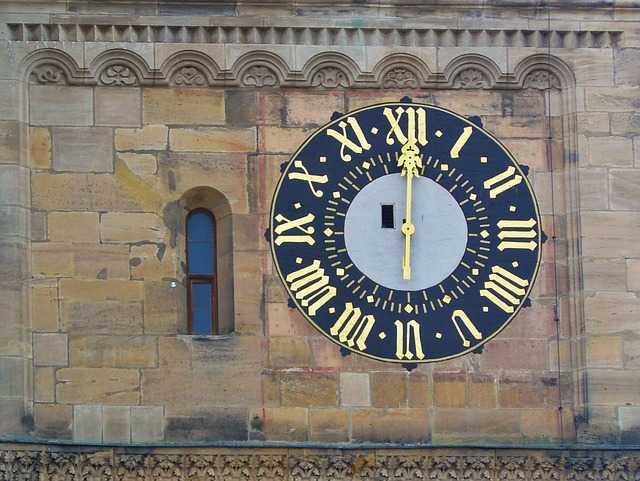
- 風水について
- フライングスター(玄空飛星派)風水…
- (2025-11-10 18:05:38)
-
-
-

- コストコ行こうよ~♪
- コストコで初購入品のレポと無料のも…
- (2025-11-10 08:40:41)
-
-
-

- ☆手作り大好きさん☆
- 12月6日経堂コルティにてワークシ…
- (2025-11-16 17:15:55)
-







