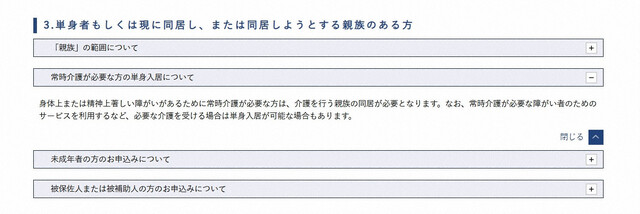2016年05月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
神慮に依る「野辺地ものがたり」
第 六十一 回 目 よく飽きもせずに、同じようなドラマを作って放送する方も、放送する方だが毎週、頼まれもしないのに、決まって同じ時間に、同じ所にチャンネルを回す女共にも呆れてしまう―― そんな事をぼんやりと考えながら、新婚以来使っている古ぼけたダブルベッドに潜り込んで、枕元のスタンドのスイッチを切ったが、時間が早いせいか直ぐには眠れそうになかった。 暫くすると、春美が寝室に上がってきた。灯りを点けて、彼がまだ寝込んでいないことを確認すると、再び階下に降りると、冷やしたワインとグラスをお盆に乗せて戻ってきた。時によって、ウイスキーだったり、日本酒だったり、種類は変化するがこうして妻が寝室にアルコールを持ち込む時には、彼は素直に、彼女の欲求に応じなければならない。知らず知らずのうちに出来上がってしまった、習慣の様になっていた…、彼は若い頃、自分の性欲が人一倍強いのではないかと、悩んだ時期がある。が、春美と結婚してみて、むしろ弱い方の部類に属するらしいことを、知らされて、愕然としたものだった。特に、四十を過ぎてからは、月に数回の夫婦の営みが、億劫にさえ感じられてならなかった。たまに彼が積極的になった時でも、三十七歳にもなって未だに少女趣味の残っている春美に、やれムードの愛情のと、変にベタベタと甘えられたりしているうちに大抵、げんなりと元気が失せてしまうのだった。 水曜日の朝は、職員会議がある日なので、普段より数台早いバスに乗る。今朝も私鉄の駅前でバスに乗り込むと、どうした理由か、いつもより却って混雑している。 奥の方に滑り込み、つり革に手を掛けようとして、ひょいと見ると、前の席に佐々木法子の顔があった。少女は教頭の姿を認めると、席を譲ろうと腰を上げかけた。彼は慌てて、その儘座っているようにと手で制し、素早くカバンから朝刊を取り出して熱心に読むふりを装った。胸元が、息苦しくなるほど鼓動が速まり、動悸が高鳴っている。―― 活字が少しも眼に入らなかった。そっと、相手に知られない様に新聞の隅から窺うと、少女は膝の上に両手をきちんと重ねて、両目を閉じていた。彼はややホッとして、少し大胆に少女の顔を見詰めたが、少女がふいに眼を開いた時の用心に、新聞紙を目の前から離さないでおいた。今朝見る少女の顔は、別人の如くに美しかった。全体に瑞々しく、皮膚に張りが感じられた――、紅を薄くさしたように、微かに赧らんだ頬。唇にも、鮮やかなピンクの明かりが遠慮がちに点っている…、自分は痴漢かも知れない、そんな考えが彼の脳裏に閃いた。正確には、視姦と呼ぶのかもしれないが、何も知らない清純無垢な少女の顔を、不潔な中年男の舐めるような視線が、事実上穢しているわけで、胸元や臀部などに自分の手などを接触させる痴漢の行為と、質的な違いは、そうないのであるから…、ただ、相手がこちらの行為に気づいていないだけの、違いしかないのだ。そう思うと、全身に鳥肌が立つような何かしらおぞましい自己嫌悪が、彼の心を暗くした……。 いつものように、これといった議題のない職員会議は、形式的な顔合わせで、短時間に終わった。会議の後で、一年B組のクラス担任である尾崎先生が、眞木のデスクにやって来た。そして、放課後に少し、折り入って御相談したいことがあると、何か神妙な表情で、教頭の耳元に囁いた。快活で、普段は冗談ばかり飛ばしては、同僚の女教師たちを面白がらせている、この若くハンサムな英語教師が、彼は特別に嫌いであった。生徒たちの間で異常な人気を博しているイケメンでスマートな尾崎が、軽佻浮薄な若い世代の典型のように、感じられてならなかったから。 尾崎の持ち込んだ相談というのは、予想外にも、重大で、面倒な問題を孕んでいるのを知った眞木は、緊張した場合の癖である、瞬きを何度も繰り返しながら、天井を見上げた。事は、あの佐々木法子に関するものであったのだ。尾崎の説明によると、佐々木法子の家庭環境が特別に複雑であることは、小学校からの申し送り書類の注意事項にも記載があった程で、かねてから注意をしていたのであるが、今度の夏休み中に、法子がちょっとした問題を起こした。とは言っても先週に最寄りの警察署に出向いて、分かった範囲では、現在のところ、法子自身が直接に犯罪を行うまでには至っていない。しかしながら、これまでの状況から判断すると、法子の置かれている立場は極めて微妙なものと言え、非行に走るのは時間の問題といった、際どい瀬戸際まで来ていることは、殆んど間違いないらしいのである。そして、その犯罪というのが、新聞や週刊誌などがことさらセンセーショナルに取り上げて、今好奇の的になっている売春行為なのだという。 法子の母親というのが、非常に男出入りの激しい女性で、現在小さな質屋の後妻に納まっているがとかくの噂が絶えない。つい最近も、万引きと主婦売春の嫌疑を受け、警察の取り調べを受けている。そして肝心の法子の方だが、近くにある私立の某女子高の生徒たちが、この夏休みに集団で売春行為を働いた事件を捜査していた警察が、その高校生の一人A子と親しく交際している佐々木法子の存在に目をつけたのである。本人は大変真面目そうで、おとなしい中学一年生の少女であるが、得てしてまさかと思われるこうした子供が、吃驚する様な変わり方を見せるのが、この年頃であることを、職務の経験上で熟知しているベテラン巡査は、法子の母親がブラックリストに載っている人物であることを思い合わせて、学校の担任である尾崎に連絡してきたのだと言う。同じクラスの生徒たちの中にも佐々木法子に関して、良からぬ噂を口にする者も現れ始めた現在、一応校内風紀の責任者である教頭先生の、お耳にお入れしておいたほうがよいのではないかと、判断したのだと、尾崎は付け加えた。 ――― 酔いが廻るにつれて、右兵衛の尉・源 正忠の毒舌は、辛辣さの度を増していた。頬と言わず顋と言わず、青々とした剛毛の密生した顔が、赤鬼の如くに上気して、テラテラと気味の悪い光を発している……。
2016年05月28日
コメント(0)
-
神慮に依る「野辺地ものがたり」
第 六十 回 目 義清はその築地塀に沿って進み、指定された門の脇で待った。程なく、内側から木戸を揺り動かす音がして、脂燭を手にした年嵩の女房が、姿を現した。女房は無言のまま義清を門内に招じ入れると、そのまま先に立って歩き出した。長く仄暗い回廊をいくつか過ぎて、白い絹の帳を幾重にも垂れ込めた部屋に至った。 そこで暫く待つように言い残すと、老女はいずくへともなく、融けるように姿を消していた。広々とした部屋には、幽かに、若者の魂を痺れさすような、得も言われぬ名香の匂いが何処からともなく漂い流れている。張り詰めた若者の神経に、その微かな香りがまるで強い酒精のごとくに作用した。 その時、薄明の光を遮って近づく、人の気配が感じられた。反射的に、義清は居住まいを正していた。見ると、藤色の衣に身を包んだ上臈が、一間ばかり隔たった所に、物の怪のように、音もなく座っている。驚いたことには、綾目も定かに弁じ得ない室内の明るさとは言え、人影は素面のままで、じっと北面の武士義清に相対し、恥じ臆する気配は更になく、一種不気味に若者の面を見据えているばかりなのである。先ほどのとは又別種の、麗妙な薫物の余香が、義清の鼻先に達している。吸う息と共に、その微かな香りを身内に感じたとき義清は、不思議と肝が座り、不敵なまでの落ち着きを取り戻していた。この匂いにはどこかで出会ったことのあるような気が、ふっとして、急いで記憶の糸を手繰ってみたが思い出せなかった。ひょっとしたら、思い違いかも知れないとも思った。 「そなたの和歌を、兄上が大層褒めておりました。また、蹴鞠の上手でもあるそうな…。珍しいことに院までが、大層、関心を示しておられる」 静かな、温かみのある、それでいて、犯し難い威厳のある声が、そう言った。声の主は待賢門院・藤原璋子。鳥羽上皇の中宮であり、義清のご主人実能の妹御でもある、高貴な女性だった。身分の卑しい義清ごときが、望んでも決して謦咳に接することなど叶わない、文字通りの 雲の上人 である。― その途轍もなく高貴な地位にある女性が、何故にこのように、奇っ怪千万な仕方で、下北面の武者ごときに対面しているのであろうか……、…自分は生命を失うな、忽ち確信に似た戦慄が義清の脳天を、貫いている。 義清は、再び激しく動揺する己の心を、懸命に抑え、必死の形相で相手を見た。 待賢門院は依然として身じろぎもせず、義清を見据えたまま、どうやら穏やかに数珠を爪繰っている様子だ。漸く、周囲の弱々しい、夢の様な薄明かりに慣れた義清の眼に、豊満なつぶつぶとした肌の美しさと、神々しい顔立ちの、実に溢れるような魅力に満ち満ちた特徴が、仔細に見て取れる。袖の下から僅かに見え隠れする、月光の如くに輝かしいお手の様子も、この若者の初心な心を妖しく幻惑するかのように、闇の中に浮き出している。 「妾(わらわ)を淫らな女性(にょしょう)と称し、噂する者が居ります…、そなたの眼にどのように映じますか?」 義清は我が耳を疑った、これは、夢に相違ない。或いは、あの鬱蒼たる森の漆黒の闇の中で、性悪な、女狐めに誑かされ、赤子の如くに愚弄されているのに、相違なかった…。このような馬鹿馬鹿しい事が、現実に起こり得ようとは、到底信じがたかったから。 信心深い彼の母親は、幼い義清に信仰心の何よりも大切なことを、繰り返し説いた。この玄妙な天地に満ちている神仏の霊妙な力に対する信仰と、我が身に、尊い血潮を衛り伝えた祖先の御霊(みたま)に対する、篤い崇敬の念こそ、人として生きる上での要諦であると、教え諭したのである。殊に、武人として、或いは、天下の政に参与する力を握った者が、敬虔な真心を失ったとき、どのような恐ろしい事になるかを、ひとつひとつ具体的な例を牽いて、説明した。血なまぐさい怨霊、身の毛もよだつ、物の怪、不吉な化物の類……、しかしながら、これは、眼前の出来事は、紛れもなく現の事態であった。義清にとって、触れることはもちろん、見ることも不可能な、女神にも等しい存在であるこの高貴な女性は、自分のような者に、何を望み、何事を期待しているのであろう―――若者は、全く相手の意図を測り兼ねて苦慮した。彼の全身には既に、おびただしい量の汗が噴き出していた。 「近くには誰も居らぬ、そなたと妾の、ふたりきりであるぞ、義清」―― 相変わらずゆったりとした静かな声音である。しかし、強く、誘い込むような、また、絡め取るような不思議な牽引力が籠っている。そこには生身の女の、熱い吐息が、生臭い媚態が、明らかに感じ取れる…突然、義清の躯が瘧に罹った者の如く、わなわなと震えだしていた。須臾にして、若者の身体が前に崩れた。 明日が水曜日だった事を思い出した眞木は、読んでいた本を閉じた。冷蔵庫の冷たい水を飲んでから寝ようと、階下に通じる梯子を降りた。居間では、勝手仕事を終えた妻が、子供達と一緒にテレビ番組を見ている。また、下らない恋愛ドラマか何かなのだろうが、三人とも一様に、喰い入るような目差しをブラウン管に注いでいた。
2016年05月23日
コメント(0)
-
神慮に依る「野辺地ものがたり」
第 五十九 回 目 彼が返答に窮していると、和恵がまた喋りだした。悪い男の、大人の人の言う通りにする事だって、お姉ちゃん言っていたけど、本当にお金を沢山呉れるのなら、言う通りにしてもいいな、あたし。ケロッとしてそう言う我が子の横顔を、父親は何か恐ろしい生物を眺めるように、見た。この娘は、どこまで分かっているのであろうか? 「バカ者!」、思わず眞木保臣が大きな声を出すと、次女はペロリと、長い舌を出しながら首を竦めた。 ― 彼は考える。あの我が家の、半分大人で、半分は子供の、小学生の娘達に較べてさえ佐々木法子は幼く、未成熟な印象を受ける。それは彼が娘達の恐るべき言動と、旺盛な肉体的成長とを身近に感じすぎているあまり、少々公平さを欠いた比較を、両者の上に施しているためであろうか…。そして、我が子を厭う反動として二人とは対蹠的な持ち味の少女を好ましく思い、必要以上の興味と関心を唆られるのであろうか?確かに、そのような心理的な傾斜が、彼の心の中に在る事は事実だがそれにしても、そればかりとは言い切れない、漠とした何かが残る。 若い時分から眞木は、自分自身を 好色 だと思っている。少し下品で、安っぽい香水のような色気をプンプンさせている様な、淫らな感じの女の方が彼の嗜好に合い、何より気が楽であった。文学などという歯の浮くような絵空事を、むしろ嫌悪していたので、甘美で、美しい恋愛などと呼ばれるものが、皆嘘っぱちであり、プラトニック・ラヴに至っては狂人の夢であると、断じていた。そうした彼が、現在の妻・春美と他人から一応「熱烈な恋愛結婚」と言われる結びつきをしたのは、矛盾であろうか。しかしそれは矛盾でも何でもなかった。あまり頭が良くない娘であった春美が、秀才で通っていた保臣青年に一方的に熱をあげ、のぼせただけの話だったから。交際期間が多少長く続いたのも、二人の恋が熱烈だったからでは決してなく、それだけ彼の逡巡が強かったからに過ぎない。もっと親に財産があり、もっと美人で才媛の女性で彼の性的な好みに合った娘が、自分を愛し、交際を求めてくるのではないかと、今にして思えば、実に儚い望みを、容易には捨てきれない時間の長さを、意味していただけなのだ。 したがって二人の婚姻も、ありきたりの打算と、常識的な諦めが上手く折り合いをつけた時点で発生した、極めて平凡な結婚なのである。それでも結構うまく暮らして来れたのであるから、また、平凡に生きて、常識的に行動し、常に大勢順応で押し通しその結果として、とにかく教頭にまでなれたのだから、妻を愛し、二人の子供を無事に育てているわけだから、現在只今の境遇に感謝の念こそ抱け、不満や不足など、これっぽっちも無い筈あった。もしかしたら自分は、身体が衰え始めた如くに、精神的にも老化現象をきたし神経の一部に、変調が起こっているのかしらん―。第一、ついぞ読みつけない小説などに興味を唆られた事自体、おかしいと言えばかなり可笑しなことであった。 ーーー五月闇というのであろうか、どことなく物悩ましく、甘美な夜が、義清の辿る雨上がりの森の中の、小径を埋めていた。松明を灯すことは禁じられていた。仕方なく馬を降りて、ほのかな星あかりだけを頼りに、二三度通い覚えた径を行く。周囲は何か厳粛な静寂が支配している如くに感じられる。稍あって、見覚えのある築地の影が眼前に浮かび出た。
2016年05月20日
コメント(0)
-
神慮に依る「野辺地ものがたり」
第 五十八 回 目 その日の彼の最後の授業科目は「道徳」であった。いつものように生徒一人を立たせて教科書を音読させ、自分は机の間を縫って、ゆっくりと歩き回っていた。ふと、何気なく眼を遣ると、窓際の前の方に席を占めている法子が、ぼんやりと校庭を眺めている姿が映った。斜め後ろから見るので表情はよく掴めないが、物思いに耽るような風に、軽く左肘を机の上に置いて頬杖をついている。 近づいて行くと、眞木の視線を感じてか、切れ長の瞳を急に彼の方に向けた。一瞬、二人の視線が合ったが、先に眼を逸らしたのは眞木の方であった。― どことなく愁いを含んだ、無表情な白い顔に、ほんの瞬間ではあったが、ある光が走り反射的にやや大きく見開かれた眼球の、白眼の部分が深い海を思わせる紺碧のヴェールで覆われているのが、強い残像となって彼の網膜に灼きついていた。ただそれだけのことであったが、謹厳な教頭の胸は早鐘のごとくに高鳴り、妖しく騒いでいたのだ。この教室で初めて少女の姿を目にした時から、不思議な磁石の力で牽引されるような、何故ともなく気持ちが引き寄せられる、不思議の原因がこの時に理解できたような気持ちがした。しかし、後になって再度考え直して見た際にはその正体はどこかに雲散霧消していて、何が何やらさっぱり分からなくなっていた。狐につままれたとは、このような事を形容する言葉だと、実感させられる思いだった。 その時以来、眞木は週に一回佐々木法子のクラスに行くたびに、相手に悟られないように細心の注意を払いながら、少女の様々な表情と身体的な特徴に、観察の眼を向ける習慣が出来たのである。しかし、夏休みを中に挟んだ五ヶ月間に、眞木が主として教室で観察し得た結果を総合しても、法子にはこれといって際立った特徴は見いだせなかった。強いて挙げれば、極めて稀に少女の両眼が大きく見開かれる時に、二つの瞳に特徴的な青い曇りが見られること、肩まで伸びた長い髪を、何気なく掻き上げる折に覗く項の艶っぽさ、青白さ。紺色のスカートの下から見える筋肉質に固く締まった、形の良いふくら脛の雪を思わせる白さ。以上の三点ぐらいである。これらとて、決して人並み外れた美質とも思われなかった。むしろ、その他の点で佐々木法子は他の同年代の少女たちより劣っていることのほうが多かった。成績はせいぜいクラスの中の下くらいだし、何事にもせよ消極的なことは、殆んど無気力と呼んでよかった。そのような、いわば魅力の少ない少女に、何故こうまで心惹かれるのか?考えれば考えるほど判らなくなってしまう。 彼は月に一度か二度次女の和恵と一緒に風呂に入り、体を流してやることがある。長女の方も、去年まではそうしていたのだが、生理の始まっている今は、決して父親とは風呂に入らなかった。何時だったか、背中を洗ってやっていると、 「パパ、ばいしゅん って、なんのこと?」 和恵がいきなり訊いた。彼は一瞬、訊かれた言葉が何であるのか、理解できずに戸惑ったがそれが 売春 であることに気づくと、赤面した。照れ隠しに、誰がそんな事をお前に話したのかと質すと、八歳の和恵は平気な顔で「おねえちゃん」からだと答える。父親に背中を向けているので、彼の狼狽には無論気づいていないが、たとえ面と向かっていても親の思惑など一切頓着しないのが、和恵の特徴だった。適当に誤魔化そうと計ったが敵は執拗であって、なかなか矛先を緩めない。何でも、姉の悦子が友達から、自分たちの学校にも売春をしている生徒がいるとか、いないとか言う噂を聞き齧って来て、「あなたも、そんな悪の道に走ってはダメよ」と姉さんぶって諭したのだと言う。そう言って本人はあっけらかんとしているのだが、彼の方はすっかり仰天してしまった。教師などといってもだらしのないもので、おませな娘たちには日頃からほとほと手を焼いている。 八歳の子供に、一体どうやって売春の意味と、売春行為の反社会性を説明したらよいというのか…。それとも、こうして悲鳴を上げている彼の旧弊さ、時代遅れ、あるいは性に対する意識の低さ、並びに、古さがこの際責められるべきなのであろうか?
2016年05月16日
コメント(0)
-
神慮に依る「野辺地ものがたり」
第 五十七 回 目 当時、最流行の蹴鞠は名人と言われた母方の祖父から直々に手ほどきを受け、相当の腕前を既に有していたが、この頃から本腰を入れて学び始めている。 何事にも人並み勝れた才能を発揮する義清は、持ち前の体力と敏捷さとで群を抜き、この遊芸の道でも主人実能から認められ、一層愛されることになった。 殊に義清が一番心を入れて修練した和歌は、ついに天下第一の貴人鳥羽上皇のお目にとまる、栄誉に与かったのである。無論、年若い稀有の俊英を直属の臣下に持った大納言の自慢を兼ねた、上皇への推挙があったればこその結果ではあるが…。 程なく義清を下北面の武者として採用する旨の、命令が下った。義清本人の得意は天にも登らん程のものがあったが、ある意味では当人以上にそれを喜び、感涙に噎んだのは父親の康清であった。彼、康清が左兵衛の志に任官できたのは、二十歳も半ばを過ぎてからのことであった。長子のこの望外な出世を目の前にしては、無欲豪胆な、この無骨な武人も柄にない虚栄心と、儚い、将来に対する野望とを、たちまちに植えつけられてしまったようであった。 武蔵守・鎮守府将軍、俵の藤太秀郷の嫡流で、代々、武勇の誉ある家柄とは言い条その実は、今を時めく源平二氏に比しても力無き、二流の旧勢力にしか過ぎず権門と貴顕に仕え、惨めな番犬を勤める、卑しい身分でしかなかった。口にこそ出さねど、父祖以来の忍従の境涯に甘んじてきた左兵衛の尉・康清がその時ことのほかに輝かしいと感じられた長男の前途に、宗祖再来、名門復活の途方もない望みをかけたとして、それを誰が愚かと嗤い、身の程知らずと批判し去ることが出来ようか―。現に、義清自身が父が抱いた夢をその儘に、若々しく燃え立った胸に、抱懐していたのであった。自己の才能と器量とに強く頼むところのある、野心満々たる若者は、狂ったように駆け回る火の如き血潮の滾りを身内に感じ、気の遠くなるような神経の昂ぶりを、抑えることが出来なかった。 あれは五月の初旬であったから、梅雨にしてはちょっと早い長雨が、四五日も降り続いた後の、五月晴れと呼ぶにふさわしい快晴の日であった。 午前中は風もなく、ムシムシとした嫌な天気だったが、昼過ぎからは、さわやかな南寄りの風が新緑の梢を、幼子の掌のように閃かせて、教室の窓から流れ込んでいた。眞木康臣は佐々木法子のいる、一年B組の教壇に立っていた。
2016年05月14日
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1