2022年08月の記事
全36件 (36件中 1-36件目)
1
-

ベランダだより 2022年8月15日(月)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年8月15日(月)「朝顔日記」8月15日のアサガオ 今日は8月15日です。 「朝顔日記」をつけはじめて一か月たったのですが、なんと写真が2枚しかありません。どうしたのでしょうねえ。 身の回りはコロナの知らせが続いて落ち着きません。モスラ君の写真も撮り忘れています。まあ、ないものはしようがないので、今日はこれでお終いです。 しかし、まあ、シマクマ君の自己満足の日記ですから、これは、これで、記録ですね(笑)。ボタン押してね!
2022.08.31
コメント(0)
-
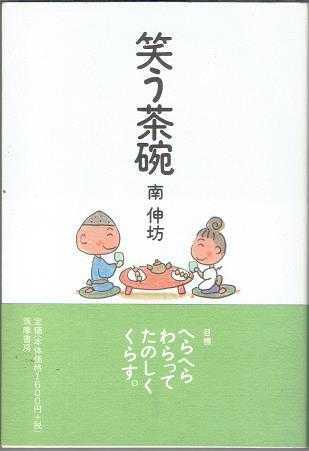
週刊 読書案内 南伸坊「笑う茶碗」(筑摩書房・ちくま文庫)
南伸坊「笑う茶碗」(筑摩書房・ちくま文庫) 単行本は2004年の新刊です。今ではちくま文庫になっています。著者の南伸坊は「ガロ」の編集長をしていたりした人で、路上観察とかハリガミ考現学とか、1980年代に才気あふれる活躍をした人です。 いろいろやっていらっしゃったことは、まあ、バカバカしいといえばバカバカしいのですが、面白いといえば面白いわけで、結構はまりました。なにが面白いと言って、まあ、イラストレイラーということもあるのでしょうね、しょっちゅうお目にかかるお顔には、才気とかいうような鋭いものはまったく感じないのですが、だれもがすぐ覚えるに違いないというようなところです。 1947年の生まれですから、2000年を超えたあたりから「老人」を標榜して、ネコに俳句を作らせたり、問題の顔を使っての「本人の問題」を追求するなど、徹底した遊び感覚の人です。 本書は「月刊日本橋」という、東京のタウン誌の連載です。はっきり言って、ちょっと時代とともに古びたようなところがあって大して面白くないのですが、ぼくのようなズレた人には受けるかもしれません。 いまどき、ケータイ いまどき、ケータイ電話を買ってしまった。つまり、いままでケータイ電話を持ってなかった。買わなかったのは、ケータイ電話に批判的だったからではない。目のカタキにしてたわけでも目くじらを立てていたわけでもない。 ようするに必要なかったのだ。たいがい事務所にいて、手許に電話が置いてあるし、外出先で電話の必要があるときは公衆電話からかければよかった。ただ、一度だけこんなことがあった。古河に蓮見に行った時だ。真夜中から明け方まで待機して、蓮の香りをかぐ。満喫して、さて、駅まで帰るタクシーを呼ぼう、というのでいつもそこから電話していた公園入口の電話BOXのところまでいくと、そのBOXがコツゼンと姿を消していたのだった。あれは何年前だったか? ともかくしかたがない。どこか赤電話のあるところを探そう(赤電話は実はとっくの昔からない。あるのは緑電話だが、近頃は緑電話とも言わないし、そもそもその緑もどんどんなくなっているのだった。)(P160) ケータイ電話が普及して、公衆電話が消えたのは90年代の事だと思いますが、実はボクは2020年まで、ケータイを持っていませんでした。 シンボーさんのように、タクシーを呼ばないと動きが取れないような場所に旅した経験も皆無ですし、外出中に誰かと電話で連絡を取る必要が、ほぼ皆無な生活でしたから、学生さんとかや、自分の若い家族たちが所持することは、トランシーバごっこの延長くらいにしか感じていませんでしたし、実は、今でも感じていません。 というわけで、この後、彼がケータイを手に入れるまでのバカ話が、あれこれ書かれているわけです。で、それも、さほど面白いわけではないのですが、まあ、「クダラネー」とか感じながら読んでしまう本です。 なんか、あんまりすすめてませんね。マア、そういう本ですね(笑) でも、こういう感じが「面白かった時代」は確かにあったんですよね。若い人は、どう思うのでしょうかね?
2022.08.31
コメント(0)
-

ベランダだより 2022年8月14日(日)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年8月14日(日)「朝顔日記」8月14日のアサガオ 8月14日に朝です。花はほとんど咲いていません。曇っているから、余計に、暑い暑い真夏の朝です。何となく不思議なのですが、これから花になる蕾はたくさんついています。 青空がうまく写らなくて残念です。まあ、曇っているのですが。 「あした咲きます!」 なんだか凛々しいですね。 「昨日咲きました!」 鳥の雛の囀りの図のようですが、もう咲いて種を育てている蕾です。 8月14日のモスラ君 はい、ゴソゴソ、這いながら葉っぱを食べています。 「はい、ぼくは、まだ、生まれたばかりです。」 「ぼくは、そろそろ変身の時期です。下の葉っぱには、昨日、お母さんが新しい卵がおいていきました。」 「まん丸です!」 拡大するとピントがあいません。スマホのカメラはホントに不便です(笑)。ボタン押してね!
2022.08.30
コメント(0)
-

ベランダだより 2022年8月13日(土)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年8月13日(土)「朝顔日記」8月13日のモスラ君 「ちょっと、ちょっと、ちょっと来てよ。これ何かなあ?」 まあ、今日は日曜日ということもあって、チッチキ夫人もお休みで、朝からベランダで洗濯物を干したりなんかしていたのですが、なにやら叫んでいます。 部屋からベランダに出るガラス戸の一番下のところに何か普段は見かけないものがくっついています。 モスラ君の蛹ですね。蜜柑の植木鉢からは結構離れたところなのですが、夜のうちにここまでやってきて蛹に変身です。いよいよ、蝶になろうという現場が見られるかもしれませんね。これからどうなるのでしょうね。8月13日のアサガオ 青空が取り柄ですが、花はしおれかけ。 日陰でひっそり咲いてますが、今日も青い花はありません。 今日も、いい天気です。猛暑が続いています。神戸のヤサイクン一家に続いて、信州の愉快な仲間、カガクン一家もコロナに巻き込まれて大変だそうです。まだ一つにならないチビラ君のサラちゃん姫とか心配です。 コロナ騒ぎが対岸の火事ではない空気がシマクマ君の生活にも広がりつつあります。「朝顔日記」とかのんびりしていて大丈夫なのでしょうか?ボタン押してね!
2022.08.30
コメント(0)
-

ベランダだより 2022年8月12日(金)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年8月12日(金)「朝顔日記」8月12日の百日紅 今日は部屋の玄関の前の百日紅です。7月の半ばに咲きはじめて、咲きっぱなしです。チッチキ夫人はあんまり好きじゃないのだそうです。「暑苦しいやん!」 まあ、一言でかたずけられても、立つ瀬がないと思うのですが、暑さの盛りに咲き続けているわけで、暑苦しいのは花のせいばかりともいえない気もします。ぼくは、ちょっといい風情だと思うのですがねえ(笑)8月12日のモスラ君 卵です。昨日も載せましたが、毎日やってきます。 ノソノソ、モスラ君は元気です。葉っぱはたっぷりあります。8月12日のアサガオ で、アサガオです。元気有りません。関西では今日(12日)か明日(13日)がお盆の墓参りの日だったと思いますが、シマクマ君もチッチキ夫人もご無沙汰です。 例年だと、ヤサイクンの家族がオバーチャン家に行くというので乗せてもらっていたのですが、今年のヤサイクン一家はコロナ騒動で、それどころではありません。 久しぶりに青い花が咲いていました。一番低いところで咲いているのが珍しいですね。 こちらは「あした咲く!」という感じです。 こちらは、「ちょっと遅れちゃった!」でしょうか。 風にあおられて花が動いているのですが、顔をしかめているようにしか見えませんね。 いかにも、「アサガオ!」です。今日は少し花がふえました。明日が楽しみですね。じゃあまた明日です。ボタン押してね!
2022.08.29
コメント(0)
-
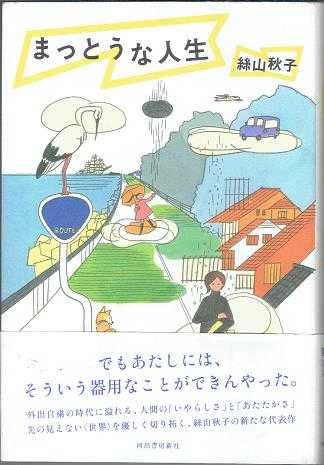
週刊 読書案内 絲山秋子「まっとうな人生」(河出書房新社)
絲山秋子「まっとうな人生」(河出書房新社) 絲山秋子という作家が、ぼくは案外好きなのですが、彼女の最新作「まっとうな人生」(河出書房新社)という作品を読んで、ひさしぶりに「そうだよな。」と納得しました。 もう十年以上も昔のことですが、彼女の「逃亡くそたわけ」(講談社文庫)という作品を読んだことがあります。その後、映画化されたりしたらしいのですが見ていません。小説は「なごやん」と「花ちゃん」という、二十代の男女の二人組が入院していた博多の精神病院を抜け出して九州縦断の逃避行をする話で、なんだかとても哀しくて痛快だったと記憶している作品でした。 この本の見開きページにある「まっとうな人生」の舞台のイラストです。なぜ、そうなったのかよく分かりませんが、あれから、十数年経って「花ちゃん」は富山で暮らしていますというのがこの作品の始まりでした。「よそ者のことを、富山では「たびのひと」と言う。何十年住んでいても出身が違うだけでそう言う。大学から関東や関西へ行って有名人になった人が、いつまでも地元でちやほやされるのと同じしくみだ。よそ者、ということを考えない日はなかった。(P10) これが、まあ、ほとんど書き出しですが、九州から富山に移住(?)して、今ではアキオちゃんと呼ぶ配偶者と、10歳になる佳音ちゃんという女の子と三人で、まあ、そこそこ平和に暮らしているお話です。 まあまあ元気、というのは一応通院しながら病気をコントロールしているということで、二年に一度くらいは再発もある。 肌のハリや髪の艶がなくなっていくように、病気も少しずつ鮮度を失っていくと感じている。麺類でいえばコシがなくなるというか。病気そのものの主張が弱くなるというか。でも他人から見たらわからない。激しく見えることもあると思う。特に妊娠中は予防のための炭酸リチウムや向精神薬が中止されて、大変やった。中略 発病したときは「そううつ病」だったのが、今は「双極性障害」に名前も変わった。初めて躁状態になったときは、なんかどこか、自分の奥の方で力をためて準備していた病気が躍り出たみたいだった。病気は強くて真っ黒で弾力があって、その勢いであたしを乗っ取ろうとしていた。気持ちの悪い病気の粒が、体の中から表面に出てきておはじきみたいにざらざらするのを感じた。あたしの皮膚には、さまざまな大きさの目が無数にあって、脳に映像が伝えられることはないのに、たくさんの目が開いて、あるいはこれから瞼を押し上げて開こうとしていると思った。神社でしか目覚めない目、台風のときだけ開く目があって、耳には聞こえない周波数の音だけに反応して目覚める目があって、生きているそろばん玉みたいなそれらの目を意識するのを狂っていたというのは簡単だが、あのときは、これでわかったと思った。うまく言葉にできないけれど、気がつくとというのはそういうことではないだろうかと今でもちょっと思う。(P11) というわけで、身体的、精神的不調と付き合いながら暮らしている「花ちゃん」の独り言小説ですが、あの時の「なごやん」もまた、なんと富山に暮らしているという偶然の再会で、作品は急展開するかと思いきや、別に何も起こりません。 まあ、それが絲山秋子というわけで、読んでいる方も、何か事件が起こったり、人の生き死にのドラマが盛り上がったり、男女関係がややこしくなったりというふうな、まあ、ありがちな「おもしろさ」どこにもありません。あるのは、なんとなく蔓延してるコロナの世相ですが、それとても、とりわけ騒ぎ立てて書かれているわけではありません。もちろん「双極子障害」という今では、はやり言葉のようになっている病気や、その病像についてのカミングアウト小説というわけでもありません。 花ちゃんの独り言は、ただ、「わかること」の、ちょっと手前で、うまく言葉にならない「わからないこと」に、じっと、辛抱しながら「ことばあそび」を楽しんでいる(?)、いや、苦しんでいる(?)風情で続いていきます。 干していた寝袋を回収に行くと、海を背にした佳音が両手をひらいて、腕を広げた。「お母さんもこうやってみて」小さかったころの「抱っこして」のポーズみたいだ。あたしが真似したら祝福を与える怪しい宗教家みたいやんと思った。「なにこれ?」「お日様が当たると、気持ちいいでしょ?」たしかに、掌のくぼんだところに朝の光が当たっている。小さくてあたたかい温泉を載せているみたいだった。「滝とか、風に向けても気持ちいいんだよ」「くぼんだところって、握手しても触らないとこだから、敏感なのかな」「焚火にあたってるみたいね」これが受け止めるってことなのか、とうっすら思った。(P250~251) 作品は2019年4月にはじまった花ちゃんの日々の独り言の記録ですが、2021年10月、コロナ騒ぎのなか、家族でキャンプにやってきた海岸での花ちゃんと佳音ちゃんのこの会話で記録は終えられます。 読み終えたシマクマ君は、ベランダに出て掌をお日様にかざします。で、「そうだよな」という納得が掌に広がるのを感じます。他人事だと思っていたコロナ騒動の当事者を経験して、ようやく、外に出てもよくなった朝の出来事でした。
2022.08.28
コメント(0)
-
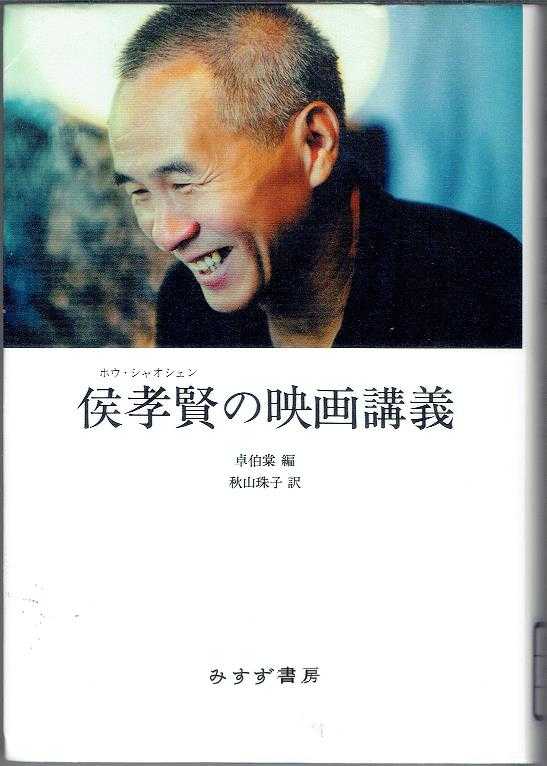
週刊 読書案内 侯孝賢「侯孝賢の映画講義」(みすず書房)
侯孝賢「侯孝賢の映画講義」(みすず書房)(卓伯棠編・秋山珠子訳) 「侯孝賢(ホウ・シャオシェン)の映画講義」(みすず書房)という本が市民図書館の新刊の棚に転がっていて、読み始めてはまりました。記事の最後に、経歴とかを写しましたが、実は、ただの1本の作品も見たことのない人なのですが、その彼が、2007年に香港バプテスト大学で行った講義の書籍化である本書を読みながら、見たくて見たくてたまらない映画監督の一人になりました。 映画を志す大学生たちに対する、実作者でもある監督による講義です。全部で6講ありますが、講義のあとでの、学生たちとの質疑応答も含めて書籍化されています。まあ、こんな目次です。目次第1講 私の映画の道第2講 映画における真実と現実――小津安二郎を手がかりに第3講 映画の美学と信念第4講 映画の作り方――ブレッソンを手がかりに第5講 質問に答えて第6講 台湾映画の現在と未来 第1講は、本人による自伝的な自己紹介ですが、第2講からは映画の実作についての現場的な発言満載です。もっとも、内容にあれこれ言うことができるほど、侯孝賢監督についても、彼の作品についても、また、80年代から2000年代にかけての台湾映画、香港映画、中国映画についても、「全く知らない」わけですから、「面白かった」というしかないのですが、記憶に残った講義を一つだけ紹介してみたいと思います。 写実についての私の考えはこうです。写実とは再創造された真実である。それは現実における真実と同等のものであり、一つの独立した存在である、と。カルビーノは小説の形式を論じたとき、小説の深度について次のように語っています。小説の深度は表面に表れ、それは潜在している、と。表面に表れるのはテキストであり、私達はそのテキストの構造を通じて、そこに透けて見えるかすかな手がかりから、言葉では伝えられず、名指しようもなく、出来事のなかに身をおいて初めて理解しうるものを感得するのです。 映像も同じです。映像こそ最も現実を「象る」ものなのですから。真実の再創造について考えるために、小津の映画、たとえば「晩春」を見てみましょう。主人公である父娘は、母親が亡くなったあと、二人で暮らしている。そんな中、父親に再婚話が持ち上がり、娘はそれに強い嫉妬を覚える。それは嫉妬であると同時に、ある種の反抗でもあります。映画のなかで二人が能を鑑賞するシーンがあります。能楽堂で脳を見ていたとき、娘は父親が再婚相手と思しき女性に会釈するのを目にする。すると娘の目はにわかに殺気立ったものになる。その後娘は、ある男性を結婚相手として紹介される。が、かたくなに結婚を拒む。しかし娘も次第に変化し、ついにその男性を受け入れ結婚する。 「晩春」についての西洋の多くの批評は、結婚前に父娘で京都旅行をし、二人で同じ部屋にとまることをとらえて、父娘の間には曖昧なエレクトラ・コンプレックスがあると解釈したりする。 けれど私から見ればそういうことではまったくない。日本の家庭では女は男を遠ざけはしません。家族で一緒に風呂に入ることさえあり、そこには私たちと違う生活スタイルがあるのです。それを踏まえなければこの映画を理解することはできない。家族の描写には地域性が色濃く反映されます。娘にとって家は自分の領域であり自分のものです。娘には、自分がずっと父親の世話をし、家は自分が取り仕切っているのだという自負があります。そこに突如、よそから人が入ってくることになるのですから、娘の反応は当然のもので、だから彼女は恋愛することになるのです。「晩春」はこうした機微を熟知してこそ撮りえた映画です。そして、その機微は、叙事構造を通してあらわされている。西洋ならばドラマを際立たせようと、父娘の関係をエレクトラ・コンプレックスの心理学の域る世界です。表層はごくシンプルで、特段のドラマ性を感じさせないにもかかわらず、それが積み重ねられることで その深部の暗流が怒涛のように渦巻くのです。(P77~P78) いかがでしょうか、ここで話題になっている「晩春」は、言わずと知れた、小津映画の傑作のひとつで、笠智衆と原節子の父娘映画の始まりのような作品ですが、映像に対する侯孝賢監督のシャープな論旨に唸りました。 知っている映画をネタにした話も、、全く知らない台湾映画や香港のスターを話題にした話もありますが、話として聞かせるのがすばらしいですね。その時代の台湾映画や香港映画のファンの方にはきっと楽しい話題満載だと思います。コロナで、ごろごろせざる得ない日々でしたが、なかなか刺激的な読書でした。みなさまも、是非、どうぞ。 侯孝賢映画監督。1947年中国広東省梅県の客家の家に生まれ、翌年に一家で台湾に移住、高雄県鳳山で少年時代を過ごす。高校卒業後に兵役に就き、除隊後の1969年に国立芸術専科学校入学、映画製作を学ぶ。1972年卒業。その後、スクリプター、脚本家、助監督を経て、1980年に『ステキな彼女』で監督デビュー。80年代に台湾で起こった社会性、芸術性を追究する映画製作の新潮流「台湾ニューシネマ」を牽引した代表的な監督の一人である。第6回ナント三大陸映画祭金の気球賞(『風櫃の少年』)、第7回ナント三大陸映画祭金の気球賞(『冬冬の夏休み』)、第36回ベルリン国際映画祭批評家連盟賞(『童年往事』)、第46回ヴェネチア国際映画祭金獅子賞(『悲情城市』)、第46回カンヌ国際映画祭審査員特別賞(『戯夢人生』)、第68回カンヌ国際映画祭最優秀監督賞(『黒衣の刺客』)など世界的な映画賞を数多く受賞し、台湾最大の映画賞である金馬奨では『悲情城市』『好男好女』『黒衣の刺客』で最優秀監督賞を受賞。2020年第57回金馬奨生涯功労賞。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2022.08.27
コメント(0)
-

ベランダだより 2022年8月11日(木)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年8月11日(木)「朝顔日記」8月11日のアサガオ 今日もいいお天気ですが、アサガオの花はあまり咲いていません。暑すぎるのかもしれませんね。 写真を撮る当人も、少々夏バテ気味です。 モスラ君たちの動向も、何故か姿を隠していて、写真になりませんでした。どうしたことでしょう。まあ、こういう日もあるということで、今日はお終いです。ボタン押してね!
2022.08.26
コメント(0)
-

ベランダだより 2022年8月10日(水)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年8月10日(水)「朝顔日記」8月10日のアサガオ ここのところ、花の数が減っています。8月も中旬に入って「朝顔もそろそろ終わりかなあ?」とチッチキ夫人もあきらめ顔です。 でも、まだ、蔓は緑なので、もう少し咲いてくれるかもです。 葉っぱもまだまだ緑です。 今日は赤い花ばかりでした。 天井近くに咲いているのも、今日は赤い花でした。8月10日のモスラ君 アサガオに比べてモスラ軍団は元気です。毎日アゲハがやってきて卵を産んでいきます。 ミカン畑の奥の方で、ノソノソ葉っぱをかじっているようです。 何枚も写真を撮っているのですが、こちらもピントがうまくぴったしになりません。 こういう風情です。不思議なことに見ているときには動きません。もうすぐ緑に変身する直前です。 こちらは、そろそろ蛹に変身しそうですが、いったいどこで蛹になっているのかが、今のところ分かりません。 というわけで、8月10日のベランダでした。ボタン押してね!
2022.08.25
コメント(0)
-

徘徊日記 2022年8月10日(水) 「都賀川から摩耶山!」西灘あたり
「都賀川から摩耶山!」徘徊日記 2022年8月10日(水) 西灘あたり 三宮のシネ・リーブルでジョニー・デップを見て、映画館の前で何となくバスに乗って、降りてみたら都賀川でした。ヒマなのですねえ(笑)。 上流に見えるは摩耶山で、見えている町並みは篠原北町あたりです。川をさかのぼれば神戸大学の農学部の裏の坂道あたりにたどり着きます。昔の通学路です。 この場所は新都賀川橋とかで、そこに見えているのが「なだけいさつ」です。で、道の向こうが灘区民センタ―だそうです。40年前に住んでいて、毎日うろついて町ですが、どの建物にも見覚えがありません。 だいたい、この立派な区民センターはなにをする場所なのでしょうね?ポカンと見上げながら、ふと東側を見ると知っている建物がありました。 金沢病院です。三宮にもあるような気がしますが、こっちの方が懐かしいですね。友達が、このすぐ南に住んでいました。 ここから東の六甲道の町並みは95年の震災で燃えたり壊れたりして、学生時代に見知った風景の影も形もありませんが、この病院は昔のままでした。 別に目的があって、今ここにいるわけではありませんが、懐かしいですね。ここから南にくだってJRの六甲道まで歩こうと思います。まあ、大した距離ではありません。じゃあ、またね。ボタン押してね!
2022.08.24
コメント(0)
-
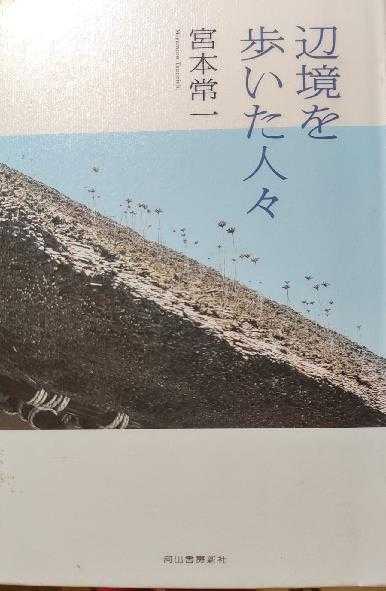
週刊 読書案内 宮本常一「辺境を歩いた人々」(河出書房新社)
100days100bookcovers no80(80日目)宮本常一「辺境を歩いた人々」(河出書房新社) 2022年になりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 Simakumaさんからバトンを受けて1月以上過ぎてしまいました。スミマセン!!その間にSimakumaさんはご自身のブログに幸田文の「おとうと」に続き、「みそっかす」・「父・こんなこと」と次々と紹介されました。「視点の高さ」を持つ幸田文の文学から何につなげるといいのか、困っていたのですが、今回も勝手な着地をします。お許しください。 79日目がアップされたのは12月11日。その直前私は青森に1泊2日の旅に出ました。「宿題」の合間の息抜きに、手ごろなひとり旅を楽しむのですが、この度の行先は「青森」でした。ずーっと以前に青春18切符で東北本線をのんびり北上し、夜行で札幌に到着し、静内を尋ねました。青森県はほぼ素通りで、八戸と青森の駅周辺で乗り換え時間を過ごしただけでした。岩手県では花巻の宮沢賢治記念館、岩手県立花巻農業高等学校など、遠野では1泊してカッパ淵などにも足を伸ばしました。北海道では静内でアイヌ、さらにホームで道連れになった方と浦川の「べてるの家」まで見学した贅沢な旅でした。青森の印象は「陸奥(みちのく)」そのものでした。 そもそも「陸奥」とは、古代の蝦夷地で、大化改新後白河以北全域を道奥(みちのおく)国としたと言われます。もちろん中央権力からの視点でしょう。それは近代化とともにさらに定着し、私の概念にもこびりついてしまっていたのです。今回、それを払拭された経緯について、お話させてください。 青森を訪れる前に観光情報をリサーチしました。訪れたいところはたくさんありましたが、時間と交通手段の関係でJR青森駅周辺しか動けませんでした。しかし、旅の後気持ちが高揚し、青森にハマりました。特に「縄文」!。昨年7月27日、北海道・北東北の縄文遺跡群は世界文化遺産に登録されましたが、私はもっぱら南の沖縄に関心が向き、恥ずかしながらあまり感知できていませんでした。 Degutiさんの方が縄文に詳しいのですが、私はこのたびようやく学び始めました。今からおよそ1万5千年前~2千4百年前までの1万年あまりというとてつもなく長い期間、縄文時代の人々の生活と精神文化が続きました。「自然が厳しく貧しい」という私の青森に対するイメージは、全くの誤りでした。むしろブナ林を中心とする広葉樹の森林や豊かな漁場という恵まれた環境の中で、世界的にも稀な定住生活が可能になったことや、また高い精神性がうかがえる死後の埋葬や祭祀、環状列石(ストーン・サークル)など、驚くことばかり!特に縄文土器の洗練された美しさやユニークな土偶のデザイン…。本当に、脳天を打たれた思いと言えばあまりに大袈裟ですが、私自身の思考の枠組みの脆さを思い知らされました。 青森旅行からしばらくたって図書館で借りた『おとうと』を読み終えたのは30日。雪景色が恋しくなって青春切符で福井に向かった電車の中でした。意志や努力だけでは思うようにならない人生や病、人間関係、世間の風当たりなどを見事に描写していました。篠田一士が「心の中に眠っているあの感覚」と評したものが、縄文と重なるかなんて、私の勝手な見方ですが、通じるものを感じたのです。 その後図書館の本棚で目に留まったのが『辺境を歩いた人々』という書名と宮本常一という名前。前から気になっていた民俗学者です。『忘れられた日本人』や『塩の道』などの方が有名なのでしょうが、今の私には「青森」の衝撃があり、「辺境」を探ってみたくなりました。手に取って目次に目を通し、松浦武四郎以外の3人の名前は知らなかったのでいったんは棚に戻したのですが、やはり気になってまた手に取り、序文を読みました。 日本のひらけていない地方をあるいてみると、きまったようにその地方のことをくわしくしらべた書物のあることに気づきます。しかもその書物を書いた人たちは、その土地の人よりも、旅人のほうが多いのです。そのうえ、かれらはかわったところを見るためにやってきて書いたのではなく、「どこだっておなじ日本の国の中ではないか、その国の中のすみのほうにあるからといって、わすれさってしまってはいけない。その土地のことをおたがいにもっと知りあって、よくするように努力しなければいけない。」というように考えて、あるいているのです。… 冒頭の一段落を紹介しましたが、ひらがな表記が多いですね。宮本常一自身が半世紀にわたって日本の国土を歩き続け、膨大な記録を残したのですが、同じように日本の、それもへんぴな地方―僻地―をあるくことに情熱をおぼえ、危険をおかし、困難な旅行をしてそれを後世に伝えた4人を、その記録を元に紹介していました。 八丈島に流され、罪をゆるされた後またもどり、島民とこころをとけあったという近藤富蔵。松浦武四郎は未開の大陸北海道の内陸までくまなくあるきました。当時松前藩に搾取されていたアイヌの人々との交流もありました。明治維新後北海道の道名、国名、郡名をきめる仕事にあたった時は、「えぞはもともと地名ではない」ことをいい、「アイヌがみずからその国をよぶのに加伊(カイ)という。」ところから、「北加伊道」という名前が採用され、のちに「北海道」と漢字を改めます。今も札幌をはじめ、地名の多くはアイヌ語が由来ですが、もしかしたらそれも松浦武四郎の影響が大きいのかもしれません。とまる宿代や食事代は得意の篆刻の報酬でまかなったり、四書、唐詩の話をしてかせいだりした文人であり、人間愛にあふれ、公正無私なヒューマニストであったわけです。自分だけ暴利をむさぼる現代の政治家や事業家と大きな違いです。菅江真澄という人は、おもに秋田、青森などの雪やあられの中での生活や移動、ききんの想像を絶する状況をこまやかに記しています。幸田文の『おとうと』の中で姉が弟を看病するあたりと通じるものがありました。そして、また私の理解が全く事実に届いていなかったと思い知らされたのです。私の未熟な想像や知識を恥ずかしく思い、同時に新しい世界が広がっていくようにも感じました。最後のひとりは笹森儀助です。北は千島、南は琉球、台湾までつぶさにあるき、多くの記録を残した探検家で、第2代青森市長に就任もしました。当初「貧旅行」と自ら命名したのは、できるだけひろくあるき、多くの人にあって地方の実際のことを知ろうとしたからだそうです。 今のように便利な交通手段も情報を得る手段もなかった時代辺境をあるいて記録した4人の人生は、過酷であったかもしれませんが、未知の世界と出会う喜びにあふれていたことでしょう。 Simakumaさんのバトンをいつも変な方につなげてしまうので大変恐縮です。無視してSodeokaさん、軌道修正なさってください。どうぞよろしくお願いいたします。2022・01・12・N・YAMAMOTO追記2024・05・04 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。
2022.08.23
コメント(0)
-

ベランダだより 2022年8月9日(火)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年8月9日(火)「朝顔日記」8月9日のモスラ君 光の加減で、なんか、ちょっと面白いモスラ君です。8月に入って、毎日のようにアゲハ蝶がやって来るのですが、そのアゲハ蝶を撮ることができないのが残念です。 で、モスラ君たちが次々と登場しています。同じ木にやって来るアゲハ蝶は同じアゲハですね。だから、新しく生まれてくるモスラ君たちは、みんな同じ種類のようです。 ミドリに変身する前の、幼虫の幼虫たちがうじゃうじゃいます。 偶然、隣の葉っぱで遭遇した二匹です。まあ、不細工といえば不細工ですが、かわいい奴らと思えば、結構かわいい奴らです。葉っぱの影で、でかくなりつつあるモスラ君も複数います。8月9日のアサガオ で、実はあんまり咲いていません。暑さが続いているせいもあります。葉っぱはまだ緑ですから、もう少し咲くとは思うのですがね。 一番上の青い花です。なんで、こういうふうに咲くのでしょうねえ(笑)日陰の花。 朝早く咲き過ぎて、早くも萎れる準備かという感じの赤い花。まあ、風にあおられているせいもあります。 こういう、爽やかな後姿の花が、毎朝、一つか二つありますねえ。 ベランダの西の端の風船カズラです。もう数日すれば、風船が茶色くなってしまうのですが、今はまだ緑の風船です。 じゃあ、また、明日。ボタン押してね!
2022.08.22
コメント(0)
-

ベランダだより 2022年8月8日(月)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年8月8日(月)「朝顔日記」8月8日のアサガオ 朝から、暑い日差しに顔を背けるともなく、いやはや、どうどうと、まあ、それがアサガオというものではあるのですが、もう30分もすると萎れてしまいます。 部屋からの全景です。花の数は少ないですが、蔓も葉っぱもまだまだ緑です。もう少し咲き続けてくれるのでしょうねえ。 ピンクの花の後ろ姿です。最初の赤い花とは色合いが違います。 やっぱり上の方で咲いている青い花です。 日向を避けて、内側に向かって咲いている赤い花です。ピントがうまく合わない感じはあいかわらずです。8月8日のモスラ君 はい、モスラ君です。4っつ木くらいある蜜柑の木が植わっている植木鉢というか、植木箱というかのあっちこっちにいてはるんですが、ある日突如消えてしまったりもします。なぜ行く方不明になるかは不明ですが、「蛹になる」か「天敵にやられる」のどっちかでしょうかね? 色も形の一人前の一歩手前ですが、愛嬌はあります。一番、行く方不明になりやすい時期ですね。 まだまだ、幼いのですが、この辺りから食べ始めますね。 ほぼ、一人前じゃないでしょうか。幼虫に「一人前」という言い草も変ですが、実は、その後の行動を追うと、まあ「一人前」という言葉を使ってもいいような気もします。 今年のモスラくんで、ちょっとすごい行動がみられるかどうか、明日からの楽しみですね。じゃあ、またね。ボタン押してね!
2022.08.21
コメント(0)
-

佐藤信介「キングダム2 遥かなる大地へ」109シネマズハットno14
佐藤信介「キングダム2 遥かなる大地へ」109シネマズハット 原泰久の人気マンガ「キングダム」が実写映画化されたのが2019年でした。マンガのファンであるシマクマ君はもちろん見ましたが、面白いというよりも、少々のけぞり気味で、現代の日本映画のありさまに、まあ、良くも悪くカンドー!?したのですが、その続編「キングダム2 遥かなる大地へ」が、今年2022年の夏に公開されました。 で、さっそく出かけました。やっぱり「キングダム」ですからね(笑)。まあ、マンガに関しては「これって史記のどこ?」とか、ちょっと気になってしまうこともあるのですが、映画に関しては歴史的考証とかについては端から期待していません。どっちかというとファンタジーのノリで見ないと、至る所でのけぞってしまうことになるのは前回で織り込みずみです(笑)。 お話は、原作の第10巻くらいまでの展開、大将軍を夢見る信少年(山崎賢人くん)が戦場で初手柄をあげる蛇甘(だかん)平原の戦いを描いたドラマでした。王位についた秦王政(吉沢亮くん)の初仕事でもありますが、魏軍相手に苦戦に次ぐ苦戦で、あわやの大逆転勝利の立役者の一人が信というわけでした。 前作で、圧倒的にのけぞらせていただいた長澤まさみさんの楊端和(ようたんわ)との再会に期待していたのですが、今回は出番なしで、期待は空振りでしたが、今回は、羌瘣(きょうかい)の清野菜名さんに涙涙でした(笑)。 原作マンガをお読みの方はよくご存じでしょうが、謎の暗殺一族である蚩尤(しゆう)の末裔ので、トーン・タン・タン、トーン・タン・タンという繰り返しのリズムに乗りながら巫舞という不思議な呼吸法の殺人剣を操る少女です。 原作マンガそっくりの顔立ちと奇異な装束に見入っていると、冷血で、ニヒルで孤独な少女羌瘣が、熱血少年信との出会いで、その「熱血」の仲間へと変貌していくわけですが、下の絵がそのクライマックス・シーンでした。「だってお前はまだ生きているじゃないか!!」 多勢に無勢、絶望的な戦場で、倒れている戦友に必死の形相で声をかける羌瘣こと清野奈々さんに拍手!拍手!でした。名セリフだと思いませんか。ここまで、クールを通してきた清野奈々さんの「熱血」が爆発して、カンドー!でした。 上に貼ったのは入場者に配られた、原作者原泰久による本作の解説集「キングダム伍」という冊子の名場面解説というか、絵コンテ紹介のページです。 これが配布された冊子ですが、表紙中央が、もちろん、信、後ろに立っているのが羌瘣です。まあ、こういうマンガの美少女のような顔立ちの方が実在することに驚きましたが、すっかりファンになってしまいました(笑)。 ちなみに冊子の巻数「伍」というのは、当時の軍隊での最小単位だった5人組のことを「伍」と呼び慣わしていたようで、ここでは、信の最初の仲間の5人をあらわしていると思います。近代の軍隊に「伍長」とかいう階級がありますが、5人小隊の長でしょうね、あれの始まりですね。 総じて、高校の文化祭の演劇を見ているような印象はぬぐえませんでしたが、まあ、見ている方の年のせいでしょうね。そういえば、ベテラン俳優の佐藤浩市が秦の丞相呂不韋という、歴史的には有名な人物として登場していましたが、彼の普通の演技が、かえって浮いているように見えたのが、ちょっとおかしかったですね。 前作が大ヒットだったせいですかね、冊子を配るとか、サービスも手厚くなっています。小学生くらいを連れた家族連れもたくさんで、人込みを避けたい老人にはちょっと危険な109ハットでした。監督 佐藤信介原作 原泰久脚本 黒岩勉 原泰久撮影 佐光朗照明 加瀬弘行美術 小澤秀高編集 今井剛音楽 やまだ豊主題歌 Mr.Childrenキャスト山崎賢人(李信)吉沢亮(秦王政)橋本環奈(河了貂)清野菜名(羌瘣)豊川悦司(麃公・秦将)高嶋政宏(昌文君・秦王側近)小澤征悦(呉慶・魏将)佐藤浩市(呂不韋・秦丞相)大沢たかお(王騎・秦六大将軍)2022年・134分・G・日本配給 東宝・ソニー・ピクチャーズエンタテインメント2022・08・17-99・109シネマズno14
2022.08.21
コメント(0)
-

ベランダだより 2022年8月7日(日)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年8月7日(日)「朝顔日記」8月7日のモスラ君 「朝顔日記」なのですが、まあ、「ベランダだより」でもあるわけで、ここのところ、すっかり気をとられている「モスラ君日記」になってしまっていますが、花でも虫でも、まあ動物でも、人間でもと括ってもいいのですが、生き物というのは面白いですね。 どっちかというと、花より虫の方が飽きないような気もします。動くからでしょうかね。もっとも、シマクマ君がのぞき込んでいるときに動くかというと、ほとんど動くことはありません。で、このからだが一晩で緑に変わっていたりするのですが、識別できるわけではありません。 まだ、小さいのですが、最初の写真のモスラ君と違って、緑に変身しています。もちろん動きません。 からだの模様が、なんか本格的になってきた、少し大きくなったモスラ君です。このモスラ君と下のモスラ君は別の個体です。 このモスラ君の右側の葉っぱに乗っている丸いものは、多分、糞だと思います。この大きさになると、かなりな量の葉っぱを食べますから、あっちこっちにこんな糞をしています。しているところを見たわけではありません。8月7日のアサガオ で、アサガオです。猛暑が続いているからかもしれませんが、花に勢いがありません。早朝から、すでに、日差しが厳しいので、咲いてもすぐにしおれてしまいます。 花というものの習性なのでしょうね、日差しの方に向かって、そんなことをすると暑いのにと思うのですが、それでも健気に咲いています。 日陰の側の赤い花が大きく咲いていました。何となく、赤色ピンボケです。 日差しの中で、ピンクの花が二つ元気です。 青い花は、今日も天井を向いて咲いています。 紅い花のアップ写真が、何とかピンボケしないで撮れないか、スマホのオートとかマニュアルとかをいじりながら努力していますが、うまくいきませんね(笑) ほら、葉っぱの影から顔を出して、お日さんを探しているようです。「まあ、皆さんお元気で!」なのですが、実際はしおれかけています。 ちょっと角度を変えてみました。 日陰で咲いている人もいます。何となく好感を持ってしまうのですが。それは、まあ、人それぞれでしょうかね。 それにしても、夏も盛りを過ぎつつあるのでしょうが、今日はヒロシマ、ナガサキのあいだの日ですね。1945年の夏も暑い夏だったようですが、今年も、とりわけ暑い夏です。ボタン押してね!
2022.08.20
コメント(0)
-

グー・シャオガン「春江水暖」元町映画館no142
グー・シャオガン「春江水暖」元町映画館 グー・シャオガンという中国の若い映画監督の「春江水暖」という映画を見たのは、昨年(2021年)の3月の中頃でした。2019年の暮れだったでしょうか、29歳で自ら命を絶った、フー・ボーという若い監督の「象は静かに座っている」という作品を見て圧倒されましたが、この映画も、負けず劣らず印象的でした。 グー・シャオガンとフー・ボー。二人は、ともに1988年生まれで、北京電影学院で「映画」を学んだ同窓です。 フー・ボーの作品を見ながら、もう数十年も昔に「ぼくもそうだった!」という共感と、主人公とともに、北のはての動物園の檻の中で静かに座っている象に会いに行こうとしながら、ためらう老人に、今、現在の自分の姿を重ねるという、幾分哀しい、重層化したリアルを味わったのですが、グー・シャオガンのこの作品「春江水暖」では、「家族」というくくりではよくあることなのかもしれませんが、いつか同じ「時間」を共有した人間 が、それぞれ違う「時間」の中で暮らしながら、ある時、ふと、同じ時間の中に戻ってくる体験、それは普通、誰かの葬儀とか結婚式とかで感じざるを得ない「時間」との出会いなのですが、その時の意識の感触は、いわゆる「記憶」とか「思い出」とは少し違うとぼくは思いますが、そんなふうな、また別の重層的な時間の世界がえがかれていました。 映画の中では、老齢の祖母の長寿のお祝いに集まった「家族」のそれぞれの肖像が重ねられる様子を見ながら浮かびあがってくる、「過去の時間」との出会いと、青年の長い長い遊泳シーンと、それを岸にそって追いかける女性という、ぼくにとっては、この映画の記憶として残るに違いない「二人の今の時間」を、出会っている自覚などもちろんないまま、まさに、生きている様子として、対比的に描かれていることに深く納得しました。 人が生きるという経験の中には、「時間」が重層化、あるいは多層化して流れていて、その時、その時の「時間」が、それぞれ流れている複数の空間を孕んでいるわけですが、一人一人が自分の世界として生きている、この重層化した個々の時間の世界を、実の自然の中に溶かし込んでいくかに見える映像の不思議をつくりだしているグー・シャオガン監督に、驚嘆の拍手!でした。 映画を見て、思い出したのが張若虚という初唐の詩人の「春江花月夜」という長詩です。まあ、題名の類似で「そういえば!」と探したにすぎませんが、面白いと思いました。「春江花月の夜」 張若虚春江の潮水、海に連なって平らかなり海上の明月、潮と共に生ず灔灔(えんえん)として 波に随うこと 千万里何処の春江か 月明無からん江は宛転として流れて 芳甸を遶(めぐ)り月は花林を照らして 皆霰に似たり空裏の流霜 飛ぶを覚えず汀上の白沙 看れども見えず江天一色にして 纖塵無く皎皎たる空中の弧月輪江畔 何人か 初めて人を照らせる人生 代々 窮まり已むなく江月 年々 祇(た)だ相似たり知らず 江月 何人を待つかを但だ見る 長江 流水を送るを白雲一片 去って悠々たり青楓浦上 愁いに勝えず誰家ぞ 今夜扁舟の子憐れむ可し 楼上 月徘徊し応に照らすべし 離人の粧鏡台玉戸 簾中 巻けども去らず擣衣の砧上 払えども還た来たる此の時 相望めど相聞かず願わくは 月華を逐うて 流れて君を照らさん鴻雁長飛して 光 渡らず魚龍潜躍して 水 文を成す昨夜 閑潭 落花を夢む憐れむ可し 春半ばなれども 家に還らず江水 春を流して 去って尽きんと欲し江潭の落月 復た西斜せり斜月沈々として 海霧に蔵れ碣石瀟湘 無限の路知らず 月に乗じて 幾人か帰る落月 情を揺るがして 江樹に満つ いかがでしょうか。白文と口語訳はいずれ追記で記したいと思います。監督 グー・シャオガン脚本グー・シャオガン撮影 ユー・ニンフイ ドン・シュー音楽 ドウ・ウェイ芸術コンサルタント メイ・フォンキャストチエン・ヨウファー(ヨウフー)ワン・フォンジュエン(フォンジュエン)ジャン・レンリアン(ヨウルー)ジャン・グオイン(アイン)スン・ジャンジェン(ヨウジン)スン・ジャンウェイ(ヨウホン)ドゥー・ホンジュン(ユーフォン)ポン・ルーチー(グーシー)ジュアン・イー(ジャン先生)ドン・ジェンヤン(ヤンヤン)スン・ズーカン(カンカン)ジャン・ルル(ルル)ムー・ウェイ(ワン)2019年・150分・G・中国原題「春江水暖」・「 Dwelling in the Fuchun Mountains」2021・03・15‐no23元町映画館no142追記2022・08・17 書きあぐねていた感想ですが、備忘録の意味もあるので、なんと書き終えてブログにのせました。引用した漢詩の白文は以下の通りです。「春江花月夜」 張若虚(白文)春江潮水連海平海上明月共潮生灔灔随波千万里何処春江無月明江流宛転遶芳甸月照花林皆似霰空裏流霜不覚飛汀上白沙看不見江天一色無纖塵皎皎空中弧月輪江畔何人初照人人生代々無窮已江月年々祇相似不知江月待何人但見長江送流水白雲一片去悠々青楓浦上不勝愁誰家今夜扁舟子可憐楼上月徘徊応照離人粧鏡台玉戸簾中巻不去擣衣砧上払還来此時相望不相聞願逐月華流照君鴻雁長飛光不渡魚龍潜躍水成文昨夜閑潭夢落花可憐春半不還家江水流春去欲尽江潭落月復西斜斜月沈々蔵海霧碣石瀟湘無限路不知乗月幾人帰落月揺情満江樹
2022.08.19
コメント(0)
-

ベランダだより 2022年8月6日(土)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年8月6日(土)「朝顔日記」8月6日のモスラ君 緑色に変わったばかりのモスラ君です。何となく小じわが目立ちます。しかし、昨日のモスラ君とは違います。 緑色になるのを日陰で待っているモスラ君です。昨日は一匹しか見つからなかったのですが、今日は4匹見つけました。 葉っぱが、あちらこちら蚕食され始めているので複数のモスラ軍団になっていることは予想していました。でも、この緑色は見つけにくいのです。 こちらは、かなり小さいモスラ君です。こうして、のぞき込んで、かなり長い時間眺めていても、ほとんど動く気配はないのですが。暫くすると行方不明になります。今年はみかん林がかなり大きいので、かなり食い散らされても、そう簡単にマルハゲ状態にはならないでしょうが、どこにいるのか、見つけるのがたいへんです。 8月6日のアサガオ で、朝顔日記です。ご覧の通りたくさん咲きました。朝早くから日差しが強いので萎れるのも早いです。観察しているシマクマ君がノンビリ朝寝を決め込んでいると萎れてしまいます。 珍しく、足元に青い花が咲きました。でも花柄は小さいですね。アサガオにも、いろいろ種類があるらしいのですが、シマクマ君には色の違いしか判りません(笑)。 日陰側の赤い花のアップです。 外を向いている小さめの赤い花です。 おなじみ、天井近くの青い花です。青い花を咲かせる蔓は、何故か天井近くに蕾ができるようです。写真の光の加減がうまく調節できないので、こういうムードになります。 外を向いている赤い花たちです。正面から撮ろうとすると光の調節がうまくできないので、この構図ばかりになります。教室の窓から外を見ている生徒さんたちを歩もい出します。 天井近くのもう一つの青い花です。同じような光の感じになります。 今日はこれだけです。明日も咲くでしょうか。もっとも、シマクマ君はモスラ君たちの動向に気をとられていて、今日も、アサガオの数を数え忘れていました。まあ、大した意味はありませんが(笑)ボタン押してね!
2022.08.18
コメント(0)
-

ベランダだより 2022年8月5日(金)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年8月5日(金)「朝顔日記」8月5日のモスラ 「朝顔日記」なのですからアサガオの花で始めるのが筋というものなのですが、アサガオの鉢の隣に置いてある蜜柑の鉢に、今年の夏も、いよいよ、モスラ君のご登場です。アサガオの写真を毎朝撮るという小学生みたいな日課に、まあ、そろそろ飽きが来ていたのですが、新しい被写体のご登場に拍手!ですね。 今朝、見つけたの一匹ですが、そのうちノソノソ(?)登場してくれるでしょう。で、今日のアサガオです。 8月5日のアサガオ 実は、結構咲いていました。黄ばんだ葉が目立ち始めて、そろそろ終わりかとも思っていたのですが、もう少し咲き続けそうです。 一番足元の日影の花の後ろ姿です。明日の蕾もついているようです。 手すりと柵のあいだから首を出している花です。朝の陽ざしから暑いので、長い時間咲いていることはできそうもありません。 青い花とピンクの花が寄り添って咲いています。 ピンクの花の正面写真です。この色だと、案外くっきりピントがあうような気がします。 4色揃い踏みです。こんなふうにそろって咲くことはあまりありませんね。 お日さんを見上げている赤い花です。この構図になるのは、逆光だと写真全体が真っ暗になるからですが、毎朝ちがう花ですが、一つ一つ、ホントよく似ています。ウーン、当たり前か? 上手く青空が写っているとコントラストがいい気がしますが、赤い花のピントは怪しいですね。 さっきの、ピンクと赤の取り合わせです。 一番足元で咲いている、小さな赤い花です。光の加減が調節できません。 そっと覗くように空を見ているピンクの花もありました。絵日記に飽きかけていたのですが、モスラ君、はい、アゲハの幼虫ですが、それに気をとられる日々が始まりました。とりあえず、今日はこれまでですが、興味津々です(笑)ボタン押してね!
2022.08.17
コメント(0)
-

カンテミール・バラーゴフ「戦争と女の顔」シネ・リーブル神戸no162
カンテミール・バラーゴフ「戦争と女の顔」シネ・リーブル神戸 ベラルーシのノーベル賞作家スベトラーナ・アレクシエービッチに「戦争は女の顔をしていない」(岩波現代文庫)というノンフィクションがあります。日本では小梅けいとさんによってマンガ化もされていますが、ロシアではカンテミール・バラーゴフという新鋭監督によって映画になったようです。 原作は、第2次世界大戦中、従軍し復員した女性兵士たちの長く哀しい戦後をルポルタージュした傑作です。映画が、ソビエト・ロシアの崩壊を経て、ようやく描かれた「戦後文学」、大祖国戦争(ソビエト・ロシアの解放戦争)批判の作品をどんなふうに描いているのか興味を感じて見に来ました。 小梅さんの「戦争は女の顔をしていない」(KADOIKAWA)は原作に忠実なマンガ化で、現在、第3巻が発売されていますが、誠実な力作です。 で、この映画です。原案という言葉通り、アレクシエービッチの原作から得たインスピレーションを映画で表現した作品で、原作の歴史的リアリズムを越えた迫力を実感しました。 第二次世界大戦、ソビエトふうに言うなら大祖国戦争に兵士として従軍し前線から復員した元女性兵士イーヤ(ビクトリア・ミロシニチェンコ)は幼い男の子パーシュカ(ティモフェイ・グラスコフ)を育てながら、傷痍軍人たちの治療に当たる病院で看護師として働いています。1945年のレニングラードが舞台です。 やがて、映画には彼女の戦友であり、男の子のパーシュカの実の母であるマーシャ(バシリサ・ペレリギナ)という女性が登場します。 イーヤはチラシの写真の女性です。金髪の美しい、美人ですが表情の動かない、並外れたノッポの女性です。マーシャは少し茶色がかった黒髪で、なぜか眼差しにウソを感じさせる美人です。裸になった彼女の下腹部には大きな傷跡があります。 第二次世界大戦のソビエトでは、50万人を超える女性兵士が従軍し、祖国防衛戦争を戦ったことは有名です。彼女たちは兵士として「英雄」ですが、女性としては最前線の男性兵士の慰安婦であったという偏見から、復員後、ひどい差別の対象であったことがスベトラーナ・アレクシエービッチの「戦争は女の顔をしていない」(岩波現代文庫)を読めばわかります。 この映画は、戦場の現実の中で、人間であることの条件を失ったり、奪われたりした二人の女性の悲劇を描いていました。 この上なく残酷で、哀切で、辛い展開の作品でした。映画の前半、イーヤは繰り返し襲ってくる意識喪失の発作の中で、そこまで可愛がっていた幼いパーシュカ少年を殺してしまいます。そこから映画は、原作の深部へと降りていくかのように、監督のインスピレーションの世界へと展開し始めるように感じました。 この映画には戦場のシーンは全く出てきません。まあ、戦後の話ではあるのですが、そこが俊逸だと思ったのですが、戦場を想起させるのは、今、目の前にいる、壊された人間であり、見捨てられた女性である二人の登場人物の姿と、病院にいる傷痍軍人たちだけです。 たとえばPTSDという言葉を、わかったふうに使う風潮があります。しかし、戦争や暴力や災害によって壊されてしまった人間も、また、生きていく他に方法がないという現実については、PTSDとい言葉や、現象についていくら勉強しからといっても、わかるわけではありません。 笑うことを失ったイーヤも、薄ら笑いで人を見るマーシャも、彼女たちが帰ってきた平和な世界からは、結局、見捨てられているのではないか、映画は、そう問いかけていました。 スベトラーナ・アレクシエービッチの原作が対比した「戦争」と「女の顔」を、「世界」と「女」の対比へと深化させてみせたカンテミール・バラーゴフという監督に拍手!ですね。これは、明らかに現代の映画でした。 で、やはり二人の女性、イーヤとマーシャを演じたビクトリア・ミロシニチェンコとバシリサ・ペレリギナに拍手!です。二人の表情のやり取りは、実にスリリングで、人間の意識の深層を、顔の表面、多分目の表情に浮かびあがらせながら、実は真相(本当のこと)と言いながら空虚なのではないか、空っぽなのではないか、という不安を感じさせる演技で、撮影技術だけではこうはいかないと感じさせてくれました。 まあ、それにしても。暗くて切ない映画でしたね。疲れました(笑)。監督 カンテミール・バラーゴフ製作 アレクサンドル・ロドニャンスキー セルゲイ・メルクモフ原案 スベトラーナ・アレクシエービチ脚本 カンテミール・バラーゴフ アレクサンドル・チェレホフ撮影 クセニア・セレダ音楽 エフゲニー・ガルペリンキャストビクトリア・ミロシニチェンコ(イーヤ)バシリサ・ペレリギナ(マーシャ)アンドレイ・バイコフ(ニコライ・イワノヴィッチ院長)クセニヤ・クテポワ(リュボーフィ)イーゴリ・シローコ(フサーシャ)コンスタンチン・バラキレフ(ステパン)ティモフェイ・グラスコフ(パーシュカ)2019年・137分・PG12・ロシア原題「Dylda」(ロシア語)「Beanpole」(英語)2022・08・02・no96 シネ・リーブル神戸no162
2022.08.17
コメント(0)
-

徘徊日記 2022年7月26日(火)大日霊女(おおひるめ)神社 阪神深江あたり
大日霊女(おおひるめ)神社 徘徊日記 2022年7月26日(火)阪神深江あたり 芦屋の朝日ヶ丘から歩き始めて、芦屋川を下り、海沿いの道から深江の埋め立て地を見ながらよたよた歩いて、阪神深江駅あたりに到着しました。 なんだか、不思議なクリーム色の鳥居のお宮さんがありました。大日霊女(おおひるめ)神社というそうです。もう6時を過ぎています。写真が暗いのはしようがないですね。 本殿の柱もみんなクリーム色で、真新しい感じです。境内は、どことも同じですね。駐車場です。お祀りかなんかあったのでしょうか、テントが張られていました。 境内に立札がありました。深江越えれば大日(おおひる)如来高い高橋 踊り松銚子が池に片葉葦 観光案内ですかね。江戸時代位の旅人用の歌謡のような気がします。後ろの石碑は西国浜街道の碑です。ちなみに西国街道というのは京都から西に下る山崎街道(淀川の右岸道路)の続きですが、西宮でバトン・タッチして下関(?)まで続きますが、芦屋の打出から山側の道を西国街道、海側の道を西国浜街道と呼んで、三宮の生田神社まで並行してありますね。 神戸の東部の街の海沿い、国道2号線より南を歩いているとよく出くわす石碑です。まあ、よく出くわすので、ちゃんと写真をとり損ねているわけですね(笑)。ああ、西国街道の石碑は明石あたりでも見かけます。 はい、神社に来たらこの方たちです。「阿」くんです。目がかわいらしいというか、機嫌が悪そうというか。 「吽」くんです。キバが邪魔そうですね。 神社の縁起の看板です。けっこう古い、地元の神社のようです。最近、いわゆる新興宗教というか、インチキ宗教が話題なので、ひょっとしてと思いましたが違うようです。 阪神深江の駅に到着しました。実際は5,6キロくらいなのでしょうが、けっこう歩いた達成感がありますね。振り向くと入道雲に夕日がさしていました。 なかなかな夏の午後でした。久しぶりに阪神電車で借ります。じゃあ、またね。バイバイ。追記2022・08・16この日の写真の追記です。芦屋川の河口付近からの風景です。阪神高速湾岸線が芦屋浜の南の新しい埋め立て地と、この右側、深江浜の埋め立て地をつないでいます。 こっちが深江浜の風景。この埋め立て地は、たぶん、ポート・アイランドより古いですね。県立東灘高校とかあります。神戸商船大学(今は神大の海事)もこの近くですが、ここに渡る深江南町側の海沿いですね。 この日の徘徊でよく出会った街路樹(?)です。多分トネリコの一種だと思いますが、ちょうど満開でした。 というわけで、せっかくなので、写真を追記しました。ボタン押してね!
2022.08.16
コメント(0)
-

ブラッド・ファーマン「L.A.コールドケース」シネ・リーブル神戸no161
ブラッド・ファーマン「L.A.コールドケース」シネ・リーブル神戸 昨秋だったでしょうか、映画「MINAMATA」での七変化ぶりに感心したジョニー・デップという俳優さんが気になって見に来ました。相方のフォレスト・ウィティカーという俳優さんも有名な方らしいのですが、ぼくは知りませんでした。 90年代にロサンゼルスで起こった事件をネタにした映画でした。人気のラッパーであった「2パック」という人と「ノートリアス・B.I.G」という二人のミュージシャン.が殺害されたらしいのですが、未解決のまま放置されているという事件の映画化でした。 ジョニー・デップ演じるラッセル・プール元刑事と新聞記者ジャック(フォレスト・ウィテカー)というお二人の渋い演技で物語の輪郭は割合くっきりしているのですが、なにせ18年前の事件の謎を追うのですから、画面にはプール元刑事の記憶の中にある「複数の現在」が映し出されていって、それが、まずややこしいうえに、事件は事件で、複数の登場人物による複数の現場、複数の時間の映像が重ねられていくわけで、見ていて訝しいことこの上ない印象の作品でした。 まあ、進行役というか、客観的な視点の持ち主である新聞記者ジャックがプール元刑事の推理を理解していくのに合わせて、見ているぼくも、なんとなく真相の方向性をつかめるという仕組みの映画でした。 で、帰ってきて、この事件が未解決のまま、今でも放置されているうえに、この映画の公開を巡って、何らかの、政治的妨害まであった! らしいことを知って、愕然としました。 映画の終盤、プール元刑事とジャック記者は、事件の真相のカギである捜査記録の公開を要求しますが「捜査中の事件の証拠」は公開できないという壁にぶつかってしまう上に、真相を究明していたプール元刑事が心臓まひで急死してしまう(実話だからしようがない)という、クライム・サスペンスとしては、いかにも、アンチ・クライマックスな結末なのですが、実は、そういう終わり方の中に、現実社会に対する批判が凝集されていた、つまりは、クライマックスだったのですね。 最近、お葬式が話題になっているアベ某の悪事について、情報開示が拒否されたり、公開される情報が黒塗りだったり、「ホント、ようやるわ💢」 ということが、ニッポンという国でもありましたが、この映画でも、チンピラの悪(ワル)たちは名指しで指弾されていますが、権力の中枢に隠れている巨悪、腐敗については「におい」だけしか表現できていません。つまりは、この作品は、そういう構造そのものを描いていて、映画そのもののわかりにくさの理由も、公開に妨害が入るということの理由もそこに起因しているということなのでしょうね。 監督であるブラッド・ファーマンやジョニー・デップとフォレスト・ウィテカーといった人たちは、ロサンゼルス市警内部なのか、アメリカの政治中枢なのか、正体ははっきりしませんが、そこに「ウソ」が存在することを告知して見せているわけで、ある意味、命がけの演技なのですね。そこはやっぱり拍手!ですね。 権力の構造的腐敗が、トカゲのしっぽ切りで批判をそらし、法律の悪用で真実を隠ぺいする、それをマスコミが無批判に唱和する、構造的な「マインド・コントロール」が世界中を覆っているのが現実かもしれません。 まあ、幻想かもしれませんが、こういう映画をまじめに作るところにアメリカの健全さを感じました。 監督 ブラッド・ファーマン原作 ランドール・サリバン脚本 クリスチャン・コントレラス撮影 モニカ・レンチェフスカ美術 クレイ・グリフィス衣装 デニス・ウィンゲイト編集 レオ・トロンベッタ音楽 クリス・ハジアンキャストジョニー・デップ(ラッセル・プール)フォレスト・ウィテカー(新聞記者ジャック)トビー・ハスデイトン・キャリーシェー・ウィガムニール・ブラウン・Jr.シャミア・アンダーソンマイケル・パレザンダー・バークレイローレンス・メイソンルイス・ハーサムジャマール・ウーラードアミン・ジョセフ2018年・112分・G・アメリカ・イギリス合作原題「City of Lies」2022・08・10・no97・シネ・リーブル神戸no161
2022.08.15
コメント(0)
-

ドゥニ・ビルヌーブ「灼熱の魂」シネ・リーブル神戸no160
ドゥニ・ビルヌーブ「灼熱の魂」シネ・リーブル神戸 予告編を見ていて「エッ?」と思いました。主人公らしい女性に見覚えがありました。「一年ほど前に見たモロッコの町で、パンをこねていたおばさんじゃないか。」 見終えて、再確認しました。マリヤム・トゥザニという監督の「モロッコ、彼女たちの朝」という作品でパン屋を営んでいた未亡人アブラを演じていたルブナ・アザバルという女優さんでした。 で、今日の映画はリドリー・スコット監督の「ブレードランナー」の続編や「砂の惑星」なんていうSF(?)を撮って評判らしいドゥニ・ビルヌーブという監督の出世作「灼熱の魂」、まあ、邦題が「ちょっと、あんたねえ」なのですが、原題は「Incendies」、直訳なら「火事」でしょうか。原作の戯曲があるらしく、その邦訳は「やけこげる魂」だそうで、そっちは理解できますが、映画のチラシのように「灼熱」という熟語を当てると、語感が内容にそぐわないと思ったのですが、まあ、その映画を見ました。 なるほど、出世作というだけありました。ドゥニ・ビルヌーブという監督の才能を感じました。 カナダに住んでいる、まだ、50歳半ばくらいでしょうか、老年に差し掛かった女性ナワル・マルワン(ルブナ・アザバル)がなくなって、大学生くらいの年齢の二人の子ども、女性がジャンヌ・マルワン(メリッサ・デゾルモー=プーラン)と男性がシモン・マルワン(マキシム・ゴーデット)の双子のようですが、公証人(レミー・ジラール)から遺書を受け取るところから映画は始まります。「父」と「兄」を探せ、探し出したうえで、二人宛の遺書を開封せよ。 まあ、そういう指示が書き残されていて、二人が「母の人生」をたどりかえすというお話でした。 母が生まれたのは中東のどこかの田舎の村で、キリスト教系の住民とイスラム経系の住民が、互いを敵として戦っている地域という設定です。地名や学校名は出てきますが、架空の場所のようです。 で、その村のキリスト教の住民の家に育ったナワル・マルワンという娘が、異教徒の難民と恋に落ち、駆け落ちしようとしますが、兄弟に発見され、恋人はその場で射殺されますが、娘は、祖母の助けもあり、身籠っていた一人目の子どもを生み落とします。そこから、この娘が、どんな経緯で村を出て、その後、何があって、結果的に、二人の子供を連れて、どうしてカナダくんだりまでやってきたのかというのが、二人の子供がたどった母の人生の謎ときでした。 が、まあ、ちょっとネタバレですが、母の人生の謎を追っていた二人は、やがて、自分たち自身の出生の秘密、父、母、兄、そして二人の双子という家族の秘密にまでたどり着きます。 秘密の謎を解くカギは、ジャンヌ・マルワンが大学で研究している数学者オイラーの方程式にありました。 映画が始まって、ジャンヌのキャラクター紹介のように提示されたこの方程式を見て「謎」の見当がつく人が、実際にいるのかどうか、ぼくには想像できませんが、後半に入ったあたりで、三人の子どもを生んだナワル・マルワンは、実はアンティゴネーを生んだイオカステーではないのかという予感は、フト、きざしました。 映画の始まりの母からの遺言「父と兄を探せ」がジャンヌ=アンティゴネーに与えられたヒントじゃないかという予感です。では、じゃあ、オイディプス王は誰なのかというわけですが、ここまででも、ちょっとバラし過ぎている気もします。どうぞ、作品をご覧ください。なかなかスリリングですよ。 この映画の物語を支えているのが有名な数式とあまりにも有名なギリシア悲劇というところは、まあ、ぼくとしては好みですし、面白いのですが、ちょっと話が作られ過ぎているきらいがあるところが引っかかりました。 しかし、岩と砂の山岳地帯の風景があり、その谷間の底を走るバスを俯瞰したパレスチナの風景と、ただ、ただ、何の躊躇もなく人が殺される殺伐たるテロルの光景には息をのみました。それだけでもすごい映画だと思います。 悲惨で過酷な人生を生きながら、「母」であり、最期まで、子どもたちに「愛」を伝えようとした、女性ナワル・マルワンを演じたルブナ・アザバルに拍手!でした。 監督 ドゥニ・ビルヌーブ原作 ワジディ・ムアワッド脚本 ドゥニ・ビルヌーブ撮影 アンドレ・チュルパン美術 アンドレ=リン・ボパルラン衣装 ソフィー・ルフェーブル編集 モニック・ダルトンヌ音楽 グレゴワール・エッツェル挿入歌 レディオヘッドキャストルブナ・アザバル(ナワル・マルワン)メリッサ・デゾルモー=プーラン(ジャンヌ・マルワン)マキシム・ゴーデット(シモン・マルワン)レミー・ジラール(公証人ルベル)2010年・131分・PG12・カナダ・フランス合作原題「Incendies」日本初公開2011年12月17日2022・08・12・no98・シネ・リーブル神戸no160
2022.08.14
コメント(0)
-

ベランダだより 2022年8月4日(木)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年8月4日(木)「朝顔日記」8月4日のアサガオ 今日は青い花が咲いていました。足元だったので、ちょっとポーズを決めた角度で撮れました。ピンクの花と揃ったところがうまく撮れないのが残念ですが「まあ、いいか。」です。 十個以上咲いていて、色も三色揃っています。青い花はいつものように天井近くで上を向いています。朝から良いお天気で、なんというか、暑さは盛りです。 「おーい、こっちむいて!」 声に出して呼びかけても知らんぷりです。 外向いている赤い花の後姿です。夏休みの真ん中くらいですが、ここのところ、前の広場で子供たちの声がしません。我が家のチビラ君たちが全員コロナに掴まったという便りがあっち、こっちの愉快な仲間から届いて、気を揉んでいます。子供たちのことも心配ですが、大人たちのことも気にかかります。 上に載せた青い花とピンクの花のセットです。ほかにもピンク色の花は咲いていましたが、撮った写真がみんなピンボケでした(笑)。 外を見ている花の正面から姿を、何とか撮ろうと、朝っぱらからベランダの柵に身を乗り出してスマホを構えている老人を見かけた人は何と思うのでしょうね。 彼女が物思いにふけって頭を載せているベランダの手すりは、まだ8時過ぎですが、もうかなり熱いのです。そんなふうにしていると、あっという間にしおれてしまうと思うのですが、毎日、こういうポーズの花があるのは不思議ですね。 正面から、赤い花を撮ると輪郭がわからなくなります。ボーっと赤い色が花全体にひろがって見える写真になります。まあ、その補正の仕方がよく分からないのですね(笑) 光の加減といい、色の加減といい、スマホのカメラは難しいというか、面白いというか、ですね。 じゃあ、また、明日、覗いてみてください。ボタン押してね!
2022.08.13
コメント(0)
-

ベランダだより 2022年8月3日(水)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年8月3日(水)「朝顔日記」8月3日のアサガオ 朝起きて、ベランダを覗きます。毎日の日課です。おや、今日はさみしいですね。 上から青い花が二つ。でも青い花だから、ちょっと嬉しい。 それから、風に揺らぐ赤い花が一つ。青空が背景で写っているのが嬉しい。カメラの光の加減で、持ったようには写りません(笑) ピンクの花がじゃれあっているように見えますが、風の仕業です。色は三とおり咲いてくれましたが、数は五つですかね。 いつまで咲いてくれるのかわかりませんが、まだ終わりではないと思いますよ。今日はこれでおしまい。ボタン押してね!
2022.08.12
コメント(0)
-

森井勇佑「こちらあみ子」元町映画館no141
森井勇佑「こちらあみ子」元町映画館 今日は元町映画館で二本立てでした。もっとも、見たのはポスターにある「教育と愛国」、「こちらあみ子」のセットではなく、「歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡」と「こちらあみ子」のセットでした。 今村夏子の小説「こちらあみ子」は、うまくいえないのですが、数年前に初めて読んで強く打たれた記憶がある作品でした。「そうだよな、そういう人間の在り方ってあるよな。でも、人というのは、そういう在り方のことを説明してしまうんだよな。この小説は、説明しないで、あみ子がここにいると書いた、書くことは説明の始まりだけど、なるべく説明にならないように描いたところがすごいんだよな。だから、誰かにこの小説はね・・・と始めると、伝わらないんだよな。」 まあ、こんな感想を持ちました。例えば、とっぴな例で申し訳ないのですが、ドン・キホーテなんていう人物は、あくまでも小説世界の人物だから、あれだけ輝くと思うのですが、現実の中に置いてしまうと、ただの困った人になりかねません。私見ですが、映画というのは、リアリズムで見ると、現実と見分けがつかないわけで、「そこに小説世界の人物をおいてしまうと・・・?」という危惧を感じながらですが、映画になったというので見に来ました。 「うまくいかないだろうな」の予想の通り、うまくいっていないと思いました。あみ子が生まれてくる前に死んだ弟の墓を楽しそうに作ります。それを見て、流産した母親が泣きます。素直だった兄がグレます。父親があみ子を遠ざけるようになり、あみ子を祖母のもとに預けます。あみ子の社会性の未熟さと、それについていけない家族の崩壊と子捨てのプロセス、小説の展開を映像化すればそうなるのですが、それでは、小説の中で「こちらあみ子」と電池が切れているかもしれないトランシーバーで呼びかけてきたあみ子に、映画は応答したことにはならないのではないでしょうか。 最後のシーンで大丈夫じゃ! と言わせる映画製作者、森井監督は、何とかあみ子の存在を肯定しようとしているように見えますが、あみ子が求めているのは、同じ場所からの応答! であって、彼女に対する肯定や否定の判断や存在のありように対する大人の理解などではないのではないでしょうか。 じっと耳を澄ませて、あみ子の声を聴く場所 に、なんとか読者を引き留めた今村夏子は、この作品を見て納得するのでしょうか? 製作者も俳優も真摯に取り組んでいることは間違いありません。あみ子を演じた大沢一菜という子役の演技にも感心しました。しかし、こちら側から描けば描くほどあみ子は遠ざけられてしまい、あるいは、隔離されてしまい、あるいは、捨てられてしまう。 うまく言えないのですが、そこのところにどうしても違和感が残った作品でした。やっぱり、拍手はしません!監督・脚本 森井勇佑原作 今村夏子撮影 岩永洋編集 早野亮音楽 青葉市子主題歌 青葉市子キャスト大沢一菜(あみ子)井浦新(お父さん・哲郎)尾野真千子(お母さん・さゆり)2022年・104分・G・日本2022・07・22-no92・元町映画館no141
2022.08.11
コメント(0)
-

徘徊日記 2022年7月26日 「芦屋川を下りました!」
「芦屋川を下りました!」徘徊日記 2022年7月26日 芦屋あたり 朝日ヶ丘から歩いてきて、芦屋川に到着しました。見えているのは芦屋ルナ・ホールです。確か学生の頃に出来て、何度かお芝居を見に来たことがあります。まあ、他の町なら市民会館とか文化ホールというところですが、芦屋はルナ・ホール(笑)。 しばらく佇んで「久しぶりに阪急で三宮まで帰ろうかな・・・」 とか、考えたりしながらなのですが「そういえば河口まで歩いたことがないな。村上春樹が猫を捨てに行ったとかいってたし。ちょっと行ってみようか。」 とか思いついてしまったわけで、南に向かってスタートしてしまいました。 この時に立っているところは、丁度、JR東海道線の線路が川の下を通過している地点です。 ずっと下流に見えるのが業平橋です。業平って、あの、男前の業平です。他にも、打出の小槌町とか、親王塚町とか、親王というのはもちろん業平のお父さん阿保親王ですね。芦屋にはなかなかな町の名前が残っています。で、その橋も渡ったのですが、写真を撮り忘れて、阪神の芦屋駅まで下ってきました。 これは下流からの写真ですが、ちょうど電車が止まっているようです。この駅は芦屋川の上にあります。ホームの下が芦屋川です。向うの山は六甲山です。 こんな感じです。電車に乗っているときは川の上で停車するのが嬉しいのですが、こうしてみてもたいしたことではないですね(笑)。 で、阪神の駅のすぐ南にあるのがこれです。 芦屋市役所です。前の広場で休憩しました。夕暮れ時でしたが、花壇の周りのベンチにはかなりの方が休憩中でした。ぼく自身は、結構疲れていて、モニュメントの写真を撮るのを全く忘れていました。 芦屋役所の南側には、名門中の名門のテニスコートや公園がありますが、川沿いに南を見れば、ようやく河口が見えてきました。 左側の松林が公園です。芦屋公園というのでしょうかね。松林の公園です。 これは、阪神大震災のモニュメント。赤いのは夕日の反射です。もう、午後6時を過ぎていますが、まだ明るいので、もう少し歩きます。 公園の、松林です。芦屋といえば松並木ですかね。 日中友好の記念碑のようです。今では、悪くいうのがはやりのようですが、国交回復を喜んだ、戦後の二つの国の歩みを忘れて煽るのはやめてほしいなという気もします。 で、ここから右岸に渡って河口まで歩きましたが、大誤算でした。高潮ようなんでしょうか、岸壁が高くて海が見えません。 河口あたりから100メートルばかり西に歩いて岩壁によじ登って撮った写真です。手前の防波堤沿いはテトラで防護されていて、向うに見えるのが芦屋浜のニュータウンです。写真を撮っているこの場所は、もう、深江浜というべきでしょうか。 芦屋川の河口に行きたかったのですが、なんか違いますねえ。村上春樹がどうのなんて、なんの関係もない海岸でした。 年を感じるの、防波堤によじ登るとかいう動作をやむなくするときです。以前ならひょいひょいだったことが、脛をすりむいて・・・ということになります(笑) 向こうに見えるのが芦屋浜の沖に新しくかかっている阪神高速の湾岸線の高架橋です。まあ、夕暮れの空が、思いのほか美しかったのでよしとするのですが、さてここからどこに行けばいいのでしょうね。ボタン押してね!
2022.08.10
コメント(0)
-

ベランダだより 2022年8月2日(火)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年8月2日(火)「朝顔日記」8月2日のアサガオ カメラも光の加減でこんな写真です。夕方とかではありません。面白がって載せています。花の色はピンクです。 朝、部屋から見た全景はいつものようにこんな雰囲気です。 天井近くに青い花が咲いているのはいつもと同じです。下から見上げて撮りました。 こちらは植木鉢からすぐの足元のところにノンビリ咲いている赤い花です。で、下の写真ですが、花芯というかおしべとかめしべがあるところに何かいるのがおわかりでしょうか? 次の下の写真はベつの花なのですが、この花にも何かいますね。ゴミではありません。実はミツバチがもぐり込んでいるのです。今日の花の写真を撮り始めたときに、顔の前をブンブン飛び回って、どうするのかと見ていると、花びらから花の芯に入っていってしまったのですが、これを写真に撮るというのは至難の技ですね。 今度は、出てきたところをとろうと、待ち構えていたのですがシャッターが間に合わないうちに飛び去ってしまいました。こういう時にビデオ機能が使えれば撮れていたのでしょうね。ザンネンながら、シマクマ君は、まだスマホのビデオ機能が使いこなせていません。 まあ、そのうち、ブログにもビデオ映像を投稿できるようにおなるときも来るのでしょうが、今はシャッター速度をいじったり、ズーム機能をいじるので精一杯ですね。 というわけで、ミツバチ相手にオタオタしましたが、肝心の姿を写真に収めることはできないまま、今日も天気の良い夏の一日が始まりました。 それにしても暑い日が続きますねえ(笑)。ボタン押してね!
2022.08.09
コメント(0)
-

週刊 読書案内 幸田文「おとうと」(新潮文庫)
100days100bookcovers no79 79日目幸田文「おとうと」(新潮文庫) DEGUTIさんが78日目、池内了の「物理学と神」を紹介されて、あっという間に三週間たってしまいました。語呂合わせで、すぐに思いついたのが養老孟司の「カミとヒトの解剖学」(ちくま学芸文庫)でした。 ちなみに、養老先生のご本は「ヒトの見方」「からだの見方」(それぞれ、ちくま文庫)から「唯脳論」(ちくま学芸文庫)、で、それらをまとめた趣の「カミとヒトの解剖学」(ちくま学芸文庫)、応用編の「身体の文学史」(新潮文庫)あたりまで、今でも面白いですね。最近では、亡くなった、ネコの「まる」の話や「虫」の話も書籍化されていますが、「考える人」(新潮社)に連載されていた「身体巡礼」・「骸骨巡礼」(ともに新潮文庫)が養老解剖学・身体論・歴史学の、最後のフィールドワークを思わせる好著だと思いました。写真も文章も素晴らしいと思います。 と、まあ、こんなふうに薀蓄を垂れるつもりだったのですが、「アメン父」(田中小実昌)から「神様」(川上弘美)、「物理学と神」(池内了)ときて、「ああ、またカミかよ!」と、ふと、気づいてしまった結果、「なんだかなあ…」という気分に襲われてしまって、とりあえず没にして、考え直しです。 で、思いついたのが幸田文「おとうと」(新潮文庫)というわけです。池内了って、池内兄弟の弟でしょ(笑)。 皆さんがよくご存知であるに違いない幸田文についてあれこれ言うのは、ちょっと気が引けますが、幸田露伴の娘、これまた名随筆「小石川の家」(講談社文庫)の青木玉の母で、その娘でエッセイスト(?)の青木菜緒が孫ということです。 幸田文は、一度は結婚したようですが、娘(たま)を連れて離婚し、父露伴の元で暮らしたひとです。1947年の父露伴の死後、父の身辺や自らの思い出を書いた随筆家として評判をとりますが、1955年「流れる」(新潮文庫)で新潮文学賞・芸術院賞を受け小説家として再デビューし、婦人公論に連載された「おとうと」(新潮文庫)は、小説としては2作目の作品のようです。 「げん」という女学校の学生とその三歳下の弟碧郎が、文筆家である父と、実母の死後、父が再婚した義理の母と暮らす日常が描かれている、おそらく作家の実生活をモデルに書かれたであろうと思われる作品です。 書き出しはこんな感じです。 太い川がながれている。川に沿って葉桜の土手が長く道をのべている。こまかい雨が川面にも桜の葉にも土手の砂利にも音もなく降りかかっている。ときどき川のほうから微かに風を吹き上げてくるので、雨と葉っぱは煽られて斜になるが、すぐ又まっすぐになる。ずっと見通すどてには点々と傘(からかさ)・洋傘(こうもり)が続いて、みな向こうむきに行く。朝はまだ早く、通学の学生と勤め人が村から町へ向けて出かけていくのである。(P5) 文庫版巻末の解説で、今となっては懐かしい文芸批評家、篠田一士が「思わず嘆声の出るような、素晴らしい描写である」と、ベタ褒めですが、続けてこんなことを言っています。 太い川が隅田川で、この土手が向島の土手でというような詮議はどうでもよろしい。いや、どうでもよろしいというよりも、読者にそういうことを決して許さないような文章の書き方がしてあるのだ。表面上は観察がよく行き届いたリアリスティックな描写をほどこしながら、その内側には、あえて童話的といってもいいほど、現実離れした、なつかしい情緒がなみなみと湛えられているのだ。だから、読者がもし現実還元したければ、わざわざ手元に東京地図など引き寄せる必要はなく、おのがじし、心の中に眠っているはずの、あの川や土手、さらに、あの四月の雨の朝の感覚を思い出せばいい。(P231) もう破格ですね。現在、どなたかの作品をこんなふうにほめることのできる批評家っているのかどうか、なんだか、幸せな時代を感じさせる批評です。 ぼくは、この作品を学生時代に読んで以来、その後、幸田文の作品群は評判に誘われてかなり読みました。で、結局そのなかで、この作品が一番好きです。 たとえば、上の引用の少し先はこんなふうな描写が続きます。 一町ほど先に、ことし中学に上がったばかりの弟が紺の制服の背中を見せて、これも早足にとっとと行く。新入生の少し長すぎる上著(うわぎ)へ、まだ手垢ずれていない白ズックの鞄吊りがはすにかかって、弟は傘なしで濡れている。腰のポケットへ手をつっこみ、上体をいくらか倒して、がむしゃらに歩いて行くのだが、その後ろ姿には、ねえさんにおいつかれちゃやりきれないと書いてある。げんはそれがなぜか承知している。弟は腹をたたているし癇癪お納めかねているし、そして情けなさを我慢して濡れて歩いているのだ。なまじっか姉になど優しくしてもらいたくないのだ。腹立ちっぽいものはかならずきかん気屋なのだ、きかん気のくせに弱虫に決まっている。― 碧郎のばかめ、おこらずになみに歩いて行け、と云いたいのだが、まさか大声を出すわけにもいかないから、その分大股にしてせっせと追いつこうとするのだが、弟はそれを知っていて、やけにぐいぐいと長ずぼんの脚をのばしている。げんも傘なしにひとしく濡れていた。だってそんなに急げば、たとえ傘はさしていても、まるでこちらから雨へつきあたって行くようなものだからだ。左手に持った教科書の包みも木綿の合羽の袖も、合羽からはみ出た袴の裾も、こまかい雨にじっとりと濡れていた。追いついて蛇の目を半分かけてやりたかった。(P6) いくらでも書き写すことができますが、これくらいにした方がいいでしょうね。ここまで、読みづらいスマホやPCの画面の文字を追って来てくれた人は、この後、どんなふうにこの少女が語り続けるのか、部屋のどこかの棚にこの文庫本はなかったのかと気がせくに違いないだろうというのがぼくの目論見ですが、そこは、まあ、人それぞれです。 ぼく自身は、今回読み直して、何故、一番好きだと思い込んでいたのか、その理由がはっきりわかりました。ぼくが「おとうと」だからですね。 篠田一士が「心の中に眠っているあの感覚」といっていますが、この作品は冒頭の数ページに限らず、読者自身の心の中に眠っている、懐かしくて、ちょっと哀しい感覚を掘り起こす力があるのではないでしょうか。 ところで、幸田文がこの作品を書いたのは、実は50歳を過ぎてからです。もしも、この作品が私小説的な実生活のモデル化の上に成り立っているとしても、30年以上も昔の出来事です。作品は、作家の記憶の世界というよりも、暮らした世界や家族に対する喜びや悲しみが作り出した作家の「こころの世界」の真実の描写だったのではないでしょうか。 ぼくには市川崑の映画のかすかな記憶がありますが、この作品を「原作」として何度も映像化されたことは、皆さんの方がよくご存じなのかもしれません。今回読み直してみて、なるほど、映像化したがる感じはよく分かるのですが、過去の記憶をたどって書いているはずなのですが、あくまでもシャキシャキとした文体で、だからこそでしょうか、どこから読んでも、ある懐かしさを喚起するのはやはり文章の力であって、そこを映像化するのは実はかなり難しいことではないかと感じました。幸田文さん、読み直して損はないと思うのですが、いかがでしょう。それではYAMAMOTOさん、次回よろしくね。2021・12・21・SIMAKUMAKUN追記2024・05・04 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。
2022.08.09
コメント(0)
-

ベランダだより 2022年8月1日(月)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年8月1日(月)「朝顔日記」8月1日のアサガオ 今日から月がかわって8月です。今日は最初に部屋から覗いたときの全景から載せてみます。数は数え忘れましたが、満開!です。 高いところに青い花が咲いています。偶然、青い花の蔓のそのあたりに蕾がつきやすいというにすぎないと思いますが、丁度写しごろの位置では咲いてくれません。 洗濯の竿あたりの高さに咲いている赤い花です。そういえば、アサガオが咲きはじめたころから、こちらの差には洗濯物があまり干されません。アサガオにつるべとられてもらい水 加賀千代女 あんまり有名すぎて、面白くありませんね(笑) これは、ベランダの手すりくらいの高さに咲いている花です。 この高さだと、こんなふうにアップ写真も撮れるのですが、上の方は無理ですね。 一番上の青い花をズームして撮って見ましたが、ピントが怪しいですね。 ベランダから二人で顔を出すようにして咲いていた赤い花を身をのり出して撮ってみました。風が吹いてきて萎れたように写っていますが、そういうわけではありません(笑) 8月となれば、旧暦ならずとも、「そろそろ秋かも」と期待する猛暑の日々ですが、暑さもコロナも収まりそうにない2022年の8月です。 夏の始まりに起こった殺人事件と、それに伴って正体を晒しつつあるインチキな人たちや、インチキなメディアの暑苦しさが追い打ちをかけ続けていますが、歴史に残る「夏」になるのでしょうかね?ボタン押してね!
2022.08.08
コメント(0)
-

週刊 読書案内 池内了『物理学と神』集英社新書
100days100bookcovers no78(78日目)池内了『物理学と神』集英社新書 川上弘美の『神様』というKOBAYASIさんからのバトンは10月21日に受け取りましたが、あいかわらず遅れていてすみません。仕事を一つを片付けられたと思ったら、風邪をひいてしまい、いつまでも治らなくてぐずぐずしています。本はすぐに決めたのですが、読み直していても、老化でなかなか頭がついていかなくなってて、読むだけでも時間がかかってしまいました。 以前、村山斉の『宇宙は何でできているのか』のあとに続く本として、『幼年期の終わり』にするか、これにするか迷ったのですが、あのとき選べなかったこの本を今回取り上げることにします。 池内 了 著 『物理学と神』集英社新書 2002年12月初版ですが、私が持っているのは2007年10月29日第15刷とありますから、随分増刷されたんですね。その上、今回初めて知りましたが、その後、2019年2月に講談社学術文庫で発行されているらしいです。その文庫も図書館から借りました。文庫版のあとがきには「思いがけなく多くの支持を得て集英社新書のロングセラーになった。しかし、さすがに10年を超すと手に取ってみる人も少なくなり、絶版の危機を迎えていた。基本的には物理学史の本であり、時代とともに古びる内容でもないので、このまま姿を消すのは残念だと思っていた。幸い、講談社学術文庫から声がかかり、その一冊に加えてもらえることになって喜んでいる。同文庫の一冊になれば長く読み継がれることが期待できるからだ。」 と、文庫化の経緯も書かれていました。私もこの本は残ってほしいと願っています。 手に入れた当時の本の帯には「神を拒絶したはずの物理学者は、実は神に踊らされているのかも……」 とあります。当時は小説を全然読まなくなって、それより、柳田理科雄の空想科学読本シリーズや「子どもの科学」や「ニュートン」などの雑誌やらサイエンス・エッセイの方が面白いと思っていました。そんなころですから、この帯の惹句はドンピシャで惹かれました。宇宙観の歴史がわかりやすく面白く書かれていました。文章がいいのですが、お兄さんはドイツ文学研究や翻訳で有名な池内紀です。物理学もドイツ語圏ってすごいですね。お二人とも、姫路西高校ご出身ですね。お互いいい影響を与え合う関係だったのでしょうか。姫路には歴史や文学や文化の厚みがあるのでしょうね。(池内紀の訳のおかげで『ファウスト』も読むことができましたし、カフカやゲーテについてのものも、温泉や散歩のエッセイもどれも落ち着いたユーモアのある筆致が好きでした。おととし亡くなられたのがとても残念です。) 以前はとてもおもしろいと思って手放さずにおいていた本ですが、実はほとんど消化(理解)できていないことが理解できて、いざ書くとなるとどうしようかと七転八倒しています。 現代は科学が宗教に取って代わった時代と言われ、物理学(自然科学)と神(宗教)は無関係なはずですが、ちょっと考えたら、ニュートンの万有引力やアインシュタインのエネルギーの公式が、ほとんどすべてのものに(量子は別)当てはまるのって、不思議で感動的で、私も神さまがいるのではないのと思ったことがあります。私は、人間社会も物理法則や生命現象のアナロジーとした方が腑に落ちるんです。つい、中二病的な類想が浮かんできます。―重力の大きい物ほど引っ張る力が強い→大きな資本が小さな資本を呑み込む経済現象。適者生存、自然淘汰。エントロピーは増大する→ものは必ず散らかる。重力から遠いほど位置エネルギーは大きい→高い所にいるものほど(権)力は大きいーなど、勝手に結び付けたりして遊んでいますが。 神と物理学を並べる狙いを筆者はあとがきに書いています。――(略)そもそもの意図は、歴史的に物理学者が「神」や「悪魔」をレトリックとして使って、物理法則の美しさを称えたり、難問を考え出したりしてきたことを、現代から逆照射して、その本来の意味が何であったかを考えてみようというものであった。机の上では唯物論者である物理学者だが、自然の摂理を解き明かしていくうちに、その絶妙な仕組みに感嘆して秘かに神の存在を仮想することがある。かくも美しい法則は神の御技でしかあり得ないだろう、と。あるいは、自らの審美眼と相容れない自然の姿に逢着すると、それを否定するために神を持ち出したりもする。厳密な論理を組み立てて得られた物理法則であれば、それを気に入らないと拒否するためには神に頼るしかないからだ。一神教の西洋に発した近代科学も、神と無縁であったわけではないのである。 そこで、物理学の歴史をたどりながら、それぞれの時代において物理学者が神の名を使って何を表現しようとしたかを提示してみようと考えた。―― また、物理学法則の特徴や概念を専門用語も数式も使わずに説明する手段として神や悪魔に仮託しようとの狙いだったと書いてもいます。そのおかげで、私も多少は、今までどんなことが問題とされてきたのかがわかりました。 筆者による「神の変遷史」を書いてみます。 第1期 17世紀の近代科学の夜明け 第1章 神の名による神の追放 この章あたりは、高校時代の倫理社会や古典物理学で習ったことの復習を兼ねて、ヨーロッパの自然科学が神の唯一絶対神の縛りをほどいて活気づくあたりのことなので、わかりやすくおもしろかったです。自然哲学の研究が始まったために、神が書いた二冊の書物―「自然」の仕組みと『聖書』の記述―が矛盾していることが発見された。天動説では、神は宇宙の中心の地球にあることが保証されていた。しかし、惑星の観察が進んでいくと、天動説では7つの星の運動を説明するためには、80を超える円運動を組み合わせなければならなくなった。星の観察が進み、さらに複雑で醜悪な理論が必要になるうちに、「神はもっと単純で美しい宇宙を創ったはず」、最小の仮定で最大の結果が得られる理論こそ美しいとの立場に立てば、地動説に移ることになった。そして、地球が宇宙の中心という特権的地位を失った時、唯一神が地球に在るという根拠もなくなってしまった。 コペルニクスの時代は、宇宙とは太陽系のことなので、神の座は宇宙の中心の太陽に据えるべきでしょうが、燃え盛る灼熱の太陽ではさすがの神も居心地が悪いだろうからと、コペルニクスは、神の居場所と宇宙体系とを切り離した。一方、ルター派やカルヴァン派は聖書に書かれていることが正しいと考え、天動説を主張し続けた。(そういえば、今も福音派の中にはそう考えるひともいると聞きます。) ガリレイが天の川が無数の「太陽」の集まりであることを発見して、宇宙は一挙に拡大することになった。そして、神はより広い星の世界全体を統括する存在になった。こうして、神は地上から追放されたが、折しも、地上の権力が教会から世俗領主に移ったのと時を一にしている。 ニュートンは1682年、宇宙は無限であると証明。もし、有限なら宇宙には中心と端があることになり、端のものは万有引力で中心に落下するから、宇宙は潰れてしまう。宇宙がつぶれることなく永遠に存在するためには、中心も端もない無限空間に星が散らばり、万有引力は互いに消し合っているに違いない。無限宇宙こそ完全なる神にふさわしいとした。 地動説、ガリレイの実験、デカルトの方法論など、近代科学の黎明期は、神が地上から追放され、神の名による干渉を受けずに自然研究が可能になった時代であった。 第2期 18世紀から19世紀末 神々の黄昏がゆっくり訪れた時期 第2章 神への挑戦―悪魔の反抗 第3章 神と悪魔の間―パラドックス この章では、神授された王権が衰退し、神のような永久機関と魔術のような錬金術も諦められた経緯がかかれていました。代わって、職業的科学者らがエネルギー保存則、エントロピー増大則を提唱します。その法則を宇宙にあてはめたら、宇宙は熱死することになると言い出す始末。また、宇宙に存在する星からの光をすべて足し上げると、太陽の明るさよりもっと明るくなって「夜空は明るい」ことになるはずとの謎も提出される。でも、この問題が解かれるはるか以前の1845年に、エドガー・アラン・ポーが『言葉の力』というエッセイで「宇宙には金の壁(ゴールデンウオール)があって、それより向こうの星の光は我々に到達しない」とか、1848年の詩論集『ユリイカ』で「あまりに宇宙が巨大であるため、光線が未だ到達し得ない領域がある」と述べたことが紹介されています。筆者はおそるべき詩人の直感と書いていますが、私もこのほうがなんとなく、なんとなくですが、イメージしやすいと思いました。 第3期 20世紀初頭、すべてを統括する神は退場し、新しい装いで再登場 第4章 神のサイコロ遊び マックス・プーランク、ニールス・ボーアの量子論、ハイゼンベルグの不確定性原理、アインシュタインの一般相対性原理の時代。このあたりはもう私にはお手上げですね。アインシュタインは最初、この確率論が気に入らなくて「神はサイコロ遊びをしない」と言ったそうです。でも、現在のIT機器は、不確定原理の量子論のおかげで機能しているんですってね。 また、ハッブルによって、宇宙が膨張していることが発見され、宇宙の熱死問題も解決された。宇宙空間は膨張し続けているので、星の廃熱を捨てられる場所もどんどん増えているんだそうです。そのかわりに、いつ、どんなふうに膨張が始まったのかが問題になってきたらしい。神が最初の一撃を加えたら膨張し始めてあとは傍観しているだけっていう説。ビッグバンですね。この説を揶揄して「ビッグバン(大きいバンって擬声音)みたい」と言われたがその通りという冗談のようなネーミングなんだそうです。 第4期 20世紀後半 神は本当に賭博が好き 第5章 神は賭博師 カオス論や複雑系が論じられる時代。この部分はレポートはパスします。「フラクタル」という自己相似的な現象についてのエピソードだけ紹介します。(例えば、木の太い幹から大きな枝へ、大きな枝から小さな枝にと次々分岐していくパターン。宇宙も、月が地球を回り、地球は太陽を、太陽系は銀河系を、銀河系はアンドロメダ銀河を回っている。割れたガラスの破片も似ていることが多い。) 寺田寅彦がちょっと出てきます。――かつて、寺田寅彦が興味を持ち(ガラスを何百枚も壊して破片の数分布を数えたとエッセイに書いている)、その弟子の平田森三(もりぞう)が専門としてさまざまに考察した(キリンのまだら模様と田んぼのひび割れた形の類似性に着目した)が、形を定量的に表現する方法が見つからなかったので、そのまま立ち消えになってしまった。フラクタル幾何学が提唱され、また空間分割や対称性の研究などが進んで、形の研究はようやく物理学の範疇に入ってきた段階と言える。―― ここで、最も古いフラクタル世界を表現したものとして、平安時代の曼陀羅図があげられているのが面白いです。世界は唯一神ではなく、八百万の神々が鎮座するという思想の表現ですね。この世をフラクタル世界なら、神は唯一ではなく、無限にどこにでも存在するという宗教観に移っていくのでしょうか。 第5期 現在 神はさまざまな危機に直面している 第6章 神は退場を!―人間原理の宇宙論「この宇宙はなぜ存在するのか」という問いに対し、神ではなく、人間にこそ答を得るための鍵があると主張する「人間原理」を唱える職業科学者(悪魔)が現れてきました。実際不思議なほど、この宇宙は人間に都合よくできているのだそうです。つまり、「この宇宙の主役は人間であって神ではない」と言えるそうです。著者は、この傲岸不遜な説には批判的ですね。 第7章 神は細部に宿りたもう 物理学の根本的矛盾を楽しんでいるような感じがします。 普遍的な平等世界を創る存在であったはずの神なのに、実は不平等な現実世界をもたらしている元凶であることが暴露されて、神への根底的不信感が芽生えてきた。神は、本来、対称(平等、一様、対等、普遍)な原理的世界を体現する存在であるはずなのに、この現実世界は対称性を破らねば創り出せない。「原理は対称、現実は非対称」なのだ。とすると、神は非対称(不平等、区別、差別、特殊)な現実世界を創ることに腐心してきたと考えざるを得ない。でなければ、人間も、神もこの世に生まれなかったことになる。自ら対称世界を具現しつつ、それを否定しなければ自らが存在しえない。神は大いなる矛盾に遭遇していると言えそうだ。 最近は経済物理学という分野もできているらしい。まだそのまま信用するわけにはいかないが、簡単な議論で本質的な部分を導き出すことはできる点が面白いと紹介している。 これから 神は姿を変えて再び立ち現れるだろう 第8章 神は老獪にして悪意を持たず 宇宙論の危機と言われているそうですが、当たり前。今のところ、人間は宇宙の地平線までの距離の300分の1しか観測できていないし、宇宙の95%の成分について、知らないまま。それなのに、わかったふうに、宇宙の年齢や構造を論じているそうです。著者はまだまだわからないことがいっぱいあることを楽しんでいるかのようです。 著者は、かつてBS-NHKの「フランケンシュタインの誘惑」という番組によく出ていて、科学や技術を持ち上げるような雰囲気のときには、水を差すような御意見番のような役回りをしておられましたね。日本の科学者の立場がどんどん苦しくなって研究費にも事欠いているとは思うのですが、選択と集中で研究費を獲得しやすい研究にも目を光らせなくてはとも思いました。湯川秀樹博士、益川敏英博士のように、社会の科学研究利用に厳しい視点を持たれていると感じました。 物理学はやっぱり手ごわかったです。自分で消化できないまま引用に頼ったので、お読みになりにくい点が多々あるかと思います。見える現実から離れて遠くの世界のことを思い浮かべ、これこそ現実なんだなって思うのは楽しい時間でした。クリストファー・ノーランの映画のいくつかのシーンがよく思い浮かんできました。 SIMAKUMAさんは、きっと読まれたことがおありかと思います。また、いろいろ教えてくださいね。今回の「人間原理」もYouTubeを参考にしました。家で大学の公開講座が見られるなんて、便利な時代になりましたね。お次をよろしくお願いします。2021・11・14・E・DEGUTI追記2024・05・03 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。
2022.08.07
コメント(0)
-

ベランダだより 2022年7月31日(日)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年7月31日(日)「朝顔日記」7月31日の夕顔 7月30日の日記で予告しましたが、夕顔が咲きました。実はこれは7月31日の夕方咲いた花で、30日の朝のつぼみの花は30日の夜に咲いてしまっていて、残念なことに写真を撮り損ねました。 角度を変えて、もう一枚なのですが、なんか構図が変ですねえ(笑)7月31日のアサガオ で、7月最後の日、31日のアサガオです。やっぱり赤い花ばかりで、七つ咲きました。 数が少ないので、一つづつポートレイトをと思いましたが、高いところの花はうまく写せません。 三つ揃ってそっぽを向いているような、勢ぞろいしてラッパでも吹いているような、昨日咲いて萎れた花があわれなようすですが、今日の花たちが「カンケーありませーん”!」という風情で咲いているのが、ちょっと面白いですね。 7月最後の美女というところです。まあ、アサガオとか見ていると、やっぱり浴衣から美しいくび筋がのぞいている女性を思い浮かべるシマクマ君なわけですが、色っぽいものですね。 咲きはじめた夕顔の白さとはまた違う美しさです。 7月の初めころから咲きはじめたアサガオが嬉しくて「朝顔日記」とか、小学生の夏休みの宿題の気分で始めましたが、今日でひと月経ちました。案外、息長く咲き続けるものですね。毎日変わり映えしない写真ばかりで、ちょっと飽きかけていたのですが、夕顔も咲いたりして、もう少し続けられそうです。 まあ、要するにヒマだということです(笑)ボタン押してね!
2022.08.06
コメント(0)
-

徘徊日記 2022年7月26日 「今日は芦屋です!」
「今日は芦屋です!」徘徊日記 2022年7月26日 今日はなぜか芦屋です。上の写真はJR芦屋駅前の広場です。近づいたことがありませんが、不思議なモニュメントもあります。某球団が定宿にしているらしい竹園ホテルもあります。 駅前から市バスに乗りました。市立芦屋病院前行ですが、目的地は市民プール前、朝日ケ丘町あたりです。このまま乗っていると甲南高校とかに行けるようです。ここから上というか、北には行ったことがありません。知人が勤めていたことを思い出しましたが、今日はここで降ります。 この写真とは反対の方角ですが、ちょっとお知り合いのおうちに寄ります。まあ、それが今日の芦屋行きのメインだったのです。 で、明るいうちにお暇(いとま)することになったので、先程の写真の道を西に歩きはじめました。 芦屋といえば松なのだそうですが、松並木です。並木ごしには海が見えます。ここはJR芦屋駅から1キロくらい北の高台です。 こちらの並木ごしには東側の高台が写っています。六麓荘とか、ぼくのような疎い人間でも知っている高級(?)住宅街はこちらのもう少し東です。 こちらの道は下り坂です。芦屋の山手は、まあ、あたりまえですが坂の町です。神戸市の岡本、御影の山手、阪急六甲あたりもそうですが、六甲山のふもとの町ですから、南に歩けば下り坂です。向うに見えるのがJRの芦屋あたりの市街です。 高台から下ってきて最初の線路が阪急の神戸線です。左に行けば、夙川、西宮北口、塚口、十三、梅田方面です。阪急電車の市内の駅は阪急芦屋川ですが、右にもう少し行ったところ、芦屋川より西です。 阪急の線路の高架の道路です。芦屋とは思えないひなびた感じがいいのですが、この高架をくぐって、まっすぐ南に歩けばJR芦屋駅ですが、今日は右に曲がって芦屋川まで歩いてみようと思っています。 芦屋川に向かって、さっきの高架の南から西に向かって歩く山手幹線沿いの街路樹です。百日紅が夕日に輝いていました。 芦屋川です。芦屋の街の西の境界です。この川の向こう側から神戸市です。上流すぐのとこに阪急芦屋川駅があります。村上春樹の小説の町です。まあ、そんなことをふと思い出して、朝日ヶ丘から歩いてきましたが、ここまでなら、大した距離ではありません。でもこの日は「そう言えば、村上春樹は河口まで猫を捨てに行ったんだよな。」とか思い浮かべてしまったんですよね。で、ここから河口まで歩くのですが、それな次回です。じゃあね。ボタン押してね!
2022.08.05
コメント(0)
-

パトリック・インバート「神々の山嶺」シネ・リーブル神戸no159
パトリック・インバート「神々の山嶺」シネ・リーブル神戸 フランスのパトリック・インバートという監督のアニメーション映画で、谷口ジローの同名のマンガ作品をアニメ化した作品ですが、夢枕獏の、もともとの原作は1998年に柴田錬三郎賞を取った山岳小説です。 で、その頃、はまっていた冒険小説というジャンルで、日本冒険小説協会大賞を受賞したこともあって、伝奇バイオレンス系の作品には手を出しかねていた作家だったのですが、この作品は読んで面白かった記憶があります。 新田次郎の「孤高の人(上・下)」(新潮文庫)に、浪人時代生活だったころにはまって以来、山岳小説をはじめ、探検物なんかも好きでしたが、2000年を超えたあたりから、まあ、50歳を境にでしょうか、あまり読まなくなってしまいました。 作画の谷口ジローという漫画家についても「坊ちゃんの時代(五部作)」(双葉社)や「孤独のグルメ」(扶桑社)のファンで読んでいるつもりでしたが、夢枕獏のこの小説が谷口ジローによってマンガ化され、評判をとっていたことには気づいていませんでした。 シネ・リーブルで予告編を見ていて「あれ?」っと、ようやく気付いた次第です。ここの所の暑さに辟易していることもあって、エベレストの風景でも見て涼んで来ようという気分で、久しぶりにやって来たシネ・リーブル神戸でした。 映画はシンプルでした。エベレスト初登頂の謎を巡って、無酸素で未踏ルートに挑む孤高の登山家羽生丈二を山岳雑誌のカメラマン深町誠が追うという構成で描かれた山岳ミステリーでした。 物語の中盤、羽生のザイル・パートナーとして登場し、不幸にも転落死する青年が岸文太郎と名付けられていることにハッとしました。新田次郎の「孤高の人」の主人公加藤文太郎を思い出しながら、夢枕獏の原作のストーリーが浮かんできたからです。 そんなにたくさん見ているわけではありませんが、ヨーロッパのアニメ映画の良さだと、勝手に称賛している静かな映像でつくられていて、特に自然の風景の美しさは、写真ではないかと思わせる細密さで堪能しました。 原画の谷口ジローは、作品の完成を待たずになくなってしまったわけですが、谷口ジローの絵の、ストップモーションの繰り返しのような独特のテンポがそのままアニメーションとして生きていて納得の作品でした。 情動を煽らない、静かなテンポで作品を完成させたパトリック・インバートという監督に拍手!でした。 懐かしさに浸りながら、客も少なく、涼しい映画館というのは、まあ、極楽ですね。監督 パトリック・インバート原作(作)夢枕獏原作(画)谷口ジロー脚本マガリ・プゾル パトリック・インバート ジャン=シャルル・オストレロ音楽アミン・ブアファ2021年・94分・G・フランス・ルクセンブルク合作原題「Le sommet des dieux」2022・08・02-no95・シネ・リーブル神戸no159
2022.08.04
コメント(0)
-
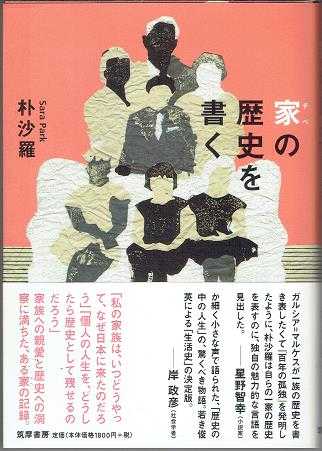
週刊読書案内 朴沙羅「家(チベ)の歴史を書く」(筑摩書房)
朴沙羅「家(チベ)の歴史を書く」(筑摩書房) 2018年に出版された本です。書いたのは朴沙羅、1984年生まれの在日コリアン二世の女性です。出版当時、京大の社会学の博士課程を出て、神大の博士課程で講師をされていた若手の学者さんです。内容は、戦後、済州島から大阪に渡ってきた、彼女の家族、在日一世の伯父さん、伯母さんからの聞き取りの記録です。 こう書くと、なんだか堅苦しいオーラル・ヒストリーを予想されるかもしれませんね。お読みいただければお分かりいただけると思いますが、その予想はハズレれると思います。まあ、とりあえず、著者による執筆の動機が語られている「はじめに」と題されたまえがきからちょっと引用してみます。 ぼく自身は、同居人が新刊当時に購入して読み終えて、棚に並んでいた本書がよろけてぶつかって落ちてきたのを片づけようと、偶然手にとって、この文章を読んで、一気読みでした。はじめに 自分の親戚がどうやら「面白い」らしいことは知っていた。 私の父は在日コリアンの二世で、母は日本人だ。父は10人(早逝した人を含めると11人)きょうだいの末っ子、母は一人っ子で、日本にやってきてから生まれたのは父だけだ。つまり、私には在日一世(日本に移住してきた第一世代)の伯父と伯母が九人(配偶者を含めると一八人)いる。伯父や伯母にはそれぞれ一人から四人の子がいる。彼らはほぼ全員が大阪に住んでいる。 彼らはもともと、済州島(チェジュド)の朝天面(チョチョンミョン)新村里(シンチョンリ)という村から来た。 中略 私が大学を卒業する頃まで、父の親戚たちは年に最低三回(正月・祖母の法事・祖父の法事)は集まっていた。いわゆる「祭祀(チェサ)」といわれるものだ。そこでは、伯父や伯母が口角泡を飛ばして、時に他人には理解できないような内容で争う。最終的には殴り合いになることも少なくなかった。 私が小学生のころは、数年に一度、親戚で集まって済州島に住んでいる親戚を訪ね、墓参りと墓の草刈りをした。そのときの写真は、いまも実家にある。同じような顔と体型の人たちが五〇人くらい、山の中にある墓に行って草を刈り、そのあと草を刈ったばかりの地面にゴザを敷いて法事をしてご馳走を食べる。 祖母の墓は山の中腹の、見晴らしのいい少し開けたところにあった。祖母の墓のすぐそばには背の高い松の木が生えていた。祖母はそこが好きだったらしい。私の生まれる五年前に祖母は亡くなったが、そういう話を聞いて、何も知らないのになんとなく寂しいような嬉しいような気持になったものだ。 私が生まれてほどなく、祖父は他界した。通夜の席で伯父たちは、祖父をどこの墓に入れるか、大阪なのか最終等なのか、祖母と同じ墓に入れるのか、いやあの二人はあんなに仲が悪かったのだから同じ墓に入れてはいけない、と言い争い、祖父の霊前で殴り合ったらしい。それを見ていた母の父は、えらいところに娘を嫁にやってしまった、と思ったらしい。 私がまだ三歳かそこらの頃、その親戚たちがどういうわけか、京都・嵐山で花見をした。そして例によって殴り合いになった。彼らは最終的にビール瓶だか一升瓶だかで殴り合い、見かねた周囲の人が警察に通報した。やってきた警察官は、伯母(伯父の妻)たちに「兄弟喧嘩やからほっといて」と言われて、特に何もできずに立ち去ったらしい。ちなみに、私はそのときみんなの弁当から、好物のハンバーグだけを取り出して食べながら「けんかをしたらいけないんだよ!」と言っていたそうだ。 この本では、こういう面白い人たちが、いつどうやって、なぜ大阪にやってきて、そのあとどうやって生きてきたのかを書いていく。いわゆる家族史と呼ばれるものだ。 このあと、この本では二人の伯父さんと二人の伯母さんにインタビューした記録が、朴沙羅という学者の卵と、その「面白い」親戚たちとの会話のように綴られていきます。 それは、戦後やむなく大阪にやってきた在日一世の70年の生活の思い出の聞き取りであると同時に、1984年生まれの在日二世の朴沙羅にとって、なぜ、「自分の親戚がどうやら『面白い』らしい」と感じるのかを考えるプロセスのドキュメンタリーでもありました。 伯父さんや、伯母さんと朴沙羅さんとのひたすら「面白い」会話のシーンを書き写したい衝動にかられますが、やめておきます。 で、著者が、おそらく書き終えて、そのときの気持ちを綴っているところ、まあ、あとがきみたいものですが、そこから引用してみます。 私は「家(チベ)の歴史」を書こうと思った。彼らの存在を歴史として残したいと思った。それは、遠くない将来に彼らが皆死に、彼らが私に見せてくれた世界が、生きている世界としてはもはやアクセスできなくなるからだった。 彼らが語ってきたことは、日本人にとっての「空白」かもしれない。けれども、私にとってはそれこそが過去であって、他の人から見たら空白であるなどとはそうぞうもつかなかったようなものだからだ。おそらく私が知らないたくさんの空白が、歴史の中にあるのだろう。 敗戦から今日までの時期に限定しても、例えば、引揚者や障碍者、被差別部落出身者が生きてきた戦後の世界やいまの世界は、私にとって空白である。でも、その世界に生きている人々にとっては、自分たちの世界ともう一つの(マジョリティの)世界の二つある。中略 彼らの生きている世界は日本人の築いてきた戦後社会の規範や知識を共有している(そうでなければ、彼らの世界を理解することも記述することも不可能だろう)と同時に、彼らの世界にしかない知識や規範がある(から。読み手が面白いと思える)。 誰のために、何のために、私は「家(チベ)の歴史」を書こうと思ったのだろうか。最初はもちろん、私のためだった。私はなぜここにいて、こんな思いをしなければならないのか知りたかった。けれども、もしかしたら「空白」を埋める一助になるのではないか、とも思っている。中略 しかし、歴史を書くことも、空白を埋めることも、空白を指し示すことも、伯父さんや伯母さんたちのためではない。 だって彼らはきっと、私がもしこの本を「書きました」と言って持って行ったら「読まれへん」「わけわからへん」「こんなもん、おれが読むと思とんか」などと言いながら、本の角で頭をしばきにくるか、あるいは「ほんでこれ売れたらなんぼになるんや」とお金の話を始めるだろうから。 この本は伯父さんたち、伯母さんたちがいなければ書けなかった。あなた方が私をここまで連れてきてくれました。あなた方がいて、話してくれたから、私は今のように生きていくことができるようになりました。どう伝えればいいかわからないけれども、ありがとうございます。(P298) 本文中で、著者のことを「学者の卵」と書きましたが、彼女はれっきとした社会学の学者です。この国の戦後社会の「空白」を、ここまで、その社会を生きた人間にそって描いた学術書を、まあ、素人の歴史好きの浅学のせいもあるでしょうが、ぼくは知りません。彼女は自分のこの著書が「伯父さん」や「伯母さん」を喜ばせることはないだろうと、やや自嘲的に記していますが、偶然手にとった徘徊老人の心をわしづかみにしたことは事実です。久しぶりに見つけた新しい書き手のことを誰かに言いたくてしようがないくらいです。皆さん、まあ、読んでみてください。
2022.08.03
コメント(0)
-
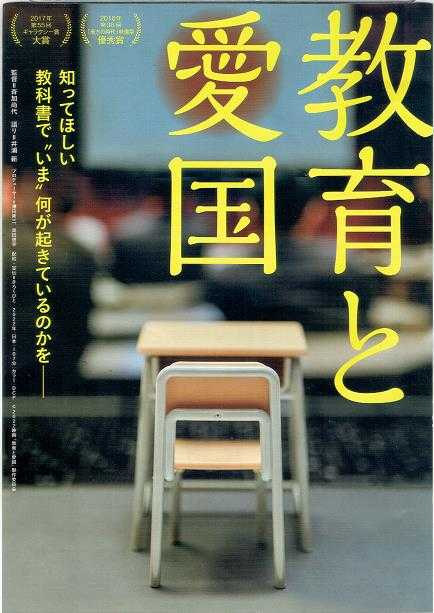
斉加尚代「教育と愛国」元町映画館no140
斉加尚代「教育と愛国」元町映画館 コロナが蔓延していて、外に出ることを控えていますが、なんだか評判らしい「教育と愛国」というドキュメンタリーに引き寄せられて、元町映画館までやってきました。 小学校の教室のシーンから始まりますが、戦後教育の柱であった教育基本法の廃止は2006年でしたが、それ以降、国家主義的な教育の押し付けがいかに浸透してきたかというプロセスを、当事者のニュース・フィルムやインタビューでたどったドキュメンタリーでした。 現場の当事者であったこともあって、それほど驚くような発見はありませんでした。 ぼくは1980年代の始めに新任教員として県立高校で働きはじめましたが、卒業式での「君が代」斉唱と「日の丸」掲揚が県立学校の現場に一律に強要された年でした。「校長、君が代の君は天皇であって、それ以外の人物をさすなんて言う解釈は、明治以来、どんな学者さんでも成り立ちませんよ。どうして、天皇の世を讃える歌を卒業式で歌わなければならないのか、あなたは生徒たちに説明できますか?できないのなら、無理に歌わせたりするのは教員としてやめるべきです。」 日頃、政治的発言など口にしたことのない国語科のベテラン教員、所属した学年の副主任だった方のこんな穏やかな口調の発言を映画を見ながら思い出しました。そのころは、まだ、「日の丸」・「君が代」が職員会議の議題、職員の賛否の対象だったのです。その後、県教委は職員会議での賛否を禁止する通達を出し、議題をすべて校長専権事項にしました。教育現場での「民主主義」なんて、とっくの昔に影も形もないのが現実です。 ぼく自身は、そもそも、国家とか愛国とかを標榜する政治も政治家も、まあ、教員であろうが、普通の市民であろうが、ただ、ただ、感覚的に嫌いなのですが、現実の学校現場には「東大一直線」の小林某とかへの信奉をひけらかしたり、くだらない、はっきり言ってしまえば、ただの国家主義・全体主義、帝国主義への個人的な「愛」に過ぎない薀蓄をおためごかしに生徒に語る教員が、複数いることも、まあ、よく知っているわけですし、90年代の終わりに法制化された日の丸・君が代が大手を振って導入され、学習指導要領の順守とかで、学校や授業への国家主義的な介入が常態化している現実を、数年ぶりに、もう一度思い出させてくれた、実に、不愉快な映画!(笑) でした。 画面に出てくる政治家も、役人も、学者も、「愛国」を背負って「反日」とかいう脅し文句を手に入れた結果でしょうか、強いものに媚びるすべだけで生き延びているヨイショ族の常套でしょうか、妙な上から目線で、実にエラそうにしゃべる人物ばかりなのが記憶に残りました。 特に繰り返し登場する、インチキ集団の頭目と思しきアベ某は大衆扇動家・デマゴーグの本性の卑しさがちょっと抜きんでいましたが、税金で葬式をされるという話題の当事者が、調子にのって「日本という国に自信を持つ事で自信を持たせる!」などと煽っている映像は、ちょっとホラーな気が漂っている不気味さまで感じさせてくれました。 見終えて思ったのですが、せっかくなので、葬式の話と一緒に湧き上がってきた、インチキ・カルトとの関係を人物ごとにテロップででも付け加えれば、映画に登場する「アベ一族」の正体がもっとあからさまにわかってスリリングだったかもしれませんね。たとえば、元東大教授伊藤某などは、まあ、大したインテリなのでしょうが、岸某の回顧談や、笹川某の評伝の著者であるわけですし、そのほかの登場人物たちの、おそらくほとんどが金と票の為なのか、ホントに信じているからなのか知りませんが、ずぶずぶの関係であることが、たぶん間違いないに違いないのですからね。 まあ、そうだからといって、胸がすくわけでもないのですが、インタビューに際して、あくまでも低姿勢を通し、これだけ「ふゆかい」なドキュメンタリーに仕上げた監督斉加尚代の根性! に拍手!でした。監督 斉加尚代プロデューサー 澤田隆三 奥田信幸撮影 北川哲也照明・録音 小宮かづき編集 新子博行朗読 河本光正 関岡香 古川圭子語り 井浦新音響効果 佐藤公彦キャスト吉田典裕池田剛吉田裕伊藤隆松浦正人平井美津子牟田和恵2022年・107分・G・日本2022・08・01 -no94・元町映画館no140
2022.08.02
コメント(0)
-

ベランダだより 2022年7月30日(土)「朝顔日記」
ベランダだより 2022年7月30日(土)「朝顔日記」7月30日のアサガオ 2022年の7月も月末、相変わらず熱い毎日ですが、ここのところ快調に咲いていたベランダのアサガオでしたが、今日は七つです。それも、やっぱり、赤い花ばかりです。 朝からお天気は快調です。もっともコロナ騒ぎの第7波というのでしょうか、ヒタヒタと迫ってきているようで、特に関西圏の感染者数は油断がなりません。 こうして天井を向いて咲いている花の正面を撮りたいのですが無理ですね(笑)。 足元にも、こうしてこっそり咲いている花もあります。これは違う蔓の花が新しく咲いたようです。 今は夏休みなのですが、近所に子供たちの声はしません。まあ、この団地も高齢化の最中なわけで、静かな真夏です。 まあ、ともかくもコロナ騒ぎが静まってくれることを祈る7月もあと一日です。 ああ、そうそう、「朝顔日記」とかいいながらですが、アサガオの鉢の隣で夕顔が蕾を膨らませています。 今夜あたり咲くのでしょうね。楽しみがふえました(笑)。ボタン押してね!
2022.08.01
コメント(0)
全36件 (36件中 1-36件目)
1
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- 59 タムタムさんカッコいい
- (2025-11-11 14:59:50)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 今年も神田古本まつりに行きました。
- (2025-11-10 15:52:16)
-







