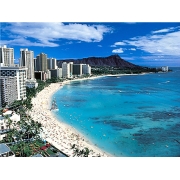PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
フリーページ
HAWAII 情報いろいろ是非覗いて見て下さい

「ALOHAの起源」

「覚えておきたいハワイ語講座」

「ハワイの花 プルメリア」

「ハワイのアンティークショップ」

「Coconut Palm」

「火の女神ペレ」

「ハワイの神話」

「サワーサップ」

「心と体を癒やすヒーリング」

「ハワイ島3つの砂浜」

「マウナケア天文台」

「カメハメハ1世のお話」

ハワイの定番「アロハシャツ」

ハワイの定番「アロハシャツ」No.2

ハワイのレイについて(No.1)

ハワイのレイについて(No.2)

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」No.2

ハワイアン・ミュージック

フラの起源と歴史

ハワイの花「ピカケ」

オアフの聖なる湾 Hanauma Bay ハナウマ湾

ダイヤモンド・ヘッド(ハワイ州自然記念公園)

「ハワイの島々の地形や地質について」

ハワイの自然で暮らす様々な動物たち

ハワイ観は三つのキーワードで

ハワイの風景が見える音楽〜 アロハ・オエ

ハワイの教え~与える人
オアフ島の癒やしの写真集
HAWAIIの基礎知識

HAWAIIの簡単歴史

ハワイの神話

ハワイ版創世記

「HAWAIIの基本情報-1」

「HAWAIIの基本情報-2」

「HAWAIIの基本情報-3」

ハワイの歴史のはじまり
コメント新着
コメントに書き込みはありません。
まだ登録されていません
カテゴリ: その他 雑関係
秋の夜長といいますが、空気の澄んだ夜に空を見上げ、マールイお月様が出ていればなんとなく幸せな気分になるのは私だけではないと思います。
そこで今日はお月見のお話。中秋の名月といえばお月見ですよね。丸~いお月様を見ながらおだんごを食べて・・・。風流でいいですね。でも、中秋の名月はまん丸な満月とは限らないんですよ。しかも日付を注意してみると、9月であったり10月であったりと、年によってまちまちです(今年はたまたま本日9月30日で、しかも満月それも何年かに1回しかない9月2回目の満月なのです、月に2回も満月を愛でる事が出来るのです)。果たして中秋の名月とはどういうものなのでしょうか。
中秋の名月の中秋とは秋の真ん中のことを指します。
旧暦の秋は7月、8月、9月ですから、秋の真ん中といえば8月15日になります。
中秋の名月ではなく仲秋の名月と書かれることがありますが、両者の意味合いは異なります。中秋が旧暦8月15日を指すのに対して、仲秋は秋の真ん中の月、つまり旧暦8月のことを指します。別の意味合いとなりますので注意してください。本来は旧暦8月15日にお月見をするので、中秋の名月と書くのが正しいといえます。
先に旧暦8月15日には満月に近い月が見えると書きましたが、実際には中秋の名月が必ずしも満月であるとは限りません。むしろ、満月でない年の方が多いといってもよいのです。これは月と地球の公転軌道の関係で、新月から満月までの日数が15日とは限らないために起こります。(今月の満月は、その典型的な例です)
中秋の名月、十五夜を観賞する慣習は、中国より伝来した行事といわれ、日本では平安朝以降、宮中や貴族社会で観月の宴が盛んに催されてきました。
京都のお月見の名所のひとつ、嵯峨の大覚寺では10月5日~7日の間「観月の夕べ」が催され、大沢池に古式にのっとり大陸風の龍頭船、鷁首船(ゲキシュセン)を浮べ、水面にうつる月を愛でる平安王朝絵巻さながらの優雅なひとときが繰り広げられます。
お月見に欠かせないのが、すすきと団子。三方に盛られる月見団子の形も関東と関西では違い、関東は丸型、関西は里芋形が一般的。京都では里芋形に餡を巻いたものもみられます。ちなみに十五夜は「芋名月」とも言われ、もとは芋類の収穫祭、畑作儀礼であったとされています。
そこで今日はお月見のお話。中秋の名月といえばお月見ですよね。丸~いお月様を見ながらおだんごを食べて・・・。風流でいいですね。でも、中秋の名月はまん丸な満月とは限らないんですよ。しかも日付を注意してみると、9月であったり10月であったりと、年によってまちまちです(今年はたまたま本日9月30日で、しかも満月それも何年かに1回しかない9月2回目の満月なのです、月に2回も満月を愛でる事が出来るのです)。果たして中秋の名月とはどういうものなのでしょうか。
中秋の名月の中秋とは秋の真ん中のことを指します。
旧暦の秋は7月、8月、9月ですから、秋の真ん中といえば8月15日になります。
中秋の名月ではなく仲秋の名月と書かれることがありますが、両者の意味合いは異なります。中秋が旧暦8月15日を指すのに対して、仲秋は秋の真ん中の月、つまり旧暦8月のことを指します。別の意味合いとなりますので注意してください。本来は旧暦8月15日にお月見をするので、中秋の名月と書くのが正しいといえます。
先に旧暦8月15日には満月に近い月が見えると書きましたが、実際には中秋の名月が必ずしも満月であるとは限りません。むしろ、満月でない年の方が多いといってもよいのです。これは月と地球の公転軌道の関係で、新月から満月までの日数が15日とは限らないために起こります。(今月の満月は、その典型的な例です)
中秋の名月、十五夜を観賞する慣習は、中国より伝来した行事といわれ、日本では平安朝以降、宮中や貴族社会で観月の宴が盛んに催されてきました。
京都のお月見の名所のひとつ、嵯峨の大覚寺では10月5日~7日の間「観月の夕べ」が催され、大沢池に古式にのっとり大陸風の龍頭船、鷁首船(ゲキシュセン)を浮べ、水面にうつる月を愛でる平安王朝絵巻さながらの優雅なひとときが繰り広げられます。
お月見に欠かせないのが、すすきと団子。三方に盛られる月見団子の形も関東と関西では違い、関東は丸型、関西は里芋形が一般的。京都では里芋形に餡を巻いたものもみられます。ちなみに十五夜は「芋名月」とも言われ、もとは芋類の収穫祭、畑作儀礼であったとされています。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[その他 雑関係] カテゴリの最新記事
-
★「貴家ではどのように元旦を迎えましたか… 2023.01.07
-
高野山ろうそくまつり 2022.07.20
-
★Facebook開設7周年 2019.01.19
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.