2021年08月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
ザ・イヤー・オブ1980(3)
なぜケント大学を選んだかについて、お話しておきましょう。一つは文学やヨーロッパ文化の比較研究など人文科学系で評判の良い大学だったことです。実はICUでの私の専攻は人文科学のフランス文学だったのですが、英文学も並行して学んでおりました。ベケットも英語とフランス語で創作活動をするノーベル文学賞受賞劇作家で、私の興味とちょうど 合っていたんですね。つまりヨーロッパ全体の中で、イギリス文学を見たりフランス文学を見たりしたかったのです。二つ目は地の利です。ロンドンにもパリにも近い。ということは、劇を見に行きやすいんですね。実際留学中にロンドンやパリには演劇(とくにイオネスコやベケットの不条理演劇)を見に出かけています。私は、1975年にロンドンでミュージカル『ジーザス・クライスト・スーパースター』を見てその舞台に魅了されて以来の観劇好きです。ベケットを卒論に選んだ理由にもなっています。後にアメリカに留学したときも、しょっちゅうボストンの劇場街やニューヨークのブロードウェイに足を運びました。今でもイギリスに行ったときは、2、3本は観劇の時間をとっています。三つ目も場所に関係しますが、イギリス南部にあるからです。イギリスの冬の大変さは当時からよく耳にしていましたから、なるべく天気が比較的良いとされる南の温暖な土地で暮らしたかったというのも理由のひとつでした。ケント大学ではダーゥイン・カレッジという寮に入りました。クラスも多くが、そのカレッジ寮で行われました。ほかにエリオット、ラザフォード、ケインズなどのカレッジ寮があったと記憶しています。確かラザフォードは理系のカレッジでした。最近知ったのですが、ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロもダーウィン・カレッジで学んだ一人です。1974年から78年まで在籍したことになっていますから、私が住む二年前までダーウィンにいたことになります。彼は大学で英語(英文学)と哲学を学んだと同窓生のページに書いてありました。さて、ブライトンの語学学校が八月で終わり、ケント大学の新入生オリエンテーションが始まるまで10日間の空白がありました。これを有効に使わない手はありません。どこかに行こうと思っていたら、クリストファが「スコットランドに行かなければ駄目だ」と言います。どうしてかなと聞くと、「とにかく素晴らしいところだから行ってきなさい。英語は通じないけどね」と彼は言います。なんでも訛りがすごくて、最初は何を言っているのかさっぱりわからない、と言います。クリストファでも意味が分かるようになるまで三日ほどかかったとか。英国人が三日かかるのだから、よほどのアクセントなんでしょうね。この話がきっかけとなって私もスコットランドにすこぶる興味を持つようになり、すぐにこの貴重な10日間をスコットランドを旅することに決めました。ダーウィン・カレッジには日本から持ってきたスーツケースに荷物を詰め込んで郵送。身軽になって、車輪付きのショルダーバッグという当時はヨーロッパでも見かけたことのないような、オシャレな鞄に旅行用品を入れて、9月1日ごろ、ブライトンのホストファミリーに別れとお礼を告げて、スコットランドに向けて旅立ちました。(続く)
2021.08.31
コメント(0)
-
ザ・イヤー・オブ・1980(2)
ブライトンの夏期語学研修は、現在のブライトン大学の前身ブライトン・ポリテクニックという単科大学のキャンパスを使って行われました。参加したのは、文化放送派遣留学制度で来た日本人。確か10人ほどだったと思いますが、社会人の方も多く、東京電力や日商岩井の方も参加していました。東京外語大学の学生もいたように記憶しています。東京電力の方は、私の記憶が正しければロンドン経済大学院に留学されたエリートで、イギリス滞在中、一度だけロンドンのご自宅に遊びに行かせてもらいました。奥様も留学に同行されており、手料理をご馳走になったのを覚えています。その節は、ありがとうございました。日商岩井の方は、確か人事部に所属しており、私が楽しそうにテニスをしていることを聞きつけ、同じテニスクラブに入会。日曜日にはよく一緒にテニスをやりました。テニスクラブでは夏にバーベキューパーティーもあり、地元の人たちと楽しく交流しました。私はまったくの初心者だったのですが、日商岩井の方には、社会勉強だといってゴルフをしにつれていかれたこともありました。語学研修先のブライトン・ポリテクニックで嬉しかったのは、そこの図書館が使い放題だったことです。ビデオ教材なども充実していたので、結構利用させてもらいました。ところで、このイギリス留学の目的は、サミュエル・ベケットの卒論を描くためでした。ですから、図書館ではベケット関係の本を片っ端から読みました。語学教師の「庭師ディック(Dick, the gardener)」さんからもベケットの作品についての興味深い話を聞いており、論文作成のヒントをもらいました。ホームステイ先のホストファミリーは、ファミリーネームは忘れましたが、クリストファーという40歳くらいのサラリーマンの方の家で、奥様はリンダ、12歳くらいの息子マイクの三人家族でした。マイクは父親のことを「クリストファー」とファーストネームで呼んでいるのが、私には衝撃でした。「イギリスでは子供が親をファーストネームで呼ぶのか」とマイクに聞いたら、最近ではそういう家庭も多いというようなことを言っていました。このような会話は夕食時に交わされます。この時も、ファーストネームの話から、当時はやっていた米国のドラマ「ダラス」(油田開発で財をなした大富豪の大河ドラマ)の話に飛び、「彼らはファーストネームで呼びすぎて、不自然だ」という話題になりました。そのクリストファーからは、意外な意見を聞きました。ある晩、BBCでチベットのダライラマの特集をしているとき、輪廻転生の話になったのですが、クリストファーは「輪廻転生はありうる」と言うんですね。西洋人から輪廻転生肯定説を聞くことになるとは意外でした。当時の私はまだ輪廻転生については半信半疑でした。もっともそれから一か月後くらいに、私自身も輪廻転生肯定説を採らざるを得なくなるような体験をするんですけどね。この会話がその「伏線」としてあったわけです。ホストファミリーには私以外にもスイス人の同居人がおり、名前はアンドレアス。私と同じくらいの年齢の若者でした。彼ともすぐに仲良くなりました。時々飲みに行ったり、グラススキー(芝の上でやるスキー)をしに行ったりしたことを覚えています。今は何をしているんでしょうね。そんなこんなで、あっという間に二か月の語学研修期間が終わりました。(続く)
2021.08.30
コメント(0)
-

ザ・イヤー・オブ・1980
誰にも「自分の人生を決めた重要な年」があるのではないかと思いますが、私の場合は1980年から81年にかけての一年が私の人生で大きな意味を持っています。1980年の夏から翌年の夏までの一年間、英国のケント大学に留学していたんですね。ICUの留学制度を使わずに、文化放送の派遣留学制度を使って自分で英国の大学を選んで決めました。時は米ソ冷戦の真っただ中。前年の1979年にはソ連がアフガニスタンに侵攻。以後、米ソ二大大国に翻弄され続けたアフガンは、長くて暗い戦争の時代に突入します。イギリスではサッチャー政権の全盛期で、教育費や福祉予算が大きく削減され、大学など教育機関もどうやって生き残って行くか模索しはじめた時代でもありました。1980年秋の米大統領選では、ハリウッドのそれほど売れていない俳優が当選。12月8日にはビートルズのジョン・レノンが銃で撃たれて亡くなっています。世界情勢も不安定な状況が続いていました。私が渡英したのは、おそらく1980年7月上旬ころでした。その後、約二カ月間、英国南部の都市ブライトンでホームステイをしながら語学研修をして、9月に英国南東部ケント州の州都カンタベリーにあるケント大学に一年間の留学生として入学しています。ICUでも英語やフランス語で専攻科目の講義を受けていましたから、夏の語学研修は英国の生活に慣れるための猶予期間のようなモノでした。早速、夏の間だけテニスクラブに入会。地元の人と交流を始めました。以前も紹介したと思いますが、その時の写真がこちらですね。人生で初めてプレーした芝のコート。キュッと止まる足下の感じが最高でした。晴れているときは毎日のように、語学学校が終わると、テニスコートに駆け付けました。その時から、誰とでもテニスをします。平日は子どもたちともよくテニスをしました。初心者からプロまで誰とでも楽しくテニスができるんですね。当時は滅茶苦茶サーブが速く、コートカバリングも素早かったですから、すぐに一目置かれるようになりました(特に子供たちから)。(続く)
2021.08.29
コメント(0)
-
竹内文書との不思議な出会い(最終回)
竹内睦泰氏に会ってからのいきさつ等は、ヒカルランドの『正統竹内文書の日本史「超」アンダーグラウンド』のシリーズに詳しいので省略します。ただここで言えるのは、竹内氏とは会うべくして出会ったということです。当然、山口先生とも出会うべくして出会っています。秋山氏とも多分、何度目かの再会です。私はほとんど覚えていませんが、19世紀にイギリスで出会っているそうです。別の惑星にいた「記憶」のようなものがあるのも、秋山氏と似ています。ただの夢だと思っていたんですけどね。別の惑星にいて、「かつて地球で暮らしていたんだよ」と言われて、ふと地球のことを思ったら、本当に地球に来てしまったという話です。その時は結構ショックでした。まるでかぐや姫の心境でした。そんなこんなで、不思議な出会いばかりです。竹内文書の本を書くのも、地球でのミッションの一つであったのだと思っています。さて、次はどこへ進みましょうか。ブログのほうも、今度は別の過去へ飛びましょう。
2021.08.28
コメント(0)
-
竹内文書との不思議な出会い5
1984年から2003年までの間に、では私は何をしていたか、ですが、基本的に一生懸命働いておりました。85年には富山支局から浦和支局に転勤。富山と違って埼玉は、毎月一回は殺人事件で県警本部に捜査本部ができる賑やかさ。さらに、その年の8月には日航機墜落事故で急に呼び出され、群馬県藤岡の現地対策本部の取材でほとんど着の身着のままの状態で、一週間駆けまわりました。遺族の取材はいつもきついモノです。続けて筑波の科学博応援取材もさせられました。さたに大島三原山の噴火の取材でも招集されそうになったのですが、それは免除に。浦和支局勤務だったとき、日航機機長によるアラスカ上空UFO目撃事件があり、UFOライブラリーの荒井氏と再会したり、秋山眞人氏と知り合ったりしたのもこのころでした。秋山氏が編集長を務めたボストンクラブにも原稿を書いています。秋山氏をはじめとする多くのコンタクティーにも浦和支局時代に取材しています。さらに1988年からは本社に異動。8年間、経済部の記者として忙しい日々を過ごしておりました。で、1996年には退社して、アメリカに行きます。ハーバード大学院とジョンズ・ホプキンズ大学院でそれぞれ修士号を取りますが、成績はだいたい平均でAマイナス(優)弱くらい(奇しくもハーバードの最初の学期と、ジョンズ・ホプキンズの最後の学期がオール優)でした。1999年にケネディ暗殺についての論文を雑誌に書いた後、2000年からニューズウィーク日本版で編集者として勤務。世界経済入門やUSビジネストレンドなどを担当しておりました。その際、これからは好きなことを書こうと決心して、かねてからの課題であった竹内文書の執筆を始めたというのが、おおまかないきさつです。その間、忙しかったですが、いつか必ず竹内文書の本を書くという気持ちはずっと持っておりました。だから仕事をしながらでも、時間を見つけては、取材を続けていました。竹内睦泰氏に取材したのも、ニューズウィーク日本版で編集の仕事をしているときでした。あれは2003年の春ごろだと思います。(続く)
2021.08.27
コメント(0)
-
竹内文書との不思議な出会い4
1984年の5月から9月にかけてでしょうか。山口先生にヒントをもらいつつ、竹内文書に書かれている聖地である尖山、天柱石、二上山を結ぶと正三角形になることはすぐに見つかりました。そして、天柱石を中心に考えると、尖山、二上山、宝達山への距離が等しいこともわかりました。竹内文書によると、天柱石は天神時代の聖地(祭壇遺跡)で一番古いので、そこからコンパスを使って描くように等距離の地点に聖なる場所を建造、配置した可能性があると考えられますね。その中で、私の目に「上古第14代国常立天皇が天空浮船に乗って徂徠ケ岳(現在の白馬鑓ヶ岳)に向かって羽根飛び登りゆくところを羽根と名付ける」という文章が飛び込んできました。それで私は羽根という地名を探し始めたんですね。すぐに富山市にある羽根を見つけます。羽根神社という神社までできていますね。現場に行って調べたところ、呉羽丘陵のすぐそばにまるで平行するように羽根という地名があったんですね。で、北の方を見ると五百羅漢で有名な呉羽山が見えます。家に帰ってさらに地図で調べたところ、呉羽山と富山の羽根神社を結んだ東経137度11分の経線(南北線)上に竹内文書が古代の聖都であるとしている位山があります。その真南の岐阜県萩原町に羽根という地名があったんですね。偶然にしてはよくできているなと思いつつ、さらに南下すると愛知県岡崎市に羽根、同じ愛知県の渥美半島に赤羽根と「羽根」の付く地名が南北一直線上に並んでいることに気づいたんですね。それはまるで位山を中心にして経線を引いて、そこに羽根という地名を置いたように思われたわけです。でも、単なる偶然かもしれませんよね。そこで私は一種の占いをします。もし、富山湾を隔てた石川県の奥能登に竹内文書が聖地としている山があり、その真南に羽根という地名があれば、それは間違いなく誰かが意図的に羽根という地名を配置していたのだと信じましょう、と。精神を鎮めて、おもむろに奥能登の地図を調べます。すると東経137度11分に竹内文書で聖地とされている宝立山がそびえているのを見つけます。宝立山は奥能登の最高峰です。それだけでも「凄い偶然」なのですが、私の「占い」ではこの山のすぐ真南に羽根という地名がなければなりません。半ば恐る恐る地図を真南に下りていきます。海岸線に至りました。そしてなんとそこに富山湾を隔てた富山市の対岸に羽根という地名があり羽根八幡神社があることを見つけたんですね。見つけたというか、過去生を思い出したというほうが当たっているのかもしれません。そこに羽根という地名があるということがわかっていなければ、このような占いをしなかったと思うんですよね。むしろ疑り深い私でも、これだけ羽根が並べば、信じるだろうとわざと羽根という地名をこれだけ並べたと考えるほうが妥当ではないかと思います。少なくとも、誰かが後の世で羽根ラインを見つけるように、過去において誰かがわざと置いたのだということが直感的にわかってしまったわけです。ただし私は、どういうわけか、この羽根ラインのことを公表するのは今ではないとも感じました。そして長い間封印して、2003年に出版した『竹内文書の謎を解く』という本の中でようやく公表したのです。
2021.08.25
コメント(0)
-
竹内文書との不思議な出会い3
もう長い月日が流れたので、詳しくは覚えておりませんが、山口教授の尖山ピラミッド説の原稿が掲載された後の動きはおおよそ次のようなものでした。早速、「サンデー毎日」が山口教授に接触、そのまま山口教授は同誌のプロジェクトメンバーに加わりました。私は独自に竹内文書の取材を進め、同文書に記録されている天柱石など古代史跡を現地に訪ねて調査を重ねました。一度、創刊間もない月刊誌ムーから取材を受けて、それが「謎の古代遺跡尖山ピラミッドと天柱石」の記事になっています。私が尖山や天柱石を取材していたときの話は、その年(1984年)の10月に出版されたマスコミ最前線のヒューマンドキュメント『共同通信社の24時間』(共同通信社刊)にも紹介されています。同じ年の夏か秋、山口教授ら数名の有志と尖山の山頂で夜間UFO呼び出し実験をやったことを今でも鮮明に覚えています。UFOは出てきませんでしたが、登山途中に雨が降り出して、全員びしょぬれに。だけど山頂では、横殴りの雨が降っていましたが、驚いたことに尖山の上だけが満天の星空でした。まるで尖山の山頂からエネルギーが出て、雲を押しのけているようで、非常に不思議な体験ではありました。下山後、喫茶・尖山でささやかな打ち上げをして解散となりました。富山地方鉄道の招待で、立山・室堂平のホテルでUFO観測会の取材に出かけたのもこのころでしょうか。そのとき初めて、UFOライブラリーの荒井欣一館長と知り合いになり、後にUFOライブラリーの原稿を書いたことがありました。竹内文書研究家の高坂克己(和導)さんとも、このころ親しくなりました。秋山さんも高坂さんとはよく知った仲だったようですから、この辺りから段々とそちら側の世界に入っていったわけですね。ただし、竹内巨麿が開祖の天津教や、竹内文書を”聖典”とする崇教真光との接触もありましたが、私はどの団体にも加わることはありませんでした。キリスト教や仏教を含め、宗教はあくまでも私の取材対象なんですね(実は秋山氏と同じで「神様好きの宗教嫌い」のところがあります)。1980年にイギリスに滞在していたときも、仲が良かったクウェートから来たイスラム教徒の留学生に「なぜ宗教に入信しないのか、神を信じないでどうやって生きていくのか」と聞かれて、「私の心の中に神がいるので、わざわざ宗教の教徒になって外に神を求める必要がないのだ」と私は答えていました。聖山・位山には、富山の地元・高岡市役所の人たちや日経新聞の記者とともに登りました。UFOに追いかけられて命からがら車に乗って逃げたという富山の無線マニアの人と一緒に、夜の同じ時間帯に現場検証したこともあります。そのときもUFOは現れませんでした。そのようなある日、突如「羽根ライン」を見つけることになるわけです。(続く)
2021.08.24
コメント(0)
-
竹内文書との出合い2
山口博先生から竹内文書を紹介してもらったところまで話しましたね。山口先生は、竹内文書について書かれた佐治氏の二冊の本のほか、私に『富山サイエンス・フィクションの世界――古代の空想と事実――』という、『古典SFの世界』とは別の山口先生の講演録をくれたんですね。その講演の中で先生は、北アルプス立山の麓の富山県立山町横江にある尖山は古代の人工ピラミッドではないかとの説を展開していたのです。これがのちに共同通信社の富山発の原稿となるネタ講演録です。両方ともこちらで読むことができます。取材した後、私は先生のアドバイス通りに、県立図書館に行って『神代の万国史』を借りて読み始めました。するとそこには、尖山がニニギノミコトがスメラミコトの時代に造られた神殿であると書かれていたんですね。山口先生と連絡を取りながら、竹内文書の取材を進め、五月中旬には原稿を書き上げました。最初は「ヒマネタ」(緊急性のない暇な時用の原稿)として、名古屋支社のデスクの手元に眠っていたのですが、サンデー毎日が日本の古代ピラミッド特集をやることがわかったので、同じ日である1984年6月19日夕刊用に山口先生の夢のある話として「尖山はピラミッド!?」という原稿が出稿されたというのが、真相です。地元の北日本新聞や名古屋タイムズが一面トップで掲載してくれたほか、意外にも産経新聞が夕刊社会面トップで扱ってくれました。山口先生とサンデー毎日は、そのときはまったく連絡を取っていませんでしたから、示し合わせることなく、同時に同じプロジェクトが進行していたことになります。本当に不思議なシンクロニシティでした。でも、これだけでは不思議な話は終わりません。(続く)
2021.08.23
コメント(0)
-
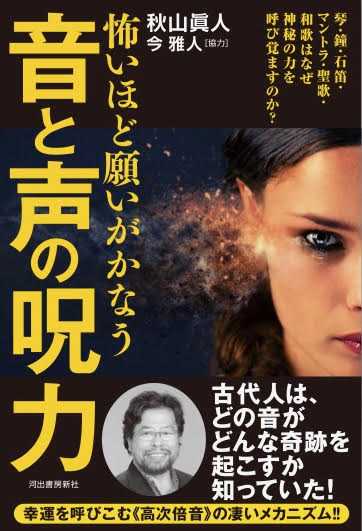
新刊『音と声の呪術』の出版と新刊『日本の呪術大全(仮)』の告知
今日は出版関係のお知らせがあります。まず私との共著が多い秋山眞人氏の新刊『怖いほど願いがかなう音と音声の呪力』が河出書房新社から出版されました。こちらです。アマゾンはこちら→音の呪力。私もお世話になっている今雅人さんが文章をまとめています。音や振動と呪力の関係は、私も以前から関心を寄せていました。まだざっと読んだだけですが、かなり踏み込んで、音がもつ神秘的な力の根源に迫っています。以前、地元のハワイダンス教室で特定の音楽が流れている間だけ、無数のオーブがまるでミラーボールのように乱舞する光景をビデオで見たことがあります。パイプオルガンにせよ、梓弓にせよ、ある周波数の振動と音のリズムが神霊を呼び寄せることはまず間違いのない事実だと思われます。その神秘の扉を開くカギやヒントがこの本の中に満載されているように思いました。続いてもう一つ。秋山氏との共著となる次の本がアマゾンで告知されました。タイトルは『日本の呪術大全(仮)』。「KAWADE夢文庫」の文庫本として出版されます。定価は792円。出版予定日は10月13日となっていますが、いまちょうど仕上げているところです。今月中には脱稿となる予定。アマゾンの告知はこちら→『日本の呪術大全(仮)』内容はまだ秘密です。
2021.08.22
コメント(0)
-
「竹内文書」との不思議な出会い
昨日、山口博先生の本の紹介をしたついでに、私と山口先生の出会いについても記しておきましょう。あれは1984年の初めごろだったように思いますが、初任地の富山支局の記者としていわゆるサツ周りをしていたときです。毎日、富山県警本部や富山署の警察官と会って油を売る(情報交換をする)のが日課でしたが、ある時、親しくなった鑑識課か捜査一課の課長補佐に富山にこんな面白い人がいるから取材に行ってみたらどうかと勧められたんですね。その時見せてくれたのが、富山大学文学部の山口博教授の講演録でした。その内容はこちらにあります。これを読んで、国立大学の先生なのに、こんなに柔軟な発想をする人がいるんだな、と思ったのを覚えています。当時私は、国立大学の教授など頭の固い人間ばかりだと思い込んでいたんですね。早速、アポを取って、夕方のケーデン(警戒電話あるいは警察電話)を掛けた後、山口教授に会いに行きました。富山市の山口教授宅で取材させてもらったのですが、初対面にもかかわらず、すぐに意気投合します。昨日も書きましたが、まるで旧知の仲のようでした。その山口教授から富山には不思議な「竹内文書」という古史古伝があることを聞き、興味を持ちます。何でも記紀には書かれていない歴史が書かれているのだとか。私が興味を示すと、佐治芳彦氏が書いた『謎の竹内文書』と『謎の神代文字』(いずれも徳間書店刊)を私に手渡し「もう私は読んだからあげます」というんですね。私はありがたく頂戴します。さらに山口教授が富山県立図書館に「竹内文書」の原本に近い『神代の万国史』があるから、借りて読むといいとアドバイスしてくれます。その日の出会いから、私の竹内文書研究が始まったわけです。(続く)
2021.08.21
コメント(0)
-
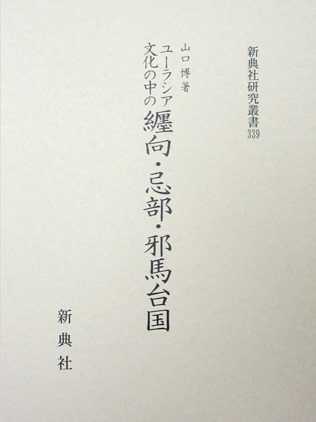
ユーラシア文化と古代日本
これが昨日お話しした山口博先生のご高著『ユーラシア文化の中の纏向・忌部・邪馬台国』です。古代日本の宗教・文化・思想の源流がユーラシアにあると考えて、両文化の比較研究を行っておられます。私も「源泉」の一つはスメル文明すなわち古代メソポタミア文明ではないかと考えていますから、先生と目指すところは一緒。ただしアプローチの仕方が少し異なっているということでしょうか。山口先生は直接シルクロードを歩かれて、ユーラシア文化を研究されました。その集大成的な本となっております。思えば山口先生に最初にお会いしたのは、37年前の1984年。僭越ですが、初めて水魚の交わりとはこのことかと思ったのを覚えています。同時に前世でもどこかでお会いしたのを感じました。そのような感じを持ったのは、1980年のスコットランドの北端にあるオークニー諸島以来の不思議な体験でした。だからこそ、37年の時が過ぎても、今でも交流させていただいているわけです。山口先生も御年89歳になられます。まだまだお元気かつ健筆でいらっしゃるので、私もうれしい限りです。
2021.08.20
コメント(0)
-

富士山の傘雲
今日は雲が賑やかでした。富士山にも傘雲が・・・富士山の左の金時山から富士山手前の矢倉岳に向かって雲が帯状にたなびいていますね。その雲の帯はそのまま大山の方面に向かっています。奥が丹沢や大山。その手前の帯状の雲が金時山の方角から流れきた雲です。帯状の雲はそのまま東京方面へと続いておりました。さて、昨日は東京へ出張。一昨日は恩師・山口博先生から大変価値ある御高著を送っていただきました。タイトルは、『ユーラシア文化の中の纏向・忌部・邪馬台国』(新典社)。かなり面白い、読み応えのある本です。早速、今度の本に使えそうな部分だけを読ませていただきました。その話はまた次の機会にお話ししましょう。
2021.08.19
コメント(0)
-
右目と左目の問題
昨日のブログではうっかり間違えて、アマテラスをイザナギの右目から生まれたかのよう書きましたが、左目の間違えでした。失礼しました。実はこの右目と左目の問題は極めて重要で、私が知る限りこれまで誰も真剣に右目左目問題を取り上げてきませんでした。取り上げようと思うに至ったきっかけは、いつものように第73世武内宿禰こと竹内睦泰氏でした。彼はそれまで、日本から大陸に渡ったスメル族には海ルートの天(海)族と、陸ルートの「スサの王」のグループがいて、理想の国をつくることができなかったので、スメルの地(いわゆるメソポタミアのシュメール)から日本にそれぞれのルートで戻ったのだと話していました。ところが、2015年になって実は第三の草原のルートがあり、ツクヨミの一族が草原ルートで日本に戻ってきたのだと言い始めました。それでピンと来たのが、アマテラス、ツクヨミ、スサノオが左目、右目、鼻から生まれたとする記紀の記述です。すぐに分かったのは、ヒマラヤを鼻に見立てた陸ルート。見事に合致しますね。しかも日本から見たら、左が海ルートで、右が草原ルートとなります。これでは海の彼方からの視点がないではないかと思われるかもしれませんが、注目すべき『日本書紀』に左手で白銅鏡を持ったときにアマテラスが生まれ、右手に白銅鏡を持ったときにツクヨミが生まれたと書かれていることです。鏡は左右が逆になる呪具の象徴ですね。加えて、スサノオは真後ろに振り返ったときに生まれたと『日本書紀』に書かれています。なぜ後ろを振り向く必要があったのか。つまり左右の視点を変えて読めと言っているように思えませんか。都の左京と言ったら、東のことです。右京は西ですね。地図上では左右が逆転します。つまり下々の者から見た視点では、スメラミコトの日本への帰還ルートは、日本に戻って振り返ったスメラミコトの左目が東南アジアの海ルートとなり、右目がモンゴルの草原ルートになると言っていることになるわけです。ほかにも記紀の国生み神話の中には、日本を見下ろす天(高天原)からの視点も存在します。あえて離れて日本を見ようとしている視点があるんですね。この視点を持って記紀を読むと、実はスメル族の「蛭子」がとった第四のルートがあったのではないかと思われてきます。海ルートの先遣隊だったのでしょうか。しかし帰還に失敗、「葦船あるいはイワクス船に乗せられて、流された」と記紀にあるのは、東南アジアのどこかの海で遭難してしまったことを意味しているのではないでしょうか。このようにイザナギの右目左目問題だけでも、結構面白く記紀神話を読むことができるのです。
2021.08.17
コメント(0)
-
海(天)の彼方から見た日本という視点
『古事記』は非常にシンボリックな話に満ちています。今日は「因幡の素兔(白ウサギ)」の話をしましょう。隠岐の島(あるいは沖の島)から因幡国(鳥取県)に渡りたいと思ったウサギが、ワニをだましてワニの背を踏み台にして渡ろうとしました。もう少しで上陸するところで、ウサギが騙したことをワニに告げると、怒ったワニにウサギは皮を剥ぎ取られてしまいます。怪我をしたウサギは八十神にも騙されていじめられます。苦しんでいるウサギをオオナムジこと大国主が助けたら、因幡のヤガミヒメを娶ることができたというのが物語のプロットです。『帝皇日嗣』の口伝継承者竹内氏によると、手籠めにされた巫女をオオナムジが助けた話であるといいます。それはそれで興味深いのですが、それよりも私が面白く思ったのは、『誰も知らない世界の御親国日本』や『竹内文書の謎を解く2ー古代日本の王たちの秘密』でも書いたと思いますが、日本を海外から見ている視点がこの神話に盛り込まれていることです。助けられた白うさぎは、因幡のヤガミヒメを娶ることになるのは、八十神ではなくオオナムジであると予言していますから、確かに神の神託を受ける巫女であったことはまちがいないでしょう。ワニはおそらくサメと同じで、鳥が飛ぶように速い鳥船に次いで早い、サメが泳ぐような速度のサメ船(ワニ船)のことであると思われます。一番遅い船は当然、カメ(亀)船ですね。浦島太郎が乗っていた釣船です。海神とされるオオワタツミの王女たちが乗っていたのは、ワニ船でした。すると一つの推理として、日本を訪れたいと強く願って、ワニ船に乗って海を渡ってきた巫女がおり、それをオオナムジが助けたという筋書きが現れます。普通、海幸彦山幸彦の話にしても浦島太郎の話にしても、あくまでも日本から海に彼方に旅立ち琉球や竜宮城に行って戻ってくるという話です。ところが、白うさぎが持つ海の向こうから日本を見た視点は異彩を放っています。これは、月の世界から来たかぐや姫の視点に非常によく似ています。『古事記』の作者は、海の向こうから見た日本という視点を持っていたということが重要なのです。そこで私は、ほかにもこの海の彼方から見た日本という視点がないかどうか、探してみました。そして見つけたのが、右目の天照、左目のツクヨミ、鼻のスサノオであったわけです。(続く)
2021.08.16
コメント(0)
-

夏の花壇
オレンジや黄色で咲き誇っているのは・・・マリーゴールド。花壇の定番品目ですね。キク科で、クジャクソウ(孔雀草)、万寿菊、千寿菊などとも呼ばれます。
2021.08.15
コメント(0)
-

ジンジャ―の白い花
本日の植物は、ジンジャーリリー(ハナシュクシャ)。ハワイではホワイトジンジャーと呼ばれているようです。ジンジャーと言っても、しょうがとは別属です。我が家にも植えてあるのですが、まだ咲いても一、二輪だけ。いつかたくさん花が咲くようになったらご紹介しましょう。
2021.08.14
コメント(0)
-

秋に向かって
我が家の浜木綿が咲きました。写真は一週間以上前に撮ったものですが、この後満開になって、今は雨に濡れてちょっとしおれ始めています。何か秋に向かっている感じがしますね。
2021.08.13
コメント(1)
-

ラクウショウの実
今日ご紹介するのは、こちらです。これはラクウショウの実です。見事になっていますね。ラクウショウは北アメリカの湿地を原産とする落葉高木です。メタセコイアに似ています。「落羽松」と書くのは、秋になると羽状の葉が枝ごと落下することにちなんだそうです。ただし、マツの仲間ではなくスギの仲間です。あまりにも見事な実が出来ていたので、撮影しました。
2021.08.12
コメント(0)
-

眠る蓮
今日ご紹介するのは、こちら。睡蓮ですね。昼に咲いて、夕方になると花は閉じてしまいます。眠る蓮とは面白い呼び方ですね。しばらく日本古代史はお休みです。
2021.08.11
コメント(0)
-

木の国と熊野問題
オオヤビコは種をまいて木の国を作ったとされていますが、最近の里山で気になるのは、ナラ枯れと呼ばれる現象です。山を見ると、集団的に枯死している樹木があるんですね。ブナ科でブナ以外の樹種であるナラやカシ類、シイ類など、どんぐりのなる木や栗の木が病原菌(カビ)に感染して枯れてしまう病気をナラ枯れと呼びます。カシノナガキクイムシという五ミリほどの虫が病原菌を媒介してこの現象が起こることがわかっています。遠因には、里山が明確な目的をもって管理されずに放置されていることが挙げられるそうです。我が家から見える山の森も一部で枯れています。こちらの里山林も・・・茶色くなったところがナラ枯れです。集団枯死が起こり、ドングリが少なくなれば、熊の問題も出てきます。木の国と熊は切っても切れない関係にあるようです。
2021.08.10
コメント(0)
-

越国の「八」「屋」「夜」の流れ
天孫日向族に高木神の「高」の流れがあるように、出雲神族にもオオドシの「大」の流れのほかに、越国に源流があるとみられる八岐大蛇の「八」「屋」の流れがあるように思われます。八岐大蛇の後に登場するのは、オロチを退治したスサノオとクシナダヒメの間に生まれたヤシマジヌミ(八島士奴美)です。その兄弟のイタケルも別名はオオヤビコ、妹のオオヤツヒメにも「屋」があります。次に因幡のヤガミヒメ(八上姫)。大国主の兄弟とされる八十神も「八」ですね。ヤガミヒメと結婚した大国主の別名も八千矛神と「八」が付きます。『古事記』や『日本書紀』の一部に、大国主がヤシマジヌミの五世孫であるかのように書かれているのも、大国主が「八」を継承したからだと見ることができます。そしてその大国主とスセリビメことカムヤ(神屋)タテヒメが結婚して生まれたのが、八重事代主でやはり「八」が付きます。それとは別に、「屋」の流れがニギハヤヒと結婚したミカシキヤ(屋)ヒメにも付いています。ミカシキヤヒメは『帝皇日嗣』が徐福の子孫としているナガスネヒコ(トミビコ)の妹ですね。トミヤ(夜、屋)ヒメとも呼ばれます。そのミカシキヤヒメとニギハヤヒの間に生まれたのが、おそらくホヤ(屋)ヒメです。というのも、ホヤヒメの正式名称がウマシホヤヒメで、兄のウマシマジと同じ「うまし」という名前を持っているからです。そのホヤヒメはアメノカグヤマことオオカグヤマと結婚して、アメノムラクモことイタテを儲けています。アメノムラクモと言えば、スサノオが八岐大蛇の尻尾から取り出した剣(後の草薙の剣)でしたね。これによって「八」「矢」「夜」などの「や」は、越の八岐大蛇に関係する王統(ヌナカワヒメ)の流れであるということがわかるわけです。枝は複雑に絡み合い、一つの大きな木を形成しますね。国家もやはりそのようにして生まれたのだと思われます。写真の木はヤクシマサルスベリです。
2021.08.09
コメント(0)
-

高木神ータカテルヒメー高倉下の流れ
天孫高族の流れでは、高木神から娘のアマテラス、その娘のタギリに「高」が継承されたのはほぼ間違いないと思われます。アマテラスの別名タクハタチヂヒメの「タ」とタギリヒメの「タ」はおそらく「高」から来ています。そしてタギリヒメの子供がタカヒコとタカヒメですから、明確に高族であることがわかります。さて、問題の宗像三女神の末子タギツヒメことタカツヒメ(高津姫)ですが、タギリヒメと同様にスサノオとアマテラスの子であれば、当然「高族」の血統なのですが、竹内氏の『帝皇日嗣』によると、高津姫ことタギツヒメは、実はスセリビメであることになります。というのも、『帝皇日嗣』ではカムヤタテヒメはスセリビメであると伝わっているからです。カムヤタテヒメがスセリビメであるという証拠は、ほかにもあります。それが「ヤ(屋)」です。カムヤタテヒメの「ヤ」は娘タカテルヒメの別名「ヤオトメ(屋乎止女)」に引き継がれています。ヤオトメは「八乎止女」とも書きますね。神に奉仕する八人の巫女を指します。スセリビメの母親は、八つの川の頭領(越の八岐大蛇)を束ねていた祭祀女王「ヌナカワヒメ」でした。その娘のスセリビメがそこから「ヤ(屋)」をもらって、「カムヤタテヒメ(神屋楯姫)」となったと推察することができるわけです。カムヤタテヒメは事代主の母親ですが、『先代旧事本紀』では高津姫であると書かれています。そして国宝の「海部氏系図」にはカムヤタテヒメとはタギツヒメのことであるとしています。それらを総合すると、スセリビメ=カムヤタテヒメ=タギツヒメ=タカツヒメとなります。すると当然、スセリビメはスサノオの連れ子であって、アマテラスの子ではありませんから、高族の直系ではないことになります。高木神からすると、義理の孫です。その義理の孫に「高」という称号が付いたことが面白いんですね。「高」がスセリビメに渡った理由は、おそらくニギハヤヒことオオドシが天火明として天孫日向族の系図に組み込まれた理由と同じです。出雲神族の正統な後継者を天孫日向族の系図に入れておかないと、自分たちの正統性を主張することができなかったのではないかとみます。クマノクスヒのケースと似ていますね。タカテルヒメの「高」は、タカテルヒメ(別名ヤオトメ、アメノミチヒメ)とニギハヤヒの間に生まれたアマノカグヤマに受け継がれます。アマノカグヤマの別名は、『帝皇日嗣』に書かれているように「タカクラジ(高倉下)」であることから、それがわかります。タギツヒメの系統から継承された「高」は、タカヒコネ(高鴨)やタカヒメからどこに受け継がれたのでしょうか。おそらくタケツノミの「タケ(タカ)」、タギツヒコの「タギ(タカ)」として継がれ、タマヨリヒメの「タ」への流れになったのではないでしょうか。三女神のうち残るイチキシマヒメの別名とみられるミホツヒメ(高木神の実孫)から、ホツ(フツ)や玉として「高」が継承された可能性もあります。そのイチキシマヒメとニギハヤヒが結婚して生まれたのが、後にタマヨリヒメと結婚してヒメタタライスズヒメを儲けた「朱塗り矢」ことオオヤマクイです。タタラは蹈鞴のこととされていますが、意外と「タカラ(宝)」とか「高良」のことではないかと思っています。
2021.08.08
コメント(0)
-

天孫「高」族の流れ
「神」「天」「大」のほかに出てくる「高」についても書いておきましょう。高はタカミムスビこと高木神の「高」です。その娘がアマテラス(天照大御神)ことヨロズハタトヨアキツシヒメ、またの名タクハタチヂヒメです。アマテラスはアメノオシホミミと結婚して、ニニギを儲けました。ただし、竹内氏の『帝皇日嗣』によると、次男ニニギのほかに、長男アメノホヒ、三男ヒコホホデミ、四男ウガヤフキアエズを儲けているそうです。このアマテラスの夫と四人の子供の五柱の男神が、誓約で誕生したことになっています。ここまでが『帝皇日嗣』で明らかになったことです。で、この「高」という名がどのように世襲されたかと言うと、最初に登場するのは、タカヒコネ(アヂスキタカヒコネ)とタカヒメです。大国主と宗像三女神の長女タギリヒメの間に生まれた息子と娘ですね。つまり高木神の「高」は、娘に「タク」として伝わり、その孫に「高」として継承されたことがわかります。ところがここで問題が起こります。そのタカヒメと結婚したアメノワカヒコが高木神を裏切って出雲神族側についてしまったんですね。怒った高木神はアメノワカヒコを射殺します。残されたタカヒコネは、出雲神族と天孫日向族の板挟みになります。そして「こんなのやってらんない!」とばかりに、アメノワカヒコの喪屋をけ飛ばして逃走します。このときオオドシを頼って大和の葛城山に拠点を置いたのだと思われます。その証拠に葛城山麓の奈良県御所市には、全国のカモ(鴨、賀茂、加茂)神社の総本社とされる高鴨神社があるでしょ。ご祭神は、アヂスキタカヒコネ。高木神の「高」族であったことがわかります。同時に賀茂(鴨)氏の祖神であることもわかるわけです。つまりタケツノミですね。その高鴨神社から葛城山を仰ぎみると、中腹に高天彦(たかまひこ)神社があります。そのご祭神が、アヂスキタカヒコネの祖父・高木神とその孫イチキシマヒメになっています。高族の痕跡が残っているんですね。ではなぜ、高木神とともに孫のイチキシマヒメが祀られているかというと、それは宗像三女神の次女であるイチキシマヒメとスサノオの四男であるオオドシが政略結婚したからです。「大」が「高」の二人(タカヒコネとイチキシマヒメ)を受け入れて、ある程度の協力関係を築いたと解釈できるわけです。そのことは『日本書紀』にもそれとなく書かれています。高木神が大物主神ことオオドシに対して「わが娘のミホツヒメをお前に娶らせて妻とさせたい。八十万の神たちを引き連れて、長く皇孫のために守ってほしい」と頼んでいますね。この「わが娘ミホツヒメ」が高木神の孫イチキシマヒメである可能性は高いとみます。またの名をアメチカルミズヒメと言います。しかし、ここに問題があります。それがタカテルヒメなんですね。母は高津姫。「高」族の正統な後継者のような名前を持っています。だけどこの高津姫の正体は宗像三女神の三女タギツヒメなんですね。次回は、タギツヒメから始まる「高」の秘密について論じてみましょう。天孫高族の正体?
2021.08.06
コメント(0)
-

イタケルからイタテへの流れ
紀国(木の国)の王となったイタケル(五十猛)ことオオヤビコ(大屋彦)についても補足しておきましょう。イタケルはスサノオの息子で、父とともに朝鮮半島などから植物の種を日本に持ってきて植えて、現在の和歌山に相当する紀伊国(紀州)に「木の国」を建国、そこの王となりました。その際、妹のオオヤツヒメとツマツヒメも紀国にやってきました。このイタケルがウガヤフキアエズの有力候補であることは既に説明したとおりですが、注目してほしいのは、このイタケという名前です。イタケはイタテ(射楯の神)と同一神(同一人物)とされているからです。そう、ウガヤフキアエズの弟もしくは息子とされる武位起(タケクライオキ)ことタケイタテも「イタテ」です。また、アメノカグヤマ(天香久山)とホヤヒメの間に生まれた息子である天村雲(アメノムラクモ)の別名もイタテ(五多底)なんですね。つまりイタケルから世襲名が渡っていることが考えられるわけです。ではこの世襲名を受け継いだイタテとは誰か。何人か候補がいます。その一人が、何と神武天皇の兄・イツセ(五十瀬)なんですね。ナガスネヒコの弩(古代中国の弓)に射られて、敗走したので、「瀬(背)」の字を入れられていますが、イタテの「イ」をもっているでしょ。『先代旧事本紀』を読んでも、ウガヤフキアエズの弟もしくは息子がイタテです。何となく辻褄が合います。そのイタテが亡くなり、ミケノも常世の国に行ってしまったので、急きょ末子サノが「ワカミケノ」となり、イツセがなるはずだった「カムヤマトイワレビコ」になったのだと私は考えています。確か竹内氏もそのようなことを言っていました。もしそうだとしたら、神武天皇ことサノは元々、熊野の人だったのではないかとも思えてきますね。上賀茂神社のもう一人のご祭神として神武天皇が隠されている、隠されているのは天皇家を護るためだと竹内氏は言っていましたが、意外とこの辺りにその理由があるのかもしれません。でも、他の可能性もあります。カギを握るのは、イタケルの妹たちです。この妹たちがキーパーソンとなったような気がします。何といっても、スサノオの娘ですものね。格としてはスセリビメ級です。この妹たちと結婚した夫、もしくはその子が「イタテ」を襲名したのだとも考えられますね。では、一体誰と彼女たちは結婚したのか、あるいはしなかったのか。イタケルの妹たちと、大綿津見の娘たちとの関係も気になる所。謎は深まるばかりです。ひまわりの季節は続きます。
2021.08.05
コメント(0)
-

アマテラスと101人の卑弥呼たち
天照大御神。菊花紋のごとく、四方八方に太陽の光を放ちます。太陽の巫女、すなわち日御子(ひみこ)ですね。でも天照だけが日巫女(卑弥呼)ではありませんでした。ほらこの通り・・・おそらくアマテラスことヨロズハタトヨアキツシヒメは高木神の娘で、第90代の日御子(祭祀王)です。三世代後の神武天皇と結婚した五十鈴姫が第93代。その後、第8代孝元天皇の異母妹ヤマトトトヒモモソヒメが第百代の日巫女を襲名。第101代目の日御子は表がヤマトトトヒメ、裏がヒコフツオシノマコトだとにらんでいます。まさに101人目の日巫女をもって、表の歴史から姿を消したとみています。
2021.08.04
コメント(0)
-

夏の空
何とまぶしい夏の青空。白くて大きい入道雲にも圧倒されます。龍神やら風神やら、いろいろな顔が見えるところが面白いです。
2021.08.03
コメント(0)
-
八咫烏の八変化
京都の下賀茂神社に参拝したことがあれば、タケツノミが八咫烏であることを知っている人は多いと思います。しかし、タケツノミがアヂスキタカヒコネと同一人物であると知っている人は少ないですね。竹内氏の継承した口伝『帝皇日嗣』には、ちゃんと同一人物であると書かれているそうです。私も最初、竹内氏からその話を聞いたときに「本当に同一人物なのかな」と疑って、調べました。すると、大国主と宗像三女神の長女タギリヒメとの間に生まれたアヂスキタカヒコネの別名は迦毛大御神で、神武天皇の道案内をしたことでしられるタケツノミは賀茂氏族の祖神となっていることに気づきます。どちらもカモの祖神様ということになりますね。更に調べると、最初アヂスキタカヒコネは九州や出雲にいますが、出雲神族とは袂を分かち、大年とともに大和の葛城山辺りに拠点を置いたことがわかります。神武東征のときは八咫烏として先導して功を上げた後、カモタケツノミとして山城の国に移ったこともわかってきます。つまり、二人が同一人物であると考えると、辻褄が合うんですね。タケツノミはタケチヌツミともいいます。神武の后となったイスズヒメの祖父(実際は義理の父らしい)とされるミシマミゾクイミミ、別名スエツミミもタケツノミの別名です。クシヒカタアマヒカタタケチヌツミという異称も持っています。最後の異称だけ説明しましょう。クシヒカタとは「奇日方」、すなわち大年神流系(櫛玉)を指します。アマヒカタは「天日方」、すなわち天孫日向系を指します。喪屋を蹴り飛ばして出雲神族と決別したアヂスキタカヒコネは、大年神流大和族と天孫日向族の側に付いたことを示していますね。そのクシヒカタアマヒカタタケチヌツミから「クシヒカタアマヒカタ」の称号をもらったのが、上賀茂神社のご祭神で、神武天皇とともに祭られているカモワケイカズチです。別名・鴨王。イスズヒメのお兄さんですね。カモワケイカズチの父親・火雷神とは、朱塗り矢ことオオヤマクイであるとすれば、すべてが説明できます。アヂスキタカヒコネは、迦毛大御神であり、八咫烏であり、タケツノミであり、タケチヌツミであり、ミゾクイミミであり、スエツミミであり、クシヒカタアマヒカタであったわけです。まさに八変化。激動の時代を生き抜いたキーパーソンでした。
2021.08.02
コメント(0)
-

空見つ日本と大日本
「大日本」という名前が懿徳天皇や孝元天皇の正式名称についていることに関連して、『日本書紀』には次のように書かれていることを書き忘れていました。ニギハヤヒは天の磐船に乗って大空を飛び回り、この国を見て降臨されたので、名付けて「空見つ日本(やまと)の国」という。つまり、『日本書紀』はニギハヤヒこと大年が事実上の日本国の初代王であったことを認めているわけですね。しかも「天の磐船」の「天」、大空の「大」という表現を使って、二つの部族の融合によって「日本(大和)」ができたこともほのめかしています。「大日本」にはまさにそのような意味が含まれているように思われます。今日の写真は、サルスベリの花。夏の花ですね。我が家のサルスベリも花を咲かせ始めました。
2021.08.01
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1










