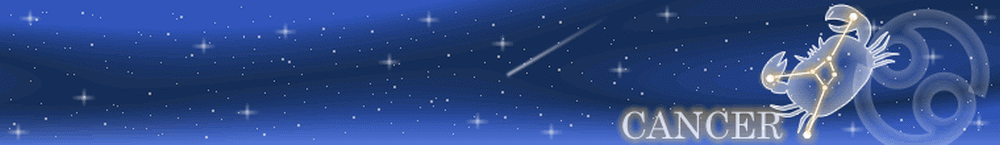2022年01月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-

在宅医療の真実
本著を読み進めている最中、“猟銃男”立てこもり事件が起こりました。 「在宅医療」という言葉が、これまでにない程あちこちで聞かれるようになり、 そのことに、誰よりも精力的に取り組んでいた医師が犠牲となりました。 残念で残念でたまらない……あまりにも悲しすぎます。 *** 多くのメディアが「在宅医療=在宅での看取り」と捉える傾向が強いのは、 そのほうが読者や視聴者の共感を得やすいからなのかもしれません。 しかし私は、在宅医療を理想的な看取りの医療と短絡的に結びつけられることに、 とても強い違和感を持ち続けています。 なぜなら在宅医療とは、必ずしも「看取りを前提とした医療ではない」からです。 むしろ、患者さん一人ひとりの「生きる」を支える医療が 在宅医療だと私は考えています。(p.12)『いのちの停車場』は在宅医療を扱った作品でしたが、やはり、「看取り」やそれに纏わる場面が数多く登場していたように思います。そんな中で、「看取りを前提とした医療ではない」や、「『生きる』を支える医療」という著者の記述には、目から鱗が落ちる思いでした。 高度急性期と急性期の病床を合わせて23万床削減。 これは急性期患者を受け入れる病床が3割減ることを意味する。 急性期病床の削減分は回復期病床の増床へ回す。 また、多くの高齢者が入院している慢性期病床を7万床(2割)減らし、 その受け皿を介護施設や在宅に求める。 在宅医療の患者は今より30万人の増加を見込む。 ここから見えてくるのは、 これまで日本の医療の中心であった急性期医療を現在の7割まで縮小するということ、 また、病院で看ていた高齢者を極力減らし、 そのぶん在宅医療へシフトさせるという方針である。(p.42)これは「地域医療構想における2025年の病床の必要量」(出典は平成29年版厚生労働白書)という図に記された説明文です。このことにより、救急医療が手薄になるのは自明のことであり、本当にこれで大丈夫なのかと、心配せずにはおれません。 私の病院で在宅医療サービスを提供していた患者さんのなかに、 90歳代の女性の患者さんがいました。(中略) 在宅医療に入ったのは8年ほど前からでした。 以来、少しずつ身体機能が低下していき、最後はほぼ寝たきりになりました。 それでも、健康管理や薬の管理は「訪問看護」、食事は「訪問介護」、 入浴は「デイサービス」と3つのメニューを使い分けながら、 1日に3,4回何かしらのサービスが入る体制を整えることで、 最期まで自宅での生活をまっとうされました。 たとえ一人暮らしであっても、いくつかの在宅利用サービスを組み合わせれば 自宅での生活は十分続けられるのです。(p.83)「訪問看護」「訪問介護」「デイサービス」等を手く活用することで、たとえ一人暮らしになっても、自宅での生活が可能であることが分かりました。私も、現在これらについては勉強中ですが、とても参考になりました。さらに、本著には認知症の高齢者についての、次のような記述も見られました。 ある男性の患者さんは重度の認知症で、ご自分で食事の用意をすることも、 朝一人で起きることもできない状態でした。(中略) そこで、そのまま自宅で一人暮らしを続けることになりました。 その際に利用したのが「小規模多機能型居宅介護」というサービスです。 一つの事業所が「通い(デイサービス)」と「訪問(訪問介護)」と 「泊まり(ショートステイ)」、3つのサービスを提供するもので、 どのサービスも顔なじみのスタッフが対応してくれるという良さがあります。(p.86)しかしながら、次のような注意点も記述されていました。これには「なるほどな」と頷かされました。 同じようなケースは認知症の患者さんにも見受けられます。 認知症の方は知らない人や知らない場所を苦手とすることが多く、 デイサービスに通うとかえってストレスが増し興奮状態に陥ることがあります。 そんなときもやはり、 デイサービスより訪問介護や訪問看護のほうが落ち着きます。(p.103)そして、「在宅医療」について述べられた中で、最も腑に落ちたのが次の部分。本著の総括とも言える文章かと思います。 生きるとは、普通の生活を営めること。 いつもこの考えを信じていられれば、 私たちはどれほど美しい人生を生きていけるでしょうか。 「在宅」にはそれだけの力があるということです。(p.164)
2022.01.30
コメント(0)
-

京都寺町三条のホームズ(2) 真贋事件簿
シリーズ第2巻は、副題「真贋事件簿」というテーマに即したお話が6つ。 事件に絡めながら、京都の有名どころの景色や情報が描かれていきます。 哲学の道や慈照寺銀閣、京都駅、南禅寺、東福寺、鈴虫寺、法輪寺、天龍寺等々、 私が訪れたことがある場所も数多く登場し、とても懐かしかったです。 ***序章『夏の終わりに』は、『黄瀬戸の茶碗』を『蔵』に持ち込んだ中年男性に対し、ホームズこと家頭清貴が、その真贋だけでなく男の素性まで見破ってしまうお話。やりとりの中、真城葵が言うところの『黒ホームズさん』が降臨し、「残念やったな。僕は若輩やけど、こんな稚拙なもんに騙されるほど未熟者ちゃうわ」。第1章『目利きの哲学』は、かつて『家宝探訪』というTV番組に鑑定士として登場していた家頭誠司に、恥をかかされた手品師・ドン影山に纏わるお話。恩人に恥をかかせた誠司に一矢報いようと画策した人物に対し、誠司は語ります。「やはりニセモノはニセモノや。どうやってもそれを本物とは言えへんのや」。第2章『ラス・メニーナスのような』は、元贋作師・米山涼介が、かつて贋作を売りつけた富豪からの依頼で絵を描いたお話。その少女像は素晴らしい出来映えでしたが、依頼者が求めているものとは違うと感じた清貴は、求められた構図の秘密を解き明かし、米山は再度キャンバスに向かうことになります。第3章『失われた龍 -梶原秋人のレポートー』は、初の梶原秋人視点のお話。これまでは、すべて葵視点でお話が進展していたので、とても新鮮な感じがします。旅レポート番組を担当することになった秋人から、初回ロケ地・南禅寺について現地でのレクチャーを依頼された清貴は、そこで『瑞竜』の書を贋作と見抜き……第4章『秋に夜長に』は、秋人の親戚の家で、秋人の番組初回を見るお話。その最中停電となり秋人や葵は大混乱しますが、清貴が一人冷静なのには理由がありました。最終章『迷いと悟りと』では、鑑定士・柳原重敏生誕祭の真贋判定ゲームで葵が大活躍。その後、清貴は実際のイベント展示作の真贋を見極めますが、その所有者は…… ***若き鑑定士・清貴と稀代の贋作師・円生の対決。このシリーズのお話の軸になっていくようです。
2022.01.30
コメント(0)
-

本当の翻訳の話をしよう
目から鱗が落ちる記述が目白押し。 村上さんと翻訳家の柴田元之さんとの対談を軸に構成された一冊ですが、 同じ英文を、2人がそれぞれどのように訳したかを対比してみたり、 明治時代の翻訳文を例示し、その変遷について論考してみたりもしています。 その中で、村上さんが『風の歌を聴け』の冒頭を、まず英語で書き始めたとか、 二葉亭四迷が『浮雲』第2編を書き始めたとき、ロシア語で書いてみたとか、 こういうエピソードがサラッと紹介されると、その語学力に圧倒されてしまいます。 そして、「翻訳」というものの奥深さを、より思い知らされることになりました。 *** 僕が翻訳するときはまず、英語から日本語に訳し、 それを何度かチェックして、合っているかどうか確かめて、 ある段階で英語を隠して、日本語を自分の文章だと思って直していくんです。 固い言葉があると少しずつ開いていく。 だからどうしても柴田さんの訳より、僕の方が長くなっちゃう。(p.122)なるほどです。と言いながらも、こんな発言も見られます。 翻訳というものは、日本語として自然なものにしようとは思わない方がいいと、 いつも思っているんです。 翻訳には翻訳の文体があるわけじゃないですか。(p.181)だから、村上さん自身の小説と翻訳作品とでは、読んでいる時の印象が違うんですね。しかし、いずれにおいても、スッキリとして頭に入ってきやすい文体だと思います。 翻訳のコツは2回読ませないことで、 わからなくて遡って読ませるようじゃ駄目だと僕は思っていて、 2回読ませないということを1番の目的にして訳しているところはある。 だからこういうとき、カッコに頼りがちになる。 でももう少し上手いやり方があったかもしれない。(p.129)これには、本当に感心させられました。このことについては、p.492にも柴田さんとのやりとりが掲載されています。1度読めば、ちゃんと分かる文章。私も、心がけたいと思います。
2022.01.23
コメント(0)
-

さよならテレビ
私が、本著タイトルから最初にイメージした内容とは、随分異なる一冊でした。 私は、苦境に喘ぐテレビ業界について論考した内容のものをイメージしたのですが、 本著は、『さよならテレビ』というドキュメンタリー作品を担当した 東海テレビのプロデューサーが、ドキュメンタリーについて記したものです。 著者が関わった数多くのドキュメンタリー作品について、その制作過程が描かれ、 ひとつひとつの作品を作るために、どれほどの苦労があったかがしっかりと伝わってきます。 なかでも、樹木希林さんが関わった作品の記述については、とても興味深い内容で、 それぞれのエピソードに、希林さんの人柄がよく表れていると思いました。 「この番組で、何を言いたいですか」 番組をモニターした後、記者にそう質問されることが多い。 最初は丁寧に答えていたのだが、だんだん馬鹿らしくなってきた。 「いま観たでしょ。それを書いてください。 小説を読んで、作家にそんな質問しますか。 画家に絵の意味を解説させないでしょ」 作品を観てもなお、作者の意図を聞くというのは、どういうものだろうか。 ただの番組宣伝の場だと思ってしまうと、そんなやりとりでいいのかもしれないが、 記者との真剣勝負を求めているというのに、あまりの残念さに、 つい辛辣なことを言ってしまう。(p.324)本著においても、著者のこの考えが貫かれているように感じました。決して「この本で、何を言いたいですか」などと、質問してはいけないのです。
2022.01.23
コメント(0)
-

ボクはやっと認知症のことがわかった
著者は、あの「長谷川式簡易知能評価スケール」を開発し、 高齢者痴呆介護研究・研修東京センター長、そして聖マリアンナ医大理事長として 「『痴呆』に替わる用語に関する検討会」の委員を務めた長谷川和夫さん まさに、この分野における我が国のパイオニアと言える人物です。 本著では、認知症の概要や、それに対する我が国の取り組みの歴史、 さらには「長谷川式スケール」の開発過程等も紹介されていて、 さすがに、第一人者が書かれたものだと感心させられます。 私自身、本著で初めて知ったことも少なくありませんでした。 しかしながら、やはり本著最大の特徴は、著者自身が認知症になったことで、医療者の立場であった著者が、現在は認知症患者の立場からも認知症を見つめ、そこで分かったことを、医療者と患者の双方の視点から記述しているということ。そのため、本著に記されている一文一文には、他の書物にはない重みがあります。 夕方から夜にかけては疲れているけれども、夜は食べることやお風呂に入ること、 眠ることなど、決まっていることが多いから、何とかこなせます。 そして眠って、翌日の朝になると、元どおり、頭がすっきりしている。 そういうことが、自分が認知症になって初めて身をもってわかってきました。 認知症は固定したものではない。変動するのです。 調子のよいときもあるし、そうでないときもある。 調子のよいときは、いろいろな話も、相談ごとなどもできます。(p.67)さて、先述したように、本著では認知症に対する我が国の取り組みの歴史も記されていますが、その中にある介護保険についての記述の中には、次のようなものがありました。 2015年には、「地域包括ケアシステム」の構築をめざすなかで、 認知症の人の意思が尊重され、 できるかぎり住み慣れた環境で自分らしく暮らし続けることができる社会をめざして 「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」が策定された。(p.144)「できるかぎり住み慣れた環境で自分らしく暮らし続けることができる社会」、私も、その実現を心から願っていますが、「住み慣れた環境」については、最終的にどこかで断念せざるを得ないことを、心に留めておく必要があると思います。子供や医療・介護者等の側にいることを求められる日が、いつか訪れることになるのです。 キッドウッドは研究で、認知症の人をよく観察し、 よい状態をもたらす質の高いケアの重要性を指摘した。 その一方、よくない状態を促進し、本人の尊厳を損なう行為として、 子供扱いする、騙す、できることをさせない、無視する、 急がせるなどがあるとした。(p.172)「子供扱いする、騙す、できることをさせない、無視する、急がせる」、介護する立場の者が、分かっていてもしてしまいがちな行動です。特に「急がせる」、そしてそれに伴う「できることをさせない」。時間や心にゆとりがないと、さらに悪循環に陥ってしまうのです。
2022.01.10
コメント(0)
-

京都寺町三条のホームズ
かねてから、その存在は知っていたこのお話。 しかし、書店で平積みされていても、なかなか手が伸びなかったのは、 カスタマーレビューにネガティブコメントが散見されるのを知っていたから。 しかし、これだけ続刊が刊行されている事実は無視できず、遂に購入。 ***真城葵は、埼玉県大宮市から京都に引っ越してきて7カ月の高校2年生。中学の頃から付き合っていた元カレとは、同じ高校に通っていたのだが、引っ越し後は連絡も途切れがちになり、やがて元カレの方から別れを告げられる。その後、元カレが新たに付き合い始めたのが、自分の親友だと知った葵は……確かめたいこと、言いたいことを言うため、埼玉に帰ろうと考える。そして、新幹線代を捻出すべく、死んだ祖父の掛け軸を、京都寺町三条のアーケード街にある骨董品店『蔵』に持ち込むと、そこには店主の孫で、皆から『ホームズ』と呼ばれる京大院生の家頭清貴がいた。この出会いをきっかけに、葵は『蔵』でアルバイトをすることに。清貴は、店に持ち込まれた茶碗に込められた思いを解き明かすと、『斎王代』に届いた怪文書の謎や、百万遍知恩寺の「手づくり市」での詐欺行為、鞍馬山荘での作家遺品焼失事件等を、葵の目の前で次々に解決していく。そして、本巻最後のお話では、葵の埼玉の高校の友人たちが修学旅行で京都にやって来る。友人たちは、葵の元カレと親友女子の交際を、皆の前で葵に認めさせようと画策しており、葵は非常に苦しい状況に追い込まれてしまうが、その危機を救ったのも清貴。また、清貴自身も元カノとの関係をスッキリさせ、今後2人の関係は…… ***お話の発端ともなる葵と元カレに纏わるエピソードの部分は、確かに少々厳しい……少女漫画なら、こういう展開も許されるのでしょうか?また、メインキャラクター・葵の印象も、誰もが好感が持てるものにはならなかったかも。さらに、多数指摘されている方言の誤用についても、なかなか厳しいレベルには違いない。それでも、年末に読んだ『春待ち雑貨店 ぷらんたん』に比べると読後感は良いもので、次巻以降も読んでみようかなと思っています。確かに『ライトミステリー』と呼ぶに相応しい、ライトな作品。既に18冊刊行されているので、まだまだたくさん楽しめそうです。
2022.01.09
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- チェンマイに佇む男達 寺本悠介の場…
- (2025-03-02 12:39:36)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 購入|「英語秒速アウトプットトレー…
- (2025-03-03 17:48:13)
-
-
-

- 経済
- 日本製鉄によるUSスチールの買収:日…
- (2025-03-06 03:19:56)
-