テーマ: どんなテレビを見ました?(79790)
カテゴリ: わたどう~ウチカレ~らんまん!
順序が逆になりますが、
あらためて第18週の内容について。
◇
祖母の代まで、
長きにわたって栄えつづけた峰屋は、
なぜ綾が当主に代わった途端に、
腐造を出して潰れてしまったのでしょうか?
竹雄や、従業員や、分家の人々は、
けっして「綾のせいじゃない」と言ってくれたので、
◇
…けれど、実際には、
「綾のせいだ」と言う人もいただろうし、
長田育恵の脚本も、そんなに甘くないのよね。
むしろ長田育恵は、
あえて「綾の責任」を疑わせるような伏線を、
いくえにも張り巡らしていた、というほうが正しい。
ある意味で、綾への厳しい仕打ちともいえる脚本でした。
…
綾の責任を疑わせる伏線は、次の2点に集約される。
2.火入れのタイミングをずらしたこと。
実際、
「女が入ると酒の神が怒って腐造を出す」
と叱られてましたし、
綾が組合の設立を呼び掛けたときも、
他の蔵元の男たちから同じことを言われていました。
竹雄はそれに対して、
「綾さんこそが酒蔵の女神じゃ!」
「あなたの言葉は呪いじゃなくて言祝ぎじゃ!」
と言ってみせたのだけれど…
結果的には、
子供のころから浴びつづけた呪いのほうが、
予言のように当たってしまったわけです。

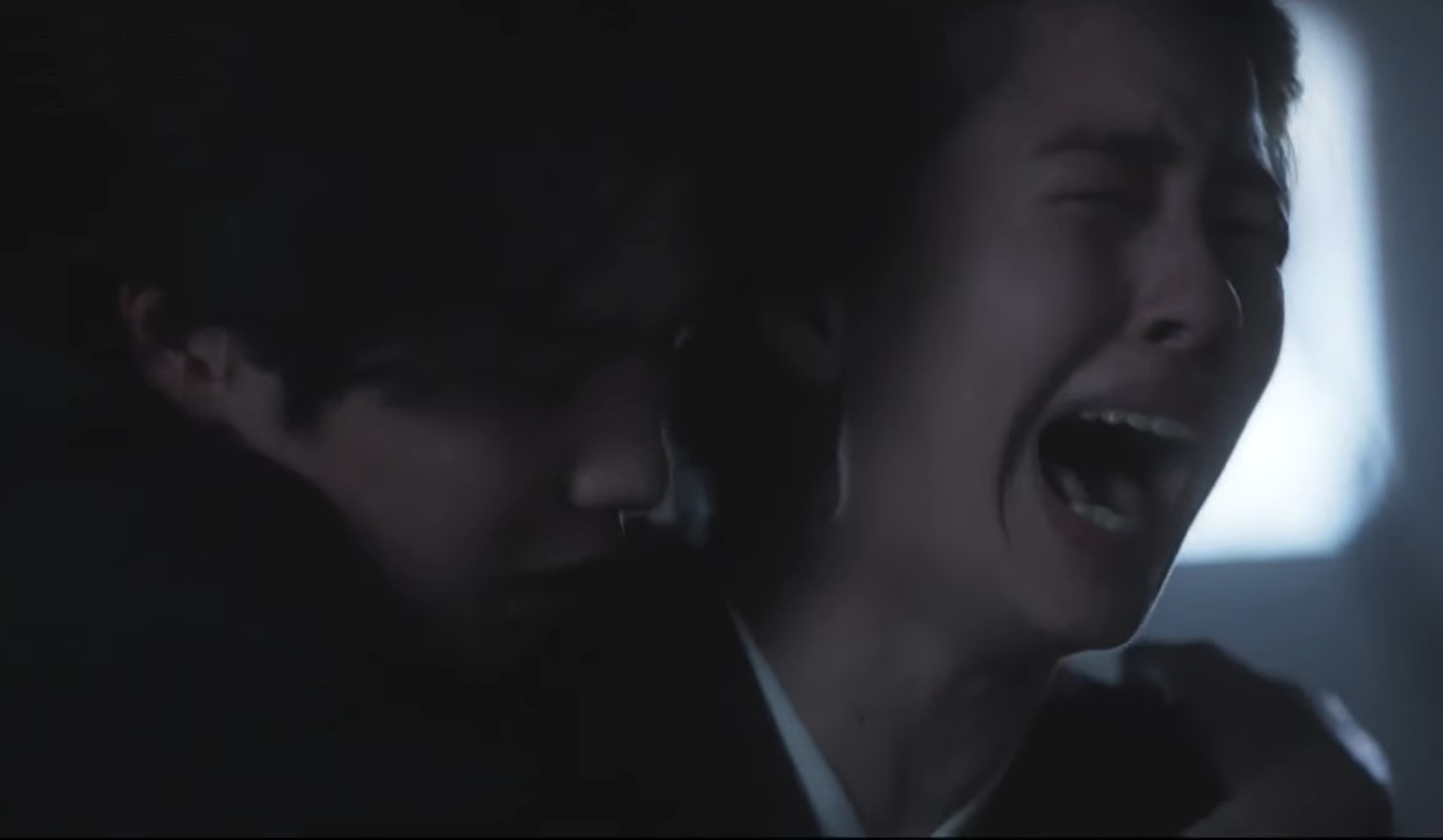
もちろん、
前代の当主も祖母だったのだから、
女性が当主になることに問題はなかったはずです。
とはいえ、
「女が酒蔵に入ると腐造を出す」というのは、
あながち迷信と言い切れないところもあって…
当時の女性は、
糠床を作ることが多かったため、
異質な乳酸菌をもちこむリスクはあったらしい。
https://jp.sake-times.com/think/study/sake_g_no-woman-admitted
もっとも、綾の場合は、
子供のころに叱られて以来、
酒蔵には足を踏み入れなかったはずなので、
それが腐造の原因になった可能性は低いのですが。
◇
むしろ、
それ以上に疑わしいのは「火入れ」の問題です。
綾は、新しい酒を造るために、
「火入れ」のタイミングをずらしていました。
しかも、試験作だけでなく、
主力商品の「峰の月」まで火入れを遅らせていた。
もちろん、
それが原因かどうかは分からないけれど、
結果的には「峰の月」が火落ちして、
いっきに廃業へと追い込まれてしまったのです。
◇
この脚本は、おそらく意図的だと思います。
史実ははっきり分かりませんが、
一般的に、実家の廃業の原因は、
牧野富太郎への金銭的支援といわれてるはず。
にもかかわらず、長田育恵は、
そのエピソードをあえて作り変え、
「女の当主が腐造を出した」 という話にしたのです。
それは、ひとつには、
「主人公の万太郎を悪者にしないため」でもあろうけれど、
たんにそれだけだとは思えません。
そもそも実家で酒蔵の当主になったのは、
綾のモデルにあたる牧野猶ではなく、
竹雄のモデルの井上和之助だったわけだから、
その史実に沿っていれば、
「新しい当主が腐造を出した話」として、
ただの不運なエピソードで済んでいたはずです。
◇
しかし、長田育恵は、
あえて綾を当主にすることで、
彼女に対する"仕打ち"を与えたといえる。
それは綾の人格に対する仕打ちではなく、
近代性への安易な信仰を戒めるための仕打ちです。
…
もちろん綾には何の悪意もありません。
彼女の中にあったのは、
酒への純粋な愛情であり、
家業を支える人々への善意であり、
新しい時代へ立ち向かう勇敢な冒険心でした。
しかし、残念ながら、
たんに愛情と善意と冒険心だけでは、
伝統や因習を打ち破ることは出来ません。
◇
科学的な根拠もないのに、
迷信じみた因習を信じることはできません。
しかし、だからといって、
それをむやみには捨てられないのですよね。
なぜなら、そこには、
経験値や統計的な必然性があるかもしれないから。
むしろ、
伝統や因習を乗り越えるためにこそ、
はっきりとした科学的根拠が必要になる。
たしかに現在では、
女性の杜氏もたくさん存在していますが、
それは科学的な裏付けがあってこそです。
むやみやたらに伝統を否定した結果ではありません。
伝統や因習を打ち破ることや、
男女差別やジェンダーの観念を打ち破ることが、
ただちに近代性に結びつくわけではない。
それを打ち破るためには、
やっぱり 科学的な根拠が必要なのだ ということ。
あるいは、
伝統や因習を乗り越えるためには、
そのための多くの失敗も要するのであって、
その失敗を乗り越えることこそが近代性への一歩だ、
…という教訓を示した脚本にも見えます。
◇
余談ですが…
仙石屋の桜を枯らしたのは天狗巣病菌。
峰の月を火落ちさせたのは火落ち菌。
長女の園子を死なせたのは麻疹ウィルス。
いずれも微生物でした。
藤丸くんは菌類の研究を志してますが、
万太郎は菌類には関心をもたなかったし、
彼の植物分類学は微生物の脅威には無力でした。
おそらく、
長田育恵がこういう物語にしたのは、
現代人がいまだ微生物の脅威に勝利しきれず、
コロナウイルスにも抗体保有率で上回るしかない、
…という現実を意識したからでもあるのでしょう。
科学はまだ万全ではないし、その限界を知ることも必要です。
場合によっては、伝統的な経験値を尊重しなければならない。
なお、
朝井まかてと大森美香の話は明日以降にしますw
尾瀬あきら「夏子の酒」石川雅之「もやしもん」





あらためて第18週の内容について。
◇
祖母の代まで、
長きにわたって栄えつづけた峰屋は、
なぜ綾が当主に代わった途端に、
腐造を出して潰れてしまったのでしょうか?
竹雄や、従業員や、分家の人々は、
けっして「綾のせいじゃない」と言ってくれたので、
◇
…けれど、実際には、
「綾のせいだ」と言う人もいただろうし、
長田育恵の脚本も、そんなに甘くないのよね。
むしろ長田育恵は、
あえて「綾の責任」を疑わせるような伏線を、
いくえにも張り巡らしていた、というほうが正しい。
ある意味で、綾への厳しい仕打ちともいえる脚本でした。
…
綾の責任を疑わせる伏線は、次の2点に集約される。
2.火入れのタイミングをずらしたこと。
実際、
「女が入ると酒の神が怒って腐造を出す」
と叱られてましたし、
綾が組合の設立を呼び掛けたときも、
他の蔵元の男たちから同じことを言われていました。
竹雄はそれに対して、
「綾さんこそが酒蔵の女神じゃ!」
「あなたの言葉は呪いじゃなくて言祝ぎじゃ!」
と言ってみせたのだけれど…
結果的には、
子供のころから浴びつづけた呪いのほうが、
予言のように当たってしまったわけです。

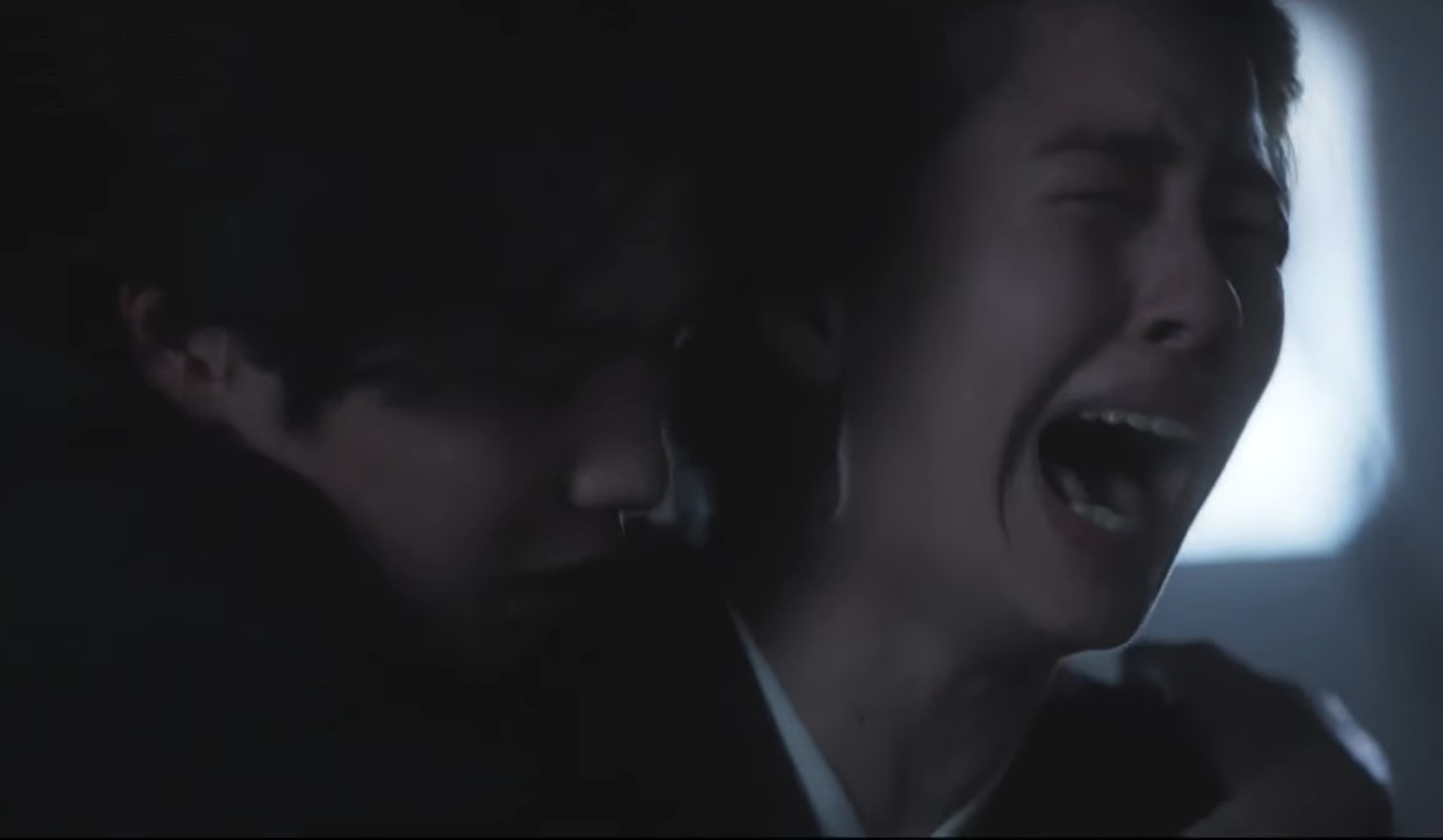
もちろん、
前代の当主も祖母だったのだから、
女性が当主になることに問題はなかったはずです。
とはいえ、
「女が酒蔵に入ると腐造を出す」というのは、
あながち迷信と言い切れないところもあって…
当時の女性は、
糠床を作ることが多かったため、
異質な乳酸菌をもちこむリスクはあったらしい。
https://jp.sake-times.com/think/study/sake_g_no-woman-admitted
もっとも、綾の場合は、
子供のころに叱られて以来、
酒蔵には足を踏み入れなかったはずなので、
それが腐造の原因になった可能性は低いのですが。
◇
むしろ、
それ以上に疑わしいのは「火入れ」の問題です。
綾は、新しい酒を造るために、
「火入れ」のタイミングをずらしていました。
しかも、試験作だけでなく、
主力商品の「峰の月」まで火入れを遅らせていた。
もちろん、
それが原因かどうかは分からないけれど、
結果的には「峰の月」が火落ちして、
いっきに廃業へと追い込まれてしまったのです。
◇
この脚本は、おそらく意図的だと思います。
史実ははっきり分かりませんが、
一般的に、実家の廃業の原因は、
牧野富太郎への金銭的支援といわれてるはず。
にもかかわらず、長田育恵は、
そのエピソードをあえて作り変え、
「女の当主が腐造を出した」 という話にしたのです。
それは、ひとつには、
「主人公の万太郎を悪者にしないため」でもあろうけれど、
たんにそれだけだとは思えません。
そもそも実家で酒蔵の当主になったのは、
綾のモデルにあたる牧野猶ではなく、
竹雄のモデルの井上和之助だったわけだから、
その史実に沿っていれば、
「新しい当主が腐造を出した話」として、
ただの不運なエピソードで済んでいたはずです。
◇
しかし、長田育恵は、
あえて綾を当主にすることで、
彼女に対する"仕打ち"を与えたといえる。
それは綾の人格に対する仕打ちではなく、
近代性への安易な信仰を戒めるための仕打ちです。
…
もちろん綾には何の悪意もありません。
彼女の中にあったのは、
酒への純粋な愛情であり、
家業を支える人々への善意であり、
新しい時代へ立ち向かう勇敢な冒険心でした。
しかし、残念ながら、
たんに愛情と善意と冒険心だけでは、
伝統や因習を打ち破ることは出来ません。
◇
科学的な根拠もないのに、
迷信じみた因習を信じることはできません。
しかし、だからといって、
それをむやみには捨てられないのですよね。
なぜなら、そこには、
経験値や統計的な必然性があるかもしれないから。
むしろ、
伝統や因習を乗り越えるためにこそ、
はっきりとした科学的根拠が必要になる。
たしかに現在では、
女性の杜氏もたくさん存在していますが、
それは科学的な裏付けがあってこそです。
むやみやたらに伝統を否定した結果ではありません。
伝統や因習を打ち破ることや、
男女差別やジェンダーの観念を打ち破ることが、
ただちに近代性に結びつくわけではない。
それを打ち破るためには、
やっぱり 科学的な根拠が必要なのだ ということ。
あるいは、
伝統や因習を乗り越えるためには、
そのための多くの失敗も要するのであって、
その失敗を乗り越えることこそが近代性への一歩だ、
…という教訓を示した脚本にも見えます。
◇
余談ですが…
仙石屋の桜を枯らしたのは天狗巣病菌。
峰の月を火落ちさせたのは火落ち菌。
長女の園子を死なせたのは麻疹ウィルス。
いずれも微生物でした。
藤丸くんは菌類の研究を志してますが、
万太郎は菌類には関心をもたなかったし、
彼の植物分類学は微生物の脅威には無力でした。
おそらく、
長田育恵がこういう物語にしたのは、
現代人がいまだ微生物の脅威に勝利しきれず、
コロナウイルスにも抗体保有率で上回るしかない、
…という現実を意識したからでもあるのでしょう。
科学はまだ万全ではないし、その限界を知ることも必要です。
場合によっては、伝統的な経験値を尊重しなければならない。
なお、
朝井まかてと大森美香の話は明日以降にしますw
尾瀬あきら「夏子の酒」石川雅之「もやしもん」




お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023.12.31 13:53:10
[わたどう~ウチカレ~らんまん!] カテゴリの最新記事
-
朝ドラ「らんまん」長田育恵と南方熊楠。 2024.08.21
-
朝ドラ「らんまん」スエコザサのエロティ… 2023.10.04
-
朝ドラ「らんまん」の時代考証がヤバすぎ… 2023.10.01
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ
政治
(220)ドラマレビュー!
(287)NHK大河ドラマ
(38)NHK朝ドラ
(31)NHKよるドラ&ドラマ10
(32)プレバト俳句を添削ごと査定?!
(207)メディア問題。
(39)音楽・映画・アート
(79)漫画・アニメ
(24)鬼滅の刃と日本の歴史。
(32)岸辺露伴と小泉八雲。
(22)アストリッドとラファエルの背景を考察。
(8)アンという名の少女の感想・あらすじネタバレ。
(31)東宝シンデレラ
(67)恋つづ~ボス恋~カムカム!
(48)ぎぼむす~ちむどん~パリピ孔明!
(38)わたどう~ウチカレ~らんまん!
(64)汝の名~三千円~舞いあがれ!
(16)トリリオン~ONE DAY!
(16)Dr.チョコレート~ゆりあ先生!
(15)警視庁・捜査一課長 真相ネタバレ!
(32)「エルピス」の考察と分析。
(11)「Destiny」&「最愛」ネタバレ考察。
(20)大豆田とわ子を分析・考察!
(10)大森美香の脚本作品。
(12)北斎と葛飾応為の画風。
(17)不機嫌なジーン
(13)風のハルカ
(28)純情きらりとエール
(30)宮崎あおいちゃん
(18)スポーツも見てる!
(41)逃げ恥~けもなれ!
(24)スカーレット!
(13)シロクロ!
(13)ギルティ!
(9)半沢直樹!
(5)探偵ドラマ!
(12)パワハラ
(7)ドミトリー&ゴミ税
(40)夢日記&その他
(5)© Rakuten Group, Inc.









