2006年02月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-

有元利夫展 小川美術館
今年も恒例の有元利夫展に出かける。毎年命日の2月24日前後に行われる展覧会。1985年に38歳という若さで亡くなった画家だ。中世ヨーロッパの教会の壁画にも見えるし、日本画にも見える不思議な絵。見ているとなぜか親近感を感じる絵。岩絵具で描かれた和風フレスコ画ということだ。宮本輝の文庫本の表紙でも有名。会場には自らが作曲したロンドという曲が繰り返し繰り返しおごそかに流れ、静謐な雰囲気が漂う。色あせたような固いごつごつとした表面に押し込められた丸みを帯びた女性たち。その周りを花びらや黄金の光が彩る。例えば「春」という作品。金色の背景、海に立つ女性。降りそそぐ花びらは祝祭の象徴か。女性はフローラかビーナスか。ブリューゲルのバベルの塔のような螺旋階段を登る女性が描かれている「花降る日」。よくみると塔のあちこちが剥げ落ちている。塔を登る女性が持つ布は何を象徴しているのだろうか。この美術館の空間にいると時の経つのを忘れてしまう。受付の方に聞いたら、小川美術館と弥生画廊とは一体で、展示のみのときは美術館に、販売する時は画廊と名前を変えるとのこと。
2006年02月28日
コメント(4)
-

新日曜美術館 サルバドル・ダリ・天才の秘密
昨日の新日曜美術館は「サルバドル・ダリ・天才の秘密」ダリは好きだ。秋葉原の電気店のワンフロアにダリの美術館があった頃は何回か足を運んだ。最初のダリとの出会いは、やはり中学校の教科書。番組でも紹介されていた「記憶の固執」。SF小説に凝っていたため、そのシュールな風土に強く惹かれた。それでも、この絵の解説を聞いたのが、昨日の番組が初めてだった。中央の薄気味の悪い生き物がダリの自画像だと初めて知った。今まで殻に覆われてつっぱっていたのだが、柔らかい自分を初めてさらけ出して描くことができたとのこと。時計が溶けるのは台所で溶けるチーズを見てインスピレーションを得たとのこと。子どものころ飼っていた蝙蝠の死骸にたかる蟻の場面は、グロテスク。幼くして死んだ兄の名前を身代わりにつけられたダリは精神的にも不安定な子どもだった。どこかで聞いたような話だと思ったら、確かゴッホと同じパターンではなかったか。番組では老いても男性遍歴を繰り返す奔放な妻ガラに対して、ダリは彼女を神格化し絶対的なものとして描くことによって精神のバランスを得ていたというような紹介であった。昨年、磐梯の諸橋近代美術館でダリを見てきた。*ここで聞いた話はダリとガラの不和はダリの性的欠陥が原因であり、作品にもそのコンプレックスが「柔らかさと硬さ」という表現として随所に現れているとのこと。ダリが眠る劇場美術館が紹介されたとき、その墓の上を多くの観光客が平気で歩いている場面があり気になったのたが、その観光客たちの足元でダリは永遠に笑い続けているのだろうか。
2006年02月27日
コメント(0)
-

土の中の子供 中村文則
昨年の芥川賞受賞作。なんとまぁ、暗く重苦しい小説だ。子どもの頃の虐待が原因で、自己破壊の願望の強いタクシー運転手の主人公。自分からあえて暴走族に殴られたり、マンションの屋上から飛び降りようとしたり・・・このマンションから飛び降りたらどうなるかと夢想するシーン。驚くほどリアルだった。思わず自分も宙を舞ってしまっているような錯覚に陥った。こういう文章表現が見事なのは、さすが芥川賞受賞作。ついでに言えば、内容に共感できないのもさすが、ここのところの芥川賞受賞作。私小説のような感覚で書かれているので、大したドラマもなく、心象風景がたんたんと連なっていくだけで、全体的な面白みには欠ける。主人公のうじうじした内面の苦悩などどうでもいいじゃないかと思ってしまうのは、自分が年を取ったせいか。つまらないことだが、恋人の名前で考え込んでしまった。白湯子って中国人だろうか?それとも「しろ ゆうこ?」と真剣に考えた。読了後ひょっとしたらと辞書を調べたら、「さゆこ」と読むのだと分かったが、フリガナでもふってほしかった。(国語力がない自分が悪いのだが)
2006年02月26日
コメント(4)
-

美の巨人たち ヴィーナスとオルガン奏者
昨夜の美の巨人たちはプラド美術館のティツィアーノ作「ヴィーナスとオルガン奏者」の紹介。来月末からの東京都美術館でのプラド美術館展とのタイアップ企画だろう。この絵に秘められた謎の種明かしを行う。背景に抱き合う男女が描かれていたなんて気づかなかった。セックスをダイレクトに描くことなどまったく不可能な時代だったので、背景には象徴的にいろいろな小道具を描きこんでいる。裸婦をヴィーナスという女神として描いていること自体、その現れ。須田国太郎展でこの絵の模写を見たばかり、いよいよ現物と御対面できると思うと期待感に胸が躍る。ルーベンスとエル・グレコにも出会えるのも楽しみ。
2006年02月26日
コメント(2)
-

ララピポ 奥田英朗
風俗スカウト、AV女優、官能小説家・・・・など次々と出てくる最低の下半身事情を抱える登場人物たち。みな、真面目に生きようと思うのだが、だんだん堕ちていく。ストーリー自体は6つの短編がうまく絡み合い、最後の作品まで読むと初めて全体像が理解できる、うまく考えられた作品。下半身にだらしのない救いようのない登場人物たちだが、なぜか憎めない。思わず笑ってしまう場面も随所にあり、かなり楽しめたが、お下劣が嫌いな方にはお勧めできません。
2006年02月25日
コメント(3)
-

ニート 絲山 秋子
今回の芥川賞作家。簡単に読めそうな短編集だったので、手にしたら実際に一気読み。でも、これって何だぁ?「ニート」とその続編「2+1」、主人公にまったく共感できない。「愛なんかいらねー」にいたっては、殺されたって文句言えないぞ~と叫びたくなる。まぁ、みんなフィクションの世界だからどうでもいいのだけれど。テーマが美しくないのも嫌だったなぁ。この作品集のなかでは「へたれ」がいちばんよかった。他の作品のように変な女が主人公ではないからだ。背景に恋人と親代わりの叔母との関係をつづった小説。場面ごとに出てくる草野心平のゴビラッフの独白の詩。昔、朗読の勉強していた時に暗喩させられた詩。再びめぐり合えて懐かしかった。幸福というものはたわいなくっていいものだ。
2006年02月23日
コメント(3)
-

向日葵の咲かない夏 道尾秀介
ホラー要素たっぷりのミステリー。夏休み直前、小学校4年生のミチオは友人S君の首吊り死体を発見してしまう。この作家、自分のペンネームを主人公の名前にしているのですね。二転三転する展開はスピーディーでよいのですが、とにかく内容はかなりグロテスク。後味もよくないし、さわやかさとはほど遠い、じっとりと湿った不快感を味わいたい人にはお勧め。カバーのエゴン・シーレのひまわりの絵のように不健全な雰囲気の漂う作品でした。(下のアイ・アム・デビッドの健全なひまわりと正反対です)
2006年02月22日
コメント(6)
-

花まんま 朱川湊人
昨年の直木賞受賞作。作者のこともよく知らず、まさかホラー小説だとは夢にも思っていなかった。いつも通る道をふと離れて見知らぬ路地に入ったら、そこは異界だったというような感じの短編集。笑いあり、心が切なくなるような話あり、逆にほんのり心が温かくなる話もあったりして、読後感もさわやか。大阪の下町が舞台で、そんな環境を知っている人には、たまらないほど、ノスタルジーを感じるのではないか。宮本輝の「泥の川」を想い起こした。いちばん怖かったのは、「妖精生物」。女性の哀しさ、情念がまとわりつくような感じの読後感。「摩訶不思議」は笑えるホラー。さすが大阪人!ってところかな。表題作の「花まんま」。輪廻転生をテーマにした作品だが、それ以上に兄妹の情愛がしっとりと描かれていて、さわやか。花まんまの何と美しいこと。「送りん婆」。これも怖い。人に引導を渡す拝み屋のおばさんと跡継ぎの少女の話。そんな特殊能力を持つ辛さ、人の気持ちのうつろいなどもしっかり描かれていて秀逸。
2006年02月20日
コメント(6)
-
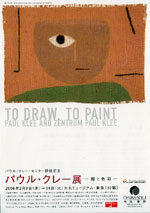
パウル・クレー展 大丸ミュージアム
クレーの年譜を追った展覧会。やはり、1914年のチュニジアへの旅によって色彩が鮮やかに変貌したことがよく分かる。ちなみにその時一緒に旅行したマッケやマルクはその後、第一次世界大戦で戦死したそうだ。クレーの水彩画を見ていると、平面に色の塗り分けをさせられた中学生の時の美術の授業を思い出す。同じ色を塗っても均一の色がでなくて悩んだものだった。クレーの絵で好きなのは有名なモザイク画のような「パルナッソス山」。今回の展覧会では、「喪に服して」が同じタイプの作品。青と赤の市松模様の中にのちの天使の絵のような単純な線で描かれた伏目の女性?。「来るべき者」は、人物を構成するそれぞれのブロックが立体的に感じられて、トリックアートのようで面白い。晩年の「無題・格子状とTのまわりの蛇のような線」は赤の背景に太い黒で格子や曲線を描いた抽象画。ミロの絵のようだ。とても温かみを感じる。難病に侵されたクレーの死の年に描かれた「無題・死の天使」。赤いマントに白い顔の天使。横にある黄色い円形の頭?は生の象徴か。ぽっかりとあいた黒い穴は死。だから天使が死神のようにも思える。
2006年02月17日
コメント(8)
-

ネクロポリス 恩田陸
イギリスと日本の文化が融合したV.ファーという地域。年に一度ヒガンの時期に聖地アナザー・ヒルに行くと、その年に死んだ死者と行き会うことができる。そこに調査に訪れた東京大学院生のジュンが不可解な殺人事件に巻き込まれるというストーリー。読み始めは辛かった。下手な訳者の翻訳小説のように物語の情景がなかなか頭に入らなくイライラするが、下巻に入ってからはめまぐるしく移り変わる展開にかわり、やっと物語の世界に追いつくことができた。ゴシック小説風のミステリー。物語の中に散りばめられたV.ファーのイギリス風にアレンジされた日本の因習が興味をそそられる。ただこの物語全体の世界観に共感できるかどうかで好き嫌いが分かれるだろう。雰囲気さえ楽しめばいいのかもしれない。恩田陸の最近の作品は、ユージニアにしろ、なかなか核心にたどりつかず、読後もスッキリしない印象の作品が続いている。もう読みたくないなぁと思いながらも、なぜかつい読んでしまう作家だ。
2006年02月16日
コメント(4)
-
大いなる遺産 美の伝統展 東京美術倶楽部
4階の展示会場を入るといきなり小林古径の「山鳥」。昨年の古径展を思い出す。橋本雅邦の「龍虎図」。波をはさんで退治する虎と龍の迫力。富岡鉄斎の「扶桑神境図」のダイナミックな筆さばき。下村観山の「三保富士」うっすらとした富士山のふもとの三保松原。菱田春草の「柿に猫」おぼろな輪郭線の柿の下の黒猫のいとおしさ。横山大観の「或る日の太平洋」波の中に龍がいるのか、背景には大観特有の富士山。土田麦僊の「甜瓜図」緑のさわやかさと曲線の美しさ。速水御舟の「びんかずらにるり鳥」単純さと複雑さの混じった構図に絶妙な色使い。竹久夢二の「平戸懐古」傘を持つピンクの着物の女性。装飾的な美しさ。鏑木清方の「いでゆの春雨」背景にうっすらと見える細い雨に気づくかどうか。徳岡神泉の「蕪」一枚お持ち帰りしてよいといわれたらこれを部屋に飾りたい。横山 操の「清雪冨士」厚塗りの白い富士山。富士はいいなぁ。これ以外にも名品多数。日本画見終わっただけでも大満足。次は洋画のコーナー。松本竣介の「都会」赤い服の女性と青い馬。シャガールの絵のよう。古賀春江の「白い貝殻」シュールな女性像。面白い。岸田劉生の「二人麗子図」絵の大部分を占める赤い色。一体何種類の赤が使われているのか。絞りの着物の表現見事。赤い画面に麗子の白い顔が映える。藤田嗣治の「私の夢」子どもの時、家にあった画集で眺めた不思議な絵。裸婦の周りを動物たちが踊る。本物を見ることができて感激。工芸品も名品多数。富本憲吉の同じ作家とは思えないまったく作風が異なる3つの焼き物。お見事!佐々木象堂作、「鋳銅色絵鸚哥置物」何のことはないインコの着色ブロンズ像。赤い体が、目を惹きつける。八木一夫の「盲亀」という名の作品2点。亀ねぇ?何かを象徴しているタイトルなのか。不思議な造詣が妙に気になる陶器。3階に下りると中国朝鮮の古陶器の数々。中でも「澱青紫紅釉輪花花盆」という12世紀中国の作品。青と紫の釉薬の美しさには心惹かれた。同じ窯の小さな杯も気に入った。屏風のコーナー。鈴木 其一「四季草花図屏風」なるほど、左から見ると金屏風。右から見ると市松模様の屏風。さすが、琳派。奥深い装飾画。国宝コーナー。平安時代の源氏物語絵巻「鈴虫」金銀をちりばめた紙の上の実に繊細な筆致のかな文字。隣の鎌倉時代の紫式部日記絵詞の力強い文字に比べると面白い。とにかく「心が満腹。目がごちそうさま」といった展覧会だった。たっぷり3時間、楽しみました。大いなる遺産 美の伝統展
2006年02月15日
コメント(6)
-
美の巨人たち 河井寛次郎
2週にわたって、河井寛次郎の特集でした。この陶芸家も、名前だけはなんとなく知っていたという程度でした。この番組を見て京都の記念館にはぜひとも出かけたくなりました。陶芸作品だけではなく、彼の温かい心が通う木彫りも見たいと思いました。彼の言葉から。「美を追わない仕事、仕事の後から追ってくる美。」アノニムの存在になろうとしたこの陶芸家の心に打たれました。「この世は自分をさがしに来た処、この世は自分を見にきた処」自分の生き様が問われます。「何という今だ。今こそ永遠。」流れ行く時間の中に、永遠を垣間見る至福の時。そんな瞬間をぜひ味わってみたいものです。「非草非人非木」=茶だそうです。なるほど~
2006年02月12日
コメント(12)
-

ポーラ美術館の印象派コレクション展 Bunkamura
コローからボナールまで、印象派関連画家の85点の作品を展示。特にルノワールとモネの作品多数。見慣れた画家の絵が多いので、気楽に楽しめるのがよかった。この展覧会で感じたのは、赤の魅力。ルノアールの赤いアネモネの花、白いスカート地に幾重にも塗りこまれたピンク。モネのばら色のボート、セーヌ河の日没。セザンヌのアルルカン。ゴッホの運河の絵の強烈な赤。そして、ルドンの日本風の花瓶。モネのばら色のボート。うねうねとした水草の見える暗い川を行く、ばら色に輝くボートに乗ったピンクの衣装の二人の女性。私には幻想絵画のように思えた。聖と俗、美と醜、生と死。モネはそんな二つの概念を対比させているのではないかと感じた。ルドンの日本風の花瓶。あのルドンの幻想的な花束と、日本の舞の描かれた磁器の花瓶のリアルさが見事にバランスを持って、描かれている。夢と現とが一枚の絵に同時に表現されている。ゴッホのヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋。青い川で女性が洗濯をしている。生きることの喜びを感じさせられる生命力に溢れた絵。その後の破滅を知っているからこそ味わい深いのだろうか。女性の輪郭線が赤でくっきりと描かれているのが危なさの予兆なのかもしれない。
2006年02月11日
コメント(14)
-
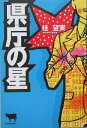
県庁の星 桂 望実
面白かったです。私も今年度、中央から、正職員たった二人の出先に転勤したもので、読んでいて、特に個人的に身につまされること多かったです。前歴踏襲、事なかれ主義、保身、責任転嫁など、役人の一面はある意味では、その通り。ただ、それが悪いかっていえば、一概にそうは言えません。その組織特有のルールがあってこそ組織は成り立っているからです。それは、民間だって同じことでしょう。どんな職場でも、結局は「人」だってことを実感します。現にこの本の主人公、県庁さんもスーパーでの研修で大きく成長しました。何故かといえば、結局は「いい人」見方を変えれば「優秀な人材」だったのですから。所詮、井の中の蛙ではダメだってこと。異文化を知ってこそ、初めて自分に気づくことができます。自らの境遇にドンぴしゃりと当てはまって、元気が出てきました。多分、映画も観に行くと思います。
2006年02月06日
コメント(7)
-

ニューヨーク・バーク・コレクション展 東京都美術館
縄文時代から江戸時代までの美術の流れを概観した構成になっています。2時間もあれば、充分時間があるだろうと思い、3時ごろ到着したのですが、どっこい、最後の方はかなり駆け足になってしまい、後悔しました。まずは、入り口近くにある、平安時代の「飛天」という仏を守る天人の小振りな像からノックアウトされてしまいました。シンバルをたたく天人のお顔のなんと優しげなこと。手の表情も繊細、とても素敵です。伝快慶作の不動明王像。よくある不ぞろいの大きさの目ではなく、両目ともパッチリと見開いた玉眼。口元もスッキリとしていて、かなりの美男子の像でした。絵画も見応えのある作品多数でした。柴田是真の「茨木図屏風」は、鬼が老婆に化けて切り取られた自分の腕を取り返しに来た場面が左右一対の屏風絵に描かれています。左側には鬼、右側には手が入っていた箱の絵。あっさりとした描写にもかかわらず、躍動感に溢れています。グロテスクな鬼の顔なのですが、その構図の美しさに感じ入りました。曽我蕭白の“石橋図”(しゃっきょうず)。今回のチラシにもなっているこの絵は、獅子の群れが絶壁をよじ登っている場面。頂上に到達して喜んだり、落ちていったりしている獅子たちの声が聞こえてきそうな絵です。何と楽しい絵でしょう。見ていてまったく飽きさせません。そして最後に展示してある伊藤若冲の「月下白梅図」。以前に千葉市立美術館で見た同名の作品よりも、ずっと梅の花が多い。じっと見ていると梅の花のひとつひとつが妙になまめかしくて、あたかもジンマシンのぶつぶつのように思えてきて、身体の中がむずむずと痒くなってくるような感じがしました。ものすごい迫力ですが、好き嫌いの分かれる絵かもしれません。隣の鶴の絵、相変らずのたまご型の胴体が好きです。このバーク・コレクション展、ほとんどの作品にコメントをつけたいほど、秀逸な作品目白押しの展覧会でした。
2006年02月02日
コメント(12)
-

容疑者Xの献身 東野圭吾
東野圭吾の直木賞受賞作。昨年末のこのミスでも第一位と絶賛された話題作。天才数学教師の仕掛けたトリックを友人の天才数学者が解明する攻防は読み応え充分。人に解けない問題を作るのと、その問題を解くのとでは、どちらが難しいか。自分で考えて答えを出すのと、他人から聞いた答えが正しいかどうかを確かめるのとでは、どちらが簡単か。という命題の元にストーリーは進んでいく。あざやかなどんでん返し、仕掛けられたトリックの見事さは、すばらしい。ただ、登場人物にいまひとつ厚みが感じられずどうもしっくり来ない。共感できない。そもそも数学教師石神が隣室の母娘を助けようとする動機(その母親への純粋な愛)というものがぴんと来なかった。親友の犯罪を暴く湯川の苦悩も、あっそうって感じ。人物をもう少し掘り下げて描ければ大傑作になったのになぁと少々、残念。まぁ、それはともかく東野さん、待望の直木賞おめでとうございます。
2006年02月01日
コメント(6)
全16件 (16件中 1-16件目)
1










