2006年09月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
ベルギー王立美術館展2 国立西洋美術館
東博の星光寺縁起絵巻の地獄図。日本の古典的な鬼に追われ、苛まれる死者たち。そうそうベルギー王立美術館展でも迫力ある地獄の絵を見ていたのだ。ヤーコプ・ファン・スワーネンブルフという画家の描いた「地獄のアイネイアス」。ギリシャ神話のトロイ戦争の英雄が、地獄に赴いた時の情景。地獄の入り口は大きなアンコウのような怪物の口となっている。(中世ヨーロッパでは、レヴィアタンという悪の海獣の口の中に地獄があると考えられていた。)死者の魂を運ぶカロンの舟。こうもりの羽を持った宙を飛ぶ舟として描かれている。無数の死者が天からボロボロとこぼれ落ちてくる。鬼ではなく悪魔に追われ虐げられる。右上で鎌首を持ち上げる恐ろしいヘビ。とにかく、これでもかというくらい緻密に描かれていて、まるで映画を見ているような感覚だった。そのあと、西洋美術館の常設展で見たダフィット・テニールスの「聖アントニウスの誘惑」に登場する悪魔たちもお気に入り。ボスやブリューゲルの描く悪魔たちも実物を見たいものである。日本に来ないものかなぁ。
2006年09月30日
コメント(2)
-

常設展 東京国立博物館本館
西洋美術館で3時間ばかり過ごした後、グリーンサロンで昼食を済ませて、東博へ移動。途中、科博の前を通ると次回の展覧会の案内。化け物の文化誌展、南方熊楠展、この二つは楽しみ。そしてミイラと古代エジプト展は前売り券を買わないとは入れないらしいので、どうしようか考慮中。さて、東博。年間パスポートを使って入館。まずはお決まりの彫刻室から。仏像展の開催ももうすぐ。浄瑠璃寺の四天王広目天。きれいにライティングされており、今も残る美しい彩色の様子、とくに着物の裾の裏地などの花柄などがはっきりと分かる。浄瑠璃寺本堂に残る二体(持国天と増長天、多門天は京博)は遠くにあり、さほどよく見えないので、こんなに間近に「見仏」することができてうれしい。三十三間堂の、湛慶と院承、隆円の作の3体の千手観音像。慶派、院派、円派それぞれの違いが比較でき、分かりやすい展示。奥の部屋の栃木県光得寺の大日如来像。運慶の作らしいとのこと。厨子の中に安置されているため、現在も金色に輝く。初期の円成寺の大日如来に比べるとふっくらとした円熟味を増したお顔。二階国宝室の絵は、禅林寺の「山越阿弥陀図」。山の向こうに大きく登場する阿弥陀如来。このシチュエーションは昔の怪獣映画のようだと一人悦に入る。京博でみた仏が群をなして山を越えてくる「山越阿弥陀図」も楽しいが、こちらは手前の雲をたなびかせた勢至・観音菩薩が完全なシンメトリーになっていて、実際の仏像彫刻のような印象。仏のありがたさをみごとに演出。皆さんのブログで話題になっている「佐竹本三十六歌仙絵」の小野小町。個人蔵でなかなか見ることができない作品という。長い髪の毛と女房装束。後姿だが華麗さ・艶やかさが画面に漂う。もともとは2巻に分けて描かれていたこの絵巻が、ひとりひとりばらばらに寸断されてしまった過程を知ると興味深い。歌川広重の「月下木賊に兎」ウサギのぎざぎざな線が印象に残る。「月に雁」は深い青色がいい味わい。お月見だ!狩野探幽の「飛禽走獣図巻」。実在の鳥の細い線のタッチと、龍など架空の動物の太い線のタッチの違いが絶妙。これも、よく皆様のブログで取り上げられている「懐月堂派の肉筆浮世絵」の数々。着物の太い墨の輪郭線が力強い。3時半になって、芸大の学生さんの伝土佐光信の「星光寺縁起絵巻」についてのギャラリートークを聞く。やはり絵巻物を見るのに解説のあるなしでは大きな違いだ。怠け者の僧侶が地蔵菩薩に連れられて地獄に落ちる。「これから真面目にやります」と必死で地蔵にお願いして姿がこっけい。東博の話題から逸れるが、ネットで調べていたら、国際日本文化研究センターの絵巻物データベースに巡り合う。こちらの地獄草紙絵巻、何というか・・・とにかくコワイ!一階の近代美術の部屋には時間切れで回れなかった。次回仏像展の時には、真っ先に回る予定。とにかく東博は一日ゆっくり時間をかけたい場所だと実感。満開の萩の花と東博本館↓
2006年09月29日
コメント(6)
-

ベルギー王立美術館展 国立西洋美術館
朝一番で美術館に到着。階段を下りてのんびりと美術館の映像を見ているうちにお客さんもどんどん増えてくる。久しぶりに音声ガイドを借りる。皆さんのブログで話題になっていたキュレーターの幸福さんへのインタビューも収録されていた。そこで、ベルギーは油絵発祥の地だということを始めて知った。この1、2年、スピリアールト展、アンソール展、ベルギー象徴派展、ゲント美術館名品展、ベルギー近代の美展とベルギー絵画の展覧会を見てきて、この国の近代の画家たちの名前を覚えてきた。今回もこの時代の画家たちの作品を楽しみに。そこにたどり着く前に、まずは16,7世紀のフランドル絵画から。最大の呼び物、ブリューゲルの「イカロスの墜落」。農夫も羊飼いも、目の前にいる漁師もだれも、イカロスが落ちたことに気づかない。無人の森の中で響く倒木の音のように、人々はイカロスの事件が本当にあったのかどうかも分からない。そんな面白さがある絵だ。作者にも「?マーク」がつけられているし、本当にイカロスのことを描いた作品なのだろうかとふと思う。ルーベンスの「聖ベネディクトゥスの奇跡」。迫力のある構図で、ドラクロワの模写と並べて展示されている。キリストの来迎を支える天使たちがいいなぁと思う。ルーベンスは、西洋美術館の常設展に展示されている「ふたりの子ども」のピンクに染まった頬がかわいくて好きだ。ヨルダーンスの「飲む王様」は、反吐を吐く男、赤ん坊のお尻を吹く母親やデレデレと酔っ払った男たちを描いて、適度に下品なところが人間らしくてよい。近年、修復した際に反吐とかお尻とかが発見されたというエピソードが面白い。若かりし頃、宴会で羽目を外した際に写したこんな写真があったなぁ。お待ちかねの近代絵画では、デルヴィルの「トリスタンとイゾルテ」。イゾルテが持つ毒薬(実は媚薬)の杯を頂点にみごとに三角形になった構図が印象的。高く掲げられた杯を中心に光の輪ができており、同時に放射状に光が拡散している。最後のコーナーが圧巻。デルヴォーの「ノクターン」。不思議な広場にたたずむ目の大きなふたりの裸婦。塔の上からその姿を覗く紳士。手に持っている丸い品物は何だろうか。そして、マグリットの「光の帝国」。とにかく、この絵を見たかった。一枚の画面の中にみごとに夜と昼が同時に表現されているさまに見とれる。「血の声」もよい。サーデレールの「フランドルの冬」を最後にこの展覧会が終わる。「ベルギー近代の美」展でこの画家を初めて知ったのだが、今回の作品も少々緑がかって描かれた空と雪景色。木々の間に家々が見えるのだが、人の気配がなく不思議な余韻が残る味わい深い絵。駆け足で紹介したが、上記以外にもすばらしい絵が多数あり、ベルギー絵画の素晴らしさを堪能した。
2006年09月28日
コメント(14)
-

灰色の北壁 真保裕一
「ストロボ」以来、何故か遠ざかっていた真保裕一の本を数年ぶりに読んだ。さてこの本、「黒部の羆」「灰色の北壁」「雪の慰霊碑」と、登山をテーマにした3編の中篇を収録。それぞれ、趣向を凝らしたミステリー仕立てになっており、最後まで気を許せない。たとえば、最初の「黒部の羆」では、時系列を敢えてずらして書いているので、いろいろ悩まされる。そこでラストのどんでん返しとうまく計算されている。それぞれの作品、真保裕一独特のきっちりとしたまじめな語り口である。それにしても山を愛する登場人物たちの何と生真面目なこと。若い頃、友人に誘われて夏山には何回か出かけたことがあるだけで、山登りにはまったくの素人なのだが、それぞれの作品、緊迫感のある登山シーンなど充分に楽しめた。一度、北アルプスの薬師岳で同行者が動けなくなり、山岳救助隊の助けを借りたことなど思い出した。個人的には、最後の「雪の慰霊碑」がいちばん好き。父と子、男と女。そんなテーマがさりげなく、ミステリの中に組み込まれており、読後感も清々しい。真保裕一の「栄光なき凱旋」上下巻、書棚にあるのだが、そろそろ手をつけるとするか。
2006年09月27日
コメント(0)
-

美の壷 「蒔絵」を見て
毎週というわけではないが、時間に余裕があるときにNHKの美術番組「美の壷」を見ている。バックに流れるジャズの曲。ほとんど分かるのだが、たまに知らない演奏者や曲目があるので、ホームページで確認するのも楽しみのひとつ。さて、先週は「蒔絵」を取り上げていた。そこで紹介されていた尾形光琳の「八橋蒔絵螺鈿硯箱」。これも、国立博物館や他の美術館で何度も見てきたものだが、いつ見てもその美しさにため息が出る。螺鈿細工のかきつばたの花を眺めながら、橋をたどっていていくと箱をぐるっと一周してしまう意匠のみごとさ。昨年、根津美術館で眺めた時は、蓋が開いていて、箱の下の流水紋様が確認でき、ここに川があったのかと気づいた時も嬉しかった。ところが、先日のこの番組で、黒い漆の部分を透かして、橋とかきつばたと流水紋様だけを写したシーンを見たときには、思わず息を呑んだ。立体的にあの箱のすべてを眺めることができた。あの箱の中だけでひとつの世界が完成しているのだ。完璧に!自分で手にとってあれこれ眺めることができれば分かるのだろうが、それが不可能な分、あれは迫真の映像であった。谷啓のナレーションにあったように川のせせらぎが聞こえてきた。あとは、箱の底がどうなっているか知りたいところである。
2006年09月26日
コメント(10)
-

魂萌え! 桐野夏生
桐野作品って、どうもすっきりとしない読後感があるのだが、怖い物見たさ(読みたさ)でどうしても読んでしまう。この本もそんな類の作品かなと思ったら、今までの路線と一転して読みやすい。新聞連載小説だったせいだろう。還暦を迎えようとする主婦、敏子が夫を亡くすところから、話が始まる。夫には実は10年来の付き合いの愛人がいたり、息子が遺産想像句を露骨に迫ったり、プチ家出したカプセルホテルで出会った老婆とのかかわりなど、目まぐるしく話が展開していくが、それぞれの登場人物がきっちりと描かれていて、飽きることがない。この力量はさすが桐野夏生。ただ主人公の心情や行動には、共感できない。世代や性が違うせいだろうか。あるいは専業主婦と職業人との違いなのだろうか。読んでいて何てとろいのだろうとイライラしてくる。かといって、自分勝手な息子のキャラも好きではない。ただ、私の親も自分のこと、こういう風に感じているのではないかとふと心配に思う。高齢者の生き方など考えさせられると感じてしまうのは、あと十数年後には自分の問題になってしまうという恐怖があるからだろうか。この作品、NHKで来月ドラマ化、敏子役は高畑淳子。映画化もされ、風吹ジュンが主人公を演じるそうだ。
2006年09月25日
コメント(9)
-
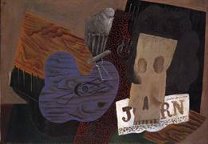
ピカソとモディリアーニの時代展 Bunkamura・ザ・ミュージアム
この展覧会も「ピカソとモディリアーニの時代」というタイトルでくくっていいのかという疑問が残る。どうしても先入観としてエコール・ド・パリの作品の数々を思い浮かべてしまうのだが、それを期待してくるとみごとに肩透かしを食らう。シャガール、ローランサン、キスリング、藤田・・・は登場せず。(ユトリロは一枚あった)いきなり、ブラックとピカソのキュビズムの作品から展示は始まった。あまりキュビズムの作品は好みではないので、しばらく続いていくと飽きてくる。しかし、そんな中でも「楽器と頭蓋骨」、ピカソ風ヴァニタス絵画の前では、しばし足が止まる。次にレジェの作品が続き、華やかな色彩を楽しむことができるようになったころ、「花束を持つ女」に出会う。花が4本でも一応、花束なんだな。でもころころっとした女性像は楽しい。さて、お待ちかねのモディリアーニ。長細い顔のデッサンはほとんど仏像にそっくり。「肌着を持って座る裸婦」、この裸婦の口元の笑みはどこかで見た記憶があるのだが思い出せず。そして、最大の楽しみだった「母と子」。モディリアーニの聖母子。1919年の制作なので、死の直前の作品。彼とジャンヌの悲劇の人生を思い起こして胸が熱くなる。肌の表面のつややかさもすてきだ。となりの「赤毛の少年」もよい。ミロやクレーの絵画を楽しんだ後、ボンボワやボーシャンの絵に出会う。学生時代、国立近代美術館で見たナイーフ〈素朴な画家たち〉展で強烈な印象を受けた画家たちだ。30年振りくらいの出会いだろうか。昔見た、セラフィーヌ・ルイの花の絵はもっと毒々しかったと思うのだが。ルソーの絵がなかったのは残念。ボンボワの「ひなげしの花束を持つ田舎の娘」。のんびりとした背景、何と健康そうな太もも!たぶん、ふたつの大戦の間に描かれたものだと思う。平和のありがたさを感じる。最期のコーナー。ビュッフェのとんがった線の作品には圧倒される。美しくはないが、なぜか、心に突き刺さる。見たくないのに、自然と目が行ってしまうような典型的な絵。気持ちが落ち込んでいるときには決して見ることのできない絵だろう。
2006年09月24日
コメント(12)
-

走墨作品展 you夢ギャラリー
走墨とは、書と絵画が融合した作品。書の味わいと水墨画の味わいを同時に楽しめます。増永広春という女流書家のオリジナルです。(書家というよりアーチストと言ったほうがよいかもしれないです。ここにリンクを張らせてもらいましたが、制作風景とか、作品とか見とれてしまい、すっかりファンになりました。)ここのところ、若冲の簡単な線で描く鶴の水墨画などを見慣れてきたせいか、この走墨の筆の運び方も心地よいです。墨と同時に明るい色の顔彩が使われている作品は、さらにモダンな感じが加わり、味わい深いものがあります。さて、昨日、出かけた東伏見のこのお店、カルチャーセンターにもなっていて、今回は、増永先生の走墨の教室の受講生の発表会が開かれていました。ブログでいつもお世話になっているMashenkaさんの作品が展示されています。生徒さんたちの展示されている奥の部屋のいちばん目立つところに堂々と掲げられていました。タイトルは「飛」。さすが、ダンスの達人!私は跳躍の瞬間を表現しているように感じたのですが、御本人はどのような意図で書かれたのでしょうか。躍動感のある筆触を感じて、自分の右手も自然に動いてくるようです。実際に筆を持ちたくなりました。「月冴えて」というタイトルでの必修作品。他の生徒さんで、兎の絵の作品がありました。兎の餅つきの絵は、まるで鳥獣戯画を見ているようで楽しいものでした。杵がゴルフクラブみたいで微笑ましかったです。「う」の字に兎のからだを重ねて書かれた作品もとても素敵でした。下は先生が書かれた兎の手ぬぐいです。さっそく居間に飾りました。
2006年09月23日
コメント(6)
-
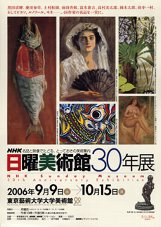
日曜美術館30年展 東京藝術大学大学美術館
NHKの日曜美術館で取り上げられた画家たちの展覧会。ゲストのコメントと一緒に展示されている。それぞれのコーナーで過去の番組が上映されてるのだが、これが10分間に簡略にまとめられたものとなっているので、非常に分かりやすかった。それにしても、金曜日の午前中だというのに、かなりの人出でびっくり。日曜美術館の人気の高さを感じた。萩原守衛の「女」に出迎えられて展覧会は始まる。こちらは藝大蔵のもの。竹橋の近代美術館のものより小振りな感じがした。高橋由一の「鮭」を見るのは実は初めて。かなり大きな作品だったのだと知る。関根正二の「神の祈り」がある。この間、竹橋のモダン・パラダイス展で「信仰の悲しみ」を見て、感激したばかりなのにまたここで同様の主題を扱った作品を見ることができて嬉しい。これは福島県立美術館所蔵とのこと。鏑木清方の「曲亭馬琴」。行灯を中心に置いて、盲目の馬琴が嫁に八犬伝を口述筆記させている光景。後ろで子どもがふたり遊んでいる。この絵だけで、貧困の中にありながらも大作を仕上げた馬琴と嫁の努力の物語として完成している。小川芋銭の「水戸浦のカッパ」は犬のよう。「蓬莱仙境図」の蓬莱山の形のおもしろさ。八木一夫のオブジェ「ザムザ氏の散歩」。これはすごい。こんな風に変身しちゃったのか。引き込まれる。昨年、庭園美術館での展覧会に行かなかったのが悔やまれる。「発芽の様相」も黒い不思議なオブジェ。発芽というより、何者かがアッカンベーをしているよう。3階の展示室。ここでは、展示作品の作家の制作光景がビデオ上映されており、なかなか興味深い。杉山寧のアトリエ、大がかりな機械仕掛けでキャンパスや椅子を動かしているのに驚いた。ここでも富本憲吉の金銀彩のシダ文様の壷に出会えて嬉しい。藤田喬平の硝子の飾筥(かざりばこ)はこうやって作られているのかと知った。最期の「知られざる作家へのまなざし」のコーナーでは、無名だった作家にスポットを当てている。田中一村も日曜美術館の番組で取り上げられて、脚光を浴びるようになったのだそうだ。このコーナーで気に入ったのが、小泉八雲の息子、小泉清の作品。この人も初めて知った画家。自分の血の中にある東洋と西洋の対立に苦しんだ画家みたいだ。「人物(女)」はゴテゴテの厚塗りの画面だが、原色の明るい色使いで裸婦のポートレート。「美しくないのだがとても美しい」なんて、めちゃくちゃな感想。となりの不動明王も迫力がある。最期に、先日、三鷹で見た高島野十郎も3点出展されていた。蝋燭、いつ見ても本物のようだ。図書館のKさん、いつもながらチケットどうもありがとうございました。
2006年09月22日
コメント(6)
-

柳生薔薇剣 荒山徹
鎌倉東慶寺に駆け込んだ朝鮮女性うねを取り戻すため、秀忠と家光の幕府を二分した争い。うねを守るために柳生十兵衛の姉矩香(のりか)が活躍するという伝記小説。どこかの書評に(隆慶一郎+山田風太郎)÷2の面白さという記事が出ていて、この作者の本を始めて読んでみた。出版社も朝日新聞社なもので、訳の分からない時代小説ではないだろうと期待して。ちなみに帯には「司馬遼太郎の歴史観、山田風太郎の奇想天外な構想力、柴田錬三郎の波乱万丈の物語展開を受け継ぐ時代小説家の登場」とあった。しかし、これはいったい何だ!という内容。幕府内の柳生と老中の権謀術数の限りを尽くしたかけひきも中途半端で終わり、後半は仲直り。最強の刺客という前フリで何ページも使い、主人公とどのように戦うのかと思えば、あっさり数行でやられてしまったり、柳生十兵衛が何とも幼稚な人格だったり・・・朝鮮の妖術使いもまったく恐くないし、だいたいこのラストなんぞ肩透かしという感じ。とにかく、あっさりしすぎの展開、はらはらドキドキ感がない。こてこての伝奇小説・剣豪小説を期待していた自分にとっては、すっかり期待外れの一冊だった。
2006年09月21日
コメント(0)
-

クリーブランド美術館展 森アーツセンターギャラリー
このクリーブランド美術館って、まったく知らなかったのですが、オハイオ州にある美術館とのこと。現在改装中で、その間、日本に出稼ぎに来たようです。出展数も60点とさほど多くはなく、えっ、もう終わりという感じで終わってしまいました。そういえば、昨年、ここで見たフィリップス・コレクション展も同じような感じでした。まずは、「印象派の時代」のコーナー。最初にクールベの描いた、「ロール・ポロー」という女性の肖像画。夕焼けを背景に黒いレースの衣装をつけた花束を持った女性。クールベってこういう肖像画も描いていたのですね。切れ長の目と、豊満な体つきがなかなかエロティック。ルノワールの「ロメーヌ・ラコー」↑は、まだ美術学生時代の作品。後のルノワールの画風とはまったく異なっています。髪の毛はルーベンス、顔はアングル、衣装の白の厚塗りはクールベ、背景はコローのように描いたとのこと。筆触を見せない顔の肌は美しい。瞳に金の絵の具が小さく置かれており、きらきらと輝いて見えます。顔と対照的に白いブラウスは筆触の後がはっきりと分かる厚塗りで存在感があります。ルノワールらしからぬルノワール、この絵、気に入りました。次の「後期印象派」コーナーの最初は、セザンヌにお決まりのゴッホとゴーギャン。セザンヌの「小川」↑。水彩画のように薄く塗られた直線的なタッチ。心地よさが感じられます。逆にゴッホの「サン=レミのポプラ」↑は、例の原色「うねうね・ぐるぐる」のタッチ。こちらを眺めていると魔法にかかったように自分もぐるぐるとゴッホの狂気の世界に引き込まれてしまうようでした。ゴーギャンの「波間にて」↑は、不思議な作品。緑の波に身体を投げ出す女性。この絵には何か深い意味があるのでしょうが、それがどんなものかは分かりません。それでもやはり惹きつけられる絵です。ルドンやボナール、ヴュイヤール、ドニなど、それぞれ味わい深い絵が続きます。そして、よかったのが、セガンティーニの「松の木」です。松の木と赤い石楠花の花が描かれているのですが、全体的に青っぽく暗く沈んでいます。線分割法で描かれた硬質な画面。近づくとやはり織物のように細長い筆触が見える。その一本一本の線をなぞって、肌触りを感じたくなります。「近代彫刻のさきがけ」のコーナーで、ロダンの彫刻を楽しむと次は、「20世紀の前衛」のコーナー。このコーナーのエルンストの「草上の昼食」は面白い絵でした。見るからに痛そうな異様な草の上に白布が敷かれており、アンコウのような魚と茄子が載っています。マネの絵との関連性は分かりませんが、描かれている絵はエルンストにしては分かりやすいものでした。ここにモディリアーニもありました。「女の肖像」。↑珍しく瞳が描かれた顔です。あごの下にあるのはイボでしょうか。亡くなる2年前の絵ですが、このころ、パリのカフェで600点あまりの絵を描いたそうです。最期のコーナーは、「北ヨーロッパの光」と題して、ドイツや北欧の作家。バルラッハの彫刻「歌う男」。この間、芸大美術館で見たような記憶があります。朴訥とした感じで素敵です。この展覧会、サブタイトルに「女性美の肖像」とあったので、女性のポートレートを集めた展覧会かなと思ったら、風景画や男性像なども多数展示されていて、このサブタイトルのつけ方、疑問に思いました。この間のモダン・パラダイス展もうそうですが、タイトルのつけ方って、企画者の意図を強く主張するものだと思っていますので。もうひとつ、作品リストを用意していないのも不親切だと思いました。この後、上の階で開催されているロエベとBMWの展覧会にも出かけました。
2006年09月19日
コメント(20)
-

芸術とスキャンダルの間 戦後美術事件史 大島一洋
Takさんのブログで知った、講談社現代新書の一冊。窃盗、贋作、盗作など美術作品を巡って世間を賑わせた戦後の美術事件を取り上げた本。著者は元雑誌編集者だけあって、臨場感ある読み物になっていて、興味深かった。三越の古代ペルシア秘宝展のニセモノ事件など記憶に残っている。今、モダンパラダイス展で東京国立近代美術館に来ているルオーの「道化師」やモローの「雅歌」の盗難事件とか、同美術館でよく見ている梅原龍三郎の「北京秋天」などが暴漢に傷つけられた事件があったことなど、初めて知った。最近、NHKの「美の壷」でちょくちょく紹介される北大路魯山人。死後、アメリカで人気が出て、贋作も増えたそうだ。私も京都の「何必館」で見た楽焼のつばき鉢など大好きだ。だが、「天才によくあるように、性格は傲岸不遜。生涯師事した弟子は一人もいない。戸籍上だけでも9回結婚。人柄がよくないため、生前はごく一部の人を除いてつきあいは少なかった。」と人間的には?マークのつく人物だったようだ。芸術作品が優れているからその作者の人格も優れているとは限らないとは分かっているのだが、NHKなどで顔写真とともに紹介されるとさぞかし素晴らしい人格者だったような錯覚を覚えてしまう。佐伯祐三の贋作事件の際の公立美術館の対応もそうだが、特に奈良国立博物館の贋作ガンダーラ仏購入の際の対応については、憤りを覚える。途中で贋作と知りながら、ばれるとまずいので周囲をだまし続ける。贋作とばれた後は頬かむりをしてやり過ごす。組織が腐るとどうしようもない。それにしても、美術展でのちょっとした薀蓄を語るにはもってこいの本である。
2006年09月18日
コメント(2)
-
大人のための怪奇掌編 倉橋由美子
昨年亡くなった倉橋由美子の短編集。新潮文庫の「倉橋由美子の怪奇掌編」と同じ。次々に繰り広げられる20の怪奇短編小説。これだけの短さでそれぞれ背筋がぞっとさせる見事さ。ユーミンの歌を登場させ、おしゃれな感じで始まる吸血鬼の話。そうかと思えばドロドロとした殺戮の世界を描いたガリバー旅行記の話。ろくろ首。カニバリズム。日常の延長にある不条理さを描いた作品など、いろいろなテイストが楽しめる。古今東西の怪奇・幻想小説の薀蓄に溢れた独自の文章も魅力的。鬼女の面など、結末が予想できる話だが、これこそオーソドックスな怪奇小説だなと思わせるような内容が好き。
2006年09月17日
コメント(2)
-

広重 二大街道浮世絵展 千葉市立美術館
街道浮世絵は当時の人にとっては、今のテレビの旅行番組を見るようなものであったらしい。安価で手に入る絵を眺めて、旅への思いを募らせていたのでしょう。この展覧会の「東海道五拾三次」と「木曾街道六十九次」。ずっと眺めていると、現代の自分たちも江戸時代の人々と同じく、旅愁が募ってくるのが不思議でした。風光明媚な風景。旅する人々。大名行列。旅籠。峠の茶店。地元の人々。土地の名物。厳しい自然環境。・・・そんな光景が版画として描かれています。木曾街道69次は、渓斎英泉24枚。歌川広重46枚の作品で構成されている。そんな中で、気に入ったのは英泉の「野尻 伊奈川橋遠景」。滝のような川に奇妙にねじれた橋が架かっている。その向こうに夕焼けと鳥の群れ。奇妙にデフォルメされた風景画は、例えば北斎のあの神奈川沖の大波のように見るものに迫ってきます。広重の「雨の中津川」は、世界で数点しか確認されていない幻の作品だそうです。雨合羽をはおった旅人の角々とした姿がユニークです。東海道53次。「蒲原 夜之雪」。初摺と後摺の二点並列展示されています。初摺と後摺では、背景の闇夜の現し方が異なります。雪明りに光る家々と対照的に夜の闇に沈む家々。どちらも深い趣があります。何度も見たことのある「箱根 湖水図」。今まで、ただ箱根の山々を描いただけだと思っていたのですが、今日初めて、大名行列が細い街道を下っていることに気づきました。「御油 旅人留女」。これは、53次の中でも最高に楽しい絵。まるで追いはぎのような客引き女に困っている旅人の声が聞こえてきます。その他、およそ110年ぶりに日本に里帰りを果たした「甲州日記写生帳」など、見所満点の展覧会でした。
2006年09月15日
コメント(22)
-

チーム・バチスタの栄光 海堂 尊
これは、面白かった。最近読んだ本の中でも、一二を争う良い出来の本。白い巨塔のシリアスと空中ブランコ「伊良部先生」のコミカルを足して2で割ったミステリーといった感じ。大学病院の心臓外科チームで突如連続して起こる術死事件。偶然か、医療事故かあるいは・・・主役の人物ふたりもいい味わい。多くの脇役も、それぞれ存在感に溢れている。特に後半、厚生労働省の技官白鳥が登場してからは、その荒唐無稽な活動で、話はどんどんテンポよく進んでいく。医者である著者、初めての作品ということで、表現にくどさや硬さが見られる部分もままあるが、それ以上に主人公と登場人物たちとの会話の妙に浸って、あまり苦にならず。惜しくも直木賞は逃したが、第4回『このミステリーがすごい!』大賞受賞作。著者の次の作品に否が応でも期待が高まる。
2006年09月14日
コメント(5)
-

国宝 風神雷神図屏風 出光美術館
昼過ぎ、しとしとと降る雨の中、皇居の緑を眺めながら出光美術館へ。エレベーター前に長い列ができていたらどうしようかと思いましたが、ちょうど一箱満員になるくらい。館内もそこそこの人出でしたが、ストレスを感じるほどでもなくてよかったです。さて、チケットを購入し、ムンクの絵を横目で眺めながら、まずは宗達の「風神雷神」と対面しました。建仁寺のレプリカは見た記憶がありますが、実物を見るのは初めて。ガラスケース越しに緑の風神が見えたときは、やっと出会うことができたと感激。宗達の「風神雷神」、間近にみると細部は全体的に「もやもや」しているのですね。たらしこみの技法で描かれているためでしょうか。特に顔や手足の筋肉など、このもやもや感によって非常に立体的に見えるのです。やはり、三十三間堂の風神雷神の彫刻からの影響を受けているのだと感じました。二人の神の今にも踊りだしてきそうな姿、この迫力に圧倒されます。本当に出会えてうれしいです。光琳の「風神雷神」は、RIMPA展に続いて2度目の出会い。こちらは、より色鮮やかになり、目にも眩しいくらいです。くちびるや腹巻の朱色が強烈な印象を残します。光琳は宗達の絵を正確にトレースしてこの絵を描き、そして抱一がこの絵の裏に銀地に夏秋草図を描いたのですね。時空間はクロスしませんが、琳派の意識の連綿とした流れを感じます。美へのあこがれも連綿と続いていきます。「琳派芸術の継承と創造」というサブタイトルが、具体的に感じられます。抱一の「風神雷神」は、ひとこと、楽しい!あの情緒溢れる抱一がこんな絵を描くなんてという驚きの方が強いです。確かに、宗達の絵に比べれば、ずいぶん崩れてはいますが、それは、比較するからであって、この絵だけでもとても素敵です。笑いがあります。もうマンガなのですね。当時、抱一は宗達の「風神雷神図」の存在を知らなかったそうです。光琳のそれがオリジナルと思っていた。宗達の絵はどこに秘蔵されていたのでしょうか。光琳の絵だって、大名家にあり、抱一だから見ることができ、当然、一般の人はその存在も知らなかったのですから。さて、三枚の「風神雷神図」以外にも、すばらしい作品と出会えました。抱一の作品が多いのですが、特に銀地の紅白梅図屏風、八つ橋図屏風の2点にはみとれてしまいました。これも光琳へのオマージュなのでしょう。MOA美術館にある光琳の「紅白梅図屏風」をもし実際に見ることができたならば、抱一はいったいどんな絵を描いたのだろうかと思いました。琳派とは関係ありませんが、最後に展示されていた仙崖和尚の指月布袋。この子ども大好きです。もう一度、宗達の「風神雷神図」のコーナーを眺めるとかなりの人だかりでした。ムンクの絵を眺めて(これもいい!)、満足感に浸りながら帰路につきました。指月布袋↓
2006年09月13日
コメント(19)
-

沖で待つ 絲山秋子
芥川賞受賞作の「沖で待つ」と「勤労感謝の日」の2本収録。30分程度で読める単行本。「勤労感謝の日」は36歳無職女性の日常とお見合いの顛末。企業に対する皮肉もちらほら。「沖で待つ」は同期入社の男女の友情の話。双方の作品とも、主人公の気持ちには共感できて、ストーリーにもすんなり入ってくる。「沖で待つ」のラストでは感傷にも浸れる。だが、残念なことに、「あっそう?」という感じで終わってしまう平板な展開。もっと波瀾万丈とは言わないまでも、もうひとひねりあったほうがよかったのでは。最近の芥川賞受賞作にありがちな難解な本がいいとは決して思わないが、それでもこれではあまりに軽すぎではないかと思う。
2006年09月11日
コメント(0)
-

エンド・ゲーム 常野物語 恩田陸
またまた、恩田陸。チョコレート・コスモスでのさわやかな余韻に浸りながら、この調子でGO!というはずだったが、結果は???長年にわたってオセロ・ゲームのような戦いを続けている一族の話。ずいぶん前に常野物語を読んだのだが、すっかり内容も忘れている。この作品、二転三転するテンポは快調なのだが、そもそも肝心な「裏返す」とか「裏返される」とか「あれ」とかについて、なかなかイメージできないので、全体像がスッキリしない。そのため、結末もこれでよかったのかどうなのか、理解不能だった。ところどころでは、ミステリアスな箇所や、スリリングさに溢れるところ、身の毛がよだつような場面があるだけに、全体的な消化不良感が残るのは残念。訳が分からないが何となく雰囲気に浸る本なのだろう。恩田ファンにとっては、そこが魅力なのかもしれないのだが・・・
2006年09月10日
コメント(0)
-
近代日本の美術-常設展示 東京国立近代美術館
小茂田青樹の「虫魚画巻」。何回もこの絵を眺めた記憶があるのだが、画家の名前はまだ印象に深くなかった。この画家に気づいたのは、今年の山種の桜さくらサクラ展で「春庭」を見てから。あの道の奥に入っていくともうこちらの世界には戻れなくなりそうな幻想的な絵。それから、この画家を追っている。さて、「虫魚画巻」。金魚もいいけれども、このごろ「虫」づいているので今回は「灯による虫」がいちばん。暗闇に広がる電灯の灯り。そしてガラス窓の・・サッシではなく木枠の・・向こうとこちら側に多数の虫。屋外ではなく、部屋の中の虫も屋外の明かりに向かってガラスにくっついているのが面白い。室内の明かりにも虫が群がっているのだろう。確かに子どもの頃、こんな光景を見かけた記憶がある。夏だなぁ。暗闇に咲く紫のアザミと白いドクダミ、そして白い巣をはりめぐらした金色の蜘蛛。こちらも、昔見た絵本の挿絵のように懐かしい。川端龍子「草炎」。この作品にも何回か出会っている。昨年の龍子展では、「草の実」だったか。金泥のすらすらっとした無数の雑草。一本一本は弱々しく見えるが全体としてみるとたくましい生命力を感じる。「虫魚画巻」は10日で終わりだそうだ。
2006年09月09日
コメント(6)
-

ぼんくら 宮部みゆき
先に「日暮し」を読んだのだが、その前段の「ぼんくら」を読んでいなかった。たまたまブックオフの100円で文庫本を見つけたので、上下併せて210円也で購入。せっかくの休みで、美術館に出かける予定だったが、「ぼんくら」を読むのに夢中になり、結局一歩も外に出ないで終わってしまった。宮部みゆきお得意の江戸の人情話。登場人物もそれぞれ個性的で魅力に溢れる。特にお徳とおくめの二人の女性のやりとりに心打たれた。ぼんくら同心井筒平四郎と甥の弓之助のコンビも秀逸。シリアスな場面とコミカルな場面との絶妙なバランスも心地よい。ミステリー色は、続編の「日暮し」の方が濃いような感じがする。鉄瓶長屋の光景は、深川江戸資料館の街並みを思い浮かべながら読んでいた。この頃のひとつの長屋って、ひとつひとつ、それぞれが独立して作られていたのだろうか。鉄瓶長屋とほかの長屋の位置関係はどうだったのかとふと疑問に思う。
2006年09月08日
コメント(0)
-

常設展 埼玉県立近代美術館
常設展、さほど展示会場は広くありませんでしたが、洋画にしろ日本画にしろ素敵な絵がいくつかありました。入ってすぐに、モネの17歳の作品が展示されていました。1858年、ルエルの眺め。印象派の登場にはまだ程遠いが、画面からは澄んだ青空の明るい雰囲気が漂ってくる。モネははじめからこんなに明るい風景を描いていたのだったかなとふと思いました。その他、洋画ではデルヴォーの「森」。得体の知れない植物のうっそうと茂る森。樹木の陰に黄色い満月。ビロードを張ったテントにうずくまる裸婦。そして暗闇に遠ざかる汽車といった、デルヴォーのおなじみの世界。いつもこの画家の絵の前に立つと不思議な画面に吸い寄せられてしまうのです。古賀春江の「コンポジション」。暗い背景にキュビズムの裸婦。古賀の不思議な情景ではないが、これはこれでよし。日本画では、速水御舟の「夏の丹波路」。後の御舟のこれでもかというくらい緻密な絵ではなく、南画風のあっさりとしてそれでいて、木々の緑が美しい清々しい絵。御舟の初期の頃の作品でしょう。小村雪岱の「青柳」「雪の朝」。貼り絵のような平面的な光景の版画。先日の川瀬巴水とはまた違った感覚の素敵な版画でした。風景・窓・絵画-アーティストの視点からという特集で、母袋俊也という画家の作品が置いてありました。箱を作りそこに開いている穴から美術館所蔵の美術品の部分を覗き見するという趣向です。小さな穴ですので、対象の作品の一部しか見ることができませんが、逆に筆致や絵の具の盛り上がりなどがはっきり見えたり、面白い発見がありました。ロッカーに宮島達男の作品があったことを知らずに帰ってきてしまったのは悔しかったです。
2006年09月07日
コメント(6)
-
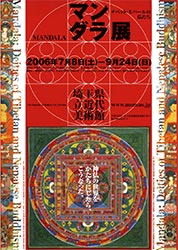
マンダラ展 埼玉県立近代美術館
昔から、マンダラという言葉には、なぜか惹かます。色あざやかで細密なマンダラ図を見るともう心はドキドキウキウキです。普通、博物館で眺める日本のマンダラ図は退色し落剥も激しいものが多いので、すごいなぁとは思いつつも、マンダラ本来が持つめくるめく恍惚の世界を味わうことができないので、残念に思っていました。しかし今回の展覧会に出ているのは、最近描かれたマンダラばかりなので、緻密で華麗なマンダラ光景を楽しむことができました。ただ、文化財的価値があるのかどうかは分かりません。最初のコーナーの仏像・仏画も興味深いものが多かったです。こちらもネパールで20世紀に作られたものばかりです。こわいもの系が好きな自分としては、異形の姿の仏たちが出てくるだけで満足です。それぞれの仏たちについての解説が分かりやすく、参考になりました。ただ、全体的に土産物屋や骨董品店で手に入りそうな展示品ばかりだったなぁという思いもしました。肉切り包丁と頭骨の杯を持つヨーギニーの像。女性ヨガ行者。↓
2006年09月06日
コメント(6)
-

モダン・パラダイス展 東京国立近代美術館
大原美術館に行ったのはもう20年近く昔で、どんな絵を見たか、記憶が定かではありません。そこで、めったに見ることのできない大原美術館の名品の数々を楽しめる展覧会だなぁと、お気楽に考えて出かけたのですが、さらにもっと深い意味がある展示コンセプトになっていて戸惑いました。事前に他の方々のブログで研究していけばよかったと思いました。副題にある東西名画の饗宴というのは、竹橋と大原そして、日本と西洋の双方の東西を引っかけているというところまでは簡単に分かるのですが、この展覧会全体で意図した目的~「現代の楽園」とは何ぞやという所まではたどり着けませんでした。思いのほか抽象絵画の作品が多かったこともありました。まぁ、今回は大原所有の絵画が東京で見ることができて嬉しいという単純な目標が達成できたことだけで良しとします。展覧会全体を貫くコンセプトについては次回、また考えることにします。さて、大原でいちばん見たいと思っていたエルグレコの「受胎告知」が、今回出展されないのが少々残念でしたが、セガンティーニの「アルプスの真昼」を見ることができてうれしい。今年はBunkamuraのスイス・スピリッツ展で別バージョンを見たので、2度もセガンティーのアルプスに出会えました。パレットで色を混ぜあわせない筆触分割の作品。一本一本の筆致が畳の目のようだ。それでいて、絵の表面は変にデコボコではなく、プレスされたように平らに見えます。モデルの女性の顔をよく見ると、口だけ明るい光が当たって、目は暗く不気味なマスクをつけた人物のようにも思えます。アルプスの清浄な光のシャワーを体感できます。ゴーギャンの「かぐわしき大地」。空飛ぶトカゲがいたりして、鳥や動物の鳴き声など、ジャングルの音が聞こえてくるようです。トカゲがヘビ、花がりんごを現しており、楽園のイブを描いたもの。大らかです。横に比較展示されている萬鉄五郎「裸体美人」も同様。どちらも豊満な肉体なんだけれども、エロスを感じられず、逆に生命力の強さを感じさせられます。日本の絵画では、関根正二の「信仰の悲しみ」。美術の教科書で見たときから印象に残る絵。関根の幻視体験から描いた絵ということ。先頭の白い衣装の女性の強い意思を持った表情と中央の何かに打ちひしがれたような赤い衣装の女性の表情の対比が興味深い。教科書で見て以来、どんなドラマを想定して描いたのかずっと気になっていた作品です。お気に入りの古賀春江の「深海の情景」がありました。真っ暗な深海に猫顔の女性の裸体像。古河の描くヴィーナスをやっと見ることができました。エル・グレコは来ませんでしたが、自分としてはそれに匹敵する作品に出合えました。中村彝の「頭蓋骨を持てる自画像」です。ブリジストンにある自信溢れる自画像に比べ、窪んだ眼窩にやせ細った弱々しい自画像。死の象徴である髑髏を抱えて、迫り来る死を受容しつつ、その向こうを見つめていこうとするような意志を感じました。10月15日までやっているので、再挑戦です。
2006年09月02日
コメント(10)
-

富本憲吉のデザイン空間 松下電工汐留ミュージアム
前回の新日曜美術館を見てから気になっていたので、はじめて、この美術館に出かけました。新橋の広大な空き地もあっという間にこんなビル街に変わってしまっていたのですね。さて、富本憲吉展。雨降りの平日日中にもかかわらず、かなりの人出。やはり、番組の影響なんでしょうね。陶芸作品に限らず、建築デザインやタピスリ、版画、書店のさまざまな意匠など、幅広く展示されていて飽きることがありませんでした。やはり、「日々の暮らしを楽しくするため」の陶器には見とれてしまいました。まず、楽焼の象の絵各鉢。尾形乾山かっ?と一瞬感じました。何ともゆったりとユーモラスたっぷりな象さんです。でも極めつけは、やはり金銀のシダの模様の角瓶。煙る銀のシダと輝く金のシダが、一面に絵付けされた赤絵の瓶。指を這わせてそのシダの細い葉の一本一本の感触を確かめてみたいなぁと強く感じました。ルオーギャラリーもほんの小さなスペースですが、小豆色をベースにした落ち着いた壁に小振りなルオーの作品がぐるっとかかっていて、椅子にのんびりと腰掛けて眺めることができる心地よい空間でした。
2006年09月01日
コメント(10)
全24件 (24件中 1-24件目)
1










