2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年03月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-
『暗殺の年輪』その2
承前この短編集『暗殺の年輪』に収録されている、「暗殺の年輪」と「ただ一撃」のいずれも女性が自害する。「暗殺の年輪」から、その場面をむせるような血の香がそこにたち籠めていて、その中に、膝を抱くようにして前に倒れている波留の姿があった。波留は穏やかな死相をしていた。冷たい掌から懐剣を離し、足首と膝を縛った紐を解いて横たえると、馨之介はもう一度手首に脈を探ったが、やがてその手を離して立上った。波留は馨之介の母である。馨之介の父は藩の勢力争いに巻き込まれ、ある上司の暗殺に失敗し、殺害された。その背後にある陰謀に気がついた馨之介は、母の秘密を知ることとなる。それに気がついた波留は、自ら命を絶ったのである。そこで、はじめて、馨之介は父が狙った相手の暗殺を決意する。それも、藩のためではなく、ただ己と母の為に。 「ただ一撃」の場合は、「辰江が死んでから、女子の肌に触れたことがない」「男のものも、もはや役に立たんようになったかも知れん」「もうお年ですゆえ、ご無理でございましょうと申し上げました」続きはまた・・・。
2008.03.31
コメント(0)
-
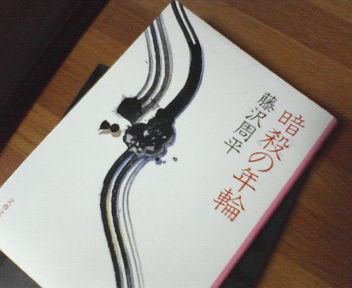
『暗殺の年輪(藤沢周平)』
この、『暗殺の年輪(藤沢周平)』は、著者の出世作を中心にしたもの。「黒い縄」「暗殺の年輪」「ただ一撃」「溟(くら)い海」「囮(おとり)」 発表順は、「溟(くら)い海」「囮(おとり)」「黒い縄」「暗殺の年輪」「ただ一撃」であり、あとがき(駒田信二)には、「溟(くら)い海」は、第38回オール讀物新人賞。第65回(昭和46年上半期)直木賞候補。「囮(おとり)」は、第66回直木賞候補。「黒い縄」は、第68回直木賞候補。「暗殺の年輪」で、第69回直木賞受賞。「ただ一撃」である。その他は、改めて。暗殺の年輪藤沢周平文春文庫1978年2月25日 第1刷1997年11月30日 第31刷
2008.03.27
コメント(0)
-
『昭和を笑わせた男たち 鬼才・天才』
2008年3月20日 NHK-hiヴィジョンで放送された、『昭和を笑わせた男たち 鬼才・天才』の録画を見ています。全部で2時間30分あるので、全部を一気には見られませんが、トニー谷、人生幸路、林家三平、桂枝雀、川田晴久・・・、まだ見ている最中。 NHKは再放送があります。これだけの番組をhiヴィジョンだけで終わらせはしないでしょう。 BS、地上波必ず放映すでしょう。その時は、是非ご覧ください。
2008.03.23
コメント(3)
-
『ダージリン急行(ウェス・アンダーソン)』
『ダージリン急行(ウェス・アンダーソン)』です。米国(?)の映画。インドが舞台だから、インドの映画かと、勘違い。ひどいものです、この思い込みは。映画は、面白い。鉄道を使ったものでは、一昨年の「明日へのチケット」が思い出されます。他にも、鉄道の傑作は沢山あります「北国の帝王」「大列車作戦」。 さて、これはロードムービーです。旅をしながら人が成長(大体が精神的に)するのが、ロードムービー。この『ダージリン急行』もその例に漏れない作品。色々な人が出てくるのも興味深い。曰く、ナタリー・ポートマン、ビル・マレー・・・。本編に先立って上映される短編『ホテル・シュバリエ』が、気に入りました。
2008.03.22
コメント(0)
-
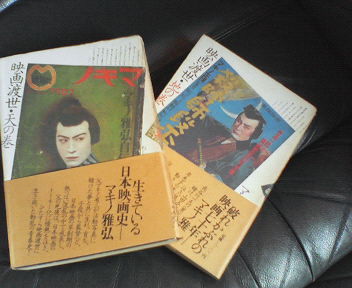
『日本侠客伝 マキノ雅弘の世界(山田宏一)』
これ『日本侠客伝 マキノ雅弘の世界(山田宏一)』は、以前山田宏一と山根貞男が編著した『映画渡世・天の巻』『映画渡世・地の巻』(昭和52年・平凡社)の、続編的あるいは、ダイジェスト版的本である。だから、やや粗っぽいところも見受けられる。しかし、山田宏一のマキノ雅弘に対する思い入れが一杯詰まっていることは十分に分かる。思い入れが強すぎるせいかもしれないが、読み進めて行くうちに、少々辟易とする。 だが、以下、マキノ雅弘の凄いところ・・・、 芝居のつけかたが印象的だった。男は腰に重心をかけて動け、女は左足に重心をおいて立って、右足を浮かせ、ちょっとうつむいて、右足で「の」の字を書いてみろ、というのである。それだけで男らしい「線」、女らしい「線」が出て芝居がきまるという・・・。p67 『日本侠客伝 花と龍(1969)』でのこと、星由里子は東宝から借りてきた女優さんでしたが、きゃしゃな体つきなのに芯が強くて、芝居もうまかった。泣くまいとこらえて笑顔をつくっても涙がこぼれてしまう、あの美しい顔は大女優だと思いましたよ。忘れられない女優さんですね。しかし、東宝は女優の育てかたが下手いうたら何やけど、あまり大事にしないらしく、星由里子のことでも、[当時]東宝専務の藤本眞澄氏から電話があって「東映からのたってのたのみでお貸ししたんですが、あんな鈍な女優に『花と龍』の玉井金五郎の女房マンの役がつとまりますか。きっとあなたが困っているのではないかと思って・・・」いうし、すぐまた同じ東宝の雨宮[恒之]撮影所長からも電話があり、「星由里子は当時の監督泣かせのナンバーワンでして、ちょっと心配になったもんですから・・・」とのこと。私は撮影の初日からすばらしくいい女優だと確信していたので、「クセのない、いい女優さんですよ」とお答えしたんですけどね。p110 この時の星由里子も、『日本侠客伝 血斗神田祭り(1966)』の野際陽子も、気持ちが高ぶり、本当に泣いてしまったという、エピソードもある。余談だが、『日本侠客伝 血斗神田祭り(1966)』の鶴田浩二と野際陽子は素晴らしい。今ではなくなったシステム、プログラムピクチャーは様々なものを残した。 マキノ雅弘の作品もその中に数えられる、当時いわゆるベスト10に入るものはなかったかもしれないが、今でも輝く作品は多い。マキノ監督の早撮りはかならずしも手抜きややっつけなどではなかったのだ。マキノ監督も、「やくざ映画一つとっても、絶対にわたしは[作品を]投げたことがない。自分の名前も出れば、客にお金をとって見せるんですからね」と語っている。(名古屋シネマテーク編「シネアストは語る――4 マキノ雅弘」 聞き手/森卓也 風琳堂)孫引きですが、ここにもマキノ監督の姿勢がある。CSなどでの放映があれば見たいと思う。 日本侠客伝 マキノ雅弘の世界山田宏一ワイズ出版2007年12月29日 第1冊
2008.03.21
コメント(0)
-

『又蔵の火(藤沢周平)』
『又蔵(またぞう)の火(藤沢周平)』は、再読です。といっても、「又蔵の火」のみで、他の収録作「帰郷」「賽子(さいころ)無宿」「割れた月」「恐喝」は、はじめて読みました。 さて、藤沢周平の特徴の一つに、斬り合い場面があると、思います。この「又蔵の火」の土屋又蔵こと土屋虎松と義理の甥、土屋丑蔵との対決は、すさまじい。ここに至るまでの、出来事と最後の対決までをもう一度読みたくて、買って手許にある本が行方不明になり、図書館で借りました。 最初読んだ時は、この対決(仇討ち)は、討つ側、又蔵に三分の理もないと思いましたが、今回の再読では、又蔵の兄を思う気持ちを幾分かは理解できました。というより、こういう物語を書く藤沢周平の作家としての思いが少しは分かったというほうが自分の気持ちに近い。 話の骨子は、土屋家の放蕩息子、万次郎(又蔵の実の兄)を、討った丑蔵と土屋三蔵を敵(かたき)と狙う、又蔵の物語。とにかく、最後の対決場面は凄惨である。その凄惨さは読んでいただくのが一番である。 この写真は、ここから引用しました。有難うございます。兄、万次郎が殺されたことについて、虎松(又蔵)と、かつて兄、万次郎と虎松が土屋家を逃げ出したとき世話をした石田が、虎松に話す・・・、「だがな、本当は殺してやりたいぐらいは思うものよ。みんなきちんとして、それでもって世間体をつくろって生きている。辛いことがあってもこらえてだ。ところが一人だけ勝手なのがいて、思うまま、し放題のことをする。世間に後指をさされまいと気張っている家の者のことなど、お構いなしだ。これは殺したいほどのものだ。世間体をつくろうのも限りがあってな。そのうちくたびれる」p40 また、藤沢周平を読んでいて、興味深いのは、次のようなところである。又蔵は脇の下の菰包みと風呂敷包みを抱え直した。菰包みには、小笠原重左衛門が餞別にくれた二尺二寸四分の久道銘の刀と、無銘の小刀が入っている。風呂敷の中身は、黒羽二重の袷、浅黄の小袖、藤色縮緬のたんな、矢立、それに縮緬袱紗に包んだ心形刀流の目録巻物、武術免状書などである。p72この時、又蔵に剣術の師、小笠原重左衛門は、それなりの支度をしていることが分かる。そのあたりの、記述に又蔵の修行態度が真摯であったことが伺われ、兄、万次郎への思いも察せられる。 さて、残る、四篇であるが、すべて、やくざの話である。そこで、はじめて見た言葉「手目」、博打でいう「いかさま」のことである。藤沢作品では「てめし」と読ませている。手許にある辞書にはこの言葉はなかった。ネットでしらべると、「手の目」という妖怪が出てくる。たぶん、これが転じていかさまになったのだと思われる。私の調べて、唯一「手目」がいかさまとして出ていた事典は「江戸語辞典」でした。 又蔵の火藤沢周平文春文庫1984年11月25日 第1刷1997年2月15日 第16刷
2008.03.20
コメント(0)
-
『実録 連合赤軍 あさま山荘への道程(若松孝二)』
3時間余の大作。可也重い。同じ時代に大学生であった自分はある面で身につまされるところがあった。同じ様な体験があるからだろう。だが、同じ様であるが、この映画にある激しさとは程遠いものであった。 私たちより、10歳以上若い人がこれを見て何を思うのか興味がある。『実録 連合赤軍 あさま山荘への道程(若松孝二)』
2008.03.16
コメント(7)
-
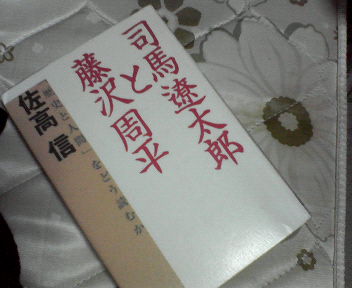
『司馬遼太郎と藤沢周平(佐高信)』
ここのところ、ず~っと藤沢周平です。前回に続き、佐高信の藤沢周平。これも、前の『山本周五郎と藤沢周平』同様に、ある一面で、司馬遼太郎攻撃の本です。私は、『燃えよ剣』や『歳月』くらいしか司馬遼太郎を読んでおらず、『項羽と劉邦』を上巻の途中で放り投げたのですが、その時は、『項羽と劉邦』を、あまり面白く思わなかったのです。その後、司馬は経済畑の人々にアイドルのように読まれ、それが気に入らず、それ以来、司馬は読んでいません。それに、司馬遼太郎は自分にはあわなかったようです。 さて、『司馬遼太郎と藤沢周平』です。藤沢は、「信長ぎらい」というエッセイで、《(信長の)こうした殺戮を、戦国という時代のせいにすることは出来ないだろう。信長にしろ、ヒットラーにしろ、ポル・ポトの政府にしろ、無力な者を殺す行為をささえる思想、あるいは使命感といったものを持っていたと思われるところが厄介なところである。権力者にこういう出方をされては、庶民はたまったものではない。》司馬にはこういう視点はない。「信長と独裁」では、逆に、「信長は、すべてが独創的だった」と礼賛している。ところが、日本の政財界の将たちは、あたかも自分たちに能力があったからのように錯覚してきた。彼らをその気にさせたのは司馬遼太郎である。p19.20 元世界銀行副総裁・服部正也は、「戦に勝つのは兵の強さであり、戦に負けるのは将の弱さ」なのに、司馬の作品は「戦に勝つのは将の強さ」と錯覚させると、批判した。p77司馬(遼太郎)と城山(三郎)はこの松下幸之助観において決定的に違う。司馬は松下を「非常にすぐれた合理主義者」と見ているが、毎朝社歌を歌わせ、伊勢神宮を流れる五十鈴川にフンドシ一つで入らせる「みそぎ研修」をやらせている松下幸之助がどうして合理主義者か。城山は、本田宗一郎と松下を対比させながら、「本田さんにとっての生涯の悔いは会社に本だと名前をつけたことだ。・・・(松下は)松下と名前がついていることを誇りに思っている」p78 《私は性格に片ムチョ(意固地)なところがあり、また作家という商売柄、人間の美しさを追いもとめる半面、汚なさも見落とすまいとするので、世間でえらいという人をも簡単には信用しない。それでも時どきえらいな、と思う人に出会うことがある。その人は、冷害の田んぼに立ちつくす老いた農民だったり、子供のときから桶つくりひと筋に生きて来た老職人だったりする。出会う場所は、テレビの場合もあり、新聞記事の場合もある。彼らは、別格自分や自分の仕事を誇ることもなく、えらんだ仕事を大事にして、黙々と生きてきただけである。だが、それだからといって、そういう生き方が決して容易であったわけでなく、六十年、七十年と生きる間には、山もあり、谷もあったはずである。しかし彼らはその生き方を貫き、貫いたことで何かを得たのだと、私は皺深い農民の顔を写した写真を、つくづくと眺めるのである。人生を肯定的に受け入れ、それと向き合って時に妥協し、時に真向から対決しながら、その厳しさをしのいで来たから、こういういい顔が出来上がったのである。えらいということはこういうことで、そういう人間こそ、人に尊敬される立場にあるのではないかと、私は思ったりする。実際人が生きる上で肝要なのは、そういうことなのである。こういう質朴で力強い生き方にくらべると、世にえらいと言われる人のえらさは、夾雑物が多すぎるように見える。》p142これは、『周平独語』の孫引きである。 佐高信と宮部みゆきの対談から、 (宮部)ごく普通の人間がごく普通に生きていても、たとえば世間さまに顔向けできないようなことや、もう自分でも思い出したくないようなことの一つや二つ、ありますよね。それこそがやっぱり人間の傷なんだし、それを大げさに見せはしないけど、生身の人間として、その傷をいっしょに生きてゆく人間を、きちっと書いていくことが大切なんだろうなって、思っているんです。(宮部)今イヤだなあと思うのは、わりとお手軽に癒やしの小説という言葉が使われていることです。藤沢先生の小説では、人間はそう簡単に癒やされるものではないし、簡単に癒やされるようではいけないんだと。p252.253 青・太字は引用です。 巾櫛(きんしつ)の妾=執巾櫛(きんしつをとる)というのがある。人の妻となること。清河八郎の詩にある。これも学んだこと。この本の底に流れる思想は、派手なものではなく、地味だが確実なもの、そういう人間を認めようというものだ。しかし、それはとても難しい。自分でも、もてはやされたりすれば、それに逆らうだけの勇気が果たしてあるのか自信はない。だから、藤沢周平に惹かれるのかもしれない。 司馬遼太郎と藤沢周平「歴史と人間」をどう読むか佐高信光文社1999年6月30日 初版1刷発行1999年7月20日 3刷発行
2008.03.12
コメント(1)
-
『ジャーマン+雨(横浜聡子)』
『ジャーマン+雨(横浜聡子)』は、よく分からないが、魅力的だ。主人公の女の子もその友達も、三人の子供たちも、すべてが人間としての存在感があり、独自のスタンスを持っている。そういう描き方だ。 71分の短い映画だが、だらだらしないだけ好感がもてる。
2008.03.11
コメント(1)
-
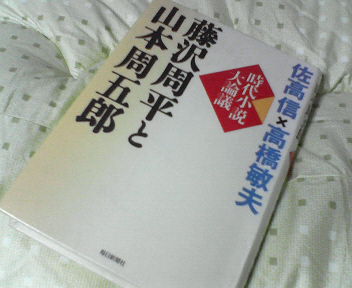
『藤沢周平と山本周五郎 時代小説大論議(佐高信・高橋敏夫)
間違えて借りた本。『藤沢周平と司馬遼太郎』を借りるつもりが、根っからの慌て者だから、この『藤沢周平と山本周五郎』を借りた。だが、時代小説を通じての思想の話はとても興味深いものであった。佐高信の「はじめに」にこうある・・・、本田宗一郎は、『徳川家康』を読み、作者の山岡荘八に、四回も質問状を出した。「江戸城をつくるとき、四国などから大勢の人を連れてきたが、城が出来ると、城内の秘密がばれるからと、みな殺しにしてしまっているんです。(略)働かせておいて殺すとは、いったい何事ですか。侍は大事だが、人足なら殺してもいいというのは、どうしても合点が行かない。人間許せることと、許せないことがある」こう思って本田は手紙を出したのだが、山岡からの返事は肝心のことに答えていなかった。 評論家の平野謙は、松本清張の解説で、誰もが書いている大物を松本清張に書いてほしい。そうしないと、いつまでたっても山岡荘八のようなできの悪い作家が捉えた権力者(家康)像しか残らない。p189 このように、この本は書かれており、司馬遼太郎なども紙芝居だと、斬って捨てている。痛快也。歴史には正史と野史があり、または歴史小説と時代小説があると言う。正史は時の権力者による歴史でしかなく、闇の歴史が、人間にとって大きな意味を持つこと、を力説する。歴史小説は正史であり、時代小説は野史(外史)であるとも。そこで、例として挙げてあるのが『斬に処す(結城昌治)』や『相楽総三とその同士(長谷川伸)』である。これらは、常識崩しである。p031 山形には「出羽三山」という言い方がありますけれども、歴史小説にも三山(※)みたいなものがありますね。この三山の前では、司馬遼太郎なんか蜃気楼みたいなものですね。p164※『夜明け前(島崎藤村)』『山の民(江馬修)』『大菩薩峠(中里介山)』 山本周五郎のよく知られている言葉に、人の満足やよろこびよりも失意や絶望のうちにこそ人間の人間らしさを感じる、というのがあります。p186 この二人(佐高信と高橋敏夫)は、徹底的に正史(権力)を斬り、闇の世界、底で懸命に生きる人間たちに注目する。それが、山本周五郎であり、藤沢周平の書いてきた小説世界である。他に、二人は隆慶一郎、松本清張、吉村昭を評価する。今、藤沢に嵌っているので、これは納得しながら読んだ。藤沢周平と山本周五郎 時代小説大議論佐高信*高橋敏夫毎日新聞社2004年11月30日発行
2008.03.10
コメント(2)
-
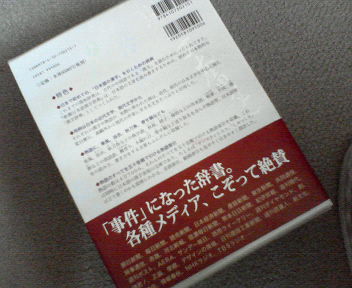
「新潮日本語漢字辞典」
『新潮日本語漢字辞典』ようやく入手。増刷されたわけですね。 新潮日本語漢字辞典新潮社編集発行 2007年9月25日三刷 2008年3月5日
2008.03.08
コメント(0)
-
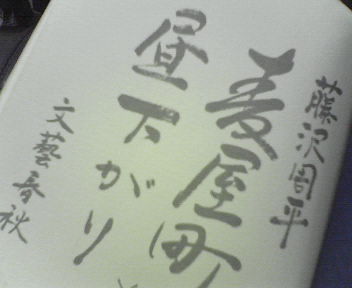
『麦屋町昼下がり(藤沢周平)』
昭和62年から64年に『オール讀物』に掲載された4篇を収めた。「麦屋町昼下がり」「三ノ丸広場下城どき」「山姥橋夜五ツ」「榎屋敷宵の春月」の4篇である。ここのところ、藤沢周平は『漆の実のみのる国』『海鳴り』『風の果て』と言った長編ばかり読んできたように思うが、長編が所謂フルコース的なものだとすれば、今回の短編はア-ラ-カルトだ。それも、第一級の味わいである。「麦屋町昼下がり」は、因縁の二人の対決。「たそがれ清兵衛」を思わせる。この作品でもそうだが、斬り合いでは、必ず二人とも傷つく。そして決着は、体力に大いに関係する。これも、藤沢の味だ。 「三ノ丸広場下城どき」は、やもめの重兵衛と手伝いに来た怪力茂登のほのぼのとした話と、血腥い決闘を描いている。 「山姥橋夜五ツ」昔の藩主の暗殺の一部始終を知りながら、それを抱えきれず自害した男とその親友。親友、孫四郎はその秘密を遺書から知ってしまう。孫四郎は妻が不義を働いたとして、離縁する。しかし・・・。というこれも中々面白い。 「榎屋敷宵の春月」は、出世争いに巻き込まれながら、正義を貫こうという、武家の妻、田鶴。小太刀の使い手である。ここでの、田鶴と剣客岡田十内との決闘も互いに斬られながらも、行き絶え絶えになり・・・、という展開。 4篇ともに、武家の物語。どの作品も映画にしたらと、思わせる。とにかく、面白い。 麦屋町昼下がり藤沢周平文藝春秋1989年3月10日 第一刷1989年4月10日 第三刷
2008.03.06
コメント(2)
-
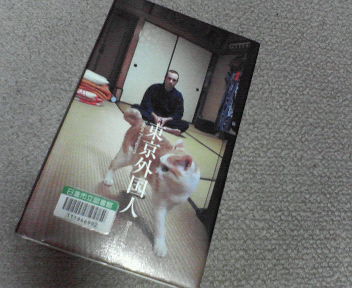
『東京外国人(Beretta P-07)』
Beretta P-07というのは、東京写真学園出身者による写真家集団のこと。これは、そのBeretta P-07の59人による写真集。東京に住む外国人の家を撮ったもの。 この種は、都築響一の『賃貸宇宙』が先にある。それのアイディアを撮ったものか? それでも、この猥雑さが面白い。 東京外国人Beretta P-07雷鳥社2007年7月19日 初版第1刷発行
2008.03.04
コメント(0)
-
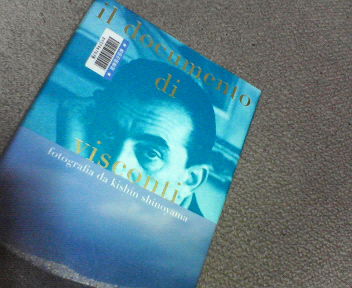
ヴィスコンティの遺影
この写真集は中中素晴らしい。
2008.03.02
コメント(0)
-
『漆の実のみのる国』続き
『漆の実のみのる国』(下)から、しかしかつて細井平洲は、治憲に「管子」冒頭の牧民篇にある「倉廩実(ソウイリンミ)つれば則ち礼節を知り、衣食足れば則ち栄辱を知り」という語句を指し示したことがある。倉廩=そうりん 米穀をたくわえるところ。穀物のくらや米ぐら。 普段私たちは、「衣食足りて礼節を知る」と認識していたが、「倉廩実(ソウイリンミ)つれば則ち礼節を知り、衣食足れば則ち栄辱を知り」であった。内村鑑三の『代表的日本人』にも「衣食足りて礼節を知る」と書いてある。「倉廩實,則知禮節;衣食足,則知榮辱」と、いうのが原文らしい。 治憲(鷹山)が、治広に家督を譲ったとき示した三か条は、一、国家は、先祖より子孫へ伝候国家にして、我私すべきものには無之候一、人民は国家に属したる人民にして、我私すべき物には無之候一、国家人民の為に立たる君にて、君の為に立たる国家人民には無之候右三条、御遺念有間敷候事、これらも、今の日本にとって忘れられた事共ではないかと、思う。
2008.03.01
コメント(2)
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-
-

- あなたが夢中なセレブゴシップ&Kア…
- 天気悪いなあ~ 雨降り心配の小さく…
- (2025-04-26 15:25:48)
-
-
-

- アニメ番組視聴録
- 11日のアニメ番組視聴録
- (2025-11-11 19:09:38)
-
-
-

- TVで観た映画
- 夫の策略で浮気相手と妻が疑心暗鬼に…
- (2025-11-18 07:25:11)
-







