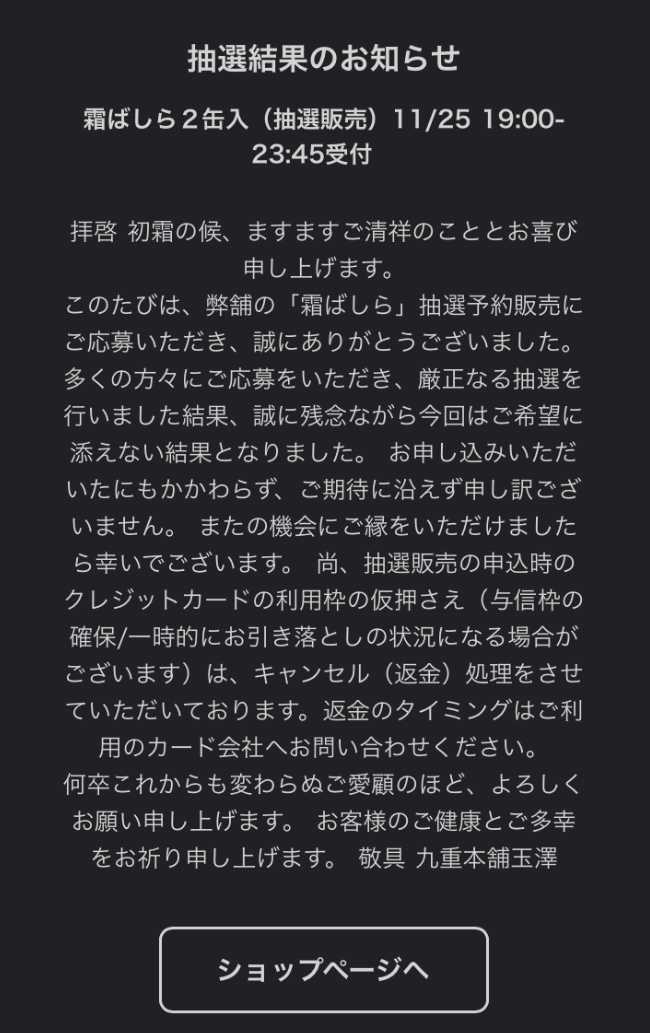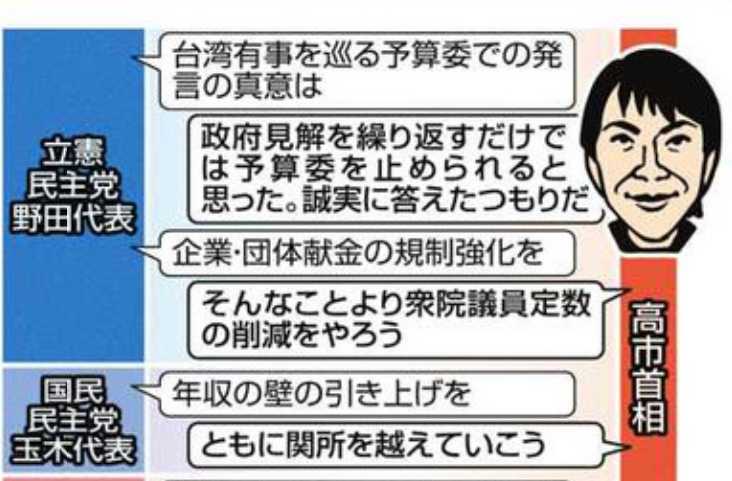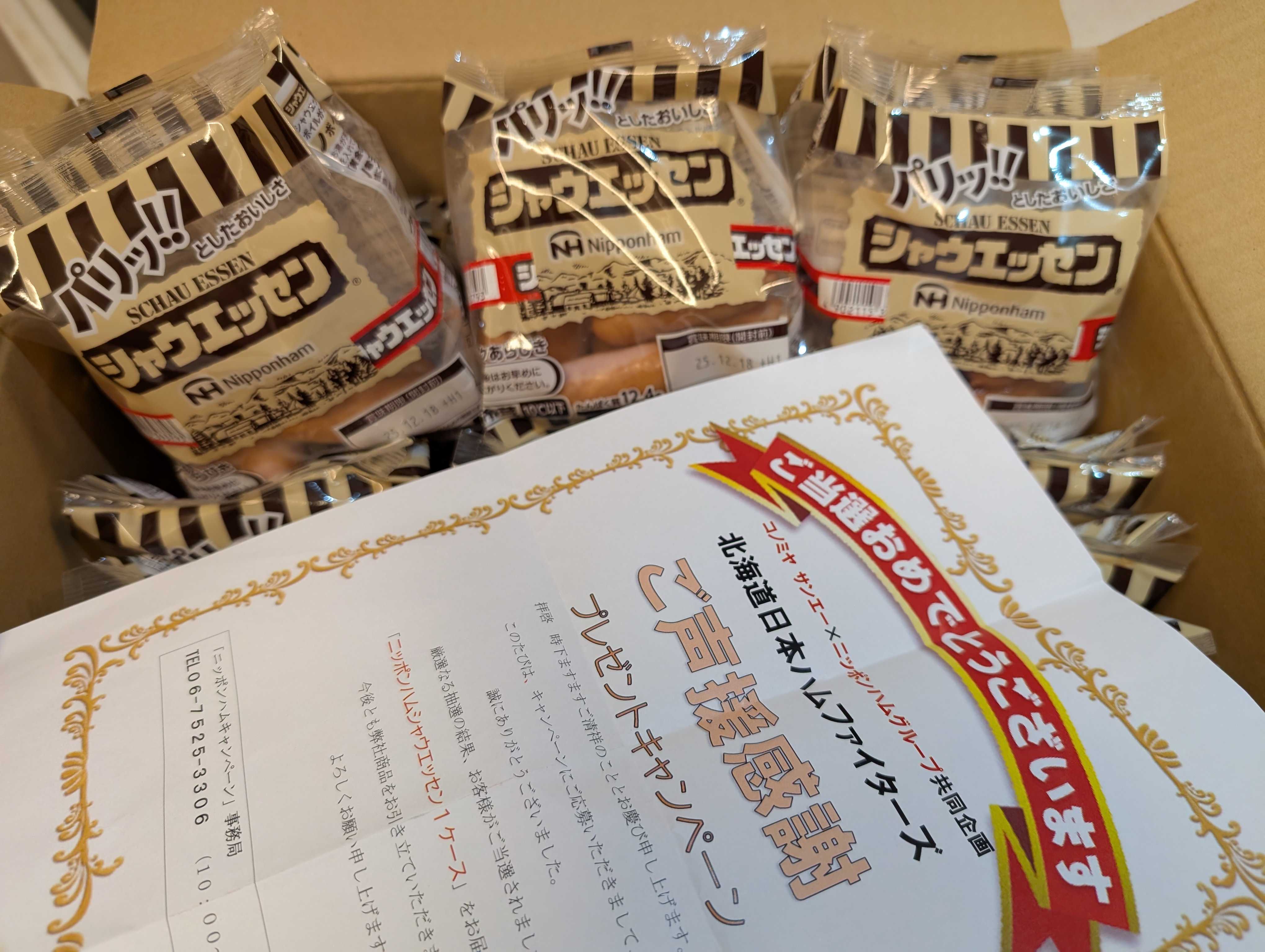2025年03月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
読売新聞「思潮」コーナーに登場!
今日も今日とて、母が亡くなった関係の手続き。区役所行ったり、銀行行ったり。でも、必要書類が色々あって、除籍の書類だ、印鑑証明だ、なんだかんだで、大変よ。まあ、そういうもんか。 銀行の手続きも複雑で、先にどこかに電話しなくてはダメ、と言われたり。別な銀行では、変な小部屋に連れていかれて、オンラインであれこれやったり。待ち時間も多く、疲れちゃった。 そんな中、知人より連絡が入り、ワシのことが読売新聞に出ておるぞと。 ん? 読売新聞に出るのは、もうちょっと先の予定なんだけど? と思ったら、私が書いた原稿が掲載されているというのではなく、PHPが出している『Voice』誌4月号に載った拙稿が、今朝の読売新聞の「思潮」コーナーで取り上げられた、ということらしい。 え゛ーーー。そうなの? やった~! 56,000字という、そこそこの分量の原稿だったんですけど、結構、気分よく、サクサク書いた記憶がある。まあ、そういう時は原稿の出来もいいものなんですけど、それが大新聞に取り上げられたとなると、さらに気分よしこちゃん。 というわけで、今日は疲れることもあり、嬉しいこともあり。禍福はあざなえる縄のごとしでございます。 嬉しいことがあったので、たい焼き買って帰りました
March 31, 2025
コメント(0)
-

レス・ギブリン著『人の心をつかむ15のルール』を読む
レス・ギブリンが書いた『人の心をつかむ15のルール』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 レス・ギブリンというのは1912年生まれのアメリカ人で、軍隊を出た後、万年筆メーカーのシェーファーに勤めていた人ね。で、シェーファーでは訪問販売で抜群の業績を挙げ、「セールスマン・オブ・ザ・イヤー」に選ばれている。以後、他の色々な業種の会社に招かれてセールスマンの心得などを講演して回り、いつしか自己啓発ライターになってしまったという人物。本書は彼が1968年に出版した代表作『Skill with People』という本の訳ですけど、原著も44頁くらいしかないパンフレットみたいな本。でもこの業界では名著と言われている。 ではこの本にはどういうことが書いてあるかといいますと、要するに人心掌握法です。 で、ギブリンの人心掌握法のキモは何かというと、「人間の最大の関心事は自分自身だ」ということ。換言すれば、人間というものは、他人から重要人物として扱われたいと思っている、ということですな。このことは太古から変わっていないし、未来永劫変わることがない。だからこの人間心理を理解すれば、あなたもたちどころに人を魅了できると。 だから他人と初めて会ったら、まず微笑む。これ重要。こちらが微笑めば、相手からの微笑みを得ることができる。相手は自分の反映だから。そして出会った最初の10秒で、以後の両者の人間関係が決まってしまう。 相手の話を全身全霊をもって聞く。相手の名前を呼ぶ。パーティーでは、主催者のみならず、その場にいる全員に気を配る。「私は・・・」と話し始めるのをやめ、「あなたは・・・」と話し始める。 それから相手に反論しない。これも重要。ギブリン曰く「相手の意見に賛成できないことはよくあるが、『絶対に反論しなければならない場合』を除いて、それをわざわざ口に出す必要はない。また相手の意見に反論する必要は、実際にはめったにない」(39頁) 自分のことを売り込みたければ、第三者の言葉を引用する。「私は有能です」ではなく、「自分は○○さんから評価されています」と言った方が効果的。なぜなら第三者の客観的な意見は、当人の意見より信用されるから。 相手に「イエス」と言わせる工夫をする。セールスでは、「この中でほしいものはありますか?」ではなく、「あれとこれ、どちらを買われますか」と問う。相手にイエスとノーの選択肢を与えるのではなく、イエスとしか言えない質問の仕方をする。 とにかく相手を褒める。それも心を込めて。しかも、相手そのものを褒めるのではなく、相手がなした行為を褒めることが重要。「あなたは優秀ですね」ではなく、「あなたが作成したレポートは見事でした」とほめる。 人は注意されたくないもの。どうしても注意する必要がある時は、第三者のいないところで注意する。その際、相手の人格を否定するのではなく、相手の特定の行為のみを注意し、こうすべきであったという代替案まで示し、注意し終わったら、「これで問題は解決した」と伝えて、和やかに別れること。 感謝するときは、相手の名前を言ってから感謝する。「ありがとう」ではなく、「○○さん、ありがとう」と言った方が効果は絶大。 人前で話す時は要点を決め、出来るだけ短くすます。雄弁家になろうとしない。 そして、これらの人心掌握術で一番重要なことは、知識としてこれらのノウハウをわきまえるだけでなく、実際に現場で使うこと。 とまあ、この本に書いてあることは、ざっとこんな感じ。 で、自己啓発本の歴史から言うと、これはデール・カーネギーの『人を動かす』という本の直系の「人心掌握系自己啓発本」ですね。カーネギーの本は1930年代ですけど、それから30年経った後も、この手の本には多いに需要があったと。 いや、それを言ったら、今だって需要はありますよね。実際、この本に書いてある人心掌握術は、今でも役に立つ。 たとえば「人の最大の関心事は自分自身だ」にしても、ホントの真理ですよね! これを肝に銘じていたら、人間関係、すごくうまくいくと思う。それに先に引用した、「相手の意見に反論する必要は、実際にはめったにない」にしても、すごい真理だと思いますもん。 というわけで、15分で読める本ではありますが、ここに罹れていることを実践したら、あなたは確実に出世できる。実践は難しいけどね! でも、本当にやったら、あなたも「セールスマン・オブ・ザ・イヤー」に選出されること間違いなし。いい本です。教授のおすすめ!よ。これこれ! ↓人の心をつかむ15のルール (レス・ギブリン) [ レス・ギブリン ]
March 30, 2025
コメント(0)
-
女性が見ている世界
今日は、午前中、ちょっと相続系の手続きをしていたのですが、午後からは暇に任せて本を読んでいました。 まだ読み終わっていないので、感想はまた後日に書きますが、その本は著者が女性でね。私より10歳くらい若いようですが、まあ、大雑把にいえば同世代と言えなくもない。昭和の感性を持っているという意味で。 で、それを読みながら思ったのですが、女性の経験というのは、我々男とは全く違うものであるなと。 まあ、そんなことは私だって百年も前からわかっていることですよ。だけど、なんとなく、いままでそのことをあまり気にかけていなかった。だって、自分の経験じゃないのだから、本当の意味で、自分の問題にはならないと思っていたから。 むしろ、そういうのを理解しちゃうという人のインチキ臭さが嫌だったりするわけよ。 たとえば、日本人なのに、アメリカの黒人の苦悩を理解するという人、いるじゃない? そういうのも、いや、あなたがいくら頑張ったって、そんなの本当の本当の本当には理解できるはずないじゃんと思ってしまう。 だから、私はそういうのにはなるべく関わらないようにしていたわけ。 だけど、今回、この本を読んでいて、女性の見ている世界とはこんなに自分の見ている世界とは違うものかと素直に思えちゃった。 なんでだろうね。歳を取ったからか。仏に近くなってきたからかな。 とにかく、なるほど、女性が見ている世界というのはこういうものかというのが分かると、また世界についての見方が少し変わってくるようなところが当然あるわけで、それは自分にとっては良い事ではあるのだろうなと。 というわけで、いい勉強になりました。
March 29, 2025
コメント(0)
-
実家に戻る
春休み、一週間ほど実家で過ごすべく、今日、帰って参りました。 ま、今回はね、昨秋に亡くなった母のための手続きを、あれこれやらなくちゃいけないということもあるのですが。面倒臭いけど、仕方ない。明日は司法書士の人に会わないと。 でも、まあ、自宅から300キロ離れると、仕事のことも忘れられるので、いい息抜きにはなりますわな。最近、働きすぎだからね。 で、今日も新東名をかっ飛んできたんですけど、高速沿いに桜が見えるところがある。愛知県内ではチラホラ1分咲きだった桜も、静岡では3分か4分くらい咲いていました。やっぱり、静岡県ってのは温暖なんだね。 で、今回もまた清水インターで、最近お気に入りのペッパーランチを堪能。でまた、食べ終わった頃にふとみると、しずおかおでんの店でタケノコのおでんというのを売っているじゃないの。へえー、そんなの食べたことない。 ということで、ついでにそれも食べちゃった。串に刺さったタケノコのおでん、2本で304円だったかな? 安い、安い。出汁がしみて、春の味でしたよ。 あ、そうそう、そう言えばその前に浜松SAで、又一庵の「あんバタぱんまんじゅう」というのを食べたのですが、これ、めちゃくちゃ旨いんだよね!これこれ! ↓又一庵 あんバタぱんまんじゅう ということで、自宅から実家までの道中、色々、食べまくっちゃった。 ま、それはともかく、しばらく東京からのお気楽日記、お楽しみに~!
March 28, 2025
コメント(2)
-
学会、がっかり
今日、所属学会の機関誌が届いたのだけど、今年も日本語版には論文が一つも載っていなかった。論文がないので、いきなり書評から始まるという。もうその時点で、学会として終わってるよね・・・。いかに会員数が激減したとはいえ、1年間のうちに投稿論文ゼロだなんて。 で、書評だけはあるのだけど、なんと私の本は短評扱いだったという。しかも、全然、内容を理解していないものだった。 もうさ、この学会に所属している意味、あるのかな? とりあえず、今後は本を出しても、学会に献本するのは止めよう。そして、なるべく早く、折を見て退会しよう。
March 27, 2025
コメント(0)
-
本の書き方
今年は既に2冊の本を公刊し、執筆方面では大車輪なんですけど、なんかね、掴んできた感じがするのよ、本の書き方のコツというか、そういうものを。 これ、誰だったか、やたらにビジネス書を書くライターが、YouTube上の「本の書き方講座」みたいなところで言っていたことの受け売りなんだけど、本を書く時、本を書こうと思って書いちゃダメなのよね。 つまり、完成品を目指して書いたらダメってこと。 完成品を書こうとしたら、それこそ一行書いては一行消し・・・みたいなことになるわけじゃん? そんなことしてたら、いつまでたっても前に進まない。 だから、もうね、テキトーでいいから、こういう方向のことを書きたいんだよなー程度のことを、めっちゃくちゃに書くわけ。順不同でもいいし、文章の完成度なんかどーでもいい、というつもりで書く。いや、書くのではなく、書き散らすの。 で、とにかく、40行でも50行でも、どんどん書く。2頁、3頁、4頁、じゃんじゃん書く。しっちゃかめっちゃかな形でもいいから書く。 で、散々書き散らしておいて、翌日、ちょっと直す。前の日に書いたものを、削ったり付け足したりして、ちょっと形を整える。 そうすると、案外、まともなものになるのよ。そうして調子が出てきたら、またバーっと書く。そして翌日、それをちょっと直す。 で、そうやって早書きして、何となく最後まで書いたら、今度はちゃんと直す。この時は、完成品を目指してもいい。 そうやって書いて行くと、案外、書けるもんなのよね。 っつーことで、最近は全部その方式で書いている。だから、ペースとしてはすごくいい。1ヵ月くらいあれば、新書くらい書いちゃうよ。 というわけで、今もその方式で順調に執筆中。春休み中にできるだけ前に進んで、夏前までに完成させる。 ま、そんな感じで、今、ガンガンやってます。
March 26, 2025
コメント(0)
-

近藤史人著『藤田嗣治「異邦人」の生涯』を読む
先日、パラミタ・ミュージアムで開催中の藤田嗣治展を見に行った時に、えらく感動して、帰りがけにミュージアム・ショップで近藤史人著『藤田嗣治「異邦人」の生涯』という本を買ったのですけど、それを読み終わりましたので、心覚えをつけておきましょう。 結論から言いますと、この本、すごく読みやすく、面白い本でした。 でね、これを読むと、藤田嗣治というのがいかに誤解され続けた画家であったかというのがよく分かる。 藤田は東京芸大の前身の美術学校を出るのですが、フランスに修行に行くと。 当時、日本の画家がフランスに修行に行くというのはよくあることだったわけですが、そういう人たちってのは、フランスで今売れている大家の作品を真似たような絵を勉強して、それで箔をつけて日本に戻ってきて、大家になるという道筋を取る。 ところが、藤田に言わせると、なぜ他の日本人は、フランスに留まって、フランスの同世代の画家たちと丁々発止、腕一本で勝負しないのかと。 だから、藤田は、日本に帰らず、そのままフランスで名を上げる。 ところが、やっかみなのか、日本の画家たちは「藤田はその芸術性が評価されたんじゃない。あのヘンテコな髪形と奇行で評判をとっただけだ。その意味で日本の恥さらし、国辱だ」と藤田をけなす。だから一時帰国した藤田が、作品を公募展みたいなところに出しても、全然、評価されないわけ。フランスでは超売れっ子なのに。 で、戦争が始まった時、藤田は日本に帰国して、軍部の命令に従って国威発揚のための戦争画の制作に情熱をこめて打ち込み、戦争中は評価されるのだけど、戦後、掌返しで戦争責任を問われることになる。いや、藤田以外にも戦争画作成に従事した画家は大勢いたし、横山大観なんて、自分の絵を売ったお金で戦闘機を4機も購入して国に納めているのに、そういう大御所に対しては責任は問わない。やっぱりここでも、異邦人である藤田をいけにえの羊にするわけですよ。 で、嫌になって藤田がフランスに戻ると、「逃げた」という。そして、日本での誹謗中傷はフランスにも届き、フランスでも一時、藤田の評判は落ちる。 まあ、本当にひどい話ですわ。私は藤田嗣治というのは、人気画家なのだと思っていましたけど、その逆だね。こんなに嫌われた画家はいないくらい。 でも、最後の最後、フランスに帰化し、フランスに骨をうずめることを決意してからの藤田は、穏やかな、そして画業に打ち込む生活ができた。そこが唯一の救いよ。そして、彼は最後の仕事として、自分自身の教会を作り、その教会を自分の宗教画で飾ることに着手する。そして、それをやり遂げてから亡くなるわけ。 いやはや、この本を読むと、藤田嗣治が日本でもフランスでも異邦人として扱われ、その異邦人性の中で苦悩しながら、自分の道を進んでいった様がよくわかる。当然、この本を読む側としては、藤田サイドについているわけだから、藤田を苛めた奴らのことは覚えておこう、という気になりますわな。特に藤田にさんざん世話になっておきながら、藤田の友人であることが知れるとやばい、ということになると、途端に掌返しで冷たくあしらった奴らの名前は忘れないぜ。 一方、ワタクシの好きな岡本太郎は、日本での評判とか関係なく藤田を慕ったそうだから、そこは良かった。 とまあ、そんな感じで、藤田嗣治の生涯をざっと振り返るには、持ってこいの本。教授のおすすめ!と言っておきましょう。これこれ! ↓藤田嗣治「異邦人」の生涯 (講談社文庫) [ 近藤 史人 ]
March 25, 2025
コメント(0)
-
今日は卒業式
今日は勤務先大学で卒業式がありました~。 久しぶりに会ったゼミ生たちは、今日ばかりは袴姿で、やっぱり華やかなものですなあ。式後、一緒に写真を撮ったり、寄せ書きとかもらったりして、わいわいやって、送り出して、一人、研究室に戻ると、やっぱりちょっと寂しいもので。 こうして毎年卒業生を見送って、もう三十数回、この気分を味わったわけですわ。 そしてあと数年で、私自身もこの大学を卒業することになると。なんでも順繰りですけれども、もうすぐ自分の順番が来るとなると、ちょっとね。どんな気分になるのかな、なんて、想像しちゃいますね。 肩の荷が下りるような、寂しいような。 でも、コロナ以降、謝恩会をやることがなくなったので、そこは寂しいな。せめて、謝恩されて大学を後にしたいものだけど、最近の情勢だと、もう、今後謝恩会が復活することはなさそうだな。 まあ、まだそういう時までは数年ありますから、せいぜい、大学人としての残り少ない人生を楽しむことにしましょうかね。
March 24, 2025
コメント(0)
-

林望先生著『節約を楽しむ』を読む
林望先生が書かれた『節約を楽しむ』という本を読みましたので、心覚えをつけておきましょう。 林先生の大ファンの私は、先生の本なら大抵読んでしまうのですが、この本は林先生のライフスタイルというか、生活哲学の本ですな。 要するに何でも自分本位でやるという。だから世間がカード決済だ、スマホ支払いだ、何だかんだと言っている間に、現金支払いを通す。銀行に「NISAが得ですよ」などと言われても、納得できなければ手を出さない。サブスクリプションも手を出さず、必要な時に必要なものを買う、というスタイルを貫く。暗号資産なんてもってのほか。 要するに、便利ですよ、お得ですよという話には乗らない、ということですな。そこは疑ってかかる。だって、それを客に勧める胴元が儲かるからそういうシステムが組まれているのであって、そこに乗っかるなんて愚の骨頂だと。ただし、自分の仕事上、本当に役に立つものであれば、サブスクリプションを受け入れるところもある。そこは是々非々で。 クルマは趣味でよく買うけれど、ローンは組まず現金で買う。なにもローンの金利までディーラーに儲けさせる必要はない。 あと酒の宴席や外食も、お金ばかりかかって健康に悪い。自分で食べるものは自分で作るにしくはない。スポーツクラブなどにお金を出して通わなくても、街中を歩けばそれで充分。夏場なら、ショッピングモールの各階をぐるり一周するだけで、涼しくウォーキングできる。 年金は60歳で受給し始めるのが良し。当分はそれには手をつけず、80歳くらいまで貯めてから使い始めればいい。 とにかく、うまい話には乗らず、必要なものだけを買い、それも十分検討して、これと思うものだけを選んで、要らないものには金を出さないということを楽しんでいれば、身の丈なりの楽しい生活ができるものだよと。まあ、この本はそんなリンボウ流のライフスタイルの提案がなされております。 ま、いいですよね、ライフスタイルに哲学があるのは。それに私のライフスタイルとはところどころ違うところもあるけれど、7割がた一緒っていう感じ。納得できます。 そんなリンボウ先生のライフスタイルですが、時々、面白いことが書いてある。 たとえば「宝くじを買う」とかね。私はリンボウ先生は合理的な人だから、確率論からして絶対に買い手が損をする宝くじなんか絶対買わないだろうと思っていましたけど、サマージャンボや年末ジャンボなど、主要な宝くじは全部買っているとのこと。先生でも一片の射幸心があるんだ! 面白い。 あと、洋服などをしまむらでお買い求め、という話も意外でした。先生によれば、ユニクロよりしまむらが面白いと。というのは、しまむらは色々なメーカーの服をロットで買って、それを売りつくしたらまた別なメーカーから仕入れるから。だから、行く度に前とは違う面白い洋服を売っていたりするんですって。それを聞いて、私も今度、しまむらに行ってみる気になりました。 あと、先生が長年愛用しているヘアクリームが、「ブリル」という、イギリスで最も有名かつ一番安いヘアクリームだというのも面白かった。日本のアマゾンで買うと結構高いけど、イギリスのアマゾンを通じて買うと、今でも2000円くらいで買えるとのこと。ふうむ。今度見てみよう。 とまあ、色々な意味で面白く読めるエッセイでした。教授のおすすめ!です。これこれ! ↓節約を楽しむ あえて今、現金主義の理由 (朝日新書985) [ 林望 ]
March 23, 2025
コメント(0)
-
書評紙対決『図書新聞』vs『週刊読書人』
現在、日本には『図書新聞』と『週刊読書人』という二つの書評紙がありまして。で、業界の噂によると、『図書新聞』の方が経営がやばいらしい。 とまあ、そんなこともあって、他の用事で大学図書館に寄った際、新聞コーナーに置いてあるこの2紙をチラ読みしてきたわけ。 そしたら、分かったことが一つ。 『図書新聞』の方が圧倒的につまらん。 二つ比べて、分かりました。こっちの方が経営やばいのも。だって、紙面が面白くないんだもん。 『週刊読書人』の方は、色々と企画がある。時の人のインタビューあり、本好き大学生が作った記事あり、著名文人の対談あり、という具合。また書評対象となる本も、『読書人』の方が素人目にも面白そう。 これに対して『図書新聞』は、企画がないのよ。あるのは書評記事だけ。しかも、つまらなそうな専門書の書評ばっかなんだ! でまた紙面の割り振りも工夫なし。昔の日本の家の「田の字型」の部屋割りみたい。ふすま取り払ったらドーンと大きな正方形の間になる、みたいな。 これじゃ、経営やばいのも無理ないわ。 でも、わし、そういうの、わかんないんだよね。ライバル紙があるなら、普通、参考にするでしょ。あっちと比べて我が方は面白くない、だったら、面白くしなきゃって思わないのかな? 宅配ピザもそう。ピザハットとかドミノピザの経営者って、ピザーラのピザ、食わないのかな? 食えば、「あ、こっちの方が旨い。うちのピザより断然旨い」って思うだろうに。思ったら、改善すればいいだけの話で。 日産も、そうだよね。日産の人たちって、なんでトヨタは売れるんだろう、なんでマツダのクルマはカッコいいんだろう、なんでスズキはインドであんなに売れるんだろう、って考えないのかな。 結局、つぶれる会社は、つぶれるようなことをしているんだよね。つぶれるようなことをするから、つぶれる。これ、自己啓発思想なんだけどね。すべて自己責任という。 ま、とにかく、この調子なら『図書新聞』はさほど遠くない将来に「おさらばえ」でしょう。せめてその前に一回くらい、私の本を書評してもらいたかったですけどね。
March 22, 2025
コメント(0)
-

『無敵のレポート・論文術』売れてます!!
今日は拙著の発売日! 全国の書店での販売が開始されました~!これこれ! ↓ゼロから始める 無敵のレポート・論文術 (講談社現代新書) [ 尾崎 俊介 ] まだ書店には市場調査に行っておりませんが、先ほどアマゾンを見たら、「売れ筋ランキング」でいきなりの407位! 結構、売れております。これね、3桁台に乗せるのって、結構大変なのよ。講談社新書に限って言えば、13位だからね。 自分の本が出る時は、いつも「売れてくれ~!」って思いますけど、今度は願いが実現するかもね。 しかし、本が売れるのって、よく分からないな。 いい本が売れるかというと、そんなことないもんね。その反面、こんなつまらない本が、なんて思う本が、やたらに売れることも多いし。 答えは、やっぱり「時流に乗る」ってことなんだよなあ・・・。 タイトルも重要だよね。最初に「○○は○○が9割」とつけたヤツ、最初に「○○の力」とつけたヤツ、最初に「シン○○」とつけたヤツ、最初に「○○の壁」とつけたヤツ、そういうのが勝つ。 でも、どういうタイトルにしたら、時流に乗れるのかというと、わかんないもんね。 難しいよ、ヒットを出すというのは。本に限らないけれども。 まあ、それでも、とにかく、いい本をコツコツ出し続けるってことが、大切なんだよなあ。 がんばりますわ。
March 21, 2025
コメント(2)
-
大手新聞社より原稿依頼キタ―――!
某大手新聞社から、原稿依頼が来ました~! こういうサプライズは大歓迎よ。今日は早速、依頼原稿の作成に取り組み、ちゃっちゃと書き上げちゃった。 最近、原稿書きの独自システムが完成してきて、すごく筆が早くなりまして。頼まれた、そのメールに返信するくらいの勢いで依頼原稿を送るというね。 現在、『Voice』という紙媒体に私が書いた文章が掲載されていますが、ネット上でも『プレジデント・オンライン』が拙文を公開中。さらに明後日には、『東洋経済オンライン』にも拙文が掲載予定。 そして明日はいよいよ『ゼロから始める 無敵のレポート・論文術』が全国発売開始! 現在、講談社の『現代ビジネス』オンラインに、この本の宣伝がガンガン出ていますからね。 田舎の大学のしがない教授にしては、結構頑張っていると思わない? でもこれ、全部、運よ。運。 今年の正月、神社にお参りに行く途中、空に昇り龍と鳳凰を見たの。そのおかげ。神社にお参りするのって、効果覿面だからね! 皆さんもお参りに行った方がいいよ、神社。 ということで、今年はこれからもガンガン行きます。次の本の執筆も、大分調子が上がって来たしね!
March 20, 2025
コメント(0)
-
恒例・古紙メモ帳づくり
今日は勤務先大学で入試関連の会議があったもので、春休み中ですが、出勤してきました。 で、会議自体はあっという間に終わる類のものだったのですが、せっかく出勤したのだから、新学期の授業で使う教材を作ったり、研究室の片付けでもしようかなと。 そんな中、毎年この時期に必ず行う恒例行事もやってしまいました。それは何かと申しますと、「古紙メモ帳づくり」。 教員なんかしていると、学生に配布する紙ものが沢山あるのですが、そういうのが毎回、数枚ほど余る時がある。 一回の授業で数枚だとしても、これが全授業1年分となると、結構な量になるわけですよ。それを捨ててしまうのはあまりにももったいない。だって、表には何らかの印刷がしてあるとしても、裏はまっさらなんだもん。 ということで、私はこういう余った紙を一年間ずっと溜めておいて、春休み中のこの時期に、その紙を使ってメモ帳を作ることにしているんです。 まずA4の紙を半分に切りまして、それを100枚くらいの束にする。で、束になった紙の木口一か所に、木工用ボンドを塗るの。それでボンドが乾くと、アーラ不思議、A6判のメモ帳の出来上がりという次第。 で、今日、作ってみたら、そんなメモ帳が6冊ほどできました。これ、大学と自宅と両方で使うのだけど、これだけあると大体1年間は持つのよ。来年の3月まで、これでバッチリ。 ということで、今日はゆったりとした暇な時間に、研究室でこそこそとメモ帳づくりに励みながら、1年も終わったなあという感慨にふけっていたワタクシなのでした。今日も、いい日だ!
March 19, 2025
コメント(0)
-

理想のシャンプーを求めて
私は何事につけても一途な方で、浮気ということはしない。 ・・・んですが、シャンプーだけは別。いいなと思って買っても、使い切る頃には飽きちゃって、また別なメーカーの別のシャンプーを試したくなるわけ。 まあ、それにはれっきとした理由もあって、あまり長い間、同じシャンプーを使っていると、なんだか頭が痒くなってくるのよ。そういうことって、ありません? っつーことで、私の理想のシャンプーを求める旅というのは、多分、永久に終わらない。 ・・・んですが、今回買ったシャンプーは、結構、理想に近いのよ~。 それは「Nileスカルプシャンプー」というのですけどね。これこれ! ↓NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン(ラフランスの香り) まずね、泡立ちがいい。 私は、泡が細かく重く濃密になるのが好きなんですが、これはまさにそう。 それから泡切れがいいところもいい。 そしてほどよくしつこくないラフランスの香りもとってもグッド。 そして何よりも、翌日、つややかに、まとまりがいい。 ということで、結構理想に近いこのシャンプー、まだ使い始めたばかりなので、先のことは分かりませんが、今のところ大満足しております。 一方、壊れたオーディオの代替案は、なかなか苦戦しております。 もう、昔はあった、手ごろな価格で価格以上の音を出してくれるオーディオ・メーカーが全部なくなっちゃって、しょぼいことになっているのよ。残っているのは、ハイエンドなヤツばっか。数十万円から百万越えとか。 結局、若い人がオーディオに興味を持たなくなったということなんでしょうなあ・・・。スマホでアップル・ミュージックか何かをストリーミングで、しかもイヤホンで聴くというスタイルが定着し、コンポでCDを聴くなんてことはなくなったんでしょう。 もう、こうなったら、ハードオフとかに行って、そこそこのモノを買うしかないのかなあ。 どうすべきか、シャンプーで頭洗って考えますわ。
March 18, 2025
コメント(0)
-
オーディオ・コンポが壊れた
自宅で聞いているオーディオ・コンポが壊れちゃった。 DENON 製のミニコンポで、結構、愛用していたのだけど、CDを認識しなくなってしまった。 で、今日、近くの家電量販店に修理に持って行ったのですが、店員さん、一目見て「ああ、古いので、もう部品がないですね」ですって。 ん? 古い? いやいや、そんな前のものではないですよ。 で、調べたら、2005年製だった。 2005年? 20年前じゃん! そんなはずはないと思って、後で自分でも調べたところ、さすがに2005年ではなかったけど、2007年の7月に買ったものだと判明。2007年というと、18年前か・・・。 いやはや、光陰矢のごとし。これを買った時、嬉しかった気持ちを今も易々と思い出せるので、せいぜい10年くらい前のことかと思っていたんだけれど、そんなに前だったとは。 まあ、買って18年使ったなら、そりゃ、壊れますわなあ。 でもスピーカーはまだ使えそうなので、CDプレーヤーの本体だけ買うか。 とはいえ、もう、手ごろな価格帯のプレーヤーを作っている会社って、あまりないよね? オンキョーもつぶれてしまったし。パイオニアもないのか? ケンウッドも昔ほどの勢いはないし。 なんか、ワタクシの世代のものがどんどん壊れ、つぶれていくようで、何となく悲しいね。
March 17, 2025
コメント(0)
-
次の本の執筆
まもなく、今度の金曜日に新著の全国発売がありますが、これはもう、私からすれば過去の話。今は次の新著の原稿執筆に励んでおります。 でね、今度の本ですが、実は1月くらいから書き始めていたのよ。金曜日に出る本の校正作業が終わった段階で、すぐに取組み始めましたのでね。 だけど、どういうわけか筆が乗らないというか。今一つ、調子が上がらなくて、珍しくしばらく放置してしまっていたわけ。もちろん、その間に色々やるべきことがありましたら、仕方がなかったというところもあったのですが。 でもね、なんか、一昨日あたりから潮目が変わったの。一旦潮目が変わって調子が出ると、私は割と原稿は早い方で、一昨日昨日の二日間で一章分の原稿を仕上げることができちゃった。で、今日もその次の章を書き始めたのだけど、引き続き調子はいい。どんどん書ける。 で、本当は今日はもう一つ、別な原稿に手を入れようかと思っていたんだけど、急遽、その予定を取りやめて、今書いている方の原稿に集中することに。だって、一旦乗り始めた筆の勢いを止めたくないんだもん。 ところで、何で潮目が変わったのか。 実はね、ちょっとあることをしたのよ。 何をしたかって? 聞きたい? 教えなーい。(めんどくさ!) ウソウソ。教えてあげましょう。 あのね、万年筆を使ったのよ。 私はもうずっと原稿はワープロで書いておりますが、アイディアを出す時はペンを使って紙に手書きで書き出すこともある。 だけど、その習慣も最近はやらず、アイディアの段階からワープロを使うようになっていたわけ。 でも、筆が停滞したことを機に、ちょっと気分を変え、紙に手書きでアイディアを書き出してみた。それも、今回はボールペンではなく、万年筆で。 そうしたら、何だか知らないけど、わーっと書くことが思いついて、止まっていた原稿が一気に進んだと、そういう次第。 で、思うんだけど、手と脳って、つながっているんじゃね? だから脳がつまったら、手を動かしてみる。そうすると、つまりが取れて、スムーズにアイディアが流れるようになるのではないかと。 筆を変えると、止まっていた原稿が進むようになるって、北方謙三先生も言っていたけど、あれは本当ですな。 というわけで、現在、執筆絶好調の私。しばらくはこのまま、突っ走ってみますわ。
March 16, 2025
コメント(0)
-
ミートソースを作る
何となく思い立って、今日の夕食は、私が用意することにしました。まあ、一日過ぎてしまいましたが、ホワイトデー的な意味も込めまして。 今日私が作ったのはスパゲティ・ミートソース。 まずナスを二本、輪切りにし、フライパンでオリーブオイルで焼きます。輪切りナスの両面に軽く焦げ目がついたら取り出しておく。 次にセロリを一本、玉ねぎを半分、ニンニク一片を粗みじんにしたものをフライパンで軽く飴色になるまで炒め、取り出しておく。 次に合い挽き肉を200グラム、フライパンで焼きます。コツは、最初からほぐさず、ある程度ハンバーグのように塊で両面に焼き色が付くまで焼いてから、荒くほぐす感じ。 で、肉が8割方焼けたら、赤ワインをフライパンに回し入れ、鍋肌の焦げを溶かし込む。そしてアルコールが飛んだら、先に炒めておいたナスとみじん切り軍団を鍋に戻し、さらにトマトの水煮缶を一缶まるごと投入。必要に応じて水も少々入れ、そこにコンソメを1個、それに塩やらスパイスやらを投入。 で、後は10分くらい煮た後、ケチャップを少々、ウスターソースを少々ぶち込み、塩加減を見ながらさらに5分くらい煮れば出来上がり。後はゆでたパスタにこのミートソースをかけ、乾燥オレガノ少々と黒コショウをガリガリと挽き、粉チーズをたっぷりかけて完成。 今日はこれに家内が作ったグリーンサラダと、用意しておいたロゼ・ワインをいただきました。基本、一品料理ながら、雰囲気はなかなか豪勢でしたよ。 ま、料理ってのは、たまにやるといい気晴らしになります。今日はずっと本の原稿を書いていたのですが、いい気分転換になりました。
March 15, 2025
コメント(0)
-

新著の見本が出た~!
一週間後の3月21日に全国の書店で発売が開始される拙著の見本が自宅に届きました~! いやはや、自分の書いた本がこうして活字になり、本となって手元に届くというのは、何度体験しても嬉しいものですなあ。今日はお祝いじゃ!これこれ ↓ゼロから始める 無敵のレポート・論文術 (講談社現代新書) [ 尾崎 俊介 ] 今度の本は、自己啓発関連の研究書ではなく、主として大学生に向けたレポート・論文の書き方指南の本。 この種の本というのは、結構沢山あって、同じ講談社新書にも何種類もある。ライバルも多いわけ。 もちろん、そういう類書は全部取り寄せて研究しましたけど、読んで面白いもんじゃないんだよね。だって、書き方の本だから、基本、マニュアルみたいなものでしょ。マニュアル読んで面白いとは思わないじゃないですか。 でも、私の本は読んで面白いからね。 なぜ面白いかというと、学部学生が書いた文科系論文の実例が沢山掲げられているから。その実例が面白いのよ。アメリカ文化を研究するってこんなに面白いことなんだ、ということがよく分かるようになっている。 やっぱり、「面白い」というのが重要よ。面白くないこと、やりたくないじゃん? この本は、論文の書き方指南ではあるんだけど、指南よりも何よりも、まず「研究するって、面白い」ということを前面に出しているところが新しいのではないかと。 っつーことで、類書のベストセラーも多いけど、その中でこの本も健闘してくれるのではないかしら。 「論文の書き方」系の本のいいところは、ロングセラーになりやすいこと。だって、毎年、卒論をかかなければならない大学4年生というのは一定数生まれるわけだから。そういう連中が、切羽詰まって、指南本を買うとなれば、その分、毎年新需要が生まれるわけで。 この本も長く長く、売れてもらいたいものでございます。いや、是非売れてもらいたい。売れてもらわないと困る! 定年後の資金源なんだから! とりあえず、一週間後、3月21日の全国発売開始と、新学期需要に期待することといたしましょうかね。
March 14, 2025
コメント(0)
-
教授会をすっぽかしかける
昨日、後期入試も終わって、お疲れ様の飲み会も終わって、さすがに疲れたのか、今日、起きたのはお昼近くっていうね。 で、その辺にあるもの食って、ポケ~っとして、何の気なしに手帳見たら、「13日、教授会」って書いてあった。 ふーん、教授会か。今日は教授会・・・。 え゛ーーーーーー! 今日は教授会?! ウソ―――!! 5分で着替えて家を出た。自宅から大学まで小一時間。気づいたのが教授会の30分前。遵法精神の範囲内で愛車を飛ばして会議室に着いた時、10分遅刻。 はい、ギリギリセーフ! (セーフじゃねえよ! 遅刻だよ!) ちなみに、今日は年度内最後の教授会だったので、教授会終了後、今年度で退職される先生方の紹介イベントがありまして、そちらの方にも無事、参加することができました。これ、参加しなかったら、長年の同僚に対して失礼だもんね! ということで、今日はビックリしましたけれども、とりあえずさほどの被害がなく、良かったわ~。 これからは、毎日、手帳をよく確認しよう! (新入社員か!)
March 13, 2025
コメント(0)
-
イギリス人とドイツ人の名前感覚
今日は、国立大学後期入試が終わったということで、夕方から大学の同僚10人と、打ち上げの飲み会をやってきました~。 で、席順の関係で、たまたま私はドイツ人の同僚とイギリス人の元同僚と向かいの席に座ったため、彼らと話をすることが多かったのですが、そこで一つ、ちょっと驚く話を耳にしまして。 私は、彼らとは非常に親しいので、学内では互いに苗字で「○○先生」と呼び合っているのですが、たとえばメールでやりとりする時などには、苗字ではなくファースト・ネームを記すことにしているんです。まあ、それが洋風の風習だと信じつつ。 そしたら、違うんだって! 親しいからといってファースト・ネームで呼び合うのはアメリカ人。ドイツとかイギリスでは、学生時代の友達同士でも、苗字の方で呼び合うのがむしろ普通だと。 え¨ーーー! そうなの? では、私は彼らに対し、勝手にアメリカ流のやり方を押し通していたってわけ? で、ふと思ったのだけど、たしかに『シャーロック・ホームズ』とかで、ホームズとワトソンは、それぞれ「ホームズ」「ワトソン」と呼び合っていたわ。ワトソン先生がホームズに対し、「シャーロック」とは呼ばないですわなあ。 今頃そんなことに気づくようでは遅いですが、今更ながらちょっと面白い発見だったのでした。いくらアメリカ文学者だからといって、アメリカかぶれしてちゃ、いかんですな。
March 12, 2025
コメント(0)
-
スズキ・フロンクスの快進撃(と日産の凋落)
昨秋に買ったスズキ・スイフトの半年点検があったので、スズキのディーラーに行ってきました。 で、点検の間、時間があるので、もしそのディーラーに、スズキの新型車フロンクスが置いてあったらいいな、もしかして、試乗とかできたら楽しいなと、ちょっとだけ期待して行ったわけ。 しかーし! ディーラーには、新型フロンクスの影も形もなかったのでした。展示もしてないし、バックヤードにも一台もない。 で、聞いてみたのよ、フロンクス、ないんですか?と。 すると、ディーラーの方曰く、あまりに売れすぎて、在庫がどこにもないと。 そのディーラーでも、まだ2台くらいしか売っていないそうですが、それも昨年11月の先行予約に運よく当たったお客さんにお渡しできたという話であって、仮に今、実車に試乗することもなく注文をかけたとしても、それを手にできるのは半年先か、1年先かという話になるらしい。 で、それと同じこと・・・いや、もっとすごいことが新型の「ジムニー5ドア」にも当てはまる。ジムニー自体だって入手困難なのに、その5ドア版となったら、もっと入手困難でありましょう。 要するに、魅力あるクルマを世に出したスズキは、クルマが売れすぎて嬉しい悲鳴を上げていると。そういうことですな。 とまあ、そんな話をスズキ・ディーラーで聞いて思うのは、日産のこと。 日産は、スズキの真逆で、売れているクルマが一つもないもんね! かつてトヨタと覇を競った日本を代表するクルマ・メーカーの凋落ぶりたるや・・・。今日、新社長のお披露目会見をやったみたいですけど、その新社長の頭の中も、カルロス・ゴーンと同じく、コストカットしかないみたいだし。コストカットすれば短期的に損切りできるかもしれないけれど、その先、売れるクルマがないのでは未来がない。変なプライド出して、ホンダの子会社になるのを拒否したけど、その決断もどうだったんだか・・・。 じゃあ、なんで日産のクルマは売れないのか? そんなの簡単よ。デザインが悪すぎる。以上。カッコいいクルマが一台もないんだもん、誰も見向きもしなくなるわ。 日産で替えるべきは、社長の首じゃなくて、デザイナーよ。まあ、デザイナーを替えようとしなかったんだから、社長の首も替えた方がいいけれど。 スズキ・フロンクスやスズキ・ジムニーを見れば分かる通り、クルマってのはいいデザインのクルマで、しかも客が納得できる価格のものであれば、売れるのよ。 ま、日産は他人の言うことを聞かないから、こんなこと言ったってどうなるもんでもないけど、スズキ・フロンクスの爆売れぶりを間近で観ちゃったものだから、つい、言いたくなっちゃった次第。妄言、多謝。
March 11, 2025
コメント(0)
-

山口周著『独学の技法』を読む
まず最初に言っておきますが、独学は自己啓発です。当たり前ですが。 っつーことで、そろそろ私も独学について少し予備知識を蓄えておかなくてはと思い、山口周さんが書かれた『独学の技法』という本を読んでみた次第。この本を選んだのは、偶然です。読書猿の『独学大全』があまりにも分厚かったので、怖れをなし、こちらを選んだとか、そんな程度。この本はそんなに分厚くないしね。 で、読んでみて驚いたのですが、この本、すごく説得力があったんです。このコンパクトさにして、独学の何たるかについて、大半のことは分かってしまったというか。 そもそも「なぜ独学が必要なのか」ということに関しても、山口さんは簡にして要を得た説明をしている。 曰く、独学の必要性は4つの観点から明らかであると。すなわち①既存の知の体系はすぐに役立たなくなるから ②ガラケーが iPhone に一掃されたようにイノベーションによって産業はすぐに蒸発しちゃうから ③人生三毛作といわれるほど人の労働期間は長くなるのに、企業の旬はすぐに尽きるから ④二つ以上の領域に通じたクロス・オーバー人材が必要とされる世の中だから。だから独学によって自分のリソースを増やしておくに越したことはないと。 だから世に独学は増えたけれど、残念なことにその大半は読書法指南の本であると。本はこう読め、こういう本を読め、読んだらノートつけろ、いや、ノートは絶対につけるな、等々。だけど、山口さんは、そもそも独学って本を読んで知識を集めることとイコールなのか? と疑問を突き付ける。 むろん、山口さんの独学観はそうじゃない。独学とは、学習のシステムであると。そしてそのシステムは四つのモジュールから成り立っている。すなわち、①戦略 ②インプット ③抽象化・構造化 ④ストック の四つ。 ①の戦略ですが、独学するにしても何を学ぶかを決めなければならない。手当たり次第に勉強しても意味はない。だからどのようテーマについて知的戦闘力をつけるつもりなのか、まずはそこから決めるべしと。それが戦略を決める、ということね。だけど、気をつけなければならないのは、決めるべきはテーマであって、ジャンルではない、ということ。経済について学ぶのだからといって、経済ジャンルの本だけを読んでも意味がない。経済にイノベーションを起こすという「テーマ」のために必要な知識であれば、哲学や音楽の本だって、読むべきなわけですよ。 で、戦略を決めたら、次はインプット。つまり本の読み方ね。本の読み方にも戦略が必要なのであって、短期的に読むべきものもあれば、中・長期的に読むべき本もあるし、娯楽のために読む本があってもいい。ただ、重要なことは古典を中心に読むこと、身の丈に合ったものを選ぶこと、自分にとって心地よい本だけを選んではいけないこと、関連分野を固めて読むこと(メタファー読書、メトニミー読書)、教養をつけるためを目的とした本の読み方をしないことなど。 次は抽象化・構造化。本をただ読んでも、それは知識が増えるだけだし、その知識だって怪しい。というのは、人間はすぐに忘れてしまうから。そうではなくて、本で読んだことを血肉化するためには、読んだ内容を抽象化し、構造化することが重要。要するに、内容の本質を自分の言葉で把握すること。例えばアリ塚のアリの中には3割くらい、遊んでいるヤツがいる、という動物学の本を読んだ際、そこから抽象化して、「平常時の業務量に対して処理能力を最適化してしまうと、環境変化に耐えられなくなるのでは?」というふうに仮説化する。そうすると、アリ塚の現状の知識が、ビジネスにも応用可能な普遍的な定理につながる可能性がでてくる。本の読み方としては、常にこういう抽象化が必要であると。 最後、ストックの仕方だけど、知識はそのストックが多ければ多いほど役に立つわけだけれど、人間の能には処理能力の点で限界がある。だから、記憶に頼ろうとせず、外部化することが重要。その際、たとえば最初に本を読んだ時には、気になる箇所にドンドン、下線を引く。二度目にはその下線を引いた箇所を中心に再読していって、その中でも改めて重要だと思ったものには付箋をつける。三度目に読む時、その付箋のついた箇所を9ヵ所程度に絞ってエバーノートなどに書き抜いておく。こうすると、本当に役に立つエッセンスを抜き出すことができますよと。 とまあ、こんな感じで独学によって活用可能な知識を蓄積していく意義と方法を山口さんは伝授してくれるのですが、本書の最後の方3分の1は、リベラル・アーツの重要性を説く章になっております。 つまりね、ビジネスパーソンがビジネスに必要だからという理由で独学するにしても、その目的のために一番役に立つのは、実は哲学とか美学とか音楽とか文学とか科学とか、とにかく本質的な教養書なんだよと。なぜなら、本物のイノベーションをもたらすものは、専門的知識ではなく、横断的な幅広さを持つ非専門的知識であるから。 で、そのことを力説した後、リベラルアーツ11のジャンルの中から、山口さんがお勧めする良書が紹介されると。 ま、本書の構成はそんな感じ。 実にバランスがいいねえ! そして、各項目ともとても説得力がある。私自身、リベラルアーツ側の人間だけど、じゃあ、私にここまでの説得力をもってこういう本が書けるかといったら、ちょっと無理かも。 いい本ですよ。これ、うちのゼミ生にも読ませようかなあ。若いうちにこういう本を読んでおくのは、とても意義あることではないかしら。 ということで、最初に読んだ独学本、けっこう収穫アリだったのでした。教授のおすすめ!これこれ! ↓知的戦闘力を高める 独学の技法 (日経ビジネス人文庫) [ 山口周 ]
March 10, 2025
コメント(0)
-

常盤新平著『山の上ホテル物語』を読む
常盤新平さんの書かれた『山の上ホテル物語』を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 仕事がらみでこのところずっと暇さえあれば常盤さんの本を読んでいるのですが、さすがに小説・短編には嫌気が差してきたので、ここらあたりでちょっとノンフィクションを読んでみようと、『山の上ホテル物語』を読んでみたと。作家に愛された名門ホテルたる山の上ホテルも、最近、閉館したばかりだし、そういう意味でもちょっと興味があったので。 だけど・・・。 うーん、どうなんだろう。 私としては、『山の上ホテル物語』と題しているのだから、この一風変わったホテルについての、社史的なものなのかと思っていたのよ。 ところがそうではなくて、このホテルを作った吉田俊男についての話でした。まあ、確かにこの吉田俊男という人物、なかなか面白いので、それはそれでいいでしょう。 しかしね、それにしては、書き方がなってない。吉田氏の奥さんである令子さんとか、あるいはこのホテルに勤め、吉田を支えた何人ものキーパーソンたちに一応、取材はしているのだけれど、その取材が断片的というか、散漫なのよ。だから、断片的な思い出の記にしかなってない。 しかも、順不同だし、繰り返しも多い。その話、さっきも聴いた、と思うこともしばしば。それに記述も曖昧で、何を書いているのか、誰が誰に向かって言っているセリフなのかすらわからない箇所も少なくない。 そういうこともあって、吉田俊男が魅力的な男だ、すごい男だ、というのは繰り返し聴かされるのだけど、結局のところ、吉田俊男についてのちょっといい話、ちょっと面白いエピソード集の域を出ない。 たとえば和田芳恵の『筑摩書房の三十年』は、もっとちゃんとした社史になっているし、あるいはマガジンハウスの社史である『二人で一人の物語』は、創業者と一緒にこの出版社を作って来た人物による濃厚な創業者伝になっていたけど、『山の上ホテル物語』は、社史にもなってないし、人物伝としても中途半端。 まあ、数人に適当に取材して、大した資料もないまま、大雑把な印象記を書いたと。所詮、その程度のものであって、読む価値なしとは言わないけれど、それほどためになる本ではありません。 そもそも、常盤さんにこういう本を書いてくれと頼んだこと自体が失敗だよね。社史が書けるようなタイプの書き手じゃないんだもん。だから、失敗の責任を常盤さんに帰するのは、ちょっと酷かも。 というわけで、小説に飽きてこれを読んじゃったけど、口直しには、なりませんでしたね。これこれ! ↓山の上ホテル物語 (白水Uブックス) [ 常盤新平 ]
March 9, 2025
コメント(0)
-

古本カフェ倶楽部活動
毎年この時期、ということはつまり春休みの一日、古本とカフェを愛好する同志を募って古本巡りをし、カフェで一服して解散というイベントをやっております。で、今年はその会合が今日だったと。 一昨年は藤が丘の「千代の介書店」、昨年は刈谷の「あじさい堂書店」に行きましたが、今年は鶴舞にある「大学堂書店」と「山星書店」に行きました。参加者は私を含めて3人。 で、今日のワタクシの収穫はと言いますと、林望先生の『書誌学の回廊』、これは私がリンボウ先生の本を全部集めることにしているので、その一環。それから河合栄治郎の『学生の与ふ』、これは仕事関連。あと芥川比呂志の『決められた以外のせりふ』、これは220円の美本で、お父さんの芥川龍之介のことや、当時の演劇人のことが色々書いてあったから。まあまあの収穫と言えるのではないでしょうか。【中古】 書誌学の回廊/林望(著者)【中古】 学生に与う 改訂版 / 河合 榮治郎 / 社会思想社 [文庫]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】 【中古】決められた以外のせりふ 新潮社 芥川比呂志 参加者もそれぞれ、何かしら買っておりました。 で、その後、近くの「喫茶クロカワ」でまったりコーヒーなど。 で、同僚同士の会話を楽しんでいたのですが、一つ面白かった…というか、ぞっとした話を一つ。 年下同僚のF先生が最近くらった経験だそうですが、授業中に『ラブアクチュアリー』という映画を学生に見せたというのですな。英語の授業で、この映画を使ったテキストを使っていたので、当然、その映画を見せたわけですよ。 そうしたら、映画の中で、恋人同士の性的な場面があったと。まあ、恋愛映画ですから、そういう場面があるのも当然でしょう。 で、そうしたら、学生から大学にクレームが出たと。で、F先生は理事だかに呼び出しをくらって、説明を求められたんですと。もちろんF先生は怒り狂って、ふざけんなと。そんなかまととぶってたら大学の授業なんて成立しねーよと。で、理事の方もそれは分かっているのだけれども、学生からクレームが出た以上、対処せざるを得なかったらしいんですな。 最終的に、善後策として、そういうシーンが出る時にはその前で映画を止めて、「これから人によっては不愉快なシーンが出ますので、見たくない人は見ないでください」的なアナウンスをすることになったと。 はあ~。そういう時代になったのか・・・。大丈夫か、この国・・・? ま、同僚同士、こういう情報交換して、不平をかこつというのも、古本カフェ倶楽部の一つの役目ですからね。 ということで、今日は古本ハンティングを楽しみ、今の日本の大学の状況も改めて確認できたりして、有意義な一日となったのでした、とさ。今日も、いい日だ!
March 8, 2025
コメント(0)
-
藤田嗣治展で藤田の何たるかを知る
今日は先輩同僚で「アニキ」ことK教授と春のドライブツアーに行って参りました。 まず我々が向かったのは、「鈴鹿の森庭園」。ここは枝垂れ梅がわんさと植わっている梅見の名所。 ・・・なんですが、今年は開花が遅く、まだ1分咲きというところ。ちょっと早かった。まあ、K先生と私の都合のつく日が今日だけだったので、仕方ないですね。でも1分咲きでも梅の香はもう漂っておりましたので、一足早く春の気配だけは感じてきました。 で、その次に我等が向かったのは、アクアイグニス。温泉施設と一流シェフのレストランが並ぶお湯と食のテーマパーク。ここでお昼を食べることにして、結局「賛否両論」で名高い笠原将弘さんの「笠庵」というお店で海鮮丼をいただきました。 そしたら、これが実に美味しかったの。さすが笠原さん。ここは来た甲斐がありました。 で、美味しい海鮮丼に舌鼓を打った後、すぐ近くにある「パラミタ・ミュージアム」へ。 今、パラミタ・ミュージアムでは藤田嗣治の展覧会をやっていたのですが、これがね、実に実に素晴らしかった。これこれ! ↓藤田嗣治展 実は、私は藤田の絵って、これまであまり高く評価してなかったのよ。それに、あのエクセントリックな藤田の外貌もあまり好みではないし。 だけど、今回のパラミタの藤田嗣治展を見て、完全に藤田への評価を変えました。あれはやっぱり、天才だわ。 展示されている絵の質・量ともすばらしい。こんなにすごい人だったんだ、ということに初めて気づきました。この展覧会は見て良かった。先日見た、愛知県美のパウル・クレー展のレベルの低さとは大違い。しかも、入館料1000円だからね。こんなに安くていいの? ちなみに、今、パラミタでは藤田嗣治展の他にHaru Guoさんの「Beyond time and space」という小展示もしているんだけど、ファッション画を描かれるHaruさんの可愛い「Fujiko」の絵にも癒されました。そこにいらしたHaruさんと一緒に写真も撮ってもらっちゃった!これこれ! ↓Haru Guo さんの Beyong time and space 展 そして、最後、パラミタ・ミュージアムからほど近い「cafe snug」というカフェでおいしいキャロット・ケーキとコーヒーをいただいて、今日のドライブ終了! 最初の枝垂れ梅が1分咲きだったのはちょっと残念だったけど、お昼ごはんも美味しくいただいたし、パラミタ・ミュージアムでの藤田嗣治展を堪能できたし、カフェも美味しかったし、今日はなかなか充実のドライブだったのでした。
March 7, 2025
コメント(0)
-

映画『花束みたいな恋をした』を観た
アマプラで『花束みたいな恋をした』を観ました。 もちろん、仕事がらみよ。レジ―さんが『ファスト教養』という本の中でこの映画に触れ、自己啓発本が悪役に使われていることを指摘していたので、どんなもんかなと。 で、どうなのかっていうことですけど、うーん、まあ、確かに主人公の若い男性・麦は、学生時代/フリーター時代のイラストレーターの夢を捨て、社会人となってブラック企業みたいなところで悪い意味でブラックに染まり、読むものといえば自己啓発本、やることといったらパズドラだけの企業ゾンビみたいになって、ヒロインの絹とすれ違っていくのだけど、まあ、こうなったのは麦の器ってことじゃないの? この映画だけ見て、自己啓発本の悪弊というところまでは読み取れなかったかな。 でも、とにかく映画制作者の観点として、麦が自己啓発本を手にとるというシーンを入れたということは、もちろん意図的なものであって、世間的に自己啓発本なんて企業ゾンビが読む本だと思われていることは確実ですな。 でもさ、世の中には『多動力』みたいな本もあれば、『DIE WITH ZERO』のような本もあるわけであって、自己啓発本でもそっちを読んでいたら、ワクワクしないことに人生の時間を費やすことも間違いだし、金を稼ぐために人生の愉しみを台無しにしていることも間違いだと分かったはず。麦が読んでいた『人生の勝算』が悪かったんじゃないの? 自己啓発本だろうと他のどんなジャンルの本だろうと、読む本は選ばなきゃ。『教授が解説 自己啓発の必読ランキング60』なんていう本も、どうやら売っているらしいし・・・。大学教授が解説 自己啓発の必読ランキング60 自己啓発書を思想として読む [ 尾崎 俊介 ] っつーことで、まあ、お勉強として観ちゃったけど、そうじゃなきゃ、私が観るタイプの映画ではなかったかな。いや、でも、菅田ファン、有村ファンにはたまらん映画だとは思います。最後の方の、二人が別れ話をするシーンは良かったよ~、などと言ってみたりして。これこれ! ↓花束みたいな恋をした [ 菅田将暉 ]
March 6, 2025
コメント(0)
-

話題の『DIE WITH ZERO』を読む
話題の自己啓発本、ビル・パーキンスの『DIE WITH ZERO』を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 この本はですね、簡単に言えば、死ぬ時に資産全部空にして死のう、ということを提案する本ですね。 人は何のために生きるか、それは人生を後悔しないように、いい思い出をいっぱい作るために生きているわけですよ。で、いい思い出をいっぱい作るためには、お金がいる。だから、人は仕事をして、お金を貯める。 ところが、人は放っておくと、お金を貯めるというのがクセになってしまって、肝心の、思い出をいっぱい作って人生を堪能することを後回しにしがちだと。 で、結局、多額のお金を残したまま、死んでしまう。そのお金を使えば、人生を楽しめたはずなのに、お金を貯めるのに一生懸命なまま、そのお金を使わずに死んでしまう。 これ、人生の無駄です。本来なら、そのお金を貯める時間を使って、人生を楽しむべきだったのに! その無駄に気づくことが大事。そしてそれに気づいたら、今後は計画的に「貯金ゼロで死ぬ」ことを実践すればいい。 大体、歳を取ると、体力は衰え、健康も下り坂となり、やれることはどんどん少なくなっていく。つまりほとんどお金がかからない状態になってしまうわけね。そんな晩年のために多額のお金を残しておいても意味ない。 それに、無計画に財産を残し、それを自分が80歳過ぎて死んだ時に子どもに分けたとしても、子どもだってもう60代で、それなりにお金を持っていて、親から多額の遺産をもらわなくてもいい年代になっている。 子供へ財産を残すことを考えるのだったら、子どもがそれを一番必要とする若い時代に生前贈与としてあげてしまい、残った自分のためのお金も、60代くらいからどんどん使って減らしていき、最後、貯金ゼロで死ぬ。この理想に向かって計画を立て、賢くお金を使う。これが、人生を豊かにするお金の使い方だと。 まあ、この本が述べていることは、そういうことです。 まったく、健全な考え方だよね! 素晴らしい! 結構、目ウロコだったわ。この本がベストセラーになるの、わかる~。 もう、還暦を越えた私としては、この本を読むのが遅すぎたきらいすらある。でも、今からでも遅くない。自分はともかく、家内が死ぬ時に我が家の貯金がゼロになるように、これから考えて生きよう、と思いましたわ。 その手始めとして、とりあえず、スポーツカー、買うわ。だって、70代とかになったら、スポーツカー運転するの大変じゃん。今なら、まだできるもんね。今買わないで、お金貯めてどうする。60代でスポーツカー乗り回して、家内といっぱいドライブして、楽しかった~って思って死ぬ方が、スポーツカーの値段分の財産を余計に残すよりいいもんね。 世の中には、「死」をテーマにした自己啓発本って色々あるけれど、この本もある意味、「死をめぐる自己啓発本」と言っていいのではないだろうか。死ぬための準備をどうするか、っていう話だからね。 そういう本として、抜群の切れ味の本でした。教授、絶賛。これこれ! ↓DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール [ ビル・パーキンス ] ちなみに、これはビル・パーキンスのはじめての本らしいですが、彼はビジネスマンであって、ライターではない。だから、この本のアイディアは彼のものだけど、実際に書いているのはプロのライターらしい。ライター雇って、調査員雇って、スタッフ固めて、みんなで書く。それで、文学エージェントに頼んで出版社に売り込むと。まったく、アメリカらしいやり方だねえ。 昨日のホリエモンの『多動力』も同じようなもんだけど、段々、「本を書く」ということが、一人の人間の所業ではなくなってくるのかもね。
March 5, 2025
コメント(0)
-

堀江貴文著『多動力』を読む
ホリエモンのベストセラー『多動力』を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 この本、ホリエモンが書いたとはいえ、インタビュー形式で語ったものを編集者が適当に編集したのだと思います。いわゆる「聞き書き」ですな。ホリエモンの著作のほとんどがこれで、本人としてはそれすら面倒臭いらしく、もう、彼がメルマガとかに書いたものやインタビューなどで話したことを出版社の方で適当に切り貼りして本にしてくれれば結構と考えているらしい。 テキトー過ぎる? でも、まさにこういうホリエモンの執筆姿勢こそが、この本のキモみたいなところがあるんですな。 ホリエモンがこの本で言っていることは、とにかく人生の時間は限られているのだから、自分のやりたいこと、しかも自分でなければできないことだけを選んで注力しろ、ということに尽きます。 だから、本を書くにしても、まえがきからあとがきまで全部自分で書き、校正から何から全部自分でやるなんて、ナンセンスだと。 自分の思想、自分の言いたいことは、あちこちで書いたり話したりしている。それは自分でやりたいことだし、自分しかできないことだから自分でやる。でも、それをまとめたり、原稿にしたり、校正したりするのは、編集者とか校正担当など、他人ができるわけですよ。だったら、それは他人に任せればいい。そんなことまで全部自分でやっていたら、自分の時間がどんどん削られてしまって、それは無駄だから。 これをホリエモンは「原液」に譬えるわけ。自分はカルピスの原液みたいな「アイディアの原液」を作っているのだから、あとはそちらで適当に薄めたりして、飲めるもの(読めるもの)にしてくれと。 なるほど。もっともなことでございます。 その他、仕事でもなんでも、自分が本当にそれをやりたいか、それをやっていてワクワクするか、それを基準にしてやる、やらないを決めればいい。ワクワクがなくなったら、そんなもの、人生の無駄だから放り出してしまえばいいと。 日本の場合、なんでも「道」にしちゃって、一つのことを延々やり続けることを美徳と考える向きがあるけれども、今、ネットの時代だから、30年かけて培ったコツとかですら、ネットに上がっていると。だったら、それを見ればいいだけのこと。見ればすぐわかることを、30年かけて修行する意味なんてないと。 あと、「何かを始めるには、十分な準備が必要だ」と考える人が日本人には多いけど、準備なんかどうでもよくて、見切り発車ですぐ取り掛かって、やっているうちに準備すればいいと。とにかく、始めることが重要だと。 キャリア形成でも、5年くらい一つのことに注力すればプロになれる。だったら、5年一つのことをやったらそこで区切りをつけ、次の5年は全く別なことをする。それでさらに次の5年に別なことをやったら、3つの肩書ができる。この「3つの肩書」こそ、何にも代えがたい強みなのであって、そこから先は他に代えがたい人材として活躍できる。とにかく、業種の壁を全部ぶち壊し、水平移動しながら、自分のやりたいことだけを全部やれと。 もちろん、ただ単に移動することが重要なのではなく、自分の興味あることにはとことん嵌ることが重要。とことんやることで、「教養」が身につく。で、その後、飽きたら次へ行く。次のところでは自分の知らないことだらけだろうけど、今はネットの時代だから、恥ずかしがらずに、知らないことはネットで調べるなり、人に聞くなりして、どんどん「知識」をためていけばいい。そうやって、「教養」と「知識」を加速度的に蓄積していけば、最強の人間になれるはず。 時間が重要だから、自分の時間を奪う人やモノは徹底排除すべし。例えば今時電話をかけて来るヤツとかは完全に無視しろと。会議中だって、自分に関係ない時にはスマホで別なことをやっていても全然OK。食事だって、冷凍食品や外食だけで十分。その分、やりたいことをやって成果を挙げればいいだけ。 ・・・とまあ、この本に書いてあることは、大体、そういう趣旨のこと。 いやあ、すがすがしいほどの割り切りだねえ。そして、実際にここに書いてあることをホリエモンはそのまま自分でも実行し、現在進行中で人生を満喫しているわけだから、大したもの。実績ある人が書く自己啓発本としては王道中の王道ですな。 しかも、実際に読むと参考になる。読めば、読者の側のマインドセットが変わってくる。私も「修行マインド」の持ち主だし、何かをやるとなったら十分な下準備をしてしないと不安になる方なので、「そんなことやってるからダメなんだよ」とホリエモンに言われたような気がします。その結果、ちょっと考え方が変わりました。 それに、「ワクワクすることだけやれ、それ以外のことをやるには、人生は短すぎる」という彼の信念は、まったく正しいと思う。その点から言っても、この本、いい本ですよ。教授のおすすめ!と言っておきましょう。これこれ! ↓多動力 (幻冬舎文庫) [ 堀江貴文 ]
March 4, 2025
コメント(0)
-
次著の方針転換
新著のPRイベントで、来月、とある YouTube 番組に出演するのですが、それはビジネス系雑誌関連のイベントなので、当然、ビジネスマンに興味のありそうな自己啓発本って、たとえばどんなものがありますか? 的な質問を受けると思うんですよね。 で、そういう風に聞かれた時に、どう答えよう? などと頭の中でシミュレーションしていたのですが、そのうちに考えがあらぬ方向に漂い始め・・・ 今、自分的に、どういうのがビジネスマン向けの自己啓発本か、という話題には興味ないなと。 だって、こういう名著がありますよ、と言ったところで、所詮、それは自己啓発本だから、総じていえば、アンチから馬鹿にされる本であるわけですよ。 馬鹿にされる本紹介されて、嬉しい? 嬉しくないよね? そうなってくると、むしろ、「なんで自己啓発本は、アンチから馬鹿にされるのか?」っていうことを話した方が面白くね? とまあ、そんなことを考えながら、その理由をツラツラ考えていたら、段々面白くなってきた。 で、この話題は結構面白いなと思っているうちに、だったら、それを本に書けばいいじゃんと。 ふむ。どうなんだろう。悪くないアイディアのようではあるが。 実は今、新書用に「還暦本(還暦世代にふさわしい自己啓発本を紹介するような本)」を書いているのですが、その新書には、そういうのより「なんで自己啓発本は、アンチから馬鹿にされるのか?」というテーマの本を書いた方がふさわしいのではないかと。 まあ、書きかけの還暦本は、また別なところから出版するとして、とりあえずちょっと「対アンチ本」を書いてみようかしら。で、チラッと書いてみて、上手く書けそうなら、そちらを優先すると。 まあ、こういうのは走り出してみないと、書けるかどうか、面白いかどうか、わからないところがあるからね。とりあえず、春休みの内に、あれこれ試してみよう。 春休みってのは、こういう風にアイディアを出したり引っ込めたりして、逡巡するのが楽しいよね!
March 3, 2025
コメント(0)
-

常盤新平訳『夏服を着た女たち』を読む
常盤新平さんの訳された『夏服を着た女たち』という本を読みましたので、心覚えをつけておきましょう。 この短篇集に載っている短篇を書いたのは、アーウィン・ショーというアメリカの作家さん。『リッチマン・プアマン』という長編小説がベストセラーになった人で、他に『若き獅子たち』なんていう長編もあるけど、雑誌『ニューヨーカー』に掲載されるような洒落た短篇でも知られている。 で、一流の作家かというと、うーん、どうかな。少なくともアカデミズムはそう考えていない。風俗作家として1.5流、トータルでは2流の作家、という辺りの評価ではないかと。 だから、日本ではあまり評価されてこなかった作家ではあるのだけれども、常盤さんはこの作家に惚れこんだ。なぜなら1.5流の風俗作家だから。1流の作家なら、日本の翻訳の大家たちが放ってはおかない。でも、アーウィン・ショーはそうじゃないから、誰も目をつけてない。その誰も目をつけないこの作家に自分は目をつけたのだから、この作家は自分のものであり、いわば自分自身だと。 多分、そういう論理で、常盤さんはアーウィン・ショーに、目一杯の思い入れを注入したのでありましょう。この作家の作品を自分が翻訳して、それを本として出版できれば・・・この思いが、ある意味、翻訳修行中時代の常盤さんの夢であり、彼はその夢を実現させるために翻訳家になったと言っても過言ではないと。 でも、実際にこの本が翻訳されて世に出るまでには随分時間がかかって、ようやく1979年に講談社から出版された。1979年と言えば、常盤さんは既に48歳。ちょうど私生活の上で、妻と愛人の挟み撃ちにあって修羅場をくぐり抜けていた頃のことでございます。でも、そういう背景もあったからこそ、この本に賭けるところはあったのではないでしょうかね。 で、実際、それを読んでみて、どうだったか? うーんとね。悪くはなかったです。でも、スゴク良かったかと言われると、そうでもないかな。 特に短いものになると、『ニューヨーカー』っぽいのよ。『ニューヨーカー』っぽいとはどういうことかと言いますと、「洗練されたO・ヘンリーっぽい」ということ。O・ヘンリーの短篇は、短いストーリーの中に起承転結があり、オチがある。そしてそのオチが、甘苦いの。ある時は甘やかであり、ある時は、人生の辛さをほのめかすような。で、アーウィン・ショーの短篇は、基本、O・ヘンリーの短篇に似ているんだけど、ちょっとだけ苦味が強い。その軽い苦みが、洗練ということであってね。だから、アーウィン・ショーの短篇は、洗練されたO・ヘンリーなわけ。 たとえば「80ヤード独走」とか。20歳の学生時代、主人公の青年はアメフトの練習試合で80メートルを独走し、監督・コーチから嘱望され、ファンも多かった。ところがその後の試合ではあまり活躍できず、さらに悪いことに、彼よりもっと才能のある選手が入って来たことから、彼の影は薄くなるばかり。つまり、80ヤード独走した瞬間が彼の人生のピークだったと。 で、その後、学生時代からの恋人と結婚するも、社会人としてはパッとせず、一方、彼の一ファンだった妻は、出版業界で頭角を現していく。立場は逆転していくわけですな。で、その状況を認識しつつ、彼は80ヤード独走した栄光の日々のことを、懐かしむと。 ま、そんな話。甘苦いでしょ? でも、まあ、これはいい作品ですよ。私は標題作の『夏服を着た女たち』よりいいと思う。 『夏服を着た女たち』も、三十代くらいの夫婦の話。三十代くらいの夫婦というと、若い夫婦というイメージがあるけれども、この短篇が書かれた当時では、すでに薹の立った夫婦という感じでしょう。 で、この夫婦が街へ繰り出して食事でもしようということになるのだけれど、夫の方がNYの町中を颯爽と歩く夏服を着た女たちとすれ違う度に、その女たちをじっと見つめる。で、それを妻が見とがめるわけ。なんで私という女がいながら、他の女に目を奪われるのかと。で、せっかくの楽しいデートが台無しになるわけ。 で、夫の方は、仕方なく自分がつい道行く別嬪さんたちに目が行ってしまうことを白状する。でもそれはただ、見ているだけで、浮気をするつもりなんかまったくない。でも、つい見てしまうんだと。 妻はさらに気を悪くして、夫をその場に残して電話をかけにいってしまう。で、その後姿を見送りつつ、夫は妻の脚のきれいさに見とれると。 何コレ? きれいな女に目を惹かれるのは男の性であると。で、この男はその性に従っているだけで、その点から言えば、彼にとって妻も目を惹かれる対象である。二人は今日、ちょっと夫婦喧嘩をしてしまったけれども、結局は仲のいい夫婦なのだ、というオチ、なんでしょうな。 どう? こういうオチ。好き? 面白いと思う? ワシはそうでもない。通俗的過ぎて、悪い意味でO・ヘンリーっぽい。あの、誤解なきよう言っておきますが、ワタクシは、O・ヘンリーは買っているからね。彼の「賢者の贈り物」とか最高だから。ここで言う「O・ヘンリーっぽい」というのは、オチのある短篇という意味であって、本物のO・ヘンリーとは無関係。 つーことで、それほどでもないなというこの短篇に、どうして常盤さんがそこまで惚れこんだかは謎。多分、「恋に恋する」じゃないけど、「自分はこれ、好き」という思いが暴走したんじゃないでしょうかね。私としては、むしろこの短篇集に収録された他の作品、たとえば「死んだ騎手の情報」とか「フランス風に」、あるいは「愁いを含んで、ほのかに甘く」の方が、よっぽど面白かった。 ちなみに翻訳の質としては、可もなく不可もなし。 それにしても、アーウィン・ショーの短篇と、後に常盤さん自身が書きまくった短篇を比べると、やはりショーの方がよほど上ではありますな。 だって、ショーの短篇にはストーリーがあるもん。たとえ短くても。私の目にはつまらない『夏服を着た女たち』にしたって、一組の夫婦がいて、すれ違いがあって、でもそのすれ違いは実は大したことはなくて、やっぱり二人はこの先も、時々すれ違いながら、それでも仲良く暮らしていくんだろうな、と思わせるところがある。しかもその中で、男の感性と女の感性の違いとか、そういう問題も描きつつ。「これこそが夫婦ってもんだよな」と思わせるストーリーであって、そこに読者の共感があるわけよ。だけど、常盤さんの短篇には、そういうストーリーがないからね。 常盤さんも、ショーの短篇にそんなに入れ込むんだったら、せめてショーの短篇のもつストーリーというものをご自身の創作にも取り入れてほしかったですな。これこれ! ↓【中古】 夏服を着た女たち / アーウィン ショー, 常盤 新平 / 講談社 [文庫]【ネコポス発送】
March 2, 2025
コメント(0)
-
年末ジャンボ
昨年の秋、母が亡くなりまして。で、その流れで、昨年の暮れ、年末ジャンボ宝くじを買いました。 何、その連関? いや、実はですね、ワタクシ、何かとても嫌なこと、辛いことがあった時は、宝くじを買うことにしているんです。そうすると、大抵、当たるもので。 やっぱり、天の采配というのはあるもので、いいことばかりは続かないし、悪いことばかりも続かない。逆に辛いことがあれば、その反動で嬉しいこともある。だから、辛いことがあった時に宝くじを買うと、マジで当たるのよ。 前に父が亡くなった年も、年末ジャンボを買ったら当たりましたからね。3300円。 で、母が亡くなった昨年、年末ジャンボを買っておいたわけ。で、今日、それを宝くじ売り場に持って行って、当たっているかどうか確かめたわけ。すると・・・ 当たっていました! 3300円! まあ、プラマイで言うと、300円のプラス。残念ながら10億円弱プラスではなかったけれど、当たりは当たりですからね! 「宝くじくらい、当ててあげるわよ」と、天国の母が得意気に言っているのが聞こえるようだ・・・。 ということで、母上、ありがとう!! 今年はやっぱりついている年になりそうです。
March 1, 2025
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1