2002年09月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
『抱きしめたい』と“Please Please Me”
ビートルズの日本での実質的なデビュー曲は『抱きしめたい』と“Please Please Me”だった。当時中学生で、まだ英語力が不完全だったので、いろんな誤解や思いこみがあって、今から考えると、冷や汗モノだけど、同時に楽しい思い出(?)にもなっています。『抱きしめたい』の原題はもちろん“I Want To Hold Your Hand”だから、せいぜい『あなたの手をにぎりしめたい』ぐらいでしょ。それが『抱きしめたい』だから、結構頭は混乱したんですよ。で、この曲では、"want to"のところを"wanna"と発音していますよね。当時はどの辞書にも"wanna"なんか出てこないから、こんなことまで悩みの種になっていた。「"wanna"は果たして、正しい英語なのだろうか」なんてね(笑)。これと似たのでは、"gonna"="going to"、"gotta"="got to"とかって、今でこそ誰もが知ってるようなことが、当時は謎だった。それから“Please Please Me”ですよ。なにしろ"please"っていえば、「どうぞ」しか思いつかないんだから、もう完全に『どうぞどうぞ私を』だと思いこんでいた。後年、"please"は「喜ばせる」という意味の他動詞だと知って、はじめの"Please"が「どうぞ」つぎの"please"が「喜ばせる」で『どうぞ僕を喜ばせておくれ』だとわかったときに、僕は飛躍的に英語力が向上したと思ったもんです(笑)。
2002.09.27
コメント(5)
-
動くビートルズを初めてみた日
それはNHKの朝の海外ニュースだった。とにかくその格好に、その歌にびっくりした。髪が長い!みんなで歌ってる!ロックンロールみたいだけど、ちょっと違う!僕がこの目で見たビートルズは、その日が初体験だった。そのとき僕は中学生。それにしても強烈な印象だった。そのあと『抱きしめたい』と『プリーズ・プリーズ・ミー』が流行って、僕はクラスで唯一のビートルマニアになった。みんな舟木一夫とか橋幸夫、三田明とか、吉永小百合だとかに夢中で、僕は異端だったけど、それがうれしかった。それまでは、2・3の例外はあっても、アメリカのモノばかりを聴いていたので、イギリスから出てきたというのも、新鮮だった。来日したときは高校生で、友人は学校をさぼって、東京まで行ったが、僕はテレビで見た。翌年、その友人たちと、バンドを組んで、ビートルズをやった。田舎ではバンドといえば、ベンチャーズばかりで、異端だったけど・・・。東京に移って予備校に通っているとき、世界初の衛星中継で、“All You Need Is Love”を歌うビートルズをテレビで見た。ポールが11月にくる。僕は今までどおり、今回もテレビで見ようと思う。
2002.09.24
コメント(17)
-
ビートルズ、ローリングストーンズを筆頭に・・・
60年代のイギリス音楽は、その後のポピュラーミュージックの歴史を変えた、あるいはその方向性を決定づけたと思う。もちろん、その初期は、アメリカンポップスの模倣が主流であり、一般的であったが、それでもそこはそれ、英国であるからして、やっぱりアメリカンになりきれない、あるいはついブリティッシュになってしまうという、愛すべき宿命が彼らにはあった。その代表的なものは、ヘレン・シャピロ、アルマ・コーガン、クリフ・リチャード etc. だ。前者2名の女性歌手については「懐かしのオールディーズ・ポップス」のテーマのところで、少しふれてみた。そこで、本日は代表的男性歌手、クリフ・リチャードを取り上げてみようと思う。もともとクリフ・リチャードは、アメリカでは売れなかったわけだけど、もしかすると初めから完全に国内向けを意識した曲作りをしていたのかもしれない。たとえばあの名曲“Summer Holiday”。まず、タイトルからして、vacation を使わず、holiday なんだから。つまり vacation は、アメリカ英語だものね(因みに、holiday は単数形でも「休暇」の意味に使えます)。随分イギリス英語っぽい響きがします。バックのシャドウズも、結構洗練された音(と当時はいわれた)で、やっぱり英国風だったと言えそうです。しかし、謎が一つ・・・。なぜ、クリフ・リチャードは日本であんなに売れたのか。当時(60年代初期)は、たとえイギリスものでも、すべてふつうはアメリカ経由だった(あのビートルズさえ)ので、アメリカで売れずに日本で売れたのは、実に興味深いです。これについては、その理由をご存じの方、あるいは知らなくても、推測でも結構ですから、教えてくれませんか。なお、クリフ・リチャードのマイベストは、“Constantly”です。原曲はカンツォーネで、素晴らしいメロディーのバラードです。必聴。
2002.09.22
コメント(2)
-
60年代イギリスを代表する女性歌手 VOL.5
ペトゥラ・クラークは、3人の中では間違いなく、一番の美声の持ち主ですね。で、彼女のヒット曲といえば、もちろん“Downtown”。この曲では、いつもアメリカのテレビドラマにでてくるような都市や、サンフランシスコ、ニューヨークのような町を思い浮かべていた。でも、今から思うととんだ見当違い。あれはまさしくイギリスの都市の“Downtown”に違いない。そのことに気づいたのは、70年代に入ってからだろうか、彼女がイギリス人だとわかってからだった。十数年前に、1年半ばかりイギリスにいたことがあって、ロンドンに住んでいたんだけど、クリスマスの頃にリバプールへ行ったんです。港に近い繁華街を、ブラブラ歩いていたら、この曲が聞こえてきて、その時、ほらほらこういう場所を歌った歌じゃないかって、再確認したようなわけでした。
2002.09.20
コメント(0)
-
60年代のイギリスを代表する女性歌手(4)
『ポケット・トランジスタ』と『グッバイ・ジョー』の日本人カバーについて。当時は大抵各社競作でしたが、『ポケット・トランジスタ』は飯田久彦と森山加代子、『グッバイ・ジョー』は中尾ミエが印象に残っています。『ポケット・トランジスタ』のように、男女が同じ曲をカバーするときに、歌詞をちゃんと変えて、歌わせることがあったけど、なかなか芸が細かいですよね。因みに、この曲の男性バージョンは、確か「♪あの娘(こ)の持ってるちっちゃなポケットランジスタ~」で (いや待てよ、「♪あの娘(こ)は僕のちっちゃなポケットランジスタ~」だったかな?だれか教えてくれ~)、女性バージョンは「♪あたしの持ってるちっちゃなポケットランジスタ~」だった。
2002.09.19
コメント(2)
-
60年代のイギリスを代表する女性歌手(3)
『ポケット・トランジスタ』『グッバイ・ジョー』がヒットしたアルマ・コーガンは、とてもいい歌手でしたが、若くしてなくなっています。そのことを知ったのはだいぶたってからですが、実に惜しい人でした。歌のうまさは、この3人に共通ですが、声が一番個性的だったのは、このアルマ・コーガンだと思うんですよね。もう少し生きてもらって、あと何曲かヒットを出して欲しかった。
2002.09.18
コメント(0)
-
60年代のイギリスを代表する女性歌手(2)
ところで、『子供じゃないの』と『悲しき片想い』の2曲の話をもう少し。今日また秀さんのページにレスがついた、カーペンターズの『イエスタデー・ワンスモア』の中の、♪Every Wow Wow Wow ~、の「ウォウ・ウォウ・ウォウ」は、この『悲しき片想い』を初めとする、当時のヒット曲の中にたびたび登場する、おなじみのフレーズのことです。数え上げたらきりがないほど、♪Wow Wow の使われた曲ってありますねえ。今度みんなで数えてみましょうか。
2002.09.17
コメント(0)
-
60年代のイギリスを代表する女性歌手(1)
ヘレン・シャピロは『子供じゃないの』と『悲しき片想い』の2曲があまりにも有名ですよね。これが流行ったとき、まだ子供だった僕らにはヘレン・シャピロより、圧倒的に弘田三枝子だった。漣健児の訳詞も実にメロディーにピッタリで、よく大声で歌ったものだった。続きはまた明日書きますね。
2002.09.16
コメント(2)
-
みんなアメリカ人だと思っていた
ヘレン・シャピロ、アルマ・コーガン、ペトゥラ・クラークの、共通点は何でしょう。そうです。イギリス人なんです。でも、当時彼女たちのことは、間違いなくアメリカ人だと思いこんでいました。もちろんアメリカのヒット曲が、日本に入ってくるという場合がほとんどだったので、そう思いこんでいたのも無理からぬことだったかもしれない。明日からちょっとこの3人について、あるいは彼女たちの曲について、ひとりずつ書いてゆこうと思っています。
2002.09.15
コメント(5)
-
オールディーズっていうジャンルはいつ頃確立したんだろう
誰かご存じですか。オールディーズっていうジャンルが、いつ頃できたのか。少なくとも60年代には、40年代や50年代の音楽のことを、こういう風には呼ばなかった。ビートルズのシングル盤の寄せ集めLPが、"Oldies But Goldies" だったけど、それでもまだその当時はジャンルとしてのオールディーズはなかった。誰かが作ったジャンルだとしたら、いつ、誰が、何の目的で作ったのか。どなたかご存じでしたら、教えてください。それから、この言葉の意味もかなり広くなってきていると思うのですが。でも、ハードロックやパンクの曲で、いくら古いヤツでも、オールディーズとは呼ばないよね。一体どの辺の時代の、どの辺の曲あるいはアーティストまでがオールディーズなんだろう。そこで、ちょっと考えてみました。かなり抽象的な定義ですが、オールディーズって『昔の曲で、でも古くさいわけではなくて、どこか懐かしくて、聴いているとちょっぴり胸がきゅんとなったり、思わず一緒に口ずさんでしまう、永遠に生き残るに違いない、西洋の(おもに米英の)青春歌謡』なのではないでしょうか。実は僕の頭の中にかなりはっきりと、年代が浮かんでいます。1960年から1966年。この間に発表された曲の中に、先ほどの定義のような曲が、ビッシリと詰まっているんですね。もちろん、その後にも同じような曲はたくさんできています。でも、その曲は、もし70年代や80年代の曲だったとしても、60年代のにおいがする曲だったり、その頃の曲が下敷きになったりしている、あるいはその頃の曲で育った人が書いたりしている、というふうには考えられないだろうか。試しに、皆さんの思いつくオールディーズの曲を1曲(あるいは何曲か)挙げてみてください。ほら、上の定義に当てはまるでしょ。しかも60年代の曲だったでしょ。
2002.09.14
コメント(10)
-
はじめまして。どうぞよろしく。
初めてこちらに日記を書くのに、さっそく人のテーマを拝借しています。オールディーズファンと言うよりは、生き証人といった方がいいかな。いわゆるリアルタイムで聞いていたモノを中心に、いろいろ語りたいです。秀0430さんの過去の日記を拝見していると、まさに「あの頃」がよみがえってきたりするんです。>秀0430さん、これから徐々に返信の形でいろいろ書かせてもらいますね。>みなさん、近いうちにBBSの方も始めますので、乞うご期待。
2002.09.13
コメント(4)
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-
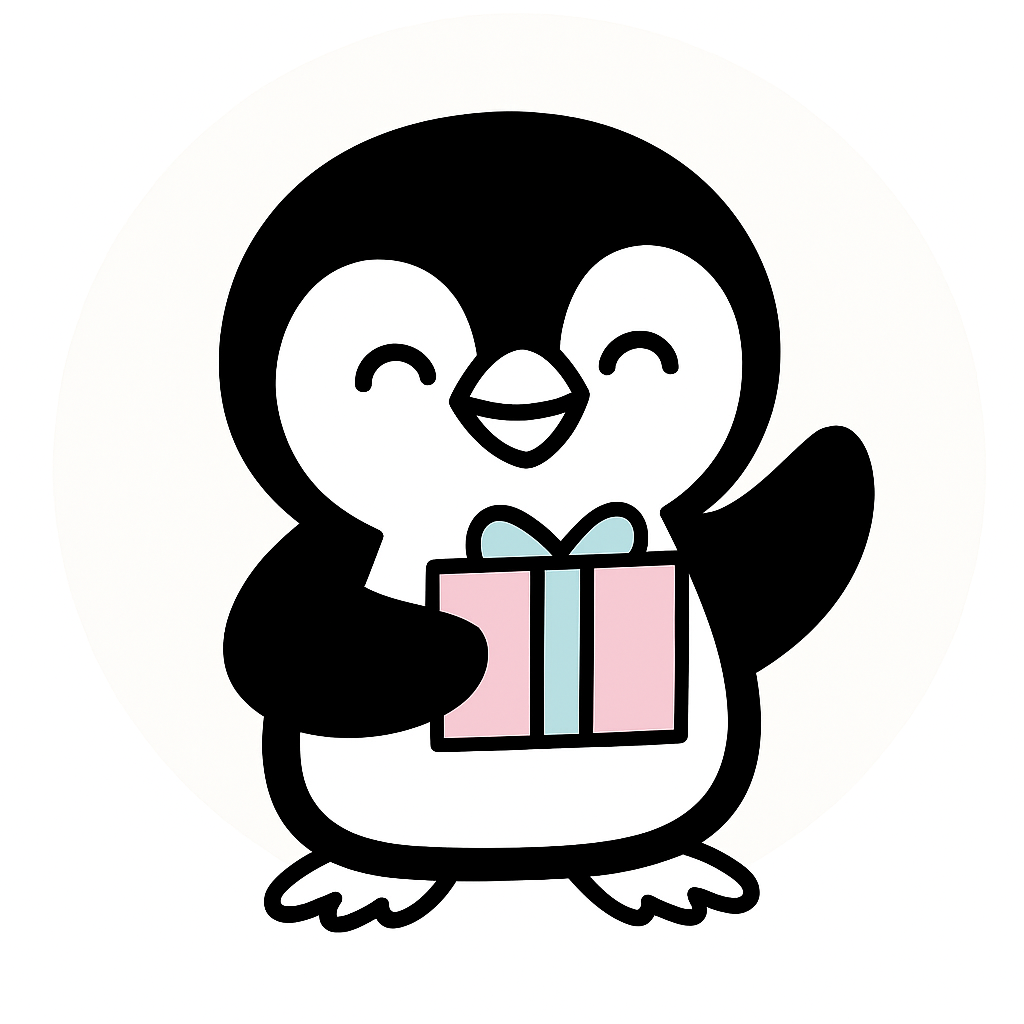
- やっぱりジャニーズ
- 楽天予約 SixTONES Best Album「MILE…
- (2025-11-20 16:44:46)
-
-
-

- 好きなクラシック
- ベートーヴェン交響曲第6番「田園」。
- (2025-11-19 17:55:25)
-
-
-

- 70年代サブカルチャー URC, ELEC, …
- まんだらけの優待のまんだらけZEM…
- (2023-06-24 23:18:46)
-






