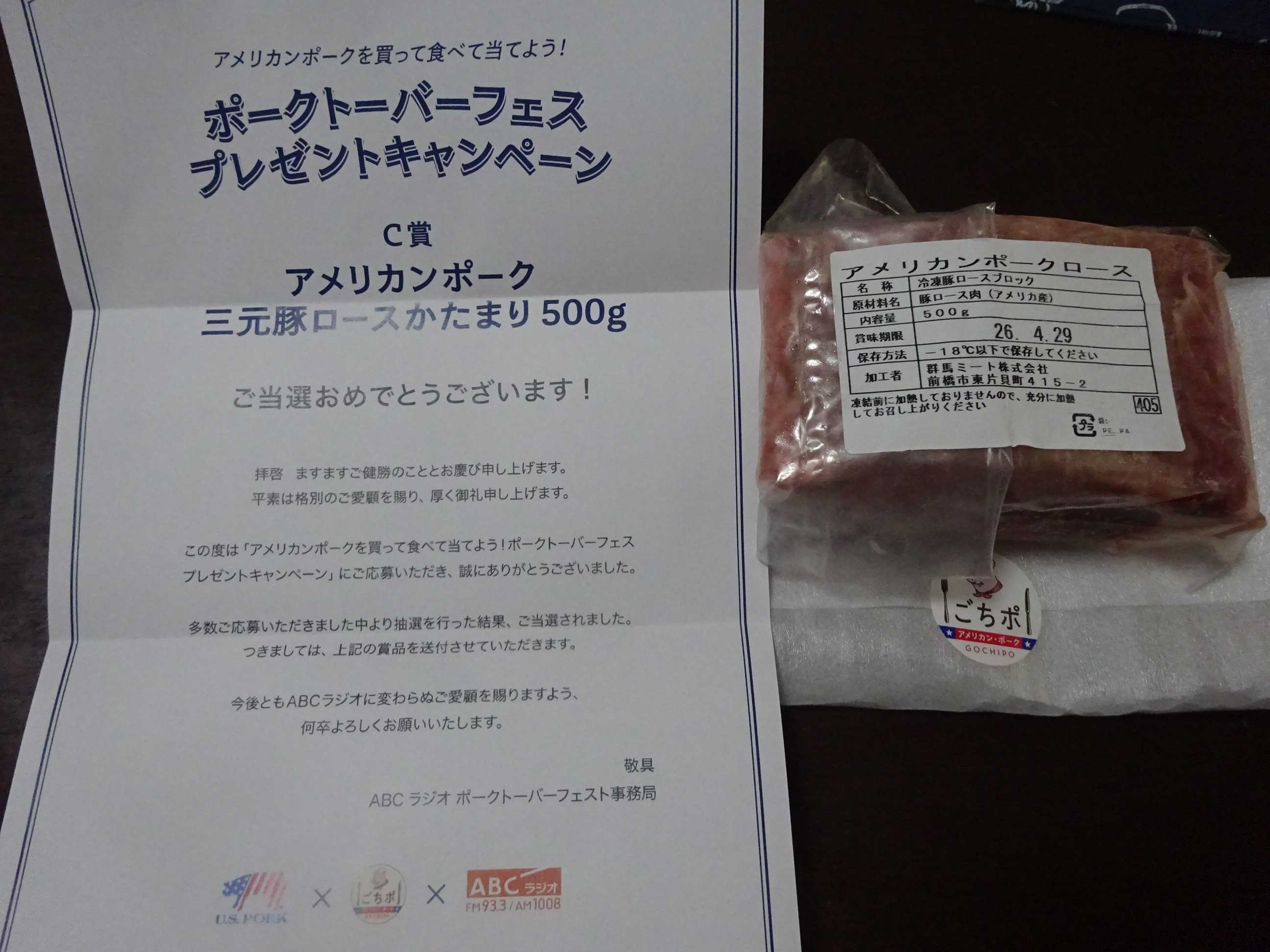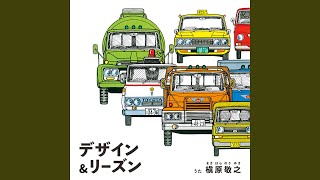2020年09月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
二条良基(感想)
二条良基は1320年生まれ、五摂家の一つ二条家の当主で、北朝に仕えた公家です。 官位は従一位太政大臣に昇り、摂政・関白に4度(数え方によっては5度)にわたり補され、晩年は准三后の栄誉を年得て、文字通り位人臣を極めました。 ”二条良基”(2020年2月 吉川弘文館刊 小川 剛生著)を読みました。 初め後醍醐天皇に仕えたがのち北朝に仕え、関白,太政大臣,摂政などを歴任しながら、博学多識で南北朝時代の歌人連歌作者として知られる二条良基の生涯を紹介しています。 文才にも恵まれ、幅広い分野にわたり著作を遺しています。 和歌では頓阿ら和歌四天王を重用し、歌道師範家に代わり指導者となりました。 また、連歌の発展には最も尽力し、救済ら連歌師と手を携え、中世を代表する詩として大成させました。 小川剛生さんは1971年東京都生まれ、1993年に慶應義塾大学文学部国文学専攻を卒業し、1995年に同文学部修士課程を修了し、1997年に同大学院博士課程を中退しました。 1997年に熊本大学文学部講師、2000年に同文学部助教授となり、同年、二条良基の研究で文学博士の学位(慶応義塾大学)を取得しました。 専攻は中世和歌史で、2009年に慶應義塾大学文学部准教授、2016年に慶應義塾大学文学部教授となり現在に至ります。 2018年に兼好法師の研究で第3回西脇順三郎学術賞を受賞しました。 二条良基は1327年に8歳で元服して正五位下侍従となり、わずか2年で従三位権中納言に昇進しました。 13歳の時に元弘の変が発生して後醍醐天皇は隠岐島に配流され、内覧であった父・道平は倒幕への関与が疑われて幽閉され、良基も権中納言兼左近衛中将の地位を追われました。 このため、二条家は鎌倉幕府より断絶を命じられる状況に追い込まれましたが、翌年に鎌倉幕府が滅亡し、京都に復帰して、建武の新政を開始した後醍醐天皇に仕えました。 二条道平は近衛経忠とともに内覧・藤氏長者として建武政権の中枢にあり、新政が実質上開始された1333年に姉の栄子が後醍醐天皇の女御となり、良基も14歳で従二位に叙されました。 1335年に父・道平が急逝し、翌年に足利尊氏によって政権を追われた後醍醐天皇は吉野へ逃れて南朝を成立させました。 叔父の師基は南朝に参じましたが、この年17歳で権大納言となっていた良基もまた天皇を深く敬愛していたにもかかわらず、後見であった曽祖父師忠とともに京都にとどまり、北朝の光明天皇に仕えました。 光明天皇もこれに応えるべく、1338年に良基に左近衛大将を兼務させ、その2年後に21歳で内大臣に任命しました。 内大臣任命の前年には母を、任命の翌年には曽祖父・師忠を相次いで失いましたが、その間にも北朝の公卿として有職故実を学ぶとともに、朝儀・公事の復興に努めました。 1343年に右大臣に任命されましたが、同時に左大臣には有職故実の大家で声望の高い閑院流の洞院公賢が任じられました。 一条経通・鷹司師平と前現両関白はともに公賢の娘婿であり、良基と公賢は北朝の宮廷において長く競争相手となりました。 1345年に良基最初の連歌論書である『僻連抄』が著されました。 南北朝時代、朝廷は実権を喪失し、関白の職も虚位であったとされます。 二条良基は公家政治家としてより、文学史上の功績によって記憶されています。 しかし、良基は政治的な無力感から文学に逃避したような人物ではありません。 長く執政の座を占めた良基は、南朝の攻撃、寺社の強訴、財政の逼迫といった危機に絶えず対処しなければなりませんでした。 こうした北朝の危機は、室町幕府の内証に原因があり、公家にはどうすることもできませんでした。 しかし、良基は政務への意志をいささかも失わず、足利義満ら室町幕府要人と提携することで山積する問題に対処しようとし、ついには公武関係の新しい局面を拓きました。 このことが伝記の主要なテーマです。 1346年に27歳で光明天皇の関白・藤氏長者に任命され、2年後の崇光天皇への譲位後も引き続き留任しました。 1351年に足利氏の内部抗争から観応の擾乱が起こり、足利尊氏が南朝に降伏して正平一統が成立すると、北朝天皇や年号が廃止され、良基も関白職を停止されました。 光明・崇光両天皇期の任官を全て無効とされて、良基は後醍醐天皇時代の従二位権大納言に戻されましたが、公賢は改めて左大臣一上に任命されました。 南朝では既に二条師基が関白に任じられていて、良基の立場は危機に立たされました。 良基は心労によって病に倒れましたが、それでも 御子左流の五条為嗣とともに南朝の後村上天皇に拝謁を計画するなど、当初は南朝政権下での生き残りを視野に入れた行動も示しました。 しかし、1352年に京都を占領した南朝軍が、崇光天皇・光厳・光明両上皇、皇太子直仁親王を京都から連行したため足利義詮は和議を破棄し、直仁親王を後村上天皇の皇太子にして両統迭立を復活させる和平構想も破綻しました。 義詮は光厳上皇の母西園寺寧子を治天に擬し、その命によって新たに崇光の弟弥仁王を後光厳天皇として擁立して北朝を復活させる構想を打ちたてました。 足利将軍家の意向と勧修寺経顕の説得を受ける形で、良基は広義門院から関白還補の命を受け、昨年の南朝側による人事を無効として崇光天皇在位中の官位を戻しました。 和平構想に失敗した公賢とその縁戚の一条経通・鷹司師平らの政治力は失墜し、政務は年若い新帝や政治経験の無い広義門院を補佐する形式で、良基と九条経教・近衛道嗣ら少数の公卿らによって運営されました。 1353年に南朝側の反撃によって京都陥落の危機が迫ると、足利義詮は後光厳天皇を良基の押小路烏丸殿に退避させ、そのまま天皇を連れて延暦寺を経由した後美濃国の土岐頼康の元に退去していきました。 押小路烏丸殿を占拠した南朝軍は良基を後光厳天皇擁立の張本人として断罪し、同邸に残された二条家伝来の家記文書は全て没収されて叔父師基の元に送られました。 そのような状況でありましたが、良基は病身を押して後光厳天皇のいる美濃国小島へと旅立ち、先に小島にいた叔父の今小路良冬に迎えられ天皇に拝謁しました。 垂井に移った天皇や良基を迎えに尊氏が到着し京都に復帰し、後光厳天皇は以後、良基と道嗣を重用するようになり、京都に留まっていた経通や公賢は二心を疑われていよいよ遠ざけられました。 1354年暮に南朝軍が京都を占領し天皇や良基は近江国に退避しましたが、これは短期間に終わりました。 これ以後は南朝の攻勢も弱まりやや落ち着いた時期を迎え、1356年に救済・佐々木道誉らとともに、『菟玖波集』の編纂にあたり、翌年春までに完成し准勅撰となりました。 1357年に南朝に奔った元関白近衛経忠の子・実玄を一乗院門主から排除しようとして、北朝側の大乗院が引き起こした興福寺の内紛において、良基が藤氏長者として裁定にあたりました。 裁定は経忠の系統を近衛家の嫡流として扱い、かつ自分の猶子・良玄を実玄の後継者とするものであったため、興福寺や近衛道嗣、洞院公賢、さらに室町幕府の不満が高まりました。 実玄を支持する一乗院の衆徒が奈良市中で大乗院派に対する焼き討ちを行ったのを機に、1358年に次期将軍に内定していた足利義詮が関白の更迭を求める奏請を行いました。 良基は関白就任から13年目にして窮地に陥り、辞意を表明し正式に九条経教と交替しました。 良基は関白の地位を追われたものの、依然として内覧の職権を与えられ、自ら太閤を号して朝廷に大きな影響力を与えました。 また、文化的な活動にも積極的に参加し、1363年に二条派の歌人頓阿とともに著した『愚問賢注』が後光厳天皇に進上され、次いで足利義詮にも贈呈されました。 関白職は九条経教から近衛道嗣に移り、天皇側近としての地位を固めつつありましたが、若い道嗣は良基の敵ではなくやがて辞任して、良基が関白に還補されました。 1366年に長男師良が内大臣に任じられ、三男は一条房経急逝によって断絶した一条家の後継者となり経嗣と名乗りました。 1367年に義詮の要請によってやむなく鷹司冬通に関白を譲りましたが、良基の朝廷内部での権勢は相変わらずでした。 この年の暮れに義詮が急死し、足利義満が室町幕府三代将軍となり、細川頼之が執事となりました。 1369年に良基の長男・師良が関白に就任し、1371年に後光厳天皇は後円融天皇に皇位を譲りました。 同年に興福寺の内紛が再燃し、興福寺衆徒は内紛の元凶は実玄を庇護した良基にあるとして、1373年に良基を放氏処分にしました。 しかし、良基は謹慎するどころか春日明神の名代である摂関の放氏はありえないと述べて全く無視し、翌年に後光厳上皇が危篤に陥ると直ちに参内して善後策を協議しました。 興福寺衆徒を非難し続けた後光厳上皇の崩御が衆徒を勢いづけ、後円融天皇の即位式を直ちに行う必要性に迫られた朝廷と幕府は要求の全面受け入れを決定し、良基も続氏となって神木も3年ぶりに奈良に戻りました。 人間として見たとき、良基の内面にはすこぶる複雑なものがあったようです。 北朝に信任されましたが、生涯、後醍醐天皇を敬慕しました。 最高位の公家であるのに、地下の連歌師、また、佐々木導誉ら婆娑羅大名とも親しく交際しました。 王朝盛代を理想とし、朝廷儀式の復興に意欲を燃やすいっぽうで、言い捨ての座興に過ぎない連歌を熱愛し、雑芸にも理解を示しました。 近年、初期室町幕府の研究が深化し、将軍権力の内実が朝廷との関係から再考されています。 これを踏まえた、精緻な観察が必要です。 また、当時の学芸の諸分野において、良基と交流を待った人物はたいへん多いです。 これも堂上から地下、あるいは公家・武家・禅林にわたっており、同時代への強い影響力を証しますが、ここでは俯瞰的な評価が求められるでしょう。第1 二条殿/第2 大臣の修養/第3 偏執の関白/第4 床をならべし契り/第5 再度の執政/第6 春日神木/第7 准三后/第8 大樹を扶持する人/第9 摂政太政大臣/第10 良基の遺したもの
2020.09.26
コメント(0)
-
北澤楽天と岡本一平 日本漫画の二人の祖(感想)
北澤楽天は雑誌の風刺画を描いたのを皮切りに、漫画におけるキャラクターの重要性や日本初の少女漫画を生み出しました。 岡本一平は新聞に挿絵を描いたのち、コマ割りと文章を組み合わせて大河ドラマ的な作品を作るストーリー漫画の原型を作り出し、漫画雑誌や全集・作品集も大ヒットさせ、経済、社会、文化的にも大きな影響を残しました。 ”北澤楽天と岡本一平 日本漫画の二人の祖”(2020年4月 集英社刊 竹内 一郎著)を読みました。 いま世界中で注目されている日本の漫画・アニメの礎を作ったのは、原型を作り出した二人の先人漫画家である北澤楽天と岡本一平であったといいます。 竹内一郎さんは1956年福岡県久留米市生まれ、横浜国立大学教育学部心理学科を卒業し、後日、博士号(比較社会文化学、九州大学)を取得しました。 九州大谷短期大学助教授をへて、宝塚造形芸術大学教授、校名変更で宝塚大学東京メディア芸術学部教授を務めています。 大学在学中の1977年に、劇団「早稲田小劇場」で鈴木忠志に師事し、1981年に山崎哲らと劇団「転位・21」を創設しました。 1983年に自らの劇団「オフィス・ワンダーランド」を旗揚げし、作・演出を担当し、1991年に文化庁新進芸術家派遣研究員制度でフィリピンに留学しました。 竹内 一郎の名前で劇作家・演出家・評論家として、また、さい ふうめいの名前で漫画原作者、ギャンブル評論家として活動し、2006年に第28回サントリー学芸賞を受賞しています。 世界中にテレビが普及した時代、各国は安価で子供が喜ぶ番組のコンテンツを求めていました。 そのとき、手塚治虫という天才が、大胆にコストカットしてアニメーションをつくる方法を考案しました。 1963年に放送が開始された「鉄腕アトム」は、世界初の毎週放送される30分アニメーションです。 これは日本の子供ばかりか、輸出されてアメリカの子供も魅了し、続く「ジャングル大帝」はさらに受け入れられました。 筆者は、日本漫画、ジャパニメーションを生み出しだのは、長い間、手塚治虫だと思ってきました。 それは間違いありませんが、近手塚にはさらに源流があると考えるようになったといいます。 それが北澤楽天と岡本一平であり、手塚以前に日本漫画史に光り輝きながら存在する巨人だったことに気付いたそうです。 明治期に北澤楽天、大正・昭和前期に岡本一平という巨人がいて、二人が切り開いた地平に手塚治虫は立っています。 そう考えると日本漫画の歴史がすっきりと見え、巨人である楽天、一平から、同じく巨人・手塚にバトンタッチされ、それが現代に受け継がれていると考えると、日本漫画史が一気通貫します。 既存の漫画研究史と異なる漫画史が湧き起こり、明治以隆、楽天、一平の育てた壮大な「漫画のスピリット」が、手塚に流れ込んで、やがて日本漫画ジャパニメーションの隆盛につながった、という流れを解説するのが本書の目的です。 北澤楽天は1876年東京市神田区駿河台生まれ、本名は保次、北澤家は代々、埼玉の大宮宿で問屋名主、御伝馬役、紀州徳川家の鷹羽本陣御鳥見役を務めた名家でした。 楽天は洋画を洋画研究所大幸館にて堀江正章から、日本画を父親の保定からそれぞれ学びました。 楽天の漫画家としての人生に最も大きな影響を与えたのは、オーストラリア出身の漫画家フランク・A・ナンキベルでした。 1895年に横浜の週刊英字新聞「ボックス・オブ・キュリオス」社に入社し、同紙の漫画欄を担当していたナンキベルから欧米漫画の技術を学びました。 楽天は、ナンキベルが日本を去った後、その後継者として同紙の漫画を担当するようになりました。 1899年に今泉一瓢の後を継いで時事新報の漫画記者となり、「支那の粟餅」で初めて時事新報の紙面を飾りました。 1902年に同紙の日曜版漫画欄「時事漫画」も扱うようになりました。 作品には、ダークス、アウトコールト、オッパーなどのアメリカのコミックストリップ作家の影響を強く受けていました。 1905年にB4版サイズフルカラーの風刺漫画雑誌「東京パック」を創刊しました。 この雑誌は、朝鮮半島、中国大陸、台湾などのアジア各地でも販売されました。 1912年に雑誌を出版する有楽社が経営に失敗して版権を手放したため雑誌を退き、退社後新たな出版社を創設して「楽天パック」「家庭パック」を創刊しましたが、1年3ヶ月で廃刊になりました。 終刊後は再び「時事新報」を漫画活動の中心に据え、1921年に時事新報から「時事漫画」が日本最初の新聞日曜漫画版として独立し、カラー漫画欄を手掛けるようになりました。 1929年にフランス大使の斡旋により、パリで個展を開催し、その際、教育功労章を受章しました。 知名度と漫画界への影響力を買われて、太平洋戦争中には日本漫画奉公会の会長も務めていました。 その後、読売新聞、東京日日新聞、報知新聞など他紙が日曜漫画版に相次ぎ参入したため読者を奪われ、1931年7月に時事新報を退社して事実上第一線から退き、10月に時事新報の日曜漫画版も終刊となりました。 時事新報退社後、芝白金の自宅に「楽天漫画スタジオ」を開き、翌年に「三光漫画スタジオ」と改名して後進を指導しました。 戦況の悪化に伴い1945年に宮城県遠田郡田尻町に疎開し、1948年に大宮市盆栽町に居を構え、新しい自宅を「楽天居」と称し日本画を描く日々を送りました。 1955年に脳溢血のため自宅で死亡し、翌年、大宮市の名誉市民に推挙され名誉市民第1号となりました。 1966年に旧宅跡に大宮市立漫画会館、現さいたま市立漫画会館が設立されました。 楽天は日本初の職業漫画家とみなされることもあり、その漫画の人気は、現代における漫画が広く一般に普及するのに多大な影響を与えました。 岡本一平は1886年北海道函館区汐見町に生まれ、津藩に仕えた儒学者岡本安五郎の次男で書家の岡本可亭の長男です。 東京・大手町の商工中学校から東京美術学校西洋画科に進学し、藤島武二に師事しました。 この時、美術学校の同級生の仲介で大貫カノと知り合い、後に和田英作の媒酌で結婚しました。 しかし、岡本家には受け入れらなかったため、2人だけの新居を構えました。 1910年に東京美術学校西洋画撰科を卒業し、帝国劇場で舞台芸術の仕事に関わりました。 その後、夏目漱石から漫画の腕を買われ、1912年に朝日新聞社に紹介されて入社し漫画記者となりました。 新聞や雑誌で漫画に解説文を添えた漫画漫文という独自のスタイルを築き、大正から昭和戦前にかけて一時代を画しました。 美術学校時代の同級で読売新聞社記者の近藤浩一路とともに、一平・浩一路時代と評されました。 1929年5月に刊行を開始した「一平全集」に5万セットの予約が入ったのを機に、12月から1932年3月にかけて一家でヨーロッパを旅しました。 帰国後、漫画漫文集「世界漫遊」などをものし、また、一平塾という漫画家養成の私塾を主宰し、近藤日出造、杉浦幸雄、清水崑らを育て、後年は小説にも進出しました。 妻の大貫カノは小説家の岡本かの子であり、長男の太郎ら3人の子を授かりましたが、次男と長女は夭折しています。 1939年にかの子が亡くなり、1941年に山本八重子と再婚しました。 太郎とは異母弟妹にあたる4人の子を授かりました。 作詞家としても活動し、1940年発売の「隣組」は戦時下にも関わらず、ユーモアのある歌詞で親しまれました。 1945年に岐阜県加茂郡白川町に疎開し、終戦後、ユーモアを織り込んだ十七文字形式の短詩「漫俳」を提唱しました。 1946年より加茂郡古井町下古井に移り、1948年に脳内出血で当地で没するまで文芸活動を行いました。 手塚が第二次世界大戦後に漫画をエンターテインメントにし、アニメーションの形式に変えて世界に発信したことが、現在の日本漫画=ジャパニメーションの隆盛につながっています。 この前提として、明治期に西洋文明を取り入れた日本で、北澤楽天がエンターテインメント性を取り入れ、漫画雑誌を大ヒットさせました。 次に、岡本一平が大河ドラマの形式を漫画に取り入れ、全集をはじめ漫画を売りまくりました。 ふたりが社会現象をつくったことが、現在の日本漫画の状況への布石になっていると、著者は考えているそうです。 漫画はまだまだ発展途上の文化であり、ウェブが情報発信の中心に座り、今日、漫画のスタイルは国境を越えボーダーレスになってきています。 今後どのような展開をするのか見当もつかない部分もあり、やがては、まったく異なる視点の漫画史が生まれる可能性もあるといいます。第一章 ジャパニメーションの発展と手塚治虫/第二章 北澤楽天の生涯と業績/第三章 岡本一平の波乱の人生と功績/第四章 楽天山脈と一平山脈に連なる弟子たち/主な参考文献
2020.09.19
コメント(0)
-
レオナルド・ダ・ヴィンチ ミラノ宮廷のエンターテイナー(感想)
レオナルド・ダ・ヴィンチはイタリア・フィレンツェのアンドレア・デル・ベロッキオに師事し、1472年に画家組合に登録し、1482年からミラノの宮廷で画家、彫刻家、建築家、兵器の技術者として活躍しました。 ”レオナルド・ダ・ヴィンチ ミラノ宮廷のエンターテイナー”(2019年12月 集英社刊 斉藤 泰弘著)を読みました。 15世紀末から16世紀にかけて、フィレンツェ、ミラノやローマを拠点に画家、彫刻家として、また美術以外にも技術者として活躍したルネサンスを代表する万能人、レオナルド・ダ・ヴィンチの生涯を紹介しています。 1499年にフランス軍がミラノを占領したため居を移し、マントバ、ベネチア、フィレンツェに滞在しましたが、1506年に再びミラノに戻り、科学的研究や運河の構築計画などを試みました。 1513年に教皇レオ10世に招かれてローマに滞在し、1516年にフランス王フランソア1世の招きでアンボアーズ近郊のクルー城に赴き、同地で没しました。 斎藤泰弘さんは1946年福島県生まれ、1978年京都大学イタリア文学大学院博士課程中退、1990年から京大助教授、1997年から文学研究科教授を務め、2010年に定年退任し名誉教授となりました。 専攻はイタリア文学、イタリア演劇で、レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿研究の第一人者であり、1980年に第三回マルコ・ポーロ賞を受賞しました。 2019年はレオナルド・ダ・ヴィンチが亡くなってちょうど500年の節目の年に当たるため、この機会にもっと深く知ってほしいという願いから、この本を書くことにしたといいます。 レオナルド・ダ・ヴィンチは1452年生まれ、フルネームはレオナルド・ディ・セル・ピエーロ・ダ・ヴィンチといいます。 レオナルド・ディ・セル・ピエーロ・ダ・ヴィンチは、ヴィンチ(出身)のセル(父親メッセルの略称)の(息子の)レオナルド」という意味です。 音楽、建築、数学、幾何学、解剖学、生理学、動植物学、天文学、気象学、地質学、地理学、物理学、光学、力学、土木工学など様々な分野に顕著な業績と手稿をのこしました。 1452年4月15日に、フィレンツェ共和国から約20km離れたフィレンツ郊外のヴィンチ村において、有能な公証人であったセル・ピエーロ・ダ・ヴィンチと、農夫の娘であったカテリーナとの間に非嫡出子として誕生しました。 ヴィンチはアルノ川下流に位置する村で、メディチ家が支配するフィレンツェ共和国に属していました。 レオナルドの幼少期についてはほとんど伝わっていません。 生まれてから5年をヴィンチの村落で母親とともに暮らし、1457年からは父親、祖父母、叔父フランチェスコと、ヴィンチの都市部で過ごしました。 レオナルドの父親は、レオナルドが生まれて間もなくアルビエラという名前の16歳の娘と結婚し、レオナルドとこの義母の関係は良好でしたが、義母は若くして死去しなした。 レオナルドが16歳のときに、父親が20歳の娘フランチェスカ・ランフレディーニと再婚しましたが、セル・ピエロに嫡出子が誕生したのは、3回目と4回目の結婚時のことでした。 レオナルドは、正式にではありませんでしたが、ラテン語、幾何学、数学の教育を受けたようです。 レオナルドの幼少期は、さまざまな推測の的となっています。 1466年に、14歳だったレオナルドはフィレンツェでもっとも優れた工房のひとつを主宰していた芸術家、ヴェロッキオに弟子入りしました。 レオナルドはこの工房で、理論面、技術面ともに目覚しい才能を見せました。 レオナルドの才能は、ドローイング、絵画、彫刻といった芸術分野だけでなく、設計分野、化学、冶金学、金属加工、石膏鋳型鋳造、皮細工、機械工学、木工など、さまざまな分野に及んでいました。 ヴェロッキオの工房で製作される絵画のほとんどは、弟子や工房の雇われ画家による作品でした。 弟子レオナルドの技量があまりに優れていたために、師ヴェロッキオは二度と絵画を描くことはなかったという話があります。 20歳になる1472年までに、聖ルカ組合からマスター(親方)の資格を得ています。 レオナルドが所属していた聖ルカ組合は、芸術だけでなく医学も対象としたギルドでした。 その後、おそらく父親がレオナルドに工房を与えてヴェロッキオから独立させ、レオナルドはヴェロッキオとの協業関係を継続していました。 制作日付が知られているレオナルドの最初期の作品は、1473年8月5日にペンとインクでアルノ渓谷を描いたドローイングです。 1476年のフィレンツェの裁判で、レオナルド他3名の青年が同性愛の容疑をかけられたが放免されたといいます。 1476年以降1478年になるまで、レオナルドの作品や居住地に関する記録は残っていません。 1478年にレオナルドは、ヴェロッキオとの共同制作を中止し、父親の家からも出て行ったと思われます。 1478年1月に、レオナルドはヴェッキオ宮殿サン・ベルナルド礼拝堂の祭壇画の制作という、最初の独立した絵画制作の依頼を受けました。 5月にはサン・ドナート・スコペート修道院の修道僧からも制作依頼を受けました。 しかし、前者は未完成のまま放置され、後者はレオナルドがミラノ公国へと向かったために制作が中断され、未完成に終わっています。 1482年から1499年までミラノ公国で活動し、『岩窟の聖母』は1483年に聖母無原罪の御宿り信心会からの依頼、『最後の晩餐』(1495年 - 1498年)はサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院からの依頼でした。 レオナルドはミラノ公ルドヴィーコから、様々な企画を命じられました。 特別な日に使用する山車とパレードの準備、ミラノ大聖堂円屋根の設計、スフォルツァ家の初代ミラノ公フランチェスコ・スフォルツァの巨大な騎馬像の制作などです。 1499年に第二次イタリア戦争が勃発し、イタリアに侵攻したフランス軍が、レオナルド制作予定のブロンズ像の原型用粘土像「巨大な馬」を、射撃練習の的にして破壊したといいます。 ルドヴィーコ率いるミラノ公国はフランスに敗れ、レオナルドは弟子のサライや友人の数学者ルカ・パチョーリとともにヴェネツィアへ避難しました。 ヴェネツィアでは、フランス軍の海上攻撃からヴェネツィアを守る役割の軍事技術者として雇われています。 レオナルドが故郷フィレンツェに帰還したのは1500年のことで、サンティッシマ・アンヌンツィアータ修道の修道僧のもとで、家人ともども賓客として寓されました。 1502年にレオナルドはチェゼーナを訪れ、ローマ教皇アレクサンデル6世の息子チェーザレ・ボルジアの軍事技術者として、チェーザレとともにイタリア中を行脚しました。 1502年にレオナルドはチェーザレの命令で、要塞を建築するイーモラの開発計画となる地図を制作しました。 チェーザレはレオナルドを、土木技術に特化した工兵の長たる軍事技術者に任命しています。 レオナルドは再びフィレンツェに戻り、1508年10月18日にフィレンツェの芸術家ギルド「聖ルカ組合」に再加入しました。 そして、フィレンツェ政庁舎大会議室の壁画『アンギアーリの戦い』のデザインと制作に2年間携わりました。 1506年にレオナルドはミラノを訪れ、1507年にフィレンツェに戻り、1504年に死去した父親の遺産を巡る兄弟たちとの問題解決に腐心しています。 1508年にミラノへ戻り、サンタ・バビーラ教会区のポルタ・オリエンターレに購入した邸宅に落ち着きました。 1513年9月から1516年にかけて、レオナルドはヴァチカンのベルヴェデーレで多くのときを過ごしています。 1516年にフランソワ1世に招かれ、フランソワ1世の居城アンボワーズ城近くのクルーの館が邸宅として与えられました。 レオナルドは死去するまでの最晩年の3年間を、弟子や友人たちとともに過ごしました。 そして、1519年5月2日にクルーの館で死去しました。 レオナルドは、一生の間に、ごくわずかな数の絵画作品と、膨大な数の《手稿》(ノートブックのこと)を、しかもややこしい「鏡文字」で書き残しました。 鏡文字とは、鏡に映さないと普通の字に読めない、つむじ曲がりの文字のことです。 この本では、レオナルドのミラノ時代に限って、制作した絵画や彫刻を、レオナルドの目を通して見ることによって解説したといいます。 後世に残る重い作品を作り上げるには、軽くて、はかなくて、気晴らしになるような時間か必要です。 ミラノ時代にはそれがふんだんにありました。 この時代、レオナルドは戦時には恐ろしい武器の発明家や軍事技師として活躍し、平時には宮廷の祝祭で奇想天外な夢の舞台を出現させるなど、宮廷のエンターテイナーとしても活躍しました。 30歳からの20年近くにわたるミラノ時代は、心からの情熱と喜びをもって自分の責務からの逸脱行為に熱中できた、レオナルドの人生の中で最も幸せな時代でした。 これまで研究者たちは、レオナルドの輝かしい姿に目がくらんで、その暗部が見えていなかったようなので、この本ではこれまで人の立ち入ることのなかった舞台裏にも踏み込んで検証してみたといいます。第1章 レオナルドが鏡文字を選んだ理由/第2章 はるかなるミラノへ-都落ちの原因は?/第3章 失われた騎馬像についての感想からなにが分かるか?/第4章 ミラノ公国はどんな国だったのか?/第5章 軍事技師と宮廷芸術家として/第6章 天国の祭典/第7章 野蛮人のパレード/第8章 『白貂を抱く貴婦人』はどんな女性だったのか?/第9章 サンセヴェリーノ夫妻の肖像画/第10章 ミラノ宮廷のエンターテイナー/第11章 『最後の晩餐』はなぜ名画なのか?/第12章 ミラノ脱出
2020.09.12
コメント(0)
-
由利公正 万機公論に決し、私に論ずるなかれ(感想)
由利公正は越前福井藩士で藩主の松平慶永(春嶽)に重用され、1857年に藩の兵器製造所頭取となって造船事業に携わり、一方で、将軍継嗣運動一橋派に関係しました。 ”由利公正 万機公論に決し、私に論ずるなかれ”(2018年10月 ミネルヴァ書房刊 角鹿 尚計著)を読みました。 福井藩の財政再建で頭角を現し、坂本龍馬の推挙により維新政府財政担当となり、幾度もの抵抗や左遷を受けながらも殖産興業と公議公論の発展に尽力した、由利公正の生涯を紹介しています。 慶永が隠居謹慎を命ぜられると、大老井伊直弼を除くことを計画しました。 藩に招聘された横井小楠の指導のもと、物産会所をおこして財政整理、物産振興にあたりました。 1861年末には輸出物産300万両に上り、藩金庫には黄金50万両蓄蔵の成果をあげました。 維新後は新政府の徴士・参与となり、会計基金300万両の調達、太政官札の発行など、明治政府の財政面を担当し、五か条の御誓文の起草にも関係しました。 角鹿尚計さんは1960年大阪市天王寺生まれ、歌号・旧名は足立尚計である。1983年に皇學館大学文学部国史学科を卒業し、福井市立郷土歴史博物館学芸員となりました。 2002年に角鹿国造家(旧万性院家)を継承し、氣比神社宮司に就任しました。 2015年に福井市立郷土歴史博物館長となり、2020年に博士(文学)皇學館大学を取得し、引き続き博物館長を務めています。 由利公正は日本の武士(福井藩士)、政治家、財政家、実業家で、子爵、麝香間祗候、旧姓は三岡、通称を石五郎、八郎、字を義由、雅号に雲軒などがあります。 由利公正の名前の読み方は、きみまさ、きんまさ、コウセイの 3 説が併存します。 1829年に、越前松平家32万石の藩士の嫡男として越前国足羽郡福井城下に生まれました。 幼年より苦しい家計を援け、槍術などの武道で名を馳せ、藩の兵器製造に手腕を発揮した、橋本左内の指導する藩校明道館で兵学を講じました。 左内の制産・公議公論の政治思想を受け継ぎつつ、左内没後は熊本から招聘された横井小楠に師事して、実学に感銘を受けました。 藩の殖産興業策を実施するため、小楠と共に西国各地へ出張しています。 下関では物産取引の実情を調査し、長崎では藩の蔵屋敷を建ててオランダ商館と生糸販売の特約を結ぶなど、積極的な経済政策を推進しました。 民富めば国の富む理である、という民富論的な富国策を実践して、藩財政の建て直しに功績がありました。 越前国福井藩16代藩主の松平慶永が幕府政事総裁職に就任すると、その側用人に就任しました。 長州征伐では、藩論を巡って対立した征伐不支持と薩摩藩や長州藩など雄藩支持の両派の提携を画策しました。 福井藩主導による開国、公武合体を進めるため、有志と挙藩上洛を計画しその首謀者となりましたが、藩論二分し遂に頓挫して罪を得、家督を実弟に譲り蟄居しました。 福井にて蟄居・謹慎中に坂本龍馬の来訪を受け、新政府が取るべき経済政策について談義しました。 このことが新政府への参画を求められたことへ結びつきました。 龍馬とは大変気が合ったようで、2度目の福井来訪時、足羽川近くの山町のたばこ屋旅館にて、早朝から深夜まで延々日本の将来を語り合ったといいます。 五箇条の御誓文の原文となった「議事之体大意」は、龍馬の船中八策と思想的な基本が共通しています。 龍馬は公正と会見して帰京した時期に、新政府綱領八策を自筆しています。 龍馬の推挙により新国家の財政担当として徴用され、徴士・参与となりました。 「五箇条の御誓文」の草案である「議事之体大意」を起草し、新政府の財源確保を大政官札の発行で補おうとしました。 その後帰京して福井の官吏として地方行政に手腕を発揮し、やがて再度徴用されて東京府知事となり、東京不燃化計画など民生の諸政策に尽力しました。 府知事時代の1872年に銀座大火が発生し、現在の丸の内、銀座、築地の一帯が全焼しました。 当時の東京は木造家屋が多かったため、東京を防火防災都市とすべく、銀座に煉瓦造りの建築物を数多く建て銀座大通りの幅員するなど、都市改造計画を立案・実行に移しました。 藩閥政治から公議政体の実現のため、板垣退助らと民撰議院設立建白書に名を連ねました。 その他、民力向上のため、有隣生命保険株式会社の設立、日本興業銀行既成同盟会等の要職に就きました。 史談会の会長にも推薦されました。 幕末明治期を駆け抜けた志士たちの中では長命で、子爵・勲一等・従二位という高い地位にまで上り詰めました。 明治の元勲と呼ばれる人物と言えぱ、木戸孝允、大久保利通、西郷隆盛をはじめ、薩長という藩閥出身者の名を挙げます。 また倒幕か佐幕か、開国か攘夷か、常に二極の抗争の結果、明洽維新がなされ、わが国が近代化に邁進したというのがこれまでの教科書的な一般認識でした。 しかし、最近の研究では、新たな史料の相次ぐ発見などにより第三極の立場が注目されつつあります。 これは、公武合体で政権を一つにして外国と交易し、そのうえで公議公論・公議政体論を実現して、近代国家にデモクラシーをいち早く導入しようとするものです。 その関係で、越前福井藩の藩是と行動が注目されつつあります。 福井藩の幕末維新に生き、明治新政府において財政の指導者となった由利公正の存在は、知られながらもあまり注目されてきてはいません。 公正の伝記でまとまったものはいくつかありますが、いずれも大著の上に戦前の刊行物であり、理解しやすい啓蒙書とは言えません。 そこで本書は、公正の入門書・研究書・啓蒙書として大方に利用されることを念頭において執筆したといいます。 生涯のうちにこれだけ多岐にわたる多くの事績を残した元勲は、公正の他に例があるでしょうか。 しかも、生涯の理念・信条は、どのような課題に直面しても動揺はありません。 旧政体の江戸幕府が終焉し、明治の近代国家に移行して、大きく価値観の変化した時代にあっても、一貫して変わることはありませんでした。 その理念・信条とは、尊皇、経綸、公論であると言えます。 橋本左内が数え年15歳時にして認めた啓発録の五訓のように、公正もまた幼・青年時の体験に基づく志にぶれることなく、ほぼ80年という長い生涯を剛直な精神で生き貫きました。 左内らとともに吉田東篁門下で養った崎門学に基づく尊皇は、藩から天皇親政という天下への時代の転換にあっても動揺はありませんでした。 公正の尊皇は春嶽のそれと違うことなく、福井藩是の根幹であり、天皇親政の元での政体こそ、議会政治である公議公論、公議政体論なのでした。 左内と師、小楠の政治・経済思想を実行した経綸と、この二人を提唱者・指導者として明君松平春嶽を中核とした福井藩是たる公論を、近代国家の政体として実現させることに尽くしました。 公正の生涯を概観する時、およそに言えば藩政時代の「三岡義由」時代と、維新後の「由利公正」時代の二期に分けることか出来ます。 これは、木戸や大久保らにも言えることですが、公正も藩政時代に、粛清・暗殺・戦死・病死等で維新を見得なかった志士たちの偉業を維新後実現に向けて懸命に尽力したのです。 現代は長寿社会で、第二の人生と言えば定年後を指しますが、当代の日本人にとって第二の人生か維新後であったとみれば、第二の人生を生きた公正らの責務こそ、国家・社会にとってきわめて重要な立場にあったと言えます。 維新後の公正の仕事こそ、福井藩論の集成であり実現でした。 本書は博物館の所蔵史料など多様な史料と新出の史料・文献を極力活用し、これまでの研究業績を参考として、波瀾に満ちたその生涯を追ったといいます。 これまでも指摘されてきたように、『由利公正伝』には公正の記憶違いや、創作と思われる実話が少なからずあり、とくに年月の表記には注意を要します。 これらは『子爵由利公正伝』でかなり改められたものの、まだ充分とは言えません。 この二書の伝記を尊重しつつも、改めるべき記述や年月の表記は修正に努めたといいます。第1章 家系と家族/第2章 福井藩士三岡石五郎/第3章 安政期までの公正と福井藩政/第4章 殖産興業と公正/第5章 藩から天下へ/第6章 新政府の綱領制定と財政策/第7章 東京と福井/第8章 東京府政の改革と発展/第9章 社会への広遠な活動と功績/第10章 栄光と終焉
2020.09.05
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1