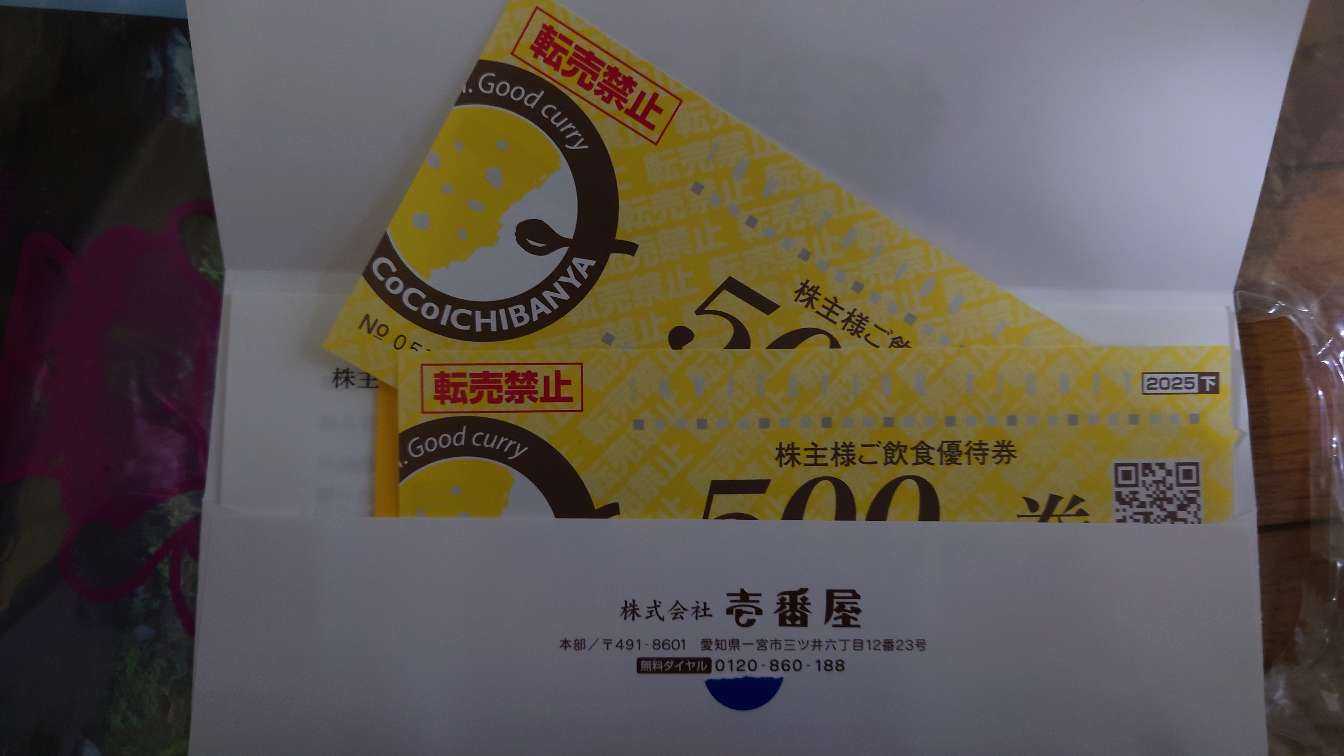2020年12月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

世界の美しい図書館(感想)
図書館は知の宝庫であり、地図(図版)の「図」、書籍の「書」を取って、図書とし、図書を保存する建物という意味でした。 図書、雑誌、視聴覚資料、点字資料、録音資料等のメディアや情報資料を収集、保管し、利用者への提供等を行っています。 ”世界の美しい図書館”(2014年12月 バイインターナショナル社刊 関田 理恵著)を読みました。 世界遺産として登録されている歴史的図書館や最新鋭の名建築のものまで、世界各国の豪華な図書館とユニークな施設を100館掲載しています。 基礎的な蓄積型文化施設の一種であり、博物館が実物資料を中心に扱い、公文書館が非定型的文書資料を中心に扱うのに対して、図書館は 出版物を中心に 比較的定型性の高い資料を蓄積します。 本書はPIE BOOKS=ピエ・ブックスの1冊ですが、発売元は株式会社パイ インターナショナルとなっています。 ピエ・ブックスを刊行してきたピエ株式会社とパイ インターナショナルは、これまで互いに協力して、デザイン書・ビジュアル書を中心に、新鮮な出版を心がけてきました。 2017年1月に、パイ インターナショナルがピエ株式会社を吸収合併し、経営の効率化を共に目指して、国内外へ向けたブランディングの強化を図りました。 パイ インターナショナルは1971年7月に豊島区で設立され、魅力ある文化・優れたクリエイターと、世界との懸け橋でありたいとしています。 PIEはPretty(かわいい)、Impressive(感動的な)、Entertaining(楽しい)で、円であり丸く、丸いのは地球であり、そこに世界が存在しています。 パイという名前はおかあさんが作ってくれる食べ物であり、家庭的で親しみがありいろいろなものがミックスされています。 世界のさまざまなデザイン・アート・文化を世界に紹介したい、届けたい。新鮮で、やさしく可愛らしい、親しみのある書籍づくりをめざしたいという思いをこめています。 人類が「書き記すこと」をはじめたのは、紀元前3000年~3400年頃の古代メソポタミアだといわれます。 古代メソポタミアの文書は粘度板に刻まれていました。 粘度板の保管場所としての図書館がいつ頃誕生したのかは分かっていませんが、シリアの古代都市エブラ宮殿遺跡から、紀元前2250年頃に書かれた粘度板が大量に保管された文書館が発見されています。 紀元前7世紀にはアッシリア王アッシュール・バニパルの宮廷図書館があり、アッシリア滅亡時に地下に埋もれたまま保存された粘土板文書群が出土しました。 ヘレニズム時代の図書館としては、紀元前3世紀のアレクサンドリア図書館が著名です。 この図書館は、付近を訪れる旅人が本を持っていると、それを没収して写本を作成するというほどの徹底した資料収集方針を持っていました。 さらに、薬草園が併設されており、今日の植物園のような遺伝資源の収集も行われていました。 つまり、今でいう図書館、公文書館、博物館に相当する機能を併せ持っており、古典古代における最高の学術の殿堂となっていました。 古代の図書館の中でも「世界三大図書館」として名高いのが、アレクサンドリア図書館、ペルガモン図書館、ケルスス図書館です。 アレクサンドリア図書館では、図書館への放火により全ての蔵書が失われてしまいました。 ペルガモン図書館はトルコのミュシア地方にあり、ケルスス図書館はトルコのエフェソス遺跡にあります。 古代の図書館は繁栄の象徴でもあり、古代ギリシャでは紀元前600年頃には図書館と文書館が大いに発展しました。 上流市民は書物の個人コレクションを収蔵して、美しい建物を競って建てました。 プラトン、ヘロドトスといった学者たちも大規模な個人図書館を所有していました。 中でも哲学者アリストテレスの図書館は数々の伝説を生み、その蔵書は何世代も後のアレクサンドリア、コンスタンティノープルにまで伝えられていったといいます。 一般市民も利用できる公共図書館が、初めて設立されたのもギリシャで、紀元前500年頃のアテナイとサモスでは、公共図書館が発展していきました。 西洋世界では、5世紀から9世紀にかけて多くの都市が戦乱によって荒廃し、ギリシャ・ローマ時代の知の遺産である公共図書館は姿を消していきました。 一方、ビザンツ帝国が台頭し、首都コンスタンティノープルの図書館では、ギリシャとローマの古典の収集が続けられました。 5世紀のコンスタンティノープル図書館では、数千冊に及ぶさまざまな分野の書物を所蔵する大図書館を運営していたとされます。 収蔵本の大半は羊皮紙の巻き物で、金のインクで書かれたものもありました。 コンスタンティノープルは本の輸出で知られ、多くの本がイスラム圈の図書館に運ばれ、学問の発展に寄与しました。 この時期の大規模な図書館は西洋ではなく、イスラム圈と東アジアにありました。 中世イスラムでの中でも著名な図書館は、アッバース朝の第7代カリフ・マムンがバグダードに設立した「知恵の館」です。 天文台や学校などを備えた、近代の大学の先駆ともいえる施設で、西暦830年に建てられた同館には150万もの書物が所蔵されていたといいます。 イベリア半島でアンダルスのウマイヤ朝が成立すると、コルドバには7つの図書館が建設され、カリフの図書館だけで40万巻の蔵書がありました。 ですが、これらのコレクションは、戦争による略奪やコーランのみを認めるイスラム教徒の手により、12世紀にはほとんどが失われてしまいました。 中世の西洋の図書館といえば、ウンベルト・エーコの小説「薔薇の名前」に登場する修道院図書館を思い浮かべる人も多いでしょう。 小説の中では8万5千冊もの蔵書があったことになっていますが、当時の修道院には多くても500冊ほどの蔵書しかしかなかったといいます。 11~13世紀にかけての中世盛期になると、学問の中心は修道院から大聖堂の学校へと移り、聖堂の図書館が発展し、大量の本を所職するようになっていきました。 1200年代のソルボンヌ大学には28基の書見台があったという記禄がありますが、本格的な書架はなく、貴重な書物の多くは祭壇の近くにしまわれていたり、書見台に鎖でつながれていました。 14世紀に入りルネサンスの時期には、多くの富裕層が個人図書館をつくるようになりました。 また14世紀の終わりには、ヨーロッパには70を超える大学が存在するようになり、そのほとんどに図書館がありました。 1452年には、イタリアにヨーロッパで最初の自治体の財産としてすべての市民に聞かれた図書館、マラテスティアーナ図書館が開館しました。 教会の会衆席に似た座席が並び、本は座席前の書見台に鎖でつながれている作りは、当時の図書館の典型でした。 1564年にはヴェネッイアにマルチアーナ図書館が誕生し、3廊式の均幣のとれた空間はその後の図書館建築に大きな影響を与えました。 1450年頃にヨハネス・グーテンベルクが活版印刷技術を発明すると、印刷工房はヨーロッパ中にまたたく問に広がりました。 16世紀の初頭には膨大な数の本が印刷されるようになり、本の価格も大幅に下がりましたが、図書館の形態変化がおこるのは16世紀末から17世紀初頭にかけてです。 この時期、イングランドでつくられたのが「ストール・ライブラリー」で、その姿はオックスフォード大学図書館に残るハンフリー公爵図書館に見ることができます。 壁に書籍を収納する「ウォール・システム」の図書館は、17、18世紀のヨーロッパで盛んに設計されました。 多くの修道院や宮殿に影響を与えたウォール・システムの図書館は、スペインのエル・エスコリアル修道院副書館だといわれます。 長さ68mもの壁面に天丈までの高さの巨人な書棚が据え付けられ、本がずらりと陳列されました。 本は壁を飾る装飾の一部になり、開架式閲覧室という図書館のイメージも決定づけました。 ケンブリッジ大学にも、画期的な建築のレン図書館が1695年に完成しました。 特筆すべきは、書棚よりも高い場所につくられた窓から、豊かな光が降り注ぐ点です。 書棚は壁にそって並ぶと同時に、伝統的なストール・ライブラリーのように壁面から直角に書棚を配しました。 このレイアウトは後の回書館建築に大きな影響を与えることになりました。 18世紀には、壮麗なバロック様式と曲線を多用するロココ様式の図書館が多く建設されるようになりました。 内装に施された豪華な装飾には、さまざまなメッセージが込められました。 たとえばバロック様式の代表的な図書館として名高い宮廷図書館には、施主であるカール6世を神格化した姿の天井画が描かれています。 また、ギリシヤにアルファペットを伝えたとされる、カドモスの物語もルネッド壁面の半円形部分に描かれています。 壮麗な図書館は、当時の権力者の威光を見せつける格好の舞台装置でした。 18世紀末から19世紀初頭にかけて、バロックやロココ様式の反動として、古代ギリシヤ・ローマの建築をもとにした、新古典主義の図書館が多く建てられました。 特徴である切れ目のない半円筒ヴォールドの天井は、パンノンハルマ修道院図書館や、国民議会図書館にその特徴を見ることができます。 19世紀に入ると機械化が進み、ますます多くの本が世の中に出回るようになりました。 図書館の規模も大きくなり、設備や運営方法にも大きな改革が見られるようになりました。 1850年には、フランスに鉄製の屋根がつかわれたサント=ジュヌヅイェーブ図書館が誕生し、1866年にはアメリカに鉄製の書架とガス灯を備えたジョージ・ピーポデイ図書館が完成しました。 大英博物館図書室は完全な鉄骨構造で建てられ、垣根をドームにすることで支柱のない、直径約40mもの大空間をつくることができました。 この放射状のレイアウトは、その後多くの図書館で採用されていきました。ザンクト・フロリフン修道院図書館/アルテンブルク修道院図書館/アドモント修道院図書館/オーストリア国立図書館(宮廷図書館)/メルク修道院図書館/マルチアーナ図書館/アンブロジアーナ図書館/パンノンハルマ修道院図書館/ストラホフ図書館/ザンクト・ガレン修道院図書館/チューリッヒ大学法学部図書館/フィンランド国立図書館/ストックホルム市立図書館/ヴェンラ図書館/デンマーク王立図書館ブラックダイヤモンド/ブランデンブルク工科大学図書館/シュトゥットガルト市立中央図書館館/ハンブルク大学法学部図書館/ベルリン自由大学文献学図書館/ドゥスリングン図書館/フンボルト大学グリム・センター/ヨハネス・ア・ラスコ図書館/ヴィブリングン修道院図書館/アンナ・アマリア図書館/ヘルツォーク・アウグスト図書館/マリー・エリザベート・リューダー・ハウス/ミニビブ/デルフト工科大学図書館/アムステルダム公共図占館中央館/グラス・パレスライブラリ/ユトレヒト大学図書館/スパイケニッセ公共図書館/サント=ジュヌヴィエーヴ図書館/フランス国立図書館リシュリュー館/国民議会図書館/シヤンテイ城図書鮪/メデイアテック・ア・ヴェニシュウー/メソン・デュ・リーブル/ピエールヴィーヅライブラリーアンドメディアセンター/ペッカム公立図書館/シーリー歴史図書館/大英博物館セント・パンクラス本館/バーミンガム公共図書館/オックスフォード人学ボドリアン国政館ハンフリー公爵図書館/ラドクリフ・カメラ/オックスフォード大学コドリントン図書館/大英博物館図書室/ダブリン大学トリニティ・コレッジ図書館オールド・ライブラリー/アイルランド国立図書館/TEA-テネリフェ・エスパジオ・デ・ラ・ザルテス/マドリード地域ドキュメンタリーセンター/カルロス・サンタマリア・センター・ライブラリ/エル・エスコリアル聖ロレンソ修道院図書館/コインブラ大学ジョアニナ図書館/アヴェイロ大学中央ず書館/新アレクサンドリア図書館/アル・バブタン中央図書館/コーラン図書館/ディヴィッド・サスーン図書館/中国国家図書館新館/籬苑書屋/中嶋記念図書館/武蔵野美術大学図書館/多摩美術大学八王子図書館/成蹊大学図書館/せんだいメディアテーク/金沢海みらい図書館/旧弘前市立図書館/北九州市立国際友好記念図書館/国際こども図書館/大阪市立中之島図書館/ビクトリア州立図書館/議会図書館/バンクーバー公共図書館中央館/ザンテユスタシユ図書館/イエール大学バイネヴキ貴重書・手稿図書館/ブルックリン中央図書館/ニューヨーク公立図書館スティーブン・A・シュワルツマン館/モルガン図書館&博物館/シカゴ公共図書館/アイオワ州法図書館/ジョンズ・ホプキンス大学ジョージ・ピーボタイ図書館/アメリカ議会図書館/ワシントン大学スザロ図書館/フランシス・A・グレゴリー図書館/ウ川アム・O・ロックリッジ・ベルヴュー図書館/ハロルド・ワシントン図書館/カンザス私立大学図書館/プリンストン大学ルイス科学図書館/デンバー公共図書館/シアトル公共図書館・中央館/リチャード・J・リオータン中央図書館/UCSDガイゼル図書館/フェニックスバートンバー中央図書館/サン・アントニオ公共図書館/フィリップス・エクセター大学図書館/ホセ・バスコンセロス図書館/パラフォシアナ図書館/スペイン図書館/王立ポルトガル文学館/図書館の歴史[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]【中古】 日本と世界の図書館を見てみよう 図書館のすべてがわかる本3/秋田喜代美【監修】,こどもくらぶ【編】 【中古】afb世界の図書館 その歴史と現在 (図書館・情報メディア双書) [ 寺田光孝 ]
2020.12.26
コメント(0)
-

義経伝説を作った男-義経ジンギスカン説を唱えた奇骨の人・小谷部全一郎伝(感想)
源義経は平安時代末期の武将で、鎌倉幕府の初代将軍・源頼朝は異母兄であり、河内源氏の源義朝の九男として生まれ、仮名は九郎、実名は義經です。 ”義経伝説を作った男-義経ジンギスカン説を唱えた奇骨の人・小谷部全一郎伝”(2005年11月 光人社刊 土井 全二郎著)を読みました。 いろいろある源義経にまつわる英雄伝説のうち、大陸に渡って成吉思汗=ジンギスカンになったという説について、その元となった小谷部全一郎の生涯とともに紹介しています。 義経は平治の乱で父が敗死したことにより鞍馬寺に預けられましたが、後に平泉へ下り、奥州藤原氏の当主・藤原秀衡の庇護を受けました。 兄・頼朝が平氏打倒の兵を挙げる治承・寿永の乱が起こるとそれに馳せ参じ、一ノ谷・屋島・壇ノ浦の合戦を経て平氏を滅ぼし、最大の功労者となりました。 その後、頼朝の許可を得ることなく官位を受けたことや、平氏との戦いにおける独断専行によって怒りを買い、このことに対し自立の動きを見せたため、頼朝と対立し朝敵とされました。 土井全二郎さんは1935年佐賀県生まれ、京都大学経済学部を卒業し、朝日新聞社に入社し、編集委員を務めました。 日本海洋調査会代表で、南極観測船、捕鯨母船に同乗しての現地取材をはじめ、超大型タンカー、コンテナ船、自動車運搬船、練習帆船、客船、フェリーなどの乗船取材にあたりました。 本書は、「ジンギスカンは源義経なり」という夢を追いかけ、常識に挑みつづけた希代のつむじ曲がりの破天荒な生涯に迫っています。 源義経は幼名を牛若、牛若丸といい、生まれて間もなく平治の乱で父義朝の死に見舞われ、母の常盤御前に連れられて放浪の旅に出ました。 平家の追及をかわすため京都・鞍馬寺に預けられたものの、16歳で元服し源九郎義経と称しました。 義朝の異母兄弟を含めて八番目の子どもでしたが、すでに叔父に当たる為朝が鎮西八郎を名乗っていたことから、遠慮して九郎としたといわれます。 鞍馬の山中で天狗相手に剣術修業を積み、京の五条大橋で武蔵坊弁慶をへこませて家来にしました。 兄の頼朝が兵を挙げるや、その傘下に馳せ参じ、木曽義仲相手の宇治川の戦いで勝利しました。 続いてさしもの権勢を誇った平家一門を、一の谷の戦いにおける鵯越えの逆落とし、屋島の奇襲、そして壇ノ浦の海戦で滅亡に追い込みました。 一連の戦いでは、宇治川の先陣争い、義経八艘飛び、那須与一の弓、敦盛最後など、数多くの合戦秘話が生まれています。 そうした大きな功績を挙げたものの、その後、兄頼朝との確執が深まって追われる身となり、現在の岩手県平泉へ落ち延びました。 ここで藤原一族にかくまわれたのですが、頼朝のたび重なる義経追捕の要求と脅しに屈した藤原泰衡の夜襲により、衣川の館で31歳で壮絶な最後を遂げたといわれます。 この若武者の華麗で英雄的な行動と、一転して迎えたあまりにも悲劇的な結末は、広く世の人びとの深い同情と共感の念を誘いました。 都落ちの道行きの過程で生まれたいくつもの逸話が、日本人好みの哀感あふれるエピソードを織り込んで長く語られることとなりました。 これは、鎌倉幕府が編纂した『吾妻鏡』や藤原兼実の日記などの官撰書に記載された正史に目を通しただけでは、決してうかがうことのできない物語でした。 義経の一代記を読み込んだ『義経記』(全8巻)はすでに14世紀には成立していたといわれます。 支配層である京の公家や武士階級とは全く縁のない、衆生によって歓迎され、語り継がれ、読み継がれてきました。 義経は時の朝廷から与えられた佐衛門少尉・検非違使の官職と、やがて「五位」の位に叙されたことから、大夫判官と呼ばれていました。 ここから、弱い立場の者が強権力に健気に立ち向かう姿に声援を送ることを「判官贔屓」といわれるようになりました。 伝説には、不死伝説、義経=ジンギスカン説ほかがあります。 不死伝説では、義経は衣川で死んでおらず、奥州からさらに北に逃げたのだといいます。 さらに、この伝説に基づいて、実際に義経は北方すなわち蝦夷地に逃れたとする主張を、「義経北方・北行伝説」と呼んでいます。 1799年に、この伝説に基づき蝦夷地のピラトリ、現・北海道沙流郡平取町に義経神社が創建されました。 しかし、この伝説を証明する考古学上の確証は、現在に至るまで一切提示されておらず、その伝説を信じたいとする域を出ていません。 義経=ジンギスカン説は、北行伝説の延長として幕末以降の近代に登場し、義経が蝦夷地から海を越えて大陸へ渡り、成吉思汗=ジンギスカンになったとします。 江戸時代に、清の乾隆帝の御文の中に「朕の先祖の姓は源、名は義経という。その祖は清和から出たので国号を清としたのだ」と書いてあったという噂がありました。 また、12世紀に栄えた金の将軍に、源義経というものがいたという噂もありました。 これらの噂は、江戸時代初期に沢田源内が発行した『金史別本』の日本語訳が発端であるといいます。 既に存在した、義経が大陸渡航し女真人=満州人になったという風説から、明治期になると義経がチンギス・カンになったという説が唱えられました。 明治時代に、末松謙澄がケンブリッジ大学の卒業論文で「大征服者成吉思汗は日本の英雄源義経と同一人物なり」という論文を書き、『義経再興記』として日本で和訳出版されブームとなりました。 大正時代に、アメリカに学び牧師となっていた小谷部全一郎は、北海道に移住してアイヌ問題に取り組んでいました。 アイヌの人々が信仰する文化の神・オキクルミの正体は義経であるという話を聞き、義経北行伝説の真相を明かすために大陸に渡って満州・モンゴルを旅行しました。 この調査で義経がチンギス・カンであったことを確信し、1924年に著書『成吉思汗ハ源義經也』を出版しました。 この本は判官贔屓の民衆の心を掴んで大ベストセラーとなり、現代の日本で義経=ジンギスカン説が知られているのは、この本がベストセラーになったことによります。 小谷部全一郎は1868年に母親の実家の秋田市寺町生まれ、父親は秋田藩の菓子御用商で秋田市上肴町に在住でした。 兄弟は不明で、戦国時代の武将・白鳥家の子孫だとしています。 1880年に上京して、本郷の原町要義塾で漢学・英学・数学を学びました。 このころ、末松謙澄の『義経再興記』、原題は『偉大ナ征服者成吉思汗ハ日本ノ英雄義経ト同一人物也』を読んで、影響を受けたといいます。 この本の種本は江戸時代末期、オランダ商館医員のドイツ人医学者シーボルトが著した『日本』であり、義経は平泉では死なず、蝦夷に渡り、大陸へ行ったとされています。 1885年に北海道にわたりアイヌと出会い、アイヌを支援する宣教師に感激し、牧師の仕事を目指そうと思ったとされます。 父親の任地である会津から、できるだけ陸路でシベリアから渡米しようと計画し、北海道、択捉島、シベリアに渡りましたが、そこで日本に送還されました。 1888年に神戸から貨物船のカナダ国籍の帆船でアメリカへ旅立ち、皿洗い、コック、農業労働などを続けて生活費と学費を稼びました。 1年後ハンプトン実業学校、現、バージニア大学に入学し、1890年にハワード大学、現、ワシントン大学神学部に入学しました。 1894年に卒業し、イエール大学神学部へ学士入学し、1895年に卒業し神学士となりました。 ハワイ布教を経て、1898年に横浜へ帰国し、横浜の紅葉坂教会で牧師を勤めていました。 在米中に見聞した先住民教育に感銘を受け、星亨駐米大使にアイヌの救済・学校教育の請願を行い、坪井正五郎が宣伝していた北海道旧土人教育会の主唱者の一人となりました。 北海道にて教育者、牧師となり虻田学園を創立しましたが、学童減少や、資金難、有珠山爆発などにより休校となりました。 1919年に満州・シベリアに日本陸軍の通訳官として赴任し、このときジンギスカン=義経の痕跡を調べるべく、満州・シベリアを精力的に取材しました。 1920年に帰国し、軍功により勲六等旭日章を授与され、陸軍省は小谷部を嘱託として遇し、佐官待遇相当の陸軍大学校教授に招聘しようとしました。 小谷部はこれを辞退して著作活動に専念し、1923年に『成吉思汗ハ源義経也』が完成しました。 元の題名は『満蒙踏査・義経復興記』で、再版10回を越える大ヒットとなりました。 しかし、翌年、成吉思汗は源義経にあらずと、歴史学・人類学・考古学の各学者反発意見をずらりと並べられいっせいに猛反論されました。 以降、この本に刺激・触発されて、さまざまな論議が交わされ、語られ、あるいは新説・新解釈が出されるようになりました。 現代になってもなお、「義経=成古思汗」をテーマとした類書が数多く出版されています。 アメリカの最高学府で学んだほどの男が、なぜこのような一見突拍子もない説を唱えるに至ったのでしょうか、なにを訴えたかったのしょうか。 これは、明治、大正、昭和と、ものの見方が極端に振れた時代にあって、何といわれようと己の信念と甲斐性を頼りに、金にも地位にも名誉にも背を向け、真一文字に駆け抜けた男の物語です。序論 源義経の謎/第1章 義経と日本人/第2章 小谷部全一郎がゆく/第3章 語り継がれる北行伝説/第4章 そしてアメリカへ/第5章 アイヌ教育に九年/第6章 満州をゆく/第7章 「成吉思汗ハ源義経也」/付 義経北行伝説ルート[http://lifestyle.blogmura.com/comf rtlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]義経北行伝説義経はジンギスカンになったか【電子書籍】[ 黒沢賢一 ]【中古】 成吉思汗ハ源義経也 小谷部全一郎 【古本・古書】
2020.12.19
コメント(0)
-

神社で拍手を打つな! 日本の「しきたり」のウソ・ホント(感想)
神社に掲げられる二礼二拍手一礼は伝統的な作法ではない、初詣は鉄道会社の営業戦略だった、といいます。 郊外の墓参りはバブルが生んだ年中行事である、結婚式のご祝儀もお葬式の半返しも伝統ではない、そもそもクリスマスはキリスト教に関係がない、ともいいます。 ”神社で拍手を打つな! 日本の「しきたり」のウソ・ホント”(2019年11月 中央公論新社刊 島田 裕巳著)を読みました。 日本人がしきたりと思っている行事にはごく最近生み出されたものが少なくなく、私たちはいろいろなしきたりとどう向き合えばいいのかを示唆しています。 島田裕巳さんは1953年東京都生まれ、1976年東京大学文学部宗教学宗教史学専修課程卒業、同大学大学院人文科学研究科修士課程修了、1984年同博士課程満期退学(宗教学専攻)しました。 放送教育開発センター助教授、日本女子大学助教授を経て、1995年に教授に昇任しましたが同年に退職しました。 2005年から2008年まで東京大学先端科学技術研究センター特任研究員、2006年より中央大学法学部兼任講師となりました。 2008年より東京大学先端科学技術センター客員研究員、2013年より東京女子大学現代教養学部人文学科非常勤講師となりました。 現在、宗教学者、作家、劇作家、東京女子大学非常勤講師、NPO法人葬送の自由をすすめる会会長として活躍しています。 拍手=かしわでは神道の祭祀や神社・神棚など神に拝する際に行う行為で、柏手と書かれることもありますが誤りです。 かしわでという呼称は、拍の字を柏と見誤った、あるいは混同したためというのが通説です。 神道は古代日本に起源をたどることができるとされる宗教で、伝統的な民俗信仰・自然信仰・祖霊信仰を基盤に、豪族層による中央や地方の政治体制と関連しながら徐々に成立しました。 持統紀に、即位した新天皇に群臣が拝礼と拍手をした記載があり、初めて天皇を神に見立てる儀礼として即位式に柏手が取り入れられ、定例化したとされます。 奈良時代には、天皇の即位宣命が読み上げられた後、参列した百官が拍手で応えたそうです。 これはひざまずいて32回も手を打つという形式で、現代の立って行う形式とは異なっていました。 799年の元日朝賀に渤海使が参列していて、天皇を四度拝むのを二度に減らし、拍手もしなかったということです。 神道には確定した教祖、創始者はなく、公式に定められた正典も存在しません。森羅万象に神が宿ると考え、また偉大な祖先を神格化し、天津神・国津神などの祖霊をまつり、祭祀を重視します。 神社は日本固有の宗教である神道の信仰に基づく祭祀施設で、産土神、天神地祇、皇室や氏族の祖神、偉人や義士などの霊などが神として祀られています。 一般的にみられる神棚は小型の神社を摸した宮形の中に、神宮大麻や氏神札、崇敬神社の神札を入れるものです。 これは札宮といい、狭義にはこれを神棚と呼び、神職の家などの神葬祭を行う家には、祖先の霊をまつるための神棚があります。 他に、神札よりも神の依り代としての意味合いが強い御神体をまつる神棚もあります。 拍手は両手を合わせ左右に開いた後に再び合わせる行為を指し、通常、手を再び合わせる際に音を出します。 音を出す理由は、神への感謝や喜びを表すため、願いをかなえるために神を呼び出すため、邪気を祓うためといわれています。 両手を合わせる際に指先まで合わせる作法と、意図的にずらす作法があります。 ずらす作法にも、途中からずらす作法と、最初から最後までずらしたままの作法があります。 また、神葬祭や慰霊祭などにおいては音を控えめにする作法もあり、音を控えめにするのは儀式の静粛さを損なわせないためなどと説明されています。 神社で行われる参拝作法の再拝二拍手一拝など、3回以下のものは短拍手・短手と呼ばれ、出雲大社、宇佐八幡、弥彦神社の4回、伊勢神宮の8回など、4回以上手を打つものは長拍手・長手と呼ばれます。 他に、8回打った後に再度短拍手を1回打つ八開手もあります。 神葬祭で音を微かに打つ偲手・忍手・短手や、直会で盃を受けるときに一回打つ礼手などもあります。 明治維新前は神仏習合の影響が大きく、拝礼の作法は地域によりさまざまで、手を合わせて祈る、三拍手、四拍手などがありました。 明治8年に式部寮から頒布された神社祭式に、再拝拍手と記されたことから、統一化の動きが始まりました。 現在の「二礼二拍手一礼、再拝二拍手一拝」は、明治40年に神社祭式行事作法が制定され、その中でひとつの作法が定義されたものです。 昭和17年に内務省神祇院教務局祭務課が編集した神社祭式行事作法に、「再拝、二拍手、一揖、拍手の数を二とす」と記載され、昭和18年1月1日より施行されました。 しきたりとは、一般には昔から行われてきたならわしとして考えられています。 昔から受け継がれてきた伝統だから、それに従うべきだというわけです。 しかし、しきたりのなかには新たに生み出されたものが少なくありません。 とくに最近では、商売として商業資本の手によって導入された新たなしきたりが広まっています。 一方で、社会が変化することで、古くからのしきたりは意味を失ったり実行することが難しくなっていたりします。 しきたりは栄枯盛衰をくり返しますので、新陳代謝が伴うのです。 そのことを踏まえるなら、私たちはしきたりに接するとき、それが本当に昔から続けられてきたのかを考える必要があります。 あるいは、そのしきたりに従うことに意味があるのかを検討してみる必要があります。 神社で拍手を打たないということは、その一歩になります。 拍手を打たない場合、必要なのは神に対して礼拝をする手段として、いったいどういう方法があるのかを考えることです。 二礼二柏手一礼だと、そこには、神に対して祈る時間が含まれず、ただ神を崇めるだけで終わってしまいます。 果たして私たちはそれで満足できるのでしょうか、と言っています。 もっとこころを込めて神に祈る時間が必要だと思えてきたら、どうしたやり方をとればいいのでしょうか。 神社には、「二礼二拍手一礼」を勧める掲示がなされていたりして、テレビ番組でも、このやり方が正式な参拝の仕方だと紹介されることが多いです。 しかし、神社の掲示にも、テレビ番組でも、なぜ二礼二拍手一礼でなければならないのかという根拠は示されていません。 礼拝の仕方を神が定めることはあり得ませんので、あくまで人間が定めたしきたりです。 神社界の組織として神社本庁があり、すべての神社ではありませんが、多くの神社はこの神社本庁の傘下にあります。 神社本庁のホームページの参拝方法という項目を見ると、永い間の変遷を経て現在、「二拝二拍手一拝」の作法がその基本形となっていますと記されています。 二礼二拍手一礼ではなく二拝二拍手一拝となっていますが、意味は同じです。 なぜそうした作法が基本形になったのか、その経緯は説明されていませんし、根拠も示されていません。 教えを説く存在がいない神道の世界では、どんなことについても、経緯、背景、根拠を明確に説明することができません。 そのため、しきたりについての説明は自ずと曖昧なものになってしまうのです。 しきたりは、その背景にある宗教の世界、信仰の世界の成り立ちを明らかにしていくための鍵になります。 しきたりにただ従うのではなく、そうしたところまで考察を深めることが重要なのです。 しきたりは、私たちの生活のあり方と密接に結びついています。 その点では、しきたりを見直すことは、私たちの生活をこれまでとは違った角度から見ていくことにつながります。 そして、しきたりの変遷には、私たちが経てきた歴史ということがかかわっています。 いったい、現在の社会において、どういったしきたりが求められるのでしょうか。 そのあり方はどうあるべきかについて、考えなければならないことは多岐に及びます。 この本をきっかけに、読者がしきたりの世界について考えてくれるようになれば、著者としてこれほど嬉しいことはありませんという。1章 神社で拍手は打つな/2章 初詣は鉄道会社の発明/3章 マイカーが生んだ墓参り/4章 結婚式に祝儀など持っていかなかった/5章 どう考えても無駄な半返し/6章 クリスマスはキリスト教の行事じゃない/7章 ハロウィンの起源は江戸時代の花見/8章 商業資本としきたり/9章 怪しげなしきたりに踊らされてどうする[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]御朱印帳 カバー付 送料無料 蛇腹 40ページ 四季草花文 紺 送料込み (※メール便のみ 送料無料)| 朱印帳 カバー おしゃれ かわいい かっこいい お寺 神社| 朱印帳 カバー おしゃれ かわいい かっこいい お寺 神社御朱印帳 カバー付 送料無料 和綴じ 60ページ 雁皮紙使用 ブック式 四季彩爛漫 生成 (※メール便のみ 送料無料)
2020.12.12
コメント(0)
-

細川忠利 ポスト戦国世代の国づくり(感想)
細川忠利は1586年に細川忠興の三男として生まれ、母は明智光秀の娘・玉子=細川ガラシャで、幼名は光千代、始め長岡姓を称しましたが、1600年に徳川家康の命で細川へ復姓し、細川内記を名乗りました。 ”細川忠利 ポスト戦国世代の国づくり”(2018年8月 吉川弘文館刊 稲葉 継陽著)を読みました。 戦国武将細川忠興を父と仰ぎ明智光秀を祖父に持つ、細川家熊本藩初代藩主の細川忠利の国づくりのあり方と、ポスト戦国世代の生き方を紹介しています。 幼少時は病弱だったため玉子がキリスト教の洗礼を受けさせたともいわれています。 江戸幕府と豊臣家との間で行われた合戦である大坂の陣に徳川方として参戦し、1620年に豊前小倉藩藩主細川家二代、1632年に肥後熊本へ転封になり、熊本藩主細川家初代となりました。 稲葉継陽さんは1967年栃木県生まれ、1990年に立教大学文学部史学科を卒業し、1996年に同大学院文学研究科博士課程退学しました。 2000年に熊本大学文学部助教授、2007年に准教授となり、2009年に永青文庫研究センター教授となりました。 博士(文学)で、専門は日本中世史・近世史(荘園制研究、村落研究、地域社会論、領国支配=初期藩政研究、細川家文書の研究)です。 細川ガラシャを母に持つ忠利は、いわばポスト戦国世代でした。 戦国武将を父と仰ぐ忠利の世代は、戦国動乱から天下泰平の確立へ転換する最大の変革期の渦中で育ち、統治者としての自己を形成しました。 忠利による国づくりのあり方を通して、この重要な時代の特質を理解するのが本書のテーマです。 世子だった長兄の忠隆が1600年の美濃国不破郡関ヶ原を主戦場として行われた、天下分け目の関ヶ原の戦いの後に廃嫡されました。 すると忠利が江戸に人質に出されて、二代将軍徳川秀忠の信頼を得ていた忠利が1604年に世子となりました。 次兄の興秋は、弟の家督相続の決定に不満を持ち、翌年の1605年に細川家を出奔しました。 1608年に小笠原秀政と登久姫の次女で徳川秀忠の養女の千代姫(保寿院)と縁組し、千代姫は1609年に豊前国中津城に輿入れしました。 本能寺の変は明智光秀が織田信長を討ったことで知られていますが、忠利と保寿院の婚姻と光尚の誕生で本能寺の変で仇敵となった明智氏と織田氏の家系が合体し、縁戚関係に発展しました。 1619年に長男光利が誕生し、1620年に父から家督を譲られて小倉藩主となりました。 1622年に、かつて出奔して大坂城に入城し、大坂の陣を大坂方として戦い、戦後浪人となっていた米田是季を帰参させ、のちに家老にしました。 1632年に肥後熊本藩の加藤忠広が改易されたため、その跡を受けて小倉から熊本54万石に加増移封され、後任の小倉城主には忠利の義兄弟である小笠原忠真が就任しました。 忠利は熊本藩の初代藩主となり、父・忠興は隠居所として八代城に住みました。 1637年の島原の乱は江戸時代初期に起こった日本の歴史上最大規模の一揆で、幕末以前では最後の本格的な内戦ですが、忠利はこの乱に参陣して武功を挙げました。 かつての一向一揆のように一揆が拡大長期化すれば、外交窓口として最も重要な直轄地である長崎をはじめ九州の支配はおぼっかなくなります。 そうした事態を防ぐために大規模な軍事動員を行い、社会を戦国乱世の状況に逆戻りさせてはならないという認識があったのでしょう。 わけても、幕府中枢の権力から離れた遠国である九州での国づくりを担当した忠利の任務の重みは、特筆すべきものでした。 江戸時代初期の大名家にとって、土一揆の戦国時代はいまだ遠い過去ではありませんでした。 武士領主と百姓とが互いの武力行使を抑制しながら、支配をめぐるぎりぎりの交渉を続け、その限りで土一揆の凍結が維持されました。 戦国の一揆の世に歴史を逆戻りさせてはならないと、エリート忠利が統治者としての自己を実現していきました。 忠利は村々が核となって形成されていた地域社会と向き合い、実践から得られた経験を蓄積していかねばなりませんでした。 社会の現実や百姓の政治意識、さらに政治的意思を無視した支配者、あるいは公私の区別をつけることができない支配者に、ポスト戦国世代の体制づくりは不可能でした。 忠利の祖父は細川藤孝(幽斎)と明智光秀であり、忠利こそポスト戦国世代のサラブレット々と呼ぶにふさわしいのです。 幽斎は初め室町幕府13代将軍・足利義輝に仕え、その死後は織田信長の協力を得て15代将軍・足利義昭の擁立に尽力しました。 後に義昭が信長に敵対して京都を逐われると、信長に従って名字を長岡に改め、丹後国宮津11万石の大名となりました。 本能寺の変の後、信長の死に殉じて剃髪して家督を忠興に譲りましたが、その後も豊臣秀吉、徳川家康に仕えて重用され、近世大名肥後細川家の礎となりました。 光秀は初め越前の朝倉義景に仕え、足利義昭が朝倉氏のもとに流寓したとき出仕し、ついで織田信長の家臣となりました。 義昭の上洛に尽力し、義昭と信長に両属して申次を務め、京都の施政にも関与しました。 室町幕府滅亡後は信長に登用され征服戦に参加、1571年に近江坂本城主となり、1575年に丹波の攻略に着手し、1579年に八上城の波多野秀治らを下して平定しました。 1580年に亀山城主となり、ついで細川幽斎、筒井順慶、中川・高山諸氏を与力として付属され、京都の東西の要衝を掌握し、美濃・近江・丹波の諸侍や幕府旧臣を中核とする家臣団を形成しました。 天下泰平は、国郡境目相論とともに土一揆を長期凍結させることによって実現されました。 その画期となったのは、大名家と百姓の武力行使と武装権や公訴権を対象とした豊臣政権の一連の政策でした。 本書の主人公忠利は秀吉・家康の次の世代で、天下泰平の確立を担った大名を代表する人物です。 武士領主による新しい地域統治のあり方を体系化して安定させ、それを基礎にした政治秩序を立ち上げて、天下泰平のかたちを確立することを目指しました。 そうして戦国の動乱へと歴史を決して逆行させないことが、忠利らポスト戦国世代の歴史的な使命でした。 忠利の、細川家当主だった1621年から1641年までの約20年間の実践は、諸大名を代表する統治者として、自己を鍛え上げる過程でした。 そして、1641年に父に先立って享年55歳で死去し、長男の光利が跡を継ぎました。 200年間以上も維持された天下泰平は、日本の民間社会を成熟させ、同時代の世界史上でも稀な江戸時代の長期平和の期間でした。 じつはこれが日本社会の成熟を実現させる条件となり、したがって近代日本のあり方を決定づけたのではないでしょうか。 こうした観点で年表を見れば、江戸時代の歴史が鎌倉幕府成立期から戦国動乱にいたるまでの、いわば戦争の中世を克服した地点に成立し、そして長期維持された、平和の歴史であった事実に気づくでしょう。 長期に及んだ天下泰平は、技術・経済・教育・思想などの諸分野で、民間社会の成熟をもたらし、その後の日本とアジアの歴史に大きな影響を与えました。 江戸時代の平和状態がいかにして長期維持されたのか、その秘密にあらゆる角度からせまることは、現在、日本史研究における最も重要なテーマの一つとなっています。ポスト戦国世代とは―プロローグ/波乱の家督相続と国づくり(誕生から家督相続へ/国づくりのはじまり―代替りの改革)/豊前・豊後での奮闘 国主としての試練(三斎・忠利父子の葛藤/百姓・地域社会と忠利/寛永の大旱魃と領国・家中)/肥後熊本での実践 統治者としての成熟(熊本への転封と地域復興/肥後における統治の成熟/「私なき」支配から「天下」論へ)/細川家「御国家」の確立 「天下泰平」のもとで(島原・天草一揆と「天下泰平」/忠利の死と熊本藩「御国家」)/「天下泰平」と忠利―エピローグ[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]細川忠利 ポスト戦国世代の国づくり (近世史) [ 稲葉 継陽 ]【中古】細川忠利宛行状
2020.12.05
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1