テーマ: 政治について(19770)
カテゴリ: 政治
昨日の読売新聞に、
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6451564
Twitterによるデモは、
少数のアカウントによる投稿が、
不当に増幅されることで成立している面がある。
たとえば、
〔安倍晋三国葬反対〕のような左派の主張であれ、
〔外国人生活保護反対〕のような右派の主張であれ、
同様の仕組みで数が増幅されている。
世論調査などとの比較が必要ですが、
ラウドマイノリティの主張が不当に増幅されれば、
実数的な世論とは異なる「世論」が社会的な力をもちかねない。
◇
Twitter は、
「ツイート数」「いいね数」「リツイート数」「フォロワー数」など、
事実上、数の多さが影響力を発揮しやすいメディアですが、
じつは複数アカウントや自動投稿が容易なので、
まったくその信頼性が担保されていません。
大量のスパムアカウントによる同一文面の頻繁な投稿に出くわします。
したがって、
Twitter のようなメディアを、
◇
このような《数の偽装》の問題は、
インターネットの普及当初から存在しており、
「2ちゃんねる」などにも見られましたが、
それは改善するどころか、むしろ悪化しています。
技術的なアドバンテージをもつ人が、
数を偽装して権力を発揮しようとするのですね。
あるいは、
システムをコントロールする立場の人間が、
アルゴリズム変更などの操作をしたりもする。
やがて一般のユーザーまでが、
数の論理に巻き込まれて党派的な動きしかしなくなり、
全体が無内容なコミュニケーションに陥っていきます。
◇
このような《数の偽装》を取り締まるには、
複数アカウントを規制するなどの方法もありえますが、
より本質的に求められるのは、
そもそも「数の論理」が意味をなさないようなメディアの設計です。
そうすることで、数を偽装する動機じたいが失われる。
◇
もともと民主制において「多数決」は最終手段でしかありません。
数の論理に頼るべきなのは、
あくまで判断の最終局面においてであり、
むしろ重要なのは、
そこへ至るまでの「熟慮」や「熟議」の過程です。
にもかかわらず、
現在のネットメディアの中には、
個人的な「熟慮」や社会的な「熟議」を促す場がありません。
その意味では、直接民主制を実現する環境がぜんぜん育っていない。
◇
たんに多数決を取るだけなら、
従来どおりの選挙や世論調査などでも十分です。
あえて、それをネット上でやるのなら、
一般的なネットメディアで使うアカウントではなく、
たとえばマイナンバーのように、
数の偽装が不可能なシステムを用いなければなりません。
むしろ、
SNSなどのネットメディアに期待すべきなのは、
「多数決」ではなく「熟議」の場としての機能です。
それこそが直接民主制への可能性を開くのだから。
◇
個人的な「熟慮」にしろ、社会的な「熟議」にしろ、
それをおこなうには、つねに二項対立的な思考が必要です。
つまり、
「一方的な趨勢」や「同調的な空気」に流されず、
対立する立場があることを前提のうえで、
たがいを比較しながら検討を深めなければならない。
しかし、
現在のSNSなどの論調は、
「趨勢」や「空気」のような数の力に流されがちで、
ろくに内容の吟味や検討がないまま、
全体の主張が一方の極へと容易に振れてしまうのです。
◇
かりに、
ネット掲示板などで政治的な「熟議」を促すとすれば、
ひとつのトピックに対して、
すくなくとも「Yes」「No」などの2つのスレッドが必要です。
そうすることで、
数の多さや趨勢に流されることなく、
つねに自分の立場を維持しながら意見を述べることができるし、
同時に、対立しあう立場の意見を比較しながら、
その妥当性を吟味して、判断の是非を検討することができる。
◇
このような「熟議」の場において、
それぞれの意見の重要度は、
たんに「賛同数」などで測られるべきではありません。
たとえば科学論文などと同じように、
「引用数」や「参照数」などで計量することもできるはずだし、
あるいは、意見のオリジナリティの度合いを、
使用語彙などから、AIで判定することも可能かもしれません。
◇
インターネット上に、
こうした「熟議」の場を形成することができれば、
それは直接民主制の可能性を開くことになります。
すなわち、
議会や司法や行政判断などの場に、
市民が直接参加する機会を作り出すことになる。
のみならず、
科学研究など専門性の高い議論にも、
一般市民への門戸を開くことになるはずだし、
それによって学会の閉鎖性などを解くことにもなるはずです。
◇
このような「熟議」の場は、
民間の事業として設計・運営されるよりも、
公共的な機関によって設計・運営されるほうが妥当です。
それが直接民主制を可能にするのなら、公的な意義もあります。
たとえば、
NHKプラスのアカウントなどは、
世帯ごとに1つと限定されていて数の偽装がしにくく、
もともと世論をはかるメディアとしての前提も備わっている。
公的な判断にかかわるトピックだけでなく、
一般的な関心の高い三面記事のような時事ネタについても、
市民の「熟慮」や「熟議」を促す場が存在することで、
無用な炎上や、デマの拡散や、
偽装的なデモ行為などを抑制することが期待できます。



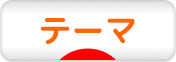
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6451564
Twitterによるデモは、
少数のアカウントによる投稿が、
不当に増幅されることで成立している面がある。
たとえば、
〔安倍晋三国葬反対〕のような左派の主張であれ、
〔外国人生活保護反対〕のような右派の主張であれ、
同様の仕組みで数が増幅されている。
世論調査などとの比較が必要ですが、
ラウドマイノリティの主張が不当に増幅されれば、
実数的な世論とは異なる「世論」が社会的な力をもちかねない。
◇
Twitter は、
「ツイート数」「いいね数」「リツイート数」「フォロワー数」など、
事実上、数の多さが影響力を発揮しやすいメディアですが、
じつは複数アカウントや自動投稿が容易なので、
まったくその信頼性が担保されていません。
大量のスパムアカウントによる同一文面の頻繁な投稿に出くわします。
したがって、
Twitter のようなメディアを、
◇
このような《数の偽装》の問題は、
インターネットの普及当初から存在しており、
「2ちゃんねる」などにも見られましたが、
それは改善するどころか、むしろ悪化しています。
技術的なアドバンテージをもつ人が、
数を偽装して権力を発揮しようとするのですね。
あるいは、
システムをコントロールする立場の人間が、
アルゴリズム変更などの操作をしたりもする。
やがて一般のユーザーまでが、
数の論理に巻き込まれて党派的な動きしかしなくなり、
全体が無内容なコミュニケーションに陥っていきます。
◇
このような《数の偽装》を取り締まるには、
複数アカウントを規制するなどの方法もありえますが、
より本質的に求められるのは、
そもそも「数の論理」が意味をなさないようなメディアの設計です。
そうすることで、数を偽装する動機じたいが失われる。
◇
もともと民主制において「多数決」は最終手段でしかありません。
数の論理に頼るべきなのは、
あくまで判断の最終局面においてであり、
むしろ重要なのは、
そこへ至るまでの「熟慮」や「熟議」の過程です。
にもかかわらず、
現在のネットメディアの中には、
個人的な「熟慮」や社会的な「熟議」を促す場がありません。
その意味では、直接民主制を実現する環境がぜんぜん育っていない。
◇
たんに多数決を取るだけなら、
従来どおりの選挙や世論調査などでも十分です。
あえて、それをネット上でやるのなら、
一般的なネットメディアで使うアカウントではなく、
たとえばマイナンバーのように、
数の偽装が不可能なシステムを用いなければなりません。
むしろ、
SNSなどのネットメディアに期待すべきなのは、
「多数決」ではなく「熟議」の場としての機能です。
それこそが直接民主制への可能性を開くのだから。
◇
個人的な「熟慮」にしろ、社会的な「熟議」にしろ、
それをおこなうには、つねに二項対立的な思考が必要です。
つまり、
「一方的な趨勢」や「同調的な空気」に流されず、
対立する立場があることを前提のうえで、
たがいを比較しながら検討を深めなければならない。
しかし、
現在のSNSなどの論調は、
「趨勢」や「空気」のような数の力に流されがちで、
ろくに内容の吟味や検討がないまま、
全体の主張が一方の極へと容易に振れてしまうのです。
◇
かりに、
ネット掲示板などで政治的な「熟議」を促すとすれば、
ひとつのトピックに対して、
すくなくとも「Yes」「No」などの2つのスレッドが必要です。
そうすることで、
数の多さや趨勢に流されることなく、
つねに自分の立場を維持しながら意見を述べることができるし、
同時に、対立しあう立場の意見を比較しながら、
その妥当性を吟味して、判断の是非を検討することができる。
◇
このような「熟議」の場において、
それぞれの意見の重要度は、
たんに「賛同数」などで測られるべきではありません。
たとえば科学論文などと同じように、
「引用数」や「参照数」などで計量することもできるはずだし、
あるいは、意見のオリジナリティの度合いを、
使用語彙などから、AIで判定することも可能かもしれません。
◇
インターネット上に、
こうした「熟議」の場を形成することができれば、
それは直接民主制の可能性を開くことになります。
すなわち、
議会や司法や行政判断などの場に、
市民が直接参加する機会を作り出すことになる。
のみならず、
科学研究など専門性の高い議論にも、
一般市民への門戸を開くことになるはずだし、
それによって学会の閉鎖性などを解くことにもなるはずです。
◇
このような「熟議」の場は、
民間の事業として設計・運営されるよりも、
公共的な機関によって設計・運営されるほうが妥当です。
それが直接民主制を可能にするのなら、公的な意義もあります。
たとえば、
NHKプラスのアカウントなどは、
世帯ごとに1つと限定されていて数の偽装がしにくく、
もともと世論をはかるメディアとしての前提も備わっている。
公的な判断にかかわるトピックだけでなく、
一般的な関心の高い三面記事のような時事ネタについても、
市民の「熟慮」や「熟議」を促す場が存在することで、
無用な炎上や、デマの拡散や、
偽装的なデモ行為などを抑制することが期待できます。


お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023.01.26 22:46:19
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ
政治
(209)ドラマレビュー!
(296)メディアトピック
(37)Re:リベンジ~ゆりあ先生~Dr.チョコレート!
(19)プレバト俳句を添削ごと査定?!
(187)映画・音楽・アート
(71)漫画・アニメ
(18)鬼滅の刃と日本の歴史。
(27)岸辺露伴と小泉八雲。
(19)NHKよるドラ&ドラマ10
(19)NHK大河ドラマ
(18)アストリッドとラファエルの背景を考察。
(8)アンという名の少女の感想・あらすじネタバレ。
(31)東宝シンデレラ
(62)恋つづ~ボス恋~カムカム!
(48)ぎぼむす~ちむどん~パリピ孔明!
(38)わたどう~ウチカレ~らんまん!
(62)トリリオン~ONE DAY!
(16)警視庁・捜査一課長 真相ネタバレ!
(12)「エルピス」の考察と分析。
(10)「Destiny」&「最愛」ネタバレ考察。
(20)大豆田とわ子を分析・考察!
(10)大森美香の脚本作品。
(10)北斎と葛飾応為の画風。
(13)不機嫌なジーン
(13)風のハルカ
(28)純情きらりとエール
(30)宮崎あおいちゃん
(18)スポーツも見てる!
(29)逃げ恥~けもなれ!
(24)スカーレット!
(13)シロクロ!
(13)ギルティ!
(9)家政夫ナギサさん
(6)半沢直樹!
(5)探偵ドラマ!
(7)倉光泰子
(4)パワハラ
(7)ドミトリー
(37)ゴミ税
(3)その他。
(1)夢日記
(4)© Rakuten Group, Inc.









