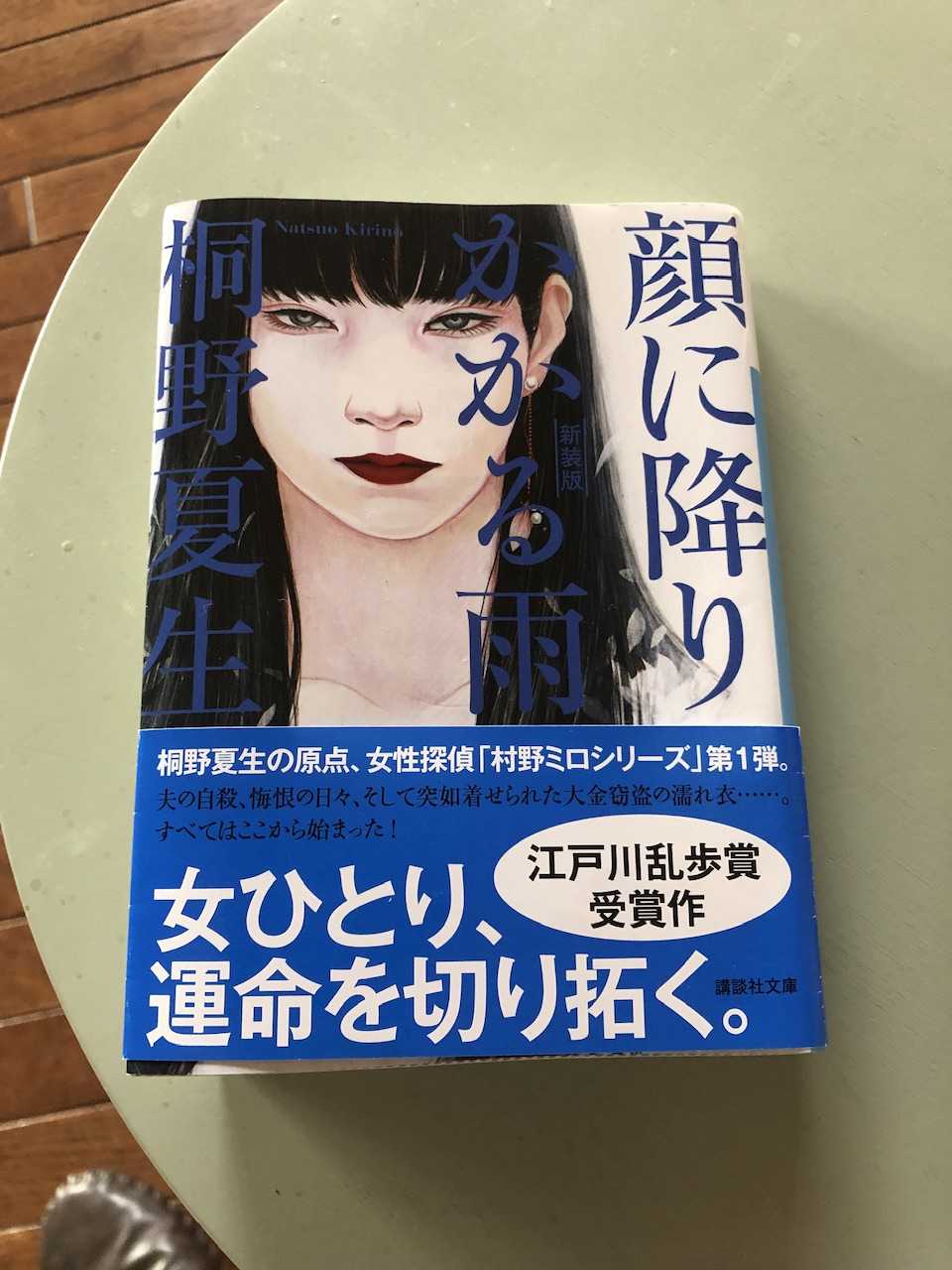2006年08月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-
笛吹けど、踊らず
ある教会の長老といわれる老年の女性が、冬が近くなったので、礼拝堂のストーブを取り付けました。一人で仕事をしたので、煙突が曲がってしまったけれど、彼女は満足でした。 日曜日の礼拝でそれを見た男性が「煙突が曲がっているじゃないか。誰がつけたんだ。」と笑ったそうです。 ある日彼女が礼拝堂のお掃除をしているところに、一人の女性信者が来合わせました。 その女性がお掃除を手伝ったのかどうかは、分かりません。 しかし水曜日の祈り会で「当番制にして、みんなで礼拝堂のお掃除をしましょう」と、提案したそうです。 ところが出席者は一様にそれに賛成することなく、かの老婦人までが同意してくれなかったことに、大いに不満だったとか。 老婦人はご自分が好きでしていることであって、それを気の進まない人たちにまで押し付けるのは本意でないばかりか、迷惑だったのだと思います。「笛を吹いたのに、踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに、悲しんでくれなかった。」マタイ11:17
August 27, 2006
-
「ぶどう園の労働者」のたとえ
35歳から水泳を始めた57歳の女性がいます。持久力、瞬発力、スピード、そのどれも高レベルなのです。教室の若いコーチに話しますと「もう22年泳いでることになりますね。すごいな、ぼくより長いや。」と、笑います。「先生はおいくつから始められたんですか?」「3歳からですから、19年かな。」「このように、後にいる者が先になり、先にいる者が後になる」マタイ20:16聖書のことばは矛盾しているようでいて、じつに現実的だと思います。
August 26, 2006
-
予感
水泳を習い始めて、もうじき2年になります。 5年ほど前、神戸のホテルに宿泊したとき、プールで優雅に泳ぐおばあさんを見ました。天井のガラス窓から入る暖かい日差しの中で、ゆったりとしたリズムで自分の泳ぎを楽しんでいる姿に、私の中でひらめくものがあったのです。 それからしばらくは仕事の都合で動きがとれずにいましたが、一昨年の10月に一大決心をしてフィットネス・クラブに入会し、「水に顔をつけられない人」のための「入門クラス」を受講することにしました。 水に浮かんだり、沈んでみたり、ビート板でのバタ足練習など、まずは水に慣れるための教室で、私はここに半年もいることになりました。 その後25mクラスに昇進しましたが、息継ぎの練習に、ほぼ毎日2時間は水に浸かっていた甲斐あって、翌年の、忘れもしない5月13日、めでたく息継ぎができるようになりました。このときの達成感と喜びには、忘れがたいものがあります。 それからはメキメキと上達するのを感じ、泳ぐのが楽しくてたまらなくなりました。 ゆっくりでしたがクロールで30分間泳ぎ続けることができるようになりましたし、平泳ぎは何の苦もなくマスターできました。 ところが、ところがです。 この期に及んで、バタフライに、苦戦を強いられているのです。 今年3月でフィットネス・クラブをやめ、4月から公認プールでの教室とサークルに入会しましたが、最近そこで、とてもすてきにバタフライを泳ぐ女性に出会いました。 するりとイルカ・ジャンプして、優雅に水中へもぐりこむ姿に、「私も、あんなふうに泳ぎたい!」と思いました。それで彼女にどんな練習をしたらいいのかを尋ね、ひたすらそれを続けた結果、まだ完全にバタフライは泳げないものの、なんだか掴みつつあるのを感じています。 バタフライは他の3泳法とはちがう、水の中での伸び伸びとした、なんともいえない動きがあります。それはまさに飛び魚になったような自由さで、水中と空中の二つの空間を自由に行き来しながら、水中では大きくうねって進むあの優雅な動きに、バタフライが完璧にできるようになったとき、私は4泳法の中で一番好きになる・・・そんな予感がして嬉しくなるのです。
August 24, 2006
-
しな布の日傘
もう何年前になるでしょうか。 百貨店の「全国職人の技展」で、上品な織りの日傘を見つけて、そのうつくしさの虜になりました。 これはシナノキという木の皮を剥いで晒し、繊維のように細くしたものを織った布で作られた「しな布」というものなのだそうです。 ぱりっとした張りのある硬い感じの織物で、その織り目から向こう側が透けて見えるところがすてきだと思いました。さらに使ってみて分かったことは、風の強い日にはその粗い織り目から風がぬけてくれるので、日傘があおられず、とても使い心地がいいのです。木の持ち手も軽くて手触りがよく、とても気に入っています。 でもこれを手に入れるために、私は一年辛抱しなくてはなりませんでした。値段が高かったのです。 それで百貨店の積み立てをして、翌年の開催を待って買い求めました。 色は二色あって、染色していない木肌の色と黒。 木肌色は自然な感じがとてもいいのですが、日よけにするには明るすぎるような気がしたので、さんざん迷った挙句、黒い方に決めました。 今年もその展示会の開催案内が届く季節になりました。
August 21, 2006
-
奈良のねこたち
ここ数年は出かけていませんが、春と夏には古都を旅行していました。 もう5年ほども前でしょうか。早春の2月、まだ花も咲いていない時期に、奈良の山之辺の路を歩きました。そこは道しるべがあってないようなところで、うっかりお墓に迷い込んだり、民家の生活道路に出てしまったりと、古道からはずれることもありましたが、そうめんを干してある風景や思わぬところでいたちやねこに出会ったりと、それはそれで楽しいアクシデントがあります。 いちごを栽培しているビニール・ハウス横を歩いていたとき、水色の毛皮のかわいい子ねこに出会いました。抱きあげると、嫌がりはしませんでしたが、ひどく鼻水が出て呼吸も苦しそうでした。鼻炎だったのかもしれません。 環濠集落の池では釣りをしている5~6人のおじさんたちに寄り添うように、一匹の茶色のおとなしいねこがいました。私が撫でようと近寄ると、その気配を感じてさりげなくかわします。 おじさんたちが口々に「りこうなんだよ」と笑いながら私に話しかけると、ようやくねこも安心したようで、撫でさせてくれました。 三輪の駅の待合室には三毛ねこが、電車を待つ乗客に混じって、イスに敷かれた座布団の上で、丸くなって寝ていました。 人に怯えるふうでもなく媚びることもなく、我が物顔に日当たりのいい場所を選んで、待合室のイス、駅舎の前など居心地のいいところにからだを横たえ、それを人々も日常のこととしているのには驚きました。 私の住むところでは待合室にねこどころか、座布団さえありません。 穏やかな人や風景の中では、ねこの性格も同じように穏やかで、伸び伸びしているように感じました。
August 19, 2006
-
「タラントン」のたとえ
春に蒔いたインゲン豆と枝豆に白い花が咲き、うれしいことに実が生ってきました。昨夜ようやく恵みなる雨が降りましたが、それまでは毎日バケツに二杯ずつ、水やりをしなくてはなりませんでした。 水が地面に滲みこむのを待ちながら、何度かに分けて少しずつ、まるであかちゃんの口に離乳食を運ぶような気持ちで与えました。 するとメダカのようだったインゲン豆が、幅2~3センチ、長さが10センチほどに成長したのです。 しゃがんで下から見上げると、白い花をお尻につけたままの小さなものから、収穫を待っているようなものまで、あちこちに下がっているのが見えます。それを摘み取るときの嬉しさは、何にも替えがたい喜びです。 こうして肥料をやり、水を与えて大事に育てると、植物はちゃんとこちらの期待に応えてくれます。 でも私たち人間の成長はどのように見えるのだろうと、ふと考えてしまいました。 「だれでも持っている人は更に与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。この役に立たない僕(しもべ)を外の暗闇に追い出せ」 マタイ25:29
August 18, 2006
-
秋
秋きぬと 目にはさやかに見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる 古今集にある藤原敏行の名歌です。 秋がやってきたことを、目でははっきりと見分けることができないけれど、風の音を耳にしてはじめて、夏が過ぎたことを実感するものです・・・という歌です。 「目」から感じさせる西日の強い鮮やかな風景、「風の音」から連想させる野分の荒涼感・・・。 五感に訴えるこのことば使いに、とても繊細な感受性を覚えるのです。
August 16, 2006
-
真如蓮
久々に「蓮」の様子を見に行ってきました。 唐招提寺からやってきた「蓮」は34鉢もあるそうですが、花を予感させる鉢は、残念ながら少ないようでした。 これは「真如蓮」という名前がついていましたが、まるで御簾のうちの姫君が恥ずかしげに扇で顔を覆うように、ひとひらの白い花びらを折りたたんでいました。
August 15, 2006
-
麻のワンピース
手作りのワンピースを着て、ミシン糸を買いに行きました。バーゲンの麻布を、覚えていてくれたのでしょう。「ワンピースに仕立てたんですか。すてきですね。そのコサージュもお手製ですか」と、若い女性の店員さん。私はすっかりうれしくなりました。いくつになっても、褒めてもらえるのは嬉しいものです。
August 14, 2006
-
やってみなくちゃ分からない
今夏の目標だった「ワンピース」を、昨日と今日で縫い上げました。 Vネックでノースリーブというきわめて簡単なものですが、それでも私にとって初めてトライしたワンピースなので、嬉しくてなりません。 6月に縫い物を始めたころは、自分が打った待ち針で指先を突き刺し、手のひらを破り、血だらけになりました。時にはせっかくの布を血で汚してしまうこともありましたが、今ではもうそんな痛い思いをすることはなくなりました。 考えてみると今までの私は、様々なことに熱中してきたように思います。 ケーキやパン作りに夢中になったこともあります。 自動車学校に通ったときは、クルマの仕組みに興味をもちました。 辞書を引きながら、自分なりに古文を読み解く楽しさも知りましたし、漢方の勉強もその延長線上にあったと思います。 運動オンチの私を啓発してくれたのは、ホテルのプールで優雅にクロールを泳ぐおばあさんでした。 しかしそのどれも共通していえることは、「やってみなくてはわからない」ということのように思います。 レシピ通りに作っていても、ケーキがうまく膨らまないことがあります。オーブンのくせや火力、作業の手際、器具の使い方・・・細かな違いが意外な結果になって現れます。 陸上で暮らしている人間が泳ぎを覚えるには、水中という全く違った環境を楽しめようになるまで練習を重ね、自分の身体に教え込まなくてはなりません。 ソーイングも、「待ち針の痛くない使い方」を説明した本に、私は出会ったことがありません。 それらはみな自分でトライし、失敗を繰り返しながら工夫を重ね、学習してこそ手にする上達法なのではないでしょうか。 人生を生きるコツも、同じようなものかもしれません。
August 13, 2006
-
白檀扇
若い頃、私が抱いていた「おとなの女性」へのイメージは、「白檀の扇」と「日傘」でした。 最近は若い女性でもUVカットの日傘をさしていますが、日傘も扇もあったほうがいいけれど、なくても特に不便を感じないもの、といったところでしょうか。 その、特になくてもかまわないものを手にするのが優雅なお洒落であり、またそれらの小道具が似つかわしい年齢というものがあるように思っていたものです。 初めて買った白檀の扇子は、京都旅行中に食事をしたレストランにうっかり置き忘れてしまいました。 「忘れ物」をしたことのない私にはとてもショックなことで、それを母に話したところ、桐の箱に入った「白檀扇」を出してきて、私にくれました。 それは意外にも修学旅行で私が、母へのお土産に買ってきたものだそうで、広げて風を送ると、ずいぶん年月が経っているにもかかわらず、私の置き忘れたものより香りが濃厚で、すっかり嬉しくなりました。 ところがそれも、数年前に私の不注意で、扇の一部を割ってしまったのです。 繊細な扇の無残な姿を目にするたびに、粗忽者の私には「おとなの女性」の資格が欠けているのだと深く反省していましたが、それでもやはり新しい白檀扇がほしくなって、買ってしまいました。
August 8, 2006
-
舞妃蓮
舞姫は、うつくしい羽衣をすっかり脱ぎ捨ててはいましたが、真夏の強い日差しの中で頭を上げ、毅然とした姿で、すっくと立っていました。
August 8, 2006
-
気品
昨日つぼみだった蓮が、今日はみごとに咲いていました。 舞妃蓮(まいひれん)という名前だそうで、大きな花びらがひらひらと風に舞っているように揺れ、優雅でいきいきとして、まるで楽しそうです。 美術館の前庭の池には、数鉢の睡蓮もあって、赤い小さなかわいい花がひとつだけ咲いているのですが、遠くてなかなか分かりにくいようです。 睡蓮は可憐な少女のように愛らしく、蓮はおとなの女性のもつ気品、という感じがします。
August 5, 2006
-
藤壺女御 -2-
ある日、思いもかけぬことに「近づきまいり給へる」折がありました。あまりのことに中宮は、お胸をつまらせてお苦しみになります。ただならぬお苦しみように、まわりの人々も慌て惑い、源氏の君も塗籠めに押し込められるのですが、ようやく落ち着きをとりもどした日暮れ、男君はそっと塗籠めを出て中宮の御張台にお入りになります。そのときさっと男君の御衣の薫物が漂い、その香りですべてをお感じになった女君は、浅ましくも恐ろしく、なすすべもなくうつ伏してしまいます。男君が引き寄せますと、御衣をするりと脱ぎ捨ててお逃げになろうとするご様子。ところが、あろうことか長い御髪が衣とともに、男君の手の中に掴まれてしまったではありませんか。追いすがる男君と、髪を絡め取られて「あっ」とのけぞる女君の白いのどもと・・・そんな悲劇的な場面を平安朝の作者は、むせるような濃い薫物の香りに包み、うつくしく官能的に描写しています。
August 4, 2006
-
蓮
唐招提寺から「鑑真和上展」のために送られてきた「蓮」の花です。たおやかな茎の、微妙な曲線がとてもうつくしく、どこか秋篠寺の技芸天に似ているような優雅さが感じられます。
August 4, 2006
全15件 (15件中 1-15件目)
1