2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年03月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
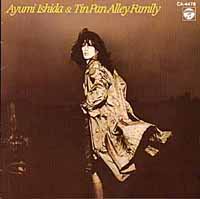
ブルーライトヨコハマ
以前のブログの中で、私にとっての「永遠の美人女優」の代名詞は、カトリーヌ・ドヌーヴだと書きました。では、日本人の中では誰になるか?というと、これはもうダントツでいしだあゆみがナンバーワン、なのです。(あえて敬称略)十代の頃からずっとずっと憧れ続けている、大好きな女優さんです。今では、痩せた女性が年齢を重ねるときにありがちな「シワシワ」「ガリガリ」という形容ばかりが浮かぶお姿です・・・(恐らく、ご本人がアンチエイジングをはじめ、美容の方面に興味がないのだと思われ)でも、「芋たこなんきん」で毎日見せるキラキラした眼の輝き、顔中に笑いが広がるときの可憐さ。今も十分、色褪せていないと思うのです。いしだあゆみがショーケン(萩原健一)と結婚していたことがある、というのは、もはやかなり“世代限定”の豆知識(?)なのかもしれませんが、私が見た、最も美しいいしだあゆみは、その結婚生活の最中、ショーケンが大麻事件で逮捕されたときの、記者会見の姿なのです。「皆さん、どうぞ彼を叱ってください。でも、私だけは彼の味方でいたい」・・・今日は泣かないつもりで来たんですけど、と言いながら、声がふるえて、一粒だけ大粒の涙があふれていました。でも、毅然として、たった一人カメラの放列の前で語る・・・その姿はすさまじく端正で。細い体の線をしゃんと伸ばして、何にも依らず、独りで地に足をつけている。その凛としたイメージこそが、私が彼女に最も魅力を感じる部分です。実は、ショーケンとの離婚騒動の渦中にあったいしだあゆみさんご本人に、新幹線の中で遭遇したことがあります。ロングスカートからのぞいた足首が、信じられないくらい、細かった…斜め前の席に、憧れの女優さんが!という状況に遭遇し、声こそ上げなかったものの、目を見開いて口をパクパクしていた私。隣にいた父親から(田舎者みたいな真似するんじゃない)と、小声で叱られたものでした。もう、あれから二十年以上が経ってしまいました。倉本聡(北の国から)、向田邦子(阿修羅のごとく)・・・名うての脚本家との仕事に数々の名作あり。実は、歌手としても、ティンパンアレーファミリー(細野晴臣、鈴木茂、林立夫、矢野顕子、岡田徹、浜口茂外也、吉川忠英、吉田美奈子、山下達郎・・・豪華!)とのコラボレーションで、「アワー・コネクション」という伝説の名盤を出しています。【ジャケット写真はまさに“日本のアヌーク・エーメ”。】“バイバイ・ジェット”という曲を初めてラジオで聴いたときの(この、かっこいい大人の世界は何なのだ?)というインパクトはすごかった。ブルーライトヨコハマだけが、この人の歌の世界と思ったら大間違い、なわけで。来月、一度は廃盤になったCDがまた再発されます。明日はいよいよ、「芋たこなんきん」最終回。泣いて笑って、じんわりと心温まり、身近な人と共に過ごす時間の大切さを改めて思う・・・そんな素敵なドラマでした。ドラマの中での“純子さん”が、そしていしだあゆみさんご本人がそうであるように。私も、耳たぶからこぼれるように光る、8ミリの真珠のピアスが大好きです。高価な買い物ではありましたが、それを手に入れたときは、(これで、大人の女に一歩近づいたかな)と、しみじみ嬉しかったものでした。
2007.03.30
コメント(15)
-

ザッハトルテ戦争
「ホテル・ザッハーは、オペラハウスのちょうど裏側、ケルントナ通りの入り口から少し横に入ったところにあった。四人はコーヒー・ショップの窓ぎわの席に坐った。『デーメルっていう喫茶店があるんです。そこのチョコ・トルテも、ホテル・ザッハーのチョコ・トルテもおんなじ味ですわ。昔、ホテル・ザッハーとデーメルとの間で、チョコ・トルテの本家争いがあったんです』絵美が長瀬に言った。」 (宮本輝“ドナウの旅人”より)前回のブログを書くのに、以前の旅の写真を見ていたら、懐かしい思い出が続々と甦って止まらなくなりました。“ドナウの旅人”は、まだ東西冷戦が続いていた、80年代前半のヨーロッパが舞台となっていますが、ベルリンの壁が崩れ、21世紀に入ってもなお、ウィーンのガイドブックにはこの「ザッハトルテの本家争い」の話題が必ず出てきます。私と同行の友人も、ウィーンに着いたら「ザッハトルテの食べ比べをしよう!」と楽しみにしていました。同様の観光客が世界中にた~くさんいることでしょう(笑)その時の記念写真がこちら。【ホテル・ザッハーにて。】 【デメルにて。】 *右がザッハトルテ、左はサクランボのトルテです*甘さ控えめ、というのがお菓子の美味しさの代名詞となっているような日本人の味覚からすると、舌にガツン!と来るストレートな甘さ。それが、砂糖を入れない濃厚な生クリームと一緒にいただくと、なぜかペロリと食べられてしまうから、不思議・・・よく言われることらしいですが、デメルのトルテの方が少し、アプリコットジャムの風味を強く感じる気がしました。摂取カロリーは気になるものの、旅の疲れが、砂糖の甘さでみるみる癒されたひとときでした。両店とも、老舗のカフェならではの重厚な内装が“これぞ、ヨーロッパ”という雰囲気で、豪勢なティータイムを過ごせます。日本でも、デメルのお菓子はデパートや直営店で買えますが、あの時“美味しい”と感じたザッハ・トルテを、帰国後は殆ど食べたことがありません。「旅先の名物」って、意外とそんなものだったりしますよね(笑)【デメルの“猫ラベル”チョコレートは好きです。これ、猫の舌の形らしいですね。】※楽天ではタカシマヤのサイトから購入出来ます。
2007.03.29
コメント(9)
-

世界オペラ座めぐり
先日のNHKニュースで、市川団十郎・海老蔵親子の歌舞伎公演がパリのオペラ座で行われている様子を見ました。出し物は「勧進帳」とのこと、海老蔵の弁慶に団十郎の富樫というのは、新鮮な印象を受ける配役です。ニュース映像では、お家芸の「にらみ」を大きな目玉で披露する海老蔵が、なかなか堂に入っていて立派でした。絢爛豪華なオペラ座の空間に負けない、気迫あふれる若々しい弁慶だったことでしょう。社会に出てまだ間もない頃、初めて連続休暇をもらって、人生で最初に訪れたヨーロッパの街がパリでした。初冬の刺すような冷気の下で、見るものすべてに興奮し、自分の内側が好奇心で燃え上がるようだったのを、今でも覚えています。このとき、せっかくだからオペラ座で何か見物しよう・・・ということになり、当日券を買ってモダンバレエを観ました。安いボックス席で、舞台からはかなり遠かったけれど、その分、シャガールが描いた色とりどりの天井画を間近に見られて、うれしかったです。あのオペラ座に、今週は三味線と長唄が響いているのだなぁ・・・と、感慨や思い出に浸っておりましたが、ふと、そういえばこれまでに、私はいくつの国で「オペラ座」というものに入ったのだろう・・・という疑問符が頭をもたげました。最近、衰える一方の記憶力を搾り出してカウントしてみると、それぞれの街を訪れたときの思い出も一緒に甦ってきて、なかなか楽しいひとときとなりました。とはいえ、文字通りオペラを鑑賞した経験は、ウィーンのオペラ座のみ。ちょうど滞在中に、ウィーンフィルの指揮者に就任して間もない小沢征爾が「フィガロの結婚」を上演するというので、多少のプレミアがついても・・・とあちこちのチケットショップを尋ねまわり、何とか(これまた安い席を・笑)手に入れたのでした。粉雪が舞う石畳の路を歩き回ったのも、今ではいい思い出です。劇場内の巨大なシャンデリア、ロビーに建ち並ぶ彫像・・・この写真はロビーの回廊から写したものですが、まさに「劇場的空間」の豪奢な雰囲気に酔いしれた一夜でした。そういう意味では、ブダペストのオペラ座も、規模は決して大きくなかったけれど、ハプスブルグ家の栄華を体感するには十分すぎるほどの美しさでした。ヨーロッパ各国の他にも、かつて植民地だった時代の名残としての「オペラ座」を見たことがあります。これはベトナム、ハノイのオペラ座。隣接するホテルが、その名も「ヒルトンハノイオペラ」というくらい、街のランドマークとして根付いているという印象でした。ライトアップも豪華でしたが、残念ながら式典が行われており、内部の見学は出来ず。・・・その式典の主賓だったのが、当時はまだまだお元気だった、この方です。大きな体と、眼光の鋭さが印象的でした。「オペラ座」といえばすぐに思い浮かぶフレーズが「オペラ座の怪人」。そういえば、先週終わった世界フィギュア!世間は、いまや女子シングルの話題でもちきりですが、私は「オペラ座の怪人」にのせた高橋大輔くんのフリーの演技に、一番感動しました。口元がだらしない男は、本来タイプではないのだけど(笑)・・・あのステップはやっぱり美しい。エキシビジョンもかっこよかったですね。モロゾフコーチは流石だなぁ~。【そういえばこの映画、まだ観ていないのですが・・・】オペラ座に限らず、歴史のある劇場の建物には、どこか「この世のものならぬ」不思議な存在が棲みついていてもおかしくない、その場にいるだけで人を幻惑させるような空気が漂っていると思います。歌舞伎座の怪人・・・やっぱり、隈取りをしていそうな感じがしますね(笑)
2007.03.27
コメント(8)
-

上海から・・・
今回の出張では、少し買い物に歩く時間があったから・・・と、上海から戻った夫が鞄から出してくれたのは、小さな花の刺繍が愛らしい、シルクシフォンのストールでした。ところどころにカットワークも施された凝った刺繍で、体に巻きつけてみると、柔らかい光を集めたような華やかさ。とても気に入ったのだけれど、パーティーに行く予定もないし・・・このストールを纏って出かける機会は、果たしていつ巡ってくるやら?うっとりと、眺めているだけでも、よしとしましょうか。忙しい仕事の合間に、私のために時間を割いてくれた夫の気持ちに感謝して。窓辺に置いた椅子の背にかけて写真を撮りました。
2007.03.23
コメント(12)
-
着物の手仕事
家にいる平日の昼間、正午になるとテレビをつけて、アナウンサーの白髪が日ごとに増えるのを心配しながらNHKのニュースをチェックし、「芋たこなんきん」を見て1時のニュースが終わるまで、チャンネルはそのまま・・・というパターンで過ごします。ニュースとドラマの間は、昼食を作ったり食べたり・・・という時間なので、テレビは完全にBGVに。そのせいか、全国からアナウンサーとタレントが生中継で色々なレポートをするという番組の名前を未だにちゃんと覚えられません(『元気』がどうとか『一番』がどうとか・・・そんなタイトルですよね)。でも、このところ、その「谷間の番組」を食い入るように見る日が増えました。なぜかというと、かなりの頻度で、着物にまつわるレポートが取り上げられるからなのです。それは例えば、絞り染めの工房であったり、加賀友禅の職人さんであったり・・・30分という凝縮された時間で、コンパクトに『職人さんの手仕事』の一面が垣間見えるのが楽しくて。最近、着物にまつわる番組が増えたように感じるのですが、私の興味と感心が、目ざとく「着物」というキーワードをテレビ欄からサーチするから、余計にそう思うのかもしれません。昨日と今日は、京都の街からお昼の中継がありました。京おどりを練習する、歌舞練場の芸妓さん・舞妓さんの様子を取り上げた今日のレポートも素敵でした。・・・が、それにも増して、本能地区(あの、本能寺があった辺りだそうです)から、着物の職人さん達の仕事場を次から次へと紹介した、昨日の番組は本当に面白かった!友禅染の模様を描く、家紋を入れる、金彩を施す・・・うなぎの寝床状の、町家の室内を有効に使い、天井まで使って反物を広げて、1枚の着物が仕上がるまでの数多くの分業行程を何人もの職人さんがこなしていく町。番組の中では、工房の公開とあわせて行われている、見ているだけでも心が躍るようなイベントの様子も紹介されていました。絞りの帯揚げを職人さんの指導のもとで作る一日講座とか、白生地からオリジナルの着物を誂える『マイきものプロデュース』とか・・・私も行って見たい!実は、楽天ブログで仲良くしていただいている、京都在住のISO0104さんが、以前この町のことと、『マイきものプロデュース』のことを紹介されていたのを覚えていて、ああこんな感じなんだ・・・と、改めて興味を持った次第です。また、いつも愛読しているブログ「和、輪、話」の1go1exさんからは、過日の私の日記にとても丁寧なコメントでご教示をいただきました。着物づくりを支える伝承の数々に触れること。それは、先人の編み出した「ものづくりの知恵」の豊かさに、驚かされ、感銘を受けることの連続です。そして、「着物」というカテゴリを通して、自分の世界が少しずつでも広がっていることを、しみじみと嬉しく思うこの頃の私でした。季節が良くなり、体調が整ってきたら、袖を通す楽しみもどんどん味わっていきたいです。
2007.03.22
コメント(8)
-

ロックな晩ごはん
予定のない土曜日の朝は、BSで「今週の“芋たこなんきん”」一挙放送を観るのが習慣になっています。(ちなみに、毎朝8:15からの本放送も欠かさず見ています・・・なのに、土曜の再放送で、前にも泣いた同じところで目頭を押さえたりしています。つくづく、おばちゃんになった自分を感じます。)11時にそれが終わって、何となくリモコンをザッピングしているうちに、いつもついつい見てしまうのが、NHKの「食彩浪漫」。各界の著名人が、自分の“自慢の一品”や“お気に入りのレシピ”を紹介する、というこの番組。登場する料理が美味しそうなのはもちろん、色々な方のご自宅やキッチンを見られるのも興味深く・・・あらかじめ見ようと思ってチャンネルを合わせるわけではないのに、毎度、ついつい引き込まれて最後までチェックするのでした。この土曜日も、やはりいつものコースでこの番組を見始めたのですが、途中からだったせいか、煮豚を作っているこの日のゲストが、誰なのかさっぱりわからない。強いウェーヴのかかったロングヘアで顔が隠れているし、声も妙にくぐもっていて・・・でも、画面の中の中年女性の、笑顔になると思い切り横に広がる口元に、どことなく見覚えが・・・しわがれた声にも聞き覚えが・・・え~っ、この人もしかして金子マリ??そう、下北沢が生んだ日本のジャニス、金子マリさんでありました。今は、ご子息のバンド・RIZEの方がメジャーに活躍していますが、私などはその息子さんが「ポンキッキーズのあっくん」だった頃から見ているので、(まぁまぁ、あの子がすっかり立派になっちゃって)・・・と、これまた“おばちゃんモード”全開の視点でしか見られません(笑)久々にテレビで拝見する金子マリさん、ずいぶん顔つきが変わられたなぁという印象でした。ジョニー吉長氏と離婚されていたことも、全然知りませんでした。パワフルな歌唱スタイルから、常にジャニス・ジョプリンを引き合いに出されることをご本人は嫌がっていたとも聞きますが、私はずいぶん昔に、深夜番組で彼女が、ジャニスの曲を数曲歌うのを見たことがあります。その時歌った「メルセデス・ベンツ」、本当にかっこ良く、エモーショナルで、今でも鮮明に脳裏に甦ってきます。でも、当時も、そしてその後もきっと、家に帰れば、二人の男の子のお母さんとして、包丁を握りフライパンをゆすってこられたのだろうなぁ。目分量で、醤油やみりんを思い切りよく鍋の中に加えていく。マリさんの、その慣れた手つきの確かさが、自分の作った食事で子どもを育てた歴史を証明しているようでした。『ロックやってても、ちゃんとゴハンは作れます』みたいなことを、ちょっと照れ隠しっぽくカメラに向かって語っていたけれど、煮卵と白髪ネギを添えたあの煮豚、すごく美味しそうだった。家族を作って、誰かと暮していくことは、女の人にとっては多くの場合、日々その人たちのために台所に立つことでもあります。それは時として、本当に大変なことだし、この便利な世の中、いくらでも負担を減らす術はあるのだけれど、「食」にまつわることは、家事の中でも最も『あなたのために』という思いが表れる部分ではないかしら?だから、食事を作る人の姿には、ついつい見る者を惹きこむ引力があるのかもしれません。台所に立つロックシンガーは、ステージの上とはまた違う、柔らかい素敵な“ママのオーラ”に包まれていて、かっこ良かったです。生活をきちんと積み重ねてきた人って、やっぱり魅力的なんだな。金子マリさんの煮豚のレシピは、番組公式サイトから見られます。http://www.nhk.or.jp/shokusai/week/20070318/index.html【お母さんミュージシャンとしては、本当はこの人をおいては語れないのだけど】えがおのつくりかた/矢野顕子リスペクトのあまり語る言葉が追いつかないので、今日のところは諦めます(笑)
2007.03.17
コメント(2)
-

ひとつだけ、を買って
ふたり暮らしのわが家では、ただでさえ食材の管理は「食べきれるように、腐らせないように」を最も重要視して行っているのですが、このところ夫が出張で家を空けることが多いため、さらにその傾向に拍車がかかっています。幸い、いつも行く大型スーパーでは、肉や魚のパックは「小量サイズ」があるし、青果コーナーでもバラ売りをしてくれています。多少割高でも、食べきれずに捨てるよりはいいと思い、少しずつ新鮮なものを買うように心がけています。山積みになった野菜や果物の中から「どれか一つだけ」を選ぼうとするときは、袋に詰められたものを買う時よりも、心なしか丁寧な気持ちになっているような気がします。食べごろに色づいた、深い赤のトマト。家で追熟させるのに丁度よさげな、まだ固いアヴォカド。ジューシィな実が詰まっていそうな、瑞々しく重たい伊予柑・・・じっくりと吟味し、「これ!」と心に決めて手に取った一つは、それだけでもう、私にとっては食べる前から「美味しそう」なものであり。そういえば、映画「ゴッドファーザー PART2」の中で、私が好きなシーンの一つに、若き日のドン・コルレオーネを演じるロバート・デニーロが、勤めていた食料品店をクビになって帰宅する場面があります。マフィアのボスの差し金で、心ならずも彼を辞めさせなければならなくなった店主が、せめてつぐないに・・・と箱一杯、ソーセージやパンを詰めて持たせようとする。それを固辞して、家に帰り着いたビトー・コルレオーネが、そっと紙包みから出して食卓に置くのが、一個の洋梨なのでした。「いい梨ね」と喜ぶ妻。彼女に柔らかい笑顔で応えるビトー。【TVで放映されるたびに見ては泣いてしまう。1よりも私はこちらがご贔屓。】ゴッドファーザー PART2ショッピングバッグから、そっと、一つずつ買ってきた果物や野菜を取り出すとき・・・ふと、あの映画のワンシーンを思い起こすことがあります。【もちろん「箱買い」の醍醐味も、お得でまた良し!なのですが♪】選べる!ちょっとお得な!お好み野菜セット(4~10種類)(無農薬野菜・無化学肥料栽培・露地栽培...
2007.03.15
コメント(4)
-

着物ことはじめ ~悉皆成仏~
スギ花粉で目と鼻はヒリヒリ、体調も今ひとつ。そして夫は週末から出張に・・・というわけで、最低限の家事だけ何とかこなして、後はひたすらダラダラと家の中で過ごしておりました。傍らには、買ったばかりの着物の雑誌、「七緒」の最新刊。今回は、着物の「収納」についての特集ということで、楽しみにしていましたが、まさに“目からウロコ”の、ためになる情報満載の一冊でした。七緒(vol.9)収納大作戦畳紙やボール箱が湿気を集めてしまうから気をつける、ウールの着物と絹の着物は一緒にしまわない・・・など、など、など。とにかく“湿気を避ける”“日光を避ける”“畳み皺を避ける”この三要素は絶対!だということが、改めてよくわかりました。実は、以前のブログでも紹介した、祖母が買っておいたという反物についても、少々残念なことがあったのです。お仕立てをお願いした際、呉服店でご主人が、反物をざっと広げて調べてくださったときに「・・・ちょっと、色が変わってますね」とのご指摘がありました。えっ?と驚いてよく見ると・・・確かに、反物状に巻かれていた時の一番外側にあった部分が、その他の生地に比べて若干、黄ばんでいるような。日焼けしちゃったのかしら?でも、ずっと箪笥にしまいこんであったと聞いた。桐箪笥は日当たりのいいところはダメ、というので、確か北向きの寒い部屋に置いてあったけれど・・・頭の中を、建てかえる前の実家の様子が秒速でグルグルまわっていたところへ「これ、カビが出てるんです」というご主人の一言。ええ~っ!カビですか!・・・と、大ショックの私でありました。周囲に高い建物ばかり続々と建ったせいで、風通しも日当たりもぐんと悪くなっていた時期が長かったので、さもありなん、という感じですが、後悔先に立たず!です。幸い、湯のしの段階で変色をカバーし、さらに着ると殆ど目立たないところへ持っていって仕立ててもらいましたので、着物としての仕上がりにひびかなかったのは、本当に呉服屋さんのおかげ。呉服屋・・・と書いていますが、着付けの先生に紹介していただいたこのお店は、商品を売る他にも、洗い張りから染め替え、お仕立てなど、着物に関するあらゆる相談事に対応してくれる、いわゆる「悉皆や」さんなのです。「悉皆」、悉く皆・・・とは、まさに読んで字のとおり。初めてこの言葉を知ったときは、うまいこと言うなぁと思っていましたが、「七緒」では、この言葉は仏教用語に由来するのだと紹介されていました。そして、特集ページで着物のお手入れについてレクチャーしてくれていた、銀座のお店のベテランの職人さんの「悉皆成仏」という言葉が、とても印象的でした。モノも人も皆、命に限りがあり、やがて成仏する。着物もしかりで、だからこそ丁寧にお手入れをして、最後まで大切に着ていきましょう・・・という、雑誌の主張はもっともだと思い。そして、花粉を口実に(?)だらしなく引きこもっているわが身を省みて、「カビないうちに、虫干しが必要だ!!」と、ひとしきり反省した次第です。※ゼロからスタート、私の着物修行・・・これまでの着物日記をまとめています※フリーページ 私の着物ライフ
2007.03.13
コメント(9)
-

「世界最速のインディアン」を観た。
「夢を追わない人間は野菜と同じだ」実在した伝説のライダー、バート・マンローの物語を、アンソニー・ホプキンス主演で映画化した作品。極悪人を巧く演じられる俳優は、当然のことながら、その正反対の魅力あふれる善人を演じてもうまい。・・・という訳で、ハンニバルとはうって変わって、出会う人誰もが魅了される、底抜けのエネルギーにあふれたチャーミングな主人公。そんな彼の生き方に、観ている側も勇気づけられる。冒頭に紹介したような小気味いいセリフも満載で、文字通り「ハートウォーミング」な映画でした。米ユタ州のボンヌヴィルというところに、大昔の湖が干上がって出来た、凄まじく広い塩の大平原がある。私はモータースポーツには関心がないので、まったく知らなかったのですが、障害物のないひたすら平らなこの塩平原(ソルトフラッツ)では、様々なマシンがコースでは出せないスピードの限界に挑戦する、「スピード・ウィーク」というイベントが毎年開催されており・・・地球の裏側のニュージーランドから、40年以上自分で改造を続けたオートバイ「インディアン」を携えて、生涯の夢を果たしにボンヌヴィルを目指す・・・その、バートの旅を追ったのがこの映画のストーリーです。ちなみにこのとき、バートは63歳の年金生活者。若くもなくお金もなく、でも夢と情熱だけは有り余るほど持っている。そんな主人公の旅路はアクシデントの連続だけれど、人々との偶然の出会いが、少しずつ、夢の実現へと彼を近づけていき。私が一番印象的だったのは、「聖地に立つ」という感動を、見事に表現した演出と演技。サッカーファンにとっても(そして他のどんな物事においても)、“伝説が生まれた場所”としての「聖地」というものが存在します。その場所への憧れ、思い入れというのは十分に理解できるもので・・・スピードの魅力に取り付かれた男が、スピードの世界記録が次々と生まれた場所に、初めて自分の足で立つ。この場面は本当に美しく、感動的でした。映画を観終わったあとで、かつてはバイク乗りだった夫から、各種の用語解説をしてもらいました。いつもは、いい映画を観たあとは私の方が饒舌なのですが、こんな風にレクチャーしてもらうのもまた楽しく。そういう意味でも、楽しい時間を過ごすことが出来ました。「おじいちゃんのロードムービー」というと、私が大好きな作品に、デヴィッド・リンチの「ストレイト・ストーリー」という映画があります。ケンカ別れしたままの兄が病に倒れたことを聞き、見舞いに行くために、時速8キロのトラクターに乗って、何週間もの旅路を行く老人・・・この映画は音楽も素晴らしかったし、しみじみと胸に染み入る余韻を残して、見る度にラストシーンで涙があふれてしまいます。(そういえばこれも、実話が元になったストーリーでした)しかし、この映画で主役のアルヴィンを演じたリチャード・ファンズワースは、実人生では、末期癌の病苦に耐えかねて拳銃自殺を遂げています。享年80歳。人生の最後の瞬間まで、充実した生を満喫して生き抜くということは、やはり並大抵のことではないのかもしれない・・・と、考えさせられてしまうのでした。
2007.03.10
コメント(4)
-

年に一度のお楽しみ
先週末、夫とドライブがてら、ランチを食べに遠征してきました。(着物パーティーの前日のこと)三重県の、志摩半島に面した的矢湾は、知る人ぞ知る牡蠣の養殖の一大産地です。 的矢がきの特色は、水揚げした牡蠣に、紫外線で殺菌した海水のシャワーを浴びせ続け、完全に無菌状態で出荷しているということらしい。 ノロウィルスの風評被害で、今冬はかなりの売上げダウンだった牡蠣ですが、わが家は夫も私も大好物! 実は、この的矢の養殖場のすぐそばに、秋~冬の牡蠣のシーズンだけオープンする牡蠣料理の店があるのです。 人気のない静かな県道沿いに、ポツンと建っている小さな店で、知らなければゼーッタイに入ろうとは思わない店構え(笑) 店内も、昔ながらの喫茶店とスナックを足して2で割ったような、今ひとつコンセプトをつかみかねるインテリア。 極めつけは店で働く方々で、全員「冬場だけ手伝いに来てます」感がにじみ出ている、思い思いの割烹着やエプロンを身につけた、地元のおばちゃん達なのです。 でも、このお店でいただく、殻つきの生牡蠣や焼き牡蠣の大きくて、美味しいことといったら・・・ 東京のオイスターバーなら、「1個ン百円」という値段がつくところを、こちらなら一品が7~800円で、獲れたての味を楽しめるのです。 都会の飲食代に、いかにお店の家賃や土地代が上乗せされているか・・・東京を離れてみて、何かにつけて実感することであります。なかでもオススメは、牡蠣フライを卵とじの丼仕立てにした「牡蠣丼」。 先週末、約1年ぶりに味わってきました。 あおさのりの赤出汁と一緒にいただくと、もう幸せ~! わが家からは、高速を使って1時間ちょっとかかる距離ではありますが、年に一度か二度、車を飛ばして食べに行くのが楽しみなイベントなのでした。
2007.03.07
コメント(4)
-

雛祭りの着物パーティー
つい先日、呉服屋さんに反物の仕立てをお願いしたことを書きましたが、土曜日の朝、思いがけず「今日の夕方ならお渡しできます」と、完成を知らせるお電話をいただきました。最初にご主人に伺ったお話では、仕上がりまでは一ヶ月、少なくとも3月半ばまでは待ってほしいということだったのに、こんなに早く仕上がるなんて・・・喜びと驚きが入り混じった気分で、お店の暖簾をくぐりました。出ていらしたご主人、開口一番「先生から、明日着ていけるように間に合わせてあげて、とご連絡いただいたものですから、特別に急ぎました」と言われて、びっくりしてしまいました。『明日』、つまり日曜日は、実は私が通う着付け教室の生徒(曜日ごとのクラスで総勢40名近く)が一堂に会して、毎年恒例のパーティーを行うことになっていました。昨年は、習い始めたばかりでお太鼓も結べないし・・・とご辞退したのですが、今年は紬の着物で出席しようと思っておりました。先生は先生で、私が仕立ての相談をして呉服屋さんを紹介していただいたとき、(せっかくならパーティーでお披露目できたらいいけど、自分では急かせるようなことは言いにくいだろうから)・・・と、私には何もおっしゃらずに、お店に電話を入れてくださっていたようなのです。何しろ今日の明日で、さぁ合わせる帯は?小物は??と、軽くパニックに陥ったことも事実ですが(笑)先生の思いやりがうれしく、ありがたく・・・祖母から母、そして私のところへ来た着物には思い入れもありますし、華やかな席でデビューさせることにしました。以前ブログで書いた、楽天のショップゆかた屋さんで誂えた長襦袢を着て、オーダーメードの贅沢をかみしめながらのお出かけとなりました。【先生と私。当日、心から感謝の気持ちをお伝えして着物を見ていただきました】私の着物は昭和レトロという感じですが、先生のお召し物は正真正銘のアンティーク。当日は、海を見下ろすリゾートホテルが会場となりました。とにかく出席者全員が着物姿ですから、その華やかなこと!今どきは、結婚式の装いでも黒を選ぶ人が多いせいか、これだけの「色彩の洪水」のようなゴージャスな雰囲気は新鮮でした。やはり訪問着をお召しになっている方がほとんどで「やわらかものの競演」という感じ。ドレスコードはないから好きな装いで、と言われてはいましたが、やっぱりこの着物にしてよかった、と思った次第です。手持ちのものの中ではこれが唯一馴染む色だった、八寸の名古屋帯を合わせました。バリ島が大好きな私が、イカット風の紋様に魅かれて選んだものです。うすいあずき色とクリーム色の二色を使った、源氏組の帯〆を合わせてみました。ほとんど白に近いクリーム色の着物。春らしいやわらかさを加えたくて、写真では見えませんが半衿を薄いベージュにしました。【アップにしないと見えませんが、実はチョコレート色のドット模様の小紋柄なのです。】帯結びなどの研究発表もあり、何より、皆さんのとっておきのおしゃれを見ているだけで「目の保養」。着物は楽し、と改めて実感した一日でした。
2007.03.04
コメント(12)
-

着物ことはじめ ~楽しい参考書~
近々、着物で出かける予定があって、ここ数日、当日着ていくものをどうしようかと悩み続けています。・・・と言っても、私の持っている着物や帯なんて片手で足りるほどの数なので、選択肢はちっとも広くないのです。でも、洋服に比べて組み合わせるアイテムの数が多い、着物の装い。小物の使い方でかなり印象が違ってくるし、センスが問われるところでもあります。足し算を続けていけば必ず素敵になる、というものでもなく、体を覆う面積が多い分、どこかで引き算も必要になり。一番の決め手は「自分なりのこだわり」なのはもちろんですが、かといって約束事を大きく踏み外しては、伝統衣裳をまとう楽しみが半減するようにも思えるし・・・「コーディネートはこうでねぇと」・・・なんて、暖冬も吹き飛ばす寒さの(!)おやじギャグをつぶやきたくなるほど、この「取り合わせ」の問題は悩ましい。もちろん、楽しくて、いつまでも飽きない悩みなのでありますが。実際に、箪笥の中身を増やすところまではいきませんが、耳年増ならぬ「目年増」を目指す私は、なるべく多くの素敵な着物姿を見ることで、コーディネートのセンスを磨いていけたらと思っています。でも、世に出ている着物の専門雑誌は、どれも大きく重い。そしてお高い(笑)私は、図々しくも着付けの先生におねだりして、バックナンバーを時々お借りしています。ご自宅での小さな教室に通っているからこそ許されるわがまま。先生は「借りた方が一生懸命読むからいいわ。買うといつでも読めると思っちゃうから」と、快く貸してくださっています。自分で唯一購入するのは、「七緒」~着物からはじまる暮らしという雑誌。誌面づくりのターゲットが、二十代~三十代の感覚に絶妙に合わされていると思います。「そうそう!そういう事が知りたかったの!」と、拍手したくなる企画が次々と・・・最新刊の「私を仲居と呼ばないで」なんて特集ページ、見出しを見ただけで笑ってしまいながらも(わかる~!!)とうなづいてしまいます。もはや、親の世代でさえも着物が日常からすっかり遠のいている私たち。ちょっとした時に頼りになる「ヘルプデスク」代わりの情報源をしっかり押さえておくことも、和のおしゃれを楽しむための大事な要素だと思います。【次号はただいま、予約受付中。巻頭特集は気になる「収納」について】【予約】 七緒(vol.9)収納大作戦*本日放映されたNHK「おしゃれ工房」、着物のコーディネートから立ち居振る舞いまで、役立つポイントがコンパクトにまとまっていてとっても良かったです。 講師は森荷葉さん。山本アナ共々、美しい声と日本語が印象的でした。
2007.03.01
コメント(10)
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
-
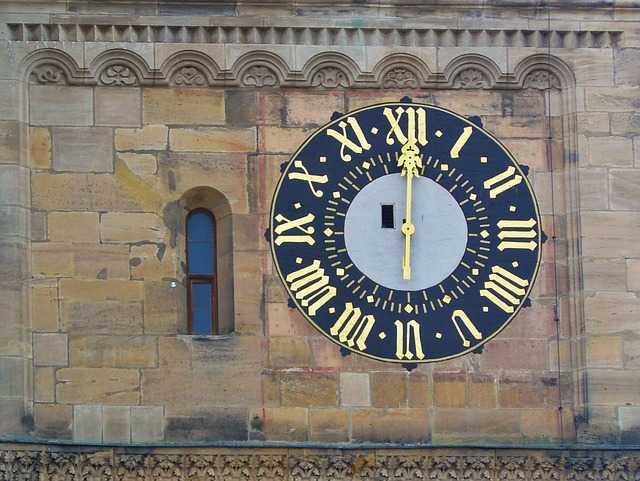
- 風水について
- フライングスター(玄空飛星派)風水…
- (2025-11-10 18:05:38)
-
-
-

- 日常の生活を・・
- 本日もドタバタ!洗濯機壊れてテンヤ…
- (2025-11-06 20:13:53)
-
-
-

- ☆手作り大好きさん☆
- 22cmドールワイドパンツ完成
- (2025-11-16 19:09:57)
-







