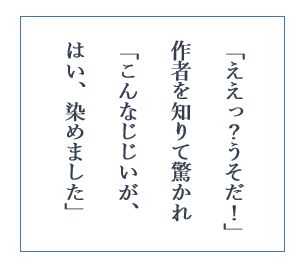2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年09月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-

「ミス・ポター」を観た。
初めて「ピーターラビットのおはなし」を手に取ったのが幾つの頃だったか、その本を誰に買ってもらったのか、もう忘れてしまいました。でも、今まで読んでいた絵本とは違う、手のひらで包み込めるような本の小ささと、描かれた絵の繊細さに(なんだか、おとなっぽい)…と思って、うれしかったのを覚えています。冒険の末に母さんウサギに厳しくお仕置きをされる、ピーターのいたずらの顛末には、ちょっと驚かされましたが(お父さんウサギはパイにされてるし)。その、一連の絵本の作者、ベアトリクス・ポターの半生を描いた伝記映画。この作品のタイトルが、「ピーターラビットと私」というようなものではなく、「ミス・ポター」であることには、大きな意味合いがあるように感じました。つまり、今から100年以上前のイギリスで、三十歳を過ぎた女性が未婚であること、かつ、上流階級にいながら仕事を持ち、収入を得ること。それが、どれだけ当時の社会から見て異端であり、周囲の無理解にさらされることを意味したか。物語の核となるのが、絵本の作者と出版者であったポターとウォレンのラブストーリーです。世間一般の「標準規格」からちょっとはみ出た二人が、やっと、自分を受け入れてくれる存在を見つけた。その喜びが、小さく火花をあげて弾けているような、クリスマスパーティーの夜のシーンが素敵。ユアン・マクレガーのチャーミングな目の表情、ホロリと来てしまいました。ポターを演じるレニー・ゼルヴィガーも、独身主義を貫く婚約者の姉役、エミリー・ワトソンも、こういう“微妙にブスい”女性を演じさせると天下一品、と再確認。実際には、両親、特に母親との価値観の断絶は、もっとすさまじいものがあったのだろうし、ポターその人も、他人から見れば可愛げのない「わが道を行く」タイプの女性だったのかもしれない…と、思ったりもしましたが。動物の物語を描いたのは、人間がうまく描けなかったからだ…という説もあるのですよね。後に、彼女が印税で買い上げ、保存したイギリスの湖水地方の広大な土地は、ナショナル・トラストに遺贈されました。映画の後半は、ロンドンを離れ、湖水地方の農場に居を構えてからの彼女が描かれます。水と緑に囲まれた、穏やかで豊かな自然の美しさ。映像を見ながら、ため息が出るようでした。ポター女史にとっては、この土地の保存に尽力したことは「世のため人のため」というよりは、自分にとっての魂の故郷を守りたい…という、ある意味、利己的な動機に基づくものだったかもしれない。でも、あの時代に彼女という人がいたか、いなかったか…という違いで、ランドスケープはどんな変貌を遂げていたかわからないのだと思うと、何と偉大な功績であったか、と感服します。お金は、稼ぐより使い方が難しいんだ…と、誰かが言っていた言葉を思い出しました。小品だけれど、俳優陣の好演もあり、映画それ自体がよく出来た大人向けの絵本のような、美しい一本でした。この映画を撮ったクリス・ヌーナンが監督した「 ベイブ」も大好きな映画で、何度見ても飽きず、何度見ても号泣してしまいます。子ブタつながりで思い出しましたが、ポターが生みだした子ブタキャラ、ピグリンは、最近「サントリーDAKARA」のCMで活躍中ですね!
2007.09.28
コメント(6)
-

「灯台」を読んだ。
スポーツニュース等で、プロ野球のダルビッシュ投手の名前を耳にすると、反射的に私の脳裏には、ハヤカワ・ミステリの分厚い装丁が浮かんでしまう。なぜ、そんな発想の癖がついてしまったかといえば、大好きなイギリスの推理作家、P・D・ジェイムズの「ダルグリッシュ警視シリーズ」の長年のファンだから(笑)。ロンドン警視庁のエリート警視で、詩人でもあり、頭脳明晰、品行方正なダルグリッシュが、部下と協力しながら難事件を解決する…シリーズに共通しているのは、上流階級の人々がからんだ、限定された人間関係の中で殺人が起こり、怪しい数人の人物たちから犯人当てが行われる「フー・ダニット」もの、だということ。しかも、殺された被害者、容疑者たちの一人ひとり、そして捜査にあたるダルグリッシュや同僚の刑事たちに至るまでの人物描写は、まるで細密画のようです。どんなフラットに住み、どんな家具を選び、どんなお茶の飲み方をしてどんな服を着るか。多くの場合、殺人事件が起きるまでに、登場人物の紹介で小説の1/4近くが費やされるという…読む側としては、読めば読むほど「どいつもこいつも怪しい」と、どんどん事件の中にのめり込んでしまうわけで(笑)新作が出るたびに、(あぁ、またあの楽しみが味わえる)…と、ワクワクしてしまうのです。しかし、クリスティやセイヤーズの後継者と言われ「ミステリの新女王」との称号を戴いてきたジェイムズ女史。実は大正9年生まれ(!!)、御年87歳。前作の「殺人展示室」のエンディングを読んで、もしかしたらもう、これがシリーズ最後かも…と思っていたのですが、今年、新作が邦訳されました。灯台今回の舞台は、VIP専用の保養地となった小さな島。少数の滞在客と従業員しかいない沖合の孤島で起きた殺人事件……って、何とまぁ「王道」なお膳立て!と、本格ミステリファンとしては頬が緩んでしまいました。人が殺し殺される、という出来事は、例え犯人がわかって事件が解決したからと言って、めでたしめでたしと明るく幕を下ろせるようなものでなく、関わったすべての人の人生を変えてしまう。その、後味の苦さも含めて、娯楽小説でありながら「人間の物語を読んだ」という満足感を毎回与えてくれます。鮮やかなトリックなどは出てこないけれど、「誰が」「なぜ」「このやり方で」殺したか、この事実を地道に追い求めていく捜査の過程は十分にスリリング。ただ、以前に比べて記憶力が落ちているせいか、のんびり読んでいては、長い物語の始めの方に出てきた微妙な伏線は忘れてしまうという危険性も…?(作者はお元気なのに、読者は情けない!)イギリスには、トランジットのヒースロー空港以外行ったことのない私ですが、21世紀になっても厳然と「階級」が存在し、そのことがいかに人々の考え方に影響を与えているかという点には驚かされます。貧しい生い立ちから努力をもって這い上がってきた、ダルグリッシュの部下のケイトという女性刑事が、シリーズが進むごとに成長していく様子を知るのも楽しみの一つ。とにかく「重厚長大」で、読み始めたら家事は二の次、となるミステリですが、秋の夜長にはうってつけとも言えます。今回の「灯台」も面白かったですが、シリーズの中では、名門出版社を舞台とした「原罪」が特に好きです。今度こそ、もうシリーズの大団円なのかも?と思えなくもないですが、ファンとしては、ジェイムズ女史の健康とご長寿を願い、つい新作を期待してしまうのでした…
2007.09.27
コメント(4)
-

「好きだ、」を観た。
印象的なタイトルに惹かれて、いつか観たいと思っていた映画でした。17歳の頃、抱いていた恋心。でも、はっきりと言葉で伝えることは出来なくて、その想いは成就しなかった。やがて17年の歳月が流れ、34歳になった同級生の二人は再会する。そして・・・・・・という、ストーリーのアウトラインはあらかじめ知っていたのだけれど、ある意味、事前の予想を裏切られる展開が続きました。登場人物はごく僅か、そしてとても限定された人間関係を描いているのに、予定調和とは無縁の、張り詰めた空気が漲っていて。シーンとシーンの間をつなぐ、頻繁にインサートされる雲の映像に、ふうっと息継ぎをさせてもらう感じが心地よかったです。どぎつさとは無縁の、淡々とした、シンプルな白磁のような作品でした。BGMが殆ど使われないこの映画の中で、登場人物たちが奏でるギターの音色が殊更に美しく響きます。雲、川面を走る光の波、日没後の、もうすぐ全てが闇に溶けてしまう夕暮れどき・・・そんなきれいな情景がたくさん詰まった映画でもあります。本当に好きな人の前に立つと、素直な自分になれない。そういう、「肩に力が入ってどうしようもない感じ」を見事に映し出した、高校時代のキャスト(宮崎あおい、瑛太)が素晴らしかった。まるで、岸辺の水門の陰から、二人の大切なひとときを盗み見しているような、そんな錯覚にさえ陥りました。そして、人生経験を重ね、日々の暮らしに少しだけ疲れ、進む方向を見失っているような現在の二人(永作博美、西島秀俊)のリアリティも、ひしひしと伝わってきました。自分の中の、一番恥ずかしい部分を見られてしまうこと。それは時に、相手を刺してやりたいと思うほどの怒りを駆り立てることもある。けれど逆に、そのことで柔らかく結びつく心もある。どんな人生もドラマティックで、どんな人間関係も奇跡を秘めている。そんなことを思わせる、清々しいエンディングが印象的でした。
2007.09.25
コメント(0)
-

「格差」
新しい自民党の総裁が選ばれることになって、ここ数日、様々なメディアで候補者お二人の主張を目にしました。この国が抱える懸案事項は山積みだけれど、とりわけ「格差の問題」ということが多く取り上げられていたように思えます。今年の初夏に、長らく横浜の実家に滞在していました。実家の新聞は讀賣と日経を購読しています。讀賣新聞の首都圏版は、週末が近づくと、映画や美術展、演劇等のプレイガイドに大きく紙面が割かれます。毎週、小さな文字でギッシリと詰め込まれたそれらの興行情報を見ていて、「これこそ『格差』だよ」…と、愕然としました。私が、ミニシアター系の映画を観たいと思ったときに、よく行くのが隣の市の小さな映画館です。支配人のご家族が総出で経営されています。観客が場内が半分以上埋まることは、ほとんどありません。大都市での公開から、3~4か月遅れての上映になりますが、それでも「この映画はスクリーンで観たい」と思う作品との貴重な出会いの場になっています。「明日へのチケット」を観たときなどは、支配人の方が「この映画をどうしても観たいという人が、上映が終わると終電に間に合わないというので、僕、その人を車で家まで送っていく約束しているんです」と、ちょっと笑いながらおっしゃっていました。聞けば、映画館から車で1時間以上かかるところでした。大都会の生活にはない良さが、地方の小さな町の暮らしにもたくさんあることは、重々わかっています。「住めば都」という言葉も、ウソではありません。ネットの普及もあって、手に入らないものは殆どないのに。どうしても、余暇の使い方の、この選択肢の少なさ、世界が広がっていかない閉塞感が拭えないのが、未だに苦しくて仕方無い時があるのです。福田新総裁が、選挙活動中に地方の町を視察して「シャッターが閉まっている店が多いねぇ」とおっしゃっていました。私の住む町も、駅前の商店街にもはや活気はありません。ショッピングセンターと、パチンコ屋と、巨大なマンガ喫茶と、レンタルビデオ店だけは、いつも駐車場にギッシリ車が埋まっています。若い人たちが、地方にとどまる。あるいは帰っていく。そのことが、地方間格差の解消の第一歩だという話が出ていますが、「ここを出ていかなきゃ何も始まらない」と思う若者たちの気持ち、私は理解できるような気がするのです。※用事と用事の合間に、どうしても行くところが見つからず、時間つぶしに入ったマンガ喫茶でこれ、全巻イッキ読みしちゃいました。ハチミツとクローバー
2007.09.24
コメント(2)
-

「太陽」を観た。
子どもの頃、両親が仕事で忙しかったこともあり、私は祖父母、とくにおばあちゃんに、べったりと甘えて育ちました。陽気でおしゃべり好きだった祖母は、昔の思い出話をいろいろと聞かせてくれました。先の戦争についても、空襲、疎開、占領下の生活など、たくさんの経験談を繰り返し話してくれて、それらは私の中で“疑似戦争体験”といってもいいほど鮮明に残っています。召集されて戦地へ赴いた祖父が、頑ななまでに戦争の話は一切口にしなかったのとは対照的でした。ソクーロフ監督が、イッセー尾形を主演に迎えて、終戦前後の昭和天皇を描いたこの映画を観ながら、なぜか祖母の言葉が思い出されてなりませんでした。「天皇陛下がマッカーサーに会ったとき、『私は命は惜しくありませんから、どうぞ国民をお助けください』とおっしゃったんだよ。それでマッカーサーは大感激して、だから日本は救われた」…今では私も、この祖母の話、特に後段の部分が史実としてはアヤシイことがわかっています。が、少なくても祖母にとっては、こう信じることが、戦争に巻き込まれた自分の人生を受け入れる上では一つの支えになっていました。おかしかったのは、昭和天皇の言葉を再現するときの祖母の口調が、あの話し方の特徴をよく捉えていたことです。形態模写、キャラクター造形を本業(?)とするイッセー尾形であれば、なおのこと。口をモゴモゴと動かし、「あっそう」と返事をする姿、「真似」と「演技」が重なり合ったハイレベルな人物描写がそこにありました。全編、セピア色のトーンの中で、画面は常に緊張感に満ちています。その、緊迫した空気の中で、天皇その人は、どこにもリアルを感じられずに、もがいているように見えます。人でありながら神の扱いをされ、当事者でありながら現実と遠ざけられている。海洋生物学の研究に勤しむ天皇の夢の中で、爆撃機が魚類の形をしている…という、シュールな空襲の悪夢のシーンは、とても幻想的で美しくさえありました。人間が、わざわざ「私は人間です」と宣言しなければいけなかった…という事例は、歴史上の珍事でしょうね。ソクーロフ監督が昭和天皇という人に興味を持ったのも、その点なのではないかと感じます。人間宣言という形で、ある意味“生まれ変わった初めの一歩”を踏み出す天皇。ラストシーンで、天皇が突きつけられる現実の過酷さに、ゾッとさせられました。一歩を踏み出してみたところで、自由に生き方(あるいは死に方)を決められるわけではなかった。一人の人間としては、戦争の当事者として自死した、あるいは殺されていた方がよほど楽だったでしょう。それさえ許されなかった、人間では責任の取りようがない惨事に結果的に手を貸した、一人の男。過日「クイーン」を観たときに、こういう映画は日本では出来ない、と思ったのと同様に、天皇を“ある男”という視点で描写するこういう作品も、日本人には無理だろうと思います。映画の中で、天皇と皇后の交わす会話が、何だか全然大事なことを突きつめず、関係ない周辺を巡り、あっそう、あっそう…と何となくわかり合ってしまうのと同じで、危ういところには触れないで、言わずもがなのまま現状を維持していく…この「何となく」な感じが、この国の持つパーソナリティなのかもしれません。この作品はWOWOWで観ましたが、こういう映画は、暗闇の中でスクリーンに向かい合い、どっぷりとその世界に浸りたかったなぁーと残念です。
2007.09.22
コメント(6)
-

お取り寄せ栗きんとん
まだ、残暑の名残も色濃いこの頃ですが、早いものでもうお彼岸です。気がつけば、家の周囲の水田でも稲刈りはすっかり終わり、スーパーでは連日さんまが特売で、秋は着々と深まりつつあります。そんな「実りの秋」の楽しみは数々ありますが、私が心待ちにしていたものの一つが、岐阜の和菓子屋さんで始まる「栗きんとん」の製造販売。栗きんとんと聞くと、かつてはおせち料理に入っているあれしか思い浮かばなかった私・・・友人に教えてもらって以来、すっかりこのお菓子のファンになってしまいました。岐阜県の中津川というところは栗の名産地だそうで、東海地方のニュースでは、栗きんとんの生産開始が季節のニュースとして報道されたり(!)するのです。平松洋子さんの本でも紹介されている「すや」、楽天でも買える「新杵堂」など、数々の栗を扱う老舗の和菓子屋さんがありますが、わが家は友人にならって、「川上屋」さんに注文しています。甘栗もモンブランも大好きなわが家の夫婦ですが、この栗きんとんを初めて食べたときはうなりました。洋菓子のマロンペーストとも、甘露煮とも違う、本当に「栗そのものを味わう」という感じの美味しさ。【それも当然、この原材料表示の潔さ!敬服いたします。】素朴でありながら、その甘さはあくまでも上品で、かけられた手間ひまが伝わってくるようです。日持ちはしないため。二人家族で一度に頼めるのは10個が限度。一つ目は渋めの緑茶で、あとはお抹茶を点ててもいいし、深めにローストされたコーヒーとも相性がいいかもしれない・・・と、並んだ栗きんとんを前に妄想が炸裂(笑)丁寧に味わいたいお茶うけがある。それだけで、なんだかグッと生活の質が上がるような気がするのでした。※楽天で買える、中津川の栗きんとんは※岐阜県発 老舗栗菓子専門店「新杵堂」の手作り栗きんとん 10個入り※川上屋※http://www.kawakamiya.co.jp/catalog/
2007.09.20
コメント(4)
-

「造顔」の理由
色々と日々の用事がたて込んで、疲れていたことは事実でした。寝不足だったことも確かです。しかし、その夜、電車のガラス窓に映った自分の顔を何気なく見た瞬間にガーン・・・あまりにも、自分の脳内にあるセルフイメージより老けて見えるので、がく然としてしまったのでした。それが今月の初め、慌しい上京をする2日前のことでした。加齢と共に、身体的な衰えは様々な形でやって来るけれど、何よりも残酷に突きつけられるのは「横に広がったものは、そのまま下に落ちていく」この、重力への抗えなさではないでしょうか。あぁ、10年前は、もうちょっと何もかもが上向きだったような気がするんだけど・・・そこで私、この際一念発起。何となくやってみて、何となく続かなくなってしまった、あの田中宥久子さんの造顔マッサージに、真剣に取り組むことを決意いたしました。東京での用事を終え、わずかな空き時間に、赤坂の東急プラザへ猛ダッシュ。田中さんのプロデュースするサロンへ行き、造顔マッサージ用のクリームと、ふき取り用のローションを購入して、サロンのお姉さんにマッサージの方法も実演つきでアドバイスしていただきました。以来、一日2回、せっせとTVの前でマッサージに励んでいます。(夫は、その最中の私の顔を見るのは忍びないらしく、この日課の間は微妙に遠巻きにしているようです・・・)【きれいなモデルさんも、マッサージの最中はスゴイ顔・・・】 田中宥久子の造顔マッサージ(でも、リンパを刺激する「痛キモチよさ」は快感です!)・・・で、なぜ、こんなにも私が必死かと言うと、実は生まれて初めての運転免許の更新が近づいているのです。どんな人でも、どれだけがんばっても、絶対に満足の行く映りにはならない、それが免許証の写真らしいですが。どうせなら、すこしでも若々しく、それなりに(笑)きれいな顔の自分を持ち歩きたいと…悪あがきでしょうか??それにしても、半ベソかいて(私には絶対ムリ!)と思いながら教習所に通っていた頃が、ついこの前のことみたいです。※教習所時代の日々のブログはこちら。今読み返しても、当時の苦労が思い出され・・・我ながら泣けます(?)VitzのCMでゴクミが、「(運転は)私のリラックスタイム」などと言っているのを見ると、未だに信じられない私ですが、おかげさまで今のところは、無事故無違反、ぶつけてもこすってもいないのは大ラッキー。これからも、安全運転に心がけていきたいと思っています。あ、それから造顔の努力も『継続は力なり』ですね!参考:Ymethod公式サイト
2007.09.18
コメント(4)
-

秋の夜長と茶の香り
ある日、着付けの先生のお宅にお稽古に伺ったときのこと。いつものように和室の襖を開けると、途端に、何ともいえぬ香ばしくて、すっきりとした芳香に包まれました。その源は、部屋の一隅に置かれた、大型のアロマポットのような焼き物でした。ただ、ちらちらと灯りをもらすキャンドルが温めている受け皿には、アロマオイルではなく、緑茶の葉がたっぷりと入れられていたのです。子どもの頃から、お茶屋さんの店先でほうじ茶の香りが漂っていると、思い切り吸い込まずにいられない性質なので、この「茶香炉」なるものにあっという間に魅せられてしまいました。すると、ありがたいことに先生が、その香炉を作られたというお知り合い(趣味で陶芸をされている方とのこと)から、小さいバージョンを取り寄せてくださいました。 この写真では、懐紙を敷いて茶葉を温めていますが、受け皿に直接茶葉を載せた方がより香りが立って、秋雨でジトッと湿った室内の空気を爽やかに塗り替えてくれるようです。一通り、鼻先でそのアロマを楽しんだ後は、軽く焙じられた茶葉を急須に移し、丁寧に淹れて舌で味わう。そんな「二度おいしい」お茶の楽しみ。冷たい麦茶から温かい飲み物が恋しくなるこの季節に、夜毎、しっとりとしたひと時を過ごしております。※先日のお稽古では、久々に袋帯で二重太鼓を練習しました※この背中の皺は、なんじゃ??(汗)茶香炉あれこれ
2007.09.14
コメント(10)
-

「本よみの虫干し」を読んだ。
サブタイトルは「日本の近代文学再読」。著者の関川夏央氏の、硬質で隙がなく、それでいてどこか、読んでいて「グッとくる」情感がこめられた文章。昔から好きです。これはずっと読みそびれていて、先日図書館で見つけた一冊。「本の虫干し」ではなくて「本よみの虫干し」というタイトルが印象的です。「根が文学嫌い」という著者が、『文学は鑑賞するものではない。文学は歴史である』つまり、文学は作家の個人的表現でありながら、同時に時代を映す鏡であって、史料なのだ…という観点に立って、樋口一葉から岡崎京子のマンガに至るまで、さまざまな作品を、時代に即して読み直していく。収められた60近い作品群には、未読の作品もたくさんありました。が、目次に並ぶ「早熟とは不運に他ならない」■『肉体の悪魔』 ラディゲ「必然の暴食、決死の美食」■『仰臥漫録』 正岡子規「屋根一枚めくればどの家も問題だらけ」■『岸辺のアルバム』 山田太一「ただ家にいたくなかった作家」■『輝ける闇』 開高健…といった章題からして、知っている本もそうでないものも、同じように興味をかきたてられ、一気に読んでしまいました。例えば、夏目漱石の「三四郎」を取り上げた章。明治四十年に職業作家となり、第一次大戦がもたらす好景気が始まる前に亡くなった夏目漱石の小説には、たびたびお金を軸に展開する心理と人間関係が描かれる。つまり漱石を「不況作家と呼ぶことができる」…など、新鮮な視点の数々に、ページをめくる手が止まらなくなりました。すぐれた文学作品は、時代を超える力を持つ。その一方で、なるほど、一つの作品が「書かれた」時代背景や、「読まれた」(あるいは「読まれなくなった」)社会を覆っていた空気の色を照らし合わせて読むと、そういうことだったのか…と腑に落ちることも数々。ホコリのつもった頭に刺激を与えられたというか、知的好奇心をかきたてられた楽しい一冊でした。【紀行文学から漫画の原作まで、幅広く面白い関川作品です】「坂の上の雲」と日本人ソウルの練習問題『坊っちゃん』の時代
2007.09.13
コメント(2)
-

「男鹿和雄展」を観にいく
一泊二日の慌しいスケジュールで、東京へ出かけていました。きっかけは、夫に東京で仕事の予定が入り、週末から上京することになったこと。実は、私たち夫婦の友人が、体調を崩して都内で入院生活を送っており、一度お見舞いに行きたいと思っていたところだったので、私も便乗したのでした。幸い、友人の病状は小康状態を保っていて、本人も気力は十分上向き。遠来の客を喜んでくれたので、まずは一安心でした。当初の目的を無事に終え、半日あまったスケジュールで何をしよう?と考えた末に、東京都現代美術館で開催されている『ジブリの絵職人 男鹿和雄展』を観に行くことにしたのです。男鹿和雄さんといえば、多くのジブリアニメの名作を素晴らしい背景画で彩ってこられたことで有名。「となりのトトロ」を初めて観たとき、あの、夏の陽が傾いていき、みるみる空が夜に移り変わっていく黄昏どきの田園風景に、目をみはったものです。何度観ても、あの空、あの雲、そしてあの森・・・アニメの表現ってこんなにすごいことが出来るんだ、と感動してしまう。その「トトロ」の背景画も含め、600点という膨大な原画の数々を一堂に会した展覧会は、本当に見応えがありました。アニメ界におけるキャリアの長い方ですから、のっけから「侍ジャイアンツ」だの「はじめ人間ギャートルズ」だの・・・タイトルを見れば主題歌が脳裏に流れる、懐かしいことこの上ない作品の背景も展示されていました。大盛り上がりで、隣の若いカップルとの温度差がすごかった私たち・・・(笑)【順路の終盤は撮影OK。等身大(?)のトトロがお出迎えする一角も】企画展示室にも、映像作品の上映をはじめ様々な趣向があり、なかでも、「折り紙でトトロを折る」コーナーは老若男女に大人気でした。【おひとり様一枚限りの専用折り紙をもらって、いざ、チャレンジ】※完成したら、顔を自分で描き入れます※場内には、ちゃんと男鹿さんの背景画を使った「撮影用コーナー」も設けられ、各自がお手製のトトロを、映画の中のいろいろな場面の前で撮影できるようになっていました。【青トトロは私、緑トトロは夫の作品。】入場までの待ち時間、80分という混雑ぶりでしたが、行列に並んだだけの価値はあった!と、大満足で美術館を後にしたのでした。人気を集めていたのは、やはりジブリアニメのコーナーでした・・・が、私はその他にも、吉永小百合さんのライフワークとしても有名な、原爆詩をまとめた『第二楽章』の挿絵の数々が特に印象的でした。戦争がもたらした、地獄絵図の悲惨さを伝えることばの数々。それとは対極の、端正なタッチで描かれた被爆地や戦地の光景が、静かな迫力をもって、絵のこちら側に立つ私達の心に深く入り込んでくる。展覧会全体を通じて、人は、世界を美しくすることも、醜くすることも出来るのだ・・・ということを、改めて考えさせられたのでした。第二楽章会場の一角に、男鹿さんご本人の仕事机が再現してあって、端に止められた手づくりの小さなカレンダー(画用紙に手描きで罫を引き、マス目の中に予定が書いてある)に、飾らないお人柄を見る思いでした。美術大学を出たわけでもなく、いわゆる『画壇』『美術界』とは無縁の世界で仕事を続けて来られた。「画家」ではなくて、あえて「絵職人」という肩書きを展覧会のタイトルに据えた、そのことが逆に、プロフェッショナルとしての誇りを感じさせて、かっこいいです。「男鹿和雄展」公式サイトはこちらから。会期は今月末まで。
2007.09.10
コメント(4)
-
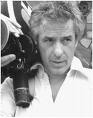
「フェイシズ」を観た。
ジョン・カサヴェテスの映画がテレビ(主にBS)でオンエアされるときは、「特集」と称して、何本かの作品がまとめて放映されるケースが多い。もう何度も観ている作品ばかりなのに、なぜか時間が許すとチャンネルを合わせてしまい、図らずも「カサヴェテス祭り」な状態になってしまうのは、なぜ?(笑)初めてカサヴェテスの映画をスクリーンで観たのは、銀座のミニシアターで行われた連続上映(しかもレイトショー)でした。ちょっと残業してから、デパ地下で売れ残りのお弁当を買い、毎週、映画館まで歩いていきました。人気のないロビーに入れてもらって、映画の始まりを待ちながら夕食を済ませたのが、懐かしい思い出です。彼と、妻のジーナ・ローランズが実際に住んでいた家は、製作資金のために抵当に入り、かつ、いくつもの映画の撮影現場として使われていたことで有名です。作品を続けて観ていると、何度も同じ場所が登場していることがよくわかります。また、ジーナをはじめ、ピーター・フォーク、ベン・ギャザラ、シーモア・カッセル以下“チーム・カサヴェテス”と言いたくなるような常連俳優が多いので、観ているこちらは「あ、あの家だ」「あ、あの人だ」…と、映画が変わってもおなじみの場所と人、という、勝手に懐かしさを覚えてしまうような錯覚に捉われます。ただ、舞台と演じる人が同じでも、各々の映画において描き出される「人生のシチュエーション」はまるで異なる。それが演出の、脚本の、そして演者の力量なのでしょう。でも、彼の映画に登場する人物は、総じてどこか欠落し、バランスが悪く、自分の心に開いた穴に自分で足をひっかける、そんな悪あがきの最中にいる人ばかり。最初に観たときは、「アメリカ人というのは、何と酒飲みで煙草のみで饒舌なのか」と、正直言ってゲンナリしました。登場人物に起こる出来事を、省略したり記号化して表現できるのが映画の強みのはずなのに、この監督は頑ななまでに、人々の感情の動きを、時間の流れまるごと、フィルムに焼き付けようとする。衝突する言葉、沸き上がる怒り、その後の放心。束の間の安らぎ。14年に及んだ夫婦の関係が、一日にして崩壊する様を描いたフェイシズ。精神のバランスを欠いて追い詰められていく妻と、その夫の姿を描いたこわれゆく女。この2作品がとくに好きです。特に、「フェイシズ」の終盤、すれ違いの末にからっぽになってしまった結婚生活を象徴する階段を使ったラストシーンは、何度見てもすごい、と思います。しかし、実際のカサヴェテスとジーナの結婚生活は、男女の愛が究極の同志愛にまで昇華された例として、今なお、人々の憧れを集め続けています。子どもの出産費用を映画につぎ込んでしまった夫が、「何も心配することはない。子どもは僕がとりあげる」とジーナに言い放った、というエピソードなんて、もう絶句ですが…この二人の結婚式の写真を以前に見たことがありますが、それはそれは幸せそうな、絵になる2ショットでした。才能と才能の幸福な出会いがあり、お互いがそれを喰い合うことなく、助け合い伸ばした…という、稀有な例がここにはあるのだと思います。物質的には満たされながら、心はいつも飢えている。充足感とは無縁の、乾いたアメリカ人の精神を描きながら、カサヴェテス本人の人生は、結果としては幸せだったのではないか…と思うのでした。【ほか、WOWOW「カサヴェテス特集」で取り上げられていた作品】アメリカの影チャイニーズ・ブッキーを殺した男オープニング・ナイト
2007.09.07
コメント(10)
-

「朔日参り」の伊勢
「伊勢には「朔日参り」といって、毎月一日、普段より早く起きて、無事に過ぎた一ヶ月を感謝し、また新しい月の無事を祈って神宮に参拝するというならわしが残っています。」(“みそか寄席”プログラムより)前回の日記の続きです。23時半を回る頃、「みそか寄席」が終わって会場の料理屋さんを出ると、赤福の本店やその周囲の道沿いに、行灯が設置されたり“朝市”と看板のかかった屋台が準備されているところでした。冒頭に書いたとおり、毎月一日には伊勢神宮に早朝参拝をするという風習があるそうです。それにちなんでか?かの有名な赤福でも、一日だけしか販売しない、その名も「朔日餅」という特別な商品が月替わりで出されます。当日は、夜明け前から参拝客、朔日餅を買う人々で内宮周辺は大賑わい。その方々のお腹を満たすため、周辺のお店では、朝の5時から朝粥や朝食メニューを出すところも。「みそか寄席」の会場である「すし久」でも、この「朔日粥」を目当ての行列ができる人気ぶりです。さて、前日、寄席で夜更かしした私たちでしたが、気合いを入れて9月1日、早朝5時に再び神宮へ舞い戻りました。まずは、おはらい町のはずれにある「とうふや」にて、朝粥で腹ごしらえ。【五穀粥と、出来たてのほの甘い汲み上げ豆腐が絶品でした。】 その後、杉の巨木から何とも芳しいアロマが立ち込める、清々しい伊勢神宮をお参り。玉砂利をザクザクと踏んで歩くうちに、ようやく、細胞のすみずみまでがスッキリ目覚めていく感じがしました。その後、再びおはらい町を歩いて、本日のメインイベント(?)「朔日餅」を買いに行きました。【五十鈴川にかかる橋の上は、赤福の本店に並ぶ人々で大行列です】 朔日餅は、月ごとにメニューが決まっていて、毎年9月は「萩の餅」、つまりおはぎ。秋の草花をモチーフにした、美しい千代紙に包まれた菓子折が、文字通り“飛ぶように”売れていました。【おみやげ用の他、店内でいただくことも出来ます】 私、赤福餅のなめらかな餡も大好きなのですが、粒あんのおはぎも程よい甘さで、とってもおいしかったです。次に食べられる機会が来たとしても、1年待たなければいけないというのが、またありがたみを増すんですよね。私たちは、伊勢市在住の知人の案内で、二日がかり、月をまたいでのイベントを堪能することが出来ました。すっかり日が昇って、お餅もあらかた売れてしまう9時過ぎには、「朝粥」「朝市」の看板も外され、町並みはすっかり普段どおりの表情に…さっきまでの賑わいが、まるで一時の幻だったかのよう。これから、観光バスでやってくる人々には、今朝こんなお祭り騒ぎが行われていたことなんて想像もつかないだろうと思うと、とても不思議な感じがしたのでした。
2007.09.05
コメント(6)
-

夜更けの寄席デビュー
伊勢神宮へ行ったことのある方なら、内宮の入り口、宇治橋の手前から伸びる「おはらい町」「おかげ横丁」と呼ばれる通りで買い物をしたり、食事をした経験がおありだと思います。江戸時代にタイムスリップしたかのような、オールドスタイルの木造家屋が並ぶ一角は、おみやげを探したり、ちょっとつまみ食いしたくなる美味しそうなものを買ったり・・・と、私の大好きなスポットです。その通りの中ほどに、古い旅館の建物が今は料理屋になっている「すし久」というお店があります。ここで、毎月最終日に、その名も「みそか寄席」という落語の会が催されていると聞き、出かけてきました。開演は、19時~と21時半~の二部構成。私たち一行は、遅い方の回に出かけました。「すし久」は、広い土間に竃が並び、上がり框に時代劇に出てくるような帳場があったりして、大変趣のあるお店です。この夜はさらに、提灯と行灯で楽しい模様替えがされていました。【提灯には、当夜登場する噺家さんの名前が。】 出演は、地元三重県出身の桂文我、そして桂宗助、桂紅雀という顔ぶれで、落語が四席、その後大喜利・・・というプログラム。二階の大広間に座布団が敷かれ、集まった客は三十人弱でしょうか。本式の寄席ではありませんが、噺家さんとの距離はほんの数メートル。とても贅沢な感じがしました。「開口一番」「宮巡り」「一文笛」「癪の合薬」・・・どの落語も、まったく聞いたことのない噺でしたが、高座との距離の近さゆえか、プロフェッショナルのなせる技か?とにかくグイグイ引き込まれ、そして何より、大いに笑いました!※嫌好法師さんのご指摘により、前座の紅雀さんの演目(=開口一番)は『看板の一(ぴん)』だと判明しました。嫌好法師さん、ありがとうございました。上方落語の特徴と言われる、見台や拍子木を使って話す演目もありましたし、落語家によって出囃子が決まっているというのもよくわかりました。(以上、NHK「趣味悠々~落語をもっとたのしもう」から得た豆知識)この日の入場料は、前売り1800円。すべてが終わったのは23時半。料金も時間も、ちょうど映画のレイトショーを見る感覚でしたが、「『生』の贅沢」を堪能できた分、本当にお値打ちだねぇ・・・と、大満足の一夜でした。もっともっと、色々な噺家さんを見てみたい、たくさんの落語を聞いてみたい・・・と、どんどん欲が出て来ます。夏の終わり、私にとっては記念すべき「第一歩」を記した一夜でした。ところで、いつもは日が暮れると人通りが絶えるこの場所で、なぜ、晦日の夜遅くに、このようなイベントが行われるのか?それには理由があるのですが、その種明かしは次回に持ち越し・・・です。【桂文我師匠(四代目)は、故・桂枝雀のお弟子さん。おやこ寄席の取り組みにも熱心なのだそうです。】
2007.09.04
コメント(10)
全13件 (13件中 1-13件目)
1