2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年10月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-

着物で歩く伊勢の夜
週末、伊勢神宮へ行って来ました。今回の目的は、“おはらい町”と呼ばれる、内宮近辺の古い町並みで、「伊勢ヨイ夜ナ」というライトアップイベントを見に行くことでした。初日が台風による雨で中止になって、ちょっと心配していましたが、この日は天候も回復、大変な盛況でした。もちろん、キャンドルの灯に彩られた夜の情景はとても美しく、幻想的ですらありました。【この日は久々に着物でお出かけしてみました。】 【五十鈴川の岸辺に並べられた灯りの数々。】 【通りもこんな感じに。右手の建物はなんと碁会所だった】 この夜はお月様もとてもきれいで、夜のそぞろ歩きを堪能しました。灯りを一つひとつ、人の手で並べていく作業は大変だと思いますが、行きかう人の顔はどれも楽しそうで、ワクワクと弾んでいて、こういうお祭り気分は好きだなぁと実感。赤福騒動で余波は広がる一方とも聞きますが、お伊勢さんのお膝元の町は大好きな場所なので、これからも活気を持ち続けてほしいと心から願っています。ちなみにこの日のコーディネートです。夫が誕生日プレゼントに贈ってくれた大島紬の名古屋帯をおろしました。軽くて締めやすくて、お太鼓がピタッとおさまって気持ちよかったです。しかし、夜が深まるにつれ、川面を渡る風がどんどん冷たくなって、襟足や袂から入る冷気に「さ、さぶぅ・・・っ」と身がすくんでしまいました。ついこの間まで、暑くて着物でなんて出歩けない、と思っていた気がするのに。いったい全体、着物で出歩くベストシーズンってどれだけ短いのよ?と思いつつ、一方では(今度はどこへ行こうかな)と、着物でお出かけの機会を心待ちにしている私です。そしてご多分に漏れず、ここで記念撮影をしてしまいました・・・(苦笑)
2007.10.29
コメント(16)
-

光と私
台風一過の秋晴れの日曜日。夫と二人で、自宅近くの公園へ散歩に行ったら、噴水に美しい虹がかかっているのを見つけました。この時たまたま、私のバッグの中にデジタルカメラが入っていたおかげで、この瞬間を写真に残すことが出来ました。思いがけず、こんなに美しい自然の不思議を見つけられることもうれしいけれど、それを記録できたという偶然にも感謝したくなります。きれい、きれいとはしゃいだ数分間の記憶は、恐らくは、時間の流れとともに思い出から消えていくから・・・まるで、はかない虹の光のように。感動や感激を刻みこんでいくのにも、様々な外部装置が必需品になりつつある、ここ数年の私です。でも、ただただ流されていくよりは、やっぱり、いつまでも思い出づくりに欲張りでいたいと思うのでした。
2007.10.28
コメント(4)
-

「あのころの未来」を読んだ。
読書週間ですね。私が十代だった頃、この季節になると、男女別に実施された「好きな作家」のアンケート結果が発表されたりして、「女子は赤川次郎、男子は星新一」というのが、ランキング1位の常連だったように記憶しています。赤川次郎にはあまり魅力を感じなかった私は、その代り(と言っては何ですが)、星新一のショートショートにすっかり夢中になりました。自分で文庫本を買うようになった、本当に最初の頃の思い出。薄いグリーンの背表紙の星作品が、次々と自室の本棚に増えていったものです。今の十代の子ども達に、星新一の本が読まれているかどうか知りませんが(それより“ケータイ小説”かな)、ここ数年、改めてスポットライトが当てられているように感じます。そもそも、星新一の作品は「SFショートショート」という分野にありながら、現実の風俗を映し出すような描写がほとんどされていない。ゆえに、時代がどんなに流れても、古びてしまうことがない普遍性を持っています。まるで民話かおとぎ話のように。その一方で、短い物語の中に込められた先見性と、人間への鋭い風刺精神があり…気鋭のルポライター、最相葉月さんが「星が一編一編の物語に注いだ視線を、現代の科学と幸福を考えるための手がかりにしたいと思った」というのは、なるほど、と思わされる着眼点で、この本もずっと読みたいと思っていた一冊でした。あのころの未来バイオテクノロジーや生命科学、生殖医療といった分野に造詣の深い著者だけあって、実際に技術や科学の進歩がもたらしている現実の事態と、星新一がショートショートの中で、エヌ氏やケイ氏に直面させた出来事を見事にリンクさせています。読み応えのあるコラムが50編収められた、とても面白い一冊でした。ただ、実際の一連のコラムが週刊誌に連載されていたのが2002年前後ということもあり、読んでいて「あぁ、そういえばそんなニュースも話題になったっけ」…と、記憶を手繰り寄せなければいけないこともしばしば。40年以上前に書かれたショートショートが未だに新鮮で、5年前に書かれたコラムは既に懐かしい匂いをさせている…何とも皮肉な結果で、このシニカルな味わいがそもそも「星新一ワールド」という気もしなくはないです(笑)【私のベストは「ようこそ地球さん」収録の『処刑』という作品】星新一の著書を探す
2007.10.26
コメント(10)
-

夢見る数学
先日のNHKスペシャル「100年の難問はなぜ解けたのか~天才数学者 失踪の謎」が、大変面白かった。…と言っても、はっきり言って、番組の内容の9割近くがちんぷんかんぷんで理解不能だったのですが(苦笑)そもそも、番組テーマの中心を占める「百年もの間、誰も解けなかった数学の難問」、ポアンカレ予想(=単連結な3次元閉多様体は3次元球面S3に同相である)からして、(これ、どういう日本語ですか??)と、目が点になってしまいました。CGや身近な例えを駆使して、わかりやすく視聴者を導こうとしている制作側の意図は、非常によく伝わるのですが…かえって(宇宙を一周するロープを引っ張る? 宇宙の形状を8個に分類?? ティーカップとドーナツは同じ形とみなすことが出来る???)と、頭が混乱する一方で…それにも関らず、最後まで食い入るように見てしまったのは、この難問を証明してみせようと試みた数学者たちの、挑戦の軌跡やその人生が、とてもドラマティックだったから。それにしても、証明に成功したペレリマン博士の解説を聞いて、名だたる数学者たちが誰もそれを理解できなかった…とか、実際に、証明が発表されてからその理論に破たんがないことを確認するまで4年がかりだった…とか、もう、素人目には「どんだけ~!!」としか言いようがない世界のおはなしでした。小学生の頃から算数が苦手で、「文章題が解けないのは読解力がないからだ」と怒られ続け(でも、本は好きだし、国語は得意なのに)とベソをかいていた私などには、到底「数の美しさ」を感じることは出来ないのだろう、とあきらめています。それにしても。人間が直面する問題は数々あれど、多くは、心のどこかで(これって、永遠に答えの出ないものなのよ)とあきらめ、それを決着代りにしたりするものですが。数学の世界では、「探せば、必ず答えは見つけられる」というのが前提なのですよね。それは、美しくも恐ろしい…まかり間違えば一生を捧げる迷宮にはまりかねない、『果てしない想像力』を要求される学問なのだということを、再認識した次第です。宇宙の果てに思いを馳せて、わからないなりに、数で世界を捉えることのロマンに触れた番組でした。【数学者が登場する映画には、なぜか心魅かれる作品が多い】 ビューティフル・マインドグッド・ウィル・ハンティング~旅立ち~ 博士の愛した数式
2007.10.25
コメント(6)
-

まっちんのお菓子、再び
昨日書いた焙じ茶のお話、実は、この日のドライブの目的は、「和菓子工房 まっちん」のお菓子を食べに行くことでした。「まっちん」は、まっちんこと町野さんが、たった一人で丁寧に作っている和菓子屋さんです。(以前書いた紹介のブログはこちらから)お店は三重県伊賀市にありますが、時折、イベントへの出店という形で出張販売をされると聞いていました。今回は、わが家から車で小一時間の場所で、デザートにまっちんのお菓子がつく、特別ランチが食べられるイベントがあると情報をキャッチして、いそいそと出かけたのでした。会場になっていたのは、若い女性がオーナーのパン屋さんで、彼女が焼くパンと、野菜たっぷりのお料理をいただいた後、まっちんの和菓子でしめくくる…というメニュー。結構辺鄙な場所だったのですが、臨時でガレージに作られた戸外のテーブルも満席になるほど、大変な盛況でした。【この日は秋晴れ。ランチのプレートにスープ付の食事。】 【まっちんのお菓子は、わらびまんじゅうと栗きんとんでした。】 ランチでいただいたパンは、天然酵母や国産の小麦粉にこだわって作られているそうで、噛むほどに小麦の甘みが口中に広がり、美味しかったです。そして、まっちんのお菓子。わらびまんじゅうもおいしかったけれど、和三盆糖を使い、一つひとつ地元の栗を手で剥いて作ったという栗きんとんは、絶品!でした。以前のブログでも書きましたが、まっちんの仕事場には、1、お金もうけに走らないこと2、自信のあるものだけをお出しすること3、習って少しでも努力すること…という貼り紙がしてあるのだそうです。今回のイベントを運営していたパン屋さんも、料理を作っていた人も、そしてまっちんも、自分なりのこだわりを持って、その基準に見合うものを作りたい!と、そんな信念があるのだと感じました。それは、恐らく「お金儲け」や「社会的地位」とは無縁の生き方でしょう。でも、ニュースを賑わせている“赤福”の包み紙を見るたびに、一般には成功者とみなされていたはずの経営者や従業員と、一見地味で不器用なこの若い人たち、どちらが「上等な生き方」といえるだろう?…と、考えさせられてしまうのでした。近々、伊勢に遊びに行って、赤福を食べるのが楽しみだったのに…本当に裏切られた気分!食べ物の恨みは恐いぞ~(…ニュースを見るたび、赤福が食べたくなって困るんです…)
2007.10.23
コメント(2)
-

焙じ茶の香に誘われて
携帯で撮った小さな写真でわかりにくいのですが、これは、ドライヴ中に偶然通りかかったお茶屋さんの店先です。緑色の四角い箱は、お茶を焙じる機械。中で焙煎されたお茶の葉が、少しずつ、下に置かれた茶箱の中に落ちていきます。辺り一面に、何ともいえない香ばしい空気が漂っていました。周囲は起伏の多い山里で、丘陵にお茶畑がきれいな縞模様を描いて広がっています。地元で作ったお茶を扱っているお店ということで、「この焙じ茶も上級品ですよ。焙じたばかりのをここでお詰めします」という店員さんの言葉と、何よりいい香りに魅かれて、お土産用も合わせて購入しました。一袋、100gにちょっとおまけで詰めてもらって300円也。【お茶の試飲もかねて、お店で出しているぜんざいをいただきました。】軒先に出された木のベンチに座って、小さい機械が一生懸命焙じ茶を作っている様子を見ながら、秋の陽を浴びてのんびり一服。少し湯ざましして淹れると美味しい緑茶に対し、焙じ茶は、淹れるお湯の温度が熱ければ熱いほど良いのだと教えてもらって、帰ってから早速、グラグラに沸かしたお湯でいただいてみました。お店で飲んだのと同じ、深い味わいで喉にささるエグみのない、おいしい焙じ茶を味わうことが出来ました。夫は舌を火傷して目を白黒させていましたが…(笑)温かい飲み物がしみじみ美味しい季節になったんですね。
2007.10.22
コメント(4)
-

君とならドーナツ
東京では、新名所にオープンした高級ドーナツショップに行列が出来ていると聞きますが、話題のお店には無縁の土地に住む私にとっては、憧れながらも高嶺の花。その代わり・・・と言っては何ですが、最近、ミスタードーナツの新商品「リッチドーナツ」ラインにはまっております。卵も、バターも、粉もグレードアップして、手に持った瞬間(フワァッ)と、今までのドーナツとは違う手触りが実感でき、初めて食べたときから一気にファンになってしまいました。もちろんお味も、これならお値段UPも納得の「リッチ」な風味に様変わりしていて・・・ただでさえ“食欲の秋”、おやつにしてしまうと明らかにカロリーオーバーなので、休日のブランチに(苦笑)。【ストロベリーミルクとキャラメルアーモンドがお気に入りです】夫は、基本的に酒飲みですが甘党でもあるため(体に一番悪いパターン!)、私のリクエストにも喜んでつきあってくれるのがありがたい。今日は秋晴れの週末、日当たりのいい席を選んで座り、ミスド独特の薄いカフェオレをお代わりしながら、ふわふわのドーナツを堪能いたしました。甘いものはこの世に数々あれど、ドーナツにかぶりついている時って、幾つになっても特別に「子どもの気持ち」に帰れるような気がするのは、私だけでしょうか。【暮しの手帖 10月号には、長尾智子さんのドーナツレシピが載っています】
2007.10.20
コメント(6)
-

のびろのびろ大好きな木
巷ではおしりかじり虫が大ブレイク中のようですが、私は、初夏に放映されていた「みんなのうた」では、カップリングされていた方の歌が大好きでした。それが、アン・サリーさんの歌う「のびろのびろ大好きな木」という曲です。当時自宅で療養生活を送っていたこともあり、毎朝、愛らしいアニメーションとともに、やわらかく温かみのあるメロディーと歌声に力づけられる思いでした。十代の頃から、大貫妙子のシルキーな声やデリケートな歌い方が好きで、アン・サリーの歌うジャズを初めて耳にした時も、同じような系列の声を持つシンガーと出会った!と一度でファンになりました。「のびろのびろ大好きな木」が収められた彼女のニューアルバムには、唱歌「椰子の実」や、石川セリが歌った武満徹の「翼」など、大好きな名曲が数々取り上げられていて、目下お気に入りの1枚です。アン・サリー /こころうたミュージシャンと心臓内科医、そして妻であり二児の母・・・という、私などの想像も及ばぬような才能とそれを活かす場に恵まれている彼女。それだけ多くの草鞋を履いてなお、歌声にはギスギスと疲れたところが微塵もなく、聴く側の心にゆったりと響いて、心地よい。それがすごいなあと思います。ちなみに、「のびろのびろ大好きな木」という曲で私が一番好きなのは、サビの部分の彼女の声の張り方で、それは朗々と歌い上げるのではなく、少し苦しげにも聞こえるような、肺活量の少ない感じ。それがかえって、私の耳に心地いい印象的な音色なのです。聞けば、レコーディング中はお子さんを妊娠中だったそうで、もしかしたらお腹が大きいということとも関連があるのかも?そう思って聴くと、命のあたたかみや重みがそのまま伝わってくるようにも思えて、歌を通じて、小さな存在への慈しみをじわりと感じ、感動してしまいます。理由もなく疲れを感じたり、ささくれ立つ心のトゲに悩まされる時に、そっと口ずさみたくなる、そんな歌なのでした。無料視聴はこちらから【初めてこの子(?)の歌を聴いたときのインパクトも相当なモノでした。】
2007.10.19
コメント(6)
-

「錦繍」を読んだ。
「生きていることと、死んでいることは、もしかしたら同じことかもしれない。」この本は、一組の男女が交わす手紙だけで構成されている、いわゆる「書簡体の小説」です。十年の時を経た偶然の再会をきっかけに、女が男にあててしたためた長文の手紙から、物語が始まります。往復書簡のやり取りをする二人は、かつては夫婦であり、ある事件をきっかけに、その結婚生活が破綻したのでした。再会の場所となったのは、秋の蔵王。そこから、14通の手紙が二人の間を往来し、1年後、ふたたび巡ってきた紅葉の季節に、その文通に終止符が打たれる…その間、二人は手紙を通して相手に向き合い、言葉を投げかけることで、自分の心に向き合っていく。過去を見つめ、現在を見つめ、そして最後には未来へ向かって、うなだれていたところからその視線を上げていきます。宮本輝の著書をそう多く読んでいるわけではありませんが、どの小説にも、登場人物の成長と、人間が生きていく上で逃れられない“因果”“因縁”の力、という要素があるように感じます。過去が、そして現在が、未来の自分を作る。そのかたちが、思いのままであろうとなかろうと…手紙の主である二人を引き裂いた出来事。そして、二人が現在、抱えている問題や悩み。それは、確率から言えば決して「よくあること」ではないかもしれない。…けれど、「あの出会いが」「あの出来事が」「あの選択が」あったから今、こうしているんだと思えるような、人生の分水嶺は、どんな人でも思い当たるのではないでしょうか。冒頭に紹介した一文は、女が、モーツァルトの音楽を聴いた感想として、何気なく頭に浮かべたという言葉です。人が人生という旅路を行く時、その道のりは厳然とした一方通行であり、誰一人時間を後戻りすることは出来ない。そして、行きつく先に命の終わりがある。でも、その終わりが始まりでもあるとしたら、一見ありきたりな人生でも、命の限りに生き抜くことに、やっぱり何がしかの意味があるのではないか。二人の交わす「手紙でしか言えない思い」を読み終えたとき、そんな、ちょっと青くさい、でも心地良い感慨に包まれました。この小説は、「大好きだ」という人と「べつに…」という人と、評が私の周囲では真っ二つで、そして私自身はどういう訳か、読みたいと思いながら今まで手にとらずに今日まで来てしまったのでした。きっと、本や映画や音楽との出会いにも“時機”というものがあって、それがどう自分の人生とリンクするかどうかで、心に残るかそうでないかが決まって来るのかもしれません。少なくとも、今、この年齢になって、この本との出会いがあってよかったと、心から思えた一冊でした。
2007.10.17
コメント(2)
-
ハスキーなおふく
着付けのお稽古に行ったら、先生から「いい陽気だから、お稽古の前に、ちょっとお庭でお茶でもいかが」と、庭先に出したテーブルに中国茶とお菓子を用意してくださいました。まっ白い、大きな花がたくさん下がったトランペットと、いい香りを漂わせる金木犀の木が、ちょうど私たちの座る椅子を取り囲んでいて、秋のお花見とも言えるような、贅沢なひとときでした。そこで、着物の模様のことが発端だったか、誰からともなく出た話題が、秋の七草。「せり、なずな…」と、何となく五七調の語呂合わせで覚えている春の七草に比べ、では秋は?と聞かれると、スラスラ言える人は少ないのではないでしょうか。実際、その場でも、桔梗と、萩と、えーっと…と、一同、七つ思い出すのに四苦八苦してしまいました。そこへ、お茶を淹れながら私たちの会話を耳にされていた先生から、突然「ハスキーなおふくよ」という発言が。はぁ??何がハスキー??とキョトンとしていたら、それが秋の七草の覚え方だとのこと。つまり、ハギ (萩)ススキ (尾花=薄)キキョウ (桔梗)ナデシコ (撫子)オミナエシ (女郎花)フジバカマ (藤袴)クズ (葛)の頭の文字を取って並べた語呂合わせなんですね。最近、朝晩は肌寒いほどの陽気になり、その時も戸外に座っていると体が冷えてくるのを感じて、早々に室内に戻りました。そのせいか、口の中で(ハスキーなおふく)と繰り返すうちに、季節の変わり目に風邪をひいて、声を枯らしているお福人形の様子なんぞを連想してしまい、笑いながら、これならしっかり覚えて忘れないぞと思ったのでした。
2007.10.16
コメント(4)
-

今日もていねいに。
今年に入ってから、雑誌「暮しの手帖」をまた購読し始めました。子どもの頃、祖母と母が定期購読していたこの雑誌を、飽かずに繰り返し読んでいたものです。先ごろ編集長が交代して、いくらかは誌面も刷新されたのでしょうが、何しろブランクが長かったせいか、変化を感じるというよりは(あぁ、懐かしい)という思いが先に立ちます。あとがきにあたる「編集者の手帖」というページの最後の一文に、新編集長の松浦弥太郎さんはいつも、同じ一行を書かれています。曰く、今日もていねいに。・・・思えば、「丁寧に」暮すということは、言葉の上ではたやすくても、実行するのは意外と難しいものです。目の前のことにしっかりと集中する。それだけのことが、一日の中でどれくらい実現できているだろう?何をしていても、頭の中では時間に追われ、「次にやらなければいけないこと」とか「前にやれなかったこと」がいつもよぎっているのではないか。段取りよく、要領よく・・・そんなことにばかり頭を使っていて、その分、心を使って目の前の世界を味わうこと、それを忘れていないだろうか?ふと立ち止まると、そんなことを痛感させられます。だけど、大人になって生活に追われているってそういうものじゃないの?と思う一方で、初々しさが大切なの人に対しても世の中に対しても人を人とも思わなくなったとき堕落が始まるのね 墜ちてゆくのを隠そうとしても 隠せなくなった人を何人も見ましたという、茨木のり子の詩の一節を思い返し、何だか頭をかきむしりたくなるような思いに捉われたり。さて、今年も誕生日が来て、38歳になりました。正解やお手本のない「生きる」という課題を、明日からも、今日や昨日までと同じように、笑ったり泣いたりしながら、ゴールへ向かってこなしていくのでしょう。今年、夫からのバースデープレゼントは、大好きなクレイジーケンバンドのコンサート(@大阪フェスティバルホール)。いつもは、大阪や名古屋でライヴを聴いた後は、最終の特急列車に飛び乗るため慌しく帰路につくのですが、この日はお泊りつきというオマケもあり、でした。時間を気にすることなく会場を後に出来るというだけで、十分優雅な気分になれました。夫に感謝です。アンコールのラストは、ニューアルバム「SOUL電波」の中でも大好きなナンバー、「生きる。」でした。【リッツカールトンの朝食の焼きたてパンケーキが大好きなのです。】【もう一つのプレゼントは、大島紬の名古屋帯。】至らぬなりに、せめてわが身の幸せを自覚し、それに見合うだけの周囲への恩返しの気持ちを忘れないでいたい・・・と、そんな思いを新たにした誕生日の一夜でした。
2007.10.12
コメント(14)
-
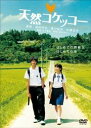
「天然コケッコー」を観た。
くらもちふさこの原作漫画は読んだことがなかったのですが、もうすぐ消えてなくなるかもしれんと思やあ、ささいなことが急に輝いて見えてきてしまう…というキャッチコピーと、監督:山下敦弘(“リンダリンダリンダ”)脚本:渡辺あや(“ジョゼと虎と魚たち”“メゾン・ド・ヒミコ”)音楽:レイハラカミエンディングテーマ:くるり…という、私にとっては「ど真中ストライク」なスタッフ陣の名前に魅かれて、公開前から興味津々だった映画。やっと観る機会に恵まれました。小学校と中学校、合わせて全校生徒が6人しかいない村の分校。その最上級生である主人公の女の子が、中学2年の夏から過ごす、2年あまりの日々を描いた物語。東京から、「イケメンさん」の転校生がやって来た日から映画が始まるけれど、二人の初恋の顛末を描いたラブストーリー…というのとは、ちょっと違う。山と田畑に囲まれた集落で、小学生が中学生に、中学生が高校生に、一歩一歩大人への階段を上っていく。分校の子どもたち、一人ひとりが「田舎の子」というくくりではとてもまとめられない、美しい個性を際立たせていました。その日常を描く上で、「密度の濃さ」と「省略の潔さ」が見事に同居しているところが、すごくよかったです。普通なら、ここをもう一歩踏み込んで、泣いたり笑ったりさせたくなるだろうところを、あえてサラリと流す脚本のテイストに、グッと来てしまいました。それなのに、一つひとつの場面で、映画の中で流れている空気の濃密なこと。日曜日の午後、テレビはマラソンと競馬とゴルフしかやっていなくて、仕方なくマラソンをつけているけど、そのうち何となく眠くなってくる…こんな、誰の生活にもあるようなひとときを描いて、じっと観る側の視線を引きつけてしまう。そういう、いつまでも余韻を残すシーンの連続なのだけれど、きっとこの映画、誰かに説明しようとすれば「淡々として、何も起きない映画」という言葉に落ち着いてしまう、不思議な作品だと思います。好き嫌いは分かれると思いますが、私はこの映画、エンドロールの最後の1秒まで、とても心地よく堪能しました。この監督は、「いつの日か、このことをきっと眩しく思い出す」と、あらかじめわかっていながら過ごす、そういう時間の味わい方にとてもこだわりがあるのでしょうね。(そして絶対“校舎フェチ”!)教室でおもらしすることもある分校の小1、さっちゃんの愛らしさと、一緒のクラスにいたら絶対好きにならないわけがないよねーと思わせるイケメン転校生、大沢くんにノックアウトされてしまった私です。【公式サイト】 http://www.tenkoke.com/【過去のブログから】「リンダリンダリンダ」を観た。※「いってきます」じゃなくて「いってかえります」、「ただいま」じゃなくて「かえりました」…という、初めて耳にする(島根の?)方言が、とっても印象的でした。
2007.10.10
コメント(8)
-

昭和47年の七五三
実家の父から封筒が送られてきて、何かと思ったらDVDが入っていました。ディスクには手書きのマジック文字で「想い出の映像」(!)とタイトルが…一体何ごと?と思い聞いてみたら、家の整理をした時に、昔撮った8ミリフィルムが大量に出てきたとのこと。すでに映写機は手元にないため、DVDにダビングする業者を探し、試しにフィルムの一部を出してみた。そうしたら、サービスでもう1枚ディスクを焼いてくれたから、そっちに送ってやった・・・と、そういうことだったらしい。何が飛び出すやら?と、恐る恐る再生してみましたら、今から35年前(!!)、私が3歳の時の七五三の映像でした。横浜の総鎮守、伊勢山皇大神宮にお参りに行った様子が映っています。境内の石段は大賑わいです。着物姿が多い・・・というのが、第一印象でした。主役の子ども達はもちろんですが、付き添い役の大人の側も、女性はほぼ100%が着物。画面を横切る人々の眼鏡が、一様に太い黒縁だったり、男の子が真っ赤なベレー帽をかぶっているところにも、時代を感じます。紅葉柄の小紋を着ているのが、三十代に差し掛かったばかりの母です。横にいるのは、当時同居していた祖父母。祖母のように、黒羽織をまとった女性の姿は、他にもたくさん映っていました。大人たちに囲まれ、千歳飴と記念品を両手に持って、アップアップ状態なのが、当時3歳の私であります。一緒に映像を見ていた夫が「連れてこられた宇宙人か」と爆笑していましたが…画面の主役である女の子は、慣れないものを着せられ、不自由さと非日常の状況に、完全に思考停止状態に陥っている様子。大人たちがカメラに笑顔を向けている中、ニコリともしません。…われながら情けない(苦笑)映像は、お参りの後、神社のすぐ近くにある祖母の実家を訪ねたところで終わっていました。死んでしまった人たちが元気だった頃の姿が、たくさん出てきた3分間でした。動く映像の中に閉じ込められた過去というのは、写真とはまた違うリアリティがあって。音声も無く、暗い色調の粗い画像でありながら、記憶の中の家族が、そして、幼い自分の目を通して見ていた風景が、様々に呼び起こされました。それは、一瞬、胸が苦しくなるほどの経験でした。そんな、未来の自分の感慨も知らず。かしわ手を打つべきところで、パチパチと延々拍手を続ける、悩みなき3歳の私です。
2007.10.08
コメント(10)
-

やっぱり絹が好き
このところ、空気もすっかり爽やかになり、秋が深まっていることを実感します。暑い夏の間は、じゃぶじゃぶと洗える木綿の浴衣でさえ、着ていくうちにすでに汗がにじんでくる有様…ましてや、精進の足りない私には、単衣の夏着物なんてまだまだ遠い存在、と思っておりました。…が、季節も巡って、また袷のシーズン到来です。この秋は、着物で行けたらいいな、と思えるお出かけの予定もいくつかあって、あれこれとコーディネートを考えているところ。とはいえ、手持ちの着物は数枚しかないので、選択肢もごく限られています。悩みが少なく済んで、いいことかもしれませんが(笑)新しい着物や帯は増えませんが、収納スペースをあまり取らない、着物まわりの小物類(帯締めや帯揚げ等)は、気に入ったものを見つけるとつい手が出てしまいます。先日は、前から買おう、買おうと思っていた正絹の腰ひもを、やっと購入しました。【3本セットのこんな感じのものです。】1年以上お稽古に通っているとはいえ、着付けの腕も知識も、まだまだ初心者の域を出ない私ですが、もし、これから着物を着始めたい!という方にアドバイスできることがあるとすれば、それは「ひも類は、絹に限る」…この一言に尽きます。そういう私も、最初に着付け小物を揃えたときは、手軽な一式セットだったこともあって、伊達締めはマジックテープ式のベルト、腰ひもはモスリン…という感じでした。(お稽古している先生の方針で、コーリンベルトの類は使っていません)でも、お稽古仲間の方からある時、正絹の腰ひもをお借りしたことがあって、モスリン製との違いにビックリしました。とにかく滑りがいいので、もたつかず、スムーズに着物の上で締まってくれます。ともすれば、決めた形がだらしなく崩れてしまう初心者の私にとって、これはとってもありがたいことでした。伊達締めも同様で、博多織りの伊達締めの、背中で“シュッ!”と締まってくれる快感を覚えてしまうと、もう以前使っていたものには戻れない…というのが、実感です。絹のものとはいえ、腰ひもも伊達締めも、探せば千円札で手に入れられるもの。でも、買ってよかった!という満足感は、まさに「お値段以上」でした。外には決して見えない小物ではありますが、だからこそ、年に不釣り合いなほどのラブリー系な色柄を選んだりして、密かに喜んだりしているのです。こんなところも、洋服のおしゃれにはない楽しみ方ですね。
2007.10.04
コメント(4)
-

ベティとちりとてちん
10月、下半期の始まりです。ついこの間まで残暑を感じていたのに、気候も急に秋めいてきたようです。市中の郵便局は、何やら唐突な印象のオレンジの看板を掲げ、テレビは番組改編期の特番シーズン。昨日から、NHKの連続ドラマも新しく「ちりとてちん」が始まりました。今年の3月まで放映されていた「芋たこなんきん」が大好きで、毎日夢中で見てしまった私。この半年は、すっかりドラマ離れしておりました。…が、昨日見た第一回の放送、15分のドラマの中で、何度ふき出したり、声をあげて笑ってしまったことか。セリフやアクションだけでなく、「間」で何とも言えないおかしみを醸し出す。テンポの良い展開と、役者さんたちの絶妙なやり取りに、すっかりノックアウトされてしまいました。舞台となる小浜には、その昔、友人を訪ねて遊びに行ったこともあり、懐かしかったです。本当に静かな、穏やかな空気の流れるところでした。主人公(現段階では小学生)の女の子の、すぐに妄想が炸裂していく性格は、今後もどれだけ笑わせてくれるかと期待してしまいます。ブログ上で交流させていただいている、1go1exさんが、このドラマのガイドブックに携わられたことを知り、早速購入してみました。このところ、「内なる落語ブーム」に火がつきかけている私にとっては、ガイドブックの落語ガイドはとても興味深く、勉強になることばかり。これからの半年間、「ちりとてちん」で、落語の世界に一層馴染んでいけたら嬉しいです。朝のひとときに、心の内側からちょっと元気にさせてくれるような、そんな楽しいドラマになってくれるといいなぁ、と思います。もう一つ、放送開始を楽しみにしていたのが、NHK‐BSの海外ドラマ「アグリー・ベティ」。ゴールデン・グローブ賞を受賞した際の、主演のアメリカ・フェラーラの歓喜を爆発させる様子が、とっても好感度大で印象的でした。冴えない女の子が、ひょんなことからモード誌の編集部で働くことになり…というお話は、何やら既視感がありますが(笑)米国で生きるラテン系の人々の現実を描くという、シリアスな側面も含めて、期待通りの面白さ。45分があっという間でした。プロデューサーに名を連ねる女優のサルマ・ハエックは、ラテン系俳優の地位向上を目指す活動にも積極的だと聞きます。(ちなみに彼女は、主人公一家の居間のテレビで流れるソープ・オペラの女優としてカメオ出演していました。)「ER」は今やすっかり見る気がせず、「デスパレートな妻たち」は1stシーズンの途中で脱落してしまった私ですが、久々にはまる海外ドラマとの出会いとなるか?これから、月曜の夜が楽しみです。
2007.10.02
コメント(6)
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-
-

- 今日のお出かけ ~
- バス旅 久しぶりのセンター南
- (2025-11-16 22:33:33)
-
-
-

- 運気をアップするには?
- パワーブレスレット・ラピスラズリは…
- (2025-11-16 22:07:47)
-
-
-

- ★「片付け・お掃除・捨てる」の成果★
- 台所の在庫整理しよう❗️
- (2025-11-16 18:00:04)
-







