2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年04月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

ポルトガルの旅 ~街歩きその2~
かなり間が空いてしまいましたが、前回のブログの続きです。ポルトガルに行って来たの、という話を友人としていて「ポルトガルって、リスボン以外の街を知らない」という反応がほとんどだったのですが(かつては私もそうでした)・・・ひなびた小さい街に、16~18世紀の美しい遺産が点在していて、旅して回るのに飽きない国でした。【同行者がかつて留学していたコインブラ大学の旧校舎】【美しい後期ゴシック様式のバターリャの修道院。世界遺産】 【漁村から、海辺の観光地へ姿を変えつつあるナザレの海岸。】 【ナザレの海岸通りで、文字通り『死んだように眠る』最中・・・】 【シントラの王宮。伊藤マンショら、天正の少年使節団も訪れた白鳥の間】 今回の旅行はフリーの個人旅行でしたが、公共交通機関ではどうしても効率良く回れない土地も多く、一日」、グレイラインのツアーバスに乗り込んで、近郊の観光地を周遊しました。リスボン版「はとバス」という訳ですが(笑)外国人用のバスでは英語・仏語・独語・西語のガイドを一人のおばさんが務めるという、その離れ業にビックリしました・・・(西欧の人にとってはそんなに大変なことでもないのかもしれませんが)。【そのバスの最終目的地が、聖母マリア降臨で知られる聖地ファティマ。】 私たちが訪れたときも、後から後から、このような巡礼の大集団が、賛美歌を高らかに歌いながら、バジリカを目指し大広場を横切って歩いていきました。第一次世界大戦の最中、三人の羊飼いの子ども達の前に、聖母マリアが出現して予言を残した、というのが「ファティマの奇跡」。コンピューターとインターネットの時代に、今もなお、その奇跡に触れたいと純粋に願う人たちが存在する。敬虔な、そして強烈な信仰心が、かえって悲劇を巻き起こしている現代社会。でも、ひざまづいて真剣に祈る人々の姿には、ただの傍観者に過ぎないこちらが、軽々しく批評めいたことを口に出来ないような迫力があり、崇高さがあり・・・気がつくと、いつの間にか涙ぐんでいる自分に気がついたのでした。
2007.04.29
コメント(8)
-

ポルトガルの旅 ~街歩きその1・リスボン篇~
デジカメというのは本当に便利なもので、フィルム式のカメラを使っている時と比べて格段にシャッターチャンスの範囲が広がりました。新しい機種になればなるほど、機械は小さく、データは大容量になり・・・それにつれて、目についたものは何でもパシャ!取りあえずパシャ!同じところを何回もパシャ!(笑)という訳で、昔に比べると比較にならないくらい膨大な量の写真が、旅を終えた私の手元に残りました。「好きこそものの上手なれ」とはなかなか行かず、あまり撮影の腕は良くないのですが、街歩きの雰囲気が少しでも伝わればうれしいです。【7月24日通りのツーリング大会】リスボンは、とにかく坂の多い港町。遥かにテージョ川を見下ろす急斜面の上り下りに、こんな旧式のケーブルカーが活躍していました。【リスボンの風物詩ともなっている、ビカのケーブルカー】【街の中には、丘の上と下の地区を結ぶ古いエレベーターもある】【エレベーターの上部にある展望台からの眺望。】リスボンは、海ではなく、スペインとポルトガルをつないで流れるテージョ川の河口に面した港湾都市です。川辺のベレン地区には、世界遺産に指定された歴史的建造物など、観光名所が集まって賑わっていました。【ヴァスコ・ダ・ガマが眠る世界遺産、聖ジェロニモス修道院の全景。】【1960年、大航海時代を記念して建てられた「発見のモニュメント」】これは、エンリケ航海王子の没後500年にちなんで建てられた建造物。先頭に立つ王子のほか、大航海時代の偉人たちの像が大西洋の方を向いて並んでいます。その昔、世界史の教科書で初めて「エンリケ航海王子」という名を目にしたとき、その字面から勝手な、一方的な思い込みで、「海のトリトン」みたいな素敵な美少年をイメージしてしまった私(!)後日、その肖像画を見て(・・・オッサンじゃん!!)と、これまた勝手にガッカリしたのでありました。ごめんね、王子。ちなみに、このモニュメントの前の地面には、大理石で描かれた大きな世界地図があり、ポルトガルがそれぞれの国に初上陸、つまり“発見”した年月日が刻まれています。【もちろん、わが日本も・・・ありました!】 【16世紀、船の出入りを監視する要塞だったベレンの塔。世界遺産】私たちが訪れたとき、ちょうど潮が引く時刻だったのか、あるいは普段より水位が減っていたのか?いつもは隠れているらしき岩場が顔を出していました。そこへ、バケツを持った父子らしきオジサン二人連れが登場。桟橋からヒラリと岩場に飛び降り(どう見ても立ち入り禁止区域)、やにわに始めたのは・・・【なんと、沢ガニ獲りでありました。ものすごい勢いで岩を裏返す!】世界遺産の足元でも、日常の暮らしは確かに息づいている。オジサン達の気合いのこもった漁(?)の様子は、忘れられない光景になりました。
2007.04.23
コメント(8)
-

ポルトガルの旅 ~食いしん坊万歳
旅の喜びには色々なものがありますが、行く先々で出会う「未知なる美味しさ」を体験することは、中でも(私にとっては)忘れられない思い出になります。・・・ということで、以下ご紹介するのは、ポルトガルで味わった美味しいモノの数々。レストランで席につくと、大抵、メニューを決める前から、パンの籠とオリーブやチーズといった「つき出し」が席に置かれます。これは要らなければキャンセルできるのですが、お腹が空いていると、ついついそれらに手が出てしまいがち。でも、うっかり食べ過ぎると後が大変でした。何しろ、お料理は大抵の場合、日本人女性にはかなり厳しいボリュームだったので・・・【コインブラの小さなレストランでいただいた、ある日の夕食。】この日、私と友人が頼んだメニューは、スープ二種類に、たこのリゾットと干し鱈の卵とじ炒め。bacalhau(バカリャウ)と呼ばれる干し鱈は、調理法が365以上、つまり1年間毎日違った料理でも食べられる・・・と言われるくらい、ポルトガルではポピュラーな食材なんだとか。ちなみに、干物状態のものを水で戻して、塩抜きして使うそうです。上の写真のお料理などは、千切りのタマネギやじゃがいもの甘味と、鱈の程よい塩気がマッチして、とても美味しかったです。【ちなみに売られている時はこんな感じ。リスボンのスーパーにて】殆ど下戸に近い私ですが、若い葡萄から作られた発泡性のヴィーニョ・ヴェルデと呼ばれるワイン(甘口のシャンパンのような飲み口で、冷えたところをいただくと美味しいのです)をちびちびと飲みながら、毎夜のディナータイムを満喫しました。【こちらは街角の小さなマーケット。買い物籠も一緒に売られていました】ポルトガルの食文化に触れる上で、もう一つ楽しみだったのがカフェ巡り。何しろ「カステラ」や「金平糖」の源はこの国にある、というのが通説ですから・・・一番気に入って、あちこちの街で食べ比べをしたのが、日本でもちょっと流行ったことのあるエッグタルト、Pasteis de Nata(パステイシュ デ ナタ)でした。【行列の出来る“元祖の店”、リスボンの「パステイシュ デ ベレン」にて】このタルトをはじめ、とにかくポルトガルスイーツは卵、卵、卵という感じで、だからこそ素朴な“お母さんの手づくり”的な美味しさを堪能できました。(しかし、コレステロール値が跳ね上がっていそうでちょっと怖い気も・・・)上の写真に写っている飲み物は、galao(ガラオン)と呼ばれる、要するにミルク多めのカフェオレです。(通常はガラスの大ぶりなグラスで供されることから、この名が)ポルトガルの人たちも、ヨーロッパ諸国の例に漏れずカフェが大好きだそうですが、好まれるのはエスプレッソだそう。私は濃い目のコーヒーは苦手なもので、もっぱらこのガラオンか、もう一つ・・・友人に教わって大好きになった、この飲み物を注文していました。 【cha de limao(シャデリマオン)。直訳すれば「レモンティー」ですが】作り方は、剥きたてのレモンの皮をカップに入れて、上から熱湯を注ぐ・・・だけ!(写真のお店では、ミントの葉を浮かべてくれています)本当にそれだけなのに、レモンのアロマが湯気と共に立ち昇り、味もすっきりと爽やかで、満腹になった食後の口と胃には最高でした。外国産の、防腐剤漬けのレモンが多く流通している日本では、ちょっと怖くて簡単には真似できないのが残念ですが・・・無農薬のレモンが手に入ったら、ぜひ家でもやってみたい、と思いました。唯一、「私にも作れる」と持ち帰れた、ポルトガルの味です(笑)※滞在中、いつも買って飲んでいたのが、LUSOというミネラルウォーターでした。軟水でとても美味しく、採取源となっている同名の町も、訪れたらのんびりとした保養地でいい所でした。帰国後、楽天でメルカード・ポルトガルという輸入食材のお店で扱っているのを発見。いやぁ、何でもネットで買える時代なんですね・・・
2007.04.22
コメント(6)
-

ポルトガルの旅 ~アズレージョの世界~
「ポルトガル」と聞いて、リスボンという首都の名前や、歴史上でその国が果たした大きな役割のことはすぐに思いついても、じゃあ何がある?じゃあ何処へ行きたい?・・・と考えて、サッカー選手とロカ岬の他、すぐには思いつかなかった私。例えば、それが同じイベリア半島で隣り合っているスペインなら、行ってみたい街の名や訪れたい名所旧跡がいくつも思いつくのですが。実際に訪れてみて、歴史や地理的条件が生み出した独特の文化が、今に息づいている姿に数多く触れることが出来ました。中でも、建物や街並に多く使われている「アズレージョ」と呼ばれるタイルの装飾は、これまで訪れたヨーロッパの国々では見たことのないものでした。それは、多くは青色の染付けで、大きなものではこのように建物の外壁を壁画のごとく飾っています。【アヴェイロにて。この駅舎は見事なアズレージョで有名】【同じくアヴェイロにて。カテドラルの外壁】このアヴェイロという街は、ヴェネツィアには遠く及ばないものの、街中を運河の水路が走っていて、モリセイロというゴンドラが浮かぶ様子が風物詩となっています。それと同時に、様々なタイル細工で飾られた家々が並ぶ、チャーミングな通りの光景が印象的でした。よく見ると、古い家や教会の手描きで描かれたタイルと、いかにも「大量生産」という感じの、プリントされた感じがありあり出ている模様のものが混在しているのですが、それらを見比べながら歩くのもまた一興、でした。【アヴェイロの街角】アズレージョは、室内の装飾にもふんだんに使われています。【コインブラのサンタクララ修道院にて】【シントラの王宮の広間。ここは天井の細工も見事でした】タイル細工が発展したのは、イベリア半島をかつて支配していたイスラムの影響はもちろん、オランダや中国・日本といった、交易を通して陶磁器の生産が盛んな国々とのつながりが生まれたことに由来するようです。その流れの一端なのか、ポルトガルではどの街でも、石畳が様々な白と黒のモザイク模様になっていて、見比べてみるのも楽しかったです。海沿いの街では、蟹や貝や魚など、海産物の絵で舗道が埋め尽くされていたりしました(笑)【リスボンで一番の目抜き通り、リベルターデ大通りにて。】アズレージョと並んで、ポルトガルの建築で独特なのが「マヌエル様式」と呼ばれる装飾。「マヌエル」というのは、ヴァスコ・ダ・ガマがインド航路を発見し、ポルトガルが海洋国として栄華を極めた時代を治めた国王、マヌエル1世を指します。という訳で、大航海時代のエッセンスを凝縮するかのごとく、異国の動植物とか、ロープや碇といった船にまつわるモチーフを意匠化した細工で、とにかく飾る!飾る!【世界遺産、リスボン・聖ジェロニモス修道院の回廊】侘び寂びの美を重んじる国から来た身としては、正直「もうカンベンしてください」という気もしないではなかったのですが(欧州を旅すると、必ずこういう“目の消化不良”を起こしてしまう私・・・)。それでも、500年以上前に、これだけのものを築き上げて神に捧げた、その偉業にはひたすら敬服するばかりでした。その一方で、ありふれた街角にふと現れる建物に、思わず足を止めずにいられない素敵な趣きがあったりして。そんな瞬間も旅の楽しみの一つなのですよね。【コインブラの広場で見かけた、小さなホテル。】この屋上の雰囲気、まるでウォン・カーウァイの映画「2046」に出てきそう・・・
2007.04.20
コメント(8)
-

帰国しました。
10日間におよぶポルトガル旅行を終えて、おかげさまで無事に帰国いたしました。現地は、春の真っ只中という感じの陽気。幸い、滞在中は天候にも恵まれました。憧れだったロカ岬には、旅の最終日に、電車とバスを乗り継いで出かけました。ユーラシア大陸の最西端。そこに立つという『ここに地終わり、海始まる』という碑文から、私が抱いていたのは「最果て」の地の荒涼としたイメージでした。でも、青空の下で、明るい陽光に照らされたその岬は・・・色とりどりの花が咲き乱れ、多くの観光客がのどかにくつろぐ、穏やかな場所でありました。大西洋からの風を受けて、地図の上で自分がいる場所を思い描きながら、記念に・・・と夫の携帯にかけてみました。500年前に、多くの船乗り達が、未知の大陸を探しに旅立った海。その大海原を目の前にしながら、遠い遠いはずの日本との通話は、驚くほどクリアーでした。この光景が、宮本輝のこの本の表紙で安野光雅画伯が描いている場所です。まだ見ぬ土地を捜し求めて、この海に漕ぎ出すことは、その昔は命をかけた大冒険。ポルトガルが栄華を極めた大航海時代が、今に至るグローバリズムの、まさに“最初の一歩”だったことを考えれば、現代の地球の狭さ、便利さが、いっそう感慨深く思えました。思えば今回の旅も、ネットで航空券とホテルを予約し、後は出かけるだけ。と、国内旅行に出かけるのとまったく変わらない手間しかかけなかった訳で・・・そのお手軽さに、未だに半信半疑な思いを抱いてしまう、時代遅れな私です(笑)水平線が見えるかと期待していたのですが、空と海とはすっかり融けあっていて、ただただ深い青色が眼の前に広がるばかり。ゴダールの「気狂いピエロ」を思い出させる光景でした。これからブログで少しずつ、旅の思い出を写真でご紹介していきたいと思っています。※おまけ※折りしもこの日、岬に通じる峠道では、大勢のバイクレーサーが集会中(?)駐車場では、こんなバイクにも遭遇しました。これがほんとの「ホンダ」製・・・?今回もお世話になりました。(ポルトガルには直行便がないため、パリでトランジットするエールフランスでリスボンまで行きました)
2007.04.18
コメント(8)
-
ここに地終わり 海始まる
北緯38度47分、西経9度30分。ユーラシア大陸の最西端、いわゆる「世界地図の左端」の地が、ポルトガルのロカ岬です。タイトルに掲げた一節は、岬に立つ十字架に刻まれた碑文。国民的詩人、カモンエスの叙事詩の一部です。横浜生まれの私が、地図の見方を最初に習った子どもの頃、一番強く心に感じたことは“あぁ、私の家は、『端っこ』にあるんだなぁ”ということでした。それ以来、大人になった今でも、海辺に立つと「今、陸と海の境目にいるんだ」と、頭の中に白地図の線を思い描いたりします。大航海時代、多くの船が見知らぬ陸地を目指して大西洋に旅立った・・・そんな国へ行ったら、その時には地図の線どころではない、深い感慨が胸を満たすのでしょうか。いつかは行って見たい、ロカ岬という場所に立ってみたい・・・そんな憧れをずっと抱いておりましたら、幼馴染みが「仕事を辞めて、1ケ月くらいポルトガルに行ってくる」という。彼女は、大学でポルトガル語を専攻し、現地で短期留学をしていた経験もあります。大げさに言えば『人生の一区切り』に、若い日に学んだ思い出の場所を再訪したい、という思いがあるらしく・・・それはいいわねぇうらやましいなぁ・・・と言っていたら「一緒に行かない?」と誘われて、ビックリ。でも、なぜか?自分でも思いもよらないことながら「・・・行こうかな。」という言葉が、口をついて出ていました。体調が万全ではないし、収入もかつてに比べれば激減しているというのに、何でまた・・・と、我ながら呆れるところではあるのです。でも、病気とその治療という経験は、いくらか私を内省的にし、今日は二度と来ない、ということを強く思うようになりました。いいことも、悪いことも、巡りあわせによって私のところへやって来るなら、臆病にならずに向き合っていきたい。美味しそうな実がなっていたら、しっかりと手を伸ばして掴み取りたい、と。そんな訳で今週、ポルトガルへの旅に出発します。旅程は10日間。帰国後、またこのブログで、楽しい旅の記録を綴っていけたらと願っています。
2007.04.08
コメント(6)
-

シネマ歌舞伎と桜の京都
あいにくの雨混じりの中、日帰りで京都へ行って来ました。一番の目的は、寺社仏閣でも都おどりでもお花見でもなく、映画館です。松竹が、ここ数年の新たな試みとして、歌舞伎の舞台を映像化して映画館で上映する「シネマ歌舞伎」というものを作っているのは知っていましたが、最新作が「京鹿子娘二人道成寺」だということは知りませんでした。愛読している1go1exさんのブログで、坂東玉三郎と尾上菊之助の二人による、この絢爛豪華な舞踊がシネマ歌舞伎になっていること、そして今春大阪と京都を巡回しているという情報をいただいて、居ても立ってもいられなくなった・・・という次第。“道成寺”は、安珍清姫伝説を下敷きにした歌舞伎舞踊の大舞台。通常は一人の女形が演じる白拍子の「花子」(実は清姫の怨霊)を、二人で演じるという趣向は以前もあったようです。ただ、これまでは「花子」と「桜子」という二人の女性が舞い踊る・・・という設定だったのを、あえて「花子」と「花子」、つまりは一人の人間が幽体離脱したような状況を、二人の舞で演出しているのが、今回の“二人道成寺”という訳です。この「一人の女を、二人の女形で」というアイディアは、玉三郎さんの発案だったとか。私は、初演の際に歌舞伎座で生の舞台を観ているのですが、その時は“ただでさえ美しいものが、さらに2倍になって出て来た!”・・・そのことのゴージャスさに、ひたすら目を奪われていただけだったように思います。当時の劇場内のポスターで、菊之助さんの役名は、シールで訂正してありました。恐らく最初は「桜子」の設定だったのでしょう。それを、同じ衣裳を揃え、振付も時には驚くような同調性で、本当に「花子の体から、魂が抜け出した」ように見える瞬間があり。(松竹シネマ歌舞伎公式サイトにて、予告編を公開中。一人が二人に・・・の瞬間が観られます)今回、改めて「シネマ歌舞伎」でじっくりと鑑賞してみて、なるほど・・・と思いました。陰と陽、純情と情念、あどけなさと大人の色香・・・そのような相反する要素が、一人の恋する女の中に混在している。その様子が、二人の微妙な佇まいの差によって、くっきりと浮かび上がっていると感じたのです。正直、(いつかDVDが出るかもしれないし・・・)と思っていたのですが、実際に劇場で観て、映像と音質の素晴らしさに感激しました。花道から登場する役者の声や衣擦れの音は、ちゃんと左後方から、つまり、劇場の1階席で見ているのと同じように聞こえてくるのです。私などは、歌舞伎を観ると言っても、天井桟敷ならぬ4階幕見席の常連なので(笑)それだけでも豪勢な気分を味わえました。時間があまりなかった上にお天気も今ひとつで、せっかくの京都も花見の名所へは足を伸ばせずじまいでしたが、祇園近辺をぐるぐると歩き回っただけでも、満開の桜をそこ此処で見られました。そして何より、“道成寺”は舞台も衣裳も桜尽くし。スクリーンの中は艶やかな桜が満開で、ある意味素晴らしいお花見体験。いい一日でした。【高瀬川沿いの桜並木。花びらがチラホラ川面に散っていました】【鴨川の夜桜 水面にもライトアップされた花影が映ります】※おまけ※【木屋町にて、高瀬川にダイブするノラ猫さん。酔い醒ましですか?】
2007.04.07
コメント(2)
-
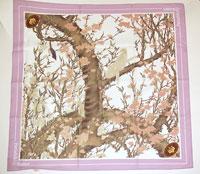
お土産・日本代表
総理官邸が、これまで特に定まったものがなかったという、海外からの賓客に対しての「お土産」を公式に作った・・・という話題を、先日のニュースで見ました。それは、日本人形でもなく漆器や陶器でもなく・・・ペットボトルを再利用した布地で作られたという、「風呂敷」。エコロジカルな日本の伝統もアピールできる、というわけですね。お土産はかさばらないものが一番だしね~って、自分がもらうわけでもないのですが(笑)それにしてもこのデザインといい質感といい、風呂敷というよりスカーフのような・・・ところでこの図案に、何か見覚えがあるような??と思っていたら、伊藤若冲の動植採絵と聞いてビックリしました。北斎でもなく、歌麿でもなく、写楽でもなく、若冲ですか!私見ですが、もし、一昔前にこの企画が実現していたら、絶対に選ばれていなかった画師だと思うのです。それは、作品の良し悪しに関係なく、単に「認知度」という点に置いて。私たち自身の多くが、「日本のイメージ」をアピールする時に思い描く作家と言われて思いつくのは、今まではもうちょっと違う人々だったような。【例えば、メジャー級のこんな感じ??】しかし、昨年、東京で開催されて「若冲と江戸絵画展」は、1日の入場者数が世界で最も多かった展覧会だったそうで・・・。私も、現実を超越した絢爛豪華な「絵にしか書けない美しさ」(by辻静雄)を持つ若冲の絵画には大いに魅了されます。日本では長い間忘れられ、海外のコレクターによってその価値を見出される方が早かったという、若冲。「日本画」の固定観念を覆す、現代的な鮮やかさ・華やかさは、外国からのお客様には歓迎されるかもしれませんね。浅草や京都によくある「日の丸ハチマキ」や「一番Tシャツ」とは、色々な意味で対極の「お土産日本代表」のお話でした。そして、ちょっと調べてみたところ、小池百合子女史が環境大臣だった時代に、すでに「もったいないふろしき」として、若冲の絵を用いた風呂敷が作成されていたんだそうです。(つまり、今回の“お土産プロジェクト”はその延長線上、ということなんですね)惜しむらくは、これらの官製「若冲風呂敷」、市販される様子のないことで・・・官邸のお土産用はムリとしても、「もったいないふろしき」なら、啓蒙用に配るだけではなく、販売して収益を環境問題のために有効活用してもいいのでは?と思ってしまったのは素人考えでしょうか・・・【若冲再発見のきっかけを作ったとも言われる名著が文庫化。】この本もですが、著者の辻先生が講師を務めたNHK「知るを楽しむ」、毎回すごく面白かったです。※上記の北斎の風呂敷は、楽天の風呂敷専門店こざくらで取り扱っています※
2007.04.05
コメント(4)
-

「シムソンズ」を観た。
金メダルを取ったフィギュアスケートは別格として、先のトリノ五輪で何と言っても夢中になったのはカーリングでした。その、女子カーリングチーム(正確には、トリノの前のソルトレーク五輪に出場したチーム)をモデルにした映画「シムソンズ」。カーリングが注目を集めるにつれ、この映画も話題になったので、ずっと見たいと思っていました。それにしても何で“シムソンズ”なんだろう?と思っていたら・・・そういう由来なんか!と、まずは笑わせてもらいました。美少女とファニーフェースの間をくるくる移り変わるような、表情豊かな加藤ローサちゃん。モデル時代から(可愛いなぁ)と思っていましたが、この主演作を観て、こんなに自然にセリフも言える子なんだ!と見直しました。ホタテと、タマネギと、カーリングしかないサロマ湖畔の町、常呂。平凡な日常から抜け出したい、でも何をしたらいいかわからない・・・そんな焦りの中にいた主人公が、やがてかけがえのない仲間を得て、氷の上で輝きをつかむまで。冒頭からぐいぐいと惹きつけられ、最後まで観てしまう。それは脚本の巧みさ、キャストの好演、舞台を支える常呂の雄大な自然・・・それらのハーモニーと、何といっても、カーリングというスポーツのユニークさやドラマ性が生み出している魅力なのでしょう。「私のこと、見つけてくれてありがとう」というセリフには、ホロリと来ました。JUDY AND MARYの「小さなころから」がBGMに流れるシーンもよかったな。>それにしても、「女子高生4人組」を主人公にした映画って多いなぁ、と思います。ちょっと考えても「がんばっていきまっしょい」、「リンダリンダリンダ」、「チルソクの夏」・・・などなど。「4人」という人数は、キャラクターの書き分けや、ストーリーの展開に色々な面で“ちょうど良い”のでしょうね。しかし、こうなるとすでに1つのジャンルと言ってもいいかも?「リンダリンダリンダ」を観たとき、一番私の印象に残ったのは、バンドをやる主人公ではなくて、ケンカ別れしてバンドを抜ける凛子役の女の子の目の強さでした。後日、「チルソクの夏」を観たら、その凛子を演じた三村恭代が、主役の4人組の一人を演じていて、リンダ-とは全く違う、純朴な陸上部員を演じていて驚きました。(上野樹里ちゃんのブラジャー姿が何度も出てくるのにも、違う意味でびっくり)平成と昭和、女子高生の“リアル”はかくも変わったか?という感じで(笑)若手女優の存在感がキラキラ輝く、名作の多いジャンルであることは確かです。【こちらは、オーバーエイジの4人組・・・】
2007.04.04
コメント(6)
-

着物ことはじめ ~買い物の喜び、お値段の謎~
前回のブログで紹介した紬の着物。購入した時には、このような経緯がありました。最初は、名古屋のデパートの呉服売り場で見つけ、一目で「これ、好き!」と思ったのが出会い。しかし、その時は購入には至らず、結局そのままに・・・それからしばらく経った昨年の暮れ。夫の出張に合わせて、久々に大阪に出かけました。彼の仕事が終わるまで、一人でミナミをふらふら歩くことに。すると、心斎橋筋のアーケード街にある、小さい店構えの呉服店の店先に「あ~っ!これは!!」ずっと忘れられずにいたあの着物が、お人形さんに着せられて鎮座しているではありませんか。この出会いは運命とも思え(大げさ?)その夜、夫に「何、そのでかい紙袋??」と仰天されるようになったのは当然の成り行きで・・・ちなみに、歳末大売出しで、デパートで見た値段の3割引になっていたばかりか、「名古屋帯もセットでつけます」という、お得な買い物になったのでした。二重の喜びです。【よっぽどご縁があったと思われ・・・おばあちゃんになっても着ていたい。】 ところで、この着物自体は、元から高級品という訳ではなく、反物は国産ですが、縫製は海外(ベトナム)で行われた仕立て上がり。人件費の部分を抑えることが、即、低価格化に結びつく・・・これは、着物の世界でも例外ではありません。そしてこの傾向が、国内で伝統を受け継いでいこうとしている職人さん達の置かれている環境を、厳しいものにしているのも事実であり。そう考えると、出来れば、安い買い物に喜ぶだけではなく、伝統的な手仕事を支えられるようなお金の使い方がしたい、とも思うのですが。「ピンからキリまで」の幅が凄まじく広いのが、着物の世界。志はあっても、先立つものが・・・(涙)デパートで仕事をしている友人談では、呉服の上代の掛け率は、場合によっては宝飾品よりも高いらしく、いずれにせよ買う側にとっては「値段の根拠」が見えづらい商品であることも事実。だからこそ、悪徳商法が問題になったりするのでしょうし、消費者としては、信頼できる購入先をちゃんと見極めることが大事なのでしょうね。何についてでも言えることですが。一方で、どんなに手をかけて作られた高級な着物も、リサイクルショップ等に引き取ってもらおうとすると二束三文になってしまうようです。過日、NHKのドキュメンタリーで見た光景。大手のリサイクルショップに、おばあさん、お母さんの着なくなった着物を十着近く持ち込んでいた若い女性。鑑定担当者から提示されていた金額は、なんと五千円でした。お店の人曰く、着物は購入後5年以上を経たものは、単なる「布地」としての価値しかなくなる、ということで・・・恐らく、丁寧にメンテナンスを施された後は「リサイクル着物」として店頭に並び、またどこかの着物好きな人に引き取られていくはず。逆に、そう考えないと何だか哀しい、と思ってしまいました。高いものは滅法高く、安い世界はとどまる所を知らず安く・・・着物ブームと言われている現在、この二極分解はどこまで進んでいくのか。そして、その中で私はどういうこだわりを持っていくか。未だ思案の最中なのでありました。ところで。同じ番組の最後の場面では、持ち込んだ毛皮のコートを売らないことに決めたという、中年の女性が登場していました。毛皮というのも劣化が激しいそうで、百万以上で購入したものでも、数万円の買取値しかつかないとか。その女性、「ここで売ったら、たった○万円の毛皮だけど、私が着続けている限り、買ったときのまま百万円のコートだもの」というようなコメントをして、「着て帰ろう。これ着て、ロシアに旅行に行こっ!!」と威勢良く去っていかれました。そうそう、その意気や良し!!女の買い物道は、“自己満足”という明りで照らされている限り、光り輝き続けるものなのよね!と、テレビの前で拍手したくなった私です。
2007.04.03
コメント(10)
-

着物でお花見
東京では満開になったという桜。こちらでは、見頃は次の週末かな?という感じですが、五分咲きでもまぁ、いいか・・・と、近隣の城址公園へ散歩に出かけました。予報では崩れると言われていたお天気も、時折晴れ間がのぞく春らしい陽気に。ちょっと、着物でも着てみましょうか・・・と思い立ちました。紬の着物に合わせたのは、酉年生まれの私にピッタリ、と、楽天のショップ「きもの ほ乃香」で購入した、おんどり柄の名古屋帯です。自分が「ちょっと着物でも」なんてことを言えるようになる日が来るとは。長い間、憧れはあっても叶えられない夢でした。それが実現できていること。もちろん、「あれも、これも」と足りないことはいくらでも挙げられるけれど、“出来なかったことが出来る”ようになるのは、大人になるとしみじみ嬉しいものですね。お花見の名所でもある公園の中には、露店もたくさん出ていました。この日は半端な時間に、ブランチを済ませたきりだった私たち。急に空腹を感じてしまったのですが・・・「焼きそば」「たこ焼き」「フランクフルト」・・・どれも、着物を汚すかも?と思うと怖くて手が出せない。結局、万一食べこぼしても被害が少なさそうな、ベビーカステラにしました。※最近は、ドラえもんの形のカステラがあるのですね。やっぱり私にとって、着物を“さりげなく”という生活はまだまだ遠い道、のようです。桜は、やっぱり見頃にはまだ早かったようで、お花見の人出もまばら、並木もこんな感じでした。ということで、家に帰って、甘い「桜」でリベンジした、というわけです(笑)~ゼロから始めた私のきもの生活。フリーページもご覧ください~
2007.04.01
コメント(10)
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-

- 日常の生活を・・
- 本日もドタバタ!洗濯機壊れてテンヤ…
- (2025-11-06 20:13:53)
-
-
-

- 地球に優しいショッピング
- ☆洗たくマグちゃん プラス☆
- (2025-09-04 23:16:08)
-
-
-

- 【日曜日(安息日)の過ごし方】
- 亀有キリスト福音教会_第一聖日礼拝_…
- (2025-11-03 07:39:23)
-







