2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年11月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
犯罪の手触り
駅からの帰り道、日暮れあとの薄暗い路上で、背後から来たバイクにバッグをひったくられてしまった。連れ去り事件や通り魔のようなニュースも頻発している今どきの世の中、バッグひとつで被害が済んだというのは幸運だったと思わなくてはいけないのかもしれない。いつものことながら、アクシデントに見舞われた私に、夫をはじめ周囲の人々は温かい気持ちをたくさん注いでくれる。不幸な経験を通じて、たくさんの人に労わってもらえる幸せを知る。正と負が表裏一体のものだということ、これまでにも何度も経験してきたことだった。それでも、私を心配して「どんな風に盗られたの」「どういう怪我だったの」「犯人はどんな奴だったの」…と投げかけられる質問の一つひとつが、実は、すごく、つらい。その問いに答える度に、何日経っても、あの夜の路上の光景に引き戻されてしまう。癒えたはずの体の痛みに、また苦しめられるような錯覚に陥る。パニック状態に陥ってしまった私には、涙を拭くためのハンカチさえ手元に残されていなかったのだ。私は元来、自分で自分を哂うのがわりと得意な方なのだけれど、今回ばかりは、なぜか笑い話にするのが難しくて、そのことに今でも戸惑っている。まるで、とてもじゃないけど飲み込めない、苦くて大きな塊のようなものを、口の中に押し込められているような感覚。この体験を消化するには、どれほどの時間がかかるのだろう。無論、いつか必ず、そのときは来ると思うけれど。なぜ、あと少し遠回りして、明るい大通りを選ばなかったのだろう。なぜ、バッグを車道側の手に持って歩いていたのだろう。盗られたモノへの執着はすでに無いけれど(お金で取り戻せないものは何も入っていなかったし)、自分で自分が情けないし、許せない。そして、ニュースで見る時にはそれなりに(怖い、ひどい)と感じていたつもりでも、実際に自分が犯罪の現場に、それも被害者となって立ち会ってみると、その現実のキツさというのは想像をはるかに超えていた。絶対の意思を持って悪事を仕掛けられたら、大の大人だって、こんなにもそれに太刀打ち出来ないものなのだ…という実感が、思いのほかダメージとなっているのだった。そんなわけで、しばらくの間ブログも更新できないままになっております。楽しかったり、うれしかったりしたことの記録を残していきたい、「いいこと探し」の場に…と心がけていたこのブログに、あえて、読んでくださる方に心地いいとはいえない、こんな経験談を書いたのは、とにかく「本当に気をつけてください」「自分の身を守るための注意を惜しまないでください」と、それを伝えたかったからです。おなじみの方々には、これでまたご心配をおかけしてしまうと思いますが、体は元気で何事もなく暮らしておりますので、ぼちぼち、ブログを再開できた暁には、ぜひよろしくお付き合いください。
2007.11.19
コメント(5)
-

「フェルメール全点踏破の旅」を読んだ。
六本木の国立新美術館に、フェルメールの「牛乳を注ぐ女」が来ています。作品数の少ない人気画家の作品を日本で見られるチャンス。さぞかし、展覧会は盛況なのでしょうね。フェルメールの作品は、全世界に三十数点しかなく、ヨーロッパとアメリカにある所蔵作品を辿って、まるで巡礼のような「全点踏破」の旅をするファンがいる……ということを、初めて教えてくれたのは、トマス・ハリスの小説「ハンニバル」でした。映画「真珠の耳飾りの少女」のヒットなどもあって、近年ますますフェルメール人気は高まっているように思います。この本は、千円で買える新書ですが、フェルメールの全作品はもちろん、所蔵されている美術館の写真や、関連する同時代の画家の作品まで、豊富なカラー図版が収められています。フェルメール全点踏破の旅いくらフェルメールが寡作で、現存する作品が少ないと言っても、私はそのすべてを知っているわけではなかったので、有名な絵画以外にも(こんな美しい絵があるのか!)と、ページをめくるたびに深い感銘を受けました。特に、「小路」と「デルフト眺望」という、2枚の都市風景画が大好きになりました。端正で、緻密で、でもどこか温もりを感じる印象。フェルメールの代名詞とも言える、室内の肖像画群に通じる魅力があると思います。「全点踏破」の本文そのものは、一つひとつの絵画について深く掘り下げられているわけではありません…が、たくさんの情報が散りばめられていて、フェルメールの遺した絵が辿ってきた数奇な運命を追いつつ、実際に絵画も鑑賞できるという、入門編としてとても面白いテキストだと思います。ポケット画集と考えても、大変に「お得感」のある一冊でした。実は、油絵を描いている知人の作品が、やはり国立新美術館で開催中の日展に入選していて、近々上京する予定もあり、時間を作って観に行こうと思っています。せっかくだから、「牛乳を注ぐ女」にも対面したいと思うものの、この手の企画展につきものの、大行列・大混雑は覚悟の上か…と考えると、ちょっと腰が引けてしまったりして(笑)でも、航空券を買わずとも本物のフェルメールが見られる機会などそうそう巡ってこないと思えば、ここはがんばるべきでしょうか。印刷では見えてこない、新たな魅力の発見があるかもしれませんね。
2007.11.07
コメント(4)
-
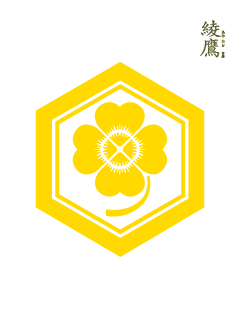
家紋ジェネレーター
日本コカ・コーラ社の緑茶飲料「綾鷹」の公式サイトに、名前と生年月日を入力するとオリジナルの家紋が作れる、「家紋ジェネレーター」なるページがあります。nade-shikoさんのブログで紹介されているのを読んで、早速私もチャレンジしてみました。そして、出てきたのがこちらの「四葉」という紋。解説文には、「四葉紋のあなたは争いごとを遠ざけ、平和を好む温和な性格。周りとの調和を大切にし、多くの人々と手に手をとって生きてゆけば必ずや、あなたも、そしてあなたを取り巻く人々も平穏で素敵な人生を送れることでしょう。持ち前の優しさと協調性を大切にして、素敵な日々を過ごしてください。」・・・とありました。ちなみに、私の本名は斉藤でもサリィでもないのですが(笑)、ハンドルネームと本名、両方とも同じ結果となったのが面白かったです。名前(ひらがな)と生年月日を入力してクリックするだけのお手軽さなので、楽しくなって、家族や知人の家紋を出してみては延々と遊んでしまいました。ちなみに夫の家紋はこちらの「楓」。「時代の空気や流れを上手に掴むその姿は、まるで美しく風にまう秋の落ち葉のよう。常識にとらわれることなく、自らの直感と感性を信じて突き進んでください。」・・・って、何だか美しすぎる気もしますが(苦笑)。「紋」というのは、着物はもちろん、日本の伝統芸能に触れていても、数多く目にする機会があります。その意匠の美しさ(時には大胆さ)は、知れば知るほど興味深いものだなあと思います。(ちなみに、綾鷹の家紋ジェネレーターで出てくる紋は、家紋デザイナーの方がこの企画のために新しくデザインされたものだそうです)以前、坂東玉三郎さんが歌舞伎の衣装についてお話されていたとき、「うち(大和屋)の家紋は衣装にあんまり映えないから苦労する」というようなことをおっしゃっていて、そんな側面からも衣装作りに心配りをされているのか・・・とビックリしたことを思い出しました。庶民の私は、そうそう紋付の着物をあつらえることは出来ませんが、ハンカチの隅にでも刺繍してみましょうかね、四葉紋(笑)【綾鷹・・・生茶派の私は、実は未だ飲んだことがありません(ごめんなさい)】綾鷹 上煎茶http://ayataka.jp/
2007.11.06
コメント(10)
-

夜間飛行の崇徳院
今日、NHKの朝ドラ「ちりとてちん」を見ていたら、崇徳院の話が出てきました。崇徳院というのは、百人一首の中でも有名な瀬を早み岩にせかるる滝川のわれても末にあはむとぞ思ふ・・・という歌を詠まれたお方で、この歌を題材にした、その名も『崇徳院』という落語の噺があります。「ちりとてちん」は上方の落語界が舞台になっているドラマなので、当然、出てきた話題は落語のほう(崇徳院といえば、非業の死を遂げて怨霊となった伝説もありますよね。なんと話題に事欠かないお方・・・)。とある大店の若旦那が、茶店で出会った美しいお嬢さんに一目惚れした。お相手のお嬢さんからは、「瀬を早み・・・」の歌の上の句を渡されたのだが、どこの誰かがわからぬまま別れてしまい、後悔のあまり、恋患いで寝付いてしまう。若旦那の病状を憂う旦那に、借金の棒引きを条件にお嬢さんを探し出すことを命じられた、幼馴染の熊五郎(熊さん)は・・・???という噺。今週のドラマは、主人公が人探しをする、というストーリー展開なので、それにかけた落語が登場してきたわけですね。「ちりとてちん」は、登場人物の名前や差し挟まれる落語の内容などが、さりげなく物語とリンクしていて、その仕掛けを見つけるのがささやかな喜びだったりします。視聴者に深読みを誘う連続テレビ小説(笑)落語の面白さ、楽しさをまだまだかじり始めたばかりの私ですが、この「崇徳院」の噺は以前に聴いたことがありました。その場所は、高度ン千フィートの空の上。今年の春、ポルトガル旅行に行った帰りの機内のことでした。妙な時間帯に目が覚めて、そのまま寝付けなくなってしまい、映画は見たくないし、読書はなお億劫だし・・・という、半ばぼんやりした状態で、何となく聞いて見たのが落語のチャンネルだったのです。ちょうど、桂ざこばさんの演じる「崇徳院」が始まったところでした。若旦那とお嬢さんの出会いの場面の美しさ、タイムリミットまでに熊さんはお嬢さんを探し当てることが出来るのか?というスリル、子守唄代わりのBGMのつもりだったのに、いつの間にか落語の中の世界にのめりこんでしまい・・・何より、熊さんの人探しのスタイルというのがかなり素っ頓狂で、こらえきれず、寝静まった機内に響くほどふき出してしまったりして。今でも、ざこば師匠の「せを~はや~みっ!」という、だみ声で張り上げる一節を鮮やかに覚えています。旅の本筋とはまったく関係ない、でも、だからこそ何だかいつまでも忘れられない出来事を、ひょんなことから思い出した朝でした。【いろいろな名人の『崇徳院』を聴き比べるのも楽しそうです。】
2007.11.05
コメント(6)
-

「マッチポイント」を観た。
ウディ・アレンが、ホームグラウンドであるニューヨークを離れ、ロンドンを舞台に撮ったスリリングな愛憎劇。プロ選手としての自分に見切りをつけ、テニス・インストラクターとなったクリス。上流階級の青年トムと意気投合したことをきっかけに、彼の妹クロエに見そめられ、結婚する。資産家であるクロエの父の会社に入り、将来を約束されるクリス。すべてが順調だったが、トムの婚約者であるノラとの情事に踏み出したことから、運命の歯車が狂い始めて…劇中、何度も「Luck(運)」という言葉が出てきます。どんなに努力をしても、才能を持っていても、人生のギリギリの土壇場で勝敗を決めるのは、運命の力。自分の力でコントロールできない流れに、翻弄される人間のドラマが、オペラのアリアにのって軽やかに描かれていきます。運を味方に、人生で勝利を手にすることは、果たして幸福と同義なのか?という、重い問いかけも。アイルランド出身のクリス、アメリカ人のノラ。外の世界から、イギリスの上流社会に入り込んだ二人の「運」が、人生をどう左右するか。浮気とその顛末、という手垢のついた題材にも関らず、最後の一瞬まで目が離せない、二転三転の展開。とても面白かったです。ノラを演じるスカーレット・ヨハンソンの成熟した色気はとても魅力的で、先のない恋に血迷う主人公の物語に、すごい説得力を与えていたと思います。人一倍強い上昇志向を持ちながら、不倫の泥沼にはまりこむや、浅はかな嘘を重ねて保身に走る主人公(ジョナサン・リース・マイヤーズ好演)。その場当たり的な行動に、(あぁ、おバカさんね)と呆れつつ、何やら哀れさとシンパシーを感じてしまうのは、彼を板挟みにする妻と愛人のウザさ加減が、イヤというほど目につくからかもしれません(苦笑)可愛さあまって憎さ百倍、とはよく言ったもので、女の「愛嬌」と「いやらしさ」は紙一重と如実に示してみせる描写は、さすがウディ・アレンという感じでした。どんな街を舞台にしたどんな物語でも、この監督の撮る映像には、古い石造りの建物のような端正な味わいがあって、それが好きです。この映画、ロンドンの名所案内のようなところもあって、その上、主人公のクリスが買い物をするのは「ラルフ・ローレン」(おぉ、アニー・ホール!)というところなど、クスッとさせられてしまいました。新作の「タロットカード殺人事件」でも、再びスカーレット・ヨハンソンを迎えてロンドンが舞台となっているようで、新しいミューズと出合ったウディ・アレンの今後に注目したいと思ったのでした。【ヴェルディやロッシーニのオペラの名曲がギッシリ。】「マッチポイント」オリジナル・サウンドトラック
2007.11.01
コメント(6)
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
-

- 私なりのインテリア/節約/収納術
- [Rakuten]「カレンダー」 検索結果
- (2025-11-15 22:08:33)
-
-
-

- *雑貨*本*おやつ*暮らし*あんな…
- お気に入り
- (2025-11-17 01:10:48)
-








