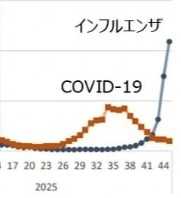2017年06月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-

第20回和郎女作品展
第20回和郎女作品展 本日の記事は和郎女作品展とします。 25日の若草読書会の折に、参加者へのお土産にとお持ち下さった押し絵作品をご紹介申し上げるものであります。 <参考>過去の和郎女作品展はコチラからどうぞ。 先ずは団扇です。 と言っても普通の団扇ではありません。飾り用の団扇です。 台座とセットになっているのですが、撮影の便宜上、床に寝かせて団扇だけを撮影しました。団扇を台座にセットして立てると、撮影者である小生が寝転がってカメラを構えなくてはならないからです。まあ、これは内輪の話です(笑)。(団扇・見返り美人・萩) 女性はすべからくこの見返りのポーズが美しく見えるものと昔から相場が決まって居りますな。上は「萩女」下は「蛍女」。源三位頼政ならぬ偐三位家持も「何れ菖蒲か杜若」なのであります(笑)。白露を取らば消ぬべしいざ子ども 露に競ひて萩の遊びせむ (万葉集巻10-2173) 蛍は万葉集には登場しないが1首だけ長歌(巻13-3344)に「蛍なすほのかに聞きて」という形で出て来る。即ち「ほのかに」にかかる枕詞「蛍なす」として登場するのみなのである。よって、万葉歌ではなく、有名な和泉式部の歌でも挙げて置くこととしましょう。もの思へば沢の蛍もわが身よりあくがれ出づる魂かとぞ見る (和泉式部 後拾遺集巻20-1162) (団扇・見返り美人 ・蛍) 下の金魚の団扇は、ひょっとすると和郎女さんの作品ではないのかも知れません。 裏面にも何やらの図柄の押し絵が貼り付けてあり、「失敗作がどうのこうの」とか 何やら話して居られましたが、話の内容をよくは聞いていなかったヤカモチさんでありましたので、どちらかが或は両方とも和郎女さんの作品ではないのかも知れないなどという印象を持ちつつ、どちらを表面とも見定めず、季節的には金魚がよかろうと、撮影した次第にて、和郎女作品展として展示してよいものかどうかも判然としないのであります。もし、違っていたら、それは全てヤカモチの不手際、同人の責任であります。(団扇・金魚) 金魚の団扇は壁や柱に掛けて飾る仕掛けになっています。若草ホールには適当な場所がなかったので、廊下に出て、二階への階段に立て掛けて撮影してみました。 上の見返り美人の団扇もこの階段に置けば、飾った状態のものを楽な姿勢で撮影できることに気付きましたが、撮り直しも面倒なので止めました。 以下の作品も壁などに掛けて飾ることが出来ますな。(熊さん) 熊さんは、少しピントが甘かったようで、写りがイマイチです。 (ミミズクさん)(ウサギさん) 上のウサギさんと下のアジサイの作品は、ひろみの郎女さんへのものとして、ヤカモチがお預かりしたのでしたが、翌26日に喫茶店ペリカンの家でその受け渡しを完了いたしました。 どういう話の流れであったかは記憶にないのでありますが、ひろみの郎女さんがご自身の部屋に飾って置くよりも喫茶店の飾りにした方がよいとお考えになったのでもあるか、その受け渡し場所となった喫茶店ペリカンの家にそのまま鎮座することとなり、現在は同喫茶店でこれを見ることができます。(アジサイ) 今年に入って4回目の和郎女作品展でありました。 本日もご来場、ご覧下さりありがとうございました。<追記> 撮影をし忘れた作品「お月見うさぎ」の写真が小万知さんから送られて参りましたので追加で掲載させていただきます。寄り添ひて たぐひてあらな 高々に 二人の月は 欠けたるもなし(偐家持)(お月見うさぎ)
2017.06.28
コメント(18)
-

若草読書会・ロンドンみやげ
昨日25日は若草読書会の日でした。課題図書はなく、恒郎女さんのご要望で、先にロンドンを旅行された凡鬼・景郎女さんご夫妻からロンドン旅行のお土産話をお聞きするということになりました。 ご夫妻のお嬢様ご夫婦がお仕事の関係で目下ロンドン郊外にご在住。そんなこともあって3月末から4月半ばまで、お孫さんたちに会いにということで、久々にご夫妻で渡英されたのでありました。 英国は雨の4月、花の5月と言われるそうですが、ずっと晴天に恵まれ、木蓮や桜が満開で、はからずもロンドンでお花見ができたとのことでした。(4月2日の若草読書会のお花見はこの関係でご夫妻共にご欠席でした。) 凡鬼さんからは、ローマ帝国が英国に進出した時代、その支配下で温泉地として発達した町、バースへの小旅行をしたことに関連して、ロンドンからバースへの道、バース街道がローマ時代につくられた道であり、ローマがどのようにして周辺地域にその支配を拡大して行ったかとか戦争に於ける兵站の重要性をローマはよく認識していたなどという話がありました。 また、通りかかったケンブリッジ大学やオックスフォード大学が思った以上に田舎町に存在しているという印象を持ったとか、今回の旅の前後にあったテロ事件に関連して、ロンドン市民が当局からの「不必要な外出は極力避けるように」という通達にも拘わらず、市民は敢えてそれまでと変わらぬ日常の行動を守ることによって「テロに屈しない」という姿勢を示そうとしているなど、ヨーロッパ文明の確かさ、力強さを感じたこと、ロンドンの地下鉄が両側の座席の間の通路が人間一人が通れる位の幅しかない狭い車両であったこと、そして、地下鉄では、度々若い人達から座席を譲って貰ったが、そのようなことは彼らにとってはごく当たり前の自然な行動であるように見受けられたこと、さすが紳士の国、英国であると感じたことやテムズ川を船で遡った時の印象その他色々の感想をお話いただきました。 景郎女さんからは「児童文学の舞台を訪ねて」というレジメをご用意下さって、今回訪ねられたマナーハウスでのお話などをお聞かせいただきました。彼女は長年にわたって子ども文庫の活動や子どもへの絵本読み聞かせの活動に取り組んで来られていますが、今回の旅は、そのような活動の中で出会った児童文学の作家たちの中でも彼女が特にお好きだというルーシー・M・ボストンとフィリパ・ピアスという英国を代表する二人の児童文学者に所縁の地を訪ねる格好の機会となったようでした。 グリーン・ノウ物語(全6巻)の舞台となるのがマナーハウス。12世紀に建てられた英国でも古い荘園領主の館がマナーハウスである。作者のボストン夫人が97歳まで住んだ屋敷であり、現在はボストン夫人の息子の故ピーター・ボストン氏(彼は「グリーン・ノウ物語全6巻の挿絵画家でもある。)の妻のダイアナさんが管理人を務めて居られて、内外の観光客のご案内・応対をされているとのこと。 レジメには、そのダイアナさんと並んで満開の桜の木の下で微笑んで居られる景郎女さんのお写真も掲載されていました。(注)グリーン・ノウ物語 1.「グリーン・ノウの子どもたち」 2.「グリーン・ノウの煙突」 3.「グリーン・ノウの川」 4.「グリーン・ノウのお客さま」 5.「グリーン・ノウの魔女」 6.「グリーン・ノウの石」 もう一人のフィリパ・ピアスの作品の舞台訪問記は、何れまたということで時間の関係で割愛となりましたが、次の3作品は是非お読み下さい、とのことでありました。 「ハヤ号セイ川を行く」 「まぼろしの小さな犬」 「トムは真夜中の庭で」 今回の参加者は、凡鬼・景郎女ご夫妻、智麻呂・恒郎女ご夫妻のほか、小万知さん、祥麻呂さん、香代女さん、和郎女さん、そして1年半ぶりの偐山頭火さん、偐家持、そして、途中から景郎女さんのお姉様の敦郎女さんが珍しくご参加下さいましたので、全11名となりました。主題のお話の後は持ち寄りの食べ物やお菓子などをつまみながらの飲み食い、雑談したり、歌を歌ったり、という恒例の通りです。 そんなことで、何と言って掲載すべき写真もありませぬ故、ヤカモチが煙草休憩にて席を外して智麻呂邸の前の公園でぷかぷかやりながら撮った写真でも掲載して置きます。(これは何?) これは何?下の草の露を写真に撮ったついでに、望遠で少し離れた場所の草を撮影したものです。草の茎を渡る蟻の姿を撮ろうとしたのですが、素早く蟻が移動するので、うまく写らなかったもの。 意味不明ながら、面白い雰囲気の写真になったので掲載しました。蟻が草の茎を渡っている姿が写っていたら「グリーン・ノウの蟻」という新作の挿絵に使えた筈であります(笑)。 (草の露) ところで、草の露の写真は何故? 若草読書会なので、「若草」と「草の露」で「草つながり」という、かなり苦しいと言うか「臭い」と言うか、無理矢理のこじつけなのであります。これでは、いくら何でもということで、智麻呂邸の玄関先に咲いていたオリヅルランの写真を撮ってみました。参加者でこの花に目をとめた方が果たして居られたかどうか。 (オリヅルランの花) この花は、今回はご欠席であったひろみの郎女さんが下さった鉢植えではないかと思いますが、小さな花を人知れず咲かせていたのでありました。 そして、紹介し忘れましたが、和郎女さんがお持ち下さった作品、希望者はどうぞお持ち帰り下さいという、彼女がご参加の場合には恒例化しているイベントもありました。 ひろみの郎女さんの分として、彼女に渡してくれと、小万知さんと恒郎女さんから、ウサギの作品とアジサイの作品をヤカモチはお預かりしたのですが、今日26日にペリカンの家にて受け渡しを完了いたしました。 彼女のブログに今朝、受け渡しの件をコメントで入れたところ、何とひろみの郎女さんは今日ペリカンの家にお立寄りで、同コメントをご覧になった彼女から「今、ペリカンの家に来ている。」との電話が入ったのでありました。そんなことで、慌ててお届けしたという次第。 ついでに、ももの郎女さん、越の郎女さんのご要望にお応えして、恩智川畔のハゼランとマンネングサを採取してお届けするという仕事もやり遂げましたので、今日のヤカモチさんは結構「働き者」でありました(笑)。 なお、和郎女さんの作品や智麻呂氏の新作絵画の撮影もいたしましたので、これらは追って、和郎女作品展、智麻呂絵画展という形で、皆さまにご覧いただくこととします。
2017.06.26
コメント(6)
-

花の時期は過ぎにけらしや
先日から気になっている花の話です。 6月16日の記事と同17日の記事で、恩智川畔で見掛けた正体不明の花として、下の写真を掲載いたしました。蕾が花開き、咲いたところを写真に収めて、何んという名の花か調べる手掛かりにしようという心算でいました。 (名前不詳の花・再掲) ところが、23日午後に再訪してみると、既に花は萎んでいて、下のような状態。他に咲いている花はない。この花は夕刻か朝方かに咲いて、日が昇ると萎んでしまうマツヨイグサのような花なのかも知れないと、今日24日朝に現地に行ってみることとしました。 しかし、花は見当たらず。小生が花の蕾と思っていたのは、花が咲き終わった後の実、種苞である疑いが濃くなって来ました。 してみると、この後、待っても花を見ることは叶わないということになる。花の時期は過ぎにけらしや、である。正体解明は来年まで待たなければならない、という気の長い話になってしまった。 しかも、ここは河原である。河川の流水を円滑にするため、河原の草などは河川管理者によって刈り取られる可能性もあり、来年またここでこの草に逢えるという保証はない。迷宮入りかも知れませぬ(笑)。 (同上) で、収穫ナシで帰るのも、と河原を歩くとハゼランが見つかりました。よく見るとあちらこちらに生えている。(ハゼラン)<参考>ハゼラン・Wikipedia しかし、ピンクの花がどれも咲いていなくて、咲いているのを撮影するには出直すことが必要かと考えたのが昨日23日のこと。 (同上) (同上・葉はこんな感じです。) で、本日24日朝、上の正体不明の花の写真が駄目なら、ハゼランの咲いているのを写そうと考えたのでしたが、下の通り、花開いているものは一つもない。 (同上)(同上) 「ハゼランよ、お前もか」である。(ハゼランの花<Wikipediaから転載>) ハゼランの生態の詳しいことは存じ上げないので、咲く時間帯などがあるのだとしても、それは知らぬこと。それにしても、つぼんだ奴ばかりで、アトは実というか種子のようなものばかりというのはどういうことなんでしょう。どの株も同じ状況である。これもまた空振りに終わりました。上の転載写真のような花を撮影する心算であったのでしたが、「恩智の川の流れとハゼランの花はままにならぬものよのう!」であります(笑)。 Wikipediaの説明を読むと「午後の2~3時間しか花を開かないので三時花などとも呼ばれる」とあるから、朝ではなく、むしろ午後3時頃に見に行くべきなのでした。(同上) とても小さな実であるが、写真に撮ると「茨の実」のようにも見える。勿論、ずっと小さいので、肉眼ではそんな感じは少しもしないのではあるが。 秋の景色のようにも見えて何やら面白いのでもありました。 (同上) もう一つ目を惹いたのはメハジキ。これは万葉植物でもある。 と言うのは万葉集に登場する「ツチハリ(土針)」は、メハジキのこととされているからである。勿論、異説もあって、ツクバネソウ説、エンレイソウ説、ゲンゲ(レンゲソウ)説などもある。わが屋前(やど)に生(お)ふる土針(つちはり)心ゆも思はぬ人の衣(きぬ)に摺(す)らすな (万葉集巻7-1338)(我が家の庭に生えている土針よ。心にも思っていない人の着物を染めるために使われないようになさい。)(注)土針は女性の比喩として使用。 わが娘よ心に染まない結婚はするな、という母が娘を諭す歌である。 (メハジキ)<参考>メハジキ・松江の花図鑑 メハジキ・季節の花300 (同上)(同上) 下の写真の土針には、よく見ると虫が付いていますな。 母としては、「悪い虫」が付くのも心配なことでしょうな(笑)。わが屋前に生ふる土針心せよ 寄りつく虫にわろきもあれば (菊針家持) (同上) 万葉集の花と言えば、何んと言っても萩。 一番多く詠われている花は萩である。 その萩がもう咲いている。(萩)<参考>ハギ・Wikipedia (同上) 萩の歌が多くある中で小生が好きな歌1首となると、やはりこれですかな。高円の 野辺の秋萩 いたづらに 咲きか散るらむ 見る人無しに (笠金村 万葉集巻2-231) (同上) 萩の近くには木苺が熟れていました。 (木苺)<参考>キイチゴ属・Wikipedia 河原には草だけでなく、木も生えている。種が流れ着いたのか、散って来たのか。センダンやナンキンハゼの若木が目に付く。 (ナンキンハゼ) 恩智川は川幅が左程に広くない川。このような木が成長するに任せるほどの余裕はないから、或る段階で、これらの木は伐採されてしまうのであろう。 そうとは知らず元気に花穂をつけて青葉を風にそよがせている。 (同上)(同上)<参考>ナンキンハゼ・Wikipedia (同上)(同上) (アカバナユウゲショウ)<参考>ユウゲショウ・Wikipedia アカバナユウゲショウやマンネングサは前の記事で紹介したように随所に見られる。彼らはしぶとく生き残ることだろう。 小万知さんがご覧になった白花のユウゲショウは恩智川の河原には見当たらない。残念。 さて、アカバナユウゲショウの本来の名は単に「ユウゲショウ」で、オシロイバナの通称がユウゲショウと同名であるため、これと区別するため「アカバナユウゲショウ」という別名を以って呼ばれることが多いということのようです。ならば、白い花のそれは、「白花のユウゲショウ」でいいことになるが、オシロイバナにも白い花のがあるから、それと区別するためには「白花のアカバナユウゲショウ」と呼ばなくてはならないという次第。ここは、オシロイバナの通称を夕化粧ではなく朝化粧に変えるべきだろう、と薄化粧のアツゲショウが言って居ります。(メキシコマンネングサ )<参考>マンネングサ属・Wikipedia コモチマンネングサ・Wikipedia コゴメマンネングサ・Wikipedia メキシコマンネングサ・Wikipedia マンネングサは花の時期がもう過ぎたのかと思っていたが、このように咲いているのもある。まあ、名前が万年草なんだから、こうでなくてはならないというもの。 この草、以前の記事ではコゴメマンネングサと表記していましたが、今回、Wikipediaの記事でよく調べると、コゴメマンネングサは九州南部から沖縄に分布とあるから、これではなく、違う種類のマンネングサのよう。道端などでよく見かけるのはコモチマンネングサとあるが、感じが異なる。外来のメキシコマンネングサのようです。(同上) こんな小さな株のものもありました。今年芽を出したばかりの株でしょうか。根こそぎ堀り出して、小さな鉢植えにしたら、部屋のインテリアとしても使えそうな可愛らしさである。(同上) 次はランタナ。これは恩智川畔ではなく、野崎観音近くで見たもの。 (ランタナ)<参考>ランタナ・Wikipedia ランタナは七変化とも呼ばれるように、花が黄色からピンクに赤にと変化して行くがこれはどうなんだろう。と言うのはこの花の隣にあったのは白い花のランタナであったからである。(白花のランタナ) 白花のランタナはどう見ても花の色が変化するとは思えない。ランタナではないみたいである。しかし、ミントか何かのハーブのようなあの独特の葉の香りや葉の形からランタナであることに間違いはない。先日、ブロ友のひろみちゃん8021さんが黄色いランタナの写真を掲載されていましたが、ランタナにも色々な種類があるようですね。 (同上)(同上) そして、次の青い花も、恩智川ではなく、自宅近くの民家の庭先に置いてあった鉢植えの花である。青い花というのがそもそも珍しいので、何んという名の花だろうと思ったのであるが、調べても分からなかったので放置していました。すると、先日ブログ管理ページの広告欄に表示された花の広告の中に、この花の写真が混じっていたのでした。 ムギセンノウやオルレア・ホワイトレースも同様の形でその名を知ったのであるが、どうしてこのようにタイムリーに広告が届くのでありましょうか。まるで、こちらのマイ・ピクチャの中身を見透かしたかのようなタイミングであります。(ルリトウワタ) ルリトウワタ(瑠璃唐綿)です。 (同上)<参考>ルリトウワタ・Wikipedia 冒頭の正体不明の花の葉は、この花の葉のように細長い葉である。ルリトウワタの葉の周囲を鋸のようなギザギザで縁どったら、正体不明植物の葉に似たものになるのだが、ということで、再び冒頭の花に話題が戻るという仕掛け。 しかし、問題のそれは、トウワタとは関係無さそうな植物であるから、無意味な仕掛けでありました(笑)。
2017.06.24
コメント(8)
-

偐万葉・もも篇(その2)
偐万葉・もも篇(その2) 今日は久しぶりに偐万葉です。シリーズ第283弾となる、偐万葉・もも篇(その2)であります。 <参考>過去の偐万葉・もも篇はコチラから。 ももの郎女さんのブログはコチラから。 偐家持がももの郎女に贈りて詠める歌20首 並びにももの郎女が詠める歌2首ほか 水走(みづはい)に 咲ける椿の つばらかに 今日も暮らさね ももの郎女(本歌)奥山の 八峰(やつを)の椿 つばらかに 今日は暮さね 大夫(ますらを)のとも (大伴家持 万葉集巻19-4152)くれなゐに にほへる桃の 花撮りつ いつしか知らず 春をまとへり(本歌)春の苑 紅(くれなゐ)にほふ 桃の花 下照る道に 出で立つ少女(をとめ) (大伴家持 万葉集巻19-4139) (椿と桃) 書に倦まば 訪ね来てみよ 鵲の 森と梟 妹待つらむぞ (森ノ宮キューズモール) 君がため わが手もすまに 春の野に 摘める蒲公英 これぞ召しませ (水走郎女)(本歌)戯奴(わけ)がため わが手もすまに 春の野に 抜ける茅花(つばな)ぞ 食(を)して肥えませ (紀女郎 万葉集巻8-1460) (タンポポの花) チリリンと レディバードの ベル鳴らし 春の小川の 道行け我妹(わぎも) (虫家持)テントウの 赤きチリリン 颯爽と 花の下行く 玉串の道 ももの郎女が返せる歌1首風吹けば 川の桜が 舞い踊り ナミテントウも サンバ踊れる (天道虫のベルと玉串川の桜) 春たけて 桜さきくさ 芝桜 鈴蘭水仙 美山ぞ幸(さき)け (花家持)(注)三枝=さきくさ。ミツマタのこと。幸け=さきけ。「さき」は「幸(さき)」と「咲き」を掛けている。(本歌)春されば まず三枝(さきくさ)の 幸(さき)くあらば 後にも逢はむ な恋ひそ吾妹(わぎも) (万葉集巻10-1895) (ミツマタと鈴蘭水仙) (美山町) 和束なる活道(いくぢ)の岡の茶畑に 逢へる兒やたれ茶々姫なるか (偐安積皇子) (茶茶ちゃん) 大峰の 深山(みやま)の奥の 静謐を 花とし咲くや 大山蓮華 (蓮家持) あぢさゐの 八重に咲くごと ペリカンの 家にある人 みな幸(さき)くあれ(本歌)紫陽花の 八重咲く如く やつ代にを いませわが背子 見つつ思(しの)はむ (橘諸兄 万葉集巻20-4448)言問はぬ 花にしあれど 道の辺に 咲きて今日もか われをはげます(紫陽花) ももの郎女が贈り来れる句に 偐家持が付けたる脇句各2句風涼しやま宿にしてねまるなり (切株の梟君) (元句)涼しさを我宿(わがやど)にしてねまる也 (松尾芭蕉 おくのほそ道) 花笠音頭 までは踊らず(石切の家持)(注)ねまる=くつろいで坐る、という意味の東北の方言。 元句は奥の細道の旅で出羽尾花沢の俳人、清風の館で歓待を受けた時の挨拶句。清風は尾花沢の豪商、鈴木道祐のこと。ふくろふはいづこ卯月の迷ひ道 (ももの郎女)(元句)笠島はいづこさ月のぬかり道 (芭蕉)さしも知らぬか袋小路と(五月の家持)(注)さしも知らぬか=それも知らぬか。 これは、「かくとだにえやはいぶきのさしも草さしもしらじなもゆるおもひを」(藤原実方 後拾遺集612 小倉百人一首51)から持って来た語句。笠島は実方の塚のある土地。現在の宮城県名取市愛島笠島。実方は陸奥守に任じられこの地で没している。芭蕉は奥の細道の旅で笠島を通った時に実方の塚のある地は何処かと尋ねるも立ち寄らずやり過ごしているが、元句はこの折の句。 花の名は覚えるものぞ水走(みずはい)の 八十(やそ)この道に咲ける兒やたれ (草家持)(本歌)紫は 灰さすものぞ 海石榴市(つばいち)の 八十の衢(ちまた)に 逢へる兒や誰 (万葉集巻12-3101) (ミヤコワスレとスミレとヨモギ) 鳥や風 運び来(きた)れる 草花の 数多(さは)に咲けかし ペリカンの家 (草家持) ペリカンの嘴(はし)にも負けずペリカンの 家にどでかくアマリリス咲く(デカルト)(アマリリス・ベラドンナ) 家持が 安積(あさか)の皇子(みこ)と 宴(うたげ)せし 丘にか妹は 蓬摘むらむ (安積皇子墓と活道の丘公園 ) やちぐさのうつろふ花とひとは言へ うつろふゆゑにいとしとわが見む (にせ家持)(本歌)八千種(やちぐさ)の 花はうつろふ 常盤(ときは)なる 松のさ枝を われは結ばな (大伴家持 万葉集巻20-4501) (アカバナユウゲショウとシロツメグサ) 紫ににほへる花をいならべつ よく見てよしと言へる兒やたれ(ペリカン堂家持)(本歌)紫は 灰さすものぞ 海柘榴市(つばいち)の 八十のちまたに 逢へる兒やたれ (万葉集巻12-3101)(紫の胡蝶蘭) 玉葱のごとやなれると柘榴の実 言へるひとあり日々また楽し(玉葱家持)玉葱を軒に吊るしてわれ言はむ 柘榴のごとやさはにしなると(柘榴家持)花柘榴八重にし咲くは秋待てど 花のみ咲きて実にはならざり(八重家持) (ザクロの花とコマツヨイグサ)(替え歌)飲めば度が過ぎ ほど知らず酔過草の 忘れ傘今宵は雨も 降りさうな (酔漢夢二)(元歌)待てど暮らせど 来ぬ人を宵待草の やるせなさ今宵は月も 出ぬさうな (竹久夢二) ももの郎女が返せる歌1首玉葱が ぶらり木になり 初夏になり 紅き花見て 柘榴と知れり(注)掲載の写真は、ももの郎女さんこと「☆もも☆どんぶらこ☆」さんのブログからの転載です。
2017.06.22
コメント(8)
-

岬麻呂旅便り205・道東(釧路・根室・知床)
本日は朝から雨。梅雨入り宣言があってから初めてというか久々の雨である。こういう日は銀輪はお休みである。旅先の場合はこのような日も雨具を着用して走るのであるが、これまでそういう目にあったのは、新発田市の加治川沿いの道とか富士市から富士宮市への道など数えるほどしかない。 それはさて置き、このような日でもよくしたもので、友人の岬麻呂氏より旅便りが届くなど、ブログ記事のネタには困らないのである(笑)。 同氏の旅は、「岬巡り」というその名が示すように、日本各地の岬・灯台を巡るというのが、その本来のコンセプト。ということで、今回はその本来の旅の目的を示すためとてか、4灯台の写真を特別に送って来られましたので、先ずはそれらの写真から紹介申し上げます。(釧路埼灯台) 「埼」と「崎」の二通りの表現があるが、これについて調てみると、「埼」は海洋部に土地が突出した地形を表現するのに対して、「崎」は山の先端部が平地に突出している地形を表現しているのだそうな。 旧海軍時代から海図などでは「埼」が使用され、海上保安庁もその伝統に従って、「埼」を使用しているとのこと。これに対して、旧陸軍陸地測量部では「崎」を使用していて、その後身である国土地理院は「崎」を使用しているとのこと。 本来の地形から言えば「埼」が正しい使い方なのかも知れないが、その突出部の前に平地があってその先が海面であるなら、山塊部が「崎」で、平地部分が「埼」ということになるところ、灯台がその山塊部の上に設置されていれば、そこは「崎」を使用する方が正しいとも言える。まあ、こんな議論をしてもそのサキは不毛であるからどちらでもよいのだが、海図と地図で表示が異なるのは如何なものかと考える人もあるようですな。 小生などは海上から見たら「埼」で、陸地から見たら「崎」でいいのでは、なんぞと鼻にも掛けないのであるが、岬でも「サキ」ではなく「鼻」と名のつくものもありますね。出張っているから「鼻」。これは分かり易い。埼・崎双方にも当てはまるから、全て「鼻」にしたらどうかと提案したが、「鼻につく」とかいう理由にもならぬ理由で「ハナ」から相手にされませんでした(笑)。こういうのを「出鼻をくじかれる」と言うのですな。(納沙布岬灯台)(花咲灯台) 灯台は日本全国で3000以上もあるそうです。 港の入口部分などにある誘導灯のようなものも灯台の範疇に入れると5000以上とか。因みに、この港口部の灯台は、右側に設置するものは赤色、左側に設置するものは白色と決められているそうです。 なお、赤白の縞模様の灯台は、1957年(昭和32年)に石狩灯台が映画「喜びも悲しみも幾年月」のロケで使用される際に、それまでの白一色から赤白に塗り替えられたのが最初で、これを契機にして全国各地の灯台にこれが広まったらしいです。<参考>石狩灯台・石狩の紅白(羅臼灯台) さて、旅の次第は、恒例により、ご本人による下掲の「旅・岬巡り報告205」をご参照戴くこととします。(旅・岬巡り報告205) 6月13日から16日までの3泊4日のご友人との道東二人旅であったようです。 (釧路港) 霧の釧路港。いいですね。初日は幣舞橋のたもとのホテルに宿泊、「夜霧の街に出て海鮮と地酒楽しむ」と書かれています。(幣舞橋) 写真の「釧路の夜」とあるのは美川憲一の歌碑だそうですが、どんな歌であったか記憶がない。(風連湖と丹頂鶴) 2日目の14日は天気が好いので釧路湿原の丹頂鶴の予定を変更し、根室・納沙布岬へと向かわれましたが、途中、風連湖で丹頂鶴をご覧になられたようです。(納沙布岬)(花咲車石) 花咲灯台の下の崖。柱状節理の球状形態でめずらしいものだそうな。 そして、日本最東端の駅、東根室駅。(東根室駅)(瀬石温泉) 知床半島南東側の海岸に湧出している温泉に、相泊温泉と瀬石温泉がある。地元民は勿論、旅人も自由に入浴できるそうな。生憎の干潮時にて湯温が高くなり過ぎていて入れなかったとのことです。海水で薄めるためのバケツなどは積んでいなかったということですな。 ブロ友のふぁみり~キャンパーさんや偐山頭火さんなら何とかしてでも入ろうとなさるかも知れませんが、ヤカモチは元よりその気がないから、パスが当然です(笑)。 3日目、15日は知床半島のドライブ。(知床五湖) 知床岬へのクルージングは予約を取り消して、オシンコシンの滝、以久科原生花園、浜小清水駅から緑駅経由して「神の子池」、裏摩周展望台、養老牛温泉を経て阿寒湖温泉泊。 お疲れ様でした。(神の子池) 最終日16日は、阿寒湖遊覧船(マリモ展示観察センター)、オンネトー、足寄動物化石博物館、幸福の黄色いハンカチ想い出広場、新千歳空港。(幸せの黄色いハンカチ想い出広場) 全行程1277kmの超ロングドライブの旅でありました。 <参考>過去の岬麻呂旅便りの記事はコチラからどうぞ。
2017.06.21
コメント(8)
-

石宝殿古墳へ
地図を見ていて以前から気になっていた石宝殿古墳というのを見て来ました。 石の宝殿と言うと、兵庫県高砂市の「石の宝殿」を思い起こさせるが、こちらの石宝殿古墳が目にとまったのも高砂市のそれを連想したからでもある。 <参考>日本三奇・石乃宝殿(生石神社)2008.11.29. この古墳は寝屋川市打上地区にある。JR東寝屋川駅の南東600m位の位置にある。コモンシティ星田の住宅団地の南西隣である。(石宝殿古墳付近見取図) と言っても、銀輪家持。電車などで行く筈もない。自宅を午後1時過ぎに出発し、MTBでやって来ました。上の地図で言うと、JR線の東側の道路を南から走って来たのでありました。この地図は北が下で南が上、普通の地図と反対になっているので、少し勘が狂うのであるが、北から上って来た坂道に北向きに設置されていたものなので、現地でこれを見ている人の目線に合わせて、進行方向である前方(つまり、南方向)を上にして表示されているという次第。これだと方向音痴な人でも読み間違いはしないだろう。極めて分かり易い表示になっている。 知らない土地でどちらが北とも南とも分からない場合、現地での前後左右に関係なく、機械的に北を上にしている地図では、行く方向を取り違えることがあるが、前方向を上に、後ろ方向を下にして表示すると、左は左方向、右は右方向と眺めている人の身体の前後左右と一致するので、見たままとなり、解釈し直す必要がない。案内地図を設置する場合は、かくあって欲しいものであります。自転車MTBは打上公園に停めて、階段の道を上る。上り切ると高良神社の前である。(高良神社<打上神社>)<参考>打上神社 案内図では打上神社と表示されているが、鳥居前の石標では高良神社になっている。 高良神社と言えば、「仁和寺にある法師、年寄るまで石清水を拝まざりければ、心うく覚えて、ある時思ひ立ちて、ただひとり、徒歩より詣でけり。極楽寺、高良などを拝みて、かばかりと心得て帰りにけり。さて、かたへの人にあひて、『年比思ひつること果し侍りぬ。聞きしに過ぎて尊くこそおはしけれ。そも、参りたる人ごとに山へ登りしは、何事かありけん、ゆかしかりしかど、神へ参るこそ本意なれと思ひて、山までは見ず。』とぞ言ひける。少しのことにも、先達はあらまほしき事なり」(徒然草第52段)が思い出されるが、これは、石清水八幡宮の摂社である高良神社のこと。 久留米に高良大社というのがある。宇佐八幡を石清水に勧請する際に、同じ九州なので、久留米の高良の神様(高良玉垂命・高良大明神)も勧請したのかとも思ったが、石清水の高良社は、元は河原社と呼ばれていて、「カハラ」⇒「カウラ」⇒「コウラ」と変化して「高良」になったと説明するものや「高麗」からの変化だと説明するものもあってよくは分からぬ。 さて、こちら、寝屋川市打上の高良神社。祭神は武内宿禰らしい。江戸時代までは、祭神は高良大明神で社名も高良神社とされて来たが、明治になって打上神社に社名が変更されると共に、祭神も武内宿禰になったそうな。尤も、高良大明神という神様の正体が不明であり、武内宿禰のことであるとする説もあることから、この説に準拠して、明治の社名変更と共に祭神の表示も変更したのかも知れない。(同上・参道の玉垣) 面白いと思ったのが、この玉垣である。右側がズラリと井上さんで、左側奥が全部田中さんである。そして、振り返ると参道反対側の玉垣にはズラリと田伐さんの名前。その他の名前もあるにはあるが、同姓の多い玉垣であることです。たまたまに 見し玉垣は 井上と 田中ばかりの 名にてあるなり (偐家持)(同上)(高良神社・拝殿)(同上) 高良神社の境内脇から石宝殿古墳へと続く山道がついている。昭和6年の銘のある石標が設置されているので、登り口であることが分る。(石宝殿古墳への登り口)(石宝殿古墳・説明碑)(石宝殿古墳)<参考>石宝殿古墳(同上・石室) 石室は花崗岩をくりぬいて造られていて、小さく狭い。火葬して納骨したものであるか。 (石宝殿古墳・右側<東側>から見た石槨)(同上・左側<西側>から見た石槨)(打上の自然・案内石碑) 鳥居前まで戻って来ると、向かいにあったのが打上行者堂。行者堂という名かどうかは、表示もないので分からないのであるが、正面の石柱に刻まれた「打上行者堂修復記念」という文字から、そういう名なのだろうと思った次第。(打上行者堂) 古墳の石室みたいな所に役小角、役行者の石像が鎮座されて居ります。(同上) この行者堂の上の小さな空間は、ちょっと休憩するには丁度良い場所である。眺めも素晴らしい。眺望をパノラマ撮影してみました。180度の眺望である。下の写真では小さ過ぎますから、特大サイズの写真でご覧になられることをお薦めします。(打上行者堂からの眺め)特大サイズの写真で見るならコチラから。 打上公園の自転車を駐輪していた場所に戻って時間を見ると14時33分。帰宅することに。帰途は下りである。楽なもの。 旧国道170号を走り、寺川交差点で右折し西へ、外環状道路に出て、これを南へ。東大阪変電所西交差点で右折西へ、恩智川畔に出て川沿いの道を南へ。 恩智川べりでは、例の名前不詳の花の咲き具合を土手の道から遠望したが、咲いている気配がない。一部顔を覗かせていた蕾も未だ花開いていないのか、よく見えない。ということで、川原に降り立つことはせず、水走の喫茶店「ペリカンの家」へと向かう。 到着が15時27分。54分を要したことになるが、思ったよりも早くに着きました。珈琲休憩である。汗だくなので、アイスコーヒー。先客は、男性が一人、小生は初めてお目にかかる人。その近くに席をとり、店主のももの郎女さんと客の男性と3人で雑談タイムでありました。男性がお帰りになり、時間を見ると16時25分。ペリカンの家の閉店時刻は17時であるから、小生もおいとますることとしました。帰宅は16時40分頃。 以上です。本日の記事は近隣散歩の記事でありました。
2017.06.20
コメント(4)
-

続・恩智川畔の花たち
6月16日の日記は「恩智川畔の花たち」でありましたが、今日の日記はその続編です。 先ずはコゴメマンネングサの群落から。コゴメマンネングサの花は6月1日の記事にその写真を掲載していますが、その頃が花の盛りであったようで、今は殆ど花が見られない。<追記:訂正注記>このページで「コゴメマンネングサ」としているものは、メキシコマンネングサの誤りでありますので、これに読み替えてお読み下さい。(コゴメマンネングサ) (同上) それでも、このように咲いているのも少しはある。 (同上) 花の散ったアトの花柄はサンゴのように見えなくもない。 (同上) (同上) 群落と言えば、こんな群落もありました。 (チチコグサモドキの群落) チチコグサモドキの群落である。チチコグサやチチコグサモドキはよく目にする草であるが、普通は他の草に混じって数本程度が遠慮がちに生えているというのであって、このように群生しているというのは珍しい。 (同上) 次はアレチハナガサのもうひとつの顔です。アレチハナガサの花は上記の6月16日の記事に写真を掲載して居りますが、可憐な美しい花である。(アレチハナガサの枯穂) 花が散るとこんな姿になる。まさに「花の色は移りにけりな」であるが、これはこれでなかなかに風情があるというもの。テントウムシの蛹がくっついていたのはご愛嬌であるが、「枯れてこそなる味もあるなれ」という趣のある佇まいである。 (同上) その傍らで元気な姿を見せていたのは、カヤツリグサ。もう蚊帳は死語にて「蚊帳吊り」なんぞというのはリアリティの無い言葉になってしまっている。(カヤツリグサ)蚊帳のことは忘られけりないたづらに 蚊帳吊り草は咲きてもあれど(家蚊持)(同上) そして、アカバナユウゲショウ。友人の小万知さんは、石川べりでであったか、白花のアカバナユウゲショウを見た、と仰っていましたが、小生は未だ見たことがない。(アカバナユウゲショウ) 白花であってもシロバナユウゲショウとは言わずアカバナユウゲショウと言うのだそうだが、赤毛のアンが年老いて白髪になっても「白毛のアン」とは呼ばないのと同じですな。 クロネコヤマトは河内にあってはシロネコカワチと言うべきだと、ヤカモチは「強弁」しているが、誰一人「勉強」になったと賛同を示さないのも同じ理由からでしょうな(笑)。(同上)<追記:2017.6.21.>小万知さんから白花の写真が送られて参りましたので、参考までに掲載して置きます。 (白花のアカバナユウゲショウ) ヘラオオバコもありました。普通のオオバコに比べて葉が「ヘラ」のように細長いのでヘラオオバコと言うのでしょう。このオオバコ、別にヘラヘラしている訳ではないのである。(ヘラオオバコ)(同上) 次はホソムギ。(ホソムギ) ネズミホソムギというのもあるので、上の写真のそれはネズミかも知れないが、下の写真のそれは穂がしっかりとして立派であるから、ホソムギだろうと思う。 (同上) そしてノビルです。花のアトになる黒っぽい粒々のもの、ノビルの種子かと思っていたが、ノビルは殆ど結実することはなく、ムカゴによって繁殖するのだという。であれば、これはムカゴであるのだろう。(ノビルのムカゴ) 花が咲いている時期やムカゴがまだ小さい時期はノビルは直立している。しかし、ムカゴがここまで大きくなり、茎も枯れかかって来ると、さすがに直立は困難なようで、このように項垂れる。こうなるともう「ノビル」ではなく「ダレル」なのである。 (同上) はい、完全にダレてますな。 (同上) (同上) ダレている奴がいれば、ネジけている奴もいる。ネジバナである。(ネジバナ) この花は拗けていても、その姿が可愛いので、誰も拗けていて怪しからんとは言わない。むしろ拗けているところが素敵であるなどと言われたりもする。この花はその見かけの可愛らしさによって随分と得をしていると言うべきか。 (同上)(同上) 上の花などは 拗けているだけでなく、曲がってもいるし、下の花などはヨモギの一家団欒に闖入し、我が物顔にそっくり返っているのであるが、通りすがりの女性などは「わあ~カワイイ」などと言い、その礼儀の無さを咎めないのである。ヤブガラシやヤブジラミやヘクソカズラなどは「不公平である。」と近く「花の取扱い均等法」の制定を国会に請願することにしているそうな。(ネジバナとヨモギ) (ネジバナ) 次は、普通に咲いているヒメジョオン。これもどこででも見かける花にてブログに載せるほどの草花ではないのであるが、「花の取扱い均等法」という話もあるそうだから、その精神を先取りして掲載する次第にて候。(ヒメジョオン) (同上)(同上) 最後はヤブガラシであります。(ヤブガラシ) (同上) さて、問題の名前不明の花です。 本日の銀輪散歩でも、堤防上の道からその花の生えている場所を遠望しましたが、まだ花の開花は見られなかったので、河原に降り立つ労は惜しみました。 以上です。
2017.06.19
コメント(10)
-

セイバンモロコシにてアシからず
今日(17日)の銀輪散歩でも恩智川の川辺を走りました。 昨日の記事で「アシの穂」として紹介した写真について、何となく気になっていたのですが、再度、その花穂を撮影することにしました。 ススキではないし、川辺なのでアシだろうと思ったのであるが、アシにしてはほっそりの小柄タイプであること、穂もボリュームが無いことなどが気になっていたのでした。 で、その写真をネットの図鑑などのイネ科やアシの仲間の植物の写真と見比べてみました。すると、どうやらアシではなくセイバンモロコシという植物のようであるのでした。昨日の記事については、追記にてその旨の訂正を行いましたが、今日撮影したセイバンモロコシの花穂の写真を掲載して、今日の日記記事とさせていただきます。(セイバンモロコシの花穂) 昨日の記事では、何となく予感がしたのか、アシでなければ「あしからず」とエクスキューズの文言を書き添えていますが、その予感が的中でありました(笑)。 セイバンモロコシという植物の名は、ぼんやりとながら過去に耳にしたか、見たかした記憶はあるものの、どんな植物であるかは存じ上げませんでした。 (同上)<参考>セイバンモロコシ・Wikipedia これがセイバンモロコシなら、恩智川畔を走れば、直ぐに目に入るのでありますから、お馴染みの植物であります。小生はこれまで、これはアシの穂だろうと決めつけていたのでした。 今回、セイバンモロコシの花穂やアシの花穂の写真をネットで検索してみましたが、この写真の姿は、アシのそれよりもセイバンモロコシのそれに近いのでありました。 (同上)(同上) 穂の赤茶色とそこから垂れ下がっている小さな花の黄色が美しい。 (同上) 今日の日記は手抜きにてこれだけにして置きます。 野崎観音の前まで走っただけでしたが、色々な花を見掛けました。それらは、また銀輪花散歩の記事に使わせていただくこととします。 ただ、昨日の日記の末尾に写真掲載した名前不詳の花の今日の姿だけご紹介して置きます。今日見てみると、濃いピンク色の蕾が花苞の間から顔を覗かせていました。 どうやら、この植物は赤またはピンクの花を咲かせるようです。手掛かりが一つ増えましたので、明日にでもネットで心当たりを調べてみます。(名前不詳の花の今日の姿)
2017.06.17
コメント(6)
-

恩智川畔の花たち
この処、銀輪散歩も目ぼしい立ち寄り先がなく、専ら見かけた花などでお茶を濁していますが、名前の知らなかった草花などに出くわし、その名前が何かと自分で調べて、これだと分ると愉快なもので、個人的にはそれなりに楽しんでいます。 昨日15日は、昼食後、恩智川畔の或る花の写真を撮るためにMTBを走らせました。その花というのは、6月9日の銀輪散歩で恩智川べりを走った際に遠目に見て、何だろうと下のような写真を撮った花でした。アレチハナガサではないかと思われたものの、遠くから撮った写真でよくはわからなかったので、近くまで寄ってその正体を確かめようというものでありました。(何の花?) 9日のそれは、河原には下りず、堤防脇の道から撮った写真であったので、アレチハナガサかもと思ったものの、確信が持てませんでした。 で、15日は河原に下りてみました。(アレチハナガサ) 近寄ってしっかりと見ました。間違いなくアレチハナガサです。 (同上) もう、これでこの日の銀輪散歩の目的は果たした訳で、引きあげても よかったのであるが、折角なので河原を少し歩いてみました。カヤツリグサ、ヒメジョオン、コゴメマンネングサなどがありましたが、これらは撮影せず。 カラスムギがいい感じであったので、カメラを向けました。(カラスムギ) カラスノエンドウの莢は熟れると真っ黒になるので、如何にもカラスであるが、カラスムギはこのように白っぽい。緑色の若い種苞が薄茶色になり、更にその色が薄くなって白っぽくなる。こうなるとカラスムギではなくシラサギムギである。(同上) しかし、種苞の中の種子はと見るとカラスムギ であることが納得される黒っぽい茶色なのである。 そして、こんな豆莢もありました。スズメノエンドウだろうと写真に撮ったのですが、何か感じが違う気がしたので、調べてみると、スズメノエンドウの豆莢は細かい毛が生えていて色ももっと黒っぽいことが分りました。ならば、カスマグサかと調べてみると、果たしてそうであった。カスマグサの豆莢はツルリとして毛がないのでありました。(カスマグサの種子)(同上) そして、アシの穂。このように間近に見ることは余りないので、何か別の植物ではないのかという疑問が生じて来るのであるが、撮影した時にはアシだと思っていたのであれば、アシに違いないと言い聞かせているのでありました。もし、違っていたら「あしからず」である。 (アシの穂) 穂先に見える小さく垂れているのがアシの花なんでしょうね。 「はい、アッシが花でござんす。」と言って居ります。<追記> アシでなかったらアシからずと申し上げましたが、どうやら、その「アシからず」のようです。アシではなくセイバンモロコシの花穂のようです。今日(17日)の銀輪散歩で、再度この花穂を写真に撮り、アシの花穂とセイバンモロコシの花穂と比較してみたところ、これはアシではなくセイバンモロコシであるという結論に達しましたので追記訂正して置きます。 <参考>セイバンモロコシ・Wikipedia(同上) 風になびいているこの草はオオニワホコリ。 もっと、背丈の低いのをよく見るが、それがニワホコリで、このように背丈の高いのがオオニワホコリなのである。(オオニワホコリ) 背が高いからと言って、それを誇っている訳ではない。背が高かろうが低かろうが「埃」に過ぎないのである。 (同上) これは河原に生えていたものではなく、川沿いの先にある加納緑地に生えていたもの。クサイだと思う。 別に「臭い」わけではない。草の藺。藺草の仲間である。草藺草・クサイグサが縮んで草藺・クサイとなったのであろうが、イグサが既にして草なのであるから、草を付けた人は余程に不精な性格であったようです。お蔭でこの草、クサイ、クサイと言われてクサっています。(クサイ<イグサの仲間>)(同上) 次は昼顔。顔花というのは、目立つ花一般に対する呼称であったようだが、やがて現在の朝顔、昼顔、夕顔などを指す言葉となったよう。 (ヒルガオ) 同じヒルガオでも、海辺や海に近い川辺では、ハマヒルガオというのがよく咲いている。 花だけを見ているとその違いに気が付かないのであるが、葉が明らかに違うのでそれと分かる。と言ってもよくは分からないでしょうから、ハマヒルガオの写真も掲載して置きます。勿論、これは恩智川畔では見られない花である。淀川の河口近くとか神戸・明石方面の海辺の自転車道を走っていただかねばなりません。(ハマヒルガオ)(ハマヒルガオの葉) 再び、恩智川の河原に戻っていただきます。 ヒメスイバが美しい赤色を見せていました。(ヒメスイバ) ヒメスイバの近くに咲いていたこの花。よく見る花であるが、名前が思い出せない。 (名前不詳)<追記>トウバナ(塔花)でした。(下記、小万知さんコメント参照) <参考>トウバナ・Wikipedia そして、見たこともないと思われるのが、この花。まだ、蕾にて、白い花とも赤い花とも分からぬ花にて、この特徴ある葉だけの手掛かりではヤカモチ捜査一課長も取り調べに苦労なのである。まあ、これも「ものは考えよう」にて、花が咲く頃にまた訪ねてみて、新たな手掛かりを得るという楽しみもあることになる(笑)。(名前不明) まあ、ヤカモチさんの楽しみは楽しみとして、上の二つの花の名前をご存じのお方が、これこれだと教えて下さることをご遠慮申し上げるものではありませんので、念のため申し添えて置きます。
2017.06.16
コメント(8)
-

囲碁例会・里山散策
昨日(14日)は囲碁例会の日。先週は雨で梅田へは電車で参りましたが、この日はお天気も好しで、愛車のMTBで移動。いつもの昼食場所のれんげ亭は「支度中」の表示であったので、店の前を素通りして梅田スカイビルへ。スカイビルの喫茶店で昼食としました。サーモンチーズサンドとアイスコーヒー。 昼食後、まだ少し時間が早いので里山を散策しました。(ナンキンハゼ) 前庭に植えられた並木が黄色に輝いて、花が咲いているかのようでした。近寄ってみると、花ではなく葉が黄色になっているのでした。 斑入りの葉の斑の部分が大きくなって遠目には黄色の葉に見え、チラリと見た印象では黄色の花が咲いているようにも見えるということであったようです。 ナンキンハゼという銘板がありました。 ナンキンハゼはよく見る樹木であるが、このような斑入りの葉のものもあるとは知らぬことでした。品種が異なるのでしょう。(同上) 里山の手前の広場では、遠足の小学生たちがお弁当を広げていて賑やかなことでした。 里山には稲のほか、ジャガイモ、茄子、トマト、レタスなどの野菜も植えられている。今日はジャガイモの収穫の日であったようで、お昼休みの時間帯を利用して、このビルで働く人たちが芋堀をなさっていました。眺めていると、「一緒にやってみませんか」と言われましたが、そこまでの時間もないので、ご辞退申し上げました(笑)。 (新梅田シテイ・里山でジャガイモ掘り) 里山散策で目を惹いた 花たちのご紹介は後に回して、囲碁例会の会場となっている部屋のあるビルをご紹介して置きます。(新梅田シティ・ガーデン5) 上の写真の正面のガラス張りの5階建てビルに会場があります。 新梅田シテイは、東西タワーの梅田スカイビル、その付属棟のガーデン5・ガーデン6のオフィス棟とウェスティンホテルのホテル棟に地下飲食店街の「滝見小路」、中自然の森、里山、屋上の空中庭園とで構成されています。(同上) もう少し近くから撮影すると、ガーデン5はこんな感じ。会場のあるのは、最上階の5階、上の写真で言うと、右端にテラスのある部分から斜めにせり出している部分までがその部屋ということになります。 会場の部屋に入ると、福〇氏が来て居られました。早速に同氏とお手合わせ。対局中に、竹〇氏、荒〇氏、平〇氏がご来場。この日の参加者は全5名でした。 小生は福〇氏に負け、荒〇氏に勝ち、平〇氏に負けで、この日は1勝2敗。これで今年の通算成績は10勝16敗。もう少し頑張らなくてはいけません。今年後半戦で何んとか五分の成績までは戻したいものであります。 さて、里山の花散歩であります。 ジャガイモ掘りの近くに咲いていたのはこの花。(ウイキョウ<茴香・フェンネル>) 何んという植物なのか分からなかったのですが、多分何かの野菜の花だろうと調べると、ウイキョウであることが判明しました。花火のような花です。(同上)<参考>フェンネル・Wikipedia 全体の姿はこのような状態。人間の背丈に近い高さです。(同上) 小径を挟んで反対側で風にそよいでいたのはバーベナ・ボナリエンシス。ヤナギハナガサ(柳花笠)という別名もある。 この花の名は、ブログ管理ページに表示される広告にたまたまバーベナの花が登場していて、それと知ったのでありますが、広告もこのように役に立つ面もあるから、うるさいだけではない(笑)。 <参考>囲碁例会・梅田の里山の花たち 2014.6.4.(バーベナ・ボナリエンシス)<参考>バーベナ・Wikipedia(同上) そして、ミント。何というミントかまでは分かりませんがミントだろうと思います。 (ミント)(同上) ミントの傍らには、白い花のカタバミが群れ咲いていました。カタバミと言えば黄色の花が普通。ピンクのムラサキカタバミや濃いピンクのイモカタバミなどもあるが、白い花のカタバミを見るのは初めてかも知れない。(白花のカタバミ)(同上) そして、これはユキノシタの仲間だろうと思う。花の形が普通のユキノシタとは異なるが、葉の感じや、花の付き方がユキノシタのそれと似ている。ユキノシタ属でネット検索するも、このような花のものは見当たらなかったので名前は不明である。(ユキノシタの仲間)<追記>小万知さんからヒュウケラという名前だと教わりました。 学名がヒュウケラ(heuchera)、ツボサンゴとも言うようです。 <参考>ツボサンゴ・花と緑の図鑑 (同上) 名前不詳と言えば、こんな花もありました。蔓性の植物だと思われるが可憐で清楚な美しい花である。(名前不詳の白い花)<追記>これも小万知さんからルリマツリの白花だと教授いただきました。 学名、プルムバーゴ(plumbago) <参考>ルリマツリ・花と緑の図鑑(同上)
2017.06.15
コメント(6)
-

補足的銀輪花散歩
先日来から、花散歩関連の記事が続いていますが、本日も銀輪花散歩の記事であります。10日の花散歩記事に掲載したヒメコバンソウの写真がイマイチであったので、ヒメコバンソウ探しの銀輪散歩に出掛けました。出掛けたのは昨日(12日)のことでありましたが、記事アップが本日となりましたので、記事の便宜上、本日の銀輪散歩として記事を書くこととします。 10日記事のそれは、枯れてしまったのを撮影した上、ピントがうまく合ってなくて、ヒメコバンソウらしくない写真になっていたので、未だ枯れていないのを探して撮影しようということでありました。従って、銀輪散歩も「走る」ことよりも「小判探し」に重点を置いて、という心づもりでありました。小さな目立たない草なので、見つけるのに苦労するだろうと思ったからであります。 しかし、なんと最初に立ち寄った花園中央公園でなんなくそれは見つかってしまいました。(ヒメコバンソウ)(同上) 小さな花と言えば、ニワゼキショウ。 この花の種も「話のネタ」になるかと撮影することに。(ニワゼキショウ) 花以上に微細なこれ。今までまじまじと眺めたことがなかったので、新発見でありました。 ヒオウギの種、ぬばたま(射干玉)を小さくしたような姿であるが、ぬばたまのような黒光りする光沢はなく、朝顔の種のようなつや消しの黒である。(ニワゼキショウの種子)(同上) 小さな花では、トキワハゼも咲いていました。 こういう小さな花や種子は、小生手持ちのコンパクトデジカメでは、なかなか上手くピントが合わないので、撮影は結構手間である。カメラのご機嫌を取りながらの撮影であります。 (トキワハゼ) 以前、小万知さんからその名を教わったムラサキサギゴケかとも思いましたが、匍匐せず茎が立ち上がっているので、トキワハゼという花かと。トキワハゼというのはカキドオシの別名かと思っていたのですが、両者は別の植物であったということを今回知りました。(コマツヨイグサ) 10日の記事にはコマツヨイグサの花の写真も掲載していましたが、つぼんでいる花しか写っていませんでした。今回、咲いているものも写しましたので掲載して置きます。 今宵は月も出るそうな、と言って居ります。(同上) 上のコマツヨイグサの右隣に写っているのはチチコグサ。 葉の緑がこれよりも濃くて葉の裏が白いのがウラジロチチコグサ。もう種を綿毛(絮)に乗せて風に散らせてしまった後にて、花の姿はない。この花は綿毛になってから目にとまるので、花がどんなであったかが記憶にない。多分目立たない花であるのだろう。ハハコグサの花が黄色なのに対してチチコグサのそれは白色だという認識はあるのだが、どうもそれが咲いている姿をしっかりと見たという記憶がないのである。 (ウラジロチチコグサ) 蟻がいました。これが花なんだろうか。花が散り、種が飛んでしまった後の花萼のようにも見える。隣の蕾のようなものに蟻がいるから、これが花でしょうか。(ウラジロチチコグサと蟻) こちらのウラジロチチコグサは随分と大きい。この草は荒れ地など痩せた土地に生えていることが多いので、普通は小型の植物というイメージなのだが、土壌に栄養分が豊富だとこのような大きい草に変貌する。コクチナシが植えられた公園外周の花壇の一画であるから、土壌に恵まれているのでしょう。花壇の主たるコクチナシに覆いかぶさるようにのさばっている。(ウラジロチチコグサ) ウラジロチチコグサにのさばられているコクチナシであるが、そんなことは少しも意に介さず、このように花を咲かせていました。こちらはウラだけでなくオモテも白い花である。(コクチナシ) (同上)(カタバミの種子) カタバミも種をつけています。 そして、笹です。笹の葉の付け根には髭があるのですね。微細な花や種子を写真に撮っていると、自然にそういう部分に目が行くようであるのが面白い。(笹の髭) (同上) 竹は花が咲くと枯れると言うが、この髭の部分が何らかの理由で成長して花になるのだろうか。そう言えば、竹の花も実際のそれを見たことがないように思う。 (同上) 以上、10日の記事を始めとする最近の銀輪花散歩記事に登場した花・植物に関連した補足記事としての銀輪花散歩でありました。 まあ、笹の髭は関係ありませぬが。補足とは言え、些か「花」に欠ける写真が多くなりましたので、最後に、忘れずに「忘れ草」の花を添えて置きましょう。万葉での「忘れ草」は八重の方のヤブカンゾウらしいですが、こちらは一重咲きのノカンゾウの花であります。(ノカンゾウ)(同上)<参考>花カテゴリの過去記事は下記からご覧下さい。 花(1)、花(2)、花(3)
2017.06.13
コメント(8)
-

墓参・花散歩・ムギセンノウでありましたか
月例の墓参。 今月は少し遅れて本日10日となりました。 墓参ではブログ記事にはならないので、墓参の道すがらに見掛けた花などを掲載するのが恒例となっていますので、先ずは、本日のそれではないのですが、以前の銀輪散歩で見掛けたものの、名前が分らず未掲載となっていた花のご紹介から始めることとします。 先ずはムギセンノウ。初めて目にする花であったが、印象に強く残る花。ムラサキカタバミの花を巨大にしたような五弁の一重咲き。麦の穂先にコスモスの花か巨大化したカタバミの花を咲かせたような、不思議な感覚に捉われる花である。(ムギセンノウ<麦仙翁>)<参考>ムギセンノウ・植物写真鑑 つまり、花は、カタバミなどに似ているので親しみの持てる雰囲気がある。花茎や葉のそれは麦のそれのように見えてやはり日頃目にしている姿に似たものがあって違和感や珍しいというものではない。しかし、馴染みの別々植物、異種の二つの植物の花茎・葉と花とが合体して一つの植物となったら、頭が少し混乱するというか、今までの自身の知識・認識にざわつきが生じる、そんな感覚になる花でありました。 しかし、これはムギセンノウという植物であると認識してしまうと、つまりこんなものなんだと「洗脳」されてしまうと、もうどうということもない普通の花に見えて来るという次第にて、洋服に下駄ばき、着物に靴ばきの人を初めて見た時のようなものかも知れない。 別名がムギナデシコ(麦撫子)。ナデシコの仲間でもあるようです。学名のアグロステンマ(Agrostemma)は、ギリシャ語のAgros(野原)とStemma(花冠)との合成によるとのこと。 このように美しい外来撫子が野原や河原に繁茂し出すと大和撫子もうかうかとはしていられないというものである。大伴家持さんだって「こちらの方がよい」と言いかねない(笑)。 (同上) 次は、 オルレア・ホワイトレース。数日後には多分忘れてしまっている名前だと思うが、純白のレース飾りのような美しい花。(オルレア・ホワイトレース) セリ科の植物であることは葉からそれと分かる。 学名はオルラヤ・グランディフローラ(Orlaya Grandiflora)。(同上)<参考>オルレア・ホワイトレース/新花と緑の詳しい図鑑 美しい二つの花の名が判明したところで、墓参と花散歩に出かけることとします。 墓参恒例の門前の言葉です。墓参の道の途中にあるお寺の門前の言葉はこれでした。(2017.6.10.の言葉) 悲しみを経験することによって、人は他者の悲しみや心の痛みというものを共感できるようになる。自身が悲しい経験をするとそんな悲しみを他者には味わってほしくないと思うようになるし、他者が悲しんでいるとそれに寄り添ったり、何か悲しみをやわらげることができないだろうかと思ったりもする。まさに悲しみは自他を結び付ける糸と言えるでしょう。 悲しみを感じると人は考える。喜びを感じても考えない訳ではないが、悲しみや苦しみは人をより深く考えさせるものであり、それが他者への理解や共感力につながって行くのであり、喜びよりも悲しみの方が自他をつなぐ糸としてはより強い糸になるということであるのだろう。 また、こんなことも言えるかと。 喜びは人とつながることによって増幅され、 悲しみは人とつながることによって軽減される。(タビラコ)<参考>コオニタビラコ・Wikipedia さて、墓参・花散歩であります。 上のタビラコは、朝、墓参に出掛けようと、勝手口を出たら、目の前の石垣に咲いていたものであります。 春の七草のホトケノザは、現在我々がホトケノザと呼んでいるシソ科の植物のことではなく、このタビラコのことである。このタビラコさんは余程に「お人好し」のようで、ホトケノザを易々と他の草に明け渡し、自身の名をタビラコ(田平子)なんぞという「仏の座」に比べれば格落ちとも言える名に甘んじたかと思えば、今度は近縁種のオニタビラコに母屋を乗っ取られそうになっている。と言うのは標準和名はタビラコではなくコオニタビラコになっているそうだからである。 田平子と鬼田平子なら、タビラコが主役で、それの大型の草だからオニタビラコという意味になるから、オニタビラコは従ということになる。 しかし、小鬼田平子と鬼田平子なら、コオニタビラコはオニタビラコの小型の草ということで主従逆転し、オニタビラコが基準の名前の呼び方になってしまう。 そのうちに別の草がタビラコと名乗ることとなり、ホトケノザの二の舞になりかねないのではないかと危惧したりもするが、当のタビラコさんはそんなこと何処吹く風と「ホトケノザも三度までは」などと思っているのかも知れない(笑)。(ドクダミ)<参考>ドクダミ・Wikipedia 上のドクダミは道端に咲いていたもの。 接近して眺めてみると花芯部はこんな感じなのですな。 下は、オダマキの実と言うか種子。途中の民家の庭先のものである。 ひろみの郎女さんのお庭にも色々なオダマキが植えられているようですが、此処のオダマキはそれらとは品種が違うもののようです。(オダマキの種子)<参考>オダマキ属・Wikipedia 同じく道端の月見草ことコマツヨイグサである。 今宵は月も出ぬそうな、と花はつぼんでござる。咲いているときは黄色い花であるがつぼむと色が赤くなる。(コマツヨイグサ)<参考>コマツヨイグサ・Wikipedia そしてヤブジラミです。 盛んに蟻が這い回っている。シラミにアリがたかるとはこれ如何に、であるが、この小さな花にも花蜜があるのだろうか。 (ヤブジラミ) それにしても、ヤブジラミ(薮虱)とは有難くない名前を頂戴したもの。 わがコンパクト・デジカメではこれ以上接近しての撮影は困難を極めるので諦めましたが、可愛い花ではある。(同上) しかし、問題はこの草の実(種苞)である。 花のアトは下の写真のような種苞がなる。この草は全体に無数の毛と言うか微細な棘に覆われている。種苞も当然にそんな状態で、草叢に足を踏み入れようものなら、コイツがズボンや衣服にビッシリとくっつくことになる。所謂「ひっつき虫」である。ヤブジラミという名もこの種苞に着目されての命名であろう。(ヤブジラミの実)<参考>ヤブジラミ・Wikipedia 墓地の小径に生えているのがこの野蒜 である。ノビルは「ヒル」として万葉集にも登場しているのは、ネギやニラと同じでその臭みに呪力があると考えられて食用に供されたからである(万葉集巻16-3829)。(ノビル<野蒜>) (同上)<参考>ノビル・Wikipedia 墓地にも色々な草が生えている。下のそれはオオバコのようだが、普通のオオバコとは様子が異なるからツボミオオバコという種類かも。(ツボミオオバコ)<参考>ツボミオオバコ・Wikipedia そして、ムラサキカタバミ。江戸時代に鑑賞用にと我が国に入って来たようだが、今は広く野生化し、雑草としても代表的なもので、もっともよく見かけるカタバミである。先日、ももの郎女さんがご自宅庭に咲いているとしてブログに写真をアップされていましたが、当ブログにはこの花のアップはなかったようです。ということで、今回アップして置くこととしました。 子どもの頃に、この花の花茎を摘んで齧ったことがありましたが、酸っぱい味がしてそこそこの味でありました。(ムラサキカタバミ)<参考>ムラサキカタバミ・Wikipedia 次は、もう枯れかかっていますが、ヒメコバンソウ。 (ヒメコバンソウ)(同上)<参考>ヒメコバンソウ・Wikipedia 更に、トキワツユクサ。この花はこれまでにも何度か掲載しているが、今回が一番よく撮れているので、重ねて掲載することとしました。 (トキワツユクサ) (同上)<参考>トキワツユクサ・Wikipedia 自宅近くまで帰って来て目にしたのがウンリュウグワ(雲竜桑)の木。枝がネジネジになっているので、落葉すると奇怪な姿となるのであるが、このように葉が繁っていると、特に目を惹くこともない木である。 桑であるなら、あの「桑の実」のような実が生ったりするのだろうかと探して「み」たが、「実」は「見」えませんでした。桑は雌雄異株だから、この木は雄株なのかも知れない。(ウンリュウグワ)<参考>クワ・wikipedia この木が落葉した姿はコチラ 最後は、チチコグサ。これも本日の写真ではないのであるが、ついでに便乗して掲載することとします。 チチコグサにも色々な種類があるようですが、これはタチチチコグサという品種でしょうか。(チチコグサ)<追記>正しくはチチコグサモドキのようです。<参考>チチコグサ・Wikipedia・チチコグサモドキ 道ばたに見る春の草たち・チチコグサ/ハハコグサのなかま
2017.06.10
コメント(8)
-

第191回智麻呂絵画展
第191回智麻呂絵画展 久々の智麻呂絵画展であります。5月3日以来ですから、1ヶ月余ぶりということになります。この間に描かれた絵は今回出展の9作品。恒郎女さんは「最近、絵を仕上げるペースが落ちている。」と仰っていましたが、40日弱で9点というのは、確かにひと頃の智麻呂氏の旺盛な創作ぶりに比べると少ない気もします。しかし、今回の作品は全て花でありますから、花の智麻呂の面目躍如、智麻呂絵画ファンの皆さまには、きっとご満足いただける内容ではないかと存じます。<参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ (母の日の花) これは、智麻呂ご夫妻のお嬢様から、母の日に贈られて来た花であります。 実際のそれはもっとボリュームのある花束でありましたが、智麻呂的手抜きで花の数も少なくし、あっさりとした感じに仕上げて居られます。これによって、絵画的には功を奏していると言うか、素敵な絵になっているのではないかと思います。 どんな風にして花びらに着色したのか不明ですが、虹色と言うかカラフルなカーネーションの花はキチンと描かれていて、この絵の主役であることを示しています。(ミヤコワスレ)<参考>ミヤマヨメナ・Wikipedia 上のミヤコワスレと下のオダマキはひろみの郎女さんからの贈り物。 智麻呂絵画ファンである彼女も色々とお花を届けて下さるのですが、今回は彼女がお持ち下さった花の絵が4点にもなりました。ミヤコワスレはミヤマヨメナの園芸種の名前で、植物分類上はミヤマヨメナということになる。(オダマキ)<参考>オダマキ属・Wikipedia 次のフリージアとキバナショウブは智麻呂氏のご友人の友〇さんからの戴き物です。友〇さんも智麻呂絵画の応援者。色々と画材の花を下さいます。有難いことであります。 (フリージア)<参考>フリージア・Wikipedia 見事なフリージア。とても豪華な雰囲気で、楽しい気分になります。 これに対して、下のキバナショウブ(又はキショウブ)は、清楚な感じで、爽やかです。しかし、この花は外来の帰化植物で、要注意外来生物に指定されているので、在来の植物の生態系を阻害することのないよう、栽培に当っては逸出しないよう配慮する必要があるとされる。園芸種として外来の珍しい植物がどんどん入って来るが、それらが野生化して日本古来の植物の生態系が崩れるというようなことがあってはならないのであるけれど、これはもう防ぎようもないことでしょうね。(キバナショウブ)<参考>キショウブ・Wikipedia 次のカンパニュラ とゴテチアはひろみの郎女さんからのもの。(カンパニュラ)<参考>カンパニュラ・Wikipedia カンパニュラは智麻呂氏のお好きな花です。 ホタルブクロの仲間ですが、釣鐘草とか風鈴草とも呼ばれる。俯いて咲いていれば「釣鐘草」であるが、このように上を向いて咲くと、釣鐘草ではなく英語名のベル・フラワーと呼ぶ方が似合いでしょうか。ホタルも雨宿りにはならぬとスルー、ホタルブクロではなくホタルスルーでありますかな(笑)。 次のゴテチアという花はヤカモチ館長は初めて聞く名前。 囲碁が趣味のヤカモチ館長は「後手チア」と「ゴテ」から「後手」を連想してしまい、ならば「先手チア」の方がいい、なんぞと馬鹿な方へと思いが行くのでありました。調べてみると学名がGodetiaとのことですから、正しくはゴデティアと表記すべきなのかも知れません。別名がイロマツヨイらしい。(ゴテチア)<参考>ゴテチア・ヤサシイエンゲイ 小生は、この花の実物は見ていないのですが、恒郎女さんによると「すごく立派で華やかな花」で、智麻呂氏のこの絵は、そのボリューム感を表現し得ていない、と厳しい評価をされていました。しかし、実物を目にしていないヤカモチ館長は、花の豪華さや可愛さが十二分に表現された、いい絵だと思うのでありました(笑)。(オンシジウム)<参考>オンシジューム・Wikipedia オンシジウムとドクダミについては取材メモが存在しませんので、何と言って申し上げることもありませぬ。オンシジウムについては、以前に智麻呂邸をお訪ねした際に花器に活けられていたのを目にした記憶がありますが、 母の日の花ではないですが、これもそのうちの一枝を抽出して写生されたのでしょう。もっと賑やかに部屋を飾っていた筈です。 写生というのは、現実の景色から色々なものを省略する行為、どんどん余分なものを削いで行き、残ったものだけを描くという引き算の作業ですから、こういう絵になるのですな。(ドクダミ)<参考>ドクダミ・Wikipedia 上記の最後の3点は昨日(8日)智麻呂邸を訪問して撮影した最新作であります。お訪ねすると智麻呂氏はこの日大腸の検査のためご自宅近くの病院に検査入院されていて恒郎女さんだけがご在宅でした。検査結果が気になっていたところ、夕方6時過ぎに恒郎女さんからお電話があり、検査結果は異状なしであったとのことで、ヤカモチ館長もひと安心した次第。で、本日(9日)銀輪散歩の帰りにあらためてお訪ねして智麻呂氏の晴れやかなお顔を拝見して参ったのでありました(笑)。 先ずは、めでたし、めでたしということで、この絵画展の結びとさせていただきます。本日もご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。
2017.06.09
コメント(7)
-

囲碁例会・雨が降ります雨が降る
<お知らせとお詫び> 現在、フォト蔵のサーバーがどうかしたのか、フォト蔵にアクセスすることが出来なくなっています。その関係でしょう、当ブログ記事の写真も殆どが表示されなくなっています。それらの写真は全て、フォト蔵に登録したヤカモチの写真をリンクして貼っていることから、フォト蔵がトラブルになると、表示がされなくなってしまうという次第。 スグに正常に復するのか長期間を要するのか、今のところ不明です。 折角ご訪問下さったお方には申し訳のないことでありますが、フォト蔵の故障が直るまで、この状態が続きますので、何卒ご容赦下さいませ。 ということで、今日は、フォト蔵の写真を利用しないで記事を書くこととします。 今日は朝から雨。梅田スカイビルでの囲碁例会の日でありましたが、朝から雨では、いかな銀輪狂のヤカモチさんでも、自転車で梅田までは「ちとキツイ」のであります。今日は電車で参りました。 本日の出席者は竹〇氏と村〇氏と小生の3名のみ。雨の所為でもあるか。 ヤカモチ〇-×竹〇氏 ヤカモチ〇-×村〇氏 竹〇氏 〇-×村〇氏 対局の次第は如上の通りで、ヤカモチは2戦2勝でした。これでも今年に入ってからの通算成績は9勝14敗で、まだ5つも負け越している。 銀輪散歩での立ち寄り先もなく、話の種もなし。実の話は昨日しましたし、花散歩も既にして種切れ、ということで、囲碁会場の5階の部屋の窓から、新梅田シテイの「中自然の森」の入口付近に咲いていた紫陽花を望遠で撮った写真を掲載して置きます。 (紫陽花)(同上)
2017.06.07
コメント(4)
-

ハナから実のある話
花散歩の記事が続きました。この頃や 花の話に 花咲けど 役に立たぬか 実のなき話 (鼻家持) ということで、 本日は「実のある話」を致しましょう。 このような話は、「実は~」とか「実を言うと~」という形で始まるのが相場であるが、偐万葉世界ではこれを「じつ」とは訓まず、「み」と訓むのでありますな。 「実にくだらぬ」と言われもすることが多い、偐万葉的実話であるが、それは「実があるだけの実の無い話」であるからであります。 一般世界で言われる「実は~」とか「実を言うと~」という意味を込める場合には、偐万葉世界では「種は~」とか「種を言うと~」で話を始めるのが通例となって居ります。実の中にある「種」にまで踏み込んで話すのだから「余程に耳よりな」と思わせる狙いがあっての「もの言い」であるが、一般世界のお方は「柿の種」なんかを連想するらしく、その狙いは常に空振り、ハナからスベっているのであります。実はあれど種しなければ無駄話 明日なる実とはならじとぞ思ふ (種家持) では、文字通りの、「実のある話」であります。 銀輪散歩的実話であります。 先ず、サクランボ。と言っても桜桃ではなく、桜の実である。(サクラの実) こどもの頃に真っ黒に熟したものを摘んで食べた記憶があるが、美味しいものではない。渋みというか苦みが後味に残る。サクランボのような味を期待して裏切られた恨みはその後味の渋さ・苦さと共に記憶に残っている(笑)。苦渋の記憶ですかな。(コリヤナギの果実) コリヤナギとは「行李柳」と書く。柳行李はこの木の枝で編むのでしょう。 枝垂れるヤナギは「柳」、ネコヤナギなど枝垂れないヤナギは「楊」であるが、大和言葉では、区別なく「やなぎ」である。 ヤナギの果実を見るのは初めてかも知れない。柳絮というのは柳の種子についている白い綿毛のこと。春の季語とされる。春になると風に飛ばされた柳絮が舞うので、春の景色、風物とされたのであろう。 上の写真のそれにも少し絮が散り残っているのが見られるが、殆どが散ってしまった後であるから、種が零れ落ちた後の果実ということになる。(クワ) これは桑の木。中国の伝説で東海の果ての海中にそびえ立つ巨木が扶桑で、その木から太陽が昇る考えられていた(「山海経」)。そこから中国では日本の国のことを扶桑の国とも呼び、日本自身も自国のことを「扶桑」と呼ぶようになったという次第。 扶桑の木は、桑の木とする説もある一方、架空の植物(これは当たり前の説ですな)、トウモロコシ、リュウゼツラン、メタセコイア、ハイビスカスなどの説もあるようです。万葉植物の比定と同様に、いやそれ以上に「水掛け論」ですから、素直に「クワ」として置いていいのではないですかね。 で、桑の実です。 近寄ってみると、実がなっていました。 (クワの実) クワは英語ではマルベリー(mulberry)である。ラズベリーとかブラックベリーみたいなお洒落な感じになる。しかし、これではジャムにはなっても万葉歌にはならない。クワも万葉植物なのである。たらちねの 母がそのなる 桑すらに 願へば衣に 着るといふものを (万葉集巻7-1357)(母がその仕事とする桑さへも、願えば衣として着られるというのに。)筑波嶺の 新桑繭の 衣はあれど 君がみけしし あやに着欲しも (万葉集巻14-3350)(注)新桑繭=春一番の繭みけし=御衣。着るの尊敬語「けす」の連用形名詞に 接頭語「み」が付いたもの。(筑波山の新桑の葉で飼った蚕の繭で織った着物はあるけれど、あなたのお召し物がむやみに着たいのです。)※万葉の頃は、恋人たちは互いの着物を交換して着るということがあった。(同上)(カラスノエンドウの実) カラスノエンドウはもう実が黒くなって弾けているものもありました。(同上) 次はチューリップの実。チューリップの花が植えられていた場所になっていたのでチューリップの実と分かったのですが、それを知らなかったら、ナニこれ?でありました。 チューリップは球根というイメージが強過ぎて種子とか実とかは思い浮かばなかったのですが、花が咲けば実がなり、種が出来るというのは当たり前のことですから、チューリップにも実や種があって何の不思議もないのだけれど、ヒトは思い込みの生き物、つい見ることを疎かにしたまま、見ないままに、見て知った気になっていることが多いということに気が付きました。(チューリップの実) 実を言えば、種を言えば、この実を割って、中の種の状態を見たかったのですが、他人様が植えたものなので、許可なくそれをしては不法行為、諦めました。割れるまで待とう、と考えたのですが「割れる頃には忘れている」というのがヤカモチさん。果たして種子を見ることができるでしょうか。 (同上) 次は古い写真ですが、トベラの実。花から若い実になったばかりのもの。 花散歩から実散歩という流れの記事から言えば、この写真が似合いかと引っ張り出しました。(トベラ・花から実へ)(トベラの花) トベラは「扉・トビラ」が語源らしいから、トベラで戸を閉めて記事を閉めるのも理にかなっているというもの。記事の戸締りも怠りなしであります(笑)。 ということで、実のある、実の無い話はこれでオシマイ。
2017.06.06
コメント(10)
-

花の名もそれとし知れば
本日も銀輪花散歩であります。 銀輪散歩にて見かけた花で名前の不明であったのが、ネットで調べていたらそれと判明したものがいくつかありましたので、先ずそれらからご紹介します。名を知らぬ花の名が判るというのは、嬉しいものであります。花の名も それとし知れば 嬉しかり それ万葉の 花にしなくも (偐家持) コンフリー(別名ヒレハリソウ)とハルガヤがそれです。(コンフリー<領巾張草・鰭玻璃草>) (同上)<参考>ヒレハリソウ・Wikipedia コンフリーはヨーロッパ原産の帰化植物で、明治時代に我が国に入って来たらしい。家畜の飼料や食用として持ち込まれたとのこと。昭和40年代に健康食品として大ブームになり、それが野生化したらしいが、これを大量に服用すると肝臓に障害を生じることが判明し、今は食用に供されることはないという。小生は今回初めて目にし、ネットで調べたら名前がそれと分かったのでありましたが、かつてはよく知られた花であったのでしょうな。 (同上) 次はハルガヤ。 これも帰化植物である。 クサムギに似ていなくもないが、クサムギほどには麦らしくないのでハルガヤなのでしょうか(笑)。しかし、カヤとは言え、チガヤのように穂が風で散るということはないから、茅より麦と言った方がいいように思いますな。(ハルガヤ)<参考>ハルガヤ・Wikipedia (同上) 次はヘラオオバコ 。 これは、初めて目にする植物ではなく、川原などで何度も目にしている。オオバコの仲間であることは、その姿から容易に知れるところであるが、ナニ・オオバコであったかがどうしても思い出せない。確か以前京都の鴨川の河川敷で見た筈、写真に撮った筈と過去のブログ記事や写真を当ってみたが見当たらない。で、オオバコの仲間で検索したら、ヘラオオバコという名前に行き当たりました。こういうのを「行き当たりばったり」と言うのでしょうか(笑)。まあ、ヘラヘラ笑っている場合ではないのですが、ヘラオオバコでありました。(ヘラオオバコ)<参考>ヘラオオバコ・Wikipedia(同上) (同上) 普通のオオバコ(下掲)よりも背も高く、穂も立派である。 (オオバコ) ここまでが、昨夜(3日夜)書いた記事。 一昨日(2日)の夜にWindows10が最新ヴァージョンに更新されましたが、その所為でか、編集途中に「Internet Explorerは動作を停止しました。」という表示が現れ、画面が固まってしまうということが何度も生じました。 こうなるとページが開き直されることとなるのであるが、その度に書きかけで未保存の記述は全て消えてしまうため、また同じことを記述し直さなくてはならないことになる。何度かこれを繰り返して遂にギブアップ。 Microsoft Edgeで記事編集ページを開き直すとそういうことは生じなくなりましたが、夜も更け、何度もの書き直しによる苛立ちから記事更新の意欲は消え失せて「また明日にしよう。」という結論になった次第。 これまでは、従来通りのInternet Explorerで編集ページを開いて日記を書いていて問題なかったのですが、直近のプログラム更新によって、このような不具合が発生しているようです。これはMicrosoft Edgeの不備なのか、楽天ブログの編集ページの不備なのか。はたまた、わがPCでの何らかの設定の不備なのか。 ということで、本日はMicrosoft Edgeで編集ページを開き、記事を書いています。(カルミア) この可愛い花を初めて見たのは奈良の霊山寺の 境内でありました。その後、奥浜名湖銀輪散歩で訪ねた龍潭寺境内でも見かけましたが、それ以来の再会でありました。 <参考>銀輪花暦 2009.5.26. 奥浜名湖銀輪散歩(その7) 2014.5.20. (同上)<参考>カルミア・Wikipedia このような白いカルミアもありました。 アメリカシャクナゲという別名も持っているようですが、この葉は有毒で、品種によっては「羊殺し(Lambkill)」とも呼ばれるそうだから、無邪気な花姿に誤魔化されてはいけないのでもある。(白いカルミア) 白い花と言えば、卯の花ですな。卯の花の匂ふ垣根に~♪という歌・「夏は来ぬ」の作詞は佐々木信綱であるが、偐家持は「冬は来ぬ」という替え歌を作ったことがある。 <参考>偐万葉・くまんパパ篇 2010.6.19.(ウツギ) (同上) 卯の花に似ているのがノイバラであるが、こちらは雄蕊の数が多く花弁が丸みを帯びて卯の花のように先が尖っていない。(野イバラ) 単にイバラ(茨、荊) とかノバラ(野薔薇)とも呼ばれるが、万葉集では「うまら」と呼ばれている(万葉集巻20-4352)。尤も、この歌「道の辺のうまらのうれに~」の作者は防人・丈部鳥(はせつかべのとり)という東国の人にて、「うばら」の東国方言が「うまら」だと言う。(同上) (同上) 上の写真でご覧のように イバラの花もウツギの花も花弁は5枚である。 で、下の花は花弁が4枚である。花弁の形は野イバラに似ているが、数が1枚足りない。葉の姿も違う。棘も無い。卯の花も花弁は5枚であるし、雄蕊の数が10個程度の卯の花とは感じが違う。ということで何と言う花なのか不明。取り敢えずノイバラモドキ又はウノハナモドキと名付けて置くこととしました。(不明) スモモの花にも似ているが、スモモの花も5弁花であるし、今頃咲くのは遅すぎるから、スモモではない。しかし、スモモモドキではモが重なり過ぎて発音が「モどかしい」から不採用としました。 (同上) 何にしてもヤカモチモドキとも言うべき偐家持には似合いの花かも、である。 (同上)<追記> この花はクレマチス・モンタナではないかという、小万知さんのコメントを頂戴しました。蔓性の植物だそうですが、小生は花に気を取られていた所為でもあるか、ツルとは気付かず、普通の木だと見ておりました。或は他の木に絡みついて「普通の木」に見せていたのかも知れません。 と言うことで、クレマチス・モンタナであり、ナニナニモドキというようないかがわしい植物ではないのでありました。 白い花ついでにシャリンバイの花も。 (シャリンバイ) (同上) 白い花続きで、更にコデマリ やユキヤナギやクチナシなどを並べると多分皆さんが白けることでしょうから、白い花は此処までとします。 で、次はアザミです。アザミも白けているようで、未だ咲いていない。わずかに一輪咲き掛けのものがあるばかり。これでは「愛しき花よ、汝は薊。心の花よ、汝は薊♪」と歌う訳には参りませぬ。よってヤカモチは黙して先へ。 (アザミ) で、次に出会ったのは余り色気のないスイバ。酸葉と言うから葉は酸っぱいのでしょう。似た植物にギシギシというのがあるが、ギシギシやイタドリの花は万葉集に登場する「壱師の花 」だという説もある。一般的には「壱師の花」はヒガンバナとされるが、こればかりは万葉時代にタイムスリップして当時の人にインタビューしてみないと何とも分らぬことであるから、永遠に「水掛け論」である。(スイバ)(同上) 花らしくない花が続きますが、コバンソウ(小判草)です。 これもイネ科植物ですから、花は殆ど目立たない。小判型の穂をほぐすと折り重なって小判型を形成している小片一つずつの奥に小さな丸い種子が納まっているのが見て取れる。(小判草) 小生には昆虫の幼虫か蛹かがぶら下がっているように見えるので、小判草と言うよりも蛹草とでも言った方がしっくりする。 (同上) 本日も花散歩の記事でありました。
2017.06.04
コメント(10)
-

銀輪花散歩・水無き月の空の下にも
更新をサボりてあればはや今日は 水無月なりとひとは言ひける (朔家持)銀輪を やれば道の辺 咲く花は 水無き月の 空の下にも (花家持)ということで、今日も花散歩であります。 前回の日記では、キュウリグサに似たノハラムラサキという花の名が判明したので、とその花の写真を掲載しましたが、今回は、そのご本家キュウリグサの写真を掲載することから始めることとします。(キュウリグサ) 万葉人は小振りの花が好みであったらしいが、ここまで極端な小振りになるとどうですかね。それはともかく、今日は小さい花でまとめてみます。 (コメツブツメクサ) 小さい花と言えば、やはりこれでしょうか。コメツブツメクサ。 米粒よりも小さく、胡麻粒位、或はそれよりも小さい位の大きさであるからコメツブツメクサと呼ぶよりもゴマツブツメクサと呼ぶ方が似合いかも知れない。キュウリグサと同じでこの位のサイズになると、カメラ任せのピント合わせではなかなかうまく行かず、撮影もひと苦労なのである。(同上) そして、同じく黄色い花のニガナ。 ニガナ、タビラコなどはつい混同してしまうのであるが、これはニガナである。 (ニガナ) (同上) ニガナも群生していると景色になる。(同上) ニガナよりも背の高いのがブタナ。花はタンポポのそれに似ているが、タンポポより背が高く、花茎が細い。こいつも群生すると景色である。(ブタナ)(同上) それにしても、ブタナとはちょっと気の毒な名前。 と言うと豚に失礼か(笑)。(同上) 小さき花となると、ニワゼキショウも外せないでしょうか。 (ニワゼキショウ) カタバミも外せません。(カタバミ) カタバミも最近は園芸種が多く出回り、何んとかオキザリスとか言って「大きな顔」してではなく「大きな花」をしたのを見掛けますが、イモカタバミもそんなうちの一つでしょうか。ムラサキカタバミよりも色が濃くて派手な感じがする。 これは自然に生えたものではなく、どなたかが道端に植えられたものかも知れない。 (イモカタバミ) 道端と言えば、よくみかけるのがこの花。多肉植物のような厚みのある小さな葉の植物。その葉に覆いかぶさるように咲いている黄色の小さな花。比較的湿気た処にてよく見かける気がするが、道のふちを黄色く染めてしまう花である。 (コゴメマンネングサ)<追記:訂正注記>この花はコゴメマンネングサではなく、メキシコマンネングサのようです。(カゼクサ<風草>) これは、雑草の中の雑草。カゼクサ。風草などと素敵な名前を頂戴したものである。尤も、ニワホコリ(庭のホコリ)という有難くない名前も頂戴しているところが雑草の雑草たる由縁である。 (同上)(同上) 風草という名に相応しいのは、むしろこのチガヤかも知れない。 このチガヤが生い茂る浅茅原は、目には見えない風の姿を視覚化してくれる。 (チガヤ) そんな浅茅原の近くにて目にしたのがこれ。 オオアレチノギク(大荒地野菊)である。似たのにヒメムカシヨモギというのもあるので、或はそれかも知れないが、綿毛の絮をほぼ拡散し尽した姿。何やら春霞を身にまとっているような立ち姿であるが、なかなかいい風情である。 ヤカモチが煙草の煙をまとっている姿もこのように風情があればいいのでありますが(笑)。(オオアレチノギク)(マンテマ) これはマンテマ。以前、魚津から富山まで海沿いを銀輪散歩した際に、滑川付近で見掛けて、その写真をブログに掲載したら、小万知さんから「マンテマ」という名前だと教わったのでありました。名前を知ると出会いが多くなるというもので、その仲間のシロバナマンテマというのにも出会ったのでありました。<参考>魚津から富山へ銀輪万葉(その2) 2011.5.23. (マンテマとシロバナマンテマ) シロバナマンテマという名前であるが、実際にはピンク色のものが多い。(シロバナマンテマ) 最後にナデシコを添えて置きましょう。 撫子は大伴家持の花、というのが小生のイメージ。赤人の菫、人麻呂の浜木綿、憶良の楝と並んで家持の撫子である(笑)。(ナデシコ)撫子が その花にもが 朝なさな 手に取り持ちて 恋ひぬ日なけむ (大伴家持 万葉集巻3-408) 尤も、これは西洋ナデシコ。園芸品種。大和撫子ではありませんな(笑)。「これはマロが詠んだ撫子ではないぞよ。」と家持卿。 しかし、ボーダレスの現代世界、西洋ナデシコの写真でも家持卿はお許し下さることでしょう。<追記> この撫子は西洋ナデシコではなくセキチク(石竹)又はカラナデシコ(唐撫子)と呼ばれる、中国原産のナデシコでした。奈良時代に我が国に渡来して来た、と説明しているサイトもありますので、そうなら、これも大和撫子と言ってもよさそうです。大伴家持さんが詠んだ石竹はこの花かも知れません。 撫子の花、つばらにぞ見むです。もっと近寄ってみます。 (同上)家持の 愛でし撫子 その花を つばらつばらに 見つつ過ぐさな (偐家持) もっと近くから。 (同上) 横顔も。蕾も。 (同上) 本日も花散歩でありました。<参考>花カテゴリの過去記事は下記からご覧下さい。 花(1)、花(2)、花(3)
2017.06.01
コメント(8)
全17件 (17件中 1-17件目)
1