2008年03月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-

カードキャッシングによる多数回の貸付を1個の貸付と認定した例
カードキャッシングによる多数回の貸付を1個の貸付と認定した例リボルビング払い(元金定額残高スライド)方式によのカードキャッシングによる貸金カードを提示することにより、業者が定めた利用限度額(30万円)以内で反復して金銭の借入れをすることができる。リボルビング払いの場合の毎月の返済額は、前月27日の残高合計が20万円以下の場合は1万円、20万を超えて30万円未満の場合は2万円、30万円以上の場合は3万円利息は毎月28日を基準日とする残元金に対して年27.6% 業者は、各貸付は別個の貸付であり、リボルビング払い方式はその返済方法に過ぎないから、貸付の法的性質がその返済方法によって変節されるものではなく、1個の貸付とみることはできない と争った福岡地裁平成18年7月18日判決は、貸付契約を1個とみるか複数とみるかは、事実を総合的に評価して判断すべき事項であであるところ、本件カード契約では、貸金契約の内容(利用限度額、返還時期、返還額、利息、遅延損害金など)は本件カード契約時にすべて合意されており、後は個別の金銭の交付が行われるだけで貸金返還請求権が発生することになっており、また毎月の返済額は各貸付の合計金額に応じて決定され、利息は残元金合計額に約定利率を乗じて算出されることなどにかんがみ各貸付は一つの貸金と認めるのが相当である。と判示した。 判例タイムズ1255号 341頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.03.30
-

廃棄物の処理を委託したものが、未必の故意による不法投棄罪の共謀共同正犯とされた事例
廃棄物の処理を委託したものが、未必の故意による不法投棄罪の共謀共同正犯とされた事例最高裁平成19年11月14日第三小法廷判決甲らが代表取締役を務める会社の保管する廃棄物につき、乙がその処理を申し入れてきた際甲らにおいて、乙や実際に処理に当たる者らが、上記廃棄物を不法投棄することを確定的に認識していたわけではないものの、不法投棄に及ぶ可能性を強く認識しながら、それでもやむを得ないと考えて乙にその処理を委託した場合、甲らは、その後乙を介して他の者により行われた上記廃棄物の不法投棄について、未必の故意による共謀共同正犯の責任を負う。 判例タイムズ1255号 187頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.03.28
-

事業用定期借地権の上限期間の改正
事業用定期借地権の上限期間の改正「借地借家法の一部を改正する法律」が平成20年1月1日から施行された。この改正は、事業用建物の所有を目的とする借地権の契約の更新などのないもの(事業用定期借地権)の存続期間につき10年以上20年以下の範囲と定めている旧規定を改め、10年以上50年未満の範囲で設定できるとするものである。存続期間50年以上の範囲では、建物所有の目的が事業用であるか居住用であるか問わない一般の定期借地権(借地借家法22条)を利用することができるから、この改正により、事業用建物の所有を目的とする定期借地権については、存続期間10年以上の範囲で自由に期間を定めることが可能となり、事業用定期借地権の活用可能性が大きく開かれた。 金融法務事情1824号 10頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.03.27
-

文書提出命令 専ら文書の所持者の利用に供するための文書
文書提出命令 専ら文書の所持者の利用に供するための文書銀行が、法令により義務付けられた資産査定の前提として、監督官庁の通達において立ち入り検査の手引書とされている「金融検査マニュアル」に沿って債務者区分を行うために作成し、保存している資料は、民事訴訟法220条4号に所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない最高裁平成19年11月30日 第二小法廷決定本件の基本事件は、原告らが、その取引先のメインバンクである被告に対し、被告が当該取引先を全面的に支援する旨原告らを欺もうしたために、あるいは、当該取引先の経営状態について原告らに対する正確な情報提供を怠ったために、原告らが当該取引先に対する商品の販売を継続し、売掛金が回収不能となる損害を蒙ったなどと主張して、不法行為による損害賠償を求めるものである。被告は欺もう行為の存在及び注意義務の存在を争っており、原告らはそれらの立証のために必要であるとして、被告が当該取引先の債務者区分を定めるために作成し、保管している自己査定資料である本件文書について文書提出命令を申し立てた。これに対し、被告は本件文書が民事訴訟法220条4号ハ所定のいわゆる職業秘密文書、あるいは同号ニ所定の自己利用文書に該当すると主張した。原々決定は、本件文書は職業機密文書にも自己利用文書にも当たらないとして、被告に対し文書の提出を命じた。原決定はこれに対し、自己利用文書にあたるとして、申し立てを却下した。本件は、その許可抗告事件である。本決定は、被告が資産査定の前提となる債務者区分を定めるために作成し、保管している自己査定資料である本件文書は、法令により義務付けられた資産査定のために必要な資料であり、監督官庁による資産査定に関する立ち入り検査において、資産査定の正確性を裏付ける資料として必要とされているものであるから、被告自身による利用にとどまらず、被告以外の者による利用が予定されているものとして、自己利用文書には該当しないと判断し、原決定を破棄した上、本件文書が職業機密文書に該当するかどうかについて更に審理を尽くさせるため、本決定を原審に差し戻した。 金融法務事情 1826号46頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.03.26
-

自動車総合保険契約 人身傷害補償特約 疾病による場合の立証責任
自動車総合保険契約 人身傷害補償特約 疾病による場合の立証責任А 狭心症の持病あり 狭心症発作予防薬を定期的に服用 運転中にため池に転落 溺死 三叉路を直進してブレーキ操作をすることなくそのまま前方のため池に転落したかなり異常な事故で狭心症発作に襲われて運転操作を誤った疑いがあった。人身傷害補償特約の約款は運行に起因する事故、運行中の事故で急激かつ偶然な外来の事故により蒙った損害を補填するとされており、傷害普通保険約款などに定められている疾病免責条項が規定されていない。原審は、保険金請求者は「外来の事故」の主張立証責任を負うところ、本件は狭心症の発作である疑いが強いから外来の事故の主張立証がされたとはいえないとして原告らの請求を棄却した。これに対し最高裁は以下のとおり判示した。自動車総合保険契約の人身傷害補償特約が「自動車の運行に起因する事故等に該当する急激かつ偶然な外来の事故により被保険者が身体に傷害を被ること」を保険金支払事由と定め、被保険者の疾病によって生じた傷害に対しては保険金を支払わない旨の規定を置いていない場合、自動車の運行に起因する事故等が被保険者の疾病によって生じたときであっても、保険者は保険金支払義務を負い、保険金の支払を請求する者は、上記事故等と被保険者が身体に被った傷害との間に相当因果関係があることを主張、4立証すれば足りる 最高裁平成19年10月19日 第二小法廷判決普通傷害保険約款においては疾病免責条項が定められているところ、約款の規定の仕方から、保険者が抗弁として疾病についての主張立証責任を負うという抗弁説が最高裁第二小法廷平成19年7月6日判決で採用された。本件の場合、疾病免責条項がないので外来の事故の要件事実であると考えたのが原審である。本件最高裁判決によれば、疾病の発作が原因の事故の場合でも保険金をもらえることになる可能性が高い。 判例タイムズ1255号179頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.03.19
-

搭乗者傷害保険金 車外での事故の場合
搭乗者傷害保険金 車外での事故の場合夜間高速道路において自動車を運転中自損事故を起こし車外に避難した運転者が後続車にれき過されて死亡したことが自家用自動車保険契約普通保険約款の搭乗者傷害条項における死亡保険金の支払事由に該当するとされた事例約款においては「被保険自動車の正規の乗車装置等に搭乗中の者が、被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を蒙り、その直接の結果として死亡したこと」が死亡保険金の支払事由となる旨が定められている。原審は「傷害」は被保険自動車内で生じた傷害をいうとの前提に立ち、本件ではそのような傷害は認められないとしたのに対し、最高裁は「傷害」は本件自損事故と相当因果関係のある傷害であれば被保険自動車内で生じた傷害に限らないとした。 最高裁平成19年5月29日第三小法廷判決 判例タイムズ1255号183頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.03.18
-

本人が違法に入手した可能性のある文書を漫然と書証として提出した行為が弁護過誤と認められた事例
本人が違法に入手した可能性のある文書を漫然と書証として提出した行為が弁護過誤と認められた事例X 妻との離婚訴訟をY弁護士に委任Xは銀行の支店長 財産分与の関係で妻の隠し財産を探すために、自分の銀行の妻の父名義の預金明細書を勤務先のパソコンから出力 他の資料と共にY弁護士のところへ届けたY弁護士は、それを書証として提出 妻の父から承諾がないとしてXの勤務先に強い抗議がなされた。 Xは勤務先で不利益な処分を受けるかもしれないと考えて、預金取引明細書問題も含めて離婚訴訟を早期に解決するために協議離婚の和解を余儀なくされた福岡地裁平成19年3月1日判決は、Yは訴訟委任を受けた弁護士として委任者であるXに善良な管理者としての注意義務を負っているところ、XがYに届けた本件預金取引明細書について、これが名義人の承諾を得ることなく違法に入手されたものである可能性が高く、このことが露見すれば勤務先において不利益処分を受ける可能性が高いことを容易に予見することができたにもかかわらず、これを漫然と書証として提出したものであって、弁護士としての善管注意義務に反しているいというべきであるとして150万円の慰謝料の支払を命じた 判例タイムズ1256号132頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.03.17
-

マンション管理組合の決議の瑕疵
マンション管理組合の決議の瑕疵マンション管理組合の総会決議について、係争区分所有者に書面による召集通知が送付されなかったことなどが決議の無効事由に年はならないとされた事例近時、マンション管理組合における組合員が津、役員間の紛争を巡って訴訟が提起されることが増加しているようである。本件は役員間の対立に端を発して理事長を解任するためにに反理事長派の役員らが臨時総会を招集した際の手続き等に瑕疵が認められるものの、重大なものではなく軽微なものであるとして決議の無効事由とされなかったものである。 控訴されている。 東京地裁平成19年2月1日判決 判例タイムズ1257号321頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.03.14
-

特殊事情の変更を理由とする賃料増額請求
特殊事情の変更を理由とする賃料増額請求借地借家法32条1項は、従前の賃料が客観的に不相当となったときに、公平の観念から、当事者の一方的意思表示により、従前の賃料を将来に向かって客観的に相当な金額に改定することを認める規定であり、その趣旨からすれば、同項が定める事情の変更は例示にすぎず、特殊事情の変更であっても、賃料増減額請求をするための要件となりうるものと解すべきであると東京高裁平成18年11月30日判決は判示した。上告されている。事案 建物 A社所有 建物の一部をパチンコ店の店舗として被告会社に賃貸 建物の一部を景品交換所に賃貸 A社の社長と被告会社の代表者は親子であったので賃料は低額であった A社 建物を原告に売却 原告は賃貸人の地位を承継 原告賃料増額請求 判例タイムズ1257号314頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.03.13
-

特殊な賃料の仕組みを有する百貨店店舗用建物賃貸借と借地借家法32条1項の適用
特殊な賃料の仕組みを有する百貨店店舗用建物賃貸借と借地借家法32条1項の適用 原告は被告から横浜駅西口に所在する本件店舗用建物を賃借して百貨店を営業している 賃料は当事者の合意による特殊な賃料の仕組みとの関係で、ほぼ一定額で高止まりしてき た。そこで原告は借地借家法32条1項に基づいて賃料の減額の請求をなし、被告は借地借家法32条1項は適用されないとして争ったものである。(共同事業を遂行するためのリスクの分担を定めた一種の無名契約であるとして争った)横浜地判 平成19年3月30日判決は賃料の減額を認めた 判例タイムズ 1256号26頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.03.12
-

廃棄物の処理を委託した者が未必の故意による不法投棄罪の共謀共同正犯の責任を負うとされた事例
廃棄物の処理を委託した者が未必の故意による不法投棄罪の共謀共同正犯の責任を負うとされた事例本件は、港湾運送事業や倉庫業などを営む被告会社の代表取締役等であった被告人らにおいて、被告会社が、千葉市内で保管中の、いわゆる硫酸ピッチ入りのドラム缶約6000本の処理を、下請け会社の代表者であるAに依頼したところ、そのうち361本が北海道内の土地で捨てられたことにつき、被告会社の業務に関し、Aらと共謀の上、みだりに廃棄物を捨てたとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律所定の不法投棄罪に問われた事案である。 被告会社が本件ドラム缶の処理に困っていることを知ったAが本件ドラム缶の処理を請け負う旨を被告会社に執拗に申し入れたのに対し、被告らは、Aらがこれを不法投棄することを確定的に認識していたわけではないものの、不法投棄に及ぶとの可能性を強く認識しながら、それでもやむを得ないと考えてAに処理を委託したところ、やはり不法投棄されてしまったものである。 本決定は、被告人らは、Aを介して他の者(共犯者)により行われた本件ドラム缶の不法投棄について、未必の故意による共謀共同正犯の責任を負うべきであるとの事例判断を示した。 刑法60条の共同正犯の内、共謀共同正犯についても、共謀者の故意が未必の故意で足りることは、自明のようにも思われるが、これまで、その点を明示した最高裁判例はなく、スワット事件判例を契機に、共謀共同正犯の成立には確定的故意を要し、未必の故意では足りないのではないかという疑義が生じていた。 本決定は、事例判断ではあるが、共謀共同正犯の事案につき、共謀者には未必の故意しかないときでも、共謀共同正犯が成立することを正面から認めたものであり重要な意義を有すると考えられる。 最高裁平成19年11月14日小法廷決定 判例時報1989号160頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.03.11
-

不当な弁護士懲戒請求と不法行為の成立
不当な弁護士懲戒請求と不法行為の成立A会社 建築工事の請負などを業とする 本店は群馬県B会社 足利市に本店を置く 建築工事の請負を業とする有限会社 AはBに対し債権があるとして、Bが第3者Cに対して有する債権を仮差押した。 Aは、仮差押の保証金として50万円を立てた この仮差押の手続きはAの代表者Y1が自ら行った 裁判所は宇都宮地方裁判所足利支部仮差押の本案である請負代金請求事件においては、第1審も控訴審もAの請求を棄却した。Aは前記保証金50万円を取り戻す手続きとして、権利行使催告の上担保取消を請求した。(仮差押の場合、相手方の意見を聞かないで発令するので、相手方に損害を与えた場合の担保として保証金を積む。本件の場合、仮差押の元となった請求権が存在しないことが確定したので、保証金をおろすには、相手方に損害があれば一定の期間に権利を行使するように催告し、その期間内に権利が行使されなければ保証金をおろすことができるが、権利が行使されれば、その結果を見てから出ないとおろせない。通常は損害賠償請求訴訟が起こされる)権利の行使の催告に対応してBはAを被告として損害賠償請求を提起この訴訟をX弁護士に委任した足利支部は「AはBに50万円を賠償すべき」との判決を出したAから控訴された Aの代理人Y2Aの代表者Y1 Xの所属弁護士会に懲戒請求この事実を秘して、控訴審で和解 AはBへ20万払うという内容懲戒請求の理由 自分は80歳の高齢で右目は失明寸前である。裁判に出頭すれば丸1日を要するという過 大な負担である。このような訴訟を起こしたXの行為は弁護士の品位を損ねる というものである。これに対し、弁護士会は懲戒請求を棄却。これに対するAからの異議に対して日弁連は棄却 Aは東京高裁に取消請求を行った この代理人がY2 東京高裁訴え却下XはAの代表者Y1と弁護士Y2に対し損害賠償請求東京高裁 請求棄却 全く理由がなかったわけでないので不法行為が成立しない最高裁平成19年4月24日判決 一部破棄自判 不法行為が成立する 50万円の損害賠償請求認める 判例タイムズ1256号 30頁 ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.03.10
-

「相続させる」旨の遺言により遺産を取得するとされた者が被相続人より先に死亡した場合、その者の子に代襲相続させるとする規定が適用ないし準用されるとした例
「相続させる」旨の遺言により遺産を取得するとされた者が被相続人より先に死亡した場合その者の子に代襲相続させるとする規定が適用ないし準用されるとした例東京高裁平成18年6月29日判決A 遺言公正証書により財産を子らに相続させる旨の遺言子供のなかのBがAより先に死亡 Bの子が、遺言によりBに相続させるとされた不動産を含む財産について指定相続分を有することの確認を求めて提訴第1審の東京地裁は請求棄却控訴審で原告は、指定相続分の確認請求から共有持分の確認を求める訴えに変更東京高裁平成18年6月29日判決は、遺産分割方法の指定による相続がされる場合においても、この指定により同相続人の相続内容が定められたに過ぎず、その相続は法定相続分による相続と性質が異なるものではなく、代襲相続人に相続させるとする規定が適用ないし準用されると解するのが相当であるとして第1審判決を取り消して原告の請求を認容いした。相続させる旨の遺言は、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人に相続させる遺産分割方法が指定されたものと解すべきとされ、相続させる旨の遺言による不動産の権利の取得については、登記なくして第3者に対抗することができるとされている。本件のような場合、代襲相続ができるか否かについて最高裁判例は存在せず学説及び下級審判決では消極説が有力であった。本判決は高裁段階では初の裁判例と思われ、最終審の判断が待たれるところである。と評されている。 判例タイムズ 1256号 175頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.03.07
-

週刊誌の記事 名誉毀損行為をした出版社に対して800万円の損害賠償と謝罪広告が命じられた例
週刊誌の記事 名誉毀損行為をした出版社に対して800万円の損害賠償と謝罪広告が命じられた例原告は芸能人である女性と結婚した男性数ヶ月で離婚女性の手記の形で両者の離婚に至る経緯を記載した記事を週刊誌に掲載記事の内容は、通常であれば他人に公表しないような家族間の出来事がその中心を占め、しかも、男性の社会的地位を低下させるものであった。本判決は、本件記事が原告の名誉を毀損する内容のものであると判断した上で、記事内容が公益を図る目的もなく、真実であることの証明もなければ、真実であると信じるに足りる相当の理由もないと判断して、本件記事を掲載した週刊誌の発行が違法な名誉毀損行為にあたるものと判断した。本判決が命じた800万円という賠償額は、損害賠償の認容額としては、最近では高めの部類に属するといえよう。本判決は、その理由として、原告の職業上の活動その他の社会的活動についての記事であれば、国民は原告の活動について批評する表現の自由があり、仮に名誉毀損の観点から言いすぎがあって違法とされるべき場合であっても表現の自由との調整を考慮すべき必要性が高い(あまり賠償額を高くすべきでない)のに対し、プライバシーについての記事はそもそも書かれるべき必要性に乏しいものであって表現の自由との調整を考慮すべき必要性が小さいこと、本件雑誌の発行部数が非常に大きく、新聞広告や車内吊広告による被害の拡大もあったことなどを指摘している。控訴されている。 東京地裁平成19年6月25日判決 判例時報1988号39頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.03.03
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 福袋2026🔹MLB ロサンゼルス・ドジャ…
- (2025-11-16 19:23:16)
-
-
-
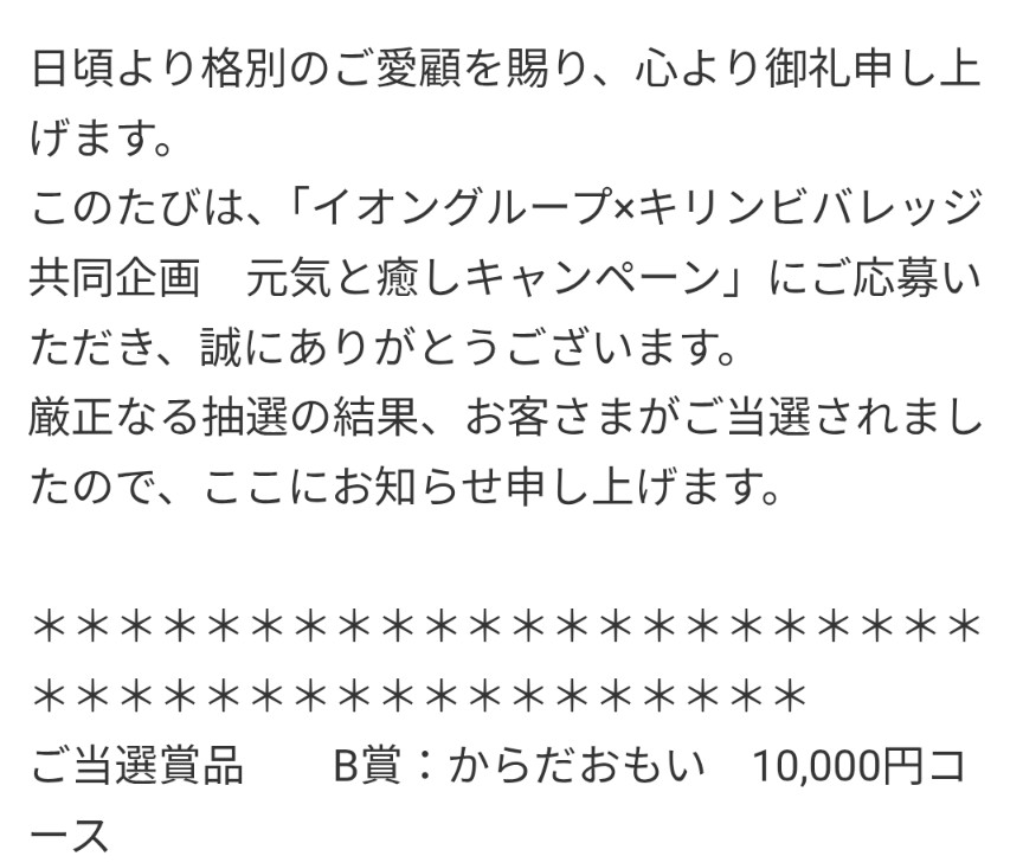
- 懸賞フリーク♪
- からだおもいデジタルカタログギフト
- (2025-11-16 00:56:51)
-
-
-

- みんなのレビュー
- #PR【レポ】KC-SKINモイストリペア…
- (2025-11-16 14:00:14)
-







