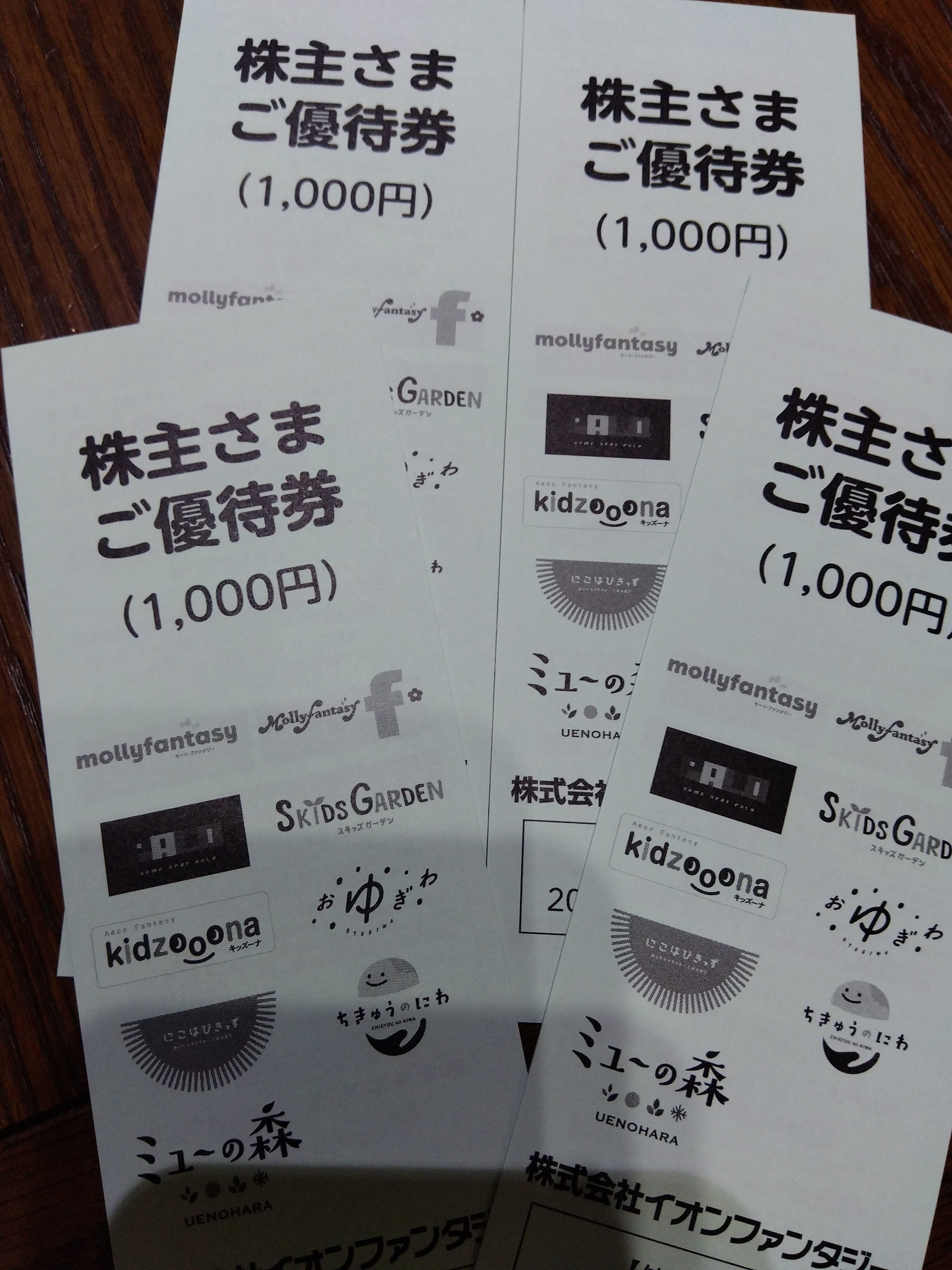2008年11月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-

非番の従業員 夜勤の同僚の夜食購入の外出での事故 業務上災害認定
同僚労働者の夜食を購入するため外出し、工場に戻る途中に交通事故にあった場合、業務上の災害に当たるとされた事例Xは、A社の工場に勤務していたところ、非番の日に、夜勤を命じられたBとともに出社し、Bの夜食が手配されていなかったため、Bの依頼により自転車でBの弁当を買って工場に戻る途中、前方から走行してきた自転車と衝突し頸髄損傷の傷害を負い、入通院治療を余儀なくされた。そこで、Xは、Y監督署長に対し、労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付等を請求したが、業務外として不支給決定がなされたため、同決定は違法であるとして、その取消しを求めた。岐阜地裁平成20年2月14日判決労働者災害補償保険法に基づく保険給付の対象は、業務上の事由などによる労働者の負傷等の業務災害であるところ、業務災害といえるためには、労働者が労働契約に従って使用者の指揮命令ないし支配下にあることが必要と解される。しかし、通常の業務運営上予定されていないような突発的な事態が発生した場合、労働者の行為が、当該事業者の事業運営上、緊急性、必要性があり、同事業者と労働契約を結んだ労働者として行うことが期待されるものであれば、業務遂行性があるものと解すべきである。Xが、Bから依頼を受けて、夜食を手配するリーダーに代って、夜食の手配業務を行うことは、緊急性、必要性があり、Aの労働者として合理的に期待された行為であり、業務遂行性が認められるとしてXの請求を認容。就業時間外または事業所施設外における災害は、事業主の支配下にあると評価できる場合は少なく、業務災害と認定されにくいといえる。本判決は、判断が微妙な限界的事例と考えられ、事例的意義を有すると評されている。 判例タイムズ1272号169頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.11.27
-

注文者の請負人の従業員に対する安全配慮義務
注文者に請負人の従業員に対する安全配慮義務を認め、同義務違反に基づく損害賠償請求が認容された事例Aは、Y1に雇用され、Y2の工場内で、高さ90cm足場面積40cm四方の作業台の上に立ってライン上を流れる缶のふたを検査する作業に従事していた。ところがAは、作業中に作業台から転落して床面に頭部を強打し、約3カ月後に死亡した。そこで、Aの父であるXは、Y1に対する安全配慮義務違反を主張したほか、Y2に対し、Y2とAの間には直接の雇用関係はないものの特別の社会的接触関係があったから安全配慮義務を負っていたとして、債務不履行及び不法行為に基づき損害賠償を求めた。東京地裁平成20年2月13日判決は、注文者の供給する設備、器具等を用いて、注文者の指示のもとに労務の提供を行うなど、注文者と請負人の雇用する労働者との間に実質的に使用従属の関係が生じていると認められる場合には、その間に雇用関係が存在しなくとも、注文者と請負人との請負契約及び請負人とその従業員の雇用契約を媒介として間接的に成立した法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入ったものとして、信義則上、注文者は、当該労働者に対し、使用者が負う安全配慮義務と同様の安全配慮義務を負うものと解するのが相当であると判断し、Y2のAに対する安全配慮義務及びその義務違反を認定し、損害賠償責任を認めた。本判決は、直接の雇用契約がない場合に安全配慮義務が認められた一事例であり、元請企業につき下請企業の労働者に対する安全配慮義務を認めた最高裁平成3年4月11日判決(集民162号295頁)と同様の判断枠組みを採用したものと評されている。 判例タイムズ1271号148頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.11.21
-

過剰販売 信販会社に対抗できる場合
呉服販売業者がその従業員に対し自社商品を過量販売した行為が公序良俗違反により無効とされ、信販会社に対しても対抗できるとされた事例呉服店Y1でパート勤務をしていたXが、Y1に対し、使用者という優越的地位を利用し、売上ノルマを課すなどして、Xの支払能力を超える立替払契約を締結させて着物等を購入させたとして、売買契約は無効であり、また、不法行為に当たるとして、既払い立替金相当額の支払いを求めた。また、Xは、信販会社Y2に対しては、上記売買契約の無効の抗弁接続(割賦販売法30条の4等)などを理由として立替払金残債務が存在しないことの確認などを求めた。大阪地裁平成20年1月30日判決は、Y1が、Xに対し、自社商品を購入することを事実上強要し、従業員であるXの過大な債務負担のもとで利益を得たとして、立替払契約の残債務が300万円を超え、その額が原告の年収額の1.5倍を超えるようになった以降の売買契約は、原告の支払能力を超えるもので公序良俗に反し無効であり、また、同契約を締結したことが不法行為に当たると判断した。また、Xは、Y1の従業員であるものの、Xの購入はY1の営業方針ないし労働環境に起因していたのであるから、事業者がその従業員に対して行う割賦販売について割賦販売法30条の4を適用しないと規定する同法30条の6、同法8条5号を適用すべきでないとして、Y2に対して、本件売買契約が無効であることをもって立替払債務の履行請求を拒むことができると判断し、Xの請求を一部認容した。呉服販売業者の従業員による自社商品の購入が公序良俗に反するか否かが問題となった事例については、これまで公刊物の上では見当たらず、本件は実務上参考になる事例と評されている。また、割賦販売法30条の6、8条5号は、事業者の従業員に対して行う割賦販売が、会社内部の問題であり、当該会社の内部自治に委ねるべきであるとして、抗弁権の接続を規定する30条の4の適用を除外したものと解されるが、本判決は、Y1のXに対する過量販売が、従業員に対する販売目標の達成を強く求めるといったY1の営業方針、労働環境に起因していたのであるから、このような場合には、事業者の内部自治を尊重すべき理由はないとして、抗弁権の接続を認めたものでる。 判例タイムズ1269号203頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!
2008.11.13
全3件 (3件中 1-3件目)
1