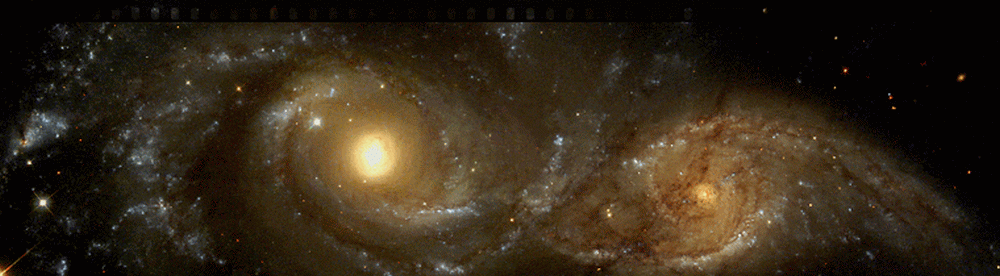2007年04月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-

毎朝起きるのが楽しみです
4月24日のブログで、今日が人生の初日ということを書きました。 今日はその続きです。 「今までの栄光や失敗にこだわらず」と書いたことについてです。 自分自身がよく陥る落とし穴があります。 それは、自分の過去の輝かしい成功に溺れてしまうことです。 実は今日という日においては、全員が横並びです。 誰もが残りの人生の初日にいますので、今日誕生したようなものです。 自分だけ人より優れている、先んじていると思うのは、全くの錯覚です。 反対に、過去の失敗にこだわる経験を持っている人も多いのではないでしょうか? 今日が残りの人生の初日ですから、今日から人生が始まります。 過去の失敗は忘れましょう。 過去の失敗にこだわるあまり、せっかく将来に用意されている希望と可能性を失わないようにしたいですね。 今日、あなたに、どのようなチャンスが待っているかは誰にもわかりません。 チャンスを取り逃がさないよう毎日を初心の気持ちで過ごしたいものです。 転職に失敗した人が、転職話を持ち込んだ人を憎んだり、挙句の果ては自分の命を絶ったりすることを聞きます。 自分の命を絶ってしまっては回復できませんのでどうしようもありませんが、転職に失敗したことにいつまでもこだわることや転職話を持ってきた人を憎むことの愚かさに早く気づきたいものです。 今日、目の前にやってくるすばらし世界と出会えるようにしたいものです。 今日はどんなに楽しいことがあるかなぁ、毎朝起きるのが楽しみです。【Bon appetit!】 ピザ Pizza is a baked pie of Italian origin consisting of a shallow breadlike crust covered with toppings such as seasoned tomato sauce and cheese. Popular throughout the world, pizza is now a symbol of cultural variation: In Brazil, pizzas may be topped with chocolate; in South Korea, sweet potato puree is popular; in Scotland, the "pizza supper" consists of french fries and a deep-fried frozen pizza; in Japan, pizza toppings may include corn, diced potatoes, scrambled eggs, mayonnaise, Camembert cheese, curry sauce, and various kinds of seafood.本格ピッツァ!送料込みのお試しセット[お一人様1回限り][送料無料]070426春10
2007.04.29
コメント(8)
-
ラオスの厨房
地方で見た厨房のかまど↑ ラオスの首都ヴィエンチャンから北に約400kmほど行った所にルアンパバンという名の都があります。 先月(3月)23日にルアンパバン県パクセン郡へ出かけました。 ルアンパバンは、1353年からランサーン王国の都として発展しました。 1975年の社会主義革命で破壊されることなく、現在では、世界遺産に登録されている旧都です。 パクセン郡はそこからさらに65kmほど北に向かって進んだ山の中にある地域です。 電気がなく、6年前までは、道路もなく、舟が唯一の交通手段でした。 郡の中心地で昼食を食べました。 アヒルを一匹つぶしたのでしょう、アヒルの肉を使った料理でした。 アヒルの生血が入ったスープのようなものが出てきてなかなか楽しめる食事でした。 ちょっと厨房を見せてもらったのが上の写真です。 これらは厨房の窯の写真です。 少々熱効率は悪そうですが、おそらくこのかまどで長年火加減をみてきたのでしょう。 厨房の外の庭でも炭を起こして、料理しています。 子供の頃に藁でご飯を炊いたことが思いだされ、懐かしい気分に浸った一日でした。
2007.04.28
コメント(2)
-

ラオスのお粥
お粥と揚げパン、左上に写っている人がお粥を作ってくれました↑ 皆さんの中には、朝食にお粥を食べる幸せをご存知の方多いのではないでしょうか? ここラオスでも、その幸せにあずかれることがわかりました。 朝だけやっているお粥屋さんを近くに見つけたのです。 早速先週の土曜日と日曜日の朝に食べに行きました。 はまりそうです。 大昔にあった映画館の前でお粥屋さんが店を出しています。 お米の粉から作った柔らか麺もあります。 テーブルの上に無造作に置かれている揚げパンは、そのまま食べても良し、ちぎってお粥の中にいれても良し。 皆さんも、お粥を食べに是非ラオスへおいで下さいね。↓このお粥やさんは廃館となった映画館の入り口に店を出してます【Bon appetit!】 時差は健康に悪影響? Researchers warn that airplane crew and passengers who frequently fly between several time zones face a number of health problems including disruptions in a woman's menstrual cycle(月経異常)and even short-term psychiatric(精神の)disturbances(乱れ). Jet lag(時差ボケ)is worse for older travelers, and its severity increases with the number of time zones crossed. The direction of travel also matters, with flights to the east bringing more jet lag than flights to the west.送料無料315円でお届け・・・鶏がゆ【代引き不可】【070426春10】
2007.04.26
コメント(2)
-

ラオスと日の丸
日本の援助であることを説明している看板↑ 道路わきに日の丸が描かれた看板をよく見かけます。 この看板が示していることは、道路で行われている改修工事が、日本の援助によるものである、ということです。 それにしても、道路があちこち工事中なんです。 歩道が掘り返されています。 歩道のあちこちが、砂や土砂の山。 工事が終わったようなところでも、大量の砂が置いてあったりしますので、終わっているのだか終わっていないのだか、判断に苦しむことがよくあります。 お陰さまで、歩く速度が日本にいたときの半分です。 歩く速度が遅くなる理由は、3つあります。 一つは、足下。 足下をしっかり見ていないと、土砂の中に足を踏み入れてしまったり、所々に突然あいている穴に落ちてしまいます。 二つ目は、暑さ。 暑すぎて、歩くのでさえやっとなのに、ましてや速く歩くことはなかなかできません。 三つ目は、早く歩いている人がいないこと。 早く歩いていると、人とぶつかりそうになるだけでなく、こちらのスピードの目測を相手が誤りぶつかってしまうのです。 ラオスは、社会主義国ですので、やはり歩く速さも周りの人と同じにする必要がありそうです。 今でも、ラオスは社会主義の旗を降ろしていません。 人民革命党の一党独裁政権が続きますが、経済の方は市場経済化を導入しています。 歳入が圧倒的に少ない国のため、外国からの援助に頼っているところがあり、このことが、日の丸が描かれた看板の多さにつながっているようです。↓工事中の道路【Bon appetit!】 男子の出生数は減少傾向? Traditionally, male births have always outnumbered(より数が多い)female ones, but since 1970, the US and Japan have experienced a downward shift in the male-to-female ratio. Researchers suspect the decline in male births can be explained, at least in part, by paternal(父親の)exposure to environmental toxins, such as certain pesticides(農薬), heavy metals(重金属), solvents(溶剤)or dioxins(ダイオキシン) chemical byproducts(副産物)produced during incineration(焼却)or the manufacture of other chemicals.「クスリを使わない小児医」として50余年間日本人の健康を見つめてきた著者が、食生活を含めた日本の伝統文化の復権や、プラス思考の習慣づけを説く↓超寿の条件新版
2007.04.25
コメント(0)
-

少しでも前へ
ラオスから、おはようございます。 皆さんは、今日一日をどう過ごされますか? おそらく、自分が目標としている方向へ、向かわれるのではないでしょうか。 自分が目標としている方向へ向かうことができたら、それがほんの少しの歩みでも、どんなにすばらしいことでしょうか。 自分の今日の行動をほかの人に話したら、「だから、お前は成功して当然だ」と言われることが確信できるような一日になることでしょう。 残りの人生は、今日から始まります。 今日が初日です。 今までの栄光や失敗にこだわらず、今日に集中していきましょう。【Bon appetit!】 ミシュラン The Michelin Guide (Le Guide Michelin) is a series of guide books to over a dozen countries published annually by the Michelin company. André Michelin published the first edition of the guide in 1900 to help drivers maintain their cars, find decent(適切な)lodging, and eat well while touring France. Today, the Michelin Red Guide is the oldest and best-known European hotel and restaurant guide.ミシュランTRANSWORLD CITYサイズ、カラー:26×1.95ブラック/リフレクター
2007.04.24
コメント(0)
-

ラオスのお酒、ラオラオ
ペットボトルの中に入っているものがラオラオ↑ 今日は4月20日のブログ、ビアラオ(ラオスビール)の話の続き、ラオラオの話です。 私の観察によれば、飲食店で飲まれているアルコール飲料はビールだけ。 ほかのアルコール飲料を飲んでいる光景を目にすることはほとんどありません。 メニューにはカクテル、例えばメキシコ料理店ではテキーラ、フランス料理店ではワイン、おしゃれなバーではコニャックやウイスキー、各種スピリッツ類はあります。 もちろん、そのような場所では、それなりに飲まれていますが、普通の飲食店ではビール。 「とりあえずビール!」と言って頼むのですが、最後までビールです。 ビールしかないのかと思ってしまいます。 ところが、ラオスには、地酒があります。 「ラオラオ」と言います。 意味は、「ラオスのお酒」。 先月末、3月31日にビエンチャンから500kmほど南に位置するサバナケット県のとある村を訪問。 そこの副村長が、手にしていたものが、少々黄色が買った色の液体の入ったペットボトル。 ラオラオだと彼が言います。 さっそく、ご相伴にあずかることに。 味は、何と「焼酎!」。 それも米焼酎。 度数が50度くらいあるということなので泡盛なのかもしれません。 味は全く同じなので、沖縄の泡盛がラオスに伝わったのか、あるいはラオスのラオラオが沖縄に伝わったのかもしれません。 この辺の歴史を蘊蓄(うんちく)として付加すれば売れそう。 液体に色が付いていたのは、ペットボトルの中に入っている木片から出る色でした。 何の木かはわかりませんが、健康に良いのだそうです。 ラオスでは、村ごと、家庭ごとにラオラオを作っていて楽しんでいるのだそうです。 市販されることはほとんどありません。 ラオラオを手に入れるためには、全国各地を歩き周る必要がありそうです。 村に行けば、地元の人がふるまってくれますし、地元の市場などでは自家製のラオラオがビール瓶やペットボトルに入れられて売られていることがあるそうです。 ビエンチャンで売れると思うのですが…。 と思っていたら、ビエンチャンのコンビニで売っていました。 本物とは違うという説もありますが…。 これはビジネスになると思うのですが…。らおらお 米焼酎 45度700ml(ラオス)LAOH LAO楽天シニア市場 【Bon appetit!】 保存処理された肉類で肺疾患? A US new study found a link between frequent consumption of cured(保存処理された)meats and chronic obstructive pulmonary disease (COPD)(慢性閉塞性肺疾患), which is characterized by swelling(腫脹)of the airways(気道). Other studies, mostly on animals, have shown a link between nitrite(亜硝酸塩)consumption and reduced lung function. Nitrites are added to cured meat as preservative(保存料), color, or anti-bacterial agents.
2007.04.22
コメント(3)
-

ガラクタの様な小片からモザイク画は作られているのですね
モザイク画を見たことがあると思います。 そうです。たくさんの小片を貼り付けていって、最後には一つの大きな作品になったものです。 駅の構内や教会の壁なんかにモザイク画があったりしますね。 一つ一つの小片は、何でもない石やタイルですが、これらが集まってすばらしい作品に仕上がっています。 何でもない小片は、私たち一人一人がいつでも手に入れられるものです。 もし全体の作品のイメージを持っていれば、小片はすばらしい作品へ変身します。 もし全体の作品のイメージを持っていなければ、小片はガラクタでしかありません。 私たちに目標が必要な理由がここにあります。 誰もが手にできるものを活かすか無駄にするかは、全体のイメージ(目標)を持っているかいないかによるのです。 あなたが手にしたものを何でもない小片だと思って捨てていませんか?(注)今日の話は、喜多川泰氏の文章から刺激を受けて書きました。【Bon appetit!】 フェデリコ・フェリーニ Fellini was one of the most influential and widely revered(尊敬された) Italian film-makers of the 20th century. His films typically combine memory, dreams, fantasy, and desire, and express a basically humanistic outlook. Filmed in color beginning with Juliet of the Spirits (1965), his movies became a celebration of life in all its beauties and grotesqueries while also exploring his wildly imaginative dream life. Four of his movies won Academy Awards for Best Foreign Language Film.フェリーニ,映画を語る
2007.04.21
コメント(3)
-

ラオスのビール
ビアラオ。コップに氷を入れてビアラオを飲みます。↑ 昨日は、夕陽がとてもきれいでしたので、メコン川沿いをしばらく歩いてしまいました。 たくさんの屋台が出ていて、みんな夕陽を楽しんでいます。 今日も、夕陽がきれいだったので、今日は歩くだけではなくビールも飲むことにしました。 ラオスには、ビアラオ(ラオスビールの意)という名のビールがあります。 ビアラオしかありませんので、銘柄を聞かれることはありません。 実は、デンマークのカールスバーグがビアラオの工場で作られていますので、カールスバーグも銘柄としてはあるのですが、頼んでいる人を見かけることはほとんどありません。 ビールを飲みながらメコン川で釣りをしている人などを眺め夕陽を眺めのんびりと過ごしました。 我々の席に、カールスバーグ娘がやってきました。 ラオス人の同僚は、カールスバーグ娘が来ると、俄然カールスバーグを飲み始め、一本でも多く彼女たちにビールを注いでもらう性癖があります。 今日も同じことが起こるなと思っていたところ、彼は今朝帰省先から夜行バス帰ってきたところなので少々疲れ気味。・・・パス。 というわけで、平和なうちに太陽が沈んでいきました。↓メコン川沿いにはたくさん屋台があります。【Bon appetit!】 キャビア Caviar is the roe(魚卵), or eggs, of various species of sturgeon(チョウザメ)processed as a piquant(ピリッとする)table delicacy(珍味). Due to its high price, it is synonymous in Western culture with luxury and wealth. The best-known caviar comes from the countries on the Black and Caspian seas and the rivers that flow into them. In 2006, however, declines in sturgeon species led to a suspension(停止)of the international trade in nearly all caviar from wild Caspian sturgeon. Caviar is never served with utensils made of what material?ビアラオ 5度 330ml(ラオス) BEER LAO
2007.04.20
コメント(2)
-

ラオスのフランスパン
PVO製サンドイッチ。このフランスパンがとても美味しいのです↑ ヴィエンチャンの街のあちこちでフランスパンの屋台をみかけます。 フランスパンを使ったサンドイッチを売っています。 ラオスは1893年からフランスの統治下にありましたので、フランスパンは美味しいと考えられますが、実は、1975年に共産党独裁政権になった時に、フランス系レストラン、商店はみな閉鎖し、ベーカリーの歴史はなくなってしまったようです。 20年近くの空白期間を経て、ようやく1994年になって北欧系のパン屋さんが営業を開始し、それからフランス系、カナダ系のパン屋が生まれフランスパンの伝統が復活したようです。 パン工房の職人の多くは1960年代後半にフランス人のためのパン工房で働いていた人だということです。 サンドイッチの具は、ラオスらしさがあふれています。 たいていの屋台では、具は各自が注文します。 と言われても何を注文していいか迷います。 ありがたいことに、オーダーメイドがあります。 「全て」を頼むと、何でも入れてくれますので、慣れたらその中から選べばよいでしょう。 メコン川沿いにあるPVOという名のサンドイッチ屋さんは、パンがとても美味しく、私の大のお気に入りです。 パン自体が、パリッと香ばしいのです。 また、パンの中に濃厚な肉の旨みとピクルスの甘酸っぱさが加わって、なんともいえない美味しさを奏でてくれます。 最もラオスらしい具は、香草(パクチー)でしょう。 パクチーが苦手な人は抜いてもらわないと、せっかくのフランスパンが堪能できません。 もっとも、ラオスではどこでも香草が出てきますので早く慣れる必要があるでしょう。 アサツキ、辛子みそもラオスらしい感じがします。 あとは、クリームチーズ、ツナ、もやしやニンジンの酢漬け、パパイヤのピクルス、生のキュウリ、オニオンスライス、マヨネーズサラダ(アサツキ、ニンジン、キャベツ、キュウリ等をあえる)、焼豚、パテ、ソーセージ、煮凝り等が入っています。 フランスよりおいしフランスパンを、堪能しに来て下さいね。[チャック袋]日清製粉 リスドオル フランスパン専用粉 2.5kg【Bon appetit!】 タイタニック The Titanic was a massive ocean liner that was thought to be virtually(事実上)unsinkable. She was on her maiden voyage and carrying more than 2,200 passengers and crew when she struck an iceberg on April 14, 1912, and sank early the next morning. More than 1,500 people were killed as a result. In 1985, a team led by Robert Ballard and Jean-Louis Michel located(位置を突き止める)the Titanic's wreck(残骸)on the ocean floor(海底). The team made a discovery that shed light on how the ship sank.
2007.04.19
コメント(4)
-

正月後のヴィエンチャン
わかりにくいですが、水の付いた枝で、仏さまに水をかけています↑ 正月3ケ日が過ぎ、昨日からヴィエンチャンの街中はいつもの静かさに戻りました。 昨日も、ビニール袋にカメラなどを入れて、濡れないように万全の支度を整えて出かけましたが、杞憂でした。 一昨日までの喧騒は全くなくなっていました。 お寺もお坊さんが片づけをしている程度で、参拝客は全く見当たらず、もちろん出店もありません。 水のために泥沼と化した道路も、昨日はもうほとんど乾いていました。 ゴミが道路にたくさん散らかっています。 水を入れて口を縛ったビニール袋で作った水爆弾の残骸がかなり落ちています。 また、この3ケ日はお寺自体が大きなオーディオ用のスピーカを用意して大きな音で音楽を流していました。 タイやラオスの音楽だと思いますが、なかなか面白い風習だと思いました。 日本なら、神聖なお寺の境内で何事だということになりそうですが、どこのお寺もガンガン音楽を流し続けていましたので普通の風習なのでしょう。 また、ヴィエンチャンのお寺はキンキラキンのお寺がほとんどです。 仏像もキンキラキンです。 水の掛け合いバトルが終わったヴィエンチャンにまた静けさが戻りました。↓金色のお寺、金色の仏像がとても多いです
2007.04.18
コメント(3)
-
ラオスのシャンゼリゼ
ラーンサーン通りから凱旋門を臨む↑ ビエンチャンには凱旋門があります。 パトゥーサイと呼ばれています。 パリのエトワールのように、凱旋門の周りの道路は反時計回りに回ります。 そして、凱旋門からメコン川の方に向って広い道路が一直線に伸びています。 シャンゼリゼのようです。 道路の名前はシャンゼリゼではなく「ラーンサーン通り」。 「百万頭の象」という意味で、1353年にラオスを建国したファーグム王の王国の名「ラーンサーン」の名前をとっています。 さすがに「フーケ」や「リド」はありませんが、ビエンチャン一のショッピングセンター「タラートサオ」があります。 「タラートサオ」では、パリにわざわざ行かなくてもヴィトンやシャネルがリーズナブル(?)な価格で手に入りますよ。 アメリカ大使館もこの通りにあります。 ラーンサーン通りの突き当りにはホワイトハウス(迎賓館)があります。 凱旋門の近くには、「ナーダオ」というフランス料理の店があり、ビエンチャンのベストフレンチと言われています。 また、首相官邸や官庁もこのあたりに集まっています。 凱旋門の上に登ると、メコン川の向こうにタイが見え、とてものどかです。
2007.04.16
コメント(2)
-
びしょ濡れのラオス正月
トラックの荷台にいる人をめがけて水をかけます↑ ラオスの新年はを水かけ合います。 昨日も今日も濡れました。 道を歩いていたら、男の子が水鉄砲で水をかけてきました。 そちらに気を取られていたら、突然男の子のお母さんがひしゃくの水を至近距離から私めがけてかけてきました。 かけられたら、「新年おめでとう」と言います。 また、歩いていたら、年配の女性がこちらに向かってきてひしゃくの水を正面からかけてきました。 もうびしょ濡れです。 今度は、小さな女の子が水鉄砲で狙ってきます。 このようなことが、歩いている間中ずーと続きます。 歩道のあちこちで、人の集団があります。 道を走るトラックの荷台に乗っている人に向かって集団で水をかけます。 トラックの荷台からも水が歩道に向かって飛んでいきます。 オートバイを運転している人もずぶ濡れです。 トゥクトゥクというオート三輪の乗客にも容赦なく水が掛けられます。 トラックの荷台の集団が別のトラックの荷台の人めがけて水をかけています。 水を入れて口を閉めたビニールの袋の投げあいも見られます。 バトルという感じです。 お寺は、初詣の人でいっぱいです。 日本の花まつりのように、お釈迦様に水をかけます。 花びらの入った水に葉のついた木の枝を浸して、その枝を振って水をかけています。 出店がたくさん出ていて、食べ物やおもちゃ、首から下げるレイ、花びらの入った水等を売っています。 水をかける人の声が一日中響き渡るビエンチャンです。
2007.04.15
コメント(2)
-

ラオスから明けましておめでとうございます
新年を祝う横断幕、今日から2550年が始まります↑ 今日から新しい年が始まりました。 昨日から新年おめでとう挨拶があちこちから聞こえてきます。 昨日は大みそかということで、どこもお祭り騒ぎ。 道行く人に子供が水鉄砲で水をかけます。 走っているオートバイに向かって歩道から大量に水がかけられています。 突然首筋から背中が冷たくなったと思ったらひしゃくのようなもので水を背中に入れられてしまいます。 昨日は私もかなり濡れてしまいした。 今日もまた水をかけられそうです。 早朝、戦々恐々して街中を歩いたのですが、散歩中の犬と早朝からやっている食堂を除き、街中は静まり返っていて、水はかけられませんでした。 昨日はいろいろな処でパーティーやバーシーと呼ばれる儀式が行われていました。 私もバーシーの儀式を見てみました。 お供え物は、花、バナナの葉等を塔のような形に作り上げてその周りに果物やお菓子を置きます。 子ブタも供えられています。 豚ではなく鳥が供えられることが普通ですが、鳥インフルエンザの影響で今年は鳥が手に入らないために、豚になったようです。 お供え物に綱っがている糸を長く伸ばして参加者がその糸をつかんでいます。 祈祷師のような人がお経のような言葉や歌を歌い儀式が始ります。 時々参加者の女性が米をみんなに振りかけます。 祈祷が終わると、供え物の所にある20cmくらいの長さの糸を、他人の手首に結び付けます。 結びながら相手の幸福や健康を祈ります。 私も、7人の人から巻いてもらいました。 3日間は外せないというので、今朝も手首に巻いたままです。 儀式の後は、飲食や踊りです。 手の指を後ろにそらせて踊る、あの踊りがラオスでもあります。 私も見よう見まねで踊ってみましたが、踊るというよりその場にいるだけという感じでした。今後の上達が期待されます。 こうして、大晦日が過ぎていきました。バーシーの儀式、祈祷師が祝詞(?)をあげる↓
2007.04.14
コメント(4)
-
ラオスのフルーツシェイク
屋台に積まれたたくさんのフルーツ。↑おいしいシェークを作ってくれます 道を歩いていると、たくさんの屋台を目にします。 歩道上に屋台だけ出している人もいますが、多くは食堂が自分の店先に屋台を出している場合が多いように見受けられます。 独立している屋台はおかずやスープを売っている屋台が多いのに対して、店先の屋台は、フルーツジュースや、自家製の春巻き、フランスパンのサンドイッチ、お菓子等を売っている屋台が目に付きます。 ラオスはとてもフルーツが豊富で、しかも、とても美味しいのです。 店先で、フルーツシェイクを頼むのも楽しみのひとつです。 バナナ、メロン、スイカ、マンゴ、パパイヤ等のシェイクだけでなく、なじみのない果物もたくさんあります。サポディーラは見た目ジャガイモのような形のフルーツですがなかなかすぐれものという感じです。ドラゴンフルーツなどもあります。 同じような屋台が並んでいても、混んでいる屋台とお客のいない屋台があるのは不思議です。 理由があると思うので、解明しようとしているのですがまだわかりません。 フルーツの屋台に次いでよく目にするのがフランスパンのサンドイッチ屋さんです。 ラオスはフランスの植民地だったこともあり、フランスパンがとてもおいしいのですが、このことは違う機会に書きますね。
2007.04.12
コメント(4)
-
ラオス正月
早朝に行われる托鉢。↑多くの人が主食のもち米等を喜捨します。 14日から正月休みということで町中が浮足立っています。 なぜ正月? 1月1日の正月は国際正月ということでお祝いはしますが、それほど盛大にお祝いすることはないそうです。 2月の旧暦正月も祝うそうですが、それほどではないそうです。 4月の正月が、ラオスの新年ということで一番祝うのだそうです。 年号も2549年から2550年になるという人もいます。 単に、2006年から2007年になるという人もいます。 年号は変わらないけど、とにかくお祝するのだという人もいます。 正月の由来を何人かの人に聞きましたが、わかりません。 日本の花祭りと関係していると思うのですが…。 とにかく一年のうち最も賑やかなお正月がもうすぐやってきます。 盆と正月が一緒にやってくるという雰囲気のようです。 私も、初めての経験ですのでいったいどんな正月なのよく見てみたいと思っています。 道を歩いていると水をかけられびっしょりになるというので、戦々恐々としています。 官庁は明後日(13日(金))が御用納めだそうです。 今日の午後銀行に行って来ましたが、相当混んでいました。 そして御用始めは、19日(木)。 明日あたりから田舎に帰る人も多くいるそうです。
2007.04.11
コメント(0)
-
土埃
↑住家の前の道。埃っぽい感じが分るでしょうか? ある統計によると、ラオスを訪れた人のうちラオスの魅力に取りつかれる人の割合は、100%です。 確かに、この結果はうなずけます。 どこに魅力があるのか、折を見てご紹介していきたいと思いますが、今日は魅力というより私の住家の前にある道をご紹介します。 この道は、空港から街へ入るメインストリートです。 広い道で、しかも真ん中辺がしっかり舗装されています。 11月から乾期のためほとんど雨が降りませんので、乾燥した土が埃となって空中を舞っています。 歩道はあるのですが、乾燥した土が溜まっているので砂の中を歩いているようでとても歩きにくいうえに、至る所で工事をしているため歩きにくい状況です。 雨が降ったら今度はぬかるみになりそうで心配です。 だからでしょうか、歩いている人がほとんどいないのです。 歩いているのは私くらいのものです。 街中に行けば、外国人の旅行者が歩いていますが、地元の人が歩いている姿を見かけません。 皆さん、オートバイやトゥクトゥクと呼ばれる乗合オート三輪車に乗って移動しています。 日中の強い日差しの中では歩けないという方が正解かもしれません。でも、夜も歩いてる人がいないんですよね、これが。 毎夕レストラン通いしている私は、住家と街中を一人歩き回っています。 こうして飽きもせず歩く理由は、魅力的(?)なレストランがたくさんあるからなのです。 ラオスの食べ物についても折を見て紹介していきたいと思います。 それにしても、今日食べたインド料理(今日はラオス料理はお休みしてしまいました)はおいしかったです。
2007.04.09
コメント(2)
-
ラオスの風に吹かれて
レストランからメコン川の夕日を臨む↑かすかな風が心地よい(対岸はタイです) 皆さん、すっかりご無沙汰してしまいました。 3月10日に日本を発って、その日はバンコクで友人たちと業務打ち合わせをし、11日にラオスの首都ヴィエンチャンにやってきました。 あっという間の4週間です。 毎日暑い日が続いています。 熱暑というか酷暑というか、とにかく太陽にあたっているとあまりの暑さにくらくらします。 ラオスは10月頃から4月頃まで乾期で、この4月が一番暑くなります。 14日の土曜日から正月休みに入ります。 その時、水かけ祭りというのが行われ、道を歩いている人は誰でも水をかけられずぶぬれになるのだそうです。水をかけられることによって心身が清められ新しい年を迎えられるのだそうです。 今日から、このWebサイトの名称を変更しました。 『ラオスの風に吹かれて』という名称にしました。 毎日暑いのですが、なぜか木陰や日陰に入ると、かすかながら吹いている風を全身が感じて、とても心が安らぎ幸せな気持ちになるのです。 その気持ちを名称に採用しました。 これから、ラオスのことを中心に書いていきます。 楽しみにしていて下さいね。
2007.04.08
コメント(8)
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
-

- あなたの旅行記はどんな感じ??
- 江戸時代末期から明治時代にかけて、…
- (2025-02-07 10:06:50)
-
-
-
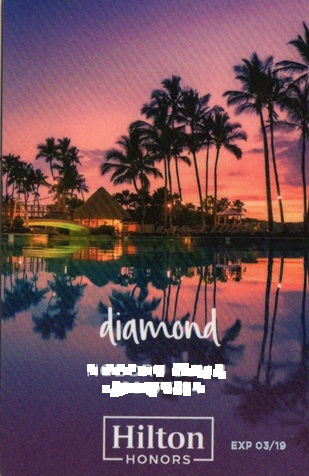
- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…
- ヒルトン ダイヤモンド会員 2026年3…
- (2025-02-17 04:57:20)
-
-
-

- 韓国!
- 外出しないと居られない私!
- (2025-02-18 10:57:47)
-