2011年12月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-

忌野清志郎(RCサクセション)「ラヴ・ミー・テンダー」+「メルトダウン」
2011年を振り返る(その3)~やっぱり原発と清志郎(2/2) もう一つ、この1年ずっと気になり続けた清志郎ナンバーが「ラヴ・ミー・テンダー」。言わずと知れた、エルヴィス・プレスリーの有名曲だが、『COVERS』に収められた各楽曲と並んで、日本語訳詞が実に見事。元のメロディを維持しながらこれだけぴったりはまった訳詞というのは、そうそう作れない。“なに言ってんだ~/よせよ~/騙せはしねえ~”、“放射能は~/いらねえ~/牛乳が飲みてえ~”。そう、反核・反原発の訳詞なのである。動画は、前回と同様、ライヴのテイクから。 前回少し触れたように、この曲を含むアルバム『COVERS』は東芝からの発売が中止になった。親会社が原発推進に加わっていたわけだから、“大人の事情”的にはなるほどだったわけだが、その当時、バブル景気に浮かれていた日本で、こんなところに目をつけていたのは先見の明があったとしかいいようがない。 けれども、それを受け止めた若者たちの多く(筆者も含む)はどこか勘違いしていたのかもしれない。皮肉にも、“ロックに反骨精神を見る”ことが、清志郎のメッセージを正当に評価する妨げになってしまった側面があったのではなかろうか。某民放の生番組でリハーサルとはまったく違うのを演り、彼らの楽曲を放送禁止にしたFM東京を叩いた姿などは、まさにその象徴だった(世の動画サイトにも、放送内容は繰り返しアップされ続けている)。でも、よく考えれば、清志郎が思い描いていたのは、その先に放送される歌のメッセージだったはずで、もっと言えば、聴き手が何らかのアクションを起こすことであったに違いない。けれども、結果として、聴き手側はそうしたアクションを十分に起こすまでは至らなかったので、今回のような惨事を迎えてしまったということになってしまったのだろう。 今回も動画の紹介ついでにおまけをもう1曲。清志郎そっくりの“友人”ZERRYが率いるバンド、ザ・タイマーズ(“大麻”と“ザ・タイガース”を引っかけた名称)による、「メルトダウン」。この表題となっている用語は、わずか9カ月の間に、日本人では知らない人はいない有名語になってしまったわけだが、20年も前にこれをタイトルにしてこんな歌をやっていた(しかもこのライヴ映像の会場は、九州電力保有の福岡電気ホールとのこと)のである。これって彼が遥か未来を見通していたということがわかるのと同時に、やっぱりその当時の世間の聴衆には本当にはメッセージが浸透しきらなかったのかな、という感じも受ける。 一年の締めくくりが暗くなってしまうのはどうかとも考えたが、一区切りで2012年に突入するまでに、ずっと気になっていた忌野清志郎のメッセージを思い出しておきたかった。 来年はどうかすべての日本に住む人たちにとって、前向きな1年となりますように。 皆さん、よいお年を。 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、ひとつでも“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓ ↓
2011年12月31日
コメント(2)
-

忌野清志郎(RCサクセション) 「サマータイム・ブルース」
2011年を振り返る(その2)~やっぱり原発と清志郎(1/2) 今年を振り返って、何よりも3月の震災と津波の被害に遭われた方々のご冥福を祈るとともに、ご家族や友人を失った方々にも、いま一度、心からお見舞いを申し上げたい。 その一方で、今回の地震・津波は単なる自然災害にとどまらず、原発事故・放射能汚染というとんでもない“おまけ”までついてくることになった。そして、放射能汚染に対する政府や自治体の後手にまわった対応に、最初は慌て、やがて憤り、しまいには呆れてくるという何とも複雑な気分を経験し、それは今も続いている。 そんな気分の中、一連の災害・事故の直後から気になって仕方なかった忌野清志郎の曲(カバー曲)が2つあった。いずれもRCサクセションのいわくつきアルバム、(1988年にいったん発売中止となり、その後、別のレコード会社からリリースとなったアルバム)『COVERS』に収められていたものである。1年の締めくくりとして、2回に分けてこれら2曲を取り上げておきたい。 ちなみに、上記アルバムは、原発事故後、店頭で品切れになるほどの異例のセールスを記録したとのニュースもあった。なので、発表当時のことを知らない人たちの間でも、もはや周知の内容かもしれない。また、世のブログやその他のメディアで頻繁に取り上げられたので、今さらと思われるかもしれないが、お付き合いいただきたい。 まず、今回は「サマータイム・ブルース」という曲である。オリジナルはエディ・コクラン(1958年)、さらには、ザ・フーのカバーでも有名な曲。これに日本語の訳詞をつけたのが、清志郎ヴァージョンである。 ちょうど23年前のこの時期(1988年12月31日~1989年1月1日)の年越しライブから、「サマータイム・ブルース」の映像をご覧いただきたい。 ついでに映像をもう1本。上記の「サマータイム・ブルース」を含む(さらには「君が代」なども入っている)メドレー。 ギター1本でこれだけ聴き手に訴えかけられるアーティストは、やっぱり稀有である。忌野清志郎という人は、そうしたアーティストの一人だった。2009年に早過ぎる死を迎えた清志郎だったが、天国でいまの日本をどう見ているのだろうか。もしもの話をしても仕方ないのは承知しているけれど、現在まだ清志郎が生きていたならば、電力会社には“ざまあみやがれ”と言ってるかもしれない。その一方で、きっと多くの人々には“前向きに生きよう”っていうメッセージを送ってくれていたことだろう。[収録アルバム]RCサクセション 『COVERS』(1988年) 【送料無料】カバーズ/RCサクセション[CD]【返品種別A】【smtb-k】【w2】 下記ランキングに参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓
2011年12月30日
コメント(0)
-

USA・フォー・アフリカ 「ウィ―・アー・ザ・ワールド(We Are The World)」
2011年を振り返る(その1)~チャリティ音楽の偉大さを想起 2011年の年の瀬も迫ってきたところで、今年を振り返ってというような記事でも書こうかと思い立った。が、振り返ってみれば、結局は3月11日のあの震災に行き着いてしまう。筆者自身は、このブログでa~haのアルバムについていつものように書いたものを朝にアップし、その日の午後にあの地震に遭った(お陰でこのa~haの『遥かなる空と大地』は、変な意味で一生忘れられないアルバムとなってしまった)。 地震直後は自分自身も気が動転していたが、やがて落ち着くにつれて、音楽やスポーツなどの力を実感する場面があることに気付いた。音楽(特にロック)に関して言うと、“何か(誰か)の為に音楽を演る”というのは不純な動機であるという意見があり、これもよくわかる。けれども、今回の震災後の状況を見ていて、音楽を含めて広い意味での“芸能界”の威力を感じた。 そうした現象、というかそのパワーが認知されることになった原点の一つは、80年代、USA・フォー・アフリカ(U.S.A. for Africa)の名のもとに著名アーティストが集合したあの企画だったのではないかと思う。曲を書いたのはマイケル・ジャクソンとライオネル・リッチー。クインシー・ジョーンズがプロデュースを引き受け、当時の有名アーティストの大共演へと発展した。“アフリカの為に”といいながら欧米でお祭り的に企画・販売(ヒット)するという構図は確かにどこか欺瞞的ではあるが、音楽を通じてこれだけ人々に訴えかけられることの凄さをものの見事に証明した企画でもあったように思う。 レイ・チャールズやマイケル・ジャクソンといった、既に鬼籍に入ったアーティストの参加も、四半世紀以上経った今となっては懐かしい。少しずつ短いフレーズを歌いまわす中で、何人かは極めて個性を発揮していた。筆者の印象にとりわけ強く残っているのは、ディオンヌ・ワーウィック(短い中で実力のほどを見事に発揮)、シンディ・ローパー(実力に裏打ちされた個性の強さが強烈な印象)であった。無論、マイケル・ジャクソンはごくごく自然にスーパースターの存在感を発揮しているし、レイ・チャールズの貫録ある歌いっぷりも見事。さらに印象的だったのは、スティーヴィー・ワンダーとブルース・スプリングスティーン(途中で二人の掛け合いの部分がある)である。どちらも歌の節回しの個性が濃く、なおかつふつう実現しないようなジャンル違いの取り合わせは、何とも印象に強く残った。 ともあれ、懐かしの「USA・フォー・アフリカ」で“音楽の力”を思い出してみていただきたい。 [収録盤]U.S.A. for Africa / We Are The World(シングル盤、1985年リリース) ウイ・アー・ザ・ワールド[DVD+CD]/USA・フォー・アフリカ[DVD]【返品種別A】 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、ひとつでも“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓ ↓
2011年12月28日
コメント(2)
-

X'masまとめ&INDEX更新
2011年も年の瀬を迎えました。クリスマスはいかが過ごされたでしょうか。 ひとまずはここ1週間ほどのクリスマス関係のリンクをまとめておきます。 エルトン・ジョン「ステップ・イントゥ・クリスマス(旧邦題:ロックンロールで大騒ぎ)」;動画編 ブルース・スプリングスティーン「サンタが街へやってくる」;動画編 ボブ・シーガー&ザ・シルバー・ブレット・バンド「リトル・ドラマー・ボーイ」;動画編 ケイト・ブッシュ「ディセンバー・ウィル・ビー・マジック・アゲイン」;動画編 上記の記事分も含めてINDEXページも更新しました。INDEXページはジャンル別、それぞれのジャンルでアーティストのアルファベット順に過去記事をリストにしたものです。お時間のある方は、ぜひ過去記事でお気に入りのアルバムや曲、アーティストなどご覧いただければ幸いです。 INDEXページへのリンク: アーティスト別INDEX~ジャズ編へ アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編へ アーティスト別INDEX~ラテン系(ロック・ポップス)編へ アーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ下記ランキングサイトに参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでもありがたいのでお願いします!)をぜひクリックしてってください。 ↓ ↓ にほんブログ村 : 人気ブログランキング:
2011年12月27日
コメント(0)
-

クリスマス・ソング特集~映像編(PART 2)
クリスマス・ソング特集~映像編(PART 2) クリスマス・ソングの映像編、第二弾です。今年、クリスマス曲として本ブログで取り上げた残りの2曲の映像をお届けします。 まずは、ブルース・スプリングスティーンの「サンタが街にやってくる」。映像は、70年代当時のものではなく、数年前、フランスでのライヴと思しきものです。今年は6月にスプリングスティーンのバックバンドであるE・ストリート・バンドのサキソフォニスト、クラレンス・クレモンズ死去という悲しい知らせがありました。ビデオでは在りし日の(そしてこの曲をやるのには欠かせない)“BIG MAN”の雄姿も収められています。 続いては、ボブ・シーガーの「リトル・ドラマー・ボーイ」です。すっかり白髪のベテランロッカー(今年で御年66歳)となりましたが、独特のヴォーカル・スタイルは変わりません。映像は、つい先頃(2011年11月)のライヴからのものです。 ブルース・スプリングスティーンにボブ・シーガーときたので、おまけをもう一つ。今年1月(約1年前)のライヴ映像です。ボブ・シーガーのライヴにスプリングスティーンが飛び入りし、「オールド・タイム・ロックンロール」をやっています。アメリカン・ロック・ファンには垂涎の組み合わせですね。 今日は24日。皆さん、素敵なイブ(といっても、もうすっかりイブの夜ですが)とクリスマス(25日)をお過ごしください。 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、ひとつでも“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓ ↓
2011年12月24日
コメント(0)
-

クリスマス・ソング特集~映像編(PART 1)
クリスマス・ソング特集~映像編(PART 1) 「個性的なクリスマス・ソングたち」と題して4回ほど書きましたが、気がつけばもう23日。毎年のことながら、もう少し早めに気付いて計画的に書けばよいものを、結局はクリスマス直前に気がつく始末です。 なにはともあれ、2回に分けてこれらのクリスマス曲の映像編をお届けしようと思います。まずは、4曲のうちの2曲です。 最初は、エルトン・ジョンの「ステップ・イントゥ・クリスマス」。1970年代当時のプロモーション・ビデオの映像です。ビデオの作りは何とも古めかしく見えますが、それもそのはず。40年近く前ということになります。とにかくエルトンが若いです。 続いては、記事の掲載順と前後しますが、ケイト・ブッシュの「ディセンバー・ウィル・ビー・マジック・アゲイン」をいってみましょう。これまた30年ほど前の映像(発売当時の映像)です。これだけ難易度の高いヴォーカルを“ふつうに”こなしてしまうわけですから、本当にこのケイト・ブッシュという人のヴォーカルの表現力には驚かされます。 残る2曲は明日にでもあらためて更新しようと思います。 下記ランキングに参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓ ↓
2011年12月23日
コメント(0)
-

ケイト・ブッシュ 「ディセンバー・ウィル・ビー・マジック・アゲイン(December Will Be Magic Again)」
個性的なクリスマス・ソングたち(4) ケイト・ブッシュ(Kate Bush)は、デヴィッド・ギルモア(ピンク・フロイド)に見出されて1977年にデビューした英国人女性シンガー。当初はアイドル視された面もあったが、その歌唱力と、何よりも独特の音楽世界が高く評価され、音楽シーンに大きな影響を与えてきた。日本では、デビュー曲の「嵐が丘(Wunthering Heights)」がTV番組『恋のから騒ぎ』のオープニング・テーマ曲として採用されたことで、ケイト・ブッシュを知らなくてもその歌声に心当たりのある人が多いことだろう。 そんなケイトが1980年末のクリスマス向けにシングル発表したのが、この「ディセンバー・ウィル・ビー・マジック・アゲイン(December Will Be Magic Again)」という曲だ。UKチャートでは29位、アイルランドのシングル・チャートでは13位にランク・インした。 ケイト・ブッシュのよさは、独自の音楽世界にある。個人的には“不思議ちゃん”という言葉がいつも思い浮かんでしまうのだが、ただのキワモノとか風変わりというので終わるアーティストではないのがケイト・ブッシュの魅力。音楽が独特であるのは、作品(アルバムや楽曲)がトータル・ヴィジョンの上に成り立っていて、なおかつ、歌がうまい。音域が広く、しかも声質を自在に使い分けられる。 12月、クリスマスに聞こえてくる曲のヴァリエーションと言えば、案外、定番で繰り返し流れる曲というのが決まってしまっているけれども、こういう個性的なのもいい。そもそもこの曲はシングルのみの発売で、彼女自身のアルバムには含まれていないが(8枚組のコレクター盤には入っているらしいが、さすがにこの1曲目当てでこれを買うわけにはいかないので)、どこかのコンピ盤などで見かけた方は、ぜひレパートリーにいれてみてはいかがだろうか。きっと個性的なクリスマスがやってくるかも(?)。[収録盤]Various / Elton John's Christmas Party (2005年)その他、各種クリスマス・コンピ盤に収録。[関連記事リンク]この曲の動画はこちらから。エルトン・ジョン 「ステップ・イントゥ・クリスマス」ブルース・スプリングスティーン「サンタが街にやってくる」ボブ・シーガー 「リトル・ドラマー・ボーイ」 以下のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、ひとつでも“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓ ↓
2011年12月23日
コメント(0)
-
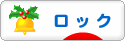
ボブ・シーガー&ザ・シルバー・ブレット・バンド 「リトル・ドラマー・ボーイ(The Little Drummer Boy)」
個性的なクリスマス・ソングたち(3) 前回のB・スプリングスティーンに引き続き、いかにもアメリカン・ロックなアーティスト、ボブ・シーガー(Bob Seger)と彼が率いるバンド(The Silver Bullet Band)によるクリスマス曲を取り上げてみたい。ボブ・シーガーは1970年代から活躍し、80年代の『ライク・ア・ロック』など、まさしく“アメリカン・ロックの王道”を行く地道で着実な活動をした人物である。 このバンドが演奏するクリスマス曲として時折耳にするのが「リトル・ドラマー・ボーイ(The Little Drummer Boy)」。もともとはチェコのキャロルに基づいて1941年に米国のクラシック作曲家によって作られたらしい(その時のオリジナルのタイトルは「太鼓のキャロル(Carol of the Drum)」)。その後、50年代になって複数の録音がなされ、クリスマス・キャロルの定番曲として定着したようである。 クリスマス・エイドのチャリティ盤(好評を博し、現在まで7作リリースされている)の第1弾(1987年)にボブ・シーガーが提供したものだが、この人は不器用というか真面目というか…、結局どう歌っても、ストレートで無骨なロッカーの歌にしかならない。とかいって、別に悪口を言っているわけではない。こういう部分こそが、ボブ・シーガー好きの筆者にとっては外せない魅力なのである。その意味で、この「リトル・ドラマー・ボーイ」も、実にボブ・シーガーらしい歌唱、彼のバンドらしい演奏に仕上がっている。要は、題材はクリスマス曲なんだけれども、どこからどう聴いてもまずもってボブ・シーガーという仕上がりになっているというわけである。 余談ながら、このボブ・シーガーのヴァージョンでは、なぜか歌詞から宗教色が消されている。もともとは貧しく捧げものもできない少年が太鼓を叩き、主イエスは彼に微笑みかけるというストーリーの詞である。ここでは、メアリ(聖母マリア)とういう固有名詞が歌詞から削除され、オリジナルでは大文字だった「彼」(イエス様)はふつうの小文字の「彼」(誰を指してるのかは不明の単なる「彼」)に変えられている。[収録アルバム]Various / A Very Special Christmas 1(クリスマス・エイド1) (1987年)[関連記事リンク]この曲の動画はこちらから。エルトン・ジョン 「ステップ・イントゥ・クリスマス」ブルース・スプリングスティーン「サンタが街にやってくる」ケイト・ブッシュ「ディセンバー・ウィル・ビー・マジック・アゲイン」 下記ランキングに参加しています。 お時間の許す方は、“ぽちっと”クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓
2011年12月22日
コメント(0)
-
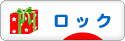
ブルース・スプリングスティーン 「サンタが街にやってくる(Santa Claus Is Coming To Town)」
個性的なクリスマス・ソングたち(2) 第二弾は、ザ・ボスことブルース・スプリングスティーン(Bruce Springsteen)が歌う「サンタが街にやってくる(Santa Claus Is Coming To Town)」である。この曲は1970~71年にジャクソン5がシングル・リリースし、少年マイケル・ジャクソンの可愛らしい歌声とともに一世を風靡した。おそらくは、このジャクソン5のヴァージョンが一般によく知られているものだろう。ただし、その起源はもう少し古く、1934年に最初に発表され、楽譜が売れまくったらしい(最初に録音したのは、同年、ジョージ・ホールという人物とのこと)。 1985年の暮れ、前年リリースのお化けアルバム『ボーン・イン・ザ・U.S.A.』からのシングル・ヒットが続いてきた中で、同アルバムからは7曲目のシングル・カットとなった「マイ・ホームタウン」のB面に収録された。イギリスやアイルランドでは両A面扱いになったとのこと。もともとは1982年のコンピレーション盤に収録されたもので、録音は1975年のライヴのものであった(当時はスプリングスティーンの公式なライヴ盤はまだリリースされておらず、ファンにとっては貴重な音源だった)。 さて、演奏内容だが、スプリングスティーンはアメリカン・ロックの代名詞のような存在で、よく言えば、ハイ・テンションでホットなロック、悪く言えば暑苦しい(?)わけで、それがそのままこのクリスマス曲に表現されているのが面白い。彼のクリスマス曲としては、過去にもう1曲リリースされた「メリー・クリスマス・ベイビー」というのもあるが、スプリングスティーンらしい仕上がりという点では、やはりこちらの「サンタが街にやってくる」の方だと思う。 上品に、あるいは優雅に、もしくは聞き流しのBGM的にクリスマス・ソングを楽しむにはあまり適さないかもしれない。けれども、アーティストの個性が前面に出て、そのアーティストらしい解釈のクリスマス曲はと言うと、筆者としては、真っ先に思い浮かぶ演奏の一つが、スプリングスティーンのこの「サンタが街にやってくる」といったところなわけである。[収録アルバム]Various / In Harmony 2 (1982年)[関連記事リンク]この曲の動画はこちらから。エルトン・ジョン 「ステップ・イントゥ・クリスマス」ボブ・シーガー 「リトル・ドラマー・ボーイ」ケイト・ブッシュ「ディセンバー・ウィル・ビー・マジック・アゲイン」 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、ひとつでも“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓ ↓
2011年12月21日
コメント(2)
-
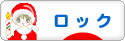
エルトン・ジョン 「ステップ・イントゥ・クリスマス(ロックン・ロールで大騒ぎ)(Step Into Christmas)」
個性的なクリスマス・ソングたち(1) 12月に入ると、ジョン・レノンを偲ぶ間もなく、街ではクリスマス・ソング一色となり、都会を歩けば、様々なクリスマス曲が耳に飛び込んでくる。気がつくと、実際、クリスマスはもうすぐそこだった。何回続くかは分からないけれど、今日からクリスマスまでの間は、“個性的なクリスマス・ソングたち”というタイトルで、そのアーティストらしさがよく表れたポップやロック界のクリスマス曲を取り上げてみたい。一応、オリジナル曲、カバー曲関係なく、“その人らしさ”というのを観点にして、12月の我が家のレパートリーから選んでいきたいと思う。 ひとまず、第1回目はエルトン・ジョンの「ステップ・イントゥ・クリスマス(Step Into Christmas)」。リリースされたのは1973年で、この年のクリスマス・シーズンに合わせてシングルとして発売され、後にはリマスター盤(『カリブ』)のボーナス・トラックや、クリスマスの企画盤『エルトン・ジョンのクリスマス・パーティ』にも再録された。 曲の作者は、ポップ界の黄金コンビ、エルトン・ジョンとバーニー・トーピンの組み合わせ。曲調としては、いかにもエルトン節全開といった風で、ノリノリのロックンロール調ナンバーである。この曲でのエルトンのヴォーカルは、どうも演奏の中に埋もれているような印象を受ける。想像に過ぎないけれど、もしかするとこのようなヴォーカルのミックスは意図的なのではなかろうか。そう思い始めると、確かに、楽器音満載のおもちゃ箱があって、その中からエルトン・ジョンのヴォーカルが聴こえてくるようなイメージもする。 余談ながら、リリース当時の日本盤シングルには「来日記念盤」(74年2月に来日公演を行っている)、「エルトンが’73年をふりかえりながら、クリスマスの想い出を歌ったスマッシュヒット!!」なるようわからんキャッチコピーがついている。そして、その当時の邦訳タイトルが「ロックン・ロールで大騒ぎ」というものだった。もしかして、クリスマス・シーズンの発売を逸してしまったので、日本盤ではクリスマスではない邦訳タイトルになったということなのだろうか?[収録アルバム]Various / Elton John's Christmas Party (2005年)Various / The Best Christmas Album in the World… Ever! (1999年)その他、各種クリスマス・コンピ盤に収録。[関連記事リンク]この曲の動画はこちらから。ブルース・スプリングスティーン「サンタが街にやってくる」ボブ・シーガー 「リトル・ドラマー・ボーイ」ケイト・ブッシュ「ディセンバー・ウィル・ビー・マジック・アゲイン」 下記ランキングに参加しています。 お時間の許す方は、“ぽちっと”クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓
2011年12月20日
コメント(0)
-
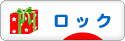
INDEXページの更新
INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。ここ最近の記事を追加しています。INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ右欄(フリーページ欄)からお入りください。アーティスト別INDEX~ジャズ編へアーティスト別INDEX~ロック・ポップス編へアーティスト別INDEX~ラテン系(ロック・ポップス)編へアーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、ぜひぜひ各バナー(1つでもありがたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓ にほんブログ村 : 人気ブログランキング:
2011年12月19日
コメント(0)
-

スティーヴィー・レイ・ヴォーン&ダブル・トラブル 『ライヴ・アライヴ(Live Alive)』
熱気が伝わってくる快演 本作『ライヴ・アライヴ(Live Alive)』は、1990年に亡くなったスティーヴィー・レイ・ヴォーン(Stevie Ray Vaughan)の生前にリリースされた唯一の公式ライヴ盤である。1985~86年ライヴテイクを集めたもので、LPでは2枚組、時間にして70分超の長編ライヴ・アルバムである。 1983年、『テキサス・フラッド~ブルースの洪水~』でデビューしてから、スティーヴィーは年に1作のペースで作品を発表していった。84年に『テキサス・ハリケーン』、85年に『ソウル・トゥ・ソウル』をリリースし、次の86年にリリースされたのが本ライヴ盤であった。 本盤は複数のライヴ音源から成る。1つは85年7月16日のモントルー・ジャズ・フェスティヴァル、そして残る2つは地元テキサスでのライヴで、86年7月17・18日のオースティンのオペラ・ハウス、翌7月19日のダラスのスターフェストでのもの。 参加メンバーの特徴としては、前作(『ソウル・トゥ・ソウル』)からバンドに加わったキーボードのリース・ワイナンスが正式メンバーとしてすっかりバンドに欠かせない役割を演じているほか、地元テキサスでのテイクには、ファビュラス・サンダーバーズのメンバーである兄ジミー・ヴォーンが参加している。“マイ・ビッグ・ブラザー”と紹介されるジミーが参加しているのは、8.、9.、12.、13.の4曲であるが、この兄弟は後に(スティーヴィーの死後)“ヴォーン・ブラザーズ”名義でアルバム(『ファミリースタイル』)をリリースしている。 本盤を聴くたびに印象的なのは、何よりもテンションの高さ。それでいて、中身が濃く、ギターがとにかくカッコイイ。これだけのものを聴かされれば、“実際にライヴが見たい”と思わない人はいないんじゃないだろうか(無論、既に亡くなってしまったスティーヴィーのライヴは見れっこないわけだけれど…)。 素晴らしい演奏などと言っておきながら、こんなことを書くのも何だけれど、実はスティーヴィー本人も述べているように、この時は“調子が悪かった”(薬物での不調)のだそうだ。あと、TV用の収録音源だったそうで、決して音は悪くはないが、どうも平板な感じがする。迫力ある演奏なのでもっといい音で録られていたらよかったのかもしれないが、まあ、大音量で勢いで聴ける盤なので、それはそれでよし。オリジナルを知らない人も楽しめる。演奏者の熱気がそのままダイレクトに伝わってくる。こういうのを真の快演と言うのだろう。[収録曲] *以下は、筆者所有の盤(広く普及しているCD盤)の収録曲。2009年の国内盤紙ジャケ(2枚組)では、LPからCD化された時に削られた曲(Life Without You)が復活し、さらにボーナストラックが追加されている模様(筆者は未聴)。1. Say What2. Ain't Gone 'N' Give Up On Love3. Pride And Joy4. Mary Had A Little Lamb5. Superstition6. I'm Leaving You (Commit A Crime)7. Cold Shot8. Willie The Wimp9. Look At Little Sister10. Texas Flood11. Voodoo Chile (Slight Return)12. Love Struck Baby13. Change It1986年リリース。 Bungee Price CD20% OFF 音楽Stevie Ray Vaughan スティービーレイボーン / Live Alive 【CD】 下記ランキング(3サイト)に参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓ ↓
2011年12月17日
コメント(0)
-

ミハーレス 『スウィング・エン・トゥ・イディオマ(Swing en tu idioma)』
一風変わったヴォーカル作 ポップ界で成功したシンガーの中には、ジャズ・ヴォーカル・アルバム制作の企画を志向する人も結構いる。それがうまくいくかどうかは、ふつうはシンガー本人のバックグラウンド(ジャズ・ヴォーカルがその人の音楽ルーツとして根づいているかどうか)次第という場合が多い。要するに、ジャズ・ヴォーカルに親しんできたポップ歌手が一度それをやってみたいというケース(この場合はよい作品になることが多い)、それほど親しみはないのだけれどちょっとカッコよくジャズ・ヴォーカルを決めてみたい場合(失敗作になる可能性が高い)のいずれかである。 メキシコを代表する男性ポップ・シンガーの一人、ミハーレス(Mijares)の『スウィング・エン・トゥ・イディオマ(スペイン語でスウィング)』は、そのどちらでもない一風変わったアルバムである。別項でも紹介したように、ミハーレスは下積みを重ねてメキシコひいてはラテン・ポップ界で成功した男性シンガーである。彼の第18作となるのが2007年発表の本作である。何も知らない人が聴いたら、本作は上の例では後者だと思われるかもしれない。実際、ミハーレスの声はこういうアレンジや作風にあまり向いているというふうな感じは個人的にはしない。 けれども、この作品が一風変わっているというのは、料理する素材の珍しさである。実は、本盤で取り上げられている曲は、いずれもスペイン語ロックの有名曲なのである。1.「ノ・ボイ・エン・トレン」はアルゼンチンのロック・シーンを牽引してきたチャーリー・ガルシア(Charly Garc?a)の曲。2.「ADO(アー・デー・オー)」と9.「哀しき愛の歌(トリステ・カンシオン)」はメキシコの大御所ロック・バンド、EL TRIの有名曲である。スペイン語ロックの古典ばかりか90年代以降の曲も取り上げていて、カイファネス(Caifanes)の6.「ノ・デヘス・ケ」、マナ(Man?)の7.「ラジャンド・エル・ソル」、カフェ・タクーバの10.「マリーア」なども取り上げている。アルバムを締めくくる11.「クアンド・セアス・グランデ」はアルゼンチン人ロッカー、ミゲル・マテオスの以前紹介したもの(「孤独のアメリカ」)と同時期の曲。 つまりは、管楽器を入れてあっさりとジャズ・ヴォーカル風アルバムを作っているのかと言えばそうではない。(少なくともスペイン語圏では)よく知られたロックチューンのオンパレードでこれをやっているという意欲作なのである。原曲を知っている聴き手にしてみれば、これがまたなかなか新鮮で、アレンジが凝っているわけではないが、これだけいろんなアーティストのロック曲を一色に染めるアレンジはなかなか面白い。 まあ、ミハーレスの他のアルバムとは明らかに作風が違うので、他のアルバムを聴いたことある人向けではあると思う。あるいはラテン系ロックが好きな人で一度試してみたい人にも向いているかもしれない。[収録曲]1. No voy en tren2. ADO3. Persiana americana4. Qui?n me ha robado el mes de abril5. Lamento boliviano6. No dejes que7. Rayando el sol8. Lucha de gigantes9. Triste canci?n10. Mar?a11. Cuando seas grande2007年リリース。 下記3つのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、ひとつでも“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓ ↓
2011年12月15日
コメント(0)
-

イングヴェイ・マルムスティーン 『トリロジー(Trilogy)』
初期三部作を締めくくる名盤 イングヴェイ・マルムスティーンはスウェーデン出身のHR/HM系ギタリスト。ネオ・クラシカル・メタルと言われることからもわかるように、クラシック音楽の要素を持ち込み、速弾きのギター・ヒーローとして知られる。1983年に故郷ストックホルムからロサンゼルスへと渡り、スティーラー、アルカトラスといったバンドのメンバーとして活躍。アルカトラスで名声を得た後、1984年にソロ・デビュー。その後は1985年、1986年とコンスタントにアルバムを発表していった。本作『トリロジー(Trilogy)』は、その原題(トリロジーは“三部作”の意味)が示すように、デビューからの最初の三枚(三部作)の締めくくりとなる作品である。 前2作との違いは、大きく二つある。一つはヴォーカリストの交代。マーク・ボールズというヴォーカリストが本作で新加入しているが、この人は高音に伸びがあり、これらの曲のヴォーカルをこなすのに向いた声の持ち主である。とはいっても、イングヴェイの作品の場合、ヴォーカルの占める比重は決して高くないことが多く、例えば、デビュー作(1984年の『ライジング・フォース』)においても、全8曲中2曲だけがヴォーカル入りであった。 本作のもう一つの特徴は、前作の“ネオ・クラシカル・メタル”路線上にありながらも、前2作と比べて親しみやすいメロディが増えた点だろう。言い換えると、仰々しい部分が押さえられ、キャッチーな部分が増えたということになる。もちろん、セールス狙いな安直な商業化をしたというわけではなく、よりファン層が広がりそうな工夫というレベルでのわかりやすさ、ストレートさが増したという感じだろうか。 全体として粒が揃っていて、アルバム全体のコンセプトも統一感がある。そんな中でも敢えて筆者の好みを挙げておこうと思う。1.「ユー・ドント・リメンバー(You Don’t Remember, I’ll Never Forget)」は、余裕を持って構えたオープニング・ナンバーといった風情で、個人的には、急に思い出して聴きたくなる曲の一つである。そこからテンポを上げて人気曲の2.「ライアー」に流れていくあたりは、このアルバムらしさをよく表していると思う。インスト曲は2曲含まれている。4.「クライング」は、勢いづいたところで一息リラックスな感じで配されていて効果的だと思う。圧巻はもう一つのインスト曲、9.「トリロジー組曲 作品5(Trilogy Suite Op. 5)」。7分余りの大作だが、いい意味で大仰しさがこの曲には体現されていて、デビュー盤収録の「ブラック・スター」、「ファー・ビヨンド・ザ・サン」、あるいは「イカルスの夢 組曲作品4」などと並んで、イングヴェイを代表する(そしてライヴでも定番の)インスト・ナンバーである。 ついでながら、イングヴェイ作品のジャケットっていまいちな写真のものもわりとあるように思う。でも、本作の場合はなかなか個性的で、個人的には気に入っている。三頭のドラゴンが空から襲いかかってきて、これに対してギターを手にしたイングヴェイ戦っているという絵画タッチのジャケット。趣味が分かれるところかもしれないが、筆者としては結構好きなのだけれど。[収録曲]1. You Don't Remember, I'll Never Forget2. Liar3. Queen in Love4. Crying5. Fury6. Fire7. Magic Mirror8. Dark Ages9. Trilogy Suite Op:51986年リリース。 【CD】トリロジー/イングヴェイ・マルムスティーン [UICY-91907] イングベイ・マルムステイーン 下記ランキング(3サイト)に参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓ ↓
2011年12月12日
コメント(0)
-

ヒューイ・ルイス・アンド・ザ・ニュース 『FORE!』
80年代を象徴するロック・アルバム ヒューイ・ルイス(Huey Lewis)は、1950年生まれの米国のロック・ミュージシャン。長い下積みを経て、1980年代にカラっとした明るいアメリカン・ロック・サウンドで一世を風靡した。1982年のセカンド・アルバム(『ベイエリアの風』)収録曲から人気に火がつき始め、翌83年にはサード・アルバム(『SPORTS』)が全米1位を獲得。1985年には、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の曲を手掛け(映画にも脇役で出演)、シングル曲「パワー・オブ・ラヴ」が大ヒットし、さらには豪華アーティストの共演となった“ウィ―・アー・ザ・ワールド”にも参加してブリッジ部分のヴォーカルを担当した。 そんな人気絶頂の中、1986年発表の第4作がこの『FORE!』であった。全11曲(日本盤、欧州盤)が収録されているが、米国でのリリースでは10曲で、日欧では8曲目に前年に全米1位となった大ヒット曲「パワー・オブ・ラヴ」が追加されている。残る10曲のうち、シングル・カットは6曲なされ、この当時多かったシングル連発の典型的なアルバムなわけだ。ともあれ、うち2曲(2.「スタック・ウィズ・ユー」と1.「ジェイコブズ・ラダー」)がビルボードで全米No.1、これらを含めて計5曲の全米トップ10ヒット曲を出した(残る3曲は、5.「ヒップ・トゥ・ビー・スクエア」、6.「アイ・ノウ・ホワット・アイ・ライク」、4.「すべてを君に」)。 全体的に、そしてシングル曲は概ね典型的に、明るいノリのアメリカン・ロックを聴かせてくれる。全体の演奏能力の高さもさることながら、本人が茶目っ気たっぷりに語るように、最後に聴き手に訴えかけるのはやはりヒューイのハスキーがかったヴォーカルである。80年代アメリカの浮かれ具合―よく言えばそれは“活気があった”ということになる―がよく反映されたヒット・アルバムで、アルバム自体も全米(ビルボード)のみならず、カナダとニュージランドで1位を獲得した。 リアルタイムのヒット時の記憶が強いので、シングル曲としてのイメージが強い曲も多いのだけれど、個人的にベストは2.「スタック・ウィズ・ユー」。ついでオープニング曲の1.「ジェイコブズ・ラダー」、5.「ヒップ・トゥ・ビー・スクエアー」あたりが個人的好みか。日本盤の収録で言えば、米盤にはない8.「パワー・オブ・ラヴ」も捨てがたい(米盤では9.以降が1曲繰り上がって全10曲の収録)。アメリカ社会も暗くなってしまったが、よくも悪くも明るく前を向いていた頃の雰囲気が(おそらく曲や演奏だけでなく、その時代の雰囲気に影響されているのかもしれないけれど)残る好盤。でもいま聴いたらやや能天気に聴こえすぎるのかな。いやはや、音楽だけでも明るくあってもいいと思うのだけれど。[収録曲]1. Jacob's Ladder2. Stuck With You3. Whole Lotta Lovin4. Doin' It All For My Baby5. Hip To Be Square6. I Know What I Like7. I Never Walk Alone8. The Power Of Love9. Forest For The Trees10. Naturally11. Simple As That1986年リリース。 【当店専用ポイント(楽天ポイントの3倍)+メール便送料無料】ヒューイ・ルイス&ニュースHuey Lewis & The News / Fore! (輸入盤CD) (ヒューイ・ルイス&ニュース) 下記3つのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、ひとつでも“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓ ↓
2011年12月10日
コメント(0)
-

エリック・クラプトン 『BLUES(Blues)』
編集盤でもこういうコンセプトの決まったものなら好盤になり得るのかも ベスト盤やコンピレーション(編集)盤というものは、一見、手を出しやすそうに思えるが実に危険を伴うものだと思う。例えば、ローリング・ストーンズはベスト盤から入るべきではないし(『レット・イット・ブリード』の項を参照)、ブルース・スプリングスティーンのベスト盤なども最初に聴くべきではない。早い話、ストーンズにしても、スプリングスティーンにしても、“濃すぎる”のである。アルバムでは押したり引いたり、緩急がついているはずのものが、ひたすら押しまくられることになるからだ。俗な喩えで言うならば、焼肉と餃子と唐揚に寿司が組み合わさって出てきて、次にラーメンを勧められたかと思えば、その後にまたステーキとカレーライスが待っているような感じである。それぞれ食べれば美味でも、これだけ一緒に出されれば食傷という結果に陥るのは当然だ。 無論、編集方針がよかったり、たまたまアーティストの残した楽曲がベスト盤にも向いていたなどの理由から、例外となることが、時にはあり得る(例としては、クリームの項を参照)。しかし、一般論として言えば、ベスト盤というものは、そうした“何でもあり”もしくは“凝縮して詰め込む”という、無神経かつ無謀な編集姿勢のせいで聴きづらいものになってしまうのが通例である。 ところが、上の食べ物の喩えを再び用いるならば、“寿司バイキング”だったり、“シーフード・バイキング”だったりするとどうであろうか。つまり、何でもかんでも詰め込むのではなく、テーマを絞っての編集盤ということである。それは場合によっては意外といいのかもしれない。そう思わせてくれるコンピレーション・アルバムの一つが、エリック・クラプトン(Eric Clapton)の『BLUES』である。 リリースは1999年と比較的新しいものの、音源自体は古い。1970~80年のアルバムや同時期の未発表音源を集めたもので、表題のとおり、ブルース系の曲や演奏を集めたものである。1枚目はスタジオ録音、2枚目はライブ音源を編んだもので合計25曲というボリューム。ただし未発表音源はその4分の1ほどで、大半は発表済みの音源である。なので、よっぽど熱心なファン以外は、わざわざ未発表テイクだけのためだけに2枚組のこのボリュームのものを聴こうとは思わないかもしれない(ただし、発売後初期には未発表のジャム・トラック4曲がボーナス盤として追加されたものもあったので、コアなファンならこういうのを聴きたくなる)。 そうは言っても、この盤については、結構お勧めなのである。70年代の人生紆余曲折の只中のクラプトンにとって、新たなものをひたすら想像するというよりも、既存のブルースをどう吸収して自分の音楽にしていくかという課題の軌跡をまとめた盤と言えなくもない。平たく言ってしまえば、テーマの絞られた編集盤なわけだ。 ちなみに、音源はリリース時点で既発表のものと未発表音源だったものが入り混じっている。未発表トラックは、1枚目(スタジオ録音)では、1.「ビフォア・ユー・アキューズ・ミー(テイク・ア・ルック・アット・ユアセルフ)」(アルバム『バックレス』の未発表アコースティック・ヴァージョン)、7.「アルバータ」(『スローハンド』の未発表トラック)、10.「ミート・ミー(ダウン・アット・ザ・ボトム)」(『461オーシャン・ブールヴァード』の未発表テイク)、15.「ビフォア・ユー・アキューズ・ミー(テイク・ア・ルック・アット・ユアセルフ)」(『バックレス』からの未発表エレクトリック・ヴァージョン)。2枚目(ライブ盤)では、10.「ファーザー・オン・アップ・ザ・ロード」が初出の音源。 細かな注目点を挙げるといろいろあるのだけれど、ここでは以前の記事(『ミー&Mr.ジョンソン』)との絡みで一点だけ触れておきたい。Disc 2にはロバート・ジョンソンの曲が2つ収められている。6.「カインド・ハーティッド・ウーマン」と9.「クロスローズ」である。純粋に“ブルース”という意味では、オリジナルにかなわないのだけれども、これらの曲の解釈としては、クラプトンは優れたセンスを示していた。 全体としては、決して未発表のテイクが多いわけではないので、これ目当てはよほど熱心なファンだけだろう。けれども、ブルース系のクラプトンを楽しみたい人には、十分お勧めできる編集盤だと思う。まあ、“バイキング”なだけに、通して聴いた後は“満腹”になるのはやっぱり確かなのだけれど(笑)。追記: 本作については、1枚ものと2枚ものの2種が存在しているようです。1枚ものはここで紹介したうちのDisc 1 のみ。聴くには長いけど、Disc 2も合わせてこそ、この“バイキング料理”は生きてくるというふうに感じますので、2枚ものの方がお勧めです。[収録曲]~Disc 1 (Studio Blues)~1. Before You Accuse Me (Take a Look at Yourself)2. Mean Old World3. Ain't That Lovin' You4. The Sky Is Crying5. Cryin’6. Have You Ever Loved a Woman7. Alberta8. Early in the Morning9. Give Me Strength10. Meet Me (Down at the Bottom)11. County Jail Blues12. Floating Bridge13. Blow Wind Blow14. To Make Somebody Happy15. Before You Accuse Me (Take a Look at Yourself)~Disc 2 (Live Blues)~1. Stormy Monday2. Worried Life Blues3. Early in the Morning4. Have You Ever Loved a Woman5. Wonderful Tonight6. Kind Hearted Woman7. Double Trouble8. Driftin' Blues9. Crossroads10. Further on up the Road1999年リリース。 Eric Clapton エリッククラプトン / Blues 輸入盤 【CD】 下記ランキング(3サイト)に参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓ ↓
2011年12月08日
コメント(1)
-

INDEX更新
INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。ここ最近の記事を追加しています。 INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ右欄(フリーページ欄)からお入りください。アーティスト別INDEX~ジャズ編へアーティスト別INDEX~ロック・ポップス編へアーティスト別INDEX~ラテン系(ロック・ポップス)編へアーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ下記ランキング(3サイト)に参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでも2つでもありがたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓ にほんブログ村 : 人気ブログランキング: 音楽広場:
2011年12月05日
コメント(2)
-

シカゴ 『シカゴ26~ライヴ・イン・コンサート(Chicago XXVI: Live In Concert)』
コレクターズ・アイテム? はたまた懐メロ? 売り方に問題が… シカゴ(Chicago)は、1969年にデビューしたアメリカのロック・バンド。その前身はデビューのさらに数年前から存在し、イリノイ州シカゴにあるデ・ポール大学の学生バンドであった。“ザ・ビッグ・シング(The Big Thing)”という名だったこのバンドは、デビュー時には“シカゴ・トランジット・オーソリティ(Chicago Transit Authority)”を名乗るも、シカゴ交通局からのクレームでバンド名を“シカゴ(Chicago)”に変更した。 シカゴは当初、ブラス・ロックと呼ばれるジャンルに分けられていたが、70年代後半から政治色を薄め、バラードもヒットさせるようになる。さらに、80年代にはAOR化しラヴ・バラード路線を突っ走った。そんな彼らのキャリアを振り返って見ると、ライヴで鳴らしたバンドでありながら、案外にライヴ盤が少ないことに気がつく。 1999年にリリースされた本盤『シカゴ26~ライヴ・イン・コンサート(Chicago XXVI: Live In Concert)』は、バンドにとってかなり久々のライヴ盤であった。これ以前の正式リリースのライヴ盤としては、第4作(1971年)があったが、作品におおむね通し番号をつけてきた彼らのディスコグラフィーの上では、20枚以上、30年近くの時間が空いたことになる。ちなみに、日欧限定のライヴ盤(1972年、番号入りのシカゴ作品としてはカウントされず)、本作よりも後にリリースのライブ盤(ただしこちらの内容は70年代のライヴ音源)もある。 いずれにせよ、リリース時点では久々のライブ盤で、“シカゴの今”を伝えるアルバムになるはずであった。けれども、セールス面では燦々たる結果に終わった。いくつも理由が考えられるだろうが、主なところを考えてみると、次のような具合だろうか。・80年代以降、ラブバラード中心のAOR系のイメージがついたため、ライブ盤を出したところで聴きたがる客層が少なかった(きれいなバラードであればあるほどスタジオ録音の方がいいと思われがち)。・70年代はライブ、ツアーで鳴らしたバンドであったが、世紀も末のこの段階では、そんなことはもう忘れ去られていた。・ピーター・セテラ(1985年に脱退)色を消そうとした選曲が失敗に終わった(古くからのファンを惹きつけられなかった)。 いずれの理由もさもありなんといった気はするが、要するに売り方が下手だっただけで、作品としての質は悪くなかったように筆者は思う。いや。それどころかこのシカゴというバンドがブラス・ロックと呼ばれるジャンルでトップ・バンドとなり、その後のバラード路線を経てバンドとしての完成度・方向性が定まった成果がちゃんとライブになっている。“コレクター向け”なんて言われたりもするが、シカゴの歩みを振り返る時、結構よくできたアルバムだと思う。まあ、いい製品作っても売れないと会社は倒産するのがいまの資本主義の世界なわけで、売り込み方を間違えるとだめという例の典型だと言われれば、それまでなのかもしれないけど…。[収録曲]1. The Ballet: Make Me Smile/ So Much to Say, So Much to Give / Anxiety's Moment / West Virginia Fantasies / Colour My World/ To Be Free / Now More Than Ever 2. (I've Been) Searchin' So Long3. Mongonucleosis4. Hard Habit To Break5. Call on Me6. Feelin' Stronger Every Day7. Just You 'N' Me8. Beginnings9. Hard to Say I'm Sorry/Get Away10. 25 or 6 to 411. Back to You12. If I Should Ever Lose You13. "(Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher1999年リリース。 下記3つのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、ひとつでも“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓ ↓
2011年12月03日
コメント(0)
-

アート・テイラー 『テイラーズ・ウェイラーズ(Taylor’s Wailers)』
ハードバップ全盛期の、締まりのある名盤 アート・テイラー(Art Taylor)もしくは本名のアーサー・テイラー(Arthur Taylor, より正確にはArthur S. Taylor Jr.)は、米国出身のジャズ・ドラマー。1929年生まれで、1995年に死去している。1940年代末からキャリアを積み重ね、ハードバップの陰の立役者として数多くのセッションでドラムを演奏し続けた。正確な数は知らないが、それこそ何百枚というジャズ・アルバムにおいてドラマーとしてクレジットされている。 そのようなわけで、バド・パウエル、ジョン・コルトレーン、アート・ファーマー、セロニアス・モンク、マイルス・デイヴィスなどと共演し、有名どころのジャズ・アルバムを聴いたことがある人はあちらこちらで彼の演奏を耳にしているわけだけれど、この人自身のリーダー・アルバムはというと、極端に数が少ない。その中で比較的よく知られている盤がこの『テイラーズ・ウェイラーズ(Taylor’s Wailers)』である。 アート・テイラーがリーダー作をあまり残さなかったのは、自分中心の活動にあまり熱心ではなかった(あるいは向いていなかった?)ためで、音楽活動の大半はフリーの演奏者としてあちらこちらに呼ばれては演奏をするというものだった。そんな彼も1度や2度は自己のグループを率いる試みをしている。本盤の“ウェイラーズ”というのが、彼にとって初めての(そして短命に終わった)自身のグループの試みである。アルバム名の『テイラーズ・ウェイラーズ』というのは、“テイラー率いるグループ、ウェイラーズ”ということである。余談ながら、ボブ・マーリーのバンドもウェイラーズであるが、このテイラーのウェイラーズの方が歴史が古く、かつ先に消滅した(ただしテイラーは、亡くなる数年前の1993年、このグループ名を復活させている)。 さて、本盤の真骨頂は何と言っても、“びしっと締まっていること”である。“やっぱジャズはこうじゃなきゃ”と言いたくもなるが、こんなジャズ愛好家にしか通じないであろう言い方をしても始まらない。テレビのバラエティ番組にでも喩えてみたい。 いつからかだろうか、だらだらと垂れ流すようになった民放の番組作り(特にバラエティものの繰り返しの多さや少しのネタで長い放送時間をかせぐ間延びの仕方)に筆者は飽き飽きしているのだが、ある段階まではそうじゃなかった。20年ぐらい前までを思い出すと、大概ふざけていながらも番組の構成には常識とそれなりの締まり(あるいは自制?)があったように思う。よくできた番組だと、その内容が真剣なものかお笑い系なのかに関係なく、どこかにちゃんとした締まりがあったのである。残念ながら、いまは視聴率欲しさか予算をけちっているのか、だらだらしたものになってしまった。アート・テイラーのこのアルバムを聴くと、実に端正でびしっと締まっている。そんなことを考えると、ジャズ界にもだらだらとした垂れ流しはあるわけで、別にテレビ界だけを嘆いても仕方ないのかもしれないけれど(笑)。 さて、本盤の締まり具合というのはどこから来るのか。最大の要因は、メンバーをうまくのせるアート・テイラーのドラミングにあるのは間違いない。つまりは、必要な時にはリズムをキープしながら、ただのキープ係では全くなく、管楽器をはじめとする他のメンバーが締まりのある演奏を披露しやすい状況を作り出している。そして、それに答えたメンバーの豪華さである。以下のパーソネルの一覧にあるように、今となってはジャイアンツたる面々が名を連ねている。[収録曲]1. Batland2. C.T.A.3. Exhibit A4. Cubano Chant5. Off Minor6. Well, You Needn’t[パーソネル・録音]2.以外: Art Taylor (ds), Donald Byrd(tp), Jackie McLean (as), Charlie Rouse (ts), Ray Bryant (p), Wendell Marshall (b)1957年2月25日録音2.: Art Taylor (ds), John Coltrane (ts), Red Garland (p), Paul Chambers (b)1957年3月22日録音 【送料無料】【輸入盤】Taylor's Wailers [ Art Taylor (Arthur) ] 下記ランキング(3サイト)に参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓ ↓
2011年12月01日
コメント(2)
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
-

- 人気歌手ランキング
- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…
- (2025-11-15 04:58:28)
-
-
-

- 好きなアーティストは誰??
- 今日の朝はヒゲダンを聴きました☆&サ…
- (2025-10-26 11:00:38)
-
-
-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン
- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…
- (2025-11-12 00:00:13)
-







