2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2004年03月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
気になるニュースから
今日はちょっとたまったニュースを見ながらあれこれ考えてみよう。「米の地下施設攻撃用「核」、5年後には製造一歩手前に」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040310-00000214-yom-intこれは3月10日のニュースなので、もしかしたらもう上のアドレスに行ってもなくなっているかもしれない。ここでは、「5年後には単なる研究だけでなく、核兵器製造の一歩手前の段階にまで移行する」と報道されている。これは、「テロリストの地下施設攻撃用」だということだ。相手がテロリストだったら、このような残虐な兵器でも使うことをためらわないのだろうか。テロリストは、もっと残虐なことをしているではないかという非難も来そうだが、核兵器以上に残虐な兵器はあるんだろうか。だいたいテロリストを正確に区別することが出来るんだろうか。ビンラディン級の有名人なら誰もが納得するかもしれないけれど、この核兵器を使った相手が、間違いなくテロリストだと証明できるのだろうか。もし、間違って誤爆したらどうなるんだろう。テロリストと子供を間違えてヘリから攻撃するようなアメリカを僕は信用することが出来ない。世界は、いつ、この暴走したアメリカにノーを突きつけられるようになるのだろうか。「<同性結婚>米大統領選の争点化狙うブッシュ氏」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040311-00001058-mai-intこれは、同性結婚に関する続報だが、ブッシュ大統領がこの件を争点にするのは、世論が同性結婚に反対しているからだ。「ペンシルベニア大世論研究センターが2月14日に行った全国調査では、64%が自分の住む州が同性結婚を認めることに反対しており、賛成は30%に過ぎない。民主党支持者でも反対55%だ。大統領の発言は民主党への揺さぶりでもあるのだ。」これは、僕にとっては驚くべきことだ。同性愛者は、結婚を認められないことで、法の下での平等という基本的な権利を侵されている。「同性愛者が結婚にこだわるのは、法的な「差別」があるからだ。比較的理解が進むカリフォルニア州でも、遺族年金の受け取りや夫婦合算の納税申告など、結婚した男女にしか与えられない恩恵が1000以上も残る。全米で38州以上が同性結婚を禁じ、他州発行の結婚証明書を拒否している。」このような差別を、民主国家であるアメリカがなぜ放置しておくのだろう。そして、その放置をどうしてこれだけ多くの人が支持してしまうのだろう。マイノリティである同性愛者の不利益は、不当なものであっても、何ら正そうとしないのだろうか。僕には理解できないこの感情は、宗教的な価値観から生まれているのだろうか。「ハイチ、米海兵隊を標的 前大統領派と対立激化も」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040311-00000147-kyodo-intこれは、ハイチの問題に関する続報だが、ハイチの問題というのは、未だに何が問題なのかがよく分からない。それは軍事クーデターなのか、民衆の蜂起なのか、ハイチ国民はこれを歓迎しているのか。アリスティド大統領は独裁者なのか、民主主義者なのか。次のようなニュースもあったりするのでますます分からなくなる。「TUP速報275号 ラムゼー・クラーク/ハイチ発言 04年3月21日」http://groups.yahoo.co.jp/group/TUP-Bulletin/message/285この記事では、「民主的に選出されたアリスティド大統領」というような書き方をしている。冒頭では次のような報告をしている。「ブッシュ政権はこの3年間、 ジャン=ベルトラン・アリスティド大統領をその地位から追い出すことに、腐心してきた。一方的禁輸措置を実施し、西半球で最も貧しい国への人道援助を一切行なってこなかった。アリスティド大統領支援に対しては妨害にこれ努めつつ、反大統領勢力を後押ししてきた。大統領を引き摺り下ろすために、容赦ない宣伝を繰り広げてきた。ハイチの憲法と法律に違反してでも選挙を行なえとの要求に、支持を与えてきた。」これが事実なら、ハイチでの事件は、不当な軍事クーデターであって、民主主義の破壊である。これもまたアメリカが行っていることだ。このアメリカが、イラクで民主主義を実現すると言うことに、盗人猛々しいという感じを抱いて仕方がない。僕は、このTUP速報をかなり前からメールで受け取っていて、この内容に深い信頼を置いている。だから、ここで報告されていることが事実なんだろうと受け取っている。これが事実だったら、アメリカが、ハイチでの武装勢力が権力を奪った時点でやっと動きだしたということの意味が納得できるからだ。アメリカ自身が、アリスティド大統領の勢力に対して攻撃するわけにはいかなかっただろうから、アリスティド大統領がいなくなって、武装勢力側が権力を握った時点で乗り込んでくると言うことに納得がいくからだ。納得がいくというのは、そういうふうに考えた方が前後のつじつまが合うと言うことであって、それが正しいと思っているわけではない。これは、この報告が語っているように、全く不当なことなのだと思う。民主主義の破壊だ。この事実は世界中が知らなければならない事実ではないかと思う。「<夫婦別姓>今国会提出は困難に 推進派、厳しい立場」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040312-00000055-mai-polこの問題は、アメリカにおける同性結婚の問題と構造的に同じ問題が、日本にもあるのだと言うことを知らせてくれるような感じがする問題だ。夫婦別姓というのは、そうしたい人にそれを認めろという要求だ。そうしたくない人に夫婦別姓を強要しようというものではない。希望する人が出来るようにするのは、当然の権利ではないかと思うのだが、人がそうすることに我慢できないと言う人がたくさんいるのだろう。自分ではなく、人が同性結婚すると言うことに耐えられない人がアメリカにたくさんいるのとよく似ている感じがする。「<テレビ朝日>「Nステ」障害者施設報道に抗議相次ぐ」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040313-00001053-mai-sociちょっと前のダイオキシン報道に続いて、「Nステ」では、また勇み足のような報道があったのかなと言う感じだ。宮台氏は、今週のマル激オン・トーク・デマンドで、テレビ朝日というのは裏を取る能力に欠けているという指摘をしていた。そこがあるから、このような取材対象から抗議を受けるようなニュースを作ってしまうことがあるのだろうか。テレビ朝日といえば、朝日新聞系列の局なのだから、報道においては、朝日新聞のバックアップがあって作っているのかと思ったら、そういう体制ではないようだ。上の報道は、僕もテレビで見ていてショックを受けたものだ。これがもし本当だったとしたら、いろいろな意味で問題が多いと思って、センセーショナルな感じがした。しかし、この報道を見てみると、センセーショナルな演出がしたくて勇み足をしたのかという感じも受けたりする。テレビ朝日の報道というのは、かなり信用を失ったのではないかと思う。「イラク攻撃開始から1年、米閣僚があらためて正当性主張」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040315-00000553-reu-int報道によれば、正当性の主張は次のようなものだ。「フセイン元大統領がもたらした喫緊の脅威は朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)よりも深刻なものだった」「私は正しいことだと信じており、それをやり遂げたことを嬉しく思っている」「イラクは喫緊の脅威だったと信じ続けている」「われわれがより安全になっているのは、イラクが大量破壊兵器疑惑の国にならないというのが理由だ」「集団墓地にこれ以上人が入ることはない。われわれが、独裁的指導者に抑圧されていたこの国(イラク)に民主主義への道筋を付けた」これらは確かに「主張」には違いないが、それが正しいことは全く証明されていない。僕は、むしろ疑問を抱いているんだけれど、主張するだけでアメリカ人はそれを受け入れてしまうんだろうか。証明するまでは疑問を持って欲しいんだけれどなと思う。「<スペイン>イラク駐留軍の撤退を表明 次期首相」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040316-00000063-mai-intここで報じられているスペインの次期首相の言葉は、論理的であり共感できるものだ。「書記長はイラク戦争に言及し「多くの惨禍をもたらし、占領がそれに輪をかけた。スペインにも多くの結果をもたらした。一つが選挙結果で、もう一つがスペイン軍の撤退だ」と米英主導のイラク統治に一線を画する姿勢を示した。 同時に「ブッシュ大統領とブレア英首相は多くの過ちを犯した。虚偽の事実で物事を始めてはいけない。彼らは反省すべきだ」とも語り、米英首脳を厳しく指弾した。」「国際社会が一致してテロと戦う必要=攻撃予告で官房長官」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040318-00000922-reu-intここで福田官房長官は、「一般論として暴力に屈すれば社会を乱す」と語っているが、どのような状態を指して「暴力に屈する」と判断するかがちゃんと定義されていないので、これは「論」とも言えないだろう。あくまでも武力で鎮圧しなければ、それ以外の対応は「暴力に屈する」と判断するのだろうか。テロリストと呼んでいる側の語る声に耳を傾けることは「暴力に屈する」ことになるという判断だろうか。テロリストと呼んでいる側は、もしかしたらレジスタンスかもしれないとは少しも考えないのだろうか。「国際社会の支援が重要=イラク開戦1年で官房長官」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040319-00000036-reu-intここでは、福田官房長官の次のような言葉を批判しよう。「国連安保理決議に基づいて武力行使された結果、イラク人が圧制から解放された」これは、認識の間違いではないだろうか。国連安保理は、イラク攻撃には反対していた。アメリカが単独で行おうとしたことに追随する国が参加したのではないか。武力行使と圧政からの解放というのは、時間的な因果関係を見ることが出来るかもしれないが、論理的な因果関係があるとは思えない。だいたい今の状況が本当に「解放」なのだろうか。「道半ばで、まだ先が見えていない状況の中で、テロの脅迫など困難が次々に起こっている」としたうえで、「(だからといって)テロに屈してイラクから撤退することになれば、イラクは無政府状態となって大混乱になる」イラクは、今の状況でも十分無政府状態で混乱しているのではないだろうか。撤退しても、同じように混乱するだろう。いずれにしても混乱するのは確かだが、その混乱をもたらしたのは、アメリカによる不当な攻撃の結果なのではないだろうか。これは、時間的にも論理的にも因果関係がありそうな感じがする。「イラク国民がこの1年間で1万人死亡したと伝えられているが、との質問に対しては、「不幸なことだとは思うが、では何もしなくてよかったのか。他に選択肢があったのか」として、旧フセイン政権が続いていればさらに死者が増えていた可能性がある、との考えを述べた。」他に選択肢がなかったとしても、選択した結果によって民間人が大量に死んだのであれば、そのことに対して責任が生ずると思うのだが、他に選択肢がなければ、その責任も消えてなくなるという論理なのだろうか。死んだイラクの民間人に対して補償をするのが、その責任の取り方なのではないか。「一方、イラク開戦の大義となった大量破壊兵器が1年経った現時点でも明らかになっていないが、国連でもイラクが大量破壊兵器を保有していると報告されていたので、現在でも存在すると思っているという。また、今後、「(大量破壊兵器が)見つかる可能性はまだある。ないわけない」と語った。」可能性だけを言うのであれば、すべての場所を探しているのではないから、探していない場所が残っている限り可能性は存在する。しかし、可能性があるということと、それが実際にあるということとは同じことではない。状況としては、「ない」という結論がほぼ出てきたというところではないかと僕は感じる。長くなったので、2つは掲示板の方にうつそう。
2004.03.31
コメント(4)
-
文藝春秋社について
今度の文春の出版差し止めの問題に関して、僕が、表現の自由を守るべきだと素直に言えないのは、文藝春秋社という会社に対するこだわりがあるからだ。吉原公一郎さんというジャーナリストが書いた「週刊文春と内閣調査室」(晩聲社)という本には「御用ジャーナリズムの体質と背景」というサブタイトルが付いている。文藝春秋社の歴史というのは、常に体制側から、むしろ言論を抑圧するような歴史があったのではないだろうか。その文春を守るために言論の自由を主張するのは、何か違和感を感じて仕方がない。吉原さんの本は、1977年の発行だから、かなり古い感じはするけれど、ここで描かれている文春は今ではすっかり変わっているんだろうか。次のような記述がある。「内閣調査室の文書は次のような言葉で閉じられている。「「赤旗」が拡大を続ける限り、日本共産党宮本体制は安泰である。しかし、いったん、「赤旗」が急激に減少を始めるようなことになれば、宮本体制は崩れる。もし、多数の赤旗読者が一時に購読を中断するようなことにでもなれば、今日の共産党は崩壊してしまう。宮本体制下の共産党の命運は、「赤旗」とともにあることだけは確かである。」この文書は最後のこの数行のために書かれたと見ても過言ではないし、「諸君!」と「週刊文春」の記事もまた、この趣旨に貫かれていた。この文書の結論もそうであるが、先に引用した内閣調査室の「極秘文書」が書いているように、政府機関の存在理由が共産党に対する破壊工作にあるというのは、政党結社の自由を保障する憲法に対する明らかな挑戦以外の何ものでもない。そして、この内閣調査室下請け期間が印刷した文書を、引用の表示なしに使用した「週刊文春」の場合は、言論の自由の問題も含めて、「なぜ書くか」という問題について、まさに自殺行為に等しい形を提示したと言えよう。」吉原さんのこの本は、内閣調査室の文書と文春の文書が全く同じであり、ほとんど同一と言ってもいいということを証明するために書かれている。内閣調査室の共産党に対する破壊工作という、政党結社の自由を破壊するための活動に加担しているのが文春だ。このようなものを書くことも「言論の自由」の範疇として認めなければならないのだろうか。もちろん、これを法的に規制するとなれば、言論の自由を侵すことになるだろうが、このようなものを書くというのは、言論の自由を標榜するものなら、書かないのが節操というものではないだろうか。書いた場合には、当然批判されてしかるべきではないだろうか。文春が書いた田中真紀子氏の長女の記事は、批判されてしかるべきもので、本来ならば健全なジャーナリズムの自浄作用として自然淘汰されるべきものだ。法律によって規制されるものではなく、言論の自由を守るために、節度ある記事が書かれねばならないのだと思う。それが、自浄作用がないために権力にスキをつかれるのではないかという気がしてならない。文春の記事は、下品なものではなく、むしろつまらないと言った方がいいものだ。田中真紀子氏という政治家を攻撃するために、その長女を利用してプライバシーを侵害しているという記事だ。これは、文春側の方が、その意図が下品なものであり、姑息な手段を用いているのではないか。吉原さんが書いているものと構造的にはやや違いがあるものの、やはりこれも言論の自殺行為ではないのだろうか。週刊文春ではないが、月刊誌の文藝春秋は、雑誌で批判した日本共産党に対して、その反論権を認めないという行為にもでている。これは言論の自由を否定する行為ではないだろうか。批判するのが言論の自由であるならば、それに対して反批判を受けるのも言論の自由を守ることだろう。2002年11月17日(日)「しんぶん赤旗」によれば、次のような記事が載せられている。「拉致問題での日本共産党の反論掲載を拒否『文芸春秋』編集長に抗議文」http://www.jcp.or.jp/akahata/aik/2002-11-17/02_0101.html言論の自由を守れと叫ぶのであれば、自らが模範を示さなければ説得力がないのではないだろうか。言論の自由を破壊するような行為をしてきたところが、言論の自由を守れということを誰が信用するだろうか。このような主張をしていると、文春の側に非があるのだから、裁判所の措置も仕方がないと主張しているように見えるかもしれない。それは僕の本意ではないので、可能な限り裁判所の側の判断も批判することにしよう。一般論として、表現の自由の価値が重要であるということは、すでにいくつも語られているのでこれ以上付け加えることもないだろう。僕は、一般論として言論の自由を守らなければならないから、この文春に対する措置が間違っているのだと単純に考えることは出来ない。これは、言論の自由が大事だからというよりも、文春の側の非に対して、出版差し止めという措置は、あまりにも重い罰でありすぎるので、今後濫用される恐れがあるから、そのバランスという面から見て間違っているのだという批判をもっと強く打ち出さなければならないと思っている。裁判所としては、昨日の日記にも書いたとおり、柳田さんが語っていたように、「書かれた側に対し、今後訴訟によってプライバシー侵害の実態を具体的に明らかにして、損害の程度と名誉回復の方法を審理してもらうように助言する」べきだっただろうと思っている。それでもなおかつ田中氏の長女の方が、出版差し止めを要求するなら、それは出来ないという判断をすべきだっただろうと思う。プライバシーの侵害はあるから、それで損害賠償という方向なら法的な措置がとれるが、出版差し止めという判断をすることは出来ないと答えるべきだっただろうと思う。裁判所の判断に対しては、田中真紀子氏の力が大きく働いているというような憶測もあるが、これはその証拠がはっきりとしない限り考えに入れるのは間違いだろう。判断の間違いの責任は、あくまでも裁判官にあると僕は思う。田中氏をバッシングする材料にするのは、今の段階では出来ないのではないか。僕は、もう一つ別の憶測の方を想像してしまう。あの記事にはプライバシーの侵害があるので、文春の側に落ち度があるのは確かである。その落ち度があるにもかかわらず、文春はそれを認めず、あくまでも正当性を主張している。これを逆手に取るというか、表現に対するある種の規制をしたいということを実現するチャンスととらえたかもしれないという憶測が浮かんできた。それは、保守的な層にとっては、自由は守らなければならないものというよりも、秩序を破壊する無節操なものというイメージがあると思われるからだ。無制限の自由を許していたら社会は悪い方へ向かってしまうというイメージが保守層にはあるだろうと思う。無制限の自由を許した結果として文春の記事があるという宣伝を裁判所の側はしたいと思ったのではないかと憶測してみた。だから、文春の側が自分の非を認めて引っ込んでしまえば、裁判所は何も出来なかったのだが、うまい具合に文春の側も強行に自己主張してきたので、確信犯的に出版差し止めをいう判断を出した、と憶測することも出来るのではないだろうか。これは憶測なので、全然見当違いのものかもしれない。裁判所は、単に考えが浅くて判断を間違えただけなのかもしれない。しかし、この憶測に少しでも真実味があれば、現実はかなり恐い方向へ進んでいるなと思ってしまう。僕の憶測の考え方は、無節操な自由は秩序を破壊するという、道徳的な面から自由を規制することを意図するというものだ。道徳を基礎にした規制というのは、意外と説得力を持ってしまうところが恐い。自由が本当に失われる可能性としては、弾圧というよりも、道徳によって法的な規制をするところから自由がなくなることの方が、影響が大きいのではないだろうか。弾圧ならば、それに反発する人も多い。しかし、道徳的なものは、受け入れる人の方が多くなってしまいそうな気もする。言論による自己主張の強い人は、だいたいが反発をする人が多いだろうが、果たして世論はどっちの方を向いているのだろうか。声をあげない多くの人々は、道徳的な人だろうか、それとも反発を感じる人なのだろうか。ヤフーでこの問題に関して検索をしたら次のようなものが引っかかってきた。「裁判官の2つの英断 発明対価とプライバシー権 - 裁判員制度では現行の三審制度の欠陥は補えない-」http://www.geocities.jp/seikatushahoni/new040319.htm「東京地裁の「週刊文春」出版差し止め妥当の判断に拍手! - 営利のためにプライバシーを食い物する全てのマスコミは自己反省を -」http://www.geocities.jp/seikatushahoni/new040320.htm「週刊文春の差し止め問題。あなたは、田中真紀子の長女の離婚に興味がありますか?」http://ch.kitaguni.tv/u/3462/%a5%e1%a5%c7%a5%a3%a5%a2/0000062867.htmlいずれも、道徳的な側面から文春批判をしているように僕には感じた。僕は、道徳的な批判はあってもいいと思うが、それはあくまでも道徳的なものにとどめるべきで、法律によらない自己規制の範囲で解決すべきだと思う。道徳的な面を規制するために法律に頼るのは危険が大きすぎる。しかし、道徳を重視する人は、「出版差し止め妥当」と判断してしまうかもしれない。果たして上のような意見は、世論の多数派になる可能性があるだろうか。文春を批判することなく、一般論としての言論の自由によって、結果的に文春を擁護するような論理になってしまうと、道徳的な反発を感じる人が増えたりしないだろうか。僕は、それを恐れる。それが、僕が文春批判にこだわる最大の理由だろうか。
2004.03.30
コメント(2)
-
「プライバシーの侵害」と「出版差し止め」とのバランス
さて、昨日の日記に書いた2の問題に対する僕の判断を考えてみたい。これに対しては、この問題の記事を読む前に、宮台氏の判断である、「この程度のぬるい記事で出版差し止めなどという判断がでるのはとんでもない(間違いだ)」というような判断が正しいのではないかと思っていた。記事を読んでみて、改めて考えてみると、本当にこの記事は「ぬるい」という形容がぴったりだと思う。この記事は「ぬるい」記事だ。とんでもなく常識はずれの私生活が暴かれているわけではない。よくあるようなもので、だからこそこれを読んで、この程度のものは自分ならそれほど気にならないという人が多いのだろう。しかし、プライバシーというのは、それを暴露された人間がどう感じるかが大事なことなので、自分にとっては平気だからこれが暴露されても仕方がないというような論理は成り立たない。このようにぬるい記事で出版差し止めがされるようなら、どんな記事でも差し止めがされてしまうという危惧を抱くのはもっともだと思う。だからこそ報道にかかわる人間たちから大きな反対の声が挙がるのだと思う。この部分の意見で考えさせられたものが、文春の今春号の中でいくつかあった。まずは次の引用を基に考えたことを記しておこう。柳田邦男氏(ノンフィクション作家)「だが、事前の販売差し止めとなると、問題は全く異質だ。繰り返しになるが、今回のような事前の販売差し止めは、国家による検閲の日常化に道を開くものであり、国家による言論と言論機関への介入であり、民主主義の否定である。今回裁判所が採るべきだった対応は、書かれた側に対し、今後訴訟によってプライバシー侵害の実態を具体的に明らかにして、損害の程度と名誉回復の方法を審理してもらうように助言することではなかったかと、私は思う。」--僕もそう思う。裁判官はそう思わなかったのだろうか。ここら辺の事実を知りたいものだ。裁判官が、全くそのようなことを考えなかったとしたら、裁判官の責任は重いと言える。しかし、裁判官がそのように助言したにもかかわらず和解の方向へ行かなかったとしたら、裁判官としては、何らかの結論を出さざるを得なくなっただろう。ここら辺は事実が分からないので場合分けをして想像してみよう。基本的に、この程度のぬるい記事で出版差し止めを判断したのは間違いだという前提で考える。1 裁判官は、上のような助言をする方向を全く考えなかった。 この場合は、出版差し止めという判断の間違いは裁判官に帰すると思う。2 裁判官は助言をしたにもかかわらず、文春の側がそれを受け入れなかった。 文春はプライバシーの侵害がないという主張であるから、侵害があるという裁判所の判断とは対立する。この場合は、あくまでもプライバシーの侵害を通そうとするものに対して、最後の手段としてやむを得ず出版差し止めの判断を下したとも考えられる。その判断は間違いである可能性があるが、その責任の一端は文春の側も負わなければならないのではないか。3 助言を文春の側は受け入れたが、長女の側は受け入れなかった。 この場合も、裁判所は何らかの判断を出さなければならない。これは、裁判所の判断であるから、判断の間違いはやはり裁判所が負うべきもので、その責任は裁判官にある。長女の側が助言を受け入れないのは、長女側の権利の一つであるから、それ自体には責任はないと思う。判断の間違いは裁判官のものだ。4 助言を文春の側が受け入れ、長女の側も受け入れた。 最後に残った場合分けのケースはこれだけだが、この場合は、なんの問題も起こらず、長女の側が受けた損害の程度に応じて、文春がどの程度の賠償をするかという話になるだけだ。実際にはこの道は取られなかったので、可能性としてはあったが、現実には選択されなかったという場合だと思う。現実に起こった可能性としては、1から3までのケースではないかと思うが、事実はいったいどうなっていたのだろうか。裁判所は、柳田氏の言うような助言を全くしていないのだろうか。どのようなやりとりがされたかというのは、公表してはいけない事実なのだろうか。判断の間違いの責任は、もちろん裁判所に一番重いものがあるのだが、2のケースなら文春にも責任が生ずると僕は思う。果たして、文春にはなんの責任もないのだろうか。出版差し止めを招いたのは、「自業自得」という面はないのだろうか。その他考えさせられた意見は次のようなものだ。筑紫哲也氏(キャスター)「プライバシーは尊重されねばならないが、人によっては不快、低俗と思われるような表現や言論を含めて許容される幅がないと、その「自由」は保たれないものなのだ。」--現実は、この反対になっているように僕は感じる。世の中の人からバッシングを受ける人のプライバシーは全然尊重されていない。おもしろおかしく笑いものにするためにプライバシーが暴露されている。いじめの構造によく似ているものを感じる。逆に、不快・低俗なものは、それが直接人を傷つけるものではないのにやり玉に挙げられて抹殺されているように感じる。それが、いきなり予告なしに、見たくない人の目の前にさらされれば問題だが、それに対してある種のマニアのような人間だけが楽しむために限定されているものも、低俗を理由に抹殺される傾向にあるように感じる。「自由」が保たれなくなっているのではないだろうか。須藤義雄氏(元田中真紀子秘書)「また今回の裁判所の判断は、田中家の娘が訴えてきたということが影響しているのかなと思います。真紀子の影がバックに見え隠れして、裁判官も心理的に影響があったと思いますよ。そうした影響を与えるだけでも、「私人」ではないと思うんですけど。」--これは、「思う」という言葉で語られているように、すべては憶測である。根拠となる事実は語られていない。事実がないということは、論理としては弱いということだ。思ったことが現実に存在するとは限らないから。思ったことがすべて現実だとするのは観念論的妄想である。室井佑月氏(作家)「家族のことを書かれて、不愉快な思いをした有名人はいっぱいいます。それでも、出版差し止めまでは出来なくて、名誉毀損の裁判で争うのが精一杯。出版差し止めなんて、田中真紀子さんのお嬢さんだから出来たのね。」--これも根拠となる事実の記述がない。憶測で語っているのだろうか。もし憶測で語っているのなら、誹謗中傷と言えるのではないだろうか。判断の誤りは裁判官に帰するものだと思うので、批判するなら裁判官を批判しなければならない。田中氏の長女の側が、強権的に何らかの行為をしたという事実があって初めて、田中氏の長女の側を批判することができるのだと思う。筒井康隆氏(作家)「実際、「週刊文春」の問題の記事を読んでみても、長女に関しては単に事実が述べられているだけで、それは彼女が何らの「重大な精神的衝撃を受ける恐れがある」ようなものではなく、悪く書かれているのは母親の真紀子氏の方なのであり、今回の申し立てが真紀子氏主導のもとに行われたことは明白だ。」--これも根拠となる事実の提示がない。悪く書かれているのが真紀子氏の方だから、それに対して動くのは、真紀子氏の方だという思い込みによって書かれているように感じる。なぜ事実の提示をせずに、このように断定的な判断を下すのだろうか。作家は、文学的な文章を書くことは得意だが、論理的な文章を書くのは苦手なのだろうか。藤本義一氏(作家)「結局の問題は、裁判官になってくると思いますよ。裁判官に向かって、文春側が報道の自由、表現の自由というのはどういう根拠に則って、というのを示さなければなりません。といっても、報道の自由というには今回の記事は次元が低すぎますな。大会社の社長のプライベートな問題を、毎回載せたりしないでしょう? だから、表現の自由だとか報道の自由だとか観念的なことを表に出すことによって不利になるんですよ。」これは、論理としてのつながりは難しい感じがするけれど、「観念的なことを表に出すことによって不利になる」という状況は、感情的なものとして理解できそうな気がする。「こんな程度のもので表現の自由なんて高尚なことをいうな」という感情は、論理としては疑問を感じるが、感情としてはあり得るかもしれないという感じはする。もちろん、感情に従って判断したとすれば、それは間違いだと思うが。飯室勝彦氏(中京大教授)「問題の記事をほめる気はないし、立派な仕事だとも思いません。しかし、立派な記事でないから許されないということになれば、これは恐ろしい。」--僕も、「立派な記事でないから許されないということになれば」やはり恐ろしいと思う。しかし、この記事の場合は、立派でないから許されないという判断だったのだろうか。プライバシーの侵害だったから許されなかったのではないか。そのプライバシーの侵害の重さと、出版差し止めの重さを秤にかけて、バランスがとれないという点に批判が成されているのではないだろうか。これは論点のすり替えのような気がするな。これは間違った批判だと思う。この批判では、表現の自由を守ることが出来ない、弱い批判だと思う。ここに続く次の部分を読むと、文春擁護の論理のすり替えをしているようにしか見えない。「絶対守らなければいけない大事な言語表現しか守られない社会では、やがてその部分さえ守られなくなる。だから外側の中間領域を、きちんと守らなければいけないのです。」--だから文春を守らなければならないんです、と続くのではないかという感じがする。一般論の正しさで文春を擁護するというこの論理のすり替えこそ、表現の自由を殺してしまうことにつながるのではないだろうか。正しい批判をしなければならないと思う。次の一文も文春擁護にしか見えない。「表現や報道の自由が損なわれれば不利益を被るはずの市民が権力による規制に賛成する現状の危険さを、心して受け止めなければならない。」--規制に賛成したくなる市民感情を生み出している、メディアの報道被害の方の責任は不問にしておいて、一般論としての表現の自由を言い立てるのは、論理のすり替えではないのだろうか。梨本勝氏(芸能レポーター)「内容以前に取材しただけの段階で差し止めなんて行為がまかり通れば、暴挙どころかファッショですよ。」--本当に上のようなことが起こればその通りなのだが、今回はそれに当たるのだろうか。これも論理のすり替えだ。文句を言うのが当然の出来事を言っておいてそれに文句を言っているだけで、今回のケースがそれに相当するという証明は何も成されていない。もし、今回のケースが、上のようなものだと思っているのであれば、認識の間違いであり、単に一般論として語っているのであれば、今回のことを論じる一般論としてはふさわしくない例を出しているだけだ。土本武司氏(帝京大教授)「とまれ、昨今、本件記事などは及びもつかないような露骨な暴露記事が氾濫しているが、個人のプライバシーを傷つけずに表現の自由を保持する方策を模索する必要がある。その際、法の力に依存するのではなく、メディアの自立的な自己規制によって、その目的の達成を図るべきであろう。」--メディアの自浄作用が低くなれば、法的な規制を招くという指摘に僕は感じた。資本主義的な価値である「売れることが一番」というものを、どのように自立的な自己規制と整合性を取っていくかという問題が肝心だと思う。スキャンダラスな内容で売るのではなく、真っ当な方法で売れる方向を見つけなければならないのだ。
2004.03.29
コメント(0)
-
問題の記事を読んだ
昨日知人から問題の文春を見せてもらった。仮処分は、文春の在庫分に下されたもので、書店に配られた分はその対象ではなかったようなので、知人はそれを入手できたらしい。これを読んでみて、次の2点について考えてみたいと思う。 1 記事がプライバシーの侵害に当たるかどうか。 2 「この程度」の記事が出版差し止めに値するかどうか。この両者は関係はあるが、従属関係にあるものではない。相対的に独立している。だから、混乱を避けるために別々に論じることにしよう。結論だけを先に言っておくと、1に対しては「イエス」だと思うが、2に対しては「ノー」だと思う。この記事は、田中さんの長女のプライバシーを侵害していると僕は思うが、「この程度」の記事で出版差し止めの処分まで出すのは行きすぎだと思う。しかし、この処分に関しては、またもう一つ別の問題も感じる。それを記述するだけの余裕があるかどうかが心配だが。今日もまた長い日記になりそうだから。まずプライバシーの考え方が、この記事がプライバシーの侵害に当たるかどうかの判断に大きくかかわってくる。僕の考えは、26日の日記に書いてあるようなものだ。純粋な公人と、純粋な私人という抽象的な存在を想定し、純粋な公人にはプライバシーはないと考える。何を暴露されても、暴露されることには文句を言えない。プライバシーの侵害は原則として成立しない。純粋な私人は、すべてがプライバシーである。従ってそれを公にしたい場合には、必ず本人の同意が必要だ。本人の同意なしにそれを暴露すれば、それはプライバシーの侵害である。この抽象的な前提がまずあって、具体的な存在のプライバシーを考えるときは、そこで公表されている私事が、公的生活にかかわっている部分は、公人のプライバシーとして判断する。暴露されること自体は非難できない。しかし、公表されている私事が、公的生活とは関わりがない部分であると判断した場合は、私人としてのプライバシーであると判断する。本人の同意なしに公表すれば、それはプライバシーの侵害である。問題の記事を読んだ印象だが、それはほとんど田中さんの長女の私事に関する記述である。記事の内容は公表を差し止められたものであるから、引用したり具体的な説明はできないと思うので、自分の結論だけを書き留めるが、ほとんど9割以上は、私人としての娘さんのプライバシーを記述していると僕は感じた。公人としての田中真紀子氏とかかわる部分はごくわずかで、一つは今週号で立花隆氏が取り上げている部分で、もう一つは、田中真紀子氏の夫の直紀氏の選挙に関して真紀子氏がどうしているかを記述した部分だけである。後は、政治的な関わりを書いた部分は全くない。長女の私事に満ちているのがこの記事だ。この私事の公表を長女の側は望まなかった。それでもあえて文春は公表に踏み切ったのだから、同意なしに公表したものとして、これはプライバシーの侵害に当たると僕は思った。文春の側のプライバシーの規定はおそらく僕とは違うのだろうと思う。だから、文春は、この記事をプライバシーの侵害とは判断せずに公表に踏み切ったのだろうと思うが、裁判所はプライバシーの侵害と判断したのだと思う。そして、プライバシーの侵害から守るために「出版差し止め」という判断をしたのだろう。この判断の是非は、また別の問題なので後で論じたいと思う。僕と同じ基準で判断しているかどうかは分からないけれど、この記事をプライバシーの侵害と判断している人が、今週号の文春でどれくらいいるか調べてみよう。筑紫哲也氏「問題となった記事も一読したが、公益性があるとは感じられなかった。」--直接的な言葉でプライバシーの侵害を結論づけていないが、公益性がないということは、プライバシーを暴露することの正当性がないということを意味すると僕は考えた。伊藤洋一氏(住信基礎研究所主席研究員)「今回の文春の記事は、田中真紀子氏長女のプライバシーを侵害している。」--長女は私人であるという理由からこの結論を出している。根拠となる考えは次の通り。「私自身は、「公人」は政治家と公務員、それに立候補者などに限定すべきで、それ以外は「私人」だと考える。」能代昭彦氏(自民党代議士・自民党報道局長)「政治家の娘は、私人であるとは思います。それにしても、プライバシー侵害の程度の問題。今回のケースは、「私人のプライバシーを侵害された」という問題を争うにはなじむと思います。」--「出版差し止め」には反対するが、プライバシーの侵害であるとは判断しているように見える。河上和雄氏(元東京地検特捜部長)「そういう基準で今回の記事を見ると、田中真紀子の娘がどうしたという話を週刊文春が3ページも費やして書くことなのか、という点は疑問に思うが、公共の関心事といえないことはない。内容が悪意に満ちていて虚偽だとも思えない。けれども、プライバシーの侵害にはなるだろうと思う。」--プライバシーの侵害は、ひどいことを書かれたときにのみ成立するのではないということを語っている。悪意もなく、虚偽でもなくてもプライバシーの侵害に当たる場合もあるという考えだと僕は受け取った。五十嵐二葉(弁護士)「プライバシーという観点から見れば、真紀子さんの娘は私人ということで確かにプライバシーには触れるかもしれませんが、それと、読者の知る権利やその他の記事の重要性を秤にかけなくてはなりません。」--これは微妙な言い方だ。はっきりとプライバシーの侵害だとは言っていない。その可能性があるという主張だと受け取るべきだろうか。弁護士だから、かえって断定が出来ないのかもしれない。二瓶和敏氏(弁護士)「従って、記事の内容が真実だとしても田中真紀子氏長女のプライバシーが侵害されたとする判断はやむを得ないと思います。」--プライバシーは、内容の真実性で判断するのではなく、報道してはいけないという判断をするものという概念からの判断。いしかわじゅん氏(漫画家)「プライバシーは侵害していると思うが、単なるのぞき見記事だと思った。」--しかし、この程度の記事で「出版差し止め」は間違っているという意見の過程で、プライバシーの侵害は認めている。以上の7人が、プライバシーの侵害を明言していると思われる人だろうか。1名は可能性の示唆だから、6.5名かな。立花隆氏を含めて、総勢35名の執筆者の中でのこの数だから、7名と考えて、その比率は20%というところだろうか。それでは、逆にプライバシーの侵害でないと明言している人を探してみよう。文春編集部「文春側は、記事が長女側のプライバシー侵害には当たらないこと、その段階で雑誌の印刷は終了し、……。」--長女は、「純然たる私人」ではないということが根拠のようだが、「純然たる公人」であるという証明はない。具体的に、この記事がプライバシー侵害ではないという証明はない。この記事に公益性があるという具体的な証明がない。やくみつる氏(漫画家・コメンテーター)「公人の定義が議論されているが、もし公人でなかったとしても、文春が取り上げた長女の「事情」は秘匿すべきプライバシーには当たらない、と考えます。」--プライバシーを公表するかどうかは、プライバシーの所有者の権利であると思うのだが、それをやく氏は否定するのであろうか。秘匿すべきであるかどうかを、どのような判断基準で考えるのだろう。次の言葉は、基本的人権を否定するような暴論であるように僕は感じる。「本来は、文春が書いたような「人生の出来事」は厳重な保護の対象になるプライバシーではない、という議論に持っていかなければならないとも思います。」--こういう議論に持って行かれたら、マスコミにねらわれた人間にはプライバシーがなくなってしまうだろう。B・フルフォード(フォーブス・アジア太平洋支局長)「週刊文春の報じた今回のプライバシーの内容は公的機関に届け出を出すものだし、周囲には当然知られることになる。プライバシーの侵害とは言い難い。」--これは乱暴な論理だ。周囲に知る人が出るからと言って、それを大マスコミで世間一般に流すことの正当性がどこから出てくるのだろうか。阿刀田高氏(作家)「今回の件は、私は今の日本の世情を鑑みても、田中真紀子氏の長女のプライバシーを侵害するものとは思えない。」--判断の基準は、今日の良識から考えて、あの程度のことを書かれても大きくとがめられるないようではないと言う根拠からプライバシーの侵害ではないと結論している。今日の良識というような曖昧なものを基準にしていることに疑問を感じる。それは容易に恣意的なものにならないか。法的な判断をするに足ほどの厳密な基準になるとは思えない。文春編集部は当事者であるから頭数に入れないことにすると、プライバシーの侵害ではないと明言しているのは3人である。比率としては8%ないし9%というところだろうか。他の大部分の人(残り70%くらい)は、直接的にはプライバシーの侵害に触れていない。「この程度」で出版差し止めはバランスを欠いているという表現が多い。ということは、暗にプライバシーの侵害を認めているとも感じるのだが。プライバシーの侵害を明言して、それでもなおかつ出版差し止めというものとはバランスがとれないのだという批判が出来ないのだろうか。プライバシーの侵害を認めてしまうと、出版差し止めへの批判が鈍ると思ってしまうのだろうか。あとこのほか、この件には田中真紀子氏の力が働いて不当な処分が出たのだと憤慨している人が多いように感じた。しかし、報道を見る限りでは、田中真紀子氏が動いたというものを僕は見ていない。何か具体的に、そういう不当な働きかけがあったという事実を誰かがつかんでいるのだろうか。これは、具体的な証拠とともに告発しなければいけないものではないだろうか。何も証拠がないのに、そうに違いないという思い込みだけで非難しているようにしか、今の段階では見えない。だいたい、今の田中真紀子氏に、司法を動かすだけの権力があるのだろうか。外務大臣の座を追われ、政権からは離れ、無所属の議員としてしか存在していない田中真紀子氏が、国家権力の一つのような司法を動かすだけの力があるのだろうか。今の政権の中枢にいる人間ならその可能性を持っていると思うが、田中真紀子氏にそれが出来るとは僕には思えないのだが。まして、その娘にどれだけの権力があるのだろうか。2の出版差し止めに対する判断については、書くだけの余裕がなくなったのでまた明日にしよう。
2004.03.28
コメント(2)
-
今週号の文春を読んで
僕も今週号の文春を買ってみた。先週号は手に入らなかったので、問題の記事は直接読んでいない。この号の出版差し止めを巡っては、僕はその裁判所の判断を支持しているのではないかと思われてしまうような表現をしているかもしれないが、僕が主張したいのは出版差し止めを批判する論理がちょっと違うのではないかという点なのだ。一般論として言論の自由や表現の自由が大事だと言うことに反対する人はいないし、僕もそれを否定しているわけじゃない。まさに一般論として正しいことなのだから、このことだけを根拠に出版差し止めを批判するのは、論理として弱すぎないだろうかという疑問なのだ。一般論というのは、あくまでも一般的に成り立つ抽象的なことを述べているのであって、抽象的に設定した対象に対する真理を語っているだけだ。具体的な存在に対しては何も語っていないのだから、一般論と具体的な現存在の関係を述べて批判しなければならないのではないかという疑問をずっと抱いている。文春の側は、問題の記事がプライバシーの侵害になっていないにもかかわらず不当な措置を受けたと批判しているのではないだろうか。僕はそれに対して疑問を抱いている。プライバシーの侵害の面はあったのではないだろうかと思っている。そう指摘する人は多い。しかし、その面を批判する論理が弱いのではないかと感じている。ここの部分に対する厳しい批判を前提として、なおその上で検閲に等しい事前の出版差し止めはバランスを欠いているという批判が必要なのではないかと思う。問題の記事に関しては、田中前外務大臣の記事として受け取られているので、田中さんをバッシングする雰囲気の中で、この程度の記事を書かれて文句を言うなんてけしからんという空気を感じる。しかし、記事は田中さんにかかわっているとはいえ、直接的にはその長女について書かれている記事なのだ。ダイアナ元皇太子妃へのパパラッチの取材に対してはかなりの憤慨を見せた世論は、田中さんの長女に対しては、同じような感情を持たないのだろうか。ダイアナさんの方がずっと公人の面が大きいというのに。文春の側が、田中さん本人をねらわずに、なぜ長女の方をねらって記事にしたかという面は、もっと批判されていいのではないかと感じて仕方がないのだ。今週号の文春では、多くの識者の意見を載せているが、やはり一般論的に語っている人が多い。その一般論に関する部分では、もちろん僕も反対はしない。それは、一般論である限りでは真理だと思う。それぞれの発言で、一般論としては正しいと思えるものの、どこに僕が疑問を感じているのかを調べてみよう。立花隆氏「真紀子のように、国会議員という公職にあり、すでに大臣を二度も務めているような有力政治家の言動の中に、政治家としての的確性を疑わせるものがあることを伝える上で、その話題が多少プライベートな領域にまで及んだとしても、それが雑誌の出版事前差し止めなどという憲法上大いに疑義がある司法処分の理由になり得ないことは、最高裁判所によって明らかなのである。それがウソデタラメでない限り、かつことさら不穏当な表現でない限り、そういう公的人物の特異な言動を伝えることは公共の利益目的の報道と見なされるからである。」--記事が、田中真紀子氏に関する記事ならば、上の論理は全くその通りだと思う。一般論を現実に適用したものとして、その解釈に賛成する。しかし、記事は田中氏本人のものではなく、娘のものなのだ。なぜ文春は娘の記事にしたのだろうか。田中氏本人なら政治家であり、公人であることは明らかであり、宮台氏的な解釈をすれば、純然たる公人であるから、プライバシーは存在しないと解釈することも出来る。しかし娘は政治家ではない。純然たる公人ではないのだ。その時に、上の論理がそのまま娘にも当てはまるだろうか。娘に対しては、プライバシーを侵しているかもしれないが、それでもなおかつ出版差し止めは不適切だという論理でないと、批判の論理としては弱いのではないか。「救済対象の私的価値と救済に伴って社会全体が失う公的価値を比較衡量するなら、失われる公的価値の方が問題にならないくらい大きいからである。」--これも一般論としてはもっともだと思う。しかし、それでもなおかつ、私的価値の救済の方法がどれだけあるのかという疑問が残ってしまう。私的価値の救済を、これまでないがしろにしてきたのではないか。それをきちんとやらないでおいて、社会の価値を守るために、私的価値を無視するような現状を放置したままで、私的価値を侵された人々はこの論理に納得するであろうか。そういう人は少数派だから、多数派の利益のためには我慢させられなければならないのだろうか。多くの人が知りたがるものであれば、個人は泣き寝入りしなければならないのだろうか。これは一般論としての疑問だ。今までの報道被害の実態を踏まえた上での上の論理の提出であれば納得する。私的価値の救済が今までどれくらい真剣に議論されてきただろうか。泣き寝入りするのは圧倒的少数派だ。僕自身も、上の一般論は正しいと思うし、今回の文春の記事も、おそらくは社会全体が失う公的価値の方が大きいと思う。それは、多くの人が指摘するように、出版差し止めによって、この記事以外の記事も読者の元に届かなくなってしまうからだ。しかし、それでもなおかつ、私的価値の救済についても真剣に議論されなければ、この真理を素直に受け入れる気持ちにはなれないのだ。「プライバシー権(憲法13条)と表現の自由(憲法21条)は、憲法上対等の重さを持つ権利ではなく、表現の自由(言論・出版の自由)の方が、圧倒的に優越的な権利だということだ。それは、憲法の文言上からも明らかなのである。」--これも、一般論としてはその通りだと思う。プライバシー権は、個人に属する権利であり、表現の自由は多くの人(社会)にかかわる権利になると思うからだ。しかし、だからといって、プライバシーを侵すことの正当性が、表現の自由によってもたらされるわけではない。プライバシーが問題にならなくなるのは、あくまでも公益性を持った公人が対象の場合のみだと思う。上のことを根拠に出版差し止めを批判するときは、この観点を忘れてはならないのではないかと思う。「出版の事前差し止めとは、実質的な検閲に他ならないからである。」--これも一般論としては全くその通りだと思う。このことには反対しなければならない。しかし、このような事態を招いた責任の一端は文春の側にもあるのではないか。その責任を忘れて、この一般論にのみ従って反対を叫ぶのは、やはり心に引っかかりがあるのである。反対と同時に、文春の側の批判もしなければならないと。たとえ、それが反対の声を落とさせるようなことになっても。堀部政男氏(中大教授)「グレーゾーンであるときに事前差し止めという決定はするべきではない。これは、やはり「例外中の例外」であるべきなのです。」--この意見は論理的には明快である。しかし、明快すぎるために、次のような解釈も出来る。グレーゾーンまでは事前差し止めはすべきでないとすると、事前差し止めになるのは、純然たる私人のプライバシーが侵害されたときに限るということになる。しかし、純然たる私人というのは、おそらく週刊誌の関心の対象にならないだろう。そうであれば、事実上事前差し止めはすべきでないという主張と同じになる。明快といえば明快だが、あえて付け加えるほどの論理かどうかは疑問だ。田島泰彦氏(上智大教授)「表現の自由とプライバシーの保護は時として相反しますから利害調整は必要ですが、一方の主張を全部認めてもう一方をゼロにするのは明らかに行きすぎです。しかも出版差し止めによって社会から情報が遮断され、読者が自分の頭で記事の是非を判断する機会が奪われてしまう。」--この主張は、一般論としては共感できるものだ。ただ、難しいのは、プライバシーの侵害の度合いの大きなものでも、一度出されてしまったら、読者が判断するために提供されなければならないとしたら、出してしまった方の得ということになってしまいかねない。そこのところの救済をどうするかという問題があるのではないだろうか。B・フルフォード(フォーブス・アジア太平洋支局長)「公人と私人の区別があるという考え方がそもそもおかしい。ニュースになるならないは、公人私人の区別で決まるのではない。それは世間の人が決める。一般の人でも、浮気しているらしいなど、様々な情報、噂が流されることもあるが、心配する必要はない。メディアがそうした情報を取り上げ、一般の人のプライバシーを侵害することなどない。世間が興味を持たないから、ニュースにならないのである。」--これはちょっとひどい一般論ではないだろうか。世間が知りたがるのであれば、なんでも報道していいという結論になってしまわないだろうか。それは、世間というものが、常に正しい判断をしうるというかなりの民度の高い世間である場合にしか成り立たない一般論だろう。実際にはどうなのだろうか。ワイドショーやゴシップ週刊誌の現状を見ていると、とても世間にまかせておいて安心できるという状況ではないように感じる。一般の人に対しては、何も起こらなければ世間は関心を持たないが、運悪くある種の事件に巻き込まれてしまったら、世間はすぐに注目する。松本サリン事件の河野さんのことを僕は思い浮かべる。「私が考えるプライバシー侵害に当たるケースとは、裸を盗撮して、写真を載せるなど、違法に情報を入手した場合だ。」--これも何ともひどい論理だ。これは、わざわざプライバシーを言い立てるほどのことはなく、そのものだけでも犯罪として告発できてしまうものだ。プライバシーを問題にするのは、直接このように明らかな犯罪として告発できなくても、個人に大きな傷を残すような行為を抑止するのが目的なのではないだろうか。明らかな犯罪でなければ何を報道してもいいという論理は、基本的人権を踏みにじるものだ。まだ記事の特集は続くが、かなり多くなったのでまた明日にしよう。文春の記事は、田中さん本人への記事であれば、プライバシーの問題は起こらなかったと思う。文春の側は、なぜ長女の記事であることにこだわったのだろう。それに、長女の側の告発に対して、プライバシーの侵害がある部分を、事前に削除するなり、それが間に合わなければ謝罪を載せて損害賠償をしたりと、いくらでも和解する道はあったと思う。それをどうして「表現の自由」として争う道を選んだのだろう。実際に文春の記事が、全くプライバシーの侵害に値しないものなら、僕のこの疑問は憶測から生まれた妄想ということになるのだが、実際の文章を目にして判断してみたいものだと思う。しかし、もしも文春の記事が、やはり田中さんの長女を記事にしている限りではプライバシーの侵害に値するものならば、さらに進んだ憶測を持ちたくなってくる。文春の側は、あえて出版差し止めというようなセンセーショナルなニュースを作りたくて、わざわざ「表現の自由」の問題にしたのだろうかと。謝罪したり和解したりするだけでは、そのことは売れ行きにはあまり影響は与えないだろう。しかし、「表現の自由」として話題になったことで、文春はかつてないほどの売れ行きを示しているのではないだろうか。商売としてはまことにうまいやり方だ。
2004.03.27
コメント(0)
-
プライバシーについて考える
週刊文春の問題は、識者の間では、表現の自由にかかわる問題であり、ジャーナリズムの危機であるという判断が大勢を占めているようだ。しかし、どうも僕には疑問が残る。出版差し止めというのは、異例の判断で、これが言論弾圧に結びつく恐れがあるというのは、一般論としてはよく分かる。一般論としてはよく分かるのに、なぜこんなに引っかかるんだろうか。それは、この件がジャーナリズムへの攻撃だとはとても思えないところにあるような感じがする。もちろん、一般論としてはジャーナリズム全体に影響があることは確かだろうと思うが、まな板に乗っている文春の記事が、果たしてジャーナリズムなのか、ということへの疑問が僕の引っかかりなんだと思う。こういうことを言うと「どっちもどっちだ」と主張しているように受け取られるかもしれないが、そうではなくて、もっと文春側の責任を問わなければならないのではないかと思うのだ。この程度の記事で権力の側につけ込まれるようなきっかけを作った責任を問う声が出てこないのはどうしてなのだろう。文春の記事が、真っ当なジャーナリズムであり、それが弾圧されたのなら迷わずに文春の側を支持できる。そうでない記事でつけ込まれる原因を作った文春にはなんの責任もないのだろうか。「この程度の記事」と言われる記事であれば、文春の側としては、それほど急いで出す必要はなかったのではないだろうか。プライバシーの侵害にならないような工夫をして、相手側の了解を取った後に出せたのではないだろうか。それを、プライバシーの侵害になるかもしれない記事をそのままで強引に出そうとしたのはなぜだろうか。この点は批判されなくていいのだろうか。文春は今週号でかなりの反論を特集したらしい。少し読んだだけだが、そこには一般論が語られているだけで、一般論の正しさで、今回の問題の正当性を主張しているようにも見える。ゆっくりと検討してみたいものだと思う。この問題の一方の軸は、文春側が主張する表現の自由の問題だが、もう一つの軸はプライバシーをどうとらえるかという問題があると思う。この両者は関連があるけれども、それはとても複雑な関連で、一緒に論じたら訳が分からなくなってしまう。表現の自由の問題は、今週号の文春を読んでからまた考えることにして、今日はプライバシーの問題だけを独立して考えてみようかと思う。プライバシーというのはある種の個人情報に当たるが、それは秘密にしておきたい、他人には知られたくない種類の個人情報というものになる。他人には知られたくないものが暴露されれば、当然本人としてはそれを差し止めたいと思うだろう。これが暴露されないようにさせるというのがプライバシー権に当たり、暴露されたときにプライバシーの侵害に当たると言うことになるだろうか。このプライバシーに関しては、何がプライバシーに当たるのかを一般的に決めるのは難しいだろうと思う。それは、何かを隠したいと思うものが、人によって大きく違うようになると思うからだ。ある人にとっては、出身地や出身校が知られたくないプライバシーに当たるかもしれない。他の人から見たらなんでもないことじゃないかと思われても、本人にとっては重大なプライバシーであるということは充分あり得る。だから、自分は平気だから、人がそれを暴露されても侵害ではないというような論理はちょっと乱暴だ。プライバシーを、その内容から判断するというのは論理的ではないと思う。一般的な規定がなく、個別で特殊な条件を判断しなければならないと思うからだ。ケース・バイ・ケースで判断するしかないとしたら、それは容易に恣意的な判断をされかねない。それでは、論理的に、恣意的でない判断をするとしたらどうしたらよいのだろうか。それは、宮台真司氏が語っていたことがヒントになると思った。宮台氏は、政治家は純然たる公人であって、公人には原則としてプライバシーはない、という見解を語っていた。政治家は、他人に対して秘密にしておきたい私生活を持つ権利がないというのだ。それは、政治家というのは、指導者として多くの人の評価にさらされなければならないからだ。もし、政治家が自分をそう見せたいという側面だけを表に出して、本当の部分でも見せたくない部分をプライバシーとして隠せるとしたら、有権者の判断に誤ったものを生じさせる恐れがある。有権者は、政治家に対してはあらゆる情報を受け取って判断する権利があるという考え方だ。政治家は、プライバシーを持たないので何を暴露されても抗議することは出来ない。争えるのは、暴露されたものが事実であるかどうかという点だけだ。この純然たる公人である政治家に対して、その反対の極にいるのが純然たる私人と言うことになる。イメージとしては、無名の市井の一市民という感じだろうか。もし、純然たる私人というものが存在したら、その人の個人情報はすべてプライバシーと言うことになる。だから、どんなことでも、その人が望まなければ暴露してはいけないということになる。どんなにつまらない事実であっても、望まない事実を暴露されたらプライバシーの侵害になる。これは内容には関係ない。プライバシーというものを上のように考えれば、論理的にはすっきりする。その具体的内容を論じることなく、抽象的に扱うことが出来る。「純然たる公人」と「純然たる私人」というのも抽象的な概念で、論理とはよくなじむ。一応このような論理的前提を認めてもらえれば、この抽象論を具体的な現実に適用するときは、純然としていない「公人」と「私人」の区別をどこでつけるかという応用問題になる。「公人」でもあるし、「公人」でもない「私人」であるという存在をどう考えたらいいかという問題だ。ある部分では「公人」であるけれども、ある部分では「私人」だという存在になるだろうか。田中さんの長女は、まさにそのような存在ではないかと思う。今週号の文春で、文集の側からの発言と思われる人の解釈では、田中さんの長女を、「公人」であるか「私人」であるかの二者択一的な判断をしていると思える人が多かった。しかし、実際的には、両者が入り交じったグレーゾーンにいる存在ととらえるのが正しいのだろうと思う。宮台氏は、このようなときにどう考えるかまでは明言していないが、僕なりにちょっと考えてみた。グレーゾーンにいる存在に対しては、その行動の側面で、その行為が公的な側面を持っていれば、その行為が及ぶ範囲に限り「公人」として存在し、その行為が及ばない範囲では「私人」として存在すると判断するのが妥当なのではないだろうか。たとえば、僕が平和運動の指導者的立場に立っている人間だとして、趣味として様々の拳銃を集めているガンマニアだったとしよう。これは、平和主義と武器の象徴としての拳銃という矛盾した存在が僕の中にあることになる。そういうとき、個人としての僕は、その趣味を知られたくないと思うかもしれない。しかし、公的な存在としての平和運動の指導者という立場を考えると、このような趣味はプライバシーの領域には入らないと判断できるのではないだろうか。公的な立場と深く関わると思えるからだ。だから、この場合はプライバシーを暴露されても、プライバシーの侵害にならないと思う。しかし、僕の趣味が、もしも少女趣味的なコレクションだったとしたらどうだろう。それは、特に平和運動を推進するという趣旨と矛盾はしないだろう。ただ、人に知られたら恥ずかしいと思うかもしれない。そんなときに、その趣味を暴露されたら、それはプライバシーの侵害になるのではないだろうか。実際には、僕は運動の指導者でもなんでもないただの一市民なので、僕に関するプライバシーを、僕の意志に反して暴露されたら、それはほとんどプライバシーの侵害になるだろうと思うけれど。田中さんの長女に関して、文春が暴露したプライバシーは、果たして公的側面にかかわっているのだろうか。離婚したという事実がかなり大きな比重を占めているように言われている。その事実は、田中さんの長女が公的に行動していた行為と深い関わりがあると認められるものなのだろうか。僕は、実際にこの記事を読んでいないのでその判断が出来ないが、もし公的側面と関わりがない部分を暴露されているのであれば、その暴露に本人が同意しない限りはプライバシーの侵害になるのではないか。田中さんの長女には、もちろん公的側面がかなりあるだろう。その公的側面にかかわる限りでは、少しもプライバシーの侵害にはならないと思う。それを弾圧されたのならば、それはジャーナリズムに対する弾圧である。それならばすっきりしてわかりやすいのだが、もしプライバシーの侵害であるならば、今度は、この程度のプライバシーの侵害が出版差し止めに値するかどうかという議論になる。程度の問題は、簡単に結論づけられる簡単な問題ではないような気がする。果たして実際にはどちらなんだろうか。この記事を見ることが出来れば、個人的には判断できるのだが、それはこのように公の場では議論はできないだろうと思う。議論をするには、その材料である田中さんの長女のプライバシーを扱わなければならない。議論をすること自体が、新たなプライバシーの侵害を生む恐れがある。何とも難しい問題だなと思う。一番に言いたいのは、この問題は、簡単に一方の主張を支持したり、反対したりしてすむものではないのではないかということかな。
2004.03.26
コメント(4)
-
今日の注目ニュース 画期的な違憲判決
憲法にかかわる画期的な判決を伝えるニュースが飛び込んできた。憲法があることによって基本的人権が守られるというのを改めて確認させてくれるニュースだ。「学生時に障害、無年金のまま…「国の不作為」違憲」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040324-00000112-yom-sociこの記事では次のように語られている。「藤山雅行裁判長は「1985年の国民年金法改正時点でも、学生無年金障害者に何の措置も講じなかったのは、『法の下の平等』を定めた憲法に違反する」と国の立法不作為(怠慢)を認め、国が3人に各500万円の慰謝料を支払うよう命じた。残る1人は「障害基礎年金の受給資格がある」と認定、不支給決定を取り消した。」まことに明快で論理的な判決だと思う。あとは、このような違憲状態がなぜこれほど長い間続いてしまったのかというのを、いろいろな角度から原因を探り報道して欲しいものだと思う。このような弱い部分をないがしろにしているような年金制度というものが、本当に国民の利益を考えて運営されているとは信じられないからだ。信頼を得るためにも、どこを直せばいいのかという報道が必要だ。このニュースは、次の記事に詳しい解説も載せられている。「<無年金障害者>放置は違憲、国に賠償責任 東京地裁判決」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040324-00001085-mai-soci判決の根拠となった事実は次のようなものだというふうに報道している。「判決は、違憲状態になったのは、サラリーマンの妻に加入を義務づけた85年の国民年金法改正時だったと判断した。理由について(1)85年改正により20歳前に障害を負った学生に対する年金支給額は引き上げられたのに、学生無年金障害者は放置され、それまでも問題だった格差がさらに拡大した(2)法が施行された59年の大学進学率は約8.1%だったが、改正時は約26.5%で、大学生の家族は裕福という社会通念は消滅した――の2点を挙げた。 そのうえで、「障害者団体の要請や、(当時の厚相の諮問機関である)年金審議会委員の指摘から是正が必要な状態だったことは明らかになっていた。放置したのは故意または過失による立法の不作為」と結論づけた。」実に明快で納得できる説明だと思う。厚生労働省の側では、「これまでの主張が認められず大変厳しい判決であると考えている」と言っているらしい。この「これまでの主張」というものがどういうものであるかの具体的報道がないので分からないが、記事から推測すると、財源確保が出来なかったから仕方がなかったということを言いたいのだろうか。次のような報道は載っていた。「こうした状況から、坂口厚労相は02年、「法と法の谷間で苦しんでいる人がいる以上、真剣に考えるのが我々の立場」と述べ、約4000人の学生無年金障害者のほか▽82年の国籍要件撤廃前に障害者となった在日外国人(約5000人)▽86年の「主婦強制加入制度」導入前に障害者になったサラリーマンの妻(約2万人)▽元々、強制加入の対象だったのに保険料が未納だった障害者(約9万1000人)――を救済する私案を公表した。しかし、年間約600億円の財源が必要なことや、「拠出制という年金の基本を否定する」と財務省が難色を示したことで、実現していない。」厚生労働省としては、立法の努力はしていたのだから、「立法不作為」による責任はないと主張していたのだろうか。しかし、この問題は財源がないからという理由で放っておかれてもいい問題ではないと思う。財源がないというのなら、さらにその財源を確保するための努力をして、なんとか解決させなければならない問題だと思う。それこそ公共事業のいくつかを凍結して、その財源を回すくらいの努力をするべきだろうと思う。公共事業が凍結されても、ちょっと不便なことを我慢するくらいじゃないだろうか。そんなものよりも、憲法で認められている基本的人権の方が国にとってはもっと重い責任を負うべきものだというのが、この判決の意味ではないだろうか。ここでは、この判決という事実に対して次のような解釈も述べられている。「原告の4人のうち3人はほぼ無収入で、年金生活を送っている両親らが子供たちの老後に備え、掛け金の工面さえしている状態だ。生活は困窮を極めており、将来の見通しも立たない。「容易に想定しがたい、例外的な場合を除いては、国は立法不作為による賠償義務を負わない」と極めて厳しい要件を示した85年の「在宅投票制度訴訟」の最高裁判決に照らすと、「今回の判決は異例」(国賠訴訟に詳しい弁護士)とする声もあるが、国は控訴してさらに争うのではなく、判決を絶好の機会と捕らえて問題解決を目指すべきだろう。」「容易に想定しがたい」というのは、国の責任のほとんどを不問にしかねない条件だ。そうではなく、明らかに困難を抱えた人に対して救済しなかったと言うことを基準にしてもらいたいものだと思った。論理的な感覚では、今回の判決が異例だとは思えない。むしろこのように判断するのが当然ではないのだろうか。国民の多くも、不慮の事故によっていつ同じような境遇になるか分からない状態にあるのだと言うことをよく考えなければならないと思う。彼らが救済されることは、我々も同じように救済されるのだという保証を得ることなのだと思う。さて、その他またたまったニュースをいくつか見てみよう。「米兵のレイプ3年で92件 太平洋軍」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040310-00000120-kyodo-intこのニュースに注目するのは、このような犯罪が、米兵の個人的資質によるところが大きいのか、それとも米軍という組織の持っている問題がこのような形で現れるのかということに関心があるからだ。統計的に言えば、このレイプという犯罪の発生率が、他の状況と比べて大きいものであれば、組織の問題である可能性が高くなると思う。国家間で発生率を比較して、アメリカでの発生率が高いようであれば、国家の問題と言うことにもなるかもしれないが。統計的な判断については述べられていないので、どこかに情報があれば比較してみたいものだと思う。「米英加の3艦に洋上給油 海自補給艦がアラビア海で」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040310-00000236-kyodo-intこのニュースに注目するのは、この行為が集団的自衛権行使に当たる軍事行動で、憲法違反だという解釈があるからだ。もちろん、それは解釈だから反対する人がいてもいい。しかし、こういうデリケートな問題では異論があるときに、その異論も配慮して報道すべきではないのだろうか。この報道では、単に事実を知らせるだけで、その事実が憲法違反に当たるかどうかと言うことには一言も触れられてはいない。そのことを意識していない人は、この問題は憲法とは全く関係ないと思ってしまうのではないだろうか。偏った報道ではないかと思う。「米NGO襲われ3人死亡 イラク北部」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040316-00000031-kyodo-int「<イラク>米国人ら3人撃たれ死亡 ヒッラー近郊」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040311-00002071-mai-int「暫定当局の米人職員ら3人、偽の検問所で射殺される」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040311-00000103-yom-intイラクでのいわゆる「テロ」は上の記事だけでなく、毎日違う記事が飛び込んでくるくらいありふれたものになって、もういちいち記録しておかなくなってしまった。そのような状況のイラクで、自衛隊に関係する記事といえば、全く別の国へ行ったのではないかと思われる、宿営地の生活に関するものだとか、どこかへ訪問したものだとか、何か違うんじゃないのと言うような感じのニュースばかりが入ってくる。次のようなものだ。「サマワ近郊の小学校を視察 佐藤隊長、修復に意欲」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040316-00000026-kyodo-int次のような文章を読むと、イラクでは戦争は過去のものになったのかという錯覚さえ受ける。「突然の来訪者に、午前中で授業を終えた約30人の児童は大はしゃぎ。6年生のモハメド・カミル君(12)は「学校では飲み水や文具が不足し、満足に使えるトイレもない。日本人の手で修復してもらえればとてもうれしい」と話していた。」これは、報道規制によって、本質的に重要な事実が入ってこなくなっているんじゃないかという疑問も感じる。その中でも、次のような記事にはやや重要性を感じた。「しわ寄せは「幼い命」に 陸自医官、病院窮状に直面」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040315-00000030-kyodo-intここでは次のような事実が報道されている。「「手で輸血したんですか」。黄疸(おうだん)症状に苦しむ生後5日目の男の子を前に、小児科担当の医官(38)はイラク人医師に聞き直した。背中に、すがるような家族の視線も感じた。 感染症の疑い。病院側が治療に交換輸血を選択し、14日未明に医師が2時間かけ注射器を手にして輸血したという。 「なぜ(電動の)機器を使わないのか」「古くて使用できない」。イラク人医師が見せた機器類に、医官も瞬時に同じ判断を下した。」友好ムードで、みんながこれから幸せになるんだという雰囲気だけが、自衛隊がいるイラクの雰囲気ではないのである。このような深刻な状況があるという現実をもっと伝えなければならないと思う。そして、さらにもう一歩踏み込んで、なぜこのような状況になったのかということを考えさせる事実を知らせなければならない。そして、なぜこのようなことが解決できないかを考えさせる事実も報道されなければならない。報道規制によってそれらが知らされないのであれば、我々はそれを求めなければならない。ここにこそ、本当の意味での言論の自由・表現の自由・報道の自由を求めなければならないのではないだろうか。「米ニュース・メディア、視聴者・人員とも減少の一途=報告書」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040315-00000601-reu-int日本のジャーナリズムも凋落の一途をたどっているが、アメリカでもそうなんだなあと言う感じがする。ここでは、「放送されるケーブル・ニュースには、新たな情報は5%しか含まれておらず、大半が同じ事実を繰り返していることも判明した」と報道されている。日本のワイドショー的報道に似たような傾向がアメリカでも出ているのだろうか。「爆発物所持で10歳男児拘束 イスラエル軍」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040315-00000251-kyodo-intこのニュースは、これをどのように解釈するかで、その人の立場というものが見えてくるのではないかということで目にとまった。たとえ子供であっても、爆発物を所持しているのは憎むべきテロリストだと解釈するだろうか。子供をテロの道具に使うなんて、テロリストの側の非人間性を示すものだと解釈するだろうか。子供でさえテロに参加しようとするほど、民族そのものに深い恨みが刻印されていると解釈する人もいるだろう。それほど深い恨みは、おそらく民族が絶滅されない限り次の世代に受け継がれていってしまうのではないかと、僕はさらに解釈してしまう。古いソビエト映画の「僕の村は戦場だった」に感激した人は、きっと最後の解釈をするんじゃないかと僕は思う。子供だって、不正に対する怒りは大きく激しいものを持つと思う。いや、むしろ子供だからこそ純粋に激しい怒りを持つものなのかもしれない。また長くなってしまったので、続きは掲示板の方へ残しておこう。
2004.03.25
コメント(4)
-
「論座」の改憲論 天木さんの改憲論
前レバノン大使の天木直人さんの改憲論は、非常に現実主義的であるのに、原則を踏み外すことなく、まず改憲ありきというものではないところが共感できるところだった。天木さんは冒頭で次のように語っている。「憲法9条は機が熟した段階で国民の手で明確に書き改められるべきであろう。しかし、その作業を進める前に、まず日本の安全保障政策について国民の間で自由かつオープンな論議を尽くし、国民の大多数(憲法の規定を上回る、たとえば3分の2以上)の合意が確認されなければならない。憲法改定は国の方向を決める大きくかつ厳粛な問題である。しかし、それを本気になって議論しようという気運が高まってきたのは最近のことである。論議は尽くさなければならない。憲法改定の文言作りを急いではならないし、急ぐ必要もない。」天木さんは改憲論者だ。改憲すべきだと考えている。しかし、それは論議を尽くしたあとにすべきだという原則は、最後まで貫いての改憲論だ。この姿勢に僕はとても共感をする。改憲すべき点があるとしても、それを早急にハンドルを切るべきではない。多くの人が賛成するような世論が形成された後に改憲へのハンドルを切るべきだ。それこそが民主主義の原則であり、民主主義のすぐれた点だからだ。一部の人間が考えたことは、たとえどのように優れた頭脳を持った人間の考えであろうと、絶対的に正しい考えではない。少しでも間違いの少ない方向を選択するために、民主主義は多くの頭でそれをチェックするというシステムを生み出したのだと思う。崩壊した社会主義に比べて、先進資本主義国がすぐれていたのは、この民主主義の制度を取り入れていたからだと僕は思う。その原則をあくまで守るべきだという天木さんの主張は、とても納得のいくものだ。この原則を守りながらも主張する改憲論はとても説得力のあるものに感じる。説得力があるから、論議を尽くせば賛成してくれる人が増えて来るという見通しが立つのではないかと思う。だから原則を守っていけるという循環にあるのだと思う。天木さんの改憲論のポイントは次のようなところだ。「私自身は、平和憲法の趣旨を維持しながら、専守防衛の立場で自衛隊を明確に認めるように改定すべきと考えている。いわゆる「芦田修生」(国会での9条条文案の文言追加)の経緯をふまえ、「国際紛争を解決する手段として」の戦力の放棄は、自衛のための戦力まで放棄するものではないという解釈が定着しており、これまでも否定するのは現実的ではないからだ。さらに、国連憲章42条に基づき国際連合が「国際の平和および安全の維持または回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動」を取るときは協力できるよう改定すべきである。加盟国の責任を果たすためであり、日本が協力しないと身勝手ということになりはしないか。ただし、これは多国籍軍とは全く異なるもので、あくまでも安保理決議に基づく国連軍である。それ以外の集団的自衛権は認めるべきでない。」この改憲論も全くその通りだなと思う。集団的自衛権を無制限に認めるのではなく、国連決議に基づく場合にのみ認めるという考え方は、憲法の原則にもかなっていると思う。これによって、憲法制定時と変わってきた状況にも対処できるし、国家権力の暴走を食い止めるための歯止めにもすることが出来る。国連については、その決定がいつも正しいわけではないと言うことで、それに従うことに疑問を持つ人もいるかもしれない。しかし、これは現実的には、正しいから従うというのではなく、民主主義の制度に従って、多数の国の意志に従うという形で国連に従うのだと思う。日本はかつて侵略戦争を起こした国家である。その軍事行動を単独で判断したら、それを信用してくれる国がどれだけいるだろうか。それらの国に対して、軍事行動を取ることの正当性を主張するために国連決議に従うという形が必要なのだと思う。この改憲論だったら、原則にも則っているし、現実にも対応している。だから多くの人の賛同を得る可能性があると思う。しかし、だからこそといおうか、天木さんはこの考えを強引に押し通そうとはしない。次のように、あくまでも民主的原則に従って進めるべきだと主張する。「しかし、国民的な合意の実現は容易ではないだろう。国民の間で大きく意見が分かれるならば、決して強引に改定してはならない。無理をすれば、国民を分断し、日本全体を不幸に陥れるからだ。国民的合意が出来るまで今の平和憲法を維持すべきである。少なくともそれは今日まで国民が受け入れてきた憲法であり、日本が再び軽々に軍事行動に走ることのないように抑止する役割を果たしてきたからである。」国民的合意が得られるまでは、平和憲法を維持すべきであるという考え方に共感する。天木さんの改憲論は、事実から導かれたものではあるが、「論」は事実そのものではない。だから、賛成する人もいれば、反対する人もいるだろう。賛成する人が多数を占めたとき、その方向に舵が切られる。それが民主主義という制度だろうと思う。天木さんのこの文章には、憲法制定時の問題である「押しつけ憲法論」に関して参考になる事柄が書かれている。まず事実として次のように書かれている。「歴史的事実から見て、我が国の憲法が連合国最高司令官総司令部(GHQ)の意向に沿って作成されたことは否定できない。すなわち1945年8月にポツダム宣言の受諾により敗戦を認めた日本に対し、その年の10月、マッカーサー最高司令官は大日本帝国憲法の改正を命じた。そして日本案がポツダム宣言の精神に沿っていないことを知ったマッカーサーは即座にGHQ民政局に改正案を起草させた。それを日本が呑む形で46年4月に最終案の骨子が決まった。元東大教授の宮沢俊義氏は46年10月、国会の憲法改正小委員会で「憲法全体が自発的に出来ているものではない。重大なことを失ったあとで頑張ったところでそう得るところはなく、多少とも自主性を持ってやったという自己欺瞞に過ぎない」と述べた。またマンスフィールド元駐日米国大使は日本経済新聞の「私の履歴書」(99年9月連載)の中で「戦争放棄を定めた日本国憲法第9条は、マッカーサーの直接の指示を受けてGHQ民政局のチャールズ・ケーディス次長を中心に作った条項でどこから見ても米国製だ」と述べている。」これは、事実としてほとんどの人が確認できるのではないだろうか。事実には異論は存在しない。正しいか正しくないかがあるだけだ。この事実は、形式的には憲法は押しつけられたという「押しつけ憲法論」を生み、だから改定すべきだという「論」を生み出す。しかし、その「論」には大いに異論が存在する。ここで提出されている天木さんの異論は非常に参考になる。天木さんの「論」の前提となる事実をまず確認しておこう。「ポツダム宣言は日本が生まれ変わるために軍国主義勢力の除去と軍隊の完全な武装解除および民主主義と基本的人権の確立を日本に求めた。」これに反対する人はいないのではないだろうか。そして、ポツダム宣言を受け入れた日本は、本来は日本独自の案として、上に書かれている趣旨を盛り込んだ憲法草案を作るべきだったのだ。「その認識と心構えがなかったために結果として「米国に押しつけられる」格好になった」とするのが天木さんの解釈だ。つまり、押しつけられたというのは形式的なことであって、本来は押しつけられる前に、平和憲法のような憲法草案を作らなければなかったのではないかと解釈するのである。それが出来なかったために、形として押しつけられたものになったというのだ。そして、天木さんは、次のものを「事実」として主張する。これは、「事実」であれば異論は存在しないものになるが、まだ確認はされていないようだ。これが事実であるかどうかを巡ってはこれからも論議されるかもしれない。「重要なことは、そのような経緯で出来た「戦争放棄」と「軍隊の不保持」を高らかに謳った9条が、軍国主義がもたらした無謀な戦争の惨禍に苦しんだ日本国民の間に幅広く受け入れられ、今日に至るまで国民の意識に定着したという否定できない事実なのである。」国民の間に幅広く受け入れられ、意識に定着したというのは、僕も事実だと思う。しかし、反対する人がまだ多くいる間は、これが「事実」であるという確定をするのはまだ難しいかもしれない。「事実」であるという確たる証拠を探したいものだと思う。天木さんの「論」はさらに続くが、続きはまたあとにしよう。さて、たまったニュースも、触れられるだけ触れておきたいとも思う。「<エジプト人作家>サーダウィさん 自衛隊イラク派遣を批判」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040308-00000076-mai-intこの中で報道されている次の言葉に僕は注目する。「現在、イラクで続いている米兵攻撃は決してテロばかりではなく、占領に反対する抵抗運動でもある。イラク人が占領に反対している中での軍隊派遣は、日本政府がどう取り繕うとも、米政府支援であってイラク人支援ではない」サマワでは歓迎する声の報道ばかりなので、その反対の声もあるという報道に注目をしたい。「米軍がアフガンで人権侵害、過剰な武力を行使=米人権団体」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040308-00000917-reu-intここでは、「防ぐことのできた民間人の死亡を招き、国際法に違反している可能性がある」という指摘に注目をしたい。「テロリストに断固として立ち向かっている」とか「独裁者を倒した」とかいう理由で、このことが正当化されるものかどうか考えたいからだ。「「米英がイラク脅威誇張」と大量破壊兵器査察前委員長」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040309-00000315-yom-intこの記事では、論理の使い方という点の指摘に注目した。次の部分だ。「ブリクス氏は、イラクが一切の大量破壊兵器を保有していないと保証できた者は、自身も含めて世界に1人もいなかったと認める一方で、米英両国は「自らが危険性を誇張していることに、おそらく気づいていた」とし、その結果、「信用失墜を招いた」と厳しく指弾している。」「一切の大量破壊兵器を保有していない」というのは、完全な否定であるが、これは現実的に証明することはかなり難しい。現実は無数の可能性を秘めているからだ。その無数に対応するためには、かなりの長い時間を必要とする。しかし、完全に否定できないから、それはあるのだという主張は論理的でない。小泉さんもそのようなことを言っていたが、どこかにあるはずだと主張出来るのは、最初からあることが確定しているときのはずだ。あるかどうかを問題にしているのに、完全にないということが確かめられていないからどこかにあるはずだというのは詭弁なのである。あるかどうか分からないのに、あるはずだと宣伝するのは、誇張したことになるというのが論理的には正しい判断だと思う。
2004.03.24
コメント(2)
-
「論座」の憲法論 改憲論に隠された真の目的
さて、延び延びになっていた「論座」の憲法論議の中の、愛敬さんの、現在の改憲論に隠された真の目的という指摘を考えてみたい。愛敬さんは、まず経済同友会意見書から次の言葉を引用する。「我々は、日本の国民がこれまで、自らの意志で憲法を作り、必要に応じてこれを改正するという、最も重要な形での国民主権の行使をしてこなかったことこそが、憲法にかかわる最大の問題と考える。」これは一般論として正論である。反対する人は少ないだろう。改憲に賛成する人のかなりの部分の人が、このような思いを抱いているのではないだろうか。しかし、愛敬さんはこの裏を読まないとならないと次のような指摘をする。「集団的自衛権の行使を梃子にして海外での軍事行動を実現するためには、米国の驥尾に付していくしかない。しかし、イラク戦争以後の米国に日本政府が盲従することを国民が喜んで受け入れるだろうか。「対米協調」を根拠にした9条改定を憲法改正国民投票にかければ、改憲派の目論見は潰える恐れもある。ならば、「憲法全体の再調整」を「国民主権の行使」の観点から正当化しつつ、その一環として9条にも手をつけるというのはうまいやり方だ。」これは一つの解釈だから、賛成できない人もいるだろうが、僕はここまで深読みして警戒する必要があるだろうと思っている。改憲派の目的はあくまで9条の改正であって、そのために改憲そのものの正当性を主張した方がいいと考えていると受け取るのは納得できる。しかも、その主張が一理あるものであれば、世論の支持を受けやすいという計算が働くだろう。愛敬さんが、「善意の人こそ、この手の罠にはまりやすいのかもしれないが、国民主権を前面に出す改憲論も、改憲の真の目的を隠蔽するための煙幕に過ぎない。」と語る解釈の方に僕は賛成する。最後に愛敬さんは9条を擁護することの意味を考えている。これが単なる空想的な平和主義ではないという論理を構築しようとしている。まず現状認識としてアメリカの現在をどうとらえるかを語っている。アメリカは外交政策としての軍事力に傾きすぎているという認識がまずある。それ以外の方法がほとんどないと言ってもいいくらいだ。特に現在のブッシュ政権は、経済政策の失敗によって失った支持を、軍事行動によって回復させようとしているので、さらにこの傾向が強くなると言う現状認識がある。このアメリカに対する対応として、韓国だってイラクに派兵しているし、同じじゃないかと見る人もいるだろうが、次の愛敬さんの指摘は考えさせられるものがある。「韓国は北朝鮮問題に対する発言権を確保し、米国の単独行動を抑止するために米国を支持した。他方、日本は大儀も法的根拠も国際世論の支持もない侵略戦争を支持するために、愚かにも「日米同盟」の重要性を強調し、北朝鮮問題とイラク戦争をリンケージして見せた。ここには、「対米追従」という思考停止と、自衛隊を「正真正銘の軍隊」にするという欲望しかない。」韓国のアメリカ支持と、日本のアメリカ支持には構造的な違いがあるということだ。韓国は、朝鮮半島での軍事行使を抑止するための発言権を確保するために支持し、日本は逆にいざというときにアメリカに助けてもらうために支持したという違いがある。在韓米軍の駐留についても、韓国内に多くの米軍兵士がいる間は、直接攻撃されて米軍兵士に大きな被害が出る恐れがある軍事行動を起こす恐れが減るだろうという計算で、米軍の駐留を希望しているという解釈も聞いたことがある。駐留する方が「国民益」があるという計算が働いていると考えられるのだ。さて、このような現状認識のもとでの9条改定を考えるとどういう解釈が生まれてくるか。これは、今後の二つの方向のどちらを我々が選択するかという問題にかかわってくる。それは次の二つの方向だ。 米国流の覇権主義的な世界戦略への軍事協力への道 (武力による平和) 非覇権主義的な国際平和の構築への道 (武力によらない平和)「武力によらない平和」は空想的だと考える人は、「武力による平和」を目指すべきだと考えるだろう。しかし、「武力による平和」が原理的に不可能であり、テロを根絶することが出来ないとしたら、一般市民としての我々は、たとえ実現の可能性に難しさがあるにしろ、「武力によらない平和」の構築に努力していくことこそが「国民益」ではないのだろうか。そして、その努力の中心に憲法9条を据えるという考えが、愛敬さんの9条擁護論なのである。それは次のようなものだ。「安全保障の問題を憲法問題とすることで、自衛隊による米軍への軍事支援を困難にし、米軍基地の正当性を常に疑わしいものとする。9条の「効用」を軽視して良いとは思えない。良かれ悪しかれ、米国の国際戦略は在日米軍基地に大きく依存している。ならば、私たち日本国民が日本政府による米国への軍事協力を拒否することは、単なる「一国平和主義」と揶揄されるべき事柄ではなく、「武力による平和」と「武力によらない平和」との岐路にある現代の国際情勢において、少しでも後者の勢力を強めるための主体的な努力と言えよう。 現在の政治状況を冷静に分析した上で、今、9条を改定すれば、日本国民はもちろん、世界の人々の利益も害すると思うのであれば、改憲派の挑発には乗らないこと。これこそ、賢明な主権者のあり方である。」「武力によらない平和」を選択する道は、困難の多い道ではあるが、決して空想的な道ではなく、これを現実的な道にする努力こそが9条擁護と結びついて来るという指摘は、「護憲派」と揶揄されて十把一絡げに扱われる側としては大切なことだと思う。愛敬さんのこの解釈に僕は賛成だ。さて、たくさんたまったニュースのストックのいくつかを整理しておいて今日の日記を終わらせよう。「イラク戦争は違法 ブリクス前委員長」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040305-00000068-kyodo-int「イラク攻撃は違法=前査察委員長」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040305-00000237-jij-intイラク戦争の違法性に関しては、それが世界の常識になるかどうかに注目していくことにしよう。「ブッシュ陣営CMの同時テロ映像、遺族が反発」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040305-00000002-yom-int「<ブッシュ米大統領>テレビCMに同時テロ映像 犠牲者家族反発」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040305-00001026-mai-int宣伝のためにテロを利用するというやり方が、逆に、人々の反発を呼ぶように僕は願っているけれど、どうなるだろうか。これについてはあまり続報がないようだ。このような宣伝が成功するようであれば、アメリカ人の庶民の民主主義意識を僕は疑ってしまう。「<米大統領政策>ドイツ人の8割以上が否定的 国際世論調査」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040305-00003021-mai-intここでは次の記述に注目した。「自国内でのテロが心配との回答は、スペインが85%と最も高かった。」「<靖国参拝>「絶対受け入れられない」 李・中国外相が批判」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040307-00000040-mai-int「靖国参拝絶対受け入れぬ 中国外相が記者会見」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040306-00000188-kyodo-int靖国参拝の問題は、内政干渉だと感情的に反発するのではなく、なぜアジアの国々、特に中国や韓国などがあれほど強い反発を示すのかという、その事実の理解をまずしなければいけないのではないだろうか。今は理解の前に感情的な反発が先にでている。理解をするというのは、それを受け入れると言うことではなく、外交政策をうまくするための前提だと思うのだが。
2004.03.23
コメント(0)
-
もう一度文春問題を考える
自分の考えていることを文章にするというのは難しいものだ。頭に浮かんだことをそのまま順番に記述してもそのつながりが分からなくなるから、何とか論理的に再構築して説明しようと思うんだけれど、それがちゃんと明確に再構築できていないから、ぼんやりしたまま記述することになって、なかなか自分が意図したように相手に伝わる書き方が出来ない。神保哲生・宮台真司の「マル激トーク・オン・デマンド」で、週刊文春の出版差し止め問題を語っていた。それが実に論理明快でなるほどと思えるものだったのだが、それでも何かが引っかかる思いが消えない。その何かを説明したいのだが、これが自分の中ではちゃんと明確になっていないので、なかなか説明できないのがもどかしい。宮台氏の論理は次のようなものであると僕は受け取った。 プライバシーの侵害は私人の場合にのみ適用される つまり公人の場合にはプライバシーは存在しない。公人の最たるものは政治家であるが、政治家というのは、その人が何を考え・どう行動するかと言うことが、選挙民の支持を獲得する大きな要素となっている。従って、たとえプライバシーにかかわることであっても、その政治家に対する判断にかかわってくるものであれば、一般にそれを知ることは民衆の利益になる。宮台氏が出した例は、たとえば平和主義を唱える政治家が、趣味として鹿狩りをやるというようなプライバシーがあったというものだった。楽しみのために動物を殺すということを趣味にしている人間が平和主義を唱えても、それを単純には信用できないという人間がいても不思議はない。もしそのようなことを知らなければ、表向きの平和主義を信用するだろうが、このプライバシーを知れば、それに疑問を持つこともあり得る。この情報を知ることによって、判断の材料が増えるのだから、このプライバシーを知ることは「公益」の範囲に入るだろうというものだ。アメリカのクリントン前大統領は、不倫疑惑で徹底的にプライバシーを暴露されたが、問題にされたのは、それが正しいか正しくないかということであって、プライバシーとして暴露されたこと自体は問題にされていなかったようだ。アメリカ大統領というのは、公人としてプライバシーはないものと考えられているからだろうか。このように考えた場合、週刊文春の問題は、田中さんの長女が私人であるか公人であるかということが重要な問題であるということになる。ここまでは実に論理としては明快だと思う。私人であればプライバシーは守られなければならない。しかし、これは純然たる私人であることが明確な場合だ。田中さんの長女の場合は、私人の面もありながら公人の面もあるという「グレーゾーン」の問題が難しい問題としてかかわって来るという指摘をしている。つまり、この記事が、私人としての面を取り上げてプライバシーの暴露をしているのであれば、それはプライバシーの侵害であるが、公人としての面にかかわってプライバシーを記述しているのであれば、その範囲でそれは許されるという判断も出来る。裁判所は、このグレーゾーンに対する判断をしていない。それは次の記事に語られている。「長女は純然たる私人として生活しており、記事には公益性がない。公表により著しい損害を被る恐れがある」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040320-00000052-mai-sociこれは、宮台氏の論理からいえば、論理として間違っているという指摘になる。「純然たる私人」という判断はあり得ないということだ。グレーゾーンとしての具体的な判断がなければ論理的ではないということだ。宮台氏の判断としては、裁判所の判断は誤りであるという主張のように聞こえる。これは、論理からすればとても明快で、やはり納得せざるを得ない。また、神保氏の言葉では、この問題の本質は、このようなプライバシーの侵害という問題にあるのではなく、文春程度の記事で、事前に出版差し止めにするような判断を前例にしてしまうことにあるという指摘もあった。神保氏も宮台氏も、この程度の記事で出版差し止めが許されてしまうようなら、どんな記事でも差し止めがされてしまうのだから、事実上事前検閲が行われているのと同じだと指摘していた。「この程度の記事」という判断は、僕自身はそれを見ていないので、神保氏と宮台氏を信じるしかないが、二人のこれまでの発言を見てきて、この判断は信頼できると思っている。しかし、ここまでの論理を認めてもなお、僕には引っかかるものがある。この問題に関する一連の日記では、この引っかかるものの方を前面に出してきたので、僕がここまでを認めるのは、前言を翻すことのように感じてしまう人もいるかもしれないけれど、ここまでを認めてもなお引っかかるものがあるというのが、本当は伝えたいことだったのだ。その引っかかるものがあるから、裁判所の判断を擁護したり、支持するということではないのだ。それではどこが引っかかるかというと、文春側の落ち度が問題にされていないことに引っかかるのだ。上のような正論が、文春を擁護するために利用されているのではないかという疑問が引っかかりになっている。特にマスコミの側が、これまでの報道被害のことを全く言及せずに、上の正論を使うことに疑問を感じる。宮台氏のように、第三者的な立場での正論のようには感じないからだ。文春の側の落ち度を問題にするのは、今度は逆に裁判所の側の間違いを薄めて擁護することになってしまうのだろうか。ここのところが難しくて、明確にならないから、はっきりしないままに自分の考えを述べることになり、なかなか自分の考え通りのことが伝わっていないなあと感じていた。両方を正しく批判できる立場というのはあるのだろうか。次の中国新聞の社説は、それに近いもののような気がする。「今回の記事は、長女を「田中家三代目の政治家となる可能性は十分にある」と強調しているが、説得性に乏しく、両親が政治家であっても子どものプライバシーは守られるべきであろう。そうした意味で「公益を図る目的」とは思えず、母親の知名度で「売ろう」とする意図は明白にうかがえる。ただ、「重大で回復困難」な損害を与える内容か、「表現の自由」とのてんびんにかけると、疑問も生じる。プライバシーは尊重されなければならないが、事前差し止めという危険な伝家の宝刀を抜くにはもっと慎重であっていい。 とはいえ、私的な生活を暴かれた被害者にも配慮は必要だろう。いったん暴かれたら元の状態に戻るのは不可能だからだ。「表現の自由」という重大な権利を主張する以上、週刊誌も興味本位なスキャンダルに走ることは自制したい。少々訴えられても売れる方が得、との商法は自らの首を絞めるだけだろう。高額な賠償判決も相次いでいる。」http://www.chugoku-np.co.jp/Syasetu/Sh04031901.html「マル激トーク・オン・デマンド」のゲストは、「噂の真相」の岡留編集長だった。宮台氏は、公人の情報提供誌としての「噂の真相」を高く評価していた。単なるスキャンダル暴露雑誌とはとらえていなかった。その対象が公人に限られていることを高く評価していた。文春の出版差し止めが、このようなメディアの死滅につながることを危惧し、それを批判していた。これはとてもよく分かる。しかし、それでもなおかつ、文春の批判もしなければ、出版差し止めを容認する世論の方が形成されてしまうのではないだろうかという引っかかりがどうしても消えない。出版差し止め問題を正しく批判するためにも、報道被害に対する批判も忘れずにいなければならないのではないかというのが、僕の言いたかったことなのだけれど、どれだけ伝わっただろうか。
2004.03.22
コメント(0)
-
再び文春問題を
「<週刊文春>異議退け、販売差し止め支持 東京地裁」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040320-00000052-mai-sociという記事が出た。僕は、週刊文春の姿勢を批判しているので、僕がこの結果を歓迎していると受け取っている人もいるかもしれないけれど、僕自身はとても複雑な思いを抱いている。山陰中央新報の社説では、「今回の場合、出版禁止の必要性と、報道されたときの影響とを比較すれば、出版禁止が及ぼす悪影響の方がはるかに大きいと言わざるを得ない。事前規制してしまうことは、かえって「表現の自由」を著しく侵害するのではないか。」というふうに書かれている。この意見は、一般論としては非常によく分かる。全く正論であり、「今回の場合」がこの判断が妥当である可能性も高いという気持ちもある。それでもなお、ここには一方の当事者の立場である、出版する側の利益主張の匂いを強く感じてしまう。文春側は、「〈1〉記事に公益目的がない〈2〉回復不能な損害を与える――の2点を明確に満たさなければ認められないとし、「今回はいずれにも抵触しない」と述べた。」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040318-00000213-yom-sociと主張しているらしい。この主張が正しければ、山陰新聞が社説で主張するように、「出版禁止が及ぼす悪影響の方がはるかに大きいと言わざるを得ない」と言うことになる。しかし、この主張が間違っていて、そもそも文春の記事そのものが、この2点に該当するようなものであったとしたらどうだろう。出版禁止が当然であると言うことになってしまう。そうなったら、これは「プライバシーの侵害」と「言論の自由」との問題なんかではなくなる。単に、ひどい報道被害を受けたときに、どのような判断をされるかという問題になるだけだ。これは、構造的には、かなり前の「ニュース・ステーション」における所沢のダイオキシン報道の被害の問題に重なるところがあるような感じがする。これは、所沢の野菜がダイオキシンに汚染されているという報道があったのだが、実際には、汚染されていたのは野菜ではなく、他のものだった。テレビの画面ではほうれん草が映し出されたので、ほうれん草が汚染されていると思われてしまい、所沢産のほうれん草は全く売れなくなった。しかし、ほうれん草は汚染されていなかったのだ。これは、明らかに報道の間違いであり、報道によって被害を受けたことが明らかだった。だから、裁判の結果では、損害賠償を認めるものになった。これを受けて、報道する側では、言論の自由を規制するものだという反発があったが、神保哲生・宮台真司の「マル激トーク・オン・デマンド」では、これは報道そのものがひどいのであると語っていた。つまり、間違えた報道が、その間違いを指摘されただけのことであって、これを前例として言論を規制させるのは、論理として間違っているというわけだ。この報道をかばってしまえば、むしろ言論の規制を正当化させることになるという。報道そのものは、全く弁護の出来ないものだったのだ。だから、この報道をもとにして、言論の自由の議論などをしてはいけないのだと僕も思う。文春の記事に関しても、この記事を巡って言論の自由を論じるのがそもそも間違いなのではないかと僕は思う。そんなことを論じる価値のない記事なのだと僕は思うのだ。それを論じてしまうと、かえって言論の価値を貶めるのではないか。文春の記事そのものに関しては、次のような見解がたくさん出ている。「長女は純然たる私人として生活しており、記事には公益性がない。公表により著しい損害を被る恐れがある」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040320-00000052-mai-soci「決定はまず、今回の記事はプライバシー侵害に当たると認定。文春側が記事の公共性や公益目的を強調したのに対し、「著名な政治家の家系に生まれた者であっても、政治と無縁の一生を終える場合も少なくなく、その私事についての記事に公共性や公益目的は認められない」と批判。また、記事は「他人に知られたくないと感じるのがもっともな内容」で、長女に回復困難な損害を与えた、と指摘した。」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040319-00000011-yom-soci「ただ、「週刊文春」三月二十五日号の記事は長女と元夫の人柄、生活などプライバシーに深く踏み込む内容だ。当事者が取材を拒み、記事化しないよう強く求めているのに、文春側があえて公表したことには疑問が残る。」http://www.sanin-chuo.co.jp/ronsetu/2004/03/19.html「祖父は元総理、両親もそろって現職の国会議員であり、わけても母は常に国民の注目を集める知名度の高い政治家である。それぞれ、れっきとした公人だが、問題となった記事は長女の私生活に関するもので、政治とはいささかの関係もない。公の場にいない家族が、政治家一家の一員だからといって、私生活を興味本位に書かれる理由はない。」http://www.kobe-np.co.jp/shasetsu04/0319ja24850.html「そうではあれ、長女というだけで近況や家族関係を根掘り葉掘り探る報道をもっぱら正当化するのは理解を得にくい。興味本位に流れる恐れもなしとはしない。 出版、報道に携わる側は人一倍強い自覚、責任が求められる。正確さに万全を期すとともに、個人のプライバシー、名誉を不用意に損ねていないか、絶えず冷静、謙虚に点検する姿勢が基本である。」http://www.shinmai.co.jp/news/2004/03/18/005.htm「不正を暴き、社会的な問題を提起しようとする週刊誌の記事はある。今回はそうしたものとは違い、個人の私生活を暴き立てようとしただけだ。政治家の利権やカネといった問題とも無関係である。雑誌を売るために、公人でもない一個人に痛みを強いる記事には公共性は感じられない。」http://www.asahi.com/paper/editorial20040318.html「プライバシーの侵害であることは明らかだ。」「しかし、今回の記事に「公益目的」があるようには見えない。文春側は仮処分の審尋で、「政治家になる可能性がある人に関する記事であり公益性がある」と主張したが、説得力はない。」http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20040317ig90.htmこのような報道を見る限りでは、文春の記事は、売るために手段を選ばないような、単なるゴシップ記事に過ぎないと見ることが出来るのではないだろうか。それなのに、その記事の中身について強く批判するような報道がないのだ。このようにひどい記事であってもなお、一般論として表現の自由の問題と結びつけて語られてしまう。そうすると、これほどひどい記事であっても、その記事が弁護されると言うことにもなってしまうのだ。次のような報道のように。「記事を読んでみても、事前に出版を差し止めなければならないような緊急性は感じられないし、人命にかかわる内容でもない。一方、田中真紀子議員の家族を「公人」とする週刊文春の見方には異論が少なくなかろう。 そもそも、公人か私人かは公判で争われるべきではないのか。プライバシーの侵害か否かもまたそうだ。出版・報道の適否については公表後に訴訟などで争われるのが妥当と思われる。」http://www.kumanichi.co.jp/iken/iken20040319.html#20040319_0000004538「異なる意見も含め、さまざまな情報を入手し、自由に意見が言えることが、民主主義の基本だ。それを損なうおそれがあるから、出版差し止めは例外中の例外としてきたはずだ。その点で今回の決定は十分に慎重であったか、それ以外に手段はなかったか、厳密に検証する必要があるだろう。」http://www.kobe-np.co.jp/shasetsu04/0319ja24850.html「田中真紀子前外相の長女の動静を記した内容からは、のぞき見趣味との印象を受ける。当事者は書いてほしくなかったろうし、心痛も理解できる。「表現の自由」を引き合いにすることに、ためらいがないわけでもない。だが、司法が伝家の宝刀を抜かねばならぬほどの緊急性、重大性があったのかどうかには疑義がある。出版物の販売差し止めは事実上、憲法が禁じる検閲として機能するからだ。」http://www.mainichi.co.jp/eye/shasetsu/200403/18-2.htmlこのような見解を読むと、今回の場合でも、出版差し止めまで行くのは問題だという主張に聞こえる。そして、その主張からイメージされるのは、この記事がひどいものかどうかは、まだ分からないのだという、記事のひどさを薄めるイメージのように見えるのは僕だけだろうか。みんなが知りたがっているのだから報道する価値があるのだと強弁しているようにも見えるのだが。そのような報道で、公人ではない一般市民がこれまで被害を受けてきたのではないだろうか。ロス疑惑の三浦さんや、松本サリン事件で報道被害を受けた河野さんの教訓が全く生かされていないのではないか。この件に関する主張として、賛成できそうなものが一つだけ見つかった。朝日新聞が社説に載せていたもので、次のようなものだ。「文芸春秋は裁判所の決定に対し、「言論の制約を意味する暴挙」との談話を出した。私人のプライバシーを興味本位で暴きながら、表現の自由をその正当化に使っているのである。それが、表現の自由の価値を結果的におとしめていく態度であることに気づかないのだろうか。 売れさえすれば、書かれる側のプライバシーなどお構いなし。今回の決定はそうしたことがまかり通っていることへの警鐘でもあるだろう。」http://www.asahi.com/paper/editorial20040318.html文藝春秋のような記事を書くことが、むしろ表現の自由を弾圧することに加担しているのではないかという僕の危惧とほぼ重なる主張だ。このような本質的な批判をした上で、表現の自由の問題を論じて欲しかった。この批判を前提としてなら、次のより本質的な問題の指摘も納得するものとして受け止められるのだ。「だが、指摘しておきたいのは、問題とされた週刊文春の記事の正当性と出版差し止めの是非とは別であることだ。」http://www.asahi.com/paper/editorial20040318.html本質的な文春への批判抜きに、この一般論を主張するようなものは、僕は信用しない。
2004.03.20
コメント(0)
-
真正保守の論理
今週号の「週刊金曜日」に「親米保守の首を獄門にさらすべし」と題された西部邁氏のインタビュー記事がある。西部氏と言えば、保守の論客で、「新しい教科書を作る会」などとも関係していた人だ。僕は、西部氏が書いた文章をまだ一度も読んだことがない。しかし、このインタビューを読んでみて驚いた。かなりの部分で共感を感じるのだ。この人が語る、この考えが保守ならば、僕も保守になってしまうんじゃないかと思うくらいだ。ほとんど全部を引用したいくらいだけれど、それは出来ないから、特に共感した部分を紹介していこう。まずは冒頭のイラク戦争への反対論だ。「今回のイラク戦争を支持した多くの自称・保守派はろくでなしだと断言します。なぜならば、イラク戦争は明らかに侵略だからです。歴史を貶めることなく、成功も失敗も含め、先人たちの叡智を受け継ぐのが保守主義者の心構えです。西尾幹二氏のように「日本の歴史はすべてスバラシかった」とみるのは、馬鹿者の歴史観です。日本がこれまでの歴史から学んだのは、巨大な武器でもって弱小国をいわれなく侵略する、そんな卑劣・野蛮・下品なことはしてはならない、ということのはず。」全く同感だ。これこそ真正保守の心意気とでもいうべきものじゃないかと思う。イラク戦争は、アメリカが巨大な武器で弱小国をいわれなく侵略したものだ、それは、日本が歴史から学んだことから判断できるではないかと叱っているようにも聞こえる。イラク戦争が侵略だと断定した理由も実に論理明快だ。次のように答えている。「「武力による先制攻撃はすべて侵略である」とパリ不戦条約(1928年)で定義されていますね。しかし、私は差し迫った脅威がある場合ならば、「予防的な先制攻撃」として仮想敵国への先制攻撃が容認されるべきだと考えます。 しかし、アメリカはイラクが他国を侵略しようとしていた根拠、すなわち、大量破壊兵器保有についても国際テロ組織との密接な連携についても、その証拠を出せなかったし、今も出せていない。そうである以上、今回のイラク攻撃は、「予防的な先制攻撃」だと見なすべきでしょう。「派遣的先制攻撃」がいわゆる「侵略」です。アメリカは国際ルールを自ら破って侵略に踏み切ったのです。」「予防的な先制攻撃」は容認するけれども、「派遣的な先制攻撃」は侵略に当たるから反対だとする論理は、実に明快で、無条件に信念としての反対を述べているのではなく、条件付きで論理的に反対を述べている。これにはほぼ全面的に賛成する。この、西部氏が侵略戦争だと断定するイラク戦争を、日本が支持すると言うことの意味を、真正保守の精神としては、西部氏は次のように受け止める。「イラク戦争を日本が支持・協力することは侵略への加担であり、歴史の常識、常識の中にある道徳、道徳の中にある価値観を汚す。伝統に自尊心を抱き、その土壌の上に独立するというのが保守の根本姿勢ならば、侵略に加担することは国辱であると喝破してこそ、伝統ある「保守の誇り」を持てるはずですよ。」まことにあっぱれな言葉という他はない。このような保守ならば、基本的な考え方は違うかもしれないけれど、尊敬に値する考えだと共感することが出来る。真正保守はこうでなければならないと考える西部氏にとっては、自衛隊員の中から、このイラク侵略への加担であるイラク派遣を批判する正論を吐くものが出てこないことを嘆いている。また、「自衛隊法第3条によって、自衛隊の任務が「我が国の平和と独立を守り」と規定されています。ブッシュに服従することのどこが国家の「独立」なのか。明らかに自衛隊法違反ですよ。」とも語っている。まことに同感だ。よくある議論として、「独裁制打倒」を評価するものに対しても、次のように真っ当な批判をしている。真正保守は、保守の陣営をひいきの引き倒しをするのではなく、あくまでも保守の原則に従って、自らを汚すような考えを持たないのだなと思う。「ゴロツキの難癖としかいいようがない。独裁国家は、何もイラクだけではない。私は独裁体制を変えるために介入すること自体を否定しないが、そのための段取りを踏むことが必要不可欠だと思う。独裁国の内部で反乱軍・レジスタンス(抵抗組織)を、「人道」という義に基づいて義援金や義勇軍で支援するのが先決ですよ。」目的が正しければ、手段が正当化されるわけではないという、ごく当たり前の論理が確認されているのを見て、こういう保守だったら、充分論理的な話が出来るのになと思う。イラクへの自衛隊派遣は、日米同盟という観点から、国益に資するのだという議論もある。これに対しても、実に論理明快な反論をしている。「アメリカが、このまま侵略を続けるなら国際社会から猜疑され、反発を喰らうでしょう。侵略に加担する日本も、世界、特にアジアから、「日本はアメリカの言うことを何でも聞いて、他国も侵略するような国なのだ」と見なされてしまう。このような状態は、明らかに国益に反します。 国が守るべきものは、国家の「安全と生存」よりも、「自尊と独立」です。「安全と生存」さえ守ればよいのであれば、アメリカの51番目の州にでもなる方がよいのではないか。「自尊と独立」の堅持のためにこそ、自主防衛すべしと私は唱えています。」こういう防衛論なら、僕も賛成だな。アメリカの横暴からこそ日本を防衛すべきだ。イラクの混乱した現状認識に対しても、卑劣なテロという言い方に対して、明快にそれを否定し、論理的に説明している。これも共感するところだ。「誤謬もはなはだしい。アメリカ軍が侵略した以上、それに対する抵抗は、「レジスタンス」と呼ぶべきです。アメリカがイラクを侵略したことで、テロリストに「大儀」が与えられました。テロを「不法の武力・暴力行使」と定義づけるなら、アメリカのやったことこそが、テロですよ。」これは、宮台氏が語っていた認識とほぼ重なるような感じがする。アメリカが、これだけひどいことをしているのだから、それに抵抗するのに、何をやっても50歩100歩じゃないかという感じになる。テロリストの側が何をしようと、アメリカがもっとひどいことをしているのだから、テロリストを非難なんか出来ないと言うわけだ。最後の憲法に対する姿勢も、真正保守の誇りを感じる言い方だ。憲法そのものに関する考え方は、おそらく僕とは違うだろうけれど、憲法改正に対するその姿勢は、とても共感するものだ。「ご承知の通り、私は憲法改正論者であります。改憲がタブー視されていた頃から憲法改正を唱え、私案も作りました。しかし、他国に侵略し、何十万にも及ぶ他国民の犠牲を利用して、改憲や憲法解釈を進めようとするのはならず者のやり方だ、と断言できます。他国民の犠牲を利用せずに自分たちの力でやれよ、と言いたい。そういう矜持が残念ながら、もはや自称・保守にはないんでしょうね。」今がチャンスだからと言って、他国民の犠牲を利用するなんて手段が姑息じゃないか、というこの心情は、イデオロギーを越えて共感するものだ。この西部氏の言葉を見る限りでは、これには耳を傾ける価値があると思える。今度、西部氏の著作を図書館で探してみようかと思いたくなった。そういうことを思わせてくれた記事だった。
2004.03.19
コメント(0)
-
「プライバシーの保護」と「表現の自由」
ワイドショーを見ていたら、週刊文春の出版差し止めの話題で様々なコメントが流されていた。それを聞いていたら、ちょっとおかしいのではないかという感じがしてきた。双方は、一般論的に言えば正しいことを言い合っているけれど、肝心のこの場合の、具体的な事実をもとにした妥当性については全く言及していない。一般論の範囲では正しいことを言い合っても、それは水掛け論になるだけではないか。まず、今回の出発点となるような事実を確認しよう。「田中元外相長女の記事掲載、週刊文春に出版禁止命令」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040316-00000315-yom-sociここで確認される事実は次のものだ。「17日発売の「週刊文春」(3月25日号)に掲載されている元外相、田中真紀子衆院議員の長女のプライバシーに関する記事を巡り、長女が発行元の文芸春秋に出版禁止を求めた仮処分申し立てについて、東京地裁(鬼沢友直裁判官)は16日、記事を削除しなければ出版・販売してはならないとする決定をした。」この決定に対しては、その判断が妥当であるかどうかという解釈がある。それに関しては、利害対立の当事者としては、当然正反対の判断があるわけである。「長女側の弁護士は16日、「公人たる政治家を親族・家族に持つ者であっても、憲法上、法律上、プライバシー権を享受するもので、地裁の決定は理にのっとったもの」とのコメントを出した。」「文芸春秋の浦谷隆平社長室長の話「記事では、長女の人権に十分な配慮をした。訴えには、誠意をもって話し合いを続けたい。しかし、言論の制約を意味する今回の仮処分決定は、わずか1人の裁判官が短時間のうちに行ったもので、とうてい承服できない」」この両者の解釈が、「この問題の場合」は、どちらに妥当性があるかを考えなければならない。優先されるべきは、あくまでも「この場合」という特殊な状況での判断だ。それから後に、一般論としての問題が生じてくるのであって、具体的な問題を判断するのに、一般論として言えることをそのまま適用するような論理は、論理の適用範囲を拡大するような論理の逸脱である。上の記事の中の両者の言い分で言えば、記事の具体的中身が、「プライバシーの侵害」に当たるかどうかという具体的検討が、判断の妥当性に大きくかかわってくる。プライバシーの侵害に当たるものであれば、田中氏の長女の側の言い分が正当であるし、プライバシーの侵害に当たらないものであれば、文春側の言い分が正当であると言うことになる。しかし、これは報道することが難しいものである。具体的な中身を報道してしまえば、プライバシーの侵害に当たる場合には、それを元に戻すことが出来なくなる。具体的な中身を報道せずに、その判断が正しいのだと言うことをどう報道すればいいだろうか。僕自身も、具体的な内容が分からないだけに、どちらの判断が正しいかと言うことは分からない。しかし、こういう重大な判断を伴う事柄であれば、双方に不利益が生じないような工夫をするべきだと感じる。たとえば、この判断が正しいかどうかを伝えるには、どうしてもその内容に触れなければならないのだから、報道される方が形式的には圧倒的に不利な状況におかれている。たとえ自分の言い分が通っても一部のプライバシーは侵害されてしまう。このように、形式的に一方が不利になる場合は、それを補う工夫が必要だ。この場合で言えば、プライバシーの侵害が結果として証明されるようなことになれば、少なくとも1億円を超える損害賠償を命ずるような前提が必要だろう。それだけのリスクを犯しても、文春の側はプライバシーの侵害ではないという自信を持ったときに、あくまでも出版をするという意志を表明すべきだ。会社にとってそれほど痛くもない損害賠償額であれば、争っても出版した方が得だという判断になってしまいかねない。争って負けた場合は、経営が傾くくらいの賠償額を課すべきだ。そうなったとき、大出版社と個人がようやく対等になるだろう。上の報道内容の中の、「言論の制約を意味する今回の仮処分決定は、わずか1人の裁判官が短時間のうちに行ったもの」という文春側の言い分は、具体的な内容を離れて、一般論としての形式面を強調したもので、これを出版差し止めの処分の不当性と主張するのには、僕は疑問がある。内容的に、出版差し止めがふさわしくないにもかかわらず、それがされたときに、それは「わずか1人の裁判官が短時間のうちに行ったもの」という批判に結びつくのだと思う。一人でやったのが悪いとか、短時間でやったのが悪いというのは、その条件に寄っているのだと思う。条件によっては、これは正当化される。週刊誌が出回ってしまえば、プライバシーの保護が出来なくなるのだから、急ぐ方がむしろ当然という考え方もあるのだ。内容が明らかにプライバシーの侵害に当たるゴシップ記事にすぎないものであるのなら、一人で判断したって間違いではない。問題の第一歩はまず内容にあるのだ。内容をどう判断したのかという報道がないと、議論はそれを飛び越えて、一般論として言論の自由とその弾圧の問題になってしまう。識者のコメントもそのようなものが多い。ワイドショーでは、なぜこのような論理面を指摘する人間がいないのだろうか。プライバシーと表現の自由は次のように定義される。プライバシー【privacy】 (1)私事。私生活。(2)私生活上の秘密と名誉を第三者からおかされない法的権利。 ひょうげんのじゆう【表現の自由】 自らの意見・思想・主張を外部へ表現する自由。憲法が保障する基本的人権の一。 内容が報道されていないので、これは僕の想像に過ぎないのだが、記事の内容は「私生活上の秘密」には間違いないだろうと思う。しかし、公人の場合は、私生活がそのまま公的な生活と結びついている場合がある。政治家の愛人スキャンダルなんてのは、そういう倫理観を持った人間が、政治家として正しい判断が出来るかという疑念を抱かせるとしたら、たとえ私生活上の問題でも、報道することの意味が出てくる。公人である場合は、プライバシーの権利を表現の自由が上回るケースもある。田中氏の長女の場合は、公人として報道する意味があるかどうかが争点になっているのではないだろうか。テレビの報道では、「将来政治家になるかもしれない個人の報道」という表現をしていたように感じた。将来性で表現の自由が主張できるものかどうか。そんなものは、将来本当に政治家になったときに報道すべきで、まだ政治家にもなっていない人間に対して、それが許されると考えるのは、論理的に見ておかしい。これでは、将来犯罪を犯しそうだからと判断して、今犯罪を犯していないのに拘禁することが許されるという論理と同じになってしまう。「出版禁止は暴挙だ 週刊文春問題で出版各社」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040317-00000191-kyodo-entこの記事には、出版者側の論理が提出されているので、それを批判しよう。「週刊文春の出版禁止問題で17日、週刊誌を発行する出版各社は「暴挙だ」「表現の自由を危うくする」などと、抗議の声明を発表した。」これは、中身の議論を抜きにした一般論なので、それだけでは、「表現の自由を危うくする」という意見に賛成することは出来ない。中身によっては、出版差し止めが当然だという判断も出てきてもいいはずだ。中身を議論せずに、結論だけを取り上げて、一般論で反対するというのは信用できない。中身を報道できないからだと言い訳したいかもしれないが、それだったら、具体性をうまく隠して、中身を検討したことを表明すべきだ。一般論に解消しようとする論理に僕は疑問を感じる。「問題の記事については「一私人のことで記事にする価値はないと思う」とみる週刊ポスト(小学館)の海老原高明編集長も、仮処分については「損害賠償請求で足りることであり、木を見て森を見ない暴挙」と批判する。」この意見は、かなり立場というものを感じる意見だ。記事そのものについては、「プライバシーの侵害」だと判断しているようにも見える。「一私人のことで記事にする価値はないと思う」と語っているからだ。それでもなお、これを「損害賠償請求で足りることであり」と判断するのは、出版者側の勝手な言い分だと思う。それなら、売れると言うことで勝手な記事を書くのではなく、プライバシーの侵害に当たることは記事にしないような、ちゃんとした自己規制が出来る出版業界にすべきだろう。それが出来ないから、権力の側の弾圧を呼び寄せるのである。損害賠償で足りるようにするためには、もしもひどい記事であった場合は、懲罰的な意味も込めて、1億円以上の高額賠償をさせるようなことも必要だろうと思う。「また光文社広報室も「公人か私人か、プライバシーの侵害か否かは公判で争われるべきだ。仮処分命令は、表現の自由を危うくする」とのコメントを発表した。」これも、プライバシーを侵害される方の感覚を失った、報道する側のおごりを感じるような意見だ。公判で争うのは、すでにプライバシーを侵害されたあとでなければ争えないのだ。プライバシーの侵害に当たるかどうかは、報道する側にしか判断をする権利がないというのだろうか。仮処分されるような報道をすることに出版者側が問題を感じない限り、このことは、権力の側の言論弾圧に利用されるだけになるだろう。「<週刊文春>販売差し止め仮処分に懸念の声」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040317-00000138-mai-sociここには、当事者である出版側の意見ではなく、学者として専門家の判断が載せられている。立場を離れているので、当事者よりも客観的な判断をしているように思われる。共感できるものは多い。それでも僕は疑問に感じるところもあるけれど。「上智大の田島泰彦教授(メディア法)は「裁判所は、田中真紀子議員の長女が純粋な私人で、プライバシー性の高い内容と判断して差し止めを認めたのだろう」と推測する。一方、「最高裁はプライバシーの侵害だけを理由とする差し止めはまだ認めていない。検閲につながりかねない問題であり、重大な要件を課さない限り、差し止めは認めるべきではなく、今回のケースも詳細な検証が必要だ」と問題点を指摘する。」これは妥当な指摘であり、この問題の受け止めとしては、まず共感できる意見だ。「立教大社会学部の服部孝章教授(メディア法)は「東京地裁がどういう理由で差し止めを認めたのか分からないが、記事の内容がプライバシーの侵害であることは間違いなく、出版後に裁判で争っても、文春側は負けると思う」と指摘する。その一方で「ただ、これで差し止めを認めるのは疑問が残る。原告側にとっても、今週号は流通ルートに乗っているうえ、大手出版社の週刊誌の差し止めとして話題になることで、訴えの利益はあまりないのではないか」という。」これも妥当な判断だと思う。問題は、「記事の内容がプライバシーの侵害であることは間違いなく」という判断が、妥当であるかどうかと言うことだ。上の文章の全体の論理的な印象から言えば、この人の判断を信用してもいいのかなと感じる。服部孝章教授が言うように、プライバシーの侵害だけで差し止めたのではなく、具体的にどのような要件が重視されてこの判断に至ったのかがちゃんと報道されるべきだろうと思う。掲示板に続きがあります。
2004.03.18
コメント(3)
-
スペイン総選挙の結果とイラク戦争・列車爆破テロとの関係
スペインから大きなニュースが飛び込んできた。このところ憲法に関する記述が多かったので、ニュースのストックがかなりたまっていたけれど、見過ごしておけない大きなニュースが飛び込んできた。「スペイン総選挙、野党・社会労働党が第一党に」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040315-00000402-yom-intというニュースだ。このニュースがなぜ大きな意味を持つかというと、この報道にも次のようにあるとおり、「事前予測ではイラク戦争を支持した与党有利だったが、投票3日前にマドリードで起きた列車同時爆破テロをめぐる国民の不安が与党批判に回る結果となった。」と、イラク戦争に対するスペインの世論の意思というものを表していると思われるからだ。この結果をどう解釈するかというのは、イラク戦争を、世界の世論がどう見ているかというものを解釈するときに、非常に重要になる。その世界の世論から、改めて日本の世論を見直すことによって、日本の現状をより深く考えることも出来るだろう。上の選挙の事実をどう解釈するかは、いくつかの報道がある。「スペイン総選挙の与党敗北、連続爆破事件で形勢暗転」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040315-00000537-reu-intこの記事によれば、列車爆破事件というテロが、選挙の際の世論を作るのに大きな影響があったと解釈している。「アナリストらはすでに、スペインがイラク戦争を支持したことへの報復などとするアルカイダと称する組織の犯行声明を有権者が信じれば、事件前の世論調査では優勢だった国民党が打撃を受ける可能性がある、と警告していた。」続報では、このテロはアルカイダのものだと言うことがほぼ確定されたように感じるが、アルカイダの報復だとしたら、どうしてイラク戦争を支持していた与党が打撃を受けるのだろう。テロそのものは、死に値する罪を犯したのではない人間を殺戮するのであるから、明らかな犯罪的行為である。だとしたら、テロを起こした犯人をまずは非難するのは当たり前のことだ。それがどうして与党批判にまでつながるのだろう。ここにはどういう論理的・感情的なつながりがあるのだろうか。スペインの国民感情としては、テロを呼び込んだのは政府のイラク戦争支持の姿勢に一番の問題があると受け取っているのではないだろうか。テロは非難すべき犯罪だが、このままイラク戦争に対して態度を変えない限り、またテロが起こるという懸念を国民の多数が抱いているのではないだろうか。またテロが起こるというのを、イラク戦争に対する態度を変えれば避けられるのなら、その方向を選ぼうというのが世論の方向だったのではないだろうか。また、イラク戦争そのものに対しては、はじめからスペインの世論は反対だった。だから、その態度を変えることは、テロに屈して変えるのとは違う。まずは、これ以上テロを呼び込まない道の選択を選んだ。そして、そのあとでもっとよく考えていこうという道を選択したのだと僕は解釈した。僕の解釈が正しいとは限らないけれど、スペインでイラク戦争反対を掲げる野党が選挙に勝ったという事実は、イラク戦争を深く解釈しようとスペイン国民が考えていることの意味の大きさを感じるものだ。「マドリードのある大学の学長は、「政府はイラク戦争への関与、アスナール首相のブッシュ米大統領やブレア英首相との関係に対する代償を支払った。投票結果は、これに対する反応だ」と指摘する。」この言葉の解釈は、世論の反対にもかかわらず、スペイン政府はイラク戦争支持の道を選んだのだから、そのことによってその後の歩みが、国民が正しいと受け取れる道に行っていれば、世論に反対したにもかかわらず政府の選択は正しかったと言えただろうが、結果としてこのようなテロが起こったと言うことは、政府の選択は間違っていたと事実が証明してしまった、と言うものだ。それが、イラク戦争支持というものが負ったリスクであり、代償を払ったと言うことなのだろう。「世論調査では、国民の90%がイラク戦争に反対との結果が出ている。」これだけの反対を押し切るのであるから、科学的真理と同じくらいの明らかな真理性がない限り、何らかの事件が起きたときには、そのリスクの代償を払わざるを得なくなるだろう。「アルカイダの犯行と断定 列車テロで米政府高官が明言」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040316-00000014-kyodo-intと言う報道を見ると、テロはアルカイダの犯行であることがほぼ固まっているのではないかと思う。この事実の解釈は、テロを政治的メッセージとしてどう受け取るかという問題と、この事件をきっかけとして部隊を撤退することがテロに屈したことにならないかどうかと言う問題がある。テロの政治的メッセージの面としては、一般市民を含む多くの人が犠牲にされたと言うことは、アルカイダにとっては、スペインの国全体が敵だと言うことを表明したメッセージだと感じる。かつて、ベトナム戦争の頃も、解放戦線の「テロ」と呼ばれるものがあったそうだ。それは、南やアメリカの協力者である、解放戦線に対しては「裏切り行為」をした人間を敵として処刑するという「テロ」だった。だから、「裏切り行為」をしない、敵でない人間は「テロ」を恐れる必要はなかった。そういうメッセージを含んだ「テロ」だったと僕は思う。アルカイダに敵だと宣言されたとき、それにあくまでも立ち向かうという立場もあるだろう。「テロに屈しない」という道だ。しかし、本来は敵ではないのだと、理解を求める道もあるだろう。それは、アルカイダを、単純な犯罪集団ととらえるのではなく、政治的に交渉の出来る相手として考えることを意味する。そういうふうに考えることは、テロを容認することでけしからんと言う人もいるかもしれないけれど、あくまでも敵として対峙したら、アルカイダを壊滅させない限りその戦いは終わらない。その覚悟で、このメッセージを受け取るのだろうか。アルカイダの方は、テロをする以外にはもう道が残されていない。あくまでも敵対すれば、今後もテロは続くだろう。それでは、テロを防ぐために、アルカイダを全滅させるという可能性はどのくらいあるのだろうか。アフガニスタン全土にミサイルを撃ち込めばアルカイダは全滅するのだろうか。その可能性はきわめて低いような気がしてならない。アルカイダは、常に生命の危険のある状況で生きているが、彼らは命を落とすことに恐れはない。もっと大事なものを守る意識があるからだ。これを狂信と呼ぶことも出来るが、命がけで攻撃を仕掛けてくる人間を敵にしなければならないと考えなければならない。それを迎える、たとえばスペインの一般民衆の側には、それは民主主義を破壊する行為であるから、断固として自分たちも命をかけて戦うのだという覚悟をすることが出来るだろうか。そんな戦いで命を落とすことはいやだと言っても、非難できないのではないだろうか。かつて、国家が社会を支配する体制を持っていた時代だったら、個人的にこのような戦いはいやだと思っても、国家は戦いを強制してきただろう。しかし、民主主義の発達によって、多くの個人がいやだと表明したら、国家が無理矢理戦争をすることが出来ない時代になったと、スペインの総選挙の結果を解釈することも出来る。もし、イラク戦争支持をやめるのなら、アルカイダが攻撃してこないと言うことであれば、イラク戦争支持をやめたいと思っても、これは政治的判断として間違ってはいないと思う。イラク戦争支持をやめても、なおかつアルカイダの攻撃があるようであれば、それはイラク戦争に関わりなく、自国の防衛という点で国民が立ち上がる必要があるだろう。ここら辺は、政治的な駆け引きの問題だと思う。果たしてどちらを選ぶだろうか。道徳や倫理の問題ではなく、あくまでも政治的判断の問題だと思う。「スペイン爆破事件、イラク戦争と関連させるのは誤り=英外相」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040315-00000596-reu-intこの記事によれば、イギリス政府としては、「イラク戦争を支持したことと、アルカイダなど武装勢力による攻撃を結びつけるのは誤りだ」と考えたいらしいが、この解釈に賛成する人はどれくらいいるだろうか。百歩譲って、イギリス政府に賛成できる点を探すと、「もし、アルカイダの関与が明らかになれば、イラク戦争を支援したためと早急に結論づける者もいるが、それは完全な間違いだ」の中の「早急」という点に妥当性を見ることくらいだ。もっと確固とした証拠を固めなければならないという点で、急いではいけないだろうが、やがてはアルカイダとの結びつきが結論されるだろうというのが僕の解釈だ。「1つだけはっきりしているのは、強固に阻止しない限り、アルカイダはイラクにおける無差別な戦争を今後も続けるということだ」と言う解釈にも僕は賛成できない。イラクにおける無差別な戦争は、アルカイダが一方的にやっているのではなく、むしろ米軍をはじめとする占領軍が行っている無差別な戦争に対するカウンターであるという解釈の方が妥当なのではないだろうか。自分たちの無差別攻撃を棚に上げて相手を非難しても、それは説得力がない。しかし、イギリスがこのような解釈をしたくなる状況は理解できる。スペインの総選挙に関しては、次のような解釈がきっと妥当だと思うからだ。「<スペイン総選挙>「米国有志連合」の各国政権に痛手」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040316-00002094-mai-intここでは、「とくにブレア英政権はEU運営で仏独の連携を封じ込めるため築いたアスナール政権との協力関係が崩れ、都合の悪い情勢になってきた。」と語られている。ヨーロッパでは、政府はイラク戦争を支持しているけれど、国民の大部分はそれに反対しているという国がたくさんあった。スペインの結果は、それらの国の国民に大きな影響を与えるだろう。翻って、我が日本では、この影響はどういう形で出てくるだろうか。日本でもかなり多くの人が、イラク戦争そのものには反対していた。これは正当性のない戦争だからだ。しかし、日米同盟という点から、心ならずも支持せざるを得ないという状況を仕方がないと受け止めている人も多い。ヨーロッパの国々とはちょっと状況が違うかもしれない。韓国の立場とちょっと似ているだろうか。スペインの列車テロは、総選挙直前に行われたという意味を考えると、その影響を計算したアルカイダの犯行である可能性が極めて高いとも言われている。日本では、今年行われる参院選が、政権を維持するという方向で大きな意味を持っている。アルカイダが同じように、テロに意味を持たせるとしたら、参院選前が危険なのではないかという指摘もあった。今回は列車がねらわれたが、列車というのは、改札を通るときに金属探知器をくぐらせるのも難しいし、テロ防衛策がほとんどとれそうにない。参院選前の危険に関しては、一般市民はかなり強く意識しなければならないのではないかと僕は感じる。
2004.03.16
コメント(3)
-
「論座」の憲法論 90年代以降の改憲論
昨日の日記で紹介した愛敬さんの文章で、90年代以降の憲法論の事実と解釈を引き続き見ていこうと思う。まず事実の指摘は次のものだ。91年の湾岸戦争を契機として、「「国際貢献」の名の下、ペルシャ湾への掃海艇派遣、PKO等協力法の成立と自衛隊の海外出動態勢が整備され、また、政治改革論議の頃には「国際貢献」や「解釈上の疑義をなくす」という観点からの9条改定論が提唱された。」この事実から導かれる解釈は次のものである。「90年代改革のキーワードは「国際貢献」である。たとえば、94年の読売改憲試案は、国民主権の規定を第一条に置いたり、大陸型憲法裁判所の設置を提言したりと、復古的・権威的な改憲論者以外の市民にも改憲の必要性を訴えようとするものだったが、やはりその主眼は「国際貢献」論に依拠する9条改定だった。」僕も、この解釈にほぼ賛成するのだが、そう考えると、今までの「押しつけ憲法論」とか、「長い間変わらなかったから」とか言うような、単純な論理では国民を説得できないと言うことに、改憲論者の方でも気づいたということなのかなと思う。「国際貢献」を持ち出せば、それ以前の理由よりも説得力を持つことは確かだ。しかし、この改憲論も頓挫した。その頓挫した理由の解釈は次のものだ。「ところが、読売改憲試案は不発に終わる。景気対策や行政改革などもっと目先の政治課題が多数あったこともその一因であろう。しかし、95年の沖縄少女暴行事件をきっかけにして国民の間に広がった日米安保条約に対する不信感を前にしながら、日米安保をグローバル規模の軍事同盟へと転換することをもくろむ「日米安保共同宣言」とそれに基づく「新ガイドライン」実施のための法整備(周辺事態法の制定)を実現するためには、時間と手間がかかり、おまけに国民投票というハードルまである憲法改正ではなく、「解釈改憲」ですまそうという便宜的な判断が政府にあったからだと考えられる。」全くその通りだなと思う。それから、この文章は最後を「考えられる」という言葉で結んでいるが、これは、論理的に考えを進めていけば、そういう結論に至るだろうと、僕もそう確信したときは「考えられる」という言葉を使うことが多い。そこまでの確信が得られないときは「思う」という言葉を使うことが多い。これは、「思う」だけなので反対の考えがあるかもしれないなと感じるときに使う。これは、事実として確かだと思ったら、「思う」も「考える」も使わない。その時は断定するような言葉、たとえば「である」というようなものを使う。さて、現在の改憲論については愛敬さんはどう書いているだろうか。まず現状認識としての解釈は、「政治改革の「成果」である小選挙区制の導入、そして社会党の「現実主義」化と凋落は、改憲実現の絶好のチャンスを提供した。このような状況下で改憲派が再び張り切り始めたのが現在の政治状況と言える。」と、とらえている。しかし、現在の改憲論そのものについては、愛敬さんは次のように受け止めて解釈している。「00年1月に両院の憲法調査会が活動を開始し、論壇でも改憲論議が再び活発になった。とはいえ、この時期の改憲論は、「改憲さえすれば、世の中が良くなる」式の全く政治的思慮を欠いた議論も少なくなかった(佐柄木俊郎「改憲幻想論」(朝日新聞社)を参照)。」これも全く同感だ。こういう風に受け止めていた人が多かったせいだろうか、愛敬さんは、「改憲論はしばし休止する」という判断をしている。それはなぜかという解釈が、また共感できるものだ。「なぜなら「9.11事件」という「千載一遇のチャンス」を利用して自衛隊の戦地への派遣を実現する一方、「テロ」への国民の恐怖が持続するうちに、「防衛秘密」保護規定(自衛隊法96条の2,122条)の導入や「有事」法則の整備をする必要がある以上、9条改定という手間をかけるわけにはいかなかったからだ。」この解釈を取ると、政府の側の改憲論は、論理的な原理・原則を大事にしたものではなく、手段としての改憲論に過ぎないと言うことも解釈できる。これは政府の立場としてならよく分かる。その方が利益としては大きいだろうから。しかし、これは庶民の利益とは対立するだろう。だから、僕は、そういう軍事的行動の拡大のための手段として使われる憲法「改正」には反対だ。僕の解釈が事実に近いのではないかと思うのは、愛敬さんの判断も同じような方向にあるからだ。僕よりも、もっと多くの事実から判断できる専門家が、同じような方向を考えているというのは、とても勇気づけられる。次の言葉にそのようなものを感じる。「繰り返すが、現在の改憲の目的の核心は、9条改定によって、自衛隊を正真正銘の軍隊と認め、さらには集団的自衛権の行使を容認して、海外での軍事行動を可能にする点にある。」「海外での軍事行動を可能にする」手段として改憲を論じてはいけないのである。その前に、自衛隊を軍隊と認め、集団的自衛権を行使すると言うことの意味を、もっと深く考えなければならないのである。無原則に容認を前提してはいけない。どのようなときに容認し、どのようなときに容認しないかをはっきりさせて原則を確立することの方が先だ。それが出来てから、現実に改憲の方向へ進むべきだ。現在の改憲論も、「国際貢献」を掲げているように見えるが、一方では、愛敬さんの次のような事実の指摘は、別の解釈を持たせるような感じもする。「しかし、現代改憲論の特徴としては、経済界からも集団的自衛権に関する政府解釈の変更や9条改定の要求がシリアスなものとして提言されるようになった点を挙げたい。経済同友会の意見書のまとめ役を務めた高坂節三(柴田工業顧問)は、集団的自衛権の行使を熱烈に擁護するが、注目すべきなのは、「グローバル化とは、日本の資本や人材が世界中に広がっていくこと、これを守るためには何らかの方策が必要だ。だから米国と提携するのだが、ここだけは自分がやる、というところがないといざというときも言いたいことが言えない」と述べている点だ(朝日新聞03年5月27日)。「ここだけは自分がやる」というのは、将来、自衛隊をアジア諸国に単独派兵させることの含みさえ疑わせる発言である。」この方向は、国際貢献とは違うなと僕は感じる。これは、「自衛」という概念の拡大解釈を生じさせる恐れのある考え方だ。海外に存在する「日本(施設的にも人的にも)」を守るために、軍隊を派遣すると言うことも「自衛」に入りかねない。これは、かつて来た道ではないのか。海外に存在する「日本」が損害を受けた場合は、それはまず「犯罪」としてとらえるべきだと思うが、「自衛」にまでエスカレートしてしまうと、「侵略」まではもう一歩行きすぎただけで行ってしまう。現在の改憲論の底に、このような考え方があるとしたら、国民はそれに充分気をつけなければならない。これは、妄想ではなく、愛敬さんは次の事実を指摘して、現実の話なのだと注意している。「「9.11事件」への「報復」として米国がアフガニスタンを空爆している最中、改憲に熱心な「読売新聞」は「国民の生命、財産を守ることは、国家の根幹的な責務だ。日本自身が国際テロの標的になれば、今回の米国と同様、個別的自衛権を発動していいはずだ」と論じた(01年10月14日)。日本も米国・イスラエル並みの「先制的自衛権」を行使すべきと平気で論じる人々が9条改定の推進派でもある事実は、軽視して良い問題ではない。」「今、何を考えるべきか」という最終章での愛敬さんの次の主張は、僕も全く同感だ。「9条改定の是非に関する議論は、このような改憲派のもくろみを踏まえて成されるべきだ。私自身は日本がこのような「普通でない国家」になることに反対だが、国民の多数が日本をそんな国家にしたいのであれば、それも一つの選択だろう。」「普通でない国家」というのは、「先制的自衛権を行使する国家」のことを指す。そんな国は、世界中でアメリカとイスラエルしかいないのだから、「普通でない国家」だ。また、多数が選択したのなら、その選択は尊重するという姿勢は、民主主義を尊重する姿勢で、これも僕は全く共感するものだ。ただ、国民が重要な選択をするということなら、次のことは大事だろうという愛敬さんの指摘は、多くの人に考えて欲しいと思うものだ。「そうであるならば、国民はその覚悟を決める必要がある。「とにかく議論をしてみよう」という「改革タブー打破論」や、小泉発言のように「自衛隊が軍隊である事実を認めよう」式の議論は、改憲論の真の目的を隠蔽するための煙幕に過ぎない。この手の9条改定論に安易に乗って、「真の選択」をしないままの選択をしてはならない。」このあと、愛敬さんは、現在の改憲論の、真の目的を隠蔽している構造をいくつか指摘して、注意を促している。これも大変重要なものなので書き残しておきたいが、今日も充分長くなったので、これは明日に回そう。改憲論議に対して、良心的に反応しても、相手の裏を読まないと、その良心的な反応を悪用される恐れがあると愛敬さんは指摘している。改憲論議がおかしいと思っている良心的な人には、大変重要な指摘だと思われる。明日紹介しよう。
2004.03.15
コメント(0)
-
「論座」の憲法論 憲法論議の歴史
「論座」2月号には、名古屋大学助教授の愛敬浩二さんの「9条改定論の変遷と現在」という文章がある。これは、憲法論議の歴史という点で参考になる資料だと思った。この中から、資料的価値があると思われる事実に関する記述を引用しよう。まずは次のことは僕は事実だと思うのだけれど、解釈だと受け取る人もいるだろうか。「改憲派が改憲論議を促すのは、特定の内容の改憲に利益を見いだすからこそである。他方、護憲派もただやみくもに「未来永劫、改憲はだめ」などと反対してきたわけではない。護憲派の市民・政治家・学者は、特定の政治状況の下で特定の内容の憲法「改正」に反対してきた。」もちろん、護憲派の中には、非論理的な「絶対反対」のものがいたかもしれない。しかし、それはすべてではない、というのが上の論理的主張の内容だ。「護憲派」といえば、そういうものしかいないというイメージは事実として間違っているという主張だというふうに僕は受け取った。護憲派は、改憲派の、特定の議論に反対してきたのであって、憲法論議は、未だに全体を包括した議論になっていないというのが事実ではないのだろうか。昨日の日記で引用したヒールシャー氏の主張のような改憲論議というのはなかったのではないだろうか。少なくとも、改憲論議での主流ではなかったと、それが事実であると指摘しているように僕は受け取った。愛敬さんは、歴史的事実として次のものをあげる。「52年10月の保安隊発足、54年3月の日米相互防衛援助協定(MSA協定)締結、そして54年6・7月の防衛庁設置・自衛隊発足へと日本の再軍備は進展し、憲法9条との矛盾は深まった。」これは、最後の「矛盾は深まった」ということが、ある種の解釈ではあるが、この解釈に反対する人が誰もいなければ、これを含めて事実の指摘と考えていいのではないかと思う。この事実に対して、愛敬さんは次のようにこれを解釈する。「このように軍隊としての内実を持ち始めた自衛隊をいかに正当化するか。改憲派はこう考えた。講和条約によって日本は「独立」したのだから、改憲が可能になった。これはもっともすっきりした解決方法だ。その際には「押しつけ憲法論」を駆使し、「自主憲法制定」で国民の「愛国心」に訴えることにしよう。」これを僕が「解釈」と受け止めるのは、考えたことの内容は、事実として指摘することが出来ないからだ。脳みその中を直接見ることが出来ない。だから、考えたことは想像するしかない。想像するしかないことは解釈するしかできないからだ。これが、もし改憲派の誰かが、直接残している言葉を提出しているのなら、それは事実になる。しかし、上の文章にはそれは提示されていない。だから、上の文章を見る限りでは、これは解釈なのだと思う。そして、解釈である以上、これは正しいか正しくないかを決めることは出来ない。妥当性があると思って賛成するか、妥当性はないと思って反対するか、どちらかの選択があるだけである。この解釈の主張だけが述べられているのなら、論証なく、自分の考えを提出しているだけなのだが、愛敬さんは、次のように、この主張の根拠となる事実を提出している。論証というのは、このようにしなければならないのだと僕は思う。「たとえば自由党の「日本国憲法が全面改正を要する理由」(54年11月)は、憲法制定時期が外国軍の占領下という異常事態で、国民の自由な意思を反映しておらず、政府も天皇の一身上の安全のために受諾を強制されたと主張した。」この事実から、改憲派の考えを推論したのである。この推論に妥当性を感じれば、解釈に賛成できる。僕は、この論証を受け入れたいと思う。賛成だ。この「押しつけ憲法論」という解釈には、僕は反対なので、その反論の根拠になるものを書いてくれていると助かったのだけれど、残念ながら、その参考になる事実はこの文章には見つからなかった。事実は、この「50年代改憲論は頓挫した」というものだった。実際に改憲はされなかったのだから、頓挫したというのを事実として受け取っていいだろうと思う。これがなぜ頓挫したかという解釈としては、愛敬さんは次のように語る。「50年代改憲は復古主義的色彩の強いものだったが、この復古的改憲を止めたのは、基地拡張反対闘争や原水爆禁止運動のような国民的平和運動の高揚であった。」これは、頓挫させた原因は、表面的にはいろいろ考えられるかもしれないが、もっとも本質的・根本的に重要なのは、「国民的平和運動の高揚であった」と解釈している。そして、この解釈の根拠となる事実は次のようなものだ。「平和運動はこの時期に広範な民衆的基盤を獲得していく。世論調査において再軍備のための改憲に反対する回答が増加し始めたのも、社会党の議席が激増したのも、まさにこの時期である。」これは、もう少し丁寧に事実を提出するとしたら、1次資料としての世論調査そのものを提出するということになるだろう。しかし、雑誌論文ではそこまではしなくても充分だと考えたのかもしれない。もし、現実的根拠なく、うる覚えや記憶違いでこんなことを書いたら、学者としての存在基盤を失いかねないので、明確な1次資料として提出されてはいなくても、僕はこのことが事実であることを信頼する。これだけ論理的に文章を展開している人が、事実の提出に関してずさんなことはしないだろうという信頼だ。57年8月に英米法学者・高柳賢三を会長として活動を開始した政府憲法調査会に関する事実としては、次の事柄が参考になりそうな気がする。「調査会での調査・審議が進むにつれて改憲論議は拡散し、高柳会長のように「9条は政治的マニフェストに過ぎない」という立場から9条改正不要論を主張するものまで現れた。最終報告書は結局、改憲の可否に関する調査会の統一見解を示すものにはならず、押しつけ憲法論についても、委員間の意見対立を反映して、「制憲過程は複雑であり、日本国憲法が強制されたものか否かについても事情は決して単純ではない」という曖昧な評価に終わった。」この憲法調査会の資料を見たら、押しつけ憲法論の反対の論拠というものの参考になるかもしれない。このあと改憲論は下火になったらしい。事実としては次のものの指摘がある。「池田勇人首相は、63年の総選挙の際に「私の在任中は改憲をしない」と明言し、その後の歴代内閣も改憲に消極的なスタンスを取った。」これがなぜかという解釈は、愛敬さんは「政府が「解釈改憲」を採用したことにある」と見ている。解釈改憲に関しては、「憲法の文言を変更することなく、憲法解釈を濫用して違憲の事態を正当化すること」と定義している。この定義によって解釈すると、「具体的には、政府は9条の文言には何ら手を加えずに、「自衛のための最小限度の実力の保持は合憲」という政府解釈を駆使して、自衛隊の増強や安保条約の軍事同盟的性格の強化といった明白な9条違反を正当化したのであった。」というふうに語っている。また、このことを別の角度から解釈する次の主張に、僕は賛成する。「立憲主義の観点からして、このような「解釈改憲」を許容し得ないのは当然だ。しかし、ここで問題にしたいのは別の点である。すなわち、「解釈改憲」は政府が自発的に採用したのではなく、国民の平和意識・憲法感覚の一定の定着と平和運動の高揚を前にして、政府が余儀なく採用したという論点である。」政府は、本音としては憲法改正をしたかったが、それは国民の支持を得られないと判断して解釈改憲の方向を取ったという解釈だ。これは妥当な解釈だと思う。「80年代における改憲論の復活」と中身だしの付いた部分では、この復活を、「アメリカの経済力が相対的に低下すると、アメリカは日本に応分の軍事負担を求めるようになる、いわゆる「安保ただ乗り」批判である」という解釈をしている。そして論理的には、「他方、日本企業が多国籍化し、政情不安な地域にも進出し始めると、自衛隊の海外出動が支配層の課題とされる。しかし、「自衛のための最小限度の実力」という政府解釈では、自衛隊の海外出動を正当化しがたい。そこで、80年代に改憲論が復活する。80年代改憲論の目的も9条改定にあった。」と分析している。妥当だと思う。そして、この改憲も実現しなかった。その理由は次のように述べられている。「なぜ80年代改憲は失敗したのか。渡辺治によれば、その理由は次の4点に求められる。1,平和と現状維持を志向する国民意識、2,戦後政治の構造(保守政治家の戦争体験、後援会政治を通じて選挙民の意識が政治に反映されること)、3,「現実主義」化を拒否する社会党の存在、および4,アジア諸国の反発と警戒である。要するに80年代改憲論は「戦後政治の抑止力」を乗り越えられなかったと言えよう(渡辺治「政治改革と憲法改正」(青木書店)を参照)。」これは、愛敬さんも引用として引いているものだが、これにほぼ賛成するから引用しているのだろう。僕は、この内容をすべて理解できていない(事実として確認できていない部分がある)から、好意的には受け取るけれども、解釈に全面的に賛成というまではまだ行かない。よく調べれば、賛成するのではないかと思う。長くなりすぎたので、90年代以降はまた明日にしようかと思うが、愛敬さんの文章の冒頭に書いてある、今の改憲論への疑問と問題点指摘には、非常に共感するところがあるので、最後にそれを引用して終わらせることにしよう。「現代改憲の目的の核心は、憲法9条を改定して(具体的には9条2項の削除)自衛隊を明確に「軍隊=国軍」に位置づけ、さらに集団的自衛権の行使を正当化することにより、海外での軍事行動(=戦争への参加)を可能にすることにある。よって、現在の政治状況の下で9条改定を議論するならば、1,戦争に狂奔する現在の米国と「同盟」関係にある(そして外交面での「対米従属」が深刻な)日本が集団的自衛権行使に踏み切れば、日本のみならず国際社会全体にどんな結果を招くのか、あるいは2,改憲によって東北アジア地域にいきなり「フリーハンドの軍事大国(憲法的拘束がなければ、自衛隊は強大な軍隊である)が出現した場合、地域の安全をかえって損ないはしないか(たとえば中国等の軍拡の理由にならないか)などの問題を考える必要がある。従って、「自衛隊は国軍だ。改憲してこの事実を明確にしよう」とか、「非武装中立など無責任だ」という発言ほど、無責任な発言はない(小泉首相の発言。朝日新聞03年11月3日)。9条改定は「真空状態」で行われるのではない。様々な利害と思惑が錯綜する現実の国際社会を舞台にして行われるのだ。この当たり前の事実を軽視してはならない。」憲法を論理的に考えて改憲を考えることは大事なことだが、そのための前提となることがまだ不十分だろうという指摘として、僕はこの主張を受け取った。
2004.03.14
コメント(0)
-
「論座」の憲法論 共感できる改憲論
「論座」の2月号に、ドイツ人ジャーナリストのゲブハルト・ヒールシャー氏のインタビュー記事が載っている。その表題は、「集団的自衛権行使を認めて大人の国になれ」というものだ。この表題だけ見ると、いわゆる「護憲派」と呼ばれる人は腰が引けてしまうかもしれないけれど、中身を読んでみると、これが実に論理明快で正当な主張に満ちている。ほぼ全面的に賛同したいくらいだ。ヒールシャー氏には、素晴らしいジャーナリスト感覚が生きている。まずは次の引用から感想を書いていこう。イラクへの自衛隊派遣をどう解釈するかというもので、全くその通りだと思う。「小泉さんは「日本は戦争をしにいくのではない、人道支援、復興支援が目的だ」と言っていますが、主観的にはそうでも、イラク戦争は今も終わっていません。イラクの人々は、当然アメリカの占領政策の応援のために送られてくると受け止めます。 アメリカは自衛権の行使ということでイラクを攻撃したわけですが、日本の自衛隊派遣は集団的自衛権を行使して、これを支えるものであり憲法違反です。同じことはアフガン攻撃に際してのインド洋上での給油活動についても言えます。あれも憲法違反です。」憲法違反であるかないかは、法律解釈の問題だが、法律というのはきわめて論理的に構成されているので、実はその解釈もかなり論理的に進めることも出来る。そういう意味では、上の「自衛隊派遣の違憲性」に関する論理の展開は、実に明快で納得のいくものだ。アメリカの先制攻撃に対する反対論も、明快で、僕は全面的に賛成だ。「フセインのような独裁者は世界中にたくさんいます。そういう政権は武力で打倒していいか、と言えば決してそうはならない。ドイツのシュレーダー首相は仮に国連安保理が攻撃を承認しても、大量破壊兵器を持っているという明白な証拠が示されない以上、イラク攻撃は支持できないと言いましたが、私も同じ考えです。」そして、次の改憲の提言は、「なぜ改憲なのか」ということに、明快に論理的に答えているという点で、僕は賛成するし共感するのである。「憲法がある以上、憲法の枠組みの中での支援にとどめるべきです。このような憲法違反をいつまでも続けるべきでないとしたら憲法を改正すべきです。」これは、ちょっと聞くと、現状が憲法にそぐわないのだから、現状に合わせて憲法を変えるべきだという主張に聞こえるかもしれない。しかし、その前提が違うことに注意したい。ヒールシャー氏は、あくまでも現実の自衛隊派遣は憲法違反であるという認識に立っている。だからこそ、論理的整合性を取るために憲法改正が必要だという主張なのである。現実の自衛隊派遣が憲法違反ではないという認識に立つのなら、論理的な改憲論ではなく、現実追随の、論理的根拠のない改憲論になるのだ。だいたい、憲法違反でないのなら、どうして憲法を変える必要があるのだろうか。ヒールシャー氏の次の憲法に対する感想は、外から見た日本の憲法の姿を知る上でとても参考になる。「外から見ると、今の日本の憲法は信用できない。戦力は持たないといいながら自衛隊を持っている。これでは外国から信用されない。自衛隊は憲法で認めるべきです。」この文章だけを取って論じられると困ってしまうのだが、あくまでも論理的整合性を取るために、自衛隊の存在を認めるべきだということで、それは「自衛」という言葉を拡大解釈させない方向で認めていかなければならない。日本の平和主義に対する次の言葉も大変示唆に富んでいる。「それはもちろんそうです。動機は大変けっこうです。侵略戦争は絶対に許されません。国際紛争の解決のために武力を行使しない、という9条1項の趣旨は、改正後も何かの形で残すべきだと思っています。 一方で、国連決議などを条件に、各国共同で軍事力を使わなくてはならない場面もあると思います。そういうときのために、軍事力を外国で行使する条件を前もって厳格に決めておかなくてはならない。ところが、今は憲法解釈の幅があまりにも広がってしまいました。だから、イラクへの自衛隊派遣のように、憲法上、本来出来ないことまで、出来ることにされてしまっている。」平和主義と憲法改正の問題との関係で、これだけ明快に論理的に説明した文章を、僕は今まで読んだことがない。「自衛隊派遣が出来るように」憲法を改正するという論議ばかりだったが、本来は、「どこから先は出来ない」ことなのかを明確に記述するのが憲法改正であるべきなのだ。次の憲法観も、僕が感じていたものと全く同じだ。「憲法を改正して、どこまで認め、どこから認めないか、もっとはっきりさせるべきです。そしてそれを例外なく、きちんと守るべきです。解釈次第で、しかも守らないというのでは国の最高法規である憲法にとってよくありません。」最高法規を尊重しないで、どうして法治国家と呼べるかということだ。次の憲法の具体的中身も、非常に貴重な助言として受け止めたい感じもする。「自衛隊の存在も、解釈で容認するのではなく、条文で規定すべきです。海外での軍事行動については、国連決議があって、国会で過半数が--3分の2以上でもいいかもしれませんが--賛成したら参加できるけれど、そうでなければ出来ないとか、日本単独での行動は許さないとか、先制攻撃には参加しないとか、具体的に規定する。それに、武器輸出三原則や、「持たず」「作らず」「持ち込ませず」の非核三原則も盛り込んだらいい。 多くを解釈にゆだねるような憲法では、強権的な政治家が登場して、勝手に解釈する危険を免れません。それならはじめから憲法で、変なことが出来ないように、具体的に、厳しく縛りをかけておく方がいいんです。」全く素晴らしいアイデアだ。憲法改正がこのような方向で進むのなら、僕は改正に賛成する。逆に言えば、この方向でない改正だったら、僕は反対だということだ。賛成も反対も、無条件のものはあり得ない。常に条件付きで賛成であり、反対なのだ。最後に、アメリカの不当な要求に対して「ノー」というために、ドイツの経験を語りながらの助言がある。これも、本当にその通りだなあと感じるものだ。「ドイツはドイツ単独ではなく、EU(欧州連合)の一部だから言えるんです。また、小泉さんがイラク攻撃を支持したのは、憲法の制約があって直接、戦闘に参加するわけではないので、支持しやすかった、かえって支持するしかなかったという面もあったかもしれません。 ともあれ、日本はアメリカとともに戦うことを目指すべきではありません。そのためにも「先制攻撃には参加しない」と憲法に書いておけばいいのです。書いてあれば「ノー」と言えます。今はなんでも曖昧にしているから危険なのです。」小泉さんがアメリカを支持するしかなかったという分析は、簡単な言葉なのにとても説得力がある。憲法があるから、直接軍隊を送らなくてすむ。送らない以上は、支持表明だけでもしておかないと同盟関係が持たない、という論理は理解できる。小泉さんも、こんな風に説明してくれれば、僕も批判的には受け止めなかったのに。「戦争に大儀があるから支持した」なんていうから、批判の対象になってしまうんだ。大儀なんてどこにもないんだから。しかし、ドイツはEUがあるから「ノー」と言えるというのは、重要な指摘だ。日本は、極東アジアでの集団安全保障のことを何も考えていない。むしろ、アメリカにすり寄っているために、極東アジアでは孤立している。どこの国も日本を信用していない。こんな状態では、アメリカに「ノー」と言えるはずがない。極東アジアでの集団的安全保障をどうするかというのが、アメリカに「ノー」と言えるかどうかの鍵を握るのだと思う。最後の言葉「今はなんでも曖昧にしているから危険なのです」というものには、本当に深い共感を覚える。
2004.03.13
コメント(2)
-
「論座」の憲法論 現在の憲法論への批判
「論座」3月号の水島朝穂さんの文章は、安倍幹事長のインタビュー記事への批判という形を取っていたが、そこには、憲法論議のための原則的な指摘が溢れていた。そういう意味で、きわめて論理的に書かれているように感じる。昨日書ききれなかった残りの部分を引用して考えてみたい。「さて、近年の憲法論議を見ていて感ずることがある。それは、議論の仕方にかかわる。憲法そのものよりも、憲法を変えること自体に妙な力みがあり、なぜ変えるのかという理由があとからついてくるような議論が少なくないことである。」という文章には、全く同感だ。僕は専門家ではないから、すべての憲法論を見ているわけではないが、同じような印象を受けていた。専門家である水島さんは、僕などよりも遙かに多くの憲法論に目を通しているはずだけれど、同じように感じていると言うことは、僕のセンスも悪くはないのだなと思える。「押しつけ憲法論」や、長い間変わらなかったのだから、ということが「なぜ変えるのか」ということの理由だと思っている人がいるかもしれないが、これだけでは論理的な根拠としては弱いと僕は感じている。本質ではなく、表面的な特徴にかかわる理由だと思うからだ。本質的な部分にかかわって「なぜ変えるのか」と言うことが論証されなければ、それは論理的な根拠になり得ないというのが僕の感想だ。同じようなことを水島さんも語っている。「「半世紀以上たつのだから、とにかく変えてみよう」と言ったおおらかな主張から、改正頻度の表面的な比較に基づき、「日本国憲法は一度も改正されない世界最古の憲法だ」とする没歴史的な主張まで「憲法とは何か」という根本問題に取り組む知的誠実さの感じられない議論が多すぎるように思う。」次の記述も、僕が感じていることとほぼ重なるものだ。「戦後半世紀に渡って、日本が米国の戦争に直接コミットすることを妨げてきた憲法9条。その歴史的役割は大きい。自衛隊イラク派遣は、「復興支援」という名目ではあるが、客観的には、米国とそれに追随する諸国(「有志連合」)による、国際法違反のイラク戦争と、その結果としての占領に加担する行為である。」憲法9条に関するものといい、イラク戦争に関するものといい、その評価に全く賛成する。このような現状の中での憲法論議は、本質的には次のようなものでなければならないという主張も全く共感するものである。「この歴史的な局面において、国家の軍事機能に対する厳格な禁止規範を、いわば規制緩和していく道を取るのか否かが、今鋭く問われているのである。」このような姿勢で議論されている憲法論議が、国会の場などでは見あたらない。軍事力を使わないようにしてきた歴史を否定し、いかにして使えるようにするか、安倍幹事長のインタビューでは、「出来なかった」を「出来る」にしたいというふうに語られていたことだが、そればかりが語られているように感じる。これは、敗戦によって、軍事力に歯止めをかけようとした先人の知恵を否定することになると思う。このような本質的な議論へ向かわない議論が続く限り、僕は憲法「改正」というものは、まだ機が熟していないなと言う感じがするだけだ。現在の憲法論で展開されている具体的な議論の方向に対する批判もある。これも全くその通りだと共感するところだ。「ところで、論壇やメディアでは、憲法の原理・原則に忠実であろうとして議論を組み立てるものに対して、「現実無視の夢想家」と言って揶揄したり、「憲法をタブー視している」とか「無益な神学論争」といったレッテル張りが横行している。憲法規範と憲法現実の乖離は、誰しも否定できない事実である。問題は、規範と現実の矛盾や乖離をどのように認識し、かつどのようにしてそれを解決していくかという方法論である。」レッテル張りというのは、だいたいが論理で対抗できないときに使いたくなる感情的反応である。そのことによって何かが論証されるわけではないが、イメージを落とすことは出来る。かつての戦時下での「非国民」というレッテルや、赤狩りの時代の「赤」というレッテルがそれに当たるだろう。論理にこだわる人間は、レッテル張りをする人間の方をこそ信用しない。レッテル張りをして批判を回避するのではなく、論理的な指摘をして批判しなければならないのである。このレッテル張りに関しては、水島さんは次のように批判している。全く同感だ。「「理念かそれとも現実か」という二項対立ではなく、規範(理念)に反する現実を規範(理念)の方向に徐々に近づけていく努力もまた、現実を踏まえた冷静な思考選択である。規範・理念をより重視する立場を戯画化した上でたたくという手法は、フェアではないだろう。 「タブー視」という言葉についても、表現の自由が保障されたこの国で、憲法を宗教的禁忌の対象にする人など実際に存在するのだろうか。とどのつまり、憲法規範や原理にこだわることを、現実無視の宗教のように描くためのレトリックではないだろうか。」レッテル張りをする人間は、内容を正しく受け止めて分析し、批判しているのではなく、自分で文句を言いたい内容を自分ででっち上げて、相手に押しつけてそれを批判している。論理を複雑化させれば、それがわかりにくくなるため、相手のイメージを落とすには役に立つ。そういうものにだまされないように、単なるレッテル張りをしているだけなのか、内容を正しく批判しているのか、見極めていかなければならないと思う。水島さんは、最後に石橋湛山の言葉を引いて、「高次の現実主義」というものを提唱している。「米ソ冷戦時代、湛山は、中国やソ連との対話を求めて努力しつつ、軍事力強化の道に警鐘を鳴らした。「国連はまるで無能無力ののように悪口を言うものがいるが、私はそうは思わない」として、将来の国連警察軍の創設による集団安全保障の発展をにらみつつ、政府は、国連強化の方向に努力すべきであると力説した。」と記述し、次の湛山の言葉を紹介している。「我が国の独立と安全を守るために、軍備の拡張という国力を消耗するような考えでいったら、国防を全うすることが出来ないばかりでなく、国を滅ぼす。従って、そういう考え方を持った政治家に政治を託するわけにはいかない。」「全人類に率先して先見の明を示した日本人の熱情と誠意を、今こそ厳粛に、そして高らかに地球の上に呼びかけるべきであろう。……憲法を冷静に読み返すとき、私は日本がそのような悪路を踏んでいくことに忍びがたいものを感じる。」全く同感だ。宮台氏に言わせると、この考え方こそが自民党の保守本流の考え方だそうだ。僕は、保守本流の考え方に賛同する。すべてではないけれど、国防と憲法に関しては、保守本流を支持する。ちなみに、今の小泉政権は、宮台氏に言わせると「保守傍流」だそうだ。小泉政権の考え方に賛成できない理由の一つに、こんなことも関係しているのだなと思う。
2004.03.12
コメント(1)
-
「論座」の憲法論 安倍さんの改憲論
「論座」の2月号に安倍晋三・自民党幹事長のインタビュー記事がある。「第三の憲法を白紙から作りたい」と題されたその記事を改めて読んでみると、以外にも共感できる部分が見つかったりして驚いている。集団的自衛権の行使は、現在の憲法下では出来ないと言う話をしたあとで、それが出来るように憲法を改正するという構想を語っていた。そして、それが拡大解釈されることのないような歯止めとしては何を考えているかという質問に対して、次のように語った。「民主主義です。民意です。何か他の方法で歯止めをかけないと日本人ってなんでもしちゃうとお考えですか。「我々の民主主義に、そんなに自信がないんですか」と私は言いたいですね。歯止めは、政策の透明性と言論の存在、そして民主主義だと思います。」まことに真っ当な論理である。一般論として反対するところはどこもない。現段階での「政策の透明性と言論の存在」には大いに疑問を感じてはいるものの、原理・原則としての上の言葉には大変共感する。安倍さんという人は、きっとまじめな人なんだろうと思う。上の言葉を、本当は信じてはいないけれど、戦略的にこう言っておいた方が得だという計算から語っているとしたら、これは手強い相手だと思うけれど、ごくまじめに本心を語っているような気がする。安倍さんは、日本を、胸を張った立派な国にしたいんだろうと思う。そのためには、集団的自衛権を基にした安全保障面でも貢献が出来る国にしたいと思っているんだろう。安倍さんは善意の人であると思う。しかしだからこそ恐いという感じもある。善意の人というのは、自分の善意が一番の価値に位置してしまうことがある。論理よりも上位に善意をおくことが、歴史の中でどれだけの間違いを犯してきたか。「地獄への道は善意によって敷き詰められている」という言葉をかみしめて、僕は安倍さんの善意に危惧を感じるのだ。次の部分も、論理の限りでは全くその通りだと共感する。「今の時代の今の軍隊では、徴兵制はほとんど意味がありません。要するに軍隊の量的な規模は、意味がなくなりつつあります。ですから、軍事的にも徴兵制は意味がありませんし、社会的にも、日本は少子化が進んで、徴兵できるわけないじゃないですか。政治的にも社会的にも、徴兵制という選択肢はないと思います。 核保有は政策として「あり得ない」とはっきりと申し上げます。日本は非核三原則を取っているし、羽田孜内閣の時に、核不拡散条約(NPT)において永久に核保有を放棄しているんです。そういう意味において事実上、その議論は起こりえないと思います。」実に明快な論理である。論理が明快だから、その言葉にも自信が溢れているのを感じる。この論理的な明快さを、憲法論でも持ち続けて欲しいものだと思う。善意よりも、論理が先行する思考をして欲しいと思う。「現憲法を好意的に迎えた日本人」と中身出しがつけられた部分の発言も共感を覚えるものだった。次のものだ。「やっぱり苛烈な戦争体験から、もう戦争はこりごりだという記憶が刻まれたんだと思います。制定当時の国民の多くは、新憲法を好意的に迎えたんじゃないですか。それと、アメリカのプロパガンダは、イラクでは失敗しているけど、日本では非常に戦略的に、うまく日本人をそういう方向に持っていくことに成功した。 日本が4年間戦って、原爆も落とされ、さんざんな目に遭わされて生活のレベルも非常に厳しい状況まで来ましたよね。ですから、その中ですっといろいろなものが入って、物量とともに、豊かさとともに憲法が来ましたからね。それは、そういうことだったのだろうと思います。しかし、最初に言いましたが、新憲法の形成過程は問題でした。それのみで改憲を言っているのわけではありませんけどね。」憲法とともにやってきた価値が、当時の日本人には、戦争中のものよりも遙かに歓迎したいものだったのではないだろうか。自由といい豊かさといい、大日本帝国憲法下のものよりも遙かにいいものが新憲法とともにやってきた。それが歓迎する気持ちにつながったのではないかという解釈は、僕もとても共感するものだ。最後の、それのみで改憲を言っているのではないと言う部分で、もっと論理的な話をして欲しかったなと言う感じがする。この記事を批判的に読もうと思ったら、思わず共感するところを拾ってしまった。それは、批判する部分がなかなか見つからないと言うことがある。これは、安倍さんの憲法論に僕が賛成していると言うことではなく、引用して検討するような具体的な話が見つからないというのが原因だ。一般論の範囲であれば、それは論理的に理解できるから、論理さえ通じれば反対することはなくなる。問題は、具体的な存在がかかわってくる部分で、その存在をどう解釈するかで、賛成か反対かが別れてくる。その具体的な憲法論がほとんどなかったという感じが僕はしている。だから、批判しようにも、批判の材料がないという感じだ。末梢的な部分では疑問を感じるところもあるが、本質的な部分で何をどうしたいのかが分からないと言うのが全体の印象だろうか。末梢的かもしれないけれど、やや疑問を感じる発言をちょっと取り出してみようか。まずは改憲論の理由を3つあげているところだ。1つ目は、制定過程の問題で、これは論理的な理由になりうる。2つ目は、時代にそぐわないというもので、これは憲法というものが基本法であるという重さをどう解釈するかで批判の対象になりうるが、論理的には理由にすることはできると思う。3つ目に僕は問題を感じる。「三点目は、新しい時代、新しい世紀を迎えて「我々の手で新しい憲法を作っていこう」という精神こそが、新しい時代を切り開いていくと私は思うんです。」これは、論理的な理由ではなく、心情的な理由になっている。安倍さんの善意の人である一面が出ていると思う。論理よりも善意を上位に起きそうな危惧のあるこの言葉に、僕は疑問を感じる。憲法論の本質ではないけれど。「しかし、我々は、国には自然権的に自衛権があるという解釈から、現在の自衛隊の存在は合憲であると考えるわけです。」僕は、「自然権的」と言うことに疑問を感じる。歴史的に形成させられてきたものではないのか。この解釈から合憲を言うのではなく、やはり、憲法そのものの文章が何を語っているかの解釈から合憲を論じるべきだろうと思っている。それから、引用が難しいのだが、集団的自衛権の問題で、歴代内閣法制局は、「持っているけれども行使しない」と考えていたのを、安倍さんは、「権利を有しているけれど行使できない」と語っている違いが僕には気になる。「行使しない」というのであれば、「やらない」というのがまず前提にあって、どうしてもやらなければならない特別の場合に限り行使するというニュアンスになる。「行使できない」と受け取っているときは、「行使できる」となった場合に、「やる」と言うことが原則になり、必要でなければやらないと言うニュアンスになる。それでは、その必要でない場合はどんな場合なのか、具体的に語られなければ、いつ行使されるか分からない。原則が「やらない」と言うことであれば、「やる」場合には、その場合が特別な場合であることを説得しなければならないので、議論の後に行使されると言うことになる。「やる」ことが原則になったら、議論なしに行使される危険があるのを僕は感じる。集団的自衛権の行使は、国民の大多数の意思が反映して、その決定がされなければならないと僕は思うんだけれどな。安倍氏の上のインタビューを分析した記事が「論座」の3月号に出ている。水島朝穂さんという早稲田大学法学教授の「理念なき改憲論より高次の現実主義を」という記事だ。この批判はなかなか共感できる部分があったので引用しておこう。「安倍氏の議論は、全体として、改憲の必要性を何となく提示してはいるが、しかし、安倍氏自身がいかなる国家ビジョンを抱いているのか、そしてそれと現状がどのように相違し、その克服のために本当に改憲という選択肢しかあり得ないのかなど、目指すべき国家像からの改憲の必要性に至るまで、説得力のある根拠は何ら提示されていない。」一般論の範囲での正しさを主張するだけで、具体的に憲法を語っていないと言う僕の感じと同じものを抱く人がいたので、この部分に共感した。これに続く次の言葉も共感するものだ。「確かに、安倍氏は、集団的自衛権を行使できるようにし、それによって日米の対等な関係を目指すとするなど、それが改憲目的であるかのように受け取られる発言をしている。しかし、集団的自衛権を行使するというなら、その前提としての国家像の提示が必要であるし、対等な日米関係についても、いかなる意味において対等なのか、またなんのための日米関係なのかを語らずして、改憲を論ずることは出来ないはずである。結局のところ、安倍氏の議論においては、抽象的・観念的な理由から改憲の必要性ばかりが強調されているという印象であった。」まことに論理明快な批判で深く共感するところだ。こういう批判を見ると、反対の側の人は、「それではおまえはどうするのだ」ということをすぐに言ってくるが、これはレベルの違う議論なので、論理的にはそれに答える必要がないのだが、感情的には、答えないと言うことをなかなか受け入れられないだろうな。批判をする人間にとっては、批判が目的なのであるから、具体的に憲法をどうしたいかは別の話なのである。安倍氏が憲法をどうするかを語るのは、安倍氏は憲法を変えたい方の側の人間だから、当然説明責任というものがあるから語ることになるわけだ。批判をする人間に、「おまえはどうするのだ」と声をかける人間は、善意に溢れてはいるのだろうが、結果的には言論を封じる言論弾圧に荷担していると、客観的にはそうなるだろうと僕は思っている。本人の主観がいかに善意に溢れていようと。国民であれば、憲法について語るのも言論の自由だし、語らないのも言論の自由だ。一般庶民であれば、誰かに説明責任を負っているのではない。何を語るかは、語る人間の意思にまかせられる。それが言論の自由だ。これからはずれる特殊な性質を持っているのは、ある種の説明責任を負っている人間だけなのだと僕は思っている。「安易な改憲は権力を暴走させる」と中見出しが付いた部分では、憲法というものの基本的性格を語っている。これは、宮台氏から教えてもらって、目から鱗が落ちるというように感じたものだ。専門家の間では常識でも、庶民の間ではどれくらい常識になっているだろうか。常識にしたいものだと思う。次のようなものだ。「そもそも憲法に与えられた機能・役割の第一義的なものは、権力担当者に対して政策的選択肢の幅を限定させることである。この考え方は一般に立憲主義と呼ばれるが、主権者である国民が、時々の権力担当者の暴走を阻むためにあえて障害として設けたものであり、その意味で、立憲主義とは、歴史的に培われてきた人類の英知の一つなのである。」「国家権力を担う権力担当者は、自明のものとしてあらゆる政策を実施する権限を有するのではない。国民主権のもとでは、憲法によって明示的に授権された権限を、その授権された範囲内で行使できるにすぎないのである。」これが国民の常識になって欲しいものだと思う。他にも、ここには共感できる部分がたくさんあるのだが、あまりにも長くなりすぎるので、ここら辺で今日は切り上げよう。
2004.03.11
コメント(0)
-
「論座」の憲法論 その1
月刊誌「論座」にこのところ憲法論の特集が組まれている。それを批判的に検討しようと思ったのだが、批判よりも共感する部分の方が多かった。「論座」3月号からいくつか引用して、どこに共感するのかを考えてみたい。まずは、「日本は集団安全保障に参画する義務がある」と題された民主党憲法調査会会長・仙谷由人氏の文章からの引用だ。仙谷氏に共感したからといって、僕が民主党の憲法案を支持しているわけではない。それは、その全体像をまだよく知らないから、支持するとかしないとかいう判断が出来ないからだ。「論座」に書かれた文章の内容を見る限りでの共感なのである。まずは、憲法9条に対する次の評価に共感した。「日本の平和を持続させてきた貴重な条文です。9条の精神は広く日本国民に定着していると思う。問題は、この条文が単なる理想ではなく、国際紛争の解決は国際協力で、つまり国連の力で実現していくという枠組みを前提にしているのに、そこが押さえられてこなかったことです。」日本が敗戦後これまで戦争に巻き込まれてこなかったのは、9条があるおかげであるということがまず一点。それだけではないけれども、それが一番大きな理由だったと思う。国際協力に国連の力を基礎にしたものを考えるというのは、きわめて現実的な方向だと思う。理想だけの言葉だけの平和主義ではないと思った。国連にはそんな力も機能もないと、国連を否定したい人がいるのも確かだろう。しかし、国連の意義は、一国の判断のみによって解決の方向が決まるのではなく、立場の違う他国のチェック機能が入るところに意義があると僕は感じている。イラク戦争は、アメリカがどんなに開戦を決議したくても、ついに国連はそうはしなかった。立場の違う国が集っているから、簡単に武力が使えないという歯止めになるのである。これが民主主義の力というものだろう。もちろん、唯一の超大国であるアメリカの意志が大きく反映するのも確かだが、アメリカは、勝手に自分の判断で戦争を始められず、少なくとも面倒な手順を踏まないと戦争が出来ないという仕組みを作っておくことが戦争の抑止になる。「国土・国民あるいは領土・領空・領海および国民の生命・財産を防衛する。そういう任務の「武力」の存在を認める以上、憲法に書いた方がいい。それが、法の支配であり、法治主義です。」これは、一般論として共感する。しかし、具体的に、どのように防衛を定義するかという現実的なところでは、異論が出てきて当然だと思う。総論賛成、各論反対という状況になるだろう。一般論としての正しさと、それを適用したときの現実への応用の正しさは別物だと思うからだ。「押しつけられた憲法だからダメだという人には「あなた方の先輩が妙な戦争をやった結果じゃないか」と反論したい。」これにも僕は共感するのだが、あの戦争を「妙な戦争」だと思わない人は共感できないだろうと思う。押しつけられたということに問題は感じながらも、押しつけられるという特殊な状況でもなければ、当時の日本人には、国民主権・基本的人権の考え方は生まれてこなかったんじゃないかとも思うと、これは押しつけられたことがむしろ幸運だったとも思える。平和主義に関しては、日本に二度と侵略的な戦争をさせてはいけないというのが、連合国の総意だったから、それを過剰に反映したところがあると思う。今でも国連に敵国条項が残っているのは、その恐れの大きさを物語っているものだろう。この恐れを払拭し、平和主義の不備を補うことは課題だが、平和主義を否定するのは、せっかくの成果を捨て去ることになるのではないだろうか。風呂の水と一緒に赤ん坊まで捨てる、というようなことわざがあるが、その比喩で表現されるものと同じになるのではないだろうか。「「月刊Asahi」の91年5月号に「私の「国連軍」合憲論」という評論家立花隆さんの発言が載っています。国連軍に自衛隊が参加するのは憲法上、全く問題がないばかりか、憲法が命じる日本の責務である、という主張です。僕はその主張に強く共感できるものを感じた。」これは、仙谷さんの言葉ではなく、立花隆さんの言葉のようだが、僕も、この考え方には、安全保障の問題は国連を基礎にしていくという前提を置いた上で、仙谷さん同様やっぱり共感を覚える。9条の問題は、安全保障の問題をどこに基礎を置いていくかということに、かなり大きくかかわっているのではないかなと思う。「アフガン戦争もそうだけど、イラクに対する武力行使は、どう考えても国際法的に合理化できない。殺戮と戦争の20世紀前半の深刻な反省の下に、国際社会は強国による一方的な制裁を認めないことにした。「あそこは悪い国だ」とか、独裁国家だとか、人権抑圧国家だとか、そういうことをある国家が単独で勝手に認定して武力を行使してはならない。それが、国連の枠組みということです。だから、ある国を軍事的に制裁するかどうかは、国連の場で多国間で、あるいは安保理の常任理事国5カ国だけでもいいですが、いずれにせよ、国連の意思としてそれを決めなくてはいけない。それ以外は単なる「暴力」にすぎない。正当性、合法性は国連の枠組みの下にしかないというのが国際法の法理です。」全く同感という感じだ。重要な問題の決定は、単独で行ってはいけない。必ずチェック機能を持たせなければ、間違った判断の影響が大きすぎるということだ。これに続けて次のようにも語っている。「それにてらせば、アメリカ軍という軍事組織が、イラクという一応国際法なり国際社会で認められた領土の中になぜ存在できるのか、あるいは、なぜそこで武力行使できるのか。国連憲章から見ても、いろいろな国際法規から見ても、誰も説明できない。フセインのような独裁者が統治しようと、その国に政府が存在する以上、その国の要請なしに他国の軍隊が足を踏み入れるのは、これを侵略と言わずに何を侵略と言うんだという話ですよ。」これは、イラク戦争が侵略戦争であるという、きわめて説得的な説明のように僕は感じる。その他、下のような文章に共感を覚える。「日米同盟の関係があるからアメリカに協力しなければならないという議論があるが、日米同盟を法的に規定する日米安保条約は、日本防衛のためのものであって、国際協力とか何とか、そんなことは書いていない。」「--現状では、憲法を踏み越えていると?(インタビューの質問)憲法も国連憲章も日米安保条約も踏み越えている。今回の自衛隊派遣は、すべてを飛び越えた超法規的な措置でしかない。」「論座」の2月号には、安倍晋三自民党幹事長へのインタビュー記事があった。これは、もしかしたら批判的検討になるかもしれないな。ちょっと注意深く読んでみようかと思う。
2004.03.10
コメント(0)
-
ヤフーのニュースから
今朝のワイドショーで浅田農産会長の自殺を報道していた。ヤフーでも次のニュースがある。「関係者に重苦しいムード 浅田農産会長自殺で衝撃と落胆」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040308-00000019-kyt-l26僕は、これはマスコミが追い込んだことがもっとも大きな原因で自殺へ至ったと感じているのだが、マスコミの報道であるワイドショーでは、自分たちの責任というものを問う報道はないようである。マスコミは、事件の本質を解明する報道をするのではなく、通報の遅れを倫理的に非難する報道に終始したように感じる。浅田農産会長がどれほど心がけが悪かったかを糾弾するような記者会見をしたように僕は感じた。何を言っても悪者にされるという状況の中で、自分が心配していたことや、判断の間違いを正直に述べることが出来るだろうか。何か言えば、さらに攻撃が激しくなると感じても、あの記者会見を見た限りでは無理はないと思う。ヤフーのニュースでは、「日本養鶏協会副会長だった浅田会長と面識がある同協会理事の中澤廣司京都府養鶏協議会会長は「気丈で協会でも常に指導的な人だったが、大変に苦しまれたのだろう。船井農場での鶏の異常を早く通報すれば天災で済んだのに、人災にしてしまった点が悔やまれる。事実関係を明らかにして、感染拡大を防ぐために協力してほしかった」と残念がった。」と語る人もいたことが報道されている。しかし、本当に、早く通報すれば「天災」ですんだのだろうか。浅田農産はそのダメージを回復できると予測できただろうか。発見した段階で、これが知られたらもう終わりだと考えることはなかっただろうか。今はもう浅田農産会長がどう考えていたかを直接聞くことは出来なくなった。しかし、構造的な問題があるかもしれないと、より本質的な問題へマスコミが一歩を踏み出していれば、ただ単に自分たちが悪いとたたかれるだけでなければ、本当の原因を解明して同業者を救うという方向へ進む気持ちを浅田農産会長が持つように働きかけられたのではないだろうか。マスコミはわかりやすい悪者をたたくことで視聴率を稼いでいる。その姿勢こそが自殺の原因ではないかと思う。本質的な巨悪を暴けなかったマスコミの責任を、視聴者は感じなければならないのではないだろうか。さて、たまったニュースのストックの中から、気になるニュースを続報も含めて追いかけてみようか。「宿営地の賃借料で大筋合意 サマワの自衛隊と地主」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040302-00000046-kyodo-intさて、この賃貸料の交渉は、僕は自衛隊が圧力に屈して、法外な値段をふっかけられていると受け取っているのだが、現地の賃貸料の水準が報道されていないので、合意した値段がどうなのかという評価が出来ない。と思っていたら、続報ではそれが報道されていた。「サマワ宿営地の土地交渉合意、決め手は雇用」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040306-00000507-yom-intこの記事では、自衛隊は最初賃貸料を7ドルということで提示したらしい。それは、次のような根拠があったからだそうだ。「しかし、宿営地近くに農地を借りる獣医師(53)は「私の賃借料は1ドナム2000ディナール(約160円)。要求は高すぎ、サマワの印象を悪くする」と不快感を隠さない。自衛隊側が最初に示した7ドルは、この額などから算出されたものだった。」地元での平均的な水準からいうと、7ドルが妥当なところだったらしい。それに対して地主側は、当初は1000ドルを要求してきたらしい。これは、まあ最初に大きくふっかけておいて、あとで少し下げても出来るだけ高い水準で交渉をしようという戦術だろうと思う。ただ円に換算して考えると、7万円ほどの水準の家賃の部屋に、最初は1000万円をふっかけられたという感じになるだろうか。もちろん、自衛隊の宿営地を作るという特殊な状況であるから、地元の人間が普通に使うよりも少々高い賃貸料になることはやむを得ないと思う。しかし、7万円が1000万円になるような要求はひどすぎるなと思う。これが、ようやく200ドルくらいの水準に落ち着いてきたらしい。しかし、これでも7万円の部屋が200万円だという感じになる。いくら特殊な状況でも、やっぱり高すぎるんじゃないだろうか。高すぎる賃貸料を、イラクに対する復興支援の一つだと解釈してしまえば我慢も出来るのかな。それにしても、これは事実として圧力に屈した交渉の一つだなと思う。「米大統領選、ケリー氏の躍進は小泉外交へのリスクにはならず」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040302-00000428-reu-intこの記事を読むと、大統領選は、ケリー氏が勝った方がむしろ小泉政権にとってはいいのではないかという感じさえする。ブッシュ氏が勝つ方がリスクが大きいような書き方だ。ブッシュ氏が勝つことを小泉政権は予想しているようだが、その時は、今の対米追従がさらに続くということになるのだろう。どちらが勝っても、小泉政権にとってはさほど大きな変動はないとしたら、小泉政権批判は、外圧を期待するよりも、内政的な問題の非合理性を批判する方に力を入れなければならないだろう。しかし、それを担う民主党の最近の不祥事を見ていると、民主党も自民党と同じ穴の狢なんだなあと思って、その追求も最後はかわされてしまいそうな感じがする。国民の一人一人がジャーナリスティックな感覚を持たなければならないなあと今更ながらに思う。「<裁判員制度>もし選ばれたら…… 多い制約、ペナルティ」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040303-00000114-mai-soci裁判員制度については、つい最近の「マル激トーク・オン・デマンド」でも話題にされていた。そこでは、裁判員制度の意義として、国民の裁判に対する意識を高めるということが一番にあげられていた。裁判というのは、その専門家である裁判官や弁護士などにお任せするという意識が、大部分の日本人のものではないかと思う。しかし、本来は人を裁くということは大変難しいことであり、論理ですっきり割り切れるものではない。専門家である弁護士や裁判官は、法に従っているかという論理的な面では、一般の人よりも正しい判断をするけれども、それはあくまでも形式の面でのみ正しいのであって、内容面で見たときに、形式だけでは割り切れないものを考慮に入れられるのは、むしろ専門家ではない我々の方ではないかと感じる。その我々の判断を取り入れることによって、裁判はもっと内容的に深い意味のあるものになるだろうし、実際にそれにかかわることによって、そこから得られたものが我々の意識を変えていくことに大きな意義がある。裁判というのは、ひどいことをした悪人が極刑にされて、それで国民が安心するというような単純なものではないことが実感として分かるようになるという。死刑制度に対する深い議論も国民の間に生まれるのではないかという期待も出来る。このように意義深い裁判員制度であるが、ニュースの表題にあるように、多い制約とペナルティが「マル激トーク・オン・デマンド」でも批判されていた。もっとも批判されていたのは、「裁判員に生涯続く重い守秘義務を負わせ、違反には最高で懲役1年の刑事罰を科す内容」にかかわるところだ。これは、職業としての裁判官に課されている守秘義務と同じものを、裁判員にも負わせようという意図があるものらしい。現在進行中の裁判に対しては、予断を与えたりする恐れがあるのでこの守秘義務も分かるのだが、生涯続くというのは果たして合理的なのかどうか疑問だ。裁判官は職業だから、日常的に守秘義務を課される立場が続くことに合理性があることが分かるが、その裁判だけにかかわっている裁判員が、それが終わった後も永久にそれに縛られるのは不合理な感じもする。裁判というのは、自然科学の法則のように、論理的にきっちりと結果が出るものではない。だからこそ専門家ではない一般庶民が裁判員としてかかわるという発想も出てくるのだ。たとえ結果が出た裁判であっても、それに批判的な人間が出てきてもある意味では当然だ。その批判を永遠に封じるような処置が、生涯続く守秘義務ではないだろうか。これは、裁判に対する批判を封じるためのものにしか僕には見えない。どのような場合には守秘義務が生じるのか、もっと具体的に規定すべきだと思う。無条件に、生涯秘密を守らなければならないとするのは、不合理なことだと思う。
2004.03.09
コメント(4)
-
憲法論の今後の展開
掲示板にあったmskさんの書き込みのように、そろそろ違う展開も必要かなという気がしてきた。憲法の歴史的側面は、まだ決着がついていないので、これも資料が手にはいる限りで集めて、これも進めていきたいと思っているが、同時並行で、具体的な改憲論の批判的検討という展開も考えてみたいと思う。自分の立場と同じ方向での改憲論に対しては、なかなか批判的視点を持つことが難しいので、まずはその反対の視点のものを求めてみようかと思っている。反対のものは、批判すべき点を見つけやすいし、また、反対の側がこちら側を批判している視点を見ることによって、こちら側の弱点を考えることもできるのではないかと思っている。久しぶりに論壇誌というものを買い求めてみようかと思っている。改憲論の特集があれば都合がいいが、「正論」「文藝春秋」「諸君」「論座」「世界」などといった雑誌を探してみようかと思っている。さて、今日はあまり時間がないので、今資料として読んでいる「昭和の歴史8」小学館ライブラリーという本からの引用をちょっと記しておこうと思っている。この本は、神田文人さんという横浜市立大学教授が書いているものだ。次の文章が目にとまったので引用しておこう。「新聞各紙の社説も、「画期的な平和憲法」(「朝日新聞」3月7日)、「憲法草案と世界平和」(「毎日新聞」3月8日)、「民主主義平和国家の構想」(「日本経済新聞」3月8日)等と、全面的に賛成し、わずかに3月8日付「東京新聞」の社説「政府の憲法改正草案要綱なる」のみが、比較的、客観的記述の性格が濃かった。 そうした中で、「読売報知新聞」の社説「人民憲法の制定」が、天皇制の存続・戦争放棄による侵略への不安を述べているのが異色であった。これは、争議後、共産党系の組合が指導権を握った同紙の反応でもあった。いずれにしろ大勢は、幣原内閣の当初の構想とのあまりの違いにとまどいつつ、全く斬新な構想を歓迎したのが、当時の世論の動向であった。」(「昭和の歴史8」小学館ライブラリー、神田文人;横浜市立大学教授、173ページ)とりあえず、当時の新聞の歓迎ぶりから、当時の世論を推測しようというための資料として目についた。「1946年(昭和21)4月17日、政府は、先の「要綱」に手を加え、「憲法改正草案」を発表した。それは、口語体・平仮名の句読点のある文章であった。元来、日本の法律は、すべて文語体・片仮名で、句読点のないきわめて読みにくいものであった。難解であることは、それだけ国民生活から縁遠く、専制的支配の象徴とされていた。 それが一挙に、分かりやすい平明な文章に変わったのは、作家の山本有三や国語運動連盟、三宅正太郎・横田喜三郎ら法律関係者が、強く政府に働きかけたからである。山本らの申し入れは、口語体の使用、難しい漢語を使わぬこと、わかりにくい言い回しを避けること、漢字の減少、濁点・半濁点・句読点の使用、平仮名の使用、改行の際の1字下げ、の7項目であったが、それら全部が採用されたのである。民主憲法にふさわしい思い切った英断であった。 それでもなお、翻訳調が色濃く、こなれた日本語からほど遠かった。「日本経済新聞」4月18日の社説「口語調の改正憲法草案」は、「例へば第10条に「国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない」とあるが、簡単に基本的人権を有するとしてもいいではないか」と、批判している。 内容はいうまでもなく、象徴天皇制・戦争放棄・基本的人権の保障・二院制の民選議会等が主要なものである。沖縄をのぞく全都道府県各階層2000名を対象とした毎日新聞社の調査(5月27日発表)により、天皇制についての動向を見ると、表のようになる。この調査によると、草案の天皇制反対が、必ずしも共和制の支持者ではないことを表しており、解説によると、「天皇制下の共和制」論者も14名いたというから、単純ではない。また、「戦争放棄」についても無条件支持は1117名で、278名は主として「自衛権保留規定」を挿入しての承認であるという。しかし、いずれにしろ、新憲法草案が圧倒的多数の支持を得ていたことが分かる。」 憲法草案の「天皇制」についての調査 内容 人数 比率 草案の天皇制支持 1702人 85.0% 草案の天皇制反対 263人 13.0% 不明 35人 2.0% 合計 2000人 100.0% 天皇制廃止 215人 10.8% 天皇制廃止反対 1711人 85.5% 不明 74人 3.7% 合計 2000人 100.0%(「昭和の歴史8」小学館ライブラリー、神田文人;横浜市立大学教授、191ページ))自衛権の問題は、制定当初から問題にされていたことが分かる。ただ、このことを問題にしていたのは、当時は共産党勢力だけだったというのが現在と違うところだろうか。その問題があったが、世論調査としては多数の国民が支持をしていたという結果が出ていたと、僕はこの資料をそう読んだ。 憲法草案の「戦争放棄条項」についての調査 回答 人数 比率 内訳 人数 比率 戦争放棄条項必要 1395人 69.8% 草案通り 1117人 55.9% 自衛権保留 278人 13.9% 戦争放棄条項不要 568人 28.4% 自衛権の放棄不要 101人 5.0% 条約による国際的保障 72人 3.6% 国民的宣誓で十分 13人 0.7% その他 382人 19.1% いずれでもない 37人 1.8% 合計 2000人 100 %(「昭和の歴史8」小学館ライブラリー、神田文人;横浜市立大学教授、199ページ)これも参考になる世論調査だと思う。その前の資料とソースは同じようだ。次の資料は、直接憲法の資料ではないが、敗戦という特殊な状況での裁判である「東京裁判」に対する解釈として、その非常時であるということをどう受け止めるかという考え方の参考になる資料だと思って書き留めておいた。「5月13日、清瀬一郎弁護士は、弁護団を代表して当法廷においては「平和に対する罪」「人道に対する罪」を裁く権限はない、と主張した。 理由は、国際法において戦争それ自体は否定されておらず、従って戦争の計画・準備・開始・遂行のごとき行為を裁くことは不可能である。また日本は、ポツダム宣言を受諾して降伏したのであり、ドイツのように「無条件降伏」ではないから、その条件に従って裁判が行われるべきである。ところが、ポツダム宣言には、「俘虜虐待者を含む一般の戦争犯罪人の処罰」は規定されているが、「平和」「人道」に対する罪への処罰はない、というものであった。つまり、45年8月8日、米・英・ソ間で協定に達した「国際軍事裁判所条例」は事後法であり、罪と刑が事前に決定されている罪刑法定主義という近代法の原則に照らせば、違法な手続きだ、というのである。 これは、東西両国際裁判共に、手続き上の弱点であったことは否定できない。裁判所はこの意見に、真正面から答えることは出来なかった。同じ見解がニュルンベルグ裁判でも主張されたが、ここでも答えることが出来ず、46年10月1日の判決の日、「裁判所条例は戦勝国の側で権力を恣意的に行使したものでなく、その判定の当時に存在していた国際法を表示したものである」と回答したに過ぎない。東京裁判においてもこれを援用し、48年11月4日の判決の日、「当裁判所はニュルンベルグ裁判所の以上の意見と、その意見に到達するまでの推論に完全に同意する」と述べるにとどまった。 しかし、国際法の横田喜三郎教授は、手続き上の不備を認めながらも、なお、国際軍事裁判の法理是認論を展開した。先の「戦争犯罪の基本問題」「戦争犯罪と罪刑法定主義」(共に、「日本管理法令研究所」第一巻第3号)のほか、「戦争犯罪の裁判所」(同第8号)「A級戦争犯罪の基礎理由」(同第10号)を執筆し、それらをまとめた「戦争犯罪論」を、47年に刊行した。 横田は、「戦争犯罪と罪刑法定主義」において、ニュルンベルグ裁判における弁護団代表スターマー博士の罪刑法定主義に基づく裁判批判を援用した上で、その「主張はかなり有力」だとしつつも、その批判も展開した。第一は、「罪刑法定主義は専制君主制のもとで裁判がきわめて恣意的に行われたことに対する反動として、それを防止し、人権を保障するために採用された」ものであるから、裁判が恣意的に行われていないところでは、「絶対にこの主義を固執」する必要はない、第二は、「大きな変動期には、特に古い秩序が破壊され、新しい秩序が建設されようとする転換期には、そうすることが不可能なことがあり、望ましくないことすらある」と論じ、ニュルンベルグ裁判における「平和に対する罪」を裁くことを是認した。 横田はこのとき、平常時ではなく転換期であるという判断のもとに、形式的な法理論を超えた立場で事態を説明しようとしていたのである。さらにいえば、日本人自身の中から戦争責任追及の動きが出てこなかったのであるから、現実には、連合軍による訴追以外に、戦争の歴史と責任を解明する手段はなかったのである。」(「昭和の歴史8」小学館ライブラリー、神田文人;横浜市立大学教授、202ページ~205ページ)今の憲法も、敗戦によって占領軍に押しつけられたという特殊な状況がある。しかし、その特殊な状況にあっても、なお正当性を主張しうる論理的根拠がないだろうかというのを、上の東京裁判の正当性の主張を参考にして考えてみたいと思う。今日はほとんどが引用の日記になってしまったが、今後の考察の資料になるのではないかと思っている。
2004.03.08
コメント(12)
-
「改憲幻想論」 佐柄木俊郎
「改憲幻想論」という本を読んでいる。まだ途中なのだがとても面白いし、その内容に共感できる。著者は学者ではなく、ジャーナリストだ。だからだろうか、とても読みやすく、自分に近い感覚で憲法を議論しているように感じる。自分が思っているようなことを、適切な言葉で表現してもらっていると感じる本だ。この本は副題に「壊れていない車は修理するな」というものがついている。これは大変適切な比喩のように感じる。今の憲法は、確かに不備なところはあるだろうが、まだ壊れているわけではない。壊れてもいないのに、早急に修理(改憲)するのは気が早いんじゃないかということだ。本当に具合が悪いのかどうか、まだよく調査しなければいけないんじゃないかと思う。この本の「はじめに」の部分には次のようなことが書かれている。「憲法改正は、本当にそれが必要な状況になったらためらうべきではないし、そうした場合にのみ、現実にも可能になるだろう。たとえば、20年先、30年、いやもっと遠い将来かもしれないが、アジアにも欧州連合(EU)のような国家統合の仕組みにつながる国際政治の胎動が生まれれば、国家主権をその限りで制限する改正が必要になるのは確かである。また、それへの加入の是非を問う国民投票制の導入なども議論になるに違いない。 さらには、日本、中国、韓国などアジアの諸国を網羅した、より普遍的な地域的集団安全保障の枠組みが実現するような状況が生まれれば、この機構の下での共同軍事行動の参加に道を開くための改憲が必要だ、といった議論が起きるかもしれない。 「改憲」はこのように「どこをどう変えるか」というすぐれて現実的な作業なのだから、そうした差し迫った具体的必要性と、それに賛成する国民世論の成熟を欠いたままでは、実現は困難であろう。詳しくは本文にゆだねるが、厳重な憲法改正手続きをクリアにするには、漠然とした「改憲賛成」などではなく、具体的な事項の改正を巡る相当に高度のコンセンサスがあることが前提条件になると考えるからである。」まず現状認識として、今が憲法改正が本当に必要な状況だとは考えていないことに共感する。それが必要になった場合にはためらうべきではないが、今はそういうときではないと言う判断だ。自衛隊のイラク派遣が憲法違反の状態であるということを見ると、自衛隊派遣が大事だと思う人間は、今が憲法改正が必要なときだと思うかもしれないが、大部分の国民がそう思うとは限らない。自衛隊派遣は憲法違反であるから、派遣をやめて憲法を守るべきだと考える国民もたくさんいる。そういう人々にとっては、憲法を変えるということが課題ではなく、憲法違反の自衛隊派遣をやめさせることの方が課題なのである。憲法改正に関しては、差し迫った必要性と、どこをどう変えるかという具体的な議論で、国民世論のコンセンサスが得られるほどそれの成熟がなければならないという主張に僕は共感する。だから、今はその時ではなく、議論の時なのだろうと思っている。もう一つ共感するのは、「国家主権をその限りで制限する改正」という言葉だ。これこそが憲法の本質であり、新しい事態が発生して、その事態に対して国家主権が暴走する恐れがあったときに、それに対する制限として憲法が存在するという、基本的な考え方に共感する。憲法は、国家権力に何かを許したり、国民が何かの義務を負うことを宣言するものではないのである。あくまでも、国民の側から国家権力をコントロールするために必要な事項を書き込んであるのが憲法なのである。次の主張などは、僕が漠然と感じていたことをズバリと言葉にしてくれたという感じがしている。これも、全くその通りと共感できるものだ。「本書の趣旨を一言で言えば「憲法のどこをどう改めるべきか、といった国民世論が成熟していない以上、当面改憲は必要ないし現実にも不可能だ、ということを説き明かしたい」ということにつきる。」今は多くの憲法論が語られているが、「どこをどう改めるべきか」を具体的に受け取って考えたいと思う。それが納得できないときは、どうして改憲なのかの疑問を持ち続けたいものだと思う。はじめに改憲ありきという議論はおかしいのだと思う。次の、「はじめに」の最後の文章も、全くその通りだと思う。「日本は確かに変わらなければならないし、変えなければいけない。そのために必要なのは繰り返し叫ばれてきたように、行財政改革や規制緩和であり、教育改革、司法改革、地方分権であり、とりわけ政治改革と国会改革の実現であろう。戯れ歌風に言えば、「日本変えるにゃ改憲はいらぬ。永田町政治が変わりゃいい」のである。」この本では、日本の憲法観として、聖徳太子の17条憲法からイメージされる「憲法観」と明治憲法に対して次のような記述がある。「先に述べたように「17条憲法」が倫理や道徳の体系であるのに対し、近代憲法は国家に権力行使の根拠を与え、具体的な統治機構を定める反面、個人の権利や自由を恣意的な侵害から守るためにその権力行使のあり方を規制するという、きわめて合理的な「理性の体系」だと言っていい。だから、国民と国民の間の関係や一般の社会秩序、モラルとは直接関係がない。それらは、民法や刑法をはじめ、一般の法律に定められている。従って近代憲法は基本的に「17条憲法」のように国民に対して倫理を説いたり、心構えや教えをたれたりするものではないのである。 明治憲法も、その意味では立憲主義に基づく近代憲法の精神に立っている。起草作業のリーダーであった伊藤博文は、枢密院の議会で「憲法を創設するの精神は、第一君権を制限し、第二臣民の権利を保護するにあり」と語っている。冒頭の調査会発言のような「17条憲法」的憲法観ではないことはおわかりいただけるだろう。ただし、明治憲法は、現実には天皇主権の原理にたち「臣民の権利も天皇から与えられたものだ」という建前に立っていたため、その近代性という面ではきわめて不徹底なものにとどまったのである。」ここに書かれていることは、憲法というものの基本的なとらえ方といい、明治憲法に対する、近代憲法としての不十分な点の指摘といい、全く、僕が思っていたことを代弁してくれていると感じるものだった。さて、たまっていたニュースについても、ちょっと見ておくことにしよう。「<イラク>住民に発砲か、反米デモ発生」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040301-00000066-mai-int神保哲生・宮台真司の「マル激トーク・オン・デマンド」では、イラクに行っていたNGOの代表のケン・ジョセフ氏と、イラク問題に詳しいアジア経済研究所参事の酒井啓子氏を招いて話を聞いている。両氏に共通しているのは、アメリカのイラクでの対応のまずさとして、イラク人を守る治安というものを全くしていないということを指摘していた。米兵は、自分がやられるのが恐いので、自分たちは厳重に守るけれど、すぐ近くでイラク人がやられていても全く手を出さないというのだ。それに巻き込まれたらたまらないと思っているのだろうか。最近の、イラク人同士でのテロ事件が頻発しているのは、重武装しているアメリカ軍が、イラク人を全く守っていないということがあるらしい。これは、直接攻撃してくるイスラム原理主義者と呼ばれるテロリストに対する怒りももちろんあるだろうが、それ以上に、何もしてくれないアメリカが占領軍として居ることに、イラクの人々はかなりの怒りを覚えているということだ。ケン・ジョセフ氏は、サマワは自衛隊が来たことによって大変危険な町になったと語っていた。マスコミで報道されている、歓迎する市民の姿というのは、ほとんど脅かされている「ヤラセ」だと語っていた。もし自衛隊も、「何もしてくれていない」というふうにイラクの人々の目に映ったら、自衛隊が来たことによってテロリストを呼び寄せて、彼らに犠牲が出たりしたら、アメリカと同じような目で見られることがないだろうか。ケン・ジョセフ氏は、イラクで自衛隊に犠牲が出た場合は、これを機に、正規の軍事行動が出来る国にするための改憲論議がわき起こるのではないかと警告していた。そのためにこそ自衛隊を送ったのではないかと疑っていた。イラクで何らかの衝撃的なことが起こったときに、感情的に舞い上がった改憲論に押し切られないように注意しなければならない。あくまでも冷静にそれを見ていきたいものだ。
2004.03.07
コメント(52)
-
鳥インフルエンザと6カ国協議
今ちまたでは鳥インフルエンザの話題が語られている。テレビのワイドショーなんかでも、それを早く届け出なかった農場の批判をしてたたくというものが多くあった。それを見ていて、僕が、この農場もこれでつぶれてしまうんだろうねと言って、隠しておけば信用を失って、それがばれたときにつぶれるかもしれないのに、なぜちゃんと報告するという発想がなかったのかなと疑問を言っていたら、栄養士さんがこんな話をしてくれた。栄養士さんの話では、ある研究会で、ケンタッキー・フライド・チキンの人がこんな話をしたのだそうだ。今の日本の流通構造では、常に次の在庫というものを確保しておかないと、商売としての競争に勝てなくなっているという。つまり、ものがあるときにそれが店頭に並ぶというのではなく、常にものがあるという状態を確保しておかないとならないそうだ。そうすると、必要量以上のものを常に用意しておかないとならない。しかもその商品をとぎらせてはいけないということになる。もしも商品がとぎれるようなことがあれば、それは他の競争者の参入を許すことになり、結局敗者になってしまうということになるらしい。ケンタッキー・フライド・チキンは、自前の農場も持っているので、そういう点で常に在庫の安定が図れるという宣伝もしているのかもしれないが、鳥インフルエンザが発症した農場では、まず発想したのは、商品をとぎらせてはいけないと言うことだったのかもしれない。届け出ることで商品をとぎらせたら競争に敗れてつぶれる、鳥インフルエンザを届け出ないで信用を落としてもつぶれる。いずれにしてもつぶれるなら、隠しおおせるものならば隠しておこうという考えに傾く可能性もある。ワイドショーでは、通報の遅れなどを重罰化して、この種の行為を防ごうという意見が多かったが、いくら重罰化しても、通報して商品の提供がとぎれたらつぶれてしまうのなら、この重罰化が有効に働かないのではないだろうか。重罰化とともに、鳥インフルエンザの発症などというものが、予想できない原因で起こったのなら、保護する施策も採るべきではないのだろうか。それがない限り、積極的に報告して問題を解決しようとするところが出てくるものだろうか。その点に大きな疑問を感じた。それにしても、競争原理というのは資本主義の根幹を支える部分でもあるが、その競争によって、不必要な商品の準備というものが常に考えられていたら、その準備がストップしそうな重大な問題が発生したときに、競争の圧力から、商品のストップが出来なくなると言うのは、構造的な問題ではないかと思う。この構造的な問題がおかしいではないかという発想から生まれたのがスロー・フードの運動でもあるらしい。資本主義の限界として、このことはもっと我々が関心を持ってもいいことではないかと僕は思った。さて、ニュースのストックがかなりたまっているのだが、圧倒的に大量のニュースが流れているにもかかわらず、その姿が見えにくいのが、6カ国協議の行方と、朝鮮半島の問題をどうとらえるかというニュースではないかと思う。時には、全く正反対の見方をさせるようなニュースも目につく。一連の流れを拾い出して、そこに共通するものを考えてみようと思う。「「協議継続でも解決困難」 北朝鮮、米国に失望表明」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040229-00000119-kyodo-int「米の敵視政策ある限り無益=北朝鮮、6カ国協議を初論評」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040229-00000047-jij-int「「午後5時がタイムリミット」=閉幕式途中で帰った米代表-6カ国協議の内幕」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040229-00000048-jij-int「<6カ国協議>北朝鮮側が失望感を表明」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040301-00002059-mai-int「次回6カ国協議は7月か=軍事介入の恐れ指摘-ロシア外務次官」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040229-00000084-jij-intこの一連のニュースを見ると、どうやら6カ国協議の行方には暗雲が立ちこめているという感じがするのだが、一方では次のようなニュースもある。「<6カ国協議>米国政府は「結果歓迎」」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040301-00002042-mai-int「6カ国協議日本代表団の対応を評価=中国次官」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040304-00000934-jij-intこれを見ると、6カ国協議はそれなりに成果を出したのかとも受け取れる。もっとも下の方の評価は、「日本代表団の態度と発言は「バランスが取れていた」として」中国から評価されたのであって、中国にとっては良かったと言うことでもあるので、日本にとっては必ずしも積極的に評価できるものではないのかもしれない。「6か国協議の作業部会、今月中にも…中国外務次官」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040304-00000411-yom-int「核完全放棄に前向き姿勢=北朝鮮が6カ国協議で表明」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040305-00000219-jij-intこの記事を見ると、6カ国協議の今後に期待するところもあるのかなと言う気もしてくる。いったいどのニュースを信じればいいのだろうかという感じがしてくる。とりあえずは、どれも疑ってかかるしかないのかなという感じかな。この問題で、本当に信頼できる人間が誰なのか、それを探すことが肝心かもしれない。
2004.03.06
コメント(0)
-
気になるニュースあれこれ
さて、気になるニュースがたくさんたまってしまったので、少し日記に書いておこう。まずは次のニュースだ。「エイズ孤児110万人 ケニア政府に危機感http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040227-00000159-kyodo-int」この記事では、「ヌギル保健相は「エイズウイルス(HIV)感染の急速な拡大で、1963年の独立以来築いてきた国家の根幹が揺らぎつつある」と、危機感を表明した。」と語るくらい深刻な状況が伝えられている。僕が疑問に感じるのは、エイズの脅威はなぜ途上国でしか語られないのだろうかと言うことだ。先進資本主義国ではこれほど深刻になっていないのであるから、ある意味では解決する方向があるのだろうと感じるのだ。それは、もしかしたら金がかかる方法なのかもしれない。だからこそ先進資本主義国では深刻な脅威になっていないのかもしれない。しかし、人がたくさん死ぬというような深刻な状況にあるのなら、それを救うために金をつぎ込むというのは、非常に価値の高いことなのではないだろうか。それはどこかで戦争をするよりも金のかかることなのだろうか。どうして、戦争には金をつぎ込めるのに、この問題には金をつぎ込めないのか。これが素朴な疑問だ。「「米国はいつ謝罪?」 被ばく50年で集会開幕http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040227-00000192-kyodo-int」米国というのは、実にむちゃくちゃなひどいことをする国ではあるけれど、論理的な行動をする国でもある。責任が明らかになれば謝罪もするし補償もする国のように僕は感じている。第二次世界大戦時の、日系人を強制収容した問題なども、その誤りを認め賠償したというニュースを聞いた記憶がある。この水爆実験に関しては、最近公開された文書には、実験当日の気象情報をつかんでいたアメリカは、被害が及ぶ恐れがあるという事実をつかんでいながら実験を強行したのだから、その責任はかなり明らかなように感じる。いつ責任を認めて、補償をするのだろうかと僕も思っている。「<米財政見通し>10年間で2兆7500億ドルの赤字 議会http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040229-00000001-mai-int」この記事では次のように語られている。「CBOの見通しによると、相次ぐ減税による歳入減やイラク関連費も含めた国防費の急増を背景とした米財政赤字は04年度に4770億ドルと過去最大を記録する。05年度以降は減少するものの、10年後の14年度まで毎年度2000億ドルを超す高水準の赤字が続くと予測している。」これを読むと、ブッシュ政権は政策の誤りを犯していると読めるような気がするのだが、アメリカの世論はどう受け止めているのだろうか。このような事実は、大統領選への影響はどの程度のものなのだろうか。今、テレビのニュースで次のようなものをしていたのが目に飛び込んできた。「<在留特別許可>ミャンマー人一家に人道上の理由でhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040305-00001046-mai-soci」日本は難民条約も批准しているのだし、ここで報道されているキンマウンラットさんは明らかに難民の条件を満たしていると見えるのに、どうして日本政府は認めないのだろうという疑問を感じていた。政府は、キンマウンラットさんをあくまでも不法滞在者と見ているのだ。それは、「野沢法相は「不法滞在者は、帰ってもらうのが原則だが、一家がそろって暮らすことは、一つの権利だと判断した」と述べた。」という記述にも伺える。一家がそろっているから仕方なく認めたというふうに受け取れる。彼一人だけだったら、不法滞在者として強制送還されていたのだろうか。もし、強制送還して、その国の政府に弾圧を受けたら、日本政府は、難民として認定しなかったことの責任を取るのだろうか。難民条約を批准していることとの整合性はどう取るのだろうか。弾圧はされないと、自信を持って言えるのだろうか。次のようなニュースもある。「ミャンマー人を難民と認定 国の調査厳しく批判http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040205-00000157-kyodo-soci」この中では次のような記述がある。「判決理由で藤山裁判長は、男性がミャンマーで受けた迫害に関する供述の信ぴょう性を認め「人種や政治的意見を理由に、拘束、拷問を受け、命を落とす可能性もあった」と判断。「難民調査官の調査は表面的事実をなぞっただけで著しく不相当だ」と批判した。」難民として認める判断もあるのだから、強制送還して迫害を受けたときには、その誤りに対する責任が生じてくると思う。日本政府は、そのように判断の重さを感じているだろうか。「<難民認定>03年は10人 入国管理局http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040228-00002059-mai-soci」この数字を見ると、日本政府は、とにかく難民を認定したくないのだなとしか思えない。主要先進国の数字と比べてみるとよく分かる。主要先進国における庇護申請受理数(2002年1月現在) イギリス 9万2000件 ドイツ 8万8300件 アメリカ 8万3200件http://cache.yahoofs.jp/cache?url=http%3a%2f%2fwww.unhcr.or.jp%2fnews%2fpdf%2frefugees25%2fref25_p13.pdf&p=%c6%f1%cc%b1%c7%a7%c4%ea++%bf%cd%bf%f4++%c5%fd%b7%d7&u=%2fbin%2fquery%3Fp%3d%25c6%25f1%25cc%25b1%25c7%25a7%25c4%25ea%2b%2b%25bf%25cd%25bf%25f4%2b%2b%25c5%25fd%25b7%25d7%26hc%3d0%26hs%3d0%26%26b%3d21%26h%3dp日本が主要先進国に入らないのなら仕方がない。この数字を見る限りでは、先進国ではないと宣言しているものだと受け取るしかない。「<同性結婚>州政府の無効訴えを却下 カリフォルニア州最高裁http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040229-00000018-mai-int」最高裁の法律判断はきわめて論理的だと思う。<同性結婚>を差し止めようとする論理的な根拠はないのだと思う。この記事の次の記述は、憲法というもののイメージとしてとても大事なものだと思っった。「サンフランシスコ市は12日から同性結婚を認め、これまでに約3400組に証明書を発行した。19日には「結婚を男女間に限ると規定した州法は、平等を保障する州憲法に違反する」として、逆に州政府を訴えた。」<同性結婚>は違法になるかもしれないが、それは、法律の方がおかしいのであり、法律が間違っているのだ、という主張のように僕は感じる。そして、その根拠は、憲法に違反するからだという明快な論理が語られている。憲法というのは、こういう存在なんだなと思う。統治権力が国民の権利を侵害してくるようなことをしてきたとき、それを押しとどめる根拠になるのが憲法なんだ。「イラク戦争賛否が争点 スペイン議会選挙戦http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040229-00000076-kyodo-int」この選挙は3月14日に行われるらしい。世界の世論の動向を見るのに、一つの物差しになるかもしれない。14日以後の続報に注目しておくことにしよう。「「最大限の貢献」要請も 空自輸送活動で連合国軍http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040229-00000098-kyodo-int」ここでは、「高官は「最大限の貢献」の具体的内容には言及しなかったが、武器類を含む米英軍の物資や兵員輸送を求める可能性がある。日本政府は「武器・弾薬の輸送はしない」(小泉純一郎首相)との立場を繰り返している。」と書かれている。憲法上出来ないと答弁していたことが、事実としてどんどん先へ進んでいってしまうものかどうか、続報に注目していきたい。憲法を無視して、事実が先へ進んでいってしまい、だから憲法を変えなければならないのだ、という議論に行かないように注目していかなければならないと思う。
2004.03.05
コメント(0)
-
買売春論議
さて掲示板の方では「買売春論議」が展開されているが、これはいろいろなところと結びついているものなので、整理しておかないと話が混乱してきそうな気がしてきたので、ここでちょっと流れを整理しておこうと思う。まず、僕がこの問題を提起したのは、「人身売買への取り組みを=米対策室長が日本に要望http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040225-00000086-jij-int」という記事を見たのがきっかけだった。、「日本の性産業などでの強制労働を目的とした東南アジアや中南米諸国からの人身売買の問題」は、買売春が違法であることが原因で巨額の不正な利益が得られることに関連しているのではないかという思いが僕にはあった。そこで、買売春が合法化されれば、この問題も解決の方向を見いだすことが出来るのではないかという発想だった。整理すると次のようになるだろうか。・買売春の違法性が闇の巨額な利益を生み出す。正規の手段で手に入らない対象には法外な値段が付くので、危ない橋を渡ってでも提供しようとする人間が出てくる。そして需要の方もかなり見込める。・上のような条件があれば、違法な手段を用いる可能性も高く、そこで人権侵害的な人身売買が行われていると考えられる。・合法化されれば、需要と供給の関係で法外ではない値段に落ち着くことが期待できる。そうすれば、犯罪を犯してでももうけようとする人間が少なくならないだろうか。また、合法化されれば、そこで働く人間を守るための法律も作られることが期待できる。・この問題は、人権侵害的な人身売買をどう防ぐかという問題意識から考えたもので、買売春の道徳性を論じようと思ったものではない。道徳性に関して言えば、僕はそれに絶対的な基準はないと思っている。以上のようなものが僕が提起した問題を整理したものだろうか。これに対してmskさんが、>競馬やパチンコのように合法化してしまえば健全化はすすむと思>いますが、そこにまた権力の利権構造が生まれるでしょうね。>罰則をものすごく厳しくして完全禁止という手もあるけれど、そ>れも抜け穴ができたり、近隣諸国にでかけるお馬鹿さんを生むこ>とになる。というふうに応えてくれた。これをきっかけとして話がスタートしたようなものだ。次にalex99さんの>売春自体は悪いことですか?という問いかけがあった。これは、僕が問題にしたものではないけれど、僕の言葉に触発されていろいろと話が展開すること自体は悪いことではないと思う。ただ、僕は買売春自体の善悪については問題にしていなかったし、善悪というような価値判断は、結局は個人の感じ方の違いになってしまい、議論としては、それは悪いとも言えるし悪くないとも言えるというところに一般的には落ち着くんじゃないだろうか。その後シャルドネ☆さんが加わって、買売春そのものの話ではなく、セックスに関する習俗に関する話題に展開していった。これも、僕が提起したものと直接の関連はなかったので、僕は掲示板では言及しなかった。これについては、違う歴史・違う生活環境にある民族が、自分とは違う感覚で物事をとらえていても、それはきわめて当然のことだろうという一般論的な感想は持っている。それを我々の道徳から断罪はできないと思っている。逆に言うと、歴史も習慣も違う我々がそれをうらやましがっても仕方がないかなという気持ちもあって、あまり深く感想を考えなかった。そのこと自体を云々するというだけの関心を持っていないからだろうと思う。僕が関心を持ったりするのは、たとえばイヌイットの習慣などを、先進資本主義国で同じようなものを考えればスワッピングというようなものになるだろうか。それをするのに、イヌイットでは全く当たり前の行為として、ただ楽しみのためだけに行っているように見えるが、先進資本主義国ではあからさまにそれを行うことが出来ずに、隠れて行う必要があるという違いにまず注目する。そして、それを隠れて行うということから、純粋な楽しみとしておおらかにやるのではなく、何かあるストレスに追い込まれて、そうしないでは、たとえば夫婦の関係性が保てないような、病理性が先進資本主義国には見えそうだ、というような面に関心を持ったりする。この一連の話題の流れに対して、男ばかりの見方が提出されていることに、mskさんが、女性の見方も知りたいという呼びかけをした。これは、とても慧眼を感じる提案だったと思う。イヌイットの習慣にしても、僕はそれは地域も歴史も違うからだという単純な理解だけしかしていなかったけれど、そういう単純な受け取り方しかできないのは、やはり男の目で物事を見ているからではないかとも思えるからだ。男にとってたいしたことではないことでも、女にとって気になることなら、そこに男の考えの中に欠けているものを女の目から気づかせてくれることがあるかもしれない。そういうことを感じたので、mskさんの発想は素晴らしいなと思った。それに応えてくれたとむぼさんの発言は、まさに、男の目では気づかない何かを教えてくれたと思っている。イヌイットの習慣にしても、女の側に選択権がないのなら、それは男の勝手な、男にとって都合のいい習慣にすぎないものになってしまうだろう。男女が対等の立場で、どちらにも選択権が保証されているというのが、民主主義が発達した後の、このような習俗ということになるだろう。もしそうでないのなら、だんだんと廃れていくのが歴史の流れになるのではないだろうか。とむぼさんの書き込みは、男が忘れているもう一方の見方を気づかせてくれる、そんなものとして受け止めたいと思う。ただ、それが感じ方の違いにかかわる部分であれば、感じ方が違うのであればそれは仕方がない。どちらが正しいとか間違っているとか議論できるものではない。議論できるのは、真理が云々出来る範囲のもので、それはかなり一般論の範囲で展開しないと難しいのではないかと僕は思っている。だから、感じ方の部分は、感想として相手の言葉を受け取った方がいいだろうと思っている。宮台氏は、買売春行為をする日本の男たちを巡って、保守性の残る男たちは、自分の買売春行為を容認しても、妻や娘の買売春行為を認めないというようなことを語っていた。でも、これは対等性という意味ではおかしいと僕は思う。自分の買売春行為を認めるのなら、妻や娘が同じ行為をしても、それが自らの意志から出た行為であれば、同じように容認するのが対等性ではないかと思う。もし、妻や娘の行為を認めないのなら、自らもそれをしてはいけないのだと思う。買売春行為自体を論じるには、それが含む範囲がものすごく広いので、その前提をかなり共有しないと難しいだろうと思う。宮台氏のレポートで、援助交際をする高校生を論じたものがあったが、その中には、優等生として育った少女が、その自画像を壊すための手段として援助交際があったというような報告があった。これなどはなかなか深い問題をはらんでいるので、道徳性のみを論じて判断することが出来ない。また、宮台氏は性的弱者としての男を論じていた。女の方は、自らが望めばセックスの相手が見つからないということはほとんどないにもかかわらず、男は、それを望んでも相手がどうしても見つからない性的弱者が存在するというのだ。そのような性的弱者にとって、買売春というのは、自分の欲望を満たす唯一の方法かもしれない。そうなればどんなに違法であっても、それをしたいという人間が出てくるだろう。村上春樹の小説には、快楽の極限を求めるセックスという描写がよく出てくる。それは、愛というよりもやはり快楽を求めるという印象が僕にはあった。今の日本に住んでいる人間で、快楽のみを求めるというモラルを受け入れられる人間は少ないだろうと思う。しかし、村上春樹が描くその情景はとても芸術的で美しささえ感じる。それは、直接買売春の問題ではないけれど、モラルとして普通の状態では快楽だけを追い求められないとしたら、買売春行為という特殊な条件の下ではそれが出来るかもしれないと、男は妄想するのかもしれないな。とりあえず、買売春論議に関しては、議論の流れがずれてきたなと感じたら、お互いの前提の共有が難しくなってきたと受け取ることにしましょう。そういうときは、違う発想の感じ方を教えてもらったんだと考える方がいいと思います。
2004.03.04
コメント(5)
-
買売春論議と今日の気になるニュース
mskさんの書き込みのおかげで、買売春の合法化についての対話がいくつか書き込まれている。僕は、こういう社会制度に関する問題は、道徳感情から判断をしない方がいいのではないかと思っている。買売春行為に関しては、道徳感情から嫌悪感を抱く人もいるかもしれないが、いやだからと言って法律で禁止して取り締まるべきだと考えない方がいいと思う。社会制度の問題は、少々ドライに見えるかもしれないが、様々な面を考慮して、社会への利益が最大になるような方向を合理的に判断して決める方がいいだろうと思う。買売春が違法である現在の状態が、不法な組織の不法な利益を生み、それの犠牲にされる人間を生んでいる。合法化によって、この状態が改善されるのかどうか。また、合法化されることによって、モラルの低下が起こったり、今は隠れて行われていることが、あからさまに見えるように行われることによって、何らかの悪影響がでるものかどうか。これは、予想は出来るが実際にどうなるかははっきりしたものは分からない。実験的に確かめて判断するしかないのではないかと思う。ドラッグ(麻薬)に関する合法化の問題なんかも同じような構造を持っているだろうと思う。違法状態であることが、ある種の組織の財源になっていたり、それを手に入れるために犯罪に手を染めるという影響があったりする。合法化によって、それらが防げるのかどうか。合法化によって誰にでも手が出せるようになると、麻薬中毒になる人が増えたりするのかどうか。オランダという国はドラッグを合法化していると聞いたことがある。だから、オランダという国がどうなったかということが調べられれば、一つの実験結果として受け取ることが出来るのではないだろうか。買売春が合法化されている国はあるのだろうか。もしあれば、その国の経験が一つの実験として受け止められるのではないだろうか。果たして、メリット・デメリットどちらの方が大きいのか。道徳を基礎にした法律としては、アメリカの禁酒法と、日本の生類憐れみの令を思い出す。いずれも板倉聖宣さんが仮説実験授業の授業書を作ったものだ。そこでは、設立の際の道徳心情がいかに美しく正しいものであろうとも、それを守りきれない人が多数いるような法律は、その法律の設定は、目的と逆の結果を招くという実験結果が出ている。生類憐れみの令では、生き物を可愛がるどころか、生き物に対する恨みさえ生まれてくる。日本の男が、これだけ買売春の禁止を守れないとしたら、法律で規制しているからかえってモラルの低下を招いているとも言えるのかもしれない。さて今日の気になるニュースは次のものだ。「<03年版人権報告>北朝鮮を昨年に続き厳しく批判 米国務省http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040226-00001033-mai-int」このニュースを解釈するには二つの面を区別して考えなければならないのではないかと僕は感じている。一つは、事実として人権侵害のある国に対し、厳しく批判していく目を持たなければならないという面だ。その指摘を重要なものとして受け止めることを考えなければならない。もう一つの面は、指摘をしているアメリカ自身にも問題があるという面だ。アメリカが清く正しい国で、間違いを犯さない立場から、他の国を断罪しているのではない。アメリカ自身にも問題はあるが、たとえ問題はあっても、他の人権侵害を指摘するということは非常に大事なことだから、あえてそれをしているというとらえ方が大切だ。この両者を一緒くたにしてしまうと、アメリカに他人を非難する資格はないということを言って、自分のことを棚に上げる国が出てきてしまうことになる。逆に、他人の欠点をあげつらって、自らに何も言及しなければ、結果的にアメリカは問題にされないということになる。ちゃんと区別しないで、一緒くたにしてしまうと、結果的に双方の人権侵害が免除されてしまうことになる。きちんと区別して、人権侵害そのものが不当なものだという認識を持って、この報告を見る必要があるだろうと思う。「北朝鮮の状況、拉致や拷問など詳述…米の人権報告http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040226-00000303-yom-int」ここには具体的に次のような記述がある。「また、関係者の証言や国際機関の調査をもとに、中国が強制送還した脱北者のうち妊娠中の女性を、北朝鮮当局が監獄内で強制的に堕胎させていると指摘。監獄では電気ショックを与えるなどの拷問が横行し、収容者には医療処置も一切施されないとしている。」これが事実だとしたら、本当にひどい人権侵害だし、許されるものではない。非難されるのは当然だ。しかし、ここでただ非難することだけにとどまるのであれば、正しい区別をしていないことになる。このことに非難する感情を持つのなら、たとえば日本における代用監獄の問題なども、同じように人権侵害として非難する感情が生まれなければ、その感情に差別感があるのではないかという疑いを感じる。アメリカが未だに収容しているという、キューバの基地のアフガン人たちへの人権侵害にも同じように非難する感情を持って欲しいと思う。一方には感じるが、もう一方には感じないというのではイノセント(無知)なノーテンキさだ。また、両方に非難の感情を感じても、どっちもどっちだというような結論に落ち着いてしまうと、正しい区別をせずに、ただ一緒くたにしてしまっただけになる。どちらも同じように非難されるべき人権侵害だという判断がなければならないだろう。「「一国主義で他国侵害」 中国、米人権報告に対抗http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040301-00000068-kyodo-int」中国は、どっちもどっちだといいたい感じなんだろうけれど、こういう暴露合戦は、権力の座に遠い人間にとっては判断の材料を増やしてくれるので歓迎する。正しく区別して受け止められれば役に立つ情報になるだろう。「<イスラエル>パレスチナの銀行を急襲 過激派の口座から金押収http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040226-00001036-mai-int」この記事は、正当性のある目的のためには手段の違法性が正当化されるか、という問題を提起していると僕は感じた。僕は、一般論的には、たとえ目的に正当性があろうとも、手段の違法性は認められてはいけないと思う。それは一度認めてしまえば必ずエスカレートしていくからだ。その手段によって、必ずしも正当性のある目的の方が達成されるとは限らない。それでも、一度このようなものを認めてしまえば、もう他のものに飛び火してもそれを押しとどめることは出来なくなる。自衛隊の海外派遣も、最初はほんのわずかの活動にすぎなかったのに、一度認めてしまったら、重武装をしてイラクに送り出すことになってしまった。構造的には、同じものを僕は感じる。ハイチ問題は一応の結末を迎えたのかなと思ったら、また気になるニュースがあった。「ハイチ武装勢力が首都入り 数百人の住民歓迎http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040302-00000011-kyodo-int」数百人というのが多いのか少ないのかの判断が難しいが、住民が歓迎しているということは、武装勢力の方に正当性があるということなのだろうか。武装勢力などというと、イメージ的には悪い奴らという感じがするのだが、住民を解放するという存在だったのだろうか。「危機収束祝う市民、首都正常化へ=多国籍部隊も活動開始-ハイチhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040302-00000336-jij-int」という記事では次のような記述もある。「現地からの報道によれば、前夜に到着した米海兵隊の約200人は大統領官邸や国際空港の警備に当たっているが、市街には展開していないようだ。これまでのところ、一般市民や反アリスティド派の武装勢力は国際部隊を歓迎しており、大きなトラブルは報じられていない。」海兵隊と武装勢力とは衝突をしていない。戦闘が行われていないことを、もちろん市民は歓迎しているのだろうが、両者の存在そのものも歓迎しているのだろうか。ここら辺はなかなか真相が分からないな。次のような記事もあるからだ。「「米国によるクーデター」 ハイチ前大統領訴えhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040302-00000100-kyodo-int」ここでは次のように語られている。「「強制的に出国させられた。米国によるクーデターだった」-。ハイチのアリスティド前大統領は1日、中央アフリカから米CNNの電話取材に応じ、辞任したと伝えられているのは間違いで、米兵に囲まれて無理やり出国させられたと訴えた。」ここには手段の不当性のにおいを感じる。目的の正当性がこれを認めてしまうのだろうか。市民にとっては結果的にはどっちが良かったのかは、これからの展開で決まっていくだろう。軍事クーデターを起こしているので、軍政が敷かれることが予想されるのだが、世界の国で、軍政が市民を弾圧しなかったという国が思い当たらない。アメリカは、このクーデターに関与していたのだろうか。関与していたとすれば、どういう利益計算で関与したのだろうか。ハイチの問題は一つの決着を見たと思ったのだが、まだ終わりはないのだろうか。
2004.03.03
コメント(33)
-
ハイチ問題その後
今日の最初の注目ニュースは次のものだ。「人身売買への取り組みを=米対策室長が日本に要望http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040225-00000086-jij-int」ここで言われているのは、「日本の性産業などでの強制労働を目的とした東南アジアや中南米諸国からの人身売買の問題」だ。宮台氏の本で、買春行為の数から言えば、日本の男が世界で一番多いだろうという記述を見たことがある。需要のあるところには供給もそれなりにあるということだ。宮台氏は、買売春をむしろ合法化した方がいいということも言っている。僕も、非合法的な組織の収入源になるようなら、合法化して、そこで働く人間を守った方がまだいいのではないかと思っている。非合法だから、悲惨な人身売買のようなことも行われるんじゃないかと思う。買売春を合法化する方が野蛮で遅れているのか、人身売買のようなことが行われている方が野蛮で遅れているのか、どっちなんだろうか。これが素朴な疑問だ。さて、以前に注目したハイチ情報に関しては、その後も様々なニュースが飛び込んできている。まずは次のものに注目しよう。「ハイチ武装集団が北西部の都市制圧、北部一帯支配下に[2月25日19時24分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040225-00000212-yom-int」この時点では、まだ次のように語られている。「しかし、野党主体の反政府勢力は24日、調停案を最終的に拒否することを明らかにした。パウエル米国務長官は、受諾を求めていたが、同案に大統領退陣が盛り込まれていないことに反発した形だ。」アリスティド大統領は、「武装勢力が首都に侵攻したら、数千人が殺害される可能性がある」と語っていたそうだ。この記事のトーンで言うと、武装勢力というものが、何か恐ろしい集団で無法な殺戮を犯す奴らだという印象を与える。本当にそうなんだろうかというのが素朴な疑問だった。果たして大統領側とその反対勢力と、どっちに理があるのだろうかという疑問を持っていた。「早期の国際部隊派遣を拒否 政治解決先決と米大統領[2月26日9時3分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040226-00000022-kyodo-int」この記事を読むとアメリカは、「交渉により平和的に事態を収拾するよう促した」とある。イラク戦争でのアメリカの態度との整合性を取るには、ハイチに対しては、アメリカは緊急の危機を感じていないと解釈しなければならない。そうすると、大統領の側にも、その反対勢力の側にも、それほどの無法性を感じていないのだろうか。複雑な利害関係が絡んでいてアメリカが国際部隊の派遣を拒否していたのだろうが、建前としてはハイチの情勢を平和的に解決できると解釈していたと受け取らなければ論理的な整合性がとれない。この時点ではそうだったのだろう。しかし、次のようなニュースを見ると、そう解釈するのには無理があるのかなという感じもある。「武装勢力近く首都攻撃か ハイチ、無法地帯化[2月26日9時48分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040226-00000030-kyodo-int」ハイチに関しては、武装勢力を鎮圧して平和を取り戻すべきなのか、大統領を追放して反対勢力にゆだねるのが理があるのか、いったいどっちなんだろう。「フランスがハイチへの国際警察部隊派遣を提案[2月26日10時15分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040226-00000978-reu-int」フランスの認識は、「フランスは、ハイチの秩序回復のため国際警察部隊の派遣を提案するとともに、内乱を招いたアリスティド大統領を非難する声明を発表した。 ドビルパン外相は声明のなかで、ハイチ全土に拡大している暴動についてはアリスティド大統領に重大な責任がある、と指摘。声明は、大統領辞任を求めるものとも受け取られている。」というふうに語られている。これを見ると、大統領の側に非があり、反対勢力にむしろ理があるとフランスは見ているのだろうか。その後のニュースでも、ハイチの混乱した状態を伝えている。「ハイチ武装集団戦線、南部にも拡大…首都パニック状態[2月26日10時27分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040226-00000102-yom-int」「退陣拒めば首都攻撃と宣言 ハイチ、反政府勢力[2月26日14時4分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040226-00000090-kyodo-int「内戦状態のハイチ、大統領への辞任圧力強まる[2月27日19時15分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040227-00000511-yom-int」「<ハイチ>首都は無政府状態に[2月27日20時54分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040228-00000067-mai-int」この記事の中には次のような記述が見られる。「首都攻防に伴う銃撃戦とともに懸念されるのは、混乱に乗じた一般市民による略奪行為だ。アリスティド大統領が米軍2万人の援護で帰還した94年、ハイチ軍は解体され、国内には警察官約4000人しかいない。実際に首都を守るのは大統領の与党や企業が貧困層や犯罪者から募った「人民機構」と呼ばれる民兵集団で、この一部が「防衛」を名目に強盗になり代わっている。」こういう事実があるということになると、どうも大統領側に理があるようには見えなくなってくる。武装勢力と呼ばれる人たちの怒りの方に正当性があるのではないかとも思えたりする。「<ハイチ大統領>隣国ドミニカに出国 流血避け辞任[3月1日1時26分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040301-00000076-mai-int」大統領は、内外からの援助が得られないということを悟って、国外に逃れたようだ。破滅的な最後にならずにすんだことは、賢明な選択だったかもしれない。「<米国>ハイチ大統領に退陣勧告 「統治能力に疑念」[3月1日2時41分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040301-00000033-mai-int」この記事を見ると、大統領退陣の決め手になったのは、やはりアメリカの影響力が一番大きかったのだなということが分かる。この記事に寄れば、「米国の声明は、アリスティド大統領が武器を与え指示した暴力集団が、首都ポルトープランスで略奪を行い、民間人や国際支援団体まで攻撃していると非難。大統領支持派に暴力行為の中止を命じるよう、アリスティド氏に求めた。さらに、現在の危機的状況は、アリスティド氏自身の行為によるとの認識も明示。「自らの責任を認め、ハイチ国民の利益のため行動すべきだ」と述べた。」ということなので、大統領を支えるということは理屈から言って出来ないのだとアメリカが判断したことが分かる。「ハイチへの海兵隊派遣命令=米大統領[3月1日9時1分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040301-00000092-jij-int」という記事に続いて、「ハイチに多国籍軍派遣 治安維持へ米が主導[3月1日8時32分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040301-00000026-kyodo-int」という記事を見ると、「反政府武装勢力の指導者の1人、ギ・フィリップ元国家警察部隊長は29日、米CNNテレビとの会見でブッシュ政権の海兵隊派遣について「完全な協力をする。戦闘の時期は終わった」と歓迎する意向を表明した。」という報道も見られる。これを見ると、アメリカが乗り出したことによって、反対勢力の側も戦闘の終結を宣言したことが分かる。アメリカの力を持ってして、ハイチの問題は解決できたのである。ここで素朴な疑問だが、アメリカは、この力の行使をなぜ最初はためらったのだろうか。そこにはどのような利害の計算が働いたのだろうか。一連の報道だけではそこが見えてこない。アメリカ国内からも、「ブッシュ政権のハイチ対応批判=「いつも遅い」-米民主党候補が討論[3月1日9時2分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040301-00000103-jij-int」というような批判が出ている。ここでは、「緊迫するハイチ情勢について、ケリー氏は「ブッシュ大統領の対応はいつも遅い」などと批判。エドワーズ氏も「(大統領は)ハイチのことを無視してきた」と、ブッシュ政権批判で足並みをそろえた。」と伝えられていている。どうしてハイチを無視してきたのか、その歴史を知ることが出来れば、アメリカがこの問題に手を出すのを最初はためらっていたのが分かるのだろうか。「<ハイチ>多国籍軍派遣、国連安保理が決議[3月1日15時6分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040301-00001042-mai-int」この記事を読むと、ハイチの問題は正当な手続きによって解決の方向へ向かうのかなという感じがする。ここでも、「アナン氏は決議採択後、「国際社会は彼らを忘れていないことを示した」と述べた。米仏両国の国連大使も歓迎を表明した。」という記述があることを見ると、ハイチの問題で一番の大きなことは、ハイチが無視され続けてきたことだったのかなという感じがする。また、最初にハイチ問題が報道されたときに、国連自身がためらっていた背景には、「安保理は26日にもハイチ情勢を協議。周辺国から早急に多国籍軍派遣を要請されたが、当面政治的介入を避けたいとして、情勢への「懸念」を表明したにとどめた。」という考えがあったようだ。そうすると、アメリカにも同じようなためらいがあったと考えることが出来る。しかし、アメリカの情報力は、いち早く対応を提案することが可能なくらいの情報力があるのではないだろうか。一連の報道を見ていると、アメリカは事態の進行から、仕方なく手を出さざるを得なかったようにも見える。情報が集まるまで控えていたが、積極的に解決を図る意志があったとは見えないのだが、それがもう一つの疑問だ。「ハイチ首都、治安維持へ米海兵隊第1陣が到着[3月1日21時42分更新]http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040301-00000113-yom-int」ここには次の報道が見られる。「武装勢力の指導者ギイ・フィリップ氏は同日、米CNNテレビに対し、ボニファセ・アレクサンドレ暫定大統領への支持を表明。その上で、「もう戦う意思はない。最悪の事態は終わった」と述べ、米軍や多国籍軍への協力を約束した。」これで、ハイチの当面の問題は解決したことになるのだろう。しかし、どうしてこのような武力衝突が起こったのか、世界へは忘れずに報道してもらいたいものだと思う。国際社会が忘れていたハイチで、いったい何が起こっていたのか。それは、平和を望む人々にはきっと参考になる事実があるのではないかと思うからだ。ハイチ問題はこれで一段落したようだが、他にも目を引くニュースは目白押しだ。とりあえず今関心があるのは次のようなニュースだ。・米国務省が発表した<03年版人権報告>・<対人地雷禁止条約>、<海洋法条約>等のアメリカの批准の動向・自衛隊のイラク貢献(米高官の「最大限の貢献」という言葉が具体的にはどういうことになるのか?)・6カ国協議の各国の評価と今後の行方・ビンラディン拘束のニュースと今後の行方(大統領選にあわせて拘束されたりしないだろうか)・イラクにおけるテロと反米感情の行方(自衛隊も標的にされるのか)・イラク基本法でのイスラム教の扱いとアメリカが押しつける民主主義との整合性・民主・佐藤観樹衆院議員に元秘書「名義借り」疑惑興味が尽きないニュースが次から次へと報道されるな。
2004.03.02
コメント(7)
-
論理的な疑問あれこれ
今日もニュースを見ながら素朴な疑問を記していこう。まずは次のニュースだ。「同性結婚禁止の改憲支持 米大統領、選挙にらみhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040225-00000056-kyodo-int」この中では、「大統領は「一部の地方行政当局者らは結婚を再定義しようとしている」と批判、結婚制度を守るため憲法修正が必要と強調した。」と語られているが、このことが同性結婚の禁止をするほどの根拠になると言うことの論理的な整合性が僕には理解できない。結婚の再定義によってどのような不利益が生ずるのだろうか。そして、その不利益は実質的にどのような損害に結びつくのか。それは、同性結婚をしたいと望む人たちの権利を押さえてでも守らなければならないものなのか。論理的に結びついてくるものかどうか、全く疑問だ。結婚の定義が変えられるというのは、本来は男女の間に成立した結婚を、そうでない関係に成立するように変えるのが悪いという考え方だろうか。しかし、そのことによって誰が損害を受けるのか。保守的な人間は、心情的な損害を受けるかもしれないが、自分が気分を損なうからと言って、人の権利を押さえてもいいという論理が成り立つのだろうか。現実に物質的な損害がない限りは、権利は認められなければならないのではないか。同性結婚を認めたくないと言うのは、ある意味ではこれまでの道徳が破壊されるのを恐れているということのように感じる。しかし、道徳を法律で押しつけた行為というのは、かつての禁酒法や日本の生類憐れみの令のように、決して期待通りのものにはならないという経験がある。道徳というのは、人から規制されて守るものではなく、主体的に自らが望んで守るところに価値があるからだ。「日本、拉致問題めぐる北朝鮮への直接非難控える=6カ国協議の冒頭声明http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040225-00000913-reu-int」この記事に疑問を感じるのは、日本国内の世論は、核問題よりも拉致問題の方が重要だというものなのに、なぜ直接の非難を控えたのだろうかということだ。この問題に関しては、世論の動向というものに追随する形で政府が動いているのではないかという感じすらしたのに、ここではなぜ世論を裏切るような展開があったのだろう。一つ考えられるのは、どこかから圧力がかかって、本当は言いたいことが言えなかったという見方だ。中国やロシアは、核問題を優先して協議を望んでいたので、こちらから圧力がかかったのだろうか。しかし、よく考えてみると、多国間協議で問題にされるのは、どの国にも深刻にかかわってくる問題が優先されるのは論理的には自明のことだ。拉致問題も日本にとっては重要な問題には違いなけれど、多国間協議が必要な問題かどうかということは、必ずしも自明ではない感じもする。そういう論理的判断から、まず核問題を優先させたのだと、政府が判断したのなら、これはそれなりに論理的な判断のように思うのだが、果たして日本の世論はこれをどう受け止めるだろうか。「精力的、日本語堪能…6か国協議議長役の王毅外務次官http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040225-00000104-yom-int」この記事は、上のものとの関連で、次のところに注目してみた。「6か国協議の準備のさなか、「米国に対して1番、影響力があるのは日本だ。米国に話をしてほしい」と日本側関係者に語った。中国外務省きっての日本通だけあって、日本の立場への理解は深い。懸案である日本人拉致問題でも、水面下で北朝鮮に働きかけてきたと見られる。」日本が、この中国の期待に応えることが出来れば、ある意味では中国に恩を売ることが出来る。そうすれば、日本のために有利に中国が動くということを要求することも出来るだろう。朝鮮民主主義人民共和国に対して、中国は非常に大きな影響力を持っているから、圧力をかけるのなら、中国の助けがあればかなりの力になるだろう。中国が、道徳的な感情や日本への同情で動くというようなことは考えられないから、お互いに利益になるようなものを与えあうという関係で外交をしていかないとならないのではないかと思う。中国へ与えるものとして、果たして日本はアメリカに影響を与えることが出来るだろうか。その点はちょっと心配だ。「対北朝鮮、核凍結の見返りない…米高官が強調http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040225-00000206-yom-int」という記事を見ると、アメリカは妥協を考えない立場であることが分かる。しかし、中国は何らかの成果を出すために、一歩でも進めたいと思っている。アメリカが、完全な形での核放棄を宣言しないと何も認めないと言う態度で、一方で朝鮮民主主義人民共和国では、何らかの妥協がなければ完全な放棄は認めないということなので、このままでは一歩も前に進まない。果たして日本が、何らかの妥協をアメリカから引き出すことが出来るだろうか。そうすれば、中国に対して強いカードを持ちうると思うのだが、日本もアメリカとともに、朝鮮民主主義人民共和国の方が折れない限り、何らの妥協もするべきではないという立場でいると、中国に対するカードは持てないということになるのではないだろうか。「6カ国協議、大きな進展ないまま閉幕http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040229-00000246-reu-int」この表題を見ると、日本の影響力は、中国が期待した結果はもたらさなかったのかなという感じがする。日本が、中国の期待に応えようとしなかったのか、応える力がなかったのか。この記事の中身を見ると次のような記述もある。「一方、ある米政府高官は、北朝鮮の非核化実現に向け、北朝鮮以外の全参加国が一致したと述べ、今回の協議は「非常に成功した」と宣言した。 同高官は「極めて重要な点で期待を上回る成果が得られた。北朝鮮の完全で検証可能かつ不可逆的な核放棄、という米国の目標に向かって協議を進めることができた」と述べた。」これはどう解釈すればいいんだろうか。アメリカは結果に満足しているということだろうか。大きな進展がないということがアメリカにとってはいいことなんだろうか。冷戦が終わって、一方の側の大国がなくなったということは、論理的にいえば過大な軍事力の必要がなくなるということにつながってくるだろうと思う。今のアメリカの軍事力は、だんだんと縮小されていく方が合理的だ。もはやアメリカと戦争をしようと思う国はなくなっているのだから。しかし、それでは軍事的な利権を持っている人間にとってはもうけの種がなくなることになる。何とか世界の緊張が残っていた方がいい。そういう意味では朝鮮半島の緊張というのは、今のアメリカにとってはまだ残っていた方がいいものなのかもしれない。一方では、ハイチで起こっている混乱などは、アメリカの軍事力を有効に使うにはあまり便利じゃないものなんだろうな。アメリカの軍事力を持ってすればハイチでの混乱を治めるのは簡単だろうけれど、一度そのような前例を作ってしまうと、今後そのような紛争はいつでもアメリカが制圧するということにもなりかねない。そうすると、金がかかるばかりであまり利用価値のない戦争に手を出さなければならないということになるのを恐れているのだろうか。世界中にハイチのような混乱というのはたくさんあると思われるからだ。正義や道徳で国家が動くというのはあり得ない。国家意志は個人の意志がそのまま実現するのではないからだ。個人ならば利害を超えた感情で動くこともあり得るが、多くの人間がかかわる国家意志では、利害の計算の結果利益の大きい方へシフトすると思うからだ。でも、論理に従って動くという可能性は持って欲しいものだなと思う。そうであれば、人間が賢くなりさえすれば、悲惨なことをもっと減らすことができるんじゃないかと思うからだ。
2004.03.01
コメント(0)
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
-

- 今日のこと★☆
- 今日は、うずしおベリー記念日ですよ…
- (2025-11-15 08:30:04)
-
-
-
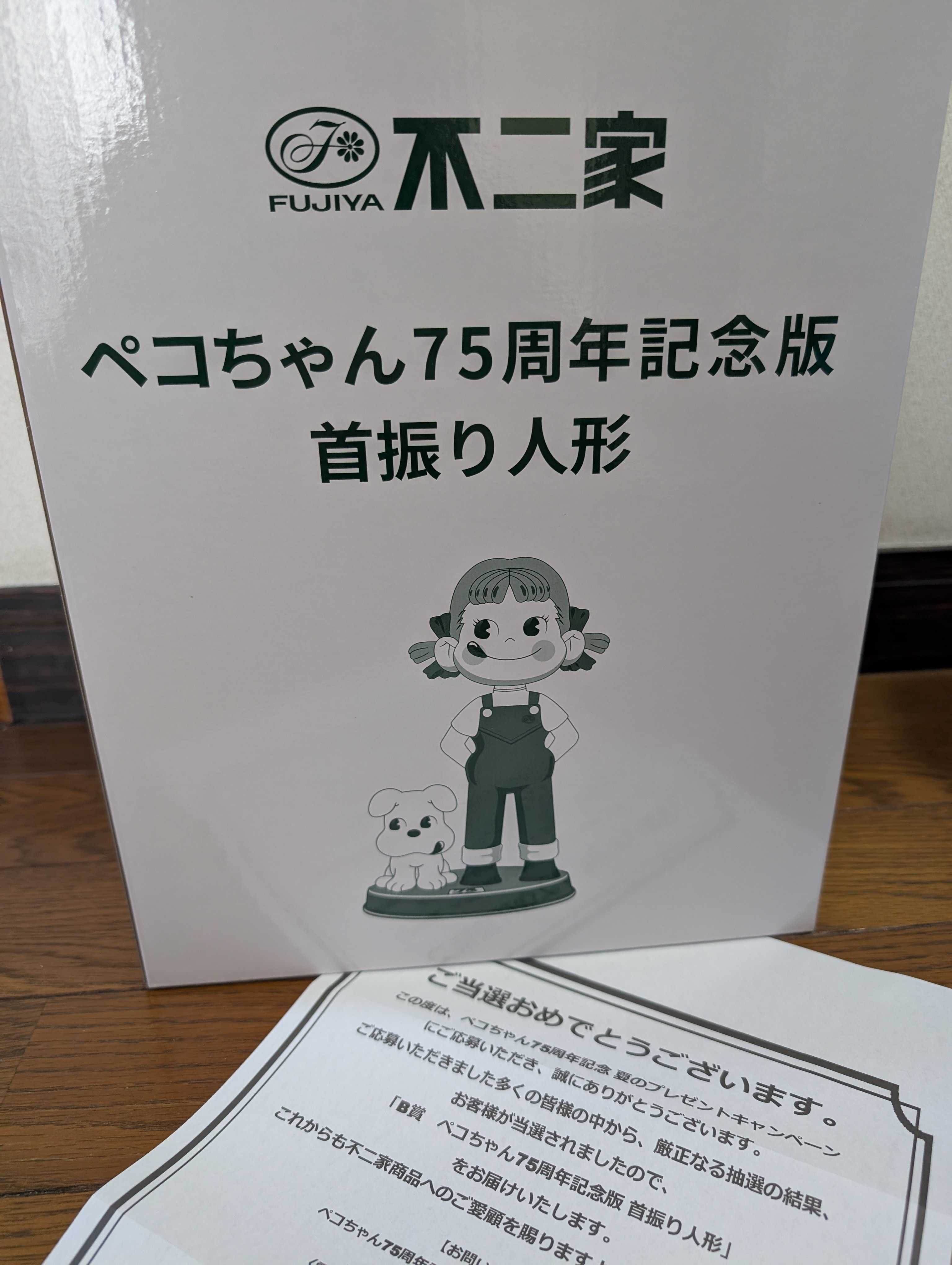
- 懸賞フリーク♪
- ペコちゃん首振り人形
- (2025-11-15 09:01:50)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 「届くのが遅すぎて使えない…」楽天…
- (2025-11-14 22:00:05)
-







