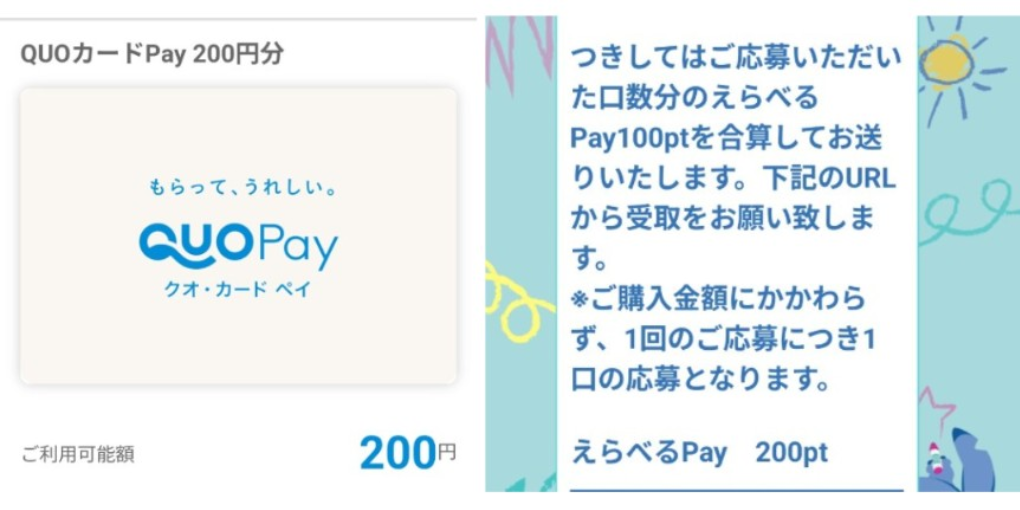2014年08月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

海外仕事術「グローバル人材の次に来るのは…」
「中国は人脈が大事だ」とは良く聞く言葉です。実際に現地で仕事をしてみると痛感します。問題はどんな人脈が自分たちの仕事に適しているのか?を見極めることが大事だと思います。だから、別にひとつの人脈にこだわることなく、色々と付き合ってみる…それに限ると実感しています。この1-2年は、上海のハーレーオーナーズクラブのメンバーと付き合うようになりました。 ビジネスである程度成功すると別荘を買い外車を乗り回すようになり、その先は「趣味こだわりの世界」に入っていくのはどの国でも同じようなもの。上海でハーレーに乗れるのは相当裕福なければ無理です。車体価格も日本の約2倍以上の上に、そもそもナンバーがなかなか取れません。譲ってもらう人がほとんどで、その値段も200万円前後と高額です。だから1台のハーレーを所有するには何だかんだで500万円は必要で、それに改造を加えていけば、パーツも高いのですぐに1,000万円オーバーです。およそ1,000人のメンバーがいると言われている上海ハーレーオーナーズクラブですが、その中心メンバーが約50名ほどいます。ホテルのオーナー、病院の経営者、航空会社の役員、医薬品メーカーの社長、レストランチェーンのオーナー、旅行会社や不動産会社の経営者、古美術商のオーナーなど、実に多彩な職業です。普通に会社をアポを取って訪問していたら、プレゼンに漕ぎ着けるだけでも相当な労力を要しますが、まずは「バイク好き仲間」に入ってしまえば、そこでバンバン紹介が始まります。経営者が多いから、プレゼンの書類も必要なし。後日、秘書に見積を送信しておけばOK…というパターンで仕事の依頼が来るようになりました。私も学生時代からバイクに乗っているので、本当にスムーズに仲間に溶けこむことができました。彼らからすれば、ほぼ同年代の日本人のバイクライフに興味津々で、「高校時代から乗ってた」ことには相当驚いた様子でした。普段は「日本人と中国人」の関係の中でビジネスをしなければならないことがほとんどですが、「バイク」という共通の趣味のお陰で「バイク仲間」となり、会話も「バイクに乗る人、乗らない人」の分類になるわけです。そのせいか私は上海で日本人の知り合いが少ないです(ほんの数名)。もちろんゴルフ仲間もいません。もう完全に上海のおっさん社会にドップリです(笑)。たいていは研修がない日の夜は、ハーレーオーナーの誰かの店に集まっています。夜に会うと荒くれ者風ですが、昼間に会うと、ビジネスマンばかりです(笑)。海外で「社会に溶け込むのは大変」というイメージを持つ人もいますが、自分に合うジャンルを入り口にすればとてもやりやすくなる、という事例の1つだと実感しています。私の場合、現地での主な仕事はサービス業の従業員の研修ですが、この3年間は一度もプレゼンをしたことがありません。また、このクラブメンバーからの紹介で、訪日旅行客のアテンドをしています。富裕層ツアーもしかり。訪日客数もこのクラブメンバーの皆さんからの波及効果で昨年だけで約2,000人が日本に来ました。MICEも彼らが経営する企業の依頼がほとんどです。このように、まともに人脈が噛み合えば歯車がどんどん回る…そんな体験をしています。海外ビジネスというと、何やら「グローバル人材」などと言う単語が流行っていてますが、それ以外にも今までとは違う「ビジネスの入口」を開けることができる「趣味を持っている人材」も大事で、(仕事によっては)その方が大事な時代になっていくのかもしれません。★レジャーサービス研究所のホームページ★
2014/08/30
コメント(0)
-

スマホが中国経済を失速させる?
中国経済はこれからどうなるのか?どんな風に失速するのか?などの報道が絶えません。色んな意見はあれど、ピークが終焉したのは間違いないでしょう。それでどんな影響があるのか?も、国や業種によって違うし、個人も職種によって違うと思います。(業績低迷になる業種もあれば、逆に好業績に転じる業種もあるでしょう)経済失速の理由もマクロ経済学の視点であれこれ語られますが、現場の視点で見るとまた違った原因が見えてきます。その1つが「スマホ」です。このところ、スマホの普及に合わせて中国のIT企業の好業績が伝えられてきます。ネット通販の伸びと金額も凄まじい勢いで拡大しています。なので、その周辺の企業は好調です。一方で、残念なこともあります。それは、かつて「中国の接客サービスはひどい!」という世界的な評判を一蹴すべく、国際的な大イベント「北京オリンピックと上海万博」を機に、マナー教育の徹底をはかりました。上海万博終了後は、しばらくはそうした成果を体験できた時期があります。しかし、それから3年も経つと段々とレベルが下がってきます。さらに追い打ちをかけているのは「にスマートフォン」の普及です。仕事の業務効率に役立つだけならいいけど、実態は「サボり道具化」してい、それに抑えが効かない状態です。先日、上海浦東空港の中のステージでピアニストの演奏がありました。まぁ客達はあまり興味なかったようですが、美しい音色が響くのは心地良いものです。しばらく見ていると、客が少ないのをいいことに、明らかに曲の途中で演奏を止めてスマホをいじり出しました。それが落ち着くと、次の曲を始めます。一極終わる度に「しばらくスマホ…」そんな演奏でした。その他、街中の店舗を覗けば客がいない時は皆スマホをいじってます。(店によっては客がいても、、、:汗)これはもう枚挙に暇がありません。ただでさえ人件費が高騰している中国。それでも生産性が向上すれば問題ないけど、逆に生産性が下がってしまっているのが現状と言えます。(もちろん極一部では接客サービスが向上している企業や店舗もあります)これは店舗だけはなくて、オフィスワークでも同様の傾向があるようです。結局、何かが普及しても使う人が「どう使うか?」が大事で、それを正しく使いこなすことができるかどうか?中国はいま、あらゆる意味で「道徳教育」の徹底が問われている気がします。それができなければ、公共事業や金融政策をどんなに弄くり回しても、経済はますます失速するのではないか?そんなことを考えました。★レジャーサービス研究所のホームページ★
2014/08/10
コメント(0)
-
トレーナー・トレーニングで最も重要なのは「評価」
今回も上海のアパレル企業の研修に来ています。毎月10-20店舗のペースで出店を進めていて、、現場の販売員の教育がどんどん後手に回っていまうという現状を打開するために、トレーナーの育成を依頼されました。新店の募集で集まった新人店員に対して、教育を担当するトレーナーをできるだけ多く育てたいというわけです。それでよく「トレーナー・トレーニング」を実施します。一般的な「○○研修」と違う点は「時間がかかる」ということです。まずは私が新人研修の見本となる研修をトレーナーたちに対して実施します。(2日間or3日間)その後、トレーナーたちと一緒にその見本研修の内容をもとに、それぞれの会社に合うように内容を改善します。あわせてPPTを作成したり実習を検討します。その後、実際の研修を想定した練習(立ち稽古)をします。(この間は大体3か月間)そして、いよいよトレーナーの試験をします。実際の販売員に対して作成した新人研修を実施してもらいます。私はこの時に、アシスタントとして参加して、トレーナーの評価をします。また、抜けがあったり、うまくいかない場合のフォローをします。そして、研修終了後にチェックリストと撮影したビデオを見せながら評価を話し合います。こそ時点で合格ラインなら、次回からソロでトレーナーデビューしてもらいます。不合格ラインの場合、再度、トレーナーテストを実施します。(今回も3日間のテストをしました)こうして、およそ半年がかりでトレーナーを20数名育成して行きます。この仕事の最も時間を要するのは、トレーナー研修ではなく、一人一人のテストに立ち合い評価をすることです。人は正しく評価してくれてる人を信用するからです。教えた後の「評価」に責任があるということです。よくある講義だけの研修では人が育たないのは当然と言えます。「言いっ放し上司」に人はついて来ないのと同じですね(笑)。販売員の場合、売上は最もわかりやすい評価です。それはPOSレジで毎日確認できます。本部はそれでいいとしても、売れるようになるために努力している人が、まだ売れてない場合、現場でよく見れば、本当は80%くらいうまくいっていて、あと残り20%の少し課題があるだけ、ということがあります。だけど売上数字は「0」です。この「あと20%だよ。それはこれとこれを改善すればOK」と評価して伝えて、再度練習に付き合うのがトレーナーです。よく結果重視、成果主義という言葉が使われますが、それは「途中は自力でやれ」と言ってるようなもので、元々「向いている人だけ」が売れて、それ以外の人たちは売れるようにならないから給与は上がらないので、転職を繰り返す、、、わけです。裏を返せば「人を使い捨てしてる」ようなもの。しかし、今の中国は段々と使い捨てができなくなりつつあります。経済はより厳しくなり、売れっ子は引き抜かれるし、売れない人も給与が安いから辞める、、、。いくら人件費が安いとは言っても、日本の店舗と比較すれば年がら年中募集、採用、教育の絶対量が大きくて、実はそのコストは膨大なのです。そんな理由もあって、トレーナー・トレーニングの依頼が増えているのです。今日の夜は上海市内で、そうしたトレーナー育成の仕組み作りの講演をしてきます!
2014/08/07
コメント(0)
-

中国の旅行社の販売スタッフが困っていること1
先月より中国の国営旅行社の従業員教育がスタートしました。先方からのオーダーは多く2つ。1つは、いわゆる「接客術」の指導。そして、もう1つは「日本の観光地の紹介方法」の指導。毎月、集合研修とOJTをすることになっています。その他は、各拠点のリーダーからのメールやチャット、ビデオ電話での質問に答える契約です。今週は、台風の影響で慌ただしかった様子です。特に、沖縄・九州の旅行商品を販売したスタッフは、台風の影響による飛行機など交通機関の遅延による対応に追われました。問合せというかクレームの連絡が引っ切り無し。上海から沖縄・九州に向かう人たちから。現在、沖縄・九州にいる人たちから。対応が落ち着いた後に、それぞれのリーダーに話を伺うと、このシーズンの沖縄・九州はいつ台風が来るのか?わからないから、正直あまり販売したくない、とのこと。(特に一般スタッフが嫌がる)ジーズン前に各県の担当者や代理店に問い合わせても、いつ来るか?はわからないし、来ないかもしれないので、あまり気にしないで頑張って売って欲しい、、、と曖昧なアドバイスばかり。それで、「来年以降は、7-8月は東京や北海道に特化したいがいかがか?」という質問がありました。観光旅行事業は天候次第で収益が変わる商売なので、そう考えても仕方ないでしょう。今月は「その対応方法の研修をして欲しい」ということになりました。難しい問題ですが、こうした販売窓口の人たちが困っていることに応えていくのは日本のインバウンド業界の盲点を見つけられる貴重な機会なのでしっかり対応してきたいと思います。★レジャーサービス研究所のホームページ★
2014/08/03
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1