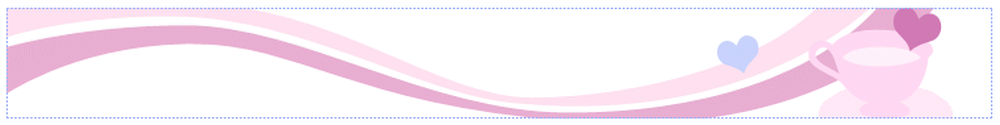2013年04月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
Clenching fists 'can improve memory'
Memory can be improved simply by clenching the fists, a study suggests.Clenching the right hand for 90 seconds helps in memory formation, while the same movement in the left improves memory recall, say US psychologists.In an experiment, 50 adults performed better at remembering words from a long list when they carried out these movements.(BBC News)*****clench(しっかりとつかむ)fist(握りこぶし、げんこつ)*****「哲学のヒント」(藤田正勝著)を読みました。哲学と言う言葉はphilosophy明治初期西周によって語訳された。ソクラテスは日がな一日どのように生きるかと議論した。良く生きるとはどういうことか。倫理の成立、道徳や倫理は何が善かという問いに対して社会が与えたひとつの解答。根本の所で誰でも自己中心的な存在、ゼウスが慎みと戒めを与え絶滅の危機を免れた。カントは道徳的な規範の根拠は理性。道徳や倫理の根拠は願いや希望、つねに吟味を重ねなければ多くの人を苦しめる。サルトル人間は自由そのものである。パスカル気晴らし。美しい花を見たり美しい音楽を聴いたりすることを通して自らの生をより充実したものとして感じ取っている。私たちは日々そこから生きる意欲を汲み取っている。私たちは感じる喜びや悲しみ意欲と深く結びつき哲学はしばしばそのような現実の世界で日々行っている。他者を気遣い思いやり配慮する人の心栄えの美しさに共感、美は人と人とのつながりに関すること。言葉とは何か考えるための表現するための道具、言葉によって世界の見え方が決まるなどとより良く生きるための素敵な考えに感動した。
2013年04月29日
コメント(2)
-
Brian Eno branches out into hospital work
His music has been heard on radio stations and in stadium concerts around the world - including at the London Olympics opening ceremony. And his light installations have been beamed on to the sails of Sydney Opera House. The latest project by Brian Eno has a more low-key setting - in a hospital in Hove where he has produced two pieces of art designed to relax patients.(BBC News)*****branch out(事業を広げる)installation(就任)*****日曜日21日は誕生日だったので今家の中にはお花がいっぱい。ひとつはバラがいっぱいのアレンジメントフラワーとランの鉢植えとアジサイの鉢植えの3組を誕生日のお祝いにもらった。家族からコーチのバッグももらった。友人から誕生日のデコレーションメールがほとんどだったけど達筆な字でおめでとうとファックスもあった。お昼にホテルのランチバイキングに行ってケーキなどいっぱい食べ過ぎたので夕食はケーキもなく控えめにした。月曜日に遅れて誕生日カードを送ってくれた人もいた。午後は英会話へ行くと家庭訪問でお休みの人が多かった。前回お休みだった人へ新しい先生のことなど前回聞いたことを伝えないといけなかった。前回ブログにも記していたのにスコットランドの食べ物などすっかり忘れて出てこなかったので記してあるのを見た。ロンドンなどで楽器を弾いて通行人を楽しませる人をbuskerと言うらしいと覚えた。昨日はフィットネスへ行って今日は陶芸だったけど腰痛が少ししたので悪化するのを避けて休んだ。
2013年04月24日
コメント(10)
-
DNA pioneer Francis Crick's Nobel prize sells for $2.27m
The Nobel Prize won by British scientist Francis Crick for his discovery of DNA has sold for $2.27m (£1.47m) at auction in New York.It was bought by Jack Wang, CEO of a Shanghai-based biomedical firm, who had flown in specially for the sale.Professor Crick won the prize in 1962 for his discovery of the structure of the DNA molecule, making it possible to decode how living beings function.(BBC News)*****biomedical(生物医学的な)molecule(分子)*****「ジムに通う人の栄養学」(岡村浩嗣著)を読みました。体を動かさないで食べると体脂肪が合成されて太る。体を動かして食べると筋肉の合成が促進する。運動後の栄養は早めに補給した方が筋肉は合成されやすいとある。運動後2時間以内に食べると太ると聞いていたけれどすぐ摂取したら筋肉ができるようだ。太りにくい体にするには筋肉を増やせばよいからすぐ食べた方がいいということかな。太る体質の遺伝子に関係するβ3アドレナリン受容体の遺伝子、痩せにくかったり太りやすかったりするのは飢餓に強いので生物にはよいけれどエンルギー過剰になりやすい。ではどんな食品を摂るべきか。血や肉を作る肉、魚、豆腐などは赤(主菜)、力や体温になるごはんパンなどは黄色(主食)、体を調子をよくする野菜キノコなどは緑(副菜)、果物と乳製品の5種類の食品を摂る事で必要な栄養素を摂ることができるらしい。ご飯と豆腐は白ばかりで良くない組み合わせだという笑い話があったらしくご飯は黄色で豆腐は赤でいい組み合わせになるらしい。電気は体脂肪が多いと流れにくくなるのはインビーダンスが高いということなど色々なことを知った。
2013年04月15日
コメント(4)
-
Environmental change 'triggers rapid evolution'
Changes to their surroundings can trigger "rapid evolution" in species as they adopt traits to help them survive in the new conditions, a study shows.Studying soil mites in a laboratory, researchers found that the invertebrates' age of maturity almost doubled in just 20-or-so generations. (BBC News)*****mite(ダニ)invertebrate(脊椎のない)*****「小さな建築」(隈研吾著)を読みました。幸福な人間は過去の行動を繰り返しているだけで先に進もうとしない。悲劇をきっかけにして発明や進歩という名の歯車が回転を始める。1755年リスボン大地震では世界の人口が7億の中5,6万人の死者が出たらしい。この悲劇をきっかけに神に頼れないとい危機から啓蒙主義、フランス革命、産業革命へと発展した。神に頼る時代の建築は古典主義、ゴシック主義と呼ぶ。神が人間を守ってくれないなら自分が自分を守らなくてはならないとヴィジオネールの建築家は考えた。ロンドンの大火、シカゴの大火、関東大震災などから木に変わってコンクリートや鉄になった。そして今生物的建築、自立しているが生物ではなく環境に依存する弱さこそ生物の本質、生物はそれ自身では生きていけない弱い存在、周りの環境に適応すべく日々少しずつ新陳代謝する。釘やボルトがなくもたれかけの構造、ゼンバーの木を織るというアイデア、人に頼らず政府に頼らず自分の力で簡単にできる被災地住宅のアイデアが傘を組み合わせて作るドーム型の家、フランクフルトには膨らむドーム型の茶室があるらしいなどと悲劇をきっかけに色々なアイデアが生まれていくのではと思った。
2013年04月10日
コメント(2)
-
Famine risks are badly managed
Famine early warning systems have a good track record of predicting food shortages but are poor at triggering early action, a report has concluded.The study said the opportunity for early action was being missed by governments and humanitarian agencies.It said the "disconnect" was starkly apparent in Somalia where no action was taken despite 11 months of warnings. (BBC News)*****famine(凶作、飢餓)*****きょうは英会話へ行った。7人もお休みだった。ほとんどの人が入学式に出席でお休みだった。きょうから新しいスコットランド出身のALTだった。スコットランドのALTは初めてだったので色々スコットランドのことを教えてもらえた。食べ物ではTablet, porridge, Iri-bruはコーラのような飲み物, shortbreadがあるとショートブレッドを食べさせてもらえた。あとHuggisはロバート・バーンズデイの誕生日1月25日にハギス(Haggis)(羊の内臓を羊の胃袋に詰めて茹でたスコットランドの伝統料理)を食べるらしい。ロバート・バーンズは詩人だというとある人が蛍の光だと皆で歌った。日本では終わりの時年末などに流れるのにイギリスでは年の初めに流れるらしい。Auld lang syneと言うらしいけど方言でold long sinceでtimes gone by久しき昔という意味。ジャムのようなMarmite を舐めさせてもらった。醤油のような味がした。Vegimiteも同じような発酵食品で体にいいからとトーストにつけて食べているらしいなどとスコットランドのことを知った。ここ2週間前から風邪で微熱があって治ったと思ったら帰り寒い所で話が盛り上がって1時間程お喋りしたらまた具合が少し悪くなった。
2013年04月08日
コメント(0)
-
Alzheimer's: A different view
For more than a decade, US sociologist Cathy Greenblat has been travelling the world studying the treatments offered to people with dementia. Her mother and two of her grandparents all developed the disease - and she wanted to understand more about the condition. In her book - Love, Loss and Laughter - she tells positive stories of ageing, dementia and end-of-life treatment, across seven countries. Take a look at some of her touching images here, as she explains what she discovered.(BBC News)*****sociologist(社会学者)*****「解決する力」(猪瀬直樹著)を読みました。心が乱れない人は頭の切り替えが速い。なぜ叱られたのか、自分の間違った考えや行動を改善する方向に目を向けられる人は平常心を保てる。注意を受け叱られた時小さなプライドを捨てて頭の切り替えをすると落ち込みや反発を避けて新たな展開が開ける。一見して難しいと思えることでも視点をかえてみれば自分の能力や経験値で解決策がある。平常心での習慣が緊急時に現われるらしい。国民一人ひとりが共に助け合いながら自分のできることをやっていかなければならない。「自己責任の時代」になった。世の中を強く生きるには自国の歴史を知り己のよりどころとすることも必要と著者はいう。言葉の力、言語技術力を身につけることも大切、同調性に埋没しては解決する力は生まれない。今ビブリオバトルという自分の読んだ本を5分間で紹介してデイスカッションするという知的書評合戦があるらしいなどと新しい楽しそうな情報を知った。本を読むとこうやって人に伝えたくなる。英語でその思いもプレゼンテーションしたくなる。本を読むと新しい事を知って頭がすっきりして解決策にもつながる気がした。
2013年04月02日
コメント(4)
全6件 (6件中 1-6件目)
1