PR
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(2)読書案内「日本語・教育」
(22)週刊マンガ便「コミック」
(79)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(36)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(77)演劇・芸能「劇場」でお昼寝
(5)映画「元町映画館」でお昼寝
(130)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(62)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(120)読書案内「映画館で出会った本」
(20)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(25)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(54)読書案内「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(29)読書案内「現代の作家」
(103)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(76)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(102)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(51)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(86)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(33)読書案内「近・現代詩歌」
(58)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(23)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(21)読書案内「水俣・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(18)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(13)映画「パルシネマ」でお昼寝
(32)読書案内「昭和の文学」
(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(23)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(18)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(40)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(22)ベランダだより
(167)徘徊日記 団地界隈
(138)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(27)徘徊日記 須磨区あたり
(34)徘徊日記 西区・北区あたり
(11)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(46)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(12)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」
(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・大岡信 あたり」
(21)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(22)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(8)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(17)映画・読書案内 パレスチナ・中東
(19)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(25)映画 香港・中国・台湾の監督
(40)アニメ映画
(24)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(55)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(41)映画 イタリアの監督
(22)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(29)映画 ソビエト・ロシアの監督
(14)映画 アメリカの監督
(99)震災をめぐって 本・映画
(9)読書案内「旅行・冒険」
(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(15)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(5)映画 フランスの監督
(53)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(13)映画 カナダの監督
(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(14)映画 ウクライナ・リトアニア・ラトビア・エストニアの監督
(9)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(13)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(11)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督
(12)映画 ギリシアの監督
(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督
(8)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督
(5)映画 アフリカの監督
(3)映画 スイス・オーストリアの監督
(4)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(3)読書案内・アニメ・コミック ジブリ
(7)週刊マンガ便「小林まこと」
(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」
(3)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督
(5)週刊マンガ便・映画 キングダム 原泰久・佐藤信介
(19)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」
(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」
(5)徘徊日記 神戸の狛犬
(5)週刊読書案内「保坂和志・柴崎友香・磯崎憲一郎とか」
(11)読書案内・映画 沖縄
(10)読書案内 韓国の文学
(5)週刊マンガ便・映画 武田一義 こうの史代
(9)映画 ミュージシャン 映画音楽
(11)映画 「109ハット」でお昼寝
(5)読書案内 エッセイ
(4)読書案内 「茨木のり子・石垣りん」
(13)映画「キノシネマ神戸国際」でお昼寝
(5)週刊 読書案内 金時鐘「見えない町」(「猪飼野詩集」より)
マイク・リー「ハードトゥルース」シネリーブル神戸no340
週刊 読書案内 金 時鐘「猪飼野詩集」(東京新聞出版局)
ロバート・レッドフォード「リバー・ランズ・スルー・イット」パルシネマ新公園no49
徘徊日記 2025年11月16日(日)「ここが西門!」 ここは鬼ノ城・その2 岡山・総社あたり
週刊 読書案内 池澤夏樹「されく魂 わが石牟礼道子」(河出書房新社)
週刊 マンガ便 ハロルド作石「THE BAND 2」(講談社)
徘徊日記 2025年11月8日(土)「ここは梅田の太融寺!」 大阪、梅田あたり
徘徊日記 2025年11月16日(日)「ここは鬼ノ城!」 その1 岡山・総社あたり
コメント新着
キーワードサーチ
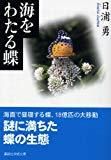
もう十年以上も昔、こんなふうに、高校生に読書案内していました。その中の一冊です。文章もその当時のものです。
運動会も終わりました。朝夕めっきり冷気が立ち込めてくるようになって、秋ですね。この国の伝統文化では月であり、紅葉であり、帰る雁であるという季節です。当然!学校では読書のシーズンということになります。ははははは。
ところで、校門を入ってすぐのところに車回しがあります。最近そこに二十匹ほどの蝶がひらひらしていることに気付いている人はいらっしゃるでしょうか。蝶といえば春のイメージなのですが、今日この頃のことです。
てふてふが一匹韃靼海峡を渡って行った。
こういう有名な詩もあるくらいです。たった一行の詩ですが題名もちゃんとあります。詩の題は 「春」
。作者は短詩で有名な 安西冬衛
ですね。
蝶の空 七堂伽藍は さかしまに
こんな俳句もあります。作者は ホトトギスの俳人
川端芽舎
。名はもちろん俳号で、 ボウシャ
と読みます。季語は蝶でやっぱり春かな?句を詠んでいる人の姿は蝶になって飛ぶと見えてくるかもしれません。これも、なかなか、いいですね。
というわけで蝶は春、秋といえばトンボに決まっています。ところが九月に入って一週間ほどした頃から飛び交い始めた薄紫の小さな蝶いるのです。誰か名前を知っている人はいませんか。(なんだ知らないのか。)
話は変わりますが、 安西冬衛
のこの詩はずっと気になっていました。一匹の蝶がこの列島の最北の海峡を渡っていく姿です。日本名は間宮海峡。世界地理的にはタタール海峡と呼ばれているサハリンと大陸の間の海峡です。「ダッタン」は「タタール」の漢字読みでしょう。一番狭い所で10キロに満たない幅の海峡だそうだですから、そういうことも、つまりチョウがひらひらすることも、あるかと思っていました。
題が 「春」
だから サハリン
から北の大陸に向かって飛翔している蝶のことをうたっているに違いないでしょうが、その姿を思い浮かべると、ホントかなと疑心が浮かんできます。チョウの仕業にしては、あまりに雄大、春とはいえ、北の海の様子としてはあまりに可憐だと思いませんか。
夏の間に 日浦勇「海をわたる蝶」 (
講談社学術文庫 )
という本を読みました。ぼくの疑いは完全にとけました。蝶は空を飛んで海をわたるのです。場合によっては数億匹という群をなして移動することもあるそうです。
列島周辺の海、大阪湾や伊勢湾、琵琶湖では当たり前の移動で、なかには台風の風に巻き上げられて南のフィリピンや台湾から吹き飛ばされてくるチョウもいるそうです。飛ぶのに疲れると波間に浮かんで翅を休めることもあるというのです。あのモンシロチョウも海を渡ってやって来た種であるとわれると、ちょっと驚きの事実だと思いませんか。
ナチュラル・ヒストリィ( Natural
History
)
という言葉があります。 博物学
と訳されています。大英博物館がそのオーソドックスなというか、典型的なイメージですね。
小学校の頃、理科室に陳列された様々な昆虫や鉱物の標本、動物の剥製、ガラスのビンのホルマリンに潜んでいる気味の悪い、得体のしれない、不思議な生物を覗き込んだ記憶はないでしょうか。
採集し標本を作り、名前を探す。新しい名前を付ける。人類の知識庫に新しい名前が一つ増える。子どもたちの好奇心を激しくひきつける。博物学とはそういう学問です。
博物館の学芸員をしていた著者はそれに飽き足らなくなったようです。膨大な知識、物の集積を前にただ羅列しておくだけでは気が済まなかったのでしょう。
発達史的見地からでないと、真に理解することは出来ないのではないか。ナチュラル・ヒストリィのヒストリィという語には、十分な重みがあるのではないか。古い博物学の内容を歴史的に意味づけ、自然史と直訳しなおすことによってその語にふさわしい内容を盛るべきではないか。 というわけで、歴史の文脈の中に現象をおくことで、全体に対する興味を作り出すことを目論むのです。スゴイでしょ。
悠久の地質時代にあって、もっとも最近の第四紀と呼ばれる百万年 ( あるいは二百万年 ) は、それまでの時代とは違う特殊な時代であり、当時生起した事件は、現在の世界を本質的に規定するものである。気候変動や氷河性水面変動や地表の諸事件に関する知識は、自然史に不可欠であり、ナチュラル・ヒストリィは同時に第四紀学としての性格を備える必要がある。
第四紀という時代は、地球が、数億年という歴史をかけて作り出した生物自然を、最高度に複雑化させた時代である。一方で海をわたる蝶のような発展段階の高い生物種とそれらが作る生物相を生み出したかと思うと、他方では落葉樹や降雨林などにひっそりと暮らす古いタイプの種及び生物相を、抹殺することなく温存している。 こうして、 博物学 の魅力に取り付かれた昆虫少年は、自然史を見据える歴史家になってしまいました。 「人類の文化」 を振り返ることだけが歴史ではありません。地球規模の生物の歴史を ナチュラル・ヒストリィ として見る歴史家だっているのです。
このすばらしい世界―きびしいと同時にやさしい世界を、私たちは滅茶滅茶に破壊し続けている。坂道を転がり落ちるような破壊の速度をゆるめ、多様性の復権に取り組まなくてはならない。そのためには、自然変化の本質をもっときびしく追及する必要がある。
人間を物差しにして縄文、弥生と調べていくのが列島文化史ですが、彼が歴史を見る時ものさしの役割をするのが 蝶 だということです。
今、目の前に飛んでいる蝶がどこから来てどこに行くのか。この列島にいる蝶のどれが元からいて、どれが海をわたってきた蝶なのか。何故北にいたはずの蝶が列島を住処とし、南の蝶が新たにこの地にやってくるのか。
それを氷河期や、温暖期との関連で論じる。何万年というスケールで蝶相が変化するさまをさぐる。最後には当然、人間の文明が滅ぼしていく蝶たちの姿も見えてくる。
著者によれば自然変貌の第三段階を迎えている現在の都市型自然は 「砂漠型自然」 だそうです。コンクリート、アスファルトで覆われた都市は蝶の目から見れば砂漠なのです。蝶は砂漠では生きて行けません。氷河期を生き延びた蝶が文明の砂漠の中で「今」滅ぼうとしているのです。
本書は 1973年 に出版された 「日本列島蝶相発達史」 という本のリメイク版だそうです。30年以上たっていますが、著者が発している警告は全く古びていません。 1983年 に亡くなった著者が現在の都市の蝶相を知ればなんというだろう、読み終えてまじめにそう思いました。( S )
追記2019・08・03
この本を紹介したのは十五年以上も前で、生徒さんたちはもう大人になっている。ぼくはただの徘徊ジジイになった。もう一度読み返す元気は今はない。職場の庭にあった面白い形の楠も切られてしまった。樟の葉っぱを食べる
アオスジアゲハ
が、タバコを喫って休憩しているぼくの周りを飛び交うのが夢のように思い出されてくる。
樹齢100年にならんとする大木が、葉っぱがゴミだ、駐車場の邪魔だという理由で切り倒される。
「安全」「便利」「平等」
、符丁のように言葉は使われて、点数が競われる時代になったが、何を育てているのか忘れた教育に未来はないだろう。学校は
「いきものを育てている」場所
だということが忘れられて久しい。
人間という生き物
はたかがか80年ほどの命だが、命のすごさは100年、200年生き続ける、庭の植物が教えてくれることだってあるのだ。地面にコンクリートを張って便利を求めることは、そろそろ考え直した方がいいとおもうのだが。
にほんブログ村
にほんブログ村


-
週刊 読書案内 斎藤環「イルカと否定神… 2025.01.29 コメント(1)
-
週刊 読書案内 2024-no142-1064 ウォ… 2024.12.25
-
週刊 読書案内 養老孟司・池田清彦・奥… 2024.10.20











