PR
X
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(2)読書案内「日本語・教育」
(22)週刊マンガ便「コミック」
(79)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(36)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(77)演劇・芸能「劇場」でお昼寝
(5)映画「元町映画館」でお昼寝
(130)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(62)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(120)読書案内「映画館で出会った本」
(20)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(25)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(54)読書案内「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(29)読書案内「現代の作家」
(103)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(76)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(102)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(51)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(86)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(33)読書案内「近・現代詩歌」
(58)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(23)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(21)読書案内「水俣・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(18)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(13)映画「パルシネマ」でお昼寝
(32)読書案内「昭和の文学」
(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(23)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(18)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(40)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(22)ベランダだより
(167)徘徊日記 団地界隈
(138)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(27)徘徊日記 須磨区あたり
(34)徘徊日記 西区・北区あたり
(11)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(46)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(12)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」
(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・大岡信 あたり」
(21)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(22)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(8)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(17)映画・読書案内 パレスチナ・中東
(19)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(25)映画 香港・中国・台湾の監督
(40)アニメ映画
(24)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(55)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(41)映画 イタリアの監督
(22)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(29)映画 ソビエト・ロシアの監督
(14)映画 アメリカの監督
(99)震災をめぐって 本・映画
(9)読書案内「旅行・冒険」
(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(15)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(5)映画 フランスの監督
(53)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(13)映画 カナダの監督
(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(14)映画 ウクライナ・リトアニア・ラトビア・エストニアの監督
(9)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(13)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(11)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督
(12)映画 ギリシアの監督
(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督
(8)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督
(5)映画 アフリカの監督
(3)映画 スイス・オーストリアの監督
(4)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(3)読書案内・アニメ・コミック ジブリ
(7)週刊マンガ便「小林まこと」
(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」
(3)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督
(5)週刊マンガ便・映画 キングダム 原泰久・佐藤信介
(19)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」
(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」
(5)徘徊日記 神戸の狛犬
(5)週刊読書案内「保坂和志・柴崎友香・磯崎憲一郎とか」
(11)読書案内・映画 沖縄
(10)読書案内 韓国の文学
(5)週刊マンガ便・映画 武田一義 こうの史代
(9)映画 ミュージシャン 映画音楽
(11)映画 「109ハット」でお昼寝
(5)読書案内 エッセイ
(4)読書案内 「茨木のり子・石垣りん」
(13)映画「キノシネマ神戸国際」でお昼寝
(5) 山田洋次「TOKYOタクシー」109シネマズ・ハットno70
週刊 読書案内 金時鐘「見えない町」(「猪飼野詩集」より)
マイク・リー「ハードトゥルース」シネリーブル神戸no340
週刊 読書案内 金 時鐘「猪飼野詩集」(東京新聞出版局)
ロバート・レッドフォード「リバー・ランズ・スルー・イット」パルシネマ新公園no49
徘徊日記 2025年11月16日(日)「ここが西門!」 ここは鬼ノ城・その2 岡山・総社あたり
週刊 読書案内 池澤夏樹「されく魂 わが石牟礼道子」(河出書房新社)
週刊 マンガ便 ハロルド作石「THE BAND 2」(講談社)
徘徊日記 2025年11月8日(土)「ここは梅田の太融寺!」 大阪、梅田あたり
徘徊日記 2025年11月16日(日)「ここは鬼ノ城!」 その1 岡山・総社あたり
週刊 読書案内 金時鐘「見えない町」(「猪飼野詩集」より)
マイク・リー「ハードトゥルース」シネリーブル神戸no340
週刊 読書案内 金 時鐘「猪飼野詩集」(東京新聞出版局)
ロバート・レッドフォード「リバー・ランズ・スルー・イット」パルシネマ新公園no49
徘徊日記 2025年11月16日(日)「ここが西門!」 ここは鬼ノ城・その2 岡山・総社あたり
週刊 読書案内 池澤夏樹「されく魂 わが石牟礼道子」(河出書房新社)
週刊 マンガ便 ハロルド作石「THE BAND 2」(講談社)
徘徊日記 2025年11月8日(土)「ここは梅田の太融寺!」 大阪、梅田あたり
徘徊日記 2025年11月16日(日)「ここは鬼ノ城!」 その1 岡山・総社あたり
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 読書案内「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
辻井達一「日本の樹木」(中公新書)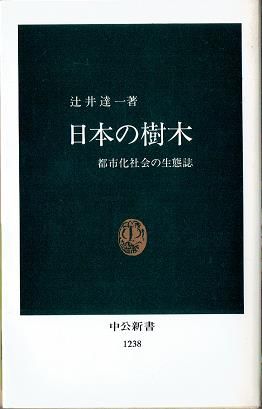
秋になりましね。紅葉した街路樹の道を歩くのですが、肩に降りかかる葉っぱの名前なんて気に書けしなかった徘徊老人が、ふと、立ち止まって散っていく風情に気を取られている自分に驚いたりします。
そういえば
「鈴懸の径」という戦前の流行歌があったはずだと思いついたりもするわけです。
♪♪友と語らん鈴懸の径 通いなれたる学び舎の街 やさしの小鈴 葉かげに鳴れば 夢はかえるよ鈴懸の径♪♪ 若い人は歌そのものをご存じないでしょう。歌われている鈴のような実をつけるらしいスズカケの木(鈴懸?)がそこらにいっぱい植わっているプラタナスという街路樹だということなんて、もちろん、ご存じない。ぼくもそうでした。
まあ、ちょっと、歌の例が古すぎるかもしれませんね?オバーちゃんの世代でも、ついていけないかもしれない。ともあれ、オバーちゃんや、ヒーオバーちゃんたちは地球温暖化のことはよく知らないが鈴懸けの小道は知っていました。ここが大事なところだと、最近思うのですがどうでしょう。
辻井達一
という 北大の植物園長
をしていた人が書いた 「日本の樹木」「続・日本の樹木」(中公新書)
という本がある。
日本の樹木についてのカタログか図鑑のような本なのですが、ただのカタログとはすこし違いますね。何より文章がいいんです。気取った学問臭がなく、学者の書く生硬さがない。素人には分からない学問用語を振り回す、かしこぶった態度がない。本物の実力を感じさせますね。
たとえば 「
プラタナス」
のページは4ページ分です。上にコピーした手書きのイラストと名前の由来が記されています。ちなみに、 「プラタナス」
の 和名「スズカケ」
の由来についてはこんな様子。
牧野博士 篠懸(すずかけ) というのがあるのを、そこに付けてある球状の飾りの呼び名と間違えてつけてしまったもので、もし強いて書くなら 「鈴懸」 とでもしなければ意味が通じないそうだ。 ちょっと解説すれば、「篠懸」というのは、たとえば歌舞伎の「勧進帳」で、山伏姿の弁慶や義経の丸いポンポンが縦についている、あの装飾のことで、「プラタナス」とはなんの類似もないということらしいですね。
なんと、命名者が勘違いして付けた名前なのです。この後、探偵シャーロック・ホームズの裏庭で産業革命の煤煙に耐えていたプラタナスについて語りはじめて、話はこんなふうに進みます。
立地への適応幅はたいへん広くて、地味が痩せた、そして乾燥した立地でも十分に育つ。しかも ロンドン での例で述べたように煤煙など 大気汚染にも強い ときているのだから都市環境にはもってこいなのである。その意味では プラタナスが育っているから安全だ、などと考えては困る 。 プラタナスが枯れるくらいだったら、それは危険信号を通り越している と考えなければなるまい。 締めくくりかたが、なんとも、鮮やかなものでしょう。「環境問題」もここから考える方がきっと面白いと思いますね。
次いでなので、 「スギ」 の項目はこんなふうです。
悲劇の武将、 源義経 が鞍馬寺の稚児として 牛若丸 と呼ばれていた頃、夜な夜な木っ端天狗が剣術の指南をした、ということになっているのも鬱蒼たる杉木立がその舞台だ。 こう書いて、つぎに、こう続けています。
これが明るい雑木林で栗の実が拾え、柿の実が赤く染まりというのではとんと凄味がなくて餓鬼大将の遊び場である。実際にお相手をしたのは田辺か、奥州の手の者か分からないが、山伏装束でもしていれば間違って通りかかった坊主、村人、杣人いずれにしてもよく見ないうちから天狗の眷属と踏んで足を宙ににげさったことであろう。そもそも怪しげな噂を撒いておいたということも十分あり得る。
スギの材は建築材に重用されるが、その葉は油を含んでいてよい香りを持ち、どこからの由来か 造り酒屋のマークになっていた 。スギの葉を球状にまとめたものを軒先にぶら下げるのである。 つまり「文化人類学」ならぬ「文化樹林学」とでも呼ぶべき時間の奥行と、世界を股にかけた幅で書かれているわけなのです。
スギで酒樽を作るから、それから来たものかどうか。 これに似た風習はオーストラリアにもある。 ここではマツだが、同じように葉を丸くまとめてぶらさげるのが造り酒屋のシンボルだ。
徘徊老人は「街」から帰ってきて、パラパラとページをめくりながら、さっきの立木を思い浮かべ、センスのいい「エッセイ」を一つ二つ読んで、ニヤリとするわけです。どうでしょう、街角で新しい樹木と出会ってみませんか。(S )
週刊読書案内2006no4改稿2019・10・22

にほんブログ村
ボタン押してね!


お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書案内「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」] カテゴリの最新記事
-
週刊 読書案内 斎藤環「イルカと否定神… 2025.01.29 コメント(1)
-
週刊 読書案内 2024-no142-1064 ウォ… 2024.12.25
-
週刊 読書案内 養老孟司・池田清彦・奥… 2024.10.20
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










