2014年11月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-

改定・武田源氏の野望
「三河一向一揆」(79章)にほんブログ村にほんブログ村 「三河、騒乱」 そうした情況のなか永禄六年十月下旬に、突然、三河に大事が勃発した。 その大事とは三河の一向門徒衆が三河一帯に一斉に蜂起した事である。 この争いは松平家康の家臣と領内を二分した大騒乱となった。 発端は松平家が、一向門徒の寺院に干渉した事から始まった。 かって三河は親鸞が北国行脚の途中、矢作の薬師堂で法話を説き、それが三河一帯に広がり、一向門徒衆を名乗るようになったと言われる。 三河の一向門徒の寺院は上宮寺、本証寺、勝鬘寺の三ケ寺が寺院を称し、守護不入を称え、独立国家の体勢をとっていた。 この守護不入とは、守護が罪人の逮捕や租税徴収などで院内に入ることを禁じたもので、寺院は勝手にそれを特権として称していた。 その野寺、本証寺に罪人が居ると家康の足軽が、勝手に寺院に押し入った事が今回の騒動の始まりであった。 その足軽達に武田の忍びの河野晋作と小十郎の二人が加わっていたのだ。 まさに信玄と信虎二人の策が効を奏したのだ。 現在の安城市、野寺の本證寺第十代の空誓(蓮如の孫)が中心となり真宗門徒に檄を飛ばし、三河の領主、松平家康に反抗した事が今回の騒動であった。 この一揆は三河の分国支配を目指す家康に対して、その動きを阻もうと試みた一向宗勢力が、一族や家康の家臣団を巻き込んで引き起こしたものである。 その意味では、松平宗家が戦国大名として領国一円の支配を達成する為に、乗り越えなければならない、一つの関門であったとも言える。 三河一帯を統べる家康も、守護不入を称える一向門徒衆をそのままにしておく考えはなかった。 家康は今川家の領土を侵略し、万全な備えをした後でと思っていたが、この騒乱に誘発された格好で彼等との戦いが始まったのだ。 家康の家臣の門徒衆は、主人と宗門の狭間で悩んだが結局は宗門につき猛烈に抵抗した。 更に松平家に対する不満分子の豪族も絡み、目もあてられない様相となった。「主人とは現世のこと、仏祖如来(ぶっそにょらい)は未来永劫。頼むところはご本尊のみ」 これが門徒衆の考えで目もあてられない、惨状を呈した。 更に日頃から鬱積した不満分子までが、門徒衆に続々と加勢したため三河一帯は荒れにあれた。 天下を取った家康が往時を思いだし、三河一向一揆は、三方ヶ原の戦い、伊賀越えと並び、わしの三大危機であった、と語っている。 三方ケ原合戦は武田信玄との合戦で、散々に敗れ馬上で脱糞して逃げ回った合戦で。伊賀越えは京に遊覧の旅をしていた時、織田信長が明智光秀の謀反で横死し、逃げ場を失い必死で伊賀越えをした時のことである。 三河一揆は敵から犬のように忠実と、揶揄され評価された三河家臣団の半数が、門徒方に与し、家康に宗教の恐ろしさをまざまざと見せつけた事件であった。 この戦いは家康も家臣たちも、もっとも辛い戦いであった。門徒方に付いた家臣等は、ご本尊を信じて主君である家康に本気で槍をつける者もいたが、 家康自身が軍勢の先頭に姿を見せると、大方の者は、「君が渡らせ給うては攻し(こうし)難し」 と逃げ散る者が多かった。 家康は反抗した家臣等の将来を思い、「良いか、家臣同士の戦で生死を賭けてはならぬ」 と厳しく従った家臣等に言い渡していた。 何れ、近いうちに蹴りをつける。そうした自信があっての事である。 信虎は久しぶりに隠居所から駿府城の大広間に向かった。 「これは珍しい」 すれ違う者が一様に驚きを示している。 義元が息災の時には頻繁に登城した信虎も、氏真が当主となってから足が遠のいていた。 併し、三河の一向一揆の騒動を見逃す手はないと勇んでの登城であった。「爺殿、いかが為された?」 氏真が驚き顔で迎えた。 それほど信虎は溌剌としていた。 「氏真殿、今が好機にござるぞ」「何を申されておるのか余には判らぬ」 氏真が困惑顔をしている。「三河の地が内乱じゃ、これを機に三河に軍勢を向け攻略なされ」 信虎が語調を強め説得するが、駿府城は腰抜けばかりが居座っていた。 ここに朝比奈泰能や三浦成常の宿老が居たなら事態は一変したであろうが、彼等は北条対策として前線の城塞につめていた。「三河の松平家康を滅ぼす絶好の機会にござるぞ」 いくらけし掛けても動こうとはしない。「この時に軍勢を出さずば、今川家は衰亡の一途をたどりますぞ」 信虎が懸命に説くが、まさに糠に釘である。「こうまで腑ぬけになられたか」 ついに言わでもない事を口走った。「爺殿と思い多少のことには目を瞑って参ったが、今の言葉は聞きずて難し」 氏真が蒼白となり躯を震わせ喚いた。 信虎は悄然として下城した。(矢張りうつけ者じゃ)と、内心で呟いていた。 こうして今川家は三河一帯を回復する絶好機を失したのだ。 一方の松平家康が最も恐れたことは、今川家の軍事介入であった。 併し、氏真の弱腰でこの急場を凌ぐことが出来たのだ。 家康は難戦につぐ難戦を制し、ついに一向一揆を鎮圧した。 これは約半年余を要しての苦い勝利であった。 これは翌年の永禄七年二月のことであった。 一揆勢は恭順し和解が成立した。 条件は一揆勢の本領安堵、道場僧俗の現状維持、張本人の助命なとで家康にとって不満の残るものであった。 だが家康は老獪な策を取った、和睦と共に三河の門徒寺、道場の破却を命じた。 これに対し門徒衆から違約であるとの抗議があったが、家康は平然と答えた。「現状維持と申さば、もともと寺や道場の前は原野であった。もとの原野にするは誓詞を違えた事にはなるまい」 と嘯き、この家康がおるかぎり三河には、一向宗を禁ずると厳命した。 こうして家康は家臣団を掌握し、三河一国の領有を保ったのだ。
Nov 29, 2014
コメント(61)
-

改定・武田源氏の野望
「信玄の誤算」(78章)にほんブログ村にほんブログ村「わたくしに・・・どなたにございましょう?」 お弓の胸に疑心が奔り抜けた、誰をわたしに逢せようと為さるのか、 「そのように心配いたすな、余の妹じゃ」 「・・・姫君さまに?」 今度はお弓が絶句する番であった。「奥で首を長くして待っておろう」 信玄が魁偉な容貌を和ませている。 お弓は近侍の若侍の案内で奥の一室に案内され顔色が変わった。「小母さま、お久しゅうございます」 豪華な打ち掛け姿の、お麻が両手をついて待っていたのだ。 「お麻殿か?」「はい、父上が川中島で亡くなり、御屋形さまが引き取って下されました」「美しく成長なされましたな」 途中、感極まって声が途絶えた。 躑躅ケ崎館を訪れお麻に逢えるとは、思ってもみなかったのに、こうして逢えるとは夢のようであった。 お麻に初めて遭ったのは二年前の、永禄四年の六月であった。 たった二年でも、少女の成長は目を見張るほど早い。「余の妹じゃ」 先刻の信玄の声を思いだし、身の縮まる思いに包まれるお弓である。 あの年の九月に第四回川中島合戦が勃発したのだ。 勘助ともあの時以来、会うことが叶わなくなった。「わたくしの母上さまと御屋形さまが申されましたが、本当にございますか?」 美しく成長したお麻が切れ長な眼を見開いてお弓を見つめた。「御屋形さまのご冗談ですよ。お麻殿の母親なんぞは嘘にきまってます」 いたいけな少女の問いに応ずる、お弓は汗の滲む思いでいる。「もう良いのです。こうして母上さまにお逢いできてお麻は・・・・」 涙ぐみ言葉を途絶えさせる娘を抱きしめ、束の間の幸せを味わった。 抱きしめながらも、娘がこのように美しく成長した事が嬉しかった。「この脇差が、わたくしの父上の形見だと御屋形さまが申されました」 お麻がそっと懐剣を差しだした。 お弓は目を疑った。お麻を勘助に託した時に渡した信虎の脇差であった。 これで訳が判った。この脇差を信玄さまがご覧に成り、お麻が父、信虎の落しだねと知ったのだ。 事実、お麻は信玄の実の妹である、それはお弓が一番に承知している。 信玄は山本勘助が突然に赤子を匿い育てた訳を理解したのだ。「母上さま、またお逢いできますね。お麻は待っております」「逢いますとも、わたくしは何度もこのお館に参ります」「良かった」 お麻が嬉しそうに笑顔で応じた。 しばしの語らいを終え、心を残し奥を去る時、 娘の声を背で受け涙が頬を伝った、女忍として初めて流した涙であった。 信玄はお弓の帰りを待ち受けていた。 「余の妹はいかがであった?」「勿体ないお言葉、身に染みまする」 「会いたくなったら、遠慮のう訪ねてまいれ」 信玄は何も詮索せず、短く言葉をかけた。「・・・-」 お弓が言葉を失っている。「父上の事じゃが結論から申す。今川家は武田家が武力でもって支配いたす。よってつまらぬ火遊びは、即刻お止め頂きたい。これが余の返答じゃ」 信玄が一気に述べ、お弓の反応を窺がっている。「駿府の大殿さまは、何方が申されましょうとお止めにはなりますまい」 お弓の反論で信玄が濃い顎髭をさすって考え込み、太い吐息を吐き出した。「余にも判っておる、こうと思われたら途中で投げ出される事はなされぬ。 そちに良き思案はないか?」 「三名の重臣達を脅したらいかがでしょう?」「それも考えた、併し、それも危険じゃ。奴等が父上の命を奪うやもしれぬ」 「・・・・-」 お弓が絶句した、全てを見通しておられる。「何としてもお止め申せ。聞けば父上の家臣は小林兵左衛門一人じゃそうな、警護の士を送ろう、そのために氏真殿に進物を贈ろう。虎皮十枚、豹皮十枚」 信玄が太い指を折って数えている。「縮羅(ちじら)二百反、黄金百枚、これで氏真殿の歓心を買おう」「大層な贈り物にございまするな」「何の、これで父上の命が助かるなら安いものじゃ」 こうしてお弓は屈強な護衛の家臣と共に駿府に戻った。 豪勢な進物を送られた氏真は感激し、信虎の隠居所を訪れてきた。「これは氏真殿、この爺になんぞ御用かの」「爺殿に警護の士が居らぬことを忘れておりました。早速、信玄殿お手配の警護の家臣をお使いなされ、信玄殿からは沢山の進物を頂戴いたした」「左様にござるか、じゃがこの老人には警護なんぞ無用にござる」 信玄の奴め、わしを監視する積りじゃなと信虎は信玄の心をよんでいる。 氏真は騒々しく騒ぎたち返って行った。「騒々しい男じゃ」 信虎が懐紙に唾を吐き出した。 信玄が信虎の護衛として送り込んだ男達は、精悍で屈強な男たちであった。「大殿、それがしは海野昌孝と申します。大殿警護を命じられ罷りこしました」 見るからに偉丈夫な男が進み出て挨拶した。「ご苦労じゃ、五名も参ったか。この年寄りには勿体ない」 信虎は一人一人に声をかけねぎらい、隠居所は一気に活気ずいた。「大殿、これは御屋形さまから与ってまいりました金子にございます」「ほうー・・これは大金じゃな」 海野の差し出す袱紗には五十枚の金子が輝いている。 「兵左衛門、この金子は仕舞っておけ」 信虎が満足そうな顔をしている。 その晩は警護の者たちの慰労をかね大いに飲んで騒いだ。 「古狸の舅殿も大層元気じゃな」 報告を受けた氏真が薄ら笑いを浮かべている。 彼は家臣等の心が離れている事を知らずにいる、それだけに悲劇であった。 今宵も進物の虎皮や豹皮を敷き並べ、腰元を侍らせ酒に溺れている。 「これは甲斐の武田信玄よりの贈り物じゃ」 と、悦に入って腰元たちを追い回している。 傍らの重臣、葛山備中守と関口兵部が憮然とした顔つきをしている。 この年の暮れに武田勢は武蔵の国に出兵した。これも北条氏康の要請に応じたことで、太田資正(すけまさ)の属城である松山城を包囲した。 これを受けた輝虎は豪雪をおして出陣したが、越後勢の進攻の知らせを受けた武田勢と北条勢は一斉に軍を引いた。 これにより越後勢は為すこともなく本国に帰還したが、翌年、二月に再び武田勢、北条勢は松山城を攻撃し守将の上杉憲勝(のりかつ)を降参させた。 越後勢はまたもや豪雪の中を押し出したが、松山城数里の地点で落城を知り虚しく兵を引いた。 まことに不思議な合戦が関東で繰り広げられている。 まるでいたちごっこである。 信玄は軍勢を引くと見せかけ、上野に疾風のように現われ松井田城、国峰城を攻略し本国に兵を引き上げた。 まさに孫子の御旗どおりの戦略を見せ付けたのだ。 これにより上杉輝虎は関東と越中に軍勢を繰り出すこととなり、輝虎は信玄と氏康の策に踊らされ、いいように振り廻されることになった。 信玄は上野の松井田城と国峰城を得て、西上野を完全に武田領としたのだ。 これで武田家は関東から手を引くことになる。 漸く念願の駿河平定戦の始まりであるが、唯一、信玄は大いなる誤算をしていた。それは松平家康の器量を安易に考えていたことである。 信玄が関東出兵で上杉輝虎と合戦騒ぎをしている最中に、松平家康は信長と結んだ清須同盟で着々と三河の地で勢力を伸ばし、今川領を狙うまで力を付けていたのだ。 信玄は駿河平定の前に、三河の松平家と対峙せねば成らなくなった。
Nov 26, 2014
コメント(63)
-

改定・武田源氏の野望
「家康自立と乱世の様相」(77章)にほんブログ村にほんブログ村 元康からの同盟の使者が、清須を訪れた時、信長は小躍りしたという。 今の信長の最大の脅威は、美濃の斎藤家であった。 信長は美濃に出兵し森部の戦いで勝利し、漸く織田家は優位に立ち、斎藤家は家中で分裂騒ぎが始まっていた。 この時期、信長は北近江の浅井長政と同盟を結び、斎藤家への牽制を強化しようと考えていたのだ。 そこに降って湧いたように、岡崎の松平元康の使者を迎えたのだ。 この同盟は元康が提案し、信長が了解したものであった。 元康は東に向え、わしは美濃、北伊勢に勢力を伸ばす。 信長の構想と元康の考えが一致したのだ。 この同盟で松平家は今川家に乗っ取られた領土の回復が出来る。 織田家は今川家の脅威を心配する事なく、美濃攻めにかかれる。 それが信長の構想であった。 信長と元康は不思議な縁で結ばれていた。 元康が六歳の頃、父の広忠は織田家に対抗するため、今川家に従属し、元康は今川家の人質として駿府へ送られる事となった。 この時の元康の幼名が竹千代であった。 併し、駿府への途中に立ち寄った田原城で義母の父、戸田康光の裏切りに遭い、尾張の織田家へ送られる事に成ったが、父の広忠が今川家に従属を貫いたため、人質として二年間、尾張に止め置かれた。 この時期に信長と知り合ったのだ。こうした従属的な信長との関係は、信長が本能寺で変死するまで続くのであった。 信虎の危惧が現実となったのだ。その証として信長は、元康の嫡男の竹千代と我が娘の、徳姫との婚約を約束した。 これで松平家は織田家と縁戚を結び、信長の軍事力を背景として三河、遠江へ軍勢を出兵させることが可能となった。 この年の二月に元康は今川家の上郷城(かみのごう)を攻め、城主の鵜殿長持を殺害し、その倅の長照、長忠を生け捕りとした。 その捕虜と自分の妻と嫡男の竹千代と娘の亀姫との交換を申しで、見事に成功させたのだ。 ここに念願の今川家との手切れが出来た元康は、それを契機に義元から貰った、元の一字を今川家につき返し、松平家康と名乗ることになった。 こうして家康は正式に今川家と断絶したのだ。 躑躅ケ崎館で会談中の四人は清須同盟の締結により、一ヶ月後にこのような状況が訪れとは思わずにいる。 「御屋形、北条の要請を受け関東で上杉輝虎と戦う事はお止め下され。このままでは領民の苦しみが増し、領土が疲弊いたします」 飯富兵部少輔虎昌が優れない顔つきで諫言した。「飯富殿は上杉勢との合戦を止め、今川領を攻めよとの仰せかな」 馬場美濃守信春が揶揄うように言ってのけた。「それがしは今川家と事を構えよとは、申しておらぬ」 飯富兵部が気色ばんで答えた。「飯富殿とは思われぬお言葉じゃ、今川氏真殿は暗愚の聞こえが高い。我等は矛先を転じ、駿河に討って出ることが先決にござるぞ」 珍しく馬場信春の言葉がきつい。「馬場美濃、この件は余に考えがある。しばし待て」 信玄が短い言葉で馬場信春を制した。 飯富兵部は信玄の嫡男義信の傅役(もりやく)を仰せつかっていた、彼の心中は、義信のことで一杯であった。 それと言うのも義信の夫人は義元の娘であり、義元の室は信虎の娘であった。 謂わば、叔母、従妹の関係で義信は、心から夫人を愛していた。 それ故に今川家の本拠地である、駿河進攻には日頃から反対を唱えていた。 信玄は義信の心境も判っている、それ故に余と義信の間で苦悩する飯富兵部が憐れに思えたのだ。「余の存念を申し聞かす。岡崎の小童が勝手な真似をせぬように今川殿に与力いたし三河、遠江の守りを固める。更に父上の申されるよう三河一帯の一向門徒衆を味方といたし、松平家に内紛を策す」 信玄が言葉を止め、三人の重臣の顔色を見て再び口を開いた。「暫くは関東で北条勢と共に、上杉輝虎との合戦に意を注ぐ」 信玄が毅然たる口調で断じた。「そのような悠長な合戦は無駄にござる、一日も早い駿河進攻をお願いいたす」「馬場、急くな我等には西上野(にしこうずけ)が必要なのじゃ。そこを確りと確保いたし駿河に討って出る」 飯富兵部少輔虎昌の顔に安堵の色が見える。「虎昌、それまでには義信を説得いたせ」 「はっ」 飯富兵部が平伏した。 翌日、お弓は再び信玄の呼び出しをうけた。濃い髭跡をみせ信玄が主殿で待っていた。お弓の顔を見て直ぐに質問を発した。 「よく眠れたかの」 「はい、お蔭さまで安眠できました」「織田と松平が同盟いたした」 「真にございますか?」 お弓の問いに信玄が大きく首肯した。 矢張り大殿の眼力は確かじゃ、改めてお弓は信虎の凄味を知った。「父上に伝えてもらいたい、書状の仰せ肝に銘じて忘れはいたさぬ。じゃが我等は、暫く関東に精力を傾注いたす」 「・・・-」 お弓が信玄を仰ぎ見た。「訳を申す。上杉輝虎、我等の上洛にとりいささか邪魔じゃ。まず北条勢と関東で上杉勢を叩く、これなくて上洛覚束ない。さらに今川家じゃが、縁戚の関係もあり、氏真殿の動きを暫く眺める積りじゃ。三河、越中については父上の申されるよう、一向門徒衆と手を結ぶ。このように父上に伝えてもらいたい」「判りましてございます」 お弓が言葉短く答えた。「尚、関東に執着する意味を申す。西上野は三国峠に近い要地じゃ、由って上杉勢を叩き、西上野を確保するまでは関東から離れぬ」 信玄が引き締まった顔付で言葉を選び、断言した。「そのようにお伝い申しあげます」 お弓が平伏して答えた。「お弓、茶所の駿河のような美味い茶はないが、甲斐の茶も良いぞ」 信玄が言葉をかけ、自ら茶を喫している。「さてー」 信玄が言葉を切りお弓を眺めみた、心の内を見通すような眼差しである。「そちにはまだ余に申す事がある筈じゃな」 お弓が肯き、信虎が策す今川家重臣への調略の件を述べた。「なにっ、まだ父上は身を犠牲とされ大それた策謀を為されておられるか」 さしもの信玄の顔色も変わった。「瀬名駿河守、関口兵部少輔に葛山備中守の三名じゃな?」「はい、今の今川家は累卵の危うき情況にございます。いずれ内輪から崩れるものと推測いたします、そこを利用しょうと為されておられます」「・・・-」 信玄が瞑目し、腕を組んで考え込んだ。 お弓は信玄の言葉を待った。漸く眼を見開いた信玄がお弓を見据えた。 身のすくむような鋭い眼差しである。「余は考えを纏める、そのような大事を聞いては見逃せぬ」 お弓が黙して面を伏せた。「お弓、そちに会わせたき者がおる。心置きなく会って参れ」 突然、信玄が話題を変え、声が平常に戻っている。「・・・・・」 声なくお弓が信玄を見上げた、これから何かが起こるような気がして、胸が高鳴った。
Nov 22, 2014
コメント(61)
-

改定・武田源氏の野望
「お弓、信玄と面会する」(76章)にほんブログ村にほんブログ村 永禄五年二月初旬に蓑笠を纏い、厳重に足拵えをし草鞋を履いた女性が、甲斐古府中の城下町に姿を現した。 女性の履物を現在は草鞋(わらじ)と云われているが、当時はわらぐつと呼ばれていた。雪の季節にはかかせぬ、便利に履物であった。 女性は城下町の繁忙ぶりを物珍しそうに、笠の下から覗き見ている。 三日月眉に切れ長の眼の女性は美しく、町行く人々が好奇な眼差しで振り返っている。権高に見える美貌が、少ししゃくれ気味の鼻がそうした感じを消し去り、温か味のある美顔に変えていた。 女性はお弓であった。彼女は信虎の命で信玄に会いに来たのだ。 この古府中には甲斐武田家の居館、躑躅ケ崎館があった。左程、要害の城郭ではなく、三方を山に囲まれていた。南は甲府の景観が一望でき、館の北東半里の山中に要害の城が築かれ、領内を治める館と館を防衛する山城を有する、典型的な城下町であった。 それ故に館の防備は簡素で外濠が、館の防衛線の最前線の役目をしているが、左程、深い濠でもなく石垣も体裁程度の規模であった。 この地に移ってから武田勢の合戦は常に、他領での戦いであった。 戦国最強の軍団を擁する、信玄にとり「人は石垣、人は城」と考え、厳重な城塞などは無用の長物であったのだ。 それ故に城下は商人や職人達が整然と軒を並べ、商いは盛況を極めていた。 お弓は物珍しくそれらを眺め、雑踏に身を任せ歩を進めている。 彼女は歩きつつ笠を持ち上げ、北の方角を見つめた。 城下町は南に面し、北側は家臣団の屋敷町である。 そこには山本勘助の屋敷もあった。 お弓は成長したお麻に会いたいと思ったのだ。 そうした思いを胸に秘め、彼女は館の門前に辿り着いた。 門衛の足軽に信虎より与った証拠の品を見せ案内(あない)を請うた。 驚いた足軽が慌てふたむき館に姿を消し、身形の立派な武士が現われた。「駿府の大殿の使いの者とはそちか?、御屋形さまがお待ちかねじゃ」 茅葺き屋根の館の内部に案内され、長廊下を伝って主殿に導かれた。 座所には中年の武将が脇息に身をもたせていた、まるで信虎に生き写しそのままである。 お弓が目を見張った。「余が信玄じゃ。遠路はるばる駿府よりよくぞ参った」 声に張りがあり、腹に響くような声をあげ眼に精気が漲っている。「お弓と申しまする」 「河野より聞いておる。そこは寒い、もそっと中に入れ」 信玄が豪放磊落に言葉をかけ、しげしげとお弓を見つめ驚嘆した。 死んだ勘助の娘に瓜ふたつではないか。「父上の書状を見せよ」 お弓が小腰を屈め丁重に書状を差し出した。「拝見いたす」 書状を手にし、深々と辞儀をして読み下している。 流石は信玄さま、お弓が信玄の態度に感心の面持で眺め入っている。「父上の書状、確かに信玄拝見した。・・・どうかいたしたか?」 信玄の眸子の奥に好意が感じられる。「余りにも大殿に似ておられますので驚いております」「似て当然じゃ、親子じゃからな。二、三質問いたす」「はい」 お弓が信玄の言葉に平伏した。「まず、本願寺の件じゃが、余はまだ時期尚早と考えておる」 弓が信虎との寝物語で聞いた事を述べた。 信玄は太い腕を組んでじっと聞き入っている。 「尾張の織田信長には、そんな臭いがすると仰せられたか?」 「はい」「余も今川義元殿を討ち取った力量には感服いたしておる」 信玄が髭跡の濃い、顎を擦ってお弓をじっと凝視した。「申しあげます。あの田楽狭間で今川義元さまが休息なされた刻限を、お知らせした者は、大殿さまの忍びにございます」「何とー、あれも父上のお指図か?」 お弓が黙して肯いた。 信玄は初めて父、信虎の謀略の凄まじさを知らされたのだ。 このような事を一腰元風情に洩らされるとは、この女子は父上の愛妾じゃな。 素早く看破した信玄である。「そちから、もう一度話が聞きたい。三日ほどこの館に逗留いたせ」 お弓は立派な一室を離れに与えられ、長旅の疲れを癒している。 先刻の信玄の顔が蘇っている。大殿に似ている相貌ながら、気迫の鋭さ、人に接する温かみの違いを悟っている。 海内一の弓取りとは、あのような武将を云うものじゃ。と感じ入っていた。 その頃、信玄は飯富兵部と馬場信春の重臣とで、父の信虎の書状を広げ語りあっていた。「驚きましたな、駿府の大殿が義元さまの討死に一枚咬んでおられたとは」 馬場信春が驚嘆の面差しをしている。 飯富兵部は信虎を甲斐から追放した時の様子を思い描いている。「父上の深慮遠謀は倅の余も叶わぬ」 信玄が太い息を吐き出した。 「両名に申し聞かす。西上野が強固に成るまでは関東から兵は引かぬ。じゃが、後は父上の申された通りに事を処すると決めた。良いの」「はっ」 二人の重臣が声を揃えた。 「申し上げます」 主殿の外から警護の家臣の声が響いた。「何事か」「真田幸隆さま、火急の用でお目通りを願って居られます」「なんと・・・幸隆が参っておるか。通せ」「はっ」 家臣の返答と同時に、柔和な顔付の真田幸隆が姿を現した。「如何、致されましたぞ」 飯富兵庫が訊ねた。幸隆は三人の傍らに腰を据え。信玄を見つめ、「御屋形、尾張に潜む忍びより火急の知らせが参っておりまする」 幸隆が緊張した口調で告げた。 「なんぞ悪い知らせにござるか?」 馬場信春が、もの柔らかく訊ねた。「さる十五日に岡崎の松平元康が、清須城を訪れたとの知らせにござる」「なに、真田殿それはまことの事にござるか?」 馬場信春が念押しした。「真のことであろう。織田信長と松平元康は何を話し合ったであろうかの」 信玄は先刻のお弓から告げられた話しと重ね合わせている。「元康が清須同盟を提案し、信長が受けた模様にございます」「父上の仰せどおりとなったか」 信玄が肉太い頬をなでさすって呟いた。「大殿の書状にも、織田信長が最大の強敵となると記されておりましたな」 飯富兵部が口をきり、何事か思案している。「三人とも良く聞くのじゃ、信長は美濃を支配いたすであろう。京への道じゃ」 信玄が信長の行動を予測し言葉を発した。「岡崎の松平元康、今川家に敵対し三河、遠江の地を狙いましょうな」 飯富兵部がずばりと核心をついた。流石は武田の重鎮である。
Nov 20, 2014
コメント(49)
-

改定・武田源氏の野望
「信虎の新たな謀略」(75章)にほんブログ村にほんブログ村 お弓が涙ぐむ信虎を見つめた。信虎の躰が一回り小さく見える。 頑固者で偏屈を絵に描いたような信虎が、人替わりしたように思える。「お弓、ちり紙をくれえ」 泣き終えた信虎がちり紙で鼻をかみ、背筋を伸ばした。「河野、信玄に伝えよ。時は待ってはくれぬとな」 「それはいかなる意味にございます」「信玄ならば判っておろう。一刻も早く関東から手を引き駿河を狙うのじゃ」 老虎が再び覚醒したのだ。「驚いたお方じゃ、よりによって今川家譜代の重臣を調略されるとは」 河野晋作と小十郎が驚いて隠居所から去って行った。「兵左衛門、そちも下がって休め。お弓に聞きたい事があるでな」 信虎が脇息を廻し、膝前に据え肘を乗せた。 小林兵左衛門が足音を殺し、座敷をあとにしていった。 それを待っていたように、お弓が口を開いた。「大殿、勘助殿はまことに討ち死なされましたのか?」 訊ねるお弓の顔色が真剣である。「お弓、まだあのちんばに未練があるか?」 信虎が口汚く勘助を罵り、お弓の顔色を窺っている。「あい、わたしが惚れたお方ゆえ未練が残ります」 お弓が平然とした口調で返事を返した。 信虎が魁偉な容貌を歪め、にやりとしお弓を見つめた。「死なれてはわしが困る、奴は生きておる」 その言葉を聴き、お弓の顔に生色が戻った。「何処に居られます?」「そう急くな。今は内緒じゃが、そのうちに会わせてやる」「本当にございますな」 念を押す、お弓に安堵の色が刷かれている。「勘助はわしと武田にとって大事な男じゃ、恐らく信玄も承知の筈じゃ。ところでそちに尋ねたき事がある、わしも心を引き締め尋ねる。そちも隠さず、真実を語ってもらわねばならぬ」 信虎が脇息から身を乗り出した。 「そのように改まって・・・・何事にございます?」 お弓がひたっと眸子を信虎の視線に合わせた。 信虎が眼をしばたたき、言葉を模索している。それが態度で分かる。 「実は、そちは内密でわしの子を産み落としたと聞いたが本当か?」 信虎の魁偉な容貌が引き締まっている。 突然の質問を受けたお弓が動悸を押さえ、信虎の顔を凝視した。「本当なればいかが為されます?」 何故、大殿が知っておられる。その疑問が真っ先に過った。「その子は何処におる?」 「古府中の山本勘助殿のお屋敷にあずけておりまする」「勘助に養育を頼んだのか」 信虎の相貌に形容できない不思議な色が浮かんだ。「あの子は勘助殿とわたしの子、養育を頼むに不審がございますか?」「うーん・・そちと勘助の子か」 信虎が半信半疑でいる。 「お弓は一度も大殿を裏切ったことはありませぬ」「それを信じろと申すか」 「信じて下され。じゃが誰がこのような話を大殿の耳に」 信虎がお弓を真っ直ぐに見つめ、自嘲気味に口許をひくっかせた。「胤が尽き果てた、わしに子が出来る筈がないの」 お弓は真実を告げたかった。だが高齢の信虎に、これ以上の気遣いをさせる事に戸惑いがあった。「その話をわしに告げた者は死んだ」 今度はお弓が驚く番であった。勘殿か?じゃが勘殿は死んではいない筈、心の中で自問自答した。「お弓、その子は男子(おのこ)か? それとも女子か?」 信虎が訊ね、お弓の顔色を覗っている。「娘にございます。今年で十二才となり、可愛い盛りにございます」 お弓がしらっと返事を還した。こうした嘘は女の得意技である。「判った、この話はうちきる。そちは甲斐に行け、わしの書状を持参いたし、信玄に直に渡すのじゃ」 「信玄さまに直にお会いしますのか?」 これには流石のお弓も戸惑いを覚えた。「そうじゃ、勘助無きあと誰が信玄に意見する。それはわしの努めじゃ」「ただ書状をお渡しすれば宜しいのですね」「それでは使者の努めが成り立たぬ、信玄の訊ねる事はわしに遠慮せずに述べるのじゃ」 「あい、判りましたぞ」 お弓が破顔した。四十才を越えている筈であるが濃艶な色気が感じられる。「大殿、今宵はご一緒に褥に入りますぞ」「阿呆め、わしの年を知っておろう」 「ただ、抱きしめて下され」 信虎は寝床でお弓の豊満で張りのある乳房を愛撫している。既に己の一物は全く用をなさなくなっていた。 併し、お弓の暖かい手でふぐりと一物の先端を柔らかく愛撫され、微かながらも快感が、余韻となって背筋にむかって駆け抜けた。「女子の躯は良いのう」 信虎がお弓の耳元に熱い吐息を吹きかけた。 そう言いながら信虎はお弓の秘所を嬲っている。(この女子はこの躰で勘助の子を産み落としたのか) そう思うと嫉妬に似た感情が湧きあがってくる。 「お弓はもう誰とも寝ませぬ、大殿の女として生涯を送ります」 この言葉も殊勝に聞こえる。「わしに遠慮はいらぬ。そちの躯はまだまだ若い」 げんにお弓の秘所はしっとりと濡れている、指がそっと差し込まれ、快感と共に吐息が独りでに洩れた。 「もう一度聞くが、甲斐に居る娘はわしの子ではないのじゃな」 お弓が、骨ばった信虎の躯をきつく抱きしめた。 暫し黙したまま、お弓の狭間に指を這わせていた信虎が口を開いた。「お弓、わしの考えを申し聞かせる。必ず信玄に伝えるのじゃ」 お弓は無言で秘所を弄(なぶ)らせ信虎の言葉を聞いている。「今後は尾張の織田信長が脅威となろう。奴の行動をみると得体の知れない臭いがする。奴は必ず上洛を画策いたしておる」 「あっ・・-」 お弓が敏感な箇所をまさぐられ悲鳴をあげた。「信長は三河の松平と同盟を結ぶじゃろう。武田の最大最強の敵は信長じゃ。 松平家は三河、遠江、駿河と今川の領土を狙って参ろう。信長は美濃、伊勢、さらに近江、越前を狙い、京の北方に勢力を拡大すると読む。今川家や北条、上杉なんぞに、係わってならぬ。そう、わしが申しておったと伝えるのじゃ」「判りましたぞ」 お弓が熱い吐息と一緒に返答をした。「これから申すことが大事じゃ。石山本願寺と強固な軍事同盟を結べと申せ、一向門徒衆の力は侮れぬ。彼等の力は日本全土に及んでおる。心して同盟をなせと、信玄に伝えるのじゃ」 信虎は語り終え、暫くお弓の躯をまさぐっていたが、微かな寝息をたて眠りについた。 お弓がそっと煙草の匂いのする、信虎の体臭の漂う寝床から滑り出た。(お麻は大殿の娘です) と、夢路を辿る信虎にそっと囁き、部屋から消え失せた。
Nov 14, 2014
コメント(83)
-

改定・武田源氏の野望
「新興勢力の台頭」(74章)にほんブログ村にほんブログ村 武田信玄と上杉政虎の雌雄を決する、川中島合戦は終わったが、その翳で戦国の世が、微かではあるが変貌を始めたのだ。 それは一国の衰亡を発端として起こった。 その国が東海一の大国、駿河の今川家であった。 上洛を目差した義元が桶狭間で討死し、倅の氏真が当主に座った時から、その衰亡が始まったのだ。 その原因は父、義元の弔い合戦もせず、女子と酒に現を抜かす、氏真の無能な所業の所為であった。 戦国乱世にあっての弔い合戦は、武将としての拠り所であったが、氏真は全く無能な男で遂に、父親の弔い合戦をせぬままに日を送り、その態度をみた多くの豪族が、今川家を見限り離脱して行った。 その影響が顕著に現れたのが三河の地であった。 ここは元々、三河松平家の支配地であったが、当主の非業の死で今川家が庇護し、そのまま属国とした一帯であった。 義元が織田信長に討たれた知るや、今川家の城代は三河の最重要拠点の岡崎城を、真っ先に放棄し、駿府へと引き上げて行った。 まさに戦略眼のない城代であった。 その空城となった岡崎城に松平元康が抜かりなく入城し、氏真に義元の弔い合戦を進言したのだ。 これは今川家への恐怖から出た進言で、こうしておけば元康は今川家の縁者として身の安泰が計れたのだ。 今川家がこのように衰退しても、その力は絶大で氏真が元康を討てと命ずれば、赤子の手を捻るように元康は簡単に討たれたであろう。 氏真からすれば元康の進言は煩わしい事であったが、元康は今川家の武将であり縁者である、そう信じきっていたのだ。 未だに駿府城には、元康の妻子が人質同然に捕らわれている。 それ故に岡崎城入城には寛大であり、宿老達も今川の為の行動と考えていた。 元康はこの好機を逃さず、三河を確りと松平家の領地として固めたのだ。 こうして大国、駿河の衰亡が、近隣諸国へ大きな影響を与えたのだ。 まさに駿河を巡り、三河、遠江、尾張、美濃の地が沸騰を始めたのだ。 駿府の隠居所の座敷に信虎を交え、五名の者達が集まっていた。 真冬というに座敷には障子戸を透かし、燦々と陽の光が差し込み、火鉢もいらないほどである。 信虎は六十七才となっていたが、一向に謀略の衰えもみせず益々、陰湿な策謀をめぐらすようになっていた。 座敷には信虎の股肱の小林兵左衛門とお弓の二人と、小十郎も同席し、武田家の忍びの頭領である、河野晋作と信虎の会話を聞いている。「河野、川中島の合戦では間違いなく山本勘助は討死いたしたか?」「左様、首級は発見できませなんだが、間違いなく山本さまの遺骸」 河野晋作にも忍びの頭領らしく貫禄も備わってきた。 お弓が顔色を変え唇を噛み締め顔を俯けた。「信玄はいかがいたしおる?」 信虎がしわ深い顔をみせ、鋭い口調で訊ねた。「信繁さまはじめ山本さま、さらに多くの武将を失われましたが、漸く心の傷を癒されたとお見うけいたします」「莫迦者が、駿河に軍勢を繰り出さずに関東に現を抜かすとはな」 信虎が口汚く罵った。「今は北条殿と手を結び上杉勢と対する、これが武田家の戦略にございます」「そちは越中の本願寺をどう見ておる。まさか調略を止めた訳ではあるまいな」「越中の一向門徒衆はお味方、ことある度に越後の背後を脅かしております」「甘いのじゃ」 信虎のしわがれ声に怒気が含まれている。「どうせよと申されます?」「輝虎が関東に出陣した留守に、一気に越後国境から攻め込むのじゃ」「上杉政虎は名を改めましたのか」 お弓である。「将軍足利義輝の偏諱(へんい)を受けてな、そのような些事はよい。何故に越中の本願寺と共に越後を攻めぬ」「留守居役の長尾政景は評判通りの武将、迂闊に攻め寄せますと痛い目にあいまする」 河野晋作が恐れる素振りも見せずに反論した。 「判った、暫くは眼を瞑ろう」 信虎がしわ深い顔を歪めている。「ところで本日、我等を呼んだ真意は何でございます?」 河野晋作が眼を光らした。 「そち達は世の中を見ておるのか?」 信虎のしわ深い顔に怒気が含まれている。「・・・-」 全員が答えに窮した。「尾張、三河をよく眺めよ、美濃では義龍が急死いたし、十四才の龍興(たつおき)が跡目を継いだ。それに乗じて織田信長め、奴は美濃攻略に奔走いたしておる。先年の五月には森部の戦いを仕掛け、今は墨俣に砦を築き小牧山にも築城しておると聞く、いずれ美濃は信長の手に落ちよう。一方の三河はどうじゃ?」「申しあげます」 それまで黙していた小十郎が、抑揚のない声を発した。 「申せー」「松平元康殿、岡崎城で勢力を張り三河の諸豪族の城を攻略いたしております。 このまま放置いたせば三河、遠江は、遠からず松平家が支配いたしましょう」「まずは三河じゃ、今川の倅は弔い合戦もせず女と酒にうつつを抜かしておる。このまま信玄が手をこまねいておれば、小十郎の申す通りになるじゃろう」「それは判っております」 「河野、そちは判ってはおらぬ」 信虎の怒声を浴び、河野晋作が顔色を変えた。「判っておるなら手をうて莫迦者が、三河も一向門徒衆の巣窟じゃ。特に野寺の本証寺は門徒衆にとり大切な寺じゃ、ここに調略の手を伸ばせ」「申し訳ございませぬ、我等は三河の一向門徒衆の力を侮っておりました。 彼等の力は小豪族や、松平家の家臣まで及んでおりますな」 河野晋作が感心の面持で応じた。「川田弥五郎は元康により、旗本に取り立てられておる。河野、その弥五郎を通じ、松平家臣達が元康に逆らうような工作を考えよ」 「承知いたしました」 「小十郎は地侍や門徒衆をそそのかすのじゃ。出来るか?」 「判ってござる」 小十郎が感情のない声で応じた。「大殿には驚きに御座います。駿河に居られ各地の様子を知っておられるとは」 河野晋作が驚きを隠さずにいる。「そちも武田の忍びの頭領じゃが気配りが足らぬ、これは全てお弓の働きじゃ」「お弓殿の」 お弓が口許をほころばしている。 成程な、武田家の軍師であった山本勘助さまを手玉に取ったお方じゃ。 河野晋作が一人、合点した。「いずれにしても標的は上杉輝虎と三河の松平元康じゃ、心して励め」「大殿は、他に何かをおやりになられますのか?」 河野晋作が尋ねた。「わしは駿府城を調略いたす」 信虎が乾いた顔で平然と答えた。「何とー」 「今川家は駄目じゃ、わしはの今川の重臣の中で瀬名駿河守、 関口兵部、葛山備中守を狙っておる」 河野晋作が一瞬言葉につまった。いずれも今川譜代の重臣達である。「成算はおありに御座いますか?」 「なくて話はせぬ」 再び怒声を浴びせられた。「大殿、お話しせねばならぬ事がございます」 河野晋作が威儀を正している。「なんじゃ?」 信虎が不審そうに河野の顔を見つめた。「信繁さまのご最後の様子にございます」「何とー」 信虎が男兄弟のなかで一番、可愛がった倅が次男の信繁であった。「どのような最期であった?」 信虎が眼を瞑っている。河野晋作が信繁の最後の模様を語った。 戦況、不利を悟った信繁は家来の春日源之丞を馬前に呼び寄せ、信玄直筆の法華経陀羅尼品(だらにほん)の経文を金粉で書いた母衣と、乱れ髪の一握りを切り取って渡した。「父の形見として吾子、信豊に渡してくれよ」 と遺言を残し、群がり寄せる越後勢の中に駆け入り、壮烈な討死を遂げた。「・・・・信繁、さぞや無念であったじゃろう。信豊に形見を残したか」 老いた信虎のしわ深い頬に、涙が伝っている。 四人が呆然と信虎の様子を見つめている。「信玄に伝えよ。政虎なんぞと合戦するから信繁を殺したのじゃ、武田の標的は今川じゃ。この言葉を伝えてくれえ」 涙が零れるままに、声を震わせる信虎であった。
Nov 12, 2014
コメント(58)
-

改定・武田源氏の野望
「激闘、川中島合戦」(73章)にほんブログ村にほんブログ村 (第四回川中島合戦) 信玄が黙然として佇んでいる。信ずる事の出来ぬ報告を聴いたのだ。 先刻は弟の典厩信繁の討死の報せを聴いても、顔色も変えずに耐えた信玄が、山本勘助の討死の報せで呆然自失となっている。 妻女山奇襲部隊の将兵が、本陣の前を駆け抜けて行く、黄備えの騎馬が一団となって猛烈な勢いで犀川方面へと疾走して行った。「はっー」 「はっー」 聞き覚えのある声を挙げ、馬場美濃守信春、飯富兵部虎昌、小山田信茂、 甘利昌忠、真田幸隆等が騎馬に鞭を与え、一斉に追撃して行く。 彼等にとっては満を持した戦であった。 馬蹄の響き、甲冑、草擦りの音が響き、その後から足軽達が笠をかたむけ、眼を剥いて、得物を手に何千名とも数知れぬ、兵士の群れが後続している。 今こそ本隊の苦戦を我等の手で晴らす。 その一念で越後勢の背後を必死で追いすがっていた。 暫く時が過ぎ犀川方面から銃声の乱れ射ちと喊声が聞こえてきた。 別働隊と越後勢が、本格的な合戦に入った合図である。 犀川の手前と対岸、更に犀川の半ばで激しい戦闘が繰り広げられた。 川水が泡立ち、血煙を挙げて川中に転がる彼我の兵士の血潮で川水が、真っ赤に変色したと言われている。 それほど激しい戦いを双方ともが繰り広げたのだ。 それは勝利の名分が、両陣営ともに欲しかったのだ。 戦国乱世には、その名分こそが家の誉れであり、武門の誉れでもあった。「別働隊が敵と合戦に入ったようじゃ。者共、仇討ちじゃ」 山県三郎兵衛が本陣前で部下を督励する声が響き、赤備えの騎馬武者が反転し、越後勢への追撃戦を開始した。 信玄は八幡原を見廻した。辺りには死骸が横たわり軍馬が斃れ、死にきれずに、苦悶の悲鳴をあげている。 彼我の兵士の遺骸は、我が軍勢の将兵が圧倒的に多い。 それだけ越後勢が精強であった証である。 そうした光景の中、空は真っ青な秋空を見せ。雲が悠々と流れ、朝日を浴び、この八幡原の北西に聳える、茶臼山の稜線が緑色に輝きだした。 信玄は床几に腰を据えた。躰が鉛のように重く感じられる。 越後勢の奇襲を受けた本隊の被害は、予想よりも甚大であった。 特に将の討死が多かった、その中に弟の典厩信繁、諸角昌清、゛初鹿野忠次、軍師、山本勘助の討死は武田にとり大きな損失であった。 信玄は一人、荒野に取り残された感覚の中に居た。胸にぽっかりと穴が開き、冷気が吹き込んでいる、そんな思いを味わっていた。(勘助、何故、余との約束を守らなんだ) 一人でに勘助に対する、恨み言が口を衝いてでる。 突然、母衣武者が駆け戻り、信玄に片膝をついて声を張りあげた。「山本勘助さま、お討ち死ににございます」「何処で討死をいたした?」 「東福寺近辺にございます」「・・・-遺骸は確かめたのか?」 「申し訳ございませぬ。、お報せが先と思い確かめてはおりませぬ」 東福寺は海津城の北に当たる一帯に位置し、武田勢が妻女山から駆け下る、その押さえとして越後の甘糟勢が、その東福寺の西に伏兵として潜んでいた場所である。 勘助め余をあざむきおったな瞬時に悟った。 政虎の本陣に突撃せんと出陣した勘助が、そのような場所で死ぬ訳がない。 信玄がぽつりと低く呟いた。「信繁の墓も勘助もここに葬ってつかわす」 信玄が重そうに床几から立ち上がった。 犀川方面からは未だに干戈の音と喚声が聞こえる。 上杉の本陣付近から法螺貝が一帯に鳴り響いた。引きあげの合図だろう。 一斉に越後勢は引き揚げを開始し、善光寺に向って撤退を始めた。 それは難戦中の難戦であったが、見事に越後勢は成し遂げた。 こうして戦国有名な川中島合戦は終りを告げた。緒戦は上杉勢が圧倒し後半は武田勢が追い討ちをかけ、合戦は午後四時頃に幕をおろした。 双方の損害は上杉勢が三千五百余名、武田勢が四千六百余名と伝えられて いるが、武田家は有力な武将を数多く失った。 この合戦で上杉家は川中島北部を辛うじて確保し、武田家は信濃の大半を領する事となった。 翌日、勘助の遺体が見つかった。いく創もの傷を負い、白の法衣は血潮に塗れ、首のない勘助の愛用の鎧を纏った武者の遺骸であった。 信繁は信玄により典厩寺を建立され、そこに葬られたが、勘助は千曲川の土手下に墓を立てられ葬られた。「山本道鬼居士墓」と碑面に刻まれている。 何故、勘助のみがこのような場所に葬られたのかは、永遠の謎である。 さらに三年後の永禄七年七月に両軍は、再び相いまもえるが、信玄には戦う意志がなく、両軍は睨みあいを続け兵を引いた。 十二年間も続いた、両雄の烈しい戦いは終りを告げるが、時代は確実に新興勢力として、織田信長、三河の松平家康が台頭してくるのであった。 (三河一揆) 武田信玄はこの年の暮れから、北条氏康との同盟をさらに強化し関東に本格的な出兵をはじめた。 信玄の関東での狙いは、西上野の支配と北条勢との強固な同盟の二つであった。 一方、上杉政虎は関東管領として北条勢、武田勢と関東で戦うことになる。 上杉政虎が謙信を名乗るのは、彼が四十一才となった元亀元年からで、彼の不幸は領国が雪深い越後であった事である。夏に三国峠を越えて関東に出馬すると、北条氏康は居城の小田原城に籠城し、謙信が折角、降した城を冬の季節に回復するという図式が何年となく続くのであった。 武田信玄の関東進出は永禄八年まで続くが、これは今川家に代わり駿河、遠江を支配する上には、北条氏康の力が必要であり、その為にも同盟を強化し、上杉勢を牽制する必要があったのだ。 しかし、氏康が晩年に家督を嫡男の氏政に譲った頃から、北条家との関係が怪しくなり、今川の領土をめぐり何度となく合戦騒ぎを起こす事になる。 こうした年月の浪費が後に信玄と武田家に、重大な脅威となるのであるが、信玄も武将連も気付かずにいた。こうして波乱にとんだ年が暮れた。
Nov 6, 2014
コメント(92)
-

改定・武田源氏の野望
「濃霧の八幡原合戦」(72章)にほんブログ村にほんブログ村 (第四回川中島合戦) すでに辰ノ刻(午前八時)に近づいているようだ。 流石の越後勢にも焦りの色が見えはじめた。 武田勢も本陣の前衛にいた穴山勢も戦闘に加わっている。 今や一兵も残さず戦場に出たのだ。本陣では信玄の周りだけが静まり、本陣直属の旗本と勘助の手勢、五百騎のみが最後の下知を待っている。「勘助、妻女山の別動隊は間にあわぬな」 信玄が軍配団扇を手に、合戦を楽しむかのような声を発した。「御屋形、今頃は千曲川を渡河し越後勢を突破しておると思われます。 今しばらく我慢下され」 事実、高坂弾正昌信率いる一万二千の精兵は、途中の甘糟勢を粉砕し一斉に八幡原を目差していたのだ。 濃霧のため、丘陵がなだらかな落差をみせる川中島の地形が彼等の進撃を鈍らせていたのだ。「駆けよー。遅れると御屋形が危うい」 高坂弾正が声を張りあげ督励し、猛然と先頭を駆けていた。 本営の数十町前は両軍が血塗れとなり、雄叫びをあげる混戦となっている。 母衣武者が本陣に駆け戻り、どっと武者が落馬した。 背に数本の矢が突き刺さっている。「典厩信繁さま、水沢付近でお討死にございます」 血を吐くような叫び声をあげ地面に転がった。「なんとー、典厩信繁さまもか」 勘助が顔色を変え、床几から腰を浮かせた。 一瞬、信玄が瞑目し低く呟いた。「はや討死いたしたか?少し辛抱いたせば勝鬨が聞けたものにな」 信玄が討死した、弟の信繁の死を悼んでいる。「御屋形、申し訳ございませぬ」 「勘助、何も申すな、ここは戦場じゃ」 信玄はこの情況でも自軍の勝利を信じているようだ。 勘助が再び平原を見渡したが、何の変化も見えない。 典厩信繁は武田勢の副将として左翼を守っていたが、越後勢最強と言われる柿崎勢の攻撃を何度も防ぎ、最早、此れまでと残兵を率い政虎の本陣を衝こうと敵勢に突入し、柿崎勢の武将と相打ちで壮烈な最期を遂げたのだ。 常に兄の信玄を助け、信玄の嫡男の義信をかばい信玄の片腕として存在を示してきた。その信繁の討死は武田家の将来に暗雲をもたらすものであった。 勘助の脳裡に思慮深い、信繁の端正な相貌が過ぎった。 自分の作戦の誤りで討死させたと思うと、悲しみをこえ憤りが湧いた。 勘助がしのび緒を引き締め戦場を眺め廻した。戦況は益々悪化している。 ここまで戦況が悪化しては、成す術はない。ただ政虎の本陣を衝くのみ。「御屋形、それがしも出陣いたします」 勘助の声に信玄が、軍配団扇を振って肯いた。「余は死なぬ、そちも必ず余の許に戻って参れ、これは命令じゃ」「はっー」 勘助が膝をついて応じ、足を引きずり采配を振った。「出陣じゃ」 勘助が兜姿で愛用の槍を抱え騎乗し、傍らに槍持ちの平蔵が控えている。「皆供、周囲に眼をくれるな、目指すは政虎の本陣のみじゃ」 「おうー」 勘助と信玄の視線が絡まった。 「いざ、参ります」 「行けー」 山本隊二百騎が乱戦の中を割って、黒旋風となって進撃を開始した。(死ぬな、勘助) 信玄は胸中で呟き床几に深々と座った。彼の前はがら空きとなっている。 夫々の兵士が生死をかけて戦っているのだ。 鞍上に顔を伏せ勘助は政虎の本陣を目指し、心のうちで歯軋りしていた。 越後勢が妻女山に居座ったのは、我等の策を読みきった政虎の策であった。 今頃になって気付くとは、奇策など遣らずに長期戦に持ち込むか、本隊を犀川に向け北国街道を扼し、海津城の兵と本隊の兵とで前後から越後勢を包み込む作戦が最善であった。 わしの誤りで多くの将兵を失った、作戦の誤りが痛いほど勘助の心を苛んだ。 敵勢の抵抗が烈しくなり、後続の騎馬武者が次々と落馬している。 勘助は満身創痍となり小高い丘に駆け上がり騎馬を止めた。「本陣は無事か?」 「諏訪法性と孫子の御旗は無事に翻っております」「よし、由蔵」 「はっ」 騎馬が一騎寄ってきた。その形は勘助にそっくりである。 「そちは騎馬二十騎を従えて打ち合わせどうり北から上杉の本陣を衝け」「承知にござる」 「さらば行け」 丘を駆け下り二十騎が猛然と敵勢の中に駆け去った。 八幡原の武田本陣の信玄は床几に腰を据え、諏訪法性の兜の唐牛の白毛を風に靡かせ前方を見つめている。彼の視線の先に十騎の武者の姿が見えた、いずれも白練りの行人包みで顔を覆っている。 あれに政虎が居るなと悟った時、十騎が一斉に抜刀し満を持し武田本陣をめがけ疾走し、一騎が猛然と本陣に駆け寄って来る。 見事な駿馬である。あれが政虎の愛馬、放生月毛だと悟った。 放生月毛の蹄から平原の草が舞い上がり、鞍上の政虎が吠えた。「信玄入道、今日こそ勝負を決する」 旗本が迎え撃ったが、たちまちのうちに蹴散らされた。「信玄、推参」 若々しい声と同時に黄金造りの陣太刀が煌き、信玄は軍配で防いだ。 政虎の陣太刀は備前長船の名刀、兼光である。「上杉政虎か?」 信玄が床几に座り吠えた。「左様、今日こそ貴様の首を奪い取る」 政虎は巧に騎馬を操り二の太刀、三の太刀と襲いかかり、信玄はその度軍配団扇で払ったが、右手と肩に浅手を負わされ軍配が斬り裂かれた。 信玄は政虎の連続攻撃で床几から、立ち上がる暇もない。 この政虎と信玄の直接対決が「三太刀七太刀」の伝説となったのだ。 傍らの原大隈が驚いて信玄の槍を手に政虎を突いた、偶然とは恐ろしいもので槍先が、政虎の放生月毛の尻を掠めた。 驚いた馬が狂奔し狂ったように本陣を駆けぬけ、平原の彼方に消えうせた。 平原から武田本陣に、政虎の若々しい笑い声が響き、「次は必ず、そのそっ首を貰いうける」 政虎にとり、信玄の首を取りそこなった事は悔しいものであった。『遺恨十年一剣を磨き 流星光底長蛇を逸す』 まさにこの文言通りの気持ちであった。「越後の小童め」 信玄が漸く立ち上がった。 「御屋形さま、お怪我は?」「原、大事ない」 これほど烈しい合戦は初めてである。 信玄の視線にけし粒のような物が、平原一面に広がり、馬蹄の音を響かせ、怒涛の如く進撃する軍勢に見えてきた。 「高坂か?」「御屋形さま、遅参いたし申し訳ございませぬ」「高坂、越後勢は犀川方面に退いておる。追撃いたし殲滅いたせ」「はっ、お怒りは後刻」 高坂弾正が鞭を鳴らし全軍に進撃を命じ、犀川方面に向かって行った。 それを見送った信玄の耳朶に、信じられない声が前方より聞こえた。 「山本勘助さま、お討ち死に」「なんとー、勘助め、余の命に叛いたか」 信玄が呆然と佇んだ。
Nov 3, 2014
コメント(68)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-
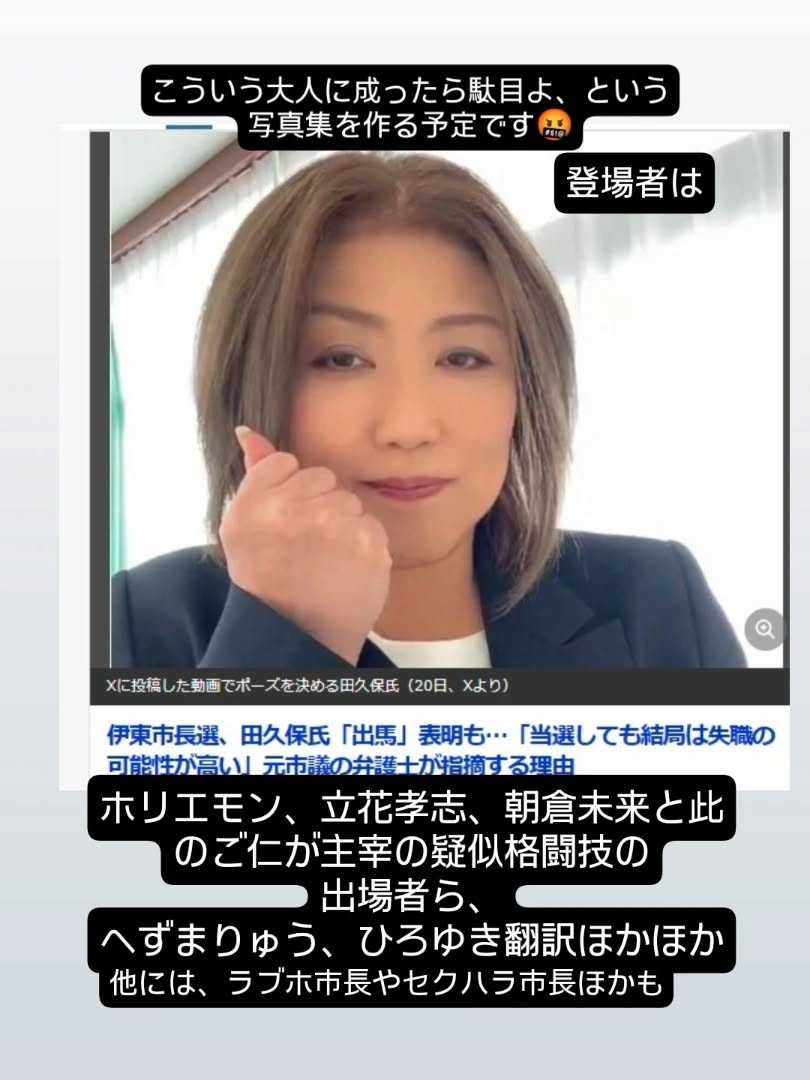
- 人生、生き方についてあれこれ
- Nov.23 田久保前市長・立花孝志氏・…
- (2025-11-23 19:32:35)
-
-
-

- 楽天ブックス
- PlayStation5 デジタル・エディショ…
- (2025-11-26 11:58:56)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-







