2013年02月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
布教するのに、説明責任がある??
このブログにて、ネットにある邪義をだしてきた。今は、調べるのはネット検索の時代である。その内容は、幼稚的であり矛盾だらけであり、歴史的な部分無視しているもばかりである。さて、その矛盾を矛盾と思わない者が多いのだが、私の友人のブログにて、以下の湘南坊遺とやらはのやり取りがある。http://ameblo.jp/soka-kennshoukai/entry-10370804932.htmlその中で、こういうのがあった。日蓮正宗系、特に今そうした行動が目立つ顕正会もそうですが、これらの教団は「折伏(しゃくぶく)」という名の「勧誘行為」をします。これは周知の事実でしょう。両者の勧誘行為は、「本門戒壇の大御本尊」に帰依せしめる為に行われるわけです。そこで考えなければならないのは、勧誘をす以上、社会的に見ても必ず「説明責任」が生じるということです。つまり、「その本門戒壇の大御本尊」についての説明責任です。薬を売る人は、その成分を熟知しているが故に薬をうれるわけです。車を売る人は、その性能やシステムを熟知しているから車を売ることができるわけです。それと同じです。こういうやり取りは、噴飯物である(爆笑)これを言ってる時点で、墓穴を掘る行為である。さて、車を売る人は、その性能やシステムを熟知してるのでしょうか?では、車の全部品全て熟知してるのでしょうか?これは、国家資格である自動車整備士の資格とくに、二級クラスの知識以上が無いと、車を売る事不可能となるのですが?(爆笑)新車の車のカタログには、全てのシステムは書かれていない。それは、トヨタでもHONDAでも日産自動車でも、三菱でもダイハツでも、どの国内及び海外車のカタログには、絶対ありません。この車は、エンジン◯◯◯で、排気量がどここう。エンジンの爆発順序どうこう。電気系がどうこうと、事細かく説明する営業マンっていないでしょう。かという私は、工業高校でしかも自動車整備士の資格があるので、営業マンより車のエンジンは、詳しかったですよ。営業マンは、どの営業マンに言える事であるが、その人がどういう物を求めているのか?そこを説明できるのが、営業マンである。私たちの信仰においても、同じ事である。説明責任というが、キリスト教教会に行き、神はどのように誕生したのか?説明できる牧師もいないのである。また、架空仏たる大日如来を拝む真言宗や、阿弥陀如来の念仏もその仏がどのような仏で、本当に救えるのか?きちんと説明できる僧侶はいないのである。このブログにあるやり取りを見れば、幼稚的な内容であり、世間というものを知らないと感じるものです。布教するのに、大御本尊について説明責任?意味わかりませんよ。血脈についても説明して、話された相手は、ちんぷんかんぷんでしょう。布教に自分自身の体験を交えて、この正しい仏法というのを話すのが布教です。車のセールスでも、営業マンがその車の事。その車の便利さ、使いやすさの説明。更に、試乗しての体験をさせて、始めて商談となるのでは?まあ、私の営業経験と、サービス業経験からして、性能やシステムを熟知してのクロージングする営業マンはいないと思います。
2013.02.26
-

本日は、支部登山でした。
昨日の夜に出発し、丑寅勤行に参加いたしました。 今日は、天気良く。素晴らしい登山でした。
2013.02.24
-
幼稚的な事たが、日蓮正宗は騙して金儲けしてるを破す。
湘南坊遺なる。坊やが日蓮正宗は、騙して金儲けしてると騒いでおる。 まあ、小生から言わせれば、金儲けが悪ならば、仕事を辞め山にでも篭れ!と言いたいとこである。 宗教は教団の金(かね)もうけにすぎないのではないか ご指摘(してき)のとおり昨今(さっこん)の宗教界の乱脈(らんみゃく)ぶりは目を覆(おお)うばかりです。ほとんどの教団は、民衆救済(きゅうさい)と社会平和の実現という宗教本来の使命を忘れ、本尊(ほんぞん)や書籍(しょせき)、守り札(ふだ)、祈祷(きとう)などを売りものにして、金儲けに専念(せんねん)している現状(げんじょう)です。 ひどい教団になると、教義がらみで信者にお金を出すよう強制(きょうせい)します。たとえば目を患(わずら)っている人に対して、「目の玉は丸いでしょう。目の因縁(いんねん)を切るために、丸いもの(お金)を供(そな)えなさい」、また足の悪い人には「足はおあし(お金)に通じるから、お金を上げればよくなります」などとまったく人をばかにしたごろ合せやこじつけで無知な人を騙(だま)しています。もっと悪質なものになると、「欲心(よくしん)があなたを不幸にしているのだから、欲心(よくしん)を棄(す)てなさい。そのためにはあなたの財産(ざいさん)を神さまに捧(ささ)げることです」などと言葉巧(たく)みに、全財産を教団にまき上げられた例もあります。 こんな宗教は明らかに金儲けを目的としたものですから、近づかないほうが無難(ぶなん)です。 では、宗教団体が資金を持つことは悪いことなのかというと、それも誤った考えです。教義を研鑽(けんさん)し、修行し、布教するためには、それを賄(まかな)う資金(しきん)がなければなりません。 仏典(ぶってん)には、菩薩(ぼさつ)の修行として貧者(ひんじゃ)に物を与える布施(ふせ)行(ぎょう)が説かれておりますし、衆生(しゅじょう)が仏や法に対して、報恩の念をもって金品を供養することを、積(しゃっ)功(く)累徳(るいとく)の行いであると賞賛(しょうさん)しています。供養とは自分にとって大切な宝を仏様に捧(ささ)げることであり、これには蔵(くら)の財(たから)・身の財・心の財の三種がありますが、大聖人は、「蔵(くら)の財(たから)よりも身の財すぐれたり。身の財より心の財第一なり」(崇峻天皇御書・御書1173頁) と仰(おお)せられ、信心という心の財を根本にすることを教えています。 「日蓮正宗の信心はまったくお金がかからないのか」という声を聞きますが、常識的に考えても、信仰するためには数珠(じゅず)や経本、仏具(ぶつぐ)、書籍(しょせき)などの費用は必要です。また御本尊に対する自発的な供養(くよう)や先祖回向(えこう)の塔婆(とうば)供養(くよう)なども、信仰者として当然なされるべきでしょう。 しかし、日蓮正宗では本山はじめ各地の末寺でも、賽銭箱(さいせんばこ)などはいっさいありませんし、他宗徒からの供養は仏の本意(ほんい)に叶(かな)わないとして、まったく受け取らないのです。また葬儀(そうぎ)、法事などにおいても、お経料とか戒名料(かいみょうりょう)もありませんし、他宗のように供養の額(がく)を定(さだ)めて請求(せいきゅう)することなどもありません。 日蓮正宗はひたすら正法を純粋(じゅんすい)に守り、弘教し、真の幸福と世界平和の確立(かくりつ)を目指(めざ)して実践(じっせん)している唯一(ゆいいつ)の宗団なのです。 (正しい宗教と信仰より) はっきり言って、日蓮正宗は、湘南坊遺なる者から、一円たりともお金は貰ってない。 また、僧侶が信者から布施を貰うのがおかしいならば、全ての仏教がおかしいとなるが?それをどう反論するのか? 現実、邪宗教の神社等で結婚したカップルが離婚した話しは多い。そういう神社等も詐欺と言うべきではないか? 日蓮正宗では、御供養は自由であるからして、信仰心から出しているのである。その御供養により、大石寺は綺麗になった。立派になった。と、毎年桜見物にくる未入信の人が言うのである。 整備をする文化財の修繕をする。これ等には、お金が、必要なのである。 小学生でも理解できる理屈であるが、何でも否定したがる者らは、こういう幼稚な事を言うのである。 では、湘南坊遺よ!架空の仏を拝ませる。真言宗や念仏等は、騙しと言わないのか?
2013.02.23
-
平安時代から鎌倉時代は、温暖期であった。
鎌倉時代は、小氷河期だから身延には、楠木は絶対存在しないと豪語してるのがいる。gooの質問で同じようなものがありました!下のURLは気候についてくわしくあります。鎌倉時代(1192-)は、古気候学の分野では中世温暖期というやや暖かい時代に属します。江戸時代は小氷期。世界的に見て、中世温暖期の最盛期は8~10世紀ぐらい。小氷期が15世紀ころからとされています。アジア地域では、これらが、いつごろから始まったか、今と比べてどの程度暖かかったか、あるいは寒かったかということについては、細かいことはわかっていません。特に中世温暖期は、世界的に十分わかったとはいえません。ですから、ご質問に即して、例えば米の作柄指数が鎌倉時代や江戸時代がいくつぐらいだったかを推定することは現在のところ無理です。ただし、歴史的な事実や科学的な分析から知られている過去の気候変動に関することがらはいくつもあります。わかりやすいところでは、ヨーロッパではブドウの収穫日、日本では観桜記録や諏訪湖の結氷記録でしょうかね。気候変動の原因についてはよくわかっていませんが、小氷期は、マウンダー極小期と呼ばれる、太陽の活動レベルが低い時期にあたっています。こうした地球外の要因とあわせて、海洋や大気、氷河、植生など地球自体にも気候を変動させる要因は沢山あります。なにか原因を決め付けてあるような記述があればそれは、眉唾ですよ。歴史と気候のはなしには興味深いエピソードがたくさんあります。参考文献のご一読をお勧めします。安田喜憲、吉野正敏(編)、講座「文明と環境」第6巻、歴史と気候、朝倉書店(ISBN 4-254-10556-8)エマニュエル・ル=ロワ=ラデュリ、気候の歴史、藤原書店(ISBN 4-89434-181-6)
2013.02.19
-
証明されている事をどうして?科学鑑定しなければならないのか?
日蓮正宗により、既に破折され尽くされているにもかかわらず。ネットで騒いでいる者が多い。破折されているに、反論不能であるから、科学鑑定と言うのであるからして、その幼稚的な答えは、負けと言えるのである。「宗門は戒壇の大御本尊をなぜ科学的鑑定しないのか? それは戒壇の大御本尊が偽作であることがばれてしまうからではないか? それが怖くて宗門では科学的鑑定ができないのだ!」 と嘯く者達は、逆に言えば「科学的な鑑定が出れば信じる。」ということであるはずである。 しかし、"科学的鑑定"と一概に言っても、研究者によって判定結果は一様ではないのである。 それでは一体、どういう立場の、どのような人間なり機関の科学鑑定を採用するというのか? その"鑑定結果"とやらはどこまで信用できるものなのか? その鑑定結果が「絶対に真正である。」などということをどう証明できるのか?・・・ という類の疑念はどこまでもつきまとうものである。 そう、彼等は、戒壇の大御本尊がニセモノだという証明以外は、信用しないのである。だから、科学鑑定というのは、逃げ向上であり、科学というものを知らないド素人がいう反論出来ない言い訳でしかない。だから、科学鑑定しろ〜という駄々っ子みたいな幼稚的姿をネットに曝すのである。今、戒壇の大御本尊へ疑難を為す者たちは、まさに斯様な、真の実力が伴わないくせに、理論だけで試合に出るような者達である。 ここまで、歴史的に文献にて証明しても信じれないのは、はっきり言って言おう!タイムマシンを造り、鎌倉時代にタイムスリップするしかあるまい。まあ、それも今の科学では、完全に不可能である。
2013.02.19
-
歴史をきちんと勉強せい!!
この増上寺は、江戸時代は上野・寛永寺と並んで徳川将軍家の菩提寺だったことで、あまりにも有名。増上寺には、徳川将軍15代のうち、6人の将軍(秀忠、家宣、家継、家重、家慶、家茂)が葬られている。もうひとつの菩提寺である寛永寺墓地には、徳川将軍15人のうち6人の将軍(家綱、綱吉、吉宗、家治、家斉、家定)が眠っている。のこる3人の将軍のうち、初代徳川家康、三代徳川家光は日光東照宮に葬られ、十五代徳川慶喜は東京谷中霊園に葬られている。増上寺の徳川将軍家霊廟は、普段は非公開。年に数回、限られた期間限定で「特別公開日」が決められ、その期間のみ、一般公開される。この徳川霊廟特別公開日には、一度、見学に行ったことがあります。http://bukkyoshugakukenkyukai.m.doorblog.jp/?guid=ONhideの日記からである。さて、歴史をきちんと勉強してるならば、徳川家光公は、日光山輪王寺である事は有名である。輪王寺(りんのうじ)は、栃木県日光市にある寺院で、天台宗の門跡寺院である。創建は奈良時代にさかのぼり、近世には徳川家の庇護を受けて繁栄を極めた。明治初年の神仏分離令によって寺院と神社が分離されてからは、東照宮、二荒山神社とあわせて「二社一寺」と称されているが、近世まではこれらを総称して「日光山」と呼ばれていた。「輪王寺」は日光山中にある寺院群の総称でもあり、堂塔は広範囲に散在している。国宝、重要文化財など多数の文化財を所有し、徳川家光を祀った大猷院霊廟や本堂である三仏堂などの古建築も多い。境内は東照宮、二荒山神社の境内とともに「日光山内」として国の史跡に指定され、「日光の社寺」として世界遺産に登録されている。(ウィキペディアより)日光東照宮を見学してるならば、日光東照宮と輪王寺は別である事は、知ってるはずである。日蓮正宗を誹謗してるわりに、歴史というものを知らなさすぎである。
2013.02.16
-
ネットに蔓延る邪義破折をまとめる。
戒壇の大御本尊と二箇相承について、詳しくここで論証をした。大御本尊については、大御本尊以外の本尊について、万年救護御本尊も鉄砲曼荼羅本尊も、日禅師授与本尊も、他現存する本尊について、何処にも御書に書かれていないのであるからして、御書に書いていないからという邪難はもう無意味である。板本尊を造る事が、大石寺独自ものとする邪難と日有上人が始めた事とする邪難について、身延久遠寺には、日向が模刻した板本尊が存在している事実。犀角独歩は、大御本尊と大きさが違うから大御本尊と無関係と言ってるが、日蓮大聖人実弟子であった日向が、独自で造ったと考えにくい。また、日向が建立した本尊を本尊と認めているのは、身延久遠寺の日蓮宗である。日蓮正宗が言ってる事ではない。また、他日蓮宗系寺院にも板本尊が存在していた事実をもって、犀角独歩の論もhideの論も、犀角独歩の真似した金原某も、湘南某もただの言い掛かりである。二箇相承について、既に大石寺から離れている。保田妙本寺(一時期日蓮正宗に帰依したが、平成になって創価学会問題後離反した古希寺院)の日我が、詳しく北山の事を記録している。また、大石寺信仰していない。徳川家康が認めているという記録が残っている。そういえば、モバゲータウンというサイトで、第三者の意見も貴重だと豪語したハゲ大先生なる者が、大御本尊は後世のものだ〜とか、二箇相承もニセモノだと吐かしておったが、ネットしか見ていないから、こういう史実を無視してネットで恥を曝す事になるのである。こういうのを出しても、反論できないから、科学鑑定だと騒いでるのが、犀角独歩である。では?どの機関の科学鑑定で、誰が判断し、どういう結果であれば納得するのか?以下は、樋田氏による科学鑑定の邪難の破折である。戒壇の大御本尊の"科学的鑑定"とやらについて▼ 「宗門は戒壇の大御本尊をなぜ科学的鑑定しないのか? それは戒壇の大御本尊が偽作であることがばれてしまうからではないか? 戒壇の大御本尊の"科学的鑑定"とやらについて▼ 「宗門は戒壇の大御本尊をなぜ科学的鑑定しないのか? それは戒壇の大御本尊が偽作であることがばれてしまうからではないか? それが怖くて宗門では科学的鑑定ができないのだ!」 と嘯く者達は、逆に言えば「科学的な鑑定が出れば信じる。」ということであるはずである。 しかし、"科学的鑑定"と一概に言っても、研究者によって判定結果は一様ではないのである。 それでは一体、どういう立場の、どのような人間なり機関の科学鑑定を採用するというのか? その"鑑定結果"とやらはどこまで信用できるものなのか? その鑑定結果が「絶対に真正である。」などということをどう証明できるのか?・・・ という類の疑念はどこまでもつきまとうものである。 こういう邪難を言い張る輩は、恐らくは、誰がどのような鑑定結果を出そうが、結局は 「やっぱり疑わしい!」と延々と難癖を吹っかけ続けるのである。 そういう人間達は結局は、「やっり戒壇の大御本尊はニセモノでした!」という"科学的検証による発表"しか素直に受け入れないのである。 では、このように問難する者達は、 "日蓮大聖人が末法の御本仏である" ということは信じているのであろうか? 日蓮大聖人が末法の御本仏であることを信じていない種類の人間達は、そもそも、戒壇の大御本尊の真偽については無関心であろう。 戒壇の大御本尊の真偽を云云する者達は、一応は日蓮大聖人が末法の本仏であることを前提としているはずである。 では、その連中に問うが、日蓮大聖人が末法の御本仏であることをどうやって検証しているのか? "科学的鑑定"はあるのか? 文献的に、あるいは歴史学的に、万人が納得できるように客観的に証明されているのか? あったら見せていただきたいものである。 ■三大秘法稟承事 弘安五年四月八日 六一歳 1595 此の三大秘法は二千余年の当初(そのかみ)、地涌千界の上首として、日蓮慥かに教主大覚世尊より口決(くけつ)せし相承(そうじょう)なり。今日蓮が所行は霊鷲山(りょうじゅせん)の稟承に介爾(けに)計りの相違なき、色も替はらぬ寿量品の事の三大事なり。 日蓮大聖人が約二千年以上前に、大地を割って涌き出でた地涌の菩薩という方々の、その一番の上首であり、釈迦如来から直に御自分一人だけに口伝相承されたその正体が、南無妙法蓮華経の文字曼荼羅御本尊である。 しかも、鎌倉時代の日蓮大聖人の御振る舞いは、この約二千年前にインドの霊鷲山という名の山頂で(というか、虚空で)口伝された内容に全く相違ない。 という、この有名な御文が真実であるということの"科学的証明"はできるのか? "証明"されたから、日蓮大聖人を信じているのか? そうではあるまい。 そもそも、法華経に説かれるこの虚空会の儀式すら、実際に起こったリアルな現実としたら、どう"科学的に証明"するのか? 「科学的に証明できなければ信じない。」とすれば、この時点で、最早、日蓮大聖人を信じる根拠はどこにもないはずである。 にもかかわらず邪妄者は何を根拠に日蓮大聖人を信じ得るのか? そもそも法華経自体が、当然であるが、釈尊の"直筆"ではないのである。 法華経が釈尊の直説である。と科学的に証明されているのか? (事実、大乗非仏説を唱える者達は阿含部以外は釈尊の直説とは認めていない。しかしこれは今は本論の論筋ではないので論及はしない)) また更に踏み込めば、「釈尊が"仏"である」ということを"科学的に立証"できるのか? そもそも"仏"という存在は科学で解明できるもののか?・・・ 結局、我々は、道理と文証、そして様々な "個人的かつ主観的な現証の積み重ね=宗教的体験" によって、仏教を、釈尊を、そして日蓮大聖人を信じているのである。 ここでいう「道理」も「文証」も、今の自然科学の研究対象では証明しきれない分野も含んでいるのである。 そういう不可思議・未知の分野も踏まえた上で、仏教を信仰しているのである。 つまり、自然科学的解明出来ない領域も踏まえた上で、鎌倉時代の実在した一僧侶である「日蓮」を「本仏・大聖人」として信じているのである。 その立場の者が、既に論証してきたように、道理・証文顕然である 「弘安二年の大御本尊」 =「本門戒壇」と銘のある「弘安二年十月十二日御建立の戒壇の大御本尊」 に関してだけは執拗に、あたかも変質者のように、 「科学鑑定せよ!」と騒ぐのは、まさに自己矛盾している。 一方で日蓮大聖人を明確な科学的証拠もなしに、いわゆる道理と文証と、人によっては、個々人の主観的経験の範疇である現証の累積によって「本仏」と信じ、 そのもう一方では、道理・文証・現証(現存する"戒壇の大御本尊"しか「本門戒壇」たるべき直筆御本尊が存在しない。)の三証顕然である「戒壇の大御本尊に対しては、 「科学鑑定して公表せよ!」 と声高に嘯くのは、全く矛盾しているではないか。 その偏向した姿勢こそが「科学的」でないのである。 一定の基準を公平・平等に運用できず、対象によって自分の都合で恣意的にまちまちの基準で対応している、その自己矛盾に全く気がつかない者達を総称して 「頭破作七分」と言うのである。 あるいは故意にそのような二重基準を使い分けているとすれば、それは悪辣で姑息な卑劣漢である。 またこれらの頭破作七分の者達の言動に乗せられて、純粋な信仰の道筋を失う者達を「信行不具足」「法門未熟」と言うのである。 このような邪難を為す者はえてして、日々の真面目な勤行・唱題・地道な折伏・寺院参詣・総本山参詣を疎かにしている者が多い。 大聖人の仏法は理論や観念だけで絶対に体得できないから、日々真面目に信仰の基本的修行に取り組んでいない者は、直ぐにこのような自己矛盾に満ちた頭破作七分の邪難に引っかかって疑念を生じ、退転してしまうのである。 例えて言えば、空手の世界で、基礎的訓練をろくにせずに、いくら流派の奥義書を朝から晩まで読んでみたところで何の力にもならない。 試合をすれば即行、秒殺である。 しかし、日々基礎的な修行を積み重ねている者が師範の指導を素直に実践し、かつまた奥義書を読むと、その知識を実際に活用できるのである。 信心の世界も同様である。 仏教とは、総じて言えば「即身成仏=凡夫が仏の境涯を開く」などという、『科学的に証明できない"現証"』を実際に体得しようとする世界であるから、本仏日蓮大聖人が定められた基本的な修行を疎かにしている者には絶対に分かり得ないのである。 今、戒壇の大御本尊へ疑難を為す者たちは、まさに斯様な、真の実力が伴わないくせに、理論だけで試合に出るような者達である。 凡夫が仏になるためには ■ 信は道の源、功徳の母と云へり。(念仏無間地獄抄 建長七年三四歳 38) ■ 夫(それ)仏道に入る根本は信をもて本とす。(法華経題目抄 文永三年一月六日 四五歳 353) という仏道の世界において、「疑い」という成仏の最大の妨げである、魔に即行・秒殺されてしまうのである。 ここでいう「信」とは妄信ではない。 あくまで道理・文証・現証の三証に依って裏付けられた厳然とした事実に対しての「信」である。 (だからといってそれは既述のごとく、現時の”自然科学的検証”で誰が検証しようと、完璧に証明しきれるものではないのである。) その成仏の要諦である、正しい三証に依って裏付けられた戒壇の大御本尊に対する「信」が生じない、過去世からの悪因縁の輩達・・・・ まずは永久に科学的に真偽を証明され得ない「経文」に照らし、自らの悪業の深さを自省してみる必要があるのではないか? それでも、まだ騒ぐのであれば、ドラえもんの世界でないが、タイムマシンを作り、鎌倉時代にタイムスリップするしかあるまい。
2013.02.15
-
紛失後の二箇の相承書
江戸時代になると、二箇の相承書のことが徳川家関係の文献に登場しています。 まず、慶長十六(一六一一・聖滅三三0)年十二月十五日、『駿府政治録』『駿国雑志』『古老茶話』によれば、家康の側近として流通経済の確立に尽力したとされる、江戸金座の頭役後藤庄三郎が、二箇の相承書を家康の面前に披露(ひろう)したことが記されています。この時、重須重宝強奪事件よりすでに三十年がたっています。『駿府政治録』によれば、 「今晩富士本門寺校割(こうわり)(引渡しの意)二ヶの相承日蓮筆後藤庄三郎御覧に備う。其の詞(ことば)に云く釈尊五十年の仏法日(白)蓮阿闍梨日興に之を附属す云々」(『諸記録』四巻三二・原漢文。括弧内筆者)とあり、続いてこれを拝した家康が、 「日蓮は爾前経を捨てなかったことはここに分明ではないか。後の末流に至って、僅(わず)かに『四十余年未顕真実』の一語を以て爾前教を棄捐(きえん)(捨てること)すべきと主張するのは、祖師(大聖人)の本意ではない(取意)」と述べたと言うことです。 また『駿国雑志』によれば、以上の家康の発言を記した後、慶長十六年十二月十日、仏法相承について家康の下問があり、時の住持日健は眼病のため、役僧養運坊が十五日駿府城に登城、後藤庄三郎が案内して家康と対面、二箇の相承書と本門寺額を進覧したところ、上に挙げた発言が家康より発せられたと、やや詳しく説明しています。 この折りに、二箇の相承書は幕府の手で筆写され、その写本を林羅山(はやしらざん)(道春)より借りて金地院崇伝(こんちいんすうでん)が日記中(本光国師日記)に記録しており、両相承書とも日辰所持本と全く同じです(「身遠山」を含めて全同。『諸記録』四巻三二)。 はたして、重須より家康に拝覧せしめた二箇の相承書は御正本か写本か。明記はなくとも、写本であればその旨書かれるはずで、家康並びに幕府側の認識では、御正本と思っていたように記録されています。『徳川実記』の同日の項にも、 「駿州富士郡本門寺の什宝宗祖日蓮の真蹟二幅。後藤庄三郎光次持参して御覧に備ふ」と、「真蹟」と記しています。そうであれば、家康の指示で重須の重宝(二箇相承を除く)が返還された天正十一(一五八一)年二月二十六日以降、この慶長十六(一六一一)年までの間に、二箇の相承書は発見され、重須に返されたとも考えられますが、そのような記録は宗門内外何れにも残されていません。ただし先の『駿府政治録』に「富士本門寺校割(こうわり)」とあれば、幕府が発見した二箇の相承書は、「校割」つまり重須側に引き渡されていたとの意で取ることは可能です。 さて、二箇の相承書を家康の台覧(たいらん)に供してから六年後、要法寺二十四代日陽が、元和(げんな)三(一六一七)年四月二十五日、重須において二箇の相承・本門寺額等を拝見、すべて御正筆であることを念記しています(『祖師伝』富要五巻六O)。 さらに妙観文庫本『興門口決(こうもんぐけつ)』には、扉の部分に、信領坊日體(にったい)(下条妙蓮寺三十九代)が、北山本門寺の御風入(かぜいれ)(虫干(むしぼ)し)の折に二箇の相承書の御真筆を拝見したことを、以下のように書き付けています。 「明治十年六月十三日北山本門寺に而(て)御風入之節御相承御直筆奉拝也 信領坊日體」*『興門口決』全十巻は、妙蓮寺二十七代日立が、宝暦元年に編した、興門の化儀・化法に関する書。 こうして二箇の相承書紛失後の行方を追っても、まことに不可解で謎に包まれたとしか言いようのない結論に至ります。しかし、以上のことを整理しつつ考え直すならば、紛失の時に当住日殿が甲州奉行に再三訴え責任をとって断食憤死(だんじきふんし)までしていることを考えれば、保田側の資料にもあるように、重須重宝強奪事件そのものが事実であったことは動かせません。 では、重須より持ち出された二箇の相承書は、果たして御正本であったのでしょうか。と言うもの、日殿が小泉より横滑(よこすべ)りした貫主であり、重須の重宝について認識が十分ではなく、写本であった可能性が考えられなくもありません。日殿等は武田兵と西山衆徒の強奪に驚き、甲府の奉行に返還を訴えることに熱中し、事件後に正本・写本を確かめる余裕が無かったかもしれず、もしそうであるならば、重須には当初から二箇の相承書は存在していたということになります。 では、なぜそれほど富士門流にとって重要な文書の存在を、明らかにできないのか。 考えられることは、身延日蓮宗等五老僧の末流にあって、二箇の相承書が現存することは、自らの門流の正当性を否定するに等しいものです。ゆえに、近代に至って身延と合同した北山本門寺として、たとえ御正本があっても公言できないという事情が考えられます。そのような重須側の姿勢を具体的に示すものとして、昭和五十七年に刊行された『本門寺並直末寺院縁起』には、天正九年の重宝強奪事件について、「日殿申状の案」等を史料として掲載しても、二箇の相承書には触れないようにしています。 あるいは御真書は重須より持ち出され、武田家滅亡とともに不明となり、その後同地を支配した徳川家の手にわたり、久能山讃明院にある可能性が、宗内で古くから語られてきました。この場合慶長十六年、家康が目にしたのは写本であったということになります。何れにしても、二箇の相承書が晴れて天下に姿を現わす日の来ることを願うばかりです。
2013.02.14
-
二箇の相承書伝承の跡
宗門史上、現在は行方不明とされている二箇の相承書ですが、古くからの文献には様々な箇所に引用され、また写本類も伝えられて、その存在をうかがい知ることができます。これについて、宗内ではいくつかの研究論文も発表されており、それらの成果をふまえた上で、二箇相承書の伝承を、ある程度確実とされる文献に絞(しぼ)った上で訪ねてみることにします。 まず二箇の相承書に触れた文献として古いものを挙げれば、重須二代学頭の三位日順師が書いた『日順阿闍梨血脈』(延元元年・一三三六・聖滅五五年後)と、同じく『摧邪立正抄(さいじゃりっしょうしょう)』(貞和(じょうわ)六年・一三五0・聖滅六九年後)があります。初めの『日順阿闍梨血脈』の方には、 「次に日興上人は是(これ)日蓮聖人の付処(ふしょ)本門所伝の導師也。禀承(ぼんじょう)五人に超え紹継(しょうけい)章安に並ぶ」(富要二巻二二)と見られます。また『摧邪立正抄』には、 「日興上人に授(さず)くる遺札(いさつ)には白蓮(びゃくれん)阿闍梨と云々」(富要二巻五○)とあります。初めの『血脈』の方だけではすぐに判らなくても、『摧邪抄』を合わせ見れば、両書が二箇の相承書を指していることに気がつきます。ちなみに『摧邪抄』にある「白蓮阿闍梨」とは日興上人の阿闍梨号ですが、宗祖御在世中にこの号を見るのは、二箇の相承書を除けば、御入滅間近の十月八日、六老僧選定の時しかありません(宗祖御遷化記録・新一八六三)。したがって「日興上人に授くる遺札」とは、二箇の相承書を指していることは明らかです。 次に、大聖人滅後一八七年のことですが、応仁(おうにん)二(一四六八)年十月十三日、京都要法寺の前身である住本寺十代日広(要法寺歴代としては十六代)が、重須寺(後の本門寺)に詣(もう)で、二箇の相承書を謹写している事実があります。この奥書に日広が、 「富士重須本門寺に於いて御正筆を以て書し奉り畢(おわん)ぬ、応仁二年十月十三日」と書いた後に、日在(要法寺十八代)が、 「私に云く先師日広富士山へ詣(もう)で玉(たま)う時此(か)くの如く直(ただち)に拝書し給う也」と、自山先師の行蹟であることを明記して伝えています。 なおこの写本をさらに大遠坊日是(亨保七年寂)が転写したものが、今日まで大石寺に所蔵されています。 要法寺ではさらに十九代広蔵院日辰が重須を訪れ、弘治(こうじ)二(一五五六)年七月七日、時の住持八代日耀(にちよう)に二箇の相承書を臨写(りんしゃ)せしめたことは、以前にも触れました(現在西山本門寺藏)。臨写とは正本(原本)を横に置いて、行数・字配り・字形に至るまで忠実に模写(もしゃ)することです。ゆえに臨写本は、大聖人が日興上人へ授けられた正本の形態をもっとも正確に伝えていると言えます。そして、日辰はこの臨写本をさらに転写した上で開版頒布(はんぷ)したということで(夏期講習録二巻9)、それが宗内で刊行された『法華経の原理一念三千法門』(小笠原慈聞著・昭和二十五年刊)巻頭に収録されています。 日亨上人もこの臨写本によって、二箇の相承書御正本(原本)の雰囲気を、いささかなりとも偲(しの)ぶに足りると評されています(興詳伝一五二)。 この臨写本の奥に、日辰は自ら由来を書き添えています。 「我(われ)日誉等と弘治二丙辰(ひのえたつ)年七月五日、駿河国富士郡重須本門寺に至る。同七日己午(つちのとうま)二刻此二ヶ御相承並本門寺額安国論等を拝閲せしめ畢(おわん)ぬ。後証の為住持日耀(にちよう)上人をして之を写さしめ、以て隨身上洛に備える。時に同月廿二日也 弘治三丁巳(ひのとみ)八月朔日(ついたち) 日辰(花押)」(原漢文) 以後、話しを進めていくなかで、この臨写本を仮に「日辰所持本」としておきます。 これまで、日蓮正宗で編纂(へんさん)されてきた御書全集が数種類ありますが、日亨上人が編纂された従来のもの、現在刊行されている『平成新編御書』、さらに『昭和新定御書』『平成改定御書』の何れについても、二箇の相承書は日辰所持本と大差のない内容であることが判ります。すなわち、成立の由来も明らかな日辰所持本は、かなりの信頼性をもって扱われてきたと言えます。 二箇の相承書写本の中でも、たとえば日有上人の晩年、尊門より大石寺に帰依した左京日教の著した『類聚翰集私(るいじゅかんしゅうし)』と『六人立義破立抄私記(りゅうぎはりゅうしょうしき)』中に、二箇の相承書が引用され、日付が『身延山付嘱書』を九月十三日とし、『一期弘法抄』は十月十三日と、日辰所持本とほぼ逆転して写されています(これと同様、逆転した日付となっているものに、他門本成寺日現の『五人所破抄斥』がある)。しかし以上の例は正本を見るのが不可能な状況における誤りと思われ、これ等の写本が存在しても、日辰所持本の正確さを揺るがすものではありません。 また日付について、前項に紹介した日顕上人御教示に基づいても、神力品に準(なぞら)える『一期弘法付嘱書』が先となり、嘱累品に準える『身延山付嘱書』が後に来てこそ、理(り)に称(かな)っていると言えます。 日辰所持本で一点問題となるのは、『身延山付嘱書』の文中、「身遠山久遠寺別当」とある箇所です。つまり本来なら「身延山久遠寺別当」でなくてはならないということです。 これについて、大聖人の御正本に「遠」となっていたのか、あるいは日耀が模写(もしゃ)する際に間違えたのか、その他の可能性も考えられますが、模写の際に日辰以外の者が拝見していたという由来書きがあること、さらに日辰は三年後の永禄(えいろく)二(一五五九)年一月十二日にも再度御正本を拝見しているので、模写の誤りというより、御真書そのものが「遠」となっていたと見る方が自然です。 こう考えるもう一つの裏付けとして、大石寺に所蔵されてきた第十四世日主上人の写本にも、「身遠山」となっていることを考慮しておく必要があります。 大石寺に蔵されている二箇の相承書として、現在最古の写本は日主上人のものです。同上人が御法主に就(つ)かれていた期間は、天正(てんしょう)元(一五七三)年より慶長(けいちょう)元(一五九六)年の間です。すなわち日主上人は、重須重宝強奪事件(天正九年)の最中に大石寺御法主に就かれていたのであり(重須の事件に大石寺はもちろん無関係)、その御登座期間における相承書筆写について、富士年表では一応「天正年間」としています。問題は、日主上人が果たして二箇の相承書を写されるに当たり、その元本としたのは何(いず)れであったかということです。 日主上人の頃、大石寺は重須と親交があったようには思われず、日主上人が、日辰のように重須に出向いて二箇の相承書を写されたとは考えにくい状況です。もちろん、二箇の相承書御正本が重須にあったことを前提とした論考です。 いわゆる、日目上人が晩年おられたのが大石寺であるゆえに、日目上人への付嘱の書である『日興跡条々事(にっこうあとじょうじょうのこと)』御正本が、大石寺に所蔵されてきたのと同様、二箇の相承書の御正本は日興上人が生前ずっと所持され、御遷化を迎えた重須に蔵されてきたと考えるのが自然です。とは言え、大石寺にはそれまで、二箇の相承書の写本が全く伝えられていなかったとは考えられず、日目上人への付嘱を内々に定められていた日興上人であれば、御存生の時代における古写本(現在は伝わらないが)はすでに大石寺日目上人の許(もと)に存し、日主上人はそれをもって写されたのではないかと推考するものです。 ちなみに日辰所持本と日主上人写本(『諸記録』掲載の写真による)を比べてみると、『一期弘法抄』は字配(くば)りや字形等ほぼ同一で、最後の「日蓮在御判」「血脈次第 日蓮日興」の二箇所に違いが見られるだけですが、『身延山付嘱書』については文字数、字配り、行数までが異なり、それぞれ写した時の元本は別々のものであったことは明らかです。 しかし、先述した通り『身延山付嘱書』の「身遠山」とある箇所は双方同じであることから、御正本がそのようになっていたという可能性はいっそう高まります。
2013.02.14
-
二箇の相承書の意義
妙教 2004年2月(第136号) 大石寺と北山本門寺の歴史・第十五話 二箇の相承書の意義 二箇の相承書とは、『日蓮一期弘法付嘱書(いちごぐほうふぞくしょ)』と『身延山付嘱書』の二通の付嘱書のことです。日蓮大聖人が御入滅を間際にした時期に、御生涯をかけて開示・弘通された三大秘法の仏法の一切を、一門の棟梁(とうりょう)と定めた日興上人に付嘱され、広宣流布に向けての前進を遺命されたものです。 以下にこの二書を掲げます。 『日蓮一期弘法付嘱書』 日蓮一期(いちご)の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す、本門弘通の大導師たるべきなり。国主此(こ)の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と謂(い)ふは是なり。就中(なかんずく)我が門弟等此の状を守るべきなり。 弘安五年壬午(みずのえうま)九月 日 日蓮花押 血脈の次第 日蓮日興 『身延山付嘱書』 釈尊五十年の説法、白蓮阿闍梨日興に相承す。身延山久遠寺の別当(べっとう)たるべきなり。背(そむ)く在家出家共の輩(やから)は非法の衆たるべきなり。 弘安五年壬午十月十三日 武州池上 日蓮花押 初めに挙げた『一期弘法付嘱書』は、日蓮大聖人が御入滅を前にした時期、弘安五年九月八日に身延山を発(た)たれますが、その前後にしたためられたものとされています。 「日蓮一期の弘法」とは、御生涯をかけて弘通された三大秘法の仏法、すなわち極(きわ)まるところ本門戒壇の大御本尊のことで、さらに大御本尊に具わる化儀化法の一切が日興上人に付嘱されたことを明らかにされています。その日興上人のお立場を「本門弘通の大導師」と定められ、御入滅後の一門の棟梁として、三大秘法の弘通を命じられています。 さらに、この弘通を進めていく中で、国主が帰依(きえ)をして広宣流布の様相が現われたならば、富士山に本門寺の戒壇を建立せよとの御遺命(ゆいめい)を示され、それまでは折伏弘通をしつつ時を待つべきである。「事の戒法」、すなわち本因下種仏法における戒法(受持即持戒を旨とする)とは、富士山に本門寺の戒壇を建立することであり、我が門弟・僧俗はこの状を守らなくてはならないと結ばれています。 日付の後に、唯授一人の血脈の次第として、大聖人より日興上人へ付嘱されたことを改めて示されています。 御当代日顕上人は、『一期弘法付嘱書』の付嘱を、法華経における神力品(じんりきほん)別付嘱の意義に準(なぞら)え、また次に掲げた『身延山付嘱書』にある「釈尊五十年の説法」の付嘱は、嘱累品(ぞくるいほん)総付嘱の意義に準えて、説示されています。 *「地涌の菩薩は神力品において結要付嘱を受け、さらに嘱累品において釈尊一代仏教のすべてを付嘱され、その内容をお持ちでありますから、その結要付嘱の意味においては『日蓮一期の弘法』という意味が示され、さらにまた嘱累品の釈尊仏法全体の上からは『釈尊五十年の説法』をお持ちなのであり、その上に『日興に之を付嘱す」と仰せになっておると拝せられる」(『大日蓮』平成一二・七P49) 次に『身延山付嘱書』については、御入滅の日である弘安五年十月十三日、武州池上右衛門大夫邸において、重ねて日興上人への付嘱を明らかにされたものです。「釈尊五十年の説法」を日興上人に相承される文に続き、日興上人を身延山久遠寺の別当に任じられ、一門の在家・出家において日興上人へ信順なき者は非法の衆であると、誡(いまし)められています。 この付嘱書について、「釈尊五十年の説法」すなわち釈尊の一代仏教を、日興上人に相承するとある箇所について、古来疑義を出す者がありますが、日顕上人は上に触れたように、「釈尊五十年の説法」とは、釈尊仏法の総付嘱の意味に同ずると示されています。さらには、日蓮大聖人の一期の弘法により、釈尊の一代仏教はその中に開会(かいえ)され、三大秘法を弘通する上の流通分(るつうぶん)の用(はたら)きをなす旨も、教示されています。 *「大聖人様が御出現になって、『内証の寿量品』の本義たる久遠元初証得の妙法蓮華経を弘宣あそばされると、一切の序分(釈尊の一代仏教を指す)はことごとくそこに入っておるわけですから、今度は序分の一切がそっくり、この妙法を弘通するための流通分となるのです。したがって、序分の一切は妙法蓮華経の体の内に納まって開会されたのであります。 要するに、釈尊一代五十年の説法は、この文底下種の妙法である三大秘法を広宣流布するための分々の助けとして流通を成ずるのであります」(『大日蓮』平成一三・三P64。括弧内筆者) すなわち、『一期弘法付嘱書』と『身延山付嘱書』の両抄は、二書がそろってこそ総別の付嘱が調(ととの)い、正しい意義が顕われるということです。 封建時代に家督(かとく)を相続するのに、惣領(そうりょう)だけではなく庶子(しょし)にまで分割(ぶんかつ)して相続した者は「田分(たわ)け者」と言われ、愚(おろ)か者の代名詞となりました。所領が一族の命綱(いのちづな)であった時代に、分割相続をすることは、一家・一族の力を衰(おとろ)えさせることになるので批判されたのです。 封建時代に家督(かとく)を相続するのに、惣領(そうりょう)だけではなく庶子(しょし)にまで分割(ぶんかつ)して相続した者は「田分(たわ)け者」と言われ、愚(おろ)か者の代名詞となりました。所領が一族の命綱(いのちづな)であった時代に、分割相続をすることは、一家・一族の力を衰(おとろ)えさせることになるので批判されたのです。 仏法の付嘱も同様であり、釈尊は迦葉(かしょう)に付し、天台は章安(しょうあん)へ、伝教は義真(ぎしん)へと、何れもただ一人に付嘱されたのであり、日蓮大聖人が六老僧に分割乃至平等に付嘱するなどということは有り得ないことです。
2013.02.13
-
『二箇相承』の行方は?
昨日の続きです。 『二箇相承』の行方は? 重須日殿憤死の後間もなく、武田一門は甲州に押し寄せた織田・徳川連合軍に天目山で包囲され、天正十年三月十一日に滅亡しました。この戦乱の中に、甲府に運ばれた重須重宝も行方不明となり、存在さえ危(あや)ぶまれる事態となったのですが、重須も西山も、これの探索追跡に血眼(ちまなこ)で当たったことは想像に難くありません。 そして重宝の一部は間もなく甲府で見つかったようで、家康の重臣本多作左衛門(さくざえもん)重次(鬼作左(おにさくざ)の異名がある)の差配するところとなりました。これの獲得をめぐって、重須と西山は必死の働き掛けを行ったことが、「日春甲府惣旦方宛(そうだんほうあて)書状」(天正十年十月十五日西山文書・蓮華第三号・以下「日春状」と略称)及び「本多作左衛門状」(天正十年十月二十八日・富要八巻一七四・以下「本作状」と略称)との二文書より知られます。 「日春状」では、日春が首尾よく作左衛門に働きかけ、五百両もの高額な買い取り金を示して、十月七日に重宝を獲得したことを、甲府にいる有力な惣檀方(そうだんほう)(檀徒の中心者)に対して知らせた内容です。続く文面では、重須側でも、西山提示の額以上を出しても重宝を取り戻そうとしていたことに触れ、西山へ渡されることが決まった事に重須は無念がり、御会式の場では喧嘩口論も飛びだしたと聞いたことなどを伝えています。ところがこの度見つかった宝物には、「二箇相承」・「額」・「八通之遺状」の三点の重宝は含まれてなかったので、作左衛門よりはこの三点について、引き続き厳重な探索を続けるとの堅い約束を取り付けたとも述べています。そして西山としては、この三点を得るのが目的であるが、他の文書が出ればそれも一緒に受け取るようにとの作左衛門の意向ゆえに、三点を確実に獲得するためにも、他の文書も受け取るつもりであると述べています。 この書状で日春が指摘した三点のうち、「二箇相承」は周知のごとくです。「額」とは重須に伝わる「本門寺根源額」のことで、大聖人が遺命された本門寺の戒壇が建立された暁(あかつき)に懸けるために、日興上人に授与された宗祖直筆の額ということですが、実物が今日に伝わらず、真偽を論ずる事さえ不可能です。そして「八通之遺状」については、西山の祖日代が日興上人より付嘱があったことを証する、日興上人直筆といわれる八通の文書のことですが、これも時代写しさえ今日に伝わっていません。以前にも触れたように、八通のほとんどは北山と対峙(たいじ)する西山が、日代の正統を証する目的で、この時代より相当以前に作り出した偽文書と見られています。 ただ、これほど西山で大事にしてきた「八通之遺状」を、西山歴代を嗣いだ日春が、重須の重宝の中にあると考えていたこと自体、不可解なことです。 この文書については、重須日殿が甲府の奉行所に申状案文にも「西山八通に置状」と書いているので、明らかに「西山に所蔵されてきた八通の遺状」(真偽はともかくとして)というのが、この一連の文書に対する当時の一般的な認識であったはずですが、日春が二箇の相承書など重須の重宝とともに、手に入れたいと書状に書いたことについて、これをどのように解釈すればよいのでしょう。日春は西山の貫主となったものの、自山にある宝物の内容さえ知らなかったのか、あるいは自山に八通之遺状の原本が無いので、日代が重須に残してきたと思い込み、それをこの機会に手に入れたいと考えたのでしょうか。何れにしても日春に垣間(かいま)見られる態度には、重須との闘争に脳裡を奪われる一方、重大な認識不足を露呈する、一山の貫主らしからぬ姿勢も見えてくるようです。 さて、日春の書状より十三日ほど遅れて書かれた「本作状」についてですが、本多作左衛門は西山びいきであったようです。西山日春より、黄金五百両を出して重宝を受け取りたいと申し出た件について、作左衛門は「五百両はいらぬ。これらの重宝はすべては新たに西山に寄進するものである」との意向を、日春に伝えた文面です。 作左衛門のこの申し出に対して、喜んだ日春は請書(うけしょ)を用意しました。その案(下書)が残されています(「日春請文の案」富要八巻一七四)が、この内容には、この時見つかった重宝の数が「日蓮御自筆物数合わせて六拾六」とあり、そのうちに御本尊が八幅含まれていたということです。また作左衛門が気前よくすべてを寄進しようと申し出たことについて、これを深謝する意も述べられています。 *宗祖御自筆の書六十六点とは、実際は宗祖御真筆だけではなく、宝物全体を合わせて六十六点あったということであろう。 このような経過をたどって、一度は日春の思い通りに事は運び、重宝六十六点は天正十年十月七日、西山に確かに寄進されたのです。ところが、肝心の作左衛門の主君徳川家康は、これより数ヶ月さかのぼる同年二月、甲州攻めの途上、重須近くの小野沢村に宿営、重須日出は挨拶に出向き、家康の庇護(ひご)を受けるほどの良好な関係を結んでいました。 重須では十代日殿憤死後、前貫主であった老僧日出が、やむなく再び貫主に就いていました。その日出が家康の宿営を訪れた時の様子が、重須に伝えられています(日出記)。 家康は日出に対して、法名と年齢を尋ねました。そして、日出という旭日を意味する法名と、米寿(べいじゅ)に達するという年齢を聞き、征討軍出立に際してこれは吉兆(きっちょう)であると、日出に会ったことを喜びました。さらに大久保新十郎忠隣(ただちか)を遣わし、武運長久の祈祷を願い、これに応えて日出は、宗祖漫荼羅本尊(建治二年二月)を授けたのです。 その後、家康一行は武田を滅ぼして帰る道すがら、五月十日に再び当地を訪れ、日出に会って漫荼羅を返還。漫荼羅御本尊の法威(ほうい)により無事帰還できたことを謝した上で、褒美(ほうび)として朱印状の交付と、本門寺堀後に称される用水路の開削(かいさく)を約束しました。 日出が授けた宗祖漫荼羅御本尊については、戦場で家康に向けられた銃弾が、替わりに漫荼羅の花押部分に当たり、家康の一命が助けられたということから、「鉄砲漫荼羅」の呼び名で本門寺の寺宝とされてきました。本門寺堀については、命を受けた井出甚之助正次によってただちに工が起こされ、間もなく完成を見たようです(富要八巻一五九)。 このような重須側の動きは、本多作左衛門が贔屓(ひいき)にした西山側の働きかけを凌(しの)ぐものでした。すなわち重須日出が家康と昵懇(じっこん)になったことで、甲府に運ばれたまま行方不明になった重宝の探索と返還について、日出が家康に懇願(こんがん)したことは間違いありません。 重須の寺伝によれば、ひとたび西山に納められた重宝は、それよりわずか数ヶ月後の天正十一(一五八三)年二月二十六日、家康の命によって取り上げられ、本多弥八郎の手で重須に返還されています。その時の重宝目録として、 宗祖御真筆漫荼羅大小十一幅、日興上人御真筆漫荼羅大小三十九幅、日興上人御真筆聖教、日興上人御真筆日澄師への遺状一通、日代筆五人立義抄一巻、日源筆安国論二巻、大聖人御珠数一連、日興上人御真筆開目抄要文三巻、日興上人御真筆内外要文二巻」(富要九巻二一) 以上のように記録されています。ここにはほぼ六十点以上を数えることができ、日春が用意した請書(先出)の六十六点と数の上ではほぼ合致するようです。もちろん二箇の相承書はこの中に見られません。同書に続いて、 「右は東照神宮様より本田((ママ))弥八郎殿、西山を闕所(けっしょ)(没収の意)に仰せ付けられ候て御取戻し下され候、本田弥八郎殿、西山より当山へ御持参誠に以て東照神君様の御政徳を以て当山永く仏法護持の霊地に罷(まか)り成り候、後生忘失有るべからざる事、天正十一年未(ひつじ)二月二十六日」と、重宝が西山より重須に返されてきた事を、喜びを交えて記しています。しかし文中「東照神宮」とは家康没後の呼び名で、史料としては後世に成ったものということが判りますが、重宝の内容と、それらが重須におさめられた経緯はほぼうかがえます。ここにある本田弥八郎とは本多正信(まさのぶ)のことで、家康の側近ですが作左衛門重次とは別人です。 同書には続いて、「平岡岡右衛門殿より御帰(かえ)し成され候覚」(富要九巻二二)として、宗祖御真筆の法華経や『貞観政要(じょうがんせいよう)』など数点が挙げられていますが、これらは先に列挙した重宝とは別に発見されたものだったようで、それが重須に納められた記録と思われます。 先に挙げた「妙本寺古記」には、甲州商人岡田宇賀右衛門が戦火の中、御大事箱を駿河に持ち出したことが記されていましたが、「平岡岡右衛門」と「妙本寺古記」の「岡田宇賀右衛門」とはやや似た名前でもあり、どちらかの史料の誤記による違いで、実際は同一人物と思われます。 そして、「妙本寺古記」に見られる、駿府城における西山日春と重須日健(日出を嗣いで重須十一代貫首となる)等の対決について、この時の家康の裁定によって、天正十一(一五八三)年二月二十六日、重宝は重須へ返還され、二箇の相承書はなお行方不明のままでしたが、事件は一往の結末に至ったのです。
2013.02.11
-
二箇の相承紛失の顛末(てんまつ)
相変わらず。湘南某は、歴史を全く調べもしないで、二箇相承は無かったと主張してるが?さて、犀角独歩なる習ひそこないの学者もそうだが、きちんと歴史を調べているのであろうか?妙教 2004年1月(第135号) 大石寺と北山本門寺の歴史・第十四話 二箇の相承紛失の顛末(てんまつ) 永禄五(一五六二)年、上行院日春の仲介により、重須本門寺と西山本門寺の和融(わゆう)が成りましたが、この状態は長くは続かず、これよりおよそ二十年後の天正(てんしょう)九(一五八一)年には重須重宝強奪(ごうだつ)という歴史的な事件が起きて、両山の関係は一挙に対立の時代へと進みます。 しかもこの事件の首謀者(しゅぼうしゃ)が、重須・西山和融の仲介を執(と)った日春であったということでも、この事件の特異性がうかがえます。この時、日春は西山本門寺十三代を嗣(つ)いでいました。そして事件の起きた天正九年は、日蓮大聖人の第三百御遠忌の年に当たっていて、不思議な時の巡り合わせも感じられるのです。 事件の概要(がいよう)は、「二箇の相承紛失の由来」として、保田日我が手記のようにして残しています(富要九巻二二)。 本抄冒頭(ぼうとう)には、「二箇の相承紛失の由来を後代存知の為に之を記す」とありますが、日我は重須・西山いずれの関係者でもなく、第三者的な立場と一往は言えます。しかし、もともとが重須日殿の師であり、事件の顛末(てんまつ)は重須の関係者より詳しく聞いていたであろうことは当然で、事件のあらましを知るための、同時代の史料でもあるこの由来記は、一定の信憑性(しんぴょうせい)を持つ内容です。以下に意訳して紹介します。 「駿河の国(現静岡県)は永い間今川氏の分国であったが、甲斐(かい)の国主武田信玄が永禄十一(一五六八)年十二月に駿府(すんぷ)に討ち入ってから、駿河一国が信玄・勝頼二代にわたり、十五年間支配されることになった。その十四年目に当たる天正九(一五八一)年三月、西山日春という大悪僧が起こした事件である。 日春は年来様々な邪義を構えて重須本門寺に干渉していたが、思うようにいかなかった。そこで、甲州に有徳の檀那(信徒)があったので、この者を通じて巧言令色賄賂(こうげんれいしょくわいろ)を先として国主に取り入り奉行に訴え、北山本門寺の重宝、とりわけ二箇の相承を奪取(だっしゅ)する謀(はかりごと)を企(くわだ)てた。国主勝頼側もこれを受け入れたのである。 そこで百人ばかりの人数を日春に指し添え、一団を北山本門寺に向けた。日春は門前で待ち、他の俗衆数多(あまた)を中に入らせ、『甲州武田殿の使いである。身延山の重宝本尊がこの度失われたというので、分国中の諸寺を調べているが、当寺の御大事箱を直接拝見したい』と呼ばわった。 時の住持日殿は、『当山には全く左様なものはない』と答えたものの、使者は簡単には引き下がらない。『是非とも詳しく調べる必要がある』とさらに威圧すれば、日殿は臆病でその場の工夫も思いつかぬ人物である。それではとおびえながら座を起(た)ち、御大事箱を開けて、中の重宝一つひとつを見せていった。すると使者は『この箱は急いで蓋(ふた)を閉め封をせよ。こちらの箱も封をせよ』と命じた。驚いてどうしてかと問う日殿に、使者は『西山日春の訴えがあり、御奉行様が詳しく調べた上で是非の判決がされるであろう。今はすぐに甲府へ運ばなくてはならぬ』と答えるや、すぐに押し取り持ち去ってしまった。その間、住職も北山衆徒も力及ばず、なるように任せざるを得なかった。 こうして甲府へ運ばれた御大事箱は、領主の館にある毘沙門堂(びしゃもんどう)と呼ばれる持仏堂に納められた。翌年三月十一日、織田信長が甲州に討ち入って、勝頼父子をはじめ武田一族宿老眷属(けんぞく)は悉(ことごと)く滅亡し、武田冠者(かじゃ)義清以来五百年続いた国は跡形も無く亡んでしまった。悪人の訴えによって悪行を極めたゆえに蒙(こうむ)った現罰である。ある経に、『仏教を破れば亦孝子無く六親和せず云々』と説かれる如くに、堕地獄は疑い無い」 日我はこのように記した後、末尾に、 「其日(そのひ)の乱入に彼の二箇の御相承並に大聖開山御筆の漫荼羅三四十幅濫妨(らんぼう)に取られたるか、何所(いずこ)に御座候とも誰人の所持なりとも大聖開山の御血脈相承富士門家の明鏡たるべし後世此旨(このむね)を存ずべき者なり、仍(よつ)て之(これ)を記す日長、日正、日堤、日侃(にちかん)、日我」(富要九巻二二)と結んでいます。 日我にしてみれば、侘(わ)びをいれてきたとはいえ、自分に背いて重須貫主に就いた兵部卿(ひょうぶきょう)日義こと日殿に降りかかった事件であったゆえに、日殿を責める気持ちも多分にあったでしょう。しかしそれより、西山日春の謀(はかりごと)から二箇の相承書が失われるという結果を招いた事態の、日興門流全体にかかわる不祥事の張本人として、日春を「大悪僧」と非難する気持ちの方が勝れて、この記録を残したことがうかがえます。 さて、保田には日我の残した「紛失の由来」とは別に、「妙本寺古記」(富要九巻二四)が残されていますが、こちらは同時代ではなく、やや遅れて書かれた史料のようです。「一、重須と西山と御大事等本門寺諍(あらそ)ひの事」との文から始まる部分が『富士宗学要集』に納められ、日我の記からは知られない内容も含まれています。 この文書では、北山に押し寄せたのは増山権右衛門(ますやまごんうえもん)(甲斐武田氏家臣)と西山衆とあり、御尊形(ごそんぎょう)(御影像の意か)を荒縄にくくりつけ、直接西山に持ち去ろうとしたものの、途中で河東代官鷹野因幡守(たかのいなばのかみ)、興国寺城代曽祢下野守(そねしもつけのかみ)等の妨げがあり、その結果として富士門徒の手から離れて甲州に持ち去られたとしています。 同記にはその後の日殿の動きも記され、この部分が日我の記に見られない内容です。すなわち重須日殿が(天正九年)三月上旬より十月中旬まで甲府に滞在、武田家の近習小路中河与三兵衛(こうじなかがわよさべえ)宅に宿して、重宝の返還を求めていたが徒労に終わり、翌年二月五日、日殿が他界するに到ったのは是非も無い次第である(後述するように、日殿は責任を負って、断食の上自ら命を絶ったのである)。しかし同月十八日に兵乱が起こり、織田・徳川軍等が甲斐を責めて勝頼の武田氏は三月に滅亡、西山に荷担(かたん)した大竜寺・小山田備中守(おやまだびっちゅうのかみ)も滅亡、「その時御大事紛失せり」とあります。 同記には続いて、甲州商人岡田宇賀右衛門(おかだうがえもん)という者が、戦乱の中に御大事の過半を警固して駿河に運び出していたので、後に、御大事箱が重須・西山のどちらに帰属するかで問題となった。すなわち北山の住持日健及び檀那井出甚助(甚之助の誤りか)等と、西山日春との間で駿府城家康の前で対決、家康は公平な立場から、往古より三百年来重須で散逸(さんいつ)無く護ってきた重宝であれば、重須に返すべきであると裁断したので、西山日春には面目無い結果となった。日春は西山から擯出(ひんずい)すべき重罪である。八通の遺書と二箇の相承書はいまだに発見されてない。興門廃失の悪鬼入其身(あっきにゅうごしん)は彼の日春に相違ないと結んでいます。 以上二通の文書が、天正九年の事件のあらましを記した保田側の記録です(別に「久遠寺の古状」があるが、事実関係は上の二書と変わりない)。これに北山の記録等を合わせることで、さらに事件の詳細は明らかになるはずです。すなわち重須には、日殿等が作った重宝返還を訴える申状の案文が三通伝えられ(富要九巻一六)、これらは日殿の甲府滞在期間中、武田氏奉行への訴えの為に作られた写しと思われます(三通すべてが奉行に上呈されたかは不明)。 三通の日付を見れば、事件直後の天正九年三月二十八日、次に同六月十三日で、訴える目的は重宝返還の件で変わりはないものの、重須を退出した日代の非を強調したり、奪われた本尊類と日妙との関係を強調するなど、内容を変えながら訴えようとした苦心もみられます。 三通から知られる内容として、西山日春の虚言を受けた甲州奉行は、増山権右衛門と興国寺奉行衆を重須に遣わしてきたこと、そして彼らは御朱印(国主の印判)を持って来たので、重須としては是非に及ばず重宝を渡さざるを得なかったという事実が先ず挙げられています。 次いで、そもそもこの度重須から持ち去られた重宝類は、かつて重須より擯出(ひんずい)された日代が、日興上人より譲られていたものであるから、西山に移されるのが当然であるという、西山側の主張にそってなされた事件であったことが判ります。日代頻出は遙(はる)か二五O年前のことですが、それでも今さらながらに蒸し返される両山対立の根深さがうかがえます。 これに対して重須側では、日興上人が重須寺を日代に譲ったということは、西山八通の遺状にも書かれてないし、二箇の相承書なども、日代に授与されたものではないから、この度の重宝運び出しは不当であると訴えています。 さらに、持ち去られた御本尊類については、日興上人より日妙(日代擯出後重須寺の主職に就いた)に対して、本門寺が相伝されたことを証する宗祖御本尊が含まれていることや、また日妙への唯授一人の付嘱、さらに日妙の三堂本尊守護を命じたことを証する本尊が含まれていることを挙げて、早く返して欲しいとの旨が述べられています。 史実が明かな今日より見れば、日妙については、日興上人より付嘱を受けるほどの立場に当時なかったのは明白で、門流の事情を知らない奉行に対して、重須が出任(でまか)せに盛り込んだ内容であることは判ります。ともあれ重須日殿は、それほど必死に訴えていったのです。 重須の所伝では、日殿その外七名が、天正九年三月二十七日より甲府に詰め返還を訴えたがうまくいかず、次いで六月十三日より極月(ごくげつ)(十二月)に到るまでさらなる訴訟に及んだものの効果なく、むしろ旅宿を破却されるなどの迫害を受け、やむなく帰山せざるを得なっかたというのです。 この史料を「妙本寺の古記」と比べると、甲府滞在期間などにやや相違がある。 日殿は翌天正十年正月朔日(ついたち)より生御影の宝前に閉じこもり、重宝還住の祈願をしつつ断食し、ついに二月六日に憤死(ふんし)したと伝えられています(『本宗史綱』三九六に「重須文書」を出典に記している)。 続く
2013.02.10
-
妙とは蘇生の義なり
正林寺御住職指導(H24.5月 第100号) 日蓮大聖人は『法華題目抄』に、 「妙とは蘇生の義なり。蘇生と申すはよみがへる義なり。(中略)妙の一字を持ちぬれば、いれる仏種も還りて生ずるが如し。」(御書360) と仰せです。御本尊に疑いのない素直な気持ちで一念を込めた真剣な題目を唱えれば蘇生され境界が開かれるとの御言葉です。 日蓮正宗の法華講に入られて「妙とは蘇生の義なり」との実体験をされた講員さんは大白法など日蓮正宗機関誌の体験談で確認ができます。その体験は御本尊からの有難い功徳であり真剣に祈った果報です。 また「妙とは蘇生の義なり」とは身口意の三業にわたり信心を実践された結果でもあります。もし、祈っても蘇生されない場合、御本尊への祈りが本当に真剣か、怠慢はないか、自らの信心に十四誹謗を犯していないかどうかをひとつ一つ省みる必要があります。 末法においては、まったく無益な爾前権教の死の法門も、末法の大白法である妙法に照され会入された上からは、活の法門としてよみがえるとされます。 毒気が深く入り本心を失い、ながい過去の世から邪宗邪義にまどわされてきた末法の衆生も、どんな極悪人でも、ひとたびこの妙法を信じて受持すれば、いかなる罪障も朝露のように消滅して、尊極無上の仏果をうることができます。 悪が善に、迷いの凡夫が仏に成ることを蘇生といい、その道は唯一、妙法受持以外にありません。反対に、妙法を信じない人々は、どれほどきれいな衣装で外見を飾り、気持ちを一新したとしても、それは一時的な薬の効果に過ぎず真の蘇生にはなりません。結局もとの六道輪廻という迷いの世界で悩み苦しみます。日々真面目に積み重ねられた妙法受持への疑いのない確信と信行にこそ蘇生の義が存し絶対的幸福があります。
2013.02.10
-
九思一言~口は災いの元~
愛媛県西条市 日蓮正宗 一心寺 長谷御住職著 大聖人は、口は災いの元であり、「九思一言」と仰せです。 すなわち、よく考えた上で言葉を選ぶ大切さを御指南です。 『中庸』という書物にも、 「言(こと)は行ないを顧み、行ないは言を顧みる」 とあります。 言葉を発する場合には、その言葉が日常の振舞に不一致ではないかどうか反省することが大切であり、 また自分の振舞等が普段のことばと矛盾していないか反省することの大切さを教えています。 人は得てして、知っていることを全て述べて知識をさらけ出す傾向がありますが、そうではなく、謙虚になり慎重に事を運ぶようにすることが大切です。自身の聡明さを求めるのではなく、深みを求める姿勢をとりたいものです。 本当、最近、熟熟思います。。。 人間は完璧且つ万能な生き物ではないので ちょっとした事がキッカケで、信頼関係が脆くも崩れさり、 人間関係や、その人々の人生や人格までも、良くも悪くも変化してしまうのだなぁと。。。 特に『人の口には戸は立てられない』との言葉とおり、 割れた皿を修復し復元するのが難儀であるが如く 本当永遠のテーマではあるなと思います。。。 常に平常心を保ち、九思一言を心掛けたい次第であります。。。
2013.02.09
-
戸田家は、現在創価学会とは無関係。。
今週発売の週刊新潮2月14日号にて、戸田城聖氏の長男が亡くなった事を報じている。その長男は、日蓮正宗の寺院。池袋の常在寺の僧侶により、通夜と告別式が執り行われた。戸田城聖氏は、創価学会二代会長であり、日蓮正宗を信じて大折伏をしてきた。戸田会長のお墓は、五重塔の脇に、天英院の墓と共にある。その戸田会長の奥様たる幾さんも、日蓮正宗常在寺にて葬儀が行われている。つまり、戸田家は、創価学会なく日蓮正宗法華講なのです。でも、今の学会員はそれも知らないのです。
2013.02.08
-
お塔開き(総本山五重塔)
正林寺御住職指導(H22.2月 第73号) 毎年2月16日、総本山大石寺におきまして日蓮大聖人の御誕生会には、五重塔のお塔開きが行われております。 五重塔は寛延2(1749)年に、第31世日因上人の代に建立されました。 堂宇内部には、日因上人が寛延2年2月3日に認められた常住御本尊が奉安されております。また、昭和41年6月11日には、国の重要文化財に指定されました。規模は、三間半(6.4メートル)四面、高さは34.3メートルで、土台から上部まで大木が貫通しており、この五重塔の大きさは東海道随一です。 塔の起源は、釈尊滅後に弟子などが仏の舎利(骨)を安置するために建立したのが始まりです。塔には、仏に対する報恩と信仰の象徴という意義があります。本宗の塔が五重であるのは、大聖人が『阿仏房御書』に、 「妙法蓮華経より外に宝塔なきなり。法華経の題目宝塔なり、宝塔又南無妙法蓮華経なり」(御書792) と仰せのように、宝塔を妙法蓮華経の五字と解釈するためです。五重塔は、総本山第26世日寛上人が享保11(1726)年6月に、徳川幕府第6代将軍家宣公の妻である天英院と共に、起塔の志を立てられ、資金を残されたのが始まりです。 寺院の建物は、本来、南向きに建立されていますが、五重塔は西向きに建てられています。大聖人が『諌暁八幡抄』に説かれるように、インドから中国、朝鮮、日本へと東に向かって伝えられてきた釈尊の仏法が力を失い、大聖人の真実の仏法が、日本から朝鮮、そして中国からインドへと西に向かい、さらに全世界へ流布するという教えに基づくものです。 私たちは、この大聖人の御教示を拝して、御法主上人猊下の御指南のもと、一天四海本因妙広宣流布の大願につながる御命題に向かって日々信行に邁進し、一人でも多くの人に正しい教えを弘めてまいりましょう。
2013.02.08
-
金原某に盗作と騒ぐ習ひそこないの学者たる犀角独歩を笑う。
小うるさいことを言うようで恐縮です。けれど、○○さん、善い資質を持っているのに、こうした常識から逸脱すると、せっかくのよい面が帳消しになってしまいます。人の文章や業績を、あたかも自分のことのように書くのは創価学会の文書の特徴です。わたしも金原某に写真まで無断使用され、挙げ句の果てに、自分のほうがわたしより先に本尊鑑別をやったとまで言い出す悪辣さです。 わたしはいちおう、いまでも連載も持つプロのライターですから、日記はオリジナルの作品です。それを文章を書き換えて、ネタ元を書かないで、自分の文章のように公開すれば、当業界で言えば、これを盗作と言います。そうした悪気がないことは承知していますが、結果的にはそうした有様となっていることを認識していただければと思い、敢えて苦言を申し上げました。 顕正会、浅井の悪を糺すことは、たいへんけっこうなことです。ですから、そうした社会悪対峙のためには、手段を選ぶ、善意、良識、一般通念に違反しないという手段を選ぶことが、大切なことであるというのが、わたしの信念です。 ご理解いただければ有り難いところです。 http://blog.livedoor.jp/saikakudoppo/archives/51822171.html さて、mixiのマイミクの日記の書き込みからである。 金原某が書いた。戒壇の大御本尊を否定する本は、犀角独歩から見たら、盗作だと言う事です。 犀角独歩の日記内容は、金原某が盗作したものならば、その盗作された本は、日蓮正宗青年僧侶邪義破折班により、木っ端微塵に粉砕されたのである。 また、妙観講講頭大草氏により破折されています。 自称大日蓮編集していた犀角独歩が、大日蓮にあった。金原某の破折を知らないわけがない。 その内容は、インターネットをみれば簡単に見れるのであるからして、知らない。存じませんは、通用しないのである。 また、犀角独歩の邪義は、妙相寺のYouTubeで有名な樋田氏に破折されている。 この習ひそこないの学者は、往生際悪く、現実に日顕上人が相手しない事を知りながらも、日顕上人しか法論をしないと言っている。 これを見て、顕正会を知っている人ならば、誰かに似ていると思ったでしょう。 そう!!顕正会会長浅井昭衛氏と全く同じ事をネットで言っているのです!! 浅井さんは、日蓮正宗青年僧侶邪義破折班から木っ端微塵に粉砕された。 もう。笑うしかありません。 ただの習ひそこないの学者でしかありません。犀角独歩に騙されない事です。
2013.02.08
-
道心の中に衣食有り、衣食の中に道心無し
【総本山第67世日顕上人猊下御指南】より 自分自身の心のなかにある金銭に対する執着、あるいはその他の色々な意味における執着を一切捨てて、信心根本というところに、そして「一心欲見仏 不自惜身命」のところにまず正対して、いわゆる、 「道心の中に衣食(えじき)有り、衣食の中に道心無し」 という伝教大師の言葉のとおり、妙法をもって自らも信行し、他をも導くということを徹底するところに真の道心が存すると思うのであります。 道心があれば御本尊様は絶対にお見捨てあそばされません。必ず生きていく道は開いていきます。しかし「衣食の中に道心無し」という言葉のとおり、お金のことやら衣食のこと、物質の充足のことを中心に考えているところには、道心というものは全くないと同時に仏法もありません。(中略) 正しい信心をもって、いわゆる顕益、冥益の功徳を積んでいくところに、おのずから御本尊様の御利益をもって様々な意味の利益、功徳が当然、感ぜられてくるところであります。これはまた大聖人様の御指南のとおりであります。
2013.02.07
-
心を師となるとも心を師とせざれ
【一日教訓】 愛媛県西条市 日蓮正宗 一心寺長谷御住職著 大聖人は『兄弟抄』の中で 「心の師とはなるとも心を師とせざれ」 と仰せです。 この場合の心とは煩悩を意味します。煩悩を師とし、いたずらに振り回されるのではなく、自身が煩悩の師となって、煩悩を逆に道心のエネルギーとせよ、と仰せになられているのです。 『御講聞書』には、 「所詮不信の心をば師となすべからず、信心の心を師匠とすべし」 と仰せです。 信心の眼を開き、その信心の心を常に自身の師とするのです。 そして、その信心の眼によって現実世界をみるならば、そこには、いながらにして真実を見出すことができるのです。 私達は、煩悩に振り回されます。私も煩悩に振り回されながら、信仰してます。 信心の心を師とする。大切な事だが、簡単にいかない。 いつも思うが、この信心は大変難しい。簡単にいなかない。苦しい事が沢山あるが、それでも、愚痴を言わず。御本尊様を根本にしていく。これが最も大切な事です。
2013.02.06
-
法四依
正林寺御住職指導(H24.8月 第103号) 「法四依」とは、仏道修行をする上でよりどころとすべき四つの法のことです。 四つの法とは、『涅槃経』に、 「仏の所説の如く、是の諸の比丘、当に四法に依るべし。何等をか四と為す。法に依りて人に依らざれ。義に依りて語に依らざれ。智に依りて識に依らざれ。了義経に依りて不了義経に依らざれ(国訳一切経涅槃経部1ー142頁) とあるように、一に依法不依人、二に依義不依語、三に依智不依識、四に依了義経不依不了義経の四つを法四依といいます。 「依法不依人」(法に依って人に依らざれ)とは、仏の説いた法そのものをよりどころとして、人によってはならないということです。仏法の勝劣浅深の判定は、釈尊が説いた経文を根本とすべきであり、他の人師・論師の所説を用いてはなりません。 末法においては、日蓮大聖人が説かれた御書を根本とすることが大切であり、さらに下種の妙法の極理は、御書を心肝に染め、血脈相伝の御指南を拝することにより正しく信解することができ、血脈への信順こそ「依法」の姿です。 「依義不依語」(義に依って語に依らざれ)とは、仏説の実義・真義をよりどころとして、経文の表面上の語句にとらわれてはならないということです。 大聖人の仏法にあっては、御書の語句の表面的意味にとらわれるのではなく、血脈相伝の深義・意義をよりどころとして御書を拝すべきです。 「依智不依識」(智に依って識に依らざれ)とは、仏の真の智慧をよりどころとして、人の浅い知識や経験則によってはならないということです。 大聖人の御仏意を信じ、血脈付法の御法主上人の御指南に信伏随従していくことが大切であり、己の我見や浅識によって仏の教えを推し量ってはなりません。 「依了義経不依不了義経」(了義経に依って不了義経に依らざれ)とは、仏の真実の経である法華経をよりどころとして、法華経以外の方便の諸経をよりどころとしてはならないということです。 末法においては、本門戒壇の大御本尊を信じ奉り、御法主上人の御指南に随順していく信心の中に「法四依」が具わっています。 http://blog.goo.ne.jp/shourinzi47320/e/7ee417bc6f25fce9a1f9b7da512ad443
2013.02.06
-
拡散お願いします!
拡散どうかよろしくお願いします! できるだけ大勢の方々へ、共有、拡散をどうかよろしくお願いします! 創価脱会への道には大変勇気づけられるブログです! 現職公明党市会議員が脱会・離党! ブログが学会員の策謀で閉鎖される! 新たにブログアップ! http://blogari.zaq.ne.jp/taazan/
2013.02.05
-
唱題の功徳とは
正林寺御住職指導(H21.6月 第65号) 百日間の唱題行も後半に入り、着実な唱題の実践で功徳を体験し、実感されている講員さんもおられることでしょう。 日蓮大聖人は『当体義抄』に唱題の功徳について、 「南無妙法蓮華経と唱ふる人は、煩悩・業・苦の三道、法身・般若・解脱の三徳と転じて、三観・三諦即一心に顕はれ、其の人の所住の処は常寂光土なり。」(御書694) と仰せであります。唱題の功徳により迷いや悩みは解消され、成仏につながる尊い徳と境界を身につけることができます。 御法主日如上人猊下は唱題の功徳を積むための基本的な心得について、 「御本尊様への絶対の確信こそが大事であろうと思うのです。この御本尊様への絶対の確信というのは、言葉を換えれば、御本尊様の功徳を信じきっていくこと」(功徳要文88) と御指南です。御本尊の広大無辺なる功徳を信じて、無疑曰信といわれる疑いなき信心に努めることが一番大事であります。 大聖人も『御義口伝』に、 「修行とは無疑曰信の信心の事なり」(御書1773) と仰せのように疑わない信心が肝要です。 唱題行では御本尊への疑いを一切無くし、堅く信じ唱えることが大切であり、唱題の功徳を顕現するために必要です。 御命題の使命を託された精鋭、広布の戦士が積む唱題の功徳は、地涌の菩薩の眷属が身につけるべき立正安国の精神が養われることです。 さらに衣座室の三軌が、我が身に具わり仏祖三宝尊と寺院への外護のため、一身をなげうって広布に尽くす死身弘法の精神が品格として顕現されます。 百日間唱題行に残された時間で正林寺支部の一人一人が唱題の功徳を実感し、唱題の功徳を積まれることに期待いたします。 http://blog.goo.ne.jp/shourinzi47320/e/bbcfe4b2c3ea634d3fac2c05f9a46f07
2013.02.05
-
まず一丈の堀を越えることから
正林寺御住職指導(H24.12月 第107号) 物事を達成するためには成すべきことを着実に一歩一歩進めていくことが大事です。成すべきことを成さず達成はありません。また成すべきことを実行せず大きな目標を立てても達成することはできません。 日蓮大聖人は一歩一歩を進めていく大切さを教訓として『頼基陳状』に、 「一丈の堀を越えざる者二丈三丈の堀を越えてんや。」(御書1132) と仰せです。一丈の堀を越えられない者が、一丈の堀よりも大きい二丈や三丈の堀を越えることがどうしてできようかという教えです。「一丈」という言葉を、階段や梯子の一段という言葉に置き換え、また距離を示す1キロに置き換え現実を見据えて、まず一つを越えることから、はじめの一歩を大事に物事の達成に向けて具体的に実践し行動して取り組むことが肝要です。 さらに「一丈」という言葉を一秒・一分・一時間・一日・一ヶ月・一年と置き換えて、人生の計画を立て物事が達成できるよう勤めることです。この勤めるとは信心と生活の両面に渡ります。一年一年と月日が経過すれば先は十年二十年となります。大聖人は『種々御振舞御書』に、 「一丈のほりをこへぬもの十丈二十丈のほりを越ゆべきか。」(御書1058) と仰せです。これからの十年二十年となる十丈二十丈は一丈の堀である一年一年を着実に越える信心活動と一生懸命に生活した陰徳により、十年二十年が経過し十丈二十丈を越えた時、一年一年の取り組み次第により陽報が顕現されます。 まずできるところから着実に積み重ねて行くことです。本年最後の月に当たり悔いの残らない年を送りましょう。 http://blog.goo.ne.jp/shourinzi47320/e/debe40b4585fd85ea702303f247b2a74
2013.02.04
-
心を磨く信心を…
正林寺御住職指導(H16.2月 第1号) 皆様こんにちは、二月に入り益々寒くなる時期です。身体に十分気を付け信心に励みましょう。 宗祖日蓮大聖人様は『一生成仏抄』に、 「深く信心を発こして、日夜朝暮に又懈らず磨くべし。何様にしてか磨くべき、只南無妙法蓮華経と唱へたてまつるを、是をみがくとは云ふなり」(新編御書四十六頁) と仰せであります。ただ入信しているだけではいけません。大聖人様は「深く信心をおこして」と仰せです。今以上に信心に志し勤行唱題をして、心を磨く信心が大切で、その結果により今以上の幸せを得ることが出来ます。 寒くなると信心を怠りたくなる気持ちが生まれやすくなります。怠慢な気持ちに流されない信心に成仏があります。御題目を唱えて寒さに負けない強い精神を信心で養うことが大事です。 二月は日蓮正宗において多くの行事がある月です。節分会(三日)・第二祖日興上人の興師会(七日)・宗祖日蓮大聖人の御誕生会(十六日)です。お寺へ参詣して御報恩申し上げることが必要です。時間をうまく調節して参詣出来る時間を心がけましょう。 皆様の心の仏性に尊い清らかな気持ちが流れかようはずです。その清らかな気持ちで人生を生きていくところに「不染世間法 如蓮華在水」(法華経従地涌出品第十五)と説かれる濁った世間に染まらない清らかな生活を送ることが出来ます。 以上、皆様の御精進を御本尊様に御祈念申し上げ、住職より今月の挨拶とさせて頂きます。
2013.02.03
-
日蓮正宗の節分会
こよみの上で立春の前日を節分といい、一般世間では豆まきをする習慣があります。世間でも行われる行事であります。 大聖人様は、正法へ導く一方便として「厄」という社会一般の慣習を利用され、 「三十三のやく(厄)は転じて三十三のさいは(幸)ひとならせ給ふべし。七難即滅七福即生とは是なり。年はわか(若)うなり、福はかさ(重)なり候べし」(四条金吾殿女房御返事・七五六) と述べられております。 他の宗派は、厄災は他から来るものとしています。しかし、厄災や不幸は、どこからか来るものではなく、自分にその原因・宿習があります。そして、厄災の原因それ自体を幸いに変えるのが日蓮正宗の信心です。一番大事なことは、御本尊様の功徳・力用を根本に、自分の信心を強盛にし、変毒為薬の法門を実生活に顕していくことです。 その一つの機縁が節分会です。 日蓮正宗の節分会と世間での違いは「福は内、福は内」といい「鬼は外、鬼は外」といわないことです。 「鬼は外」といわない意味は、法華経守護において誓っている鬼子母神という鬼の神と十羅刹女という鬼の神がいるからです。これら餓鬼界の鬼子母神と十羅刹女は法華経に説かれる鬼であり世間でいう鬼とは違います。法華経を信仰し御本尊様を信じる人々を守る善い鬼です。善い鬼を家の外に出しては、諸天善神の守護がなくなるため日蓮正宗では「福は内」とだけいい「鬼は外」はいいません。このような意味が日蓮正宗の節分会にあります。 節分会の目的はそれぞれ人生の節目において様々な厄があるため、厄年にあたっての厄払いを行う意味があります。世間でいう厄年の節目には、経験しやすくなる災いを幸いに変えていくため日蓮正宗では節分会を行います。 節分会では厄払いの御祈念の他に、当病平癒の病気が治るようお願いする御祈念や高校進学と大学受験、就職祈願などの御祈念をお願いすることができます。 信徒教化の一環として日蓮正宗では節分会があり、自らの厄と過去遠々劫の罪障を消滅するために大切な行事です。 【日蓮正宗 正林寺 掲示板】より http://blog.goo.ne.jp/shourinzi47320/e/8c7fd893666edc274a5b89f4f86280f8
2013.02.02
-
依法不依人を勘違いしてる者がいる。
降魔の剣にてこういう書き込みがあった。依法不依人、肝に命ずべし 投稿者:フランコ 投稿日:2013年 2月 1日(金)03時05分51秒 Popocatepetl.aitai.ne.jp 返信・引用 年が明けて早いものでもう1ヶ月が経ちました。この掲示板の書き込みがめっきり減ってしまったのは、主催者の樋田さんが法論で学会に負けてしまったからかしら。もっとも、それによって学会の正しさが証明されたわけではないし、学会も法華講も共にダメダメだってだけの話なんですけどね。本門戒壇の大御本尊様を信仰する集団においてもっとも法論が強い人は、御本尊しか信じていない人です。御本尊にプラスして御本尊以外の何事かを正しいとたてている人は、そこの部分が弱点となって法論に負けてしまうのだな。依法不依人!この南無妙法蓮華経に余亊をまじえばゆゆしきひがごとなり! です。 まず、この者がいう法論とは、中野法論であろうかと思うが、これを見てみれば分かるが、もう法論でない。これをみて小樽問答と同じだと私は、感じたものである。この者は、依法不依人の法をただ、南無妙法蓮華経という題目と思っているらしい。さすが「御書根本」「大聖人直結」という創価学会らしい考え方であり、正しい仏法でない。正しい師に従わずに、自分勝手に仏法をかじるとこういう恥をネットに曝すのだと感じるものです。正しい仏法は、師から弟子へと正しく伝わるこれを信じる事である。かつて創価学会では、このような指導していた。★「仏法は、もちろん獅子相承(師匠から弟子への相承)、血脈相承といって、ただ一人の大導師を定めて、民衆救済の大法を伝持するのである。 正像末の三時にわたり、釈迦も、天台も、伝教もこの方程式によって法を伝えた。すなわち釈迦は迦葉に、天台は章安に、伝教は義真に、その所持の大法を相伝、付嘱したのである。 このように、仏法を流通させるには師匠から弟子への相承がなければならず、これがなければ正しい仏法ではないことは、『伝持の人なければ猶木石の衣鉢を帯持せるが如し』(『顕仏未来記』五〇八頁)のご文によって明らかである。 わが日蓮正宗は、宗祖大聖人より二祖・御開山日興上人へ、日興上人より日目上人へと、代々法水を写瓶(しゃびょう)して、七百年間、六十六代にわたって、広布の時を待ち望み、大法を清らかに厳護してきたのである。 はじめにあげた一大聖教大意のご文(※「此の経は相伝に有らざれば知り難し」全集三九八頁)のごとく、相伝がなければ、日蓮大聖人の大仏法は、まったく理解することはできないのである。」(『大白蓮華』昭和三十七年九月・一三六号七十六頁「相伝について」)正しい仏法は、正しい師から教わるものである。創価学会や顕正会のように、自分勝手に仏法を判断し、自分勝手に解釈してならないのである。自分勝手な判断で仏法を推し量ると、創価学会や顕正会のようになるのである。「よき師とよき檀那とよき法と、此の三つ寄り合ひて祈りを成就し、国土の大難をも払ふべき者なり」(新編一三一四ページ)1、この御文の「師」とは、同時代におわす存在としての「師」である。■「在々諸仏の土に、常に師と倶に生まれん」■「若し法師に親近せば速やかに菩薩の道を得ん。是の師に随順して学せば恒沙の仏を見たてまつることを得ん」大聖人を「師」と立てた宗派が悉く異流儀となっていることが御相伝の「僧」を蔑ろにした何よりの現証である。それは創価学会も全く同じである。結局は大聖人=戒壇の大御本尊は富士大石寺に厳としておわしますのであり、この大御本尊へ身・口・意の三業を以って信行できないことは、いくら口先で大聖人を「師」と仰いでも、身が伴っていない証拠である。「仏宝法宝は必ず僧によりて住す』(四恩抄)にあるように2、大聖人は仏宝であらせられる。であるから、「必ず僧によて住す」のである。3、大聖人は仏宝=火 であられるから、「薪なければ火無く」で、 必ず 薪=僧宝 の方の御内証におられるのである。←三宝一体義であるから、「師」とは、御当代御法主上人(また御法主上人に純真な信行によって連なる御尊師方)である。
2013.02.01
-
十四誹謗を慎もう
御書拝読 松野殿御返事(妙教 2005年1月) 信行のポイント (中略) ここでよく考えなければならないのは、講中での人間関係の良し悪しは、一体誰が作り出しているのかということである。つまり、組織を構成しているのは、私たち一人ひとりの法華講員であり、他人のせいにしたり、人を指差すのではなく、理想的な組織の構築は、私たち一人ひとりの自覚と責任にあることを知らなければならない したがって私たちは、漫然と講中に籍を置くだけでなく、まずトラブルや怨嫉の源を断つべく、意識して我が心を治め、言葉や振る舞いを正して、講中での和を大切にし、異体同心、和合一致の組織を築き上げていくように、皆ができるだけ協力していくことが必要であろう。 その講中の異体同心の信心、行体を確立していく上で、殊の外重要な誡めが十四誹謗を犯してはならないという日蓮大聖人の御教示である。 この十四誹謗について、大聖人は本抄で、自行確立の面からと、化他和合の面からの二つの観点より御教示され、この自行と化他にわたって十四誹謗を犯さずに修行し、題目を唱えていくところに、はじめて大きな功徳を成就していくことができる旨を仰せである。 そのことは、十四誹謗の内容から言っても、第一の慢から第十の誹謗までは、自らの信心の姿勢や行を誡めたものであり、第十一の軽善から第十四の恨善までは、正法正義を受持し、信行に励む者に対して、怨嫉したり誹謗してはいけないと誡めたもので、自ずと自行と化他に対する二つの誡めが含まれていることからも、明らかである。 以下に十四誹謗の内容について、一つ一つ詳しく述べたい。 十四誹謗は法華経譬喩品第三に明かされているもので、同品の偈に、 「又舎利弗慢懈怠我見を計する者には此の経を説くこと莫れ凡夫の浅識深く五欲に著せるは聞くとも解すること能わじ亦為に説くこと勿れ若し人信ぜずして此の経を毀謗せば即ち一切世間の仏種を断ぜん或は復顰蹙して疑惑を懐かん汝当に此の人の罪報を説くを聴くべし 若しは仏の在世若しは滅度の後に其れ斯の如き経典を誹謗すること有らん 経を読誦し書持すること有らん者を見て軽賤増嫉して而も結恨を懐かん」(開結175~6) と説かれている。この文について、中国天台宗の第六祖妙楽大師は、 「今の文は但説不説を云うのみ。有る人此れを分かって云く、先に悪因を列し、次に悪果を列す。 悪因に十四あり」(法華文句記五大石寺「訓読法華文句記会本六上」二二四) として、譬喩品には慢・懈怠・我見などの者には、誹謗・不信等のために罪障を作らせることになるので、法華経を説いてはならない。これに対して、利根で智慧明了で、仏道を求める人には説くべしと、説かれている。これを慈恩大師がさらに釈して、悪道に堕する悪因に十四あるとして十四誹謗を挙げている。 経文では、これらの十四誹謗の悪果として、地獄・畜生等の堕して苦しむ相(すがた)や、さらに適(たまた)ま人界に生を得たとしても、種々の病気や種々の苦しみの報いを受けることが説かれている。 その十四誹謗の第一が「慢(きょうまん)」である。慢は増上慢と同じで、「方便品」第二には、 「此の輩は罪根深重に、(中略)未だ得ざるを得たりと謂い、未だ證せざるを證せりと謂えり」(開結一〇〇) と説かれている。即ち慢は、正法にして驕(おご)りと侮(あなど)りの心をもち、正法をどこまでも謙虚に学んだり求めたりしないことをいう。 第二は「懈怠(けだい)」である。それは、自分の楽しみや世間の浅いことには時間を惜しまず、労を厭わず、せっせと精を出すが、勤行や唱題、参詣や登山、折伏などの大切な仏道修行を怠けること、またなすべき行を怠ることをいう。 第三に「計我(けが)」。これは、自分の考えを中心として正法を推し量って曲解(きょっかい)し、我見に執着することをいう。自己や我への執着は大なり小なり誰しも持っているが、その我をもととして正法を計ることである。 第四に「浅識(せんしき)」とは、自分の浅はかな知識や考え、経験をもって仏法を安直に判断したり評価したりして、それ以上の深いものを求めようとしないことをいう。 第五に「著欲(じょくよく)」。経文に「深く五欲に著せる」とあるように、財・名誉・飲食など世俗の欲に執着して、仏法を求めようとしないことをいう。 第六に「不解(ふげ)」。経文には「聞くとも解すること能(あた)わじ」とあるように、仏法を聞いても正しく理解できないこと、また理解しようとしないことをいう。 第七に「不信(ふしん)」。『念仏無間地獄抄』に「譬喩品十四誹謗も不信を以て体と為せり」(御書三九)と仰せのように、今ここで明かしている十四誹謗の本体、つまり一々の誹謗が種々の相(すがた)・形をもって現れるその源・本体となるもので、正法を信じることができないこと、また信じようとしないことをいう。十四誹謗を生む根本となるもので、最も注意を払い誡めるべきものである。 第八に「顰蹙(ひんじゃく)」。憎む心をもって顔を顰(しか)めることから、正法を憎み、非難することをいう。 第九に「疑惑(ぎわく)」。一往一通り頭では分かっているが、心から信じきれず、正法を疑い、惑(まど)うことをいう。例えば御本尊の意義や功徳を教えられても、心から信じることができず、疑って勤行や唱題をためらうことなどがこれに当たる。 第十に「誹謗(ひぼう)」。正法に対して言葉をもって積極的に悪しざまに謗(そし)ることをいい、その罪障は最も大きい。 第十一に「軽善(きょうぜん)」。これ以下の四つは、経文に「経を読誦し 書持すること有らん者を見て」と条件が付されているように、正法、即ち御本尊を受持し、信行に励む人に対して、軽んじ侮ることをいう。 第十ニに「憎善(ぞうぜん)。正法を信受する僧俗を憎むことをいう。 第十三に「嫉善(しつぜん)」。正法を信受する僧俗を嫉(そね)み妬(ねた)むことをいう。嫉むことも妬むことも共に、他の勝れたものに対して羨(うらや)んだり憎んだりするところから起こる感情で、今日特に創価学会が日蓮正宗に対して、怨嫉(おんしつ)の念を強くもって破壊しようとする行為は、まさに学会自らが宗門の正当性と正しさを認識している証でもある。 第十四に「恨善(こんぜん)」。正法を信受する僧俗を恨むこと。字義から言うと「恨」の字は、同じウラミでも心中に根に持つ深いウラミをいう。 以上が十四誹謗であり、これに対して本抄は、 「此の十四誹謗は在家出家に亘(わた)るべし、怖(おそ)るべし怖るべし」(御書一〇四六) と仰せのように、在家の信徒も出家の僧侶も、共に悪果・悪報を招く大きな業因となるので、恐れ慎んで十四誹謗を誡めていくべきことを強く説かれている。 私たち日蓮正宗の僧俗は、この大聖人の御教示の通り、自行と化他行に亘って十四誹謗を犯さないよう、十分に注意したいものである。 心豊かな晩年を迎えるために さて、今私たちは確実に高齢化社会を迎えている。特に日本においては、2010年には65歳以上の高齢者が全人口の五分の一の割となり、さらにその十年後の2020年には四人に一人となるといわれている。一体どんな時代がやってくるのだろうか。私たちは決してこの現実から逃れることはできない。ならば自らの老後をどう迎えていくか、否、老後をどう仕上げていくか、という問題を真剣に考えて、日々歩んでいかなければならない。 若い時や壮年時にはどれほど苦労が多くても、人生の締めくくりとなる晩年は、すべての悩みが解決し、所願満足して、歓びと感謝の中に、心豊かに過ごしたい。このような思いは熟年の域に足を踏み入れた私ばかりではなく、人生半ばを過ぎると、誰もが抱く思いではないだろうか。 しかし晩年はといえば、フランスの哲学者アランは、 「青年は恋愛を欲しがり、 壮年は地位を欲しがり、 老人は貧欲になって、地位も金も名誉もすべて欲しがる」(『精神と情念に関する八十一章』) と述べているように、地位も名誉も全て欲しがる貧欲な老後が待っているという。長年勤めてきた仕事への愛着を断ちきれるであろうか。また「進む時は人任せ退く時は自ら決せよ」との言(越後長岡藩家老・河井継之助)もあるように、その立場や地位から自らの意思で去ることができるのであろうか。これらに執着がある限り、歓びと感謝につつまれた心豊かな老後はやって来ないだろう。貪瞋癡(とんじんち)の三毒を抑制し、わが心を潔(いさぎよ)く無にすることができてこそ、幸せな老後を迎えることができるのではないか。 心豊かな幸せな老後を迎えるためには、まず信心によって功徳善根を積み、わが心の罪障消滅と生命(いのち)の浄化・色心の六根清浄を成就していくと共に、世法の上からも、人としての徳を限りなく積んでいくことに、心がけていかなければならない。 信心も自行のみでは真の苦楽を超越した自受法楽の境界は得られないのであって、他のための折伏と育成に悩み苦しんでこそ、人のあり様、世の中のあり様を客観的に体得し、自らの三毒を抑え、種々の執着より離れることができるのである。 また、先程から述べて来たように、自行と化他行にわたって十四誹謗を犯すような信心を繰り返していては、仏法上悪果を招く罪業でしかないのであるから、十四誹謗を誡め、慢や懈怠のない自行を心がけていくと共に、同じ法華講員同士で悪口を言い合うことのないように、十分に注意していかなければならない。このような不断の清らかな信行の積み重ねにより、心が鍛錬され、三毒を抑制し晩年の自分を作り上げていくことができるのである。 大聖人は、正月一日を正法をもって愛でることを悦ばれた『十字(むしもち)御書』に、 「とくもまさり人にもあいせられ候なり」(御書一五五一) 「法華経を信ずる人はさいわいを万里の外よりあつむべし」 「法華経を信ずる人はせんだんにかをばしさのそなえたるがごとし」(ニ文共に御書一五五二) と仰せられ、この信行に励む者は幸を万里の外から集め寄せ、もともと良い香りのする栴檀(せんだん)にさらに芳(かぐわ)しさを添えるように、徳も積まれ、人に愛されるようになると、正法信行の功徳を御教示である。 信心の上から、我が生命を過去世にまで遡(さかのぼ)って浄化しつつ磨いていくと共に、さらに世法の上からも人の生き方をよく学び、修練を重ねて己を磨いていくことが必要である。 宋の黄堅(こうけん)の編んだ「古文真宝」には、学問の修養について、 「厚く積みて薄く発す」(宮城谷昌光著『中国古典の信行録』四十) と教えている。ひたすら学問に励んで、徳を厚く積み重ねることによって、はじめて幽(かす)かに徳が光を発するのである。我が身に積み重ねていく信心のくどくも、丹誠を込めて長く深く積み重ねていくことにより、光り輝く人間性が、ふとした言動の中に現れるのである。 弥よ私たちは、地涌の菩薩の一類として、清らかな自行化他の信行に徹し、自らの過去久遠からの使命である衆生救済に精励すると共に、人の生き方もしっかりと学び、心豊かな晩年を迎えられるよう努力をしていきたいものである。またそのことが正法を受持し信行に励んできた実証といえるのだから。 http://www.geocities.co.jp/sarariwoman/hokkeko/shingyo_point_0501.htm
2013.02.01
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
-

- FXデビュー!!!
- 今月は自慢できるほど稼いでもないし…
- (2025-11-16 21:10:09)
-
-
-

- 絵が好きな人!?
- ボタニカルアート教室に慣れてきまし…
- (2025-10-25 19:13:07)
-
-
-
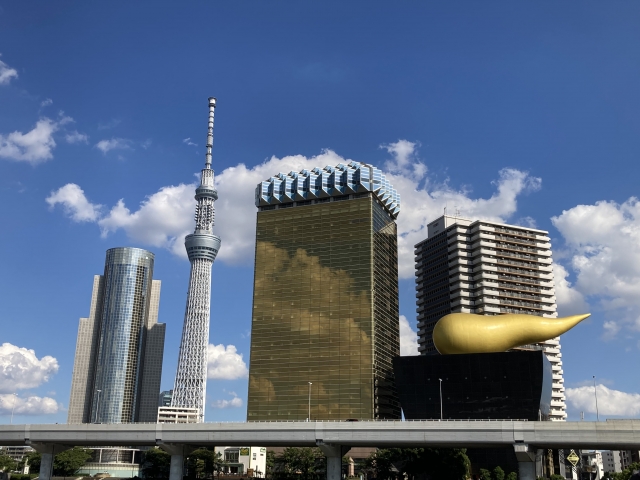
- ◆パチンコ◆スロット◆
- 東京都清瀬市 低貸スロット(2.5円…
- (2025-11-17 00:00:09)
-







