2013年01月の記事
全56件 (56件中 1-50件目)
-
正しい宗教の条件
正林寺御住職指導(H22.6月 第77号) 正しい宗教を判定する場合の基準に、人間の世界を離れた架空の世界を基盤とした宗教ではなく、人間のための宗教であり、人間がよりよく、幸せに生きるための宗教であることが大事な条件です。 そのためには、正しい生命観に基づき、正しい道理を備え、全人類を救済する現実の力をもった宗教が大切です。 ではどのような方法で宗教を判定したらよいのでしょう。 日蓮大聖人は、「三証」と「五義」という基準をもって宗教の正邪を判定するように教えられています。 三証とは文証、理証、現証のことです。 文証とは、仏菩薩が説いた経論などによる証拠であり、教えが独断ではなく、仏の説いたお経にも裏付けられるのかを確かめることです。 理証とは、教えが原因と結果の道理にかなっているかどうかを確かめることです。 現証とは、その教えが単純に理論のみの観念ではなく、現実に人間の生活の上で証明されるのかを確かめることです。 五義とは教・機・時・国・教法流布の前後の五つを知ることをいいます。正しい宗教の選択と仏法を広めるに当たっての規範で、正しい宗教を知る上で大切な条件です。 「教を知る」とは、経律論や、あらゆる思想、哲学、宗教の勝劣浅深を見究めることです。「機を知る」の機とは衆生の機根であり、教えを受け入れられる状態にあるかどうかを見定めることです。「時を知る」とは、広まる教えに相応した時代であるかどうかを知ることです。「国を知る」とは、それぞれの国が、どのような教えに縁のある国かを知ることです。「教法流布の前後を知る」とは、先に広まった教えを知って、次に広まるべき教えを知るということです。 正しい宗教の条件を備えた教えを信仰することが末法で幸せに生きる道です。
2013.01.31
-
育成について
大白法 平成22年12月1日付 日蓮正宗の基本を学ぼう 育成について 前回は、日蓮正宗に入信して間もない方への育成について、以下の三点に集約して述べました。 まず第一に御本尊を受持させること、そして信仰の根本である勤行・唱題の奨励、最後は、折伏のできる人材に育てることです。 今回は、寺院参詣と講中活動を実践する人材を育成することについて、学んでいきます。 【善知識に交わる大切さ】 日蓮正宗に入信しても、初めはなかなか支部に馴染めない人もいます。また組織活動が嫌いで、御本尊を受持して心静かに信仰をしたいので御報恩御講の参詣や座談会、勉強会、折伏などの活動や行事に参加したくないと、思う人も多いようです。あるいは、法華講の組織に頼らなくとも、必要な時にはお寺に行って御住職・御主管に相談すればよいので、組織の指示を受けたり、講頭をはじめとする在家の人の激励などは受けたくないと言う人もいるでしょう。 このような独り信心を願う人には、正しい信仰をしていく上で「善知識」に交わることが大切であることを教えてあげましょう。 「善知識」とは正しい仏道へ誘い導く師匠や同志、機縁となるものを言います。根本の「善知識」とは末法下種の三宝のことですが、ひいては本門戒壇の大御本尊を信じ、御法主上人猊下に随って仏道に精進する僧俗すべてを指します。 『衆生身心御書』には、 「麻の中のよもぎ・つゝの中のくちなは・よき人にむつぶもの、なにとなけれども心もふるまひも言もなをしくなるなり」(御書 一二一二頁) と仰せです。この御文は、麻の中に生えた蓬が麻と同じように真っ直ぐに成長するように、また、蛇が筒の中にいると否応なく真っ直ぐになっているように、善知識との交わりを深めれば、振る舞いも言葉も善知識と同じように丁寧になり、信心もまた素直な確信に満ちたものとなる、との意味です。 これと同じように、大聖人様の仏法を修行する者同士が、お互いに広宣流布という高い理想に向かって精進するとき、一人ひとりが互いに善知識となって境界を高め合う間柄になるのです。 大聖人様は『三三蔵祈雨事』に、 「仏になるみちは善知識にはすぎず」(同 八七三頁) と仰せになられています。一生成仏をめざす私たちにとって、善知識が集う本宗の寺院こそ、大聖人様の正しい信仰を教わり、実践し、信心を磨く道場であり、その寺院に参詣して、同志と共に信仰の活動をしていくことが成仏への道であることを教えていきましょう。 大聖人様は『蓮盛抄』に、 「凡そ世間の沙汰、尚以て他人に談合す。況んや出世の深理、寧ろ輙く自己を本分とせんや」 (同 二九頁) と仰せられています。世間法でさえ大事に当たってはよき相談相手を求めるのに、仏道にあって自分一人孤立し、その自己中心の心を本分として、大聖人様の正しい信仰を貫けるはずはありません。 入信の日以来、指導教師である御住職・御主管のもとに信心を磨き、支部の一切の人々がお互いに啓発し合い助け合いながら信心を深め、報恩感謝の信心を学びます。そうして、広宣流布に向かって精進していくために寺院と法華講の組織があるとの認識を持つことが大切です。 その上から、善知識の同志として正しい信心の向上を図れるように諭し、激励し、細やかに面倒を見ながら、その信心を守り・育てていくべきです。 【寺院は異体同心の信心を培う道場】 寺院は、大聖人様の御遺命である広宣流布大願成就のために、僧俗和合して信行学に励むべき法城です。 大聖人様は『生死一大事血脈抄』に、「総じて日蓮が弟子檀那等自他彼此の心なく、水魚の思ひを成して異体同心にして南無妙法蓮華経と唱へ奉る処を、生死一大事の血脈とは云ふなり。(中略)若し然らば広宣流布の大願も叶ふべき者か」(同 五一四頁) と仰せです。私たちは常に自らの信心に濁りはないか、大御本尊に対する潔い信心に任しているかということを省みて、お互いに切磋琢磨するためにも所属寺院に集い、ここを法城とし信心活動の拠点として、指導教師の御指導のもと僧俗一致して進んでいくところに、広宣流布の大願成就への道があることを教えていきましょう。 また、一人ひとりが大聖人様から与えられた広宣流布の使命を全うするときに自己の幸福も自ずから叶うという意識を共有して、広く信心活動の参加を呼びかけ、展開していきましょう。 【寺院とは信心錬磨の道場】 日蓮大聖人が『一代聖教大意』に、 「此の経は相伝に有らざれば知り難し」(同 九二頁) と仰せのように、教学は世間の学間とは異なります。信心を根本として、御講、勉強会等で指導教師の御住職・御主管から教えていただくことが大切です。 『新池御書』に、 「此の僧を解悟の智識と憑み給ひてつねに法門御たづね候べし」(同 一四六一頁) と御指南の通りです。 信は行学を起こし、行学は信を深めます。教学によって仏法の裏付けとなる道理が判ってくると、仏法に対する確信が深まり、しっかりとした行体になっていきます。また、独断や偏見のない正しい信仰の在り方や、折伏・弘通に必要な知識も身についてきます。 教学を疎かにする姿勢であっては、しばしば我見をさしはさんで信心が狂ったり、難に遭ったときに簡単に退転することにもなります。素直な信心をもって寺院に参詣し、指導教師から直接、教学を学ぶことの大切さを教えましょう。 また御講や御会式等、寺院の諸行事では、受付や誘導整理、寺域の清掃、行事の準備・片付け等を、自ら積極的に行うことも大切です。寺院のあらゆる行事を通じて、少しでも身の供養をさせていただこうというお給仕の精神を養い、自らの信心を錬磨することができます。すなわち寺院は、信心錬磨のための道場でもあるのです。 また寺院の活動を通して、ほかの講員の悩みや苦しみを克服した体験、唱題によって大きく境界を切り開いた功徳の体験など、様々な信心によって勝ち取った功徳の実証を、見聞きすることができます。同信の仲間の功徳の実証は、それを見聞きしたほかの多くの法華講員の信心を奮い立たせ、一人ひとりの生命を蘇生させるような大きな力を与えることになります。 私たち大聖人様の仏法を受持信行する者は、常に自らの信心を鍛え、励むことが大事ですが、そのためにも寺院における支部活動にはたいへん重要な意義があるのです。とかく怠惰に流されてしまいがちな凡夫の信心を蘇らせ、奮い立たせてくれるのが、支部の仲間の真摯な信心の姿勢です。その姿はお互いがお互いを模範として、それぞれに信心修行に励む糧となるのです。 現在、平成二十七年の御命題成就に向けて、全支部が、一丸となって折伏誓願達成に日夜邁進しています。同時に総本山へのご登山、寺院参詣・講中活動を通して新入信者を育成し、互いに励まし合い、しっかりと支部講中の足腰を固め、一歩いっぽ着実に広布の大道を歩んでまいりましょう。 http://okigaruni01.okoshi-yasu.com/senmyouji-sin/kihonwomanabou/221201/01.html
2013.01.30
-
法華講連合会の目的と信条
正林寺御住職指導(H24.9月 第104号) 法華講連合会結成50周年記念大会が平成24年7月22日に総本山大石寺の大講堂で開催されました。記念大会の砌に御法主日如上人猊下は、 「これからも健全な発展のため、連合会の『目的』と『信条』を忘れることなく、しっかりと御奉公に励んでいただきたいと思います。」(大白法 第842号) と御指南されました。 法華講連合会の目的とは「法華講連合会規約」の第5条に、 「連合会は、日蓮正宗総本山及び末寺を厳護し、日蓮正宗の教義を護持弘宣して、広宣流布達成に資するとともに、法華講支部の発展をはかり、講員の信仰増進に寄与することを目的とする。」 とあります。 信条とは第12条に、 「連合会の法華講員は、次の各号に掲げる信条を堅持し、信行学に精進しなければならない。 一 本門戒壇の大御本尊を信仰の根本とし、総本山を厳護するとともに、所属の寺院・教会を広布の道場として護持発展せしめること。 二 行学二道、異体同心の御聖訓を身に体し、御法主上人猊下の御指南を遵奉し、指導教師の指導を受け、僧俗和合して広宣流布に邁進すること。 三 篤く三宝を敬い、日蓮正宗信徒たることを深く自覚し、四恩報謝の念を体し、もって世人の模範となること。」 と記されており、以上の目的と信条を法華講員一人一人が銘記すべきことです。
2013.01.29
-
冬は必ず春となる
正林寺御住職指導(H25.2月 第109号) 宗祖日蓮大聖人は文永九年(一二七二)二月に極寒の佐渡において『開目抄』を紙や筆の乏しい塚原三昧堂において著されました。現在は塚原三昧堂の跡地に佐渡塚原跡碑が建立されています。 この厳しい寒い時期において信心修行の姿勢を大聖人が佐渡御配流の地におかれ弟子檀那に身を以って振る舞われた御教示と拝します。 大聖人は『種々御振舞御書』に、 「塚原と申す山野の中に、洛陽の蓮台野のやうに死人を捨つる所に一間四面なる堂の仏もなし、上はいたまあはず、四壁はあばらに、雪ふりつもりて消ゆる事なし。かゝる所にしきがは打ちしき蓑うちきて、夜をあかし日をくらす。夜は雪雹・雷電ひまなし、昼は日の光もさゝせ給はず、心細かるべきすまゐなり。」(御書1062) と佐渡の塚原三昧堂での様子を仰せです。 大聖人は『妙一尼御前御消息』に、 「法華経を信ずる人は冬のごとし、冬は必ず春となる。いまだ昔よりきかずみず、冬の秋とかへれる事を。いまだきかず、法華経を信ずる人の凡夫となる事を。」(御書832) と仰せです。私達の人生や信心においての厳しく苦しい環境では、大聖人が極寒の佐渡塚原で御生活された様子を我が身に受け止めて拝し、寒い冬は必ず暖かい春となることを信じて諦めず、厳しい極寒のような生活を堪え忍んで一日一日を大事にし一丈の堀を越えるように生活していくことです。その辛く苦しい人生での環境が貴重な経験となり資糧となって人間性や精神が養われていきます。 大聖人が仰せの「冬は必ず春となる」との御言葉を常に心得て信心して生きていくところに幸せと成仏があります。
2013.01.28
-
アンチ日蓮正宗hideを徹底的に切る!!
嘘やデタラメを平然とネットでやってる。自称俳優のhideであるが、その内容は、もう池田創価学会の創価新報やフェイクと同じ低レベルな内容である。 さて、御秘符であるが、調べたら、黒川氏のブログに以下の内容があった。 日蓮正宗における「御秘符」とは当代猊下が本門戒壇の大御本尊に御祈念され、また与えられた人のことを猊下が大御本尊に祈られ、病気の治癒を祈られるものだ。 この自称俳優は、日蓮宗誕生寺の御秘符伝説と混同して、デタラメを出したのである。 また、創価学会では、御符と称して何やら?信者に売っているようである。 つまり、hideなる者は、池田創価学会や顕正会同様に、自分自身が正しいと思い込み。正しい信仰を否定するならば、嘘やデタラメを平然と出すのである。 調べてもいなければ、証拠というのも存在しない。 このhideが、日蓮正宗に何故?怨みがあるか知らないが、池田創価学会は、日蓮正宗の存在が邪魔であるから、日蓮正宗を潰すために、嘘デタラメな内容で、日蓮正宗を攻撃 してきた。 シアトル事件をはじめ、芸者写真事件や、他僧侶誹謗や、役員誹謗をしてきた。 それと全く同じ事をやってるわけです。 人間は、こういう嘘やデタラメを簡単に信用してしまうものである。現にネットやコンビニにある雑誌等には、芸能界の裏と称して、名前を隠して、不特定な記事を出している。 こういう情報は、アンチには喜ばれるのである。どんな芸能人でもアンチは、存在するのである。 人の不幸な事や、欠点や悪い癖を見て、誹謗すると、彼らアンチらは、満足するのである。ようは、自分自身が劣っているのに他人が、劣っているという事で、喜びを感じるのである。 私達は、欠点だらけの人間である。人の欠点を見て、莫迦にしてるのは、小さな人間である。 だから、池田創価学会員は、法華講と聞くと逃げるし、ネットでしか騒げないアンチらは、現に私に正々堂々と法論すらしない。できないくせに、人の欠点ばかり探してるのだから、情けない人間というか、畜生である。
2013.01.27
-
アンチ日蓮正宗hideの妄想を切る!日蓮正宗は、薬事法違反?
日蓮正宗を誹謗するなら、何でもありの自称俳優の習ひそこないの学者が、またまたくだらないインチキ内容を言っている。 まず、この大石寺の法主が信者に授与しているという日蓮の「薬草」、いわゆる「御秘符」なるものを科学鑑定すべきである。そして「御秘符」の「薬草」成分について、速やかに科学的に分析すべきである。 そしてこれが厚生労働省が薬として認可しているものに適合しているのかどうか。 薬でないものを薬として信者に飲ませているとなると薬事法違反の疑いがあるのではないか。 さらに仮にこれが薬として適合しているとしても、大石寺の法主は、薬剤師の資格を持っているのか。薬剤師の資格がないのに、薬を調合して信者与えているとすれば、薬事法違反の疑いがあるのではないか。 又、薬でないものを、日蓮から伝来している「薬草」としてカネをとって信者に授与しているとすれば、詐欺の疑いがあるのではないか。 こんな疑惑逃れのためか、日蓮正宗では信者に対して、こんな指導をしているという。 「御秘符は薬ではない。信心で呑みなさい」 しかし御秘符なるものが薬ではないとしても、日蓮正宗が信者に呑ませていることは事実である。 これが、習ひそこないの学者のブログ内容である。 さて、御秘符であるが、私は呑む(飲むが正解である)は、聞いた事がない。 御秘付であるが、私が始めて知ったのは、池田大作氏が、御秘付を過去に授与されたというネット情報であるが?私個人、御秘付が薬とか飲むものとは、聞いた事がない。 日蓮正宗大石寺には、様々な伝説や言い伝えがある。それは、全国各地のどの宗派の寺院や神社によくある話しである。 それを否定するつもりない。否定するならば否定するなりのきちんとした根拠と証明をしなければならないからである。 さて、日蓮正宗大石寺には、江戸時代に目の病気が治ったという伝説がある。私も読んだが、御秘符の話しは無い。 御秘符は、調べてみようと思う。 自称俳優に聞くが、呑ませている(正しくは、飲ませている)という事実であると、言っているが? では、お主その証拠を持っての書き込みであろうな?事実と言うならば、薬事法違反でお主が、警察に通報か?または、裁判所に訴えただろうな? お主、嘘デタラメをネットに曝すで無い!逆に日蓮正宗大石寺から名誉毀損で訴えられたらなら、お主に勝ち目は無い。 証拠もなければ事実も無い。嘘デタラメを書いても誰も信用されない事をよく覚えておきなさい。
2013.01.27
-
アンチ日蓮正宗hideが言う。金箔を買う金が無かったと、小氷河期を破す。
宗祖の御書に書かれた供養のうち、銭(ぜに)に関しては、二十数人から「百六十数貫」にのぼっており、昭和51年当時で一千万円を超える莫大な金額となっている。(聖教新書32『御書に見る鎌倉時代・167頁』)真書が滅した御書も相当数あるからおそらくこの倍近い金額が具わっていたと考えられる。当時のカネは日本で鋳造されたものではなく「宋銭」、つまり中国の貨幣が信用され、使用されていた。昭和三十二年、大石寺の大講堂を新築するさい、木箱に詰められた古銭が二千枚ほど発掘された。明治初年まで「遠信坊」のあったところだが、この場所こそ、日興上人が大石ヶ原に建立した大坊(六壺)が建立された場所であったと推定されている。古銭の種類としては、大聖人の時代に使用された「北宋銭」や足利時代に流通した「唐銭」が混入しており、大聖人・日興上人の御遺物に歴代の上人が広布の日に備えて蓄えられたものが、大事にされすぎて手つかずになったものと推察される。分量の基準を云えば、日本酒の標準的な容器(一升瓶)が約1800ミリリットル。その10分の1が1合、10倍が一斗、さらに10斗を「一石」である。つまり、よく御書にある米一石とは、一升瓶に米を入れて百本分という分量となる。米一石が銭一貫文で、現在に換算すると約10万円くらいである。 宗祖の信者はけっこうな量の御供養をしていたものです。(笑)、しかし、この時代(鎌倉時代)から江戸時代にかけて米は主食ではないことをしっかり覚えておくべきである。ましてや宗祖のような出家が米の飯を食するということは特別な行事や法要のめでたい時くらいで、米はハレの食事だったのである。(網野善彦『日本史の虚像のゆくえ』大和書房)江戸時代もそうだが、米は主に貨幣の替わりに流通していたもので、よほど豊作で余剰米が出ないかぎり一般庶民には特別な行事(法事・祭事)のさいに食するものであった。故に御書に書かれた「米」の量は他の雑穀に替えられたと考えてよく、食料そのものの蓄えはけっこうな量にのぼると思われる。米に限らず、宗祖は集積していた「塩」を銭や必需品に交換している。『上野殿御返事』に、「七月なんどはしほ(塩)一升を銭百、しほ五合を麦一斗にかへ候しが、今はぜんたい(全体)しほ(塩)なし」とある。宗祖は精進料理なので調味料は使用しないので寄進された塩などは他の物品に交換していたものである。以前この内容を出したのだが、自称俳優hideは、この内容を皮肉っている。まさか?御書に存在しない人物に授与された御本尊が多数ある事をまさか?知らないと言うのであろうか?また、真筆御書の大半が失われている事くらい、いくら習ひそこないでも知ってる事であろう。つまり、今現存する御書のみを見て、大聖人は貧乏だと決めつけるのは、ただの習ひそこないの学者である。>身延に庵室が造られたのは、文永11年の6月で、この建物は3間4面、高さ7尺の小さなものであった(『日蓮と本尊伝承』92頁)>右の如き状況の中に、5尺弱の厚板に漆・金箔の施された巨大な板本尊が、台座に据えられて安置されたことを想像するのははなはだ困難である。(同94頁)こういう事を出すだろう。たしかに『庵室修復書』等の記述によれば、大聖人の住まわれた建物は、さほど大きいとは感じられない。しかし、●人はなき時は四十人、ある時は六十人、いかにせ(塞)き候へども、これにある人々のあに(兄)とて出来し、舎弟(しゃてい)とてさしいで、しきゐ(敷居)候ひぬれば(弘安元年11月29日御作『兵衛志殿御返事』御書1295、全集1099頁)●抑(そもそも)貴辺の去ぬる三月の御仏事に鵞目(がもく)其の数有りしかば、今年一百余人の人を山中にやしなひて、十二時の法華経をよましめ談義して候ぞ(弘安2年8月11日御作『曽谷殿御返事』御書1386、全集1065頁)このように、多くの人々を身延の地に収容しえた状況を勘案すれば、庵室はともあれ、身延の建物のすべてが、戒壇の大御本尊を安置できないほど狭隘(きょうあい)・狭小なものでなかったことは明らかである。(森岡雄樹 御尊師『大日蓮』H20.5)御書から見ると、多くの信者が当時の身延に参詣されていた事が分かる。これらをみれば、分かるが、金箔が買えないとか、漆を買えないとか、楠を手に入れる事は、不可能とする事は、出来ないのである。ちょとした常識があれば、言う事無い邪義である。小氷河期説は、簡単に破折できる。そもそも小氷河期とは、太陽の黒点が消滅して起こる説と、火山活動の大噴火による説とがあり、14世紀半ばから19世紀半ばまで続いたという説と、太陽の黒点が消失した17世紀から18世紀までとの二説があるのである。もし、脳乱して痴論を吐くが如き鎌倉時代が小氷河期で温暖性の樹木が枯渇したのであれば、同じく温暖系の植物である米が生育するのは大矛盾であり、他の温暖系の植物が枯渇した記録は、吾妻鏡にも無い。小氷河期とは、「期間中の気温低下が1℃未満に留まる、北半球における弱冷期」と定義されている。平均気温が1°C下がって温暖系の樹木がすべて枯渇するのであれば、鎌倉時代に温暖系の植物は壊滅的事態に遭遇しているわけである。そのような史実は無いのである。無知徒輩に云っておく。・・・もちっと、平均的な史学を学んでから論じろ!!
2013.01.26
-
珍論!大石寺奉安堂は、東大寺大仏殿を模範としたのがおかしいを破す。
自称俳優hideが、珍論で日蓮正宗を誹謗してる。何やら彼は、東大寺大仏殿を見学し、大仏殿が奉安堂に似てるのをおかしいと思っているようだ。今、顕正会で奉安堂を安普請と言ってるのであるから合わせて破折しようと思う。奉安堂の規模とそれを支える技術・工法広谷純弘(建築研究所アーキヴィジョン)はじめに奉安堂は延床面積15,760,83平方メートル(4,767・64坪)、御信徒席5,004席、最高高さ55メートルを誇る、日本でも最大級の寺院建築です。前回のレポートでは、その大空間に伝統的な日本建築のイメージを重ねた上で、耐震性に優れた構造を確保するための技術を紹介させていただきました。今回はその大きさを実感していただくために、皆様もよく御存じの奈良の東大寺大仏殿(金堂)との比較を行いながら、御説明をさせていただきたいと思います。規模の比較東大寺大仏殿は、木造建築としては世界最大の建造物として知られています。皆様のなかにも実際に目にされて、その大きさに驚かれた方も多いと思います。東大寺大仏殿は、奈良時代に聖武天皇の勅願により創建されたのち、二度にわたる戦火で焼失し、建久6年(1190年)と宝永6年(1709年)に復興再建を繰り返しています。現在の大仏殿は、江戸時代に復興されたもので、その当時、大量の巨材を調達することが困難であり、また経済的な理由も伴い、奈良、鎌倉時代の大仏殿よリも縮小して再建されています。現在の大仏殿は、基壇の下からの高さが約50メートル、広さは間口約57メートル×奥行約50メートル=2,850平方メートル(約862坪)です。それに対し、奈良、鎌倉時代の大仏殿は、高さは約50メートルと同じですが、広さは間口約86メートル×奥行約50メートル=4,300平方メートル(約1,300坪)はあったと言われています。つまり、奈良、鎌倉時代の大仏殿は、現在の大仏殿の、約1.5倍の広さを誇っていたことになります。これらに対して、奉安堂はさらに大きく、高さ55メートル、広さは間口75.1メートル×奥行116メートル=8,711.6平方メートル(約2,635坪)の大建築となります。これは図にありますように、そのなかに現在の大仏殿がすっぽりと納まってしまう大きさであり、奈良、鎌倉時代の大仏殿と比較しても2倍以上の大きさとなります。内部空間の大きさ大仏殿は外周部に28本、内部に32本の柱を持ち、これによってその巨大な木造建築を支えています。そして中央部に大仏像を設置するため、26メートル×23メートル=598平方メートル(約180坪)の柱のない空間を構成しています。これに対して奉安堂のホール(外陣・内陣)は、内部に一切柱が立たない無柱空間となっており、その大きさは、間口55.6メートル×奥行84.5メートル=4,698.2平方メートル(約1,421坪)と大仏殿の無柱空間の約7.8倍になります。この大きな空間の天井は、ゆるやかな曲面として設計し、その天井の高さは、一番高いところで約20メートルになります。また奉安堂は、ホール(※本堂、妙音註)をホワイエ(前室)、御僧侶控室、さらに基壇回廊によって囲むような形で計画しております。ホワイエ(前室)は間口55.6メートル×奥行16.2メートルの広さを持ち、約2,000人の方が待機できることを想定しています。また回廊は7.75メートルの幅を持つ屋外空間ですが、深い軒の下にあるため、雨天時にも傘をささずに歩くことが可能です。屋根・本瓦葺きの再現奉安堂も大仏殿も非常に大きな屋根が特徴的です。大仏殿に限らず、歴史的建築物では本瓦葺きという伝統的な瓦屋根が多く見られます。そこで奉安堂では、本瓦葺きの重厚をイメージを現代の材料と枝術で再現することにいたしました。と言いますのは、奉安堂の大きな屋根を大スパン構造(※注)で支えるには、土で造った瓦では、その重量が構造体に大きな負担となるため、より軽い材料が求められるからです。そして様々な検討の結果、軽さと耐久性を兼ね備えた材料として、ステンレスを選択しました。その上で、伝統的な日本建築の重厚さを再現するために、ステンレスで丸瓦と平瓦の形状を作り、それを組み合わせることで、陰影の深い重厚な屋根を形成することにいたしました。丸瓦の大きさは、直径250ミリ、丸瓦と丸瓦の間隔は500ミリとし、ステンレスの上にフッ素樹脂を焼き付けて瓦のいぶし銀色の色調、つやを再現いたします。※大スパン構造:大きな距離を途中に柱を設けずに、大梁で支える構造を言う。奉安堂の大屋根は、ホール(外陣・内陣)内に柱を設けず、周囲の壁内の柱だけで支える大スパン構造である。最新技術の採用これまでは奉安堂と大仏殿の大きさを中心に、比較を行ってまいりましたが、次に、その時代のなかで類を見ない大きさの建物を建てるための技術的な解決について、奉安堂と東大寺大仏殿を比較してみようと思います。共通して言えるのは、その時代の最先端の枝術を用いているという点です。現在の大仏殿は、鎌倉時代の再建時にほぼ原型が造られたと言われています。鎌倉時代の東大寺の再建を担ったのは重源(ちようげん)という人です。当時の日本にとって新技術は大陸からもたらされるものでした。大仏殿を再建するに当たり、重源も宋の建築様式を取り入れ、大仏様(だいぶつよう)という様式を生み出しました。大仏様の大きな特徴の一つは構造的な面にあります。建物の横揺れを止めるため、柱に貫(ぬき)という横材を貫通させ、それを多用することでしっかりとした骨組みを形成しています。当時の最新技術を採用することによって、非常に強固な構造を実現しているのです。この点では、奉安堂でも同様なことが言えます。前回のレポートで報告させていただいたとおり、私どもは奉安堂の特徴として、「伝統的なイメージの外観」「高い耐震性」「無柱の大空間」という3点を挙げさせていただきました。そして、それを調和のとれた形で実現するために、新しい技術を用いて、いくつかの特徴ある構造的解決を図っています。これまで使われてきた構造形式に続く、第4の構造形式として近年登場してきたCFT構造や耐震ダンパー(※レポート2参照)の採用などが挙げられます。CFT構造は、従来の構造形式よりも高い剛性と粘り強さを重ね備えた構造で、耐火性能の上でも優れています。また制震ダンパーは、地震時のエネルギー吸収と変形抑制に対し、非常に有効な構造体と考えられております。このように奉安堂の建設に際しては、これらの新しい技術を用いて、耐震性に優れた強固で安全な構造を目指しているのです。安全で合理的な工期の短縮大仏様(だいぶつよう)のもう一つの特徴は、あらかじめ用意しておく部材の断面寸法の種類が極端に少ないことです。それは同じく大仏様の代表的建築である東大寺南大門の部材が、わずか5種類の断面寸法でほとんどそろってしまうことでも判ります。意志の疎通を欠きやすい大人数の集団で短期間に建設を行うには、非常に便利で機能的な様式であったと言えます。奉安堂も同じように工期を短縮しながら、伝統的な日本建築のイメージを実現し、かつ安全で質の高い工事を行うことが求められました。そのため早い段階から工事担当者も実施設計に参加して、合理的に工期が短縮できる施工方法や、大規模な建築物を効卒よく施工できる技術を検討した結果、様々な枝術を取り入れることが可能になりました。その代表的なものの一つは、屋根工事のリフトアップ工法です。その利点は高所作業の低減による安全性の確保と工期の短縮です。一般にはドーム球場や運動施設での使用が多いため、今回のような伝統的な日本建築のイメージを持った建物に使用されるのは、初めてではないかと思います。もう一つは、外壁に使用しているプレキャストコンクリート板の採用が挙げられます。プレキャストコンクリート板は、工場で生産し現場に搬入されますので、高い品質を確保することができます。さらに現場でコンクリートを打設した場合と比較して、コンクリートが固まるまでの養生期間が不要となり、現場での作業が軽減され、工期の短縮が可能となります。また、先程述べさせていただきましたCFT構造の柱は、鉄筋・型枠工事が不要なため、これも工期の短縮につながっています。現在、奉安堂は最新の技術と合理的な工法に支えられて、徐々にその雄大な姿を翼しつつ、着々と工事が進められています。『奉安堂の規模とそれを支える技術・工法』(大日蓮668号)自称俳優hideは、この文章を読んで、大仏殿を模範したのがおかしいらしい。そもそも模範とは、見習うもの。手本の意味である。世界最大級の木造建築物を模範し、比較してるのがおかしいと言うならば、その根拠を持って批判すべきであろう。日本寺院であるからして、日本の伝統的な建築物を参考がおかしいと思うのが、ズレていると言うしかない。日本建築物の美を日蓮正宗は、批判していない。東大寺大仏殿を批判した事も無いし、他仏教建築物を批判もしていない。日蓮正宗を排他だの批判的宗教と批判してる自称俳優hideに言う。お主こそ美意識に欠けた排他的な人格である。
2013.01.26
-
漆を塗ってあるから、大御本尊は後世に造られたものだ。
●戒壇の御本尊様は楠の板である。(中略)その時分は鉋(かんな)がなかった。鎌倉時代は手斧(ちょうな)であるから、あの御本尊は手斧削りである。それを見れば、すぐわかる。それを知らないで、「漆(うるし)を塗ってあるから、あれは足利時代にできた」とか、最近は「徳川時代にできた」などと、とんでもないことを言う。ところが(大御本尊の)後ろを見ると、削った跡がちゃんと残っている。それを見ても、明らかに鎌倉時代である。手斧で、明治時代の人は知っているが、丸いものではない。あの時代には、鉞(まさかり)みたいな手斧で削った、その板です。(中略)そういうことを見ても、はっきり鎌倉時代の板本尊である。(第66世日達上人・昭和47年9月12日/『慧妙』H17.5.16)●戒壇の大御本尊は楠の厚木です。表から見ると、こういう板です。ところが、これは大変な板です。ただの板ではないのです。(中略)後ろから見ると丸木です。丸木を、表だけ(平らに)削ってあるわけです。(中略)これを削った手斧は、鑓(やり)手斧とも鑓鉋ともいいますね。それで削った。それは赤澤朝陽氏がちゃんと言明しております。だから鎌倉時代のものである。(中略)足利時代から、今日使用しているような手斧ができてきますが、鑓手斧は鎌倉時代のものです。(第66世日達上人・昭和52年5月28日/『慧妙』H17.5.16)-----------------------赤澤朝陽は彫刻を行う仏師。後に、創価学会の模刻本尊の彫刻を行ったあげく、自らも信心を失い、今日では学会側に付いている。現実に、大御本尊を見た事無い輩や、信仰を失い経歴詐称して嘘をネットに出す輩らが、ネットで騒いでる。いくら、騒いだところで、大御本尊を否定できない。否定するならば、文献ばかり見ていないで、鎌倉時代にタイムスリップするしかあるまい。それも出来ないのであるから、素直に日蓮正宗の教義に従うしか無いのである。
2013.01.25
-
身延に楠が無いを破す。
この妄説は、身延の邪僧・安永弁哲が『板本尊偽作(ぎさく)論』なる悪書の中で言い始めたもので、まったく虚偽(きょぎ)の疑難(ぎなん)である。 まず、楠(くすのき)が生育する適地は、暖温帯湿潤気候の、標高500メートル以下の場所であるが、山梨県甲府市から身延を通って駿河湾に流れる富士川の沿線は、まさに、この暖温帯湿潤気候に属しており、また日蓮大聖人がお住まいになった草庵(身延山久遠寺)は標高300数十メートルの地である。 そして事実、今日でも身延には、楠が生育しているのである。 例えば、身延の入り口にある日蓮宗大野山本遠寺の境内には、町で天然記念物と指定された巨木(通称「大楠」)をはじめ、複数の楠が生えているし、他ならぬ身延山久遠寺の本堂付近にも、楠の大木が何本も生育しているではないか。 これをもって、「身延に楠は生育せず」との疑難は根底から崩壊している、といえよう。 それにしても、身延の僧侶が、自山に生育する楠を、平気で「生育せず」と言い切り、また、それを今まで破折してきた創価学会の会員が、一転して「身延に楠はない。ゆえに戒壇本尊は偽作」などと言い出すのだから、謗法者の節操の無さには呆(あき)れる他ない(『慧妙』H17.5.16)。自称俳優hideが、鎌倉時代は小氷河期だと言ってるけれども、自称俳優であり、歴史学者でなければ、気象予報士でもないし、植物学者でもない。ただの習ひそこないの学者である。この習ひそこないの学者は、実際に身延に行って見てるのか?この習ひそこないの学者が言うように、身延に楠が無いとしても、日興上人の折伏にて、楠が生息してる地域からの可能性もあるわけです。そもそも鎌倉時代が小氷河期だと言ってるのは、この習ひそこないの学者である自称俳優のhideのみである。しつこいが、この自称俳優hideは、歴史学者でなければ、気象予報士でもない。ただの自称俳優である。mixiにて、自身のデタラメの持論を曝け出して他の者から、自然で小氷河期で全ての植物が全滅は有り得ないという意見にブチ切れした。なんとも低脳な人であろうか。肝が小さい輩である。いくら、歴史学者でなければ、気象予報士でない。ただの自称俳優が、歴史学者でも言わない。気象予報士でも言わないような事を言ってるのだから、信用も無い。デタラメな持論である。あの経歴詐称の犀角独歩もそうであるが、ただ持論を言ってるだけで、歴史学者でもなければ、ただの自分自身を偉そうに見せている。ただの習ひそこないの学者である。
2013.01.25
-
法に依って人に依らざれ
正林寺御住職指導(H18.5月 第28号) 私達は絶対的幸福である成仏をめざすには、人(人師・論師)の言葉に頼ることなく、正しい仏法(三大秘法)や正しい御経に頼ることが大事であります。 日蓮大聖人様は『報恩抄』に、 「法に依って人に依らざれ」(御書一〇〇〇) と仰せです。正しい仏法に依って、正しい仏法に依らない人の言葉には、一時的な幸福は存在しても絶対的幸福はないのであります。「法」とは、法華経である経文の底に秘される下種仏法の南無妙法蓮華経であり、法華経の経文上の脱益仏法や法華経以外の爾前諸経ではありません。 さらに「法」とは日蓮大聖人様が出世の本懐として御建立あそばされた三大秘法の南無妙法蓮華経である総本山大石寺の奉安堂に在す本門戒壇の大御本尊です。また日蓮大聖人様の正しい仏法を七百年以上も前から血脈相承によって御所持遊ばされる時の御法主上人に依ることが法に依ることになります。 つまり、三大秘法の南無妙法蓮華経と現在の御法主上人で在られる第六十八世日如上人猊下の仰せに依ることで正しい仏法に頼ることとなります。三大秘法の御本尊と御法主上人猊下は法華講員が信心していく上での命綱・命脈です。 この命綱となる法に背くことを謗法といいます。謗法とは誹謗正法のことであり、正しい仏法に対し謗ったり悪口をいうことでもあります。その謗法の罪は、法律で罰せられることはありません。しかし、日蓮大聖人様は『立正安国論』に、 「法華経の第二の『若し人信ぜずして此の経を毀謗せば、乃至其の人命終して阿鼻獄に入らん』」(御書二四〇) と仰せであり、正しい仏法に背いた場合、命終において地獄の中で最も辛く苦しい無間地獄にいくことを御教示であります。信心は人の言葉より、正しい法に従って精進することが大切であります。
2013.01.25
-
身延にも、中山にも、上代から板本尊が存在
―古文書の曲解(きょくげ)も、自己矛盾により論理破綻― 前号において、本門戒壇の大御本尊が板御本尊である意義について簡略に説明した。今回は、「板本尊は大聖人御在世には存在せず、大聖人滅後、富士門流(日有上人時代)によって造立されるようになったものであるから、戒壇大御本尊は偽作である」との疑難について破折していく。 この疑難の根底には、大聖人の御書や富士門流上代の文献に板本尊に関する記述が確認できない、とする考えがあるのだが、しかしながら、これを理由に大御本尊を否定することはできない。 なぜなら大御本尊以外の大聖人の数多(あまた)の御本尊であっても、そのほとんどが御書や上代の文献に記されていないからだ。したがって文献に記述がないことをもって大御本尊を否定する根拠にはならないのだ。 まして大御本尊は、他の一機一縁の本尊と異なり、一切衆生を救済する一閻浮提総与の御本尊である。この出世の本懐である重宝を末代に残すためには、安易に口外しないなど、重々の配慮をもって厳護されたであろうことは当然のことである。 さて、大御本尊が御板であることを理由に難癖(なんくせ)をつける輩(やから)に対し、門下上代において板本尊が存在していた証拠を示そう。 まず、日蓮正宗に伝わる板御本尊のうち、戒壇の大御本尊を除いて最も古いものは、栃木県信行寺に伝わる8世日影上人造立の板御本尊である。 この御本尊は、総本山に所蔵される弘安3年の大聖人御真筆御本尊を謹刻されたものであるが、このような化儀を日影上人が独創するとは考えられず、大石寺門流の伝統を踏まえ、造立された御本尊であることが明白である。したがって、板御本尊造立の始まりが日有上人からである、とする疑難は崩壊しているのである。 次に大聖人滅後の身延山に、板本尊の存在を確認できる文献がある。身延の古文書(身延山33世遠沽院日亨の記とされる)に 「一、板本尊 本尊は祖師の御筆を写すか、下添え書きは第三祖向師の筆なり、下添え書きに云く、正安二年庚十二月日右日蓮幽霊成仏得道乃至法界衆生平等利益の為に敬って之を造立す」(『身延山久遠寺諸堂建立記』日蓮宗宗学全書22-P56)とあり、大聖人御筆の御本尊を模写した板本尊が、民部日向によって造立されていたことが判(わか)る。それは、もともと身延山久遠寺の本堂に安置されていた大御本尊を、日興上人が身延離山の際に富士へ御遷座(せんざ)されたため、その後に民部日向が、大御本尊を真似(まね)て板本尊を造立したものと推察できるのである。 さらに、身延上代の別の板本尊の記録と思われる中山3世日祐の『一期所修善根記録』には、 「身延山久遠寺同御影堂、大聖人御塔頭、塔頭板本尊 金箔 造営修造結縁」(日蓮宗宗学全書1-P446)と、観応2年に修理された身延上代の御影堂には板本尊が安置してあった、と記されている。 この他にも身延では、日向造立の板本尊以外に、行学院日朝(日有上人と同時代)が大聖人御真筆の御本尊を彫刻して板本尊を造立した記録が残っているなど、複数の板本尊の存在が知られている。 またさらに、中山門流の宝物記録である『本尊聖教録』(大聖人滅後50年頃、3代日祐著)には「板本尊一体」と記されており、当時、中山門流にも板本尊が存在していたことが判る。 これらのことから、日有上人以前の日蓮門下最上代より、板本尊造立の史実が存したことが判明し、それが造像本意の他門にまで及んでいることは、滅後の弟子たちが身延における大聖人・日興上人の大御本尊安置の化儀を踏襲(とうしゅう)したもの、と考えるのが当然である。 しかして、これらの史実は、大御本尊の成立時期が宗祖御在世乃至日興上人身延在住期にまで遡(さかのぼ)ることを意味しており、日有上人が初めて板御本尊を造立したなどとする見解は否定されるのである。 次に、この民部日向造立の本尊について、近年、ネット上において異論を唱える者が出てきた。 その主張とは、「日蓮正宗、日蓮宗を問わず、板本尊ではないが、板本尊そっくりのものがかつては多数存在していた。したがって、1300(正安2)年12月に日向造立の板本尊なるものも、『日蓮幽霊成仏得道乃至法界衆生平等利益の為に敬って之を造立す』と書いてある文があることからしても、これは板本尊というよりも、当時、中国から伝来して仏教界に普及しはじめていた本位牌や寺位牌をモデルにした板位牌だったと考えられる」というものである。 この主張は、門下上代に板本尊が成立していたことの傍証となる日向造立の板本尊を、何とか否定せんとする苦し紛(まぎ)れの説だが、はたして、日向が造立したのは「位牌」だったのだろうか。 かつて、その身延の板本尊を御覧になった59世日亨上人は、それが本尊であることを断言されている(『大白蓮華』66号)。宗内外において学匠と名高い日亨上人が、位牌と本尊の形態を見間違うはずはない。 また、先に引用した『身延山久遠寺諸堂建立記』には、 「一、板本尊本尊は祖師の御筆を写すか」と、明らかに板本尊と明記してある。これをわざわざ「板位牌だった」などと解釈する方が無理な話だ。しかも、この文献の別項目には、位牌に関する記述も示されており、筆録者が板本尊と位牌とを別物としていることが明らかである。 以上のように、日向が造立したものを「板本尊」と断定したのは、当宗ではなく日蓮宗なのである。 これらの史実から、板本尊造立という化儀は、けっして大石寺門流独自のものではなく、むしろ、大聖人の化儀を門下の弟子たちが継承したもの、と見るべきである。 これらの史実から、板本尊造立という化儀は、けっして大石寺門流独自のものではなく、むしろ、大聖人の化儀を門下の弟子たちが継承したもの、と見るべきである。 また現在、ネット上において散見される大御本尊に関するさまざまな誹謗(ひぼう)は、三宝破壊の逆徒が我見をもって唱える、全く根拠のない邪義である、と喝破(かっば)するものである。
2013.01.24
-
アンチ日蓮正宗hideを破す。
mixiで、他法華講から叩かれて、mixiで逃げ現実に私との法論から逃げている。自称俳優ことmixiでのhideであるが、こりずに自身のブログで騒いでるようである。戒壇の大御本尊についても、二箇相承について、散々破折を加えたが、懲りずに習ひそこないの学者が騒いる。ここで、惠妙(株式会社惠妙発行)から、ネットに蔓延る邪義を破すシリーズを転載する。(『慧妙』H24.7.16) 昨今、インターネットの掲示板の利用が問題となっている。というのも、不特定多数が匿名(とくめい)で情報交換する掲示板において、薬物の取り引きや売買春の勧誘、さらには殺人予告や集団自殺の呼びかけなど、さまざまな犯罪に悪用されていからである。 この問題は世法だけに止まらず、宗教上においても当てはまる。仏法に無智浅識(せんしき)なる者どもが、自身の我見のもとに好き勝手に己義を唱え、正法誹謗(ひぼう)の重罪のかぎりを尽くしている現状が、ネットの世界で蔓延(まんえん)しているのである。 このような宗教上の犯罪者を、世間のネット犯罪のように警察が取り締まったり、法律で裁(さば)くことはできないが、必ず仏天の厳罰によって裁断される、と確信するものである。 さて、今回は、本門戒壇の大御本尊への誹謗のなかでも、大御本尊が板本尊であることから起こる疑難をとりあげる。ネット上には、 「板本尊は大聖人御在世には存在せず、大聖人滅後、門下弟子によって造立されたものである」「文字の部分を削ることは大聖人の御聖意に反する」「大御本尊の元となる楠(くすのき)は当時、身延には自生していなかった」「大聖人当時は金箔(きんぱく)、漆(うるし)を買う資金がなかった」などの疑難がある。 板本尊を否定する者には、大聖人の御本尊は紙幅のみであるという考えが前提にあることから、楠によって造立された板御本尊の存在を認めないのであろう。 大聖人御一代中に顕(あら)わされた多数の御本尊には、それぞれ建立意義と目的に異なりがあり、御本尊図顕(ずけん)における大聖人の御化導を相伝仏法の上から正しく拝さなければ、本義を見失うこととなる。ゆえに、正法不信の者がいくら邪智(じゃち)浅見をもって御本尊の深義を理解しようとしても、けっして大聖人の御聖意に辿(たど)り着けることはない。 当宗僧俗はすでに周知のことであるが、大御本尊が何たるかを知らない者どもに、簡略に説明しておこう。 元来、大聖人所顕(しょけん)の御本尊は、大きく2種類に分けることができる。 1には、弟子や檀那への個人に与えられた御本尊である。これは、主に授与者の信行の対象として安置すべき御本尊であり、ほとんどの御本尊に授与者の名前が認(したた)められている。 2には、特別な意義と目的のもとに顕わされる御本尊で、その時々の境地より御図顕され、授与者が示されていないものもある。 戒壇の大御本尊が、このうちの後者に当たることは言うまでもない。 当宗においては、戒壇の大御本尊をもって信仰の主体としている。その理由は、大聖人の宗旨が戒壇の大御本尊に極まるからであり、法義的に三大秘法のすべてを惣在(そうざい)する上から「三大秘法惣在の本尊」と称し、また末法万年の衆生を救済するために万人を対象として御図顕され、一閻浮提(全世界)すべての人々が信受すべき御本尊である意味から「一閻浮提総与の本尊」とも称するのである。 これは大聖人が、『観心本尊抄』に 「此の時地涌千界出現して、本門の釈尊を脇士と為(な)す一閻浮提第一の本尊、此の国に立つべじ」(御書P661)と仰(おお)せられ、さらに『三大秘法抄』に 「三国並びに一閻浮提の人懺悔(さんげ)滅罪の戒法のみならず、大梵天王(だいぼんてんのう)・帝釈(たいしゃく)等の来下(らいげ)して踏(ふ)み給ふべき戒壇なり」(御書P1595)と仰せられた本尊義が示すところである。 そして、26世日寛上人も、大御本尊について 「故に弘安元年已後、究竟の極説なり。就中弘安二年の本門戒壇の御本尊は、究竟中の究竟、本懐の中の本懐なり。既にこれ三大秘法の随一なり。況や一閻浮提総体の本尊なる故なり」(文段集P452)と、大聖人の「究竟中の究竟」「本懐の中の本懐」たることを仰せである。 つまり、本門戒壇の大御本尊とは、個人に与えられた一機一縁の本尊とは意義も目的も一線を画す、特別な本尊であり、大聖人が末法万年の一閻浮提の衆生救済のために、紙幅ではなく、木の板に認(したた)められたことは、むしろ当然と拝せられる。大御本尊の建立意義を正しく拝せば、板御本尊である道理も必然性も理解できるのである。 板御本尊を否定する輩(やから)は、まず自身の宗派の本尊形態を顧(かえり)みるがよい。もしそこに、板本尊が祀(まつ)られていたり、過去に安置されていた史実があれば、当宗の大御本尊を誹謗する前に、自宗の本尊を攻めるがよい。 学会員しかり、日蓮宗しかり、保田妙本寺しかりである。 宗旨の根幹と御本尊建立の意義に迷い、正しい宗門史を理解することもできず、支離滅裂な愚論を展開するネット上の誹謗者には、大御本尊の真偽を語る資格など微塵(みじん)もなく、増上慢も甚(はなは)だしいと、念告しておく。(つづく)
2013.01.24
-
厄は転じて幸いとなる
正林寺御住職指導(H24.2月 第97号) 世間一般で厄年の認識は、人の一生のうち、厄にあうおそれが多いため忌み慎まねばならないとする年とされています。 数え年で男性は25・42・61歳、女性は19・33・37歳とされています。特に男性の42歳と女性の33歳を大厄とされ、その前後の年も前厄・後厄とし恐れ慎む風潮があります。 厄年の方に心得てほしい日蓮大聖人の教えがあります。 大聖人は『四条金吾殿女房御返事』に、 「三十三のやくは転じて三十三のさいはひとならせ給ふべし。七難即滅七福即生とは是なり。年はわかうなり、福はかさなり候ベし」(御書757) と仰せです。プラス思考・善知識として厄年を心得ていくように御指南です。故に厄年を忌み嫌うのではなく人生の絶好の転換期として前向きに考えることです。 また大聖人は『経王殿御返事』に、 「わざはひも転じて幸ひとなるべし。あひかまへて御信心を出だし此の御本尊に祈念せしめ給へ。何事か成就せざるべき。」(御書685) とも仰せです。厄年に関わらず人生どのような災いも幸いに変わり、心して強盛に御本尊へ御祈念していけば何事も成就しないわけがなく、必ず叶うのであると諭されています。 さらに大聖人は『十字御書』に、 「法華経を信ずる人はさいわいを万里の外よりあつむべし。」(御書1552) と御本尊を信じる人は幸いを集めることができると仰せです。 大聖人は『弥源太入道殿御消息』に、 「今生の禍、後生の福なり。」(御書1255) と御本尊を信じ題目を唱えると今世での禍は来世の福となることを御教示です。
2013.01.24
-
「祖道の恢復」と御報恩
「祖道の恢復」と御報恩 菅原信了御尊師 宗旨建立七百五十年の慶祝御報恩の感激覚めやらぬ「広布大願の年」も孟春二月を迎えました。 今月は興師会、御誕生会を奉修し、宗開両祖に深く御報恩謝徳し奉るとともに、 六年後の御命題達成のため、広布推進会第一期の中盤の月として、折伏・育成に全力で取り組むべきであります。 また青年部対象の広布推進会が全国一斉に開催されております。 御法主日顕上人猊下は、御登座の砌「祖道の恢復」「異休同心の確立」「広布への前進」を掲げられ、 以来、常に大聖人様の仏子、地涌の菩薩として、 邪見を(いまし)誡め正道に則り、本因下種仏法の弘宣に励むよう一貫して御指南あそばされました。 したがって、平成三年一月六日の、 「あくまで正しく、私一人になっても法を護ってまいります」(大白法 三四〇号) との御指南は、御法主として、仏祖三宝尊を深く尊崇あそばされる御立場から、 世間を(たぶら)誑かし惑わす池田創価学会の外道義を断固破折される覚悟の御言葉であり、さらには日興上人の、 「衆義たりと雖も、仏法に相違有らば貫首之を(くじ)揣くべき事」(御書 一八八五) との御遺誡に則られ、もって「祖道の恢復」を、率先垂範される破邪折伏の御一念の御振る舞いと拝するのであります。 したがって、我々日蓮正宗門下の僧俗は、御法主日顕上人猊下の御指南を心肝に刻み、 日蓮大聖人の仏法に違背することなく、御歴代上人の御教訓を体し、 その精神をもって信心に、行体に、教学に精進することこそ、 一人ひとりの成仏のための「祖道の恢復」の実践であり、 成仏の直道を歩む姿なのであります。それはまた自らの信仰の心が、文底下種仏法に立った思いなのか、と常に我が心に問うことも大切なことであります。 『上野殿御返事』には、 「聴聞する時は然(も)へ立(た)つばかり思(をも)へども、遠(とを)ざかりぬれば捨(す)つる心あり」(同 一二〇六) と仰せられています。この御文を拝し奉りますに、誰もが少なからず経験することです。 すなわち御講などに参詣し、御法門を聴聞したとき、 それまでの間違った考えに気づき、折伏しよう、唱題しようと勇み心が湧き、 (ほっしん)発心するのでありますが、時間が過ぎ、家に帰りますと、すぐにその勇み心も忘れてしまい、(しま)終いには折伏や唱題を人に押しつけられたと思う邪念に埋没してしまうのであります。 この「とをざかりぬれば」とは、時間や距離のことのように思えるのでありますが、根本は心が「とをざかる」のであります。 我が心が、御本尊様から「とをざかりぬれば」ではないでしょうか。 大聖人様の教えから心が「とをざかり」、成仏の直道から心が「とをざかり」、 ついには仏法から大きく外れた不信心の姿となるのであります。 この「とをざかり」の心は何故に生じるのでしょう。 『寿量品』に、 「而もきょう(し)恣の心を生じ(ほういつ)放逸にして五欲に(じゃく)著し悪道の中に(お)堕ちなん」(法華経 四四二) と釈尊は説かれています。「」とは「おごりほしいままにする」との意味であり、 「放逸」とは「ほしいままに」「きままに」という心の動きであります。 長い間信心しているという心から、仏法のことは少し理解していると得意になって気ままな心になり、 五欲すなわち五塵という、成仏とは反対の煩悩に埋没し、結果として悪道に堕ちる原因を作ることになると説かれているのであります。 言い換えるならば、悪道に堕ちる因である五欲から「とをざかりぬる」自分になるように発心することが肝要なのであります。 それには何をどのようにするのか、それは『蓮盛抄』に、 「是を以て法華に云はく『悪知識を捨てゝ善友に親近せよ』」(御書 二九) と仰せられています。「悪知識」とは、悪道に堕す(はたらき)作用であり、 生活している周囲の友人・知人等の、仏法の道理から離れさせるような言葉、信心を破る言葉であります。 「善友」とは、成仏に導く知人・友人の激励の言葉でありますから、 時には厳しい助言もあります。感情が波立つ言葉もあります。「善友」は「善知識」のことであります。 しかし、善友にしても悪知識にしても、自分の感情や都合に合わせて選ぶのではありません。『方便品』に、 「仏(かっ)曽て、百千万億無数の諸仏に(しんごん)親近し」(法華経 八八) とあるように、仏の教法に、我意我見に負けることなく (しん)信(ぷく)伏(ずい)随(じゅう)従することが「親近」するということであり、正直な信心の上から判断することなのであります。 我々は、自分の境遇で物事を識別判断するものであります。しかし、身近な問題で判断できないことは、知人・友人にその解決を(ゆだ)委ねることがあります。ところが仏法のこと、信心のことは注意しなければなりません。同『蓮盛抄』に、 「止観に云はく『師に(あ)値はざれは、(じゃ)邪(え)慧日に増し生死月に甚だしく、(ちゅう)稠(りん)林に曲木を(ひ)曳くが如く、出づる期有ること無し』云云」(御書 二九) と仰せのように、仏法の深い道理は「師」に親近し、その教えに信伏し随従しなければ得ることができないのです。 師に随従しない場合は、人それぞれの境遇での邪念の智慧に惑わされることになるからであります。 この意味から、御講に参詣し、それまでの浅い見識を見直し、認識を深め、視野を広くし、信心を確かなものにする心がけが大切なのであります。 しかし、忘れてならないことは「(じっけ)習気」という惑です。 この習気は、生活する中での長年の習慣で身についたことが、 意識するしないにかかわらず考え方に出るもので、 その中には創価学会の教えの残塊も含まれます。 この習気を転ずるためには、唱題と折伏が大切なのであります。 『十章抄』に、 「真実に円の行に順じて常に口吟(ずさ)みにすべき事は南無妙法蓮華経なり。心に存ずべき事は一念三千の観法なり、これは智者の(ぎょう)行(げ)解なり。日本国の在家の者には但一向に南無妙法蓮華経と唱(とな)えさすべし。名は必ず体にいたる徳あり」(同 四六六) と仰せであります。人は過去世からの因縁果報によって、その人の人生の境遇があります。この現実は、その人が求めたものではありませんが、 『蓮盛抄』の「邪慧日に増し」との仰せのごとく、邪悪な智慧が原因となっての境遇であり、境界なのでありますから、その境遇から脱却すること、 改善することを考えなければならないのであります。 我々は、幸いにも御本尊様を信心する境遇にあり、すでに成仏の種子を植えられているのです。 その尊い成仏の種子を育てることに心を尽くすことが、今の境界を高めることになるのであります。 御法主日顕上人猊下は、 「妙法蓮華経の体はそのまま、妙法蓮華経を行ずるところに顕れる」(大白法 六一三号) と御指南あそばされました。折伏をしたいとの一念を叶えてくださることも唱題にあります。 折伏したいがその相手がいないと思っても、唱題することで必ずその人は現れます。 それは過去からの因縁で現れます。話が相手に通じないとの悩みも、唱題することで幾つもの道は開けます。 また、御講に連れて行くことも一つの道です。特に折伏して御本尊様の御前に連れて行くことは、地涌の菩薩が地涌の友を御本尊様に御紹介申し上げる崇高な行為であることと認識すべきです。 心に御本尊様を忘れ、自分が地涌の菩薩の一人であることを忘れて、世間の低い思想をもって仏法を観たり、 謗法の残塊を残したままで信心したり、あるいは自己流の考え方で仏法を解釈して、どうして境界を高めることができましょう。 一心不乱の唱題でよくならない境界はありません。真剣な折伏で消えない罪障はありません。 「祖道の恢復」は、日蓮大聖人の仏法を広宣流布する上において忘れてはならない心得であり、御報恩の一念に存することであります。 唱題行と折伏の実践、御講への参詣によって成仏の種子は培われ、育まれるのであります。 六年後の『立正安国論』正義顕揚七百五十年に向かい、地涌の菩薩として、真の法華講員として境界を高め、一人でも多くの地涌の友を、御本尊様、日蓮大聖人様の御前に御紹介申し上げ奉り、御報恩申し上げようではありませんか。 http://homepage3.nifty.com/y-maki/sinngyou/51-100/74.html
2013.01.23
-
間違ってるというならば、正しいものがなければならない。
インターネットにて、蔓延る邪義は沢山あるけれども、どれを見ても、これが正しいものだという証明をしたものが全く見当たらない。ただ、文献をいじってるだけで、肝心なこれが正しい信仰だ。これが正しい仏教だとする証明をしていない。では?何が彼等が言いたいか?日蓮正宗が正しいと、都合が悪いのです。都合悪いからおかしいだの、間違ってるだのと騒いでるだけである。ある者は、日蓮正宗は他宗教を批判がおかしいから、間違ってる宗教だと言うけでも、では、それら宗教が正しい宗教であり、本当に人々を救っている宗教と言えるのでしょうか?キリスト教徒は、戦争してきた歴史があります。イスラム教のイスラム原理主義者らは、自爆テロをしてそれを聖戦と言ってる。他仏教宗派にしても、本当に救える宗教なのか?現実に救えていないのです。井の中の蛙大海を知らずという言葉があるけれども、本当に宗教というものが理解できてるのか?ただ、感情的になって言ってるだけでしか無いのです。私達の日蓮正宗の信仰というものが、間違ってると言うならば、正しい宗教。これが正しいものなのだとい論証をしたものを出してもらいたいものです。
2013.01.22
-
不軽菩薩の振る舞い
正林寺御住職指導(H19.7月 第42号) 折伏をさせていただく時、不軽菩薩の振る舞いが大切です。不軽菩薩の振る舞いとは、折伏する相手を軽蔑することなく敬うことであります。 釈尊は法華経の『不軽菩薩品第二十』に、 「我深く汝等を敬う。敢えて軽慢せず。所以は何ん。汝等皆菩薩の道を行じて、当に作仏することを得べし。」(法華経五〇〇) と説かれるように、不軽菩薩の振る舞いを心がけて折伏し、私達の過去遠々劫の罪障からくる軽率な言動と慢心を押さえ、相手の仏性を敬い長所を見つめながら折伏することが大事です。 日蓮大聖人も『崇峻天皇御書』に、 「法華経の修行の肝心は不軽品にて候なり。不軽菩薩の人を敬ひしはいかなる事ぞ。教主釈尊の出世の本懐は人の振る舞ひにて候けるぞ。」(御書一一七四) と不軽菩薩のように人を敬いながら折伏することが大切な振る舞いであると御指南です。不軽菩薩の人を敬う振る舞いを忘れた折伏には、様々な弊害を生じさせます。折伏時の振る舞いは、非常に大事なことであり折伏する相手に影響もあります。そのために不軽菩薩の軽蔑することなく他人を敬う振る舞いが大切です。 不軽菩薩の振る舞いを実行することで徳を積むことができます。不軽菩薩はその功徳により、大神通力、楽説弁力、大善寂力を得ることができました。 大神通力とは、身に神通力を示現すること。 楽説弁力とは、自在無礙に弁舌する力。 大善寂力とは、心に禅定、すなわち心を静め真理を観察し、心身ともに動揺することがなく、安定した状態を得ることです。 二年後に向かえる七万五千名の精鋭に加えさせていただくには、不軽菩薩の振る舞いは当然ながら身に備えて参加させていただくことが望ましいでしょう。
2013.01.22
-
5000万円離脱僧勧誘事件
2000年 平成12年9月21日 5000万円で離脱僧勧誘認定 創価学会副会長・八尋頼雄、青年部長・正木正明、SGI事務総局アジア部長・久野健の三人(役職は事件当時)が、福田毅道尊師に五千万円で離脱するよう持ちかけていた件に関する裁判で、一審(東京地裁)は、学会側が敗訴。そして、平成十二年九月二十一日、二審の東京高裁でも、再び、学会による五千万円離脱勧誘工作が、事実と認定された。 ●事件経緯 自ら五千万円という金額を口に出して離脱を勧誘しておきながら、そのことを公表されるやいなや、虚偽の事実を公表され、名誉を毀損されたと訴え出た、八尋頼雄・正木正明・久野健の、三人の学会幹部――。事の起こりは、平成四年十月初めに遡(さかのぼ)る。 同年十月三日から五日にかけ、創価学会は、当時SGI事務総局アジア部長であった久野を窓口にして、福田毅道尊師に接触し、宗門離脱をもちかけた。 久野らはその際、福田尊師に対し、 「お金のことは、あまり言いたくないが、創価学会本部としては、まず五千万円まで出す用意がある」 「あなたが離脱をしないのは、猊下にお金をもらっているからじゃないんですか。五千万円までなら出せる。猊下にそんなお金は全額返してから、離脱するのです」 「五千万円までなら出せるんだけどなあ」 などと述べ、五千万円提供することをエサに、宗門離脱を強く勧誘したのである。 久野らから勧誘された福田尊師は、学会による離脱勧誘行為の存在を宗内に知らせるべく、その顛末(てんまつ)を、記した文書を関係方面に配布し、また、同年、十一月十七日に開催された全国教師指導会の席上でも、その事実を公表した。 ところが、公表したことを逆手に取って、同年十二月十九日、八尋ら三人は、御法主日顕上人猊下と福田尊師を相手取り、合計三千万円の損害賠償と新聞各紙への謝罪広告の掲載を求め、東京地裁に提訴した。 東京地裁は、平成十二年三月二十七日、八尋らの全面敗訴という当然至極の判断を下した。 八尋らは、その判決を不服として東京高裁に控訴し、なおも五千万円という金額を提示しての離脱勧誘をした事実はないと主張し続けた。 しかし、平成十二年九月二十一日、一審判決を支持し、八尋ら学会側の控訴を棄却、宗門の全面勝訴となった。 足かけ九年という長い年月をかけ、慎重な審理を進めた一審の判断を元に、東京高裁は、控訴から半年足らずという迅速さで判決を下したのであるが、その判断は明快そのものであった。 http://blog.goo.ne.jp/jikensi/e/5a181f5fc6b172890f3ce71833fb9c9d これが、創価学会の裏の姿である。
2013.01.21
-
謙虚で感謝に満ちた信仰心
正林寺御住職指導(H21.12月 第71号) 平成二十一年立正安国論正義顕揚七五〇年の記念総登山には布教講演がありますが、ある布教講演の折に、 「謙虚で感謝に満ちた信仰心」 ということを講演のなかで話されていました。この「謙虚で感謝に満ちた信仰心」をお聞きして、当然ですが改めて初心にかえり仏祖三宝尊への信心について見つめ直す大切なことであると感じた次第です。 「謙虚で感謝に満ちた信仰心」を常に心がけて信心を志していく時と、心がけずに信心をしていく時とでは功徳や幸福感に違いが生まれ生活のなかにも当然果報の違いがあります。 さらに「謙虚で感謝に満ちた信仰心」を実践する上で求めることがあります。善知識である御本仏日蓮大聖人(仏宝)、妙法の御本尊(法宝)、日興上人をはじめ御歴代上人(僧宝)の仏法僧の三宝を求めることが当宗の信心修行には大事です。 大聖人から日興上人、御歴代上人へと伝わる血脈相承からの妙法の血液(法水)が流れる正しい血管(血脈)にしっかりとつながろうとする「謙虚で感謝に満ちた信仰心」が一生成仏に求められます。 心がけとして「御本仏のお覚りである南無妙法蓮華経の御題目を丁寧に大切に有難くお唱えしてお供えする」気持ちで実践することも求められます。 また布教講演の折に、 「心が変われば、態度が変わる。態度が変われば、習慣が変わる。習慣が変われば、人格が変わる。人格が変われば、運命が変わる。それが妙法によってなされた三世常住の仏の命。その輪が講中全体に広がればあなたの住む土地が国土世間が立正安国による常寂光土となるのです。」 ともお話をされておられました。 改めて初心にかえり自行化他にわたり見直すべき大事なことです。自身の心が善知識を忘れた自分中心の信心に変わっていないか「謙虚で感謝に満ちた信仰心」をもとに心・態度・習慣・人格・運命が変わるよう精進することが大切です。
2013.01.21
-
現御隠尊日顕上人猊下お言葉 仏眼寺本堂改修庫裡新築落慶法要の砌
昭和五十五年十二月十七日 本日は当仏眼寺が、本堂を改修し、御宝前を荘厳せられ、また庫裡を新築せられまして 仏恩報謝の説を表わされたことは、まことにお喜びにたえない次第でございます。 皆さんも御承知のように、当寺は一説には康永二年(一三四三)の建立ともいわれてお りますが、日興上人のお弟子である日尊上人の開基であります。その開創の年につきまし ては、康永二年には日尊上人は京都におられ、その二年後にはお亡くなりになっておりま すから、それよりもかなり以前に建てられていたのではないかということも考えられるの でありますが、いずれにいたしましても非常に古い歴史をもつ、宗門の名刹でございます。 ところが、その古刹である当寺におきましても、その長い歴史の中においてはいろいろ な大難があったのであります。近いところでは、当寺の開基であられる日尊上人の終焉の 地である京都の要法寺の末寺とされるという、法難がありました。 この要法寺というのは、興門八箇本山(富士大石寺・北山本門寺・京都要法寺・伊豆実成寺・下条妙蓮寺・小泉久遠寺・保田妙本寺・西山本門寺)の内の一つでありますが、本来、その根本の意味から考えますならば、総本山である大石寺の末寺であるわけでございます。即ち、大聖人様の出世の御本懐であらせられる本門戒壇の大御本尊様は、大聖人より日興上人へ伝えられ、日興上人は日目上人へ、以来日道上人・日行上人へと伝えられまして末法万年にわたる広宣流布の基盤とされたのでありますが、その根本道場が大石寺でございますから、あくまで大石寺が総本山であり、他の七箇寺はすべて末寺となるわけであります。 そのような筋道は、宗門の根本の時代にあってはきちんと解っておったのでありますが、 時の流れに従っていろいろと社会の変動があり、あるいは魔縁の興盛等によりまして、い つしか根本の筋道を忘れてしまい、大石寺が総本寺であることを忘れて八箇本山のそれぞ れが、自分の寺が本寺である。との我見をもつようになってきたのであります。その辺の 経緯は今ここで簡単に申し述べられるものではありませんが、明治の時代を迎え、大石寺 を中心とする正法の僧俗は、いかに興門のなかではあっても、我見をもって正しいものを 認めない者達と一緒になっていては到底、正しい広宣流布はできない。というふうに考え まして、大石寺が独一の本寺として独立すべく官に請願を繰り返したのでありますが、当 時の法律によって、それは認められなかったのであります。しかし、それでも何回となく 請願を繰り返し、明治三十三年「一九〇〇)、ついに、日蓮宗富士派として、独立したの でございます。 そのときに、大石寺が独立したことを嫉んだ京都の要法寺が、いろいろな難題をふっか けてまいりました。その内の一つとして、この仏眼寺――あるいは近くにある日浄寺もそ うでありますが――について当寺は元々、日尊師が建てたものであるから要法寺の末寺 である。したがって即刻、寺を引き渡せと言ってきたのであります。そして、いろいろ な紆余曲折がありまして控訴審まで争いましたが、日尊師の開基である。ということもあって、遺憾ながら二回とも大石寺が敗れてしまったのであります。よって当仏眼寺は、大石寺の元を離れて要法寺の末寺となることで、法律的に決着が付いてしまったのでございます。 しかしながら、当時の住職であられた佐藤日照御能化――当寺の先々代の住職であり、 また現在の日浄寺住職・佐藤暢道師の御親父であられますが――は、法律的には完全に敗 れたにもかかわらず、強い信力をもって、門の所に陣取って対抗されたのであります。そ の時の因難は筆舌に尽くせぬ情況であったと承っておりますが、昭和十八年に――当時の 時局の進展に伴って制定された。宗教団体法の助けもあったようでありますが、要法寺 との紛争に一切の解決をつけて、大石寺の末寺として認められたのでございます。 これもひとえに、当時の檀信徒の皆様が――本日ここにおいでになっておられる方も多 多あろうかと思いますが――一致結束をして我々は大石寺が根本の本寺である。仏眼寺 が要法寺の末寺になるようなことは、絶対に承知できない。という大石寺に対する信仰と 団結の力、及び住職の強い信念によって勝つことができたのでありまして、その一致結束 しての力により、不当な判決をくつがえし、既に入っていた要法寺の僧侶を排除して、こ の仏眼寺を真の大石寺の末寺として、今日に在らしめたのでございます。 今日、仏法上の問題について官に提訴し、国法に解決を求めるというような者が宗門の 中にも出てきておりますが、この仏眼寺の例を引くまでもなく、仏法に逆らった、また仏 法を全く忘れたところの、謗法の見解でございます。 この、ただ今申し上げた事件は、たとえ法律(世法)がいかなる無法な形によってでも 勝つことがあっても、正しい信心があるならば必ずそれをくつがえし、本当の正しい勝利 がそこに表われるということの実証であると存ずる次第でございます。 本日御参詣の方の中には、昨今入信の方もありましょうからそういうことを御存知では ない方もあるかもしれませんが、この仏眼寺は長い歴史があるとともに、住職並びに檀信 徒の命懸けの信心によって正しく護られたのでありますから、その深い意義を忘れること なく、総本山大石寺を根本とし、戒壇の大御本尊様を根本とする信心を、どこまでも貫い ていっていただきたいと念願する次第でございます。 明年にはいよいよ七百御遠忌を迎えるのでありますから、いよいよ自行化他の信心修行 に邁進せられることを念願いたしまして、一言、本日のお祝いの言葉に代える次第でござ います。 おめでとうございました。 (文責在速記者) 今日、これを何故出したかと言うと、あるSNSサイトにて、日寛上人が天台を真似している。パクリだと騒いでるのがいた。 日蓮正宗大石寺の教義は、大聖人の時代から変わりありません。 変わって、おかしいならば古希の寺が沢山あるし、戦後に日蓮正宗の寺になった古希の寺は、沢山あります。 その現実の事からして、教義は全く変わってない。変わっておかしいならば、日蓮正宗になる必要も無いわけです。 ネットで騒いでるのは、北を南と言い。白を黒と言うような考えしか無い人たちである。 ようは、言っても無駄。ネットで騒ぎ現実に起きている事には、目を向けずひたすら、その狭い領域から出られない。世間知らずなのです。
2013.01.20
-
人生を優雅に飾る智慧の「慧」
幸せになるためには、正しい智慧である「慧」がなければいけません。智慧を得るためには、御本尊様に御題目を唱えることです。「戒」と「定」に依って得た、悪心の戒めと心の落ち着きを定めたことで、正しい智慧である「慧」を御本尊様から「以信代慧(いしんだいえ)」で頂くのであります。 御本尊様は三大秘法である「戒定慧の三学」です。我見や我欲によって筋が通らなければ御利益を頂くことが出来ません。御本尊様に間違った祈りを捧げても御利益は当然ありません。御利益は正しい信心によって現れます。 『御義口伝』に、 「一念三千も信の一字より起こり、三世諸仏の成道も信の一字より起こるなり。此の信の字は元品(がんぽん)の無明を切る所の利剣なり。其の故は、信は無疑曰信(むぎわっしん)とて疑惑を断破(だんぱ)する利剣なり。解とは智慧の異名なり。信は価の如く解は宝の如し。三世の諸仏の智慧をかうは信の一字なり。智慧とは南無妙法蓮華経なり。信は智慧の因にして名字即なり。信の外に解無く、解の外に信無し。信の一字を以て妙覚の種子と定めたり。今日蓮等の類南無妙法蓮華経と信受領納する故に無上宝聚(むじょうほうじゅ)不求自得(ふぐじとく)の大宝珠を得るなり。信は智慧の種なり、不信は堕獄の因なり」(御書1737) と仰せです。智慧を得るには「信」が大事であります。 智慧には、聞慧、思慧、修慧という三つの智慧があります。聞慧とは教えを聞くということです。聞いて考えるところに湧いてくる智慧が思慧です。更に御本尊様を受持信行して三大秘法の妙法の功徳が根本となり、顕れてくる智慧が修慧であります。 また「四智」があります。仏が具える四種の無漏智です。世間法に染まっていない智慧であります。唯識論で説く智慧と大智度論に説かれる智慧があります。天台大師は大智度論の四智を四仏知見に拝しています。 唯識で説く四智は、八識の大円鏡智・七識の平等性智・六識の妙観察智・五識の成所作智です。更に日蓮正宗では、九識で中道実相の真の智慧「法界体性智」があります。大智度論では、道智・道種智・一切智・一切種智を説きます。「本門の題目」が、最高の「慧」であり、御題目の南無妙法蓮華経を唱えることで最高の智慧を得ます。智慧は、疑うことなく御本尊様を信じることです。間違った我見や我欲を払拭させるところに、有り難い智慧が湧きます。 世の中には、邪な智慧を振り絞って生きている人がいます。善悪の判断力が出来ていないため、邪智による悪道を進むのであります。邪な智慧・邪智が不幸を生みます。頭の回転が好く閃き智慧が湧いても、善知識における智慧と悪知識における智慧があります。充分に識別し「戒」と「定」の意義を持って判断することが大事です。判断する大切なときが勤行唱題です。成仏は自分自身の邪智を止め、折伏でも邪智を止めることが大切です。 「戒定慧の三学」を具える三大秘法の御本尊様に御題目を唱えれば、正しい智慧が湧き生活を安穏にしていくのであり、それが平和と幸福に繋がります。その修行が寺院で行われる唱題行です。 【正林寺法華講員手引書】より http://blog.goo.ne.jp/shourinzi1972/e/1ec138ca0e3bdf94ba63f527ab512c8b
2013.01.20
-
創価学会脱会体験談。妙観講Tさんの体験談。
このブログにいろんな体験談を載せていこうと思います。現証にしかずですので、その体験談を沢山の方々に読んでもらいたいと思います。私は、小学生の時に創価学会に入信し、学会活動にのめり込むようになりました。 青年期は、地域の幹部として、また輸送班として、任務優先の生活をし、池田大作が書いたとされる書籍も全て読破しておりました。 ところが、昭和62年、『聖教新聞』を読んでいるうちに、学会内部で伝えられる池田大作像と、本物の池田大作は全く違う、ということに気づき、昭和63年初頭、創価学会の活動を全て停止しました。 当時は、創価学会が決定的に謗法化してしまう以前でしたので、私は、自分の判断に間違いないかを、自分なりに調べていきました。 ところが、その過程で、とんでもない慢心を起こしてしまったのです。 それは、「池田大作と直接会ったこともない私ですら、彼の本性がわかるのに、なぜ、猊下様は気づかないのだろう」というものでした。 後にして思えば、猊下様は深い御慈悲の上から創価学会を善導あそばされていたのですが、私は、そんなことにも気づかず、慢心の上から批判の心を懐いてしまったのです。 その後、創価学会が宗門への反逆を露わにしたことにより、平成3年1月、正式に創価学会を脱会して、正宗寺院に付いたものの、私の生命の底辺に、この大慢心が巣くっていたために、3回も勝手に所属寺院を移り変わる、という過(あやま)ちを犯してしまいました。 しかしながら、現在の講中において皆さんと接していくうちに、その純粋で求道心旺盛な姿に照らし、私は、自分の慢心した信仰姿勢を深く恥じ入るようになりました。 そして、ある勉強会で、御僧侶の尊さと重大な存在意義について学んだ時、私は、かつて自分の慢心から、猊下様や御僧侶に対して批判の心を懐いてしまった、それが謗法であることと、その罪の深さを思い知りました。 以来、毎日、朝夕の勤行の中で、その謗法を懺悔申し上げ、罪障消滅を願って折伏にも励みました。 折伏は、自らの悪業(あくごう)の深さゆえか、最初のうちこそなかなか成就しませんでしたが、発心から1年を経た頃から、毎月のように入信・帰伏する人が出るようになりました。 それに伴って生活上にも功徳が現われ、数年前に趣味を生かして立ち上げた事業が、一気に売上げ倍増したばかりか、思いがけず、ある貿易代行会社から要請が舞い込んできて、海外への輸出も始まったのです。 おかげで、この大不況の中にもかかわらず、経営も安定し、経済的にも時間的にもゆとりをもって信心活動に励める境遇となりました。 もっと自分にできる御奉公はないか、と考えた私は、創価学会の恐ろしい実態を広く社会に訴えるべく、平成22年、「創価学会脱会者を支援する会」を立ち上げ、街宣活動を始めることにしました。 創価学会の狂気の実態を思うと、非常に危険なことだとは思いましたが、かつて学会時代に誰よりも強く池田大作を宣揚(せんよう)してきた、その罪障を懺悔していくつもりで闘いを開始したのです。 都内や千葉県・埼玉県などで、スピーカーを取り付けた自家用車を走らせ、創価学会の悪行を訴えていくのですが、その街宣活動の反響は非常に大きなものがありました。 まず、創価学会に対して疑問を抱きつつも、誰にも相談できなかったという方達から、どんどん電話が入ってくるようになりました。 それと同時に、学会員からの妨害も半端ではありませんでした。 私の近所に怪文書が配布されたこともあります。 怪文書の内容は、 "Tは頭が狂って、ある特定の宗教団体(※学会とは書かないから笑止です)を批判するために街宣活動をしている" というものでした。 街宣カーとして使用している私の自家用車には「創価学会脱会者を支援する会」という看板を付けているにもかかわらず、姑息にも、怪文書中の写真では「創価学会」という名称が削られていました。 他にも、チンピラのような学会壮年部が私の車に体当たりしてきて街宣活動をやめさせようとしたり、 私の車に空き缶を投げつけたり、 学会女子部が狂ったように走行中の車の前に立ちはだかってきたり等々、 学会員の妨害行為を挙げたらキリがないほどです。 しかし、こうした妨害や嫌がらせは、最初から予測していたことです。 私は全く怯むことなく、信念として街宣活動を継続していきました。 すると、創価学会を脱会したい方、創価学会に対して危険な団体だと同調してくれる方がどんどん現われてくるようになり、その方達と個別に話していったところ、私の直接の折伏だけでも、一昨年は9名、昨年は7名の方が、勧誡・御授戒を受けることができました。 また、それ以外でも、この街宣活動がきっかけとなって帰伏する方が次々と現われ、その数は、これまでに20名を超えております。 今後も、迷える創価学会員を1人でも多く救い出し、登山ならびに総会には、さらに多くの人達の手を引いて集えるよう、全力で頑張っていく決意です。 http://sudati.iinaa.net/gensyo/escape.html#2 この方は、自分自身の慢心した心気づきました。よくネットで猊下の心を知らずに、猊下を誹謗するのがいます。猊下が悪い。教導していない等を言ってるのがおりますが、猊下の心を理解しようとせずに、自分自身の慢心した考え方で言ってるのです。自分自身で勝手に慢心してはならないのです。正しい仏法を学ぶには、血脈相承された御法主上人に従い信心していく事が、大切なのです。
2013.01.19
-
信心は所作仏事が大切
「所作仏事」とは、私達が朝夕の勤行で唱える『如来寿量品第十六』の経文です。私達の凡眼凡智では知ることの出来ない、仏様の御化導は五百塵点劫の大昔から一度も止まることなく続いています。仏様の振る舞いを真似ることが「所作仏事」であり、あらゆる人生の迷いを消滅させることが出来ます。 「所作仏事」とは、心の迷いや悩みを煩悩即菩提させる作法です。つまり、迷いや悩みを生む言動を止め、幸せになる言動を行い所作することです。末法の御本仏で在らせられる日蓮大聖人の御指南を拝し信心していくところに「所作仏事」があります。その時代々々で、背景が異なりますので、その時の御法主上人猊下の御指南に従って、その時代の「所作仏事」を行うことです。 「所作仏事」とは、「所作」が振る舞い・動作・所行のことで、能作に対する語です。能作は所作を発する身口意の三業です。「仏事」が仏の教化、法を弘める行為(弘法・弘通)と日蓮正宗の行事や御本尊様に御供養すること、御先祖様に追善供養することです。それらの所作と仏事を素直に行うことで成仏できます。 具体的な仏事を成す所作は、勤行唱題を基本とする御本尊様への御給仕や日蓮大聖人の教えを伝える折伏です。御本尊様が御安置される仏壇を常に綺麗にし、朝にはお水や御飯を供え御給仕をします。御本尊様への御給仕は、日蓮大聖人が生きておられることを心に思い浮かべることが大事です。御本尊様は生身の日蓮大聖人の御魂が墨に染め流されております。粗相のない様、丁重に御給仕することです。 この御本尊様への御給仕で身に付く作法が、成仏に繋がる振る舞い「所作仏事」です。御本尊様への御給仕で身に付けた作法を、御給仕だけに止めるのではなく、生活の場に広げることで落ち着いた行動がとれるようになります。その行動には「防非止悪」という非を防ぎ悪を止める働きがあり、煩悩の根源である貪瞋癡の三毒を静めます。更に成仏を妨げる作用を防ぎ「我此土安穏」な境界へと通じるものです。この振る舞いを一生涯全うすることで成仏が出来ます。 「所作仏事」が即折伏に繋がり、御本尊様の御利益により人々を成仏へと自然に導くことが出来ます。折伏での「所作仏事」とは、「不軽菩薩(ふきょうぼさつ)」の振る舞いを心がけることです。誹謗中傷・悪口罵詈を受けても同調せずに「忍辱の鎧」を着て振る舞うことが大事です。『崇峻天皇御書』に、 「不軽品にて候なり。不軽菩薩の人を敬ひしはいかなる事ぞ。教主釈尊の出世の本懐は人の振る舞ひにて候けるぞ」(御書1174) と仰せであり、『百六箇抄』に、 「今日蓮が修行は久遠名字の振る舞ひに介爾(けに)計(ばか)りも違はざるなり」(御書1695) と御指南の如く、日蓮大聖人の御修行は久遠の古仏の振る舞いです。一番はじめの仏様が「久遠の古仏」です。この「久遠の古仏」が中心となって、垂迹仏と言われる様々な仏様が居られます。私達も御先祖様を忘れてはいけないように、仏様の先祖「久遠の古仏」を忘れて他の仏様や神様を崇めていては本当の功徳を頂くことが出来ません。世間の多くの人は、この事を全く知りません。日蓮大聖人だけが仰せになることであり、日蓮正宗だけが世界で主張しているのです。そのため、他宗では成仏できないと折伏をし、布教しているのです。 その「久遠の古仏」の振る舞いが「所作仏事」であり、常日頃の御本尊様への御給仕もそうです。勤行唱題をして御題目を唱える姿も「所作仏事」であり、寺院参詣により自然と身に付いていきます。 【正林寺法華講員手引書】より http://blog.goo.ne.jp/shourinzi1972/e/a82562623f4f32f0e7c243f2866f7aa7
2013.01.19
-
結局は、人を見てグダグダ言ってるだけ
riricoさんのアメブロを見て思ったが、結局は人を見て言ってるだけである。このブログのS君は、口では浅井せんせ~を信じると言ってるだけで、大聖人の言葉。仏様の言葉を信じていない。結局は、人を信じてる。御書からして、浅井さんの指導は、間違ってるし、そもそも御書のどこに、在家の指導者に従えなんて、書いてあるのでしょうか?「凡(およ)そ謗法とは謗仏謗僧なり。三宝一体なる故なり」(新編六〇八頁)三宝つまり、仏宝日蓮大聖人、法宝戒壇の大御本尊、僧宝日興上人随一として、歴代御法主上人。となるのであるからして、在家の指導者が僧宝で無い。三宝一体故、顕正会や創価学会でも、仏法を知らない一般でも、日蓮正宗の三宝を誹謗する者らは、謗法である。1,一体三宝(内証) 末法出現の仏・法・僧は、内証においてはともに久遠元初の三宝であり、大御本尊と一体のものと拝する三宝。2,別体三宝(外用) 末法における仏宝は宗祖日蓮大聖人、法宝は本門戒壇の大御本尊、僧宝は唯授一人血脈付法の日興上人と、形式の上から立て分けて拝する三宝。3,住持三宝(化導) 文底下種の三宝を令法久住せしめ、末法万年の衆生を済度する意義から拝する三宝。歴代上人はすべて僧宝として尊信される。これが、理解されていない。日蓮正宗は、衣法不衣人とか言っていて人師がどうたら言っているのは、矛盾だ~と騒ぐのがいるが、三宝一体であるからして、住持三宝からして、法宝を受け継ぐ僧に従うのが正しい仏法である。それを知ったかぶったり、知らないくせに矛盾だと言ってるのは、単に習ひそこないの学者である。結局、顕正会も創価学会でも、騒いでるのは、自己中心的な考え方であり、正しい仏法を見ようとせずに、人がどうこうと騒ぐしか出来ないのです。如何に、法が正しく、法を教える僧が正しいかを見れないのである。
2013.01.18
-
法華講掲示板降魔の剣の洗脳学会員西村健一様を破します。。。
法華講掲示板は、沢山ありますが、洗脳されている学会員等沢山おり、とても不憫であり居た堪れません。海外で反発を受ける日蓮正宗 投稿者:西村健一投稿日:2013年 1月18日(金)04時14分1秒 p7024-ipngnfx01sasajima.aichi.ocn.ne.jp 返信・引用http://www.youtube.com/watch?v=23YvAJrc6vQアジアや南米の国からも反発を受けています。こんな書き込みがありました。アジアでの反発として、台湾のマスコミが報道しております。台湾のマスコミも日本のマスコミ同様であり、スキャンダルや鷽が、好きな様でして、学会との裁判をそのまま報道したに過ぎません。また、今その台湾では、法華講員は、二万人以上がおりますし、寺院も増えております。アルゼンチンについてですが、キリスト教圏内の国にての布教についてですが。実は、マザーテレサを破折した事が原因であります。大聖人様の時代から、現代に至るまで、邪宗破折して、難にあう事があります。大聖人様は、伊豆流罪や、佐渡流罪になりました。法華経にて、正法を広める者には、難に遭う事が説かれております。今の創価学会は、大聖人様の仰られた破邪顕正を忘れ、他宗教と仲良くすれば良いと思っている節があります。破邪顕正を日蓮正宗に向け、稚拙な内容でしか言えず、異質な宗教に陥っております。今、そのアルゼンチンですが、日蓮正宗の布教を許されおります。この西村健一様という学会員の方は、学会の報道を鵜呑みにし、恐らく、様々な事象を自ら検証しておらず、ただただ、ネットて燻っているのが現実であります私が、ここに書いたのが、事実だと言う証拠は、実際に大石寺に行かれてみれば分かると思います御開扉のある日等は、必ず様々な国々から遥々来られております二大法要では、多くの国々から海外信徒の方々が参加しております実際に足を運びましたらいろいろな事が分かりますし、学会等の報道は、真実では無いと白日の元に晒される事は一目瞭然です
2013.01.18
-
人生を忍ぶ大切さ(忍辱)
正林寺御住職指導(H16.4月 第3号) 法華講正林寺支部の皆様、年度も新しい四月になりました。気持ちも心機一転、変わる時期でしょう。 特に新しい生活を迎える方や新入社員の方と新入生には、仕事や学校に対し不安が生まれるものです。生活リズムが全く変わり、新しい生活リズムと新しい対人関係に慣れるまで不安があるでしょう。 不安を自分だけの重荷として抱えることなく、御本尊様に御題目を唱えて相談することが大切です。それが御本尊様の前に座る毎日の勤行唱題になり、自然と新しい生活の不安を取り除く方法になります。まず御本尊様に相談する習慣を毎日行うことからはじめましょう。 宗祖日蓮大聖人様は『法衣書』に、 「法華経には柔和忍辱衣と申して衣をこそ本とみへて候へ。又法華経の行者をば衣をもって覆はせ給ふと申すもねんごろなるぎなり」(新編御書一五四六) と仰せです。日蓮大聖人様は毎日の勤行唱題により、心の不安に負けない強靱な衣を着ることが出来ると御教示です。故に愚癡をいわず耐え忍ぶことであり、自分だけの力で不安に対し忍ぶことなく、御本尊様に相談し一緒に忍ぶことです。人生同じ耐え忍ぶにしても、相談相手なしに忍ぶより御本尊様という有難い仏様、相談者と一緒に忍ぶことで不安な人生も楽しく変わるはずであります。 新しい生活に慣れるまで大変ですが、御題目を唱えることを忘れず忍んで生活していきましょう。 以上、皆様の御精進を御本尊様に御祈念申し上げ、住職より四月度の挨拶とさせて頂きます。
2013.01.18
-
たとえ遠く離れてても。。。
この日記のTITLEは、Every Little Thingの1stAlbumに入っていた曲であり私の好きな曲の一つであります♪前置きは、さておき。。。信心に距離は関係ありません。。。どれほど離れていようとも、日蓮大聖人様を信じ南無妙法蓮華経と唱えるならば、直ちに戒壇の御本尊様:日蓮大聖人様に通じ、大功徳が頂けるのです。。。この台詞、何処で聞いた事ある方もおられるかと思いますが爆元顕正会員の方々は御存知かと思います。。。顕正会版の勤行要典の前書きに書いてありましたね。。。末寺の信徒の方々から口々に言われる事ですが。。。『本山所属ってスゴイ事だよ!!』『縁が無いと誰でも本山所属になれるものじゃないよ!!』等言われますが、それぞれの因縁や使命、背負ってる業により導き出された結果、今、在籍している、所属寺院に居るんですよ。。。宗教だけに限らず、今、現在、置かれてる環境や住まわれている場所には、メリット、デメリットの比率が違えどあると思います。。。端から見ました時、メリットしか見えてこず、いろいろ夢が広がり羨望感を抱くと思います。。。私達は生身の人間であり、霞だけ食し生きてはいけません。。。周りくどい言い方に感じるかもしれないですが。。。残念な事に苦笑私達はロボットやサイボーグではないですからね生活あっての信心ですから、やはりそれを見定め浮足立たぬよう、生きていけたらなと思います。。。本山の近くに住まなければ信心できないという謂われもありませんしね本山近くがどうと言うより、結局は、何処に住んでても同じですよ♪住まわれてる所の、県民性等、自分自身に合う合わないや、経済的な状況等、何処の土地でも、いろいろありますから。。。生きてたらいろいろな事がありますが、投げやりになり、自棄や無茶振りで、自分の人生をダメにして頂きたくはないなと思います。。。まずは足元を固め強い自分になっていく事が大事ですね
2013.01.17
-
人生の恥をかくす衣
正林寺御住職指導(H21.10月 第69号) 人生には失敗をして人にもいえない恥があるものです。失敗した経験が信心において御本尊へ御題目を唱えることで、今後の資糧となり無駄にはなりません。 日蓮大聖人は後生の恥をかくすための衣について『寂日房御書』には、 「法華経は後生のはぢをかくす衣なり。経に云はく『裸者の衣を得たるが如し』云云。此の御本尊こそ冥途のいしゃうなれ。よくよく信じ給ふべし。(御書1394) と仰せで法華経である御本尊が後生の恥をかくす有り難い衣となります。 大聖人が『寂日房御書』に恥をかくす衣について簡潔に「裸者の衣を得たるが如し」と仰せであり、裸の者が暑さ寒さをしのぐ衣服を得るようなものであると御教示です。 御書の「経に云はく」とは法華経『薬王菩薩本事品第二十三』に説かれる、 「如裸者得衣」(法華経535) とお示しの経文であります。 その衣とは法華経の精神にもなる『法師品第十』に、 「柔和忍辱衣」(法華経332) と説かれた、衣座室の三軌の一つである如来の衣を着る意味があります。 柔和忍辱衣について『法衣書』に、 「殊に法華経には柔和忍辱衣と申して衣をこそ本とみへて候へ。又法華経の行者をば衣をもって覆はせ給ふと申すもねんごろなるぎ(義)なり。」(御書1546) と御教示です。柔和忍辱の衣を着させていただくことで、人生の失敗や挫折などの恥をかくすことができると拝します。 さらに一生成仏において「此の御本尊こそ冥途のいしゃうなれ。よくよく信じ給ふべし。」と仰せのように臨終においては、今生でのあらゆる恥をすべてかくしていただける尊い御言葉です。
2013.01.17
-
総本山所属だと幸せなのかしら
実は、私は、総本山塔中寺院所属なんです。。。よく、『ひろし君の寺院は、日蓮正宗内でのブランド的な寺院だよね~』と、言われますが。。。総本山塔中寺院所属、特別布教区だからと言い、他寺院や布教区と何等変わりは、全くありません。。。総本山塔中だから、功徳がデカイとか?他布教区より、幸せになれるなんてありません。。。登山すれば、自分自身の所属寺院と比べてしまうからかもしれないですが、信心から見ましたら同じなんです。。。私は、地元寺院の方々と折伏もしますが、だからといっても、修行は同じです。。。隣の芝生は良く見えると言いますか。。。良く見えるのかもしれないですが、全然変わりは、ありません。。。ただ、私は今の寺院に縁をしただけです。。。信心は変わりありませんそれは、総本山で言うならば、理境坊でも百貫坊や石之坊でも、塔中寺院。西、東の塔中寺院。総坊でも、常来坊でも、信心では変わりありません。。。何処に所属しても、同じ日蓮正宗です。目標も、御命題も同じです。。。私達は、所属が何処だろうが、仏祖三宝尊に対して、きちんとした信仰を目指していかないといけないなと思います。。。
2013.01.16
-
消化不良を起こさない折伏を
化他行である折伏をするとき、相手の受け入れる気持ちを見失うと、消化不良を起こさせる結果になります。 一般的に消化不良を起こすという意味は、食べ物を食べて、消化が十分に行われない病症。疲労・運動不足・暴飲・暴食または不良消化物・腐敗物などの摂取によって起り、食欲減退、胃部の疼痛、または嘔吐・下痢などを発することです。 折伏において見た場合、消化不良を起こすとは、信心に対する理解が出来ないこと、こちら側の要求が高すぎて戸惑い、そこから信心に対し敬遠する気持ちを生むことです。消化不良を起こすということは、本来、幸せになり安穏になるはずが、反対の道をたどることでもあります。 特に消化不良を起こしやすい人は、信心に対して日の浅い人や、日頃、生活や仕事に追われ、熱心に信心修行をされない人に起こる可能性があります。折伏や法統相続などの教化育成にも、十分に起こりうる可能性を持ちます。 消化不良を起こすと、折伏がスムーズに行きません。勤行唱題によって、相手の取り巻く、環境や性格と機根を十分に見つめ、洞察力を身に付けることが大事でしょう。自己中心的な折伏になると、相手が消化不良を起こします。 これは折伏に於ける禁じ手であり、広布の道を閉ざす行為です。十分に誡め折伏することです。 相手が信心に対し、どれくらいのレベルに達しているのか、家庭訪問に於ける対話の中で掴むことです。そして、消化不良を起こさない折伏と教化育成は、慈悲と柔和な気持ちが大切です。貪瞋癡の三毒が、心の中で騒いでいるときは、心を静めてから、地涌の菩薩の自覚に立ち折伏をします。 私達の貪瞋癡の三毒が、原因となり、思わぬ災いを引き起こすことがあります。この三毒を悦び、混乱させる宗教団体が創価学会です。つまり師子身中の虫を操る能力に酔い楽しむ集団です。彼等の脳内に、快楽的な覚醒作用をもたらすため、非常に気分を良くするものですが、「喜ぶは天」というように、天界止まりの一時的な快楽で、命終には三界六道輪廻の法則により、地獄に堕ちるのです。このことに気付かず現状の安泰さに、正信が完全に麻痺しています。 消化不良を起こさない折伏には、「地道に焦らずコツコツ」という心構えが大切です。落ち着いて折伏教化育成を行い、御法主上人猊下が御指南される「一年に一人以上の折伏」を基本にします。その姿勢に、現実を冷静に明らかと見ていける、凡眼ではない、仏眼に通じる眼が御本尊様の力用で仏果を得ていくのです。その眼が生活の場に繁栄されることで、「我此土安穏」な境界を作り上げていけます。 更に「五義」という、教機時国教法流布の先後を、唱題根本に見つめることが大事です。それぞれの家庭において複雑な違いがあります。こちらの家庭には、効果のある話しでも、あちらの家庭には逆効果ということもあります。家族の中でも、また性格が異なります。この点を見逃すと消化不良を起こし、信心を敬遠する気持ちが生まれます。上手く飲み込み、消化できるように、難しい法門を噛み砕いて、教化育成することが重要です。 御住職様の御指導のもと、折伏教化育成を実行するところに、消化不良を起こさせない折伏が出来ます。 【正林寺法華講員手引書】より http://blog.goo.ne.jp/shourinzi1972/e/3e488cc2d957899a7688492ebbf4b7a4
2013.01.16
-
折伏が閉ざした人心の目を開く
日蓮大聖人は御書の中に『開目抄』を残されております。『開目抄』は、末法の迷える私達の、閉ざし盲目となった、心の目を開くために書き残されたのです。『開目抄』の「開」の字には、二意あり、一には障りとなるものを除く(所除)の義、二にはものを見る(所見)の義があります。 盲目とは、四種類あり、外典の人、爾前の人、迹門の人、脱益の人であります。 『開目抄』では、現代の人々が忘れかけている、主人や師匠と親に対する感謝の気持ちを強く訴えられています。この主師親の三徳を人々が忘れるために、世の中に不安定な状況を招き寄せることを仰せになられています。 主人や師匠と親のことを考えず、己自身のことしか考えない自己中心的な人々が現在氾濫しております。自己主張はある程度必要ですが、必要最低限度があります。この必要最低限度を心得なければ、人間関係に亀裂が生じ世間から孤立するのです。つまり主人や師匠と親との関係が悪くなります。正しい信心に付かないために受けた当然の果報です。自己中心的人格は、過去からの我慢偏執と正しい仏法を信じないところから来ています。 自己中心的な考えや我慢偏執により心の目が閉じています。折伏では開示悟入という、仏様が示された四仏知見を心得ていくことが大事です。閉ざした心の目を開く要素であります。『曽谷殿御返事』に、 「されば境と云ふは万法の体(たい)を云ひ、智と云ふは自体顕照の姿を云ふなり。而るに境の淵(ふち)ほとりなくふかき時は、智慧の水ながるヽ事つヽがなし。此の境智合しぬれば即身成仏するなり。法華以前の経は、境智各別にして、而も権教方便なるが故に成仏せず。今法華経にして境智一如(いちにょ)なる間、開示悟入(かいじごにゅう)の四仏知見(しぶっちけん)をさとりて成仏するなり」(御書1038) と仰せであります。折伏により相手の心を開いて上げ、歓喜をもたらす仏様の教えを示し、実際に信心を体験して悟りを得て、成仏という境界に入らせることが「開示悟入」であります。「開示悟入」は教化育成や法統相続にも大事な心がけになります。 心の目が閉じている原因には、いくつか考えられます。大まかに二つあります。一つは、先に上げた我慢偏執が強い人で、信心には全く興味がなく心に入れようとしない場合と、もう一つは外見では心の目が閉じているように見え、実は信心を心から求めている場合があります。この以上の二つを心得て折伏することです。 この外見では心の目が閉じているように見え、実は信心を心から求めている場合について考えてみましょう。比較的、我慢偏執が根強い方よりも折伏の成就に繋がります。信心を本当は求めているけれども、きっかけが掴めずに思い悩む人がいます。この思い悩みにも、二通りあります。日蓮正宗に全く縁していない人と、縁しているけれども信心に不安や戸惑いを感じている人がいます。 折伏は、まずこの戸惑いや悩みを取り除くことです。それを「抜苦与楽」といい、心の閉じた目を開くことに繋がります。いかに、この点を折伏では充実させるかに成就の鍵があります。人それぞれに機根である性格や価値観が違います。この違いを充分に勤行唱題で、個々の眼力を高め、明らかに折伏する相手の状況を把握することが大事です。自行化他で培われた状況判断が生活や仕事に必ず役立つはずです。それが命に刻まれた尊い功徳です。 一人でも多くの人を折伏で心の目を開かせましょう。心の目を開かせることが広宣流布に繋がります。 【正林寺法華講員手引書】より http://blog.goo.ne.jp/shourinzi1972/e/745949f771bb3d24e8a3b3693e6270ce
2013.01.15
-
七つの慢心を誡める信心(七慢)
正林寺御住職指導(H23.5月 第88号) 日蓮大聖人は慢心について『撰時抄』に、 「慢煩悩は七慢・九慢・八慢あり」(御書869) と仰せです。 仏教では「七慢」「八慢」「九慢」と慢心について説かれています。「七慢」とは七つの慢心をいい、慢心とは、他をあなどる心、自ら驕り高ぶる心をいいます。「七慢」とは、慢・過慢・慢過慢・我慢・増上慢・卑慢・邪慢をいい、『倶舎論』や『品類足論』などに説かれています。 一番目の「慢」は、自分より劣った者に対して「自分は優れている」と自負し、同等の者に対しては「同等である」と心を高ぶらせることをいいます。 二番目の「過慢」は、自分と同等である者に対して「自分の方が優れている」と思い高ぶり、自分より優れている者には「同等である」と侮ることをいいます。 三番目の「慢過慢」は、自分より優れている者に対し「自分の方が優れている」と自惚れて、他を見下すことをいいます。 四番目の「我慢」は、今では「耐え忍ぶ」というような意味で使われていますが、仏法本来の意味は、自我に執着し、我尊しと自惚れ、それを恃むことです。 五番目の「増上慢」は、未だ悟りを得ていないのに、「自分は悟った」と思うことをいいます。 六番目の「卑慢」は、自分よりはるかに優れている者に対して、「自分は少ししか劣っていない」と思うことです。 七番目の「邪慢」は、自分に徳がないのにも関わらず、あると思い「自分は偉い」と誇ることをいいます。 慢心を起こさないように、常に題目を唱えつつ、自分の信心生活を謙虚に反省していくことが成仏には大切でしょう。
2013.01.14
-
正信会から宗門に復帰された御僧侶
白蓮院 元主管古谷得純御尊師 宗務広報 923号 平成14年12月9日 白蓮院(東京都江戸川区)、宗門へ復帰 本日、これまでいわゆる正信会僧侶により不法占拠されていた白蓮院(東京都江戸川区)が20年ぶりに宗門に返還されました。 これは、同教会元主管・古谷得純が、御法主日顕上人に対し奉り、本宗の教義及び信仰の根幹である血脈相承を否定して管長を誹毀讒謗したことを猛省し、 深くお詫び申し上げたうえ、返還に及んだものです。 同人は、昭和57年2月5日付の擯斥処分が有効であって、現在は白蓮院主管の地位にないことを認め、秋元広学渉外部長の立ち会いの下、 兼務主管・梶原慈文師に同教会およびその財産一切を引渡しました。 なお、本日付で新たに夏井育道師が主管に任命され赴任しました。今後、同師が白蓮院主管として職務を執行してまいります。 以上 古谷得純御尊師は初代主管・観法院日健贈上人の第27回忌に当たる平成14年(2002年)11月27日に返還を申し出られたとのことです。 現在古谷得純御尊師は東京第一布教区に所属する無任所教師として余生を送られています。 ■■■■■■■■■■ 妙徳寺 元住職真下昭道御尊師 宗務広報 815号 平成11年11月26日 妙徳寺(四日市市)、宗門へ返還 去る11月1日、これまでいわゆる正信会の者に不法に占拠されていた四日市市の法宣山妙徳寺が17年ぶりに宗門に返還されました。 これは、同寺元住職・真下昭道が、本宗の教義及び信仰の根幹をなす金口嫡々唯授一人の血脈相承を否定する異説を唱え、管長に対し誹毀讒謗をしたことについて、 前非を悔いてお詫び申し上げたいと申し出たものであります。 同人は、昭和57年9月16日付の擯斥処分が有効であること、したがって、同寺の占有権限のないことを認め、宗務院の早瀬庶務部長・秋元渉外部長の立ち会いのもと、 同寺兼務住職・福家重道師に対し同寺を明け渡したものです。 なお、住職は、11月22日付をもって福家重道師から豊田陽道師に交替になり、今後は、豊田陽道師が同寺の住職として職務を執行してまいります。 以上 真下昭道御尊師は、退去後、親族の日蓮正宗御僧侶のもとで謹慎しておられましたが、謹慎が解けないまま逝去されました。 しかし、日顕上人の大慈大悲により、日蓮正宗の僧侶として葬儀が執行され、霊山に旅立たれました。 ■■■■■■■■■■ 専唱寺 元住職岩切寿英御尊師 宗務広報464号 昭和63年6月3日 専唱寺(宮崎市)、宗門へ返還される 去る5月24日、これまでいわゆる正信会の者に不法占拠されていた宮崎市の本地山専唱寺が6年ぶりに宗門側に返還されました。 これは、同寺元住職岩切寿英が、本宗の教義及び信仰の根幹をなす金口嫡々唯授一人の血脈相承を否定する異説を唱え、管長に対し誹毀讒謗をしたことについて前非を悔いてお詫び申し上げたいと申し出たものであります。 同人は、御法主上人猊下に対する代表役員等地位不存在確認請求訴訟(現在最高裁に係属中)を取り下げるとともに、昭和57年8月21日付の擯斥処分が有効であること、したがって同寺の占有権限のないことを認め、宗務院の秋元渉外部長の立ち会いのもと、同寺兼務住職長岡錬道師に対し同寺を明け渡したものです。 なお、兼務住職は、同日付をもって長岡錬道師から岩切智順師に交替になり、今後は、岩切智順師が同寺の兼務住職として職務を執行してまいりますが、当面同寺は、佛知寺墓地管理事務のみを取り扱ってまいりますので御了承下さい。 以上 元住職岩切寿英御尊師は上記原田篤道御尊師の項目で取り上げたように、平成2年(1990年)12月17日に特赦により日蓮正宗の僧籍を回復しました。 その後、岩切寿英御尊師は平成6年(1994年)に岐阜県大垣市の経説寺住職に就任し現在に至っています。 専唱寺は一旦廃寺になっていましたが、平成13年(2001年)10月10日に再興され、宗教活動が再開されました。 ■■■■■■■■■■ 遠信寺 元住職原田篤道御尊師 宗務広報 430号 昭和61年11月19日 遠信寺(袋井市)、宗門へ返還される 去る11月17日、これまでいわゆる正信会の者に占拠されていた静岡県袋井市の新池山遠信寺が4年ぶりに宗門側に返還されました。 これは、同寺元住職原田篤道の申し出によるもので、同人は、昭和57年9月16日付の擯斥処分が有効であること、したがって同寺の占有権限のないことを認め、 宗務院秋元渉外部長の立ち会いのもと、同寺兼務住職高野千道師に対し同寺を明け渡したものです。 これに伴い、原田篤道は、御法主上人猊下に対する代表役員等地位不存在確認請求訴訟(現在最高裁に係属中)及び遠信寺に対する地位確認請求訴訟(静岡地裁)を取り下げ、 遠信寺側も建物明け渡しの目的を達したため、原田篤道に対する建物明渡請求訴訟(静岡地裁)を取り下げました。 なお、同寺は兼務住職高野千道師が占有管理をして行きますが、当面同寺における宗教活動は行ないませんので御了承下さい。 以上 正信会側は原田篤道師が「出奔」し、遠信寺がバリケードで封鎖されたと継命昭和61年12月1日号で報道しています。 その後、遠信寺は袋井市から掛川市に昭和63年(1988年)1月11日に移転し、宗教活動が再開されました。 その後平成2年(1990年)12月17日に原田篤道御尊師は特赦により僧籍を回復し、平成6年(1994年)4月に花巻市法王寺住職に就任され現在に至っています。 参考資料:平成3年(1991年)1月6日教師指導会 また、正信会の僧侶が許されたのか、今後も許されるのか、という質問があります。この件について申し上げます。 元正信会に属していた岩切寿英と原田篤道の二人が、三年から四年くらい前に、自らの非を認め、心から反省懺悔して、不法占拠していた寺院を明け渡し、在家として陰ながら寺院の仕事を手伝い、謹慎生活を続けて今日まで勤めてまいりました。この様子を御法主上人猊下がお聞きになり、開創700年という慶祝の年に当たって、本人が心から前非を悔い、反省し、また、許されるなら是非、僧侶に復帰を願っている、という心を御覧あそばされて、大慈大悲を賜り、必要な手続きを経て、12月17日、特赦の措置をとられたのであります。二人とも、来る1月11日から、白衣小僧として当分の間、大坊に在勤修行の上、末寺へ所化として数年間在勤し、しかるのち、元の僧階に復帰を許されるという予定になっておりますので、皆様方にはよろしく御理解の上、もし本人にお会いの節は、暖かく励ましていただきたいことをお願いいたします。 参考資料:優良運転手として表彰された原田篤道師 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/citizen/c-matsuzono/resources/1257817217451.pdf 私が住む茨城にも、正信会の寺院がつくば市と龍ケ崎市にあります。。。 私が、顕正会員だった時に、つくば市の本修寺に行った事がありました。。。 全く正信会の事を知らずに行ったのですが、この本修寺の僧侶の話しから、顕正会がおかしいという事が分かりしました。。。 法華講員になってから、この僧侶に日蓮正宗が正しいという事を話しましたが、 全く話しになりませんでした。。。 歳からか?耄碌したな~と感じました。 今、この正信会の僧侶は、 茨城県つくばみらい市に新たな寺院を建立した。。。 地元法華講の方と行ったのですが、 日蓮正宗の寺院の板本尊と全く違った本尊と、 本尊の前に大聖人の人形が?がありました。。。 正信会も、学会同様に自らニセ本尊を作るようになり 本修寺は、そこの僧侶が亡くなりましたら、日蓮正宗に復帰となりますが、 つくばみらい市の寺院は、残ります。。。 私達が、祈り思う事は、この日蓮正宗に復帰した御僧侶の方々の様に、 自らの誤りを認め、早く日蓮正宗の正しい信心を取り戻して頂きたいと願うばかりです…
2013.01.14
-
折伏で話術が磨かれる
信心をしていない人でも、話が上手く話術に勝れている人がいます。末法時代には、邪な能力が勝れ邪智に秀でた人が生まれるときです。邪智に長けている人は、信心から見た場合、「三類の強敵」や「第六天の魔王の眷属」、「悪鬼入其身」した人が、邪智に満ちた話術に長けている人に当てはまります。 日蓮正宗の信心でいう折伏は、邪智に依る話術を振りかざすものではありません。御本尊様から功徳を頂き「六根清浄」となる、身口意の三業の上から話術を磨いていきます。邪な自分自身の立場を正当化するために弁護をするような、浅はかな話術を身に付けるものではありません。邪智に勝れた話術を身に付けている人は、大概、自己保身のためや名聞名利を磨くものであります。日蓮正宗における話術は、「慈悲心」が根底にあります。 折伏で話術が磨かれるということは、話し上手になることであり、人見知りをする人や対人恐怖症に悩んでいる人の心を開く道であります。折伏をすることで、人と触れる事への恐怖心を取り除き、人との繋がりが、対話することで楽しさを感じ、同時に話術を磨いていきます。話術を磨くには、特別緊張することではなく、気持ちを落ち着けリラックスした感じが大切です。御本尊様から頂いた「歓喜」の気持ちをもって接していくことです。その土台となるものが「唱題」です。 折伏する相手の選び方は、気持ちが分かり合える人を選択しましょう。気持ちが全く分からない人とは、話が上手くいかず折伏になりませんし、話しづらくなり先に進みません。また水掛け論や平行線を辿(たど)るだけで、進歩がありません。『報恩抄送文』に、 「親疎(しんそ)と無く法門と申すは心に入れぬ人にはいはぬ事にて候ぞ、御心得候へ」(御書1037) と御教示のように、法門といわれる日蓮正宗の仏法を聞き入れそうにない人には、話さない方がよい場合があります。この御書の意味は、妄りに法門を説いてはいけないという御指南と、非常に大切な御法門は、親しい人、疎遠になっている人に関係なく、理解しない人には話していけないということです。 話術の秘訣は、話すタイミングを見逃さないことです。相手が呼吸をする息付く時が、こちらのペースに持っていくチャンスです。相手の話が途切れる合間と呼吸する時を巧みに活用しましょう。相手の雰囲気やペースに振り回されないことが大事です。相手のペースに入りますと折伏は成就しません。自分のペースに相手の気持ちを持っていくことが大切です。そこに私達の信心を理解してくれる考えが芽生え、同情心が生まれ、相手が信心をしなければいけないと発心するのであり、そこには動執生疑もあります。 話術で大切なことが、「情熱」と「勢い」です。棒線一方な緩急がなく、心を動かさない口調ではいけません。相手の気持ちが動き感動を覚え、心に一生涯残るような話題を提供することが大事です。そして言動である振る舞いが重要になります。話の内容が素晴らしいものであっても、振る舞いが内容の偉大さを下げるようであっては折伏が成就しません。話術には、振る舞いというジェスチャーも重要な働きをします。 もし、話しが下手であっても、勤行唱題を怠ることがなければ、御本尊様が自然と話術が上手くなるように導いて下さいます。自信を持って折伏するところに、邪智による話術ではなく、本当の慈悲に満ちた話術が磨かれていきます。 【正林寺法華講員手引書】より http://blog.goo.ne.jp/shourinzi1972/e/573bd5258ff7a1cbd327d903c3675d8f
2013.01.13
-
当世の習ひそこないの学者
大聖人様は、この 「一念三千の法門をふりすすぎたてたるは大曼荼羅なり」 という御法門について、 「当世の習ひそこないの学者ゆめにもしらる 法門なり」とおっしゃっております。 つまり頭だけで理解しようとしても、ここのところはどうしても解らないのです。たしかに御法門というのは難しいところもあります。 けれども、大聖人様の仏法を正しく拝していくときには何が一番大事かと言えば、 「日蓮大聖人様は久遠元初の仏様なのだ」ということを頭のなかに植えつけることです。その上で御書を拝読し、法華経や一切経を読めばいいのです。ただ頭だけで勉強をしていこうとすると、身延派などの人達と同じように、同じ御書や法華経を読んでいるのに狂ってしまい、大聖人様の本当のお姿が解らないで、日蓮大菩薩などと言い出してしまうのです。 我々は末法の凡夫ですから、まずそこのところをしっかりと頭のなかに入れてしまうことが大事です。その上で御書を読んでごらんなさい。よく理解できるはずです。それが身延派の学者達のように、たとえ一生懸命に勉強したとしても、大聖人様が御本仏であられるという ことが解らないと、大聖人様は菩薩だということになってしまうので す。ですから、この根本のところをしっかりと頭のなかに収めていけ ばいいのです。難しいようだけれども、実は少しも難しくないのです。 ここが御法門を学ぶときの非常に大事なポイントなのです。 にもかかわらず、「当世の習ひそこないの学者」は理だけに走ってしまって、根本のところが解らないからおかしくなってしまうのです。 平成20年。夏期講習会日如上人御講義より。
2013.01.12
-
【折伏における話術の要諦】共感的理解
恋愛マスターの僕から言わせて貰います!! 一方的な押したり引いたりも 一方的な押しっぱなしも恋愛に限らず折伏は上手くいかないです~(*´Д`)=з 相手の気持ちを汲み取り、自ら動くことで理解したいという思いもつ事で結果は自ずと変わってきます… 焦らず気長にやっていきましょう♪ 【折伏における話術の要諦】 話術の要諦は、自分自身の感情をコントロールすることがまず大事です。感情を律することが出来れば、自分自身の悩みや迷いである煩悩を操ることが出来ることに繋がります。つまり「煩悩即菩提」を身口意の三業に振る舞うことが出来るわけです。折伏をするところに自然と成仏するために大事な修行があり、それが日蓮正宗の折伏です。 更に話術の要諦には、話すと同時に相手の心の状態を観察する余裕が必要です。心の状態を無視しては、相手を納得させる折伏は到底出来ません。微妙な心理状態を察することが出来るように、日々勤行唱題で磨くことです。この相手の微妙に動く心理には、赤子を育てるように扱うことが大事です。この育て扱うことが、法統相続に生きてきます。こちらの一方的な振る舞いでは、相手の微妙な心を読みとることは出来ません。自分の感情に相手も反応しますので、その点も考慮して己の言動を、巧みに相手の心理や感情に響かせていきます。上手に誘導しながら、こちら側の雰囲気に包み込んでいきます。この時、三悪道から来る言動は厳に慎みましょう。三悪道の命は、相手も敏感に反応し、感応して地獄餓鬼畜生の気持ちになります。 次に、受け止める人にも依りますが、「声の質」が重要です。話の内容よりも「声の質」に説得させる力があります。また「声の質」だけでもいけませんが、日蓮大聖人の説かれる教えの素晴らしさと、相手の心を動かす「声の質」をもつことです。「声の質」とは具体的に、一つは相手に聞き心地の好い、心が安らぐ安心感を施すことが出来る「声の質」です。女性的な「声の質」が時として絶大な効果を発揮します。人間は本能的に女性的な柔らかい声を聞くと、気持ちが緩みます。まず、ここに動執生疑を生む要素が含まれます。この「声の質」を活用できるのは一部の人に限られます。 折伏における話術は、長所を生かすことが大切です。男性的な「声の質」であれば、謗法厳戒という、謗法に対する行為に怒りの命を持って謗法を責めることです。けじめを付けて瞋の気持ちを持ち、叱りつけることに絶大な効果があります。このけじめを付けず、感情任せに叱りつけると距離を置いて付き合われてしまいます。この点を注意して「瞋は地獄」の感情を巧みに活用することです。普段は、柔和な振る舞いで相手の心を和(なご)ませ、いざ烈火の如く、仏・菩薩界に具わる地獄界の命を以って、謗法に対し瞋の気持ちを現すと、動執生疑を起こすことがあります。普段からの何気ない言動には、すでに折伏への意味が含まれています。 日蓮大聖人の教えを説く以外も間接的に折伏が行われています。つまり「所作仏事」です。 相手との共通の話題を持つことも必要です。そこから何かが見えるはずです。趣味や仕事、家庭における様々な悩み、子育てやお姑さんとの関係、共通する話題があれば、特別に話術がなくても、自然と上手な話し、会話が出来るものです。この長所を生かすことが、折伏における話術に欠かせません。共通の話題を持つことは誰にでもできます。そして自信を持って対話をすることです。御本尊様を信じて御題目を唱えれば必ず折伏は成就します。焦らず地道に、御法主上人猊下の御指南「一年に一人以上の折伏」を心がけましょう。 【正林寺法華講員手引書】より http://blog.goo.ne.jp/shourinzi1972/e/527f5eccf09a56e4ce945c682ea220de
2013.01.12
-
正法を誹謗した人間は必ず「十五の悪相」を現じ、無間地獄に堕す。
死後の世界は必ずある。 阿闍世王が釈尊に質問をしたというのです。「仏様、あなたの言われるとおりなら、悪衆生は死後、地獄に堕ちるわけですが、どうして、それを知ることができるのでしょうか。誰か、見てきた人でもいるのでしょうか。また、死後に餓鬼界や畜生界に堕ちる、あるいは人界や天界の衆生として生ずる、ということを、どうして知ることができるのでしょうか。誰か、見てきた人がいるのでしょうか」と。 これは今日においても、世間の謗法の人々を折伏した時に、往々にして出る質問であります。「死んだ後のことなど、どうして分かるのか」「死んで帰ってきた人はいない、誰が見てきたのか」等という質問がそれです。 これに対し、釈尊は「よく聞きなさい。わかるように説明してあげるから」と言われて、臨終の相に差別があることを説かれています。 すなわち、「人が命を終えて地獄に堕ちた場合には、15種類の相が顕われる。餓鬼界には8種類、畜生界には5種類、人界・天界にはそれぞれ10種類の相がある。だから、臨終において、15種類の地獄の相が顕われたなら、その人は地獄に堕ちたのである」と仰せられたのです。 何故、このように臨終の相に違いが顕われるのか、といいますと、生と死の境である臨終は、一生の総決算であるとともに、死へのスタートです。それ故、臨終の相には、その人が生前、どういう生き方をしてきたのか、死後、その生命がどうなってしまうのか、ということが如実に顕われるのであります。 もし臨終において、皆、同じ相になって差別がなかったなら、死後に成仏や堕地獄という差別がある、といっても信じられないかもしれません。ところが、臨終の相には厳然たる違いがあって、正法を信仰して成仏した人は成仏の相、謗法を犯した人は地獄の相になって、亡くなるのです。 つまり、死後の命に差別があるからこそ、その違いが臨終の相に顕われてくるのである、と釈尊は示されたのです。 では、地獄に堕ちた場合の15の相とはどのようなものか、一つずつ見ていきましょう。 「一には、自らの夫妻・男女・眷属において悪眼をもって瞻視す」ーー集まってきた家族などを険しい目つきで見上げる。臨終の時には、すでに地獄の苦しみが始まっていますので、恐怖と苦しみのあまり、黒目が上を向いて、険しい目つきとなってしまうのです。 「二には、その両手を挙げて虚空を捫す」ーー悶絶して、手で空を掴む。 「三には、善知識の教に相い随順せず」ーー臨終に至ってなお、成仏の法に従おうとしない。周囲でお題目を唱えるように言っても、嫌だといって従わない、という姿です。 「四には、非号啼泣嗚咽して涙を流す」ーー狂乱して泣き叫び、嗚咽して、涙を流す。 「五には、大小便利を覚せず知ぜず」ーー本人の意志と関係なく、大小便が垂れ流しになる。 「六には、目を閉じて開かず」ーー苦しみのあまり、固く目を閉じてしまう。 「七には、常に頭面を覆う」ーー苦しみのあまり、手で顔面をかきむしったり覆ったりする。 「八には、側に臥して飲す」ーー倒れたまま飲み食らう。本当に、喉が渇いたり、お腹が空いたというのでなく、神経に異常をきたして、手あたり次第に飲み食いする、という状態です。 「九には、身口臭穢なり」ーー身体が腐って、口や皮膚の毛穴から腐敗臭が出てくる。これは、医療に従事している人からよく聞く話です。たとえば、癌の患者が亡くなる時などは、生きているうちから凄まじい臭いが出て、病室の前を通っただけで、身体に臭いが移ってしまうことさえあるそうです。 また生前に限らず、臨終の後においても、腐敗臭を放つのは地獄に堕ちた相です。現代では、遺体をドライアイスで凍らせた上、棺に消臭剤を入れたりして、腐敗臭を防いでいますが、この経典の説かれた3千年前には、ドライアイスも消臭剤もありません。ですから、そのような処置は取らない、遺体を自然のままにしておく、ということを前提にして、腐敗臭が出てくるのは地獄に堕ちた姿だというのです。 「十には、脚膝戦掉す」ーー恐怖のために、足や膝が震えてしまう。臨終は生と死の境ですから、臨終が近付いてくると、死後の恐ろしい地獄の苦を感じ始めるため、恐怖して震えだすのです。 「十一には、鼻梁欹側す」ーー鼻筋が曲がって、生前と全く人相が変わり悪相となってしまう。まるで般若の面でも被せたような相に変貌してしまうこともあります。 「十二には、左眼動す」ーー黒目が完全に横にいって、白目がむき出しになってしまう。 「十三には、両目変じて赤し」ーー両目が真っ赤に血走ってしまう。 「十四には、面を仆して臥す」ーー苦しみのあまり、顔を枕に臥して悶絶し息絶える。 「十五には、身を屈めて左の脇を地に著けて臥す」ーー苦しみのあまり、身体をエビのように屈め、横になったまま息を引き取る。 釈尊は、この15の相を挙げて、「もし臨終に臨んで、これに該当する姿が顕われたなら、その人は間違いなく無間地獄に堕ちたものと知りなさい」と説かれました。
2013.01.11
-
「紲」其の二
ています。 この御文の前段には、大聖人様御自身が、竜ノロの死罪、伊豆・佐渡の流罪は過去世からの宿業であり、過去の重罪が今生の信心により軽く現れたものと示され、その中で、涅槃経に説かれる例えを引かれています。 経文は大変長いので通釈すると、 「身寄りも助ける人も住む家もなく、病と飢えに苦しむ貧しい女性がほうぼう回ってようやく泊めてくれる家を見つけました。しかし、そこで女性は子供を産んだので、迷惑がった主人に追い出されました。 女性は生後間もないその子を抱いて余所の国を目指しました。道中は、暴風雨や寒さが襲い、蚊やアブ、蜂、毒虫などに狙われる大変なものでしたが歩き続け、大きな河にぶつかりました。 河を渡らなければ目指す国に辿り着けないので、子供を抱いて渡りましたが、河の水はとても急で流されてしまいました。女性は必至に子供を抱き、離さなかったのですが、急流に呑まれてついに母子共に河に沈んでしまいました。 しかし、どんな大変な状況でも子供を守ろうとした慈恵の功徳によって、女性は命終の後、梵天に生じた」というものです。 釈尊は続けて、文殊師利菩薩に対し 「正法を護ろうとするならば、貧女が恒河に在って子供を愛念するあまり身命を賭した如くしなさい。 そうすれば、貧女が、自分は子供を守りたいだけで、天に生じたいなど願わずとも梵天に生じたように、解脱を求めずとも得られる」 と仰せられています。 このお経文を大聖人様は御白身に当てられて、貧しいとは法財(正法の信によって積んだ功徳)がないこと、女性とは少し慈悲のある者、客舎とは娑婆世界、子供とは法華経の信心・了因の子、追い出されるとは流罪、産後間もないとは信仰して間がないこと、悪風とは流罪の勅宣、蚊虻とは無智な人に悪口を言われること、母子共に水に没するとは、最後まで法華経の信心を捨てずに頭を刎ねられたこと、梵天に生ずるとは仏界に生ずること、と示されています。 因みに最初の、貧女が病や飢えに苦しむとは、自らの罪障に苦しむことです。 大聖人様御自身は、御本仏としてのお振る舞いですから、罪障などあるはずもないのですが、もったいなくも示同凡夫の上から御身に当てられて仰せられるのは「私もそうだから、お前達もいちいち疑わずに、真っ直ぐ精進しなさい」と、弟子檀越の信仰の指針を定められたものと拝せられます。それは、法難をはじめとして、何かあると不信を抱く人が、大聖人様御在世中にも沢山いたということです。 我が慈本寺の講中の方を見ますと、皆さんそれぞれに悩みがあり、次々と起こる諸問題にも、「なんでこうなるの?」という疑問を信心で飲み込んで、必死に信行に励まれています。 とにかく、御題目を唱えて一歩一歩階段を登るように、障害を乗り越え、そして、現在は幸せであり、それが御本尊様のお陰、さらに、その恩返しをしたいと決意されている方もおります。 まさに「諸難ありとも疑ふ心なくば、自然に仏界にいたるべし」との、大聖人様の仰せのままの心持ちです。 大聖人は、『南条殿女房御返事』にて 『夫れ水は寒(さむさ)積れば氷と為る・雪は年累(かさな)つて水精と為る・悪積れば地獄となる・善積れば仏となる・女人は嫉妬かさなれば毒蛇となる。』(新編一二二七頁) と女性の業の深さを述べられていますが、一方で、 『この法華経のみに、「この経を受持する女性は、他の一切の女性に優れるだけでなく、一切の男性をも超えている」と説かれています。所詮、たとえ一切の人々に悪く言われたとしても、女性にとっては、最愛の人と思う男性に愛おしく思われる事を超える喜びはないでしょう。それと同様に、一切の人が憎むならば憎めばよい。釈迦仏・多宝仏・十方の諸仏をはじめとして、梵天・帝釈・日天・月天等にさえ愛おしく思っていただけるならば、何の不足がありましょうか。法華経(御本尊様)にさえ、誉めていただけるならば、何の不足がありましょうか。』(四条金吾女房御返事 新編七五六頁 取意) と仰せであります。 これほど有り難く、心強い御指南はありません。この御文は、もちろん男性にも通じます。正法を信受している我々は、常に御本尊様に護られているのです。 最近よく使われる言葉に「勝ち組・負け組」があります。色んな場合に使われています。例えば、年収であったり、正社員かどうか、結婚しているかどうか、子供がいるかどうかなどです。 人をこういう些末なことで線引きすること自体、おかしいのですが、私達は目先の損得や条件より、大切なものがある事を知っています。ですから我々は「勝ち組か 負け組か」と言われれば、勝ち組です。 しかも、広大無辺なる御本尊様の功徳に浴し、過去の先祖も救い・現在の罪障も消滅させ、来世は善処(ぜんしょ)に生まれると約束されていますので、これほどの勝ち組はおりません。 大聖人様は『上野殿御消息』に 「我より劣りたらん人をば我が子の如く思ひて一切あはれみ慈悲あるべし」(新編九二二頁) と仰せです。 自分が唯一最高の仏法にめぐり会って、幸せへの道を知ったのであれば、他の人へも自分の子の様に思い、教えて共に幸せになっていこうと願っていくべきで 正しく唱題を重ねると、まさに妙法の不思議なはたらきによって、自他の幸福の実現のために祈れるようになり、慈悲の心が生じてきます。 そうなると、先程から言われている日如上人の御指南を素直に拝する事が出来、自然と御命題達成へと体が動いて行けると思います。 どうか、本日参詣の皆様には、この推進会でお話し下さった体験発表・指導の数々を胸に刻んでご精進されますことを心よりお祈り申し上げ、本日の話とさせていただきます。
2013.01.11
-
紲 其の一
きずな [絆・紲]とは… 【断ちがたい人と人との結びつき】の事を言います… 人は決して一人では生きていけません… お互いを理解し合い、共感しながら築いていけるものだと思います… 「絆」は今でこそ、良い意味で人々が口にし、活字に躍っていますが、 原意は、あまり良いイメージはありませんでした… 動物をつなぎ止める綱のことを意味します。「ほだし」とも読み、自由を縛る意味が強かったのです…。 日蓮大聖人は「絆」と同じ意味の「紲」の字を用い、 「生死の紲を切る可し」と、生死への執着を断ち切り、妙法に生き抜くよう仰せになっております… 時代を経て、次第に、人と人との麗しい結びつきの方が強調されるようになりました…。 「束縛」から「連帯」へ――そこには、人間性の光を勝ち取った先人の歴史が垣間見えるようです… 日蓮正宗法華講慈本寺支部/婦人部 婦人部 婦人部広布推進の砌 慈本寺御住職 『「女人となることは、夫にしたがって夫をしたがえる身となることになります』 http://www.jihonji.net/fujinbu.html ~より~ みなさん こんにちは。慈本寺の小橋道芳と申します。 四月とは思えないような気候ではありますが、このように会場は、華やかでかつ熱気に包まれた中、婦人部広布推進会が盛大に開催されましたこと、誠におめでとうございます。 実は、私にとりましてこの広布推進会でお話しさせて頂きますことは、非常に有り難いことではありますが、一年で最も緊張する日であります。 それは、大勢の御信徒の前でお話しさせて頂くことに不慣れという事もありますが、それ以上に、この東京第二教区の御住職方は、宗内でも第一線で多方面にわたって御活躍されている蒼々たる方々だからです。 有り難いことに、教区の御住職様方と先日お会いしましたら、「今度の推進会で話すんだって。原稿は出来てるの?」とか「婦人部の方にお話するのは難しいよ~」と気にかけて頂きました。 私が、「実は、何かヒントになるかと綾小路きみまろのDVDを買って見ましたが、確かにおもしろいのですが下品すぎて、御宝前で話すには不向きだと分かりました。」と答えましたら、 「そうか、じゃあそれをネタにすればいいよ。」とアドバイス戴き「婦人部総会の話、楽しみにしてるからね~」と愛情のこもった激励を頂きました。 前置きはこれぐらいにさせて戴いて、本題に入りたいと思います。 昔から、結婚という漢字を辺とつくりに分けて、「糸がよろしく、女のたそがれ」とひねくれて読まれております。さらに、夫婦とは「夫を女が箒で掃く」という読み方もあるそうです。 二つを合わせますと、愁いを含んだなんとなく儚げな新妻も、そのうち強くなって、休日寝転がっている夫を、掃除時にじゃまにして箒(今で言えば掃除機)で追い立てるようになってしまうという事でしょうか? 離婚率が上がったとよく報道されますが、少々調べてみますと、明治時代の方が、今よりも離婚率は高かったようであります。これは、明治時代の女性は処女性よりも労働力として評価されており、再婚についての違和感がほとんどなく、嫁の追い出し・逃げ出し離婚も多かったこと、離婚することを恥とも残念とも思わない人が多かったことが理由とされているそうです。 この離婚率も、大正・昭和初期には減少し、平成に入ってまた上昇傾向にあるようです。 さて、大聖人様は、夫婦の在り方について、実に細かくいろいろと述べておられます。さらには親子、兄弟、夫婦等、肉親のいわば本能にも近い愛情について、何度もふれておいでになります。 ここでは次の三点についてふれてみたいと思います。 第一に、妻は夫を信頼して頑張っていきなさいということについては、たとえば 「いへ(家)にをとこ(男)なければ人のたましゐなきがごとし」(新編一四七六頁)とか、「女人となる事は物に随て物を随へる身也」(新編五二二頁) といって女性を励ましておられます。 これを読み替えると、初めから夫のことをダメだと思うのではなくて、「女人となることは、夫にしたがって夫をしたがえる身となることである」ということですから、つまり、夫を信頼することが大事ですよということになります。 第二は、逆に夫の働きの陰で、夫を支え動かす妻の力の大切さについては、 「や(矢)のはしる事は弓のちから、くものゆくことはりうのちから、をとこのしわざは女のちからなり」(新編九五五頁) と言われています。 つまり大聖人は、夫だから男だから、あるいは働きがあるから女より偉いとか、逆に妻のほうが働きがあるから夫より偉いとか、そういう夫婦の在り方についての固定観念は全く持っておられなかったのです。夫婦のありようはそれぞれの夫婦によって千差万別であっていい、ただ大事なことは夫婦が信頼しあうということであります。 そこで第三は、夫婦がお互いを尊重し合って暮らすことの大切さについてですが、それについては、夫婦を一羽の鳥・家の骨組みにたとえられています。 夫婦が別々になったら飛ぶことはできませんし、家に例えるなら、家が倒れてしまいます。 だから 「夫たのしくば妻もさかふべし。夫盗人ならば妻も盗人なるべし。是偏に今生計りの事にはあらず、世々生々(せぜしょうじょう)に影と身と、華(はな)と果(このみ)と、根と葉との如くにておはするぞかし……夫と妻とは是くの如し」(新編987頁) 「女人はおとこを財とし、おとこは女人をいのちとす」(新編1349) ということがもっとも大切であります。 夫婦がおたがいを「財」とし、「命」とするような、何ものにもかえがたい存在として尊重しあい、大事にしあう結びつき。それこそ夫婦のあるべき姿であると大聖人様は述べられました。夫婦は二をもって一とし、はじめてその働きが全うするのであります。? 現代の夫婦のあり方とは多少違うかもしれませんが、夫婦の本質は普遍であります。夫婦となることは過去世からの因縁であり、決して偶然では無いのです。 大聖人様は、 『心地観経に云く「有情輪廻して六道に生ずること 猶車輪の始終(しじゅう)無きが如く 或いは父母と為り 男女と為り生生世世(しょうじょうせぜ)互いに恩有り」等云々』(新編三四四頁) と仰せであります。 皆さんの御主人は、一年中素足に革靴を履いて 女性に甘い言葉を囁くタレントとは ほど遠いかも知れません。 中には、気の利いたこと一つも言わない御主人に、幻滅している方もいるかもしれません。 しかし、現実の生活の上で、御本尊様を信じ共に歩んでいる伴侶ほど頼もしい相手は居ません。 しかも、厳格に勤行をし、御仏智を頂いて、正直で素直な性格であれば、必ず大成し大きな傘となって家族を守ってくれるでしょう。 皆さんの御主人はどうですか? 今日は、是非とも御主人を見直す日にしていただきたいと思います。また、中には残念ながらまだ信心を出来ない御主人もおられるかも知れません。ただ、信心をしないことを嘆くのでは無く、今日こうやって推進会に行くことを認めてくれている訳ですから、その部分では感謝しなければなりません。 また、皆さんは、妻であると同時に母でもあります。 母親の役目は、優しさや慈愛です。貪むさぼり・瞋いかり・癡おろかの三毒に左右されることなく、御題目を唱えて変毒為薬し、優しさと慈愛に満ちた人格で、子供を育成することが必要です。 子供の微妙な心の変化を見逃すことなく、日々勤行唱題を根本に五感を鋭く磨く必要があります。五感を常に磨くことで微妙な子供の心理が分かるはずです。子供に家事や仕事で気持ちが集中出来ない問題もありますが、「柔和忍辱の衣」を心がけ忍耐力をもって対応することが大切です。 様々な自分自身に力がないことを御本尊様から御教示いただき、それがまた智慧に変わり、子育てに活かされるはずです。 子どもを育てるということは、親の大切な仕事ですが、同時に仏道の功徳を積むことでもあるのです。それは親の子でありながら、御本尊さまの子であるからに他なりません。 大聖人様は、四条金吾に子供が生まれた際には 『就中 夫婦共に法華の持者なり 法華経流布あるべきたね(種)をつぐ所の 玉の子出で生れん 目出たく覚え候ぞ』(新編四六四頁) と仰せであります。 このように、功徳を積むということは、じつは何気ない日常生活の中にたくさん潜んでいるように思います。 夫婦喧嘩は、法統相続にマイナスとなります。子供が幼少の頃は、判断基準が未熟なため、心に多くの障害を植え付けトラウマを形成しかねません。夫婦喧嘩をする暇があるなら、御本尊様に向かう時間に費やしましょう。夫婦喧嘩は、一家和楽を破壊する原因となります。夫婦喧嘩は、三毒が強盛になるため心が汚れていることを物語っています。唱題をして心の汚れを御本尊様に洗い流して頂くことが必要です。夫婦で御本尊様に向かう姿を見て、子供は育ちます。そして自然と勤行唱題を覚えていきます。 要は、どれだけ真剣に子供の将来を思い、御本尊様に願っていけるかに尽きるのです。 次に信心のあり方についてお話し申し上げます。 大聖人様は『妙一尼御前御返事』にて 『夫信心と申すは別にはこれなく候。妻のをとこをおしむが如く、(乃至) 親の子をすてざるが如く、子の母に はなれざるが如くに(乃至)南無妙法蓮華経と唱へたてまつるを信心とは申し候なり』 と御指南され
2013.01.11
-
仏法は学問ではありませぬ
何やら、小生のブログに書いた内容に疑問を持ちネット上で燻っおられる方がいますが。。。こちらは罪障消滅になりますので非常に有り難く感謝してもし尽くせない位です。。。仏法は学問でなく、自身の体験を通し感じるものであります。。。この信心は一生成仏が叶う大法であり、理論や理屈だけでは成仏は叶わないのですよ。。。『現証は一切に如かず』ですしね。。。
2013.01.11
-
四恩報謝の念を体する信心
正林寺御住職指導(H24.10月 第105号) 日蓮正宗の信心では四恩を知り、四恩に感謝して恩を報じることが大切です。 日蓮大聖人は『四恩抄』に、 「仏法を習ふ身には、必ず四恩を報ずべきに候か。」(御書267) と仰せです。また『開目抄』に、 「仏弟子は必ず四恩をしって知恩報恩をいたすべし。」(御書530) と仰せのように、仏法を習い信心する身においては必ず四恩を知り四恩を報じることが大事です。 四恩について『上野殿御消息』に、 「仏教の四恩とは、一には父母の恩を報ぜよ、二には国主の恩を報ぜよ、三には一切衆生の恩を報ぜよ、四には三宝の恩を報ぜよ。」(御書922) と仰せであり、四恩とは父母の恩、国主の恩、一切衆生の恩、三宝の恩をいいます。信心では四恩に報い徳を謝することです。 父母の恩とは、この世に出生して法華経である御本尊に巡り会い信心する身となったのは、父母の存在によるためです。 国主の恩とは、広く人が社会生活を営むに当たり国家社会から受ける衣食住などの恩恵を感じることです。 一切衆生の恩とは、すべての生あるものに皆から恩を感じることです。 三宝の恩とは、仏法僧の三宝の恩で信心をして功徳を積み利益を賜ることに恩を感じることです。特に四恩の中で三宝の恩を報じることが肝心です。 四恩報謝の念を体する信心には、さらに世人の模範となる四徳を具えた姿勢が必要です。大聖人は『上野殿御消息』に、 「四徳とは、一には父母に孝あるべし、二には主に忠あるべし、三には友に合って礼あるべし、四には劣れるに逢ふて慈悲あれとなり。」(御書921) と仰せです。四徳である孝と忠と礼と慈悲を意識した振る舞いが法華講衆に求められる信心であり、そこに好感や信頼感を得て異体同心することができます。
2013.01.10
-
仏教の真実は何処にあるのでしょうか?
■仏教各宗派分裂の理由 皆さんは、自家の先祖代々のお墓があるお寺の、その宗派をご存知でしょうか。 仮に念仏系か真言系かくらいは知っていても、「あれ? 浄土宗だっけ? 浄土真宗だっけ?」という感じかも知れません。 そもそも、釈尊(お釈迦様)の教えである仏教は、どうしてこのように多くの宗派に別れてしまったのでしょうか。それは各宗派の宗祖たちが、膨大な経典の中から、それぞれに好き勝手に経典を選んで宗旨を立てたからです。 そして選んだ経典によって、教義も本尊も異なったものとなり、互いにまったく相容(あいい)れない、異質なものとなってしまっているのです。果たしてこの状況は、釈尊の本意なのでしょうか。念仏も真言も、すべてが真実の仏法であるとすると、釈尊はまるで思考分裂のような存在になってしまいます。 そんな莫迦(ばか)なことはありません。これら諸宗の宗祖たちは、釈尊の教えに迷い、どこに真実があるのか分からず、あるいは知っていながら無視して「自分はこれが良いと思う」と勝手に、これが真実だと決めつけたに過ぎません。 仏教というのは、言うまでもなく「仏(釈尊)の教え」です。であるならば、釈尊の教示に従わなければ仏教とはいえません。 釈尊は、一代50年の説法のうち、最初の42年間にさまざまな方便(ほうべん)の教えを説きました。これは、法を聞く人々の素養がまちまちで、何を求めているかも違い、いきなり真実の法を説いても信解(しんげ)できる状態ではなかったため、病に応じて薬を与えるごとくに、種種の方便教を説いたのです。 そしてその後の8年間に、仏法の真実たる『法華経』を説きました。 まず、法華経の序分にあたる開経の『無量義経』には、 「四十余年未顕真実(しじゅうよねんみけんしんじつ)」 すなわち「四十余年には未(いま)だ真実を顕(あらわ)さず」と説かれ、これまで42年間にわたって説かれた膨大な経典は、真実を説いたものではないと斬り捨てました。 また『法華経』の方便品(ほうべんぽん)には、 「唯(ただ)一乗の法のみ有り 二無く亦(また)三無し」 「正直に方便を捨てて 但(ただ)無上道(むじょうどう=最高の教え)を説く」 と説かれ、さらに『法華経』の法師品(ほっしほん)には、 「我が所説の諸経 而(しか)も此(こ)の経の中に於いて 法華最も第一なり」 と説かれ、法華経こそが真実の教えであると宣言されているのです。 念仏宗が依経(えきょう=宗旨のよりどころとなる経典)としている『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』という浄土三部経も、あるいは真言宗が依経としている『大日経』等も、42年間に説かれた方便の経々の一つであり、真実の教えではありません。 にもかかわらず、これらの宗祖・開祖はこの釈尊の本意を知らず、あるいは知ってて無視し、我見(がけん)によって経を選び、勝手な宗派を立ててしまったのです。これが、現在の仏教各宗派分裂の根本原因です。 また、天台宗や日蓮宗、法華宗系は、本来は法華経を依経としていますが、これはまた別の理由により誤りを犯しています(詳細はそれぞれの項目にて)。 ■信じてなくても危険 こうして釈尊の本意に反して分裂し、衆生済度(人々を成仏に導く)の目的を見失ってしまった既成仏教は、現代人の生活から遊離(ゆうり)し、葬式や法事等以外では無縁の存在になってしまいました。 また自家のお寺が念仏宗であったとしても、今どき「阿弥陀(あみだ)様に救っていただこう」とか「死んだら極楽浄土に行くんだ」などと本気で信仰している人はごくまれであり、ほとんどはお年寄りの気休め程度のものでしかありません。 それではこれら邪宗の害毒も、世間一般の人々には無縁なのでしょうか。信じているわけでもないし、日常的には無縁なわけですから、特に問題ないような気がするかもしれません。 でも、例えば自分の親族が亡くなったりすれば、そのお寺にお布施をします。お寺の本堂に入れば、お焼香をし、その寺の本尊に合掌礼拝(がっしょうらいはい)して拝んでしまいます。また友人・知人の葬儀等に出席したときも同様のことがあります。 実は、その宗派を信じていなくても、たったこれだけで罪障(ざいしょう)を積むことになります。邪(よこしま)な宗派に布施をし、邪な本尊に手を合わせただけでも、その宗教に加担したことになるのです。特に先祖代々、その寺の檀家総代などを務めてきたような家庭の場合、さまざまな不幸に見舞われるケースが数多く見られます。 正月の初詣ということで、気軽に近所のお寺に行って手を合わせて拝む……こういうことですら、邪宗の毒を受ける因になります。日常生活と疎遠な存在だからといって、決して甘く考えることはできません。 この第3章では、これら日本中に巣くう既成仏教各宗派について、それらがなぜ邪であるのか、その所以(ゆえん)を道理・証文・現証にしたがって明らかにし、世間の人々の注意を喚起したいと願うものです。 (百堝繚乱より) この章に掲載されている、各宗教に関する文章は、基本的に『諸宗破折ガイド』(宗旨建立七五〇年慶祝記念出版委員会編)を基とし、適宜に要約し、さらに必要に応じて加筆して構成されています。 ネットで、仏教は思想だの言う無知な者がおる。こういう輩は、現実に法華経を読んだ事も無いし、まして、釈尊が説かれた全ての経典すら、読んだ事も無い。そして、ネット等に蔓延るくだらない。習ひそこないが書いた物を鵜呑みにし、実際に経典から我々の信仰の矛盾を説明できてない。 説明できてない理由は、経典を知らない。法華経を知らない。そして、現実に日蓮正宗を信仰して、幸せになっている私達を知らないし、実際に大石寺を知らないのである。 ただ、習ひそこないが目立ちたい。偉いだと言いたいから、騒いでいるだけである。 ならば、騒いでいる無知な者よ。日蓮正宗の信仰の矛盾を経典から、破折してみよ!できるわけない。実際にそやつの妄想での思い込みで騒いでいるだけである。 私達の信仰は、文証、理証、現証として正しいと証明できるのである。
2013.01.09
-
善知識と悪知識を見分ける眼を
人は生きていく時、知識が必要です。知識がなければ生きることは出来ません。人は本能的に無意識のうちに学んで知識を身に付けています。これを身に付けよう、あれを身に付けようと、その都度、確認をして知識を身に付けることは少ない方です。興味のあるものには、直ぐに飛びつく性質を持っているのが人間です。本能的に行うところが多いことでしょう。ここがまた危険なところであり、注意しなければいけません。この本能的な部分を有効に活用すれば、勉強は苦になりませんが、現実問題として難しい面があります。また善悪を識別しない知識には、人道から脱線する可能性があります。 日蓮正宗の信心は、この善悪の知識を正しく判別し、仏様の眼を御本尊様から頂いて現実を冷静に判断し、生活を有効にするよう説かれた教えです。その修行が勤行唱題にあります。知識の中にも「善知識」と「悪知識」があります。『御講聞書』に、 「末法当今に於て悪知識と云ふは、法然・弘法・慈覚・智証等の権人謗法の人々なり。善知識と申すは日蓮等の類の事なり。総じて知識に於て重々之(これ)有り。外護(げご)の知識、同行の知識、実相の知識是なり。所詮実相の知識とは所詮南無妙法蓮華経是なり。知識とは形を知り、心を知るを云ふなり。是即ち色心の二法なり。謗法の色心を捨て法華経の妙境妙智の色心を顕はすべきなり。悪友は謗法の人々なり。善友は日蓮等の類なり云云」(御書1837) と説かれていますように、仏教においても善知識と悪知識があります。御題目を御本尊様に唱えるところに最高の善知識を得ることが出来ます。謗法の知識が悪知識となり人々の心を迷わす原因になります。悪知識を正して、善知識を教えていく行が折伏です。世の中を混乱させる悪知識は折伏によって消滅させることが出来ます。そのため折伏は重要であります。 世の中には悪知識に心身が汚染された人は多くいます。外見は悪知識に染まっていないようでも、心の方が悪知識に浸かっている人や、心は悪知識に染まっていなくても、周囲の影響で外見が悪知識に浸っている人、心身両面が悪知識にどっぷり浸かっている人と悪知識の汚染のされ方も生活環境や縁する人によって千差万別です。折伏では悪知識の染まり具合を入念に分析することが大切です。 知識も善と悪の判断基準を持ち合わせていませんと非常に危険です。法統相続でも教えることが大事ですし、自分自身にとって迷いや悩みの種になり、三毒強盛となって心身を害する要素を秘めています。『富木殿御返事』に、 「諸の悪人は又善知識なり」(御書584) と仰せのように、「人の振り見て我が振り直せ」という悪人の言動を真似ないよう、善知識と考えるように御指南です。これも法統相続では必要です。 正しい善悪の知識を判断する基準を得る唯一の場所が、日蓮正宗の寺院です。寺院で行われる永代経や御講の御住職様による御法話を聴聞することで正しい知識を得ることが出来ます。特に仏法における善知識と悪知識といわれる正邪を判別する教えは日蓮正宗以外にはありません。お寺へ参詣して正しい知識を身に付け、生活を安泰にしていきましょう。 【正林寺法華講員手引書】より http://blog.goo.ne.jp/shourinzi1972/e/3c128cba4757cb08622a88292xxx-xxx-xxxxx
2013.01.09
-
日蓮正宗では、僧が上で信徒は下と差別してるではないか?
十四、宗門には「僧が上、俗は下」という僧俗差別観があるのではないか この世に存在する一切のものに、現象(げんしょう)面での差別(さべつ)と普遍(ふへん)的な面での平等(びょうどう)という両面があることは、誰もが知っています。 第九世日有(にちう)上人は『化儀(けぎ)抄』において、 「貴賎道俗(きせんどうぞく)の差別なく信心の人は妙法蓮華経なる故(ゆえ)に何(いず)れも同等なり、然(しか)れども竹に上下の節(ふし)の有るがごとく、其(そ)の位をば乱(みだ)せず僧俗の礼儀(れいぎ)有るべきか」(聖典973頁) と仰せられ、僧侶と信徒はもちろんのこと、身分の高い人と低い人も、信仰のうえでは本質(ほんしつ)的に平等であるが、役割(やくわり)のうえでの地位の差は存在し、そこに礼儀が必要であると御教示されています。 ところが創価学会は、宗門が創価学会に送付した文書の中から、 「あたかも僧俗がまったく対等の立場にあるように言うのは、信徒としての節度(せつど)・礼節(れいせつ)をわきまえず、僧俗の秩序(ちつじょ)を失(うしな)うものである」(お尋(たず)ね文書 平成二年十二月十三日付) 「僧俗には大聖人の仏法に即(そく)した本来的な差別が存するのは当然であります」(宗務院よりの指摘 平成三年一月十二日付) という、差別に関する部分のみを採(と)り上げて、あたかも宗門僧侶が宗教的権威(けんい)を振(ふ)りかざし、信徒の上に君臨(くんりん)しているように印象(いんしょう)づけています。 しかし、これらの文章には、 「御本尊を拝する姿においては、一応平等であります…」(お尋ね文書) 「『化儀抄』でいう信心の意味するところは、妙法の御本尊に向かって本門の題目を唱えるところ、すなわち九界即(そく)仏界という本因妙(ほんにんみょう)成仏の義をいうのでありまして、そこには当然僧俗の差別はなく、平等であり…」(宗務院よりの指摘) との文言(もんごん)があり、明らかに僧俗が信仰のうえで平等である旨(むね)が明記されています。 創価学会は、これらの文書の僧俗は平等であるとする部分を故意(こい)に覆(おお)い隠(かく)して、差別の面のみを誇張(こちょう)しているのです。この一事(いちじ)を見ても、いかに創価学会が偏(かたよ)った宣伝をして会員を惑(まど)わしているのかがわかります。日蓮正宗には、僧俗は平等にして差別、差別にして平等という一貫(いっかん)した精神が伝えられているのですから、創価学会がいうような「僧侶が宗教的権威を振りかざす」とか、「信徒の上に君臨する」などの宗門への非難(ひなん)は、創価学会の捏造(ねつぞう)以外の何ものでもありません。 日蓮正宗の僧俗は、御法主上人の御指南のもと、広宣流布をめざし、僧俗一致・異体同心(いたいどうしん)して自行化他(じぎょうけた)の信行(しんぎょう)に精進(しょうじん)しているのです。 あなたの疑問は、創価学会の悪質(あくしつ)きわまりない情報に紛動(ふんどう)されたところからきているものであり、一日も早くその朦霧(もうむ)の迷(まよ)いから覚(さ)めるべきです。 (創価学会員折伏教本より)
2013.01.08
-
日蓮正宗の信心は師弟相対が大切
日蓮大聖人は『華果成就御書』に、 「よき弟子をもつときんば師弟仏果にいたり、あしき弟子をたくは(蓄)ひぬれば師弟地獄にを(堕)つといへり。師弟相違せばなに事も成すべからず」(御書1225) と仰せであり、師匠と弟子が師弟相対した信心が大事であることを御指南です。「師弟(してい)」とは師匠と弟子のことで、師匠は模範となって人を導く方、弟子は師について教えを受ける者です。師弟の関係について仏法では、師弟相対や師弟不二をもって真の師弟のあり方としています。 「師」とは師匠であり日蓮正宗において、宗祖日蓮大聖人と第二祖日興上人已来、歴代の御法主上人猊下であります。更に末寺の御住職様も法華講員の方には師匠になります。 「弟」とは弟子であり、日蓮正宗に入信した法華講中の講員さんが弟子の立場になります。 この師弟相対した筋目を心得て信心していくところに成仏があります。 第二祖日興上人は『佐渡国法華講衆御返事』に、 「このほうもん(法門)はしでし(師弟子)を、たゞして、ほとけ(仏)になるほうもん(法門)にて候なり(中略)なをなをこのほうもん(法門)は、しでし(師弟子)をたゞしてほとけ(仏)になり候。しでし(師弟子)だにもちが(違)い候へば、おな(同)じほくゑ(法華)をたも(持)ちまいらせて候へども、むげんぢごく(無間地獄)にお(堕)ち候也。」(歴全1-182) と師弟相対しない信心は、無間地獄に堕ちると非常に厳しい御指南をされておられます。 師弟相対する信心は正法の「令法久住」に必要不可欠です。師弟相対しないところには、正法を末法万年といわれる未来まで伝えることは出来ません。そのためにも師弟相対した信心は大事であります。弟子は我見を差し挟むことなく、日蓮大聖人の教義を師匠から正しく学ぶことです。その学んだことを心に染め、更に折伏で正しく教えていくことが理想です。 御住職様から御指導を仰ぐことも師弟相対の信心になります。師弟相対する信心の実践は、寺院参詣における永代経や御講に参加し、御住職様の御法話を拝聴させて頂くことです。また日蓮正宗の機関誌である「大日蓮」や「大白法」を読んで、御法主上人猊下の御指南を拝読させて頂くことです。 更に、支部総登山等で総本山大石寺に登山をして、また大きな法要や行事に参加をし、御法主上人猊下の御指南を賜ることが師弟相対の信心につながります。日蓮正宗では、御法主上人猊下の御言葉は、信心の根幹でありますので疑うことなく、信伏随従(しんぷくずいじゅう)し「信」をもって拝することが大事です。 無いとは思いますが、もし疑問が生まれた場合、自分自身の信心を見直し、信心の原点にかえることが必要です。そして過去からの謗法の思想や生涯において根拠もなく身に付いた考えと我見が、心の中で魔となっていないか確認することです。勤行唱題で魔の働きを打ち破ることが必要でしょう。そして、御住職様や講頭さんに相談をして正しい信心に立ち返ることであります。 師弟相対の信心は、寺院参詣が基本です。率先して御住職様の御法話を拝聴させて頂きましょう。 【正林寺法華講員手引書】より http://blog.goo.ne.jp/shourinzi1972/e/207eec038acf9eeb7c512dd9a1e30842
2013.01.08
-
守護国家論より
日蓮大聖人は『守護国家論』に、 法に依って人に依らざれ、義に依って語に依らざれ、智に依って識に依らざれ、了義経に依って不了義経に依らざれ (新編御書127・全集44) 大聖人は涅槃経に説かれる法の四依について、四つの依りどころとすべき点を御教示と拝します 「依法不依人」…修行する人は教そのものを依りどころとして、教を説く人に依ってはならないこと 「依義不依語」…教の意義に従い、表現の文章に依ってはならないこと 「依智不依識」…真の智慧に依って、凡人の情識に依ってはならないこと 「依了義経不依不了義経」…中道実相の義を説いた了義経に依って、そうでない不了義経に依ってはならないこと このブログに何回も出している。 衣法不衣人。これを言うと日蓮正宗は、血脈相承は矛盾と言うだろうが、正しい法を伝えているのは、僧である。 法をよりどころにし、人をよりどころにしてはならない。 よく、あの人がどうだの、あの人が何だかんだ言って、人ばかり見ていて、全く正しい法を見ていない。 人ばかり見て、人をよりどころに信心はできない。 正しい法に従い。正しい法を実践する事が、正しい信心と言えるのである。
2013.01.07
-
折伏は福田に下種をして育成が必要
福田とは、田が作物を生ずるように、供養することにより福徳を生ずる対象。三福田(さんぷくでん)や八福田(はちふくでん)があります。 三福田は、供養すれば福徳を得ることのできる三つの対象。敬田(三宝)・恩田(父母)・悲田(貧苦者)、または報恩福田(父母)・功徳福田(三宝)・貧窮福田(貧苦者)ということです。 八福田が、(これらに施すとよく福を生むことを、田の稲を生ずることにたとえていう) 仏・聖人・和尚・阿闍梨あじやり・僧・父・母・病人に施すことです。異説もあります。 日蓮正宗で説くところの「福田」を考えた場合、折伏や育成、そして法統相続に関係し、人の心の「田んぼ(福田)」に種を植え育てていきます。つまり「下種」です。縁ある人の「福田」に御題目の南無妙法蓮華経を植えていきます。末法は「本未有善」という、未だ善となる仏様の種が命に植えられていない人が生まれてくる時です。信心を知らない人に、御題目を教えていく時代です。「福田」に御題目の南無妙法蓮華経を、植えていくことが非常に大事であります。「福田」に植えられた種を育てるための肥料は、日蓮大聖人が説かれる教えでなければいけません。 末法時代では、法華経以外やまた釈尊の法華経では、「福田」に種を植えたことになりません。末法に下種する種は、釈尊在世の教えでなく、日蓮大聖人の文底下種仏法でなければいけません。釈尊の仏法では、かえって毒となって不幸になります。それは釈尊自らが、大集経において説かれています。それが「白法隠没」ということで、日蓮大聖人は『上行菩薩結要付囑口伝』に、 「今末法に入って仏滅後二千二千二百二十余年に当たりて聖人出世す。是は大集経の闘諍言訟(とうじょうごんしょう)・白法隠没(びゃくほうおんもつ)の時なり云云」(御書944) と御教示のように、末法の人々の「福田」には、末法に出世される聖人が流布する種でなければならないのです。 日蓮大聖人は『衆生心身御書』に、 「ひへ(稗)のはん(飯)を辟支仏(びゃくしぶつ)に供養せし人は普明如来となる。つち(土)のもちゐ(餅)を仏に供養せしかば閻浮提の王となれり。設(たと)ひこう(功)をいたせども、まことならぬ事を供養すれば、大悪とはなれども善とならず。設ひ心をろ(愚)かにすこ(少)しきの物なれども、まことの人に供養すればこう(功)大なり。何に況んや心ざしありてまことの法を供養せん人々をや。其の上当世は世みだれて民の力よわ(弱)し。いとまなき時なれども心ざしのゆくところ、山中の法華経へまうそう(孟宗)がたかんな(笋)ををく(送)らせ給ふ。福田(ふくでん)によきたね(種)を下(くだ)させ給ふか。なみだ(涙)もとヾまらず。」(御書1217) と仰せです。文底の法華経に基づいた最高の種を「福田」に植えれば、計り知れない功徳があると御教示なのです。 「福田」に下種された種を育成するには、自行化他に精進することだけです。毎日の勤行唱題と折伏、寺院参詣や総本山への登山が大事です。それらを確実に行うことで、「福田」に植えられた種が育ち、成仏の境界へと向かいます。 【正林寺法華講員手引書】より http://blog.goo.ne.jp/shourinzi1972/e/c888a08f6e8d3263bac52ffe0699cabd
2013.01.07
-
僧侶を蔑ろにしてはならない。
顕正会も創価学会もそうだが、僧侶を蔑ろにしている。 僧侶を蔑ろにするのは、正しい信心でない。かつて、戸田城聖氏はこのような指導をした。 「先代牧口先生当時から、学会は猊座のことは、いっさい感知せぬ大精神で通してきたし、今後も、この精神で一貫する。これを破る者は、たとえ大幹部といえども即座に除名する。信者の精神はそうでなければならない。むかし、関西に猊座のことに意見をふりまわして没落した罰当たり者があったそうだが、仏法の尊厳をそこなう者は当然そうなる。どなたが新しく猊座に登られよう、学会会長として、私は水谷猊下に お仕えして来たのといささかも変りはない。 新猊下を大聖人様としてお仕え申し上げ、広布への大折伏にまっすぐ進んで行くだけである。」昭和31年1月29日付聖教新聞・戸田城聖全集 第3巻235 現実に私、多くの学会を折伏しているが、夜逃げした学会員。廃屋化した家に住む学会員を多く見ている。 創価学会は、日蓮正宗の僧侶を誹謗してきた。その現証が現れている。 戸田さんの時代から、猊下を誹謗していた輩はいたようである。 アンチの連中は、思い込みじゃ〜と騒ぐだろうが、現実に多くの現証として、没落したり等が多くあるのだから、それは思い込みでなく、文証、理証に基づく現証に他ならないまである。 本当か?わからないが、日恭上人の死を仏罰だと法華講に散々誹謗した学会員は、その誹謗通りに真黒焦げになって亡くなっている。 また、ある顕正会員は、勤行中に突然死! これも、日達上人に対して誹謗している団体に夢中になってしまった現証と言える。 顕正会員や創価学会員だった者が、日蓮正宗に入ってからくるのが、経済面での苦悩である。三宝誹謗をしてきたので、経済面が苦しいのである。 かつて、戸田城聖氏が戦時中に御本尊を捨てた者が、日蓮正宗に入信したら救われるか?の質問に、救われるが、どん底の生活まで落ちてから、救われると指導している。 誹謗なんかしてはならないのである。 今年は、団結前進の年である。末寺では御住職を中心に団結して、さらに折伏を前進しなければならない。 中には、住職が気に入らないから、移籍するだの、あの人が嫌いだの何だかんだ言っている者がいるけれども、そういう事を言っていたら、団結にならないし、まして、前進しない。
2013.01.06
-
信心は「発心」が大切です
「発心」とは、菩提心を起すこと。また一般に、あることをしようと思い立つこと。発意。発起という意味があります。信心は自らの「発心」が無ければ実りませんし、当然成仏もできません。 「発心」は信心以外にも、世の中のあらゆることに必要な心構えです。発心を忘れて、何かを成し遂げようという横着な人が世の中には見受けられます。発心が有るか無いかで人生も大きく変わってきます。心を発す「発心」は人間生きていく上で大事なことです。この「発心」も善悪を十分心得た上で、心を発さなければ人生を天国と地獄に分けます。善知識と悪知識を理解した上で発心し、気持ちをそのことに集中させることで大成します。 『一代聖教大意』に、 「五戒・八戒・乃至三聚浄戒(さんじゅじょうかい)の上に六度・四弘の菩提心を発(お)こすは菩薩なり。仏界の引業なり。蔵通二教には仏性の沙汰無し、但し菩薩の発心を仏性と云ふ」(御書95) と御教示であります。自ら心を発すことで、仏様の命である仏性が御本尊様の力用により涌現されます。信心でいうところの「発心」は、心を発すことで同時に仏様の命が蘇ります。その信心に則った「発心」を生活のあらゆる場面で活用するところに、経文に説かれる「我此土安穏」があります。 「我此土安穏」とは『御義口伝』に、 「我此土安穏(がしどあんのん)とは国土世間なり。衆生所遊楽とは衆生世間なり。宝樹多華菓とは五陰世間(ごおんせけん)なり」(御書1770) と御教示であります。発心し御本尊様を受持して御題目を唱えれば、住んでいる私達の国土世間が「安穏」になります。つまり仏様が安住する常寂光土に変わります。 第二十六世日寛上人は「六巻抄」の『文底秘沈抄』に、 「夫れ本尊とは所縁の境なり、境能く智を発し、智亦行を導く。故に境若し正しからざる則んば智行も亦随って正しからず。妙楽大師の謂えること有り『仮使発心真実ならざる者も正境に縁ずれば功徳猶多し、若し正境に非ざれば縦い妄偽なけれども亦種と成らず』等云々。故に須く本尊を簡んで以て信行を励むべし。若し諸宗諸門の本尊は処々の文に散在せり、並びに是れ熟脱の本尊にして末法下種の本尊に非ず。」(六巻抄42) と御本尊様について御指南されています。更に「発心」にも触れられ、「仮使発心真実ならざる者も正境に縁ずれば功徳猶多し」と中国の妙楽大師の言葉を引用され、はじめは発心が真実でなくても正境である御本尊様に縁すれば、功徳を頂いて発心が本物に変わり成仏していくと仰せです。 日蓮正宗の御本尊様は、末法下種の御本尊様で、今の時代に相応しい御本尊様です。この御本尊様に縁し御題目を唱えることで、志したことがあらゆる障魔を乗り越えて成功していきます。何事に於いても「発心」という心を発すことが大事です。信心をし御本尊様を受持するところ「発心」が本物になります。 【正林寺法華講員手引書】より http://blog.goo.ne.jp/shourinzi1972/e/b46710a988861b83cb92cb244faef6e7
2013.01.06
-

初登山
昨日、初登山行きました。 昨日は、天気も良く素晴らしい!登山になりました。 登山する度に、歓喜してますが、今年は、団結前進の年。今年の初登山に参加された方々を見ると、今年も絶対に全支部誓願達成すると感じました。 今年は、御影堂の落慶大法要があります。私も今年は、必ず誓願達成をしたいと思います。
2013.01.05
全56件 (56件中 1-50件目)
-
-

- 超合金
- 僕の夢のコレクション(146) 鋼鉄ジー…
- (2025-09-25 20:55:09)
-
-
-

- 戦闘機の写真を撮るのが好き!
- 三沢基地航空祭2025.09.21
- (2025-11-17 06:30:08)
-
-
-
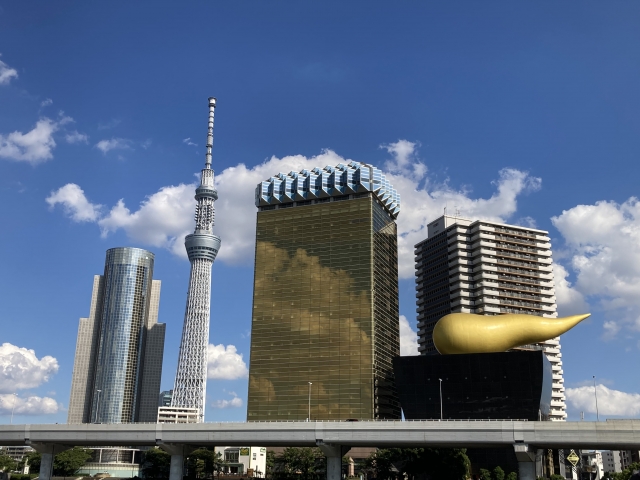
- ◆パチンコ◆スロット◆
- 東京都清瀬市 低貸スロット(2.5円…
- (2025-11-17 00:00:09)
-








