2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年02月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
昭和女子大オープンカレッジ、幼き日からの縁が、4月からの僕の講座に結びつく。
東京の友人が、2月21日の、各新聞の朝刊の折込に、昭和女子大オープンカレッジのチラシが入っていて、オサメのコーチング講座が出ていると、連絡くれた。オサメというのは、MUSAMEJIの子ども時代のあだ名だ。小学校や、中学の友人達と、今でもみな仲が良い。1月に上京した時、そのうちの7人で、三軒茶屋の「魚孝」という小料理屋さんに集まった。魚孝は、茶沢通りにある、もともと魚屋さんで、東京でもこんなおいしい魚が食べられるなんてと福岡の友人が、出張の時わざわざ、食べに行くくらいの隠れた名店だ。ここの女将さんは、魚屋さんの一人娘で、僕が5,6才だった頃、17、8才だったのだなあ。魚屋さんの店頭で、ゴムの前掛けで、鉢巻姿はりりしくて、キリットとしていて、透明な裸電球に照らされている顔が素敵だった。すごくきれいなお姉さんと、子供心にも思える、あこがれのイメージだった。僕の父も、”陽子ちゃん、陽子ちゃん”とファンだった気がするなあ。さて、この魚孝で、僕が今年初の上京ときいて、男性3人、女性3人が集ってくれた。幼稚園と中学で一緒だったのが1人、小学校と中学校で続けて一緒が、4人。中学から一緒というのは1人。それぞれも幼稚園では一緒だったとか、みなどこかで、つながっている。僕の通った幼稚園は、昭和女子大付属昭和幼稚園。昭和27年の秋から29年3月までの1年半、僕はここへ通った。当時園長だった先々代の人見円吉先生の真っ白な髪が、子供心に印象に残っている。その長男で後の先代の理事長が人見楠郎先生。当時、幻灯(スライド映写機)や、テープレコーダー、8ミリカメラなど、時代の先駆的製品を、現場に取り入れて記録し、父兄や子ども達にもよく上映会をしてくれた。戦後まもなくで、まだまだ子どもの健康のための栄養補給が難しい時代、学校内で、なんと10匹ほどヤギを飼っていて、そのヤギ乳を園児のおやつに出していたことなど以前に、この楽天日記にも書いた。集った中の1人が、僕らの中学校同期で構成する「ML」へメールを入れてくれる。 >きょう、朝刊に昭和女子大オープンカレッジの折込が入っていました。そこに鮫島君の新講座の案内があったの、ごらんになりましたか?母に教えたら、ひぇー、あの鮫島君が、えらくなったのねえとすごく喜んでました。(あのぉ、附小に入学して、最初に隣の席に座ったもん同士なんです、アタシタチ)人気講座になりますように!(映画のような、シニア)同伴割引はないのね?とか >今日、うちのほうにチラシが入っていました。結構、オープンカレッジの講師って、へーという有名人もやるようになったのですね。その中の1人?!料金は、3回で24,000円とは1回、8000円!。元を取った気にさせるには、凄く、内容がなくちゃね。講演料で、東京福岡の交通費でるの?すごく働かなきゃならないわね。とか。この講座のそもそものきっかけを作ってくれたのは、中学時代の同級生で、学芸大付属小や御茶ノ水大付属小で、長く教員をしていたT,Y君。彼が、昨年昭和女子大教授に転進、僕をオープンカレッジでのコーチング講座講師として、紹介してくれたのが、そもそもの始まりなのだ。4月からは、月1回は、必ず上京機会が出来、今年、80歳の母が何よりも喜んでくれている。さて、僕の講座、何人くらいの方がお越しくださるのだろうか。ご指摘のように、確かに、料金付けは、こちらがすることではないが、月1回土曜日、13時から17時までの4時間で、1回8000円って、結構いい値段かもしれない。その金額に見合う、十分な、満足感を持ち帰っていただくようベストを尽します。まあ、まずは”観て、聞いて、やって”コーチングって面白い、から感じていただこう。自分探しと、他者への配慮、人間って、いいもんだよね、コミュニケーションってこんなちょっとした工夫でこんなに変わるの?という醍醐味を、きっと皆さんに新たな気付きを得ていただける講座であることは,間違いありません!って、保障します(自分で言うと、だめかなあ。)ここです。↓https://www.oc.swu.ac.jp/entry/detail.asp?CNO=5119&userflg=0”もう申込みしました”と、嬉しいメールが……うーんまだこない。
2007.02.27
コメント(1)
-
24日の、コーチング参加のプロコーチからフィードバックを頂いた。
24日、25日は、2日間通しで、コーチング基礎講座とファシリテーション入門講座として福岡で、開催した。皆様に、礼状を書いたところ、早速の返信を続々といただく。なかの、お1人は、プロコーチ。やはり彼女からのフィードバックは、ズシンと、僕の心に響く。;:;:;:;O.S様おはようございます、鮫島宗哉です。週末の貴重な時間、ご参加、ありがとうございました。何より、あの場にいていただき、有難く思います。さて、参加いただいて、ご自身の振り返りはいかがでしたか?今回の私の講座から、お役に立つ場面があったらまた是非、お教えくださいね。終わってみると、時間配分や、説明と実習のバランス、テキストの構成と、いたらなかったことをいくつか見出しています。ぜひ、フィードバックをくださいね。ネガティブフィードバックOK、是非おねがいしますね。P.S今回、参加の方々、2日で延べ18人、内5人の皆さんは両日参加でしたので、私も含め、14人でのスタートですが[ms九州C&F]という、メーリングリストをつくろうか思っています。コーチングやファシリテーションへの思いの発現、勉強会などに発展させたり皆様の、情報交換や情報提供、交流の機会にもなればとおもいます。ちなみに、MSは、muneya samejimaの頭文字?ではなく”みんな、最高!ますます、しあわせに!”の、ことです!!招待状発送を近々しますので、よろしかったら、ご参加ください。鮫島宗哉;:;;:;::;返信を早速頂いた。鮫島宗哉さま >24日は、一日講座に参加させていただき、本当に ありがとうございました。 >そして、御礼に変えてFBをいたします。 ネガティブFBもOKということですが、 いい、悪いに分けず、自分の視点ですが、 感じたこと、お伝えいたします。 ・上半身のこなしがきれい。(特に胸の張り方に安定感がある) ・自分のしたいことをはっきり伝えているので、参加者が信頼できる (コーチングとファシリテーションをしていくということを 言い切っていらした点) ・休憩のお茶の時間に、鮫島さんらしさを感じました。 社交性と気さくさです。 ・鮫島さんの講座は美人の参加が多い! ・声の通りや、聞き取りやすさ、いつものとおり抜群です。 ・全体を通して、伝えたいことがたくさんあることが、伝わってきた。 ・「○○さんのお隣の○○さん・・・」のアイスブレイク、 私も使いたいと思いました。 (名前を覚えることが自然にできたし、そのあと、名前を呼びやすくなった) ・声かけ、目を合わせる分量が、男性に対して少ないことが、気になりました。 意識して、男性の様子をうかがうようにすると平等になると思います。 ・コーチングの専門用語、固有名詞(人の名前、会社の名前)が多く プロコーチとの会話だといいと思うのですが、 初級コースでは、もっと小出しにしたほうが、 コーチングへの期待感が高まると思います。 ・本、お茶、お菓子の準備に、鮫島さんの意気込みを感じました。 (お一人で準備されたことを考えると、大変だったと思います。 この一生懸命にひとは心を動かされるのだと思います) ・一人一人の自己紹介が丁寧で参加者同士の話しやすい環境を作り出した。 ・みんなが眠そうになったときに、アイスブレークといって、 運動をしたのは、ナイス判断でした。 私も、ちょうど集中が切れはじめていました。 あれがあるのとないのでは、 そのあとの時間の過ごし方が大きく変わっていたと思います。 ・8時間の場を仕切る(前後の準備時間、食事会の時間含め) 鮫島さんの体力、やる気、気迫を感じました。 私自身の学びは、 ・自己紹介で、「プロコーチです」と名乗ることで、 自分の意識を変えることができた。 ・出会う方からエネルギーを頂いた。 ・場を仕切ることに関して、最初から最後まで、すべて学びでした。 最後に、メーリングリストへのお誘い、ありがとうございました。 ただ、現在の時点でも、 頂いたメールへのクイックレスポンスができずにおります。 これ以上、頂くメールが増えるとますますのクイックレスポンスから、 遠ざかり、皆様へご迷惑をおかけしてしまいます。 大変心苦しいのですが、今回のメーリングリストへの参加、 辞退させていただきたいと思います。 何卒ご理解していただきたく存じます。 鮫島さんのC&Fのご発展、お祈りします。 ☆~~~~~~~~~~~~~~~~☆うーんさわやかな、返信、そして、観察力の確かさ、フィードバックは、何にも変えがたい、多くの気付きを与えてくれる。O.Sさん、ありがとうございました。
2007.02.26
コメント(1)
-
地場の建設関係の某社社長にコーチングのお話をする。
九州地場のある建設関係の会社社長にコーチングについて、お話をさせていただく機会があった。友人の紹介で、お目にかかるのは初めてだったのだが、当初、1時間という予定が、社長とのやり取り自体が、コーチング的になり、気が付くと2時間も経っていた。自律・自立型の社員を育てること、出来の悪い部下を、少しでもアップするよう環境設定することが中間管理職の仕事だということ、うまく行かない時こそ、部下のやる気をどう引き出したらよいか問われる、経営者である自分自身が、ともすると自信を失いそうな時、どうするかなどお話が、次々と弾む。コーチの存在で、孤独が癒され、自分の思いを言葉にすることで自分をふり返ることができることがわかると大変興味を持って、コーチングの考えを捉えてくれた。まず自社の役員と部長クラスに、1日研修を実施したいとのご意向が示さた。これまで自社には、コンサルタントは100人以上導入、いろいろな付き合いをしてきたがコーチというのは初めてだったとのこと。「話を聞いてくれる人がコーチとおっしゃるが、その前に、信頼感を持てる相手かどうかが肝心ですね]とフィードバック!まさに、コーチングで言うところの、”ラポール”を社長の在り方と、この一言で、こちらも感じ取ることが出来た。素敵な経営者だと思った。こんな方が、コーチングやファシリテーションに関心をもってくれて社内に導入をはかったら、確実に人材は育ち、業績アップは間違いない。僕も一緒に、その現場に居合わせたいと心から思う。先日の石川尚子コーチの原点にもどってのコーチングを考えることとつながる。改めて、ラポールありきでのコミュニケーション、その成立は、[クライアントを、結果が出せる人と信じるスタンス]にこそあり、コーチは、その軸足をはずしてはならないということを再認識する、社長との今日の出会いだった。
2007.02.22
コメント(0)
-
ただいま、24日のコーチング講座は8人、ファシリテーション講座は10人の申込。
昨年札幌で実施したスタイル、コーチング&ファシリテーションの組み合わせでの連続講座。福岡で初めて、鮫島宗哉、自主公開講座である。24日、コーチング基礎講座、25日、ファシリテーション入門講座、いよいよ今週末に迫ってきた。両日とも、何とか、応募の人数は確保できて、メールと、この楽天日記と、メールでしか告知はしていなかったが、お願いを個別のメールで先週末から必死で書きまくったら今週色々と動いてくださった友人の方々のサポートのおかげで、全く新しい方からも、WEBでのお申込などが届くのだ。とても今回は、気持ちが明るい。昨年夏、日本ファシリテーション協会の夏合宿でであった、市役所のお役人が、部下のお1人を推薦し、参加を促してくださった様子。先週17日(土)に開催の「日本ファシリテーション協会」のファシリテーション基礎講座に参加された方からも、2人。そのうちのお1人は、コーチング講座にもと、2日間連続で参加とおっしゃる。さらに、2月10日の、日本コーチ協会福岡支部の勉強会に参加の中からも3人、そして、なんと支部運営委員の中のお2人が、ファシリテーション講座のほうに参加を申し込んでくれている。まさに、コーチングで言うところの、「承認」の嬉しいラッシュ!とmusamejiはかなりいや相当、嬉しい。先日の、石川尚子スペシャル勉強会にこられたI.Aさんから、メールが届く!”24日は8人、25日も10人!またまたたくさんの方たちと出会えるんですね、ワクワクします。それから講座内容も。「ファシリテーション」はきちんと学び身に付けたいものだったのでとても楽しみにしています。最近、目先の忙しさ・あわただしさにかまけてしまっていましたが、25日の講座は、久々に、自分の今後のために時間を使う機会になります。ぜひぜひ、手加減ナシでビシバシと鍛えていただければ嬉しいです。それでは、いよいよ4日後ですね、どうぞよろしくおねがいします。”;:;:;:;:;:;まだ、お申込み、時間はあります。23日一杯、お申込お待ちします!http://form.on.arena.ne.jp/rtform18/1630h7wxw2/index.cgi
2007.02.21
コメント(0)
-
musameji、大学生のための「就職支援講座」を担当する。
古巣博報堂の先輩で、大学で講師をされているI.S氏からメールを頂く。返信した内容から。;:;:;:;:;さて、今の大学生のご指導の状況についての興味深いお話ありがとうございました。実は、BSさんからの依頼で、大学低学年(つまり1年、2年対象)の「就職支援講座」のインストラクターを要請され、F工業大学の環境社会学部などで学生相手にまさに、自己PRの書き方指導をする機会がありました。今、大学も、自らの存続をかけて、色々と学生向けのサービスに余念がないようです。地方大学で、偏差値があまり高くない学生を抱え、良い社会人として、ニートへ行かないようにいかに指導するか、大学も心を砕いているかの様であります。 >コーチングの件ですが、最近の私の周りでは、3年生の学部生か院生との付き合いぐらいで、3年生は就活で忙しく、院生は皆な留学生でお金に困っており、ちょっと対象になりにくいですね。しかし、就活の件で博報堂を受けたいという学生がおりまして、エントリシートの記述内容について、チェックして欲しいという依頼を受けて、初めて博報堂のエントリシートの質問を見ました。内容を見れば一朝一夕で記述できるような内容ではないようです。つまり3年生というより1年生の時から目標を持たせる必要がありそうです。大学生が4年間を通して、どんな目標を持たせ勉学をしていくか、などのテーマで自覚していく必要がありそうです。そんなテーマが成立するのでしょうか。大学ではそんなテーマではあまり授業に取り入れていないように思いますが。まさに、ご指摘のとおりのようです。そこに目をつけて、パッケージで各大学へ”就職支援講座”を売り込んでいくのがBSさんの新しい戦略のようです。しっかりインストラクターに、有料の説明講座があり、コーチ仲間からの紹介だったのですがなかなか良く出来ている、支援ツールを作っているなと思いました。もっとも学生に、目標を持たせることもともかく、一方で、まさに団塊世代が長い会社生活のあと、次はどんな人生目標を持つのか?にも通じる侮れない内容、構成の、指導法やツールで、団塊世代の生きがい探し?にも十分使えるなと感じました。びっくりです!コーチングやマーケティングの視点は、多いにこの講座を学生に語るには私にとって博報堂経験は役にたちそうです。私も興味深く、楽しんで、学生に対応しています。面接前のエントリーシート用に、自己紹介を、150字で書かせるワークの時、目標チャート作成シートで、何もかけないところから何を言っているのか分からない文章、しかし、質問しながら、エピソードを聞くと、だんだん語れるようになる。吹奏楽のコンテストで、金賞をとった、とかサッカー部主将だったとき、前年で6位から4位にした。じゃ、君が関与して、うまく行った部分は何さ?それを箇条書きでまず書いてごらんというと少しずつ、しかしだんだん見違えるように、文章が出来ていくのです。学生たちは、”君は結果を出せる”と信じて接すると文章も、2時間程度の間に、見違えるほど分かりやすくなるのです。若い人の潜在力と変化を目の当たりにして、かれらに接することが大変僕にも励みになりました。 >とにかく今の学生は論理的な文章を書くという経験が足りません。私も時折テーマを持たせ、宿題として次週に持ってこさせるのですが、N大学では170名中7名、N県立では60名中1名でした。点数には反映させないと断っていたからかもしれませんが。とにかく今の大学生は論理的な文章を書くことは本当に苦手のようです。1年生時から目標を持たせるという教育をしていないようですね。そのままでは、若い時に目標なんて、なかなかつくれませんよね。イエ、大人になっても、目標や夢は?と聞かれると答えられない大人もたくさんいることに驚きます。それを、コーチングで、では夢探しからしますか?と進行するのですが。 >しかしK大学などは、新聞の記事をテーマに文章を書かせていますよね。1年に1度社外講師をしておりますが、久留米大学などは意外と熱心のように感じます。どんな目標を持って勉強し、その結果就職活動にもあわてないで対応できるなどのテーマによるコーチングなどはいかがでしょうか。1~2年生対象でのコーチングなどありそうですよ。一度N大の理事に相談されたらいかがですか。あまりお役に立てなくて申し訳ございません。十分情報をいただき、ありがとうございました。元気が出てきました。N理事長に、すぐにでも面会に行く気持ちに駆られています。コーチングとファシリテーションまずは、学校の先生と職員さんに研修して経験してもらおうかと考えています。実は、4月からリバレインのNHK文化センターで、[コーチング講座]を再開します。団塊世代を意識して、[自分探し、コーチング入門]というタイトルです。”自分探し”、”他者理解”、そして”人間関係の円滑化”は、個人でも、組織でも永遠のテーマのようで、その面では、わたしの目のつけた分野は仕事はあるはずなんですが、なかなかスピードが出ませんのが悩みです。お忙しい中今日は、お返事ありがとうございました。また、お時間あれば是非、お目にかかりたいと思っています。よろしくお願いします。
2007.02.20
コメント(0)
-
心理カウンセラーの方たちの集まりで…!
musamejiのコーチの仲間の1人で、鹿児島で活躍されている「マザーズコーチ」として有名な、佐々木のり子さんという方がいる。http://www.sasakicoach.com/昨年の暮れ、佐々木さんから珍しくケータイに電話を頂いた。”すっかりご無沙汰してますがお元気?福岡の友人をご紹介したいので、相談に乗っていただけますか?”そんなきっかけで、出会ったのが、心理カウンセラーの桃本美奈子さんだ。そしてまもなく、桃本さんにお会いし、なんと、桃本さんの心理カウンセラーのグループの方たちに90分、お話をさせて頂くことになった。それが、今夜19日の夜のことだったのだ。メンバーを元気にする話がよいとのことで、しかも、聴衆は全員心理カウンセラー!僕は、コーチングのコーチ!コーチングと心理カウンセリングは、似ている部分もあるだろうが、やはり違うもの。互いのことは、よく分からないままでいることも現実だ。コーチと心理カウンセラー、対立しないかな?!どんなお話を求めていらっしゃるのか、コーチングでいいのかと危惧しつつ、では、博報堂時代の経験をベースに、マーケティングの話にしましょうと、テーマは、”マーケティング視点で捉える、心理カウンセラーの仕事とは”~名刺を作ろう、自分の仕事を、キャッチフレーズにしてみる~となった。心理カウンセラーの立場では、コーチングは、後からうまれた分野で、好意的ではないかもという、心配がないでもなかった。そこで、心理カウンセラーの方たちが、自分の仕事を捉えなおすヒントとしてマーケティング視点から、話を構成してみた。皆さん、心理カウンセラーの資格をとっても、なかなか独立できない方が多いのが悩みでもあるとも聞いた。当日は、マーケティングの意味や、歴史、代表的理論などを[枕]としながらマーケティングの4PとUSPという捉え方をご紹介。プロダクト、プライシング、プレイス、プロモーションのいわゆるまーティングミックスの4Pのうちのプロダクトを、カウンセラーとしての自分の仕事を考えることとして、見つめようとお話を進める。そして、USP(ユニークセリングポイント)の視点で、それを他人とは違った特徴付けとして捉えてみる、と説明する。ペアになっていただき90秒で、自分の考える心理カウンセラーとは、と互いに聞きあっていただくワーク。これは、きわめて、コーチング手法の「傾聴」のワークのスタイルだ。34人の参加者がいらしたが、皆さん90秒で、自分の仕事のことをきちんと語れたようだ。その後は45秒に短縮してまた語り、さらに15秒としてもう一度まとめを試みる。実は、テレビCMは15秒なんですよ、と申しあげると、知らなかったという方もいて、15秒でも、メッセージは伝わることに、トライしていただく。聞き役は、相手の語る15秒のコメントを、ポ゚ストイットに書き留め、最後に相手に渡し、文字数にして約80字のキャッチフレーズができている!皆、一人ひとり違った”自分の考える心理カウンセラー業”への思いが、集まった。これらは、いわば、”心理カウンセラーという仕事の端的な紹介メッセージ”ともいえる。その後のワークは、相手の良いところを、口に出して伝えるという「至福の1分」ゲーム。自分の長所や良いところを、相手の口から具体的に聞くことの意味を感じていただきました。このワークは、毎度どなたも、みな笑顔笑顔で、盛り上がる。最後は、相手からもらった、良いところコメントを、先ほどの15秒のメッセージに付け加え、丁度90分の僕の持ち時間は納まった。そして参加者全員で、出来上がったキャッチフレーズを発表しあう。参加の皆さんからは、大変面白かった、気づきが色々あった、といっていただく。また、”これで名刺を作るきもちになりました!”と思いがけないフィードバック。聞くと、参加の半数以上の方が、自分の心理カウンセラーとしての名刺を持っていなかった。34人中30人が女性で、ほとんど他に仕事を持っていたり、主婦の方のよう。新しい行動を促すという、コーチの役目を、結果、果たすことが出来たと知ってmusamejim」なんだか嬉しかった、心理カウンセラーという方々34人と一挙に知り合いになって、ぼくには、大変有難く嬉しい時間となったのだ。新しい名刺が出来たら是非、またお会いしましょう。ありがとうございました。そして、佐々木のり子コーチ、離れた鹿児島から、ご縁を結んでいただき感謝です。ありがとうございました。
2007.02.19
コメント(1)
-
自分探し、他者発見、コミュニケーション、そしてまた自己へ
自分探し、確かに、いつでも人はそうなんですね。結局、他人より、自分に興味があるんだ。先日読んだ本、鷲田清一[じぶん…この不思議な存在]は面白い。コーチングも、[自分探し][他者発見]そして[他者とのコミュニケーション]つまり、関係性、という言葉、そして[そのための自己開示]へだから、[自己確認のための”自分探し”]という一連の鎖の中にあり、これは円の形、回っているのだ。つくづく、「コーチング」などという大変面白いコミュニケーションの考え方、スキルに、僕は、博報堂を退社して、上手くめぐりあえたものだと思う。これって、55歳を過ぎて、自分で得た、”天の配慮”だったのだろうか。コーチングとか、ファシリテーションとかへの関わり、いまや、僕には、自分の天職だと思うのです。「仕事」は、「志事」になるのです!定年過ぎたら、仕事はもういいなんて事は、絶対ありえないよ、団塊の世代にうったえたいmusamejiである。今日は、短く、思い付きです。
2007.02.18
コメント(2)
-
ファシリテーションが出来ることは、会社から評価の対象になるのか?
この日、日本ファシリテーション協会のファシリテーション基礎講座が、開催された。20人の定員が見事に満員御礼。今回、僕は、講座運営委員として、サポート役である。ぼくが嬉しいのは、そのうちの4人が、僕が紹介した日本コーチ協会福岡支部からの会員達だったということだ。つまり、コーチを仕事にしている人、コーチングを学んでいる人がファシリテーションにだんだん興味を持って来てくれはじめたのだ。その他、多かった職業では、市役所や町役場、の職員の方が7,8人もいらしていること。福岡県内の福岡市以外の市町村からだ。朝9時半から17時半までのみっちりの研修の講師は、加留部 貴行さん。彼は今、3回目の出向で、九州大学の助教授。僕を、「ファシリテーションの世界]へ招じてくれた恩人である。彼の軽妙な、進行に、参加者も全く疲れを感じないで、時間を過ごす。最後に、質問の時間をとった。ある、企業に勤めるサラリーマンの方が質問した。「ファシリテーションが出来ることは、会社から評価の対象になるのでしょうか?」加留部氏は、うーん、なかなか今すぐは難しいでしょうが、いずれ、コミュニケーションこそ、すべての問題や争いの解決策として、きっと評価されるようになるのでは、と答えていた。講座の後は、懇親会。これをファシリテーション協会の仲間内では[泡の会]、つまり泡、ビールと、OUR、我われに、かけてそう称しているのだが、そこで、1人の女性会員が、問題提起!”私は、ファシリテーションのファシリテーターをする人間が、評価を求めるなんて、とんでもないと思うんです!。だってそうでしょ!ファシリテーションって、全体を良くしようという思いが、ファシリテーターという振る舞いになるのです。自然にそういうことが出来ることに、意味があるのであって、それを、会社の評価をもらえそうだから学びたいなんて、最初から違う。””うーん、なるほどねえ”加留部氏は”いつでも、どこでも、誰とでも、それがファシリテーション”って言ってきている。”ファシリテーションを資格制にしようという話があるって言ってたよね””イエそれは正式にはないんですが、大阪と東京でも、意見が異なっているんですよね””フーン、では資格になるとどうなるんだ?””少なくとも、今プロファシリテーターという人には、意味があるのでは?””なるほど、僕は、今ファシリテーターって名刺に書いているけどねえ””ファシリテーターには「天然」と、「養殖]の二つがあって、養殖でもやはりたくさんいたほうが良いという流れはあるんですなあ””コーチにも、天然、つまりネイティブコーチと言われる人たちがいるね。””まあ、外部基準しか頼るものがなくて、みな、資格を取ろうとして大枚60万円も使わなくてはという現状はやはりおかしいよねえ””イエ、コーチ資格は、年限を設けて、さらに一定の経験時間をこなさないと資格を維持できないらしいですよ”いつの間にか、ファシリテーションの話から、「コーチの資格」の話しずれていっている1!皆なもう、いい加減酔っぱらってしまった。8時間のけんしゅうの後は、やはり少々疲労感、そんな仲間達であった。僕自身は、ファシリテーションに資格はいらない、誰でも、どこでも、やることが出来ることが良いこと、そしてファシリテーションそのものには、出来の良いとか悪いはない、と思っている。それは、すべて、[場]の表現なのだと思う。もし、人と違うファシリテーションができる、ということを評価される可能性は信じたいが、だから、勉強するというのではないよなあ。コミュニケーション自体が、場の言葉のやり取り、それのプロセスに、上手い下手は関係ないと思うのだ。もしあるとすれば、ファシリテーターは、みなの気持ちを、納得させようという気構え、この会議の中に、きっと答えがあると信じる、ファシリテーターの決意、そんな思いがすべてだと思うのだ。では。
2007.02.17
コメント(0)
-
ファシリテーションって、どう説明するの?
ファシリテーション、簡単に、言ってしまうと企業などでの「会議」を、もっと活性化し、むしろ面白い、楽しくしてしまおうと言うスキル。[会議]と言うのは、企業にとって、時間単価のかかる社員達を複数集め、集まって実施する、いわば原価の掛かった時間のはずなのに、当の参加者達のホンネは会議なんて出たくないという意識がどこかにあるのではと思います。そんな状態が続くことは、会社にとっては、利益機会も失う、もったいないことでは?その解消を図りませんかと言う意味合いがあります。ファシリテーションと言う意味は、”集団の知的創造プロセス”を促進し、引き出し、円滑にすると言う意味合いなのですが、これから、コーチングと並ぶ、コミュニケーションのスキルとして注目されるものと思います。コーチングは、”あなたの中に答えがある”という前提があります。ファシリテーションは、”この会議の場に、答えがある”と言って、進めます。コーチングとファシリテーション、これからの企業や組織で要求される2大コミュニケーションスキルであると言っても過言ではないでしょう。両者共通の部分もありますが、個別のコミュニケーションと、集団でのコミュニケーション、その微妙な違いは、コーチングを学んだ方では、気づきの違いも面白いものです。むしろ、組織としては、ファシリテーションの方が、実利的面もあるかも知れません。会社の同僚同士、上司と部下の方が共に参加されると効果はより増進し、実践しやすいのではと思います。これまで、組織や企業の会議運営などに疑問や、また改革意欲を持っている方がいらしたら、きっとお役に立てるものと自負しております。どうぞよろしくお願いします。;:;:;:;:;:K.Tさまメール拝受しました。ファシリテーションに関心を寄せていただき感謝です。>それで、お願いですが、>1、ファシリテーションのことがわかってできたら何が可能になるか>2、研修時間はどれくらい必要か?>3、費用はどれくらいか?>>他に伝えるプレゼン資料があればありがたいのですが・・・ご期待に添える内容か分かりませんが書いてみます。まず、ビジネス現場でのファシリテーションの意味合いは、企業や、NPOなどの組織で、で会議運営や、知らない人が集まって意見をまとめる時などに、円滑なコミュニケーションを可能に有効なスキルとして、取り入れ、効果をあげており、注目されてきているところです。問いの1、ファシリテーションのことがわかってできたら何が可能になるかですが、A,組織で、地域で、人があつまる活動において、メンバーの意見、参加を引き出し、当事者としての意識を持たせることが出来る。B,意見の異なった人たちが、話し合いを通じて、能力を持ち寄り、合意形成をめざし、問題の解決に向けて円滑なコミュニケーションのプロセスを踏むことができる。C,その成果は「相互が享受すること」でより効果を増し、一人ひとりの中に潜在していた意識や、資質が引き出され、仲間やグループとしての一体感やまとまりを生みだすことも出来、いわば民主主義のベースを形成することができるものとも言える。D,会議の面白さに目覚めると、組織が明るくなり、計画の実行が速やかになり、それはすなわち、」企業業績の向上として、きわめて目に見える効果が出てきます。E,また、人事での対人関係がコミュニケーションの活性化で円滑になり、働きやすい、人を大切にする社風を生み出すことも可能でしょう。など、目に見えること、目に見えないこと双方で、変化と向上がもたらされます。2、研修時間はどれくらい必要か?研修としての基礎講座としては、A、1日8時間の研修初歩的な知識と、構造を把握、体験型(ワークショップスタイル)でのグループ研修を通じて、実感、体感を得ていただけます。B、2日間16時間の研修さらに、グループでの体験型研修の数を増やせ、テーマを具体的にして、時間をかけることで、深化させることが可能です。また、書く、描くスキルの習得の時間を充実することが可能となるでしょう。大体、2日間あれば、十分ファシリテーションの基本と初歩的応用まで、学習が可能です。3、費用はどれくらいか?研修講師のギャラは、1日30万から40万が主流です。熟練者で、東京では50万以上でしょう。会場費、教材費がその他見込まれます。必須のツールは、ホワイトボード。他に、模造紙、マーカー、付箋紙(ポストイット)、セロハンテープなどです。研修人数は、10人から30人くらいまでが、一番効果的効率的でしょう。ただし、100人でも、2日間としての研修構成は勿論可能です。私の、「1日ファシリテーション研修の勧め」企画書を添付します。ありがとうございました。
2007.02.16
コメント(0)
-
コーチングが後から効いてくる…、漢方的フィードバック。
コーチも、クライアントに育てられている…コーチングをしていて、そう感じることがある。クライアントの思いがけない反応で、コーチは、「シマッタ、これはフィードバックとしては適切ではなかった」と思うことがある。僕自身も、コーチングのときではなかったがまじめでひたむきな、研究者タイプの女性と、いろいろと話が弾んだときに“○○さんって、暗いタイプの人かと思ったけど、実際は明るい人だったんですねえ。”という感想を、“○さんって、本とは暗いんじゃない?”、とネガティブアプローチで聞いてしまったことで、えらく、傷つけたことがある。1年ほども経って、実はあの時、といわれて、彼女の、傷つき具合をあらためて、ごめんなさい、と思ったことがある。これは、コーチとしては、大失敗である。先日の勉強会でのコーチング・デモンストレーションの、ミニ・コーチングで、クライアント役の参加者にコーチ役は、こんなフィードバックを返した。“どうも、あなたのお話に、熱を感じないんですが…”“どうして、私がそう受け止めてしまっているのでしょう”これに、クライアントは、“エッ?そうですか?、そんなつもりはないけれど…”と、詰まってしまった。コーチ自身は、このとき、クライアントとの状態を見て、自然なニュートラルな気持ちから、この質問を発したのあろう。オーディエンスの1人だった僕はコーチのフィードバックに、これは結構、思い切った言い方だなと、やや驚いた。クライアント自身は、このセッションでは、始めから淡々と、やりたいことを話して、しかもその内容は、スケールの大きい話で、周りにはやや分かりにくかった。やれると思っていますという割には、他人事のような話しぶりでもあった。もっと具体的な行動にして話をすすめられたら、と周りも思いながら、聞いていた。「まず聞こう」、というコーチングで始めると往々にして、クライアントが、思いのままに話しをしだすと、まとまらない。クライアント自身も自分の言おうとしていた趣旨がぼやけてしまうことがある。僕自身も、クラインととの最初のセッションでクライアントもやや緊張し、また興奮気味でもあって、いろいろなはなしに次々とつながり広がり、結局、何をテーマにするの?ということがままある。特に第1回目のコーチングではそういうことがある。「傾聴」をしっかり実行してコーチは、役割をはたそうとする。”まず聞こう”というコーチングでは、聞いてもらえるということの心地よさ、しゃべって、すっきりした、ほっとした、という感想が多い。それは、そのとき、コーチとクライアントの間に安心感、信頼感が生まれたからなのだ。それを、ラポールという。ラポールがあれば、たいていのコーチングは機能していくとも言える。第3者が大勢いる中でのコーチングのデモなどのときは、せいぜい6、7分のショートコーチング。そんなときは、[それで、今ここで、何をはっきりさせたいのですか?][あなたの課題を、もう一度整理してご自身の言葉で言いなおせませんか?][今日は時間が余りありません。コーチの私に、今何をして欲しいですか?などと、現状を傾聴することを、省いて、テーマの明確化へいくだろう。ショートコーチングで、もし現状を聞いてしまうとキリがない。ラポールがあるという前提の元に、すぐクライアント自身の「ギャップ」や問題点]に、すぐ、切り込んでいくことになる。「現状」を、省いてしまうのだ。初めてコーチングをしていく時、“どう思いますか?”と聞くことよりも“どう、したらよいですか?”“そのために何をしますか?”などと、行動につながる質問を進めていくこともコーチング的質問だし、普通だ。しかし、気の弱い、まだ、自分自身へも十分な承認を与えていない、自己肯定感がない、少ない、いやむしろ自己否定感のほうが強い人に対しては、まずどうしたいかより、どう感じているかの気持ちを聞いていくことが重要だ。落ち着かない気持ちのとき、”何が、恐れなのでしょうか?”と聞いて行くのは、アティテューディナル・ヒーリングのアプローチだという。気持ちの共有、共感から入らないと肝心のラポールが生まれない。セッションがすすむと、コーチング自体ずっとギクシャクとなってしまう。ところで、”熱が感じられない”、とのコーチのフィードバックに対し、クライアント自身は、どう感じたのだろう。「絶対なしとげなければ!と切羽詰まっているようでは、ダメだと自分は思うタイプ。逆に自分には、嬉しい承認だったかもしれない。」と思ったという。コーチの”熱を感じない”、というフィードバックはクライアントの心に、これからも引っかかるだろう。それを、良い方向へ転じて、受け止めて行くということにクライアント側の在り方や感性で、コーチのほうも、救われたり、報われていることがある。”機能するコーチング”、気付きの瞬間というのはコーチングのさなかであることもあるが、時間がたって、翌日、あるいは1週間後、ということもある。ジワッと効いてくる漢方的質問、コーチングもなかなか奥がふかいのだ。
2007.02.15
コメント(0)
-
自主講座には、これから共催者が必要かなあと、考えるmusameji
2月24日、25日の自主講座、メールを友人知人たちに、個人的に送っている。日本ファシリテーション協会(FAJ)で親しくしているT.I氏から、メールをいただいたことで感じたこと。彼は、 >主催者と講師が同一であるというのは、難しいことがある。 >プランナー的見地からしますと、「セミナー」という商品は、リピートが難しい=ビジネスモデルを確立させにくい商品だと思います。そこで結局、PRの幅が顧客の幅になります。PRにはニュース性が必要だから、PRをがんばればがんばるほど、今度は、内容面での「講師から提供するもの」のリピーティングでしづらくなり、常に新しい講義内容を開発していかねばならなくなり、とどのつまり、新しい顧客に確立した内容を届けるか、確立した顧客に新しい内容を届けるか、どちらにせよ、安定的なリピーティングが望めません。まさに、そのとおりで、今やっている、メール主体では広がりが期待できずかといって、マス媒体はターゲットがぼやけ費用対効果からも踏み切れていないのだ。これまでの講座では主催し、自分で実施するという福岡での実施形態と、第3者的な人へ人集めをお任せして、講師として現場に赴く、という2本立てでやってきている。札幌、苫小牧での実施は、共催の形で実施したのでそこそこ人数を得ることが出来た。福岡では、人集めのサポートを、お願いできる関係を見出していない。現状、作っていないのが事実です。ご紹介を頂いたときは、ビジネスとして、扱い料の設定はしているのだが。6月に熊本、そして長崎での開催実施を、予定しているが主催は、ご当地の方のサポートを得て開催を進行中である。これは、やはり大変、嬉しいことで、しかも、人集めに対し負担感が非常に軽減される。あまり考えずに、そういうパターンをとっていたが、今回、T.I氏の指摘で今後は福岡でも、共催相手の必要を再認識した。T.I氏とは、ファシリテーションを通じての新たな友人になったのだが、彼の、周囲への、献身的な姿勢、自己開示能力にはいつも敬服している。コーチに必要なことは”存在としてのコーチ”と、石川尚子コーチの勉強会でおっしゃったがファシリテーションのファシリテーターも”在り方としてのファシリテーター”を問われているのかも知れない。その人の、ファシリテーションの事前の準備や参加者への配慮は知らず知らず周囲への信頼感を作っている。安心して人々が、考えを言える環境を作ること。まさに、人間力に通じること、のひとつだろう。今回の講座、ファシリテーションの勧めは、コーチの人たちへコーチングの勧めは、ファシリテーションの仲間へ是非、関心を持っていただきたいという発想もあって案内してみた。今回で、通産9回目の実施なので、いつもの講座をまたしますという感じでメールを出している。きっと受け取ったほうも、ああ、またやるのか、日程は?うーんその日は駄目だ、とかよくやるねえ、人はコーチングやファシリテーションにそんなに興味を持っているの?ということかなとも思っている。ご案内をするという行為に、躊躇する気持ちは否めないのだが、なんとかそれを押さえて発信しているのが、現実である。講座の開催日の2ヶ月前に、BCCで第1信,1ヶ月前に第2信、2週間まえに、個人宛でこの人にはと思った方に個別でと今毎日メールをせっせと書いている。多分3回は、案内メールがいくので、受け取るほうも、迷惑!ではあると思う。今回は、企業からの参加を期待して、企業勤めの方への、周囲へのお声かけをお願いしている。周囲へ言いふらしていただけない?と厚かましくお願いしている。ありがたいことに、会社の休憩室に張っておきました、などと伝えてくださって色々なことろで助けていただいているなと改めて、その人との関係に、熱い気持ちを思うのである。今のところ、コーチング&ファシリテーションの両日への参加を申し込みしてくださった方が、コーチ仲間から2名。ファシリテーション講座への参加意向は、3人。コーチング講座はまだ、1人と言ったところだ。まだまだ、広く伝えるより自分の周囲へ、人頼み、口伝え、まあ口コミしか、手立てを取らないつもりだ。そのためには、良かったと思っていただける「講座の実施]、参加して良かったと喜んでいただけるだけの内容の充実、を、モットーとして講座当日、その日を懸命に尽力を尽くすこと、と思って準備している。
2007.02.14
コメント(0)
-
10日のスペシャル勉強会はお弁当つきでやってみた。
”コーチングが機能する”ということは、コーチが、クライアントを、”結果を出す存在として信じる”ことに始まる。石川さんのご自身の経験実例がベースのエピソードは、場面が生き生きと伝わってくる。落語の熊さん、八田つぁんの会話のようだ。長時間ではあったが参加者一同、すっかり石川尚子コーチのファンになっている。最初に石川コーチが投げかけた”在り方としてのコーチ”というコーチングの原点を見つめた視点は、思いのほか、参加者の気持ちを捉えたようだ。会場一体が石川コーチにラポールを持ち、一生懸命聞いていた。やがて、午前の部が終了し、昼休みへ。今回は、いつもの午後からの勉強会とは違って開始時刻が朝10時だった。終了時刻は石川コーチの飛行機の時間ぎりぎりまでの15時という昼食時間を挟んでの勉強会だった。そこで、事務局としては参加者の方たちに、お弁当をつけた。そして昼食時間をいつもの1時間から、1時間30分へたっぷりとった。供したお弁当は、今福岡でOLたちに人気というマクロビ弁当。福岡の舞鶴にある、エヴァーダイニングというお店のマクロビおむすび工房から届けていただいた。マクロビオテック、ご飯は玄米食で、おかずも自然食材を中心の、肉を使用しないメニューだ。お味のほうも、皆さんの笑顔をみて満足いただけたと確信。コーチの勉強会へのお弁当としてこのマクロビ弁当、スローライフ、薬膳や食育の思想にかなってコーチの皆さんにも支持された。もうひとつ、お弁当を小学校の給食のようにテーブルを囲んで7人組の島を7つ作り、座っていただいた。丁度、隣の同じような部屋が空いていたので、食堂として、次の間を使用できたのがラッキーだった。マクロビ弁当と、皆で囲む給食スタイルでのお昼ごはん、これらが思いのほか、参加者には、好評だったつまり、普段話をめったにしないコーチ同士で、話を十分出来る時間にもなり。参加者同士での感想や、気付きを共感し発散し、テーブルの仲間でしていただけたと思う。これは、ファシリテーション手法的には環境設定、アイスブレークとして、”機能した”のではと…手前味噌で自画自賛のmusamejiである。
2007.02.13
コメント(0)
-
きのうの続き。ヒルマン監督は、…。
昨日の続き。さて、この日負けると12連敗となる試合の前、ヒルマン監督は、選手たちを集めて何と言ったのだろうか?”諸君、チームが11連敗したその責任は、すべて私にある。君たちには、何の責任もない。君たちは、勝つために自分たちの力のすべてをかけて、懸命にやっている。しかし、勝てないのは、すべて采配をする監督とコーチである自分たちの責任だ。君たちには勝つ、力がある。我々は、それを信じている。さあ、今日こそは勝とう。”身体を硬くして、ミーティングルームに集まった選手たちはどう受け止められただろう。お前たちの、力不足だ。バカヤロー。今日負けたら、承知しないからな。…、これまでのことならば、そういう言葉が浴びせかけられたのかも知れない。しかし、ヒルマン監督は、負けている責任は、自分たち監督やコーチの采配のせいだ。と言ったのだ。そして、選手たちに、君たちは、勝てる力を持っているはずだ。これをいわれて、奮い立たない選手はいないだろう。その日、勿論、日本ハムは連敗にストップをかけた。ヒルマン監督も白井一幸ヘッドコーチも、コーチングのコーチ資格を持っている分けではない。しかし、彼らは、見事にコーチングのコミュニケーションで選手たちの、持てる力を引き出している。今、プロ野球の現場にもコミュニケーションにこそ潜在力を引き出す力があることに気がつき始めたようだ。野球のようなメンタル面が大きいスポーツは特にそうだ。大リーグでも、ベンチ内が和気藹々のチームと寡黙なチームでは、競り合ったときコミュニケーションが活発なチームの方が勝つ割合が高いという。そりゃ、微妙なチームワークはまず選手が話をよくするコミュニケーションのよいチームの方が微妙なタイミングでのプレーをこなし、勝敗が決まることはあるのではといえる。そういえば、田口のいるカージナルスはそんなチームだったそうだ。北海道の駒大苫小牧東の選手たちもどんなに点差があっても逆転できるという自信に満ち溢れて最後までプレーをしているそうだ。精神が、明るく、希望を持っていると思いはがけない、力が生まれる。彼らは、経験を重ね、ますますポジティブになっているのだそうだ。コーチが出来ることは、「クライアントは成果を出すことが出来る人である」と信じるスタンスに立つこと。コーチがそのスタンスをぶれなければ、相手は、必ず進歩するのだ。今、彼のいる位置から、少しずつ、しかし必ず前へ進んでいく。それを、確かめ、励まし、伴走して行くのがコーチなのだ。ついつい、我々も、コーチングを学び、実践していくうちにコーチングのスキルの習得に目が行く。勿論、スキルを磨くことは大切だがコーチのあり方、こそクライアントにとって、大きな力になり、彼らの未知の力を、引っ張り出すはずだ。”BEING、あり方としてのコーチ”を改めて、参加者は深く胸に刻んだはずだ。石川コーチ自身、最初のクライアントから、コーチングを依頼受けたとき、まだ、資格を持っていなかった、だから、スキルもない自分がコーチングはできないし自身もなかった。それを、石川コーチのコーチ、小野仁美さんに相談したところ「クライアントはあなたのスキルを信じているのではない。あなたの人間性を信じて、コーチングを依頼してきたのでは?」と激励され、引き受ける自信が出来たという。コーチングは、スキルではない。在り方だ。”機能する”ということは、コーチが、クライアントを、”結果を出す存在として信じる”ことにつきる。そのことをあらためて石川コーチは提示され参加者はコーチングの原点に返った1日だった。
2007.02.12
コメント(3)
-
11連敗中の日本ハム、ヒルマン監督は、選手たちに何と言ったと思いますか?石川尚子コーチの話からご紹介。
昨日は、日本コーチ協会福岡支部の勉強会。2月もスペシャル勉強会として、今年3回目として実施。「今日、良かった。自分にとって、久しぶりに感動する時間でした。」何人かの参加者の方が、帰り際わざわざ鮫島のところへ寄ってこられ、耳打ちし、握手を求められ、言って帰られました。講師だけでなく、企画をしたこちらにも承認をいただけたと感謝です。講師をしていただいたのはわざわざ、札幌から、約束を果たしに自前でお越しいただいた石川尚子コーチ。当初は宮崎で仕事があったのだが、直前に延期になりそうとは知らないこちらはすっかり宮崎からの飛行機でと思い込んでいたのだが。朝10時から、夕方16時まで6時間を越え、予定時間を大幅にオーバーしての勉強会での講演だった。一番伝わったのは、コーチングとはスキルではない。スキルのコーチングではなく、コミュニケーションだけのコーチングでもなくそれは、”存在としてのコーチ”と[結果を出す人]として、コーチが信じているクライアントとの感情のもたらす時間。そんなコーチのコーチングセッションは、揺がないものになる、とのお話だった。今、懸命にスキルを習得しようとコーチングを勉強中の方々には目からうろこ、というか、原点帰りの価値を、再確認できたと時間だったのではなかったか熱狂的なファイターズファンの石川コーチの披露する中から。日本ハムファイターズの、白井一幸ヘッドコーチは、エラーをした選手を決してけなさない、くささない。この選手はできるヤツ、と信じる。そうでなくて、コーチの立場はとれると思いますか。コーチや監督が、選手を信じることで、その選手は次回本当の力を出せるはずだ。それを、「今度ミスしたら、2軍行きだぞだ」といったら、その選手は次回本来の力を次に発揮できるだろうか?言葉一つで、萎縮もすれば、実力発揮もできる。コミュニケーションの力というのはこんなところから始まる。新庄選手は、図抜けて明るかったという。白井さんに、人は新庄ってどんな選手?と聞くそうだ。そんな時、聞かれて、新庄の良いところしか見ていない、だから人にもいいとこころしか話さない。新庄は裏表がない、練習熱心で、素直ですばらしい選手ですよと。すると、ポジティブイメージがだんだんと大きくなっていく。名もない、ファイターズの若手が北海道で初めてフランチャイズとして北海道のチームとなったとき道内の小学校の給食の時間に、3人一組で、たくさんの小学校へ食事をいっしょに食べることだけで行かせたという。野球を教えるとかではない、ただ一緒に過ごさせた。児童たちには、生まれて初めて接する、プロ野球選手たちだ。ニコニコ、選手に名前を聞く、サインをほしがられる。選手たちも、自分たちの存在が、喜ばれることを感じてそれまでの東京にホームがあった時代にはまったく感じなかった仕事への誇りを初めて感じた。すると、その日の夜の試合では、いい気持ちで臨む。ファインプレーも、ヒットも生まれたという好循環が開始したらしい。これって、[承認・アクノリっジメント]が人にいかに機能するかの話。もうひとつのエピソード。優勝の前年、2年前、日本ハム、11連敗ということがあったそうだ。ヒルマン監督は選手を集めてミーティングを持ったという。「そのとき、ヒルマン監督は、選手たちに何といったと思いますか?」石川コーチは、それを、我々にも考えて欲しいと質問した。さて、答えは…。これは、明日書きましょう。お読みの方、是非、あなたがヒルマン監督の立場でどう言ったら監督としての言葉、選手を鼓舞できる言葉を発することが出来るかここは、ヒルマン監督になりかわって考えてみてください。問題 「11連敗中のチーム、その監督は、選手たちに、何を言えばよいのだろう!」以下、明日。書き込み大歓迎です。(弘中勝氏の、13万部メルマガ[ビジネス発想源]のやり方だあ!!?)
2007.02.11
コメント(1)
-
団塊世代のご同輩へ、musameji「自分探しのコーチング・入門編」を、NHK文化センターで4月からスタート。
「自分探し、団塊世代のためのコーチング入門」という企画書を1月の半ば、福岡のNHK文化センターに提案していた。1年間、お休みしていた、「コーチング講座」を、改めて再構成、再設定したいと思った。そして、4月から、講座を1年ぶりで復活することが決定した。こんな呼びかけをしたい。団塊世代の第一陣の皆様、“よりよく生きるために、「コーチング」で、新しい人生の設計をしませんか?”そして、もっと仲良くなって、お互いの絆を大事して行く。そこに賛同し、行動できる人たちが、まず集い、地域を、社会を変えるコミュニケーションの第一歩を踏み出しませんか?昨年60歳を迎えた昭和21年生まれは約152万人今年2007年に60歳を迎える昭和22年生まれは約225万人(団塊世代第1期) 一気に1年で73万人が増加。これが3~5年続く。まさしく年齢ピラミッドの大団塊。企業・組織などで働いてきた人達が、60歳を迎え、新しい時間、お金、そして知識と経験を携え街に出てくる。みな、今までとは違った生き方を要求され、自己で作り、考えなくてはならない部分が大きくなる。戦後世代の先導として、ベビーブームにうまれたわれら団塊世代は、答えは、選択、マルバツ式で、与えられた課題を達成することで評価され、それに従いつつ、戦後の驚異的復興の一員として、日々汗してきたのだ。これからの彼らの時間、自由はあるが、もしかしたら、たまらなく孤独を実感するかも知れない。自分自身から会社や仕事を取ったら、何も残っていない状態!やがて1年ほど経過した頃、自信喪失、孤独、離婚、無趣味、仲間不在、ひいては引きこもり、自分で気づかないうちに”軽い鬱”状態になる人もいて、いえ、自殺者すら周囲には出てくるかも知れない。生甲斐がもてる前向きの人生に変えて行きたい。思いを共有できる仲間つくりも大事な要素。自分自身が他から必要とされていると思える周囲からの声、承認が、どれだけ励みになることか。”自身の才能や、考えをしっかり作り、自己開示し、自ら実践すること。”そんな風な定年後の生き方を実現すればきっと後半人生は、他人様のお役に立ち、自らも自立し、一層輝くものになるだろう。そんな背景をベースに、新しい仲間つくりへの、“声かけ”として「自分探しのコーチング」、4月10日(火)から、NHK福岡文化センターで開講。第2、第4火曜日の19時から21時。”働く、暮らす、生きる”は、企業を卒業してもまだま続く。あらたな、新しい生き方を再構築するためのヒント、コミュニケーションの日常生活での、考え方とスキル、団塊世代も今このときに、会得しませんか。
2007.02.10
コメント(1)
-
「恋」をテーマにする、musameji。
人生は、楽しみたい。人と付き合うこと、自分を良く知ること、他人を理解すること、好きになれば、何でもジャンプできる若いときは、そうだったではないかということを、だんだん、頭で理解し、ジャンプしなくてはと、分かろうとする「理性」と「感性」の両方が大事だ。そして、それは両者のバランスがもっと必要なんだ…って。直感、直観、この言葉に、どうも釈然としない気持ちを持つようになって久しい。どうしてそうなったのかなあ?直観で決まっていくことってなんだ?恋をするのに、理屈はなかった。恋、若さに恋はつきもの、恋という直観だけは、自分だけの”よすが”として信じきれるものはなかった。ふーん、もう、恋なんて縁がないよなあ。みな、直観でやった、直観で選んだ、とはよく言うこと。世の中に、人々は、直観で、本とは何を求めているのだろう。直観は、直感、でもある。逆に、直感は直観でもある。その背後には、直観を呼び込む、集積、習練があるはずだ。この年になって、敢えて僕はそういいたい。理性は、合理的な考え方、を導き論理的、倫理的、合理的などという、明文化、可視化の領域だ。それは、暗黙知を、言葉で解消したいという試みでもある。くだくだ考えているうちに、そう、もう一度、直観を信じる人生にしなくちゃあと、強く思った。直感といえば、やはりそれは「恋をすること」だと、あらためて気がついた。それは、かつての自分の専売特許だったはずなのに。[恋待ち]、青春期、何もないときよく、[恋]の出現に期待で胸を一杯にしていたことを思い出してくる。恋、いいよねえ。さてその対象は?!それが分かれば、世話ないさ。でも、健全にキャッチフレーズを作るとすると”家族に、初恋。 団塊世代の忘れ物!”なんてのはどう?
2007.02.09
コメント(2)
-
さあ今度は、2月24日、25日は、鮫島宗哉の自主公開講座の実施。
musameji、かつて愛読の立原道造の詩”浅き春に寄せて”にもあるように、「今は2月、たったそれだけ、昔々の約束は、もう残らない…」http://plaza.rakuten.co.jp/musameji/diary/200602010000/なんて、なんか、はかない思い出の季節でもある。学生時代は、学年末試験の真っ最中だった。何かしないと、またまたもう3月ということになってしまう時間かも知れない。さて、今度は、僕自身の、自主公開講座だ。2月24日(土)と25日(日)の2日連続で福岡にて、今年最初の自主公開セミナーを開催する。それぞれ20名定員で募集予定だが来ていただく人数を確保するのがなかなか大変なのも現実。これまで、人数集めは、このWEBと、メールだけが広報!いえ狭報!!の告知媒体である。であるので、皆様の、関心と興味と、クチ込みのサポートが大事な頼りという状況です。今回は、福岡でも、コーチングに加え、初めてファシリテーション講座を実施し、今ようやく関心の集まったところをトライする。コーチングとファシリテーションの双方に、共通するところを是非、実感していただきたく二つ、連続で実施をしてみようと思う。ご参加された方は、きっとなるほどね、そして、楽しかったと断言していただける!、と手前味噌で申し上げます。もちろんどちらか1日だけでも、大歓迎です。昨年8月、北九州某市の7年次の職員の方たちへファシリテション講座を、2日間研修として実施なんとそのときは81人という人数だったが何とか乗り切ったがおかげさまで、アンケート結果が大変良かったので自信を持てたのだ。昨年12月10日に札幌で初実施、今回、福岡での実施を決行する。 概要;:;:;:;:;:;:;:;:~コーチングとファシリテーション、 実践体験の場、2日間の集中開催!~ 円滑なコミュニケーションの実感・実践ラボラトリー!夢の実現は目標と課題を明確に、その達成のために!会話を通じて、人の目標達成をサポートする、話題のコーチング!効果的な会議運営を実現し、集団の知的創造プロセスを引き出す、ファシリテーション! 24日は、コーチング基礎講座、スキルを体系的に紹介、ロールプレーを中心に、体感!“今日のあなた自身の気付き、自己信頼”が、“明日の自分”を勇気付け、励まします。25日は、ファシリテーションの体験、さて、“集団の知的創造プロセスとは?”ファシリテーションは、参加者相互の信頼、新しい出会いも、生みだします。・どちらか一方の参加だけでも、参加はOKです。なお初日終了後、懇親会を予定しています。☆コーチング、ファシリテーション2日間です。日 時 : 2月 24日(土) コーチング講座 25日(日) ファシリテーション1日研修 時 間 : 10:00~18;00 場 所 : 西日本リビング新聞社アビリティルーム 福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号 サンライトビル 9階 市営地下鉄「天神駅」徒歩8分 「西鉄福岡駅」徒歩3分 募集定員 : 20名 講 師 : 鮫島 宗哉 (日本プロコーチ認定評議会 アソシエートコーチ) 日本コーチ協会福岡支部 支部長 / 日本ファシリテーション協会九州支部 運営委員 ;:;:;:;:;:;;:;:ということで、申し込みフォームをここに作りました。http://form.on.arena.ne.jp/rtform18/1630h7wxw2/index.cgi講座料金など、詳細は、お問い合わせください。あるいは、申し込みフォームをご覧ください。ここ、楽天の「お問い合わせ」からでもOKです。私書箱へのメール、心待ちにしております。
2007.02.08
コメント(0)
-
先に、3つ目の嬉しいことをご披露する。musameji
今日は、2つ目の嬉しい話を書くつもりだった。ところが、嬉しいことが実は、本日新たにもう一つあって、先に、3つ目の嬉しいことをご披露する。今週土曜日10日に、日本コーチ協会(JCA)福岡支部の勉強会スペシャルを開催するが、講師として、札幌からICF国際コーチ連盟プロフェッショナルコーチの石川尚子さんを、お招きする。1月28日からメルマガとJCA福岡支部ホームページで告知をしてきたがなんと、本日7日の15時に満杯、満席となったのだ。会場のキャパの都合で、先着50人までと告知していたが締切時間ぴったりで満席になったのだ。大変嬉しい、そして驚きでもあった。日程的に、3連休の初日だし、このところ、わがJCA福岡支部の勉強会は1月11日の本間正人氏のスペシャル勉強会、1月27日は定例勉強会で年間テーマ決め、と連続で開催してきた。お金も時間も、余分に必要だしと2月のスペシャル設定は悲観的要素はあるといえばあったのだが、皆吹っ飛んだ。申し込みが間に合わなかった一部の方から、何とかして欲しいとメールが来たが、今回はルールどおりで行かざるを得ない。満員御礼、まさに嬉しい悲鳴である。早速、まだ札幌にいるはずの石川コーチにも連絡。メッセージが届く!”すばらし~\(^o^)/ですね~。こんなに短期間で、この集客力!!さすが!としか言いようがございません。とても信頼ある集まりを築かれているんだな~と実感します。”福岡支部の集客力は、信頼力!見事にコーチとしての承認メッセージは我々のハートを射てしまっている。今回の講座、石川コーチには、2つのお願いをしている。一つは、”北海道日本ハムファイターズの昨年優勝のヒミツは、コーチングにあり!”というお話をしていただこうとしている。プロスポーツの世界で、コーチングって実際はどう使われているのか?という興味はコーチングを学び、コーチとして活動している仲間たちには大変興味深いテーマであると思ったのだ。石川コーチ自身、ファイターズ熱狂ファンで、白井ヘッドコーチとも親しい。今回、福岡のコーチたちに、このテーマは当たったのではと企画を進めたmusamejiとしては、悦に入っている!自己満足?!2つ目に、石川コーチには石川コーチのプロのこれぞコーチング!を、見せていただこうとしている。実際のコーチングプロセスというのはなかなかみることは出来ないものなのだ。もとより、コーチとクライアントの2人の間で行われるコーチング会話は守秘義務があって成立する。だから、それは他人の目や耳に触れたり入ったりすることは原則ないわけだ。今回は、それを、公開でやっていただこうと思っている。どんな目標設定で、どう行動計画がうまれるか、会場の方からリクエストでコーチングを受けていただこうと思う。これは、わくわくドキドキのひと時だろうと、期待も大きい。人生が変わるきっかけに、コーチングが関係したり、寄与したりすることは実際のところ多いのだ。石川コーチと僕は、札幌で2004年の12月に初めてお会いした。その後、僕が札幌でサポートしていたUHBの番組企画で、出演打診をしたり(実際は石川コーチ忙しくて一回も出演していただけてない)WEBのNETラジオのコーチング番組の「コーチ紹介」コーナーで石川さんがmusamjiに、バトンを渡して下さって、出演したりなんてことがった。そのときの僕の日記http://plaza.rakuten.co.jp/musameji/diary/200510300000/石川さんの出演コーチング番組http://www.on-going.com/wcn/wcn_14_051029.htmlmusamejiの出演http://www.on-going.com/wcn/wcn_15_051105.htmlそして、2005年11月に札幌で開催した、初めてのmusamejiの自主公開コーチング講座に、石川コーチが、ゲストで2時間講座を持ってくださったり、コーチ仲間として、お付き合いをさせていただいてきた。昨年12月のファシリテーション講座では、なんと受講者として参加してくださってプロフェッショナル資格の石川コーチの謙虚さ、真摯な学習姿勢にまたまた、たくさんの気付きと、刺激を受けたのだった。そして今回、発端は宮崎で仕事があるので帰りに福岡へ寄る時間がありますが、お会いしませんかと連絡を頂いたのだ。僕1人で石川コーチを独占するよりはJCA福岡支部の皆様へ、何か話をしてほしいとお願いしたら屈託なく受諾してくださった。こんな展開で準備を進めてきたのだ。運営委員として、1月に発刊された石川さんの著書を是非、PRに努め、少しでも、著作が皆さんにも読んでいただけたらと思う。観光遊覧の福岡滞在を、講師のほうへ使わせてしまうのだからそのくらいは気持ちあらわそうねえという、福岡支部運営委員の気持ちでもある。では、最後は石川さんの書籍紹介。 ”おかげ様で、かねてからの目標であった本の出版にこぎつけました。できあがってしまうと、ただの1冊の書籍なのですが、この形になるまでに、多くの時間と試行錯誤、そして、多くの方がたのご協力がありました。私にとってはとても重みのある1冊です。コーチとして、教育現場を垣間見たときに痛切に感じるものがありました。その体験をまとめました。想いを込めて書きました。ぜひ、お手にとっていただけますと幸いです。”(石川尚子)『子どもを伸ばす共育コーチング ~子どもの本音と行動を引き出すコミュニケーション術~』 岸 英光 監修 / 石川 尚子 著 つげ書房新社 1,785円(消費税込)●第1章:『認められていない子どもたち』との新鮮な出会い●第2章:『枠を作っている子どもたち』との前進しない対話●第3章:『無気力・無関心を装う子どもたち』が自発的になる “存在承認”のアプローチ●第4章:『“わからない”で片付けようとする子どもたち』が “自分で考え始める”アプローチ●第5章:『本当は背中を押してほしい子どもたち』が 一歩踏み出し“行動”を起こし始めるアプローチ●第6章:『無限の可能性を持っている子どもたち』が 未来に向かって“夢”を描き出すアプローチ●第7章:『これからの世の中を変えていく子どもたち』から もらった感動●第8章:『だからコーチングが大事!』
2007.02.07
コメント(3)
-
僕のファシリテーション講座と、FAJ日本ファシリテーション協会
今月は、「コーチング1日講座」を2月24日(土)、「ファシリテーション1日講座」を翌25日(日)に開催を控えている。何人くらい、いらしていただけるかと、やはり気になる。早くも、友人を誘って参加しますと、ファシリテーション講座のほうにはお申し込みがちらほら。ありがたい事である。これまでも、講座を開催することを決めるのはいいのだが宣伝PRは、基本的に友人知人へのメールでしか告知しないので、やはり簡単に人は集まらない。わが身は広告会社出身ではあるが、マス媒体を頼らず、口コミ頼みでそろそろ、西日本新聞や、西日本リビング新聞、など地元活字メディアの効果も確認しなくてはいけない。福岡地区の、コミュニケーションに興味を持っていただけるターゲットにパブリックリレーションが成立すればと思うのだがなかなか難しい。そんなやや、憂鬱なこの数日の間に、実は嬉しい話が、2つ起きている。今日はそのうちの一つを、お話する。昨年12月、札幌で、「ファシリテーション講座」を実施した。http://plaza.rakuten.co.jp/musameji/diary/200612130000/その参加者の中から、4人の方たちが、2月1日に、”FAJ日本ファシリテーション協会”の会員登録をしてくれたのだ。そして北海道でもファシリテーションの普及を願って、FAJ北海道支部の設立をしたいとの意向まで表明くださったのだ。僕のファシリテーション講座は、自主講座であるが、FAJの伝えようとする基本部分は押さえていると自負している。そもそも昨年8月に、2日間研修として北九州の某市で、講師役を依頼されたことが、ファシリテーションの講師にも手を染めた最初である。講師をするにあたり、テキストはオリジナルを求められた。作成にあたっては、巷の関連書籍をかなり読み込み僕なりにそれまでの、基礎知識と情報を再構築し構成した。結局出来上がったテキストは、なんとFAJ会長の堀公俊さんの著作数冊からのメモや抜粋が一番多くなった。結果、まとめたレジュメは、軽くパワーポイント200枚を越すものになってしまった。つまり資料作成のための読み方、要旨をつかみ、メモを作りながらという作業で、僕にとってはFAJ会長の堀公俊さんの著書[ファシリテーション入門]日経文庫が中でも一番すごい本だということが、明確に分かってきた。新書の小さな本ではあるが、ファシリテーションの把え方と説明、密度の濃い内容と全体の構成がすばらしい。理論だけにとどまらず、多くのアイスブレークや、スキルを漏れなく、ダブりなく紹介、触れているが、決してカタログ的ではないのだ。簡素で的確な説明の奥に、ふかい知識と経験がこめらている堀さんの文章が伝わってくる。実際の講座進行に当たっての、アイスブレーク、ツール紹介、そして時間配分など、FAJ九州支部の加留部貴行支部長から学んだメモの書き込みが、講師手元用のテキストである。さて、出来上がったテキスト、これは、堀さんにも見ていただかなくては、と思った。こんなテキスト作ったのですがご承認を頂きたたいと思った。まず、どうしたらいいかなと、支部長加留部さんに、みてもらい相談した。すると、こともなげに”堀さんに直接相談しちゃったら?”この一言で、福岡にいらしたときの堀さんにお会いした。その後資料をメールで見ていただきあっさり、そして快く、ご了解を頂けたのだ。出来上がったテキストは、7割FAJ公認!?、3割鮫島宗哉オリジナル!という構成のモノになった。そんなテキストをベースに2日間研修をまずは8月に実施したのだ。おかげさまで、希望者81人に対しての講座であったが、無事終了。その後送られてきた、研修評価でのアンケートが、皆さんから想像以上の好意的反応で、大変嬉しかった。それは、僕もファシリテーション研修をこれからは実施できるという大きな自信になったのだ。http://plaza.rakuten.co.jp/musameji/diary/200608180000/”頼まれごとは、試されごと”とはsumairuさんが、ご自分の日記で書いていたがまさにそのとおり。そのときの2日間を「1日研修」に圧縮して、札幌で実施をした。札幌での講座の始めに、日本ファシリテーション協会北海道の結成を皆様には目指していただければ嬉しい、とアジテーション!したが、見事にそれに答えてくださったと思うのだ。北海道での発起人のS,M氏から、準備にあたって、何をまずしたら良いのか、規約や組織表はあるのだろうかと、鮫島へ相談があった。僕からは、直ちにFAJ九州支部の運営委員たちにメールをした。会長の堀さんにもメールが目に留まり、すぐご自身からもメールを頂いた。北海道でのこのような動きガあることを喜んでくれた。後はお任せできることになった。本部の理事のお1人が、今北海道釧路で長期出張で仕事をしているなど情報もあってサポート体制イメージも固まってきた。今後、北海道の立ち上げを、もし福岡からもサポートできたら九州支部運営委員もかなり嬉しいはず。だって、まだ北海道行ったことないという九州支部会員は意外に多いのだ。直行便が増えるきっかけ!にはならないか。今日は、ファシリテーション関連での、一つ目のニュースを、書いてみた。明日は、もう一つの嬉しいニュースを書いてみる。
2007.02.06
コメント(1)
-
今夜は、料理は、僕が…。musamejiのハンバーグだ。
さて、今日は、僕は終日家で仕事。外での仕事がないときは、企画書や、新しい講座の準備の為の資料つくり、そしてメールを書いているとあっという間に時間がたっている。昼は、家内が生ラーメンを使って、醤油ラーメンを作った。夜は、家内が、英語の家庭教師というので僕の出番。最近、2週間に一回程度だが、料理を担当する。ぼくが担当する時の定番メニューは、ハンバーグがおおい。丁度、会社を辞めて程ない頃、NHKテレビ「今日の料理」で覚えた取って置きのハンバーグの作り方を、僕流でやっている。今日はそのレシピーを、昔の日記から紹介する。;:;;:;:2003年4月30日の日記から抜粋半年ほど前、NHKの料理番組を見ていたら、ハンバーグの作り方のコツが非常に説得力をもって紹介されていたことがあり、それを見てためしに作ったところ思いのほか上手にできて、[お父さんのハンバーグ」と言うのが今や定番になっています。では、作り方を紹介しましょう。材料・牛肉ひき肉170グラム、・豚牛のあいびき400グラム、・牛乳1/2カップ・塩小さじ1/2・たまねぎ1個、・パン粉15グラム・卵2個・ナツメグ、・胡椒少々おいしく作りる秘訣の第一は、まず1、牛のひき肉170グラムの方を包丁でさらに細切れにして、たたいて、それに塩を小匙2分の1、溶き卵1個、をいれよくかき混ぜ、5、6分間、グチャグチャになるまでこね合わせ、とことん練るのです。(これが、あとから加える合びき肉のつなぎの機能を持つ、いわば糊の役目になるものです)2、次に、たまねぎ1個をみじん切りにして、オリーブ油大さじ1を落としたフライパンで炒める。みじん切りの最初の分量の半分程度になるまで、よく炒め、別の皿にさましておく。3、ボールにあいびき400グラムに、牛乳でふやかしたパン粉(1/2カップ)、さっきのたまねぎのさましたもの、ナツメグと胡椒少々、塩小匙1/4を入れ、ざっくりとかき混ぜまし、最初のペースト状の肉をくわえ、指でざっくり混ぜる。このときはあんまりかき回しすぎないことが大事、そのほうが肉の味が活きて、おいしい。4、一個分約150グラムのお団子にして平たくして、真ん中をちょっとへこませオリーブ油大さじ2をひいた熱してたフライパンにかける。5、このあとにもうひとつのポイントで、最初の3分は中火でやや強めに下の面がよく焼けるようにします。これは下地としてある程度強度を持たせるためで、さらにバターを1カケラ、風味付けに落とし、弱火でフライパンをゆすって油をよくまわしふたをして約4,5分。6、白っぽくなったらうらがえして、ふたをしてさらに2、3分、しみでてきた肉汁をすくってはかけるという行為をします。いつも火が強すぎてうらがえしたら、見た目に焦げ目が結構きつい事が多いのですが、このくらい平気だよと取り合わずにします。7、表面から透明な肉汁がでてきたらハンバーグの焼き上がり。8、フライパンに残った油にケチャップとウスターソースをいれて煮立たせて、さらに粒マスタードをいれてかきまぜると、ハンバーグにかけるソースができあがり。9、あとは付け合せの野菜ですが、お勧めは、サヤエンドーのバター炒め、サーッと茹でて、お湯をよく切ってからバター、塩、胡椒を加えてフライパンでいためるのです;:;;;:;:;もう何回も作っているのでだいたい手順や塩梅は頭に入っている。あらためてレシピーをみると今は、かなりおおざっぱになっている。ポイントは、基本の肉を良く練ってのり状にすること、たまねぎをあらかじめ炒めておくこと。塩と胡椒の塩梅。パン粉をあまり多くしないことが、外れない、おいしいハンバーグのコツのように思う。きょうの付け合せは、キャベツの味噌汁。付け合せは、コンビーフ入りのキャベツとピーマン炒め。このハンバーグ、これまで、子供たちからは大好評で絶対残されたことがない。家内は家内の作り方で、ハンバーグを作るので我が家は、2通りのハンバーグがあることになる。ぼくの作り方はちょっと手間が掛かるので、家内は自分はいいわ、といって、ぼくのやり方を覚えようとしないのだ。まッ、いいか。
2007.02.05
コメント(1)
-
日曜日の過ごし方。
昼間は3月を思わせる暖かい日曜日であった。久しぶりに再開のジョギングだが、毎日続けている!今日は、日曜なので、休もうかなと思っていたが夕方、家内が、ウオーキングするというので、では一緒にと付き合う。夕方になると気温は冷え込んできて、マフラーを首に巻いて、運動スタイルというより、普段着の防寒だ。中2の娘はテレビを見ながらソファでうたたねをしており、声をかけても億劫そう。シューティングゲーム用の自慢のガンの手入れに余念のない高1の息子のほうは、珍しく一緒についてきた。長男は、最近母親である家内に、何かと話を仕掛けるという。よく笑っていると家内は嬉しいようだ。やはり見ていると女親は男の子に親しげで、父親はその逆だ。ただし、我が家の場合、娘は、決して父親に親しげにしてはくれない。我が家は、博多湾に面した福岡市西区のマリナタウンという地区にある、約1キロの海岸線の波打ち際まで、我が家のマンション棟から約200メートル。我が家をでて、海岸の一番端にまわり、そのまま一周してもどってくるコース。ウオーキングのスタイルを真似て、手をしっかり振って歩いてみる。ジョギングとウオーキング、足の筋肉の使う部分が違うのかいつもと違う足の疲労感を感じる。夕方の海岸。いろいろな人たちが浜に出て、楽しんでいる。熟年夫婦と思われるウオーキングカップル。結構多いのが黙々と入っているジョギングの人たち。男性や女性、若い人も年取った人も。ベンチで肩を寄せ合う若いカップル。自転車も多い。砂浜でキャッチボールをしている、小学生とその父親。数人でキャキャ言いながら、写真を撮って群れている女子高生。カイト凧を揚げて走る子供たち。車椅子をおしながらお年寄りに寄り添いゆっくり歩いている初老の女性。防波堤では、釣りをしている人びと。われら家族は、夫婦はバラバラ。並んで歩くなんてまったくしない。僕は、満ち潮になってきた波打ち際を海水につからないようギリギリのコースを楽しむ。砂の上なので、足首が負荷がかかって、より運動になるのもいい。家内は、コンクリート舗装の松林寄りのサイクリング道を、僕とはすっかり離れて歩いている。息子はとみると、さらにその奥の松林の道をあるいている。皆ばらばらだ。最後は、マンションの近所にある、スーパーで待ち合わせ夕方の買い物と、アイスクリームを買ってもどってきた。朝は、映画にみなで行きたいなどといっていたが、結局ばらばらに動き出しなにもしなかった日曜日。とうとう今日一日も暮れていく。外食もせず、夕方のつかの間のウオーキングが唯一の休日イベントだったと思えばいいか。お金も使わない、平和な1日というべきなんだろう。
2007.02.04
コメント(2)
-
ファシリテーションの入り口って、こんなところから…。
ファシリテーション、初めての人々同士が集まっているとき、緊張感がとれて、だんだん打ち解け話をしたくなって、互いが、相手から引き出し、新しい何かを作り出したり、やりたくなったりする。そんなことではと思う。ファシリテーションの講座の準備をするとき、今回はどうしようかなあと考えているときが結構楽しい。例えば、しょっぱなの「グループ分け」をどういうやり方で、実施するかということなど。もし、20人の人が集まっている、とする。その当日初めて出会った人ちを、5,6人で1グループとし5人なら4組、4人なら5組としたいと運営進行したいこちらは、考える。一番簡単な方法は、こんなやり方である。全員を、アイウエオ順で、グルっと円になって並んでもらう。普段は「姓」で並ぶことが多いそれぞれの名前。今日は、下の名前、「ファーストネーム順」で、行きましょう、なんて言うと、すぐ、盛り上がる。職場では、ファーストネームで自分を呼ばれる事などほとんどないから新鮮である。大企業の、部長が、ゆういちくん、まさおさん、けいすけさん、などと分かるとほほえましかったりする。たまに、姓は違うのに、名前は、一緒で”ひろしくん”同士だったなど、お互いの親密度が上がることもある。ではア行の方は、この辺ね、あきらさんという名前のかたいますか?次、カ行の方は?…では、出来たところで、一番最初の方から、番号を入ってください。1,2,3,4、5まで、一巡りして、では、1番の方でここへ、2ばんの方でここ…などとグループを作る。これは、ラインナップという、「アイスブレーク」の一つ。他に、誕生日順(誕生月も)とかも、作りやすい。ラインナップではみな、自分のことを、言わないと、人との位置関係が取れないので、いやおう無しに自己開示する。それを情報として、自分の位置を知ることになる。そのためには、自分のことを、それそれが、クチにだし、人に伝え、アッピールし会場を動き回らないと、自分の場所が決まらない。その場所は、他人との関係で、明らかになるのだ。簡単なワークであるが、ファシリテーションのための一番最初の自己開示と、他者の情報の必要性、重要性を感じていただける。今回はほかに、もっと面白いグループ分けはないかなあと別のやり方も、考えようかなあ。例えば、当日の全員の中で、”同じことでくくる共通の仲間さがし”をするのはどうかな。特徴、特性は何かを考え、全員にアンケートしながら、その人たちが全体で何人くらいいるかを見るのって面白そうだ。めがねの人、フーン50パーセント以上だ、とか。ネクタイの人。今朝、6時前に起きた人!などもある。会場の皆さんにも考えてもらう。大体、外観など、外からわかる事実で聞いていく人が多い。だんだん、工夫したくなる。今日の行動ですが、交通手段で、バスで来た人!とか、今朝、ご飯を食べたか、パンをたべたか、それとも食べなかったか、さらに、好き、嫌いを聞きたくなったりする?ホークスファン?、ファイターズファン?ジャイアンツファン?、タイガースファン?音楽ではどう?クラシック派?ポップス派?ジャズ派?など。うーん、もうちょっとひねって、”10人に1人”という条件で、全体の10パーセントのことは何だろうと考えて見ましょう、というやり方でグループを作るのはどうかな。自分の特徴や、個性で、”10パーセントの仲間がいること”って何だろう?結構この発想は面白そう!例えば、福岡に住んで、10年以上経った人!40歳まで、独身だった人!転職経験がある人!ピアノを習ったことがある人!ウン?だれのことだ?!ひょっとして自分を基準に言ってないか!!タモリの、「笑っていいとも」の番組の中で、ゲストに、100人に1人の確立のアンケートというのを、毎日しているけどあれも、アイスブレークの一つだね。その会場の参加者全員が一つになって共有空間をつくり、一緒に番組を進行し、盛り上げていくという雰囲気を作るのだ。ファシリテーションの導入で用いるアイスブレーク、氷を割る、つまり、緊張感のある、初対面の集まった人々の気持ちを溶かす、そして、まず気持ちから一つにまとめていくという意味合いだ。ファシリテーションなんて、難しくいうけれど要は、気持ち共有することから、まずは始まるのだ。そして、共有できることは気持ちから、情報へと、だんだん進み、自己を開示すると、他人の開示も受け入れやすくなるというプロセスになっていく。あなたも、こんな、プロセスを一緒にやってみませんか?2月25日(日)鮫島宗哉のファシリテーション講座、お楽しみに。
2007.02.03
コメント(0)
-
我が家では、ニワトリを飼っていたことがある、子供時代の話。
今、宮崎県で、トリインフルエンザが3箇所で発生し、東国原知事も就任そうそう、大変だ。子供の頃我が家では、ニワトリを庭の一隅に小屋を設け飼っていた。東京の世田谷だったが、常時10羽くらいはいた。毎日産み落とされた玉子を取りに、トリ小屋へ入るのは、子供の僕の仕事だった。1950年代初め、昭和25,6年のころの話だ。当時ニワトリは、貴重な蛋白源玉子は、栄養源で、モミを入れた紙箱のなかにおさめて入院見舞いになどに持参したほどだ。ニワトリの餌つくりもやった。大根の菜っ葉を細切れにして、米糠をまぶし、だしをとった後の煮干など混ぜ、水を加えてかき混ぜて出来上がり。トリ小屋中に5,60cm位の長い、底が三角形の餌箱があって、バケツで運び、それを入れていく。円い、トリの飲み口む部分が、受け皿のように飛び出て、必要な量だけ水が出るという独特の容器もあったなあ。トリ小屋に、アワビの貝殻をいくつかぶら下げていた。夜、貝の内側が光るので、イタチ避けといっていたが、ホントにイタチがいたのかは分からない。ただトリが襲われて、朝見ると羽が散乱していた記憶はある。白色レグホンが多かったが、チャボも時々いた。僕は、3歳くらいの頃、飼っているニワトリに額をつっつかれて、後年もしばらくその傷あとが残っていたことがある。大きなオンドリのトサカとクチバシが迫ってきたことだけは、今でもありありと目に焼きついている。泣き声を聞き付けた祖母がすぐに駆けつけ救いだしてくれたがその憎っくきオンドリは、その日のうちに絞められて、夜の食卓に乗ったらしい。僕らの子供の頃は、鶏肉というのはあまり好物ではなかった。家で飼っているトリを絞めて、肉をとるということもあったが、その肉は、決して今のようにやわらかくはなく美味いものではなかったと思うのだ。子供の頃のことはいくらでもきりなく、思い出す。こんなことでも、書いておかないとどんどん忘れて風化しちゃうんだなあ。宮崎の、トリインフルエンザが、最小被害で終結することを祈らずにおれない。
2007.02.02
コメント(1)
-
musameji、2月1日から、ジョギングを再開した。
今日から2月かあ、!!ですね。久しぶりに朝、ジョギングを再開約30分、自宅周辺のいつものコースを走る。我が家は、福岡の玄界灘の博多湾に面する能古島を正面に見る位置。左に、壇一雄の住まいのあったことでしられる能古島、右に金印の出土した有名な志賀島を眺めながら走れるという絶好のジョギング環境だ。海岸線を沿って走り、室見川防波堤の先でターンもどってくる中間に、お隣のマンション群の中庭がある。そこに備えてあるスポーツ遊戯で、懸垂や、腹筋、屈伸などを休憩がてら念入りにして、また走り出す。チンタラスピードであるが、30分位である。今日は海風が強く、追い風だった往きは、ひょいひょいと走れる。ちょっとまだ寒く、首までウインドブレーカを引き上げる。耳には、MDウオークマンからのヘッドホーン。聞いているのは、自分のコーチング講座の録音なんだ。自分のしゃべりの改善は、自分が一番分かると思い、できるだけ、録音したものを、聞き返すのだが、とりっぱなしがたまっている。人前での話し、自分で聞くと、キリなく、もっともっと、あそこはこういう言い方があったなどとこれで良かったとは思えないものばかり。走っている距離は、万歩計で4000歩足らず。たぶん距離で3キロちょっとだろう。息がハーハー言うほどの走りかたではない。せいぜい、もどってきて最後の、我が家のあるマンションの7階まで、階段を、出来るだけ駆け上がって終了、がいつものやり方である。ちょっと汗ばんで、さっと浴びるシャワーが気持ちいい。体重が1キロは落ちているのが嬉しい。今朝は、久しぶりだったせいで、走り出しでふくらはぎとひざがしばらくしてがくがくしたが、なんともなく、身体中の循環が良くなった感じでさわやかである。このところ朝早くの時間で、クライアントさんとの「コーチング」を入れるようになって朝、走る時間設定がどうも億劫だったがやはり運動後の爽快感は、得がたいもの。2月、毎日走り再開と決意。この日記も、こんな感じで、毎日かけるかな?
2007.02.01
コメント(1)
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
-

- 楽天写真館
- 2025年 1-3月 フラワーケーキ VOL.3
- (2025-11-14 04:30:22)
-
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-12 17:20:55)
-
-
-
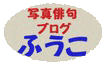
- 写真俳句ブログ
- 夕焼けチャイム fu
- (2025-11-14 14:28:22)
-







