2009年03月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
ジャン=ルイ・フランドラン『性と歴史』
ジャン=ルイ・フランドラン(宮原信訳)『性と歴史』~新評論、1987年~(Jean-Louis Flandrin, Le Sexe et l'Occident, Seuil, 1981) 性や家族の歴史に関する研究で有名なフランドランの論文集です。原著は、以前紹介したJ=L・フランドラン『農民の愛と性―新しい愛の歴史学―』よりも後に出版されていますが、邦訳は同『農民の愛と性』よりも先に刊行されています。 まずは本書の構成を掲げてから、印象に残ったところを中心に内容紹介や所感を書いていきたいと思います。 本書の構成は以下のとおりです。ーーー序 「性」の歴史のためにI 愛 1 感情と文明―書名調査から― 2 単数形の愛l'amourと複数形の愛les amours(十六世紀) 3 トロアの婚約儀礼=クレアンターユ(十五―十七世紀) 4 愛と結婚(十八世紀)II 性道徳と夫婦の交わり 5 結婚に関するキリスト教教義―ジョン・T・ヌーナン著『避妊と結婚』をめぐって― 6 西欧キリスト教世界における避妊、結婚、愛情関係 7 閨房での男と女III 子どもと生殖 8 幼少年期と社会―フィリップ・アリエス著『<子供>の誕生』をめぐって― 9 乳幼児への態度と性行動―過去における構造とその変化― 10 子どもに関する新旧俚諺 11 フランス古俚諺中の娘たちIV 独身者の性生活 12 晩婚と性生活―論点と研究仮説― 13 若者の性生活における抑圧と変化 14 イギリスにおける家族と非合法的愛―ピーター・ラスレット著『旧世代の家族生活と非合法的愛』をめぐって―原注訳者あとがきーーー 序も含めれば15の論文が収録されていることもあり、調査対象も調査方法も多様なものとなっています。 いくつかは未刊の論文も含まれていますが、基本的には、既刊の雑誌論文を再録となっています。序論で、「性」の歴史の意義と本書の構成(対象や方法)について概観した後、それぞれの部の各論に移ります。それぞれの部の冒頭には、そこに収録された数章の初出とその簡単な紹介も記されています。 第1部の1,2,4は、特に書名の分析を通して、愛についての過去の態度(や意味合い)を探ります。 第1章は、16世紀と現代の出版物一覧を利用して、そこに現れる「愛」という言葉の数や、用法を分析します。第2章は特に、そのタイトル通り、単数形と複数形の愛が、それぞれどのように使われるかを分析しています。いろいろ西洋史の研究を読んできているつもりではいますが、このような書名調査は珍しいのではないかと思います。 数量的分析も行ったこうした章は、その方法論は興味深いですが、第1部の中では特に第3章を興味深く読みました。これはクレアンターユという婚約儀礼の分析で、民俗学的な性格もあります。 クレアンターユというのは、特に男性が、意中の女性に対して、結婚するという意図をもって贈り物をし、女性も、そういう意味のものとして、その贈り物を受け取る、という儀礼です。本来、キリスト教社会の中では、婚約にも司祭の立ち会いが必要だったようですが、この儀礼は、司祭の立ち会いなしに、本人たちだけで行ったことにその特色があります。贈り物は、その内容自体は特に重要ではなく、たとえば梨ひとつ、切り分けた菓子ひとつ、なんていうのも例として挙げられています。「贈り物の授受こそがもっとも重要な儀式だったと思われる」(75頁)というのですね。 第二部では、第6章が分量もあり、興味深かったです。フランドランは、特に16世紀以降の、近世~近現代の時代を専門とされていましたが、本章では初期中世についても、懺悔聴聞規定書という史料をふんだんに援用しながら記述しています。特に大きなテーマは、西欧キリスト教世界のなかで、避妊がどのように認識されていたか、ということで、このことについて通史的に整理されています。「反自然の罪」(同性愛、自慰、正常位以外の体位などなど)について、懺悔聴聞規定書がどのように規定しているかを分析した後、あらためて避妊の位置づけが検討されます。夫婦の中の避妊と、婚姻外関係の中の避妊ではどう解釈が異なっていたか、ということにも目を向けながら、結婚や愛情についても検討していきます。 第3部。まず第8章は、もはや古典的研究ともいえるフィリップ・アリエスの『<子供>の誕生』の「批判的要約」となっています。 16-17世紀頃以前は、子供は小さな大人として捉えられ、<子供>という観念が登場したのが16-17世紀である、というのがアリエスの説の大きな部分ですが、もちろん現在では批判もされています。同時に、その書の意義はいまなお大きく、たとえば徳井淑子先生は『色で読む中世ヨーロッパ』のなかで、服飾史の観点からアリエス説を評価しています。いずれにせよ、西洋における子どもの歴史を勉強する際には、避けては通れない基本的文献でしょう。 第10章と第11章では、ことわざを史料に用いて、子どもや娘たちの社会における位置づけを検討します。多くのことわざが紹介されているので、それだけでも楽しいです。 なにより、第3部の中で―そして私は本書全体の中でも―興味深く読んだのは、第9章です。初期中世から近代まで、通史的な観点で、子どもに対する親たちの態度を分析し、その中で、愛情や性関係についても検討します。とくに、ここでは子どもの数の抑制に関する検討が多く、長期にわたって嬰児殺しがしばしば行われていた、ということが説明されます。その他、避妊、中絶、里子の慣行についても言及されます。この章を読んでいると、特に、ものごとに対する人々の感性、よくいう心性が、いかに時代や社会によって異なっているか、ということを感じさせられました。フランドラン自身も解説も特に言っていないと思いますが、この論文はいわゆる心性史研究の成果に数えられるのでは、と感じました。 第4部はいささか疲れ気味で読んだこともあり、十分に読めませんでした。晩婚や若者の性行動については、『農民の愛と性』でもふれられていたため、その知識が補強される部分がありました。 第14章はラスレットの研究に対する、きわめて批判的な書評となっています。 全体についてざっと書いてみましたが、一点だけ訳書として残念だった点を書いておきます。それは、人名表記にブレがあること。ヌーナンという研究者はしばしば言及されるのですが、ノオナンと書かれた箇所が多々ありました。また、聖アンブロシウスという名が登場したすぐ後、同一人物が聖アンブロジオと書かれていました。これらが、特に気になりました。 なお、本書は1992年に『性の歴史』と改題され、刊行されています。この新版は未見ですが、こちらではこれらの表記が整理されているかもしれません。 以前に一度は読んだことがあるはずなのですが、ほとんど覚えていないのみならずこうしたメモも書き留めていなかったので、今回あらためて通読できて良かったです。なにより、2009年3月現在で手元にあるフランドランの著作が、これで全て読めました。 特に、初期中世からという長期的な視野で一つのテーマについて分析した第6章と第9章が、興味深かったです。その他、近代に関する研究でも、史料や方法などについて、勉強になりました。(2009/03/24読了)
2009.03.29
コメント(0)
-
ジャック・ヴォワズネ「獣性と世俗の軽蔑―5世紀から11世紀」
Jacques Voisenet, "Animalite et mepris du monde (Ve-XIe siecle)"dans Jacques Berlioz et Marie Anne Polo de Beaulieu (dir), L'animal exemplaire au Moyen Age ― Ve - XVe siecle, Presses Universitaires de Rennes, 1999, pp. 29-40. 今回は、ジャック・ベルリオズ/マリ・アンヌ・ポロ・ド・ボーリュー監修『中世の模範的動物―5世紀から15世紀―』所収の、ジャック・ヴォワズネ「獣性と世俗の軽蔑―5世紀から11世紀」を紹介します。 まずは論文の構成を紹介した後、その構成にしたがって、感想も加えながら、全体的な内容紹介を書きたいと思います。 本論の構成は以下のとおりです([ ]内はのぽねこによる補足)ーーー[序][第1節] 禁欲と、堕落の動物誌[第2節] 聖なる虫[第3節] 「小さな」虫[第4節] 救済の翼ーーー 初期中世以来、修道士(修道的生活)は、世俗を離れ、世俗の富を蔑視し、天を目指して生活することを目標としました。この世俗(悪)と天(善)の対比には、動物のイメージもあてはまります。この論文では、その代表として、虫(地を這うもの)と、鳥(空を飛ぶもの)の二種類の動物に焦点が当てられます。 第1節は、修道士たちの禁欲に対する態度を中心に見ながら、それに関係する動物たちについて論じます。 世俗の生活(人生)は、つかの間の、はかないもので、クモが巣をはる行動のようなものだ、という考えがあったそうです。財産、名誉、性欲は拒むべきものとみなされました。財産については、物質的な豊かさは、結局は虫に食われてしまうよ、ということで、そのはかなさが強調されます。性の拒絶については、性の交わりなしに子どもを生むと考えられたハゲワシや、自然発生する(と考えられた)虫が、その模範となります。 虫は、大食らいで、土を這っていることから、特に堕落と結びつけられましたが、しかし、その自然発生はマリアの処女懐胎の例証となっていると考えられたように、聖なる側面も持っていました。 第2節は、その虫の聖なる側面について論じます。 修道士は、謙遜という美徳を追求するため、あえて体を傷つけたり、みすぼらしい恰好をしたりしました。そこで、虫に服を喰わせたり、あるいは傷口を喰わせたりする聖人もいたという例もあります。 また、第1節の部分でふれたように、その自然発生は、虫に誕生と再生というイメージを与えることになります。 第3節では、虫という蔑視されるような存在に近づくことが、救済を求める者たちには不可欠だと考えられたという例が示されます。具体的には、アリとミツバチという二つの虫について、簡単に記されます(それぞれ1段落)。 たとえば、アリは、財産を共有し、共同で働きますが、これは修道院で財産を共有し、共同で働く修道士になぞらえられます。 最後に第4節は、翼や羽の象徴性について論じます。第3節の最後にふれられるミツバチが羽をもつことから、ここに話が発展しています。 具体的に取り上げられる動物(鳥)は、ワシとハトです。ワシは、その急上昇が天に近づくこと、つまり善を象徴しますが、急降下することが世俗的生活への接近ということで悪くとらえられるという、二重のイメージをもっていました。ハトは霊的生活の象徴で、たとえばアルルのカエサリウスという人物は、禁欲や施しによって世俗財産から解放された人々は「霊的なハト」になる、と言っているようです。 特にこの節で強調されているのは、羽が遠心的運動と上昇的運動の二つを同時に示す、ということです。遠心的運動というのは、世俗や罪から離れていくことを示し、上昇的運動は、そのまま天の救済に上っていくことを示します。 このように、この論文は、聖人伝や修道院の戒律(会則)を主要な史料としながら、修道士たちが追い求めた、禁欲と世俗の蔑視を中心とする修道的生き方と、動物との関連を示しています。 短い論文ということもあってか、あまり強いインパクトはありませんが、あえて挙げるならば、羽がもつ二重の象徴性(遠心的運動、上昇的運動)がこの中では強調されていて(第4節の中で、二度書かれています)、興味深かったです。(2009/03/24読了)
2009.03.28
コメント(0)
-
筒井康隆『私説博物誌』
筒井康隆『私説博物誌』~新潮文庫、1980年~ 博物誌風エッセイ集です。50の項目があり、動物、植物、鉱物が、架空の存在も含めて紹介されています。 まず、動物学者の日高敏隆さんの解説によれば、これらの動植物などに関する記述それ自体に誤りはないそうです。本書で取り上げられる動植物のなかで、興味をもったものについてはネットで調べながら読んだのですが、本書に書いてあることが書かれていて、勉強が深まるといった具合でした。 筒井さんのお父様は動物学者で、大阪・天王寺動物園の園長をされていた方だそうですが、そのお父様も本書の中で幾度も言及されるだけでなく、監修も手がけられているそうで、興味深かったです。 さて、本書の記述の特色は、動植物を取り上げながら、その関連で人間の在り方を描く、というところにあると思います。ときにはドタバタ作品風の記述もあったりですが、そのような「フィクション」と、取り上げる事項についての記述ははっきり区別できるので、誤解はまずないでしょう。 では、50項目全部取り上げるのは大変なので、興味深かったところを中心に書いていきます。「ヤドリギ」で、寄生動物をいくつか紹介しているなかで、私たちにもなじみ深いものとしてヤドリガニが取り上げられています。あの、アサリを食べていると貝殻の中から出てくる小さなカニが、これだそうです。あれ、寄生していたんですね。貝が取り入れたプランクトンを食べているんだとか。勉強になります。 小説に登場する架空の植物、「トリフィド」。その植物の登場するジョン・ウィンダム『トリフィドの日』という作品が読んでみたくなりました。最近、筒井さんの作品を読むとどんどん読んでみたい作品が増えていきます。「アホウドリ」では、それを絶滅寸前に追い込んだのがある個人だったということを知って、勉強になりました。羽毛は羽根布団に、肉は肥料にされたとのことですが、アホウドリは捕まえやすいことから、どんどん殺されたのですね。 またこの項目では、クジラの乱獲についても言及があります。クジラの数が減ったのは、日本が捕鯨に乗り出す以前、欧米諸国による乱獲が原因なのに、こんにちの日本による捕鯨を責めるのは身勝手である、と書かれています。まったくそのとおりですね。ただ、筒井さんの記述は、そこで欧米諸国を非難するだけにとどまらず、もっと広い視野をもたれていることに特徴があり、変なプロパガンダみたいなものを感じさせないところが素敵だと思います。というのが、ラテンアメリカや太平洋諸国の先住民に対して欧米諸国がひどいことを行ったことに話を広げると同時に、「他民族に対する残虐行為なら、日本人もずいぶんやっている」と、自国もきちんと見つめているのです。 捕鯨の問題については、オーストラリアなどの一部の過激派たちは、クジラは殺しちゃいけないけれど増えすぎたカンガルーは殺していい、みたいなことをおっしゃっているようで、なんともなぁと思います。自国の行っていることを冷静に見つめずに他国ばかり非難するのはおかしなことで、同時に私は、「だから○○人はこうこうだ」というような、変なレッテルを貼って他国を非難することもおかしいと思います。ある国民になんとなく通じる国民性というものはあるでしょう。そしてそれはその国それぞれ。自らの価値観に合わないからといって、他国の国民性を非難するのはナンセンスです。もちろん、他国の在り方によって自国がなんらかの不利益を被る場合もあるでしょうが、しかしその他国の人々をひっくるめて非難するのは間違ったことだと思います。 最近、ネットで、いろいろどうかなぁという記述を目にするので、なんとなく思っていたことを書いてみました。「リンゴマイマイ」の項目は厳しかったです…。陸上軟体動物苦手なので…。「ミチバシリ」の項目では、ワイリー・コヨーテとロード・ランナーの追いかけっこの話があって、楽しく読みました。コヨーテとロード・ランナーのアニメは、大好きだったので(最近も某サイトでたまに楽しんでいます)。 本当はさして毒があるわけでもないのに毒クモとして恐れられることになったというタランチュラについても、興味深く読みました。 というんで、まずなにより勉強になりますし、関連する話や誇張表現も楽しく、良い読書体験でした。やっぱり筒井さんの作品は面白いです。(2009/03/25読了)
2009.03.27
コメント(0)
-

エマニュエル・ル=ロワ=ラデュリ『気候の歴史』
エマニュエル・ル=ロワ=ラデュリ(稲垣文雄訳)『気候の歴史』~藤原書店、2000年~(Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l'an mil, Editions Flammarion, 1983) 近年、気候(あるいは環境)の歴史が注目されてきているようです。 気候の歴史については、たとえば、・永田諒一「ヨーロッパ近世「小氷期」と共生危機―宗教戦争・紛争、不作、魔女狩り、流民の多発は、寒い気候のせいか?―」『文化共生学研究』6、2008年、31-52頁 などがあります。 環境の歴史については、・ロベール・ドロール/フランソワ・ワルテール(桃木暁子/門脇仁訳)『環境の歴史―ヨーロッパ、原初から現代まで―』みすず書房、2007年(買ってはいるものの未読です)・大黒俊二「環境史と歴史教育―究明、貢献、退屈―」『歴史評論』650、2004年、2-9頁 などがあります。また、・甚野尚志・堀越宏一編『中世ヨーロッパを生きる』東京大学出版会、2004年 の中にも、自然と人間をテーマにした部が設けられています。 とまれ、本書『気候の歴史』は、こうした歴史を研究する際の必読書となっているといえるでしょう。 著者のル・ロワ・ラデュリは、『モンタイユー』(刀水書房、1990年)などの民俗学的研究でも有名です(『モンタイユー』を、ものすごく興味深く読んだのを忘れられません)。方法論に関する論文「歴史家の領域―歴史学と人類学の交錯―」については、このブログでも記事を書いたことがあります。 そんな著者は、1960年代には気候の歴史について精力的に研究をされていたようで、本書はその貴重な成果です。 本書の構成は以下のとおりです。ーーー序論第一章 調査の目的第二章 森林と葡萄の収穫日第三章 一つのモデル―最近の最温暖化第四章 「小氷期」の諸問題第五章 作業仮説第六章 中世の気候の年代学と「小気候最適期」の諸問題第七章 気候変動が人間におよぼした影響と気候変動の気候学的要因あとがき原注資料 アスペン会議のダイアグラム参考文献手稿史料図表一覧図版一覧訳者あとがきーーー 以下、印象に残った部分を中心に、全体をかんたんに紹介してみます。 序論と第一章は、気候それ自体の歴史を研究するという問題意識、方法論の表明となっています。 特に興味深かったポイントは、3点あります。(1)人間中心の歴史からの脱却 有名な歴史家マルク・ブロックは、次のように言っています。「風景の目に見える特徴や[道具や機械]の背後に、一見きわめて冷徹な文書やそれを制定した者たちから非常に離れたように見える制度の背後に、歴史学がとらえようとするのは人間たちなのである。そこに到達できない者は、せいぜいが考証の職人にすぎないであろう。よい歴史家とは、伝説の食人鬼に似ている。人の肉を嗅ぎつけるところに獲物があると知っているのである」(『新版 歴史のための弁明―歴史家の仕事』6頁) ル・ロワ・ラデュリはブロックを称賛しつつも、この言葉には異議を唱えます。彼は、歴史家の任務を、人間の専門家にとどめるのではなく、「歴史学者とは、時間と古文書に関わる人間であり、年代順に記録されたいかなるものも彼には無関係ではありえない(……)彼はまた、ある場合には、それ自体としての「自然」に関心を抱くこともありうる」(33頁)と言います。「物理的歴史と人間的歴史もまたありうる」、と。 このことについては、第三のポイントにも関わるのですが、私自身はやはり、究極的にはその時代、その地域に生きた人間を探ることが、歴史学の目的なのでは、と思ってしまいます。物理的歴史は、そうした過去の人間の現実をさらに正確に浮かび上がらせるために有用だからこそ、歴史学にとって有意義なのではないか、と。…しかし、物理的歴史(それこそ気候や環境の歴史)が、今日の諸問題を考える手掛かりになることを思えば、やはりその意義は大きいわけですが。(2)学際的研究 とまれ、気候の歴史を探るにあたっては、伝統的な歴史家が依拠してきた古文書(文字史料)だけでは十分ではありません。気候学、地理学、地質学、花粉学、年輪年代学など、いわゆる自然科学の諸分野の知見をふんだんに取り入れる必要があります。そして本書は、まさにそうした自然科学の成果を多く紹介しながら、過去の気候状況を明らかにしようとしています。(3)研究の二つの段階 ル・ロワ・ラデュリは、気候の歴史には、二つの段階があると言います。第一段階は、(人間中心主義を一切排除して)気候それ自体の歴史を明らかにすること。第二段階は、第一段階の成果を取り入れながら、過去の気候と人間の歴史を結びつける作業です。 本書は、それ以前の研究が不十分であったために、第一段階を中心的に論じます。(1)で所感めいたことを書きましたが、私自身は第二段階の研究が、歴史学の究極的な目標のように思います。もっとも、それも第一段階の研究が不十分であれば、失敗に終わるでしょう。そういう意味で、第一段階の重要性があるのでは、と思うのです。 第二章は、気候の歴史を探る方法として、森林(特に年輪年代学)と葡萄の収穫日に関するデータを手掛かりとする研究を紹介します。 第三章は、1850年頃から、(地球は)「再温暖化」の時期にあり、1940年頃からは、世界的な「冷涼下」が起こっている、というデータを示し、具体的にその分析を行います。このあたりから、気候の歴史を研究する上で、氷河が果たす重要性が指摘されます。 第四章から第六章にかけて、気候の歴史の分析は、新しい時代から過去に遡っていきます。 第四章は、1600年頃から始まり1850年頃に終わる「小氷期」に関する綿密な分析です(本書の中で最も頁数も多いです)。自然科学の知見だけでなく、文書史料も多く紹介されます。私が専門に勉強している時代ではないため、流し読み気味になりましたが、その方法論は勉強になります。また、膨大な知見に驚かされます…。 第五章は、第四章の補足、といえるでしょう。 第六章は、(紀元千年以降の)中世の気候を分析する試みです。文書史料も不十分ですし、科学的データも誤差の幅が大きいようで、この時代の気候についての綿密な分析は難しいようです。簡単に気候の歴史の流れを示せば、1000年~1200年頃に割合暖かい時期、「小気候最適期」があり、 1200-1300年頃にいったん寒くなってきて(氷河の前進)、第四章で分析したように、1600年ころから「小氷期」のピークがくる、ということになります。 第七章は、まず前半が気候の歴史と人間の歴史の結びつきを簡単に検討(特に小麦の収穫について)するという、研究の第二段階の試みとなっています。後半は、気候変動の要因について詳しく論じます。後半は大気循環に関してなどなど、自然科学の知見の紹介なので、ほとんど理解が追いつきませんでした。流し読みでした…。 というんで、おおまかな気候変動の流れについては把握できましたが、細かい部分まで理解は追いつきませんでした。それでも、理解できないなりに、普段ふれることのない気候学の成果(原著は30年近く前になりますので、データは古びているのでしょうが)や方法にふれることができたのは興味深かったです。 ここで思ったのは、学校教育は無駄じゃない、ということ(当然ですが)。中学生の頃、気候(というよりも天気)について理科で学んだ覚えがありますが、ほとんど覚えていません。覚えていれば、本書も若干ではあるでしょうが、理解しやすかったのかな、と思います。 学校で勉強している頃は、「こんなの勉強して何になる」と思う方も多いでしょうが(私もいくつかの分野についてはそうでした)、あれは全て、以後の勉強をする際の道具を獲得する過程だと思います。たとえば、私はなんであれ勉強は面白いと分かりましたし(もちろん自分自身が勉強する分野は限られますが)、今後何かを勉強しようというとき、学校で習ったことを身につけているかどうかは、作業の効率にも関わってきます。 たしかに、たとえば日常生活で微分積分をすることは私にはありません。それでも、今後何かのきっかけで数学面白い!となったときに、やはり初歩的な作業は身につけていた方が、その奥にある楽しさにもたどり着きやすいのではないか、と思います。 もう一つ例を挙げれば、百人一首も一時期覚えさせられましたが、一時に無理に詰め込んだものはさっぱり抜け落ちてしまっています。覚えていれば、高田崇史さんの『QED 百人一首の呪』ももっと楽しく読めたでしょう。 もちろん、これからもいくらでも勉強は続けられますし、それは喜ばしいことです。それでも、学校で習うことくらいは身につけておきたかった、といまさらながらに思います。覆水盆に返らず…。 …ずいぶん脱線してしまいましたが、ちょっと話を戻して…。 本書は、自然科学のデータに依拠する部分が大きいのですが、ピエール・アレクサンドルという研究者は、文書史料を中心に、中世の気候に関する研究を行っているようです。ただ、その研究書は入手するのが難しいようで(いくつかの大学図書館には入っているようですが)、今後読めるかどうか気になります。もっとも、アレクサンドル氏の論文は一本ですが入手してみたので、また機会があれば読んで、記事にも書きたいと思います。 なにはともあれ、数年ぶりに本書を通読できて良かったです。(2009/03/20読了)
2009.03.25
コメント(3)
-

森博嗣『四季 冬』
森博嗣『四季 冬 The Four Seasons Black Winter』~講談社ノベルス、2004年~(愛蔵版『四季』講談社、2004年) 『四季』シリーズ最終作です。 今回は、もはやなんともいえません。 いわゆるネタバレも含むので、文字色を反転させて、いくつか書いておきます。(ここから) おそらく、四季さんが犀川先生たちと接触していた時期よりも、ずっとずっと未来の話。四季さんは、きっと、「その方法」を成功させ、生きているのでしょう(と、私は読みました)。そして、いろんなことを回想します。 本書に登場するロボットは、一般名詞としてはウォーカロンと呼ばれています(彼女たちは、パティなど、固有名詞ももっています)。 ウォーカロンは、「女王」シリーズに登場するロボットの名前だったような…。ここで、「女王」シリーズともリンクするようですね。というんで、また機会があれば、「女王」シリーズも再読しようと思います。全く覚えていませんので、新鮮な気持ちで楽しめると思います。 S&Mシリーズ、Vシリーズと一気に(細かい設定にも気をつけながら)再読して、続けて『四季』シリーズも再読できたので、ずいぶん人間関係が把握できました。さらにいえば、Gシリーズ、Xシリーズも既に読んでいるので、こうした未来のシリーズへの伏線にも気付きながら…。 GシリーズやXシリーズの続編が出る頃にはこれらの内容も忘れてしまっているおそれがあるので、記事は多少詳しく、いわゆるネタバレになるのも割り切って書いてみました。(ここまで)(2009/03/20読了)
2009.03.24
コメント(1)
-

森博嗣『四季 秋』
森博嗣『四季 秋 The Four Seasons White Autumn』~講談社ノベルス、2004年~(愛蔵版『四季』講談社、2004年) 『四季』第3作です。今回は、内容紹介から感想から、すべて文字色反転させておきます。ネタバレ満載の記事になりますので、シリーズ未読の方はご注意ください。ーーー1998年~2001年(西之園萌絵、M1[23歳]~D1[25歳];犀川創平、36~38歳) 1998年。 儀同世津子のもとを、メール交換をしていた椙田泰男が訪れる。真賀田四季の情報を追っていた世津子に、椙田は、20年前に四季に会ったことを告げる。同時に椙田は、各務亜樹良を探していた。世津子が何か知っているならと、情報交換をもちかけたのである。 西之園萌絵にとっても、犀川創平にとっても、真賀田四季は忘れることのできない存在だった。 そして、2000年春。萌絵はN大学大学院の博士課程に進学し、国枝桃子は私立C大学の助教授となる。萌絵は、研究領域が近いことから、もっぱらC大学で国枝の補助をしつつ、週に1~2度N大学で研究する、という生活になっていった。 その頃、久々に萌絵のマンションで開かれたパーティーの中、犀川は、1994年の妃真加島事件の際に、四季が何かメッセージを残していたはずだと思い至る。やがて手掛かりをえた二人は、イタリアへ向かう。年はかわり、2001年になっていた。 モンドヴィの街では、犀川・萌絵の二人は、椙田泰男(保呂草潤平)・各務亜樹良の二人と出会う。4人は、四季が残したメッセージにたどり着く。ーーー 大きな流れはこんな感じです。今回は、『四季 夏』以上に、S&MシリーズとVシリーズのリンク、展開を楽しみながら読みました。椙田泰男さんは、Xシリーズでも登場しますね。なるほど、Xシリーズで椙田さんがやたら西之園さんを避けていたように思いますが、これで理由が分かりました。 なお、『捩れ屋敷の利鈍』は、国枝先生がC大学に移ってからこの事件(?)の前までの話ですので、2000年中に起こったものと思われます。 イタリアで、犀川先生が保呂草さんに会うのも、またなんともわくわくする展開でした。さすがにこの二人、劇的な再会とはならず、割と淡泊な会話ですね…。 犀川先生のお母様のもとに、西之園さんが挨拶に行くのもわくわくしました。読みながら緊張しました…(笑) 最後に、印象的な部分を引用しておきます。人間は、どうして泣くんだろう。どうして、どうして、どうして、それを言うのが人間?けれど、涙を見てくれる人がいる。疑問を受け止めてくれる人がいる。それだけで、充分ではないか。彼女は目を瞑って息を吸った。静かに。自分が泣くことを許すように、沢山のことを許さなくてはいけない、と彼女は思った。(196-197頁)(2009/03/20読了)
2009.03.23
コメント(0)
-

森博嗣『四季 夏』
森博嗣『四季 夏 The Four Seasons Red Summer』~講談社ノベルス、2003年~(愛蔵版『四季』講談社、2004年) 『四季』シリーズ第2作です。背表紙にも書いてあるのでここにも書いてしまいますが、『すべてがFになる』の背景が描かれています。 それでは、ごく簡単に内容紹介と感想を。ーーー真賀田四季、13歳(1978年)~14歳(1979年) 四季のために、妃真加島に研究所が作られ始めた。まだ論文は発表していないものの、彼女の才能は有名になっており、バックアップする人々も増えていた。 四季は、この頃、叔父の新藤清二に惹かれていく。彼と二人で遊園地に行った際、泥棒に首を絞められるという事件も起こってしまう。しかし彼女は、彼のことをかばう。 そして、四季はさらに新藤との接近を試み…、その事件は起こる。ーーー 今回も、ネタを割ってしまうメモをしていますので、感想は文字色を反転しておきます。(ここから) 今回も、感想というかメモですが…。 四季さんの世話役だった森川須磨さんが、アメリカで死亡します。このことに、四季さんが少なからず動揺するのが、なかなか印象的だと思います。 遊園地で四季さんの首を絞めるのは、保呂草さんですね。こんなところで、彼も四季さんと(しかもこんなかたちで)接触していたとは…。 遊園地の事件の現場には祖父江さんもいて、そして林さんも駆けつけるわけですが、四季さんが名前を問うのに、彼は答えます。「犀川といいます」と。『赤緑黒白』の記事でも、反転させた感想の部分に書きましたが、林さんというのは下の名前なのですね。そして…。 高校生の頃の喜多先生と犀川先生が一緒にいるときに、紅子さんに会うシーンもなかなかどきどきしました。なるほど、こんな感じでS&MシリーズとVシリーズを結ぶ事実が明かされていったのかと…。綿密な設定ですよね。 というんで、四季さんの事情も興味深いですが、二つのシリーズがリンクする過程を楽しく読みました。(ここまで)(2009/03/20読了)
2009.03.22
コメント(0)
-

森博嗣『四季 春』
森博嗣『四季 春 The Four Seasons Green Spring』~講談社ノベルス、2003年~(愛蔵版『四季』講談社、2004年) 真賀田四季が主人公の『四季』第1作です。一度目は単行本(愛蔵版)で通読していたのですが、例によってすっかり忘れていました。4年ぶりの再読です。 ごく簡単にはなりますが、内容紹介と感想を。ーーー 真賀田四季、5歳。 僕は、病院で彼女と知り合った。透明人間の僕は、誰にも見ることはできない。だから、いつも包帯で顔をぐるぐる巻きにしている。でも彼女は、そんな僕の素顔を見たいという…。 ある日、病院で殺人事件が発生した。僕も、いくぶん意識していた看護師が殺されたのだった。ところが彼女の死体が発見された部屋は、発見時には鍵がかけられていた。なぜ、部屋に鍵がかけられていたのか? 四季は5歳にして、既に多くの書物を読み、天才少女としての名声を高め始めていた。ーーー 以下、ネタを割ってしまうメモもしているので、感想は文字色を反転させておきます。シリーズ未読の方はご注意ください。(ここから) まず、「僕」のことなのですが…。これは、四季さんの多重人格の一部としての「僕」と、透明人間あるいは四季の実の兄の「僕」の二人がいるとは思うのですが、後者の方が分からなかったです。初読のときも分からなかったように思うのですが、今回も無理でした…。 ところで、病院の中庭のことは、覚えていました。ちょうど『四季』を愛蔵版で読んだのが、私自身入院中だったこともあるのか…。なぜか、覚えていました。 メモをいくつか。 まず、四季さんの世話人として活躍(やがて疲れていく)する方が、森川須磨さん。あの森川素直さんと関係があるのかどうか…。 メタナチュラル協会(『赤緑黒白』参照)の佐織さんと四季さんの出会いも描かれますし、各務亜樹良さんが四季さんのために動き始めることも分かります。 とまれ、ここではVシリーズとのリンクが示されています。(ここまで)(2009/03/20読了)(2009.03.24追記) フリーページの、『四季(愛蔵版)』から、この記事にリンクしています。 なので、『四季 春』の記事にのみ、以降の巻へのリンクをはっておきます。『四季 夏』『四季 秋』『四季 冬』
2009.03.21
コメント(0)
-

森博嗣『赤緑黒白』
森博嗣『赤緑黒白 Red Green Black and White』~講談社ノベルス、2002年~ Vシリーズ第10作、シリーズ最終作です。2009年の段階で、本書以降の作品刊行後に再読していることもあり、タイトルからなんとなく予想がつきましたが、予想は当たりました(再読とはいえ、本書の内容自体はすっかり忘れていましたが)。 なにはともあれ、内容紹介と感想を。ーーー瀬在丸紅子、29歳。 某年、森川素直が夏休み終わりに阿漕荘に引っ越してきてから、約半年後。 銃殺された第一の被害者は、全身を赤いスプレーで塗られていた。その体周辺のアスファルトも、赤くされていた。 被害者の名は、赤井。その恋人という田口美登里が、保呂草のもとに依頼に訪れる。赤井を殺したのは、ミステリ作家の帆山美澪に違いない、その証拠を挙げて欲しい、というのだった。帆山は、赤井が殺された現場のマンションに住んでいるが、事件当時のアリバイを主張し、また、赤井と彼女の接点も浮かんでこなかった。 保呂草が依頼を断ろうとしに田口のもとを訪れると、彼女自身が被害者となっていた。彼女は、その名にちなんでか、緑色に塗られていた…。 事件は繰り返される。瀬在丸紅子は、頭のいい犯人をいかに追い詰めるか、苦心することになる。ーーー 今回は、シリーズに関するネタバレになることもかなり書くので、感想は文字色を反転させておきます。一連のシリーズを未読の方はご注意下さい。ーーー(以下、文字色反転) まず、紅子さんの年齢について。『黒猫の三角』33頁では、「紅子は、今年の冬が来れば、ちょうど三十歳になる」とあります。なお、『黒猫の三角』事件は6月のことです。 さて、『恋恋蓮歩の演習』16頁には、「今回の事件は三月に起こった」とあります。「今回の事件」というのは、豪華客船からの人間消失事件のことでしょうし、「三月」も、『黒猫の三角』以前ではないはずです。そうすると、三月にはすでに紅子さんは三十歳になっていると思います。 また、『赤緑黒白』自体が、夏休み終わり(9月末?)から半年後ということで、つまり3月と思われます。そうすると、『黒猫の三角』の記述を信じるなら、紅子さんはもう30歳になっているはずですが、本書17頁では、彼女は「ぎりぎりまだ二十代」となっています。こちらが正しいなら、紅子さんは三月生まれということになるでしょう。 とまれ、『黒猫の三角』の記述から、私は紅子さんが12月生まれと想像していたので、『恋恋蓮歩の演習』の記事では、彼女の年齢を30歳と書いたのでした。 続いて、林さんについて。本書ではまだ彼の本名は明らかにはされませんが、ラストでは、もうぎりぎりまで答えが提示されていますね。彼が小鳥遊さんと香具山さんに預けた祝儀袋には、「○川林」と書かれています(○の部分は、二人には読めない漢字です)。さて、ここは、林というのは彼の姓ではなく名である、ということを示す伏線となっています。そしてこのことに気付けば、『黒猫の三角』114頁で紅子さんが言う、「ハヤシさんって、あのね、木を横に二つ並べて、ハヤシと読むのよ(……)あら……、だって、変わっているでしょう?」という言葉の意味も、またストレートに理解することができます。『黒猫の三角』の時点では、小鳥遊さんたちと同じく、このセリフを口にする紅子さんが変わり者だと思ってしまったわけですが…。 そして、本書で登場する少女。彼女の名前はまだ明らかにされませんが、ラストのあるセリフで、それは示唆されます。なんとなく謎解きにまつわるまどろっこしさ、すっきりしない感じは、後のXシリーズに通じていますね。 最後に、印象に残った部分も引用しておきます。結局文字色を反転させますので、感想のこの部分とまとめておきます。「普通じゃない。そう、誰だって、普通じゃないわ。普通っていうのは、つまり平均でしょう? 平均したものは、シーソーの中心に来る。だけど、そこには誰も乗っていない」(193頁)ーーー(反転ここまで) シリーズの伏線にも注意しながら、Vシリーズ全10作を再読しました。あらためて、伏線の妙にうならされます。ずいぶん早い段階で全体の構想があり、それから書いていらっしゃるのか…。まだ森さんのエッセイを十分に読んでいない(あるいはいくつか読んでいても忘れている)ので、そのあたりの事情も気にしながら、今後も森さんの作品を再読していこうと思います。(2009/03/14読了)
2009.03.17
コメント(0)
-

森博嗣『朽ちる散る落ちる』
森博嗣『朽ちる散る落ちる Rot off and Drop away』~講談社ノベルス、2002年~ Vシリーズ第9作です。今回は、第7作『六人の超音波科学者』と同じ舞台です。 それでは、内容紹介と感想を。ーーー瀬在丸紅子、29歳。 某年、『六人の超音波科学者』事件の一週間後。 保呂草潤平に、警察が土井超音波研究所の地下に入るという情報がもたらされる。同時に、そこに侵入して欲しい、という依頼も。 保呂草は、瀬在丸紅子、小鳥遊練無、香具山紫子とともに、超音波研究所へ向かう。祖父江七夏に煙たがられながらも侵入した奥には、内側から閉ざされたドアがあった。その部屋に入り、さらに地下に降りると、そこには一人の人間の遺体があった…。 研究所に向かう前、紅子は小田原博士からある研究者に会うよう指示される。その研究者は、一年数ヶ月前に外国で起こった、スペースシャトルの事件を教えてくれる。それは、シャトルで宇宙に行った4人の飛行士たちが、全員殺されていたという、奇妙な事件だった。 その事件と、研究室の遺体には関連があるのか。そして、練無の苦い過去との関連は…。ーーー スペースシャトルの事件と、なんともスケールの大きな事件も絡んできます。それにしても、ある短編が、シリーズ終盤のこの作品の伏線になっているとは…。あらためて、森さんの作品のすごさを感じました。 ちなみに、『今夜はパラシュート博物館へ』所収の「ぶるぶる人形にうってつけの夜」は、この事件よりも前のことのようです。たしかあれが夏でしたから、この事件は秋ということになるでしょうか? 事件自体はそろそろ謎解き重視というよりも、もっと壮大な雰囲気になってきていますが、本作でも、小鳥遊さんと香具山さんの二人の関係が良かったです。(2009/03/14読了)
2009.03.16
コメント(1)
-
筒井康隆『みだれ撃ち讀書ノート』
筒井康隆『みだれ撃ち讀書ノート』~集英社文庫、1982年~ 1976年から1979年に『奇想天外』に連載された分を中心とした、「讀書ノート」です。そのタイトルから、いろんな本を批判しているのかと先入観をもっていたのですが、むしろ幅広い分野の面白い(興味深い、重要な)本を紹介しています。「作家が書評する時」という章では、本書(当時の連載)が、「SF以外何も読まない」人が多い若い世代に対して、教育的効果を及ぼそうという意図ももっていることが語られます。分かりやすかったのは、筒井さんご自身はドタバタを多く書いておられますが、それ以外にも、いわゆる固い純文学や専門書なども大量に読んでいるのだぞ、という意味もあるというところ。なにはともあれ、、その読書量と作品を見る眼に憧れます。先に、むしろ面白い本を紹介していると書きましたが、同時に、その本について的外れな批評をしている人物のことはやっつけているようなところもあります。 本書で興味深かったのは、南米の作家を多く取り上げていることです。以前読んだ『着想の技術』の中で、塙さんという編集者が、筒井さんに南米系の作家を紹介された、というエピソードがありました。「知の産業―ある編集者」というそのエッセイは、読んだときに涙がとまらなかったほどで、とても印象に残っていたので、それで本書を読んだときに注意しながら読めたのだと思います。 筒井さんの作品を読み始めた頃の記事には何度か書いていますが、私はSFというジャンルは読まず嫌いでした。が、本書を読んでいると、SFというジャンルの可能性の大きさや、その知的・実験的性格に気付かされました。SFについては、宇宙で異星人同士が戦争をする、みたいな狭いイメージを持っていたのが読まず嫌いの原因ですが、たとえば時間に関する問題、筒井さんが強調しておられる虚構性の在り方など、勉強になる部分がとても多いジャンルですね。 というんで、SF関連で興味をもったのは、次のような作品です。 まず、徹底的に時間について考察されたという広瀬正さんの著作。『タイムマシンの作り方』を紹介している回は、広瀬さんの執筆活動の時期区分とそれぞれの意義を紹介し、また広瀬さんご本人の紹介もしていて、そのラストでは涙ぐみました。 同じく時間の問題に関連して、A・カルペンティエール『時との戦い』。 本書の中で3度紹介されている、かんべむさしさんの作品も読んでみたくなりました。 …それにしても、こうやって本を読めば読むほど(そして、本書の性格にもよるのでしょうが)、自分の勉強不足を思い知らされます。小説の分野にしても、西洋史の分野にしても…。 でも、悲観はしません。これからもっともっと勉強できる余地があり、勉強の楽しさを味わえるわけですから。 謙虚な気持ちになれる読書体験でした。(2009/03/12読了)
2009.03.13
コメント(1)
-

森博嗣『捩れ屋敷の利鈍』
森博嗣『捩れ屋敷の利鈍 The Riddle in Torsional Nest』~講談社ノベルス、2002年~ Vシリーズ第8作です。S&Mシリーズ番外編ともいえますね。本書は、講談社ノベルス20周年企画ということで、密室本のかたちで発売されました(本の中身全体が袋綴じ)。 内容紹介の方はともかく、感想の方は全体を文字色反転にしておきます(シリーズ未読の方はご注意ください)。ーーー1999年以降(?)(西之園萌絵、大学院生/国枝桃子、私立大学助教授) 保呂草潤平は、秋野秀和と名乗り、熊野御堂家の屋敷を訪れた。そこには、N大学大学院生の西之園萌絵と、その先生の国枝桃子も客として招かれていた。 屋敷の当主、譲は、彼らをメビウスの輪の形をした建物、捩れ屋敷に案内する。内部は36の部屋に分かれ、それぞれが少しずつ捻れることで、メビウスの輪の形状をしたその建物は、特殊な鍵のシステムもあり、一方に一部屋ずつしか進むことができない。その中の一つに、秘宝、エンジェル・マヌーヴァが飾られていた。しかし、それは柱に鎖で取り付けられており、鎖自体も芸術的価値が高いことから、取り出すことはまず不可能だと保呂草は言う。 翌朝、事件が発覚する。屋敷の執事が、譲が見あたらないということで、西之園たちと捻れ屋敷を見に行くと、屋敷は外側から鍵がかけられ、そして内部では、密室状態の中、遺体が横たわっていた。そして、完全な密室状態の小屋の中でも、譲が絞殺されているのが見つかる。 西之園萌絵は、指導教官の犀川創平に連絡を取りつつ、密室の謎に挑む。ーーー(以下の感想、文字色反転) 保呂草さんが名乗る名前は、『黒猫の三角』のあの人の名前ですね。 今回、紅子さんが「あの方」の○○にあたるということを知っている状態でS&Mシリーズから再読をしているわけですが(どの作品でその事実を知ったかも確認する意味で再読を進めていますが、本作以降のようですね)、その知識があると、うまい伏線だなぁと思うところがしばしばです(特に携帯電話)。本作のラストの方で、保呂草さんが、紅子さんから、西之園さんに決して関わらないように釘を刺されたことは、GシリーズかXシリーズあたりの伏線にもなっているかも知れません。 本作自体で楽しい(嬉しい)のは、国枝先生がしっかり登場していることです。この事件の少し前に、私立大学の助教授になったということなので、このこともGシリーズかXシリーズで確認できるかと思います。そしてそうすれば、この事件の年代も特定できそうです(ネット上で、その作業をされているページがあるのも承知していますが、できるかぎり自分で整理してみたいので、 2009.03.09現在では事件年代を特定していません)。 事件自体の謎の方は、んー、なんとも。捩れ屋敷の方は、仕組みがよく理解できないままでした…。(反転ここまで)(2009/03/08読了)
2009.03.12
コメント(0)
-

森博嗣『六人の超音波科学者』
森博嗣『六人の超音波科学者 Six Supersonic Scientists』~講談社ノベルス、2001年~ Vシリーズ第7作です。今回はある事実にふれますので、未読の方はご注意ください。 それでは、内容紹介と感想を。ーーー瀬在丸紅子、30歳(?) 瀬在丸紅子と小鳥遊練無は、土井博士が設立した研究室のパーティに招かれた。保呂草潤平と香具山紫子は二人を研究室まで送るが、車のエンジンがかからなくなり、二人も研究室に入ることになる。 仮面をし、車いすに乗った土井博士を含め、研究室には六人の研究者がいるという。ファラディ博士が顔を見せなかったものの、パーティはつつがなく進んだ。土井博士がある発表をするということで、テレビ局の人間も二名招かれていたが、保呂草と紫子は彼らの手伝いをすることになる。 一方、祖父江七夏は、橋を爆破するという予告電話を受け、警官たちとともに現場を訪れていた。そこは、土井博士の研究室へ向かう道にある橋。七夏が研究室側の岸に渡ったとき、予告通り橋が破壊された。七夏はやむなく、研究室へ向かう。 彼女が研究室に着いてしばらくした頃、事件が発覚する。パーティに現れなかったファラディ博士が、絞殺されているようなのだった。七夏を先頭に、紅子たちは事件の調査に乗り出す。その中で、紅子たち自身も何者かに襲われ、さらには首を切断された遺体も発見される。ーーー ちょっと文字色を反転しておきます。 紅子さんが研究室に呼ばれたのは、「桜鳴六角邸」の元所有者だった小田原博士(『黒猫の三角』参照)の紹介で、小鳥遊さんが招かれたのは纐纈氏の関係(「気さくなお人形、19歳」『地球儀のスライス』)です。こんなところで作品がリンクしているとは…。 ところで、本作はプロローグが楽しかったです。『魔剣天翔』を読んで以来、小鳥遊さんと紫子さんの二人の関係がとても素敵に見えてきました(会話が楽しいのも含めて)。そして、紫子さんがこのグループをつなげる役割を果たしている、といったことを保呂草さんが指摘していますが、頷きながら読みました。 それでは、興味深かった言葉を引用しておきます(文字色反転)。「そう、目先の整合性のために、将来の矛盾を見過ごす。人が犯すミスの多くは、それと同じメカニズムです」(275頁)(2009/03/07読了)
2009.03.11
コメント(0)
-

森博嗣『恋恋蓮歩の演習』
森博嗣『恋恋蓮歩の演習 A Sea of Deceits』~講談社ノベルス、2001年~ Vシリーズ第6作です。今回の舞台は、海上、豪華客船。人間失踪と絵画盗難が今回の事件です。それでは、簡単に内容紹介と感想を。ーーー瀬在丸紅子30歳 某年、3月。 豪華客船ヒミコが、愛知県に到着する。そこに保呂草潤平と香具山紫子は乗船、さらには瀬在丸紅子と小鳥遊練無も無理矢理乗り込むことになる。ところが、出港してしばらくして、銃声のような音が響く。さらに、人間が落ちたらしいという目撃情報も多数あった。香具山紫子も、そのように証言する一人となる。 同じ船には、フランスの富豪ボナパルトと、関根朔太の幻の自画像をもっているという鈴鹿幸郎、明寛の親子も乗っていた。鈴鹿側がボナパルトに自画像を見せるという契約になっていたようだが、しかし、その自画像もトランクから消えてしまっていた。事件が起こったのは、船のSブロック内。カウンターを通らずにそこに行くことは不可能だが、不審人物は目撃されていなかった…。 * 事件より、数ヶ月前。 保呂草は、各務亜樹良の依頼で、鈴鹿家を探る。香具山紫子は、アルバイトとして、その手伝いをしていた。鈴鹿がヒミコに乗るという情報を得て、彼らも船に乗ることになる。 同じ頃、大学院生の大笛梨枝は、カルチャースクールで出会った羽村怜人に恋をしていた。たまたまその頃、彼女は瀬在丸紅子と知り合いになる。そして大笛もまた、羽村とともにヒミコで旅行に向かった。ーーー この作品あたりから、なんとも感想が書きにくくなりますね…。 いくつものアクション・シーン(?)を経たラストが素敵でした。 一箇所、興味深かった部分があるので、引用しておきます(文字色反転)。 場所など、どこであっても同じこと。私たちの周囲には、そもそも逃げ場など存在しない環境ばかりだ。デスクから離れることはできない。窓から飛び出すことはできない。夜はベッドから逃げられない。友人たちを裏切ることはできない。 むしろ、そういった逃げ場のない設定こそが、人間に「安心」という幻想を見せる条件でさえあるのだ。(12頁)(2009/03/07読了)
2009.03.10
コメント(0)
-

ミシェル・パストゥロー『黒―ある色の歴史―』(英訳版)
Michel Pastoureau (Translated from the French by Jody Gladding), Black. The History of a Color(Michel Pastoureau, Noir, histoire d'une couleur, Seuil, 2008)~Princeton University Press, 2008~ 『青の歴史』(邦訳の記事はこちら)に続く、ミシェル・パストゥロー氏による色の歴史第2作(の英訳)を通読しました。購入から3ヶ月かかりました。が、今回はノートをとりながら読んだので、ノートという成果を残せて良かったです。それから、『青の歴史』が邦訳されているので、本書もきっと邦訳されると期待しているのですが、その前に通読できたのも良かったです。 さて、ここではまず構成を紹介して、次に黒の(象徴の)歴史についてレジュメ風に通史的に整理し、最後に興味深かった点についてつらつらと書いていきたいと思います。 というんで、本書の構成は以下のとおりです(拙訳。章と節の番号は本書にはありませんが、便宜的に付しました)。ーーー序論―色彩の歴史のために―第1章 はじめに黒があった―原初から紀元千年― 第1節 闇の神話 第2節 闇から色へ 第3節 パレット[色彩群]から語彙へ 第4節 死とその色 第5節 黒い鳥 第6節 黒、白、赤第2章 悪魔のパレット[色彩群]の中に―10世紀から13世紀― 第1節 悪魔とその図像 第2節 悪魔とその色 第3節 不安を煽る動物誌 第4節 闇を晴らす 第5節 修道士たちの論争―白対黒 第6節 新しい色の秩序―紋章 第7節 黒の騎士とは誰だったか第3章 お気に入りの色―14世紀から16世紀― 第1節 肌の色 第2節 暗い肌のキリスト教化 第3節 染物師とイエス 第4節 黒く染める 第5節 色の道徳的規範 第6節 君主の贅沢 第7節 希望の灰色第4章 白黒世界の誕生―16世紀から18世紀― 第1節 インクと紙 第2節 白黒の中の色 第3節 線影と斜め格子模様 第4節 色彩戦争 第5節 プロテスタントの衣服規範 第6節 きわめて暗い時代 第7節 悪魔の再来 第8節 新しい考察、新しい分類 第9節 新しい色の秩序第5章 黒という全ての色―18世紀から21世紀― 第1節 色の大勝利 第2節 啓蒙の時代 第3節 メランコリーの詩 第4節 石炭と工場の時代 第5節 図像に関して 第6節 現代的な色 第7節 危険な色か(*第5章の英語タイトルはAll the Colors of Blackですが、良い訳ができませんでした)ーーー(1)黒の象徴史概観(本書の内容をごく簡単に、レジュメ風に整理しています)○原初:黒=はじめの色(創世記、ギリシャ神話…) ∴黒=母胎としてのイメージ←→黒=恐怖というイメージ○ラテン語:明るい黒(肯定的)と暗い黒(否定的)の対立が重要 →黒=否定的イメージとは限らない○初期中世…3つの基本色:白、赤、黒 ・人名でも、この3色が使われる割合高い ・個人の識別:司祭(白)、戦士(赤)、職人(黒) ・黒…良い黒と悪い黒の共存↓○紀元千年以降 ・黒=否定的イメージ→悪魔の色;悪魔と関連する動物たちの色(熊、猫、カラス、フクロウなど…) ・光=闇(黒)を晴らす ・色=光という観念→黒は色彩の秩序から除外される ・修道士の論争:クリュニー修道士(黒)とシトー会修道士(白)の対立 ・紋章の誕生 →白、赤、黒の3基本色に、青、緑、黄(、紫)が加わる ・黒の騎士=自らの素性を隠して行動…黒は否定的というより、匿名性を示す↓○14世紀~16世紀 ・黒=お気に入りの、贅沢な色に(王侯君主たちのあいだで。特に15世紀、フィリップ善良公) ・黒い肌…伝統的に否定的なイメージ →14世紀~肯定的側面も付与 例)シェバの女王、聖モーリス ・技術的にきれいな黒が作れるように←道徳的理由からの社会的要求が先行 ・奢侈禁止法(人々が各々の身分にあった服を身につけるように;派手な色を禁止) →黒の大流行へ↓○16世紀~18世紀 ・活版印刷の誕生→カラフルな手写本から白黒の本へ=人々の感性の歴史にとって重要な展開 →図像も色なし木版画などへ ・プロテスタントによる色彩破壊chromoclasm→カトリックの教会などを非難 =鮮やかな色へのを非難 ・17世紀=「黒の時代」…"ヨーロッパの人々が最も悲惨だった時代"(p. 134) →黒があふれる:衣服、家屋(室内)、魔女・悪魔など…○ニュートンのスペクトルの重要性="色についての知識と色の使用の歴史における転換点"(p. 152) ・従来の色彩の秩序:白、黄、赤、緑、青、黒(例:緑は黄と青の中間ではない!) ・17世紀~科学的実験の進展→ニュートン(1642-1727)登場 ・新しい色の秩序:紫、藍、青、緑、黄、橙、赤 ※緑は青と黄色の中間 ※白と黒が色の秩序の中にない! ↓○18世紀~19世紀 ・啓蒙の時代=色のオアシス(二つの白黒の時代の中間) →青、白、灰色、黄色、緑の流行・使用の拡大 ・18世紀~黒=男性服の主要色に ・19世紀後半~いたるところに黒が浸透:多くの職業の制服○20世紀 ・黒の復権、白黒世界の再来:写真=活版印刷に次ぐ第二の白黒世界 ・映画も白黒 ・ファッション界でも黒の復権○21世紀 ・黒の危険な意味薄れる(過去には、黒猫などに関する迷信や諺) ・肯定的な意味も薄れる(黒が権威となるのは柔道の黒帯などくらい) →中立的な色になるのか?(2)興味深かった点 まず、序論。ここでは、色の歴史の方法上の問題点などが示されます。というんで、内容は『青の歴史』序論や、『ヨーロッパ中世象徴史』所収の「中世の色彩を見る―色彩の歴史は可能か?―」と重複しています。 ここで面白かったのは、色の歴史シリーズを続けてもあまり意味がないのではないか、とパストゥロー氏自身が書いておられることです。出版社の要請にもよるようですが、結局はある一つの色だけを独立して論じることに意味はなく、その他の色と比較史ながら見る必要がある、というのが氏のスタンスです。なので、シリーズを続けても、結局は同じようなことになってしまうのでは、というのですね。実際本書にも、『青の歴史』と重複した部分が多々あります。 第1章では、第5節のカラスについて論じた部分ももちろんですが、語彙の問題が面白かったです。 上のレジュメにも書きましたが、古代・初期中世では黒や白について、その色自体よりもその明るさや暗さの方に重点が置かれました。古ドイツ語では、暗い黒はswarz、明るい黒はblachで、現在のドイツ語schwarzは前者起源ということになります。一方、古英語では暗い黒はswalt、明るい黒はblaekで、今日の英語blackは後者起源です。ちなみに、古英語で光沢のない白はwite(→今日のwhite)、光沢ある白はblankで、こちらはフランス語のblancにつながりますね。なるほどなぁと思いながら読みました。 カラスについても書いておけば、北欧神話、ゲルマンの神話では、カラスは神聖な性格を持っていました(神聖、好戦的、全知の象徴)。ところがキリスト教により、カラスは否定的な性格を与えられます。 第2章では、最近動物の歴史に関心を寄せているので(勉強は進めていませんが)、第3節を興味深く読みました。ここでは、カラス、熊、猫、猪について1段落ずつ解説した後、悪魔的なイメージをもつ動物の図像表現についてもふれられています(註1)。 第3章では、第1節と第2節の、肌の色について論じた部分が面白かったです。第1節で、盛期中世で黒い肌が否定的なイメージをもったことを示した後、第2節では、13-14世紀から、それに肯定的なイメージが与えられることを論じます。具体的な例として、シェバの女王、プレスター・ジョン(註2)、東方の三賢人(内一人のバルタザルが、14世紀から黒い肌で描かれるようになるとか。註3)、聖モーリスについて、紹介されます。 第4章は、印刷術が白黒世界を生み、それが新しい人々の新しい感性につながっていく、という指摘が興味深いです。逆の方向ですが、第5章の白黒写真からカラー写真への移行についても同じことが言えると思うのですが、たとえばずっと図像や映像を白黒で見ていたのに、それらがカラーになったときは、かなり新鮮な体験だったと思うのです。 第5章では、内容に直接関係のないネタですが、ファッションについて論じている部分で、ミシェル・パストゥロー氏自身もファッション・ショーの審査員としてよく招かれている、と書かれていたのが面白かったです。氏は、紋章学や動植物、色彩に関する中世史家としてはもちろんですが、一般に色彩の分野でもかなりの有名人なのでしょうね(実際、『色をめぐる対話』や『ヨーロッパの色彩』といった、一般向けの色彩に関する本も刊行されています)。 そしてこの英訳版は、図版が全てカラー(黒が、テーマなので、それこそ白黒写真もありますが…)で、きれいな装丁の本です(フランス語の原著は未見なので分かりません…)。それだけでも価値があるといえます。 というんで、良い読書体験でした。註1) 『色彩・図像・象徴―歴史人類学研究』所収「キリストの動物誌・悪魔の動物誌」参照。註2) プレスター・ジョンについては、池上俊一『狼男伝説』の記事で、多少詳しく紹介しています。註3) 東方三博士については、アゴスティーノ・パラヴィチーニ・バッリアーニ「人生の諸時期」の記事でふれています。(2009/03/07読了)
2009.03.09
コメント(0)
-

関哲行『旅する人びと(ヨーロッパの中世4)』
関哲行『旅する人びと(ヨーロッパの中世4)』~岩波書店、2009年~ 岩波書店から刊行されているシリーズ「ヨーロッパの中世」の第4巻(第4回配本)です。 関先生はスペイン史のご専門ということです。実は、先生の著作を読むのは今回が初めてなのですが、本書は具体的で興味深い事例を豊富に紹介していて、とても面白く読むことができました。 本書の構成は以下の通りです。ーーー序章 「他所」への憧憬 1 移動起点としての都市ないし都市ネットワーク 2 聖書的言説(コスモロジー)第一章 移動の動機と条件 1 移動はどのように行われたか 2 ガイドブックと通訳、旅の装い 3 宿泊施設と宿泊・食事サービス 4 旅の危険と旅行者の法的保護 5 貨幣・度量衡制度と両替、為替手形第二章 祈りと贖罪の旅 1 武装巡礼としての十字軍 2 カトリックの聖地巡礼 3 聖地と聖遺物 4 ユダヤ人の聖地巡礼第三章 移動と労働 1 同職ギルドと遍歴職人 2 商人と定期市 3 商人居留地と自治権 4 遍歴する兵士と牧羊業者 5 移動する海民と農民第四章 学びと説教(伝道)の旅 1 「十二世紀ルネサンス」 2 「知」を求めて移動する学生と教師 3 「神の言葉」を伝える遍歴の聖職者たち 4 巡回する異端審問官と異端者第五章 外交交渉と儀礼の旅 1 移動する宮廷 2 イスラームとの外交交渉 3 モンゴルとの外交交渉 4 ビザンツとの外交交渉第六章 女性とマイノリティー 1 移動する女性たち 2 流浪する貧民 3 追放されるユダヤ人とジプシー(ロマ) 4 奴隷と兄弟団結論 超克される異界 1 中世的移動の特質 2 中世的移動とアメリカ「発見」 3 中世的移動とコンキスタドール 4 異界の消滅 5 病原菌と動植物の移動索引参考文献ーーー 興味深かった点を中心に、書いていきたいと思います。 まず序章では、中世を三段階に分けて、それぞれの段階の旅(移動)の性格を概観します。レジュメ風にまとめると、次のようになります。 初期中世=「半遊牧民社会」(中世スペイン史家コルターサルによる定義)…ゲルマン人、ノルマン人などの移動 盛期中世(11-13世紀)…農業の発展、人口増加→都市の叢生、ネットワーク→十字軍、サンティアゴ巡礼 中世末期(14-15世紀)…移動の質の変化(余暇、観光などのウェイトが増す);「周縁民」を含む多様な社会的身分の人々も移動 こうして、全体を簡単に概観した後、本論に入っていくのですが、まず第一章でぐっと興味をひきつけられます。上に挙げた構成の標題を見ても分かりますが、ガイドブックの話や宿泊施設の様子など、楽しく読みました。 ほかに興味深かったのは、第1節でいろんな移動の仕方が紹介される部分です。中でも川を渡る話が面白かったです。常設の橋が架けられた河川は少なかったため、旅行者は浅瀬を渡るか渡し船を利用しなくてはなりませんでした。ところが渡し守さん、長雨で増水しているときには割増賃金を要求したり、ひどい事例ではわざと船をひっくり返して旅行者を溺れさせ、持ち物を奪うこともあったとか。 また第5節では、たとえば地域によって度量衡が異なることを利用して、各地で不正が行われていたことなどが紹介されます。 第二章は、中世の中で主な旅(移動)の要因であった十字軍と巡礼について論じます。特に、サンティアゴ巡礼について興味深く読みました。 一つは、サンティアゴへの巡礼路が、「医療空間」としての機能を持っていたこと(71-72頁)。巡礼路にある教会や修道院、施療院が心身を病んだ巡礼者に無償の医療行為を提供していたそうです。また、巡礼路には多くの薬草が自生していたことから、これらを利用した治療も行われたとか。 もう一つ特に興味深かった点を挙げるなら、それは聖地サンティアゴ・デ・コンポステラの性格です。古代からのサンティアゴの歴史的変遷(巨石文化、ローマ時代の神殿、異端者の墓、そして聖ヤコブの墓)を見た上で、著者はここにある「捏造された聖地」「捏造された聖遺物」としての性格を指摘します。しかし、そのように異教や異端の聖地と連続する場だからこそ、民衆信仰と強いつながりも持っていて、そのため多くの民衆を惹きつけることになった、というのですね。 以上、第一章で旅の全体的な条件を、第二章で主な旅の在り方を見た上で、第三章以下は各々の社会的身分の人々が、どのように、どのような動機から移動(旅)したのかを見ていきます。私自身は中世説教の勉強してきたこともあり、第四章を特に興味深く読みました。 そして、終章。大航海時代といえば、新しい時代の幕開け、というイメージが強いですが、しかし本書では、中世からの移動の在り方がその下地になっているということで、中世との連続性が強調されています。たとえば、コロンブスが「インド」(アメリカ)に行ったのは、終末論的な思想が背景にあったといいます。世界の終末は近い、その後到来する神の王国の実現のためには、全世界に神の言葉を宣べ伝えなければ…。というんで、「アメリカ『発見』も、…宗教的文脈の中に位置づけられる」(279頁)というのですね。 第5節の病原菌と動植物に移動についても(さらっと流されていますが)、興味深く読みました。ミシェル・パストゥロー氏が精力的に進めておられる動植物の象徴史の観点から見ても、「新世界」との接触は興味深い調査対象となりそうです。 このように、本書は旅(移動)という観点から中世世界を描き出しています。普段はなかなかこのようなかたちの通史を読むこともないので、新鮮で、また興味深く読みました。 上でも少しふれましたが、たとえば第五章3節「モンゴルとの対外交渉」では、ギョーム・ド・ルブルク、モンテコルヴィーノ(この二人は高校世界史でも登場しますね)、セビーリャ出身のパスクアールの三人によるモンゴルへの旅を、それぞれについて詳しく書いています。このように、節ごとに事例を多く紹介しているので、本書の論はとても具体的で、分かりやすいです。 いろんな職業や境遇の人々についても目が配られているのも嬉しいです。基本的には旅(移動)の観点からになりますが、いろんな人々の具体的な状況が浮かんできます。 というんで、良い読書体験でした。 次回、第5回配本は、小澤実/薩摩秀登/林邦夫『辺境のダイナミズム(ヨーロッパの中世3)』。3月下旬刊行予定のようです。(2009/03/06読了)
2009.03.08
コメント(0)
-
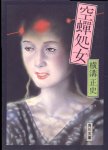
横溝正史『空蝉処女』
横溝正史『空蝉処女』~角川文庫、1983年~ 横溝さんの短編集です。解説の中島河太郎さんの言葉によれば、角川文庫(旧版)の横溝作品シリーズの最終刊ということになります。戦前の作品から戦後の作品まで、それまでの角川文庫未収録作品9編が収録されています。 それでは、内容紹介と感想を。ーーー「空蝉処女(うつせみおとめ)」疎開先で、私は不思議な令嬢に出会う。月夜に散歩に出た私は、不思議な歌声を聞いた。それは、まるで夢うつつの中で歩いているような女性が歌っているのだった。彼女は、珠生という名前らしいが、戦争中に何らかの体験で記憶を失っており、名字も分からないという。彼女が身を寄せる家に若者が帰ってきて、若者は彼女に惹かれ始めるが、しかし一つ問題があった。未婚のように見える彼女であるが、しかし子供を持っていたような素振りも見せるのだった…。「玩具店の殺人」戦前に工房で働いていた仲間たちで戦後作ったおもちゃ屋は、それなりに繁盛していた。ところが、そろばん担当ということで、仲間たちから疎まれていた人物が加わることになり、さらに事件が起こる。ある朝、おもちゃ屋で、女性が死亡していた。しかも、その片目はくりぬかれていた…。「菊花大会事件」新聞記者の宇津木俊助は、自動車事故の現場に遭遇する。死者の服のポケットからは、暗号らしきものが書かれた菊花大会のチケットが出てきた。後日、俊助は、菊花大会で、同じくメモを見比べながら菊の花を見ている女性を発見する。「三行広告事件」住宅を求める三行広告を出した後、同じ人物がその住宅を貸し出す三行広告を出す。しかも同じ事例が繰り返されている…。このことに興味をもつ由利先生と三津木俊助だが、その日彼らを訪れた依頼人が、彼らの前で死亡した。三行広告と男の死に関連があるらしい。由利先生たちは事件に挑む。「頸飾り綺譚」事業のため、妻の首飾りを質に入れてしまった山名耕作。しばらくの間妻を欺くべく、偽の首飾りを作ったが、それが彼を苦しめることになる…。「劉夫人の腕輪」神戸の中国人友達とともに、私は劉夫人を交えた食事に参加する。私は、彼女の腕輪がやけに気になっていたのだが、意外な事実が判明する。「路傍の人」どことはなしに散歩をするのを日課にしていた私。ところが、どこに行っても同じ男に出会うようになる。「路傍の人」と心の中で呼ぶその男と、ある機会に意気投合する。すると男は、直感的な推理力で、いくつかの事件を事前に察知する。「帰れるお類」とっても人の好い山野三五郎についての、涙なしには聞けないような素敵な逸話。「いたずらな恋」私の友人で、ハンサムな磯部富郎が巻き込まれた不思議なエピソード。ーーー 枕元の友にして、前半は一日一編ずつというスローペースで読んだこともあり、その後感想を書くまでに時間が空いてしまったこともあり、後半は特にさらっとした紹介になりましたが、いずれも短い話なので、一気に読めると思います。「菊花大会事件」「三行広告事件」は、つかみは面白いのですが、なんとも唐突な感じがありました。ですが、時局を思わせる作品です。「帰れるお類」「いたずらな恋」は、ユーモア色もある作品。同時に、どちらもちょっと胸がちくりとするような感じもあります。 表題作は、岡山県吉備郡に疎開していた「私」が主人公ということで、横溝さんご自身を連想せずにいられません。現在、倉敷市真備町となっていますが、ここに横溝さんの疎開宅があります(小規模ながら、横溝正史博物館も興味深いです)。以前、疎開宅や博物館に行き、周辺の横溝さんゆかりの地をまわったことがありますが(記事はこちら)、そのときに本作の舞台になっている大池にも行っています。というんで、本作は場所を思い浮かべながら興味深く読みました。 本書のなかで一番面白く読んだのは「路傍の人」です。タイトルからも、面白いのが間違いないと思えてきますが、内容も素敵でした。*表紙画像は、横溝正史エンサイクロペディアさまからいただきました。(2009/03/01読了)
2009.03.05
コメント(2)
-
「2009年2月の読書記録・小説部門」
今回は、2009年2月に記事を書いた本のリストです。番号は、今年記事をアップした順番で、印象に残った本には☆マークをつけています。15.横溝正史『死仮面』(春陽文庫版) ☆16.鷺沢萠『ありがとう。』17.高田崇史『カンナ 天草の神兵』18.佐藤友哉『青酸クリームソーダ <鏡家サーガ>入門編』19.森博嗣『黒猫の三角』20.横溝正史『びっくり箱殺人事件』 ☆21.竹内海南江『お姫さまと山男 旅する私のおかしな恋愛』22.森博嗣『人形式モナリザ』23.森博嗣『月は幽咽のデバイス』24.横溝正史『殺人暦』25.筒井康隆『小説のゆくえ』27.森博嗣『夢・出逢い・魔性』28.森博嗣『魔剣天翔』 ☆29.森博嗣『今夜はパラシュート博物館へ』~総評~ 2月は14冊の小説・エッセイの感想を書きました。 横溝さんの『死仮面』は間違いなく☆です。春陽文庫版は、長らく幻とされていた原稿を加えた完全版で、なかなか手に入らないこともあり、見つけたときの喜びもとても大きかったですし。内容も充実しています。 同じく横溝さんの『びっくり箱殺人事件』は、この2ヶ月本を読んできて一番笑えた作品のように思います。私が今まで読んできたユーモアミステリの中でも、トップクラスの面白さです。 森さんの『魔剣天翔』は、事件自体は地味な感じですが、最終章の1シーンと、エピローグの1シーンの感動から☆をつけました。エピローグの、二人の後ろ姿がとても印象的です。
2009.03.01
コメント(2)
全18件 (18件中 1-18件目)
1










