2009年02月の記事
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-
J=L・フランドラン『農民の愛と性―新しい愛の歴史学―』
J=L・フランドラン(蔵持不三也/野池恵子訳)『農民の愛と性―新しい愛の歴史学―』(Jean-Louis Flandrin, Les amours paysannes (XVIe-XIXe siecle), Editions Gallimard, 1975)~白水社、1989年~ 前回、西洋史関連の文献で『世界で一番美しい愛の歴史』を紹介しましたが、これを機に、買ったもののしばらく読んでなかった本書を通読してみました。 フランドランは、近世・近代史が専門なので、私が専門に勉強している時代とはずれるのですが、性と愛の歴史の大家ですね。性の歴史の後は、食の歴史に関心を移し(これらはまた、人間の欲望の歴史ともいえます)、その成果の一つは、次の邦訳書があるので、日本語でも読むことができます。フランドラン/モンタナーリ編『食の歴史』(藤原書店、全3巻) さて、本書の構成は以下のとおりです。ーーー序章 新しい愛の歴史学に向けて第一章 ゲームの掟 I 教会法の制約 II 父親の権威 III 家庭の事情第二章 愛と結婚 I 愛は存在したか II 貧しき人々の愛 III 配偶者の選択第三章 欲望と暴力 I 愛の手ほどき II 男女交際 III 悲劇的な愛終章 変遷原注訳者あとがきーーー 本書は、16世紀から18世紀という時代を中心に、農民たちの愛と性の在り方を、史料に豊富に語らせながら描いています。 おおざっぱにいって、第一章は結婚、第二章は愛、第三章は性を扱っていますが、これら3つは、前出『世界で一番美しい愛の歴史』の中でも、愛の歴史を論じる上で重要な領域と指摘されています。 内容とは関係ありませんが、構成が、序章と終章を除けば3章からなり、それぞれの章が3節からなっているというのも、すっきりとした形で良いですね。 さて、本書を寝る前の枕元の友としていたわけですが、なにぶん私は近世史・近代史に明るくなく、整理もしていないので、十分に理解できたとはいえません。そこでここでは、その全体の印象について簡単に書いておくことにします。 まず、序章で本書の方法論が示されます。特に、史料の扱い方について、です。 文学作品は有用ですが得られるのはイメージであり、より具体的な情報は統計的なデータや、裁判記録から得られます。ところがこれらもエリートの記録であって、農民たちの生の声は聞こえにくい。そこで、フランドランが注目するのが、諺や歌謡です。本書は、これらの史料をふんだんに引用しながら、農民たちの愛や性の実体を描こうとする試みです。 第一章で興味深かった点をいくつか挙げておきます。・本書ではしばしば、レチフ・ド・ラ・ブルトンヌという人物による『父の生涯』という作品が引用されていますが、その作品の中で、主人公エドモン・レチフは、自分の意中の人がいたにも関わらず、父の意思に従っているシーンがあります。一章II節の標題にもなっていますが、当時の父親の権威の強さがうかがえます。・長男は家庭の中でいろいろな特権をもっていた(料理の中でも美味しいところを食べることができたり)のですが、同時に、たっぷりの婚資(女性が嫁に行くときに持参するお金)をもたらす女性と結婚するよう強制されていたとか。先にひいたエドモンの例もそうなのですが、本人が愛する女性が貧しかったら、親に反対されてしまうのです。 第二章で興味深かった点もいくつか挙げておきます。・第一章とは反対に、「子供たちを彼らが愛することのできない相手と結婚させたり、彼らの意思に反して宗門に入れたりする父親は、この掟に著しく背いていることになる」という史料の存在が指摘されます(有名なルイ13世の宰相を務めたリシュリューの言葉)。同じく、相手に愛情を抱くことができなければ、婚約が解消される、という事例も示されます。・農民たちのあいだで愛情がいかに捉えられたかを示す史料として、諺や歌謡が多く例示されています。ここは読み物としても楽しいです。・また、第一章でも指摘されていたかと思いますが、結婚する条件として、その相手とお付き合いしていることが周囲の人々の顰蹙をかっているため(妊娠したり)、その人と結婚しないともう自分は誰とも結婚できないのだ、という状況がありました。これを逆手にとり、「架空の罪を設定して」好きな相手と結婚する、という事例も多かっただろうという指摘もあります。 第三章では、割合生々しい性の在り方も指摘されます。 その第III節では、ちょっと話が変わり、標題通り、女性がたとえば父親不明の子供を産むような場合に、厳しく断罪されたこと(冒頭の事例では、女性は死罪とされています)などが指摘されます。ただ、女性たちにも戦う権利は残されていて、この子の父親は誰それだと、その男性を告発することもできました。これも、時代によって異なるわけですが…。 終章は、非嫡出子の出生率、婚前妊娠率などのグラフを掲げながら、第三章の終わりの方で論じられた問題をさらに詳しく論じています。 上にも書いたとおり、本書の対象の時代について私は詳しくなく、また本書の記述はあるテーマについてけっこうまちまちの時代の事例を挙げながら論じているため、なかなか理解ができない部分もありました。ノートもとらずにざーっと読みましたし、記事を書くにも時間がかかったため、十分な紹介とは言えませんが…。 訳者あとがきでも指摘されていますが、本書は民俗学的な雰囲気ももちます。農民たちの愛や性を論じるにあたって、主な対象の時代である16-18世紀の史料だけでなく、19世紀、さらには20世紀の事例も紹介されているからです。 フランドラン自身もアナール学派の歴史家といえるかと思いますが、まさにアナール学派第三世代あたりからが力を入れている歴史学と民俗学の接近を感じられる著作でした。 理解は不十分ですが、ひとまずこの機会に通読することができて良かったです。(2009/02/20読了)
2009.02.27
コメント(0)
-

森博嗣『今夜はパラシュート博物館へ』
森博嗣『今夜はパラシュート博物館へ THE LAST DIVE TO PARACHUTE MUSEUM』~講談社ノベルス、2001年~ 講談社ノベルスからの第3短編集です。今回はS&MシリーズとVシリーズのリンクもあって、楽しいです。 それでは、それぞれについて内容紹介やコメントを。ーーー「どちらかが魔女 Which is the Witch?」 [主要人物]西之園萌絵、犀川創平、喜多北斗、大御坊安朋 [内容紹介]西之園萌絵のマンションで開催されるパーティー。今回の話題は、大御坊安朋と彼の大学時代の同級生という木原恵郁子の二人が提供する。まず、木原は、大学時代、帰り道に自分をつけてくる男がいたことを話す。男は地下鉄の駅まで自分をつけてきて、その後は古びた建物に入る。ある日、木原が彼を追ってその建物にある喫茶店に入ってみるが、そこで男を見つけることはできなかった、という。 [コメント]なんとなく、問題の真相は途中で分かりました。それでも、温かい物語で好きです。今回も諏訪野さんが素敵です。「双頭の鷲の旗の下に Unter dem Doppeladler」 [主要人物]犀川創平、喜多北斗 [内容紹介]犀川と喜多の母校、私立T学園で学園祭が行われた。二人のほか、西之園萌絵と国枝桃子も、講演を聞くために学園を訪れる。ところがその前夜、妙な事件があった。ある校舎の一部の窓ガラスに、まるで散弾銃を撃たれたように、細かい穴が無数にあいているのだった。 [コメント]ノスタルジックな気持ちになれる作品です。「どちらかが魔女」も素敵ですが、個人的にはこちらの方が好みです。国枝先生の意外な一面が見られるのも良いです。「ぶるぶる人形にうってつけの夜 The Perfect Night for Shaking Doll」 [主要人物]小鳥遊練無、香具山紫子 [内容紹介]香具山紫子から、N大学に出没するというぶるぶる人形の噂を聞いた練無。紫子は、ぶるぶる人形を見るイベントに参加しようと、練無を誘ったのだった。翌日、練無は大学で、ぶるぶる人形を見るイベントの広告を発見し、フランソワと名乗る女性からその話を聞く。紙で作られたその人形は、どこからも吊られていないので、一人で踊り、人が近づくと燃えてしまうという。 [コメント]このあたりから、シリーズに通じるネタバレなしには書きにくくなってきますね…。ファンとしては嬉しい、S&MシリーズとVシリーズのリンクです。(反転)ここで登場する西之園さんは、萌絵さんではない、ですよね。建物の形があれなので、おや?と思ったのですが、彼女でも、そこに知人の名前が見えるなら使ってしまいそうですし。(ここまで) 南Z大学が登場するのもびっくりでした。伏せ字の位置にびっくりですが、N大学とすると国立N大学とかぶってしまうからでしょうか。こちらが紫子さんの通う大学なのでしょう。 夜、大学でのイベントということで、「誰もいなくなった」(『まどろみ消去』)に通じるものがあります。「ゲームの国 The Country of Game」 [主要人物]磯莉卑呂矛、メテ・クレモナ、角谷歩美 [内容紹介]依頼に応じ、島を訪れた名探偵の磯莉卑呂矛とその助手、メテ・クレモナ。二人は、前村長の玉島諭司のもとを訪れる。三十年前、島の男が、9人の島民を殺した。男は死刑に処される前に不思議な言葉を遺していた。その言葉とおりか、彼の死から26年目、男の孫にあたる娘が失踪を遂げたというのだった。磯莉たちは調査を始めるが、翌朝、玉島家で密室殺人事件が起こる…。 [コメント]事件自体はどうでもいいと言っても良い、それほどにアナグラムやその他の遊び心が楽しい作品です。探偵の磯莉卑呂矛さんはアナグラムが大好きで、いろいろなアナグラム作品を紹介してくれます。しばらく分からなかったのですが、「のっそり、お手」に気づき、他のアナグラムも「もしやあれか」と見当をつけて見てみるとあたっていて、楽しめました。割と暇な時間にのんびり読んだので、こうやって楽しみながら読めて良かったです。(反転)「切って苦、死して邪気」 そうこなくては。これは傑作だ!(ここまで) の部分(156頁)は、アナグラムが解けてから読んだらますます笑えました。「私の崖はこの夏のアウトライン My Cliff is Outline against this Summer」 [コメント]ホラー、あるいは幻想小説といったところでしょうか。「卒業文集 Graduation Anthology」 [コメント]タイトル通り、卒業文集です。若尾満智子先生が担任をもった教室の生徒たちが書いた文集なのですが、先生の魅力が伝わってきます。もちろん、それだけではありませんが。「恋之坂ナイトグライド Gliding through the Night at Koinosaka」 [コメント]どこか幻想的な短編です。こちらもラストに納得でした。「素敵な模型屋さん Pretty Shop of Models and Toys」 [コメント]工作好きの少年が主人公です。私は読書好きで、逆に手作業はさっぱりですが、こうやって何かが好きな人の文章を読んだり言葉を聞いたりすると、なんであれ何かに打ち込んでいる人はかっこいいなぁと、あらためて思います。 既にどこかに書いたかも知れませんが、以前ラジオで、カップラーメンのフタを集めまくっている方が紹介されていました。一般には「何の役に立つのか」と思われそうなこんなことでも、とことん追求しているのはかっこいいと思いましたし。ある意味では、自分の趣味にはこんな利点がある、という次元すらも超越していて、純粋な印象さえあります。 …そんなこんなで、私は模型には興味がありませんが、本作は模型に打ち込む少年の姿に、どこか憧れのような感情を抱きながら、楽しく読みました。ーーー 本作も再読ですが、この作品くらいから、読み直すのは初読以来初めてになるように思います。というんで、より記憶が薄れていて、新鮮な気持ちで楽しめました。 上にも書きましたが、「双頭の鷲の旗の下に」は国枝先生のファンには嬉しい作品です。 今回は「ゲームの国」がとても楽しめて、良かったです。(2009/02/22読了)
2009.02.26
コメント(2)
-

森博嗣『魔剣天翔』
森博嗣『魔剣天翔 Cockpit on Knife Edge』~講談社ノベルス、2000年~ Vシリーズ第5作です。ついにエンジェル・マヌーヴァや各務亜樹良さんも登場し、Vシリーズもますます佳境に入っていきます。 それでは、内容紹介と感想を。ーーー某年、11月。 有名ジャーナリスト・各務亜樹良に呼び出された保呂草潤平。まず、各務が女性であることに驚く。 そして、各務からの依頼は、半年前にフランスから日本に戻ってきた有名画家・関根朔太のもとにあるという秘宝(魔剣)、エンジェル・マヌーヴァを盗み出してほしいというものだった。 なんとか関根に近づく手段はないかと試案する保呂草に、小鳥遊練無から思いがけない誘いが入る。朔太の娘、関根杏奈が所属するチームによるフライト・ショーへの誘いだった。 * 練無は、憧れの先輩、杏奈からフライト・ショーの招待券をもらう。そこで、香具山紫子、保呂草潤平、森川素直、瀬在丸紅子、紅子の息子のへっ君、その使用人で拳法の師匠の根来機千瑛も誘い、森川の姉のワゴンで出発する。 ところが、当日、事件が発生する。一度演技を終えた後、ふたたび飛び立った4つの飛行機のうち、2台に異変が起こる。二人乗りの飛行機の中、後ろに乗っているパイロットが、背中から銃撃されて死亡していたのだった。しその飛行機に乗っていた自称ジャーナリスト・アシスタントも現場から逃走していた。 会場にきていた刑事の祖父江七夏たちに協力しながら、練無は事件の謎に挑む。ーーー 内容紹介でも、あえて事件の謎に挑むのは練無さんだと書きましたが、本作は練無さんの物語だと思います。 事件自体は、空中での完全密室の中で起こった殺人事件と、謎は魅力的なものの、割合地味な印象も受けます。それは、保呂草さんの逃走劇や、本作のもう一つの大きなテーマである関根朔太やエンジェル・マヌーヴァの存在が大きいからかもしれません。 最終章とエピローグでは、涙がおさえられませんでした。ちょっと文字色を反転させて書いておきます。(ここから)今回は、最初から最後まで練無さんと紫子さんの仲がちょっとぎすぎすしてしまうのですが、きっとそれがあったからこそ、第九章で練無さんを抱きしめる紫子さん、その二人の姿がとてもきれいに感じられたのだと思います。S&Mシリーズから再読してきて、Vシリーズはなかなか登場人物に感情移入できないでいたのですが、今回で、この二人の大ファンになりました。(ここまで) それでは例によって、付箋をはったところの引用もしておきます(文字色反転)。木の葉は偶然にも、私の足もとに舞い降りる。こんな奇跡的なことが無限に発生して、日常を形成するのだ。(18頁)(2009/02/21読了)
2009.02.24
コメント(3)
-

森博嗣『夢・出逢い・魔性』
森博嗣『夢・出逢い・魔性 You May Die in My Show』~講談社ノベルス、2000年~ Vシリーズ第4作です。今回はテレビ局を舞台にした事件です。 それでは、内容紹介と感想を。ーーー某年、秋。 クイズ番組に出場することになった香具山紫子、小鳥遊練無、瀬在丸紅子は、保呂草潤平とともに、東京へ向かった。 保呂草は、そのテレビ局にいる友人と久々の再会をする。友人は、上司―柳川から悩み事があると相談を受けているという。保呂草は、東京にいる知人の探偵、稲沢真澄を紹介する。 稲沢はテレビ局にきたものの、待ち合わせの時間になっても柳川は現れなかった。そして、練無たちは、人気タレントの立花亜裕美が、ある部屋から出てきて、泣いてしまうのを目撃する。 立花が出てきた部屋から聞こえた不審な音。その後、部屋に保呂草と稲沢が入ると、そこには二箇所を撃たれて死亡した柳川が倒れていた。 柳川は、夢に出てくる女に怯えていたという。そして立花は、その部屋で幽霊を目撃したというが…。ーーー 久々の再読ですが、すっかり忘れていました。なので謎解きシーンでは、まさか紅子さんそこで…!?と思いながら、はらはらしながら読みました。案の定でしたが…(笑) 今回登場する探偵の稲沢さんが、とてもいい味を出しています。というんで今回は、稲沢さんの情報についてメモをしておきます。稲沢真澄(31歳…保呂草より2歳年上):無口な探偵。3年前、カイロで保呂草と出会う。(2009/02/21読了)
2009.02.23
コメント(1)
-

筒井康隆『小説のゆくえ』
筒井康隆『小説のゆくえ』~中公文庫、2006年~ 筒井さんのエッセイ集です。断筆宣言後に書かれた100のエッセイが収録されています。 本書は、以下のように、9部構成となっています。I.現代世界と文学のゆくえII.表現の自由に関する断章III.予想がつかぬ意外性IV.すぐそこにある豊穣V.時代を見る眼と通時性VI.「悪魔の辞典」新訳の悪夢VII.約1トンのコーヒーVIII.筒井家覚書IX.映像化された哲学的思考 簡単に、それぞれの部に収録されたエッセイの傾向について書いておきます。 第I部は、筒井さんが監修を手がけた、岩波書店『21世紀 文学の創造』への寄稿文など、文学論を扱ったエッセイを集めています。 第II部は、標題通りですね。断筆のきっかけとなった、日本てんかん協会の会長への回答や要望、あるいは断筆解除の際の覚え書きなどが収録されていて、興味深く読みました。 第III部、第IV部は、書評集といえます。第III部はいろんな作家の作品への推薦文、第IV部は三島由紀夫賞選評など、選評集となっています。 第V部は、筒井さんと親交のあった星新一さんや半村良さんの思い出や、思い出の本、ミステリなどについてのエッセイを集めています。 第VI部は、自作についてのコメントを集めています。筒井さんによる『悪魔の辞典』の邦訳も未読ですが、ここでは『わかもとの知恵』という本が気になりました。子供向けの雑学本とのことですが、面白そうです。 第VII部は、食事に関するエッセイが中心です。 第VIII部は、筒井さんご自身に関するエッセイを中心に、雑多なエッセイを集めた感じです。ここに収録された「読み、語り、聞かせること」というエッセイを、とても興味深く読みました。子供に読み聞かせをする大切さを説いた文章ですが、今後も大切に読み返したいと思いました。私は子供の頃は読書が嫌いだったのですが、アンデルセン童話やグリム童話、あるいはギリシャ神話などなど、主要な物語を知らないことが現在とても悔やまれます。もちろん、童話や寓話、神話は、年を重ねてからもあらためて見えてくることがあるわけですが、将来子供をもつことがあれば、いろんな物語を聞かせてあげたいと思っています。 第IX部は、絵画、劇、映像(映画)に関するエッセイを集めています。冒頭におかれた「すべてを絵に語らせよ」というエッセイは、マグリットの絵画について論じています。いわゆるシュールリアリズムの作品を見るのは好きなものの、画集もダリのそれしか持っていませんし、その運動に関する知識も貧弱ですが、あらためて興味をかきたてられました。 職場でのお昼休みの友に少しずつ読んだのと、最近記事を書くのが疲れ気味のこともあり、簡単ではありますが、このあたりで。記事を書くのも無理なく、ゆったりのペースにするとしましょう…。(2009/02/20読了)
2009.02.22
コメント(0)
-
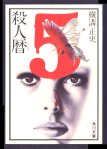
横溝正史『殺人暦』
横溝正史『殺人暦』~角川文庫、1981年5版(1978年初版)~ 1931年(昭和6年)から1933年(昭和8年)の間に書かれた、6編の中短編が収録されています。 それでは、それぞれについて簡単にコメントを。ーーー「恐怖の映画」[内容紹介]河村プロダクションの人気俳優・菅井良一は、河村省吾の愛妻にしてプロダクションの首脳女優、蘭子と不倫の関係にあった。自らが大会社に入る手続きを進めながら、彼女との関係を清算すべく、彼女と逢い引きしているところに、河村本人がやって来る。菅井はとっさに、蘭子を大道具の「鉄の処女」に隠し、その場を切り抜けるが、その後、両目をつぶされ、殺された蘭子の死体が発見される。[コメント]ミステリというよりも、サスペンスやホラーの風味が強い作品です。陰鬱な雰囲気が全体に漂いますが、この手の味わいも好きです。「殺人暦」[内容紹介]存命中に死亡広告の出された五名の男女。彼らは、探偵の結城三郎に脅迫者を突き止めるよう依頼するが、彼ら自身が脅迫される理由については、決して語ろうとしない。5名の内の2名は、過去にその秘密に携わった人物の息子あるいは姪で、事情は分かっていない風であったが…。 事件の解明には、結城探偵だけでなく、そのライバルにして、決して人は殺さない泥棒、隼白鉄光も関わる。二人は敵対しつつ、事件を解決する方向では一致していたが、ついに事件は起こる。犯人の予告通り、5名のうちの一人が、舞台で殺された…。さらに犯人は、新たなターゲットを示す予告を出す。[コメント]解説で中島河太郎さんも書いていらっしゃいますが、ちょっと盛りだくさん過ぎな感じはあります。最初の内は結城探偵と鉄光の対決もあるのですが、いつの間にやら結城探偵は出てこなくなりますし…。5人の死を予告する脅迫者の存在はありますが、しかし犯人当てミステリというより、サスペンス風味が強いです。ラストも唐突な感じですし、もう少し枚数の多い作品にしていればもっと良かったのかも、と思いました。「女王蜂」[内容紹介]かつて、畦柳半三郎が道楽半分で起こしたプロダクションに所属していた女優、紅澤千鶴は、外国人銃撃の容疑で逮捕され、出獄後は上海に渡って死亡していた…はずだった。彼女に関して苦い思い出のある半三郎の下に、当時プロダクションに出入りしていた富士郎が、ある情報をもたらす。それは、千鶴が生きており、しかも現在は鷲尾子爵の令嬢、芙蓉子と名乗っている、というものだった。彼らが真相を探り始めた頃、別の人々も彼女の周辺を探り始めていた…。[コメント]金田一シリーズ『女王蜂』とタイトルは同じですが、無関係です。こちらはなかなか複雑ですが(というのも、人間関係がおいおいにしか分からないので)、スリルを感じながら読み進めました。「死の部屋」[コメント]アメリカから久々に帰国した知人、木藤氏を、「私」が訪れ、その後、彼からある告白を聞くという物語です。「三通の手紙」[コメント]冒頭に3通の手紙が掲げられ、最後にきれいにまとまっています。「九時の女」[内容紹介]実家が破産の危機にあった探偵作家、寒川譲次のもとに、彼らが「九時の女」と呼んでいる女性から電話がかかってきた。ダンスホールで何度か踊った程度の彼女は、寒川に、彼が必要としている三千円を差し上げるかわりに、一つお願いを聞いて欲しい、という。それは、ある邸宅に行き、応接間に落ちている赤いショールを持ってきてほしい、というのだ。 怪しい依頼だが、実家の危機を救うためにも、彼は依頼に応じる。訪れた邸宅は、「九時の女」が何度か一緒に踊っていた人物の家だった。そして応接間には、たしかにショールはあったが、それは暖炉に頭を突っ込んだ男の死体の手に握られていた…。[コメント]この短編集の中で、いちばん楽しく読んだ作品です。寒川さんの探偵役も良いです。ーーー と、この短編集にはシリーズキャラクターは登場しませんが、面白く読みました。※表紙画像は、横溝正史エンサイクロペディアさまからいただきました。(2009/02/15読了)
2009.02.19
コメント(2)
-

J・ル=ゴフ/A・コルバンほか『世界で一番美しい愛の歴史』
J・ル=ゴフ/A・コルバンほか(小倉孝誠/後平隆/後平澪子訳)『世界で一番美しい愛の歴史』(Dominique Simonnet et. al., La plus belle histoire de l'amour, Editions du Seuil, 2003)~藤原書店、2004年~ 本書は、雑誌『エクスプレス』編集主幹のドミニク・シモネ(本書では、ドミニック・シモネと表記されています)が、9人の歴史家・小説家に行ったインタビューを通して、先史時代から現代までの愛の歴史を通史的に描いています。 なお、ドミニク・シモネはミシェル・パストゥローとともに刊行した『色をめぐる対話』(邦題)という小著でも、インタビューアーとしての手腕を発揮しています。 さて、本書の構成は以下の通りです。ーーープロローグ(ドミニック・シモネ)第一幕 まずは結婚 第一場 先史時代―クロマニョン人の情熱(ジャン・クルタン) 第二場 ローマ時代―禁欲的な夫婦の出現(ポール・ヴェーヌ) 第三場 中世―そして肉体は罪とみなされ…(ジャック・ル=ゴフ)第二幕 感情も加わって 第一場 アンシャン・レジーム―性秩序の支配(ジャック・ソレ) 第二場 フランス革命―美徳の恐怖政治(モナ・オズーフ) 第三場 十九世紀―うぶな娘と淫売屋の時代(アラン・コルバン)第三幕 そして最後に快楽 第一場 狂乱の歳月―これからは気に入られなければならない!(アンヌ=マリー・ソーン) 第二場 性の革命―遠慮なく楽しもう!(パスカル・ブリュックネール) 第三場 そして今―愛は自由なのか?(アリス・フェルネー)ドミニック・シモネによる執筆者プロフィール訳者あとがきーーー プロローグで、愛の歴史は感情(愛)、結婚(生殖)、性(快楽)という3つの領域に還元されるとあります。愛の歴史は、これらの3要素の結びつきや解離をめぐって、揺れ動くことになります。これらはまた、それぞれの幕の標題にも使われていますね。 第一幕第一場では、恋愛の感情はクロマニョン人から始まるといいます(埋葬の在り方からうかがわれるとか)。また、農耕の始まりととともに「のどかなカップルの時代も終わる」というのも面白いです。農耕の始まりとともにリーダーが生まれ、貧富の差が拡大する。『食の歴史』によれば集団生活を営むようになるため伝染病も広がっていくとのことですが、人類の発展にとって非常に重要な農耕は、同時に多くの負の面ももたらしているなぁ、とあらためて思いました。ちょっと脱線しましたが、愛の歴史についていえば、女性はしなきゃいけない家事がうんと増えますし、また、一定の権威者が人々の私生活まで牛耳るようになり、人々は自由に伴侶を選ぶことも難しくなっただろう、とのことです。 ローマ時代以降について、しばしば言われるのは、ある時代の図像や文学が、必ずしも同時代の反映ではない、ということ。たとえば、ローマ時代では性器をあらわにした彫刻が広場に置かれ、風刺文学などではエロティックな描写もあるわけですが、現実には性に関する規制はかなり多かった、といいます。やがて、性生活とは子供をつくるためにあるのだから、過剰な行動は慎みなさい、という規範が広まっていくそうです。これはすなわち、キリスト教が広まる以前から、禁欲的な思想、結婚の在り方が生まれていたということで、とても興味深く読みました。 ただし、ローマ時代のこうした道徳は人々をかなり抑圧していました。ところが、中世にキリスト教式結婚が広まると、夫婦の合意が必要となります。男女問わず、権力や家族の意向に逆らって、望まない結婚を拒否することができるようになる、このことをル・ゴフは強調します。 …と、第一幕について外観的に書いてみましたが、第二幕以降も面白いです。 ちょっと広い話にしてみれば(あるいは当たり前の話を繰り返すことになりますが)、結婚の平均年齢や、たとえば貴族層や農民層での結婚・恋愛の在り方の相違などは、それぞれの社会階層(身分)のライフスタイルの在り方とも関わってきますし、結婚・恋愛について社会・家族が押しつける価値規範というのも、同時代のより広い思想(たとえば宗教や政治的イデオロギー)や制度(たとえばいま読み進めているフランドラン『農民の愛と性』でも扱われている婚資)との関わりを見なければなりません。 逆にいえば、本書を読めば、簡単にではありますが、愛の歴史を通じて、同時代の背景も浮かび上がってくる、といえると思います。 インタビュー形式ですので、読みやすいだけでなく、内容的にも幅広い情報も得られ、有意義でした。(2009/02/11読了)
2009.02.18
コメント(1)
-

森博嗣『月は幽咽のデバイス』
森博嗣『月は幽咽のデバイス The Sound Walks When the Moon Talks』~講談社ノベルス、2000年~ Vシリーズ第三作です。今回もまた、保呂草さんや紅子さんの知り合いの邸宅で、事件が起こります。 それでは、内容紹介と感想を。ーーー瀬在丸紅子、29歳/保呂草潤平、28歳 9月。 保呂草は、仕事の関係で篠塚家を訪れていた。そこに、同じく保呂草と仕事上の関係もあり、森川素直の姉でもある森川美紗もやってくる。二人は、篠塚家の当主で篠塚建設の社長、宏邦と面会し、彼から一つの相談をもちかけられた。3日前に、何者かから届けられた名画。それを買う仲介をしてほしいと言うのだった。 * 「無言亭」付近で森川美紗に声をかけられた紅子は、彼女とともに篠塚家へ向かった。途中、宏邦の娘で彼女の友人でもある莉英と出会い、二人は喫茶店へ向かう。そこで紅子は、莉英が、その友人の神部和明と結婚するということを聞く。 篠塚家に戻り、保呂草と紅子が知人だということを知った莉英は、二人ともをその夜のパーティに招待する。 * 阿漕荘へ引っ越ししてきた森川素直のもとで遊んでいた小鳥遊練無と香具山紫子は、保呂草からの連絡を受け、3人で篠塚家を訪れる。パーティだというが、まさに、篠塚家には満月の夜に狼男が出るという、その家の噂をしていたところだった。 ところが3人が訪れたときには、すでに事件が起こっていた。密室状況の中、女性が死亡していた。頭部を殴られたようであり、大量の出血をしていた。さらに、噛まれたような傷もあり、体が部屋中にひきずりまわされたかのように、部屋の中は血まみれだった…。ーーー 何度目かの再読です。2000年頃から、小説を読了したら感想を書くようになっていますが、このシリーズは、このあたりから感想が書きにくくなってきたのを覚えています。今になっても書きにくいですね…。 今回の再読は、登場人物のデータを把握するためと割り切って、『人形式モナリザ』の感想記事でも登場人物整理を書きましたが、ここにも新たな点をメモしておきます。・森川美紗(29歳)…森川素直の姉。骨董品商。3人の弟がいて、素直は末っ子。・祖父江七夏の娘(5歳)…七夏と林の間に生まれた子供。(2009/02/15読了)
2009.02.17
コメント(0)
-

森博嗣『人形式モナリザ』
森博嗣『人形式モナリザ Shape of Things Human』~講談社ノベルス、1999年~ Vシリーズ第2作です。今回は、夏休みに遊びに行った長野県で、紅子さんたちが事件に巻き込まれます。 それでは、内容紹介と感想を。ーーー瀬在丸紅子、29歳/保呂草潤平、28歳 7月。 小鳥遊練無と友人の森川素直は、長野県の別荘地、蓼科にある美娯斗屋というペンションでバイトをしていた。そこに、練無の友人の香具山紫子、保呂草潤平、瀬在丸紅子がやって来る。 3人がペンションに訪れた日、保呂草と紫子は霧ヶ峰美術館を訪れる。ところがそこでは、絵画の盗難事件が発生していたという。紫子は、その絵画を描いた画家、中道豊と話をする機会を得た。犯人は凄い盗み方をしたというのだが…。 一方、紅子の前夫である林も、交際している部下の祖父江七夏とともに長野を訪れていた。長野県警の知人から、中道の絵画が盗難された事件を聞き、7年ぶりに美術館専門の窃盗犯が動き始めたことを知る。 * そして、保呂草たちが、ペンションの人々とともに「人形の館」を訪れ、観ていた人形文楽の舞台で、事件は起こる。文楽で有名な岩崎雅代が、麻里亜をまるで人形のように扱うその舞台の上で、とつぜん麻里亜が血を吐いて倒れた。林と祖父江も訪れており、観客の足止めなどの措置はとられたものの、「人形の館」の中は騒然とする。さらに、紫子たちが雅代の安否を確認に行くと、彼女もまた背中をナイフで刺されて死亡していた…。 保呂草たちは、6月の事件に続き、この事件の謎に挑む。ーーー 数年ぶりの再読でしたが、シリーズ第2作から、祖父江さんも登場し、美術品の窃盗事件も起こっていたのかと、新鮮な気持ちでした。 『黒猫の三角』も衆人環視状況での密室殺人事件でしたが、今回は密室の要素は薄いものの、衆人環視状況という点は共通します。そして、殺人はいかに行われたか、という点も興味深いですが、今回はその動機も興味深いです。S&Mシリーズ以上に、動機はどうでも良い、という論調は強いですが、逆説的に(?)、動機も重要な要素になっている、というか。 さて、今回は、主要人物についていくつかのデータをメモにしておきます(そろそろ、人物関係を把握して、次シリーズ以降の再読に備えなくては)。(年齢はこの事件時点=某年7月)・保呂草潤平(28歳)…探偵。なんでも屋。・小鳥遊練無(19歳)…国立N大学医学部2年生・香具山紫子(19歳)…私立大学文学部2年生・森川素直(20歳)…練無と同じ大学、同じクラスの友人。アマチュアのロックバンドでベースを担当。・瀬在丸紅子(29歳)…科学者。「桜鳴六角邸」離れの「無言亭」に住む。・へっ君(小学6年生)…紅子の息子。・根来機千瑛(?)…瀬在丸家の使用人。練無が通う道場の世話役。・林(39歳)…愛知県捜査一課の警部。紅子の元夫。12年前に結婚(当時27歳)。6年前に離婚。・祖父江七夏(28歳)…林の部下、愛人。離婚歴あり。林との間に娘あり。 最後に、印象に残った部分を引用しておきます(文字色反転)。 失われることは、悪いことではないのだ。 削り取られて、そこに形が現れることだってある。 万が一にでも、美しい形が生まれることがあれば、尚更だろう。 その希望こそが、生きる動機ではないか。(42頁)(2009/02/11読了)
2009.02.16
コメント(4)
-

竹内海南江『お姫さまと山男 旅する私のおかしな恋愛』
竹内海南江『お姫さまと山男 旅する私のおかしな恋愛』~集英社be文庫、2006年~ 「世界ふしぎ発見」のメインレポーターとして活躍しておられる、竹内海南江さんの書き下ろしエッセイです。同文庫既刊の『おしりのしっぽ』に続く、第二作ということになります。 さて、竹内さんは恋愛が苦手とのことですが、本書はまさに恋愛がテーマ。して内容はといいますと…。 大きなテーマがいくつかありますが、なぜ自分は恋愛が苦手か、というのが一つ。というか、このことについていろんな方向からアプローチしているわけですが、あえていえば、愛情にはいろんな種類があるよ、というのも、もう一つのテーマでしょうか。 本書では、竹内さんの意外な面がいろいろと見えてきます。小学校、中学校でのイジメの件は悲しいですが、悲しいようには書いていません。むしろ、それを通して早くから大人になった(状況を客観的に見たり)、ということや、足が速くなったなどなど、プラスの側面も強調しておられます。男の子からのいじめには徹底的に戦った、というあたり、かっこいいなぁと思いながら読みました。 さて、まずちょっと重たいところを紹介しましたが(でも、エッセイ自体は重たいようには書かれていません)、その他に意外なことといえば、すごいこだわり、でしょうか。チャーシューを食べるのが苦手なのに、チャーシューはダシだからツユが美味しくなると思って、チャーシュー麺を注文する、とか、保育園に行きたがらなかった、とか。保育園の件、特にお母さんにバイクで連れて行ってもらう、そのお母さんと過ごす一時だけが楽しかったというあたりは、なんだかすとんと納得できました。 それから、上にも少し書きましたが、愛情にはいろんな種類がある、ということ。家族愛、友人愛、恋愛と、竹内さんは大きく三つを挙げて、竹内さんご自身は家族愛と友人愛が強くて、恋愛が弱いのでは、と書かれています。逆に、恋愛が弱くても、多くの方から愛情を受けている、と。…あとはまぁ、他人からの恋愛感情に気付かない、ということも書かれておられます。 おまけ(?)として、いくつかレシピが紹介されているのも嬉しいです。いつか試してみたいです。 竹内さんの撮り下ろし写真や、竹内さんによるイラストもあります。 というんで、竹内さんのファンには嬉しい一冊です。(2009/02/07読了)
2009.02.15
コメント(0)
-
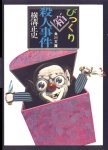
横溝正史『びっくり箱殺人事件』
横溝正史『びっくり箱殺人事件』~角川文庫、1977年13版(1975年初版)~ 表題作と、金田一耕助シリーズの「蜃気楼島の情熱」の二編が収録されています。「蜃気楼島の情熱」は『人面瘡(金田一耕助ファイル6)』の記事にゆずりまして、ここでは表題作についてのみ記事を書いておきます。 さて、「びっくり箱殺人事件」は、横溝作品の中でも異色の、ユーモア色全開のミステリとなっています。それではあらためて、内容紹介と感想を。ーーー 梟座でレヴュー「パンドーラの匣」を企画した熊谷久摩吉、自信はあったもののちょっと心細くなり、多芸多能でスリラーも書く深山幽谷先生のところへ相談に行く。踊り子たちが脚を上げるだけでなくて、スリラー風味を加えましょうという趣向だった。そこで幽谷先生、自分の仲間5名を、怪物団として登場させることにする。フランケンシュタインやハイド氏などなどが、舞台の1シーンで大暴れ、というのである。 舞台は成功をおさめていたものの、7日目に事件は起こる。まず起こったのは怪物団殴られ騒動。暗がりの中で、怪物団5人と幽谷先生、何者かに殴られ、みな顔にブチができてしまう。ところが殴られたのは6人だけでなく、企画部の田代信吉、レヴュー作家の細木原竜三も、ブチができていた。 なにはともあれ舞台の幕は開き、女優の紅花子と俳優の石丸が登場する。ところが、花子の台詞や仕草も違い、冒頭で「パンドーラの匣」を開くのは花子のはずなのに石丸が開いた。…とたん、箱の中からナイフが飛び出し、石丸は舞台の上で死亡する…。 幽谷先生の娘にしてマネージャーの恭子や、トンチンカンな新聞記者、六助なども活躍するも、さらに事件は繰り返される。さて犯人は誰なのか…。ーーー 冒頭から、ユーモアあふれる文章で、わくわくしながら楽しく読みました。殴られたらブチはできるし、殴るときの音はボエン(たしか、ドラえもんでもこの擬音があったような…?)。怪物団も、顎十郎くんやシバラクくんなどなど、楽しい名前の人たちです。一人、横溝さん意識しておられたのかどうか分かりませんが、灰屋銅堂さんも登場します。この名前の人物は、「百面相芸人」(『ペルシャ猫を抱く女』所収)にも登場するので、嬉しい驚きでした(二人は別人ですが)。 警察は等々力警部も登場するのですが、これは作者曰くに「捜査陣全体の人格化された人物」とのこと。金田一さんとコンビを組む等々力警部とは別人と考えた方が、ショックは少なくてすみます(笑) とにかく楽しく笑いながら読めるのですが、それでいて謎解きの妙も楽しめます。本作も昭和23年(1948年)と、戦後の、質の高い作品をもりもり発表しておられた時期のこともあってか、ユーモアだけにとどまらないミステリとしての面白さも抜群です。 楽しい一編でした。※表紙画像は、横溝正史エンサイクロペディアさまからいただきました。(2009/02/08読了)
2009.02.13
コメント(2)
-

森博嗣『黒猫の三角』
森博嗣『黒猫の三角 Delta in the Darkness』~講談社ノベルス、1999年~ 瀬在丸紅子さんを中心に、保呂草潤平さん、香具山紫子さん、小鳥遊練無さんが活躍するVシリーズ、第1弾です。初読のときの衝撃は忘れられないですね。 それはともあれ、内容紹介と感想を。ーーー瀬在丸紅子、29歳 6月6日。 探偵にしてなんでも屋の保呂草潤平のもとを、小田原静江が訪れた。彼女は、保呂草の住むアパート、阿漕荘の家主であった。依頼の内容は、息子の家庭教師の斡旋。彼女の夫は、彼女が経営する塾の教師だったが、息子は別の家庭教師を希望しているというのだった。保呂草は、同じアパートに住む小鳥遊練無に、この仕事を持ちかける。 ところが午後、保呂草はふたたび静江から連絡を受け、彼女が住む桜鳴六角邸を訪れた。そこで彼女は、その日届けられたという封筒を示し、中の3枚の新聞記事を彼に示した。それは、3年前からそのあたりで起こっていた、殺人事件の記事だった。3年前の7月7日、11歳の少女が絞殺された。2年前の7月7日、22歳の女性が、昨年の6月6日には33歳の女性が絞殺された。そして今年の6月6日は、静江の44歳になる誕生日だった。彼女は、保呂草にその日一日の警備を依頼する。 その日は、静江の誕生パーティーが行われた。桜鳴六角邸の離れに住み、保呂草たちとも親しい瀬在丸紅子と、その執事である根来機千瑛も参加する。保呂草は、小鳥遊と香具山紫子を雇い、3人がそれぞれトランシーバーを持って、警備にあたった。 午後8時半頃、静江は一人自室に入り、内側から鍵をしめた。その後、中に入った人は誰もいないにも関わらず、外で見張りをしていた小鳥遊は男の影を目撃していた。そして、静江はドアも窓も内側から鍵をかけられた密室の中で、絞殺されていた…。 事件の担当には、3年前から事件を追い続けており、また紅子の前夫でもある林がつくことになる。紅子たちは、ときに林も交えて意見交換をしながら、事件の謎に迫っていく。ーーー 物語の内容を振り返ると、なんとも深いものがありますね…。今までに少なくとも2回は読んでいるのですが、瀬在丸さんと保呂草さんがテストの点数について話をするシーンはとても印象に残っています。 ただ、特に瀬在丸さんの人格について忘れてしまっていたので、そういえばこんなだったと思いながら、新鮮な気持ちで読みました。トリックはおぼろげに覚えていましたが、その後の事件で混乱しましたし…。 さて、次回のVシリーズは『人形式モナリザ』です。(2009/02/08読了)
2009.02.12
コメント(2)
-

佐藤友哉『青酸クリームソーダ <鏡家サーガ>入門編』
佐藤友哉『青酸クリームソーダ <鏡家サーガ>入門編』~講談社ノベルス、2009年~ 久々の<鏡家サーガ>です。今回は、デビュー作『フリッカー式 鏡公彦にうってつけの殺人』の主人公、鏡公彦さんが主人公です。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。ーーー コンビニ帰り、今まで知らなかった路地裏で、公彦はそれを見た。少女が、竹ヤリで男を突き刺し、殺しているのを…。公彦に見られたことを知った少女は、「責任をとれ」と、公彦に迫る…。 * 少女―灰掛めじかは、公彦を自分の部屋に招き入れた。彼の胸に爆弾を取り付け、めじかは一つの条件を出す。それは、一週間以内に、自分が人を殺す動機を明らかにしなければ、その爆弾を爆破させる、というものだった。 めじかに美味しい料理を出してもらいながら、敵対しながら、公彦はその動機について考える。過保護の長男、潤一郎に名探偵役を依頼し、姉の稜子にフォローされ、時には兄の創士から電話連絡が入りながらの、それはめじかとの戦いとなる。ーーー 冒頭からいきなりだなぁと思いながら読み進めましたが、人を殺しまくる少女が、自分がなぜ人を殺すのかと問う、その問題設定は面白く、物語に引き込まれる感じでした。笑いもあり、楽しいですね。 鏡家7兄弟も登場していて、それが「入門編」たる所以でしょうか。 …これを読むと、久々にクリームソーダが飲みたくなりますね…(笑) あとはちょっとメモの意味も込めて、鏡家7兄弟のリストを掲げておきます。・長女:癒奈…30歳の誕生日前日に自殺・長男:潤一郎…科学者。初瀬川研究所でロボット作り。・次女:稜子…同人漫画家。・次男:創士…小説読み、美形、交際家。・三男:公彦…大学生・三女:佐奈・四女;那緒美(2009/02/07読了)
2009.02.11
コメント(1)
-

河原温『都市の創造力(ヨーロッパの中世2)』
河原温『都市の創造力(ヨーロッパの中世2)』~岩波書店、2009年~ 岩波書店から刊行されているシリーズ「ヨーロッパの中世」の第2巻(第3回配本)です。このシリーズのタイトル(テーマ)の多くが目新しいのに対して、日本でもなじみがあり、研究も蓄積されている都市が扱われているという意味で、異色な感じもします。…が、中世都市の概観的な整理に加え、最新の研究動向をふまえた興味深い内容となっています。 本書の構成は以下のとおりです。ーーー序章 都市のヨーロッパへ第一章 中世都市の誕生 1 中世における都市の原型 2 中心地としての都市第二章 空間システム 1 都市イメージの形成 2 都市人口と都市化 3 都市プランの形態学 4 都市の公共空間 5 都市空間の分割第三章 組織と経済 1 都市の団体形成 2 権力の行使―都市貴族の形成 3 商業と金融業の世界 4 労働の枠組み 5 財政 6 都市の防衛―市民軍と傭兵 7 記録の場としての都市第四章 統合とアイデンティティ 1 社会的絆と空間的統合 2 市民的宗教のかたち 3 祝祭とソシアビリテ 4 時間意識の統合第五章 秩序と無秩序 1 社会的不和と政治的暴力 2 災厄の諸相―飢饉、疫病、戦争、災害 3 環境と衛生 4 モラルの浄化と社会規制 5 救貧のポリティックス 6 都市とユダヤ人第六章 「聖なる都市」から「理想の都市」へ 1 都市の自立と従属 2 人文主義と都市イメージの変容 3 都市景観図に見る都市の視覚イメージ終章 中世ヨーロッパ文明の中の都市参考文献索引ーーー 以下、興味深かった点について書いておきます。 まず第一章は、基本的な事項の整理となっています。 ラテン語でヴィク、ポルトゥス、ブルグスなど、いわゆる都市を示す語はいろいろあるのですが、それらの性格を整理している部分が、特に勉強になりました(なにぶん基本的なところも押さえられていないので)。 第二章は飛ばしまして、第三章では、4節の労働の枠組みのところで気になる部分がありました。それは、同業組合(ギルド)が、それぞれの職業集団がもつ「名誉」の度合に応じて都市内に序列化されていた、ということ(113頁)。ここではブザンソンの例が示されますが、ル・ゴフによる職業についての研究(『もうひとつの中世のために』所収「中世西洋における合法的な職業と非合法の職業」)や、パストゥローが染物師についての研究()などが示すような、職業の象徴性(貴賤の程度)についても、あるいは都市ごと、地域ごとに違いが探れるのかな、などと想像しました。 ふたたび第四章は飛ばしますが、第五章、第六章が、本書の中でもっとも興味深く読んだ部分です。 第五章では、災厄や環境について紹介している部分が特に面白かったです。豚がうろちょろしていたことを紹介している部分で、せっかくだから「王を殺した豚」についても言及があればより面白かったのでは、と思うのはないものねだりですが。街路に平気でゴミを捨てていたということですが、このあたりの衛生や不潔に関する感性も興味深いですね(最近、『不潔の歴史』という本も出ているようですが…)。 第六章は、中世から近世へと移行する局面にあっての、都市の性格について論じています。フランスや英国という、近代国家化が進んだ地域では、都市の自治が弱まっていった(議会を構成する一つの要素となっていく)一方で、近代国家化にすぐには進まなかったドイツ、イタリアでは、都市の重要性は弱まらなかった、といいます。後者の地域は「都市ベルト帯」と呼ばれるようですが、なるほど!と、とても勉強になりました。2節での理想の都市論や、3節で扱われる都市景観図についても、興味深く読みました。 * 都市と農村、政治、経済…こういった基本的な部分についての勉強から学生時代はずっと目を背け続けていたので、本書は苦手なテーマではありますが、それでもいろんな都市の類型的な整理から、興味深い話題もあり、勉強になった一冊です。 第4回配本は、関哲行『旅する人びと(ヨーロッパの中世4)』(2月下旬発売)のようです。こちらも楽しみです。 それにしても、このシリーズが当初の予定通りきちんと毎月刊行されているのはすごいと思います。(2009/02/05読了)
2009.02.10
コメント(0)
-

高田崇史『カンナ 天草の神兵』
高田崇史『カンナ 天草の神兵』~講談社ノベルス、2009年~ カンナシリーズ第2作です。今回の舞台は天草。鴨志田甲斐、貴湖、柏木竜之介の三人は、天草四郎の謎に挑むとともに、現地で起こった殺人事件に巻き込まれます。 それでは、内容紹介と感想を。ーーー 失踪した早乙女諒司が、熊本にいるらしい…。出賀茂神社に連絡が入り、甲斐、貴湖は熊本に向かうことになる。ところがそんな話になったところに居合わせた雑誌記者の竜之介は、熊本にも長崎にも住んでいたことがあるということで、彼も同行することになった。 今回は、天草・島原の乱の性格について議論になる。それはキリシタン一揆という性格だったのか、圧政に苦しむ農民たちによる一揆だったのか、はたまた「乱」だったのか。そして、天草四郎は、なぜ「四郎」という名前なのか。 天草に渡るとき、そこで殺人事件が起こっていたということを知る。諒司と思しき一人の旅行者が、事件のまわりに現れているようだった。 事件は、孤児の世話などをするロザリオ園、そしてその母体となる天草ロザリオ教会の周辺で起こっていた。園の園長(シスター)が何者かに殺害され、被害者につきまとっていたという男も謎の死を遂げていたという。 甲斐たちは、諒司の行方を探るべく、事件についても情報を集めていった。ーーー 天草・島原の乱にまつわる謎について、特に興味深く読みました。それにしても、ふだん気にせずに当たり前に思っている部分(たとえば天草四郎という名前)についても、鋭い疑問を投げかけていく、そこがこのシリーズやQEDシリーズの魅力ですね。 四郎の名前についての説は、両シリーズの中でもやや弱いかなぁと感じてしまいましたが(インパクトはあります)、楽しく読みました。 ラストのあたりでは、ちょっと分からないシーンもありましたが…。(2009/02/07読了)
2009.02.09
コメント(0)
-

鷺沢萠『ありがとう。』
鷺沢萠『ありがとう。』~角川文庫、2005年~ 2000年に刊行された『ナグネ・旅の途中 場所とモノと人のエッセイ集』に、単行本未収録エッセイを追加して文庫化された一冊です。『待っていてくれる人』『かわいい子には旅をさせるな』の2冊のエッセイを紹介しましたが、本書はその2冊に比べると厚いです(文庫で320頁弱)。その分、いろんな話にふれられますし、未収録エッセイの部も嬉しいです。 本書は、第1章が「場所」、第2章が「モノ」、第3章が「人」、第4章が「単行本未収録エッセイ」となっています。 ここでは、読みながら付箋を貼った箇所を中心に、興味深かったところについていくつか書いておきます。「砂壁のアパートで」鷺沢さんの、お父様にまつわる思い出です。印象的だった言葉があるので、これは記事の末尾に引用します。「風呂桶の許容量」怒りを爆発させるまでのキャパシティについての話ですが、こちらもふむふむと頷きながら読みました。けっこう、人に注意をするのは気が引けてしまうものですが、我慢しすぎると変な爆発をしてしまうかもしれませんし、上手に注意したり怒りを発散させるのも大事だなぁ、と思います。そうなれば、悲しい事件も減るかもしれませんね。「手鏡事件」鷺沢さんが「手鏡事件」と名付けている、あるオソロシイ話です。…たしかにオソロシイ…。「ケロヨン人形」鷺沢さんのお友達が幼い頃に経験した、ケロヨン人形をめぐる思い出話が中心ですが、「あきらめること」の意味も、それも大事な意味を伝えてくれるエッセイです。こちらも印象深い言葉があるので、記事の末尾で引用します。「長野五輪に思う」長野五輪で活躍した、日本生まれでアメリカ育ちのキョウコ・イナ選手への日本人の反応を見て、これが韓国人と日本人との間だったらまたずいぶん変わっているだろう…と、鷺沢さんが考察されるお話です。米国の在り方と日本の在り方の違いももちろんですが(日本は血統的日本人が大多数ですが、米国は違います)、国どうしの間にある他国への感情などなど…。日本がこれからもきちんと向かい合って、より良い方向にもっていくべき課題の一つですね。「鵄が見守る島」対馬の位置(それは地理的な位置でもあれば、歴史的な位置でもあります)についての考察、興味深く読みました。同時に、ここでは地理的な「壁」、国境などの人為的な要素も含む「壁」、そして人間の心の中の「壁」という風に、いろんな壁についても語られます。じっくり読みたい一編です。「塩と砂糖と魔法の国」先日読んだ『かわいい子には旅をさせるな』所収の「マースーの話」にも記されていたことですが、日本で最近まで塩が専売されていたことと、沖縄は粟国の塩との問題について、この話でも描かれています。不勉強にして私は塩の専売のことを知らず、その質の悪い塩が沖縄の良質の塩を禁じて流通させられたがために起こった問題についても、知りませんでした。「マースーの話」によれば、 1997年まで、(劣悪な)塩の専売は続いた、ということで…。あらためてこの国はどうかしているなぁ、と思います。あ、もちろんいまの政治家の方々が国民のことを考えた政治を行っていてくだされば、現在形で「どうかしている」ではなく「どうかしていた」と書きますが、素人の私から見れば、どうも政治家の方々は自分たちの利権を守ることに必死のようですので…。「寂しい価値観」鷺沢さんの中学校の先生がたが、どうもちょっと寂しい価値観をお持ちだ(った)、という話については、別のエッセイ集でも読んだ覚えもありますが、この話もそうです。自分の学校から偏差値の高い大学へ行く生徒を増やすことばかり考えてしまう、そんな寂しい価値観についての話です。「負け犬のススメ」雑誌編集者やライターも交えながらの、酒井順子さんとの対談です。Lesson1からLesson3まで、そして「負け犬たちの午後」の4編があります。楽しく読みました。 そして、酒井順子さんによる解説。鷺沢さんにとっての旅の意味を書いたあたりなど、そして最後の部分など、涙なしには読めませんでした。酒井さんは、こう書いています(文字色反転)。「ホームにいれば見ずに済むような、と言うよりホームにい続ける人達は見て見ぬフリをし続けるような事実も、アウェイにおいて彼女は直視していました。ですから彼女の旅は決して、楽しいだけのものではなかったはずです」(315頁) 私自身は、インドア派で、めったに旅をしませんし、海外旅行も一度だけ、しかも観光地をふらりとするだけで、なにもその地について分からなかったように思います(日本を新しい目で見ることも、その旅行では特に得られなかったような)。 けれど、たとえばこうして鷺沢さんのエッセイを読み、日本にある問題を知る。それも、一つの勉強になっているのでは、と感じています。 それでは、上でふれていました、印象的だった部分を引用しておきます(文字色反転)。[前略]忘却というやさしい機能がなければ人が生きていくのはひどく難しくなるのだろう。 けれどそれでも、人は、我慢して、努力して、唇に血と滲ませながら「忘れない」ようにしなければならない出来事にときどきぶちあたる。 いろんな「別れ」を経験したけど、すべてキレイな「別れ」だったわ、というようなことを言う人を私は信用しない。血膿のしたたるような思いをどこかに包み隠しながら、それでも平穏に生きようとつとめている人を私は好きだ。 ―「砂壁のアパートで」より「あきらめる」ことは、実は「あきらめない」ことよりずっと辛いことなのではないか、と。「信じずにいる」のも「信じる」よりずっと難しいことなのではないか、と。「あきらめる」や「信じない」選択は、その逆の選択の、何倍もの苦渋を強いられるのではないか、と。[中略] 最後まであきらめるな、あきらめさえしなければ必ず望みは叶うものだ、というようなことを本気で口にする人は、きっと、奥歯を噛みしめて、額に血管を浮かばせながら、それでも「あきらめる」を選択するしかなかった、信じたいのに、信じられればそれほど楽なことはないのに、それでも「信じない」を選択するしかなかった、そういう経験のない人なのではないかと思う。 ―「ケロヨン人形」より(2009/02/04読了)
2009.02.08
コメント(0)
-

横溝正史『死仮面』(春陽文庫版)
横溝正史『死仮面』~春陽文庫、1998年~ 本書の刊行まで、角川文庫版などに収録された『死仮面』は、全ての原稿が見つかっていなかったため、一部を中島河太郎さんが補筆していました。ところが、この春陽文庫版は、その幻の原稿の発見を受けて、完全なかたちで『死仮面』を収録した一冊となっています。ネット古書店でもなかなか見つからなかったのですが、先日(2月1日)に、よくお世話になっているブック・オフさんで発見したのでした。見つけたときは感動のあまりちょっと震えもくるくらいでした。この手のチェーン店ではなく、古本屋で見つけていたならもっと高価になっていたろうと思うと、この出会いを本当に嬉しく思います。 …と、前置きが長くなりましたが、本書には、表題作「死仮面」と、「鴉」が収録されています。「鴉」については、角川文庫『幽霊座』の記事にゆずるとして、ここでは、表題作についてのみ、内容紹介と感想を書いておきます。ーーー 昭和23年(1948年)秋。『八つ墓村』事件を解決した金田一耕助が磯川警部を訪れると、警部は新たに金田一耕助の興味をひく事件を抱えていた。 マーケットの奥の方、人通りの少ないところに、野口慎吾という、人付き合いのない彫刻家の店兼住居があった。そこで、女の腐乱死体が発見された。野口によれば、女の名は山口アケミ。女は、死ぬ間際、自分のデスマスクを作り、ある女性のもとに送ってほしいと言い残したという。その送り先の女性とは、参議院議員で教育家の川島夏代だった。 野口は警察から取り調べを受け、精神鑑定に護送される途中で、逃げてしまったという。 …そして、東京。三角ビルに事務所を構える金田一耕助のもとに、上野里枝という女性が依頼にやってきた。彼女は、川島夏代の妹で、山内君子の姉だという。三人の姓が違うのは、父親が全員違うから。そして、君子というのが、デスマスクをとられた山口アケミと同一人物のようであった。 川島夏代が経営する女学院には、脚の悪い男が現れ、その頃から、夏代の健康状態も悪化していったという。そしてついに、夏代が殺害された…。 女学生の白井澄子の協力を得ながら、金田一耕助は事件の真相に迫る。ーーー …ある事実が判明したとき、衝撃のあまり震えがきました。 本作は、金田一耕助シリーズの中でもかなり重たいです。冒頭から独特の雰囲気があります。 また、金田一シリーズではありますが、ある意味では内容紹介にもふれた白井澄子さんが活躍するのを、金田一さんがフォローするような、そんな感じもあります。いくつかの章は、白井さんを中心人物とした視点で進んでいくからです。 本作は、昭和24年(1949年)と、戦後初期―『本陣殺人事件』や『獄門島』など、充実した作品を発表していた時期―に書かれたこともあってか、トリックも秀逸だと思います。 冒頭でも書きましたけれど、とにかくこの文庫との出会いは感動でした。もちろん内容も面白く、ずっと大切にしたい一冊となりました。*表紙画像は、横溝正史エンサイクロペディアさまからいただきました。(2009/02/01読了)ーーー 本日(2月7日)、やっと新居でネットを接続しました。既にパソコンに向かってだらだらの時間が出始めているので、気をつけていきたいと思います…。 けれど、新居ではテレビも置いてないですしまだ新聞もとっていないので、天気やニュースを把握するためにも、ネットをしない日はなかなかつくりにくくなろうかと思います。せめて、あまりだらだら向かわないように努力ですね。
2009.02.07
コメント(4)
-
「2009年1月の読書記録・小説部門」
今回は、2009年1月に記事を書いた本のリストです。番号は、今年読んだ順番で、印象に残った本には☆マークをつけています。1.森博嗣『夏のレプリカ』2.森博嗣『今はもうない』3.森博嗣『数奇にして模型』4.筒井康隆『邪眼鳥』5.筒井康隆『虚航船団』 ☆6.横溝正史『双仮面』7.森博嗣『有限と微小のパン』8.鷺沢萠『待っていてくれる人』 ☆9.鷺沢萠『かわいい子には旅をさせるな』10.島田荘司『Classical Fantasy Within 第四話 アル・ヴァジャイヴ戦記 決死の千騎行』11.島田荘司『Classical Fantasy Within 第五話 アル・ヴァジャイヴ戦記 ヒュッレム姫の救出』12.島田荘司『Classical Fantasy Within 第六話 アル・ヴァジャイヴ戦記 ポルタトーリの壺』13.島田荘司『Classical Fantasy Within 第七話 アル・ヴァジャイヴ戦記 再生の女神、アイラ』14.森博嗣『地球儀のスライス』~総評~ 1月は14冊の小説・エッセイの感想を書きました。ただし、『Classical Fantasy Within』は、4冊分の感想を一つの記事にまとめています。 ☆は、『虚航船団』と鷺沢さんのエッセイにつけてみました。 『虚航船団』は、文房具たちの性格の詳細な描写と、世界史など、壮大な物語です。 鷺沢さんのエッセイは久々に読みましたが、笑いあり、考えさせられる話ありで、良い読書体験でした。 2月には、新居でインターネットができるようになるはずなので、更新の頻度はいまよりは増やせるかと思います。けれども、ネットに向かうとだらだら時間を過ごしてしまうこともあり、適度にしたいと思っています。
2009.02.01
コメント(2)
-
レオポール・ジェニコ『歴史学の伝統と革新』
レオポール・ジェニコ『歴史学の伝統と革新―ベルギー中世史学による寄与―』(森本芳樹監修/大嶋誠・斎藤絅子・佐藤彰一・丹下栄訳)~九州大学出版会、1984年~ レオポール・ジェニコは、ベルギーの中世史家で、本書でも強調されるとおり、研究にあたってのコンピューターの利用を強調し、そのための共同作業を主導されたり、史料の個々の性格を明確にし、さらなる研究に役立てるべく、「西欧中世史料類型」という叢書を創刊されたり、多くの業績を残しておられます。 森本芳樹先生は日本の、西洋中世農村研究の権威ですね。「所領明細帳」という史料の分析で有名ですが、私は不勉強ながらまだ一冊もそのご著書を読んだことがありません。とまれ、森本先生はルーヴァン大学留学時にジェニコに師事していました。本書は、先生がジェニコを日本に招いて実現されたいくつかの講演をもとにした論集となっています。 本書の構成は以下のとおりです。ーーー凡例著者序文図表一覧第一章 『新しいものと古いもの』―歴史学の方法的進歩について―(大嶋誠訳)第二章 ベルギーにおける中世史研究(丹下栄訳)第三章 中世史学とコンピューター(佐藤彰一訳)第四章 思いつきよりも調査と図表を―ナミュール伯領における慣習法特許状―(斎藤絅子訳)第五章 史料の生命―L・ジェニコによる『ブーローニュ伯の系図』と『フリゼの記念祷設定簿』の研究―(森本芳樹稿)付録I 中世文献史料用語解説付録II ルーヴァン大学コンピューターによる史料処理センター(略称セテドック)関係文献目録付録III 『西欧中世史料類型』の構成と既刊分冊リスト付録IV 『ベルギー農村史センター叢書』付録V ベルギーの中世史関係研究機関リスト監修者あとがき索引(事項、同時代人名、研究者名、学術機関名、地名)地図ーーー まずは第一章から第五章について、簡単に紹介しておきます。 第一章は、自然科学の研究が急速に進歩していくのに対して、歴史学研究は比較的緩慢な進歩である、というところから話が始まります。では、歴史学はどのような発展をたどっており、これからどうあるべきなのか、と。 歴史学は、医学などと同様に定量化の手法を利用し、(偶然性にも作用される)自然科学同様に蓋然性の説明を行う、という面があります。人間の生活全体に関わる問題を対象とすることで、研究の領域は拡大し(食事などの肉体的欲求、権力欲、感情、自然環境との関わりなど…)、史料の扱いも精緻なものとなっていきます。そして、史料を扱うにあたってジェニコが強調するのはコンピューターの利用で、彼は、「私にとっては、コンピューターを採用しない歴史家は、顕微鏡を拒否する生物学者に匹敵する」とさえ言います。 最後にジェニコは、研究方法が新しくなっていくにしても、旧来の方法を排斥するのではなく、豊かにしていくことが重要である、と述べます。 第二章は、ベルギーでの中世史研究について、フランスのそれとドイツのそれと比較史ながら論じています。フランスは、『アナール』に代表される問題意識の斬新さを、ドイツは(史料処理などの)手法の伝統的厳密さを、研究の特徴としています。ベルギーは、両者の性格を併せ持ち、特にドイツのように手法の厳密さを重んじる、と言います。 問題意識については、都市史、農村史、法制史などなどの諸領域についての研究の具体例を列挙しており、もちろん興味深いのですが、第二章の重点は後半、ベルギーでの史料の扱いに置かれています。具体的には、中世の史料目録である『中世ベルギー・ラテン語作者・作品目録』の刊行と、そこに収録された史料をコンピューター処理するための研究センターについて、詳しく紹介されます。そのセンターはルーヴァン大学の史料処理研究センター(Centre de traitement electronique des documents, Universite de Louvain. 通称セテドックCETEDOC)です。 そして、冒頭にもふれました、『西欧中世史料類型』刊行の経緯についてもふれられています。 第三章は、中世史研究にあたってコンピューターを利用する意義を、具体例を挙げながら論じています。 セテドックでは、1200年以前に書かれ、刊行されたすべての文献史料がコンピューターに入力されているといいます。そこで、具体的には、たとえば、ある単語を検索し、その語がつねにどの語と結びついて使われるか、ということを知ることで、その語が中世でどのように用いられていたかがより明確に理解できます。たとえば、"nobilis"(貴族)という語は、つねに"vir"(男)と結びつきますが、"homo"(人)とは結びつかなかったとか。こういう事実が、コンピューターを使えば圧倒的に短い時間で浮かび上がってきます。 これは出力―コンピューター利用の方法―についての話ですが、もう一点、ジェニコは史料を入力する際に注意すべき点を挙げます。それは、そのデータがあらゆる研究者に役立つものでなければ無意味である、ということ。たとえば、ある研究者が、自分が使う史料のある一部分をコンピューターに入力しようと言ったとき、ジェニコは、それはあなたが研究を終えた後には誰の役にも立たなくなるので、史料の全体を入力してほしい、と反駁したとか。 その後は、プログラムのあり方や、さらに、具体的なコンピューター利用の例が紹介されます。 第四章はなかなかどきっとする標題ですが、要は、史料を丁寧に読み、地図や年表にまとめることの重要性を説きます。卒業論文作成時にも、修士論文作成時にも、結局は(簡単にではありますが)地図と年表にまとめながら作業をしたなぁ、と、ふと思い出しました。作業としては正直退屈ですが、年表に整理すればすっきりと自分の研究対象の問題や流れが把握しやすいんですよね。 森本先生が、ジェニコの講演ノートや論文をもとに書かれている第五章は、ジェニコの具体的な研究方法がうかがえる興味深い論文です。ここでは特に、いかにジェニコが丁寧に史料を分析しているかが示されます。ジェニコは、いわゆる「写本」(copie)を、それぞれが独自の価値をもっていることを強調し、「版」(version)と呼ぶべきであろうと言いますが(第二章、53頁)、その具体例ですね。 『ブーローニュの系図』については、その14の写本を詳細に分析し、三つの系統があること、「系図」がなぜ作成され、そしていかなる意味を持ったか、が示されます。 『フリゼ教会の記念祷設定簿』の方は、一つの版に(時代を超えて)様々な手が加えられている史料の分析を通じて、修道院と世俗世界との関わりの変化を論じています。 * これら五章が興味深いのはもちろん、末尾に付された5つの付録も、貴重なデータベースとなっています。特に冒頭でもふれた「西欧中世史料類型」の全体の俯瞰図と、1983*年までの既刊リストは嬉しかったです。私自身は分冊40の『例話』(L'Exemplum)と、分冊81-83の『説教』(The Sermon)に、とてもお世話になっています。大学を離れ、気の赴くままに西洋史関連の文献にふれられるわけですから、またこの叢書のいくつかも読んでみたいと思っています。 ちょっと脱線しましたが、索引もテーマごとに分かれていて検索しやすく、また、本文や註で引かれる外国語の研究も、邦訳のない著書であっても全て原題の意味が日本語で示されていたりと、とても丁寧な作りの本となっています。監修者あとがきでは、この本が生まれることになった背景から紹介されていますが、そこにも、仕事の丁寧さがうかがわれます。 よくいく古本屋に本書が置いてあるのを在学中から知っていて、ずっと気になっていましたが、買うのはやっと今年になってしまいました。それでも、買って、読んで良かったです。ジェニコには『中世の世界』という訳書もあるので(訳は森本先生)、こちらも読んでみたいと思いました。 良い読書体験でした。(2009/01/30読了)
2009.02.01
コメント(0)
-

森博嗣『地球儀のスライス』
森博嗣『地球儀のスライス A SLICE OF TERRESTRIAL GLOBE』~講談社ノベルス、1999年~ 森博嗣さんの第二短編集です。 それでは、それぞれについて簡単にコメントを。ーーー「小鳥の恩返し The Girl Who was Little Bird」 [主要人物]島岡清文、島岡綾子、白坂美帆 [内容紹介]清文が34歳のとき、父親が殺された。事件の日、現場には一羽の小鳥がいて、第一発見者の妻は、小鳥を飼い始めていた。その後は、清文も小鳥の世話をしていたが、ある日、小鳥は逃げていった。 時が経ち、病院に看護師として美帆がやってきた。美帆は、清文に、自分は逃げていった小鳥である、と言う。美帆は有能であったし、清文はそのウィットに感心する程度であった。しかし、次第に美帆に心が傾いていき…。 [コメント]好きなお話です。「片方のピアス A Pair of Hearts」 [主要人物]カオル、トオル、サトル [内容紹介]カオルは、恋人のトオルの双子の弟、サトルと出会い、トオルよりもサトルに惹かれていく。トオルとの結婚も近い時期だった。そして、トオルが海外に行っている間に、事件が起こる。サトルが殺害されたのだった。 [コメント]こちらは、どこか不思議なお話です。「素敵な日記 Our Lovely Diary」 [コメント]こちらも不思議なお話です。日記に記録をつけていく人々が、次々に不可解な状況で死んでいく、というお話。「僕に似た人 Someone Like Me」 [主要人物]俊一、まあ君、まあ君のお母さん [コメント]?、でした。「石塔の屋根飾り Roof-top Ornament of Stone Ratha」 [主要人物]犀川創平、西之園萌絵、諏訪野 [内容紹介]西之園萌絵に招かれて、犀川、喜多、国枝が彼女のマンションを訪れた。西之園の側からは、叔母の佐々木夫人と、愛知県警本部長も出席。その席で、犀川は師、西之園博士が分析した奇妙な事実について問題を出す。石塔と不可分のはずの屋根飾りについての問題。狭い幅の中に、地面で全部つながった5つの石塔があった。それらに屋根飾りはなく、少し離れた地面に、それらの屋根飾りだけが作られていたという。なぜ、五つの石塔と屋根飾りは、そのように作られていたのか。 [コメント]西之園さんが大学四年生の頃の話です。雪の日、ということなので、あるいは『有限と微小のパン』事件の後、年が明けてから(つまり1998年)の話かもしれません。 主要人物の欄にあえて諏訪野さんの名前を挙げたほど、諏訪野さん大活躍です。 謎も魅力的で、S&Mシリーズは短編も面白いですね。「マン島の蒸気鉄道 Isle of Man Classic Steam」 [主要人物]犀川創平、西之園萌絵、諏訪野 [内容紹介]犀川、喜多、大御坊の三人が同じ時期に英国付近にいたこともあり、西之園萌絵の招待で、彼らはマン島を訪れる。ここには、佐々木夫人と諏訪野もやって来ていた。今回の謎は、マン島のシンボルの三本脚についての話になったとき、脚が逆向きになっている写真があると、諏訪野が紹介してくれる写真。 [コメント]再読ということもあってか、写真の方の謎は答えが分かったのですが、それとは別のターンテーブルの問題の答えが分からないままです…。それはともれ、今回は西之園さんが大学院生になってからの話。何年のことかは書かれていませんが、なんとなく、先と同じく1998年のことかな、と想像します。「有限要素魔法 Finite Element Magic」 [コメント]こちらも「僕に似た人」同じく、?でした。「河童 Kappa」 [主要人物]日下部淳哉、其志郎、亜依子 [内容紹介]大学を中退した日下部淳哉が寂れた農村に住んでいた頃の話。友人の其志郎が訪れるとき、下宿先の娘、亜依子がお茶を持ってきてくれた。彼女は其志郎に思いを寄せているようであったが、其志郎は冷たい。ある日、其志郎がいないときに、亜依子が淳哉のもとを訪れてきて…。 [コメント]ホラーテイストの作品です。こういうのも好きです。「気さくなお人形、19歳 Friendly Doll, 19」 [主要人物]小鳥遊練無、纐纈[こうけつ]、香具山紫子 [内容紹介]バイトに出かけていた練無に、大柄の男が声をかけてきた。そして、男の主人、纐纈老人が練無にバイトを依頼する。内容は、週に数時間、一緒に遊ぶこと。かなり高額の時給に怪しむ練無だが、結局バイトを引き受ける。続けている内に、練無は、自分が纐纈老人の既に亡くなったという孫娘に似ていることを知る。 [コメント]Vシリーズの主要人物たち初登場の作品です。おぼろげに覚えていましたが、良いですね。根来機千瑛さんの名前もあり、懐かしくなりました。2月からはいよいよVシリーズ再読となると思います。「僕は秋子に借りがある I'm in Debt to Akiko」 [主要人物]木元、秋子 [内容紹介]木元が食堂で食事をしていたら、「壊れている」感じの女子学生に声をかけられた。それが、秋子との出会いだった。近づきたくない、と思いながら、どこか彼女にひきつけられ、一緒に過ごした。後日、朝早くに秋子から連絡が入り、ともに出かけることがあった。他愛のない話ばかりだった。木元が、姉が死んだ話をすると、秋子は自分にも兄がいたが死んでしまったという。秋子の母が何度も聞いているという、形見のテープ。秋子が重そうに抱えている雑誌。秋子の話は全て嘘かも知れない、と考えながら、木元は彼女に、自分でも思いがけない一言を発していた。 [コメント]なんというか、森さんの短編集は、まるで音楽のアルバムのように、いろんな味わいの短編を収めていると思います。本書でいえば、不思議な話、ホラータッチの話、ミステリ色の強いS&Mシリーズ短編、そして、音楽でたとえればバラードのような本編…。 味わい深い物語です。ーーー 何度目かの再読ですが、楽しく読めました。 コメントで?をつけた2編は、書き下ろしだそうです。なんとなく、なるほど、と思いました。 上にも書きましたが、2月からはVシリーズ再読に挑戦となると思います。S&Mシリーズの再読を始める前までは、既刊作品の多さに、再読をためらっていたのですが、早く読まなきゃと慌てることもなく、楽しく読み進められていて良かったです。 それでは、一つだけ、印象に残っている一節を引用しておきます(文字色反転)。「許して下さい」と言い続ける人間が、世の中に存在することを、僕は初めて信じた。 ―「僕は秋子に借りがある」より(2009/01/27読了)
2009.02.01
コメント(2)
-

島田荘司『Classical Fantasy Within』第四話~第七話
島田荘司『Classical Fantasy Within 第四話 アル・ヴァジャイヴ戦記 決死の千騎行』島田荘司『Classical Fantasy Within 第五話 アル・ヴァジャイヴ戦記 ヒュッレム姫の救出』島田荘司『Classical Fantasy Within 第六話 アル・ヴァジャイヴ戦記 ポルタトーリの壺』島田荘司『Classical Fantasy Within 第七話 アル・ヴァジャイヴ戦記 再生の女神、アイラ』~講談社BOX、2008-2009年~ 2008年10月に再開した、島田荘司さんによる大河ノベル『『Classical Fantasy Within』、その第二部が2009年1月に完結しました。これを機に、二部の全4巻(第四話~第七話)を一気に読んだので、まとめて一つの記事とします。 ちなみに、第三部の再開は2009年9月になるそうです。 さて、4巻まとめての感想ということで、全体を通して読んでいない方には興ざめになる部分もあろうかと思います。数行空けてから記事を書きますので、興ざめがいやな方はお気を付けください。ーーー 千の塔の街と呼ばれた美しい都、サラディーン。しかし、大地震、隕石、ペストの流行により、街はもはや荒廃していた。雹の降る冷たい朝、ショーン・マスードは、王室守備隊の全体集会に召集された。そこでは、司祭から、サラディーンを救う唯一の方法が伝えられる。神託により知ったというその方法は、五日間で、地上で最悪の土地といわれるアル・ヴァジャイヴを横断し、さらには紅海も越えて、イスラエルの地へ行き、降り立った月の中にいる女神と出会うこと―。明らかに無謀なその方法だが、神託によれば、完全に不可能ということでもない、という。きわめて過酷ながら、国を救う可能性のために、千人の騎士たちが、アル・ヴァジャイヴへと向かった―。 酸を吐く竜たちに、一隊の大部分はやられてしまった。残った十数名は、ショーンを中心に進んでいく。 サラディーンは、アル・ヴァジャイヴの地に三つの要塞を築いていた。砦からサラディーンに戻ってくる者はもはやいなかったが、砦では彼らを助けてくれるであろうはずだった。 第一の砦では、彼らはあつくもてなされた。ショーンたちを引き留める者は多かったが、ショーンたちは先を急ぐ。しかし、ここで新たな仲間が加わることになる。第一の砦、ブーシェフル一の踊り子、サミラだった。 さらに、恐ろしい翼手竜や蛮族たちの襲撃を乗り越えながら、一行は第二、第三の砦をなんとか経由しながら、イスラエルに向かっていく。そしてそのためには、ポルタトーリの壺にまつわる謎の暗号も解かなければならなかった。ーーー かなり唐突な始まり方、唐突な終わり方、という印象です。第二部自体は完結のようですが、CFW自体は未完結なので、今後、このもどかしさが解かれるのを楽しみにしたいと思います。島田さんによれば、第一部、第二部など、一見なんのつながりもなさそうで、最後には大きなミステリだったことが分かる、とのことですが、どうなるのでしょう??上にも書きましたが、第三部からの再開はしばらく先になるようですが、楽しみですね。 第二部は、ある意味では吉敷竹史シリーズや御手洗潔シリーズにも共通しますが、女性が特別な意味を持っているように思います。サミラにヒュッレム姫、そしてショーンたちの目的は月の女神と結ばれることです。 かっこよかったショーンにも、終盤では「ん?」となってしまいましたが、そこはそれ。上にも書きましたように、唐突な始まりではありますが、物語にどんどん引き込まれる感じでした。この手の、いかにもファンタジーといった物語はほとんど読んだことがありませんが、どこかRPG風ですね。 楽しかった、というよりも、先への楽しみがますますふくらんだ感じです。(2009/01/25読了)
2009.02.01
コメント(0)
全21件 (21件中 1-21件目)
1










