2009年10月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-

山内昶『タブーの謎を解く―食と性の文化学』
山内昶『タブーの謎を解く―食と性の文化学』~ちくま新書、1996年~ 読みやすい文体でつづられた、タブーを中心に扱った文化人類学の入門書、といったところでしょうか。副題のとおり、タブーの中心となり、またそれぞれが通じ合っている食と性に焦点があてられています。 本書の構成はつぎのとおりです。ーーープロローグ第1章 奇妙奇天烈な文化装置 一 ヒト、この雑食動物(オムニヴォラ) 二 ヒト、この好色動物(エロトマニア)第2章 その肉を食うな 一 宗教のせいか 二 功利のためか 三 親愛のゆえか第3章 その人とセックスするな 一 生物学的説明 二 心理学的解明 三 社会学的究明第4章 タブーの文化象徴論 一 カオスとコスモス 二 リーチの文化記号論第5章 タブーの暗号解読(デコード) 一 世にも奇怪な『聖書』のタブー 二 世にも珍妙な日本のタブー第6章 タブーの弁証法 一 外食制と外婚制 二 タブーの侵犯 三 ユートピア幻想エピローグーーー こうしてあらためて構成を見てみると、見出しの付け方が凝っていますね。第2章では「せいか」「ためか」「ゆえか」と3通りの言い方を使い分け、第3章も「説明」「解明」「究明」となっています。こういうところも勉強になりますね。 さて、内容の方ですが、第1章で、人間は本来なんでも食べるし、誰とでも性交渉できることを挙げ、しかし、実際には多くのタブーが設けられていることを示すことで、これを問題提起とします。なぜ多くのタブーが設けられているのか? この章では、人間に近いサルやチンパンジーの生態を、人間との比較のために描いています。サルなどにも禁忌は見られますが、しかし人間のそれは、サルのものとは違っているようで…。 本書で挙げられるタブーを全て示すことはできませんが、特に大きく扱われているのが、食の領域ではなぜペット(とされている動物、犬や猫など)を食べないのか、性の領域ではなぜ近親者とはセックスしないのか、ということです。 第2章と第3章と、食と性それぞれの領域のタブーについて、旧来の説明のあり方を紹介し、しかしそれらが不十分であることを示します。これらの問題を解決する答えがあることを示唆しながら、それぞれに割合説得的な部分がある諸説を批判していく過程で、次章以降への期待は高まります。 さて、私は文化人類学には疎いですが、第4章が、本書のひとつの山場になるのかな、と思います。食と性と、その領域は違えど、タブーには共通する性格がある、というのですね。それを示す説として著者が強調するのが、ターナーが提起したリーメン(境界)論、そしてリーチによる文化記号論です。私たちは、内と外、上と下などなど、世界を二分法的に見る傾向がありますが、しかしそれぞれ二つに分けられるもののあいだには、どちらにも属さず、同時にどちらにも属する線があります。たとえば、隣り合ったある部屋Aと別の部屋Bのあいだにある敷居がそうですね。そして、このようなどちらにも属さない領域(リーメン)によって、タブーが説明できる、というのですね。 第5章は、第4章でみたタブーの解読格子を使って、聖書などに描かれた多くのタブーの説明を試みます。 第6章は、第1節で交換の形態について見て、第2節で、このように多くのタブーが設けられているにもかかわらず、タブーをあえて侵犯する時期(祭り)があることについて論じます。 境界がタブーになる、というのはとても説得的で、以前読んだことのある、同じく境界の象徴性について論じた赤松憲雄『異人論序説』を連想しました。…が、それがあらゆるタブーに適応できるのか、または境界にありながらタブーとされない事例はないのか、といったところが気になってしまいます。たとえば、ウサギはペットして飼われることもあります。本書では、ペットは、動物と人間の境界にある存在ということで、食タブーになる存在、ということになっています。ところが、現在日本でウサギを食べるのは、特にタブーではないですよね。とても細かい指摘なのですが、なぜ犬(もはやペットの定番)は食べずに、小学校でも飼っているウサギは食べて良いのか。 食(あるいは動物)に関するタブーについては、ミシェル・パストゥローが展開している象徴という考え方もとても説得的で(たとえば、豚に関する論考)、個人的な印象としては、境界という大きな枠組み(一般論)を設けるのも重要ですが、結局は個別の事例を検討していく方が重要なのかな、と感じてしまいました。ただし、象徴の歴史という視点でいけば、近親者との性交渉がタブーとなっていることは説明しがたいとも思いますし…。 と、ちょっとひっかかったとはいえ、上に書いたことは単なる印象論です。本書は、全体としてとても興味深く読むことができました。ひとつ面白かったのは、人類が火を使って料理をするようになったことが、動物的な人間が真に人間的な存在になるきっかけだった、という説です。火を通さないかたい食べ物を食べていると、顎や咀嚼筋が重要なウェイトをもちますので、その分脳が発達する余裕がありません。ところが、火を通した柔らかい食べ物を食べるようになって、顎などの筋力を低下させ、脳の発達や咽喉部の発声器官を発達させることができた、というのですね。 このような興味深い指摘や説の紹介も多々あり、面白い1冊でした。(2009/10/22読了)
2009.10.26
コメント(0)
-
筒井康隆『虚航船団の逆襲』
筒井康隆『虚航船団の逆襲』~中公文庫、1988年~ 筒井康隆さんのエッセイ集です。 最近ばたばたしていて、読了から感想を書くまでに時間があいてしまったので、いつにもましてとりとめのない記事になりそうですが…。 本書は、大きく次の4つのパートに分かれます(連番は便宜的に付しました)。1部.「悪意」への期待2部.現実と超現実の居心地よい同居3部.座長口上4部.虚航船団の逆襲 1部が日常的なエッセイ、2部が書評集、3部が座長をつとめた頃の、大一座に関する文章集、4部が『虚航船団』についての書評への反論がメインとなっています。 1部では、「学歴偏重時代」という風刺色の強いエッセイが好みです。特に、「ぼくが不思議でしかたがないのは、塾へやる金があればどうして学校をもっとよくしようという方に金を使わないのか、どうしてそういう方向に母親たちの頭が働かないのかということである」という一文は痛快でした。 そしてとても興味深かったのは、「辞書の馬鹿げた利用法」というエッセイです。『翻訳の世界』という書物に、「辞書での遊び方」というテーマで書かれた文章だそうですが、この中で筒井さんは「等」を使った都々逸を作っていらっしゃいます。辞書をぱっと開いたページに出てきた言葉で遊んでみる、という文脈で出てくるのですが、この都々逸が面白いのです。そして、「これくらいのことがすらすらできなければ文章のプロではない。特に翻訳家には欠かせぬ能力であろう」とおっしゃっています。私は職業にしているわけではありませんが、訳を作りながら読み進めている外国語文献もあります。そのなかで、自分の語彙のなさを痛感しているのですが、この一節を読んで、あらためてその思いを強くしました。ですが、訓練あるのみ、ですね。 2部では、筒井さんのいろんな書評を読んできた中で気になっている南米の作家たちに、あらためて興味がそそられます。 3部では、役者としての筒井さんの活躍にふれられます。筒井さんは小説もものすごいですが、舞台もものすごいのだろうなぁと思わされます。 4部での、書評への逆襲もとても痛快でした。そして同時に、私もブログというかたちで本の感想や紹介を書いているわけで、自分のスタンスのあり方についても考えさせられました。基本的に作品への批判的なことは書かないことをモットーにしていますが、ときには書いてしまうこともありますから…。 そんなこんなで、全体的に興味深く読めた1冊です。(2009/10/14読了)
2009.10.21
コメント(0)
-
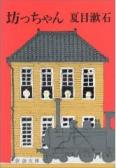
夏目漱石『坊っちゃん』
夏目漱石『坊っちゃん』~~新潮文庫、1995年105刷(1950年初版)~ 大好きな作品です。今回何度目かの再読をしました。 親譲りの無鉄砲で子供の頃から損ばかりしている―。そんな「おれ」が、勢いで学校を出て、四国のある村の中学校に赴任することになります。 同じ数学の山嵐とはウマがあいそうだと思いながら、ある出来事をきっかけにケンカになってしまい、どうも話せなくなったり。教頭の赤シャツは割合良い奴かもしれないと思ったものの、やはりいやな奴だと分かったり。 生徒にもいたずら、嫌がらせをされ、何度となく東京へ帰ろうと思いながら過ごす日々が描かれています。 なんといっても勧善懲悪が痛快です。この主人公くらい真っ直ぐな人が多ければ、世の中こんな悲しいことも少ないだろうに…と思ってしまいます。主人公も子供の頃はいたずらっ子ですが、しかし彼はきちんと謝ることを知っています。悪いことをしてへらへらとそれから逃れようとする、生徒たちや赤シャツ、野だのような人たちがとても対照的ですが、しかし現実にはこういう人たちも多々いて。 ちょっと思ったのは、同じ勧善懲悪でも、水戸黄門などのような時代劇とはさっぱり違うこと(これほどの作品と時代劇を比べること自体不遜ですが…)。 何が言いたいかというと、主人公が、果たして赤シャツは悪い奴なのかどうかと悩むシーンがあることです。時代劇では、悪代官は徹底的に悪ですが、たとえば女中さんが何かで困っているときにすっと代官さんが助けたり、あるいは(まずないのでしょうが)町人に優しい言葉をかけたり、というシーンが少しでもあれば、どれだけ越後屋さんと悪だくみをしていても、ずいぶん印象が変わってくるだろう、ということ。 赤シャツはずるい人間ですし、この物語の終わり方を思うに(解説も参考にさせてもらいましたが)、今後もずるい人間のままかもしれません。けれども、懲らしめようと心を決める前に、主人公はじっくり考えています。なんだか今回は、そのシーンが印象に残ったので、とりとめがなくなりましたがちょっと書いてみました。 痛快といえば、終盤の卵のシーンが大好きです。 そして今回、あらためて物語のなかで清さんが果たす役割の大きさに感動しました。 好きなシーンはたくさんありますが、今回ふせんを貼ったところを、文字色を変えて掲げておきます。「考えてみると世間の大部分の人はわるくなる事を奨励している様に思う。わるくならなければ社会に成功はしないものと信じているらしい。たまに正直な純粋な人を見ると、坊っちゃんだの小僧だのと難癖をつけて軽蔑する。それじゃ小学校や中学校で嘘をつくな、正直にしろと倫理の先生が教えない方がいい。いっそ思い切って学校で嘘をつく方法とか、人を信じない術とか、人を乗せる策を教授する方が、世の為にも当人の為にもなるだろう。赤シャツがホホホホと笑ったのは、おれの単純なのを笑ったのだ。単純や真率が笑われる世の中じゃ仕様がない。清はこんな時に決して笑った事はない。大に感心して聞いたもんだ。清の方が赤シャツより余っ程上等だ」(51頁) 100年以上も前に書かれた(注:坊っちゃんは1906年に書かれたそうです)社会批判が、現代にもそのまま通用すると思うと、人間の進歩のなさを感じると同時に、なんだか悲しくなってきますね…。(2009/10/12読了)
2009.10.16
コメント(2)
-

北山猛邦『「クロック城」殺人事件』
北山猛邦『「クロック城」殺人事件』~講談社ノベルス、2002年~ 第24回メフィスト賞受賞作、北山猛邦さんのデビュー作です。 簡単な内容紹介と感想を。ーーー 1999年9月。世界は終わりを迎えようとしていた―。 * ボーガンで、<ゲシュタルトの欠片>を打ち消す能力をもつ探偵の南深騎のもとに、若い女性の依頼人が訪れた。 『クロック城』から抜け出してきた彼女は、その城の当主・黒鴣博士の娘で、黒鴣瑠華と名乗った。『クロック城』の地下室に、顔が浮き出ているという。そして、城にいる<スキップマン>と呼ばれる化け物を倒して欲しいというのが、その依頼内容だった。 深騎は、幼なじみの奈美とともに、『クロック城』を訪れる。 城の正面には、巨大な三つの時計がかかっている。真ん中の時計は現在の時間を、左側の時計は10分前の過去を、右側の時計は10分後の未来の時間を、それぞれ刻んでいた。 内部は3つの棟に隔てられており、それぞれ『過去の館』『現在の館』『未来の館』と呼ばれていた。それぞれの館に移動するには、『現在の館』の1階ロビーを通らなければならない。 ところが、深騎たちの滞在中に、『過去の館』『未来の館』それぞれで殺人事件が起き、それぞれの遺体から切断された首は、『現在の館』最上階の部屋に置かれていた。眠り続ける美女、未音の部屋に…。 そして『現在の館』ロビーには常に人の目があったため、事件はいわば密室事件の様相を呈していた。ーーー 正直、なんとも読み進めにくかったです。惹きつけられる感じがあまりありませんでした。 世界の終末に加え、それを食い止めようとする二つの組織の抗争など、SF的設定ももつミステリです。 割合うーん…と思う部分もあったのですが、解明の中で、奇抜で新鮮な部分があったので、そこが良かったです。(2009/10/12読了)
2009.10.15
コメント(1)
-

壺井栄『二十四の瞳』
壺井栄『二十四の瞳』~新潮文庫、1998年77刷(1957年初版)~ 名作です。 簡単に内容紹介を書いたうえで、感想を。ーーー 瀬戸内海沿いのある村の分校に、一人の女の先生がやって来ます。その分校では、年配の男性教師と、若い女性教師が勤めるのが長い習慣になっていて、このたび、新しい女性教師が赴任してきたのでした。 ところが村の人々や子どもたちは彼女にびっくりします。綺麗な洋服を着て、颯爽と自転車で通勤してきた先生― それが、大石久子先生でした。 大石先生は、12人の1年生のクラスの受け持ちになります。最初は村の人からも悪く言われることがあるのですが、ある事件をきっかけに、彼女は村にとって大切な先生となるのでした。 そして、時は流れ…。彼女が最初に受け持った子どもたちが5年生になり、本校に通うようになり、そして、戦争を経て、戦後へ…。 大石先生と12人の子どもたちを描く名作です。ーーー 今回再読なのですが、読む前から絶対泣く!と分かって読み始めて、終盤ではもう涙をとどめられませんでした。 戦争前の平和の時代から始まり、苦しい戦争の時代を経て、まだ苦しみの去りきらない戦後の時代へ…大石先生も物語のなかで20歳以上の年齢を重ねることになります。解説にもありますが、時代柄、重たくて苦しい物語にもなりえるでしょう。ところが、本作は―もちろん何度も悲しい思いになりますが―、その根幹はとても暖かくて、優しいのです。大石先生の明るい人柄も、もちろんその大きな理由のひとつでしょう。 今後もときには読み返したい、素敵な物語です。(2009/10/12読了)
2009.10.14
コメント(0)
-

川端康成『伊豆の踊子』
川端康成『伊豆の踊子』~新潮文庫、1999年123刷(1950年初版)~ 4編の短編が収録された短編集です。 いつものような内容紹介のかたちではなくて、つらつらとそれぞれについて簡単にコメントを。「伊豆の踊子」 学生の「私」が、旅先で、旅芸人の一行と出会い、その中の踊子に思いを寄せていきます。嫉妬のような感情も抱きますが、しかしそれは、恋心ともまた違うようにも感じました。 一行と数日を過ごした後の、船の中での少年との会話(それぞれほんの一言ずつしか書かれていませんが)を、この感想を書くにあたってぱらっと見てみたのですが、じぃんときてしまいました。一行と過ごした時間の濃さ、「私」が彼らに―もっといえば、踊子に―抱く思いの強さが、ひしひしと感じられます。 あまりに有名な話でありながら、数年前に初めて読んで、しかもあまり内容を覚えられないという有様ですが、しかし今、今の自分なりに、味わいながら読むことができました。「温泉宿」 これは…なんとも分からない物語でした。独特の文体で、ある宿で働く何人かの女たちの生き方や行動がとりとめもなく(?)描かれているような…。「抒情歌」 亡くなった昔の恋人へ、「私」が語りかけます。 「私」は、子どもの頃は神童と言われていましたが、それはその不思議な能力のためでした。まだひらがなも百人一首も覚えていないのに、かるた取りでは正解の札を手に取り、捜し物を見つけ、さらには未来も予知する力がありました。 そんな彼女が恋人と出会い、過ごしたシーンの回想では、二人の心がいかに通じていたかが描かれます。なかでも、「私」の母親が亡くなったときの二人の描写が印象的でした。 ところが…。あらすじ的なことはここまでにしておきましょう。 仏教の経典や、キリスト教、ギリシア神話などのこの世とあの世のあり方、死者のあり方、輪廻の存在などなどを、「私」が考え、死者に語っていくその内容を、興味深く読みました。 最後に、印象的だった一節を引いておきます(文字色反転)。「私が今夜あなたにものいいかかける言葉もおかしなことだらけのようですけれど、でも考えてみますと、私は幾千年もの間に幾千万の、また幾億の人間が夢みたり願ったりいたしましたことばかりを言っているのでありまして、私はちょうど人間の涙の一粒のような象徴抒情詩として、この世に生まれた女かと思われます」(113頁)「禽獣」 多くの動物たちを飼って暮らす、四十歳近い独身男性が主人公です。彼の、動物たちとのふれあい(?)が多く描かれる中で、一人の女性の思い出、あるいは現在の彼女への思いも、本作の大きなテーマの一つとなっています。 …あまり十分には分からず、味わいきれなかった感がありますが…。 先日も芥川龍之介を読みましたし、いわゆる近代文学も少しずつでも読んでいこうかなぁと思います。分からない部分もありますが、教養にもなりますし、単純に味わい深い部分も多くあるでしょうし。以前『雪国』を読んだときも、ものすごく面白かったですし、やはり名の残る作品は面白いでしょうから。(2009/10/10読了)
2009.10.13
コメント(2)
-

秋月涼介『紅玉の火蜥蜴』
秋月涼介『紅玉の火蜥蜴』~講談社ノベルス、2004年~ 秋月さんの第3作で、デビュー作『月長石の魔犬』に続く風桜青紫シリーズ第2弾です。 それでは、内容紹介と感想を。ーーー 火に魅せられた「私」は、この街を火で浄化することを決意する。 * 犬首事件と時を同じくして起こっていた連続放火事件のなかでも、奇妙な殺人事件が起こっていた。手足を縛られ、生きたまま焼き殺された寺の住職の遺体が、女性のものだったのだ。 事件に興味をもった鴻薙冴葉警視は、梅崎に補佐されながら、また犬首事件で知り合った風桜青紫の助力を求めながら、捜査にあたっていく(あるいは、捜査をかき乱す)。 過去の火災現場で、少年を見殺しにした消防士。母親が焼死していく状況を目にした人々。そして、事件関係者の人々がもつ、事件の中で殺害された金融業者との関わり…。 繰り返される連続放火と殺人事件に、冴葉のみならず、外科医の嘉神も自らの関心から関わっていき…。ーーー 第1作に比べ分量もありますが、その分内容も濃いものとなっています。 章ごとに視点が変わるのですが、それぞれの立場や心情、過去のしがらみが割合丁寧に描かれていて、狭義のミステリにとらわれない、物語としても楽しめました。 特に、消防士の柏木さんと神崎さんが描かれたパートが面白かったです。最後に二人が活躍する章ではぞくぞくしました。 一点、気になった点もあります。ちょっと文字色反転。<ここから>それは、遊佐警部補と梅崎さんの対決(?)のシーンが物語の中で果たしている役割が、結局あいまいになってしまっているように思われることです。あの章は、単にサスペンスフルな雰囲気を加えるだけの役割だったのでしょうか。それとも、今後のシリーズの伏線として生きてくるのでしょうか。後者なら今後に期待ですが、そうでなければ、その部分も真相解明の中に読み込まれていれば良かったのでは、と思いました<ここまで>。 風桜さんが語る寓話(今回は怪談ですが)も、お約束のような場面でありながら、このシリーズでの楽しみな一幕です。 楽しみといえば、今回も居酒屋のシーンでおなかが空いてきてしまいました(笑) シリーズになれてきたこともあるのか、第1作よりも味わいながら読めました。(2009/10/10読了)
2009.10.12
コメント(0)
-

森博嗣『森博嗣のミステリィ工作室』
森博嗣『森博嗣のミステリィ工作室』~講談社文庫、2001年~ S&Mシリーズ完結後に発表された、森博嗣さん初のエッセイ(?)集です。 まずは本書の構成を掲げたうえで、全体の感想を。ーーー第1部 森博嗣のルーツ・ミステリィ100第2部 いまさら自作を語る第3部 森博嗣の多重な横顔 第1章 建築学科助教授の顔 第2章 漫画人の顔 第3章 趣味人の顔 第4章 ミステリィ作家の顔あとがき文庫化にあたって解説 杉江松恋INDEXーーー 3部構成になっていますが、すべての部が興味深いです。 まず第1部は、森博嗣さんのミステリ(というか、漫画や小説の創作)に影響を与えた100冊の本を紹介します。過半数が海外ミステリで、私はほとんど海外ミステリを読まないので、参考にしたいと思います。筒井康隆さんの作品も二作紹介されていて、どちらも既読ですが、森さんの感想を興味深く読みました。 そういえば、ポーのオーギュスト・デュパンが「シリーズ探偵の元祖」という指摘も、そういえば!と思いました。シリーズ探偵の存在はいまや当たり前になっていますが、それがいわゆるミステリの誕生とともに生まれていたということが興味深いですね。 第2部は、S&Mシリーズと2作の短編集のあとがきです。森さんはご自身の作品にあとがきを書かれませんが、私はあとがきも好きなタイプの読者なので、こういう企画は嬉しいですね。 第3部では、森博嗣さんの短編漫画が読めるのが嬉しいです。第1部の100冊の中にも何冊か詩集がありますが、森さんの作品にはいつも詩がありますよね。それが漫画作品でも感じられました。ふだんは読まないタイプの作品ですが、ふしぎな味わいです。 森茉莉探偵事務所のシリーズはただ楽しく読めます。 森博嗣さんファンには嬉しい1冊です。(2009/10/09読了)
2009.10.11
コメント(0)
-
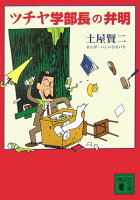
土屋賢二『ツチヤ学部長の弁明』
土屋賢二『ツチヤ学部長の弁明』~講談社文庫、2006年~ 土屋先生がお茶の水女子大学の文教育学部の学部長をつとめていらした間に発表されたエッセイを集めた一冊です。 学部長としての講演やHPへの言葉など、こういう文章を書かれる方が学部長で、しかも授業を受けられるなんてわくわくするだろうなぁと感じさせられます。 本書の中でいちばん興味深かったのは、いしいひさいちさんの作品『現代思想の遭難者たち』を評する「哲学をオチョクる方法」です。いしいさんが描いた哲学者に関する4コマ漫画の中からいくつかを選んで、評していくのですが、有名な思想家・哲学者たちのエッセンスに楽しくふれられる内容となっています。逆に、エッセンスが楽しめるまでに描かれているということは、これらの思想家たちの思想を的確に理解していることが前提となっているわけで、そのすごさも痛感しつつ、内容も興味深い一編です。 また、本書にはいしいひさいちさんの4コマ漫画がいくつか掲載されていて、そちらもとても楽しめます(ちなみに、いしいひさいちさんも土屋賢二先生も、岡山県は玉野市の出身でいらっしゃいます)。 本書はいろんな媒体に掲載されたエッセイを集めていることもあり、内容的にもバラエティに富んでいるような印象があります。その他のユーモアエッセイ集と同じく、楽しく読めました。(2009/10/05読了)
2009.10.10
コメント(0)
-
芥川龍之介『蜘蛛の糸・杜子春』
芥川龍之介『蜘蛛の糸・杜子春』~新潮文庫、1994年53刷(1968年初版)~ 少年向けの作品10編を収めた短編集です。 では、それぞれについて簡単に内容紹介を書いた上で、感想を。(なお、どんなストーリーだったかの自分用のメモの意味も込めているため、簡単な流れも書いています。オチまでは書いていませんのでご安心ください) ーーー「蜘蛛の糸」地獄に落ちた大泥棒のカンダタは、生前、蜘蛛の命を救ったことがありました。それに免じて彼を地獄から救い出そうとしたお釈迦様は、一本の蜘蛛の糸を、地獄にいるカンダタのもとへと垂らします。カンダタは夢中で糸を上っていきますが、彼の後から、幾人もの人々が糸を上ってくるのでした…。「犬と笛」笛の上手な木こりの髪長彦は、その笛の音のお礼として、山の3人の神々から、嗅げ、飛べ、噛め、の3匹の犬をもらいます。さて、数日後、彼は侍たちに出会います。侍たちは、さらわれたお姫様の救出に向かっているといいます。その話を聞いた髪長彦は、3匹の犬たちの協力を得て、お姫さまの救出に行くのですが…。「蜜柑」汽車に乗っている私の向かいに、みすぼらしい少女が座ってきます。彼女を疎ましく私ですが、彼女が必死に電車の窓を開けて、あることをする姿を見て、気持ちにも変化が起こってくるのでした。「魔術」マテイラム・ミスラ君に魔術を見せてもらった私は、魔術を教えてほしいと頼みます。ミスラ君は、決して欲を起こしてはいけないということを条件に、魔術を教えてくれるのですが…。「杜子春」唐の都、洛陽に住む杜子春という若者の前に、ある老人が現れます。貧しい杜子春は、老人の助言によって、一夜にして金持ちになります。彼のもとには多くの人が集まるようになりますが、しかし、再び貧しくなったとき、誰も彼を相手にしなくなりました。そこで彼は、仙人になることを希望します。老人はそれをかなえる条件として、老人が出かけているあいだに、一切口をきかないよう告げるのですが…。「アグニの神」インド人のお婆さんのもとにとらわれた少女は、アグニの神の口寄せをさせられていました。日本人の書生が少女を救いに行きますが、少女はお婆さんのもとを逃れるためにある作戦を立てていることを、書生に伝えます。しかし、お婆さんの呪術の前に、少女はいつものように眠りに誘われてしまい…。「トロッコ」良平が8歳の頃のこと―。鉄道敷設工事が始まり、そこで使われているトロッコに、彼は興味をもちます。ある日、トロッコで作業をしている人の良さそうな男に声をかけ、良平はトロッコを押したり乗ったり、楽しい時間を過ごすのですが…。「仙人」口入れ(職業斡旋所)に、仙人になりたいとやって来た男がいました。口入れの主人は困って医師に相談します。すると、医師の妻が、自分のところに来させなさいといいます。20年働けば仙人になる術を教えてあげると言われた男は、ただひたすらに働くのですが、はたして医師の妻の思惑は…。「猿蟹合戦」蟹たちが猿をやっつけた後の、後日譚です。それは、なんとも生々しい現実で…。「白」犬の白は、隣の家の犬の黒が犬殺しにやられるのを見ながら、その場を逃げてしまいました。ほうほうの体で家に戻った白は、しかし家の子どもたちから攻撃されます。白は、体が黒くなってしまっていたのでした。家を追われた白の物語です。ーーー 久々の再読ですが、楽しく読めました。少年向けの作品が多いということで、読みやすくもあります。 私は、表題作の一つ「杜子春」がとても楽しめたのですが、解説には、「『蜘蛛の糸』に次ぐ名作である」とあります。解説にとらわれずにいきましょう。もちろん「蜘蛛の糸」も面白いです。 その他、「白」が好きなタイプの物語です。 「猿蟹合戦」は、ちょっとあんまりな…。「しょせんは気楽な戯作である」という解説の言葉にうなづきました。 「トロッコ」も少年向けのお話なのでしょうけれど、「蜜柑」と同じく、深みのある物語だと感じました。 なにはともあれ、どの作品も楽しめました。短い話ばかりということもあり、気楽に読める作品集です。(2009/10/04読了)
2009.10.09
コメント(3)
-

秋月涼介『迷宮学事件』
秋月涼介『迷宮学事件』~講談社ノベルス、2002年~ 秋月涼介さんの第二長編です。ノンシリーズ作品です。こちらも、先日紹介した佐藤友哉さんの『クリスマス・テロル』と同じく、密室本のかたちで刊行されました。 それでは、内容紹介と感想を。ーーー 7年前に起こり、迷宮入りになった事件がある―。 若槻恭太郎が下宿している北龍館のオーナー、北条霞美は、下宿者たちを呼び集め、そんな話を始めた。有名な建築家、東間真介の建てたその屋敷は、迷路のようになっていて、地下には迷宮があるという。屋敷では、真介の妻が首を切断されて絶命されており、密室状態になった迷宮の中心には、赤子の死体があったという。一部の週刊誌などでは、左手を失い、再生を願っていつも迷宮に入っていた真介が、赤子になって発見された、などという荒唐無稽な話まで作られているようだった。 霞美はその行動力から、事件関係者にアポをとり、関係者に話を聞いてまわるとともに、その屋敷の見学をさせてもらうという。そして、そこに下宿者たちも同行するようにと求めるのだった。 真介の養子にされるはずだった、当時屋敷に同居していた画家は、精神がどこか錯乱したようになっていた。 事件後、解雇された当時の家政婦は、その屋敷を相続することになる真介の弟に不信感を抱いていた。 そして、屋敷の地下には、真の闇に満ちた迷宮があった。 七年前の密室事件の真相が、次第に明らかにされていく…。ーーー シンメトリーになった屋敷の構造と同じく、章立てもシンメトリーになっていて、なんというかすっきりとした綺麗な構成だなぁと思います。霞美さんたちは過去の事件について、おおまかにしか知らない(それこそ新聞記事や週刊誌の記事程度の情報くらいの)状態から始まり、次第に事件の状況を知っていくという、往路の章。そして、迷宮の中心で事件解決の糸口がつかめた後、次第に事件が解明されていく復路の章。綺麗だなぁと思います。 復路の章で事件が解明されていく過程を、わくわくしながら読みました。(2009/10/04読了)
2009.10.08
コメント(0)
-

秋月涼介『月長石の魔犬』
秋月涼介『月長石の魔犬』~講談社ノベルス、2001年~ 第20回メフィスト賞受賞作、秋月涼介さんのデビュー作です。 それでは、内容紹介と感想を。ーーー いかなる欲求も抱かずに生きてきた霧嶋悠璃は、たった一つ、希望を見つける。それは、彼女が自殺を企図したときに出会った「先生」に殺されることだった。いつか殺してあげるよ―そう約束してくれた「先生」のもとで、彼女は殺されることだけを夢見て生きていく。 * キャリア組の若き警視、鴻薙冴葉は、連続して起こっているいくつもの猟奇的な事件の解決に心を燃やしていた。犯人にコードネームを付けるのが癖の彼女は、過去の二つの事件の犯人に「人喰い魔(マンイーター)」「血涙に忍び寄る者(ブラッディストーカー)」の名を与えていた。そして、二つの事件に共通する、殺された上に左腕が切断された男の存在。それぞれの事件の犯人と思われる彼らを殺した犯人には、「見えざる左手切断魔(インビジブルレフトハンドハンター)」の名を与えていた。 されに、猟奇的な事件が発生する。ほぼ時を同じくして殺された二人の女性。彼女たちは首を切断された上に、その首には犬の首が縫いつけられていたのだった…。 * 石細工品の作成・販売を行う青紫堂にお手伝いとして通う鴇冬静流は、マスターの風桜青紫が作ったブローチをなくしてしまっていた。彼女が無断で持ち出し、大学で付けていたそのブローチを、彼女のサークルの先輩が奪い取ってしまったのだった。その後一週間、その先輩とは一切連絡がとれていなかった…。 そして、そのブローチが犬首殺人事件に関係していることが判明する。ーーー 本書が刊行されたときには一度読んでいるので、おそらく8年ぶりくらいの再読になります(その間に再読しているかもしれませんが…)。 例によって大部分は忘れていたのですが、鴻薙冴葉警視のことは印象に残っていました(その後の作品にも登場するからですが…)。事務処理能力には長けていながら、現場での行動や事件の判断能力にはどうも疑問符が付く彼女は、思い込みで行動しては、部下をいらいらさせてしまっています。おそらく最初に読んだときは、ずいぶん良くない印象を抱いた気もしますが、今回は、どちらかといえば憎めないキャラクタだと思いながら読みました(職場の上司がこうだと苦労が絶えないだろうと思いますが…)。 まったく内容とは関係ないですが、静流さんと青紫さんが居酒屋で食事しながら事件について話をするシーンがあるのですが、その中で運ばれてくる料理が美味しそうで、読みながら食欲が刺激されてしまいました…(笑) 事件の解明はそれとして面白かったのですが、本書では論理性よりも、背後の犯人たちの心理や行動のあり方の方を興味深く読みました。 今回から、秋月さんの作品の再読を進めようと思います(といって、現時点での最新作の記事は既に書いているので、実質本書を含め3冊の再読ですが…)。(2009/10/04読了)
2009.10.07
コメント(4)
-

土屋賢二『猫とロボットとモーツァルト 哲学論集』
土屋賢二『猫とロボットとモーツァルト 哲学論集』~勁草書房、1998年~ 土屋賢二先生の論文集です。西洋史の論文は多々読んできていますが、他分野の論文はまず読むことがないので、良い経験になりました。帯のとおり、「語り口は易しく水準は高く」ですが、しかしなじみの薄い分野の論文はなかなか難しいものです(単純に予備知識がないことで苦労します)。ですので、先に『ツチヤ教授の哲学講義』を読んで、多少なりとも予備知識や、土屋先生の考え方の方向性をつかんでおいたのが良かったと思いました。 さて、前置きが長くなりましたが、まず、本書の構成は以下のとおりです。ーーーはじめに一 猫とロボットとモーツァルト二 存在は解明できるか三 存在の問題の特殊性―ハイデガーとウィトゲンシュタイン―四 時間とは何か―プラトンとアリストテレスの時間概念五 何が知覚されるか―アリストテレスの答え六 だれもいない森の中で木が倒れたら音が出るか―アリストテレスの解決七 どうして分かるのか―赤色と行先初出一覧ーーー 特に印象に残った章についてのみ、簡単に感想を書いておきます。 表題論文「猫とロボットとモーツァルト」は、「芸術とは何か」という問題に関する考察です。ここでは、芸術の定義を与えるのではなく、芸術を理解して、芸術作品を生み出すロボットを作るにはどうすれば良いか、という観点から、芸術の性格を明らかにしていきます。まず、このアプローチから興味深いですね。 タイトルにあるモーツァルトは有名な芸術家の例ですが、猫は、たとえば猫がピアノの鍵盤の上を歩くときに出す音がなぜ芸術と認められないか、という問題の例となっています。 本書の中でもっとも興味深かったのは、第四章「時間とは何か」です。 哲学のなかでいう時間は、「継起の順序、純粋持続(前後方向の延長)、過去・現在・未来の区別、運動が成り立つための条件など」という性格をもつという観念が、ほぼ常識として定着しているそうです。ところが、このように考えると、プラトンとアリストテレスの時間の観念がどうにも分からなくなる。では、二人は時間をどのように考えていたのか―それが、本稿の考察の対象となります。 たとえばプラトンは、太陽、月、惑星が、時間を作った、と考えます。上の常識的な観念からいえば、太陽の運行がどうであれ、あるいはこうした天体が一切なくても、時間は存在しそうなものです。ではプラトンは、なぜそのように、時間よりも太陽、月、惑星が先に作られたと考えたのでしょうか。この問題についての先行研究を紹介しつつ、それらを批判した上で、土屋先生はきわめて「常識的」な解決を示しているように思います。それは、私たちが日常で時間を意識するのは、時計によって知られる時間によって、予定を立てたり、作業の経過時間を認識したりするときですが、プラトンは時間をまず第一にそういう意味での時間だと考えている、ということです。「時間があまりない」という用法で使われる意味での時間ですね。 ここでは、プラトンの時間観念を明らかにする部分のほんの一部だけを簡単に書いてみましたが、その論証の流れも説得力に富み、知的興奮が得られましたし、アリストテレスの時間観念を明らかにする部分もとても興味深かったです。『ツチヤ教授の哲学講義』でも、土屋先生は、哲学を「形而上学的に考える」タイプと、ウィトゲンシュタインのように「言葉の問題として考えるタイプ」に大別し、後者のタイプを支持することを表明されています。そうすると、過去の哲学者たちが、たとえば、「本当に時間は世間一般でいう時間ではなくて、○○という性格のものだ」と言った言葉が、単にある言葉の使い方を変えようという提案をしているにすぎない、と理解されます。さらに、ある種の哲学的問題は解決しえないということを示したり、言語ゲームの考え方によって、より日常生活に近いかたちで哲学的な考察を進めたりすることも可能になります。 なにぶん哲学初心者なので、これまでの研究史の流れも、こんにちの学会の研究動向も把握していませんが、土屋先生のようなアプローチは、近寄りがたい哲学がより身近に感じられ、また理解もしやすく、興味深いなぁと感じます。また、研究のスタンスという部分にも関わってきますが、難解な言葉を羅列するのではなく、哲学的に難しい問題も、易しい言葉で明らかにしていこうとされている姿勢に、とてもあこがれます。 全てを理解できたとはいえませんが、興味深い1冊でした。(2009/09/03読了)
2009.10.06
コメント(0)
-

土屋賢二/森博嗣『人間は考えるFになる』
土屋賢二/森博嗣『人間は考えるFになる』~講談社文庫、2007年~ お茶の水女子大学の哲学教授にしてユーモアエッセイ集を多く発表しておられる土屋賢二さんと、(当時)某国立大学の工学部助教授にしてミステリ作家の森博嗣さんによる対談集です。お二人の書き下ろし短編も楽しめる嬉しい一冊。 まずは本書の構成を紹介したうえで、全体的な感想を。ーーー絶妙「文理」対談 1 教授・助教授「書く」語りき 2 大学はやっぱりミステリィ(1) 3 大学はやっぱりミステリィ(2) 4 趣味は工作、コンピュータ 5 友達は必要か!? 6 (売れる)ミステリの書き方短編小説 消えたボールペンの謎(土屋賢二) そこに論点があるか、あるいは何もないか Here is a talking point or nothing(森博嗣)文庫版あとがき 対談の成果(土屋賢二) 対談の思い出(森博嗣)ーーー まず、自分にとって本書を読んだタイミングが良かったな、ということを思いました。森博嗣さんの作品は早くから読んでいましたが、土屋賢二さんの作品を読むようになったのはつい最近のことです。そして、お二人の作品をどちらも楽しむようになった今だからこそ、そのお二人の対談も楽しく読めたのだと思います。 お二人の対談を読んでいると、なんというか、森博嗣さんの考え方の独特さがとても際だっているように感じました(笑) 割と、土屋先生の考え方は自分の考え方に近い…というか…。 対談の中で特に面白かったのは5番目の「友達は必要か!?」です。森さんくらいさっぱり考えられたら楽だろうなぁと思いますが、なかなかたどり着けない境地です。 短編小説は、どちらも面白かったです。土屋先生のはユーモアエッセイのノリで、しかもミステリ風味という、二度楽しめる作品。森さんのは…やられました。 短いのですっと読めますし、楽しめる1冊です。(2009/10/01読了)
2009.10.05
コメント(0)
-

池上彰『そうだったのか!現代史』
池上彰『そうだったのか!現代史』~集英社文庫、2007年~ テレビでもおなじみ池上彰さんによる、(世界)現代史の概観です。とにかく分かりやすく、簡単な言葉で書かれているのでとても読みやすい1冊です。 本書は構成は以下のとおりです。ーーーはじめに第一章 冷戦が終わって起きた「湾岸戦争」第二章 冷戦が始まった第三章 ドイツが東西に分割された第四章 ソ連国内で信じられないことが スターリン批判第五章 中国と台湾はなぜ対立する?第六章 同じ民族が殺し合った朝鮮戦争第七章 イスラエルが生まれ、戦争が始まった第八章 世界は核戦争の縁に立った キューバ革命第九章 「文化大革命」という壮大な権力闘争第一〇章 アジアの泥沼 ベトナム戦争第一一章 ポル・ポトという悪夢第十二章 「ソ連」という国がなくなった第十三章 「電波」が国境を越えた!「ベルリンの壁」第一四章 天安門広場が血に染まった第十五章 お金が「商品」になった第十六章 石油が「武器」になった第十七章 「ひとつのヨーロッパ」への夢第一八章 冷戦が終わって始まった戦争 旧ユーゴ紛争おわりに主要参考文献ーーー 世界史はずいぶん勉強してきているのですが、それでもいかに現代史に疎いかということが痛感できる1冊でした。 第五章、第六章では、戦前(戦時中)に日本が犯したことの意味を考えさせられますね…。恥ずかしながら、台湾の日本人観というものを今回はじめて知ることができました。 また、第六章のなかの次の一節は、忘れてはならないなぁと思います。「韓国を旅行中の日本の若者が、上手な日本語を話す韓国人のお年寄りに驚いて、『日本語が上手ですね、どこで覚えたんですか?』とたずねたところ、お年寄りが突然怒り出し、『覚えたくて覚えたんじゃない。無理やり教えられたんだ』と言うのですが、日本の若者は意味がわからずにポカンとしている……。こんな情けないことがしばしば起きています。『日本人は自分の国がしたことを知らない』と批判される理由のひとつになっています」 逆に、すぐ上でふれましたが、台湾の章では、日本の占領後に中国(国民党)が無茶をした際に日本語が果たした役割や、国民党の横暴によって相対的に日本の植民地時代の辛い記憶が薄れたということなど、とても勉強になりました。 そして本書を読んで全体的な印象を思うに、戦後の世界を考えるうえで「共産主義」がひとつのキーワードになるんだな、ということ。冷戦や朝鮮戦争、ベトナム戦争、ソ連の解体などなど、共産主義という観点から関連づけられる多くの事件(そしてこんにちも尾を引く諸問題)が概観できるんだなぁ、と。 もう一点、パレスチナ地方の今日の紛争のきっかけとして、イギリスが果たした役割が指摘されていて、こちらも興味深かったです。この点は私の同期も以前に指摘していて、たしかにそうだなぁと思っていたところでした。要は、イギリスが、アラブ人にもユダヤ人にも甘い約束をし、しかもその地域をフランスと分け合おうという密約もする…。私は不勉強にしてよく分からないのですが、こんにちの中東問題について、イギリスはどういう役割を果たしているのでしょうか。 残念な事件が多々ある中、EUについての第十七章は、希望のある記述となっています。人類は愚かなことを繰り返してきましたが、それでも明るい方向に進んでいける可能性が示されている、とでもいいましょうか。 あらためて、とても勉強になると同時に考えさせられる1冊です。(2009/09/29読了)
2009.10.04
コメント(0)
-

佐藤友哉『クリスマス・テロル invisible×inventor』
佐藤友哉『クリスマス・テロル invisible×inventor』~講談社ノベルス、2002年~ 密室本(7年も前のことなので書いておきますが、当時、講談社ノベルスでは、ノベルスの中身丸々袋綴じのかたちで刊行する密室本という企画がありました)として発表された、ノンシリーズの長編です。 それでは、内容紹介と感想を。ーーー 高校受験を控えた中学3年生の小林冬子は、衝動に駆られて、貨物船に乗り込んだ。 そしてたどり着いたのは、名も知らない島だった。 人口500人ほどのその島で、冬子は熊谷という男に生活場所を与えてもらう。しかし、それは労働の対価としてのことで、冬子はしばらく慣れない肉体労働をする。 そして、その仕事に冬子は不向きだと熊谷も判断し、次に彼女に与えられた仕事は、監視だった。それは、小屋に住み、ひたすらパソコンに向かって作業をしている男を、向かいの小屋から監視するという内容だった。 ある日、ずっと監視を続けていた冬子だが、一瞬目を離した直後、男がいなくなっていることに気付く。そして、男は完全に行方不明になってしまっていた。ーーー 本書で描かれる大きなエピソードは、上記のように冬子さんが体験した密室状況からの人間消失事件と、その島での数々の体験ということになるのですが、本書にはまた別の主題(メッセージ)があります。 佐藤友哉さんの作品を刊行順に読んでいた私は、本作のそのメッセージに大きな衝撃を受けたものです。同時に、思い切ったかたちの作品だなぁという驚きもありました(そういえば、浦賀和宏さんの『浦賀和宏殺人事件』もかなり思い切っているなぁと思いましたね)。 なんとも言いにくい作品ですが、冬子さんを主人公とする物語は物語として面白かったですし、もうひとつの主題も含めて、全体として興味深く読みました。(2009/09/27読了)
2009.10.03
コメント(1)
-

佐藤友哉『水没ピアノ 鏡創士がひきもどす犯罪』
佐藤友哉『水没ピアノ 鏡創士がひきもどす犯罪』~講談社ノベルス、2002年~ 鏡家サーガ第3作です。これは面白かったです。 それでは、内容紹介と感想を。ーーー 18歳、フリーターの僕は、"紘子"とのメール交換を楽しみにしながら、単調な日々を送っていた。外に出れば他人の目が気になり、劣等感に襲われながらも、ただそのメール交換だけを楽しむ日々。ある日、鏡創士という年下の生意気な男と出会うが、鏡は僕についてずけずけと本質を指摘してくる。そして鏡は、ビールなどを持ってアパートにやって来るようになった。 ※ 幸せな(あるいはそう演じていた)家族が崩壊に向かっていた。 私はその状況を、発端から手記(遺書)に認めていく。 優秀な頭脳をもつ長女の梢が、ある事件をきっかけに壊れてしまう。そして家族は梢によって家の中に閉じこめられ、逃れようとしたら即座に殺されてしまう、という事態に陥っていた。梢に殺されるのを、償いだと諦める者。諦められないながらも、逃れられない者…。 そんなある日、父親が密室状況のなかで死亡するという事件が起こる。 ※ 小学4年生の僕は、クラスメイトの伽耶子を守ろうとしていた。純粋で、精神的にもろい伽耶子をおそう『奴』から、なんとしても守ろうと…。 その頃、僕たちの住む田舎の周辺で殺人事件が繰り返されていた。物騒ななか、僕たち生徒から慕われていた担任は産休をとり、伽耶子はかわいい子猫を目の前で傷つけられるという体験をしてしまっていた。 ますます彼女を守ろうと決意を固める僕だが、伽耶子を大きな悲劇が襲うことになる…。ーーー 3つのパートが交互に語られていきます。第1のパートの「僕」が、あまりにもとんでもない(というかどうしようもない)人間で、読んでいて不快な感じにもなりました。また、本書については表紙がその雰囲気をよく伝えてくれていると思うのですが、全体的に重たい雰囲気が漂っています。 …が、物語としてとても面白かったです。裏表紙にもあるとおり、前二作のような「馬鹿げた世界」ではないこともあるのでしょうが、私には初期3部作(?)のなかでもいちばんとっつきやすく、面白いと感じられる作品でした。 素敵な読書体験でした。(2009/09/27読了)
2009.10.02
コメント(0)
-
「2009年9月の読書記録・小説・エッセイ部門」
今回は、2009年9月に記事を書いた本のリストです。番号は、記事をアップした順番で、印象に残った本には☆マークをつけています。118.蛇蔵&海野凪子『日本人の知らない日本語』 ☆119.土屋賢二『ツチヤの口車』120.霧舎巧『霧舎巧 傑作短編集』121.森博嗣『ZOKURANGER』122.松尾由美『ハートブレイク・レストラン』 ☆123.佐藤友哉『デンデラ』124.ジーン・ウェブスター『あしながおじさん』 ☆☆125.島田荘司『自動車社会学のすすめ』126.深水黎一郎『花窗玻璃 シャガールの黙示』127.ジーン・ウェブスター『続あしながおじさん』 ☆☆128.佐藤友哉『エナメルを塗った魂の比重 鏡稜子ときせかえ密室』129.西尾維新『偽物語(上)』130.西尾維新『偽物語(下)』 9月は13冊の小説・エッセイの感想を書きました。『日本人の知らない日本語』はコミックエッセイですが、せっかく(?)なのでここに含めてみました。 9月は洋書も含めて西洋史関連の文献を読むのに力を注いだり、あるいは枕元の友に長めの本(池上彰さんの著作です。10月には記事をアップします)を読んでいたりで、休みが多かった割にはあまり小説・エッセイの数は稼げませんでしたが、面白い作品をたくさん読めたなぁという印象です。 なんといっても面白かったのは、『あしながおじさん』と『続あしながおじさん』です(基本☆は一つだけなのですが、強調の意味もこめて二つつけてみました)。本編は知っているけれど(そして好きだけれど)続編は読んだことがない、という方は、ぜひ続編の方も試してみられることをおすすめします。 その他☆を付けたのは、『日本人の知らない日本語』と『ハートブレイク・レストラン』です。『日本人の知らない日本語』は、本屋でも平積みされていましたし(今もでしょうか)、一般でも人気だと思うのですが、実際面白かったです。私は本を多く読んでいる方だと思っていましたが、それでも知らない言葉や使い方がいろいろ発見できましたし、他国の文化や価値観にもふれられますし、そしてマンガの絵柄が好みなのも良かったです。 松尾由美さんの作品を読むのは今回が初めてですが、ちょっと非日常的な設定に、しかし論理的で優しい謎解きが準備されていて、素敵な短編集でした。ほかの作品にもあたってみたいと思います。
2009.10.01
コメント(2)
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 『むせるくらいの愛をあげる』4~6巻
- (2025-11-15 00:00:05)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 今年も神田古本まつりに行きました。
- (2025-11-10 15:52:16)
-
-
-

- ジャンプの感想
- ジャンプSQ.25年12月号感想♪その3
- (2025-11-14 13:43:41)
-







