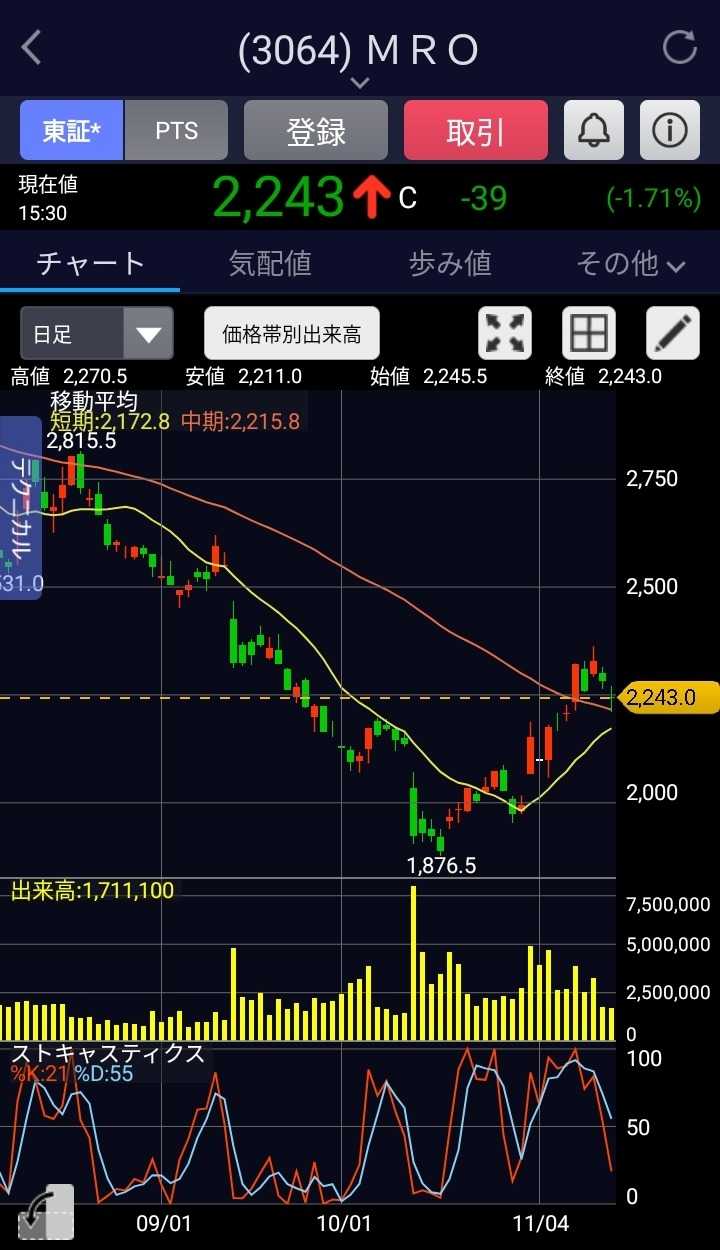2012年10月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-

10月のおしゃれ手紙:千葉の友人
9月に続き今月も私の体調は、小康状態。 ■それにひきかえ■、癌を患っている友人は、急に悪くなったようだ。10月24日~25日にかけて、訪ねた千葉の友人は、癌の進行が進んでいた。痛みがひどくて、日に5度の痛みどめを飲んでいるという。それにもかかわらず、夫婦で薔薇園に連れて行ってくれた。一緒にランチも・・・。彼女の家で一泊した。いつもなら、一緒の部屋で眠る私と友人だが、今回は、隣の部屋で寝た。夜中に苦しんで、私が起きないようにという気遣いからだ。早く寝たので夜中の2時頃、目が覚めた。友人の起きている気配がしたので、隣の部屋へ。痛み止めで少しは、楽になったのか私と話をし、お茶を飲んだ。彼女いわく、来てくれると、気がまぎれる・・・。彼女を見舞いに行ったことを後悔したり、やはり、行ってよかったと思ったりしている。■2012年10月の映画■*コッホ先生と僕らの革命*ソハの地下水道*バグダッド・カフェ*オカンの嫁入り*イラン式料理本*ル・アーヴルの靴みがき ■書き残したネタ■*東京駅の特別な出口*友人と森のレストランへ*シンプルに暮らす*領土問題*「二年間の休暇」の難点。*土人、女性は家事をすることが好き。*キラキラネーム*和泉市の美術館*もっと緑が欲しいのだ!(駐車場)*「清貧の思想」*橋元大阪市長 *みどり学*ファーストレディ *「小石川の家」*あさぶら*小説「アーレンガート」*「北極星」*アルミ缶エコ*江戸時代、和歌山の防災意識*子供と春の花と桜 ・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年10月31日*大大阪を見つめたダイビル *・・・・・・・・・・・・・・
2012.10.31
コメント(0)
-

神無月のころ:東京駅赤レンガ駅舎
神無月のころ、東京駅というところに行きぬ。八角形ドームをのせたルネッサンス様式の赤レンガ駅舎は、威風堂々としている。丸いドーム、干支の飾りなど、さすが辰野金吾の手によるものと、感じいった。赤レンガ駅の後ろの高いビル群に、少しことさめて、このビルなからましかばと覚えしか。(赤レンガ駅の後ろの高いビル群に、少し興ざめし、このビルがなかったらなと思った。)10月24日(水)~25日(木)、千葉に住む友人宅に行った。ついでに、新装なった東京駅を見た。残してくれてありがとうと言いたいが、やはり廻りの高層ビルが目に入ってしまう。それに比べて、去年行った■ヨーロッパの駅■ドイツのフランクフルトやパリの北駅は、周りとの調和がとれていて、美しい。■赤レンガ駅舎の復原■東京駅は、辰野金吾によって1914年(大正3)に建てられた。その後、東京大空襲で焼失。現在の建物は2階建てで、1947年(昭和22)に再建されたもの。東京を代表する建物のひとつだ。2006年度に復元工事を開始。2012年10月1日完成。 ■神無月の頃:もと■神無月のころ、栗栖野といふ所を過ぎて、ある山里に尋ね入る事侍りしに、遥かなる苔の細道を踏み分けて、心ぼそく住みなしたる庵あり。木の葉に埋もるる懸樋の雫ならでは、つゆおとなふものなし。閼伽棚に菊・紅葉など折り散らしたる、さすがに、住む人のあればなるべし。かくてもあられけるよとあはれに見るほどに、かなたの庭に、大きなる柑子の木の、枝もたわわになりたるが、まはりをきびしく囲ひたりしこそ、少しことさめて、この木なからましかばと覚えしか。「徒然草」吉田兼好 <口語訳>神無月の頃、栗栖野という所を通り過ぎてある山里にたずね入る事がありましたが、遥かな苔の細道を踏み分け、ひっそりと住みなしている庵があった。木の葉に埋もれる懸け樋の雫の他には、少しも音をたてるものはなし。閼伽棚に菊や紅葉などが折り散らしてある、さすがに住む人があるからなのだろう。これでもいられるんだなと、あはれと見ているうちに、むこうの庭におおきな蜜柑の木が、枝もたわむほどになっているが、周りをきびしく囲っており、少し興ざめして、この木がないほうがましかもと思えた。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年10月27日**・・・・・・・・・・・・・・
2012.10.27
コメント(0)
-

昔語り:稲刈り休み
子どもの頃の秋の仕事の思い出は、稲刈りだ。今と違って、機械など使わず、全てが手作業。多くの人でが必要となる。当時は、子どもといえど、小学4年生くらいになると、労働力として期待されていた。もう少し小さい子どもでも、それより幼い子どもの子もりをする。だから学校は「稲刈り休み」となる。学校の先生の家も米を作っているので、「子どもには勉強を!稲刈り休みなど、とんでもない」とならないのであった。私の家では、父と母と私が朝早くから、田んぼに行った。私より4歳年下の妹は、いとこと遊んでいた。 田んぼに着くと、父と母、それに私は、少し間隔をあけてならんだ。右手に鎌を左手に実った稲を掴んで刈り取った。3~4回分を一か所にまとめる。そうして、刈り取ると、今度は、3~4回分の稲を藁でくくる。くくった束を「一束=いっそく」といった。全てを束ねると刈り取った稲の束を天日干しにするためにはざ架け用をする。そのためには、ひとにぎりくらいの太さの3本一組になった棒を何組も立てる。3脚になったその3本一組の棒に洗濯物を干すような竹竿を乗せる。その竹竿に稲の束を架けるのだ。 もちろん、この一連の仕事の合間には、ひと休みがあり、昼休みがあった。しかし、時間が来たら帰れるというような仕事ではなかったので、子どもの私も、必死で働いた。父は右手が不自由だったが、左手で稲刈りをし、左手で稲を束ねた。私は鎌で手を切ったこともなく、稲刈りを手伝った。しかし、いつ頃からか、稲刈り休みはなくなってしまった。その頃からだろう、人々は工場や会社で働き始めた。そうして、皆で豊作を祝うことがなくなって秋祭りが衰退していった。私は、稲刈り休みのあった頃、子どもでよかったと思う。楽ではない作業だったけれど、その先に必ず、米のご飯が食べれるというあの満ち足りた思いを経験できたからだ。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年10月26日*父の麦わら帽子:目次*・・・・・・・・・・・・・・
2012.10.26
コメント(0)
-

おしゃれ手紙48◆秋たけなわ
■天地 はるな様■ 秋たけなわ。いかがお過ごしですか?読書の秋。 素晴らしい一冊に出会いました。 江原 恵という人が書いた「家庭料理をおいしくしたい」。【中古】afb家庭料理をおいしくしたい / 江原恵 先日出かけた折に、たまたま古本市に出くわしたのですが、その時、何気なく手にとった一冊が私に元気と勇気をもたらしてくれるとは! 目次には「自然食品は本当に自然か?」や「カニ風味かまぼこは中流幻想の象徴」など 料理の話だけではなく、その時代の社会背景を併せて書かれてある文章には、身震いがするほど。 私の疑問が簡潔明瞭に解説してあり200ページほどの単行本。 ぐぐーっと引き込まれて、あっという間に読み終えてしまいました。 今から10年ほど前に発刊されていたようですが、私にとっては「目から鱗」本。 この本にめぐりあえたことに感謝。 食欲の秋。 昨日、新米を炊きました。 近所の人にもらったなめこと父の畑でとれた大根をおろして、なめこ丼。 旨い!の一言。 毎年この季節になると松茸がはやしたてられるけど、松茸を食べる機会が殆どなく食通でもないし、茸に大枚をはたくほど裕福でもない私にとって秋の味覚は、なめこなのです。 でも、なんで松茸だけがこんなにもてはやされるんでしょうね。 京都の錦と京極の松茸を売っているお店の絢爛豪華には、まいりました。 とりあえず、実りの秋に感謝。 文化の秋。 イギリス人の女友達と京都の寺町に。 何でも、ドイツ人の彼のお母さんの誕生日プレゼントを贈りたいらしく、あれやこれやと一緒に さがし回った結果、選んだのは絵巻模様のハンカチ。 これなら送料もかからないし、日頃から「チープ」を合言葉にしている私たちには、まさしく「逸品」。 これに気をよくして、これまた「チープ」なイタメシ屋で食事をしていたら彼女に「Genji Story」の 概略を教えてくれと言われ、思わず喉が詰まる思い。 結局、はるなさんに泣きついたり、学生時代に読んだ『あさきゆめみし』を思い出しながら、後日、彼女にFAX・を送ったのですが たどたどしい内容は、ともかくとして、これがけっこう楽しくて自分にとってもいろいろと学ぶものがありました。 片言でしか話せないけど、いろんな国の人と話せたらどんなに楽しいか。 英語のみならず、スペイン語もまだまだ勉強中。 二兎を追うものはなんとか、と言うけれど、どっちもボチボチ学んでいけたらなーと思っています。 チャンスをくれたサルサに感謝。 はるなさんは、どんな秋をお過ごしですか? 浜辺 遥 追伸:先日「買ってはいけない」の講演会でM氏にお目にかかりました。 やんちゃぶりは、相も変わらず。 葉っぱで作った虫を頂いたんですが、生きてるように見えるから不思議。 やっぱりM氏は「げにあやしき」 ◆おしゃれ手紙◆・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年10月25日*量りウリって愉快だ*・・・・・・・・・・・・・・
2012.10.25
コメント(0)
-

みどり学:日本の公園
■第4回 公園のプランを考える。 西欧の公園をみて、なぜうらやましがるのか。 日本の公園が公園としてのあるべき方向から少し外れているのではないか。 それを足がかりにして、まずはじめに公園の本質を考える。 次に公園のマスタープランのあり方を鶴見緑地を素材にとりあげるほか、公園の量と質との関係や公園の有料化の問題にもふれる。■みどり学■by高橋理喜男■はじめに■*日本の公園は都市公園法にもとづきつくられ管理されている。*ただし、都市公園のみ。*昭和31年にできた法律。 1人あたり6平米を確保する。 ただし市街地では3平米。 大阪全体では6平米で、欧米では10平米以上。■公園の種類■★住区基幹公園*街区公園(従来は児童公園と称した) 半径250m程度の街区に居住する人々が利用する0.25haを標準とする公園。 *近隣公園 半径500m程度の近隣に居住する人々が利用する2haを標準とする公園。 *地区公園 半径1km程度の徒歩圏内に居住する人々が利用する4haを標準とする公園。全国各地にある中央公園と称する公園はこの類のものが多い。 ★都市基幹公園 総合公園 市町村全域の人々が、総合的に利用することを目的とした公園。 *運動公園 市町村全域の人々が、運動に利用することを目的とした公園。 運動公園も半分は緑で残さなければならない。*総合公園*風致公園★大規模公園 複数の市町村に住む広範囲の住民が利用することを目的とした公園。◎いろいろな建物を建てて、真の公園ではなく「ガラクタ公園」になってしまうのを防ぐため建物の敷地面積を公園の全面積の2%以下に規定。特別なもの、例えば動物園などは5%以下に。全体の建ぺい率は7%以下におさえる。大阪城公園は7%以下。■芝生大阪の芝生は、府下の公園を合わせても0.4平方メートル。アムステルダムの場合10平方メートルと日本の25倍もある。芝生が少ないと踏まれて痛むので量的に必要だ。パーク、ガーデン、プレイグランド(プレジャーガーデン)がある。この中で大きな木があるイメージがパーク。日本の場合は、あってもガーデン、プレイグランドばかりで本当の公園=パークは少ない。関西では、「奈良公園」がパークである。以上みどり学講座No.4「公園のプランを考える」1990年10月23日(火)6:30~8:30帰宅市民教養センター講師:高橋理喜男 最近は、学校芝生運動がさかんになってきた。運動場が芝生に変わるとケガの減少やこどもたちの情操教育になる。また、温度が下がるので夏は過ごし易いといいことだらけだ。1990年に受けた講座だが、あれから20年以上たったのだと思うと感慨深い。■みどり学講座■1990年10月に受けた、講座。■みどり学講座:はじめに■ 近年、グローバルな視点から、地球環境における緑としての森林資源に対する一般の関心が急速に広まるとともに、その破壊に伴う危機感も高まっております。それに比べて、私どもの身近にある緑に対してはどうでしょうか。 「緑ゆたかな街づくり」、「自然と人間の共存」といったスローガンやキャッチフレーズは、相変わらず巷にあふれているのですが、いざとなるといつもあとまわしにさててきました。それが積み重なって都市砂漠の拡大を招いてしまったといえます。いま、それに歯止めをかけ、生活環境の中にゆたかな緑を回復していくためには、市民ひとりひとりが根本から緑の問題を考え直す必要があるように思います。■みどり学講座:概要■ ■第1回 緑の価値を考える。 ■永井荷風「日和下駄」■ ■鏑木清方■ ■森林の価値■ ■第2回 農の風景を考える。 ■はざぎ・失われた農の風景■ ■野筋(のすじ)■ ■第3回 公園の生い立ちを考える。■ ■第4回 公園のプランを考える。 ■第5回 グリーンベルトを考える。 ■第6回 大仙公園を見る。(現地調査 ) ・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年10月23日*器歳時記:味噌ガメ*・・・・・・・・・・・・・・
2012.10.23
コメント(1)
-

NGO「緑のサヘル」カレンダー
10月も半ばを過ぎたからネットでカレンダーを探していた。そこで見つけたのが、上の「緑のサヘル」カレンダー。「緑のサヘル」って何?とさっそく調べて見た。■緑のサヘル■サハラ砂漠を越えた南側、ここは、かつて久しぶりに緑を目にしたアラビアの商人たちによって、「岸辺(サヘル)」と呼ばれました。今、その「岸辺」では砂漠化が進み、人々の生活基盤が奪われています。なぜ、緑の「岸辺」は砂漠となってしまったのか。砂漠化には、地球的規模での気候変動や海水温度の変化など、その土地に住む人々の力が及び得ないところでの「自然的」な要因が関係しています。しかし、それだけではなく、耕作地拡大のための森林地の開墾、商品作物や穀物の連作、家畜の過剰放牧など、当たり前の「人間活動」も大きな要因になっています。このような「人間活動」により、土地の力が弱まり、植物が生長しにくくなる土地になってしまうことを、砂漠化といいます。NGO「緑のサヘル」は、砂漠化の進むサヘルの土地を、人々が生活を続けていくことの出来る「緑の岸辺」に戻すため、活動を行っています。 カレンダーの収益金は、緑のサヘルの活動資金というわけだ。先日見た映画■「ル・アーヴルの靴みがき」■。アフリカの少年は、貧しさゆえに、先に密入国した母親を追って命がけで不法入国したのだった。貧しさは、温暖化などによる砂漠化で、作物が出来なくなったから。そして、その温暖化を作ったのは、私たち、先進国の人間だ。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年10月20日*柿は女の生涯 *・・・・・・・・・・・・・・
2012.10.21
コメント(0)
-

ル・アーヴルの靴みがき★アキ・カウリスマキ
■ル・アーヴルの靴みがき:あらすじ■♪音が出ます!心をみがけば、きっと奇跡はおこる。北フランスの港町ル・アーヴル。パリでボヘミアン生活を送っていたマルセル・マルクスは、いまはル・アーヴルの駅前で靴をみがくことを生業としている。家には献身的な妻・アルレッティと愛犬ライカが彼の帰りを待っている。その小さな街で暮らす隣近所の人々の温かな支えも、彼にとってはなくてはならない大切な宝物だ。そんなある日、港にアフリカからの不法移民が乗ったコンテナが漂着する。警察の検挙をすり抜けた一人の少年イドリッサとの偶然の出会いが、マルセルの人生にさざ波をおこす。しかし同じ頃、妻のアルレッティは医師より、余命宣告を受けるのだった…。 この映画を見たのは、監督がアキ・カウリスマキだったから。しかし見たことがなかったので、この映画が、アキ・カウリスマキ監督らしいものなのかどうかは分からない。ぶっきらぼうな感じのセリフや表情。マルセルの妻は、にこりともしないし、出てくる人、みんな、ぶっきらぼうなセリフ。しかし、内容はあたたかい。こんなに皆、善良な人ばかりいるのだろうか、映画だからだよねといいたくなるような人ばかり。おとぎ話としかいいようのないような、内容。最後に起こる奇跡。これがアキ・カウリスマキなのか?それにしても、ヨーロッパには、不法移民が次々に入ってくる。■君を想って海をゆく■もフランスに不法侵入した若者が英仏海峡を泳いで渡り、途中で命を落とすという物語だった。もし、成功してヨーロッパで住み始めても、市民権を得るのは大変なことだろう。ましてや、成功した人の陰に、その数以上の死者もいるのだ。ヨーロッパに来なくても、アフリカで、幸福に暮らせるような世界を作らなければならない。目の前の不法侵入者を助けるだけではすまないのだ。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年10月18日*台風のあと・・・椋(むく)の実ひろい *・・・・・・・・・・・・・・
2012.10.19
コメント(0)
-

イラン式料理本★女性の地位
■イラン式料理本:あらすじ■イランから届いた、とっておきの家庭の味。新婚夫婦のキッチンから、ベテラン主婦の台所まで、さまざまなイラン人女性が披露する今晩の献立や、伝統的な家庭料理の作り方。そこから浮かび上がるのは、男と女、嫁姑、家族というドラマ。そしてイラン社会の“今と昔”。さまざまな思い出とともに引き継がれる家庭料理は、笑いや涙というスパイスによって、味わい深く熟成されていく――。主婦歴40年の監督の母、14歳の時に40歳の夫のもとに嫁いだ母の友人、現代女性代表の妻、13歳で結婚した伯母、9歳で結婚、もうすぐ100歳の友人の母親、双子を育てながら大学に通う妹、主婦歴35年、5人の子の母でもある義母・・・。監督をめぐる7人の女性の料理を通して、イランの今の女性を描いている。面白いのは、義母。「2年前に手を洗ったから、きれいよ」と冗談を言う。彼女が結婚をした当時は、今よりももっと封建的で、夫が妻の名前を呼ぶことも許されなかったという。また、姑は、嫁に強く当たったようだ。しかし今は、「オレと母さんが2人がかりでも、おまえにはかなわない」と夫に言わしめるほど、無敵の女性となった。そんな彼女も、なんだかんだ言いながらも、家族のために手の込んだ料理を作る。義母の次の世代、つまり彼女の娘=監督の妻となると、また家事に対する考え方が全然違うのが面白い。監督の妻は、家に来た海外からの客に、缶詰料理を食べさせたそうだ。その上、そのことを堂々と客に言ったという。バラサなくてもいいだろうと言う監督に、「突然、夜、客を連れてくる方がどうかしてる」と反撃。「昔のように、床に座らず、椅子の生活になったけど、頭の中は、相変わらず、昔のまま」と憤慨する。義母と妻のような女性は、イランではまだ、珍しいのだろう。ほとんどの女性が、黙々と料理を作り、のんびりとくつろぐ夫をしり目に、黙々と後片付けをしていた。少し昔なら、食事の支度が少しでも遅れると、男は女を怒鳴ったり、叩いたりしたらしい。しかし、自分の意見をはっきりと言う監督の妻や義母やを見る限り、確実にイランでの女性の地位は、上がっているのだろうと思う。ちなみに、我が家でも、食事を作るのは、ほぼ100%私とイランなみ。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年10月16日*父の麦わら帽子:芋穴*・・・・・・・・・・・・・・
2012.10.17
コメント(0)
-

ノーベル賞・山中教授あれやこれや
スウェーデンのカロリンスカ研究所は8日、2012年のノーベル生理学・医学賞を、様々な種類の細胞に変化できるiPS細胞(新型万能細胞)を作製した京都大学iPS細胞研究所長の山中伸弥教授(50)と英国のジョン・ガードン博士(79)に贈ると発表した。 体の細胞を人為的な操作で受精卵のような発生初期の状態に戻すことができることを実証し、再生医療や難病の研究に新たな可能性を開いた点が高く評価された。細胞作製を報告した2006年8月の論文発表からわずか6年での受賞となった。◆山中伸弥(やまなか・しんや)=1962年9月4日生まれ。大阪府出身。神戸大医学部卒。大阪市立大助手、奈良先端科学技術大学院大助教授、教授を経て、2004年10月から京都大教授。10年4月から同大iPS細胞研究所長。07年から米グラッドストーン研究所上席研究員も務める。 10月8日、映画からの帰りに、ノーベル賞受賞を知らせる号外を受け取った。私の前に受け取った中年夫婦が、号外を見ながら言った。「かしこそうな顔をしとるなぁ。」見ると、いかにも科学者という顔でなかなかのイケメン。関西弁でいう「シュとした」顔だ。連日の報道で、山中教授のことが分かってきた。■関西人である。大阪府出身、神戸大医学部卒。大阪市立大助手、奈良先端科学技術大学院大助教授、教授を経て、2004年10月から京都大教授。という経歴もだが、サービス精神が旺盛だと思う。手術が下手な自分を山中をもじって「ジャマナカ」と自虐ネタで笑わせる。研究室でマウスの世話をしていたので、これまた「山中」をもじって「山チュウ」と言う。■夫婦で記者会見に臨む。京都大学では、ノーベル賞を受賞した時のマニュアルというのがあるそうだ。1回目の記者会見は、受賞者のみで、2回目は夫婦でという。しかし、ほとんどの受賞者が、妻を記者会見に出さないそうだ。そんな中で、山中教授は、夫婦で仲良く臨んだ。そして、奥さんもユーモアを交えながら話すのが、気持ちよかった。奥さんは、山中教授が不遇な時代に、医者として家計を支えたという自負があり、夫はそれを感謝しているからだろう。ちなみに、山中教授は奥さんを「ボス」と呼ぶそうがほほえましい。■話が上手い。インタビューを聞いていても、ユーモアと交えて、話す。人を引き付ける力を持っている。今や時の人となった山中教授だが、研究室を立ち上げた当初は人集めに奔走する日々だったという。1999年12月、37歳、まだ6年ほどしかたっていない奈良先端科学技術大学院大学、その助教授の公募に応募して採用が決定。奈良県・生駒の山を切り開いた真新しいキャンパスで、有名でもない新人の山中氏が学生を集めるのは、大変なことだったと思う。当時は、はったりにも似たプレゼンだったが、プレゼンの上手さが学生たちの心を捉えた。■マラソンで資金稼ぎ。アメリカに比べ、研究費の少ない日本。人件費や研究材料など、けっこうお金がかかるらしい。研究費集めに苦労し、今年3月には、自身が京都マラソンで完走することを条件にネット上で寄付を募り、レース前までに約900万円が集まった。「ジャスト・ギビング・ジャパン」という寄付を取り次ぐサイトを通じて行われた活動で、レース終了後も閉鎖されずに残っていたため、受賞発表後に再び寄付が集まり、数時間で10万円を超えたそうだ。この他に、特筆すべきは、研究室で働く人への思いやりだ。今、山中氏の研究室には、大勢の研究者がいるらしいが、その殆どが、正社員ではないそうだ。彼らのうちの全部とはいかなくても、研究に頑張っている人には、暮らしに困らないような正当な賃金で、正規に雇用すべきというのが山中教授の持論。ノーベル賞受賞者が、このようなことを言うのを始めて聞いたが、好もしい人だと思った。「iPS」のiは、iフォーン、iパッドなどと同じように広がればいいという所から小文字にしたそうだ。骨粗鬆症のために痛む腰を思うと、是非、成功して欲しいものだ。人類は、どこまでも欲張りで、元気で長生きしたいと思っている。しかし、人間ばかりが増えても、食糧や水、エネルギー問題がある。人類は、この折り合いをどうつけるのだろうか?・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年10月15日*ハレとケ*・・・・・・・・・・・・・・
2012.10.15
コメント(1)
-

オカンの嫁入り★母娘
■オカンの嫁入り■「おかあさん 結婚することにしたから。」陽子(大竹しのぶ)と娘の月子(宮崎あおい)は、ずっと母一人子一人で仲良く支え合って暮らしてきた。ある晩、酔っ払った陽子が若い金髪の男・研二(桐谷健太)を連れて帰ってきて、彼との結婚を宣言する。あまりに突然の事態に戸惑う月子は、母に裏切られたという思いから陽子にも研二にも素直に心を開けず、家を飛び出してしまうが……。 私的には、すっきりしない映画だった。リアリティがないのだ。気になったことを書いてみると・・・。*母娘が住む家が立派すぎる。大家さんのもので持ち家ではないが。 大阪で、あの広さの家だと、母親ひとりの稼ぎでは、借りることが出来ない広さだ。*大家さんとの距離が近すぎ。いくら人情が厚いとはいえ、今どき、惣菜を持ってきてくれるか?*陽子(大竹しのぶ)の声が、耳についた。独特の声なので、囁くような時にはいいのだが、「月ちゃん~。月ちゃん~」と娘を大声で呼ぶのは、どんなものかな。*関西弁。陽子(大竹しのぶ)と月子(宮崎あおい)って、関西弁の似合わない顔だ。*陽子(大竹しのぶ)の夫は、月子(宮崎あおい)が産まれる前に死んだという設定だが、若い時になぜ、再婚しなかったのか?*歳の差。陽子(大竹しのぶ)が連れてきた男性・研二は、30歳の金髪。陽子は、45歳くらいという設定。実際には、大竹しのぶのしわが多いので、50歳過ぎに見える。45歳としても15歳の歳の差婚ということになるが、不自然だ。だって、陽子の青春時代に、研二は産まれたのだ。同じ時代を生きたものにしか分からないおもいってあるのだが、このふたりにとって、そういう感情がないのではないか。娘の月子は25歳だから、そっちだと納得なのだが・・・。昨今の芸能人の歳の差婚をいかがなものかと、いつも思っている。母娘の名前は、太陽と月。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年10月11日*伝説の少女漫画「マキの口笛」*・・・・・・・・・・・・・・
2012.10.11
コメント(0)
-

バグダッド・カフェ★色彩
■バグダッド・カフェ:あらすじ■♪音が出ます!ドイツはミュンヘン郊外、ローゼンハイムからの旅行者ジャスミンは、アメリカ旅行中に夫と喧嘩をし車を降りてしまう。彼女は重いトランクを提げて歩き続け、モハーヴェ砂漠の中にあるさびれたモーテル兼カフェ兼ガソリンスタンド「バグダッド・カフェ」にやっとの思いでたどり着く。いつも不機嫌な女主人のブレンダ他、変わり者ばかりが集う「バグダッド・カフェ」。いつも気だるいムードが漂う中、ジャスミンが現れてから皆の心は癒されはじめる。あの不機嫌なブレンダさえも。そして二人はいつしか離れがたい思いに結ばれていくのだが……。 色彩の美しい映画だった。中でも、黄色が多く使われていた。多くというより、どの場面でも黄色が使われていた。最初に気がついたのは、けんか別れをした夫が、砂漠に置いて行った、中にコーヒーの入った黄色いポット。「バグダッド・カフェ」のスタッフが着ているシャツやTシャツ、バンダナ・・・。制服ではないのに、黄色が多様されている。そうそう、店のカーテンも黄色と赤。日本で1989年3月に公開されたのは91分のアメリカ・バージョン。1994年8月に公開された〔完全版〕はアメリカ・バージョンの30シーン以上のパートでカットが長くなっている108分のヨーロッパ・バージョンであった。今回の〔ニュー・ディレクターズ・カット版〕は1994年のヨーロッパ・バージョンをベースに、監督自らが色と構図(トリミング)を調整し直し、2008年のカンヌ国際映画祭で初公開された。今回は■第1回大阪・中之島ごはん映画祭 ■の作品。このバグダッド・カフェには、美味しいごはんはない。出てくるのは、コーヒーがほとんど。耳から離れない主題歌「コーリング・ユー」はアカデミー賞最優秀主題歌賞にノミネートされ、その後、80組を超えるアーティストがカバーするほどのスタンダード・ナンバーに。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年10月10日*サルビア歳時記:10月の季語*・・・・・・・・・・・・・・
2012.10.10
コメント(0)
-

ソハの地下水道★ユダヤ人迫害
■ソハの地下水道:あらすじ■その暗闇はやさしい秘密を隠している。1943年3月、ナチス支配下のポーランド。地下水道の労働者・ソハは迷路のように入り組んだ地下を熟知しており、盗品をそこに隠しながら飢えをしのいでいた。そんな中、ゲットーからトンネルを掘って地下に逃げ込んできたユダヤ人たちを偶然見つける。最初こそ金目当てでかくまうが、ユダヤ人たちの運命がナチスに追い込まれていくにつれ、次第に彼らに気持ちが寄り添っていき…。1943年ナチス政権下のポーランド。迷路のように張り巡らされた地下水路にユダヤ人をかくまった、ひとりの男の真実の物語。第84回アカデミー賞■外国語映画賞■にノミネートされた作品。 ナチスドイツによるユダヤ人の迫害は、これまでも数多く描かれてきた。しかし、ポーランドにいるユダヤ人が地下水道に隠れていたということは知らなかった。見ごたえのある映画だからと夫に勧めると夫は、このことを知っていた。「ソ連軍がもっと早く*ワルシャワ蜂起軍*を援助していたら、ユダヤ人や蜂起軍の被害は少なかった」と夫は言う。*ワルシャワ蜂起とは*ソビエト赤軍占領地域がポーランド東部一帯にまで及ぶと、ソ連はポーランドのレジスタンスに蜂起を呼びかけた。7月30日にはソ連軍はワルシャワから10kmの地点まで進出。ワルシャワ占領も時間の問題と思われた。ポーランド国内軍はそれに呼応するような形で、8月1日、ドイツ軍兵力が希薄になったワルシャワで武装蜂起することをソ連軍と打ち合わせた。ヴィスワ川対岸のプラガ地区の占領に成功したソ連赤軍は市街地への渡河が容易な状況にあったにもかかわらず、蜂起軍への支援をせずに傍観を決め込んだ。ソ連赤軍と共に東方からポーランドへ進軍しプラガ地区に到着していたジグムント・ベルリンク将軍の率いるポーランド人部隊「ポーランド第1軍団」のみが対岸の蜂起軍支援のための渡河を許され、彼らポーランド人軍団はベルリンク将軍以下必死で蜂起軍の支援をしたものの、その輸送力は充分ではなかった。ソ連赤軍は輸送力に余裕があったにもかかわらずポーランド第1軍団に力を貸さなかった。のちにポーランド人民共和国最後の国家指導者で1989年の新生ポーランド共和国初代大統領となったヴォイチェフ・ヤルゼルスキはこのときポーランド第1軍団の青年将校として現地におり、物資補給作戦に参加している。彼はこのときの燃え盛るワルシャワ市街を眺めながらソ連赤軍に対して涙ながらに感じた悔しさをのちに自伝『ポーランドを生きる』のなかで赤裸々に吐露している。 ソビエトはイギリスやアメリカの航空機に対する飛行場での再補給や、西側連合国による反乱軍の航空支援に対し同意せず、質・量に勝るドイツ軍に圧倒され、蜂起は失敗に向かっていく。映画に描かれたユダヤ人の悲惨な生活に愕然とし、映画では、描いていないことを知って、またまた愕然とした。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年10月9日* 豆名月・栗名月・・・片見月*・・・・・・・・・・・・・・
2012.10.09
コメント(0)
-

コッホ先生と僕らの革命★サッカー
■コッホ先生と僕らの革命:あらすじ■♪音が出ます!イギリスから自由の風が吹いてきた。1874年、イギリス留学をしていたコンラート・コッホは、ドイツ・ブランシュバイクの小学校に英語教師として採用される。コッホが、英語に慣れ親しんでいない生徒たちに関心を持ってもらうために思いついたのは、ドイツにはまだ伝わっていなかったサッカーだった。コッホの試みは成功、生徒たちはサッカーに夢中になる。しかし、イギリスかぶれのサッカーを心よく思わない教師や父兄たちは“サッカー禁止令”を出し、彼を更迭しようと画策。生徒たちは先生とサッカーを守るため、力を合わせ闘うことを決意するが…。 ドイツ・サッカーの創始者、コンラート・コッホの実話だ。1874年といえば、今から約140年前の話。当時の学校では、ドイツは英語を習わなかったのかとビックリ。オーストリアやスイスなどドイツ語圏は広いから必要がなかったのだろう。また、隣国が大国フランスだから、教えるならフランス語か。舞台となるのは、金持ちの男の子が通う学校。そんな中に、たった一人、貧しい母子家庭の子どもがいる。(このこが可愛い!!)貧しい家庭だからと露骨に皆、彼をいじめる。サッカーを始めると、彼はめきめき頭角をあらわす。そして、クラスの一員として一目置かれるようになる。コッホ先生は言う。「サッカーは貧乏人にも金持ちにも平等だ。」・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年10月7日*トリビアの井戸:運動会と綱引き *・・・・・・・・・・・・・・
2012.10.07
コメント(0)
-

おしゃれ手紙:47◆ターシャ・チューダの世界
■浜辺 遥さま■猫をかいました。飼ったのではなく買ったのです。チョー忙しい人間のTさんが、遥さんちの小犬の里親になっているという、先日のお手紙。「忙しいし、家が狭いから犬や猫は飼えないの」という、はるなお得意の逃げ口上は通用しませんね。そう、私、犬も猫もあまり興味がありません。友人のSさんとの黒猫の「ミューミュー」こと「ミューシャ」は、どうやら私に気があるらしく、おじゃますると必ず、私の膝に乗ったり体を寄せてきます。他に、沢山人がいてもですよ。モテるのは、嬉しい。それがたとえ猫であっても・・・。だからミューミューを撫でるのですが自分で飼おうという気にはなりません。犬もまたしかり。とはいえ、私、子ども時代は、ウサギや鶏、金魚、そして蚕まで世話をし、牛と「ひとつ屋根の下」してたんですよ。「忙しいし、家が狭い」今の私にピッタリなのが、今回ご紹介する猫の置物。猫の置物が欲しいと思い始めたのは、Sさんチの置物の猫を見てから。こちらは黒猫で、なんとも品のある眠り猫。私もおなじ物が欲しい、欲しいと思い続けてはや数年。おなじ物は手に入らなかったのですが、私のは三毛猫。出会った所は、古道具屋さん。その時、私は、3ヶ月間の講座を終了したところ。「自分をほめてやりたい」気持ちでした。そこで見つけた三毛猫の置物を迷わず買ったのです。 Sさんチの置物のような気品はないけど、とぼけた顔して、愛嬌たっぷり。置物とはいえ、猫は猫。名前を考えました。●天地 甚五郎・・・日光東照宮の眠り猫を彫った名工、左甚五郎にあやかって。●ホームズ・・・茶と白と黒の三毛猫なんです。どちらも、イマイチぴったりこないので没。でも、置物の猫やバラに名前をつけるなんて私ってやっぱりヘン?こんな、へんなことばかりを書き続けた「おしゃれ手紙」も私からは、これを含めて後2回。衣食住、すべておしゃれに暮せたらいいな、と思っているけれど完璧には至難のわざ。しかし、そんな完璧なおしゃれ人間を見つけました。といっても本で見たのですが・・・。 彼女は、アメリカのニューイングランド地方に住む80歳を過ぎた画家。古風な服が、よく似合う人。庭仕事の合間に稲や猫、小鳥に山羊の世話を優雅にやってのけるのです。もちろん、本業の絵も・・・。「ターシャ・チューダの世界----ニューイングランドの四季----」読書に秋に、遥さんもいかがでしょう。ターシャの暮らしぶりに心をうたれた 天地 はるな◆おしゃれ手紙◆・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年10月5日*トリビアの井戸:道普請 *・・・・・・・・・・・・・・
2012.10.06
コメント(0)
-

第1回大阪・中之島ごはん映画祭
■第1回大阪・中之島ごはん映画祭■『人』と『食』のつながりを描いた『おいしい』映画を一堂に集め、単に映画を観るだけでなく、食を体験しながら、また音楽を聴きながら、人と語らいながら、自然の恵みを感じながら楽しむライフスタイル型の複合イベントである『ごはん映画祭』。2010年に東京で誕生して以来、多くの方にご好評を得てきた『ごはん映画祭』がついに大阪中之島に登場。みどりを活かしたにぎわいづくりを推進する大阪府のプロジェクト『中之島にぎわいの森づくり』ともタイアップし、中之島の水や豊かなみどりに囲まれた空間で、映画上映だけでなく、トーク・ライブなど『人と食のつながり』を五感で楽しめる映画祭を目指します。 【開催日程】2012年10月6日(土)~10月14日(日)【開催場所】メイン会場:梅田ガーデンシネマ サテライト会場:中之島BANKSほか【企画・主催】大阪中之島ごはん映画祭運営委員会■10月6日(土) 12:25『ペンギン夫婦の作りかた』 14:50『しあわせのパン』 17:10『バグダッド・カフェ』 19:30『eatrip』■10月7日(日) 12:25 『しあわせのパン』 14:50『かもめ食堂』 17:10 『ディナーラッシュ』 19:30『プロヴァンスの贈りもの』■10月8日(月・祝) 12:25『かもめ食堂』 14:50『バグダッド・カフェ』 17:10『オカンの嫁入』 19:30■『南極料理人』■■10月9日(火) 12:25『eatrip』 14:50『オカンの嫁入』 17:10『未来食卓』 19:30『アメリ』■10月10日(水) 12:25『プロヴァンスの贈りもの』 14:50『青いパパイアの香り』 17:10『転々』 19:30『バグダッド・カフェ』■10月11日(木) 12:25 ■『アンティーク』■ 14:50『アメリ』 17:10『ディナーラッシュ』 19:30『かもめ食堂』■10月12日(金) 12:25『南極料理人』 14:50『eatrip』 17:10『青いパパイアの香り』 19:30『未来食卓』■10月13日(土) 10:00『アンティーク』■10月14日(日) 10:00『南極料理人』・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年10月3日*イチョウのまな板*・・・・・・・・・・・・・・
2012.10.03
コメント(0)
-

植物切り抜き帳:サトイモ
【稲よりも古い野菜】地下茎を食べるさといもは山に自生するやまのいも(自然薯じねんじょ)に対し、里で栽培されることからこの名が。原産地は、インド東部からインドシナ半島。南方で利用されているタロイモも同じ仲間です。 日本への渡来は、稲作が始まった縄文時代後期より古いとされています。【名月に供える、きぬかつぎ】秋一番に出まわるのは、子いも用品種の石川早生。陰暦8月15日の月見は芋名月ともいい、皮ごとゆでた子いもを供えます。平安時代の女性のかぶりもの、きぬかつぎを思わせるので、皮ごとゆでたさといもを、俗にきぬかつぎとも。塩をふるだけの素朴な味わいです。 【いもの子を洗う】混み合った状態を「いもの子を洗うよう」とたとえるのは、かつては桶の中にいもを入れて棒でかきまわしながら洗ったことに由来します。■野菜図鑑■ 父は、サトイモのことをタイモと言っていた。8月7日の七夕の朝、サトイモの葉に溜まった滴を集め、願い事をした。ずいきという芋の茎は、油揚げと炊くとトロリとして美味しかった。今も時々使うが、余った芋は、植木鉢に植えて楽しんでいる。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2012年10月1日*落ち穂拾い*・・・・・・・・・・・・・・
2012.10.01
コメント(0)
全16件 (16件中 1-16件目)
1