2024年03月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-

久々青葉山ウォーク
3月30日(土)朝、家の窓から外を眺めると、いい具合の薄曇り、森で山野草の写真撮影をするには絶好のコンディションです。三居沢のほうは何度か歩いていましたが、こもれび広場を中心とする標高の高いエリアのほうはまだ歩いていませんでしたので、この日気合いを入れて歩くことにしました。前回の三居沢ウォーク(24日)での反省から、カメラボディはOLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIとRICOH GXR、レンズはM.ZUIKOの2本(12-40mmズームと45mm F1.8)、そしてRIKENON 50mm F2LとオールドZUIKOのマクロレンズ80mm F4を持って行くことに。そして三脚とLEDリングライトも忘れずに。強力な手ぶれ補正機構の備わったE-M1 Mark IIIは手持ち撮影、そして手ぶれ補正が効かないGXRはリングライトを着けた超どアップ専門で三脚とセットに、という目論みです。しかし、これだけの機材をリュックに詰め、また手に三脚を持って歩き回るのはけっこうしんどい。しかも、朝はいい具合の薄曇りだったのが、お昼から午後にかけてはすっかり晴れてしまってこの時期としては強い日差しが。これは想定外です。結論から言うと、リングライトの出番がほぼゼロ、むしろGXRでは拡張しない最低感度(ISO100)でも最高シャッター速度1/4000秒でも白飛びしてしまうほどの明るさでした。やっぱりNDフィルターが必要か?それともこのように晴天で強い日差しが当たるようなコンディションのときにはGXRを使わないようにするか・・・さて、今日のウォーキングのようすはどうだったかというと・・・3月24日(土)、もっとも標高の低い三居沢入口から入って周辺エリアを歩いた際の印象は、「カタクリの花がぜんぜん咲いていない」「セリバオウレンの見頃がまだまだこれから」「ナガハシスミレはつぼみすら見られない」そして「イワウチワのつぼみもなく丸い葉だけ」しかも数が少ない気がする・・・「ショウジョウバカマもまったく咲いていない、つぼみも出てない」という感じで、例年に比べてかなり出足が遅いと感じました。そして今日。こもれび広場から出発して歩くのはずいぶん久しぶりなので、どのコースを歩くかちょっと迷いましたがまずは、「チゴユリのみち」を回って一旦こもれび広場へ戻ったあと、「きいろいみち」を行き、疎林広場から「化石のみち」、「ヤマドリルート」を歩いて花木広場へ出て、「わんぱくのみち」を通ってふたたび「チゴユリのみち」からこもれび広場へ戻る、という長距離コースを歩く強行軍となりました。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROカタクリの花が咲いていました。道の脇にショウジョウバカマの花も。しかし背が低い。首(花茎)を伸ばす前に花が開くのですね。この2枚はマイクロフォーサーズのE-M1 Mark IIIとM.ZUIKOレンズの組合せですので、きれいにクッキリ写るのはあたりまえかもしれません。さて、GXRとRIKENON 50mm F2Lレンズの組合せではどうでしょう。RICOH GXR and MOUNT A12 + RICOH XR RIKENON 50mm F2L with PENTAX CLOSE-UP RING K No.1 (9.5mm)地面から直接咲いているようなショウジョウバカマの花をアップで。レンズ単体では60センチまでしか寄ることができないので、9.5mmの接写リングを入れています。近くへ寄ると、絞り開放では被写界深度が浅くなりすぎるのでF4に絞っていますが、15年くらい前のカメラと何十年も前のオールドレンズとの組合せでも十分使えるレベルの写真が撮れるみたいです。こちらも同じ条件で撮影したセリバオウレンの花。たいていは真っ白な花なのですが、ときどきこの写真のように黄色い花があります。「オウレン」も漢字では「黄連」。黄色いものが連なるからなのですが、これは根の話です。枯れているわけでもなく黄色いのは何が原因なのでしょう。
2024.03.30
コメント(0)
-

雨のち晴
3月29日(金)朝、傘なしでいけるかだめか・・・中途半端な雨降り。地下鉄に乗り、青葉通一番町駅で降りて外へ出ると、ギリギリ傘なしで歩ける程度に弱くなっていました。良覺院丁公園を通りかかったときは、花期を過ぎたサザンカとこれからつぼみが膨らむボケ、ボチボチ咲きはじめそうなスミレを観察。by OLYMPUS STYLUS XZ-2こちらは雨に濡れるボケの木。花が咲くのもあと少し?楽しみです。昨日の最高気温は12.9℃だった仙台ですが、今日の予想最高気温は昨日より6℃高い19℃。これは5月並みなんだそうです。予報通り、昼過ぎからは一気に青空が広がって、日差しも強くなり、気温がぐんぐん上がってきました。南風が強くなるとも言っていましたが、昼の時点では風はそれほど強くなかったです。雨上がりの片平丁・・・日当たりの良い石垣の隙間から首を伸ばして咲くヒメオドリコソウです。暖かい日差しを喜んでいるかのようです。雨が降っていたのがウソみたい。気持ちよいお昼の散歩を終えて、大学生協の売店(さくらショップ)でおやつでも買おうかと弾正(だんじょう)横丁を歩いて行くと、ちょうどさくらショップ前の桜並木周辺で何やら工事をやっているようでした。近くへ行って見てみると・・・なんと!by SHARP AQUOS Sense7弾正横丁の道路へはみ出していた桜の木の枝を、バッツンバッつん切っているではありませんか!かなり太い枝も、切り口がクッキリ見えています。これはなにか道路交通法上の問題でもあるのでしょうか。背の高いトラックなどの通行を妨げているとか・・・。これから開花に備えてつぼみを膨らませている(と思う)桜の木にとっては、なんとも大迷惑な剪定作業です。こうなってくると、過去の桜満開の頃撮った写真を引っ張り出してきたくなります。・・・が、なかなかみつからない。去年のシーズン中に撮った写真は、スマホ、XZ-2、E-M1 Mark IIIのライブラリを見てみましたが一枚も見つかりませんでした。さらに前の写真を探すしかないか・・・
2024.03.29
コメント(0)
-

昨日の雪がウソのように
3月27日(水)昨日は朝から雨が降り続き、昼頃からはみぞれ混じりになって深夜まで降り続きました。地面にはシャーベットのような積雪。朝のニュースでは、まだ3センチほど積雪があるといっていたので心配しましたが、家を出たときにはほとんど消えていて少し路面が濡れている程度でした。そして、今日の予想最高気温は13℃。連日、上がったり下がったり、しかも振れ幅が大きいです。緑水庵の庭園を外からちょっと覗いてみると、昨日の雨や雪のおかげで池に水が少し溜まっていました。良覺院丁公園では、ボケのつぼみが膨らんできていました。花が咲くまではまだもう少しかかりそうですが。お昼はあまり時間がなかったのですが、ほんの少しだけ片平周辺を小回り。放送大学宮城学習センターの北側、柳町通りに面した敷地の端に、シャクの葉らしきものがあるのを発見。by OLYMPUS STYLUS XZ-2シャクといえば、もっと暑い時期に咲き出すイメージですが、葉が出てくる時期については意識したことがありませんでした。今から葉を出して準備を始めているのか?
2024.03.27
コメント(0)
-

仙台の最高気温、昨日より14℃低いという予報
3月26日(火)昨日、仙台の最高気温はなんと18.9℃!外を歩いていると汗ばむほどの暖かさでした。しかし、今朝の天気予報では「昨日より14℃低い5℃」の予想でした。福島市はさらに落差が激しく、昨日より15℃低くなって5℃の予想。朝はそれほど寒くなかったなあ、と思ったら昨晩からどんどん一方的に気温が下がっていき、最高気温が真夜中の11.3℃だったようです。家を出るときは雨が降っていましたが、お昼にはシャリシャリしたみぞれになっていました。傘の上にどんどん溜まっていき、ズッシリ重くなってしまいます。雪が降っている状態での撮影では、必ず落ちてくる雪が写ります。シャッター速度が遅くなると、白い線として写ります。シャッター速度を上げると、静止して写ります。さて、どちらが良いだろう・・・と、急に気になり出しました。そこで、東北大学片平キャンパス内、学都記念公園の桜の木を入れた「引き」の構図で、一度試してみました。広角端6.0mm(28mm相当)の広角でF5.6まで絞り込み、ISO感度も800まで上げてシャッター速度を1/800秒になるように設定してレリーズ!すると、落ちてくる雪がほぼ静止して写りました。by OLYMPUS STYLUS XZ-2けっこうイイ感じかもしれません。ということで、その後しばらく、シャッター速度がいつもより速くなるような設定で撮っていたら・・・せっかく咲いた花に溶けかけのかき氷みたいなシャーベット状の雪が乗ってしまった良覺院丁公園のマンサク。マンサクの花と雪のコラボも望遠端24.0mm(112mm相当)で、ISO感度を高めにしてシャッター速度が速めになるよう配慮するとけっこうイイ感じの写真が撮れました。大満足です。
2024.03.26
コメント(0)
-

ヒョロッとしてポチポチと白い小さな花を咲かせる・・・シロイヌナズナ?
3月25日(月)昨日も日中は16.4℃まで上がってぽかぽかだった仙台ですが、今日もそれ以上の暖かさ(18.9℃まで上がったようです)でした。お昼に外へ出てみると、桜の木の下の地面を草が生えないように何らかの処理をしている(たぶん)場所のあちこちで、小さな白い花をポツポツ咲かせている背の低い野草が生えているのに気づきました。近寄って見てみると、タネツケバナのような花、そして細長い実。ミチタネツケバナか何かかな?・・・でもなにか違う。そうだ!葉のかたち。by OLYMPUS STYLUS XZ-2根葉(こんよう)(根出葉(こんしゅつよう)、根生葉(こんせいよう)とも)と呼ばれる「地上茎のきぶについた葉」のかたちが明らかに違います。Googleの画像検索で調べてみると・・・どうやらシロイヌナズナのようです。Wikipediaによれば、世界の広い範囲に分布しているみたいですが、日本では帰化植物として入ってきたようです。「岩場、砂地、石灰質といった土壌でも容易に生育することができ、・・・農耕地、道端、線路、荒地など攪乱された場所に広く分布するため、一般に雑草とみなされるが、競争力が低く、背丈も小さいため、有害雑草には分類されない。」驚異とはみなされていないようですね。しかしこのような生命力の強い植物だからこそ、「草も生えない」こんな場所で伸び伸びと花を咲かせることができているのでしょう。
2024.03.25
コメント(0)
-

超久しぶりの三居沢ウォーク/いわゆるOMベローズ望遠マクロレンズはどう扱うべきか
3月24日(日)3月も最終週に入ろうかという時期になってきました。年が明けてから、早々に(1月8日)三居沢をちょっぴり歩いたくらいで「青葉の森緑地」を歩いていません。もうそろそろセリバオウレンの季節だなあ・・・と考えたら何としてでも三居沢へ行きたい衝動に駆られました。そこで、昨日からどんな機材を持っていこうかどのスポットを重点的に見ていこうか狙う被写体は何にしようかと、いろいろ考えを巡らせておりました。そして結局持って行くことにしたのはRICOH GXR(レンズユニットでRIKENON50mmF2Lレンズ一本)PENTAX接写リングKセットのうちNo.1 (9.5mm) とNo.2 (19mm)・・・足せばNo.3 (28.5mm)と同等になるからOLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIM.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROM.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8MEIKE EXTENSION TUBE 10mm, 16mm・・・50センチまでしか寄ることのできない45mmF1.8レンズの近接撮影用さらに、もしかしたらという淡い期待でOM ZUIKO 1:1 AUTO MACRO 80mm F4OM AUTO EXTENSION TUBE 65-116mmの等倍マクロセットもリュックの奥底に忍ばせて行きました。デジタル一眼レフを手に入れて、中古やオークションでマクロレンズを手に入れ、徹底的にアップで撮ることを追求した時期がありました。今回持ち出した80mmマクロレンズもそのひとつなのですが、無限遠まで対応している50mm、135mmとは違ってかなり撮影距離、拡大率の範囲が限定されてしまうので、それらと比べてどうしても出番は少なかったです。おそらくいちばん最近使ったのは、ちょうど2年前、2022年3月27日にやはり三居沢へ行ったときです。そのときは気合いを入れて三脚を持っていきましたが、撮影倍率優先で撮影しようとしたのでエクステンションチューブの伸び縮みやヘリコイドは固定して三脚ごと動かしてアングルを決めたりピント合わせをしたりしていたようです(忘れてました)。カタクリのつぼみを撮ってみたら、あまりにもどアップすぎて2枚だけ撮ったところですぐ交代・・・ただ、セリバオウレンの花のアップではさすがの描写でした・・・というようなこのときの良い印象があって、今回の久々持ち出しということになったわけです。2年前の経験から、効率よく撮影するためにはやはりマクロスライダーが必須だという結論に達していたはずなのですが、今日はそんなこともすっかり忘れて三脚すら(まあいいか)と置いていく始末・・・よく考えれば、かつてフォーサーズ一眼レフ機をメインで使っていた頃はカメラは三脚に固定し、光学ファインダーを覗き込むことはなく、ほぼすべてライブビューを利用していました。アングル決め、フレーミング、ピント合わせはすべて背面液晶パネルのライブビュー画面を見ながら、というスタイルでした。高感度に設定するのを避けて(MAXでもISO800までと決めていた)、リモートスイッチを使ってそっとレリーズ、でも風のせいで被写体ブレ頻発、という感じ。マイクロフォーサーズ機に移行してからは、ISO感度もガンと上げ(最近では躊躇なくISO6400まで上げます)、手持ちで電子ファインダーを覗き、その中で任意の場所を一部拡大表示させたりしながらピントを合わせて撮るスタイルになっており、またそれほど撮影倍率や撮影距離にこだわらない絵作り(周囲の状況も入るように撮る)を心がけるようになってきていたので、2倍(相当)、4倍(相当)の超接近マクロ撮影で(のみ)活躍の場が与えられるようなこのレンズの出番はますます限定されてしまうのかもしれません。しかし、このレンズならではの被写体や撮影のシチュエーションは、探せばまだまだあると思いますのでそのときには大いに活躍してもらおうと思います。・・・ということで、今回はせっかく持って行ったものの、一度もリュックから取り出されることはありませんでした。やはりライカ判換算160mmの望遠マクロ、2倍相当の超どアップで、セリバオウレンの花が画面いっぱいに写りますが、逆に「セリバ」もバックに入るところまで引くことができませんので、より焦点距離の短い、あるいは距離を取って撮影可能なレンズと組み合わせないと終始どアップばかりということになってしまいます。専用のクローズアップレンズ(フィルターネジにねじ込んで装着する虫眼鏡レンズ)もありますが、これ以上のどアップは私のフォトスタイルでは需要がありません。でも、写りそのものはやはりさすがという感じ。いまのデジタル用マクロレンズに負けないクオリティなので、ぜひ機会を見つけて使ってやりたいです。カメラボディをもうひとつ用意して、いわゆるOMベローズマクロレンズ専用にしてしまい、レンズは外さずマクロスライダー、三脚に常時固定しておくというスタイルも良いかもしれません。それならば、フラッグシップ機は必要ないのでちょっと前のE-M5 Mark IIなどを中古で買う、という手もありかな?今日の三居沢ウォークは、いつもの定番、駐車場から一本道を上って行き、途中で森の花園コースへ入ります。アップダウンのあと、またメインロードへ戻る手前のイワウチワエリアが最初のターゲット。でも、まだ時期が早かったようで、つぼみすら出ていませんでした。それにしても、なんだかいつもより葉の数が少ないように感じました。大丈夫だろうか・・・メインの散策路に合流したら、また駐車場に向かって戻ります。するとセリバオウレンがいい具合に咲いている絶好のフィールドが数十メートルにわたって広がっています。ちょうど咲きはじめた良いタイミングのセリバオウレンの花があちこちに。しかし、ちょっと前からしっかりと日が照ってきて、想定していた薄暗い中での撮影とはいかなくなってしまいました。RIKENON 50mm F2L、M.ZUIKO 45mm F1.8を開放で使うことが困難な状況に。昼過ぎとはいえ、まだまだ低い太陽の光が横から差し込んできて被写体を明るく照らしてしまいます。NDフィルターが必要なのか?と、初めて心によぎりました。なんとかRIKENON, M.ZUIKOの「単体では寄れない」レンズにエクステンションチューブを入れてアップで撮るセリバオウレン撮影は一通りこなすことができました。あまり時間がなくてちょっと物足りない感はありましたが、まずまず。LEDリングライトも思ったほど出番がないほどの明るい状況でした。by RICOH GXR+MOUNT A12, RICOH XR RIKENON 50mm F2Lこのどアップ写真は、50mmレンズにPENTAX接写リングKのNo.3 (28.5mm)を入れて撮ったものです。日陰だったのでリングライトを使用しています。こちらはもう少し引きで撮るために接写リングをNo.3からNo.1(9.5mm)に取り替えて接近は控えめに撮影したものです。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III, M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8こちらは手持ちの機材の中では最新のデジタル用レンズ、45mm F1.8で撮影したものです。マイクロフォーサーズ機で撮ると90mm相当の中望遠レンズとなります。寄れるのは50センチまでですので、もっと寄りたい場合はエクステンションチューブを使用することになります。これからカタクリ、イワウチワ、各種スミレ、ショウジョウバカマなど、これから続々被写体となる花のシーズンがやってきます。今年は何回、山に行けるかわかりませんが、いつでも対応できるよう心の準備をしておこうと思います。帰ってきてから、NDフィルターについてちょっと調べてみました。どれくらいの減光がいいのか、ちょっと検討がつかなかったのですが、なんと「可変NDフィルター」なるものが存在するということを初めて知りました。偏光フィルターのように2枚のガラスを回転させて調整できるものだそうです。こういうフィルターをひとつ、調達してもよいかもしれません。XZ-2には内蔵NDフィルターが装備されているので、すでに便利に使っています。開放F値の明るいレンズを絞らずに使いたいときには必須かもしれません。※2年前にOM 80mm F4マクロレンズを持ちだして三居沢に出かけたときのはなしは、この日記ブログで詳しく書いていました。2022年3月27日(日)「OLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIとOMオールドマクロレンズで青葉山へ」本来ならば、写真・カメラ関係中心に記事を上げているGoogle Bloggerのブログ「shinodak-photostock」で書くべき内容だったかもしれませんが・・・さて、話題は少し変わりまして・・・現在所有しているOMマクロレンズのうち、望遠系の2本OM ZUIKO AUTO-1:1 MACRO 80mm F4OM ZUIKO AUTO-MACRO 135mm F4.5について、マイクロフォーサーズ機で使用する場合には、焦点距離が2倍相当になるので、それぞれ160mm、270mmというけっこう強烈な?望遠マクロ領域となってしまうところが使いづらさに繋がっているのではないか、と最近感じています。135mmマクロレンズは、無限遠までいけるので、ときどき青葉の森歩きに同行させるのですが、やはり被写体との距離が離れがちになってしまうため、十分なスペースが確保されていないと、向きや角度、距離(つまり撮影倍率)に制限がかかってしまいます。80mmマクロレンズの場合は、撮影距離、撮影倍率の制限がさらに厳しいので、なかなか出番を与えてやることができない。それならばいっそのこと、本来の画角で撮影することができる、いわゆるフルサイズ機で使うというのはどうだろうかと考え始めました。これらMF望遠マクロレンズ専用機として使うと割り切れば、基本は三脚に固定し、マクロスライダーも活用することになるので、求められる機能としては、・離れたところからもフレーミングなどを確認することが容易なように、バリアングルパネルが装備されている・ピント合わせが容易なように、画面上の任意のポイントを自在に拡大して表示できるこの2点が満足されれば、正直何でもいいということになります。候補として考えられるのは、Canon RPSony α7Cです。Canon RPは、以前一度検討してみたことがありますが、中古で10万円前後くらい。操作性については未知数です(Canon機を使ってみたことがないので)。Sony α7Cは、中古でもあまり安くならず15万円前後くらい?操作性はこちらもまったくわかりません。いずれにしても、たった2本のOM ZUIKOレンズのためにそんなお金をつぎ込む価値があるか否か・・・また結局悩むだけで終わりそう?
2024.03.24
コメント(0)
-

気合いを入れてGXRを持ち出したのに・・・
3月23日(土)今日は土曜日。今年に入って、まだRICOH GXRの出番がたったの1回だけ(3月10日)なので、今日はどんより曇った薄暗い天気でもあることだし、RICOH XR RIKENON 50mm F2Lレンズ向きなコンディションだと思いました。いちおう、OLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIとM.ZUIKOレンズ、OMレンズのセットもリュックに入れて片平へやってきました。お昼に行う作業の前に、1時間半ほど時間が取れそうだったので、まずはGXRで片平周辺を歩きながら撮影を・・・と考えました。それならリュックは不要、カメラだけ持って出れば十分、と思ったのですがそれが失敗でした。ピークを過ぎた東北大学金属材料研究所(金研)裏の白梅、放送大学宮城学習センターの庭に回ってハハコグサ、そして隅の方へ行ってツバキの花を撮っていました。裏側(庭の中側)には赤い花、外側(柳町通りと片平丁通りに面した側)には斑入りの花が咲いています。昨日みつけた、落ちた花はまだきれいな状態を保っていました。昨日、XZ-2で(道路側、柵の向こうから)撮ったときは思うような写真が撮れなかった印象があったので、近くへ行って撮るのはもともと狙っていたわけですが。悩んだのは、RIKENON 50mm F2Lレンズの最近接撮影距離。このレンズは60センチまでしか寄れません。でもGXRのAPS-Cセンサーでは、ライカ判の75mm相当という中望遠の画角・・・接写リングを入れるか入れないか・・・悩んだ末、一旦いちばん短いリング(No.1, 9.5mm)を入れて試してみることに。すると・・・by RICOH GXR+MOUNT A12, RICOH XR RIKENON 50mm F2Lちょっと寄りすぎで落ちた花だけがアップになってしまいました。それでは、とリングを外して60センチギリギリの距離でピントが合うか試してみます。バックのまだ木について咲いている花も入る良いアングルを探し、後ろに下がって柵のキワまで持って行けば、とてもイイ感じに撮れる!よしっ、とピントを確認してからシャッターを押した瞬間!パシャッとシャッター幕が開いて閉じる音がするはずのところ、「パ」で終わり、「バッテリーを交換してください」のメッセージ。なんとバッテリー切れです。良いところなのに!交換か・・・あっ!予備のバッテリーはリュックのポケットに入れたままだった。ちょっとの時間だからカメラだけ持って出ればいい、と考えたのが間違いでした。バッテリーのことに気づいて、それだけ上着のポケットに入れていればそれで事足りたわけではありますが・・・結局、とりあえずその場は断念。一旦戻って確認してみると、やはり最後のショットは記録されていませんでした・・・残念。満充電していたバッテリーに交換して、午後にあらためて出発。リベンジは果たせました。ランチのあと、店を出ると・・・雨が降ってました。ちょっと傘なしでは外を歩けないくらいの降り。ということで、折りたたみ傘を買いに東京洋傘へ向かいます。傘をゲットして、定禅寺通りを西へ。そして西公園通りを南下して、櫻岡大神宮の裏を回り、なだらかな石段を降り、また通りを上って行きます。石垣の石の間からホトケノザ、ヒメオドリコソウが「ガオーッ」と花を咲かせていました。ランチ後、ほんとうは仙台城三の丸へ行ってネコノメソウを狙おうと思っていたのですが、それも叶わずリュックに入れたE-M1 Mark IIIは今日一日を通じてまったく出番なし。GXRのほうも、防水ではないので雨が降り出してからは大事を取ってリュックから取り出すことはありませんでした・・・とはいえ、数少ないGXRの出番、十分に活かすことができた一日だったと思います。
2024.03.23
コメント(0)
-

街中のふきのとう
3月22日(金)昨日はおなかの調子が悪かったので、外を歩いていてもカメラを取り出してなにかを撮影するという気になれず、ほとんど写真がありませんでした。仙台高等裁判所のふきのとうも、いくつか咲き出していたのを確認してはいたのですが写真を撮っていませんでした。今日は、昨日よりは少し調子が戻ってきたので朝の出勤時に通りかかった「ふきのとうスポット」で、少し撮影しました。1週間の出張で仙台を離れていた間に、ずいぶん進みましたね。by OLYMPUS STYLUS XZ-2でも、去年の今ごろと比べると、ちょっと遅い?というか数がずいぶん少なくなった印象です。とくに、道路に近い場所では、去年は石垣のキワまでびっしりだったのに、今年はかなりまばらです。去年と今年とで何が違ったのでしょう?放送大学宮城学習センターの庭(?)、片平丁の通りに接する柳町通りとの南側角には、立派なツバキの木があります。赤い花と紅白の斑入りの花。手前に、きれいな斑入りの花が落ちていました。柵の外から覗き込むようにXZ-2で撮影してみましたが、なんだかイマイチ。でも、時間がなかったので1枚だけ撮ってあきらめました。お昼には、同じ放送大学宮城学習センターの庭で先日見つけたハハコグサをチェック。前に見たときは、花が埋もれるようになっていましたが、今日見てみると私がイメージしていたハハコグサに近い状態となっていました。ナツズイセンの葉もかなりニョキニョキと伸びていました。(暖かくはないですが)日が照って良い天気だったからか、片平丁小学校の角にいるイヌノフグリの花がたくさん開いていました。もう、今までにもたくさんの花が咲いたので、そろそろ「ふぐり」がいい具合になっているのではないか、と探してみたら、手前で撮影しやすそうな「ふぐり」が見つかりました。でも、XZ-2ではなかなか思うように撮れませんでした。週末にでも、E-M1 Mark IIIやGXRでガッチリ狙っていこうと思います。
2024.03.22
コメント(0)
-
朝、クリニックへ
3月21日(木)昨日の午後からおなかと熱で具合が悪くなりました。寝る前の体温は37.9℃。おなかがムカムカしていたので何も口にせず、早めに就寝。しかし、熱がもう少し上がったような感じ、そしておなかは胃のあたりが痛くなってきた・・・明日は休み明けの出勤日ですが、どうなるか。あまり寝ることもできず朝になりました。熱を測ってみると、36.9℃。ちょっと下がりました。でも、おなかの具合悪さは続いていたので、3年くらい前にコロナの検査をしにいったことのあるクリニックへ。血液検査もしてみたのですが、どうもウイルス性の胃腸炎らしいとのこと。胃の薬を出してもらってひとまず安心。2時間ほど遅れて出勤することに。お昼はまだおなかの調子が良くなかったので、売店でパンをひとつ、そしてスープ春雨を買って、それをランチに。早くもとの調子に戻ってくれればいいですが・・・
2024.03.21
コメント(0)
-
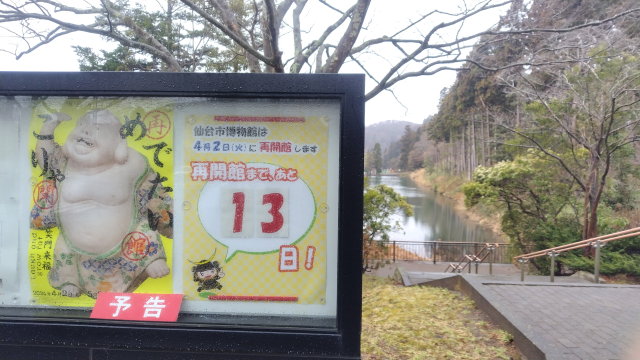
雪交じりの寒い一日
3月20日(水)今日は春分の日、つまり休日です。先週、20℃越えの東京にいたのに、仙台へ戻って来た途端、強風と低温。この気温差には、身体もびっくりです。朝は薄暗かったものの、まだ雨は降っていませんでした。さて今日はどのように動くか・・・仙台城三の丸のネコノメソウチェックか、三居沢のセリバオウレンチェックにでも出かけようかと考えていたのですが・・・真冬並みの気温、冷たい強風に加え、ときおり雪交じりになる冷たい雨が、やる気をどんどん削いでいきます。それでもお昼過ぎ、三の丸方面へ歩いて行きました。by SHARP AQUOS Sense7長沼(仙台城のお堀)に沿って南へ歩き、三の丸へ上がって行く入口付近で、ネコノメソウがスタンバっているのを確認しました。花はまだもう少し先のようですが。しかし、このあたりも以前に比べてしっかり除草作業が行き届くようになり、かつてのような野草天国ではなくなりました。ネコノメソウもかなり少なくなった印象です。午後になって、なんだかおなかの調子が良くないなあ、と思っていたら寒気もしてきて(ちょっとこれはヤバいかも)・・・家に帰って体温を測ってみたら、なんと37.9℃!こりゃダメだ、と早めに寝てしまいます。明日になっても良くならなければ、近くのクリニックへ行ってみよう・・・
2024.03.20
コメント(0)
-

ロングラン出張もいよいよ最終日
3月19日(火)本八幡駅前のカプセルホテル、レインボーを拠点にして、東京(金町、西新橋)や千葉(津田沼)へ行ったり来たりする約1週間の長期出張も、今日が最終日です。最後のミッションは、津田沼の千葉工業大学で開かれている学会での発表です。宿をチェックアウトして荷物をすべて持ち、JR総武線で津田沼へ。午前中、自分の発表も含めて学会に参加し、お昼に終了。3日間の学会ですが、まともに参加したのが今日だけだったので、最後の最後にチラッと企業の知り合いの方と短い挨拶を交わしたあと大学の同僚と出会い、一緒に東京駅へ移動しました。ランチをどうするか、ちょっと迷ったところで「改札を出てラーメンでも食べますか」ということになり、八重洲側から外へ。地下に入って北側の旭川ラーメン「番外地」(こちらは先日おじゃましました)の前を通り、南側の旭川ラーメン「遊亀亭(ゆうきてい)」へ。彼はこのお店を知らなかったようで、すぐそばのラーメンストリートみたいに混雑もせず、おいしいラーメンが食べられるこのお店を気に入ってくれたようでした。食後、改札を入る前に大丸へ寄って「まい泉」のひれかつサンドと海老カツサンド購入。いつもなら駅ナカの地下で買うのですが、いま工事中なので外で買うしかありません。改札を入り、まだ新幹線まで時間があるなあ・・・と、カフェで時間つぶししようかと探してみても、落ちつけるカフェはなさそう、なんて言っているうちに新幹線の発車時刻が迫ってきました。結局そのままホームへ上がり、はやぶさの指定席で仙台へ帰ります。指定席は、いつもなら通路側にとるところですが、今回は窓側の席に。それは、昨日の会議(進捗報告会)が実は今日もやっていて、最後の締めのところだけでもオンラインで聞こうと思ったからです。席に着いて早速PCを取出し、ネットにつないだら・・・「そういうことで、・・・」と、肝心なはなしは聞き逃してしまいました。もう少し早い時間の新幹線にしておけばよかったか?1時間半後、仙台駅到着。ホームに降りると、やはり東京・千葉とはちがって肌寒い。後ろで「寒~い!」と言ってるお姉さん方。なんとか無事に用務も済ませて戻ってくることができました。
2024.03.19
コメント(0)
-

学会の合間に千葉から東京へ
3月18日(月)千葉県の津田沼駅前にある千葉工業大学で現在開催中の学会、今日は2日目です。しかし、東京で会議があるため、今日はそちらのほうへ。総武快速線で、東京へは30分ほどで行けます。東京駅から歩いて皇居の二重橋などを眺めつつ、西新橋のほうへ向かいます。by SHARP AQUOS Sense7けっこう風が強い。お堀端の柳が激しくなびいていました。午前中、私が入っているサブグループの報告。私の持ち時間は20分、発表は15分となっていますが、先週事前に行ったサブグループ会議では大幅な時間オーバーだったので、心して話します。すると、なんとピッタリ15分で話すことができました。よかったよかった。ほかのグループメンバーの報告も終わり、ほかのサブグループからの報告もつつがなく進んで、夕方にはささやかな懇親会。ささやかすぎたからか、現在は企業に勤める学生時代の研究室の後輩に、「ぜんぜん食べられなかったから、どこかへ行ってもう少し飲みましょう」と誘われました。明日はまた津田沼で学会発表がありますが、準備は出来ているのでとくに慌てることもない。じゃあ、行くかと。四半世紀前(!)の学生時代の話で盛り上がり、そして明日の学会の話をすると、「○○さん(やはり同じ研究室出身)も来てますかね」と、へんな雲行きに。電話かけてみます・・・出た。でももう宿に戻って寝ていたみたい。それでも出てきてくれました。津田沼駅前で飲み始めたのですが、たしか店に入ったのは21時半くらいだったはず・・・が、気づけば0時前になっています。調べてみると、23時50分の電車を逃すと帰れなくなる!ということで、なぜかダッシュで駅へ急ぐことになってしまいました。
2024.03.18
コメント(0)
-

上野国立博物館の中尊寺展、4度目のチャレンジでようやく
3月17日(日)今回の出張では、隙を見て3回上野に赴き、国立博物館の「中尊寺展」にチャレンジしたのですが、いずれも断念していました。今日はラストチャンス。今日から始まる学会は、夕方の会議に間に合えばよいので、午前中は時間が取れます。到着したのは8時50分頃。開館は9時半なのですが、すでに並んで待っている人が。私は12番目でした。その中には前売り券をすでに持っている人もいますから、かなり先頭集団に食い込んでいると思います。みるみるうちに行列は伸び、係の人に案内されて中へ入ったときには相当な人数に。「当日券をこれから購入する方は列の右へ」と言われたので出たら、前から4番目になりました。そしてチケット売り場のほうへ誘導され、自動販売機の前の先頭に立つことができました。時間が来てシャッターが開き、急いでチケット購入、1,600円なり。by SHARP AQUOS Sense7人混みを離脱すると、前売り券を持っている人たちの列の後ろにつくように案内されました。いよいよ敷地内へ入って玄関前にまた並んで待ちます。10時頃に先頭の人たちが入り始めます。ほどなく私も中へ。本館の建物は大きいですが、中尊寺展の部屋はひとつだけです。部屋へ入ると大きなディスプレイに、最近8Kでスキャンした金色堂内部の映像がブワーッと出ています。じっくり鑑賞。壁にはパネル、そして部屋の中には金色堂内に安置されている33体の仏様のうち真ん中の11体が、ガラスケースに入れられて立っています。正面、左右、そして背面もじっくり鑑賞することができます。光背は、横に寝かされて展示されていました。金色堂の模型も。これは写真撮影OKとのことでパシャパシャ撮りました。ひとつひとつじっくり、説明文も読みながら見て回ったのですが、出てきて時計を見ると10時20分・・・なんと、たった20分で終わってしまった。博物館の常設展も眺めて外へ出ると、ちょうど昼時。東京駅へ行ってヤエチカのラーメン屋さん(旭川ラーメン 番外地)でランチ。総武線快速で津田沼へ移動し、学会会場の千葉工業大学へ。受付をしてから会議に出席・・・という流れでした。
2024.03.17
コメント(0)
-

学会と学会の合間の一日
3月16日(土)昨日でひとつめの学会が終わり、明日からはもう一つの学会が始まりますが、今日はそのはざまでとくに用務のない一日です。これはチャンス!いけそうなら上野の国立博物館でやっている中尊寺展を見たいな、と思ってまずは上野へ。実は、この出張で東京入りした初日(移動日)にもチャレンジしてみたのですが、午後だったからか「混雑しています」「30分待ち」と。昨日もやはり午後にトライしてみましたがこんどは「40分待ち」。やっぱり断念。三度目の正直!と、今日は朝イチで宿を出るつもりでしたが、コワーキングスペースである宿のラウンジでちょっとデスクワーク・・・とやっているうちに10時になってしまいました。お昼前に到着して見ると、「60分待ち」になってしまっていました。またも断念か・・・と、それなら新宿へ行ってOMシステムプラザだ!そうとなれば急ぐ必要はない。いったん東京駅へ行って「まい泉食堂」でお昼をいただいてから中央線の快速でドーンと新宿へ行こう。急遽ですがプランが決まったので一気に余裕が出ました。東京駅に着いて、改札内の「まい泉食堂」へ行ってみると、まだ時間が早かったので空いています。やったーふつうのトンカツやかつ丼ではおもしろくないよな・・・とメニューを見てみると、「塩ヒレかつ丼」なるものがあるのを見つけ、即決。ちょっとスパイスが入った塩が振ってあるカツの下には温キャベツ、塩昆布がパラパラとまぶしてあります。これはほかではなかなかないメニューだ。奥の突き当たりのカウンター席に案内され、提供を待っているととなりの席にボリューム満点のサラリーマン風の兄さん。カツカレー大盛りをオーダーしていました。塩ヒレかつ丼が来て、by SHARP AQUOS Sense7じっくりゆっくり味わっているとしばらくしてお隣のでかいカツカレーがドン。それをあっという間に平らげてさっさと去って行きました。見掛け通りの食いっぷりだなあ、と感心しながら味わってランチ終了。新宿駅へ移動して、西口界隈をちょっと歩き、OMシステムプラザへ。ダメ元で長年愛用している「高級コンデジ」OLYMPUS STYLUS XZ-2のホットシューカバーが壊れたことを訴えると、「あるかもしれない」と、E-M1初代のカバーとE-PL7のカバーを持ってきてくれました。E-M1のほうはうしろの端子フタが浮いてしまうのでダメ、E-PL7用のフタはバッチリでした。・・・というか、型番もXZ-2用と同じMCC-1。ただし、XZ-2用には黒なのですが、E-PL7用のカバーは白かシルバーしかないとのこと。しかも、白は110円なのに対し、シルバーは倍の220円。いちおう両方装着してみて眺めると、やっぱり白はプラ感満点で、チープです。シルバーがカメラ本体とマッチするかちょっと心配でしたが、装着してみるとなかなかいい具合です。倍額を奮発!(?)してシルバー購入。今日はこれだけでも満足です。ちょうど向かいに銀座ルノアールのカフェがあるので、そこで一服。となりにおじいさん二人組がやってきて、やたらとOM-1の中古価格の話題で盛り上がってました。こっちだと3万円安いとか、延々OM-1の値段の話。まあ、そういうあれこれで悩んだり考えたりするのが楽しい、というのはありますが。宿に戻って、夕食は鶏唐揚げ定食980円。そのあと、となりのお兄さんが大生ビールを頼んだので、よしこっちも!と大生を頼んだものの、目の前にダンッと置かれたのを見だらほんとうに大きくてちょっと後悔しました。
2024.03.16
コメント(0)
-

葛飾のおみやげといえば・・・?
3月15日(金)本八幡駅前のカプセルホテル、レインボーを拠点に約一週間、学会や会議をこなす出張、今日は3日目です。昨日に引き続き、東京理科大学葛飾キャンパスで開かれている学会の会場へ。自分の発表は昨日終わっているので今日は気楽に聴講、情報収集メインです。午前中聴講したあとお昼には、今年からスタートする研究会関連の会議。午後は時間があったので、京成柴又駅で降りて帝釈天参道へ。出張のおみやげに草団子を、と思ったのですが・・・うすうす感づいていましたが日保ちしない。「明日中には食べてくださいね」と言われてしまったので、おみやげ断念。京成線で京成八幡駅まで戻ってきて、まっすぐ宿へ戻るのももったいないな・・・と、京成八幡駅とJR本八幡駅のあいだにある「アンジュールカフェ」(Googleマップ)で休憩。by SHARP AQUOS Sense7この出張でいろいろなカフェに入り、コーヒーやケーキをいただきましたが、なかなかベイクドチーズケーキにありつけなかったので、ネットで調べてベイクドチーズケーキが食べられそうなお店を探したというわけです。このお店のチーズケーキは、好みの「かため」なしっかりベイクド。コーヒーはサラッと軽めで、深入りが好きな私としては、ちょっとインパクトがうすめな感じでした。でもそのあたりはそれぞれの好みですね。店内に流していたBGMの選曲がどれも私の嗜好にマッチしていたので、Googleマップの口コミに書いたら、オーナーから返事が来ました。宿に戻って風呂に入り、夕食は豚しょうが焼き定食980円をいただいたあと、生ビールと期間限定の海老から揚げで締めて就寝です。
2024.03.15
コメント(0)
-

本八幡駅周辺にて
3月14日(木)今日は3日間開催される学会の中日。自分の発表も行い、会場をあとにして本八幡駅へ戻ってきました。駅の北側、京成八幡駅前にある「イデカフェ 京成八幡駅前店」でカフェタイム、by SHARP AQUOS Sense7そして夜は本八幡駅の南側にある焼き鳥屋さん「鶏亀(とりき)」でちょっと贅沢な?夕食。
2024.03.14
コメント(0)
-

千葉県、本八幡駅前のカプセルホテル「レインボー」一年ぶりの長逗留
3月13日(水)3月といえば春の学会シーズン。今年も行きます春の学会。去年のちょうど今ごろ、やはり春の学会参加などのため千葉へ出張していました。そのときに宿泊したのが、今回もお世話になる「カプセルホテルレインボー 本八幡」です。サウナが売りの宿。by SHARP AQUOS Sense7チェックインしてすぐに大浴場へ。サウナは入りませんが、温・冷・激冷のお風呂のうち温と冷(27℃くらい)に入りました。このカプセルホテル、館内にデスクワークができるラウンジがあります。電源は勿論、仕切られたデスク、Wi-Fiと、作業するのにはバッチリの環境です。今回はモバイルディスプレイも持ってきました・・・が、コンセントの口が2つしかない。ひとつはPC、もうひとつは備え付けの照明スタンド・・・すると、ディスプレイ用の電源が確保できない。USBポートが用意されていないのにUSBから電源をとる照明がついたデスクもあるので、持ってきたUSB-Aポートふたつ、USB-Cポートひとつを備えたACアダプターでPCと照明の電源を確保すれば、ひとつ余ったコンセントプラグの口をモニターに充てることができます。窮屈なビジネスホテルより安く泊まれるし、寝るときだけカプセルに収まりますがそれ以外は自由に館内をうろうろでき、くつろいだり大浴場を楽しんだり食事や晩酌をしたり、そして必要ならばリモートオフィスばりにデスクワークもできる・・・こんな良い環境はない、と思うのです。
2024.03.13
コメント(0)
-
一番町の金港堂が4月30日に閉店というニュース
3月12日(火)河北新報の速報サンモールにある金港堂本店が、ビルの老朽化などを理由に4月30日で閉店するということです。本店ビルは1966年完成のものだったんですね。このビルは5月以降に解体され、本社機能を市内の別の場所に移すとのことですが、どこへ移るんでしょうか。同じ並びにあった丸善のビルはずいぶん前に解体されて、今は駐車場になっていますが、金港堂のビルを解体したあとはどうなるのでしょう。新しいビルが建つのか?本店のほかに、県内には泉パークタウン、石巻、大河原に3店舗あるそうで、そちらはこのまま営業を続けるみたいです。小説の文庫本なども、電子書籍を読むようになる前はよくここで買っていましたが・・・残念です。
2024.03.12
コメント(0)
-

震災から13年
3月11日(月)今日は3月11日。2011年に起きた東日本大震災から13年目を迎えました。数日前から、世の中「震災から13年」ムードがあちこちで伝わってきています。あの日は、昼休みに当時霊屋橋近くにあったクッキー屋さん「KENT(けんと)」でクッキーを買い、3時のコーヒーブレイクを楽しむ予定でしたが、3時が待ちきれず2時半頃からコーヒーを入れて、クッキーを一枚、そしてコーヒーを・・・というところで地震、というような流れでした。なので、3月11日は「KENTのクッキーをいただく日」みたいになっていました。霊屋橋近くのお店は数年前に店じまいしてしまったので、今は一番町のお店へ行かないとクッキーが買えないのですが、今日もお昼にサンモールへ行ったついでにクッキーを買ってこようと考えていました。しかし、サンモールは通りかかったものの大町のほうへ流れてラーメンのランチ、そのまま戻って来てしまったので、代わりに大学生協売店(さくらショップ)で別のクッキーを買ってくるという当初の目的からの逸脱。by SHARP AQUOS Sense7さらには、2時半からコーヒーを入れて2時46分のそのときを迎えようと考えていたのに、うっかり3時になってしまっていました。大失態です。グダグダな13年目・・・
2024.03.11
コメント(0)
-

今年初出動のGXR
3月10日(日)RICOH GXR長年愛用しているカメラではありますが、このカメラを持ち出して何かを撮影した最後は、なんと去年(2023年)の12月2日。今年に入ってからは一度も出番なしです。そんなこともあり、今日の散歩のお供は当初OLYMPUSのミラーレス一眼機、OLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIにしようかと考えていたのですが急遽変更して、RICOH GXRにsmc PENTAX 24mm F2.8とRICOH XR RIKENON 50mm F2L、そしてPENTAX 接写リングKのNo.1(9.5mm)と2(19mm)という装備で出かけることにしました。片平キャンパスの片隅(日当たり良好の一等地)でオオイヌノフグリやオニノゲシ?、ヒメオドリコソウが咲いているので、まずはそれらで肩慣らし。オオイヌノフグリは、厄介者の外来種ということを知って以来なかなか撮影意欲が湧きません。今回もスルーしてしまいました。久々のGXR、今日の初レリーズは、ノゲシ?オニノゲシ?の花。by RICOH GXR+MOUNT A12, smc PENTAX 24mm F2.8ノゲシは在来種、オニノゲシは外来種です。ノゲシと比べて、オニノゲシは「葉が硬くて光沢がある」「葉の縁が刺々しい」「葉が茎を抱く」葉を触ってみれば、その固さ具合からある程度わかりそうですが、このときは写真に撮っただけで触らなかったのでよくわかりません。触っておけば良かった・・・ヒメオドリコソウは、昨日もそうでしたがやはり首を縮めて寒そうにしているように見えます。24mmレンズ(ライカ判の36mm相当ですが)は、単体で25センチまで寄れますが、接写リングを入れることによりヘリコイド繰り出しに下駄を履かせるかたちとなり、(ムリヤリ、ではありますが)さらに接近しどアップで撮影することが可能です。PENTAX接写リングKのいちばん厚みのないNo.1(9.5mm)を装着して撮影したのが上の写真ですが、小さい上に寒さのためか背も低い地面すれすれ高さの花を、大迫力で撮影できました。絞りはF2.8開放ですが、写りはけっこうシャープでボケ具合もちょうど良い。撮影体勢が苦しくてたいへんでしたが、その甲斐ありました。ちなみに、この接写リングNo.1を28mmレンズに装着すると、ライカ判で約1/2倍の接写になるということなので、APS-CセンサーのGXRマウントユニットでは1/2×1.5=約3/4倍相当以上の接写ということになる?極端なアップでもないほどほどの拡大率で、被写体にかなり接近するという難点を除けばかなり使いでのある組合せかもしれません。でも、たいていは単なる広角レンズとして使うことが多いので、まあ25センチまで寄ることができれば十分、というケースがほとんどですが。by RICOH GXR+MOUNT A12, RICOH XR RIKENON 50mm F2L片平丁小学校の西南角、歩道に面して低い石垣があり、そのあいだにイヌノフグリが根を張り、小さな花を咲かせていました。ここは日当たりが良く、しかもその日光を遮るほかの植物がほとんどいないので、茎を立ち上がらせることができないイヌノフグリにとっては絶好の一等地といえるでしょう。道を歩いていてもすぐ目にとまるオオイヌノフグリの花と違って、色も派手ではないしとにかく小さいので簡単に見つけることはできませんが、この場所は数少ないイヌノフグリ撮影ポイントです。レンズをRICOH XR RIKENON 50mm F2Lに交換、そして接写リングも9.5mmのNo.1に19mmのNo.2を連結して、単独で28.5mmのNo.3相当にして装着。レンズ単体では60センチまでしか寄ることができませんが、28.5mmの接写リングが入るとかなりの接近戦になります。拡大倍率も1.25倍、つまり1.25×1.5=約1.8倍相当ということに。この組合せで撮ったイヌノフグリの花がこちらかなりレンズの光学設計範囲から逸脱した撮影距離なので、全体的にぼんやりした感じになってしまいます。絞り込めばシャープになりますが、それではこのレンズでなければならない意味が失われます。撮って出しのJPEG画像に明るさ調整やトーンカーブ調整を施しても限界がありますので、Luminar Neoでノイズ除去とスーパーシャープ処理を施してみると、ピントを合わせた領域のシャープネスを向上させることができます。やりすぎると不自然になってしまいますが、うまくやればそこそこイイ感じの雰囲気が出るように思います。
2024.03.10
コメント(0)
-

未だ寒い?ヒメオドリコソウの花
3月9日(土)日当たりの良い場所では、春の花「ヒメオドリコソウ(姫踊り子草)」がピンク色の花を咲かせ始めています。しかし、まだまだ寒いからかあまり首を伸ばさずに地面に這いつくばるように背が低いです。by OLYMPUS STYLUS XZ-2まだまだ春本番とはいかないようすですね。
2024.03.09
コメント(0)
-

11年前の今日のはなし
3月8日(金)2013年3月8日付のFacebook投稿良覺院丁公園でハコベの花の写真を撮っていたときのエピソード。記憶はしていますが、もうそんな昔になってしまったんですね。投稿したハコベの花の写真は、RICOH GXRにXR RIKENON 50mm F2Lレンズ、そしてPENTAX K接写リングをNo.1からNo.3までフル装着し、さらに絞りをF2開放にして撮った渾身の一枚でした。このときは撮って出しのJPEG画像ファイルをリサイズしてアップしましたが・・・by RICOH GXR+MOUNT A12, RICOH XR RIKENON 50mm F2LLuminar Neoで処理したら、さらにクオリティアップするでしょうか。実際に試してみました。リサイズして解像度を落としているので、ノイズ軽減処理の効果などはわからないと思いますが、若干コントラストが上がって引き締まった・・・かな?ほとんど見た目は変わっていないようにも思います。GXRの撮って出しJPEG画像が優秀なのか、単にサイズが小さいために違いがわからなくなっているだけなのか・・・めしべの先のふさふさ部分にマスクをかけて、シャープ化処理をしているので、そこは若干ふさふさ感が増しているようにも見えますが。最近ではRIKENON 50mm F2Lレンズに接写リングを付けて近接撮影するというようなことはほとんどなくなりましたが、また試してみたくなりますね。
2024.03.08
コメント(0)
-

良覺院丁公園のマンサクが咲く
3月7日(木)昨日、東京出張から仙台へ戻って来ましたが・・・やはり東京と違って仙台は寒い。地下鉄で出勤、青葉通一番町駅で降りていつものように歩きます。良覺院丁公園へ立ち寄って、マンサクチェック。ずいぶん花が開いてきていました。by OLYMPUS STYLUS XZ-2塀のこちら側が良覺院丁公園、向こう側は茶室・緑水庵のある庭園です。緑水庵庭園側から枝を伸ばしてこちら側でじっくりと花を眺めることができます。向こう側の庭園では、苔が傷むので自由に歩き回ることができず、マンサクの木の近くへ行くことができません。やはりこのマンサクの木は、良覺院丁公園側から鑑賞するのがいちばんです。それにしてもマンサクの花は、かなり個性的な姿です。なぜこんなかたちになったのでしょう。まだまだ咲き始めで、つぼみもたくさんあります。これから次々と花開いていくようすを楽しむことができそうです。
2024.03.07
コメント(0)
-
仙台へ帰るのですが・・・帰れるか
3月6日(水)朝7時半頃に、郡山駅で新幹線がオーバーランしたために車両の整備を行っている影響で、最初は東京~仙台間といっていましたが、その後東京~盛岡間に拡大していると報じられました。朝、帰りのルート検索をgoogleマップで・・・と、どうしても新幹線が候補に挙がらず、新宿発の夜行バスばかり出てきて「なんだ?」状態になっていました。えきねっとではなんとか夕方発のはやぶさを確保できましたが、予定通り乗車できるか少々不安です。お昼になっても東北新幹線は「大幅遅延」状態。はたして予約した新幹線に無事乗って仙台へ戻れるでしょうか。今日は学会の最終日。バスで出るまで少し時間があったので、八王子駅前のヨドバシカメラをちょっと冷やかしてみるか・・・と立ち寄ったところ「何かお探しですか?」と声をかけられ、思わず「XZ-2のバッテリーがひとつ膨らんでしまってるんですよね・・・」と切り出してしまいました。そのあと話の流れで、OLYMPUS STYLUS XZ-2用のバッテリーLI-90Bの後継品LI-92Bを1個購入することに。ポイントを使って2400円くらいで手に入れることができたのでよかったのではありますが、(なぜ八王子でバッテリーを?)という不思議なひととき。※ちなみに、バッテリーがなんだか膨らんでいるんじゃないか、と気づいたのは去年の11月17日でした。(当日の日記参照)バスで学会会場である工学院大学へやってきました。ポスターを回収し、午後のオンライン会議に備えます。休憩室の片隅でなんとかオンライン会議を終え、夕方会場をあとにして八王子駅へ戻ります。宿に預かってもらっていたキャリーバッグを受け取り、さあおみやげをゲットしに松姫本店へ!数分歩いて到着!・・・と、閉まっている?見れば今日は定休日だったみたいです。なんということか!次回、いつ八王子に来れるかわかりませんが、機会があればまた狙ってみたいです。とりあえず今日のうちに仙台へ戻れたのでよかったよかった。
2024.03.06
コメント(0)
-

八王子ラーメン?
3月5日(火)昨日から東京八王子に滞在中。学会会場で貼り出されていたポスター、なんと「八王子ラーメン」の説明。八王子ラーメンなんてはじめて知りました。さっそく夕方宿に帰ってから、近くにあるお店「中華そば専門店 八王子ラーメンよしだ」へ。もっともオーソドックスな「中華そば」をいただきました。「あきたこまち」と書いてあった半ライスもつけます。by SHARP AQUOS Sense7ラーメンはちょっと濃いめの醤油味スープにうっすら透明なラードがコーティングされ、固そうに見えるけれども食べてみるとホロッとするチャーシュー、刻んだ玉ねぎ、そして小さめののりが乗ってたいへんおいしかったです。あきたこまちのライスもいい具合に炊かれていておいしい。元気なおかみさん、八王子にははじめて来たんですよ、といったら「何にもないでしょ!」と。そんなことないですよ。
2024.03.05
コメント(0)
-

東京八王子へ出張
3月4日(月)明日と明後日の二日間、東京八王子の工学院大学で開かれる学会に参加するため出張です。今日は移動日。八王子ははじめてです。ご当地おみやげが何かないかと探したところ、「松姫もなか」がヒット。ちょうど本店が宿から近かったので、ちょっと偵察に。もなかは餡をよく練ってあるので、意外と日保ちするようです。・・・2週間。座った松姫様の姿、二口くらいで食べられるお手軽サイズ、ふつうのつぶ餡のほか、練り餡、栗餡、しそ餡、そしてゆず餡の合計5種類ものバリエーションがあるとのこと。仙台へ帰るときにおみやげとして買うとして、とりあえずバラで買って帰って試食してみようと思いました。5種類のもなかをひとつずつ、そして串団子を2本、こちらはふつうのみたらしと、「素焼き」(しょうゆをつけてそのまま焼いただけ)、さらにおいしそうに見えた酒まんじゅうを購入。京王八王子駅地下で購入した弁当を夕食としていただいたあと、試食和菓子たちをいただいてみました。どれもおいしい!全部食べることができるか心配していましたが、ぜんぜん大丈夫でした。by SHARP AQUOS Sense7みたらし団子のみたらしは、ふつうにイメージしていたものとちょっと味が違っていて、とてもおいしかったです。酒まんじゅうも、粒あんが甘さ控えめ、皮?ももっちりしていてたいへんおいしい。もなかの5種類の餡の中では、個人的には「しそ餡」がナンバー・ワンでした。明後日返るときに、ぜひもう一度お店に出かけて、おみやげを購入しようと思います。
2024.03.04
コメント(0)
-

片平公園の臥龍梅、ひとつだけ開いていました
3月3日(日)仙台でもぼちぼち梅の花が咲いてきていますが、片平公園にある臥龍梅(がりょうばい)は、ほかと比べると遅め。年によっては横の桜と一緒に咲いていることもあったりするくらいなので、今の時期は花が開くにはまだまだだろう、と思っていたのですが・・・ちょっと時間があったので、「まあ、まだ咲いてないだろうなぁ」と、見に行ってみました。by OLYMPUS STYLUS XZ-2いちばん左が臥龍梅、そこから右には桜の木が並んでいます。近くへ行ってみてみると、ちらほらと白くふくらんでいるつぼみがありました。おお?これは期待できるかも・・・よく見ながら探してみると、高い枝の先にひとつだけ開いているのを発見!これから次々と開いていくのを見るのは楽しみです。
2024.03.03
コメント(0)
-

晴れたけれど寒い一日、冷たい強風
3月2日(土)朝の天気予報でも、「昨日より気温が下がって真冬並みに」と言っていましたが、家の中から外を見る限り、日も射していたしぽかぽかと暖かそうな雰囲気でした。しかしいったん外へ出てみると・・・ビュービュー!冷たい風がかなり強い。車で出かけ、二郷堀へ行ってみましたが、西から(二郷堀の上流側から下流、山から海に向かって)の風がかなり強く、堀の水が自然の流れ以上に風に押されて波立ちながら流れていました。二郷堀にかかる一本松橋脇のホトケノザ、by OLYMPUS STYLUS XZ-2絡み合うように斜面を覆い、赤紫色の花がいくつか咲いていました。ここから端を渡った向こう側には「一本松橋」の名の由来となった松の木が立っていました。しかし震災の津波に遭い、なんとか耐えたものの、2020年に伐採されてしまいました。一本松のあとには若い桜の木が植えられました。その後、橋に取り付けられていた「一本松橋」「いっぽんまつばし」のプレートが取り外されてしまいました。桜の木が立派になったら、「一本松橋」から「一本桜橋」か「桜橋」に名前が変わってしまうのでしょうか。
2024.03.02
コメント(0)
-

さて3月、春っぽいものたち
3月1日(金)仙台では昨日から続いて今朝も雨が降っていました。しかし昼頃には雨も上がり、傘なしでランチに出かけることができました。良覺院丁公園にてby OLYMPUS STYLUS XZ-2石垣の石の間で見かけたミチタネツケバナ(たぶん)。まだ首を伸ばしていません。花も開いてはいませんが、これからが楽しみです。片平丁通りに入ってくると・・・ふきのとうがほぐれてきています。さらに通りを下って行くと・・・これはナツズイセンの葉です。花が咲くのは名前の通り夏になってからですが、その頃にはこの葉は姿を消します。さらにハハコグサ。まだつぼみですが。だんだん春らしい顔ぶれが見られるようになってきました。
2024.03.01
コメント(0)
全29件 (29件中 1-29件目)
1










