テーマ: どんなテレビを見ました?(80676)
カテゴリ: 音楽・映画・アート
NHK「世界サブカルチャー史 欲望の系譜」シーズン4。
21世紀の地政学《ゴシック編》の全3回を見ましたが…
Twitterの感想も不評が多かったようだし、
民放のバラエティならともかく、
NHKのドキュメンタリー番組の水準としては、
ちょっと見劣りのする内容だったように思う。
◇
で、例によって、
音楽惑星さん と意見交換をしました。
自分的にいろいろ気づきもありました。
今回もその内容をこちらに掲載します。
◇
赤字 がわたし。
青字 が音楽惑星さんです。

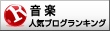

21世紀の地政学《ゴシック編》の全3回を見ましたが…
Twitterの感想も不評が多かったようだし、
民放のバラエティならともかく、
NHKのドキュメンタリー番組の水準としては、
ちょっと見劣りのする内容だったように思う。
◇
で、例によって、
音楽惑星さん と意見交換をしました。
自分的にいろいろ気づきもありました。
今回もその内容をこちらに掲載します。
◇
赤字 がわたし。
青字 が音楽惑星さんです。
NHK「サブカルチャー史」ゴシック編の内容って、あんなんでいいのかな?なんか上っ面な感じで本質からズレてる気がするんだけど。
どうなんでしょうね。まあ、文化史に「正史」があるわけじゃないし、サブカルチャーとして「ゴシック」を語ったら、ああいう風になるのかな。
すくなくとも「ゴシック」のメインストリームにはなってないと思う。
あのNHKのシリーズって、番組名が「サブカルチャー史」になってますが、《アメリカ編》なんかを見ると、完全に「メインカルチャー史」ですよね(笑)。B級映画ならともかく、スター俳優が出演するハリウッド映画なんてメインカルチャーなんだから、サブカルチャーじゃないですよ。だから、番組のコンセプトがもともと曖昧なんじゃないでしょうか。英国のロックミュージックだって、サブカルチャーじゃなくてメインカルチャーだと思いますよ。
サブカルチャーがしだいにメインカルチャーに変わるのよね。日本の漫画やアニメも元来はサブカルチャーだったのに、いまや国家経済を支えるメインカルチャーだもんね。
《アメリカ編》はけっこう見ごたえがあったけど、言われてみれば、たしかに「メインカルチャー史」だったね。だから、よけいに《ゴシック編》のサブカルチャー史が薄っぺらく見えるのかな。しかも日本のゴスロリなんぞを結論にしてるから、内容が全体にキッチュで軽薄なんですよ。いまや日本のゴスロリは海外にも輸出されてるから、そこに焦点を当てたい気持ちも分かるんだけど。
ゴシックの本流から見れば、日本のゴスロリは枝葉末節でしょうね。
日本の覆面レスラーがゴシックだ…とかいう話も唐突だし。
あれはメキシコのルチャリブレから来てますよね。アステカ文明の影響だろうと思います。
まあ、南米先住民の生贄文化やドクロの文化って不気味だけどさあ。それをゴシックの文脈でとらえる必要があるのかっていう。
今回の番組でプロレスのことを取り上げたのは、たぶんヘビメタがプロレスの文化に近い文脈で消費されてることを念頭に置いたんだと思います。
あー、そうなのね。
それもまあ、枝葉末節だと思いますが(笑)。
プロレス入場曲-ハードロック・ヘヴィメタル- https://t.co/1eoVoqSIER
— まいか (@JQVVpD7nO55fWIT) June 27, 2024
もともとゴシック的な美学をもってたのは、ハードロックやヘビメタよりも、グラムロックですよね。ルー・リードやアリス・クーパーやデヴィッド・ボウイなんかがノワール風のロックオペラやシアトリカルロックを作ってた。厳密にいえば「ノワール」と「ゴシック」は違うと思いますが、そういうグラムロックからゴシックロックが派生して、さらにヘヴィメタルと融合してゴシックメタルになるんだと思います。
今回の番組ではグラムロックのことには触れてなかったね。
サブカル的にはプロレス寄りのヘビメタのほうが重要なのかな(笑)。
ただ、番組全体は英国中心史観で作られてたと思います。わたしは、そこがいちばん気に入らない(笑)。
英国のゴシックロマンスを起点にするから??
英国のゴシックロマンスはもちろん重要なんだけど、そこへ至る前提として大陸のロマン主義があるわけでしょ。ユゴーの「ノートルダム・ド・パリ」とか、ゲーテの「ファウスト」とか。そういう大陸ロマン主義のおどろおどろしさというのが前提にある。
そうですね。
英国中心史観って、ロックのビートルズ中心史観もそうだけど、大陸的な要素を必然的に見落とすでしょ。
萩尾望都の「ポーの一族」とか永井豪の「デビルマン」だってそうなんだけど、日本のマンガ文化もドイツロマン主義の影響を受けてることを認識すべきです。手塚治虫にはゲーテの影響があるし、萩尾望都にはトーマス・マンの影響がある。
英国ゴシックからの流れをいうんなら、藤子不二雄Aの「怪物くん」を挙げるべきだ!(笑)
そう(笑)。もれなくドラキュラもフランケンも出てくるよ!
ドイツといえば、グラムロックは基本的に英国の潮流ですけど、ルー・リードの「ベルリン」とか、デヴィッド・ボウイの「ベルリン三部作」とか、イギー・ポップの「イディオット」みたいにドイツに関連した作品もけっこう多いです。
英国のゴシックロマンスも、ドイツ文化に発想の源泉を得てますよね。とくにゲーテの「ファウスト」は、フランケンシュタインを考えるうえで欠かせない。近代性への批判という意味で。
悪魔に魂を売ったファウスト博士がいなければ、フランケンシュタイン博士もいないし、ジキル博士も、天馬博士もいないわけでしょ。そういう認識があってこそ、試験管ベビーやヒトゲノム計画が「ゴシック」の文脈に繋がる。ティム・バートンの「シザーハンズ」や枢やなの「黒執事」だって、ゲーテの「ファウスト」の流れから見ないと分からない。
それから「サイボーグ009」のギルモア博士もそうです。石ノ森章太郎の「サイボーグ009」や「仮面ライダー」や「人造人間キカイダー」がなければ、永井豪の「デビルマン」もありえないはずです。
キューブリックのストレンジラブ博士もその系統だよね。オッペンハイマーのことも意識してると思うけど。
あのモデルはヴェルナー・フォン・ブラウンとかエドワード・テラーとか、いろいろ言われてますね。
そして、そういう文明批判と同時に、「ゴシック」には異教的なものへの負の眼差しがあるわけよね。ゲーテの「ファウスト」にもワルプルギスの夜が出てくる。これはトーマス・マンの「魔の山」にも関係する。ケルト的な、あるいはゲルマン的な異教文化の象徴です。
それからキリスト教の世界では、異教の神々を悪魔よばわりしたり、異教の精霊を堕天使よばわりするんだよね。だから、メフィストフェレスは異教の神さまなんだと思う。永井豪の「デビルマン」や庵野秀明の「エヴァンゲリオン」は堕天使ですね。
ファウスト博士は錬金術師なんです。錬金術も東方の異教的な文化だと言っていい。
そうだね。
近代の科学技術は錬金術の影響を受けてるわけですよ。アイザック・ニュートンも錬金術師だった。錬金術は、古代ギリシアにもあったはずなのに、中世のカトリック教会はそれを排除してしまった。ところが、十字軍のときにイスラムから逆輸入されて、それが近代科学の発端になるわけです。
まさに、それこそが「ゴシック」だよね。異教的であると同時に近代的でもあると。
異教の文明にしても、近代科学文明にしても、カトリックの神を否定するという点で同質なのです。東方の異教文化に対する視線は「ゴシック」の共通要素かもしれません。ルーマニアのドラキュラも、東欧の正教文化に対する暗黒的なイメージが重なってるんじゃないでしょうか。
冷戦時代のベルリンも東方世界に囲まれた飛び地だったから、何かせめぎ合うような場所だったと思う。
NHKの番組ではチェコの映画のことを取り上げてましたが、チェコのプラハも錬金術師の多かった町だし、西欧カトリック社会を裏返すような異質な要素に満ち満ちてる。フランケンシュタインにはユダヤのゴーレムの影響もあると思います。いずれにしても東方の異教文化ですよね。さっき「怪物くん」の話をしましたが、あれに出てくる狼男も、東欧や北欧の獣人伝承です。
チェコの「闇のバイブル/聖少女の詩」という映画は、1968年のプラハの春のさなかに作られてるんだけど、社会主義の立場からカトリックを批判してるのか、それともカトリック教会による抑圧を社会主義政府による抑圧に重ねてるのか、よく分からない。チェコの人たちは、カトリック信仰をみずから選んだんじゃなくて、ハプスブルク家に押しつけられたのだし、宗教改革も封じられてきた。そしてハプスブルク家が退場したと思ったら、こんどはソ連から社会主義を押し付けられた。
いろんな抑圧のなかで地下文化を育んできた国ですね。シュルレアリスムの発信地でもあった。英国から「ゴシック」の影響を受けるまでもなく、もともと奇怪な想像力を肥大させてきた国だと思います。
南北戦争時代の南部社会もゴシックロマンスの舞台になってきたんだけど、それについても今回の番組では取り上げてない。
南部ゴシックについては、ちょっと分からないです。なぜ米国南部が「ゴシック」になるのかが、いまいち分からない。ヨーロッパの「ゴシック」とはちょっと違うでしょう。異教的なわけでもないし、異民族的なわけでもないし、先住民の文化を「ゴシック」ととらえてるわけでもないし、むしろ南部の白人社会を「ゴシック」として表象してるわけですよね。
北部から見たら、南部の社会が野蛮で暗黒的に見えたんだろうね(笑)。よくいえば西部劇みたいに逞しくてカッコいいけど、馬に乗った人たちが道端で決闘して殺し合ったりしてたわけだから。19世紀の日本人がチョンマゲ結って切腹したりしてたのと同じで、野蛮な未開社会に見えたんじゃないの?20世紀になってもKKKなんかが黒人のリンチ殺人したりしてるし。ビリー・ホリデーの「奇妙な果実」とか。
それはやはり「ゴシック」というより「ノワール」じゃないかと思います。
まあ、そうだね。ナサニエル・ホーソンとかエドガー・アラン・ポーの場合も、要するにサスペンスのことを「ゴシック」と言ってるんだろうね。それでいうと、同じころの英国にダフネ・デュ・モーリアの「レベッカ」とかシャーロット・ブロンテの「ジェーン・エア」とかがあって、そちらもサスペンス要素がゴシック風味になってる。
あとは、大きなお邸がゴシック建築に見えるかどうかって話かもしれませんね(笑)。
欧米でいちはやく「ロッキーホラーショー」を体験した人が、80年代の鹿鳴館ギャルになった可能性もありますが…。
自分はてっきりフランス人形の影響かと思ってました(笑)。フリフリのお人形みたいなドレスを着てるから。
人形って怖いもんね。ホラー映画にもよく出てくるね。
古い人形は怖いんですよ(笑)。日本の市松人形も怖い。
四ツ谷シモンの関節人形みたいなのも不気味だしね。日本の場合は、とくに大正時代に、怪奇趣味的なものや退廃趣味的なものが和洋折衷のなかで生まれてきて、人形文化もそういう面を負ってるんじゃないかな。
江戸川乱歩とか澁澤龍彦あたりを「ゴシック」の文脈で括ることもありますよね。
ジム・シャーマンの「ロッキー・ホラー・ショー」は75年の英国映画だけど、同じ年にケン・ラッセルが「トミー」を撮ってて、当時としては、そっちのほうが評価が高かったはず。そしてケンちゃんは86年になって、その名も「ゴシック」という映画を撮ってるわけです。わたしが「ゴシック」の文化に触れたのも、この映画が最初でした。観たのは90年代になってからだけど。たぶん三鷹オスカーの3本立てとかで。
三鷹オスカーの3本立て(笑)。
そのときはメアリー・シェリーのこともブラム・ストーカーのこともよく知らないから、内容もよく分からなかったんだけど、いま考えると「ゴシック」の何たるかを知る上でお手本のような映画だったと思います。
ディオダティ荘の怪奇談義を再現してるわけですよね。
ケン・ラッセルってエキセントリックな人だけど、じつはイギリスの正統をとても意識してる人だと思う。D.H.ロレンスとか、オスカー・ワイルドとか、ザ・フーとかのキテレツな部分こそが英国らしさだと考えてたんでしょう。
あれも、ひとつの英国らしさなんですね。
そんな彼がなぜ「マーラー」を撮ったのかはよく分かんないんだけど(笑)。
プログレの起源をマーラーに探ったとか?
マーラーも分裂症的でキテレツな音楽だからかな。
70年代に長尺の楽曲を収録したプログレのアルバムが売れるようになってから、マーラーのような長大なクラシック音楽も売れるようになったそうです。英国のロック文化とドイツ系のクラシック文化が、重厚長大な美学で重なり合ったともいえます。それまでマーラーやブルックナーなんて聴く人はあまりいなかった。
もともとの「ゴシック」の語源は、西ゴート族のゴテゴテした野蛮な文化の蔑称なのだけど、それを18世紀以降のゴシック・リヴァイヴァルのなかで、英国人やドイツ人が自民族的なルーツとして再評価していくわけよね。異民族の異教文化に対する恐怖心とか侮蔑の感情が根底にありつつ、それを反転させたところに新しい価値が生まれてきた。
ラテン的ではない、ゲルマン・アングロサクソン的な価値。
そういう意味でいうと、日本にも「ゴシック」に相当するものはあると思います。たとえば弥生土器にくらべて縄文土器はゴテゴテしてる。能・狂言にくらべて歌舞伎はゴテゴテしてる。奈良の都市仏教にくらべて山岳修験道や北陸の浄土真宗はゴテゴテしてる。これは神仏習合の結果だけど。つまり、上方の朝廷文化から見ると、列島周辺の土着の文化ってゴテゴテしてるんですよ。
洗練されてない。
わたしは荒木飛呂彦の「岸辺露伴」の志向に日本のゴシックを感じるんだけど、それはたんに怪奇趣味的だからじゃなくて、都の仏教的な文化と対極的な土着の習俗を掘ってるからなんです。たとえば、小泉八雲みたいに出雲の神話を探ったり、北陸の浄土真宗的な泉鏡花とか、滝沢馬琴みたいな房総半島のヤンキー武士の世界をリスペクトしたり、目のつけどころがいちいちゴシックだと思うのよね。
馬琴の「南総里見八犬伝」って千葉のヤンキーなんですね(笑)。
あれは戦国時代の木更津キャッツアイですよ。荒くれ者の野武士集団だから。
岸辺露伴は京都に行くべきじゃない、と。
いや、べつに京都で百鬼夜行に遭遇してもいいんだけどさ(笑)。このあいだNHKでやった「密漁海岸」も伊勢が舞台だった可能性はあります。でも、いままでのところは、おおむねゴシックな感じがするんです。
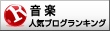

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.06.29 13:58:53
[音楽・映画・アート] カテゴリの最新記事
-
片山杜秀:松竹の木下恵介・木下忠司・山… 2025.02.16
-
片山杜秀:小津安二郎と斎藤高順のポルカ… 2024.12.10
-
日テレ「県民ソング栄誉賞」になぜ??…と… 2024.11.30
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ
政治
(224)ドラマレビュー!
(293)NHK大河ドラマ
(50)NHK朝ドラ
(37)NHKよるドラ&ドラマ10
(32)プレバト俳句を添削ごと査定?!
(216)メディア問題。
(44)音楽・映画・アート
(82)漫画・アニメ
(26)鬼滅の刃と日本の歴史。
(33)岸辺露伴と小泉八雲。
(22)アストリッドとラファエルの背景を考察。
(8)アンという名の少女の感想・あらすじネタバレ。
(31)東宝シンデレラ
(77)恋つづ~ボス恋~カムカム!
(48)ぎぼむす~ちむどん~パリピ孔明!
(38)わたどう~ウチカレ~らんまん!
(64)汝の名~三千円~舞いあがれ!
(16)トリリオン~ONE DAY~ゼンケツ!
(29)Dr.チョコレート~ゆりあ先生!
(15)捜査一課長~恋マジ~あのクズ!
(42)「エルピス」の考察と分析。
(11)「Destiny」&「最愛」ネタバレ考察。
(20)大豆田とわ子を分析・考察!
(10)大森美香の脚本作品。
(12)北斎と葛飾応為の画風。
(17)不機嫌なジーン
(13)風のハルカ
(28)純情きらりとエール
(30)宮崎あおいちゃん
(18)スポーツも見てる!
(41)逃げ恥~けもなれ!
(24)スカーレット!
(13)シロクロ!
(13)ギルティ!
(9)半沢直樹!
(5)探偵ドラマ!
(12)パワハラ
(7)ドミトリー&ゴミ税
(40)夢日記&その他
(5)© Rakuten Group, Inc.









