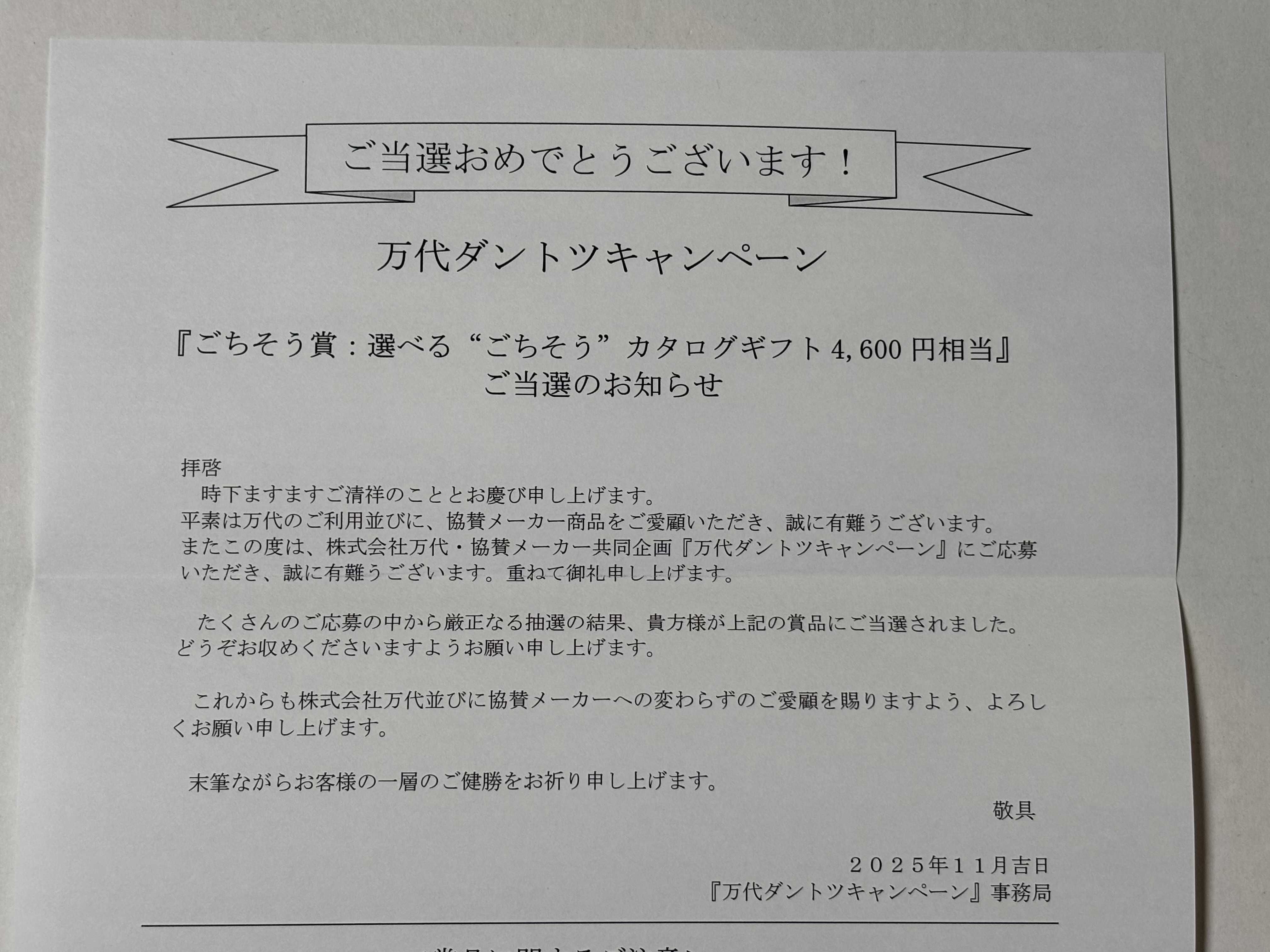全42件 (42件中 1-42件目)
1
-
第34月法 傷だらけのおのこ
外は晴れているというのに、これで3日は外出していません。お腹の締め付け感が、16日の外来検査以来、一段とひどくなったからです。でも、おかずが切れる明日は、ぜひとも買い物にゆかなければなりません。徒歩10分、自動車なら5分。自動車は、ものを運ぶのは楽ですが、ハンドルを切る際に、時に激痛が全身に走り、「こんどはハンドルが切れずに衝突するのでは」という恐怖感があります。 天気予報では、明日は、日差しがないそうです。うぅっ。日曜日だからスーパーも混んでいるだろうな。レジで立って並ぶ時間がまたとても長いのです。でも、ゆかなければなりません。ニンジン、ダイコン、ヨーグルト、スキムミルク、ショウガ、うどん、パン、缶詰などなど。 昨日は、小生の病気に効くという漢方薬を発注いたしました。病院で予防的、或は本格的な化学治療が始まるまでに、先手を打つためです。今晩は、11歳年上の姉さん(実際の姉ではなく父方の従姉。私には兄弟はいない)から、励ましの電話を1時間いただき、勇気をいただきました。 もはや、我執は日々薄れてゆきます。かくなる傷だらけのおのこが、身丈に合わぬ夢を見るのはやめたのです。はーやく、はーるになあれ。梅が咲き、桜が咲く、いまはそれだけが、楽しみです。 追伸 『妙法蓮華経秘密釈』は、体調がもう少し良くなったら再開する予定です。もうしばらく、ご猶予ください。
2008年01月19日
-
第33月法 仏法サラリーマンならぬ、ただの病人
退院してからは、自宅療養ということで、ずっと一人きりで家にいます。あれほど楽しかった一人暮らしがこれほど苦痛になろうとは、以前の私が想像力をいかに欠いていたかが分かります。 買い物・料理・掃除・洗濯そのほかいろいろ、いわゆる家事が、病人の病状をかんがみることなく回ってきます。腹の傷は、しばらく歩いたり、同じ姿勢を続けると痛み、掃除など何かの工程一つこなすと熱が上がり、ベッドに横にならなければなりません。病院にいるときのように、早起きをして、朝・昼・晩の食事を取りたいのですが、疼痛のため、病院から与えられた睡眠薬と痛み止めを飲んでも夜が寝られず、夜が明けて寝付くと昼だとか1時になっている次第です。それでも連続して取れる睡眠は、せいぜい2、3時間です。外科手術というものが、病巣そのものよりも、他の痛みでこれほど苦しむものだとは知りませんでした。 きょうは、さいたま市はとても寒かったですが、晴れていたので、買い物をすぽっかすために、近所のそば屋さんで、2時過ぎに、普通人のランチメニューをいただいたのはいいですが、家に帰ると、具合が悪くなり、お腹を締め付けられ、かつたたかれたような痛みで、6時近くまで横になっていなければなりませんでした。無理をして全部食べたのがあだとなったのです。ちなみに、この日は食事はこれ一食となりました。 時間は自由にあるように見えて、痛みで本もまともに読めず、DVDも見られず、迫り来る漠然とした絶望感に縛り付けられます。それでも、生きなければならない残酷さ。小生としては、当ブログで11月まで(実際書いていたのは、10月中旬まで)展開した『妙法蓮華経秘密釈』の思索と修行に戻り、1冊の本にまとめ上げたいという最後の願いがかなうかどうか、いよいよ分からなくなって来ました。 小生の苦しみは、術後の過程での一般的出来事なのか、皮下脂肪など縫い合わせの不具合なのか、こんどの16日の外来で、勇気を出して主治医にたずねますが、お腹の縛り加減などで再手術などやはりあり得ず、「仏法サラリーマン」としての復帰を考えると、お見舞いに来てくれた上司や同僚には本当に感謝の気持ちでいっぱいで報いたいのですが、それはまた非常に慰めのないものに思えて来て、もう語るに悲しみにたえません。「どうして、おまえは、痛みで、苦しい、苦しいと言いながら、ブログは平気で書けるのだな」「私のような単独者が、病気と闘う方法は、書くことしかないからです。小生のさがです。嗚呼、苦しい」
2008年01月13日
-
第32月法 魔の山からの生還
約2カ月ほどの入院生活(手術からは1カ月強)を終えて、一昨日、退院いたしました。手術は、約10時間に及び、切り刻まれた痛みは、今なお続きます。いつ死んでもいいと、仏法を学問として修行する身でありまがら、いざとなると、親兄弟、妻帯なしの単独者でありながら、猛烈な生への渇望を求め、手術に臨みました。お念仏の増上寺のすぐ近くの病院で、必死に心で題目をとなえ、あとは何を思っていたのか、思い出せません。手術は、一応成功ということですが、切られた傷が深くうずきます。 生まれて初めての入院で、大手術からの生還、小生の人生観は、人間を失格していたことだとつくづく気づきました。男も女も、30までにはお互いに伴侶を求め、生活の基盤を築き、お互いを知り合うことで、人間を構築してゆく。そして、二人の結果から、その子孫が、親や祖父母を養い、歴史を伝えることに人間社会というものの根幹がある。かの『人間失格』を書いた太宰ですら、社会を築いていたのです。 伯母や従姉や従兄などの親類、会社の上司や同僚、友人などが、約30人ほど病室をたずねて来てくれたことは、ほんとうに嬉しく、彼らが帰ったあとに泣いたものです。 一般の現代人が死に至る時、仏教の教理などは役には立たないということも分かりました。私がずっととなえていたのは題目ではあり、一切の意味を失った「ナムミョウホウレンゲキョウ」でした。鎌倉時代の聖人が、すべてを『法華経』にゆだねるという他力を、題目のもとに一念三千の天台理論を修行としたのです。しかし、題目は、意味をもつ限り、修行にはならないのです。 病気やけがなど自分ですべてコントロール出来ると思っていた自分が、主治医に絶対的に自分の命を預け、その結果は、法(法華経)に任せたのです。幼少のみぎりより、母の影響でとなえつづける題目、そこには深い意味などなかったのです。それゆえに修行たりえたのです。私は、もう、死んでも、生きても、いい。
2008年01月09日
-
第31月法 一念三千の法門(2)…妙法蓮華経秘密釈(法華経秘釈)第二巻・其の六
「無辺行菩薩(むへんぎょうぼさつ)よ、ボンゾは、三世間(さんせけん)をもう一度確認しとう存じます。ここで、もう一度つまびらかに説いていただけますでしょうか」「むろんじゃ、仏法は繰り返し、説き直すことに仏法たるゆえんがある。しかも、万華鏡の即興の言語力(げんごりき)がなければ、説き直すことが許されない。それが、転法輪(てんぼうりん)というものじゃ。 第一に、五蘊世間(ごうんせけん)――。色(しき)・受(じゅ)・想(そう)・行(ぎょう)・識(しき)を包括しかつ絶え間なく持続する世界じゃ。色とは、地・水・火・風・空の五大(ごだい)からなる物質のことじゃ。むろん、有情の身体もこれに含まれる。受とは、感覚し感受すること。想とは、表象(ひょうしょう)すること。行とは、意志し要求すること。識とは、認識し判断すること。それらが仮和合(けわごう)することによって、銀河宇宙の物理の世界が成立している。恒星や惑星や彗星(すいせい)を成り立たせている元素から、すべての非情と有情は発現する。物質はさまざま因縁果報に組み合わされ、やがて感受作用をもつようになる。そしてまだ意志はないものの、外界を己のうちに現象として表象するようになる。すなわち、そこには結界が生じ、煩悩の欲求が生ずる。そして、認識作用が生ずる時、物質に魂を吹き込むのじゃ。それを現代の科学文明では生命誕生というのであろうが、仏法の側からすれば、ただの五つのもののあつまりが衆生に結実したに過ぎない。生命体は、地・水・火・風・空の五大(ごだい)のなかに五蘊を結界のうちに固めた衆生世間であるとともに、この宇宙が始まったときより、裾野をどこまでもひろげてゆく絶対持続の世間でもあるのじゃ。生命体の細胞の一つ一つが、太陽系の惑星空間を突き抜け、膨張する銀河の果てまでの世界とはつながっておるのじゃ。千万億の銀河が集まって出来ている宇宙の星辰(せいしん)は、ひとつひとつが生き物なのじゃ。これは、娑婆(しゃば=サハー世界)の結界を超えた、いうなれば、とめどもあふれ出る絶対持続を観ずる時間論じゃ。 第二に、衆生世間(しゅじょうせけん)――。人間を含めあらゆる有情は、五大五蘊が仮に集まって存在するに過ぎず、実体はないのじゃが、これは、娑婆結界にとどまる時間の無常の存在論である。大海原の娑婆のなかの矮小(わいしょう)なDNAを囲んだ細胞が、やがては草木虫獣鳥人へと分化し、40億歳まで種と個体を養生進化させたのじゃ。娑婆有情は、ほとんどが個体の死をもたらすが、種の持続はつづいておる。人間の種は、古いサルから枝分かれし、最初の新しいサルから継承されて500万年という寿命をたもっておる。サルも人類も共に、有情の結界からのスパンとして等しく40億年の進化を経てきた現実に残る兄弟の化石なのじゃ。おぬしは、母さまの胎(はら)のなかでおったときに、魚類、両生類、爬虫類、哺乳動物、人類へと生命進化を十如是(じゅうにょぜ)を自在に生きておったのじゃ。人間界に生を受けたボンゾには、時間を管理し、地球環境を切り開く権利と能力をもつものとの自覚があるかも知れぬが、それは、衆生世間に付随する錯覚なのじゃ。衆生世間においては、時間は伸縮し、時間として外在化する。 第三に、国土世間――器世間(きせけん)ともいう。地獄の住人は、焼け解ける鉄と凍てつく氷に依存して住み、餓鬼は、地獄のすぐ上の地中に依存して住み、時に山や大地にも現れる。畜生は、大地と水と空中に依存して住み、阿修羅は、海辺と海中を本拠地とする。人間と声聞と縁覚は、大地に依存して住み、各々夫々生活する器の区別がある。天上神は、虚空を棲処とし、仏と菩薩は、自在に生き、住処もとどまるところを知らずまた自在である。報身仏としての阿弥陀仏、薬師如来、大日如来等は、それぞれの西方極楽浄土、東方浄瑠璃(じょうるり)世界、密厳(みつごん)浄土等の主宰国に住しておる。また、観世音菩薩は、補陀落(ふだらく)浄土におられるともいう。因縁果報により衆生の時間が空間に外在化したものが、器の世間である。それとともに、地球環境という器をもあらわしているものなのじゃ。真空のエネルギーのなかに地・水・火・風が混ざり合い、ちりあくたが集積して、生命体もとであるこの星辰は成ったのじゃ。これは、時間が空間に外在化された如是と言っていいじゃろう。 うぬの色心(しきしん)のかげろうの存在そのものを考えてみれば、ボンゾの体は、宇宙の五元素と五蘊から成る宇宙人(びと)の塵芥(じんあくた)であり、衆生世間としてみれば、40億年をDNAを細胞に結界して、生き抜いた生物であり、現存する地球の有情の一つのカテゴリーとしてみれば、500万年の進化を生き抜いた人類という種を維持する乗り物であり、魚類から両生類、両生類から爬虫類、爬虫類から哺乳類、哺乳類から類人猿、そして類人猿から人類への枝分かれの進化の道筋を付けたのが、46億年を五蘊世界に生きた地球の偶然の国土環境であり、文明の名字をもった個人としてみれば、うぬの肉体を養う直接の環境が、21世紀の文化・文明の蝟集(いしゅう)する倭国(わこく)という島嶼国(とうしょこく)の仮名(けみょう)の因縁果報だということじゃ。 うぬの心身は、六道輪廻をめぐる実体のないもので、うぬの過去・現在・未来は、五蘊世間にあつめられ、ある時代の衆生世間に固められ、十如是(じゅうにょぜ)の因縁果報の作用によって、ある器世間の一員となり、十界をめぐるのじゃ。おぬしの一念が、妙法蓮華の仏種(ぶっしゅ)にふれて、菩提心をおこし、成仏を願わば、まずは、この三千法界を観心(かんじん)するところから始めねばならぬのじゃ。 現在のボンゾの一念が、三千の法界宇宙にわたることを認識し、また、法界の三世間の時間とその外在化と、それを超越した絶対的持続を覚り、仮に十如是の和合によって、己が仮名の名字色心(みょうじしきしん)に結実していることを覚り、因縁と果報によって生ずる空観(くうがん)を等しく観じ、十界互具を懺悔(さんげ)と慈悲のもとであきらかに覚るならば、うぬは、法師と呼ばれるに値しよう。 宇宙法界の闇に生まれ、死に、また生まれ、地球という器が出来上がり、こんどは、衆生として生まれ、死に、また生まれ、そして、生きた因業(いんごう)が、果報として生まれ変わり、生きたという世間が化石の器のごとく残されてゆく。しかるに、それもはかないもの、雨風に溶かされ、土に埋もれるも、閉じ込められたぼろぼろの色心は地・水・火・風に帰ってゆく。色は、地水に流され、心(しん)は、風火に昇りて、五蘊を探し求めて、銀河をさまよい、新たな世間を探し求めよう。 しかるに、以上の十界互具(じっかいごぐ)と十如是と三世間の渡り合いについては、仏と仏のみがきわめられているのであって、それがまた久遠仏(くおんぶつ)の特性であり、それを諸法の実相というのである。現象界の諸行無常が諸法実相であるとともに、ブッダの一念三千の覚りを諸法実相ともいうのじゃ。そして、そのまねびを保証するを、妙法蓮華経の仏種()という。このたねは、諸々の大乗経浩瀚(こうかん)ともいえど、妙法蓮華のみに宿るものなのじゃ。わしは、そのことが言いたいがために、厖大(ぼうだい)な三大部をあらわし、三世間を最後に発見し、一念三千の法門を説くにいたったのじゃ」 ここは、どこだろうか。 グリドラクータにあることは間違いはないのだが、周りはすでに夜の闇に閉ざされており、山の地面の自分には足がなかった。虚空の清冽な空気のなかで、ボンゾは、アナンタ・チャーリトラから台(たい)の教えを確実に相承(そうじょう)していた。「無辺行様、無辺行様、どこへゆかれました」「時間のあるところ陰入会(おんにゅうかい)五蘊仮和合があり、衆生仮和合がある。ただ、久遠実成のシャーキヤムニ・ブッダこそは、諸々の仮和合を脱しており、宇宙の膨張時間をも超越しておられる。そこには、すでに輪廻転生があり得ない。とどまる衆生時間のなかで、そして同時にあふれる宇宙の五蘊時間のなかで、この身で覚るを、即身成仏(そくしんじょうぶつ)というのじゃ。それこそは、空間浄土に外在化されない絶対的持続の実存じゃ。これを一念三千の観心に覚ることが出来るか否かに、法華の仏法はかかっておるのじゃ。 『止観』の要諦(ようだい)はこれで終わりじゃ。よう最後までわしの長広舌(ちょうこうぜつ)に堪えたうぬに感謝したい。わしの本懐、一大因縁はうぬに相承された。しかと色心に刻みつけられたはずじゃ。しかるに、わしの理法には、修行法がない。そのことについては、語るをやめよう。それは、蓮の仕事じゃ」 そうして耳のなかの鼓膜が大きく膨らんだり、閉じたりするうちに、ボンゾの意識も朦朧(もうろう)として来た。 シャーキヤムニ・ブッダの声が遠くの闇から聞こえる。「諸々のブッダは、ただ菩薩のみを教化したもう。すべての所作は、この一大事のためなり。ブッダの知見をもって、衆生に示し、導き入れ、衆生をして覚らしめんがためなり」(陰暦10月16日、楽天大衆=だいしゅ=に示す 『法華経秘釈』第2巻おわり ※「お知らせ」をご覧ください)
2007年11月25日
-
第30月法 一念三千の法門(1)…妙法蓮華経秘密釈(法華経秘釈)第二巻・其の五
「百界千如(ひゃっかいせんにょ)は有情を尽くすも、一念三千(いちねんさんぜん)は有情非情にわたる。倭(わ)の蓮法師(れんほっし)が後にこれに気付き、主著にもあらわしたが、わしとしては、この世とあの世と、そしてすべての法界が生まれ出づる前より存在している真空の法界をも、すべてに網羅するために前提としておきたかった、わしなりの、いわば阿毘達磨倶舎(あびだつまくしゃ)、すなわち諸法を解説(げせつ)する蔵(くら)というわけじゃ。要するに、仏法ゆきわたらざるところはなく、三千法界にひらく世界どこであろうと、我々、山川草木人獣鳥虫(さんせんそうもくじんじゅうちょうちゅう)が即身成仏(そくしんじょうぶつ)する種は、みおちみちておるのじゃ。その先の観心(かんじん)の観心、すなわち、本尊については、のちの蓮にゆだねるとして、その台(たい)の観心のしんじちの法門の甚深(じんじん)をおぬしに授けよう」「無辺行(むへんぎょう)菩薩よ、ここで、ひとつ質問をさせてください。百界千如に加えられる三世間(さんせけん)は、五陰(ごおん)世間と、衆生(しゅじょう)世間と、国土(こくど)世間とに分かたれますが、その分類に疑義がございます。衆生は、五陰、すなわち五蘊(ごうん)が来り集まって固まったものでありますがゆえ、異なる分類にするには重なりがあるのではないでしょうか。また、器(き)世間とも呼ばれる国土世間は、十界(じっかい)の棲処(すみか)の空間と異なるところはなく、千如を三千に分け隔ててみても、数学の幻術があるだけで、その名字(みょうじ)にはあまり意味がないようにも思えるのですが……」「それは、よい問いじゃ。さればこそ、きょうの説示では、三世間(さんせけん)と十如是(じゅうにょぜ)を乗じて、30世間とし、それに十法界(じっぽっかい)たがいに具(ぐ)する100法界を乗ずる数学を、わしは採用しておらないのじゃ。書では、わしはたしかにそう言った。しかるに、いまは、蓮の分類にもしたがって、十界互具(じっかいごぐ)する法界を十如是で、まずは乗じたのじゃ。これは、いわば生き物の世界じゃ。五蘊と衆生と器との三世間こそは、わしが、『妙法蓮華経』に付け加えた中華台(たい)の観心のための方便じゃった。それを、おぬしに分かりやすいように乗算法を変えてみて、解説して来たわけじゃ。 諸法の実相のおもての相をみたならば、そこには環境に変化しない生まれつきの性があり、実体の本質があり、潜在能力があり、そして、それらが顕現(けんげん)すると活動と行為があるのじゃ。因業(いんごう)は、無明(むみょう)と渇愛(かつあい)が縁となってたすけられ、今生と来世の果報を作するのじゃ。因にむくいて報ずるとは、あの世の世界をいったんとおって、輪廻転生することじゃ。相を本とし、報を末とするのじゃ。本末(ほんまつ)は、すべて縁から生ずる。ゆえに、九つの如是(にょぜ)には、実体の本質というものがあったとしも、名字(みょうじ)の空(くう)があるのみじゃ。ゆえに、実体そのものはない。 如是相・如是性・如是体・如是力・如是作・如是因・如是縁・如是果・如是報・如是本末究竟等という、文字(もんじ)という仮名(けみょう)の空が、本末に究竟(くきょう)に平等にゆきわたっているにすぎぬのじゃ。相でおりながら無相、無相でおりながら相、相でもなく無相でもない如是、縁でおりながら無縁、無縁でおりながら縁、縁でもなく無縁でもない如是、報でおりながら無報、無報でおりながら報、報でもなく無報でもない如是……、是(これ)の如(ごとく)く、それぞれがあるがままに空性中道(くうしょうちゅうどう)であり、仮名の言の葉の理屈をも超えて、究極に本と末が平等にゆきわたっているということじゃ。 諸法を客観的かつ内省的に見極めること、そして、おのずからの生と謙虚に重ね合わせること、それを、己が心の中の人間界の十界で覚ることが出来れば、百界が成仏じゃ。渇愛(かつあい)ではなく慈悲の心でもって、鳥や獣の物言えぬ存在の相と非存在の報が分かれば、餓鬼道の飢えの苦しみも分かれば、三百界が成仏じゃ。それらは、十法界がたがいを具する十界互具の世界じゃ。法界が、空性が平等にゆきわたる世界と覚れば、たちまちに百界千如(ひゃっかいせんにょ)に花開こうぞ。しかるに法華の観心は、そこにとどまるものではなかったのじゃ。それは、肉に骨にかたまった有情差別(しゃべつ)の覚りの世界じゃ。応身(おうじん)であらせられたシャーキヤムニ・ブッダが、法華涅槃時(ほっけねんはんじ)にあえて示された慈悲は、山川草木悉皆成仏(さんせんそうもくしっかいじょうぶつ)のあまねきにゆきわたらぬとこなきの仏法だったのじゃ。 十界互具とは、いわば仏法に内在する空間論である。我々は、そこに生きておってじつは生きておらない。菩提心(ぼだいしん)をおこしたものだけが覚る世界じゃ。十如是とは、縁起(えんぎ)の空観(くうがん)の言語体系である。我々は、因縁果報について、言葉という仮名名字(けみょうみょうじ)を用いて、順序だって戯論(けろん)ではなく、かくのごとく解説(げせつ)出来る。これは、いわば仏法の言語学である。 そして、三世間とは、いわば仏法に内在する時間論である。第一に、始まりも終わりもなく、宇宙空間を絶対的に持続する時間。第二に、有情の生活するところに流れとどまり伸縮する時間、第三に、空間に外在化される時間と、時間には三つの区別がある。すなわち、三世間じゃ。世間とはいうが、じつはこれは三つの時間論なのじゃ。 三種の世間を発見し、観心をいたすことこそは、いっしょう生き身に『妙法蓮華経』を読みくだいた、わしの最大の仕事じゃった。これにより、止観(しかん)は有情を乗り越え、無情非情をも乗り越え、ハマー(摩訶)に達し、般若波羅蜜多は成ったのじゃ」 アナンタ・チャーリトラは、いよいよ止観業(しかんごう)の要諦(ようたい)を明かさんと、ボンゾを見つめた。(陰暦9月22日 楽天大衆=大衆=に示す 『法華経秘釈』第2巻つづく)
2007年11月01日
-
第29月法 地蔵と観音
法華経秘釈『一念三千の法門』近日中アップロード 『法華経』では、地蔵菩薩を持地菩薩と言います大地の裏から表から支えもつ菩薩です六道を輪廻する我々の苦しみを地から救ってくださる菩薩です『観音経』の最後に登場し観音菩薩の普門示現の自在力を証明するのです観音菩薩はいつも音を観じて空からやってきます持地菩薩は衆生の泣き声を聞きつけて大地の蔵からやってきます観音経の説法者はお釈迦さまですそのときです発起人の無尽意菩薩が観音菩薩が無量の衆生を救ってこられたのに感謝してみずからの首飾りを観音さまに差し上げようとしましたところが、観音さまは、それを受け取ろうとはしませんでしたお釈迦さまは受け取るように観音に言ってみましたそれで、観音さまは瓔珞を二つに分けて、お釈迦さまと多宝如来に差し上げたのです持地菩薩は錫杖を大地に打って大歓喜しました「観音経を聴くもの、観音の御名をとなえしものは幸いなり 南無観世音菩薩」持地菩薩は、空の友の神通力を証明いたしました観音さまはにっこりと笑いました 以上は、『妙法蓮華経』第25品『観世音菩薩普門品』(略して『普門品』『観音経』)のお話ですすべて33身の観音さまは法華経がふるさとです南無妙法蓮華経
2007年10月29日
-
第28月法 花のいのち
花はせいいっぱい咲いている我を張り、がんばる人間とは次元がことなるところに彼らはいる無情説法を、あなたは聞いたことがあるだろうかそれは、シャーキヤムニ・ブッダが仏法を説く前から説いている仏法だくだらない生臭坊主が説く説法と比べるべくもない彼らは、無情説法を聞き取ることあたわず自分等と同党の師資相承しか聞き取れない山川草木の声、風雨の声、空雲の声、星辰の声花ばかりではなく、石も歌っているこの世は、無情説法であふれている有情説法は、それは、処世術とご利益には役立つではあろうけれども無情説法を聞けるものも、説くものもいないこの21世紀精神異常者でなくともそれを願うものは、いったい、いるのであろうか(陰暦9月10日 楽天ブログ大衆=だいしゅ=に示す)
2007年10月20日
-
第27月法 有情百界千如…妙法蓮華経秘密釈(法華経秘釈・第二巻)其の四
家で誦経(ずきょう)するように滞りなく出来るか不安であったが、ここで言えないと、今夜でグリドラクータ(霊鷲山=りょうじゅせん)の夜も終わってしまうのかと勝手に決め込み、ボンゾは咳払いを2回すると、気合を入れて、『方便品(ほうべんぽん)』の有名なくだりを唱え始めた。「……所以者何(しょいーしゃーが)。仏所成就(ぶっしょーじょーじゅ)。第一希有(だいいちけーう)。難解之法(なんげーしーほう)。唯仏与仏(ゆいぶつよーぶつ)。乃能究尽(ないのーくーじん)。諸法実相(しょーほうじっそー)。所謂諸法(しょいーしょほー)。如是相(にょぜーそう)、如是性(にょぜーしょう)、如是体(にょぜーたい)、如是力(にょーぜーりき)、如是作(にょーぜーさー)、如是因(にょーぜーいん)、如是縁(にょーぜーえん)、如是果(にょーぜーかー)、如是報(にょーぜーほう)、如是本末究竟等(にょーぜーほんまっくーきょうとー)」 ボンゾとアナンタ・チャーリトラ(無辺行菩薩=むへんぎょうぼさつ)のみの世界となったグリドラクータの闇のなかで、ボンゾの普段の声量をはるかに飛び越え、それはマイクロフォンを通した宇宙コンサートの主の他人の声のように朗々と響きわたった。「おぬし、なかなかいい声じゃ。わしの前世は中華の坊主だったが、倭語(わご)の音読みでも充分美しいもんじゃのう。むしろ、こちらの方が、五音がはっきりしていて、区切りも良く、落ち着いていて、いいかも知れん。これも、羅什(らじゅう)の書き換えの成せる業じゃ。中華でも、朝鮮でも、倭でも、どの国の言葉でも、等しく音楽になるように、漢字が配列されておるのじゃ。梵語の原語よりはるかに、こちらの方が美しい。序巻にもあるように、『妙法蓮華経』は、東アジアでひろがるとの釈尊の預言があったが、特にうぬの生国の倭国に、この経が保持されると白毫相(びゃくごうそう)が光を貫いたとおりじゃ。わしの解説(げせつ)した一念三千(いちねんさんぜん)理論体系も、倭国の台宗(たいしゅう)のなかで成熟をみて、新義台にいたり修行の事(じ)を得るようになったのじゃからな。 21世紀という末の世に、『妙法蓮華経』が一番、人々に読誦(どくじゅ)されている国は、倭国に他ならない。しかるに、経文がいまだに一部宗教的営業団体の玩具の状態なのは悲しいことじゃ。ボンゾよ、西暦2020年より、いよいよ本当の末法に突入する。それは、うぬが預言したとおりじゃ。白蓮(びゃくれん)の法を真実に復活させるもの、それは、すぐれた文学的表現力をもつものであり、それと同時に幻視の音楽を奏でることの出来るサットヴァのみが成せる業じゃ」「しかし、それは、絶望的な話です」「なにをぬかすのじゃ。それは、そなたの文業と幻視にかかっておるのじゃ」「なんということを、おっしゃるのでしょう。この国では、わたくし以前のとっくの昔に、真の文学的表現は尽きております。わたくしは文学者としては挫折いたしたものであります。一般に表現力が下った現代においてすらも、わたくしの文学的才能は認められてはおりません。以前にも申したとおり、わたくしは、一介の独覚(どっかく)であります。また、それでいいのです」「いいや、それは、わしが許さん。おぬしの文学的才能を誰が、判定したというのじゃ。そんな奴らこそは、文学のくずのような男だったのじゃろう。うぬを見込んで、今晩は、一念三千の理法の円満を講ぜよう。わしが華人として骨肉のあるころの講義ではどうしても舌足らずだったところだ。その後、うぬの国の蓮法師が、わしの一念三千の理法から、一念三千の事法を導き出し、経文をからだで読み込む色読(しきどく)と、『妙法蓮華経』の題目音読と、経文信心に身口意三密(しんくいさんみつ)を置き換え、相即相入させ、凡夫(ぼんぷ)の実践としたのじゃが、わしがいわんとする本当の理の体系を、おぬしに進ぜよう。もう一度言うが、台の根本の一大事は、一念三千の理法にあるのじゃ。これが、根本識を時空にひらくものであり、覚悟あるアーラヤが、この理に触れると、とんでもないことになるのじゃ。よくよく、うぬの色心(しきしん)にとどめ、うつつに戻ったならば、おぬしの文章力(りき)で書き直し、大衆(だいしゅ)に示すがよい。わしも、それをひそかに期するところじゃ。 しんの文学は、妙法蓮華のなかで花開き、それはあらたな仏典となるものじゃ。 うぬは、すでに台宗の素養のあるものだから、骨格だけをつないでゆこうぞ。それでは、『十界(じっかい)』を口に出して言ってみい」「仏教でいう存在と生存のカテゴリーです。迷える世界から覚りの世界への存在領域、すなわち、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅(あしゅら)、人間、天上、声聞(しょうもん)、縁覚(えんがく)、菩薩、仏界のことです」「そのとおりじゃ。うぬの住む人間界にもまた十界が具足(ぐそく)しておるのじゃ。戦争で、爆弾や銃弾や核が落ちれば、人間界にあってもそこは即地獄であろう。人間界で戦争が始まれば、勝者の論理で合法的な殺人だと定義されるが、因と縁によりその指導と前線の渦中にいる人間は、地獄、餓鬼、畜生、修羅の四界をめぐる化身であり、人間道をたもつことが出来ない。 現代倭国のように科学文明がゆきわたり、平和を享受するな国家ではあっても、天界どまりの仕合わせぐらいがせいぜいじゃがのう。心を清くし、行いをただせば、有頂天あたりものぞけるじゃろうが、大多数の労働者・資本家たちは、市場原理で価値をはかる経済社会システムに侵され、その心は人間をよそおう修羅と畜生と餓鬼じゃ。競争に敗れ、借金と犯罪に手を染めるものは、人の財産を盗み、或はみずからに命を絶ち、或は他人を殺し、ひとりひとりばらばらと地獄に堕ちてゆく。 しかるに、仏縁にふれて菩提心をおこせば、縁覚以上の四界が見えて来よう。阿含(あごん)や諸々の大乗経典を手に取り、諸行無常の空観(くうがん)を体得すれば、声聞・縁覚にはなれよう。ところが、この二界にも阿修羅の自殺の可能性は残されておるのじゃ。彼らは、自らの覚りのみに専念することによって、あらたな煩悩に陥る。というのも、利他を忘れた彼らには、色心の解放というものがないからじゃ。孤独な自利の修行を進めてゆくにつれ、彼らは、色(しき)を分析し尽くし、空(くう)を突き詰め、覚りの妄執に固められ、みずからの色心にあつめられた五蘊(ごうん)がばらばらになったような虚無感を包まれるようになり、やがては生き物としての生の喜びをうしない、草木が枯れるように若くして骨から枯れてゆくのじゃ。 彼らが、再び仏法を取り戻すためには、大乗の般若の空だけではおよばない。さらに、『妙法蓮華』をひもとき、五種法師(ごしゅほっし)にならんとすれば、慈悲をやがては覚り、利他をじねんに及ぼせば、加持身(かじしん)がやって来て菩薩の道が見えてこよう。そして、菩薩の加持身が、文底秘沈(もんていひちん)の仏法の究竟(くきょう)にふれるとき、即身にして成仏が成り立ち、仏の本地身(ほんじしん)が説法するのじゃ。このとき、空と慈悲が、くるまの両輪のようにひとしく円満に転がり、修行者は、法華に転がされ、法華を転がし、そしてついには、法華が法華を転がすのじゃ。それは、究竟(くきょう)の法身説法(ほっしんせっぽう)のときなのじゃ。 同様に、他の九界にも、たがいに十界は互具(ごぐ)しよう。地獄にも、修羅道にも、仏・菩薩の階段はあるのじゃ。それが、種となればこそ、悪人・悪霊の成仏もあり得るのじゃ。一方、仏・菩薩界といえども、絶対界とは言えず、そこにも絶え間なき修行はあり、堕落すれば地獄や餓鬼も示現するのじゃ。応身仏であられたゴータマ・ブッダは、久遠実成(くおんじつじょう)のシャーキヤムニ・ブッダとなられた後も、無住処涅槃(むじゅうしょねはん)におられ、我々と一緒に修行されておられるのじゃ。ゴータマは、言語のうえでのつくりものの神ではない。往来永劫を回帰する仏じゃ。真実の仏・菩薩は、一カ所にとどまらず、じしん衆生を見守るとともに衆生とともに修行されておるのじゃ。 シャーキヤムニ・ブッダも言われたが、我々は、成仏したのちは、無住処涅槃におもむき、すなわち、この世とあの世を自在に往き交い、娑婆(サハー)世界を利するのじゃ。仏菩薩には、形がない。仏像には、はっきり形があるではないかと愚かな衆生は言うじゃろうけれど、ある生きている人間がどんな器量が良い人間でも、悪い人間でも、ひとつしか顔を持たぬようには仏像は作られてはおらない。 いったい、たとえばシャーキヤムニ・ブッダのお顔は、この娑婆世界にいくつあるのだというのじゃ。天竺国、西域、毛唐国では、その地方のお顔になり、中華や朝鮮、倭国では、例外もあろうが、モンゴロイドのお顔になる。すなわち、仏菩薩は色心そなえる応身(おうじん)時代の御姿は、衆生と同じ一つだったにもかかわらず、形なき仏・菩薩となられた後には、百千万億のお顔があり、どれも方便の姿なのじゃ。その御姿は衆生に慰安と祈りを与えるが、偶像崇拝がゆき過ぎればそれも煩悩と堕し、仏法を損なうことになろう。 地獄、餓鬼、畜生、阿修羅(あしゅら)、人間、天上、縁覚、声聞、菩薩、仏界の十界に、それぞれのなかの十界が掛け合わせられ、百界となる。これが、十界互具じゃ。谷底の深淵といえども、悪人成仏の種はあり、天上、仏菩薩といえども、絶え間なき修行があるということ、仏道とは、そうとう厳しい教えなのじゃ。 ボンゾよ、十如是(じゅうにょぜ)をもう一度、思い出してみい。こんどは、現代日本語で解説(げせつ)してみよ」 アナンタ・チャーリトラは、原本の『サッダルマ・プダリーカ・スートラ』にはない、十如是がよほどお好きなようだった。「諸々の法が、どのような特性・属性をもち、どのような本質を有するのか、主体としてどのような形体をたもつのか、その形体にはどのような潜在能力があって、それが顕現作してどのような活動をするのか、どのような直接的な原因があるのか、どのような間接的な原因と条件があるのか、それらによってどのような直接的な結果があるのか、またどのような間接的な結果があるのか、そして第一の相から、性、体、力、作、因、縁、果、報の第九までの事柄が究極的にどのように無差別平等に一貫してゆきわたっているのか、以上の十のカテゴリーにおいて、実相をむすび、諸法の実相を知られるをいいます」「よいかな。よく言えた。そのことは、仏菩薩だけが、知っているのであって、声聞・縁覚らの、あずかり知るところではないところじゃ。空法を覚った声聞・縁覚の二乗は、仏法を方程式のように考え、空が絶対の真理であると固定化させ、空があたかも実体としてあるかのような錯覚を抱くようになってしまった。空に溺れる阿羅漢(あらかん)たちは、人生の傍観者と成り果て、慈悲の因と縁をはなれ、実践を離れ、仏法を学問とし磨き立て、修行は自己満足でしかなくなった。そこで、慈悲深きゴータマ・ブッダは、『お前たちでも、成仏はかなうのだ』と一乗妙法を示され、彼らに救いの手を差し延べたのじゃ。その御言葉に、二乗たちの目からうろこが落ちて、まずはブッダの慈悲を知るようになる。慈悲をもらった彼らは、じねんに慈悲を返すことを思い、一乗たる菩薩道、すなわち仏道を歩むことになったのじゃ。 諸法の実相、つまり、ありのままの世界を観察すれば、空は色の、色は空の裏側に固定化されるものではなく、十界互具の百界が、十如是と仮和合(けわごう)して、法界は千界真如(せんかいしんにょ)に現成(げんじょう)する。羅什の『妙法蓮華経』で説かれるのは、ここまでじゃ。いうまでもなく、梵本の『サッダルマ・プンダリーカ・スートラ』には、十如是はない。羅什が、白蓮の法を方広(ほうこう)するために忍び込ませた作為じゃ。しかるに、さらなる三世間(さんせけん)が必要じゃった。これは数合わせではない。妙法蓮華を即身成仏方便経とするために補足かつ解説せねばならぬものだったのじゃ」(陰暦8月27日楽天大衆に示す 『法華経秘釈』第2巻つづく)
2007年10月07日
-
第26月法 三諦円融(さんだいえんゆう)…妙法蓮華経秘密釈(法華経秘釈・第二巻)其の三
目の前には、アナンタ・チャーリトラ(無辺行菩薩=むへんぎょうぼさつ)が、細い目で見据えるようにして、自分を見つめていたのに、ボンゾは、蛇ににらまれた蛙のごとく動けない。「ボンゾよ、『妙法蓮華経』第2巻は、まだ、終わっておらないぞ。経文に書かれたこと以上に、経文の解釈と、そこから導き出される体系が、時に後に仏教宗派の根本教義となることがあるが、これからわしが述べる一念三千(いちねんさんぜん)並びに十界互具(じっかいごぐ)の体系が、まさにそれに相当するのじゃ。しかるに、それを教義と言っても誤りになろう。何故なら、それは、一宗教の一宗派の教義とか思想というには妥当ではなく、人類・生命体・宇宙の必然の摂理・法則であるからだ。それを、西欧でひろまった宗教のように「プロヴィデンス」と安易に言ってしまってはならぬのじゃ。おのれが摂理を覚り、他に及ぼし、解脱するというのが菩薩道であり、有情として生まれたからには、それを目指すのが、仏道に他ならぬのじゃ。それは、人間だけではない。動物であれ昆虫であれ、身を動かす事の出来ぬ草木や花ですらだにもがの智慧じゃ。ただ、人間は、他の有情と世間(環境)に及ぼす力が甚大であるがゆえに、道を踏み外してはならぬのじゃ。そのために、仏法は有るのじゃ。分かるか、ボンゾよ、菩薩よ、理解せい。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年09月18日
-
第25月法 開三顕一(かいさんけんいつ)…妙法蓮華経秘密釈(法華経秘釈・第二巻)其の二
「ボンゾよ、目を覚ませ」 アナンタ・チャーリトラ(無辺行菩薩=むへんぎょうぼさつ)の声だった。老人のような声ではあるが、言語明瞭にしてよどみなく、批評精神にあふれた精力的な声でもあった。やはり、いかにも高僧然としていて近寄りがたかったが、ヴィシシュタ・チャーリトラ(上行菩薩=じょうぎょうぼさつ)に比べればよほど人間に近い存在のような気がボンゾにはした。「ブッダの説法が始まろうぞ。 シャーキヤムニがこの娑婆世界に応身仏(おうじんぶつ)として出現された本懐は、一つには、この一乗真実と三乗方便を語るにあったのじゃ。このすぐれた『妙法蓮華経』の教えは、仏がごくある限られたときに説くべきことであって、うぬは、グリドラクータ(霊鷲山=りょうじゅせん)の会衆といっしょに、ウドゥンバラ(優曇鉢=うどんばつ)の花の3千年に一度しか咲かないような非常に希な機会に恵まれたのじゃ」(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年09月01日
-
番外月法 お盆のはなし
昨日は62回目の終戦記念日でした。そして今晩は、お盆の「送り火」の日で、NHKテレビ(1チャンネル)で「京都・五山送り火」を生中継していました。偶然テレビをつけると、リアルタイムで中継されていて、8時半まで見ました。 この期間、各家庭では、精霊棚や仏壇に新鮮なお水をたたえ、お供え物をして、御先祖様や配偶者や、若くして亡くなった子や孫など親しかった者の御霊をお迎えいたします。そして、数日間留まられた御霊をこんどは、あの世へよまたお送りするのです。じつに今月13日から16日はお盆(月遅れぼん)でもあります。画面で、「妙法」の文字が点火され、法華経『如来寿量品(にょらいじゅりょうほん)』の読経が聞こえたそのとき、凡三も合掌いたしました。凡三の亡父は京都の出で、爺様は、大正時代に京都で電機屋を営んでいましたから、縁がないわではないのですが、とりわけ京都が好きだということもないのですが、今晩は、ことさらに感慨深くテレビを拝見いたしました。 ◇ お盆という言葉は、盂蘭盆会(うらぼんえ)の略語のことで、『盂蘭盆経(うらぼんきょう)』に由来します。ウランバナすなわち盂蘭盆とは、梵語(ぼんご)の音写で、本来は、「倒懸(とうけん)、さかさまに吊るされるような非常な苦しみ」というほどの意味です。釈迦の十大弟子の第二で、神通(じんずう)第一のマウドガリヤーヤナ(目ケン連=もっけんれん=。略して目連=もくれん)尊者が、あるとき餓鬼道(がきどう)で苦しみにある母を幻視(げんし)したことから、当時、天竺(てんじく=インド)の7月15日に自発的に懺悔(さんげ)する僧たちを供養し、その功徳で母を救ったという逸事が、「お盆」の本当のもとの話です。この7月15日は、僧たちの夏安居(げあんご)最終日の自恣(じし)の懺悔と重なります。 本来は、陰暦7月15日(今年は8月27日。現代の暦では、これを「旧ぼん」という)に行われるべきものですが、今の暦で毎年日が動くと行事がやりにくいというような理由などから、陽暦の15日に合わせ、7月15日を「ぼん」、8月15日を「月遅れぼん」と称しています。だから、現代では日取りの上で、3種類のお盆があるわけです。比較的に「月遅れ」の方が、本来の盆に近いものです。凡三は、旧ぼんに墓参することにしていますが、今年は、まとまった休みが月遅れぼんの週にとれましたので、猛暑を押し切って敢行したしだいです。 日本では、奈良・平安朝から貴族階級の間で公事として行われ、鎌倉時代からは施餓鬼(せがき)もあわせて行われ、先祖供養として庶民にもゆきわたり、江戸時代に至り、市が立ち、閻魔詣(えんまもう)で、盆踊りなど民間行事も盛んになったというわけです。盆踊りというのは、本来は、この世のためではなくて、あの世のためのものなのです。現代人の盆踊りは、一体だれのためなのかを考えると、なんだかおかしいような気がします。でも、いまあるひとが、真夏に汗をかき、おどりくるい、子孫たちの元気なことを、あの世の人も不成仏霊ではない限り、みな喜んでいることでしょう。ちなみに、『盂蘭盆経』そのものは、天竺撰ではなくて中国で作られた偽経とされています。 凡三は、母龍英院と父龍雲院の供養のため、昨日さいたま市の墓前に自家用車で参りました。神通力はほとんどない凡三ですが、あの世の御経、『妙法蓮華経』第十六品『如来寿量品』を御霊前に読誦いたしました。また、戦没者のためにも、第二十五品『観世音菩薩普門品』(『観音経』)と『般若心経』を自宅仏壇でささげました。 家と同様、車のクーラーは、壊れてきかない状態なのですが、かくなる猛暑でも、なければないで、どうにか水をのみのみ、どうにか汗をふきふき、過ごせるもので、昔は、みんなこうだったのですし、この方が、自然というものなのかも知れません。ナム・サッダルマ・プンダリーカ・スートラ。(陰暦7月4日 陽暦月遅れ盆記す)
2007年08月16日
-
第24月法 三止三請(さんしさんしょう)五千起去(ごせんきこ)…妙法蓮華経秘密釈(法華経秘釈・第二巻)其の一
宿命通(しゅくみょうつう)によって前世を見ていたゴータマ・ブッダは、三昧よりゆったりと立ち上がられた。ブッダは、前世の菩薩の修行に誓願を立てたことをつまびらかに思い出していたのだった。 ゴータマ・ブッダは、シャーリプトラ(舎利弗=しゃりほつ)尊者に告げられた。「如来(タターガタ)の智慧(ちえ)は仏(ブッダ)の智慧にして、甚だ深くして量りがたし。その智慧の法門は、理解しがたく、容易に入ってゆくことが出来ない。修行者といえども、声聞(しょうもん)や辟支仏(びゃくしぶつ)には、知ること能わざるところなり。ゆえはいかん。如来は、百千万億の仏に出会い仕えて、無量の道法をまねび行じ、とおく勇猛精進し、甚深なる未曾有の法を成就し、時機に応じて説きたまえるところなれば、その意図するところの根本を理解すること難しければなり。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年08月05日
-
番外月法 あぁサイテーの人生哉
昨日の参院選の関東地方は、前日の猛暑と打って変わって、午後からは刺すような大粒の雨嵐となり、意志ある国民が駆けつけ、やっと愚民政治の本質をうち崩そうと投票所に向かったと思われます。凡三は、金曜からの大阪出張で身も心もぼろぼろ、今は蒲団と書物の中で心身を修復中であります。いくら、給料が一般企業よりはましだとじはいえ、これマスコミ・ジャーナリズムは賤業にほかならず、歎きに苦しむ我も我なし、ああ、サイテーの人生、創作三昧に生きられるのはいつのことや、四捨五入で我もかくに50歳、いよいよ追いつめられ、掌と白髪に意志の表象としての現実を見て、つくづくこの世の果てまでもが、悲しく、もうどうにもならず、オルガの亡霊も、いまや、たたりではなく、守り観音と、一緒に同衾するふしだらなサイテーの生活に沈没(ちんもつ)する我なり…。嗚呼。酒、さけ、ぐち、なげき…の反復の繰り返し… 『妙法蓮華経秘密釈 一念三千あるいはホウベン』は、来週には仕上げまする。 方便凡三吠
2007年07月30日
-
第23月法 書写法師…妙法蓮華経秘密釈(法華経秘釈)その五
「我が法身、すなわち、久遠実成のシャーキヤムニ・ブッダは、密宗での呼び名をマハーヴァイローチャナともいうが、系の太陽の寿命とともにこの尊称はなくなるであろう。我は、法身としてしか存在し得ず、宇宙の一陣の風となろう。空無の真空の力こそは我なり。 我の最後にして最大の仕事は、太陽系第三惑星に住む、地獄の住人たちに始まり、地上に住む人間をはじめとする一切衆生たち、天の神々すらも生命が終わるとき、彼らのアーラヤ(阿頼耶識)をほかの宇宙銀河のいずれか惑星に転ずることである。ただし、かの経文を修行するものに限られよう。あとは、一切、十界(じっかい)の差別(じっかいしゃべつ)を問わない。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年07月08日
-
第22月法 真末預言…妙法蓮華経秘密釈(法華経秘釈)その四
そのときシャーキヤムニ・ブッダは語られた。「驚くには値しない。将来の『正しき教えの白蓮』の教えは、東洋の果ての粟粒のごときモンゴロイド単一民族の国で、『妙法蓮華経』すなわち『法華経』という名で保存される。ただし、今から五五百歳(=ごごひゃくさい。2500年)を過ぎ去った後には、仏法は、形骸化し、やがては廃れるだろう。破戒の鸞や怪僧・蓮が措定した方便の末法は終わり、本当の末法がやって来よう。それは、壊劫(えこう)、すなわち地獄界が壊れてゆくことの始まりなり。それと同時に、東アジアの衆生に慰安を与え続けて来た極楽浄土も衰退してゆこう。 西方浄土は、地獄の照り返しの方便である。ヤマラージャ(閻魔王=えんまおう)の力が弱まるごとに、アミターバの光も弱くなろう。そしてアミターユスの寿も有限となろう。それは、すべて、西暦2020年から1万年を舞台とするであろう。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年06月24日
-
第21月法 ネアンデルタールの呪い…妙法蓮華経秘密釈(法華経秘釈)その三
猿が二本足で歩いているような猿人(えんじん)の姿が見えて来た。そして脳の容積が二倍になった原人、そして脳の容積がホモ・サピエンスとほぼ同じになった革の褌(ふんどし)姿の旧人、そして肩から衣服を身につけている新人の姿が、シャーキヤムニの光線のなかに現れては消えて行った。旧人と新人のはざまで、お互い槍や石斧を用いて血を流し合って戦争をするネアンデルタール人とクロマニヨン人の凄絶な戦いも見えた。 この決死の戦争で新人に味方したのは、体力や脳の大きさではなくて、喉の構造の違いだった。少し前かがみだった旧人は、発音上、より複雑な言語表現を操ることが出来ないゆえに、比較的多くの語彙(ごい)を有する新人の陰謀に打ち負かせられたというわけだった。記号の多さは、知性の発展にも寄与した。ブッダの白光が、彼らの頭蓋を貫いた。脳の容量が同じではあっても、脳髄の構造が微妙に変わったのだった。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年06月10日
-
第20月法 光中東漸…妙法蓮華経秘密釈(法華経秘釈)その二
天神と菩薩と阿羅漢と王と人非人等は、ゴータマ・ブッダの眉間の白毫相(びゃくごうそう)の光のなかに、六道を輪廻する人間や動物や天上の神々を見た。また、菩薩が修行を積み重ね、やがては如来となり、仏国土を築き、人々を救済している姿も見えた。 シャーキヤムニ・ブッダと縁のある土地からは、ブッダの縁起の教えをより徹底され、空(くう)を説くナーガールジュナ(龍樹=りゅうじゅ)と、空の崇高な思想が虚無的で退廃的な思考に陥らないように、空と不空(ふくう)を覚るために瑜伽(ゆが=ヨーガ)の実践を行いつつ、人間の生命体としての根本識たる阿頼耶識(あらやしき=アーラヤヴィジュニャーナ)の在り処を求め、かつその清浄と消滅を修行とするマイトレーヤ(弥勒菩薩とは別。無著の師)と、アサンガ(無著=むじゃく)とヴァスバンドゥ(世親=せしん)兄弟の一派が現れた。彼らは、瑜伽行派(ゆがぎょうは)と言われた。現代でいうところの唯識(ヴィジュニャプティマートラター)の哲学体系をつくった菩薩たちである。弟のヴァスバンドゥは、『倶舎論(くしゃろん)』を書いた後に、大乗に転向した。彼らは、北西インド、ガンダーラ地方の出自であった。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年05月27日
-
第19月法 いわれ…妙法蓮華経秘密釈(法華経秘釈)その一
ボンゾは、姿の見えないヴィシシュタ・チャーリトラ(上行菩薩)に聞いた。「菩薩よ、世尊は何がゆえにこの光明を放たれたのでしょう。何の徴候でしょうか。わたくしボンゾは、なんのゆえがあって、いまここにいるのでしょうか」 たくさんの菩薩や神々たちも、その名も知らぬ居士(こじ)の方を振り返った。「うぬと同様の質問をその昔、マイトレーヤ(弥勒菩薩)が、マンジュシュリー(文殊菩薩)に問うた。それを、わしは今思い出した。 いま、シャーキヤムニ・ブッダ(釈迦牟尼仏)は、大法の雨を降らし、大法の鼓を打ち鳴らし、大法の義を述べんと欲せられているのだ。わしは、過去の諸々のタターガタ(如来)たちが、かつて同じ奇瑞(きずい)を示されるのを見たてまつったが、かの光を放ったあとに、みな等しく白蓮の法を説かれたことを知っている。しかし厳密に言えば、シャーキヤムニ・ブッダはすでに、『サッダルマ・プンダリーカ』を説いてしまわれた。しかるに我々は、追いつかねばならぬ。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年05月13日
-
第18月法 妙法蓮華経秘密釈 プロローグ
「ボンゾよ、聞こえるか。宇宙の始まりの説法が始まろうぞ。永遠に繰り返される銀河宇宙と、生きとし生けるものの輪廻の去っては来るは諸行無常、始まりは、終わりの始まり、そして終わりは、始まりの始まり、物語の円環は、永劫(えいごう)回帰せん。 水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星等がめぐる太陽系も、七十億年の後は亡びよう。それよりはるかに早く、十数億年ののちには、この水と緑の第三惑星の有情は、あまねく生命を保てず、そのアーラヤ(阿頼耶識)浮遊し、骨肉を失わん」 ボーディサットヴァ(菩薩)は、夢追い人に語った。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年05月04日
-
第17月法 末世の三業受持…五種法師(最終回) 妙法眼蔵 其の二(下)の二
受持(じゅじ)が正業だと日蓮が言ったが、霊感と法力の堕落した現代人にとっては、いきなり題目をとなえ、つぎに経文をもつだけの信心はなかなか容易ではない。それでも今の日本人は、みんながみんな読み書きをするようになったのだから、二十八品(にじゅうはっぽん)の経文をまずはよむべし。そこに、感動のあるものが、次へ進めばよい。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年04月06日
-
第16月法 正・像の三業受持…五種法師 妙法眼蔵 其の二(下)の一
さても、21世紀の五種法師である。すなわち、普段着で民間に住し、折伏(しゃくぶく)ではなく、摂受(しょうじゅ)によって『法華経』を衆生に知らしめようとしている在家の居士のことである。「夫、摂受・折伏と申す法門は、水火のごとし。火は水をいとう。水は火をにくむ。摂受の者は折伏をわらう。折伏の者は摂受をかなしむ。無智悪人の国土に充満の時は摂受を前とす。安楽行品のごとし。邪智謗法の者多き時は折伏を前とす。常不軽品のごとし。(中略)夫、釈尊は娑婆に入り、羅什は秦に入り、伝教は尸那に入る。提婆・師子は身をすつ。薬王は臂をやく。上宮は手の皮をはぐ。釈迦菩薩は肉をうる。楽法は骨を筆とす。天台云、時ニ適フ而已等云云。仏法は時によるべし」(『開目抄』日蓮撰) 現在は、直接に『法華経』を非難するものは、ほとんどいないと言っていいくらいである。最澄と日蓮のおかげで、浄土系宗派を除いては(「融通念仏宗=ゆうずうねんぶつしゅう=」では所依=しょえ=の経典の一つとして選ばれている)、各派で、宗門所依のテキストには選ばれていなくとも、一目置かれている経文なのである。謗法(ほうぼう)というよりはむしろ無智、すなわち、現代においては、日本人と非常に縁の深い経文――聖徳太子は7世紀初頭に、『法華経』の注釈書である『法華義疏(ほっけぎしょ)』を撰述され、伝教大師は8世紀終わりに、決定的に『法華経』を選び取られ、叡山(えいざん)を立てられ、9世紀初頭に成った『日本霊異記(にほんりょういき)』(景戒=きょうかい=撰)によれば当時すでに、『法華経(法花経)』と観音菩薩の霊験が広く民間に浸透していたことが分かる。また、この書には、官の許可なく私的に得度した無名の私度僧(しどそう)の説話がたくさん収められており、そのなかの、法華経の禅師が、熊野の山の断崖絶壁に身を投げて亡くなったあとも、岩につりかかって、風雨にさらされ、しゃれこうべになりながらも、舌だけが残り、法華経誦経(ずきょう)の修行を続ける怪異譚は印象的である。そして、13世紀には、文殊師利(もんじゅしり)菩薩としての「法華経の禅師」と、上行(じょうぎょう)菩薩と観世音菩薩と妙見菩薩の三身即一身(さんじんそくいっしん)としての「法華経の行者」が、前後して東粟国(とうぞっこく)に化現(けげん)され、からだは小さけれど、この国は、法華を転がす国とはなったのである。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年04月01日
-
第15月法 あまりにも芸術的な…五種法師 妙法眼蔵 其の二(中)
身と心が曲がっている人が、『法華経』を必死に読んでも、何も感ずるところがないから不思議である。そのようなやからに対しては、この経文は、ただの漢文にとどまるのである。欲の塊のような人、人を呪う人、思いどおりにならない世界を呪う人が、経文を呪術の道具として用い、効果のないことをいぶかり、瞋恚(しんに)の気持ちを抱くと、この経は、仇(あだ)をなす。20世紀は、軍事思想と各種新興宗教の影響で、一見この経文が流布したように思えるが、そういうふうに経文はおもちゃにされた時代でもあった。やれハルマゲドンだの、やれ日蓮本仏だの、教祖本仏だのと、『大集経(だいじっきょう)』の「月蔵分(がつぞうぶん)」、すなわち『月蔵経』に説かれる白法隠没(びゃくほうおんもつ)をいいことに、戯論(けろん)が喧伝された。そんなことはいっさい、経文には書かれていない。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年03月16日
-
第14月法 最期の道元となえしもの…五種法師 妙法眼蔵 其の二(上)
教外別伝(きょうげべつでん)を宗とする禅家に属し、類い希な文章力によって少なからぬ著作を残された道元禅師は、死を前にして、一生の道場と決めた越前・永平寺から故郷の京の街に戻り、高辻西洞院(にしのとういん)俗弟子・覚念(かくねん)宅に入った。すでに、病は膏肓(こうこう)に入り、禅師の五大(ごだい)の均衡を損じ、禅師は、身体の自由を無残にも奪われる身となっていた。若於園中(にゃくおーおんちゅー) ソコガ遊園デアロウガ若於林中(にゃくおーりんちゅー) 林ノ中デアロウガ若於樹下(にゃくおーじゅげー) 木ノ下デアロウガ若於僧坊(にゃくおーそうぼー) 僧坊デアロウガ若白衣舎(にゃくびゃくえーしゃー)在家ノ者ノ家デアロウガ若在殿堂(にゃくざいでんどー) 殿堂デアロウガ若山谷曠野(にゃくせんごっこうやー)ソコガ山谷ヤ荒野デアロウガ是中皆応(ぜ-ちゅーかいおー) ソコニハ皆スベテ起塔供養(きとうくーよう) 塔ヲ建テテ供養スベシ所以者何(しょーいーしゃーがー) ナゼナラ当地是処(とうちーぜーしょー) マサニ経巻ノ有ル所即是道場(そくぜーどーじょー) ソコハ即修行ノ道場デアリ諸仏於此(しょーぶつおーしー) 諸々ノ仏ハココニ於イテ得阿耨多羅三藐三菩提(とくあーのくたらさんみゃくさんぼーだい) 最高ノ覚リヲ行ジタノデアリ諸仏於此(しょーぶつおーしー) 諸々ノ仏はココニ於イテ転於法輪(てんのうぼーりん) 仏法ノ教エヲ回シタノデアリ諸仏於此(しょーぶつおーしー) 諸々ノ仏ハココニ於イテ而般涅槃(にーはつねーはん) ニルヴァーナニ入ラレタノデアル 禅師は病床を抜け出し、経行(きんひん)しつつ経文を誦(じゅ)した。そして、最期の力で、柱にその経文を書き付けた。「妙法蓮華経庵」とみずから名付けた部屋で、禅師は、最期の修行をしていたのである。ここでの仏法のまねびは、師資相承(ししそうじょう)、只管打坐(しかんたざ)の方法ではなく、『妙法蓮華経』へのひたすらの信心である。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年03月03日
-
第13月法 妙法眼蔵 其の一(下)
仏滅後、釈迦の生前の一代説法を確認するとともに散逸するのを防ぐために、直弟子の大迦葉(だいかしょう)が座長となって、阿難(あなん)と優波離(うぱり)が、教法と戒律の編集責任者となって、第一結集(けつじゅう)が行われた。行者たちの類い希な記憶術と編集術によって、釈迦の説法は、経と律にまとめられた。とはいうものの、この経典は、筆記されたものではなく、行者たちが暗唱されたものであり、彼らの阿頼耶識(あらやしき)に体系的に熏習(くんじゅう)されたものだ。それらは時間とともに、徐々にパーリ語の小乗経典にまとめられて行った。そののち標準語のサンスクリット語でも筆記されるようになった。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年02月18日
-
第12月法 妙法眼蔵 其の一(中)
凡三が先述の『如来滅後五五百歳(にょらいめつごごごひゃくさい)』で繰り返し説明したように、『大集経(だいじっきょう)』「月蔵分(がつぞうぶん)=俗に『月蔵経』ともいう」に説かれる白法隠没(びゃくほうおんもつ)の時は2020年に終わり、白法、すなわち、白蓮(びゃくれん)の法は、澆季(ぎょうき)に復活せむ。 白蓮の法とは、正しき教えの白蓮、別称を、「無量義経」「最勝修多羅」「大方広経」「教菩薩法」「仏所護念」「一切諸仏秘密法」「一切諸仏之蔵」「一切諸仏秘密処」「能生一切諸仏経」「一切諸仏之道場」「一切諸仏所転法輪」「一切諸仏堅固舎利」「一切諸仏大巧方便経」「説一乗経」「第一義住」「妙法蓮華経」「最上法門」という。四大訳経家(しだいやっきょうけ)最大の鳩摩羅什(くまらじゅう)三蔵(さんぞう)が、経の題目を『妙法蓮華経』と漢訳され、この漢字の配列が、北東アジアで決定的に定着した。略して『法華経』という。 仏法が、正法時に教(きょう)・行(ぎょう)・証(しょう)を眼蔵する時はとうに過ぎ去り、像法時に教・行を眼蔵する時も完全に終わらんとし、仏法は末法によって行を滅せられんとする時、「教」のみが残ると言われ、その教えに眼蔵せられる有時(うじ)の行を我々が探し求める時である。教えの認識を即身に修行とし、修行にあなたのフォームを与え、それを創造的にかつ絶望的に繰り返すことによって、あなたの存在と時間を銀河の絶対持続のなかに引き込み、そしてその瞬間に、あなたは引き込まれ、あなたは、あなたでなくなる。その一時に、あなたを縛り付ける物質的な煩悩から解放され、あなたは即興のときを永劫のひとときに生きるのだ。その時、あなたは、誰でもない。あなたからは、すっかり我(が)抜け落ちてしまっている。それは、世界を切り開くときであり、宇宙の進化の一齣であろう。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年02月10日
-
第11月法 妙法眼蔵 其の一(上)
十方(じっぽう)仏土中者(は)、法華の唯有(ゆいう)なり。これに十方三世一切諸仏、阿耨多羅三藐三菩提衆(あのくたらさんみゃくさんぼだいしゅ)は、転法華(てんほっけ)あり、法華転(ほっけてん)あり。これすなわち、本行菩薩道の不退不転なり、諸仏智慧甚深無量(じんじんむりょう)なり、難解難入(なんげなんにゅう)の安祥三昧(あんじょうざいまい)なり。(中略)これを妙法蓮華経ともなづく。教菩薩法(きょうぼさつほう)なり。これを諸法となづけきたれるゆゑに、法華を国土として、霊山(りょうぜん)も虚空もあり、大海もあり、大地もあり。これはすなはち実相なり、如是なり、法住法位なり、一大事因縁なり。仏之知見なり、世相常住なり。如実なり、如来寿量(にょらいじゅりょう)なり。甚深無量なり、諸行無常なり。法華三昧なり、釈迦牟尼仏なり。転法華なり、法華転なり。(中略)よろこぶべし、劫(こう)より劫にいたるも法華なり、昼より夜にいたるも法華なり。法華これ従劫至劫(じゅうごうしごう)なるがゆゑに。法華これ乃昼乃夜(ないちゅうないや)なるがゆゑに。たとひ自身心を強弱すとも、さらにこれ法華なり。あらゆる如是(にょぜ)は珍宝なり、光明なり、道場なり。広大深遠なり、甚大久遠なり。心迷法華転なり、心悟転法華なる、実にこれ法華転法華(ほっけてんぼっけ)なり。心迷えば法華に転ぜられ、心悟れば法華を転ず。究尽(くじん)すること能(よ)く是の如くなれば、法華、法華を転ず。かくのごとく供養恭敬(くぎょう)、尊重讃歎する、法華是法華なるべし。正法眼蔵 『法華転法華』仁治(にんじ)二年辛丑(かのとうし)夏安居日(げあんごび)、これをかきて慧達(えだつ)禅人にさづく。(略)今日の出家は、従来の転法華の如是力の如是果報なり。いまの法華、かならず法華の法華果あらん。釈迦の法華にあらず、諸仏の法華にあらず、法華の法華なり。ひごろの転法華は、如是相も不覚不知にかかれり。しかあれども、いまの法華さらに不職不会にあらはる。昔時も出息入息(しゅっそくにっそく)なり、今時も出息入息なり。これを妙難思の法華と保任(ほうにん)すべし。 開山観音導利興聖宝林寺 入宋伝法沙門 道元記 ◇ 以上は、道元の主著『正法眼蔵』からの省略引用である。 後書にもあるように、道元42歳の仁治2年の夏安居に、すでに慧達禅人なる出家者が自分のもとに心も新たに参禅したのを機会に、これを書き与えたものである。42歳といえば、道元の言の葉の天才が、春の山に満開に咲き誇り、記号としての言語を道断し尽くし、言即是仏、仏即是言のうちに身心脱落(しんじんだつらく)された、いわば禅師の最大にして最深の即身是仏(そくしんぜぶつ)の有時(うじ)であった。それから44歳の『諸法実相』までの2年間が、『眼蔵』の山頂と言われている。奇しくも、最初と最後が『法華経』ネタになっているのは因縁果であろう。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年02月02日
-
番外月法2 2006 Best 10 CD & DVD of 305
1.『J.S.バッハ/世俗カンタータ全集』ペーター・シュライアー指揮/ベルリン室内管弦楽団/ベルリナー・ゾリステン(合唱) アルヒーフ・ポリドールF00A 29027/34(CD8枚組・国内限定盤) 1889年12月に限定プレスで出たもの。同時期に出た25枚組のカール・リヒターの『教会カンタータ選集』は手に入れることが出来たが、当時、シュライアーの凄さが分からなかった青年はカタログから外した。17年の歳月の後に、ディスクユニオンお茶の水クラシック館で見つけたしだいである。外盤では、廉価盤として容易に手に入れられるのだが、リヒター盤と対で、国内盤が欲しかった。解説書の「パロディー対照表」も収穫。 その作曲家には、その人を代表するジャンルというものがあり、その因縁が最高傑作に結び付く例が多い。モーツァルトはオペラであり、最高作は、後期四大歌劇である。ベートーヴェンは、交響曲ではなくカルテットであり、最高作は、後期弦楽四重奏曲群である。ジャンルにこだわらず千曲以上書いたシューベルトではあるが、やはり、彼を決定付ける分野は歌曲であり、最高作は、三大歌曲集である。それらの代表ジャンルのおおよそを聴いていないで、その作曲家を語るのなら、それはすべて参考にならない、まやかしの評論である。 音楽の父、バッハはというと、むろん、『ミサ曲ロ短調』や『マタイ受難曲』、『フーガの技法』、諸々の鍵盤作品など超傑作はあるものの、バッハの因縁のジャンルは、カンタータである。だから、カンタータの大体を聴いていないで、バッハを語るなど資格なきものである。 青年の頃からいい鼻をもっているつもりだったが、片手落ちであった。教会カンタータさえ聴いていれば、残りのバッハはすべて分析出来るとにらんだものの、世俗カンタータの教養がない私は、やはりバッハをとらえ切れなかった。有名な『狩のカンタータ』『結婚カンタータ』『コーヒー・カンタータ』『農民カンタータ』だけでも聴いて欲しいものである。それらは、モーツァルトのドイツ語オペラとウェーバーをつなぐ線である。ドイツ庶民の愚直かつ機知あふれる娯楽である。 シュライアーはじめ、テオ・アダム、エディト・マティス、ルチア・ポップ等名歌手が勢ぞろい。ポップは、我が青春の永遠のアイドルだ。2.『ザ・コンプリート・ジャック・ジョンソン・セッションズ』 マイルス・デイビスソニー・ミュージックエンタテインメントSICP431~5(CD5枚組・国内限定盤・DSD Mixing) 中古屋で出回っているが、必ず盤質の良いものがあるとは限らない。運よく新品様中古を見付けることが出来た。エレクトリック・マイルスの方向性は、大編成の和声とリズムの混沌たる『ビッチェズ・ブリュー』セッションズと、比較的小編成のタイトなリズム形から一切が構築される『ジャック・ジョンソン』セッションズに代表される。その中間的な混交が『オン・ザ・コーナー』であり、そのどれもがマイルスの金字塔だ。ここでの主役は、マイケル・ヘンダーソンのエレクトリック・ベースの呪術的ともいえるルーティン・リフであり、ジョン・マクラフリンの創造的な短いコードとそのリフである。剥き出しのベースとリズム・ギターが音楽の素形を立ち上げ、マイルスがストレートにジャズのイディオムを振り捨てんばかりにロックンロールを演じる。ところで、出来上がってみれば、それは、徹頭徹尾マイルス・ミュージックだから不思議である。アイデアは、第一にマクラフリンであり、次にヘンダーソンのものだったが、本番のセッションが始まるや、マイルスの強靭な精神のエネルギーに包摂される。マイルスが吹いていないところでも、マイルスが鳴っている。3.『ショスタコーヴィチ/弦楽四重奏曲全集』 フィッツウィリアム弦楽四重奏団ユニバーサル UCCD9292/7(CD6枚組・国内限定盤) 2005/7発売の紙ジャケ限定盤。すでに、デッカの外盤でもっていたのだが、解説書が読みたいのと、ジャケットに惹かれて、また、「リマスター」とは書いていないが、音質向上を期待して購入した。聴いてみてまずは、音質がリマスターされているのに北叟笑む。全く新しい録音のように聴こえる。非リマスター盤も、もともと悪い音ではなかったが、霧がはれ、弦が一つ一つ太くなり、明確に響くようになった。 繰り返し10回は聴いてしまった。演奏家が生前の作曲家と交流があったという縁をもつが、この演奏の全体の水準は高い。特に、最後の作品となった『15番』は、どれよりも素晴らしい。作曲家の招霊妖術を再現しているのは、この演奏だけだ。 昨年がショスタコーヴィッチ生誕100年に当たっていなければ、もしかしたら購入していなかったかも知れない。それを考えると恐ろしい。デッカ盤は、中古屋に売りに出した。4.『フォアキャスト:トゥモロウ』 ウェザー・リポートCOLUMBIA 82876-85570-2-S1(外盤CD3枚+DVD1枚) 2006の新譜ではあるが、新しい曲は、2曲のみ。しかし、全体が本当の新譜のように聴こえるのは、プロデュースがし直され、おそらくリマスターされたからだろう。ベスト盤としても聴けるのだが、時代によってのアルバムごとのリマスターの凸凹があまり気にならないのが不思議だ。このような、マスター・テープ或は原盤以上の音が家庭で聴けるような時代になって、少し長生きして凡三も本当に感激である。 おまけのDVDは、音質が劣るが、78年当時の最高のリズム隊を抱えていた時のものであり、貴重な映像である。やはり、ライブでの「ウェザー」は、作曲家・プロデューサーのジョー・ザビヌルではなく、演奏家ウェイン・ショーターのサックスが、バンドを動かしていたことが分かる。マイルスの呪術的指導性を、ウェインは、ウェザーで再現している。ウェインのテナーやソプラノが入ると、曲が息づき、生き物のフィギュアを得る。怖い。5.『マーラー/交響曲全集』 ショルティ指揮/シカゴ交響楽団LONDON DECCA 430 804-2(外盤CD10枚組) バラで集めていたが、2番、3番、9番が長年欠落していたので、思い切って、ボックスを購入した。これで、マーラーのボックスは、7種類目だが、バーンスタインのグラモフォン盤と双璧であることを実感。特に、2、4、5、6、8、9は絶品。『大地の歌』は収録されていない。ショルティはその昔、ワーグナーの『指環』やモーツァルトの『魔笛』などオペラ作品にいたく感動し、オペラ指揮者だと思い込んでいたが、このボックスCDを聞き直し考え直させられた。ブラームスの交響曲全集も買ってみたが、こちらも、絶句してしまった。今年は、他の全集も買ってみよう。スコアに忠実で恣意がない。他の指揮者・楽団では聞こえない楽器がはっきりと聞こえる。少し、弦が硬いが、よく鳴っているので文句は付けられない。むしろ、ブルックナーとは異なり、ウィーン・フィルのあの分厚いくすんだ弦よりも、マーラーがねらっていた響きはこちらかも知れない。『9番』の鉄鋼の響きは、メカニカルにしてデモーニッシュ。ショルティに脱帽。6.『ショスタコーヴィッチ/管弦楽曲&協奏曲集』 アシュケナージ、バルシャイ、ハイティンク、プレヴィン、ケーゲル、シャイー他/ロイヤル・コンセルトヘボウ管、フィラデルフィア管、ロイヤル・フィル、ヨーロッパ室内管、ボストン響他 UNIVERSAL DECCA 475 7431(外盤CD9枚組) ショスタコーヴィッチ生誕100年で、出たユニバーサルの企画ボックス・セットの一つ。他に、『交響曲』『弦楽四重奏曲』『声楽』『ピアノ&室内楽』編が出ている。日本盤と外盤では、同じ企画でも、区画分け、CD枚数が違うので、要注意。小生が買った外盤の管弦楽集には、『森の歌』や『ステパン・ラージンの処刑』等の歌もの、ピアノ、バイオリン、チェロの協奏曲も入っている。 このセットのメーンは、映画音楽とバレー音楽である。悪くはないが、飯を食うために才能を浪費していたことが分かり、ことさらながらに、ショスタコーヴィッチが、20世紀の職業音楽家であったことを思った。しかし、彼はまた、浪費することをコントロールすることが出来た、意志の人でもあった。それだからこそクラシック音楽の交響曲、協奏曲、室内楽曲等のジャンルで、歴史に残るものを作すことが出来たのである。7.『ブルックナー/交響曲全集』 ロジェストヴェンスキー指揮/ソビエト国立文化省管弦楽団 露ヴェネツィアCDVE04240(外盤CD11枚組) 再発ではあるが、2006年新譜である。同じヴェネツィア・シリーズの同じ指揮者の『ショスタコーヴィッチ交響曲全集』も良かったが、ショスタコーヴィッチばかりになってしまうので、こちらを選んだ。メロディア音源だが、リマスターした感じはしない。音のバランスが少し悪いが、音が悪いと言えるほどではない。『0番』は、ハルモニア・ムンディ盤の方が音が全体に分厚かったが、管楽器はこちらの方がよく聴こえる。 雑で無神経なロジェヴェンの汚名は、このセットを聴けば解消される。また、いわゆる『0番』のみならず、『00番』も全集に含み、両演奏とも、最高水準にある。これだけでも、買うに値する。8.『ディープ・パープル・ライブ・イン・コンサート1972/73』eagle vision EV30140-9(外盤DVD) 昔、『マシン・ヘッド・ライヴ72』で出ていたものの再発盤。おまけに、アメリカでのカラー映像3曲が足されている。国内盤にさきがけて出回っていたので、1月に早々購入した。ビデオ・テープ当時より音がよくなっている。疑似ステレオであろうか。リッチー・ブラックモア、イアン・ギランが凄いのは当たり前のことだが、こうして聴き返してみると、ベーシスト、ロジャー・グローヴァーがバンドのキー・マンだと理解した。よく聴いてみれば、イアン・ペイスのドラムスでもなく、リッチーのカッティングでもなく、ロジャーのリズム形がこの第2期黄金時代の楽曲を隅々まで支配している。おそらく、作曲面でも当時のほとんどの曲に本質的にかかわっていたのではないだろうか。だから、リッチーはロジャーを首にしようとたくらんだのだ。9.『クイーン・オブ・ノイズ』 ザ・ランナウェイズユニバーサルUICY-93042(国内盤CD・2006年24bitリマスター) デビュー30周年ということで、ガールズ・ヘビーメタル・ロックンロール・バンドの草分けの代表作3枚(上記タイトル他に『悩殺爆弾』76年、『ライヴ・イン・ジャパン』77年)が、2006年に24bitリマスターで再発された。3枚とも、素晴らしいアルバムだが、曲がいいのと、ジョーン・ジェット色が強い、セカンド・アルバムをあえて選んだ。ファーストでは、ジャッキー・フォックスのベースが差し替えられてしまったが、セカンドでは、うねりあるジャッキーの音が聴ける。 当時は、なんだか、たいそうな色物として勘違いされていた節もあった。だが、全員が10代で、このボーカル、このギター、このベース、このドラムスである。いま聴けば、曲の良さはむろんのこと、テクニック、音程、品格、ソノリティと申し分ない。リマスタリングで、ギター、ベース、ドラムスの音の分離がくっきりしていて、細部まで聴こえるようになった。それでも、あらはほとんど聴こえて来ない。悪徳プロデューサー、キム・フォーリーの実力も相当なものだ。 昨年10月21日、ドラマーのサンディ・ウェストさんが、肺癌のため他界された。47歳だった。合掌。10.『シベリウス/交響曲全集』 ベルグルンド/ヨーロッパ室内管(Chamber Orchestra of Europe) FINLANDIA RECORDS 3984-23389-2(外盤CD4枚組) シベリウス一筋、ベルグルンド3度目の入魂の全集。交響曲のみで、今までのように余計な管弦楽曲は入っていない。オーケストラの性格から室内楽的に凝縮した演奏となっている。無駄な音を削ぎ落とし、必要な音だけが鳴っている。時折、北欧人ならではの剥き出しの自然が噴き出るところもあり、もしかしたら、これこそが、シベリウスがスコアに描いていた音かと感激してしまう。(この項おわり。陰暦12月朔日記す)
2007年01月19日
-
番外月法2 2006 Best 5 Book of 49
1.『精神のエネルギー/ベルグソン全集5』 渡辺秀訳(白水社) ベルクソンのいわゆる四大著作以外に、落ち穂拾いをしている昨今ではある。今年のベルクソンは、上記著と『笑い』を読了。レグルス文庫(こちらは入手可能である)の宇波彰訳と平行させながら読んだ。一つのテーマで、過去の講演・論文を集めたものだが、濃密かつ論理的である。物質的完成を生命進化に重ね合わせ、物質を極めてゆくうちに、物質のエネルギーは蓄えられ、生が自由を得ようと物質を貫く何ものかにぶち当たる。それを、精神のエネルギーと言ってよいのだろうか。非合理主義的哲学者の論述は、実にいつも超合理主義的であって興味深い。1913年のロンドン心霊研究会の講演を含む。2.『大乗仏典1 般若部経典 金剛般若経、善勇猛般若経』 長尾雅人、戸崎宏正訳(中央公論社) 般若経典群の白眉である。『金剛般若経(こんごうはんにゃきょう)』には、唯識の論師・無著(むじゃく)の注釈・詩頌(しじゅ)が添えられている。「空」という言葉を一つも使わずして空を説く経である。『般若心経』ほどの凝縮はないが、相当にコンパクトな般若経である。内容的に最もすぐれていると思われる。一節をここに要約して引こう。「スブーティよ、覚りを得た諸々の如来の無上の覚りは、実はこの教え(経文)から生ずるからである。この経文から諸仏世尊が生まれるからである。それはまた、なぜか。スブーティよ、仏陀の教法、仏陀の教法というが、それは、実に仏陀の教法ではない、と如来は説くのであり、それゆえ、仏陀の教法と呼ばれるのだからである」 『善勇猛般若経(ぜんゆうみょうはんにゃきょう)』も、徹底して空を説く。「何々は、何である」という固定概念をことごとく否定してゆく。そして、菩薩の修行すらも否定される。「あらゆる実践は実践から生じる。そして、実践を妄執することによって転倒がある。しかし、菩薩は実践を妄執しない。それゆえに、彼には転倒が伴わない、といわれる。そして、無転倒なものとなった彼は、もはや何に対しても実践するということがない。それゆえに、菩薩の実践には実践がない、といわれる。善勇猛よ、実践がないというのは、何かについて実践するのでもなく、実践しないのでもなく、また、実践のすがたをあらわさないことであり、これこそ菩薩の実践といわれる。このように実践する彼こそ、知恵の完成を実践しているのである」3.『高僧伝 日蓮』 金岡秀友(集英社) 真言宗の僧侶が書いた日蓮伝。凡百の宗門の伝記を凌駕する。日蓮という現象を、密教的変容としてとらえている。また著者は、『法華経』のなかにも密教的な要素を見出し、それが日蓮に影響を及ぼしていることを見る。凡三は、さらに、日蓮を創造的密教僧として位置付けたい。『大日経』や『金剛頂経』を直接使わずして、日蓮は、和様密教を自らの修行のなかから編み出したのだ。題目は、究極のマントラとしてある。『法華経』をよく読み込み、それにより創造的な修行をするならば、万善同帰経ならぬ、万全天地善悪正負能生の曼荼羅経でもある。著者が、薬王麿と蓮長の創造的進化を、伝記物語のなかで肉付けしてくれたらもっとよかった。しかし、それは、すぐれた文学者の仕事であろう。4.『澁澤龍彦 初期小説集』 (河出文庫) 偉大な文筆家であり、日本では珍しい神秘家の澁澤であったが、小説家としては寡作であった。彼の最高傑作は、中編小説『高丘親王航海記』であり、これは動かない。彼には、いわゆる長編小説は一つもない。これは、非常に残念なことであり、当時の編集者の怠慢でもある。 初期小説集は、2005年5月に新刊文庫として出た。9編が収められているが、『エピクロスの肋骨』と『マドンナの真珠』がいい。前者は、肺病病みのコマスケが病院を抜け出すところから始まる。門衛の元校正係をコマスケの詩文の力でヤギに変え、それを売り飛ばして、夜行列車に飛び乗った。その列車には、ヤギ男の娘がちょこなんと猫になってシートに座っていた。夜の街角で、大きな黒い瞳をライターとして淫売する、シャルロット猫娘のこましゃくれた言動がいじらしい。さすがのコマスケの神通力も、この物凄く目の大きい猫娘には通用しなかった。5.『創価学会の実力』 島田裕巳(朝日新聞社) 2006/8の新刊本。私のような部外者にとって、自分が取材したように創価学会の内幕が分かるような構造になっている。高度経済成長期において、犯罪組織にならず、まがりなりにも日本の社会福祉に貢献した“必要悪”だったことが分かる。貧しい地方の次男坊、三男坊が都会にやって来て、頼りになったのが互助会的なこの組織だった。日蓮宗の現世利益的なところだけを切り取り、日蓮の一面である排他性を逆に求心力として利用した。しかし、日蓮正宗から破門されたあと、彼らが一つにまとまるのは至難の業になった。「お山」はすでになく、イベントも力つき、いまや選挙だけが唯一の結束の場になっているという。私は思うのであるが、今こそ学科委員は、宗教を取り戻すべき時なのではないか。創価学会員一人一人が、日蓮とそのルーツである天台の仏教をしっかり学び直し、『法華経』28品(ほん)を繰り返し色読(しきどく)し、折伏(しゃくぶく)ではなくて摂受(しょうじゅ)で平和裏に仏法をやり直すことを期待したい。それが、日蓮のねがいでもあろう。(この項つづく。音楽関係は、後日アップいたします)
2007年01月15日
-
番外月法2 2006 Best Book & CD DVD LD 前文
小生、人間凡三にとっては、ものを食べることや酒を飲むことも楽しみではあるが、それよりいっそう、単独者・凡三としては寝食を忘れ、書を読み、音楽を聴き、音楽劇やパフォーマンスを見ることこそ、我が血潮の生存が最高度にたしかめられる時である。 生来、蒲柳(ほりゅう)の質で、いくら身体を鍛えても、こうして大人になっても、丈夫にならなかった凡三であるから、齢とともに飲食の摂取法を矯正し、高脂肪、高蛋白、高アルコールの相対指数を涙ながらに抑え込み、食いしん坊の化仏が出る前に、黙ってコップと箸を置くことにしている。 しかし、読・聴・観は、いかんともしがたい。三昧(ざんまい)といえば三昧ではあるが、仏教用語としての三昧(さいまい、三摩地=さんまじ)という行為には程遠い。文字に淫し、音響に淫し、形色に淫するのである。おろかなことではある。妄執であろう。だが、私の今のこころを血と肉とに成り立たせたのは、過去に凡三が幼少のころから見聴きして来た字・声・色に他ならぬ。それらが、すべてだとは言わないが、西洋流に言うならば、私凡三の自我を成り立たせたのである。もしも、私が、梶井基次郎や坂口安吾を読まなかったなら、カフカやホフマンやゴーゴリを読まなかったら、幻想家の竺河原凡三は今にないだろう。バッハやシューベルトやブルックナー、コルトレーンやドルフィーやマイルスを聴かなかったら、凡三が今に生きているかも分からなかった。エックハルトの説教文、ショーペンハウアー、ニーチェ、ベルクソンの哲学書をひもとかなかったら、凡三の批判精神は萎縮していただろう。さらに、『法華経』『涅槃経』『金剛般若経』『般若心経』等の大乗仏典や、龍樹(りゅうじゅ)や世親(せしん)の論書、空海、最澄、日蓮、道元、源空、親鸞などの撰述を読まなかったら、仏法家・竺河原凡三は今にあり得ない。 なにも、人間形成の要素として、「読・聴・観」がすべてとは言わない。経験そのものや話し言葉による伝授は直接的に人間を学ばせるものだ。しかし、人間の後天的な性格に大きな影響を及ぼすのは、その人間が何を読み、何を聴き、何を見たか、その質と量である。この三つの学問に終わりはない。大学までの学問は、この三つを容易に身につけさせるための教養を授けるところである。だから、実利的な就職問題と切り離しても、高学歴には意味があるのである。学歴によって語彙(ごい)が豊富になれば、人に教えてもらうことなしに、新聞やテレビなどを参考に、「読・聴・観」に挑むことが出来る。ただ、これを学ぶに、学問としての箔や飾りにしようなどという浅はかな魂胆がある場合は、何も得るものはなく、ただの鼻持ちならないスノッブである。みずからに好き好んで、ある作家、経文、音楽家に三摩地(さんまじ)するのである。 仏法は、経文を読み込み、小さくとも、みずからに経蔵を作さねば修行が始まらぬ。作家は、厖大な文字を読み、みずからの辞書を作らねば第一の創作は始まらぬ。音楽家並びに音楽評論家は、厖大な音符を聴き、みずからのレコーダーを作らねば作曲の第一歩は始まらぬ。美術家は、たくさんの風景や色々な人物を見て、みずからのカメラを作らねば筆や鑿をもつことが出来ないだろう。貪欲な凡三は、「読・聴・観」に大楽を得て、この世とあの世とのはざまで、あの世とこの世を観るのである。 例によって、前置きがずいぶんと長くなってしまったが、2006年に凡三が読んだ本と、聴観したCD・DVD・LDのなかで、ベストのものを並べおく。 なお、2006年に読んだ本は、49冊、購入したCD・DVD・LDは、139点(305枚)である。ここで断ると、新譜は一部を除いてほとんど買わない。本も同様である。それでも、実際に計ると、中古と新譜の割合は、本、音楽ともに8:2くらいである。新譜とは言っても、新音源、デジタル・リマスター盤、再編集盤(本)が多い。ただ、ランク・インしたもので、新譜・新刊のものがあれば、解説に説明してある。
2007年01月15日
-
第10月法 如来滅後五五百歳その五 五濁悪世
真説末法にいたり、地獄が徐々に消滅してゆく相を(第6月法で)明らかにしたが、末法突入とともに、地上の人間界はどうなるのか、改めて述べよう。 2020年以降もしばらくは、平均寿命は、先進国、後進国を足して世界平均で80歳くらいまで延び続けるであろう。先進工業国では、30、40歳くらいから心身の五大(ごだい)のバランスがすでに損なわれているにもかかわらず、薬物治療と延命医療により、人間の寿命はさらに増延してゆく。 一つの薬が、ある病気を治すとともに副作用を発症させる。副作用を抑えるために次の薬が与えられる。だが、その薬にもまた副作用がないとは言えないのである。西洋型の対症療法的化学薬剤は、いったん服用するとやめることがなかなか出来ないものだ。何故なら、根本の個々人の体質の改善を図るという治療法ではないからだ。よって、薬物治療は、東洋医学の漢方に頼るべきではあるが、ここにも、問題がある。21世紀の時代では薬剤の元になる草木や動物成分が、相当に汚染されており、処方どおり充分煎じても、効き目がどうしても薄くなるからだ。また、東洋医学では、投薬の前に、脈拍をはじめその人の身体を裏に表にくまなく調べて、正確な体質を見立てられる技量が前提であるが、漢方医の質の低下により、その見立てもあてにならない。よって、たとえ完全な薬材がそろったとしても、適切な処方が出来ないということになろう。 以上をかんがみると、我々がはかれるささやかな防衛策は、自分の体質を自分で正確に知ったうえで、日常の食物の食材を自らの体質に合わせて集め、料理して服用することである。由緒正しき素材であれば、健康食品も利用出来ないことはない。これからは、自己管理の医食同源が問われるということである。そのためには、まず、自らの体質を知り尽くすことである。これは、親が幼少時から子供に諭し、教えるとよい。学校の勉強より、むしろこちらの方が大事とも言えるか知れない。親は教えるばかりではなく、子の体質を知ることによって、また自らの体質を改めて知り、弱点と長所を把捉し、家族の絆を深めるのがよかろう。自らを知ることは、とりもなおさず、仏法を知ること、すなわち、大乗の修行の初歩でもある。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2007年01月01日
-
第9月法 観世音(上)
先日、招待券をもらった手前、仏像特別展「仏像 一木にこめられた祈り」(上野・東京国立博物館 平成館)にお参りに行って来ました。仏・菩薩・明王・天部等の64作品どれもが尊く、たとえそれらの尊から形式的に魂が抜かれていましょうが、しばしこの世を離れ、『観音経(かんのんぎょう)』を心に誦(じゅ)し、己の自我を浮遊させ、ほとけの加をじっと受け止め、空(くう)に持(じ)すると、仏・菩薩の慈悲が滋味に沁みて吸い込まれゆくようで、不思議な感覚がありました。少し寝不足でまいったのですが、加持身(かじしん)となって歩いていると、頭が軽くなって、健やかになりました。そして、気が付いてみれば、ここは、いかにも世俗的な博物館という空間であり、いかに自らが場所を勘違いしていたのかを自覚したしだいでした。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2006年12月06日
-
第9月法 観世音(下)
=上段(上)より以下につづく= さても、かの滋賀・向源寺=こうげんじ蔵(渡岸寺=どうがんじ=観音堂=所在)の国宝・十一面観音菩薩立像(じゅういちめんかんのんぼさつりゅうぞう=貞観年間859-877作/像高194センチメートル)には圧倒されるとともに、尊い加持身をいただきまして、凡三は自らの阿修羅(あしゅら)を解脱することを得ました。 正面のふくよかなお面は、やさしさに満ち足りていてました。異例ともいえる脇面から頂上仏面までせり上がるようにある変化面は、一つ一つ、大きく、くっきりと、見事におかしらを化粧されていました。お顔の右側三面の変化(へんげ)面は牙をむき、後ろの、観音様は暴悪相に大きくお笑いになっていました。それでも、大きなおかしらは邪魔にならず、お腰をゆらせて不思議な均衡をとられ、長いしなやかな右腕が延びて掌が与願印(よがんいん)を示され、見るものの心を安心(あんじん)に導かれます。左手に掲げられた水瓶(すいびょう)には、病の熱に乾くものに用意された霊水が入っています。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2006年12月06日
-
番外月法 カオルコさんへの手紙
カオルコさんへまず、信仰・信心という言葉を頭から安易に使うのは、やめましょう。凡三は、その言葉があまり好きではありません。仏教は仏法によりて、まねびて、修行によって覚りを得る教えです。浄土真宗とキリスト教等は、信仰・信心と言う以外、修行も、覚りもないのですが、本当の教えは、一に経文であり、第二に修行です。最初から、覚りを求めてはいけません。経文によって我々は、仏教を知るのであり、それに基づいた修行によって、結果的に即身成仏するのです。日蓮の修行は、実は真言密教の三密加持(さんみつかじ)――身密(しんみつ=身に印契=いんげい=を結ぶ)、口密(くみつ=口に真言をとなえる)、意密(いみつ=心に本尊を観ずる)――に由来します。しかし、真言密教の身・口・意を彼の独自の体系に基づいて、煩雑で形式主義的な本来の三密を、すなわち、口密に「唱題」を、意密に「法華経の物語の読解と瞑想」を、そして身密に、「法華経の色読(しきどく)」を充てたのです。これは、とてつもない密教的変容なのです。日蓮こそは、創造的密教僧と呼ばれてしかるべき菩薩なのです。ゆえに、三密を等しく具足(ぐそく)しなければいけません。浄土系の仏教は、源空(法然)は、称名念仏の口密一密(いちみつ)、親鸞は、絶対他力の意密一密と二密を欠き、三密加持を円満に具足していません。ただ単に、唱題することによって、現世利益を期待するのならお門違いというところです。あなたも尊崇する日蓮は、一生貧乏で、無期懲役、死刑判決を食らい、早すぎる晩年は、極寒の甲斐国の道なき山で、床と屋根しかないような草庵を結び、ただひたすらに法華経の修行をしていた、そういう人間です。そういう人間を宗祖とする宗教に、金持ちになりたい、良い相手と結婚したいと、願うのは嘆かわしい限りです。彼の仏法のすべては、『法華経』28品から能生(のうしょう)するのであり、その法力の妙なることを日本国にひろめるために日蓮は、この東粟国(とうぞくこく)に出生したのです。いわば、『法華経』のエージェント(代理人)というのが日蓮の正体です。だから、彼を日蓮本仏などといって本尊化することなどは、日蓮の仏法に反します。もう、賢いカオルコさんのことだから分かりましたね。意密を行うために、『法華経』28品をまずは、通しで読んでください。大きな書店で、岩波文庫、レグルス文庫(ともに上中下の三分冊)が簡単に手に入ります。置いていなければ、書店で注文してください。『法華経』を読まずして、仏教を語る資格なしです。いずれも平易な日本語訳が出ていますから、この物語を読解したのなら、次に、書店で『真読 法華経 開結』(平楽寺書店版)を購入して、序品から28品までを通しで声を出して、一文字一文字ふりがなを頼りに、仏壇の前で読誦(音読)してください。要品の『方便品』や『如来寿量品』、『普門品』などだけではなく、すべてを声に出してとなえます。1年がかりでもいいです。最初から最後までやります。次に、あなたの人生として経文を考え、今度は、これからの経験に照らして身体で『法華経』を読み込んでください(=身密)。そして、あなたの身体に『法華経』が書いてあることが分かったならば、感謝のつもりで唱題しましょう。時間がなければ、1回で充分です(=口密)。ただ、必ず声に出すことです。そうしないと、口密が成立しません。そして、この段階で安心が得られたのなら、即身成仏の第1段階ということです。そうなったら、この娑婆世界では、もう、なにも、怖いことはありません。機がまたおとずれれば、上記の工程をさらに繰り返します。そのあとは、自分で自分なりの修行を作ってください。『法華経』のすばらしさを客観的に覚るために、ほかの代表的大乗経典『華厳経』(けごんぎょう)、『涅槃経』(ねはんぎょう)『般若心経』(はんにゃしんぎょう)『金剛般若経』(こんごうはんやきょう)、『理趣経』(りしゅきょう)などもお読みになってください。そこにも、やはり『法華経』が書いてあって、法華経の修行に役に立つはずです。凡三は、悲しみを忘れかけたとき、逆説として、『心経』と『金剛経』を補助のお経として、読誦いたします。そして、音になった言の葉から空(くう)が身に沁みて来ると、『法華経』の慈悲がこの身を包み込んでくれます。カオルコさんも、修行によってどうかお仕合わせになってください。南無妙法蓮華経ナム・サッダルマ・プンダリーカ・スートラ
2006年11月14日
-
第8月法 招霊妖術と仮面の道化…ショスタコーヴィッチ(下)
『交響曲第4番・ハ短調』は、ショスタコーヴィッチのキャリアの前半においてマーラー等の西欧的影響を自己のものにしようと、音楽のあらゆる要素を展開させようとした音絵巻である。3楽章しかないが、規模は、あの有名で軽薄な『第5』より大きく、演奏時間は約60分である。ちなみに、この曲が初演されたのは、作曲から四半世紀を経て、フルシチョフのスターリン再批判がなされた61年のことだ。56年最初のスターリン批判以降、交響曲でいえば『第11番』『第12番』と体制寄りともとらえられる通俗的な響きをもつ“大曲”を書いた後、大きく揺り戻しする。『第4』初演を前後して、ショスタコーヴィッチの書法には、革新と深化が進んでゆく。『交響曲第13番・変ロ短調〈バビ・ヤール〉』(62年)と『交響曲第14番・ト短調〈死者の歌〉』(69年)は、歌とシンフォニーの必然的合体であり、歌の内実がもはやシンフォニーの形式を問うていない。60年の『弦楽四重奏曲第7番・嬰ヘ短調』には、アンサンブルにおいて、四重奏トゥッテイの比重が減って、三重奏、二重奏、ソロと、様々な音楽対話のバラエティが試されるような実験が聴かれるようになる。『同第11番・ヘ短調』(66年)以降の弦楽四重奏曲は、伝統形式にありながら器がもたなくなってしまったかのような、内実優先の告白的な秘儀である。あらゆる古典音楽の技法と要素がぶち込まれると同時に、バルトーク的な現代的な変容が試され、果てには骸骨だけのような特殊な形体を取るに至った極めて特異な作品群である。最後にたどり着いた『同第15番・変ホ短調』(74年)は、全6楽章がすべてアダージョであり、すべてが四分の四拍子、しかも切れ目なく演奏されるという異様さのなかに豊饒性が展開される。とはいうものの、これは水墨画のバラエティである。西洋的な対位法は後退している。4本の弦の一度書きの祈りの様々な歌の交錯である。郷愁の強く臭うボロディン的なテーマから曲が導かれる。むせるようなスラブ・ロシアの土着の亡霊が深く弦に刻まれる。第2楽章から、死を前にした老妖術師の、死者との対話、或は招霊の呼び掛けの儀式が始まる。祈祷具の長剣が大きく空を切る。太く大きい祈祷文は、長続きしない。しかし、ふらふらと、亡霊たちは現れ、祈祷師の声に酔い痴れ、亡者は踊りだす。インテルメッツォのはずが、祈祷師の身振りは最後の力を振り絞って一心不乱に大きくなる(第3楽章)。悪霊までもが祈祷師の優しい夜の妄想に引き寄せられ、狭い部屋が姿無き亡霊たちの浮遊舞踏場となる(第4楽章)。第5楽章は、月光のモチーフがエロイカと運命のエコーのなかに閉じ込められ、祈祷師が男泣きとなる葬送の歌である。それはゆったりとしたリフレーンとなる。第6楽章冒頭、亡霊たちがざわめき始める。スラブの子守歌にも葬送のリフレーンにも、それは抗する。すると突然、祈祷師の心臓に異変が起こると同時に、天使が彼の目の前に現れ、彼を慰める。祈祷師は、最後の余力で、自らの罪の告白を祈るように進上する。そして、音楽は終わり、祈祷師は力尽き、近しい魂魄も、悪霊も、すべてが無に帰して逝く。ベートーヴェン以来の弦楽四重奏曲書きは、バルトークだというのが批評家の定説ではあるが、私は、あえてショスタコーヴィッチを取る。彼の交響曲が比較的に社会に向かってアピールするソ連共産党員としての顔を現しているとすると、カルテットには彼のアナーキーな内面の妄想と瞑想がある。この対比に、機械的労働と個人の実存にますます分裂せざるを得ない現代的な切実な狂気が、重なって見えて来ないだろうか。『バイオリン協奏曲第2番・嬰ハ短調』(67年)、『バイオリン・ソナタ・ト長調』(68年)、そして死の4日前に完成した『ビオラ・ソナタ・ハ長調』(75年)等は、どれも思索性の高い曲群であり、強い霊性も伴っており、聴くものに強い緊張も強いるが、聴き終わった後の解放感は何ものにも代えがたい。複雑な横顔をもつ全集書きだったショスタコーヴィッチについて、一つのジャンルの曲群だけを聴いて、理解したなどと言わないでほしい。たとえば二つの代表的オペラ、『ムツェンスク郡のマクベス夫人』と『鼻』も聴いたらよかろう。彼がモーツァルト並みに劇場感覚にすぐれていたことと、彼のなかの生命欲の激しさと機知の縦横さが分かるだろう。しかし、この分野はスターリンによって抹殺されてしまった。大粛正のさなか、彼が32歳にして、弦楽四重奏曲を初めて書き上げたことは興味深い。一方で、ソ連共産党の党人としてのショスタコーヴィッチにも、ぬかりはなかった。彼は、62年よりソ連邦最高会議代議員に選ばれ、以後死ぬまで職責を果たした。レーニン勲章をはじめ国家の栄誉の数々にも浴した。だけれども、彼の音楽は、最後まで決して堕落することはなかった。スターリンの亡霊とスターリンに粛正された悪霊たちは、ショスタコーヴィッチの枕許を離れることはなかった。その悪夢こそが、晩年の創作の源泉ともなったのである。「わたしの交響曲の大多数は墓碑である。わが国では、あまりにも多くの人々がいずことも知れぬ場所で死に、誰ひとり、その縁者ですら、彼らがどこに埋められたのかを知らない。わたしの多くの友人の場合もそうである。メイエルホリドやトゥハチェフスキイの墓碑をどこに建てればよいのか。彼らの墓碑を建てられるのは音楽だけである。犠牲者の一人一人のために作品を書きたいと思うのだが、それは不可能なので、それゆえ、わたしは自分の音楽を彼ら全員に捧げるのである」(『ショスタコーヴィチの証言』ヴォルコフ編・水野忠夫訳〈5 わたしの交響曲は墓碑である〉)『交響曲第4番』『同6番・ロ短調』『同7番・ハ長調』『同8番・ハ短調』『同10番・ホ短調』『同13番』『同14番』は、そういった性格をもつものである。私は最初、大風呂敷でヒステリックな狂騒を極める彼の交響曲のソノリティに辟易したものだが、ハイティンク、ロストロポーヴィッチ、バルシャイ、ロジェストヴェンスキー、コンドラシン盤と全集で5種類、バーンスタイン盤も新旧両方とも完備してゆくうちに、聴く機会は少なくなくなった。私にとって、聖なる作曲家、シューベルトとブルックナーはおくとして、最近では、コレクションのうえでははるかに充実しているブラームスやマーラーよりも、手が延びてしまう。他に、『第1』と『第9』も一聴に値するものだと信ずる。3本のゆり、3本のゆり、十字架のない私の墓の上で金箔を冷たい風に吹き払われる3本のゆりは雨を含んだ黒い空に時おり洗われその美しさはいかめしい王笏のように重々しい1本は傷口から生えたもの、夕焼けがくるとこのたましいのゆりは血に染まるようだ3本のゆり、3本のゆり、十字架のない私の墓の上で金箔を冷たい風に吹き払われる3本のゆり2本目は虫くいの寝所でもがく私の心臓から生え3本目はその根で私の口を裂くどれも私の墓の上にわびしく生えまわりには土だけ、その美しさは私の生のように忌わしい3本のゆり、3本のゆり、十字架のない私の墓の上でギヨーム・アポリネール詩、ウサミ・ナオキ訳(一部表記変更有り)『交響曲第14番〈死者の歌〉』~第4楽章「自殺」「結局、死というのは簡単なことである。もしも人間が死んだら、それはやはり死んだのであり、元気でいるなら、それはやはり元気であるのだ」(同 6〈張りめぐらされた蜘蛛の巣〉)と唯物論的な言い方をしつつも、ショスタコーヴィッチの楽曲の多くの音符には――先ほど、『弦楽四重奏曲第15番』で実証もしたが――不気味で不思議な呪術性が宿っている。それは、報いられず、非運にも、無念のうちに死んで逝ったものたちを再び甦らせようという妖術のように聴こえるのは私だけであろうか。あの端正で美しい『ピアノ五重奏曲・ト短調』ですらも、弦のうなりのなかに、たくさんの悲しい不成仏霊を私は観てしまう。ショスタコーヴィッチの作品は、捨て去られ、忘れられ、或は忌み嫌われ、成仏出来ない阿頼耶識(あらやしき)を代弁し、すなわち悪霊を呼び出し、激しくこの世を呪い、のたうちまわる魂魄を顕現させる。彼は、即物的な音の科学者をよそおう招霊妖術師の横顔をもつ。彼が生み出した音符の多くは、そう、霊媒とも言えるのである。王様、皇帝、帝王この世の支配者たちは、観兵式を思いのままやれたがユーモアには、ユーモアには命令出来なかった毎日ごろごろして暮らすお偉方たちの宮殿にさすらいのイソップが現れ出ると彼らはみじめに見えたものだおべっか使いのほっそりした足に汚されているお邸でナスレッジン・ホジャは将棋をさすようにあらゆる俗物性を洒落でやっつけた彼らはユーモアを買収したがったそれだけは買えないぜ!彼らはユーモアを殺したがっただが、ユーモアに馬鹿にされた!ユーモアと闘うのは楽ではない次々と死刑にして行ったちょん切られたその首が、銃兵の槍先にのっかったしかし、旅芸人の笛が物語を始めたその途端、ユーモアは叫んだわしはここだよ! わしはここだよ!そして威勢よく踊り出した政治犯として捕まったユーモアは、すり切れたぼろ外套をつけ目を落とし、さもしおらしく、刑場へと歩いて行ったどう見ても従順そのもので、あの世への覚悟も充分だったところがふいと外套から抜け出し、片手を打ち振ったさあ、隠れんぼ彼らはユーモアを独房に閉じこめたがどっこい、そうは問屋がおろさなかった鉄の格子も、石の壁も、ユーモアはするりと抜けて行った風邪で咳きこみながらユーモアは一兵卒として、ざれ歌とともに進んで行った鉄砲かつぎ、冬宮殿めざしてユーモアは嫌われるのにはなれてしまったそんなことはかゆくもないユーモアは自分自身すらもユーモアで扱うことがあるユーモアは不滅だユーモアは機敏だそしてすばしこいどんな物、どんな人も通り抜けて行くエフゲニー・エフトゥシェンコ詩、ウサミ・ナオキ訳(一部省略、表記変更有り)『交響曲第13番〈バビ・ヤール〉』~第2楽章「ユーモア」まるで、ショスタコーヴィッチ自身のカリカチュアを歌っているような歌詞である。彼の楽曲のなかのアレグレット=スケルツォなどでは、ユーモアが抜け出して、最高に踊りまくるのである。或は、暗い短調の管弦のうなりのなかにも、舌をだして出没する。『交響曲第7番』の第1楽章のあのボレロのパロディ(ターラッーラ、ラッラッ、……)は、仮面を被った作曲者がスターリンの前で、裸の尻をさらして、ひょっとこ踊りを披露しているように私には聴こえる。そこに、過去に犠牲になった幽霊たちも加わり、さらには、マスクをいいことに共産党幹部も加わる。子どもたちも、おもしろそうなので、小さな仮面を付けて、見よう見まねで踊りだす。最後には、ソ連人民全員が、仮面の尻踊りを大地に舞い狂うのである。すでに、スターリンの存在はバラバラだ。これは、自らの汚れた五臓六腑をすべて吐き返してしまうようなおかしさだ。熱く、凶暴で、手が付けられない。こんな作曲家は、ショスタコーヴィッチだけである。笑いは、人間の心身が限りなく機械に近付き、創造性のない繰り返しが発覚したときに社会的身振りとして生じる、とフランスの哲学者は言った。しかし、ショスタコーヴィッチの笑いは、招霊妖術の幻想が契機となっていて、爆発的かつカーニバル的な笑いである。恐ろしいことに、この笑いには目的がない。招霊の祈りは、我々が自らに機械としての物質性を徹底して否定しようとするときに生ずる。このカーニバル的な笑いは、フィードバック認識されると、当事者の客観を解放する働きをする。顔をゆがめて笑うものは笑われるものにまた笑われ、笑うものと笑われるものの区別はなくなり、私は私ではなく、あなたであり、あなたはあなたではなく私であり、そして、あなたも、私も、結局は誰でもないのである。そう、あなたも、ショスタコーヴィッチを聴きながら、憑坐(よりまし)の躍りを、声がかれるまで一緒に笑いたまえ。ハッ、エフッ、ウハハハハハハハハハァア……(この項おわり)
2006年11月03日
-
第8月法 ショスタコーヴィッチ(下) 付録
以下、ショスタコーヴィッチに関する参考盤を挙げる。すべてが現役盤ではない。CD・レコード盤で名盤と呼ばれるものは、レーベルや配給元が変わったりして繰り返し販売されるものである。ゆえに、あえてレコード番号を記さなかった。すべて、ボンゾー・コレクションからの紹介である。★★★★☆『鼻』ロジェストヴェンスキー指揮/モスクワ室内音楽劇場管 録:75年(メロディア・ビクター)※鼻が少佐から抜け出し、人格を身につけ、祈りを捧げ、警察と格闘するなど、とんでもないが、ちょんちょこちょこちょこ舞台を踊りまくる。少佐は、逮捕された鼻を顔に付けるが、くっつかない。なんとも、ふざけた、楽しい音楽、指揮ぶりだことか。★★★★★『交響曲全集(1~15番)』ハイティンク指揮/ロンドン・フィル、ロイヤル・コンセルトヘボウ管 録:77~84年(デッカ・ユニバーサル)※平均的全集魔であるところのハイティンクが、全きの鬼になった。彼のブルックナー、マーラーも悪くはないが、おそらく彼の代表作と言ってもいいであろう。録音も抜群にいい。★★★★☆『同』ロストロポーヴィッチ指揮/モスクワ・アカデミー響、ナショナル響、ロンドン響録:73~95年(テルデック)★★★★☆『同』ロジェストヴェンスキー/ソビエト国立文化賞管 録:83~86年(メロディア・ヴェネツィア)※剛腕ゴリゴリ・ドス聴かせのロジェヴェンが、お国物では繊細なところも見せる意外性がある。ただし、彼の本質的なところは、ショスタコをやるうえでは必須の条件なのである。★★★★『同』コンドラシン指揮/モスクワ・フィル 録:61~75年(メロディア・ヴェネツィア)※問題作『第4』の四半世紀ぶりの初演を担った当事者の明くる年(1962年)の録音、フルシチョフが公演を封じ込めようとした『第13番』の初演2日後(1962・12・20)の録音がリアルに聴ける。以上の二つのメロディア音源は、ロシアのヴェネツィア盤から現役盤で出ている。値段は、廉価盤と言ってもよい。あえてリマスターをしていないらしいが、音は悪くない。★★★『同』バルシャイ指揮/WDR響 録:92年~98年(BRILLANT CLASSICS)※超廉価盤。小生は11枚組を\2520(新品)で購入。★★★★『交響曲第1番・ヘ短調』バーンスタイン指揮/シカゴ響 録:88年(グラモフォン・ユニバーサル)★★★★★『同第7番・ハ長調』バーンスタイン指揮/シカゴ響 録:88年(グラモフォン・ユニバーサル)※上記1番とのカップリング。バーンスタイン渾身の怪演。この曲に必要な迫力、ユーモア、霊気を具足し、自在にリズムを伸縮させる。これは、本当に生きているショスタコ自身に聴かせたかった。★★★★『同第9番・変ホ長調』バーンスタイン指揮/ウィーン・フィル 録:85年(グラモフォン・ユニバーサル)※6番とのカップリング、これも名盤。★★★☆『同4番・ハ短調』ゲルギエフ指揮/サンクトペテルブルク・マリインスキー(キーロフ)歌劇場管 録:2001年11月20-22日(フィリップス・ユニバーサル)※最後に21世紀を代表する演奏を一つ。2004年度レコードアカデミー大賞受賞盤。ゲルギエフは4番から9番までのいわゆる『戦争交響曲集』を8年かけて完結――去年5枚組で発売――したが、そのなかから4番を挙げておく。細部に忠実なようでいて、全体がぼやけている。ショスタコーヴィッチの演奏で大事なことは、曲の観念性を、演奏者の肉体性でもって抱き締め、破壊しなければ、曲の本当の姿が浮かび上がらないということである(4番)。また、独自のリズム感が表出されていないのが残念。打楽器が入る所などで、べったりとした重い単調なリズムで、興ざめだ。作曲家の笑いは死に、創造的進化が止まってしまうようだ(7番、9番)。独自のリズム感と、さらなる伸縮自在の即興性が求められる。弦はよく鳴っていていいのだが、管楽器とのバランスがよくない。★★★★『バイオリン協奏曲第2番・嬰ハ短調』コンドラシン指揮/オイストラフ(バイオリン)モスクワ・フィル 録:68年(メロディア・ヴェネツィア)※上記コンドラシンの交響曲全集(12枚組)に収録されている。★★★★☆『ピアノ五重奏曲・ト短調』アシュケナージ/フィッツウィリアム弦楽四重奏団 録:83年(デッカ・ユニバーサル)※ショパンとスクリャービンの独奏ピアノ以外は全く聴く気のしないアシュケナージだが、これは凄い。見直した。★★★★☆『同』リヒテル/ボロディン弦楽四重奏団 録:83年(メロディア・EMI)※少しリヒテルのピアノが重たく動きが悪いようにも思えるが、聴けば聴くほどに味が出るというもの。★★★★★『弦楽四重奏曲全集(1~15番)』フィッツウィリアム弦楽四重奏団 録:75~77年(デッカ・ユニバーサル)※カルテットから一つを採れと言われれば、これになろうか。端正と狂気。録音のバランスもいい。名演。★★★★★『同』ボロディン弦楽四重奏団 録:78~84年(メロディア・EMI)★★★★☆『弦楽四重奏曲集(1~13番)』ボロディン弦楽四重奏団 録:60年代中頃~72年(メロディア・シャンドス)※シャンドスからの復刻版。24ビット・デジタル・リマスターの威力ここにあり。新盤に劣らぬ名演。★★★★『ピアノ三重奏曲第2番・ホ短調』アイザック・スターン、ヨーヨー・マ、エマニュエル・アックス 録:87年(CBS・ソニー)※チェロ・ソナタとのカップリング。本当は、もっと怖い曲なのであるが、三様に演奏を楽しんでいる感じ。スリリング。録音が良い。★★★★★『バイオリン・ソナタ・ト短調』オイストラフ/リヒテル 録:69年録(メロディア・ビクター)※69年5月3日のクレジットを信用すれば、68年に作曲されたこの曲の初演ということになる。ボリューム、技量、掛け合いと、鬼気迫る恐ろしいライブである。バイオリンからはたらたらと血が流れ、ピアノは骨髄をたたきのめす。こういう演奏をジャズと言ってはいけないのだろうか。★★★★☆『ビオラ・ソナタ・ハ長調』バシュメト/リヒテル 録:85年(メロディア・ビクター)※リヒテル主宰のオイストラフ追悼盤(2枚組)のなかの1曲。
2006年11月01日
-
第7月法 ショスタコーヴィッチ(上)
先月25日で生誕100年を迎えたドミートリー・ドミトリエヴィッチ・ショスタコーヴィッチ(1906・9・25サンクトペテルブルク-75・8・9モスクワ)は、コンプレックスの作曲家である。コンプレックスとは、複雑な、入り組んだというほどの意味である。もっと分かりやすく言えば、本人の顔がよく見えて来ない作曲家である。彼は、ソ連共産党の権力者たちに対し、戦いを挑むとともに、自己を韜晦した。そして、一応の天寿を全うした。彼のオペラの最高傑作『ムツェンスク郡のマクベス夫人』に対し、1936年の共産党機関紙・プラウダに「音楽の代わりの荒唐無稽」と評論が出て、作品は上演禁止になった。国家から不適格という判定をされたということは、社会主義国家であるから、権力者から何か因縁を付けられ、事情がこじれると、連行、監獄行き、そして最悪の事態も考えられなくもない。しかし、賢い彼は、同年に書き上げていた傑作『交響曲第4番・ハ短調』を撤回し、翌年、俗に「革命」という名で有名な『交響曲第5番・ニ短調』を書き上げ、名誉を回復したのだった。1945年という記念すべき年に、『交響曲第9番・変ホ長調』が初演された。ソ連政府は、「凱旋の勝利」を祝う革命的かつ民族的で大規模な音絵巻を求めていた。古典音楽において、『第9』という言葉の意味するところは大きい。過去の大作曲家の最後の交響曲が『第9』であり、どれも決定的な名作と来ている。しかも、ロシアの交響曲作家の代表格チャイコフスキーが、6番までしか書いていないのだから、いやがうえにも期待は高まった。しかし、発表された曲が30分足らずの簡潔な書法で書かれたものだったため、決定的な『第9』を期待していた政府側から公的な批判がまた始まった。48年には戦後のイデオロギー的締め付けがショスタコーヴィッチにも及んだ。人民の意思に反する形式的音楽、すなわち西欧的デカダン音楽を作っていると断定され、苦しい立場に追い込まれた。いわゆるジダーノフ批判である。以前、『マクベス夫人』が、社会主義リアリズムに合致しないというお叱りの理由は、簡潔かつ明解で真実であることに反しているというものであったから、実におかしな話である。しかしショスタコーヴィッチは、批判の翌年の49年、スターリンの森林計画を称えたオラトリオ『森の歌』を作曲し、共産党幹部を納得させた。バッハの『平均律クラヴィーア曲集』の枠構造を借りて、51年に書き上げたピアノ作品の最高傑作『24の前奏曲とフーガ』も、英雄的なソ連人民の偉大な事業にふさわしい音楽ではないとけちを付けられると、翌年、共産党大会に寄せてカンタータ『我らの祖国に太陽は輝く』を作曲し、“反射神経”のいいところ見せている。蛇足になるが、50年にソ連では、政治犯の死刑が復活している。79年にニューヨークで刊行された『ショスタコーヴィチの証言』(ソロモン・ヴォルコフ編)という本があり、当時は大変な評判だったものだが、誇大妄想的な事実認識を、私は、あまり信用しない。彼の芸術的信念の告白ですら、本当の自分、すなわち作曲家としての真の実存を我々には語ってくれない。“証言”の言葉の数々には、度々仮面を被らずにはいられなかったショスタコーヴィッチが、自分の本当の素顔を忘れてしまった観がある。だが、彼の本当の仕事が、文筆ではなく音楽であることが幸いして、我々は、彼の音符を全身全霊で聴き取ることが出来る。ゆえに、ここに、私がショスタコーヴィッチという現象を鑑賞したその歴史を証言したいと思うのである。ショスタコーヴィッチは、ソ連共産党という20世紀の最も先鋭的な政治思想の環境のなかで生き抜いた作曲家だが、作曲家として見る場合、既製の技法と作品形式にこだわった人で、本質的には反時代的とも言えるほどに保守的な人ある。表面的にはアバンギャルドを装っていても、作品の骨格は古典的そのもので、その意味で字義どおりのクラシック音楽家なのであった。ショスタコーヴィッチは、20世紀の最新技法、ジャズのイディオム、無調や12音技法などをも使い古して行った勤勉な作曲家であった。技法を一つ一つをマスターし自家薬籠中のものにすると、発明者も出来ないような、創造的な適用進化を示した。それは、ウィリアム・フォークナーが大長編小説「ヨクナパトーファ・サーガ」で示した実験にも似ている。20世紀以降において、芸術的な創造的進化は可能であるかという命題を担った芸術家でもあった。1975年に至るまで、クラシック音楽の全集を書いていた奇特な作曲家は、彼の他にいない。かの“交響曲の父”ヨーゼフ・ハイドンからめんめんと続いた西洋音楽の「全集書き」の伝統は、実にショスタコーヴィッチで終止符を打ったのである。21世紀現代に演奏される曲目として、交響曲と弦楽四重奏曲を30曲も20世紀に書き残したことは、これだけでも特筆されるべきことである。我々にもっと身近なポピュラー音楽の歴史を振り返れば、ビートルズは70年にすでに解散し、同年、エレクトリック・ギターの革命児ジミ・ヘンドリックスは他界した。モダン・ジャズの最重要人物、ジョン・コルトレーンは、67年に亡くなっている。ジミと共演したがっていた、もう一人のジャズの重要人物、マイルス・デイビスは70年春に『ビッチェズ・ブリュー』を発表し、ジャズをフォー・ビートから解放した。編成楽器は全面的に電気化され、メロディー楽器のインプロヴィゼーションは残ったものの集団即興が渾然一体となり、ジャズの世界でも大音響が意味をもつようになった。そしてこれが、ジャズのミリオン・セラーの始まりでもあった。成長するロックの世界では、70年代は、レッド・ツェッペリンやディープ・パープルなど大音響のイギリスのロック・バンドが台頭し、ビートルズ・メンバーの個人的活動とローリング・ストーンズ、そして、アメリカのボブ・ディラン等が先導役となり、ロックを先進的な同時代音楽として宣揚し、世界の音楽マーケットを独占しようとしていた時代だった。英米のメジャーのロック・バンドは、成長する企業体であり、音楽業界の中で恐ろしいほどのレコード・セールス、興行成績を記録した。クラシック音楽の同時代性は、20世紀において、フルトヴェングラー、トスカニーニ、ワルター、ホロヴィッツ、クライスラー、ハイフェッツ、カザルス、エリザベート・シューマン、マリア・カラス等といった名人の演奏がビジネスとして確立され、録音技術の向上とともに、それをカラヤンやバーンスタインやショルティ、グールドやアシュケナージ、シュヴァルツコップやフィッシャー=ディースカウ、ドミンゴ等が決定的に受け継ぎ、演奏家百花繚乱といった時代である。クラシック音楽は、すでに作曲されるものではなく、いかに演奏するか、すなわち再現芸術として同時代性を有するのであって、そんな時代に、オペラ、交響曲、協奏曲、管弦楽曲、室内楽、ピアノ曲、合唱曲、オラトリオ、カンタータ、歌曲等の既製の型枠に、律義にせっせと曲を書き入れてゆくなど時代遅れも甚だしいと言わざるを得ない。ただし、飯のたねに映画音楽など劇場付随音楽をたくさん書いたという点では現代的であるが――。蛇足になるが、33年に書いた映画音楽『呼応計画』のなかの『朝の歌』は、全左翼陣営の愛唱歌になった。ショスタコーヴィッチは、自由主義陣営の音楽産業をよそに、決められた容れ物に、自分の創造欲を満たすべく技術の粋と魂魄を入れて行った。作品が、売れるとか売れないとかいう市場原理を離れて、溶液を満たしてゆくことが出来た。一方で、現実を生き延びるために、時には、最悪の事態だけは避けるように、容器には巧妙な希釈液も入れて行った。とはいえ彼は、クラシック音楽の主なジャンルで、駄作もあるが、数々の傑作を残した。彼の場合、駄作は必然ともいえる。彼が純粋なものを目指していたことは、15曲ある弦楽四重奏曲、『ピアノ五重奏曲』、『第4交響曲』や後期の13番以降の交響曲を聴けば分かるだろう。しかし、そこにも毒液の影響は及んでいるのだ。まっとうな曲を書いていても、作曲する彼の指には、希釈液の臭いがこびりついていて、洗っても洗っても、それは落ちないのだった。それが、ショスタコーヴィッチの悲しみである。でも、彼は、振り子のように聖と俗に揺れる作品群を書き続けて行った。ショスタコーヴィッチの芸術を社会的に判定するものは、市場原理ではなくて、ソ連共産党の思想原理であり、彼はそれをよくわきまえていた。もしも、彼がアメリカのような国に生まれ、或はほんの若いうちから移民したと仮定すると、どうだろう。彼は、希釈した曲でも、いわゆる受けのよい曲が書け、ジャズのイディオムを使って組曲なども自在に書ける。また一方で、映画音楽を職人のようにも書けた人である。そういう才能を、ハリウッドやレコード会社がほうっておくだろうか。彼はもしかしたら、ガーシュウィンやクルト=ヴァイルのような成功を収め、ブロードウエーのミュージカルの王様となっていたかも知れない。しかし、彼は、自由主義国に生まれなかったし、亡命をする意志ももたなかった。彼は、ソ連共産党の繭のなかで糸を紡ぐ職業音楽家となったのである。ソ連共産党のもとで、彼がみじめな暮らしをしていたと、我々現代21世紀の資本主義社会の立場から笑うことは出来ない。我々もまた、異なることはないのである。現代のように世界中が自由主義で覆われ、グローバリズムなどと言われるようになると、我々は残忍な市場原理主義のあぎとの犠牲となるのである。我々には亡命など逃避する余地がない。我々の人間性、我々の仕事、我々の芸術、我々の恋すらもが、蜘蛛の巣のように張り巡らされた市場原理が働いていて我々は逃れようがない。方法とジャンルの開拓者ではなく、保守的かつ適度に浮気性な彼の性格が、特殊な政治体制のなかで、結果的に幸いしたのであろう。ショスタコーヴィッチのことを、純粋な作曲家とは間違っても言えない。だが、不純な作曲家とも我々は呼ぶことも出来ない。時に、彼の旋律や和声は、えもいわれぬ気高さと崇高さを、淫蕩で猥雑な狂騒のなかで示すことがある。聖なる淫売ともいうような相貌を、彼の作品は我々に提示するのである。それを、また彼は、音響の圧力のなかに隠蔽しようとするのだ。社会と家族の犠牲のなかで、淫売婦になってしまった少女のけなげさが、彼の音楽には、におう。この感覚は、クラシック音楽というよりは、ジミ・ヘンドリックスやジョン・コルトレーン、アルバート・アイラーの擦り切れてゆくとこへの聖なる代償を喚起させる。『交響曲第1番』や『ピアノ協奏曲第1番』は、アバンギャルドではあるが、ドビュッシーやシェーンベルク、ストラヴィンスキーが示したような必殺のオリジナリティがない。彼らは皆、全集を書くのをやめた人たちである。だがショスタコーヴィッチは、最新技法を伝統技法のなかに組み合わせ、統合することによって自らの書法を確立し、ジャンルによっては音楽的に進化かつ深化を遂げて行った。逆にいえば、方法の開拓者ではなかった彼にとって、無駄な時間を浪費しないで済んだと同時に、処刑防止の仮面をも慎重に身につけることが出来たというわけだ。(この項つづく)掲載曲とその参考盤を挙げておく。興味のある方は、実際に聴いていただければと思う。弦楽四重奏曲と交響曲その他については、次回月法で紹介する。★★★★★『ムツェンスク群のマクベス夫人』ロストロポーヴィッチ指揮/ロンドン・フィル ガリーナ・ヴィシネフスカヤ、ニコライ・ゲッダ他(東芝EMI)★★★★『同』チョン・ミュンフン指揮/パリ・バスティーユ歌劇場管 マリア・ユーイング、ラーリン他(グラモフォン・ユニバーサル)★★★『ピアノ協奏曲第1番・ハ短調』シャイー指揮/ブラウティガム(ピアノ)/ロイヤル・コンセルトヘボウ管(デッカ・ユニバーサル)★★★★☆『24の前奏曲とフーガ』タチアナ・ニコラーエワ(メロディア・ビクター)★★★★『同』キース・ジャレット(ECM)★★★★『同』ウラディーミル・アシュケナージ(デッカ・ユニバーサル)
2006年10月01日
-
第6月法 如来滅後五五百歳その四 浄土崩壊
市場原理主義と経済成長至上主義を国是とし、いわゆる先進国として通用している日本という国家で、世紀をまたいで、二つの象徴的な殺人事件が起きたことを、あなたもご存じであろう。1994年6月27日の長野県と、95年3月20日東京都で、Aという金剛乗を標榜する似非仏教者の指令の下、サリン散布によって19人が死亡、約5500人以上が重軽傷を負った。この他にも、Aは、89年から95年の間に、元信徒ら8人を殺害している。また、2001年6月8日には、大阪府の小学校に乱入したTという男が、児童8人を刺殺し、他に15人の児童・教員に重軽傷を負わせた。これらの事件から跳ね返される影響は、今も多くの被害関係者の間でさめやらぬもので、二人は、罪もない人々に、暗い影を投げ掛け、それをはらす努力を、一切行おうとしなかった。Aはいやしくも仏教者を名乗っている。Tの不幸な家庭環境を言い、改心にはもう少し時間が必要だった、と弁護側や接見の心理学者が言うが、一方で専門化の権化である彼らは、無辜の子ども8人の命の代償について、真剣に思いをめぐらせたことがあるのだろうか。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2006年09月01日
-
第5月法 如来滅後五五百歳その三 真説末法=壊劫の到来
それは必ずやって来よう月は離れ遠く空に星は無く氷のなかに閉じ込められた妙法蓮華経の文字をもう誰も読むものはいないそれは必ずやって来よう焼けた空海は蒸発し大地は溶ける妙法蓮華経の文字はこぼたれ言霊の絶えるとき我々は滅亡する煩悩が集めた地水火風が宙空に固まって我々は出来上がった我は海空は我我は大地マグマは我也我は空即是色に色即是空を輪廻するそれは必ずやって来よう盲目的意志は太陽の最後の光に焼かれるそれでも残忍にも宇宙意志は終わらないタンハーは宇宙をかけめぐりサットヴァ・カルマンは異なる宇宙銀河に転生しよう永劫なる惑業苦それは必ずやって来よう進化は五大に惑星が固まる一から繰り返されようそして新たな知的存在がまたも妙法蓮華経を記すであろう我々が亡びようとも繰り返される妙法蓮華経なる永劫回帰戦後60年は終わっても、今月は、忘れてはならない月である。61年前の8月6日と9日に、広島と長崎で原子爆弾が投下され、30万人の無辜(むこ)の民と、無数の獣と鳥と虫と、数え切れない花と草と木とが、夏の生命の燃え盛る季節に死滅した。生き延びても、生き地獄を見た人々、いまも後遺症に苦しむ人がいる。桜の季節と、太陽の季節、亡者たちの声のうめきが、聞こえて来る。耳をふさごうが見えて来、目を閉じようが、聞こえて来る。桜の木の下で、飲み、歌い狂い、炎天下の砂浜やプールで水しぶきをあげ、家族・同朋が楽しむ海水浴――夜の闇に、白昼夢に、彼らが私を取り巻き、悲しみの涙で私を放さない。嗚呼。しかし、亡者たちに付きまとわれ、息苦しくも、私には彼らのにおいが、無性になつかしい。彼らが、とても他人とは思われないからだ。そういうとき、凡三の小さな胸に色心受持する『白蓮の法』と『般若の法』を捧げる。両法の加持力により、山川草木人獣鳥虫の即身成仏せんことを願わむ。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2006年08月04日
-
第4月法 如来滅後五五百歳その二 そして2020年…真説末法の算定
仏教は、法身説法、久遠実成など永遠の命の方便を説く一方、生者必滅、盛者必衰、会者定離等の諸行無常の科学の無視し得ない事実を表明する。ゆえに、釈迦如来であらせられても、師事した過去仏はおられ、前身であられた菩薩もおられ、未来仏についても語られるのである。ただ、サットヴァ・カルマンこそは、すべての源泉であり、宇宙意志というものがあるとするなら、それに充ててもいいだろう。応身仏として地球上の知的生物として出生された釈迦牟尼は、サットヴァ・カルマンの顕現であったことは、間違いのない事実である。彼が、修行をし、覚り、どこへ往ったかは定かではないが、それを我々は、解脱といい、大般涅槃といい、仏界というのである。サットヴァ・カルマンを統括するもの、指図するもの、この世の自然界を設計するものは、どこにも絶対に存在し得ない。しかし、釈迦牟尼仏の法身を能生させた教えが、唯一存在する。それは、何を隠そう、『サッダルマ・プンダリーカ・スートラ』という書物である。ある人格神が地球や宇宙を創ったというフィクションを宗教として信ずる一神教のユダヤ・キリスト教、イスラム教などの根本聖典に書いてある物語が、全く地球46億年の年表と符合せず、カンブリア紀(約5億7500万年前-5億900万年前)に出現したピカイアという、ちっぽけな脊索動物が、人類をはじめすべての脊椎動物の祖先であり、約500万年前後から始まったサル(猿人)からホモ・サピエンスへの進化を説明出来ないのと異なり、仏典に書いてあることは、「四劫」一つを取っても、生命の起源、地学や宇宙物理学の科学を預言していたようだし、いや、むしろ科学がやっと仏教に追いつきつつあると言える。一方、「五五百歳」は、卑近な人類の歴史学ともほぼ一致するのである。蛇足になるかも知れないが、真説末法のおおよそを述べた後に、五五百歳的速疾日本史を試みるつもりである。茫洋たる宇宙は、誰が創ったものではなく、知らずして出現し、存在してはやがては消えてゆくものである。(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2006年07月01日
-
第3月法 如来滅後五五百歳その一 サットヴァ・カルマン
伝教大師・最澄撰述と伝えられる『末法灯明記(まっぽうとうみょうき)』という小部1巻の著作がある。本人撰かどうか、あれこれ穿鑿されるが、間違いなく最澄の思いが沁みとおっている述作である。後世に及ぼした影響といえば凡百大部の仏典を上回ることは間違いなく、この書に触れて、山を投げ捨てて、切実な実践解釈に出たのが、鎌倉新仏教の各宗祖たちだと言っても許されるだろう。とりわけ、源空(法然)、親鸞、日蓮は、最澄の教機時の定義と心の叫びを自らの教えの根拠とした。『灯明記』曰く、「問ふ、若ししからば今の世はまさしく何の時に当れるや。答ふ、滅後の年代多説有りといへども、しばらく両説を挙ぐ。一つには法上師等『周異記』の説に依りて言く。仏、第五の主穆王満五十一(三)年壬申に当りて入滅したまふ、と。若し此の説に依らば、其の壬申より我が延暦二十年辛巳に至るまで一千七百五十歳なり。二つには費長房等『魯春秋』に依りて、仏、周の第二十(一)主、匡王班の四年壬子に当りて入滅したまふ、といふ。若し此の説に依らば、其の壬子従り我が延暦二十年辛巳に至るまで一千四百十歳なり。かるがゆへに知んぬ。今の時のごときは是れ像法最末の時なり。彼の時の行事既に末法に同ぜり。然れば則ち末法の中に於ては、たゞ言教のみ有りて行証無けん。若し戒法有らば、破戒有る可し。既に戒法無し。何の戒を破するに由りてか破戒有らん。破戒尚無し。いかに況んや持戒をや」(以下本文は、一定期間を経過しましたので削除いたしました)
2006年06月05日
-
第2月法 シューベルト
「フランツ・シューベルト――余の大音楽家よりも重みの少ない芸術家であるフランツ・シューベルトは、それでいてすべての者のうち一番大きい音楽の世襲の富をもっていた。彼はそれを手一杯に優しい心でばらまいた。だから音楽家たちはまだ二三世紀は彼の思想や着想を食って生きるだけのものはあろうと思われるぐらいだ。彼の作品には使い古されぬ発想の宝庫がある。他の人たちは使い古すことに偉大さがあるのだろう。もし、ベートーヴェンを楽師の理想的な聴手と呼んでいいとすれば、シューベルトは、自身理想的な楽師と呼ばれていい権利があろう」(『人間的な、あまりに人間的な』下巻・第二部「漂泊者とその影」フリードリッヒ・ニーチェ著/阿部六郎訳)拙著『妄想無間 仏法サラリーマンはかく語りき』で、フランツ・ゼラーフ・ペーター・シューベルト(1797・1・31-1828・11・19)は、俎上に載せて、一通り料理したつもりだが、再びここで取り上げる。シューベルトを論じることは、私にとっては、限りないインプロヴィゼーションを実感させてくれるからだ。ニーチェが指摘したとおり、シューベルトほど音楽の本当のオリジナルを書いた人を私は知らない。そして、その尽きせぬ泉ほど即興の材料になるものは他にはありそうにも思えないほどだ。ビートルズとカーペンターズで始まった音楽渉猟歴は30年強、食い尽くしたレコード・CDの黒銀の円盤は、5千枚を超えた頃から数えていないが、『妄想無間』の前文に37尊の一角として列挙されている16人の作曲家・演奏家は、格別の存在だ。酋長の鼻唄であろうが、俗謡であろうが、いやしくも音楽と呼ばれるものに対しては、何かしら聴く耳をもち、なんでも好きになってしまう私ではあるが、16尊は、私の現代の五蘊(ごうん)を形成した重大元素だと言ってもいい。なかでも、究竟(くきょう)は、シューベルトとブルックナーである。彼らの音楽がなかったなら、わたくしのような人間が、果たしてこの齢まで生き延びることが出来たか疑問である。苦しいときも、楽しいときも、悲しいときも、喜びのときも、瞋恚(しんに)のほむらを抱き、憎しみと恨みに身がさいなまれるときも、みんな、彼らと一緒だった。彼らは、私にとっては私を見守っていてくれる仏・菩薩のようなものだ。私には、いまや一切家族がいないから、こんなことを言うのではなく、そうとしか言えないから言うのだ。最初は、リズムに身を任せ、美しいメロディー、妙なる和声、予測もつかない即興のどれかを聴いているだけだったが、修練を積むうちに、それらの差異を認めつつも渾然一体のものとして把握すると、彼らの音楽が、仏や菩薩となって私の体に入り込み、私も音楽からイメージされる実相に入り込み、この世を生きるわたくしの心と体の区別はなくなり、すなわち私の阿頼耶識(あらやしき)が音楽の力によって抽出され、絶対持続の宇宙意志へと涅槃に導かれるのである。彼らと共にある音楽鑑賞史は、私の仏法修行の軌跡でもある。興奮と狂騒、やすい涙を誘い、カタストロフィを演出する楽曲は少なくないが、生き物の根源的な喜びと悲しみを知らしめ、宇宙意志とそこからの解脱に至らしむる楽曲は極めて希なるものだ。普遍的に阿頼耶識の顕現を知らしめ、その成仏と解脱を導く作曲家・演奏家はいるのであって、その成否が、私にとっては、音楽家としての高低と価値づけられる。ジャンルを問わずそういう音楽家は存在する。たとえば、ロック・ミュージシャンのジミ・ヘンドリックスの演奏には、必ずしも、いつもというわけではないが、聖なる火花が彼岸を映し出している。年によっては、花粉症でくしゃみ地獄となるが、それでも春は、私の一等好きな季節である。すべてが始まるときである。草花が芽吹き、鳥たちは卵を生み、雛を育てる。この季節を逃すと、新しい生は封印される。春は残酷な季節でもある。気楽に行った山登りが、雪崩で惨事となり、突風が環境を破壊し、入学や入社を決定的に拒否される時でもある。せっかく1年を我慢して咲き出た梅や桜の花びらは、短い命に妍を競い合い、死にゆく。桜という花は、仏法のテキストのような花で、やれ、酒だ、団子だと席を取り合い、花見という儀式に妄執する人々も、散ってしまえば、悲しみの無常を知る。私も、オルガと、雨あられと降り注ぐ桜花を見つめ合った時を思い出すにつれ、淡い花びらの色彩に赤い怨念の情が映し出される。ことしの桜も、嗚呼! とっくの昔に散ってしまった。あるのは、葉桜ばかりである。いわんや、オルガとの桜などをや。さても、フランツ・シューベルトである。彼は十界互具(じっかいごぐ)せる世界を音にした作曲家である。十界とは、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間、天上、声聞、縁覚、菩薩、仏界のことで、存在のカテゴリーである。これを現代語で説明してみれば、シューベルトは、天と地、仏界と魔界、春夏秋冬、そう、山川草木人獣鳥虫すべてを変幻自在に表現出来た作曲家と言えるのだが、春の憧れと残酷を、顕現させる曲をたくさん書いた人でもある。彼は、31歳の生涯で1千曲以上を書き上げた人だから、季節の限定は危険ではあるが、冬と春を描くのに巧みであった。ちなみに、彼は、楽曲の大半を、誰かに頼まれもしないのに書いた。彼は、めん鳥がせっせと卵を生むように曲を書き、積極的に社会に売り込もうとしない例外的な作曲家だった。当時の人には、金の卵の価値はほとんど理解されなかったのだ。そんな政治・経済学を有しない作曲家が他にいるだろうか。『野薔薇』『緑野の歌』『ミューズの子』『蝶』等の歌曲は、自然の命の躍動感を写し取ったかのようであり、代表作『冬の旅』中の『春の夢』は、最期の冬をあてどもなく旅する悲しい男の見る幻の追憶である。最初の連作歌曲集『美しき水車小屋の娘』は、恋に敗れ、春の小川に成仏する若者の悲哀を言い尽くして限りがない。3曲ある『バイオリン・ソナチネ』や『ピアノ三重奏曲第1番・変ロ長調』、『未完成交響曲(ロ短調)』より前の若書きの交響曲や、劇音楽『ロザムンデ』などは、春を表す季語が聴き取れ、優しさと喜びにあふれている。ただ、こんな優美な楽曲のどこかに、いや、至るところに、シューベルトの悲しみは、尽きることなく歌い続けられる。それは、耳をふさごうが、曲の音響が終わっても、えんえん続くのである。名だたる作曲家には、悲しみの色というものがあるのだが、シューベルトの悲しみは、どうにも業のように深く、永劫に癒されることのない、絶対持続の悲しみだ。生き物が生まれた限り、抱え続ける、かなしみ――どんな曲を書くときもシューベルトはそのことを忘れなかった。これは、クリエーターとしてはつらいことであり、彼の指先からは自然にそういうものが流れだし、彼はその意味を常に問うように曲を書いた。彼の早すぎる晩年の音楽的深化はここに由来する。シューベルトを書き殴り屋だと誹謗するものは、この悲しみを聴き取れないものに他ならない。絶対持続の悲しみを、最期の歌曲集『白鳥の歌』の後半で、ハインリッヒ・ハイネの『歌の本』の『帰郷』より、たった6詩を選び取って、題名を付して、それらを氷に閉じ込めたシューベルト――この世の人間の力ではどうにもならない力と必死にあらがうシューベルト。ここには、彼の文学的教養と感受性を疑うものに対しては決定的な回答があるし、また、現代音楽の方法を導いた先見性が豊富に見出される。ワーグナーには告白がなかったが、彼の楽劇の伝統を逸脱した方法と、新ウィーン学派の無調と表現主義の淵源はここにあるのである。ただ、彼らには、シューベルトの黄泉のデーモンが決定的にない。なお、この歌曲集は、シューベルトの死後、出版者・ハスリンガーが3人の詩人に付曲されたものを、一つの表題を付して2冊にまとめたものである。『白鳥の歌』の後半は、100か0の幸か不幸かしか望まない男が、天を担ぎ支えなければならなくなった業苦を嘆く『アトラス』(『歌の本』「帰郷」第24)で幕が開く。世界の業苦は、アトラスの叫びでもある。それは奇しくも、ベートーヴェン後ドイツ浪漫派を一身に背負うシューベルトの姿とも重なる。忍び寄るような暗いピアノの二つ音から導かれる『彼女の肖像』(同23)の優しいメロディーは、オルガの不在の追憶だ。鎮魂歌のように伸びる旋律は、嘆きをますます激しいものとする。極度に音符が切り詰められる音空間は、時間を失った男のミニチュアでもある。一見スキップするように、楽しそうに始まる『漁師の娘』(同8)とのランデブーは、瀬踏みのバルカローレのリズムの繰り返しが、永遠の他者性と恋の不成就を象徴する。神秘的で不気味なピアノ伴奏が、蜃気楼のように『都会』(同16)の幻影を現出させる。オルガを失った場所を、また、私は往ったり来たり、さまよっているのだ。『海辺にて』(同14)は終始、沈痛な表情を隠さない。不幸な女が流す涙が、白い手に落ちて、手を濡らした。そして私はその涙を、女の手を口に当ててすすった。それからというものは、女の涙が毒となって私の体に棲み着いているのだ。『影法師』の街は、夜の闇に死んでいた。丑三つ時、一人の男が、ある廃屋の前でたたずんでいるのが見える。男は、激しく苦痛に身をよじり、天を仰いでいた。弔いの鐘のようなパッサカリアのピアノの霊気に乗せて、祈祷文のレチタティーヴォが始まる。それは、しだいに叫びとなりメロディーを消し去り、その身を真っ二つに引き裂いた。月明かりに見えたドッペルゲンガーの割れた顔は、私のものだった。その時、アスファルトの上の私の影がいつの間にかなくなっていて、私は空中分解していた。そして、終曲の『鳩のたより』(ザイドル詩)で、空中分解した私の阿頼耶識が、ふたたび呼び寄せられ、やわらかな鳩の羽ばたきに乗って大空に運ばれて、5月の蒼穹のうちに成仏するさまを描き切るのだ。なんという魔法であろうか。現象的な平凡な景色からでも、シューベルトには、感覚的な知覚認識の考えから欠落した諸法の実相が見え、それが音になり、実際の詩歌のディクションや、鳥の声や小川のせせらぎなどの実音が、シューベルトのなかでもっと別な次元の和声になり、我々山川草木人獣鳥虫の阿頼耶識――つまり、宇宙意志を歌い切るのだ。生き物が生きてゆくことの悲しみ――残忍な宇宙意志のもとに従わざるを得ず、それに人生をもてあそばれ、仕合わせになれない山川草木人獣鳥虫の定め。さらに、驚くべきことに、そこからの必死の解脱への躍動が、音の底に鳴り響いているように思えてならないのである。私の仕事は、その音を探り当てることである。我々には、こういう音楽に触れ、音の実相を聴くことによって、解脱を得ることも可能なのである。シューベルトやブルックナーは、宇宙意志の形而上学を音に自然に組み立て、さらに、そこからの解脱を表現した。それは、銀河宇宙が始まった時から鳴り響いていた音であり、解脱の方法は、彼らの清浄な個性と利己的な愛を離れた慈悲の努力による。宇宙意志の偉大さと恐怖を曲にしたものは、少なからず存在するが、そこに留まらず、己を捨てて、解脱への方便を作曲したものは極めて少ない。まずは、『美しき水車小屋の娘』『冬の旅』『白鳥の歌』と、三大歌曲集を聴くべし。次に、『交響曲第9番・ハ長調 ザ・グレイト』『弦楽五重奏曲・ハ長調』『弦楽四重奏曲・ニ短調 死と乙女』、さらに、『ピアノ・ソナタ第14番・イ短調』『同16番・同』『同19番・ハ短調』『同20番・イ長調』『同21番・変ロ長調』を落としてはなるまい。ここには、音楽芸術の究竟の高みがある。
2006年05月08日
-

第1月法 マイ・ネーム・イズ・ボンゾー・ジクガワラ
昨年2月、拙著『妄想無間 仏法サラリーマンはかく語りき』を三一書房から上梓した縁で、この度は、ホームページ連載の大役をおおせつかった。プロデューサーのN・T・トーマス氏には感謝するしだいである。この連載は、ニルヴァーナ(涅槃)すなわち、あの世(彼岸)からの視点で、この世の諸々の事象のまぼろし、すなわち無常を語るという構造があるのでご了解願いたい。もっとも、多くの素材を古書と鬼籍の人物に求め、有史を地球46億年と設定し、この世に生きとし生けるものの細胞とデオキシリボ核酸(DNA)を生き証人として随時自在に引用するため、現代を語るにあまりにも地に足がついていないとご批判を受けるかも知れない。正直に告白させていただくと、私は、某新聞社に毎日通っている勤め人である。出勤の前に、また休日の日も、朝に夕に新聞を、毎日のうたかたの出来事を山羊も食い切れないほどに読みあさるのが、この会社に入ってからの私の第一の仕事である。長期休暇を取って旅行に出ても、戻ってくれば、ためてあった新聞のうずたかい積み重ねを、一つ一つ取り崩しながら、時間を取り戻すがごとく読まなければならない。これは、私が飯を食うための経済活動であるから、いかんともしがたいことである。勤め人を演技することしか経済的活動を知らない無能無策の私であるから、仕方ないと言えばそうなのだが、この砂をかむような時間が楽しかったなどということはほとんどなかったというのが、正直な告白である。新聞記事の有意義を決して否定するつもりではないが、おそらく会社を辞めれば、新聞の社説などはおそらく毎日は読まないだろう。いや、社説はおろかニュースの大半もテレビで間に合わせるかもしれない。説教じみて申し訳ないが、あなたは、毎日起きている事件や事故を人生のテキストにしてはならない。世の中の雑事をおろそかにしてはならないが、それだけに毎日足をすくわれると、諸法の実相はますます遠のき、皮相的な事象だけが真実だと錯覚するつまらない人生をあなたは送らなければならなくなるだろう。真実などというものはどこにも無いのだ。有るのは、事実の関係が絶えず移り変わる空性(くうしょう)だけである。あなたが、あなたの自我と感覚器官によってとらえられた現象だけがすべてだとザッハリッヒに論理を展開すると、物質的成功の成否に一喜一憂する人間として、あなたはこの世の消費財となろう。人間は、日々努力し、切磋琢磨し、職能技術を上げ、交際範囲を広げ、人格を陶冶するべきであるというごもっともな意見があるかも知れない。とはいうものの、収入や名誉のために、スキルを上げ、人脈を広げ、高人格をてらうことが、人生の目的なのであろうか。まっぴらの御免である。人間の可能性をいたずらに信用してはならない。知性を自由に操る人類という生物種は、極めて自分勝手であり、自らの安楽のためには、他者の命や、環境破壊などほとんど意に介せず、やりたい放題を、(猿人時代を含め)500万年のあいだ続けているのである。人類は、今から約1万5千年前に、野生の麦から食用に適する品種を作り上げた。バイオテクノロジーの嚆矢である。農耕によって、放浪生活が抑えられ、定住化が進むと、その後わずか1万年の間に、人類の人口は約千倍にも膨れ、地球全体で約1億人になったと言われる。他の動物と異なり、高い知性によって武器と言語が使える人類は、地球環境――動物や植物も当然含めて。環境異変というリスクには左右されたものの――を料理する独占的自由をほしいままにした。好き勝手に殺し、移動し、切り崩し、他の動植物と自分たちを区別するため境界線を引き、耕しては安住の地を求めた。そして、しばしの安息の地を錯覚すると、仲間内に激しい序列闘争が起こり、血の代償に王権と富が確立されてゆく。その戦いは、いまだに続いており、我々人類には安息の地などは無縁のような感慨を与える。20世紀に入っての二つの世界大戦、わけても最後の大戦で我が国は、二つの原子爆弾を見舞われた事実を忘れてはならない。新世紀の扉が開かれても、イラク戦争は、市場原理主義――なにも私は、株式・経済用語として使っているのではない。地球上の有機物(むろん人間も含む)、無機物合わせてすべての物質と、心とか精神、魂とか言われる抽象物をすべて商品として序列化するシステム――教をグローバリズムと称して、民主主義というものと一緒に押し売りに出る戦争ビジネスが、今でも健在であることを証明した。民主主義というものがたとえ有効に働いたとしても――それを否定するつもりは毛頭ないが――行き過ぎた人間の欲望をコントロールするのと、富を均衡ある方程式で再配分するのがせいぜいのところである。それも、必ずしも長続きはしないものだ。政治家に国民はだまされ、国民は愚民化し、その国の政治家はその国民に見合った、愚かなものになる。政治家が先か、国民が先か議論もあろうが、民主政治は悪循環からなかなか容易に抜け出られない。日本が戦後、経済的に豊かになったのは、アメリカに首根っこをつかまれたときが時機にかなっていただけであって、運が良かったことが第一の要因である。優れた技術や特殊なマネジメントも経済発展の要因ではあるが、国民性の優位や自主性などをゆめゆめ思わないことである。ソ連を中心に共産主義国家がかもす東西冷戦と朝鮮半島の南北分断が、キーワードである。以上、この世の世界情勢を概観してみたが、私は、あえて、そういう欲望の人類の歴史から解脱したく、ここ20年このあいだ、わたくしがごとき凡夫がそれなりに出来る修行を仏典の研究と並行して追い求めた。ビッグ・バンから銀河系に浸透する宇宙意志と、風・火・地・水が空(くう)に固められた我々の惑星と身体を、46億年を輪廻する存在として、創造的な思考の持続をインプロヴァイズし、自分勝手な知性をととのえて、宇宙意志を志向する本能的な肉体の形而上学を覚り、いったんは覚った宇宙意志をあの世にかえし、ふたたびみずからの即興で、この世を豊かにする方法をおろかなりに模索してみた。非常に乱暴な言い方かも知れないが、そういうことを仏法として私は把握した。それらのことなどを由緒正しき論文調で説明しても、ただむなしいばかりか、信用してもらえないおそれがあるので、仏典、そして音楽や文学などを題材に、私小説の文体でエッセイを進めさせていただく。文章を即興させることは、私の修行でもある。それによって解脱が得られれば幸いである。この世に有ると実体的にものを考えることの徹底的な否定こそが、仏法の般若波羅蜜(はんにゃはらみつ)、すなわち直観的な智慧である。覚ろうではないか。150億年の宇宙意志の在り処と、我々の実存を――。なお、私は特定の宗教団体に属するものではなく、独学で仏典を第一のたよりに銀河の宇宙線と引力を五蘊(ごうん)に感受しながら仏法を探るものである。プロフィール1960年9月東京生まれ。84年早大卒。某新聞社に勤務する会社員作家。著書に、『妄想無間』(三一書房)、『文学鑑定』(鳥影社)がある。独身。
2006年04月17日
全42件 (42件中 1-42件目)
1