2010年07月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-

アントワープ王立美術館コレクション展 東京オペラシティ
「アンソールからマグリットへ ベルギー近代美術の殿堂」というサブタイトルのとおり、ベルギーの近代美術を概観する構成となっている。ただしアンソールは初期のころの写実的な絵が多く骸骨が躍るような幻想的な絵は出展されてないし、マグリットの絵も2点しかない。どちらかというと始めて名前を聞く画家も多いのだが、中には強烈な印象の残る絵もありかなり楽しめる内容の展覧会であった。第1章の「アカデミズム、外交主義、印象主義」では、隣国フランスに同調しつつ、ベルギー独自の絵画運動を行った画家たちの作品。特にヤン・ストバーツ(はじめて知った画家)の「バラのシャワー」は、いい絵であった。森の奥の階段から裸婦が楽しそうに下ってきて、バラの花の咲き誇る中を歩いている。実際にこんな場面だったら、とげが刺さって、絶対に痛くて歩けないと思うのだが、それはそれ。うっすらと犬の影が見えたり、裸婦の表情が分からなかったりするが、幻想的な作風には思わず見とれてしまった。第2章の「象徴主義とプリミティヴィズム」では、レオン・フレデリックの「咲き誇るシャクナゲ」が素晴らしい。レース越しに窓から降り注ぐ光を浴び、紫のシャクナゲの鉢植えが咲き誇っている。少女に当たる光の表現も見事。この画家は、Bunkamuraのベルギー展などでも見たことがあるが、大胆な明るい色調がっ素晴らしいと思う。反面、レオン・スピリアールトの禁欲的な自画像は、絵を眺めている方も圧迫感を感じるほど。第3章「ポスト・キュビズムとフランドル表現主義と抽象芸術」。このコーナーをうまく通過したことが当時としては画期的。このあたりが、今回の展覧会の中枢となっている。グスターブ・フォン・デ・ウースティネの「リキュールを飲む人たち」は面白い絵。画面の二人の女たちは実は画家に描かれた絵であるのだが、それもよく見るとだまし絵のようになっており、その立ち位置を理解するのには、時間がかかる。第4章の「シュルレアリスム」は、やはりマグリットの絵に尽きる。マグリットの「9月16日」は、それだけで情緒ある詩的な雰囲気のある一本の大木。そこに三日月が浮かんでいるというありえない光景。しかし絶対的な存在感を示す素晴らしい一枚であった。ぐるっとパスで入場無料だし、併設の「幻想の回廊」展は、まさにこの「シュルレアリスム」の続きのような日本人画家の作品ばかりで楽しめ、大満足。
2010年07月31日
コメント(6)
-

造形作家 友永詔三の世界「木彫の乙女たち」 ニューオータニ美術館
この彫刻家、プリンプリン物語の人形作家ということを会場ではじめて知った。どの少女の彫刻も細長く、特に両手の指の繊細な長さに見とれてしまった。竹林の中で、平等院鳳凰堂の雲中供養菩薩か、飛天か、迦陵頻伽のように身体をそらせた少女たち。その姿には驚かされた。羽をつけた妖精か天女の像もある。大部分が、サイプラスという材質の木。知らない樹木だが、調べるとどうも豪州ヒノキらしい。木目がうまく身体にマッチしたつるつるの木肌が美しい。楠素材はノミの跡が残るデコボコとした表面。松の木はさらに固いのだろう。木の素材によって、少女の様子がかなり変わってくるのが楽しい。奥の部屋は「プリンプリン物語」の人形たち。この番組は特に見ていたわけではないが、かなり長期間放映されていた記憶がある。
2010年07月25日
コメント(4)
-

濱田庄治とその系列 石洞美術館
はじめて、京成の千住大橋駅で降りた。駅の間近にこの美術館はあった。外観は二つの楼閣が並んでいるように見える。その一方が、美術館となっている。中は1階に小さなスペース。緩やかな螺旋状の廊下を登り、階上に大きなスペースの展示室がある。趣がある空間だ。まず、バーナード・リーチが鹿を描いた下絵がある。一瞬、宗達の絵かと思った。リーチが琳派の影響を受けていることが分かる。今回の展示は、濱田庄治とその息子、孫の陶芸作品が並ぶ。沖縄の壷屋焼の赤絵の茶碗や鉢が気に入った。益子焼の土の質感を感じさせる作品と異なり、薄い肌色に赤絵で唐黍の文様が描かれている。そこに一筋の緑の葉が心地よく映えている。沖縄のはっきりとした陽光がイメージできる。多くの茶碗も並んで展示されている。普段使いの中に美があるといった民藝運動。本当にひとつひとつ手にとって肌触りを感じてみたい作品ばかりだ。濱田庄治と息子の濱田晋作の大鉢が並んでいる。濱田晋作の大鉢「白釉縁黒大鉢」に一際目をひかれた。まるで、中心は満月のよう。中にウサギが見えないかと真剣に眺めた。
2010年07月24日
コメント(0)
-

誕生!中国文明 東京国立博物館
学生時代の歴史の授業では、中国文明最初の王朝は「殷」であると習ったのだが、今では「夏(か)」と呼ばれれる王朝があったことが分かっている。紀元前2000年頃のことだ。この展覧会では、この、「夏」王朝の出土品の展示から始まる。チラシにも使われている「動物紋飾板」は一見の価値あり。動物がうずくまった姿を上から見たところ。トルコ石のブルーの輝きが、今なお美しい。4000年という気の遠くなる時間を経て、今、こうして目前に見ることができるという感激。あとは、巨大な青銅器がいくつも展示されている。今はドラム缶などが当たり前なんで、当時は金属は最高権力者しか持てなかったことを想像するのに苦労する。今回出展されている多くの青銅器は、さほどオドロオドロシイ文様が見られないので、ちょっと残念。ただ、暗い室内にぼぉっと、青銅器や鐘が浮かび上がる展示方法には感動した。異空間にスリップしてしまったような感覚になる。金縷玉衣(きんるぎょくい)は、3年前の東博の中国国家博物館名品展で見たことがある。その時のもの全体に赤みがかった石で造られていた記憶があるが、今回は、全体が、青い輝きの石で造られている。美しい。死後も身体が永遠に残ってほしいという願い。ミイラと同じ発想。この権力者が自ら言いだしたのか。それとも、それだけ周囲の人から愛されていたのか。そんなことをふと考える。大きな建物の副葬品があった。7階建ての建物を形作ったもの。死後もこんなゴージャスな家に住み続けることができるように祈ったのだろうか。後半の神仙の世界。青銅の神獣の奇怪な表現。虎の身体に龍の首と亀の脚を持った怪獣である。頭には、さらに6匹の龍がうごめいている。じっと見ていて飽きることが無い。このあたりのコーナーがもっと充実してくれるとさらに面白かったのだが。それぞれのコーナーはきれいにまとまっていた。展示方法に工夫もされており楽しめた。ただ、あまりにもきれいに整いすぎていた感じで、当時の人々の怨念とか呪詛とか、祈りとか、そんなおどろおどろしさが伝わるともっと素敵だったと個人的には思うのだ。
2010年07月23日
コメント(6)
-

トリック・アートの世界展 -だまされる楽しさ-
昨年、Bunkamuraで見た、だまし絵展は、アルチンボルトやら暁斎やら、古今東西のだまし絵のオンパレードを楽しんだ。そんなノリで出かけたため、かなり肩すかしをくってしまった。こちらは、日本の現代作家の作品ばかりだったからだ。でも、そこはトリックアートの面白さ。物足りないなぁと思いながらも、それぞれの作品にはけっこう見入ってしまうものもあった。高松次郎の「影」シリーズから展覧会は、始まる。描かれた影から実態を連想する一連の作品。竹橋の近代美術館の常設展の作品が好きで、私は、けっこう親近感を感じている。飛び出した釘が出ていて、その影が描かれたものか、本当の影なのかが分からないというミステリタッチの作品もあった。そのあとは、見方によって、凹んだり飛びだしたように見える図形を描いた絵。見る位置によって色が変わるボールのオブジェなど、トリックアート定番といった作品が続く。スーパーリアリズムの絵画。絵だか写真だか分からないという点がトリックなのだろうか。遠目から見ると写真にしか見えない生タマゴを割る時の絵。迫真の描写。上田薫という画家のシリーズだ。中川直人のヴィヴィヴィッドな絵も鮮烈だ。森村泰昌のゴッホに扮した自画像の写真。こちらは、逆に絵画にしか見えない。だがよく見ると白目の充血がまさに写真。福田美蘭の登場人物の目から眺めて名画を再構成した絵。ラス・メニーナスの侍女の視点であの舞台を眺めるとこうなるのかと新しい発見もある。期待をするとガッカリするかもしれないが、軽い気持ちで見に行けば、かなり楽しめるのではないかと思う。
2010年07月22日
コメント(0)
-

江戸絵画への視線 山種美術館
琳派、やまと絵、狩野派、文人画、諸派などの作品を通して江戸絵画を概観しようとする企画。特に岩佐又兵衛の「官女観菊図」をほんの数センチの間近に見ることができるのが圧巻。老眼の身にはあまりにも近すぎて、逆に離れざるを得なかった。背景にうっすらと金泥が引かれているさま。官女の着物の文様の細やかさ。髪の毛一本一本の表現。うっすらと紅の惹かれた唇。御簾の一本一本の枝の表現。薄墨のかすれたような菊の花々など、又兵衛の執念に驚愕する。琳派では、抱一の「宇津の山図」など見どころも多い。抱一の養子、酒井鶯浦の「白藤、紅白蓮、夕もみぢ図」の3幅対の掛け軸がよかった。白→紅白→赤と横のバランスのよさ。それぞれの掛け軸の縦の構図のバランスの良さがうまくマッチしている。文人画では、はじめて知った日根対山という画家。「越渓秋色図」のかすれた水墨と紅葉の赤さが絶品。池大雅の「指頭山水図」は、筆を使わずに指や爪、手のひらなどで描いた山水画。どこの部分で書いたのだろうと推理するのも楽しい。伝長澤蘆雪の「唐子遊び図」は、芦雪の絵にしては、子どもがかわいすぎる。どちらかというと応挙が描く子どもに近い気がする。だから「伝~」となっているのだろう。琳派に、光琳の作品が無かったのがちょっと残念ではあったが、とても見ごたえのある展覧会であった。
2010年07月21日
コメント(2)
-

ブリューゲル 版画の世界 Bunkamura・ザ・ミュージアム
ちらしの「聖アントニウスの誘惑」の奇想天外な光景。近代のシュールレアリスムの画家の絵ではないかと間違うってしまうくらいにステキ。3連休、最後の休日の3時過ぎ。Bunkamuraのチケット売り場にちらほらの人。混んでいるのかなぁと思い、扉をくぐり、怪物たちの姿のパネルを見ながら、会場に入ると、絵の前にずらっと人が並んでいる。というか、最初の絵まで行列していて近づけない。何しろ細かい版画なもので、絵の直前でじっと見入ってしまうからだ。特に音声ガイドを借りている人。これは仕様がないのだが。壁と壁の間にも動かない行列。これはたまらないと、列の後ろから眺めることにする。後半は、やや列も途切れがちで、絵の前に立つこともできたが、それにしても驚いた。みなさん、忍耐強い。若者カップル多し。チラシの効果が大きいのかもしれない。最初は、風景画。雄大なアルプスの山々がすばらしい。このあたりは、落ち着いて見られない作品もあり、残念。再度出直すことにする。ブリューゲルというと油絵のイカロスの失墜を思い起こすのだが、今回も版画が出ている。落ちるイカロス。でも、風景はまったく変わらず。宗教画のコーナーになってくるとまさに異次元世界。チラシの「聖アントニウスの誘惑」「最後の審判」など、もうこれでもかというくらいに、描きこまれた化け物や異形の人々。家畜人ヤプーの世界。ボスの影響が大であることを確認した。有名な「バベルの塔」がある。いつかブリューゲルの油彩を見たい。キリスト教の7つの大罪のコーナー。解説を読むとなるほどと分かるが、絵だけ見ていても迫力満点。私は恥ずかしながら映画の「セブン」で、この主題を知ったのだが、当時の人はこういう絵を日常的に見ながら、生活を道徳化していたのだ。日本の地獄絵と同じ。しかし、背景の建築物も斬新で凝りに凝った形で驚いた。生活の寓意や教訓をテーマにした作品。なるほどと思うものも多し。「大きな魚は小さな魚を食う」は弱肉強食とのこと。裂かれた大きな魚の腹から、デロデロとあふれ出る小さな魚たち。これも現代人の目から見ると少々気色が悪い。でも、当時の人々にとっては、みんな自然なことなんだと改めて実感。帆船のさっそうとした姿が美しい。ここにもイカロスとダイダロス親子の姿や、海神たちの姿が描かれているものもあって楽しかった。後半は列も途切れがちで、自由に移動できたが、4時半過ぎに入り口に戻るとまだまだ長蛇の列であった。
2010年07月20日
コメント(10)
-
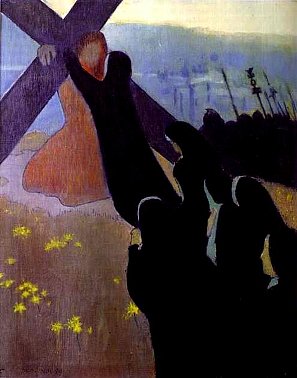
オルセー展 2回目 国立新美術館
入場者数40万人を突破した、空前絶後の展覧会。やはり大混雑であった。しかし2回目となれば、最初から人の列にまぎれて忍耐強く回るのではなく、見たい作品をグッと絞ることができるので、混雑にはめげることはない。モネの「日傘の女」あたりは大混雑。ところが、端っこの「ロンドン国会議事堂」の前はなぜか人がいない。このサーモンピンクの陽光は、本当に美しい。私の中では、モネの作品の中でも「黄昏のベニス」と1,2を争う作品である。点描画の新印象主義のコーナーも大混雑でするー。セザンヌのコーナーも同様だったが、「水浴の男たち」と静物画を見たかったので、ここは我慢で人込みに並ぶ。「水浴の男たち」の夏の雲と日差しがいい感じ。そういえば、関東地方も梅雨明け。ロートレックは、袋小路の一室で身動きがとれそうもないのでスルー。ゴッホとゴーギャンを比べると、やはりゴッホの並びの方が、人の列が厚い。人気の差が歴然。でも、私はゴーギャンが好き。まだタヒチに行く前の細かい規則正しいタッチの作品がたまらない。「星降る夜」の手前のカップルの表情を確認したかったので、間隙をぬって、絵の前に。女はニコニコ笑っているが、男の表情は分からなかった。夜空に輝く北斗七星はいつ見ても美しい。ポン=タヴェン派、ナビ派あたりにくると、最初から人込みに紛れて進んできた人々は疲れ果てたのであろう。人混みの混雑もだんだん解消してくる。そして、モローのオルフェウスあたりでちょっと厚い列。最後のスローで最後の気力を振り絞ると思う。そこで今回のオルセー展の主眼は、このあたりを良く見ることに置いた。特に、ここのところお気に入りのヴァロットン。端正な自画像を含め、4点もの作品があるのだ。麦わら帽の少女の絵は、何度見ても素敵だ。この展覧会のヴァロットンは、調和のとれた作品が多いような気がする。ドニの作品は何と9点もある。「カルヴァリオの丘への道」。十字架を抱えるイエスにすがりつく黒い修道女たちの切々とした動作。誰一人として表情が読み取れないのも不思議。奥にはローマの兵士の軍団が見える。足元に咲く黄色い花が、我関せずと美しく咲いている。ナビ派の面目躍如たる作品。モローの「オルフェウス」。ポスト印象派というタイトルから錯覚してしまうのだが、この絵が描かれたのは1865年。この展覧会の中で一番古い絵だ。印象派の名前の由来となったモネの「印象・日の出」は1872年。別にこだわることもないのだろうが、展示意図や展示方法など、ちょっと引っかかってしまった。もちろん、絵は文句のつけようもなく素晴らしい。そして、ルソー。累々たる死体の山。合間からこめかみの鉄砲の傷穴から真っ赤な血を流す男の顔も覗く。日野日出志のアイデアの源はここにあったのかもしれない。そして、蛇使いの輝く両目にまたも呪いをかけられてしまうのだ。ボナールの「ル・カネの見晴らし」に心地よく送られて、2度目のオルセー展の見学終了。
2010年07月19日
コメント(4)
-

マン・レイ展 国立新美術館
土曜日、午後。オルセー展に比べると、信じられないくらいガラガラの会場。この日の夜、「美の巨人たち」でも放映されていたモンパルナスのキキとアフリカの仮面を映した「黒と白」とそのネガフィルムのバージョンの2枚は、美しかった。経年劣化のために使えなくなっていたオリジナルのネガを瞬間的にスキャンして作った作品とのこと。仮面の黒と白いキキの対比。縦と横の対比。キキの大きな瞳を覆う閉じられたまぶたの曲線の見事さ。キキとマン・レイの破局寸前の最高傑作だと美の巨人たちでは紹介されていた。この展覧会、マン・レイの生涯を追って作品を展示している。画家、女優たちなど各界の著名人のポートレイトも多数あって、それなりに興味深い人物も多かったのだが、いささか盛り上がりに欠ける印象が残った。ソラリゼーションなどを駆使したパリ時代の作品。シュールレアリスムの数々の作品。キキを撮影したヌード写真など、よく写真集で目にするような見ごたえのある作品が少なかったのがその理由だろう。どうしても晩年を共に過ごしたジュリエットが作った財団中心の所蔵作品中心であるためなのかもしれない。
2010年07月17日
コメント(0)
-
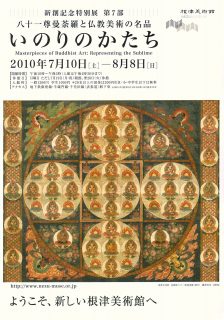
いのりのかたち 根津美術館
日本橋の三井記念美術館で奈良の仏像を見た後は、表参道の根津美術館に向かう。こちらでは、色鮮やかな仏画が多数出展されている。ふつう、仏画というと退色して姿のはっきりしない仏を描いた掛け軸を思い起こすが、根津には保存状態のよいものが多く驚いた。「金剛界八十一尊曼荼羅」、とにかく、美しい曼陀羅である。この精密な諸仏の配置。緑と赤、仏と草花のハーモニーが抜群である。とても鎌倉時代のものとは思えぬ美しさが残っていて、まるで、最近のチベットの曼荼羅を見ているかのようであった。それ以上に驚いたのが、平安時代の大日如来像である。もともと大日如来は他の如来と違って、宝冠や瓔珞などの飾り物をまとっているのだが、それらが色鮮やかに仏の白い身体を飾っている。800年以上前のものとは思えず、つい最近描かれた仏画のようである。その他、愛染明王像の深紅の身体と羊歯のように渦巻いている火炎の光背の文様に見とれ、赤い日輪の中の獅子の頭に座す大日金輪像にも強く惹かれた。金の唐草紋のある深紅の袈裟をつけた高麗の阿弥陀如来の仏画も名品が多く出展されていた。仏画は仏像と異なり傷みやすく、オリジナルの美しさが無くなると興味を失いがちになるのであるが、久しぶりに美しい仏画を多数眺めることができて、感激した展覧会であった。
2010年07月13日
コメント(0)
-

奈良の古寺と仏像 三井記念美術館
曾津八一のうたにのせてというサブタイトルがついてはいるが、八一の歌や書にはあまり興味が湧かなかった。あの枯れ枝のような堅い書には、あまり惹きつけられない。それよりも、奈良の仏像たちと、日本橋で出会うことが出来る幸せ。どんな仏像が出展されているのか、ほとんど知らずに眺めていただけに、感動の連続。最初の立体展示のコーナーには、観音菩薩など白鳳仏の小品が出迎えてくれる。東博の法隆寺宝物館のミニ版といったイメージ。正歴寺の薬師如来倚像(いぞう)は、イスに腰掛けた東京深大寺にもあるが、日本では珍しい姿の仏像。二重のまぶたに柔和なよきお顔。東大寺と岡寺の菩薩半跏像が並んでいる。2体の菩薩の表情を比べるのも面白い。私はふっくらとした丸顔の岡寺の菩薩の方が好きだ。如庵ケースの八一のコーナーは軽くいなして、次の部屋は、東大寺、西大寺などの仏像を楽しむ。東大寺の鎌倉時代の四天王。とくに下ぶくれの少々マンガチックな持国天が好きだ。腰のくびれもいい感じ。五劫思惟阿弥陀像はお坊ちゃまのような四角いお顔が愛嬌たっぷり。まぁあの螺髪。はじめて見る人はびっくりすると思う。螺髪のつんつんした様は西大寺の塔本四仏像の方がすごいと思う。木くそ漆で盛り上がっているのだろう。4体とも表情のリアルさがいい。最後のコーナー。思わずうなってしまったのは、室生寺の国宝釈迦如来像。室生寺に行っても、暗い堂内で遠くに見えるだけのこの像が、なんと目と鼻の先で拝観できる。この釈迦如来像、こんなに白かったのかぁとまず驚く。そして、足の裏の木目の様子、両胸の木目のようすなどもよくわかるし、足の裏はつやつやと輝いている。さらに仏の指の間の水かき(縵網相)がばっちりと見えるのもすごい。とにかくこの像を見ることができたのは、予想外の大収穫であった。釈迦如来像は7月25日までの展示。
2010年07月10日
コメント(12)
-
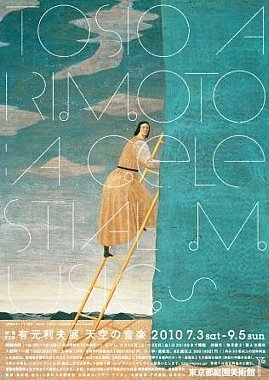
有元利夫展 天空の音楽 東京都庭園美術館
梅雨空の湿った空気は不快だが、逆に庭園美術館の木々は緑が鮮やかで光り輝いて美しい。一歩、洋館の中に入ると、ひんやりとした清々しさが漂う。冷房のありがたさを感じるのだが、もうひとつは、有元の絵が醸し出す雰囲気のおかげでもあると思う。私は、毎年2月末の有元の命日前後に、三番町の小川美術館(弥生画廊)で開かれる有元の展覧会に出かけている。美術館からお知らせの絵ハガキが届く。ただ残念なことに今年は行きそびれてしまったので、この展覧会はグッドタイミング。小川美術館も、重厚なドアをくぐり、暗い廊下を経て、辿り着く展示スペースは胎内めぐりか洞窟を思わせる。この空間は有元の絵にピッタリな趣であるのだが、今回の庭園美術館も絵に描かれたひとりひとりの人物が、まるでこの洋館の住人で、我々を出迎えてくれるように感じられる。そう、この雰囲気は2年前の舟越桂の「夏の邸宅」と同じである。外光を遮ったほの暗いエントランスにいきなり、有元のしっくいのようなフレスコ画が現れる。あの螺旋階段を昇る女性を描いた「花降る日」という絵だ。舞い落ちる花びらが、散華のようで美しい。振り返ると、天にかけられたような黄色いはしごを登る人物を描いた「厳格なカノン」がある。空の白い雲の形がおもしろい。次の部屋には藝大の卒業制作「私にとってのピエロ・デラ・フランチェスカ」がある。派手な色遣いとまだまだ堅い人物である。その後、年を追うに従って、だんだんと柔らかく、浮遊・飛翔する人々の作品が登場してくる。画面には曙光が差し、花々が散り始める。この頃の明るい色遣いの作品が好きだ。80年代になると、病気との闘いもあったのだろうか、画面も暗い色調が中心になってくる。最後の大作、「出現」は山越阿弥陀図に通じるという説があるが、なるほど、有元は自分の死期を予測して描いたのかもしれないと思った。しかし、生まれたばかりの子どもを残して38歳という若さでの夭逝は、さぞ無念であったことだろう。私が有元の絵を知ったのは、宮本輝の小説のカバー絵にも使われ始めた頃で、すでに有元の死後であった。その後、東京ステーションギャラリーの展覧会で、はじめて実物の絵を見たことを思い出した。それ以来の有元ファンであるが、今回の庭園美術館での展覧会は素晴らしい環境の中でまとまった作品を見ることができ、今年の夏いちばんの思い出となりそう。
2010年07月04日
コメント(10)
-
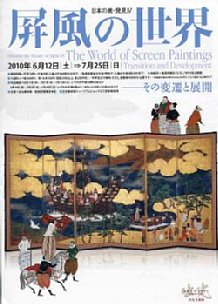
屏風の世界 出光美術館
中国から伝わった屏風は、大画面の絵を表わす手段として発達した。当初は寺院の宗教儀礼用の山水画であったのが、やがて花鳥画、物語絵、名所、風俗画とあらゆるジャンルに広がったのである。この展覧会では、出光美術館所有のそれぞれのジャンルの屏風を合計20点ばかり展示している。今回、楽しみにしていたものは、岩佐又兵衛作と伝えられる二つの屏風。蟻通・貨狄造船図屏風と三十六歌仙図屏風。貨狄・・・の屏風は、それこそ、大画面のスクリーンにグロテスクな龍と鳥の化け物の頭をつけた船を造る場面?が描かれている。三十六歌仙屏風の方は、やはり屏風の大画面を利用して三十六歌仙の姿と、扇面の平家物語や風景画などが、上下に並べられている。なるほど、屏風ってのは大画面の絵も小さな絵も何にでも利用できるものだとこの2つの屏風を見て、改めて感じた。又兵衛の絵は、三十六歌仙の「人麻呂」と「赤人」も別に展示してあり、真上から近距離で眺めることができうれしい限り。江戸名所図屏風や祇園祭礼図屏風。いつも思うことだが、こういう屏風を見るのは非常に体力がいる。座敷に寝転がってのんびり楽しむわけにはいかないからだ。ぎっしりと描かれた人物を中腰で食い入るように見つめているとどっと疲労が押し寄せる。せめてソファでもあればなぁと思うのだ。また、今回は琳派の華麗な装飾屏風は、展示されていなかったのが残念であった。そうそう、今年から出光美術館は、ぐるっとパスの恩恵が割引料金のみになってしまったのも非常に残念であった。
2010年07月01日
コメント(4)
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
-

- フォトライフ
- 源氏物語〔34帖 若菜 56〕
- (2025-11-25 11:30:04)
-
-
-

- アニメ・特撮・ゲーム
- まどドラ ホーリーマミゲット
- (2025-11-24 09:57:24)
-
-
-

- フィギュア好き集まれ~
- 僕の夢のコレクション(158) タイムク…
- (2025-11-25 23:57:08)
-







