2012年10月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
いちじつ(感想)
”一日”(2012年5月 文藝春秋社刊 西村 賢太著)を読みました。 主に芥川賞を受賞した後に書かれた文章を集めた第二随筆集です。 第一随筆集は、私小説の一本道を行く無頼派作家の”一私小説家の弁”でした。 それは、内容のほとんどは私淑する藤澤清造についてのものでした。 この第二随筆集は、私小説礼賛などの文学魂の吐露から、東スポ連載の”色慾譚”までが掲載されています。 西村賢太さんは、1967年東京・江戸川区に生まれ、町田市内の市立中学校を卒業後、家を出て東鶯谷のアパートに下宿し、その後、飯田橋、横浜市戸部町、豊島区要町、板橋などでアパートに住んだそうです。 この間、港湾荷役や酒屋の小僧、警備員などの肉体労働で生計を立てました。 16歳頃から神田神保町の古本屋に通い、戦後の探偵小説の初版本などを集め、土屋隆夫の作品を通じて田中英光の生涯を知ってから、私小説に傾倒するようになったそうです。 23歳で初めて藤澤清造の作品と出会い、29歳の頃から清造の作品に共鳴するようになり、清造の没後弟子を自称し、”藤澤清造全集”の個人編集を手掛けています。 清造の墓標を貰い受けて自宅に保存しているほか、1997年頃から毎月29日には菩提寺の石川県七尾町の浄土宗西光寺に墓参を欠かしません。 2003年に同人雑誌に参加して小説を書き始め、2004年に文學界下半期同人雑誌優秀作に選出されました。 2006年に芥川賞候補、川端康成文学賞候補、三島由紀夫賞候補となり、2007年に第29回野間文芸新人賞を受賞しました。 2008年に芥川賞候補、2009年に川端康成文学賞候補となり、2010年に第144回芥川賞を受賞しました。 万に一つも受賞の可能性はないと思っていた芥川賞を射止めて、前後の心境や過去の出来事などが書かれています。 内容は、私小説のこと、酒呑みのこと、お金のこと、性体験のことなど、最後の無頼派作家の日常がたんたんと記載されています。 この道ひとすじという生き方は、結局、長い間に報われることが少なくないという気がしています。
2012.10.30
コメント(0)
-
独立して成功する「超」仕事術(感想)
独立自営という言葉には人々を引きつける魔力がありますが、独立後に行きづまったという話をよく聞きます。 独立の条件や自営のノウハウとは何でしょうか。 ”独立して成功する「超」仕事術”(2003年3月 筑摩書房刊 晴山 陽一著)を読みました。 家族3人を道づれに40代後半で筆一本で独立した男の挑戦の物語です。 晴山陽一さんは、1950年に東京で生まれ、早稲田大学文学部哲学科を卒業して出版社に入り、経済雑誌の創刊と英語教材の開発を手がけました。 元ニュートン社”コモンセンス”副編集長、ソフト開発部長を務め、今は作家・英語教育研究家です。 サラリーマン時代、入社以来20年余の間、会社のために誠心誠意働いてきたそうです。 会社の存続のために過酷なリストラも行ったりしましたが、いかに努力しても一向に家族より会社のほうが大事というふうにはなりそうもなかったとのことです。 47歳の時に会社をやめました。 自分の時間を会社のために使うより、家族のために使うことを選んだのです。 でも、もし独立に失敗したら、むしろ家族を不幸にするわけです。 会社をやめた時、親しい友人が、筆一本で食べていくのは絶対ムリだと忠告してくれたそうです。 でも、独立を断行してしまいました。 独立した翌年に出版した”英単語速習術”が10万部を越えるヒット作になりました。 独立後5年で刊行点数はほぼ30冊となり、年間6冊のペースはかろうじてクリアしました。 収入の目標は年収1000万円でしたが、たまたまヒットに恵まれた2年間については越えることができました。 印税生活というと世間の人は何もしないでお金が入ってくるウハウハ生活を思い浮かべるようですが、その舞台裏は実は自転車操業だそうです。 独立して本を書くようになると、お金は、すばやくよい仕事をして、自分の力で稼ぎ出すものになちました。 サラリーマン時代には、なけなしの金が減っていくという悲哀に似た感情が常に伴っていましたが、独立後は、元気よく入ってきて、元気よく出ていくという感じになりました。 貯めた中からいくら使うかではなく、使った分は必ず稼ぐという、ポジティブな消費者に変わりました。 いわば、自給自足の原始生活に還ったような不思議な感覚です。 サラリーマン時代には決して味わうことのできなかった、賎しさとも表裏一体です。 人から与えられた仕事をこなすのではなく、自分の仕事を自ら開拓しやりたい仕事をします。 執筆の条件は、早く書く、多く書く、売れるものを書く、印税率のよい出版社で書く、刷り部数の多い出版社で書く、営業力のある出版社で書くです。 その前提条件は、書けるものを書く、書きたいものを書く、書きがいのあるものを書く、未開拓な領誠にチャレンジするです。 何よりも優先する条件は、編集者とうまが合うことだそうです。 一般的に、独立するには、気力・体力・知力・財力・協力が必要です。 本書には、クリエイティブに生きるための具体的なヒントが満載です。プロローグ 独立の5つの条件(気力、体力、知力、財力、協力)第1章 それは突然やってきた!(気力の章)第2章 「個人事業主」になる(財力の章)第3章 会社をやめて友達できた!(協力の章)第4章 デスクワークは立ってやれ!(体力の章)第5章 知的生産のための13のヒント(知力の章) 脱「計画」病、生身からの発想、すきま時間はぼんやりしよう、体験的スランプ脱出法、人生を三倍楽しむ法、多機能人間のすすめ、仕込みの時間、速度は力なり、一時間先を読め、自分ブレスト、形容詞を消せ、書物は資料と割り切れ、スパイラル式執筆法エピローグ 果報は仕組んで待て!
2012.10.23
コメント(0)
-
日本「再創造」(感想)
東日本大震災は、大地震、大津波、原発事故という戦後最大の複合災害でした。 かつての敗戦後、廃墟となった国土の復興にひたすら邁進してきた日本は、戦後最大の危機に直面しました。 しかし、危機に怖気づいて、慌てふためき、思考停止になってはいけません。 ピンチこそは新しい時代を生み出すチャンスだと考えるべきです。 ”日本「再創造」”(2011年6月 東洋経済新報社刊 小宮山 宏著)を読みました。 現在、課題が山積している日本が課題先進国になれば再び大発展できるといいます。 昨年の東日本大震災の際に、すでに本書は脱稿されていたそうです。 小宮山宏さんは、1944年栃木県生まれ、1967年東京大学工学部化学工学科卒業、1972年同大学大学院工学系研究科博士課程修了、1988年東京大学工学部教授、2000年工学部長、大学院工学系研究科長、2003年副学長などを経て、2005年に28代総長に就任し、2009年に総長退任後、三菱総合研究所理事長、東京大学総長顧問に就任しました。 専門は、化学システム工学、地球環境工学、知識の構造化です。 日本は自前のエネルギー・資源は少なく、少子高齢化が急速に進んでいます。 先進国になって久しい日本は、少子高齢化、低い食糧自給率、環境問題、地域間格差などたくさんの難しい問題を抱えています。 社会システムの綻びも随所に目立ち始めましたが、日本が抱える困難に、近い将来、必ずや世界も直面することになると言われます。 悲観論が横溢するのは、正しい情報を手にしていないためです。 冷静かつ客観的に現状を見れば、日本は世界でも稀な恵まれた国です。 日本には、技術と人、そして経済があります。 日本には課題が山積しており、その課題を解決して行けば高質の経験値と価値が創出され、世界の文明の発展に貢献できるはずです。 日本が直面する課題を解決するために、地域ごとに快適なくらしが営まれる社会を実現するプラチナ社会構想と、低炭素社会実現のためのビジョン2050を提案しています。 これからの世界は、目指すべき社会の姿そのものを競う時代に入りますので、そのフロントランナーを目指そうという提案です。 プラチナ社会では、市民が中心となり自治体を場として、産官学の力を結集して各地にそれぞれ市民が欲する社会を実現します。 被災地域に関して、プラチナ社会を創造すべく復興へ向けた活動を開始しているそうです。 また、関東東北地域の電力システムの危機に関して、エネルギー効率の向上によって、エネルギー消費を減らすことを提案しています。 快適さを増し、コストを減らしつつ、エネルギー消費を減らすことが可能だそうです。 そして、非化石資源の増強が必要になっていて、自然エネルギーの導入を加速しなければなりません。序 章 「課題先進国」から「課題解決先進国」へ第1章 「普及型需要」と「創造型需要」―先進国における需要不足の正体第2章 21世紀のパラダイムと情報技術の役割第3章 「有限の地球」を救う「ビジョン2050」第4章 創造型需要にこそ活路あり1―環境で世界市場を切り開く第5章 創造型需要にこそ活路あり2―技術で活力ある高齢社会を実現する第6章 「プラチナ社会」の実現に向けて
2012.10.16
コメント(0)
-
フェルメール全点踏破の旅(感想)
ニューヨーク在住のジャーナリストが、フェルメールの全点踏破の旅をした記録です。 ”フェルメール全点踏破の旅”(2006年9月 集英社刊 朽木 ゆり子著)を読みました。 ”盗まれたフェルメール”の著者だった関係で、ある日突然、集英社の男性誌副編集長から、世界中のフェルメールを全点踏破する企画に興味あるかという連絡が入り、フェルメールの絵37枚を全部連続して見るという旅に出ることになったそうです。 17世紀オランダの画家、ヨハネス・フェルメールは、作品が世界中でわずか30数点という少なさ故に、欧米各都市の美術館に散在するフェルメール全作品を訪ねる旅が成立します。 朽木ゆり子さんは1950年に東京で生まれ、国際基督教大学教養学部社会科学科を卒業し、大学院行政学修士課程修了、コロンビア大学大学院政治学科博士課程に学び、日本版エスクァイア誌副編集長を務めたことがあります。 ヨハネス・フェルメールは、1632年にオランダのデルフトで生まれました。 父親、レイニエル・ヤンスゾーン・フォスは、絹織物職人として活動するかたわら、居酒屋・宿屋を営んでいました。 後に、姓をフォスからファン・デル・メールに変えました。 ヨハネス誕生の前年に、画家中心のギルドである聖ルカ組合に画商として登録されています。 1641年に、現在フェルメールの家として知られる、メーヘレンを購入し転居しました。 ヨハネス・フェルメールは、生涯のほとんどを故郷デルフトで過ごしました。 初め物語画家として出発しましたが、やがて1656年頃から風俗画家へと転向しました。 フェルメールが描いたとされる絵は、現在地球上に37枚しか存在していません。 フェルメールの魔法にかかった人は、その絵を全部見たいという願望に突き動かされるそうです。 これまでアートに興味を持つのは女性が多かったようですが、フェルメールには男性のファンも多く、さらに贋作や盗難、ナチスによる略奪といった側面もあって、ジャーナリスティックな話題としても遜色がありません。 これまで、フェルメールの作品数は32枚から36枚とされてきました。 現在、世界のフェルメール専門家の大部分は、フェルメールの34枚の絵に関しては、本人の筆によるものだと大筋で合意しています。 しかし、”フルートを持つ女””聖女プラクセデス”の2枚に関しては、フェルメールの作品と考えるには無理があるという点で大筋の合意があるようです。 ところが、2004年に37枚目の絵が浮上し、国際的なニュースになりました。 それが、”ヴァージナルの前に座る若い女”です。 フェルメールは、伝統的な意味での宗教的主題を描いていません。 にもかかわらず、彼の絵を見ることで精神的な飢餓感を満たされたように感じます。 その理由を解き明かすことが、彼の絵を全点見て歩く旅の一つの目的だったそうです。 また、個々の作品がなぜ特定の都市の特定の美術館に所蔵されるようになったのかが気になるそうです。 しかし、この旅での全点踏破は叶わなかったとのことです。 フェルメールの絵を所蔵している美術館に行くと、目的の絵が別の美術館に貸し出されていたことがあったためです。 33枚のフェルメールの絵を見る旅を終え、見る事が出来なかったのは”合奏””聖女プラクセデス””手紙を書く女と召使””音楽の稽古”でした。序章 フェルメールの魔法ベルリン/ドレスデン/ブラウンシュバイク/ウィーン/デルフト/アムステルダム/ハーグ/ロッテルダム/ロンドン/ロンドン/パリ/エジンバラ/ワシントン/フィラデルフィア/ニューヨーク終章 深まるフェルメールの謎
2012.10.09
コメント(0)
-
伊藤雅俊の商いのこころ(感想)
日本は今、明治維新、太平洋戦争の敗戦に続く、第三の大きな転換期にあります。 ポスト資本主義という世界共通の問題と本当の資本主義の洗礼を受けていない日本固有の問題とが混在して起きている経済の危機的状況は、いよいよ深刻の度を深めています。 ”伊藤雅俊の商いのこころ”(2003年12月 日本経済新聞社刊 伊藤 雅俊著)を読みました。 日本経済新聞の連載の”私の履歴書”を加筆し単行本化したものです。 わずか2坪の洋品店から出発し一大流通グループに築き、流通産業の勃興期、成長期を生き抜き、幾多の難局を乗り越えてきた生涯を振り返っています。 伊藤雅俊さんが心配なのは、日本人が経済大国の現状に満足し、政府に頼って、何とかなるだろうという頑廃的な空気が強く感じられることだといいます。 これから先の日本経済は生易しいものではなく、恐慌が起こる可能性さえ否定できません。 それなのに、日本人は鈍感で無防備すぎるといいます。 自分の人生を振り返れば、人の世では、考えられないようなことも起こり得ることが分かるそうです。 人間の力ではどうにもならない、運命の力が働いているように思うといいます。 伊藤雅俊さんは、1924年に東京で生まれ、1944年に横浜市立商業専門学校を卒業し、1956年に羊華堂の社長となり、1958年に株式会社ヨーカ堂を設立し、イトーヨーカ堂、セブン-イレブン、デニーズなどイトーヨーカ堂グループの創業者として活躍しました。 株式会社イトーヨーカ堂は関東地方を中心に25都道府県に店舗をもつゼネラルマーチャンダイズストアで、セブン&アイ・ホールディングスの子会社であり中核企業です。 創業は1920年で、現名誉会長・伊藤雅俊さんの母親・伊藤ゆきさんの弟にあたる吉川敏雄さんが東京市浅草区に”羊華堂洋品店”を開業したのが始まりです。 羊華堂が繁盛したため、吉川敏雄さんと14歳の差がある伊藤譲さんが手伝い始め、浅草、千住、荻窪に3店舗あるうちの浅草の一店をのれん分けされました。 伊藤譲さんの弟・伊藤雅俊さんは、学校卒業後、三菱鉱業に就職し、入社後すぐ陸軍特別甲種幹部学校に入校し、陸軍士官を目指したが敗戦を迎え、三菱鉱業に復帰しました。 空襲で焼け出された伊藤ゆきさんと伊藤譲さんは、足立区千住で羊華堂を再開し、1946年に伊藤雅俊さんも三菱鉱業を退社し、羊華堂を手伝うことになりました。 1948年に伊藤譲さんが合資会社羊華堂を設立して法人化し、1956年に気管支喘息の持病を患っていた伊藤譲社長が死去し、伊藤雅俊さんが経営を引き継ぎました。 伊藤雅俊さんは、創業のこころを忘れないといいます。 創業は業を創るということで、無から有を生み出すようなところがあり、「お客様は来てくださらない」「お取引先は売ってくださらない」「銀行は貸してくださらない」という、ないもの尽くしの状態からの出発だったそうです。 あるのは、お客様に誠心誠意を尽くそう、お取引先に決してご迷惑をかけまい、借りたお金は約束通り必ず返そうという、真摯な気持ちだけだったそうです。 その創業のこころを忘れずに、努力を積み重ねることで、何物にも替え難い信用が生まれ、どうにか食べていけるのだといことです。 創業から時間がたって商売が大きくなり、信用が独り歩きしてありがたさを忘れ、多くの方々に支えられて商売が成り立っているのだということに思いが至らなくなった時から、衰退がはじまるといいます。 自分の力を過信し、倣慢さに気付かなくなった時が危機のはじまりです。 中央からは革新が生まれにくいように、大企業からも革新は生まれにくいという問題があります。 企業規模が大きくなればなるほど、社員が会社は潰れないと思うようになり、ハングリー精神が希薄になって挑戦の気概が薄れるからです。 革新は辺境、苦境から生まれるのは確かですが、革新を続けられるかどうかは別の問題だということです。1お蔭さまです―私の履歴書 商人道の基本は誠実さ/つながりが薄かった父/母ゆき/異父兄/兄の勧めで進学決定/繰り上げ卒業/千住・羊華堂/結婚/継承問題/海外視察/スーパー勃興期/借金嫌い/非合併路線/労働組合/株式上場/石油危機、需給変動の恐ろしさ/大店法/セブンイレブン/チェーン協会長/本物の資本主義/荒天に準備せよ/アメリカの本家を支援/社長辞任/トップ交代/変化対応業/育英財団/家業と企業/金婚式2忘れ得ぬ人々 鯨岡兵輔さん/渋井賢太郎さん/関口寛快さん/西脇秀夫さんと三井銀行の方々/小山五郎さん/野村證券の方々/北裏喜一郎さん/前川春雄さん/岡田卓也さん/西川俊男さん、中原功さん/西端行雄さん/安田栄司さん、和田源三郎さん/大高善雄さん、渡辺喜一郎さん/田島義博先生/渥美俊一さん/滝田実さん/田中角栄さん、渡辺美智雄さん/住本保吉さん/中島董一郎さん、藤田近男さん/丸田芳郎さん/飯田亮さん/高橋高見さん/五島昇さん/盛田昭夫さん/松下幸之助さん/高橋荒太郎さん/藤沢武夫さん/平野繁太郎さん/S・M・ウォルトンさん/J・P・トンプソンさん/G・W・ジェンキンスさん、D・R・ウェグマンさん/P・A・F・ギフォードさん、L・エアリさん/J・L・ワインバーグさん、J・C・ホワイトヘッドさん/D・H・コマンスキーさん/M・カプランさん、M・ガーストさん/P・F・ドラッカー先生3伊藤雅俊・商売の要諦 「資本より元手」「まず、お客様ありき」「漬物石としての存在」「浮気せず本業専念」「商業の極意は自由であること」「質がよければ、安く借りられる」「基本の徹底と変化への対応」「荒天に準備せよ」「創業のこころを忘れず」「革新は辺境から生まれる」
2012.10.02
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- カルディで見つけたら是非☺️十割そば…
- (2025-11-17 10:31:25)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- クマ対策の最新の情報‼️⚠️
- (2025-11-17 16:09:48)
-
-
-
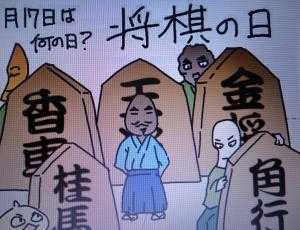
- たわごと
- 家の解体て早いものだね( ^ω^)…
- (2025-11-17 10:32:38)
-







