2008年11月の記事
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-

俗な日本語
おととい、10/27の課題が返ってきました!時間がなかったのでとりあえず赤で書いてあるところを見直したら、とんでもないところが見つかりました「全体に口語をそのまま持ちこんでいるところがあります」という注意が途中にあり、「うーん、そうかも」と思っていたら・・・。最後の最後に、とんでもない日本語が思わず笑ってしまいました。「医薬文献に、こんな日本語ないでしょー!!!」笑っている場合ではないのですが、つい。1ヵ月前、わたしは何を考えていたんだろう「この日本語はおかしい」という判断もできないくらいに、文体というものを認識していなかったのかな?(たしかに、文体の勉強を始めたのは11月に入ってからですが)今、そんな日本語をおかしいと思うということは、1ヵ月前に比べるとものすごく成長しているのかな?そんなかんじはしないけど・・・訳をしているときって、ずっと机に向かって同じことを考えているから、視野がすごく狭くなっている気がします。それもとんでもない日本語を書いた原因のひとつかもしれません。応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 30, 2008
コメント(0)
-

「typically」の謎が解けた!!・・・かも
トライアリストの課題を訳していて、昨日も今日も「typically」が出てきました。うわ、やなやつが出てきたわたしはもうずっと前から「typically」が苦手です。どういう日本語にしたらいいのか、わかったことが一度もないから。「typically」を辞書で引くと、 ・典型的に ・一般的に ・通常は といった訳語が書いてあります。 (「例によって」「概して」というのも書いてありますが、 そのことばを使うにはあまりにも場違いな英文にしか 出会ったことがないので、ここでは無視します)3つあるけど、どれもしっくりこない。まず「典型的に」。これは副詞なので、形容子または動子を修飾することばです。でも、このことばは名子しか修飾できないと思うのです。「典型的」というのは、なにか誰もが納得するような「型」があって、まるでそれみたいだ、という意味で使われることばだと思います。したがって、「典型的」のあとにくることばは意味の上では「型」と同じく名子でなければならない。だから、「典型的に」として後に形容子や動子をもってくるのはおかしいと思うのです(ただし受身ならOK)。例を挙げると、 ・二人は典型的に議論している ・あのゲームは典型的におもしろいとは言わないですよね。後に名子がくる「典型的な」なら、いくらでもあり得ます。 ・二人は典型的な議論をしている ・あのゲームのおもしろさは典型的だ (名子と典型的の位置が入れ替わっていますが、よしとします)この「典型的な」という訳語、 「typical」が「典型的な」だから、じゃあ 「typically」は「典型的に」でいいや。というかんじでてきとーに作られたものじゃないのかな、と思いました。(辞書に載っているマイナーな副詞って、そういう訳語多いですよね)そして「一般的に」「通常は」。この2つも、あまり使いたくないと思っていました。今日までは。なぜかというと、「一般的に」「通常は」なんて言ったって、書いた人にとっての「一般」「通常」と読む人にとってのそれとが一致しないと使えない。しかも、一致することなんて滅多にない、と思っていたから。そもそも「一般」「通常」ということばを使うときには、その対象が属する母集団がはっきりしていること、その母集団がある一定の概念を共有していることが必要だと思います。その基盤があってこそ、「一般」「通常」がどういうものか、そのことばを見た(読んだ)だけで理解できるのです。そこまで考えて、はっと気づきました。医薬翻訳では、書いた人と読む人は同じ母集団に属すると考えていいのではないか。どちらもその文章のテーマに関する専門家なのだから。わたしは「書いた人」を自分にすり替えていたのだろうと思います。だから、自分がよく知らない分野で「一般」ということばを使えなかった。でも、わたしはただの翻訳者なのだから、わたしがその「一般」の内容を理解する必要はありませんよね。わたしの役目は内容を理解することではなく、英文の内容を過不足のない日本語にすること。(その過程で理解が必要になるときも少なからずあるのでしょうけれど)「英文を書いた人の立場から訳文を構成する」わかっているつもりでしたが、まだまだ理解が浅かったようです。長年(といっても、数年かな)悩みの種だった「typically」から、いい勉強をさせてもらいました。ありがとう~最後に一言~今日書いた内容は、お風呂に入りながらぼーっと考えたものなのであちこちボロがあるかもしれません。ボロを見つけた方、指摘していただけるとうれしいです☆応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 27, 2008
コメント(3)
-

メディカプラス2000
メディカプラス2000を買うことにしました!!トライアリストが作製した、複数の辞書から用語を拾った医薬専門辞書。買いたいな、でもどんなものかわからないのに買うのも不安だな、と思っていたところにトライアリストのミニ全国大会が開催され、先輩に実物を見せてもらいました。見せてもらって、「これは必需品だ!!」と思いました。あらゆる(と言っては語弊がありますが、それに近いと思う)専門用語とその訳語が載っていて、訳語の信頼度もある程度わかるようになっている。でも、高い。買いたい。だから買う。そんな簡単な値段ではない。でも、どうしても欲しいし、必要だ。ダメと言われるかも。ダメとは言わなくても、嫌な顔をされるかも。そう思いながら、夫にお願いしました。「誕生日プレゼントもクリスマスプレゼントもいらないからメディカプラス2000を買わせて!!」(来週誕生日なので)すると、拍子抜けするくらいすんなりとOKしてくれました。もちろん、どうでもいいからすんなりOKしてくれたわけではなく、わたしの気持ちを汲み取ってくれてのこと。とてもうれしかったですほんとにほんとに、ありがとう。十二分に役立ててみせるからね。応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 26, 2008
コメント(2)
-

医薬の文体の身につけ方
先週の中ごろから、医学雑誌を読み始めました。今取り組んでいる課題の内容に近いものの方が動子や形容子の使い方のお手本が載っているだろうと思い、「医学のあゆみ 大動脈瘤―基礎と臨床」を購入。少しずつ読み進めているのですが、やっぱり効率よく文体を身につけることは難しそうだな、と感じています。先生のおっしゃるように、内容は気にしないで文体だけに注意して読んでみると・・・。名子+動子、形容子+動子、様子+動子など、見慣れないものがけっこう目につきます。それに印をつけて、ワードにメモって・・・、という作業をやっていたのですが、ふと思ったんです。これじゃあ、「文体」は身につかないのでは??文体というからには、その分野の文章固有の雰囲気、リズムなどがあるのではないかと思うのです。わたしは文体を見ずにことばだけを見ていたのではないかと思いました。その証拠に、2つほど記事を読んだのですが、内容はまったく頭に入っていません。何に関する記事だったのかさえそれならと、文章の表面だけを見ずに、文章のリズムがわかるように内容も見ながら読んでみました。ふんふん。これなら、リズムや雰囲気もいつの間にか身につきそう。「あれなに?」「これなに?」といちいち立ち止まってしまう癖さえ克服できれば、カンペキかもしばらくはこの方法でやってみようと思います応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 25, 2008
コメント(4)
-
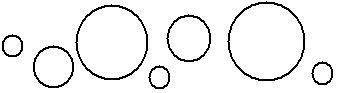
トライアリスト ミニ全国大会 ~意味領域~
明日は書きません、と言っておきながら、何日も記事をお休みしてしまいました。すみません11/20~昨日までは、飲み会だったり、わけもなくものすごく落ち込んでいたり、風邪をひいたりでほとんど勉強していませんでした・・・。やはり睡眠時間が短すぎるのかもしれません。夫から「疲れてるんじゃない?」と言われたし。自覚はないのですが。この数日間、ひとつだけ自分を褒めてあげたいことがあります。それは、文体の勉強だけは一日も欠かさなかったこと!(数分、という日もあったけど)落ち込みそうなときこそ、褒めてあげないとね。自画自賛でもさ。さて本題の「意味領域」。全国大会でショックを受けたのは、「意味領域を認識している人が少ない」ということ。先生が何度も何度も一生懸命説明なさっていて、「こんな当たり前のこと、どうしてそんなに説明するんだろう」そう思っていました(関連記事はこちら)でも、よく見ると一生懸命聞いている人が多数・・・。その様子から判断するに、みんな意味領域を実感として理解していないらしいのです。ものすごくびっくりしましたどうやって英語を読んでいるのそう思いました。お隣に座っていた先輩にそのことを訊くと、「ひとつひとつの単語に自分の知っている訳語をひとつひとつ当てはめて読んでいる」とのことでした。なんて気の遠くなるような作業でしょう。英文を読むのが、ものすごく大変じゃないですか。わたしが意味領域に気づいたのは、中2か中3のとき。塾に通うようになり、課題の多い塾だったので毎日たくさんの英文を読んでいました。するとある日、いちいち日本語を考えなくても英文の意味を読めるようになっていることに気づいたんです。英文をたくさん読むとそうなる、と話に聞いていたので、「これかー!!」とうれしくなりました。たぶんその頃、意味領域に気づいたのだと思います。英文を読むとき、辞書をひきますよね。同じ単語でも、ぴったりな訳語がなかなか見つからなくて辞書を隅から隅まで読んだりしていました。それを繰り返しているうちに、あるとき気づいたんです。「訳語はたくさん載っているけど、根元はひとつにつながってるな」と。それからは、情報量の少ない単語ほど訳語を当てにするのをやめました。(その頃は情報量なんていう認識はありませんでしたが)英文を読んでわからない単語にぶつかり、それが「たくさん意味がありそうな単語だ」と思うと、辞書に載っている訳語・例文すべてにざっと目を通し、いったん訳語はすべて忘れて、その単語の概念をつかんでから英文を読む。類義語が好きで、類義語の欄ばかり拾い読みしたり。高校の頃は「辞書は何回でもひけ。隅々まで読め」という先生のことばをそのまま実行したり。本当の意味をあらわす辞書を作ろうとしたり。(意味全体をことばで言い表すことができず、作ることはできなかったのですが)そういうことがいろいろな単語の「意味領域」を身につけることに役立ったのかな、と思います。そして、今の英文の読み方。「英文 → 英文の表す概念」というかんじです。訳すときは「→ 日本語」が続きます。わたしにとって、英文は各単語の概念の玉のつながりです。その概念の玉は三次元で、ぽよぽよしていて、きちっとした一定のかたちを持っているものではありません。どんなふうに英文を読んでいるかというと、1.こんなかんじで英文があって、 (○は各単語の意味領域)2.場やまわりの単語と影響しあって、3.意味領域が互いにつながって、小さくなっていって (=情報量は大きくなって)4.最後には文の示す意味にたどりつくというかんじ。日本語は一切介在させません。意味の取りづらい文は特に。意味の取りづらい文のときは、2のときに意味領域をいろいろひっくり返し、文意に沿うところを見つけ出していきます。今、課題を訳すときに一番困っているのは ・文体 ・文意にあう日本語を見つけられないことこの2つ。課題の英文は、流し読みだと1ページ5~10分程度で読むことができます。専門用語の数にもよりますが。でも、課題を訳すとなると、1パラグラフに数時間・・・。今のところ、この2つを解決する方法は文体を身につけることなのかな、と思っています。応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 24, 2008
コメント(0)
-

トライアリスト ミニ全国大会 ~冠詞~
昨日は勉強しようと机に向かったものの、集中できないまま気づいたら机で爆睡していました~月曜日、全国大会に触発されていつもより遅くまで勉強したのがいけなかったようです。ペースを守ることは大切ですね全国大会では、冠詞の役割がわかったことが一番の収穫でした「a」「the」の使い方がよくわからず、中学・高校で何人かの先生に質問したのですが、明確な答えは返ってきませんでした。そのため、今までわたしは冠詞を無視して英語を読んでいたのです。「a」は文章に初めて出てくる単語、「the」は出てきた単語、無冠詞複数は一般的な単語、というくらいの認識で。全国大会では、先生が文章の中から文を選び、その文で冠詞がどのような役割を演じているのかについて説明してくれました。名子の強弱を判断し、それに基づいて「が」「は」の使い分けや訳文の語順を決める。トライアリスト入会時にいただいた資料に詳しい説明が載っていたのですが、やはり先生に直接説明していただくと理解の深さが全然違いました。なんとなく、という程度だったのが、冠詞についてかなり明確なイメージを持つことができるようになりました。課題を訳すときも、先週と今週では文を読んだときに浮かびあがってくるイメージが違います。大げさに言うと、ぼんやりとしか見えていなかった文がくっきりと浮かびあがってくるかんじ。先生いわく「冠詞がわかっていないと、文の意味の三分の二程度しか読み取れない」とのこと。早く冠詞を自分のものにして、文をしっかり読み解くことができるようになりたいです!!ほかにもうれしいことがありましたわたしが「は」の使い方をよくわかっていない、ということを察してくれた先輩がお勧めの本を教えてくださいました!「日本語に主語はいらない」(金谷 武洋 著)という本です。さっそく月曜日に買ってきて、通勤電車で読んでいますまださわりの部分くらいしか読めていないのですが、とてもおもしろそうな内容です。医学雑誌も買いました。今の読書量ではいつまでたっても文体が身につかないので。月曜にネットで買ったので、届くのは明日くらいかな。全国大会では、ショックなこともありました。それは意味領域のこと。このことについては、また別の記事で書こうと思います。(明日は飲み会なので、記事はたぶん書きません)応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 19, 2008
コメント(3)
-

トライアリスト ミニ全国大会 2日目
2日目、参加しようか迷っていましたが、参加してよかったです!内容は ・冠詞について ・意味領域について ・実務翻訳経営学 ~「自分を売り込むコツ」など~ 現在翻訳者としてご活躍なさっている先輩の 体験談も聞かせていただきました!! ・情報子辞典についてなど。(内容は別の記事で書きます)2日間全国大会に出席して感じたことは、会員の方々の熱意がとても強いこと。自分で辞書を作ったり、ことばとことばの結びつきのリストを作ったり(日本語版も英語版も)、医学雑誌を読んだり。一人でやることの短所が見えてしまったりして最近ちょっとエネルギーが下降気味だったのですが、それを補って余りあるほどのパワーをもらいました!夜はまた先生や先輩方とお茶→居酒屋に行き、たくさんおしゃべりしてきました。昼も夜もとても楽しくて、充電完了!!というかんじです。おかげで今日は、いつもよりも数倍元気に仕事に向かうことができましたでも、先生、連れまわしてしまってごめんなさい!この場を借りてお詫び申し上げます。そして、遅い時間まで付き合っていただいてありがとうございました。とても楽しかったです応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 16, 2008
コメント(0)
-

トライアリスト ミニ全国大会
今日は、トライアリストのミニ全国大会に出席してきました!全国大会とは、毎年おこなわれている勉強会のようなもので、先生やほかの会員の方と直接お話できるとても貴重な機会でした。今日の内容は、 ・翻訳にかぎらず何かを学習するときの学習段階について ・メモリーと容量について ・意味(領域)について ・冠詞(a, the)、複数形についてなど。(内容については別の記事で書きます)講座は先生一人が話すのではなく、会員も参加して議論を展開するかたちで進んでいきました。和気あいあいとしていて、先生もとても話しやすい方で、楽しく講座を受けることができましたとくに、先生の声がすてきでした穏やかで優しい、落ち着いた話し方をなさっていて、声を聞けただけでも満足☆というかんじ(笑)本人いわく「賛否両論の声」とのことでしたが、わたしは好きです講座が終わってからはルーマニア料理を食べに行って、たくさんおしゃべりをしてきました~先生のおもしろいおはなしや先輩方の経験談、翻訳についてのおはなしなど、いろいろなことを話しました。ブログのあの山の向こうにあかね雲を書いていらっしゃる朝露さんと会うこともでき、とても充実した時間を過ごすことができました先生は話をするときにいつもおちを考えていらっしゃるらしく、さすが関西人だな~、と思いました。明日はちょっと予定があって講座には参加しないつもりでしたが、やっぱり参加しようと思いますデザートのパパナッシュです。シュークリームの皮のようなもの(あったかい!!)に甘いソースがかかっていて、とてもおいしかったです応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 15, 2008
コメント(8)
-

人を動かす
今、この本を読んでいます。「人を動かす」デール・カーネギー 著 山口 博 訳創元社どの仕事にも当てはまることだと思うのですが、仕事ではこちらの希望通りに人に動いてもらうことが必要です。相手が嫌がりそうなことをお願いしなければならないときもあるし、周りの都合を考えずに突っ走ってしまう人を相手にしなければいけないこともあります。今の仕事で役立ちそうだと思って読み始めたのですが、将来翻訳の仕事を始めてからも充分に役立ちそうなので紹介します。10月末~11月はじめにかけて、仕事でとても大変なことがありました。複数の部署に迷惑をかけて、ドタバタして、調整して、それだけで一日が終ってしまうような日が続いたのです。でも、トラブルの原因に「これ」というものはありませんでした。わたしにも他部署にも、それぞれに悪いところはありました。でも、そのどれもが決定的なものではなかったのです。それぞれが相手を思いやって対応していれば、もっともっと小さなトラブルで済んでいたはずのことでした。(勝手に突っ走る人がいたことが原因といえば原因かもしれません。しかも主な関係者4人中2人。)結局、一番多くを受け持ったわたしに責任があるようなかたちで終わりそうなのが不満です(愚痴です、ごめんなさい)トラブルも収まってきて、ある程度落ち着いて眺められるようになったとき、「わたしがもっとうまく人を動かせていれば、こんな事態にはならなかったのかもしれない」と思いました。勝手に突っ走らせず、わたしの言い分を理解してもらえていたら。ちょうどその頃、夫がこの本を知人から借りていました。そしてわたしの話を聞いて、是非読むようにと強く勧めてくれました。読んでみると、わたしが求めていたものにぴったりの内容でした。どうやったらこちらの希望通りに相手に動いてもらえるのか。一言で言うと、その方法は「相手の身になって考える」です。私の解釈ですが。なんだ、そんなこと、と思いますよね。でも、読んでみるとなかなか奥が深いのです。これまでぼんやりとしかわかっていなかったこと、人とうまく付き合うための手段として考えてもいなかったようなことがわかりやすく、明確に書かれています。苦手だな、と思っていた相手ほど、これまでと180度違う対応をしてみよう!と思うようになりました。(うまく説明できる自信がないので、内容の詳しい説明は書きません)今日、実際にちょっとやってみたら、けっこう調子がよかったです翻訳では、人脈や交渉が大事だということをよく聞きます。翻訳家として仕事をするとき、この本が大いに役立ってくれるだろうと期待しています明日は、初めてのトライアリストのミニ全国大会です!昨日あたりから、もうわくわくが止まりません。まるで遠足前の子供みたいです(笑)ルーマニア料理も食べに行くみたいだし、楽しみです応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 14, 2008
コメント(0)
-

ことばとことばの結びつき
トライアリストの入会時にもらった冊子などでは、「ことばとことばの結びつき」の大切さについて繰り返し述べられています。そのデータを集め、いつでも見られるようにしておかなければならない、とも書かれています。なので、データを集めることにしました初めて「ことばとことばの結びつき」について読んだのは10月なのですが。スタート、遅いです(^^;なぜ1ヵ月もかかったのかというと、平たく言えばめんどくさかったから・・・。「ことばとことばの結びつき」の考え方自体は、翻訳の勉強を始める前から持っていました。日記など、なにか文章を書くときに「あれ、このことばにつながる動子(形容子)って、これだっけ?」「そういうのが載っている辞書があればなぁ」とたまに思っていたのです。でも、「ま、いっか」とそのまま済ませていました。翻訳の勉強を始めてから(トライアリストに入会する前)は調べる頻度は増えたのですが、たいして変わらず。トライアリストに入会してからは、その大切さに気づくことはできたのですが、「一流になればできるようになるはず。だって一流なんだもん」という、わけのわからないことを考えていました。本当は、データを集めなくてはならない、ということはわかっていたんです。でも、その気持ちをなかば無意識に押さえつけていたのです。「動子も名子も無限にあるのに、それをデータとしてとっておくなんて。気が遠くなる」このめんどくささが先にたってしまって。でも、何度も「ことばとことばの結びつき」について読んでいくうちに「やらなくちゃ」という気持ちを抑えられなくなりました。そしていつの間にか、「どうして一流の人はできるのか」について考えていました。その答えは、「それが身についているから」。では、どうして身についているのか?経験があるから。身につけようと努力しているから。それなら、わたしも努力しなくては。「ことばとことばの結びつき」がわからない、ということを何度も経験しているのだから。経験で身につけるより、データを集めたほうが何倍も早く身につくし、あとあと役に立つのだから。そう思って、先週くらいからやっとデータを集めはじめました。とりあえず、課題文の訳例と「医薬の文体を学ぶ本」からです。トライアリストが薦めるこういうことを新しく始めるたびに、「どうしてすぐに始めないんだろう」と思います。「師匠の言うことに不満があっても疑問があっても、間違いだと思ったとしても、最初は無条件にそれを真似ること」これが大切だと、いろんなところに書いてあります。わたしは、これが苦手みたいです。翻訳のときだけではなく。理解して納得してからでないと始めないことが多いのです。無条件に真似るということの重要性は理解しているのに。不思議なことに、スポーツではそれがありません。無条件に真似ます。たぶん、「できない」ということをわかっているからでしょう。そして翻訳でそれができないのは、おそらく多少なりともプライドがあるからなのでしょう。プライドほど邪魔なものはない。人と接するときも、仕事をするときも、なにか新しいことを始めるときも、いつもそう思います。気をつけていてもなかなかひっこんでくれません。もちろん、プライドは大切です。でも、ありすぎると邪魔ですね。応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 13, 2008
コメント(2)
-

映像翻訳で不思議なこと
映画を借りてきて家で観るとき、いつも字幕で観ています。するとたまに、どうしてこの訳にしたんだろう、というところがあります。映像翻訳ですから、セリフが入る時間やタイミングに気をつけて翻訳しなければいけないことはわかります。でも、ほかの言い方のほうがよかったのでは?と思うことがあるんです。今日観た映画では英語で「20分で行く」と言っていたところを字幕で「すぐ行くわ」と言っていました。どうして「20分」を「すぐ」にしたんだろう。「20分で行くわ」が長すぎるなら、「20分後に」にでもすればよかったのに。登場人物のキャラクターや場面の雰囲気を考えると「すぐ行くわ」が最適だったのかな?不思議です。映像翻訳だからこそ、の理由がなにかあるのでしょうね。いつか理由を知りたいものです。~おまけ~字幕で映画を観ていると、英語でなんて言っているかけっこうよくわかるんですよね。でも、字幕なしだとほとんど英語を聞き取れません。(ひとつの映画で両方試してみました)不思議です。頭の中で、日本語を英語に変換する作業と英語を聞く作業を同時におこなっているんでしょうね。人間の脳ってすごいんだな~!と感心してしまいます。応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 11, 2008
コメント(0)
-

遅れた課題
この前の帰省で課題の提出が遅れていたのですが、やっとその遅れを取り戻すことができそうです。11/10分の課題を今日訳し終えました!訳をざっとチェックしたとき、添削されていた「受け身が多すぎる」という点に気をつけて、自分が医師になったつもりで文章を読んでみたのですが、なかなかうまくいきませんでした。強い名子と弱い名子の区別が難しいところもあったし。考えようとしたのですが、眠くて頭が働いてくれません本当は今日仕上げてしまいたかったけど、今日はちょっと早めに寝ることにします。明日、すっきりした頭で最終確認ですおやすみなさい応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 10, 2008
コメント(0)
-

訳すときに気をつけること
最近、課題を訳すときに意識的に気をつけていることがあります。 1. 知らない専門用語があっても、必要以上に調べない (どういう形容子、動子と結びつくのかがわかる 程度に調べる) 2. 情報子を把握してから訳す 3. 「が」と「は」の使い分け 4. 語順(とくに形容子、景子)1.は、文体を身につけることを最優先にしたいからです。翻訳するのに必要のない知識を身につけることに時間を割くより、その時間を文体の勉強に充てたいと思います。2, 3, 4は、情報量理論に基づいた訳し方を身につけたいからです。初めての課題のときに2をやってみたのですが、情報子がどういうものか、それを翻訳にどう利用するのか、いまいちわかっていなかったようです。どの文も「N+V+N」になってしまうし、それがわかることが翻訳にどう役立つのかもわからないしで、情報子を把握することをやめてしまいました。最近はそのときに比べれば情報子のこともわかってきたので、もう一度情報子を把握してから訳す、という手順を踏むようにしてみました。すると、今までは「なんとなく」で決めていた語順をしっかり根拠に基づいて決められるときもあり、とても訳しやすかったです。辻谷先生がおっしゃっているように、様子と景子の区別は難しかったです。一番の原因はまだわたしが様子、景子の定義をきちんと理解していないことにあると思いますが。難しいなー、と思うことばかりですが、10月にできなかったことを今月は少しだけでもできるようになって、ちょっと成長した気分です応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 9, 2008
コメント(0)
-

医薬の文体-2
今日はさっそく、「医薬の文体を学ぶ本」で勉強してみました。「はじめに」にを読んで、どきっとしました。同じ翻訳者でもそのときの気分、体調などによって目に見えて文体が変化することがあるこれ、わたしに当てはまります・・・。私の場合は、文体だけでなく字体まで変わります。もちろん仕事のときには気分で文体が変わらないように気をつけています。漢字で書くかひらがなで書くか、自分なりの基準をもっていることばもあるし、名子に前からかかる形容子が多くなりすぎないように気をつけているし、同じかたちの文末(である、など)が続かないようにしています。ほかにも気をつけているところはあると思いますが、今は思いつきません。でも、こうやって気をつけていても、書いているときに文体が変わっているかどうか自分で気づくことは難しそうです。いろいろな時期に書いた自分の書いた文章をいくつか、まとめて読んでみれば、気づくことができるのかもしれません。「はじめに」を読むだけでなく「医薬の文体を学ぶ本」に載っている文章を書き写すこともやってみました。ことばそのものや言い回しなど、「こんな言い方をするのか」と思うところがいくつもあっておもしろかったですただ、問題なのは書き写すという作業に集中してしまって文体に注意を払わなくなってしまうこと。これじゃあ、せっかく書き写しているのに効果が半減してしまいますよね。内容に気をとられすぎず、かつ書き写すことだけに集中することなく、文体そのものを学びながら書き写していくのは思っていたよりも難しい作業になりそうです。応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 8, 2008
コメント(0)
-
世界で一番きれいな人
今日は会社の同期の結婚式でした。そして明日も結婚式。今年は6件も結婚式があって、まさにラッシュです結婚式のたびに思い出すのが、大学生のときにバイト先で聞いたことば。バイトではホテルの宴会場のウェイトレスをしていて、結婚披露宴がとても多かったんです。何年も宴会場で働いている黒服の人(新郎新婦の先導をしたりする、披露宴スタッフの中で一番偉い人)が、あるときこんなことを言いました。披露宴のとき、一番きれいなのは花嫁さんなんだよ。どんな花嫁でも、会場の誰よりもきれいなんだ。どうしてだと思う?それはね、顔が幸せに光輝いているからだ。聞いたときは、ふーん、そんなものなんだなぁ、としか思わなかったのですが、友人の結婚式・披露宴に出席するたびに、そのことばは正しかったと実感しています。どの花嫁さんも、とてもきれいわたしも、自分の結婚式のとき、こう思ったのを覚えています。今、世界中どこを探しても、わたしより幸せな人は絶対にいない。同じくらい幸せな人はいるかもしれないけど。結婚式・披露宴に出席するたび、幸せのおすそわけをいただいているようで、とても満ち足りた気分になります。幸せの瞬間に立ち会うって、とてもうれしいことですね
November 8, 2008
コメント(0)
-

医薬の文体
今日は11/3分の課題を仕上げ、昨日返ってきた10/6分の課題の見直しをしました。見直しで一番目についたのは、訳例の文体でした。わたしの訳と、全然違う。これが文体ってものなのか。「文体を身につけられなければ、医薬分野の翻訳はできない」ということばの意味を実感しました。今日読み返していた「翻訳者のための日本語講座」に知識よりも文体を学ぶことを優先するように書いてありました。知識があると、内容を理解できるがために内容を自分のことばに変換してしまい、文体が身につかないのだとか。ためしに、文体を身につける作業をやってみようと10/6分の課題の訳例を音読してみました。でも、なかなか文体だけに集中できませんでした。内容が理解できるから、読みながら内容について考えてしまうのです。知識が文体の習得を妨げている。1ヵ月かかって、やっと「翻訳者のための日本語講座」に書いてあったことを理解することができました。本を読まなくても課題を訳しているだけで、知識は身につく。ということは、翻訳の勉強をしている=どんどん文体を身につけにくくなっている、ということですよね。この1ヵ月、知識と文体とどっちを優先するかずっと迷っていました。今後は文体を学ぶことを最優先事項にしようと思います。この1ヵ月ちょっと、文体は身につけないまま知識を身につけて、かなりもったいないことをしてしまいましたもう1ヵ月。でも、まだ1ヵ月。勉強は何年も続くのだから、1ヵ月で気づくことができてよかったと思うことにします応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 7, 2008
コメント(0)
-

1回目の課題 添削結果
1回目の課題が返ってきました!!郵便受けを開けるとトライアリストからの封筒が入っていました。真っ赤な紙面を見てもショックを受けないように心の準備をしてから開けようかと思ったのですが待ちきれず、家についてすぐに封を切りました。開けてみて、びっくりしました。わたしの予想以上に訳文の隅々までしっかり添削されていて、こんなにしっかり見てもらえるのかとうれしくなりましたそして内容。わたしなりに一生懸命考えた訳文をたくさん直されていればかなりショックを受けるだろうと思っていたのですが、意外と平気でした。ショックを受けなかったわけではないのですが、自分の訳のどこがどう悪かったのか、どう訳せばよかったのか、そういうことを見ていくのがとてもおもしろくて、ショックなんてどこかに飛んでいってしまいました。一つ一つの添削内容を見ていくと、わたしにも文章の書き方の癖のようなものがあるのだということがわかりました。ことばの選び方や語順のほか、一番目立ったのは文章を受け身で書いているということ。この癖がついたのは、学生のときだと思います。研究室のゼミは自分で論文を選び、その内容を紹介するという形式でおこなわれていて、その論文の訳をレジメとして使っていました。そのため、1年に6本くらい論文を訳していたのです。そのとき、ずっと受け身で文章を書いていました。わたしだけでなく先輩も同期も、みんなそういう文章を書いていたのでそういうものだと思っていました。でも、修士論文を書くときには受け身を使わないように指導されたような覚えがあります。たしかに、自分がやったことを文章にまとめるのだから受け身は変だよなー、と思った気がします。それを考えると、ほかの人が書いた論文も受け身で訳すのは変ですよね。そんなことにも気づかないなんて。癖ってこわいです。次の課題からは、自分が書き手になったつもりで文章を書いていこうと思います応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 6, 2008
コメント(2)
-

一人でやる、ということ
昨日は、なんと帰ってきたのが夜の12時でした忙しいのは先週まで、と思っていたけど、全然そんなことなかったです。祖母の危篤や最近の仕事の忙しさから、翻訳の仕事って大変だな、と思うことが三つあります。一つめは、翻訳の仕事では祖母の危篤といえども、請け負った仕事を断ることはできないということ。会社という組織に勤めている限り、そういう時はほかの人が代わりに仕事をしてくれます。でも翻訳だとそうはいきませんよね。自分が仕事をしないと、それを発注したお客さんが即困るのですから。二つめは、つらいことや悔しいことがあっても、それを話せる人がいないということ。会社には一緒に働いている同僚がいるので、なにかあってもその日のうちに話を聞いてもらったりなぐさめてもらったりすることができます。でも翻訳だと、そういう気持ちを自分一人で処理しなければなりません。三つめは、なにか間違ったこと、間違ってはいないにしてもよくないことをしているとき、それを注意してくれる人がいないということ。私の会社の研究開発職はチーム制ではありません。一人で複数の商品を担当し、開発していきます。それでも、先輩や上司がわたしの仕事ぶりをちゃんと見ていてくれて、陰日向からフォローし、教え導いてくれます。でも翻訳だと、一人です。もちろん基本的にはそうだろう、というだけで、どうしても都合がつかないときには翻訳会社が代わりの翻訳者を探してくれたり、つらいときには夫や友人が話を聞いてくれたり、間違ったときには心ある人が指摘してくれたりするでしょう。でも、会社勤めをしているときと比べれば、その回数は圧倒的に翻訳者のほうが少ないと思うのです。「好きなだけでは翻訳の仕事はできない」という理由は、「好きだから」というきっかけの気持ちと「翻訳の仕事」に必要とされる気持ちの強さに大きな開きがあるからだと考えてきました。今日書いたようなことも、その理由の一つになるのかな、と思いました。応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 5, 2008
コメント(6)
-

心臓について、勉強中・・・
今日は一日、買ってきた本やネットで心臓について勉強していました。心臓の発生や、心電図や、心エコーや、X線・・・。あわよくば課題にも手をつけたいな、と思っていたけれど、手が届きませんでした~本の内容も、専門用語が多くて本だけでは理解するのが大変でした。辞書をひいたりネットで検索したりと、いろいろなものを使って調べました。ネットでは、医大の講義資料とか、病院のレジデント用の資料とかを見つけることができて、かなり勉強になりました。講義資料なら信頼性も高いと思うし、いいものを見つけた、というかんじです。でも、授業料を払ってない人に見られちゃっていいのかな??勉強していて、1つ心配になったことがあります。それは「こんなに細かく、しっかり勉強するべきなのかどうか」ということ。わたしはどちらかというと完璧主義なほうで、「やるならしっかり」というタイプです。今日勉強した心臓についてもそうです。翻訳という仕事をするかぎり、手に入れられる知識はすべて手に入れたいと思うし、そうするべきだと思っています。それに今後のことを考えると、今回の課題の範囲だけでなく少しでも多くの知識を手に入れたいと思います。どうせやるなら基礎・応用と順を追って勉強したいし、基礎知識はいちいち調べなくてもわかるくらいに身につけたい。でも、今はそういう勉強の仕方をする時期ではないのかもしれない、とも思うのです。今は時間の制約がある。限られた時間のなかで ・課題の内容についての勉強 ・課題そのもの ・医薬分野の文体の勉強 ・日本語を磨くこと ・その他いろいろこのようにいくつもの勉強をしなければならない。そういう状況で、1つの勉強にどこまで時間を割くのか。どういうふうに優先順位をつけ、時間配分を決めるのか。こうやって考えると、やっぱり知識を身につけることだけに大きな時間を割くことはできないですね。適切なところで手を打ちたいと思います。適切なところ、というのがまた、難しいのですが。それに、じゃあいつしっかり勉強するのか、という疑問もわいてくるのですが。それとも、本や辞書があれば、知識を身につける必要はないのかな??でも、本や辞書の内容を理解するためには最低限の知識は必要だろうし。うーんいずれにしろ、もっと時間がほしいです!!!応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 3, 2008
コメント(0)
-

日本人としての誇り
今日は、わたしが日本人としての誇りを持つようになったきっかけを書こうと思います。10/17の記事の続きです。わたしは大学の2年目のとき、カナダに留学しました。ホームステイだったのですが、カナダに行ってすぐの頃、夕食のときにとてもショックな一言を言われました。その日の夕食では付け合せにコーンがあって、それをフォークで突き刺して3, 4個ずつ食べていました。そのとき。「日本では、これもみんな箸で食べるの?1つずつ?」「ええ、そうですよ」「うわー、信じられない!めんどくさい!」かなり頭にきました 和食では、コーンなんか食べないんだ! しかも、こんなふうにバラバラでは絶対に食べない!思わずそう言い返しそうになりましたが、言ってもわかってくれないかんじの人たちだったので、なにも言いませんでした。でもこのとき、ムカついた自分にかなりびっくりしてもいたのです。 日本のことをバカにされて頭にくるなんて。 そんなこと思ってもみなかった。そして、こう思ったんです。 わたしって、日本人なんだなぁ・・・。 日本のこと、好きなんだなぁ。 日本に対して、誇りをもっていたんだなぁ。これが、わたしが「日本人である」ということと、「日本人としての誇り」を意識した初めての出来事でした。こうやって文章にするとたいしたことない出来事に思えますが、わたしにとってはすごく印象的なことでした。あんなに頭にきたのは、もしかしたら、留学に向けて高校生の頃から箸遣いに気をつけてきたからなのかもしれないけれど。結局、留学中に箸を使う機会は一度もなかったんですけどね。留学中は、ほかにも日本と外国の違いをいろいろ見つけました。授業のときに名前をローマ字で書いてみたとき。 韓国の人に、日本語はひらがなの一つ一つがローマ字に 対応する、ということをどうしてもわかってもらえませんでした。 名前の「み」は、韓国では「my」と書くほうがおしゃれなのに。 「mi」なんて変だよ!! と、ずっと言っていました(笑)台湾の人に、中国語を習っていたとき。 仲良くなった台湾の人と、日本語と中国語を教えあっていたとき。 中国語では、疑問文のとき「ま」という漢字を最後に 書くそうです。そして、「?」は書かない。 日本語の「か」と同じようなものが中国にもあるんだー!!と 思いました。 そして、発音ではあまり母音を使わない。 発音を練習していたとき、 「日本語ではどの発音にも必ず母音がついてくる」と話すと、 「だから子音だけの発音が苦手なんだね!!」と納得されました。 「t」とか「p」とか、子音だけの発音って、すごく難しかったです。そのほか、日本に帰ってきてから、ネット上で偶然知り合ったマレーシアの人とチャットをしていたとき。 日本の「四季」を説明して紅葉の写真を送ったとき 「葉がこんな色に変わるなんて!!きれい!!!」 とすごくびっくりされました。 そうだよね、マレーシアには四季なんてないよね、と 日本に四季があることがうれしくなりました。こんなかんじで、ほんのちょっとしたことに始まり、その後のいろんな経験をつうじて、わたしの「日本人としての誇り」が育っていったんだろうな、と思います。英語の学習を目的として留学したけれど、実際には英語以外のことをたくさん学びました。英語なんて二の次、というくらいに。留学して本当によかったです応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 2, 2008
コメント(0)
-

客観的に読むこと
自分の書いた文章を客観的に読むことって、難しいですね。会社で報告書を書くとき、ひととおり書き終わったら客観的に読むようにしています。間違いはないか、わかりづらいところはないか、ことば遣いがおかしいところはないか。パソコンの画面上で読み返し、プリントアウトして読み返し、修正し終わってからまた読み返します。そしてまた間違いを見つけ、修正し、読み返します。そうやって、完成!と思ってから提出します。それでも、たまに間違いが残っていることがあります。原因は、客観的に読めていないことにあると考えています。翻訳の課題も同じように読み返してチェックしています。でも、報告書と同じようになかなか客観的に読むことができません。最初の数行は客観的に読んでいけるのですが、「あ、ここ、わかりづらかったところだ」「あれ、この言い方、おかしいぞ?」というふうに翻訳そのものを意識すると、あっという間に主観的になり、その後しばらくは客観的に読むことができなくなってしまいます。そしておかしいところに気づくことができずに課題を提出してしまうのです。今日、ちょっときっかけがあって10月分の課題の一部を読み返してみました。何度も読み返してチェックしたはずなのに、「あれ?」と思うところがいくつかあって、がっかりしましたいい翻訳をするためには、チェック機構をしっかり働かせることも必要だと思います。そして、「客観的に読むこと」はチェックの精度を上げる方法の1つではないかと思います。どうやったら客観性を高められるのか。社会人になって以来、もしかしたら学生のときからずっと考えているのですが、なかなかうまい方法が見つかりません。今のところ 1. プリントアウトして、紙で見る 2. 文書作成から時間がたってからチェックするの2つをおこなっているのですが、2. はなかなか難しいです。数日では効果が低いので。なにか、いい方法はないものかなぁ。応援お願いします!!語学分野のブログランキング
November 1, 2008
コメント(0)
全21件 (21件中 1-21件目)
1










