2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年10月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

ガブリエラ・モンテーロ Bach & Beyond/オキザリス
『今日のクラシック音楽』 ガブリエラ・モンテーロ 「バッハ&ビヨンド」今日も彗星のように現れたベネズエラ生れの新人女性ピアニスト、ガブリエラ・モンテーロを採り上げてみました。 今年5月に買ったCDですが、収録されているのは12曲全て大バッハの作品ばかり。 タイトルはBach & Beyond。 おもしろいタイトルをつけているなと思いながら、興味を抱いて会計カウンターに差し出しました。 帰宅して早速聴いてみると第1曲が誰もが聴いたことのある「主よ、人の望みの喜びよ」であり、聴いていると何やら音楽が変わってくる。 あわててディスクについている解説書を読んでみると「Improvisation on themes by J.S.Bach」と書いてあります。 それでタイトルのBeyondの意味がわかりました。インプロヴィゼーション、つまり即興演奏で大バッハの音楽をピアノで弾いていることになります。 60年代からモダン・ジャズではよくあることでした。 最も有名なのがモダン・ジャズ・クワルテット(MJQ)やフランスのジャック・ルーシェ・トリオが挙げられます。しかし、彼女の演奏にはジャズのように崩したところがありません。 しっかりとクラシック音楽でのピアノ演奏の基礎を積んだことは演奏を聴いていてわかります。 MJQやジャック・ルーシェのような完全にジャズにしてしまった手法ではなく、ショパンやドビッシー、ラフマニノフの香りをいっぱいに撒き散らした響きがピアノの音色から感じられます。モンテーロの心の中に湧き上がる感興のままに、自由に即興演奏を繰り広げているかのような感じがします。 バッハを弾く時は「こうすべき」というクラシック音楽の堅苦しい束縛がなくて、バッハの音楽が羽を広げて大空を舞うかのような音楽が展開しています。ジャズでもない、ムード音楽でもない、クラシック音楽でもない不思議な音楽空間へと誘うピアニストです。マルタ・アルゲリッチの前でピアノを演奏した時に、アルゲリッチは興奮してあちこちに電話をかけて、「これほどの才能には滅多にお目にかかれない。 彼女は類稀なアーティストだ」と言い、モンテーロの弾くラフマニノフのピアノ協奏曲第3番を聴いて、「私の後継者」とコメントしたほどの逸材、ガブリエラ・モンテーロは、私を不思議なバッハの世界へと導いてくれて、今でもその世界での居心地を楽しんでいます。1970年生れの36歳。 これから彼女はどんなピアニストに成長していくでしょうか、非常に楽しみな芸術家に出会った喜びがあります。 (EMIレーベル 3574772 2005年5月21-24日録音 海外盤)収録曲01.主よ、人の望みの喜びよ02.イタリア協奏曲からプレスト03.ビヨンド・バッハ04. G線上のアリア05. ゴールトベルク変奏曲から アリア06. ヴァイオリン協奏曲 ホ長調から アダージョ07. プレリュード ハ長調08. 羊たちは安らかに草をはむ09. 2声のインヴェンション ニ短調10. ブランデンブルク協奏曲第3番から アレグロ11. キーボード協奏曲 ニ短調から アダージョ12. トッカータ ニ短調・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』 1887年 初演 リムスキー=コルサコフ 「スペイン奇想曲」1891年 初演 マスカーニ オペラ「友人フリッツ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ともの『今日の一花』 オキザリス今はこの花を町内のあちらこちらで見かけます。 公園の植え込み、道端、家の庭、校庭、畑と言う具合に歩けば見かける花です。 撮影地 大阪府和泉市 2006年10月28日
2006年10月31日
コメント(8)
-

森 麻季 イタリア・オペラ アリア集/クレマティス
『今日のクラシック音楽』 森 麻季 イタリア・オペラアリア集~愛しい友よ 大変なソプラノ歌手が日本で生まれたものです。 まだ生の声を聴いてはいませんが、このディスクに収録された彼女の歌唱は伝統的なコロラトゥーラ・ソプラノの歌い方をしっかりと踏まえており、決して破綻することのない、それでいて数多くのこれまでの名歌手がそうであったような、スリリングな風情までも堪能できる、まさに国際舞台で活躍できる第1級の技量の持ち主であることがわかります。 名前を伏せて人に聴かせてもきっと名のあるイタリア人ソプラノ歌手と思ってしまうかも知れません。森 麻季のプロフィールはCDのライナーノーツに詳しく書かれていますが、もうそんなことはどうでもいい、このディスクに刻印された彼女の声が全てを語っています。コロラトゥーラの類稀なる技術と透明感のある美声、深い音楽性と華のある容姿が聴く者を魅了してくれます。このCDは先日10月25日にエイペックス・レーベルからリリースされた、彼女にとって2枚目のアルバムですが、HMVが朝10時に開店するのを待ちかねたように買い求め、帰宅するとすぐにCDプレーヤーに載せて聴きました。ここに収録されたアリアはコロトゥーラの名曲ばかり網羅されており、私はその中でも技術的に難度の高いドニゼッティの「ランメルモールのルチア」~(狂乱の場)から聴き始めて、彼女の透明な美声、技術的には完璧と思われる歌唱に脱帽の思いで聴いて、それから第1曲から順番に聴いていき、全部聴き終わってもう一度始めから聴き、これを2度繰り返すほどに感銘、感動しました。このディスクは多くのクラシック音楽ファンに、とりわけ日本人に、日本が誇る素晴らしいソプラノ歌手、森 麻季の声を聴いて楽しんで欲しいと思います。収録曲1. ドニゼッティ 「シャモニーのリンダ」~私の心の光2. ベッリーニ 「夢遊病の女」~ようこそ皆さん・・私にとって今日という日は3. ドニゼッティ 「ランメルモールのルチア」~狂乱の場4. ベッリーニ 「清教徒」~あなたの優しい声が5. ロッシーニ 「セビリアの理髪師」~今の歌声は6. ヴェルディ 「椿姫」~不思議だわ・・・花から花へ7. プッチーニ 「ラ・ボエーム」~ムゼッタのワルツ8. プッチーニ 「ジャンニ・スキッキ」~私の父さん大勝秀也指揮 ヴロッツワ・スコア・オーケストラ (エイペックス・レーベル AVCL25115 2006年6月22日ー25日 ポーランド録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1944年 初演 コープランド バレエ音楽「アパラチアの春」1946年 初演 ハチャトリアン チェロ協奏曲1957年 初演 ショスタコービチ 交響曲第11番「1905年」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 夏の名残り クレマティス(鉄線)4軒先のおうちの庭に「鉄線」の木がありますが、そこで一輪だけまだ美しい紫色の花を咲かせていました。 この時期に咲くとは珍しい花です。 撮影地 大阪府和泉市 2006年10月28日
2006年10月30日
コメント(14)
-
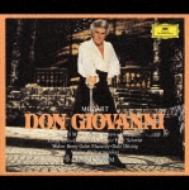
モーツアルト オペラ「ドン・ジョバンニ」/ヒメツルソバ
『今日のクラシック音楽』 モーツアルト作曲 歌劇「ドン・ジョバンニ」ウオルフガング・モーツアルト(1756-1791)は前作「フィガロの結婚」上演の大成功のあとをうけてオペラ「ドン・ジョバンニ」を書き残しています。物語は17世紀のスペインの町を舞台にしており、好色な貴族ドン・ジョバンニが町の娘ドンナ・アンナの誘惑に失敗するとそれに激怒した彼女の父の騎士長を刺し殺してしまいます。その復讐を許婚のドン・オッターヴィオと共に誓うドンナ・アンナ。ドン・ジョバンニはその後にかつて棄てた女ドンナ・エルヴィアラに遭遇しますが、従者に押付けて逃げてしまいます。 そしてその村の結婚式に出会い、その娘ツェルリーナまでも誘惑しますが、現れたエルヴィラに彼の不実を暴露されてしまいます。そうして、ドン・ジョバンニ退治に3組の連合が組まれます。墓地に逃げ込んだドン・ジョバンニの主従は、口を開く(死んだ)騎士長の石像を晩餐会に招待するように仕向けます。 それでもエルヴィラと主従はドン・ジョバンニを改めさせようと説得しますが、聴こうともしません。そこへ約束した通り、石像の騎士長が現れて、いっこうに悔い改めないドン・ジョバンニを地獄に追い詰めて、ジョバンニは業火に包まれてしまいます。 そうして全員が登場してドン・ジョバンニの末路を歌い、それぞれの人生へと旅立って行きます。この歌劇はオペラブッファ(喜歌劇)という形式なんですが、音楽は人間の業の深さを抉り出しているのかのようで、喜劇という思いがしないオペラです。 女性遍歴と殺人という奇行や、ドン・ジョバンニのふてぶてしい言葉など人間が持つ生々しい心のひだを描いているからでしょうか。裏切られてもまだドン・ジョバンニに心を寄せるドンナ・エルヴィラは心の襞を歌いつくすさまなどはその典型だと思います。これは「ドン・ファン」というタイトルでも有名な話で、音楽ではR. シュトラウスが交響詩「ドン・ファン」を書いています。このオペラ「ドン・ジョバンニ」は1787年の今日(10月29日)、プラハで初演されています。愛聴盤 カール・ベーム指揮 ウイーンフィル(ザルツブルグ音楽祭 1977年公演のライブ録音) (グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック 1977年ザルツブルグ音楽祭ライブ録音)シェリル・ミルンズ(Br) アンナ・トモワ=シントウ(S) ペーター・シュライアー(T) エデイット・マチス(S) ワルター・ベリーなど最盛期の豪華歌手陣による舞台の録音です。国内盤としては廃盤かもしれませんが大好きなもう1枚↓(EMI原盤 東芝EMI TOCE9442 1959年録音)カルロ・マリア・ジュリーニ指揮フィルハーモニア管弦楽団エバーハルト・ヴェヒター、ジョーン・サザーランド、エリザベート・シュワルツコップ若きジュリーニの遺した不朽の名盤として愛聴しています。現在最も安い廉価盤でイタリアオペラ臭くないドラマを味わえる盤としてお薦めはこれ。 3枚組で¥1,157です。↓ただ上記3枚のうちベーム盤をのぞいていずれも対訳が付いていませんので、初めて聴く人には辛いところがあります。映像ならこれです↓ (SONYレーベル SVD46383 1987年ザルツブルグ音楽祭ライブ 海外盤)サミュエル・レイミー、アンナ・トモワ=シントウ、ジュリア・バラディ、キャスリン・バトルなどの豪華歌手の競演をカラヤンが見事に統率したザルツブルグ音楽祭の舞台を収録したDVDで、価格は今なら2,200円という廉価盤です。 但し、字幕は英語、ドイツ語、フランス語のみです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1787年 初演 モーツアルト オペラ「ドン・ジョバンニ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ヒメツルソバ 撮影地 大阪府和泉市 2006年10月28日タデ科 タデ属 ヒマラヤ地方が原産地でピンク色の小さい花が、コンペイトウのようにつぶつぶ状に球形に集まって咲いています。 春・秋に開花しますが、四季を通じて咲いているようです。 明治中期に日本に渡って来たと言われています。 繁殖力が強く、カーペット状に群生して咲いています。
2006年10月29日
コメント(4)
-
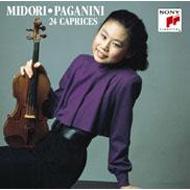
パガニーニ 「24の奇想曲」
10月27日と28日の日記記事があべこべになってしまいました。 混乱を招いてしまい申し訳ありません。 この記事は昨日に、昨日のチャイコフスキー「悲愴」は今日掲載すべき記事でした。 お詫び申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』 パガニーニ作曲 「24の奇想曲」「カプリース」と呼ばれているニコロ・パガニーニ(1782-1840)の代表的な24曲の無伴奏ヴァイオリン音楽です。17世紀~18世紀にかけてはイタリア・ヴァイオリン界は空前の活況を呈していたと言われています。 百花繚乱のごとき優れたヴァイオリン奏者を輩出したと言われています。 そうした中でも一際光輝く人がこの時期の最後に現れたパガニーニです。イタリア・ジェノヴァ生まれで、「ヴァイオリンの魔神」とさえ呼ばれるくらいに、パガニーニの技巧は人間業を超えたものと言われたそうです。 彼は革新的なヴァイオリン奏法を生み出した人で、二重奏法、左手のピッツィカート、スタッカートの飛躍的な奏法、フラジオレットなど独自の奏法を生み出しています。 そして超絶的なヴァイオリン演奏はヨーロッパを征服したとも言われています。今日の話題曲「カプリース(24の奇想曲)」作品1は、こうしたパガニーニが独自に生み出したヴァイオリン奏法を、フラジオレットを除いて全て用いて演奏する無伴奏のための小品集です。 楽譜出版当時はパガニーニ意外に弾ける人がいなかったとさえ言われているくらいに超絶技巧を要する作品です。作品を聴いてみるとわかりますが、甘美な旋律、表情豊かで多彩な音楽が速いアルペジオや、スタッカートの飛躍、重音奏法などが随所に現れています。 ヴァイオリン奏法を知りたければこの「カプリース」を聴けば良いとまで断言できるほどの作品です。この「カプリース(24の奇想曲)」を書いたニコロ・パガニーニは1782年10月27日にイタリア・ジェノヴァで生まれています。愛聴盤 五嶋みどり(VN)(SONYレーベル SICC344 1988年12月ニューヨーク録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1782年 誕生 ニコロ・パガニーニ(作曲家・ヴァイオリン奏者)1901年 初演 ドビッシー 「夜想曲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 大輪の菊菊の季節になり手塩にかけた盆栽菊の展示会があちらこちらで開催されています。 この写真も菊花展で撮ったものです。 撮影地 大阪府和泉市 2006年10月24日
2006年10月28日
コメント(2)
-
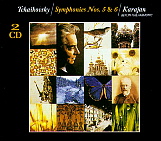
チャイコフスキー 「悲愴」/ヤマジノキク
『今日のクラシック音楽』 チャイコフスキー作曲 交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」本来ならこの曲についての記事は10月29日に記載すべきだったのですが、今日が29日と勘違いをしておりました。 訂正しておきます。ピョートル・チャイコフスキー(1840-1893)が書き残した交響曲第6番「悲愴」です。彼は「マンフレッド交響曲」(作品58)を含めると全部で7曲の交響曲を書いており、この「悲愴」が最後の曲になっています。 初期の3曲はよく習作扱いをされていますが、ロシアやスラブの地の薫りのする美しい音楽なのですが、何故か演奏会や録音にはあまり採り上げらず、専ら後期の第4番~第6番に人気が集中しており、中でもこの第6番は「悲愴交響曲」として絶大の人気を誇っている曲です。「悲しみ」「寂寞」「哀感」「苦悩」など、およそ人間が備えている心の中の「負」の感情・心象をこれほどまでに普遍的に顕わに描き出している音楽は、世界の古今東西を探してもないであろうと思う曲が今日の話題曲です。チャイコフスキー自身も、この曲については「生涯で最高の傑作」と機会のあるごとに語っていたというエピソードが残されているほどに、絶対的な自信作として確信していたのしょう。この交響曲は、上述のようにおよそ人間の心の内に介在する「絶望」「恐怖」「悲しみ」「寂しさ」「淋しさ」「悲哀」といった「負」の感情・心象が非常に高い普遍性を伴って、極上の美しい旋律で描き出されている、実に稀有な芸術の輝きいっぱいの「心の負」の交響曲だと思います。第1楽章第2主題の弦楽器によって奏でられる、しっとりとした、しかも深々と哀感を込めた美しい旋律。 第2楽章のしなやかさと流麗さがセンティメンタルで、甘美なリリシズムを湛えながら流れる、この上ない美しい旋律。そしてこの交響曲の白眉となっている「アダージョ・ラメントーソ(悲しみを込めたアダージョで)」の終楽章。 通常はアレグロというのが終楽章なのですが、ここでは連綿と悲しみ・淋しさ・苦悩などが美しくも、哀しく謳われており、喘ぐような暗い、重苦しい色合いに塗り込められた色調で、まるで苦悩と絶望の情念が極限にまで深められた末に、限りない寂寞感を残しながら、チェロの消え入るような最弱音によって静かに曲が閉じられます。何故? 何故チャイコフスキーはこのような「悲愴」感溢れる音楽を書いたのでしょうか? 初演後に彼は弟にこの交響曲に副題を付けるとすれば何がいいかと尋ねると、弟は「悲愴なんかどうだろう」と答え、チャイコフスキーは即座に気に入ってそれを命名したという、有名なエピソードが残されており、それが今日も「悲愴」と呼び続ける所以なのですが、チャイコフスキーはこの初演が終わったわずか9日後に、53歳の生涯を閉じており、文字通りこの第6番の交響曲が彼の最後の作品、白鳥の歌となってしまいました。当時の帝政ロシアの圧政による国民の苦悩を描いているとか諸説ありますが、私は彼が同性愛者であったがために帝政ロシアの「ロシア正教」にそぐわず、苦悩の末に死の道を選んだのではないかという説だろうと想像します。この曲に描かれた「苦悩」「絶望」は、同性愛者チャイコフスキーの「悲しみ」であったように思えてなりません。その交響曲第6番は1893年の10月29日、チャイコフスキー自身の指揮によってペテルスブルグで初演されています。愛聴盤 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリンフィルハーモニー(EMI原盤 DISKYレーベル ライセンス発売 1971年録音)レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨークフィル(ドイツ・グラモフォン 419604 1986年録音)カラヤン盤はEMI原盤をDISKYに放出した録音でどこかでまだ在庫があるかもしれません。 カラヤンを選んだ理由は1958年に初めて「悲愴」と出会ったのがカラヤン/フィルハーモニア管弦楽団だったことからです。 LP盤が擦り切れるほどに聴きこんだ懐かしいディスクで、私にとって「悲愴」の原点となる演奏です。この2つのディスクの際立った違いは、カラヤン盤が45:55、バーンスタイン盤が58:32という演奏時間の違いです。バーンスタインは晩年になるに連れてテンポが遅くなっていますが、この「悲愴」は尋常ではありません。 おどろおどろしいくらいに絶望と苦悩を描いており、特に終楽章の17:12はカラヤン盤とは7分も遅いタイムで演奏されて情念のすごさを描いています。私はベスト盤という言葉を極力使わないようにしておりますので、この2枚のディスクがベストという意味ではありません。 他に、ムラビンスキーやフリッチャイ、朝比奈 隆などの私の好きな録音盤がありますが今日は割愛させていただきます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1893年 初演 チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ヤマジノキクコスモスに変わり「秋の定番」菊があちこちで見られ、「菊花展」も開かれる時期になりましたが、野に咲くこういう菊はとても情緒のある「秋の花」の一つです。 撮影地 大阪府和泉市 2006年10月23日
2006年10月27日
コメント(8)
-
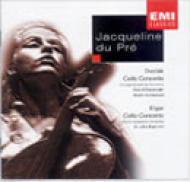
エルガー チェロ協奏曲/私のリスニング・ルーム
『今日のクラシック音楽』 エルガー作曲 チェロ協奏曲独奏チェロで奏でられる曲は、ピアノやヴァイオリンに較べて極端に作品数が少ないですね。 チェリストのミッシャ・マイスキーはあまりに曲の数が少ないので、シューベルトの歌曲をチェロ独奏(ピアノ伴奏付き)で演奏して録音するなど、チェリストにとってはレパートリー確保に大変だと思うときがあります。その数少ない独奏チェロによる演奏曲の中でも、ハイドン、ドヴォルザークなどの名曲と肩を並べて人気の高い作品に、イギリスの作曲家エドワード・エルガー(1857-1934)が書き残した「チェロ協奏曲ホ短調 作品85」があります。この曲はエルガー晩年の最後の大作で1919年に書かれています。曲の冒頭に独奏チェロが奏でる旋律は「ため息」のような情緒を醸し出しています。 それ故に雰囲気は愁いに満ちており、20世紀に書かれた現代音楽とは思えないロマンあふれる情緒で曲は展開していきます。 それでも音楽は高まりながら緊張をはらんでいき、クライマックスを築いてのちに初めの旋律が戻ってきて静かに第1楽章を終わります。曲は切れ目なしに第2楽章へと進み、憂鬱な感じの音楽が支配しています。 この感じのままで、まるで迷走するような音楽が、やがて静かに音が落ちていき、スケルツオ風に軽快な次の楽章へと進んでいきます。第3楽章は非常に短い音楽でありながら、瞑想のような美しい旋律が現れて「夢の世界」への誘いのような音楽が広がっています。終楽章は語りのようなモノローグ風に音楽が始まります。 それが力強い主題の提示へと進み、「空想」へと向かうような中間部のゆったりとした旋律が奏でられる様は見事です。 最後には第1楽章の冒頭の「ため息」のような旋律が独奏チェロで現れて、音楽は一気に高められてドラマティクに曲を閉じています。 比較的単純で簡潔な構成でありながら、色彩豊かに彩られた19世紀ロマン派音楽のような佇まいを帯びて、エルガー独特のロマンティックな音楽です。このチェロ協奏曲は1919年の今日(10月26日)、イギリスでエルガー自身の指揮で初演されています。愛聴盤 ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ)、サー・ジョン・バルビローリ指揮 ロンドン交響楽団(EMIレーベル 5555272 1965年8月19日録音 海外盤)レコード史上に燦然と輝くデュ・プレ20歳のデビュー盤で、現在もこの演奏を凌駕する演奏が出てこない「不滅の名演奏」盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1865年 誕生 ドメニコ・スカルラッティ(作曲家)1919年 初演 エルガー チェロ協奏曲1956年 没 ヴァルター・キーゼキング(ピアニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『私のリスニング・ルーム』プロフィールの写真として私の部屋を掲載しましたところ、このページをリンクしている方々から問い合わせがありましたので、大きめのサイズで掲載しておきます。画像右側はCDラックで、もっと右にも続くのですが画面に入りきらずに中途半端になっています。この部屋は私の仕事部屋・読書用書斎、それに音楽を聴くリスニング・ルームを兼ねています。 画像では写っていませんが、左側に愛蔵書を収容しました大型の本棚を置いています。 撮影日 2006年10月23日
2006年10月26日
コメント(8)
-
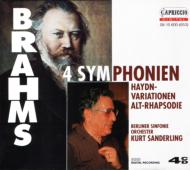
ブラームス 交響曲第4番/夕映えのススキ
『今日のクラシック音楽』 ブラームス作曲 交響曲第4番 ホ短調作品98秋に聴きたい音楽はたくさんありますが、うってつけの作曲家の一人にヨハネス・ブラームス(1833-1897)がいます。「渋く」「重厚」で、そこはかとなく「寂しさ」や「侘しい」情緒を醸し出した音楽を数多く書いており、ブラームスの音楽の特徴の一つになっているようです。そうした彼の作品の中でも、とりわけ「秋」を感じさせる曲に交響曲第4番ホ短調(1885年作曲)があります。 この曲(彼の音楽が全てそうであるように)は、四季の秋を表現しているわけではありません。 この曲を聴くと、そこはかとなく「人生の秋」「人生の夕映え」「人生のたそがれ」「心の秋」を感じてしまいます。 52歳の時に作曲されたこの曲は冒頭から彼の「ため息」が聞こえてくるような「ため息のモチーフ」と呼ばれているヴィオリンの哀愁を帯びた、哀感を湛えたような旋律で始まり、曲全体が「渋い」トーンで書かれており、第2楽章のチェロの主題はまるでブラームスの嘆きのような哀愁美に溢れた美しい音楽です。 第4楽章のパッサカリアは36の変奏がなされており、「新古典主義」と呼ばれたように古典的な佇まいの中で、思いっきりロマンを醸し出した古今の「パッサカリア」と変奏の美しさの極致を表現した音楽だと思います。この第4番を聴きますと、ブラームス晩年の「孤独」の「寂しさ」を感じられてなりません。すでに作曲家として大成して押しも押されぬほどの名声を確立していた頃の曲ですが、彼には愛する妻もなく、子供もなく、生涯独身を貫き、シューマン亡き後はシューマンの妻であるクララ・シューマンへの実らぬ恋心を抱き続けていました。親しくしていた友人(名指揮者ハンス・フォン・ビューローなど)が次々と彼岸のかなたへ旅立って行った頃に書かれているだけに、いっそう、忍び寄る「人生の秋」を感じてしまいます。 私は、そういう彼の当時の心境に実らぬクララ・シューマンへの思慕を、この曲で思い存分に嘆いて、死に近づいていく自らの「人生の夕映え」を謳っているのではないかと、この曲を聴くといつも同じことを感じます。私自身が年を重ねるにつれて、そういう感じがよく理解できるようになって来たように思われます。このブラームスの交響曲第4番は1885年の今日(10月25日)、ブラームス自身の指揮によりマイニンゲンの宮廷劇場で初演されており、第1楽章が1回、第3楽章が2回もアンコール演奏されるという成功を収めたと伝えられています。今日は、私の一番好きな音楽の一つであるこのブラームスの「人生の秋」をじっくりと味わってみたいと思っています。愛聴盤 クルト・ザンテルリング指揮 ベルリン交響楽団(カプリッチオ原盤 10600 1990年録音)↓ザンテルリング重厚で、どっしりと落着いた構えで、旋律を遅めのテンポでじっくりと歌わせ、弦楽器の響きが古色ががった、いくぶんくすんだような響きで、その上にまるでほどよくブレンドされたような管楽器が柔らかくかぶさり、ブラームス特有のロマンテイックな美しさを味わえる演奏・録音です。 私の一番好きな演奏です。他にはオットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団(EMI レーベル 562760 1957年録音)↓クレンペラージョン・バルビローリ指揮 ウイーンフィルハーモニー(パレ原盤 EMIリマスター Diskyライセンス発売 HR708222)↓バルビローリ朝比奈 隆指揮 新日本フィルハーモニー(フォンテック FOCD9206/8 2001年3月19日 サントリーホール ライブ)↓朝比奈 隆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1825年 誕生 ヨハン・シュトラウスII(作曲家)1838年 誕生 ジョルジョ・ビゼー(作曲家)1875年 初演 チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番1885年 初演 ブラームス 交響曲第4番ホ短調・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 夕映えのススキ撮影地 大阪府和泉市 2005年10月24日
2006年10月25日
コメント(16)
-
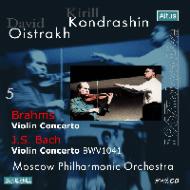
ダヴィッド・オイトラフ/イヌホウズキ
『今日のクラシック音楽』 ブラームス作曲 ヴァイオリン協奏曲ニ長調 OP7760年代にはキラ星のごとく指揮者、ピアニスト、ヴァイオリニスト、チェリスト、歌手等の「巨匠」と呼ばれた演奏家が数多くいました。そしてそういう名演奏家と呼ばれた再現芸術家たちの来日演奏会のラッシュでもあった年代でした。 その頃に生まれたクラシック音楽愛好家たちから羨望の眼で羨ましがられることがよくあります。そうした演奏家たちの生演奏体験のなかに、ロシアの不世出のヴァイオリニスト、ダヴィッド・オイストラフ(1908-1974)の素晴らしい演奏が今でも脳裏に残っています。 1967年4月16日の東京文化会館でした。曲はブラームスのヴァイオリン協奏曲、指揮はキリル・コンドラシン、モスクワフィルハーモニー管弦楽団との共演でした。オイストラフが奏でるヴァイオリンからは、骨太で雄大な分厚い、それでいて例えようもない美しい音色が弾き出されているというLPからの印象でした。 メンデルスゾーンやチャイコフスキー、ベートーベンの協奏曲、或いはベートーベンのヴァイオリン・ソナタでもそうでした。ところがこの夜のオイストラフのブラームス演奏を初めて生で聴いて、これほどに歌うヴァイオリニストだったのかと驚きと感動に包まれたのです。 第2楽章の「アダージョ」は勿論のこと、第1楽章のブラームス特有の重厚で渋みのある分厚い音楽でも、オイストラフが奏でる音色には「歌心」とでも呼べばいいのでしょうか、歌いに歌った美しい音色が会場に響き渡っていました。当時はこの曲をLPでジノ・フランチェスカッティの独奏ヴァイオリン(バーンスタイン指揮 ニューヨークフィル)で聴いていて、彼も「歌う」ヴァイオリンでしたが、それを凌駕する骨太で、重厚で、しかも曲のどの部分でもヴァイオリンが歌っているのでした。当夜の演奏会の模様がNHK音源として残っていて、それが2002年にCDで復刻されました。 今でも年に数回この演奏を聴いているのですが、目を閉じていますといつでもオイストラフの演奏する姿が浮かび上がってきます。 私には嬉しい贈り物のようなCDへの復刻でした。オイストラフは1974年の今日(10月24日)、オランダ・アムステルダムでの演奏旅行中に心臓発作によって不慮の死で66歳の障害を閉じています。このCDです。↓ (ALTUSレーベル ALT047 1967年4月16日東京文化会館ライブ録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 『今日の音楽カレンダー』1885年 初演 J.シュトラウス オペレッタ「ジプシー男爵」1948年 没 フランツ・レハール(作曲家)1974年 没 ダヴィッド・オイストラフ(ヴァイオリニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 イヌホウズキ自宅近くの空き家の庭でひっそりと咲いていました。 この花は「オオイヌホウズキ」や「アメリカホウズキ」など見分けがつかないのですが、葉の色や形で多分「イヌホウズキ」に間違いないお思います。 撮影地 大阪府和泉市 2006年10月22日ナス科 ナス属 道ばたなどでよく見かける花です。 日本には相当古い時代から渡来していたと推測されているそうです。 夏から秋にかけて、白い小さな花が咲きます。 花が散って実が成ると緑色から黒に変わっていきます。 かなりな毒を含んだ植物だそうです。
2006年10月24日
コメント(10)
-

プロコフィエフ ヴァイオリン・ソナタ第1番/ヤマジノホトトギス
『今日のクラシック音楽』 プロコフィエフ作曲 ヴァイオリンソナタ 第1番へ短調 作品80 セルゲイ・プロコフィエフ(1891―1953)は、ヴァイオリンソナタを2曲書き残していますが、1番と2番の完成で言いますとあとの2番の方が先に書き終えています。それでも第2番と呼ばれており、2年後の1946年に完成したソナタを第1番と呼んでいます。これは後で完成していても、先に第1番が作曲され始めたためだそうです。プロコフィエフは、ラフマニノフなどと同じように、帝政ロシアの上流社会で育てられており、ロシア革命の混乱を避けて1918年に祖国を離れていますが、1936年にソ連に戻って祖国で亡くなった作曲家です。彼は自由に音楽を書ける環境を求めて日本でしばらく滞在したのちに、アメリカやパリで生活を送りますが、快適に音楽を書けても、どうしても故郷のロシアに郷愁をそそられたのでしょうか。祖国へ戻ることになりました。しかし、革命政府の芸術への制限は彼の想像を超えたものでかなりの抑圧を受けながらの作曲活動が続きましたが、オペラなどに素晴らしい作品を残しています(とりわけ「3つのオレンジへの恋」はもっと普遍的に上演されるべき、美しい音楽だと思います)。1940年代に、プロコフィエフは転倒と脳震盪が原因で健康状態は悪くなっていきました。そういう最中に書かれたのがこのヴァイオリン・ソナタ第1番です。しかし、曲自体にはそういうことを全く感じさせない、色彩感豊かな情緒の音楽で、しかも抒情的な美しささえ感じられる音楽です。初演時には演奏者のダヴィッド・オイストラフとピアノのレフ・オボーリンに、第1楽章の終わりは「墓場に吹く風」の如く演奏するようにと指示したエピソードが残されています。政治の音楽への抑圧に対する彼自身の精いっぱいの抵抗と見るには、穿った見方でしょうか?このヴァイオリンソナタ第1番は、1946年の今日(10月23日)、上記の2人の演奏家によって初演されています。愛聴盤 ギドン・クレーメル(Vn) マルタ・アルゲリッチ(P)(ドイツグラモフォン 431803 1991年録音 輸入盤)↓プロコフィエフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1897年 初演 スクリャービン ピアノ協奏曲1933年 初演 コダーイ 「ガランダ舞曲」1946年 初演 プロコフィエフ ヴァイオリンソナタ 第1番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ヤマジノホトトギス私の好きな秋の被写体の一つですが、今回は暗い所で咲いていたために内蔵ストロボ発光の設定がうまく出来ずにこんな写真になってしまいました。 三脚使用で撮っているのは常のことですが、この花は地面にすれすれに咲いていましたので、やはり低台の三脚が必要と感じました。 そうすれば花の横から撮れるのですが惜しいことをしました。撮影地 静岡県島田市 童子沢 2006年10月15日ユリ科 ホトトギス属 若葉や花にある斑点模様が、鳥のホトトギスの胸にある模様と似ていることからこの名が命名されたそうです。 開花時期 9月初旬~11月中旬 秋に日陰に多く生えています
2006年10月23日
コメント(8)
-
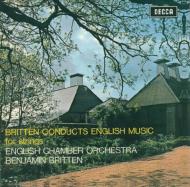
パーセル 「シャコンヌ ト短調」/ママコノシリヌグイ
『今日のクラシック音楽』 パーセル作曲 「シャコンヌ ト短調」イギリスの作曲家が書いた弦楽合奏のための音楽を収録したディスクで、やはりイギリスの作曲家・指揮者・ピアニストでもあるベンジャミン・ブリテン(1913-1976)がイギリス室内管弦楽団を振ったCDの紹介です。この録音はLP時代から好きな作品集で、聴いてますととても心が平安に穏やかになる音楽ばかりです。収録曲1) パーセル 「シャコンヌ」ト短調2) エルガー 「序奏とアレグロ」作品473) ブリテン 「前奏曲とフーガ」作品294) ブリテン 「シンプル・シンフォニー」作品45) ディーリアス「2つの水彩画」6) ブリッジ 「ロジャード・カヴァリー卿」この中でも白眉はヘンリー・パーセル(1659-1695)が書いた「シャコンヌ」ト短調です。この作品が書かれた経緯がはっきりとしていないのですが、多分何かの舞台作品の付随音楽だろうと推測されています。 音楽は4声部で書かれているために最初は弦楽四重奏用として書かれたのであろうと思われているそうです。弦が冒頭から威厳のある深みを持った旋律を奏でており、す~と引き込まれるような美しさをたたえた情緒があり、しかも実に表情豊かな旋律が弦4部でコクの深い味を響かせています。7分間ほどの短い曲ですが、感動的な音楽です。その他のブリテンやエルガーの音楽も秋の夜に一人で聴くのがもったいないほどの、清冽な響きとテクスチュア豊かな音楽を聴くことができます。愛聴盤 弦楽のためのイギリス音楽 ベンジャミン・ブリテン指揮 イギリス室内管弦楽団 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD3610 1968-1971年録音)DECCAらしいピラミッド型の優秀録音盤で、1200円という廉価盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1752年 没 アレッサンドロ・スカルラッティ(作曲家)1811年 誕生 フランツ・リスト(作曲家)1970年 没 サンソン・フランソワ(ピアニスト)1973年 没 パブロ・カザルス(チェリスト・指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ママコノシリヌグイこの花を見つけた時は「秋の鰻つかみ」とばかり思っていたのですが、野草図鑑でよく調べてみますと「ママコノシリヌグイ」でした。 可愛い表情の花です。 撮影地 静岡県島田市 童子沢 2006年10月15日タデ科 タデ属 ピンク色の米つぶのような花をしています。 茎に痛そうな下向きのトゲがあり、このトゲで継子のお尻をふいた、という意味で命名されたと言われていますが、本当でしょうか?
2006年10月22日
コメント(4)
-
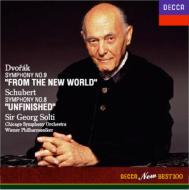
サー・ゲオルグ・ショルティ/彼岸花(白花)
『今日のクラシック音楽』 ドボルザーク 交響曲第9番「新世界より」ハンガリーからは数多くの名指揮者が生まれています。 フリッツ・ライナー、ジョージ・セル、ユージン・オーマンディ、アンタル・ドラティなどが20世紀を代表する名指揮者としてその名をとどめています。そうしたハンガリー出身の指揮者の中でもとりわけ有名なのが、サー・ゲオルグ・ショルティです。ショルテイは現代の録音技術の進化と共に歩いた指揮者で、数多くの曲をLPステレオ録音時代からディジタルCD録音まで残しています。 1960年代にはイギリスのコヴェント・ガーデン王立歌劇場の音楽監督として就任、名声を確立して「ナイト」の称号を与えられていますから、正式にはサー・ゲオルグ・ショルテイと呼ばれています。1969年にフランスのジャン・マルティノンの後を受け継いでシカゴ交響楽団の音楽監督に就任して、1991年にバレンボイムにその地位を譲るまで指揮を執り、シカゴ市民から絶大の信頼を得た指揮者でした。あれは1990年だったか、彼が退任前にシカゴ響と来日した折に、大阪のシンフォニーホールで鳴り響いたブルックナーの8番の名演が目に、耳に焼きついています。どの曲の演奏も、明晰な表現とダイナミックな推進力でパワフルにオーケストラを鳴らす指揮者でした。 オーケストラコンサートだけでなく、オペラ指揮者としても非凡な才能を発揮してプッチーニ、ヴェルデイなどのイタリアオペラ、ベートーベン、ワーグナー、R.シュトラウスなどのドイツ・オーストリアのオペラなどを数多く上演、録音を行なっています。とりわけ1958年ー1965年にウイーンフィルを指揮して当時の世界の一流歌手を揃えたワーグナーの4部作「ニーベルングの指環」は、今も尚、ワーグナー音楽の聖書のように讃えられている録音です。私が大学生時代にワーグナー音楽に心酔するようになったのもこの録音でした。それにミサ曲、オラトリオなどの教会音楽などにも素晴らしい演奏があり、ヴェルデイの「レクイエム」などの名演奏を遺してくれています。1912年の今日(10月12日)、ショルティはハンガリーで生まれています。今日は彼の誕生日に因んで、名演の一つであるドボルザークの交響曲第9番「新世界より」を紹介しておきます。いかにもショルテイらしい、明晰でダイナミックな音楽表現と、切り込み鋭く、パワフルなシカゴ交響楽団との演奏で、素晴らしい録音がいっそうの迫力を添えており、テインパニーを叩く音などは怖さを覚えるほどの迫力で迫ってくる超優秀録音盤です。愛聴盤 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD5018 1981年1月シカゴ録音)その他ショルティ指揮の愛聴盤(1) バルトーク 管弦楽のための協奏曲 シカゴ響 (DECCAレーベル 4757711 1981年、89年録音 海外盤)「弦・打楽器・チェレスタのための音楽」がカップリングされています。(2) マーラー 交響曲第5番 シカゴ響(LONDONレーベル 43329 1970年録音 海外盤)(3) ワーグナー オペラ「ローエングリン」全曲ドミンゴ、ジェシー・ノーマン、ディースカウなどを揃えて、ウイーンフィルの美音を引き出した見事なオペラ演奏・超優秀録音盤です。 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD3155 1985-6年 録音)(4) ヴェルディ オペラ「仮面舞踏会」 (TDKコア TDBA0092 1990年ザルツブルグ音楽祭ライブ収録)カラヤンが振る予定だった演目で、ドミンゴ、ヌッチ、スミ・ジョーなどの名歌手を揃えたすぐれたライブ映像です。 私はNHKで放映されたこれと同じ映像をVHSに録画しており、それを楽しんでいます。 ハイビジョンで収録されているため画質はとても美しいものに仕上がっています。(5) ヴェルディ オペラ「椿姫」 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCDB9003 1994年ロンドン公演ライブ)ソプラノのゲオルギューの衝撃のイギリス・デビューを飾った名舞台ライブです。(6) ワーグナー 「ニーベルングの指環」管弦楽作品ウイーンフィルとの歴史的ステレオ録音から20年以上たって再録音した4部作の聴き所のオーケストラワークで、DECCA特有のピラミッド型優秀録音で、迫力のあるワーグナー音楽を楽しめます。(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD5031 1982年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1858年 初演 オッフェンバック オペレッタ「天国と地獄」1912年 誕生 ゲオルグ・ショルティ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 彼岸花(白花)静岡・島田市の大代川土手に咲いていました。 もうこの花の時期も終わったかと思っていましたが、意外とまだ咲いているのですね。撮影地 静岡・島田市大代川 2006年10月15日
2006年10月21日
コメント(6)
-
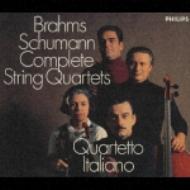
シューマン 弦楽四重奏曲/アブラススキ
『今日のクラシック音楽』 シューマン 弦楽四重奏曲第1番イ短調 OP41の1ロベルト・シューマン(1810-1856)はどうも一つの音楽ジャンルをまとめて書く傾向にあったようです。 彼のピアノ恩師であったフリードリッヒ・ヴィークの娘クララと激しい恋に落ちて、ヴィークの猛反対を受けてしまい、とうとう法廷にまで結婚の可否を仰いだ結果、シューマンとクララは法廷の認めることで勝訴してめでたく結婚しました。それが1840年でした。 その結婚の年にシューマンは歌曲を立て続けに作曲して100曲以上の曲を書いています。 それを人は「歌の年」と呼んでいます。 その翌年(1841年)には2曲の交響曲(交響曲の年)、更に1842年にはシューマンは「室内楽」へと目を向けて新たに室内楽作品を書き残しています。1842年の6月から7月にかけてシューマンは3曲の室内楽作品を書き残しています。 3つの弦楽四重奏曲がそれです。 第1番の書き始めが1842年6月4日、第3番を書き終えたのが7月22日ですから、わずか50日間で3曲の弦楽四重奏曲を書き終えるとというスピードぶりです。 いかに彼のインスピレーションが凄かったを物語るエピソードです。3曲の内で最も好きなのが第1番のイ短調です。 他の2曲はヘ長調、イ長調で書かれており、曲想も第1番に比べて悲劇的なところが多少なくなって明るい輝かしい作品となっており、特に第3番は演奏頻度がとても高い作品と言われていますが、第1番の緊張の漲る曲想、情緒はロマンあふれる音楽でありながら、どこかベートーベンの室内楽作品が持っている緊張感と力強さをそのまま踏襲しているかのような劇的な内容に魅かれます。ロマンティックな情緒を漂わせていながら、非常に力強い音楽となっているのが魅力です。 秋の夜長に聴く音楽としては格好の室内楽作品の一つでしょう。愛聴盤 イタリア弦楽四重奏団 (Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック PHCP20280~2 1968年ー1971年録音) この演奏はLP時代も含めて再発売を何度となく繰り返してきており、このクワルテットで聴けるのは現在は3枚組みでシューマンの3曲、ブラームスの3曲を収録しています。 LP時代に聴いていたのをこの3枚組みに買い換えて聴いています。 古いアナログ録音ですが、実に鮮明な音質になって甦っています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1860年 初演 ブラームス 弦楽六重奏曲第1番1874年 誕生 チャールズ・アイヴズ(作曲家)1920年 没 マックス・ブルッフ(作曲家)1958年 誕生 イーヴォ・ポゴレリチ(ピアニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 アブラススキ 撮影地 静岡県島田市 童子沢 2006年10月15日イネ科 アブラススキ属日本全土にどこにでも観られる「イネ科」の植物です。
2006年10月20日
コメント(2)
-
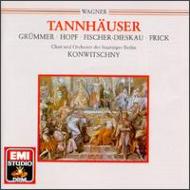
ワーグナー オペラ「タンホイザー」(追記あり)/秋の野芥子(アキノノゲシ)
『今日のクラシック音楽』 ワーグナー オペラ「タンホイザー」リヒャルト・ワーグナー(1813-1883)はこの「タンホイザー」がドレスデンで初演される前には、ロシアやパリで作曲の筆をとっていましたが彼の作品が舞台に上がることはなく、ベルリオーズなどとパリ時代に親交を深めていたものの、友だちとしての上演への協力もなく不遇の時代を過ごしており、オペラ「リエンツェ」がドレスデンで上演されたのは1842年の10月20日。 1843年の1月にオペラ「さまよえるオランダ人」が同じくドレスデンで初演され、この成功によってドレスデン宮廷歌劇場の指揮者に就任してのちに構想を持っていた「タンホイザー」の作曲に取り掛かり、1845年10月19日に初演されたそうです。パリ時代の不遇に負けずに不屈の闘志と精神で粘り強く生きてきたワーグナーがようやくこの「タンホイザー」によって自信を深め、次の「ローエングリン」へと進んでその「ローエングリン」作曲後に「歌劇」から「楽劇」へと総合舞台芸術への道を歩んでいきました。「タンホイザー」は3幕から成るオペラで舞台は13世紀初頭のドイツ、今では観光地となっていますアイゼナハのワルトブルグ城です。女性の力によって魂が救済されるというワーグナーの好みのテーマで貫かれている物語です。 ワルトブルグ城主の姪エリザベート姫と吟遊詩人タンホイザーの悲恋を描いています。吟遊詩人タンホイザーは、愛欲の神ヴェーヌスの誘惑の虜となり歓楽に耽るさまから幕が上がります。 しかしエリザベート姫のいる城が恋しくなりやがて城に戻り、おりからの「歌合戦」に参加したのはいいのですが、友だちのヴォルフラムの清らかな愛の歌への反発から歓楽と愛欲の神ヴェーヌスを賛美する歌を歌い追放されます。ローマ法王の許しを得ようと巡礼の旅にでますが許されずに戻ってきたタンホイザーを、エリザベート姫は自分の命と引き換えに彼の魂を救うという悲恋物語です。「序曲」はコンサートプログラムでもよく取り上げられる曲で、劇中に演奏される「巡礼の合唱」の旋律などが使われており、崇高な佇まいの音楽です。「ヴェヌスブルグの音楽」は第1幕が上がると歓楽の場面のバッカナールという音楽で、これもよく演奏されます。 序曲にも取り入れられています。「夕星の歌」は吟遊詩人ヴォルフラムが、夕星たちよ姫が天国に上るときに歩んでいく道を照らしてやってくれと歌う第3幕のアリアで、これも有名な、美しいバリトンのアリアです。「巡礼の合唱」はこのオペラの代名詞のような曲で崇高な雰囲気の合唱曲です。このオペラ「タンホイザー」は1845年の今日(10月19日)、ドレスデンで初演されています。愛聴盤 エリザベート・グリュンマー(ソプラノ)、ハンス・ホップ(テノール) フランツ・コンビチュニー指揮 ベルリン国立歌劇場管弦楽団・合唱団(EMIレーベル 7632142 1960年10月 ベルリン録音 海外盤)(追記)もうこういう演奏は二度と聴けないのではないかと思えるほどの深い、重厚なドイツ音楽の響きのする演奏をとても気に入っています。 40年以上前の録音ですが音質は良好です。 現在東芝EMIカタログから消えていますので早い時期での復刻を望むものです。 紹介のCDは英語訳付きの輸入盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1814年 作曲 シューベルト 歌曲「糸を紡ぐグレートヒェン」1845年 初演 ワーグナー オペラ「タンホイザー」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 秋の野芥子(アキノノゲシ)撮影地 静岡県島田市 童子沢 2006年10月15日キク科 アキノノゲシ属昭和初期に台湾から渡来したそうです。 道端や川原、畑の畦道、公園などに自生で咲いています。
2006年10月19日
コメント(4)
-
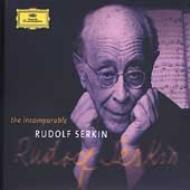
ベートーベン ピアノソナタ第31番/アケボノソウ
『今日のクラシック音楽』 ベートーベン作曲 ピアノソナタ 第31番 変イ長調 作品110ルードビッヒ・ヴァン・ベートーベン(1770-1827)は耳の障害に悩まされながらも100数十曲の音楽を書き残していますが、耳だけではなくてリュウマチや内臓疾患に悩まされ続けた作曲家だと言われています。50歳を過ぎた頃には病気も慢性化して彼の体を蝕んでおり、しかも確実に進行していたそうです。 そんな状態の51歳の頃(1821年)には「荘厳ミサ曲」の作曲をしながら、2曲のピアノ・ソナタを書いています。第31番と32番のソナタがそれです。 ベートーベンは32曲のピアノソナタを書き残していますから、この31番が彼のソナタとしての絶筆前の作品となった曲です。しかもこれら2曲が上述のように、病気との闘いの中で書かれています。特に31番は闘病の苦しい中で書かれている曲だけに、音楽には悲哀とか悲壮感のような情緒が散りばめられており、聴く者を感動へ誘う音楽です。ある意味、病を得た人であればより鮮明にわかる情緒の音楽だと思います。ピアノから紡ぎ出される第1楽章の叙情溢れる楽想は、聴く者の胸をしめつけてくるようです。しかし、何と言っても見事な音楽を表出している終楽章は深い感動を与えてくれます。 ベートーベン自筆の言葉で書かれた「嘆きの歌」が、泣き叫ぶかのように悲痛に訴えてきます。その後に「フーガ」の楽想となってもう一度「嘆きの歌」が戻り、最後にまた「フーガ」によって曲が結ばれています。ベートーベンの音楽の根底を成している「人生観」「人生哲学」- 不幸な苦しい境遇であっても耐え忍ぶことが優れた人間であり、成長する - が感じられる楽章で、聴いていて最後には大きな勇気が与えられるように感じる曲です。私事になりますが、2度の脳梗塞を患い、言語障害と闘って治さねばならない立場になってこの曲を改めて聴きました時に、私はベートーベンがこの曲に込めた・秘めたメッセージを初めて理解できたように思ったものです。「諦めるな!」。 ベートーベンが人間の可能性を信じて、勇気を自らに与えようとして書いたこの音楽が、人類への発信でもあったのかとリハビリを続ける私を励ましてくれた一曲でした。涼しい風が吹き渡る秋の夜に、もう一度ベートーベンに感謝しながら今夜はこの曲を聴こうと思います。愛聴盤 ルドルフ・ゼルキン(ピアノ)(ドイツグラモフォン 474328 1987年 ウイーン・ライブ録音)↓ゼルキン後期の3大ソナタ第30番、31番、32番を収録しており、当時ゼルキンはすでに80歳を超えていたのですが、純粋で高雅で緊張感をも漂わせる演奏が、より一層私を勇気付けてくれました。 私の盤はこれ1枚ですが紹介のCDはロストロポービチとのブラームスのチェロソナタがもう1枚組まれています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1893年 没 シャルル・フランソワ・グノー(作曲家)1904年 初演 マーラー 交響曲第5番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 アケボノソウ先週末から静岡県島田市へ行ってました。 15日の日曜日には島田市金谷町にある「童子沢(わっぱざわ)」へ野草花を撮りに行きました。 その中の一つで「アケボノソウ」です。撮影地 静岡県島田市 童子沢 2006年10月15日りんどう科 センブリ属 湿り気のあるところに咲く花で2年草で、1年目は葉を広げるだけだそうです。 2年目の秋に白いクリーム色の5弁花が咲くそうです。斑点がたくさんあるのが特徴で、白い花びらを明け方の空に、 花びらにある斑点を夜明けの星に見立てて名づけられたそうです。
2006年10月18日
コメント(11)
-
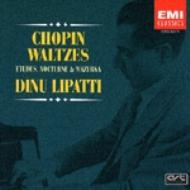
ショパン ワルツ集
『今日のクラシック音楽』 ショパン作曲 「ワルツ集」フレデリック・ショパン(1810-1849)が亡くなったあとに、彼の机の抽斗から一通の封筒が出てきたそうです。 その封筒には「わが悲しみ」という言葉がポーランド語でショパンの自筆で書かれていたそうです。 リボンで結ばれていて、彼の生前には誰も目にしないように、大切に保存しておいたのでしょう。 封筒の内には手紙が入っていて、それはマリア・ヴォジンスカという女性と彼女の母親からの手紙でした。ショパンは生涯に3人の女性を真剣に愛したと言われています。 そのうちの一人がこのマリアでした。 二人は幼馴染みで、彼女の家は伯爵家でしたが、ショパンの母がこの伯爵と遠縁にあたる筋という縁から、二人は子供の頃からよく遊んだという仲だったそうです。有名なショパンのポーランド脱出が20歳の時で、パリに住んだ彼はそれ以後一度も祖国に戻っていません。 それで伯爵家との縁も無くなり、マリアとも会うことなく月日が流れて行きました。ショパン25歳の時に、彼の両親が湯治旅行に出かけ、その時ばかりはショパンも出かけて行き、その帰りにドレスデンで伯爵家族と思いもかけない劇的な再会を果たします。伯爵家は、ショパンを歓迎して昔と同じ交際を続けてくれたのですが、彼はそれよりもマリアが美しい娘に成長しているのを見て、恋心が芽生えてきました。翌年も二人は再会して熱い恋心を育んでいったのでしょう、ショパンは彼女にプロポーズをしたのですが、結局伯爵家との家柄の違いとショパン自身の病弱を理由に、この婚約話は暗礁に乗り上げます。その2年後にショパンは病に倒れてしまいます。 その頃にマリアとその母親から冒頭に書きました手紙が届いていたのでした。ショパンは「ワルツ第9番変イ長調」をマリアに捧げ、その楽譜を自分の机の奥深くにしまいこんでおり、この曲はショパンの生前には演奏されることも出版されることもなかったそうです。これが「ワルツ第9番」が「別れのワルツ」と呼ばれている所以です。ショパンはその生涯にワルツを20曲以上作曲したと言われています。 「ワルツ」はもともと踊る為の音楽ですが、ショパンのそれはダンス用に書かれた音楽ではなくて、ワルツの形式とリズムを使って書かれたもので、あくまでも詩的に心象を表現した曲集です。シューマンは「もしショパンのワルツで踊るのなら、相手の婦人の半分は伯爵夫人でなければならない」と語ったそうです。 ショパンのワルツを言い得て妙なる表現ではないでしょうか。そのショパンが1849年の今日(10月17日)、パリで39歳という若さで生涯を閉じています。愛聴盤 ディヌ・リパッティ(ピアノ)(EMI原盤 東芝EMI TOCE59178 1950年録音)↓リパッティアルトゥール・ルービンシュタイン(ピアノ)(RCA原盤 BMGジャパン BVCC37233 1963年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1849年 没 フレデリック・ショパン(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 イヌタデ 撮影地 大阪府和泉市 2006年10月12日
2006年10月17日
コメント(14)
-

マリオ・デル・モナコ/冬珊瑚
『今日のクラシック音楽』 マリオ・デル・モナコ(テノール)7月27日と10月16日は、私にとっては特別な日です。 イタリアのテノール歌手、マリオ・デル・モナコ(1915-1982)の誕生日と命日です。 今日は命日にあたります。 1年に二度、私はモナコが遺した名演奏、名録音をこの2日で楽しんでいます。 1961年、私がまだ高校2年生だった年ですが、NHKの招きでイタリア歌劇団が来日して東京、大阪でオペラやリサイタル公演を行ないました。 そのときの歌手がソプラノのレナータ・テバルデイであり、メゾ・ソプラノのジュリエッタ・シミオナートであり、そしてマリオ・デル・モナコでした。この来日時の大阪公演で私はモナコの「道化師」とシミオナートの「カヴァレリア・ルステイカーナ」の舞台を観ました。 フェステイバルホールの1階最前列オーケストラピットに立つ指揮者の斜め後でした。モナコの道化師にただただ圧倒された夜でした。 シミオナートのサントッツアの舞台の興奮冷めやらぬうちに「道化師」が始まり、終ったあとはシミオナートのことが頭から消えてしまうくらいにモナコの白熱の名唱に酔いしれて、秋の夜の中之島をぼ~と歩いていたのを覚えています。モナコはテノール歌手としては、ドラマテイック・テノールでその声はまるで「鋼」のように強靭で、突き刺さる剣のような高い声は「黄金のトランペット」と形容される歌手でした。彼の得意とする「道化師」のカニオは、いまだもってこの人の名唱を凌駕するテノールはいないのではないかと思うほどです。 客席で観ていて、劇中の白眉のアリア「衣装をつけろ」では、私の真ん前にモナコが座り、白粉を塗りながら目を大きく開けて、私をぎょろっと睨みながら歌い始めたときには、鳥肌が立つ思いで引き込まれていきました。↓デル・モナコ「空前絶後」という言葉がありますが、まるでモナコのためにあるような、まさに「空前絶後」のテノールです。 この人の名唱を聴くときには襟を正して正座するほどの姿勢になってしまいます。今日もその10月16日がやってきました。 今日は何を聴こうかな、カラヤンとウイーンフィル、テバルデイとの共演の「オテロ」? それともテバルデイ、バステイアニーニとの「アンドレア・シェニエ」か同じオペラの唯一テバルデイとの日本共演舞台の映像? いや、やっぱり1961年の来日公演の映像から「道化師」?今は真夜中の12時を過ぎたばかりです。 朝起きたときに題目を決めよう。 そして40年前にタイプスリップする楽しみを思いながらぐっすりと寝ることにします。 おやすみなさい。お薦めCD マリオ・デル・モナコ オペラアリア集 モナコの魅力満載のアリア集で、「衣装をつけろ」「星は光りぬ」「誰も寝てはならぬ」「オテロ」幕切れのアリアなどがカップリングされています。 この中にマイアベーアの「アフリカの女」から「おおパラダイス」が入っていますが、これこそ劇的な表現に満ちた、「黄金のトランペット」を満喫できる「空前絶後」のアリアです。(DECCA原盤 ユニヴァーサル・クラシックス POCL4375 1955年ー1964年 録音)↓デル・モナコ昨年の日記を少し加筆・訂正して掲載しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1821年 誕生 フランツ・ドップラー(作曲家・フルート奏者)1912年 初演 シェーンベルグ オペラ「月に憑かれたピエロ」1926年 初演 コダーイ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」1938年 初演 コープランド バレエ音楽「ビリー・ザ・キッド」1982年 没 マリオ・デル・モナコ(テノール)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 冬珊瑚先日叔父がふいにやって来てぽんと一鉢置いて帰りました。 以前鳥が種を運んで来たのを育てていると、しっかりと根を張って大きくなったと言ってたのが、この「冬珊瑚」でした。 小さな白い花をたくさん開花させています。 撮影地 自宅庭 2006年10月12日なす科 ナス属 ブラジルが原産地で日本には明治時代に渡ってきたそうです。 花のあとは実が成ります。 それも青色から橙色、赤と変化していきます。
2006年10月16日
コメント(8)
-

金木犀
ともの『今日の一花』 金木犀今年の開花は少し遅れていたようですが、ようやく町内も甘い香りに包まれるようになってきました。 そんな金木犀を撮ってみました。 撮影地 大阪府和泉市 2006年10月12日
2006年10月15日
コメント(12)
-
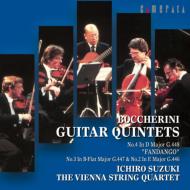
ボッケリーニ 「ファンタンゴ」/マリーゴールド
『今日のクラシック音楽』 ボッケリーニ作曲 ギター五重奏曲第4番「ファンタンゴ」今日はイタリアの作曲家ルイジ・ボッケリーニ(1743-1805)の書き残した「ギター五重奏曲第4番」を聴いてみようと思っています。ボッケリーニは終生イタリアで過ごしていたと思っていましたが、何とスペインで長年暮らしていたのですね。 彼のことを調べてみると作曲家でもあり、名うてのチェロ奏者でもあったそうです。 ウイーンやパリで演奏家として成功を収めた後に、25歳(1768年)でスペインへ落ち着いているそうです。もともと王侯貴族の高雅で典麗、洗練された宮廷音楽に魅かれていたそうで、27歳(1770年)でスペイン王子の宮廷演奏家に就いており、そこで過ごした15年間で多数の音楽を書き残したそうです。弦楽五重奏曲やピアノ五重奏曲、チェロ協奏曲などが有名で、これらの作品はこの15年間に書き残されているそうです。 特に、弦楽五重奏曲は125曲も書き残したそうで、まさに驚異の作曲家です。ボッケリーニは自分の作品を編曲する名人で、今日の話題曲「ギター五重奏曲」はオリジナル曲から自らギター演奏用に編曲しています。 そのオリジナルとなったのは弦楽五重奏曲で、このギター演奏の第4番は作品10の6(弦楽四重奏曲)と作品40の2を編曲した作品だそうです。3楽章形式で、特にカスタネットが使用されるこの作品はスペインの情緒が全編にわたって流れています。 「ファンタンゴ」とはスペイン舞曲の一つで、曲の冒頭から聴く者をスペインへと誘ってくれる音楽が顕著に顕われた、色彩豊かで情熱的な音楽が展開しています。独奏楽器・ギターを用いた事やカスタネットを使っていることで、作品はローカル色に富んでいて、情熱的な音楽が展開しています。愛聴盤 ウイーン弦楽四重奏団 鈴木一郎(ギター) (カメラータ・レーベル CMCD15033 1997年ウイーン録音)私が聴いていますのはNECレーベルでリリースされた旧NACC-1024という商品番号ですが、いつに間にやらカメラータからの再発売となった盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー1843年 初演 メンデルスゾーン 劇音楽「真夏の夜の夢の音楽」(全曲)1883年 初演 ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲1985年 没 エミール・ギレリス(ピアニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 マリーゴールド秋花のネタも尽きてきて、こんな花を撮っています。 撮影地 大阪府和泉市 2006年10月12日
2006年10月14日
コメント(1)
-
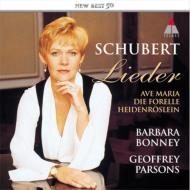
バーバラ・ボニーのシューベルト歌曲集./小紫
『今日のクラシック音楽』 バーバラ・ボニー 「シューベルト歌曲集」まだ日中は少し暑さの残る日ですが、夜になると涼しさよりも肌寒さと形容した方がいいかも知れないこの頃です。 秋に似合う音楽を聴こうと10年前の1995年3月に購入しました、アメリカのリリック・ソプラノ、バーバラ・ボニーの歌うシューベルトの歌曲集を久しぶりにCD棚から取り出してじっくりと聴いてみようと思います。 昨年のこの日も日記に書いたのがこのCDでした。 夜の帳が降りて周りの騒音もなくなり、はるか彼方の鉄路を走る電車や近所の道路を走る車の音が、一際高く聞こえてくるのも夜の静けさを強調しているようです。 そういう静寂に包まれた夜に珈琲カップ片手に聴く音楽をついつい探してしまいます。このCDの第1曲が「アヴェ・マリア」なんですが、掛け値なしに私はどなたにでもこのCDを薦めている理由がこの「アヴェ・マリア」なんです。買ってきたCDをプレーヤーに載せてボニーの声が流れ出すと、私は不覚にもはらはらと涙を流して聴いていました。胸をつかれる想いで聴いていました。こんなにクリアーで、純粋な声があるのかと思われるほど、この歌唱は尋常ならない美しさに溢れたもので、追っ手を逃れて洞窟に逃げ込んで切羽詰った状況に置かれたエレンという女性がマリアに捧げる祈りの歌。魔物たちがこの岩穴に住み着かないようにしてください。聖処女さまのやさしい聖いご加護があれば、父とわたしは定められた運命に従順に従いましょう。この乙女にやさしく身をかがめてくださいませ、父のために切なる祈りを捧げるこの子のために!アヴェ・マリア!数えきれないほどこの曲を聴いてきましたが、涙を流して聴いたのはこのボニーの歌唱だけです。CDのライナー・ノートにドイツ文学者で音楽評論家の喜多尾道冬氏が書いておられるように、この曲の詩が深い意味をもって伝わってくる歌唱だと思います。全部でシューベルトの歌曲が「アヴェ・マリア」「ただ憧れを知る人だけが」「野ばら」「ます」「水の上で」「夕映えのなかで」「糸を紡ぐグレートヒェン」「岩の上の羊飼い」など17曲収録されていますが、この「アヴェ・マリア」一曲を聴くだけでも価値のあるCDだと思います。秋の長雨も上がり、空は澄み渡ったかのような一日が終わり、夕暮れが釣瓶落としのように訪れて、夜の帳が降りた静かな秋の夜に響き渡るボニーの歌声はまるで天使の降臨かとさえ思ってしまいます。愛聴盤 バーバラ・ボニー(ソプラノ)、ジェフリー・パーソンズ(ピアノ)(テルデック原盤 ワーナークラシックス WPCS21241 1994年4月録音)↓ボニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 小紫先日既にこの花画像を掲載しましたが、構図に不満が残っていましたので、近所のおうちの垣根からぶら下がるように実をつけている「小紫」を撮ってみました。 先日の画像よりはるかにいい構図になっていましたので、今日も「小紫」を掲載することにします。 秋らしい鮮やかな紫が映えています。 撮影地 大阪府和泉市 2006年10月12日
2006年10月13日
コメント(6)
-
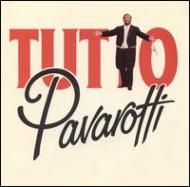
ヴェルディ 「女心の歌」/朝顔
『今日のクラシック音楽』 ヴェルディ作曲 「女心の歌」~オペラ「リゴレット」から一昨日の大阪は朝から晴れ渡った好天気で、昨日の花画像掲載の「コスモス」を撮りに環境公園に出かけて、青空の下で気分よくコスモスをカメラに収めていました。 ところが午後3時ごろから急に雲行きが怪しくなってきて、夕方からポツリ、ポツリと落ちてきました。 夜になると篠つく雨となり、それが昨日の夕方ごろまで続きました。今日は打って変わって快晴。 「女心と秋の空」とはよく言ったものです(女性には失礼になるかもしれませんが)。 そんな天気の激しい移り変わりから、ヴェルディが書いたオペラ「リゴレット」の第3幕で主人公マントーヴァ公爵が歌うアリア「女心の歌」を採り上げてみました。好色な公爵マントーヴァ(テノール)の女漁りの手伝いをする家来のリゴレットは、自分の娘ジルダが公爵に誘惑されてしまったのを知って、公爵への復讐を誓いますが最後はジルダの死を招いてしまうという悲劇を描いたオペラです。このオペラはドラマティックで、しかも音楽はとてつもなく流麗なのが特色で、「あれかこれか」 (マントーヴァ公爵)、「悪魔め、鬼め」(リゴレット)、「慕わしき人の名は」(ジルダ)、「愛する美しい乙女よ」(四重唱)、「女心の歌」(マントーヴァ公爵)などの美しい旋律のアリアが彩りを添えています。このアリア「女心の歌」は、このオペラを聴いたことがなくてもどこかで聴いたことのある歌の一つに数え上げられるほどの有名曲で、「女心は、風に舞う羽毛のようなもの。 いつも動いて落ち着かないものだ。美しい顔をして泣いたり笑ったりしているが、あれはみんな偽りだ・・・」と歌われるのですが、女性からすると「とんでもない、何てことを!」と抗議の声が上がりそうなアリアです。テノール歌手のアリア集の定番の曲となっています。今日はイタリアの偉大なテノールのルチアーノ・パヴァロッティの誕生日です。彼の得意のこの「女心の歌」を聴いてみようと思います。愛聴盤 ルチアーノ・パヴァロッティ(テノール)(DECCAレーベル 425681 1988年録音 海外盤)2枚組CDで、およそテノールなら歌いたいという有名アリアを網羅しており、2枚目はイタリア民謡・歌曲が収録されたパヴァロッティの魅力を充分に味わえる決定盤のようなディスクです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1855年 誕生 アルトゥール・ニキシュ(指揮者)1872年 誕生 ヴォーン・ウイリアムズ(作曲家)1910年 初演 ヴォーン・ウイリアムズ 海の交響曲1935年 誕生 ルチアーノ・パヴァロッティ(テノール)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 西洋朝顔この花も夏からず~と咲いているような感じで、自宅近くの公園のフェンスに絡まってまだ咲いています。 ちょっと季節はずれな感もありますが、美しい色で咲いていましたので撮ってみました。 撮影地 大阪府和泉市 2006年10月3日
2006年10月12日
コメント(4)
-
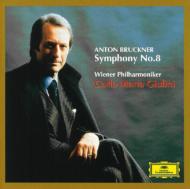
ブルックナー 交響曲第8番/コスモス
『今日のクラシック音楽』 ブルックナー作曲 交響曲第8番 ハ短調アントン・ブルックナー(1824-1896)の創作ジャンルはほぼ交響曲に限られていると言っても過言でないほど、現代では彼の作品を演奏する再現芸術家は指揮者とオーケストラにほぼ限られています。 彼は、生涯に11曲のシンフォニーを書いていますが(9番は未完)、世に認められたのは7番で「大器晩成型」の典型的な例の作曲家でした。この第8番は彼の遺した11曲の交響曲の中でも最高の傑作と呼ぶにふさわしい曲だと思います。 最も美しい、またもっとも壮大な伽藍のような、まるでアルプスを仰ぎみるようなスケールを誇る作品です。 楽器編成は大きな規模に拡大されて、ハープが3台要求されていたり、ホルンが8本要する大交響曲です。彼自身「私が書いた曲のなかで最も美しい音楽」と語っており、第3楽章「アダージョ」は特に美しさが際立っています。 彼は敬虔なカトリック教徒だったそうですが、この曲(他の交響曲にも言えることですが)には禁欲的な深い精神性と、パイプオルガンのような広大な音楽宇宙と重厚さが備わっている傑作です。ブルックナーの交響曲はオルガンを使って書かれていたそうですが、全ての交響曲に共通しているのは曲の「書式」です。 混沌とした宇宙の創造を思わせるかのような弦のトレモロで始まる第1楽章。 まるでアルプスの巨峰を仰ぎ見るかのような、宇宙的なスケールを感じさせる終楽章。 そして中間楽章は寂しさ、哀愁を湛えたアダージョと、「野人」「自然人」と呼ばれた彼の素朴さを伝えるスケルツオなどで構成されています。 ブルックナーの交響曲の特徴は顕著で、その例はいくつか挙げられます。(1)「ブルックナー開始」とよばれる曲冒頭の音楽の特徴で、弦楽器のトレモロから始まり、雄大な第1主題が浮かび上がってくるという書き方(原始霧とも呼ばれています)で、彼の交響曲のいくつかに顕著に表われています。 聴く者に何かが始まるという予感を与え、やがて宇宙の鳴動のような巨大な音楽が姿を現す前の開始音楽のことです。(2)「ブルックナー休止」という特徴があります。 普通、楽章主題が別の主題に移行する時には「経過楽句」という中間的な旋律を用意して、そのあとに別の主題を表します。 ところがブルックナーはその「経過楽句」を使わず中間的な旋律を用いないで、管弦楽全てを休止させています。唐突に楽想が変わってしまいます。 これもおそらくオルガンを使って作曲をしていたために、そのオルガン的な音楽がもろに表現されているのだと思います。(3) この方法を何と呼ばれているのか知りませんが、ひとつの音型を繰り返しながら、音楽を盛り上げていく手法も用いられていて、繰り返し演奏されるやり方はいたるところに見られます。ほぼ全曲がこのスタイルで書かれており、8番もその例に漏れません。 おそらくこれほど一貫したスタイル・書式を貫き通した交響曲作曲家は、他に誰一人としていないと思います。 それほど頑固に「スタイル」を守った人でした。その彼がウイーンで最初に熱狂的に迎えられたのが、この第8番の交響曲でした。ウイーンの音楽好きに熱狂的に迎えられるという歴史的成功を収めた初演だったそうです。そのときブルックナーは68歳。 上述のように大器晩成型の最たる例でしょう。しかもその4年後に彼には死が忍びよっていたのです。そして、1896年の今日(10月11日)、ブルックナーは72歳の生涯を閉じています。愛聴盤 カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 ウイーンフィルハーモニー(ドイツグラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG3605 1984年録音)↓ジュリーニもう1枚 カラヤン指揮 ウイーンフィルハーモニー(SONY Classical SVD46403 1988年録画 輸入盤)↓カラヤン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1830年 初演 ショパン ピアノ協奏曲第1番1896年 没 アントン・ブルックナー(作曲家)1937年 誕生 アイザック・スターン(ヴァイオリン奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 コスモス(秋桜)昨日は自宅から車で20分のところに在る「環境公園」に行ってコスモスを撮ってきました。 第3期まで花を観賞することが出来ます。 今は第2期まで花は満開でした。 11月半ばまで楽しめるそうです。 ここは四季の代表的な花だけを植えており、広大な畑のようなところに植えられています。 2月は水仙、6月はラヴェンダーといった花が一面に咲いているところです。 花畑とスポーツグラウンドのあるところです。撮影地 大阪府和泉市環境公園 2006年10月10日
2006年10月11日
コメント(14)
-

ツウィリッチ ヴァイオリン協奏曲/サツマイモの花
『今日のクラシック音楽』 ツウィリッチ作曲 ヴァイオリンと管弦楽のための協奏曲エレン・ターフィー・ツウィリッチ(1939-)については私はよく知らない作曲家ですが、アメリカのトランペット奏者で、作曲も手がけており1983年には交響曲第1番でピューリツァー賞を受賞したそうです。Naxosレーベルには珍しい、あまり知られていない作曲家や作品が多数録音されているので、毎月CDショップでチェックして1~2枚買って聴いています。この曲も昨年の11月にリリースされた世界初録音というふれ込みの1枚です。「ヴァイオリン協奏曲」は1998年に作曲されたそうですが、前衛的なところが皆無で旋律が非常に美しい現代音楽です。 伝統的な3楽章形式で書かれていて、約26分間ほどの演奏時間の作品です。曲の冒頭から実に鮮烈にヴァイオリンの美音が弾き出されるように流れてきます。 現代音楽特有の「響き」を重視した音楽ですが、わけのわからない音楽ではなくて、非常にわかりやすい音楽で書かれており、ヴァイオリンの持つ美しいメロディーラインがくっきりと浮かび上がってくる音楽です。しっとりとした情緒とか雰囲気を望むべくもありませんが、細い優美な弦の美しさをクリスタルのような響きで味わえる逸品です。SF映画のバックにでも流れてくるような現代音楽特有のテンポ、響き、和声、リズムが刻みこまれたヴァイオリンの美しい音色を、特有の響きで味わえる作品です。このCDです。 パメラ・フランク(Vn) マイケル・スターン指揮 ザール・ブリュッケン放送交響楽団↓(Naxosレーベル 8.559268 1998年10月 ドイツ・ライブ録音)カップリングはツウィリッチの「リチュアルズ(5人のパーカッション奏者とオーケストラのための)」です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』1813年 誕生 ジュゼッペ・ヴェルディ(作曲家)1919年 初演 R.シュトラウス オペラ「影のない女」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 サツマイモの花この花が自宅近くの青空駐車場の片隅で「ヤブガラシ」と一緒に咲いていました。 おそらく種が飛んできて咲いたのでしょう。 昨年はたしか咲いていなかったと記憶しています。 ヒルガオ科の花で、昼顔に似た小さな花です。撮影地 大阪府和泉市 2006年10月3日
2006年10月10日
コメント(4)
-
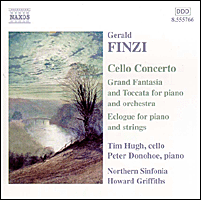
フィンジ 「ピアノと弦楽のためのエクローグ」/コリウスの花
『今日のクラシック音楽』 フィンジ作曲 ピアノと弦楽の為のエクローグ神社の秋の大祭(だんじり祭)も2日間の予定をすべて終わって今日はのんびりとした時間を過ごしています。 こんな時に聴く格好の音楽がないものかとCD棚を物色していますと、長い間聴くことのなかったジェラルド・フィンジ(1901-1956)の作品集がありました。 このCDにはチェロ協奏曲、大幻想曲とトッカータ、ピアノと弦楽のためのエクローグが収録されています。 ジェラルド・フィンジはイギリスの作曲家で、20世紀初めに生まれているにもかかわらず、その音楽はまったく前衛的、現代音楽的な情緒はなくて、ロマンの薫りがむせ返るようなリリシズムに満ちた音楽を書き残しています。晩年に書かれた作品40のチェロ協奏曲などはもっと渋みが深くなればブラームスの音楽かと思われるほどのロマンに溢れた、メランコリーな作品を残しています。この中で今日は「ピアノと弦楽のためのエクローグ」について書いてみたいと思います。「エクローグ」とは牧歌的な会話とでも訳せばいいのでしょうか、この作品ではピアノと弦楽合奏がまるで掛け合いのように交互に現れて、美しい叙情的な旋律が穏やかに展開されています。曲の冒頭からピアノ独奏が流れますが、これがとても美しく叙情的に、優しさとどこか懐かしげな雰囲気のある透明感を響かせていて、聴く者の心を捉えて離しません。 独奏のあとに弦楽合奏が奏でる旋律がとても穏やかで、そこからピアノと弦が絡み合っていきます。 しかし、美しい旋律にはどこか寂しげな情緒がたたえられており、孤独な雰囲気さえ漂う音楽です。秋の夜長のひと時に珈琲カップを手にしながら、自分の歩んできた人生を振り返りたくなるような音楽です。フィンジ28歳(1929年)の時の美しい音楽に溢れた、演奏時間11分弱の作品です。愛聴盤 ピーター・ドノホー(P) ハワード・グリフィス指揮 ノーザン・シンフォニア(Naxosレーベル 8.555766 2001年1月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 コリウスの花これは大失敗でした。 ピント合わせの位置を誤ったために漫然とした画像になってしまいました。 撮影地 大阪府和泉市 2006年9月22日
2006年10月09日
コメント(4)
-

だんじり祭
『だんじり祭』昨日は市制50周年記念事業の一つでが、和泉市だんじり大連合グループ18台が揃い、パレードが行われました。 その折の「やりまわし」(スピードを保ったまま角を曲がる危険な走行)の写真です。 今日は快晴のようです。 町の中でもうだんじりのお囃子が聞こえてきます。 今日も神社社務所詰めの合間にカメラを持ってだんじりについていきます。 提灯をつけて走るだんじりの夜の曳行を撮ろうと思っています。撮影地 大阪府和泉市 2006年10月7日
2006年10月08日
コメント(8)
-

今日からだんじり祭/キバナコスモス
『今日からだんじり祭』今日と明日は泉州一帯は燃える秋となります。 町の衆が待ちに待った年1度のお祭です。 明朝から市内の各町村でだんじりが練り歩き、風のように走り抜ける2日間です。今朝から神社ではだんじりの「宮入り儀式」が行われます。 うちの町内では2台のだんじりがありますから、その2台が揃って神社に曳行してきます。 祭の成功、だんじり走行の安全と五穀豊穣を祝う儀式が行われます。 昨日は朝からその宮入りの準備で、酒屋・八百屋・魚屋・スーパーへと、供物の発注と支払いに自転車で走り回ってきました。1台は新調のだんじりです。 すでにお披露目曳行は10月1日に終わっていますが、あいにくの雨で屋根は幌を被っていましたので、祭本番では美しい姿を披露してくれます。 今日の天気予報は「おおむね晴れ」ですから、きっと素晴らしい祭日和となるでしょう。隣町では小学校の同級生がだんじりの「総括」という責任あるポストに就いています。 その彼からだんじり曳行の写真を撮るように頼まれています。 うちの「宮入り」が終わればそちらへも行ってきます。 忙しい一日になりそうです。 昨年の秋祭りの様子です ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 キバナコスモス自転車で10分ほどの休耕田が一面にコスモスを咲かせていました。 そのうちの一つ、「キバナコスモス」です。 撮影地 大阪府和泉市 2006年9月30日
2006年10月07日
コメント(10)
-
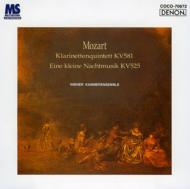
モーツアルト クラリネット五重奏曲/彼岸花
『今日のクラシック音楽』 モーツアルト作曲 クラリネット五重奏曲イ長調 W.A.モーツアルト(1756-1791)は交響曲、ピアノ・ソナタ、ヴァイオリン・ソナタなどの器楽曲、協奏曲(ピアノ、ヴァイオリン、フルート、クラリネットなどの独奏楽器)、室内楽作品(弦楽四重奏、五重奏曲、ピアノ三重奏曲、フルート四重奏曲など)、オペラ、宗教音楽などの広範囲にわたる作品をわずか35歳の生涯で書き残しています。 今年はモーツアルト生誕250年というメモリアル・イヤーということで、シューマンの没後150年やショスタコービチ生誕100年の記念年を蹴散らすかのように記念行事的な演奏会や録音などが行われています。正直言って私はモーツアルトの作品を好んで聴きたいという思いはなくて、クラシック音楽を聴いて50年以上になりますがモーツアルトの作品のディスクは、他の好きな作曲家のそれと比べますと格段に少ないように思います。 また年に聴く回数も他の有名作曲家に比べて少ないのです。 では嫌いかと訊かれると、決してそうではありません。 ロココ風の華やかさがあまり好きではないのかもしれません。 交響曲でもハイドンの端正な音楽の方がお気に入りなんです。そんなモーツアルトの作品の中で、掛け値なしに好きなのが「クラリネット五重奏曲イ長調」です。クラリネットはモーツアルトによってオーケストラの楽器群の中で、一際輝くような楽器となったのが「クラリネット協奏曲」です。この曲は1789年に書かれていますから、モーツアルトが亡くなる2年前にあたります。 その頃のモーツアルトは華やかなピアノ演奏家としての30歳前の生活はどこかへ行ってしまい、借金まみれの生活であったそうです。 借金で苦しむモーツアルトにいつも手を差伸べていたのが、アントン・シュタットラーというクラリネット奏者でした。 記録によれば当時彼のクラリネット演奏は右に出る者がいないほどの名手だったそうです。 経済的な援助を与えたばかりでなく、モーツアルトに書かせたクラリネットの曲がこの五重奏曲であり、協奏曲でした。 その頃にはまだクラリネットはオーケストラの中でも市民権のもたない楽器で、宮廷オーケストラでもこの楽器がなくて、必要な時だけ奏者を呼んでいたと言うのが実情だったそうです。モーツアルトはシュタットラーの演奏を聴いていたく感動して交友が始まったそうです。 シュタットラーは金銭面での功労だけでなくて、クラリネットを世に出した最大の功労者かも知れません。この曲は、そんな借金生活の中からこれほどの美しい、優美さ、典雅さ、気品、光のような輝きと影、優しさと愁いに満ちた音楽が生み出されているのが、まさに奇跡としか言いようがありません。 第1楽章冒頭からいきなり典雅な佇まいの主題が現れると、何度聴いても涙がこみ上げてきます。 それほど苦しい生活の中で、どう心を収めればこのような美しい音楽が書けるのかと。 まるで自分の死の予感を感じているように透明な音の響きに驚かされます。私の一番好きなモーツアルトの作品です。 今日は「仲秋の名月」。 天気が良くないかもしれませんが、久しぶりにこの曲にどっぷりと浸かってみたいですね。愛聴盤 アルフレート・プリンツ(Cl) ウイーン室内合奏団員 (DENON CREST1000シリーズ COCO70672 1979年9月録音)以前はブラームスのクラリネット五重奏曲とのカップリングでしたが、ディヴェルトメントとのカップリングになっています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1882年 生誕 カルロ・シマノフスキー(作曲家)1886年 生誕 エトヴィン・フィッシャー(ピアニスト)1969年 初演 ショスタコービチ 交響曲第14番「死者の歌」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 彼岸花9月22日に長居植物園を訪れた際に撮りました赤と白の彼岸花です。 この花ももう終わりですね。今日も道端で群生しているのを見かけましたが、無残な姿で咲いていました。 撮影地 大阪市立長居植物園 2006年9月22日
2006年10月06日
コメント(10)
-
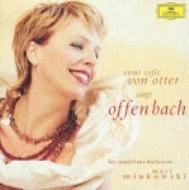
オッフェンバック オペラ・アリア集/小紫
『今日のクラシック音楽』 オッフェンバック アリア集2002年11月にメゾ・ソプラノのアンネ・ソフィ・フォン・オッターが実に珍しいオッフェンバックのオペラ・アリア集をリリースしています。 今では舞台で観ることのできないオペラもあり、非常に価値のあるアルバムだと思います。ジャック・オッフェンバック(1819-1880)はフランスのオペレッタ作曲家として名を残しており、「ホフマン物語」「天国と地獄」などのオペレッタが特に有名で、私もこの2つのオペラ以外で知っていうのは「美しきエレナ」くらいです。 今日の話題を書くために少しオッフェンバックについて予習をやってみたのですが、彼は1850年にコメディ・フランセーズの作曲家になってオペレッタの下地が出来ていったようです。そして、彼を一躍有名にしたのが「天国と地獄」で1858年に初演されて、その後1860年にこの「天国と地獄」がウイーンにも紹介され爆発的な人気を得たようです。 オッフェンバックのこの「天国と地獄」が、ウイーンのスッペ、シュトラウスIIなどに影響を与えて、ウイーン風オペレッタが出来上がっていったそうです。 謂わば、ウイーンのオペレッタの祖でもあったわけです。そんなオッフェンバックが書いたオペレッタからアリアを選んで、パリで行われた演奏会でのライブ録音がこのCDです。1喜歌劇 「ジェロルスタン女大公殿下」 から 担え銃! / 皆さんは危険がお好き・・・ああ、軍人さんが好きなのよ2 喜歌劇 「ジェロルスタン女大公殿下」から ええ、将軍さん、ある方があなたのことを愛しているの・・・3 喜歌劇 「ジェロルスタン女大公殿下」 から 軍人たちの歌 ああ!これが有名な連隊ね4 喜歌劇 「ファンタジオ」から ごらん、黄昏の中5 喜歌劇 「ファンタジオ」から なんと魅力的なささやきが突然聞こえてくるのだろう?6 喜歌劇 「レウ゛ュー・カーニウ゛ァル」から 未来の交響曲 - 婚約者たちの行進曲 7 喜歌劇 「大公夫人」から アルファベットの六重唱8 歌劇 「ホフマン物語」 第3幕 - 間奏曲とホフマンの舟歌 美しい夜、おお、愛の夜 9 喜歌劇 「美しきエレーヌ」 から 美しい青年たちの死に10 喜歌劇 「青ひげ」 から 村のには羊飼いの娘たちがいて11 喜歌劇 「青ひげ」 から 大オーケストラのための序曲12 喜歌劇 「リッシェンとフリッツヒェン」 から 私はアルザス生まれ / 僕はアルザス生まれ13 喜歌劇 「パリの生活」から 第2幕の終曲 我らはこの家に入るのだ14 喜歌劇 「鼓手長の娘」から 輝かしい称号なんて私にはどうでもいい15 喜歌劇 「ペリコール」 から ほろ酔いのアリエッタ ああ!なんという食事をとったのかしら16 喜歌劇 「地獄のオルフェ (天国と地獄)」から 地獄のギャロップ聴いてみればわかりますように、とにかく楽しいアリアを彼のオペラから選び、ミンコフスキー指揮するルーブル宮音楽団のサポートを得て、録音としては初めてというオッターのアリア集は、聴いていて体が浮きそうになるくらいに、明るく、楽しい音楽に満ち溢れています。そのオッフェンバックが1880年の今日(10月5日)、パリで61歳の生涯を閉じています。 愛聴盤 アンネ・ソフィー・フォン・オッター(Ms)、マルク・ミンコフスキー指揮 ルーブル宮音楽団(ドイツ・グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・クラシックス UCCG1135 2001年12月パリ・ライブ録音)↓フォン・オッター廉価輸入盤はこちら↓輸入盤フォン・オッター1975円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1792年 初演 グルック オペラ「オルフェオとエウリディーチェ」 1880年 没 ジャック・オッフェンバック(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 小紫この木も実をつける時期になりました。 町内の家々の垣根や庭に紫の小さな実が色づいています。撮影地 大阪市長居公園 2006年9月22日
2006年10月05日
コメント(8)
-
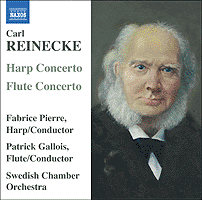
ライネッケ 「ハープ協奏曲」/ヨウシュヤマゴボウ
『今日のクラシック音楽』 ライネッケ作曲 ハープ協奏曲ホ短調 OP182カール・ライネッケ(1824- 1910)は作曲家でもあり、ピアノ演奏家、指揮者、教育者でもあった、現代で言えばマルチタレントとなる音楽家になるでしょう。ドイツの前後期ロマン主義時代を生きた音楽家とも言えるほどに86歳の長命者でした。 メンデルスゾーンやシューマンにピアノを師事しており、20歳を過ぎてはフランツ・リストの娘コジマのピアノの先生も務めています。36歳(1860年)の時にはライプチッヒ・ゲヴァントハウスの指揮者に就任しており、ブレーメンでブラームスの「ドイツ・レクイエム」の世界初演の指揮者でもありました。 またライプツィヒ音楽院の教授も兼ねており、門下生にブルッフ、グリーグ、スヴェンセン、シンディング、ヤナーチェク、アルベニスなどの生徒がいたそうです。若い頃にはメンデルスゾーンやシューベルトの影響もあったそうですが、ブラームスとの親交が大きくライネッケの作風を変えたと言われています。 堅牢な構成による作品を多く書くようになったそうです。作品には交響曲(3曲)、ピアノ協奏曲(4曲)、ハープ協奏曲、フルート協奏曲などがあり、実際に彼が書き残した作品は1000を超すだろうと言われているくらいに多作家だったようです。 ピアノ作品だけでも膨大な数にのぼると言われています。そのライネッケの書いた「ハープ協奏曲」。 最初は癒し系のBGMのような音楽かと思って聴き始めますと、なかなかどうして、これが本格的な協奏曲なのには驚きました。第1楽章からしてすでに当時のドイツ・ロマン主義音楽のような旋律が流れてきます。 和声はブラームスのように堅牢・強固ですが、メンデルスゾーンのような流麗な旋律に満ちており、均整のとれた造型で、音楽はあくまでも美しく、聴く者を至福の時空に誘ってくれます。曲は3楽章形式で、第1楽章は上述のようにドイツ・ロマン主義の王道を歩くかのような堂々とした音楽で、そこにハープ特有の美しい音色が鳴り響く、伝統的なアレグロ・モデラートです。私が一番好きなのは第2楽章のアダージョで、ハープの奏でる優しく、抒情的な旋律がとても美しく響いています。これは全くの拾い物の音楽でした。このCDです。 ファブリス・ピエール(ハープ) パトリック・ガロア指揮 スウェーデン室内オーケストラ↓ (Naxosレーベル 8.557404 2004年10月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1916年 初演 R.シュトラウス オペラ「ナクソス島のアリアドネ」1959年 初演 ショスタコービチ チェロ協奏曲第1番1982年 没 グレン・グールド(ピアニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ヨウシュヤマゴボウもうすでにこの花も盛りを過ぎていますが、今でも道端や空き地、公園、林の中などで観られます。 この被写体は花としては盛りを過ぎていますが、これから実に成っていこうとしているところがよくわかります。 撮影地 大阪府和泉市 2006年10月3日やまごぼう科 ヤマゴボウ属 開花時期 7月ごろ 実がなって黒く熟し、ぶどうのような形をした実がいっぱいついています。 つぶすと赤紫の汁が出ます。 昔は赤インクとして使ったようです。
2006年10月04日
コメント(4)
-

バッハ ヴァイオリン協奏曲/アレチヌスビトハギ
『今日のクラシック音楽』 J.S.バッハ ヴァイオリン協奏曲ホ長調 BWV1042大バッハには「ケーテン時代」と呼ばれる時期があります。1717年から1723年までの時代で、アンハルト・ケーテンの領主であったレオポルド公に仕えた時期のことで、バッハ65年の生涯で最も恵まれた時代で、彼自身が「わが生涯で最良の年」と語ったそうです。それはレオポルド公が大の音楽好きで、自身もヴァイオリン、チェロ、チェンバロを弾きこなす人だったそうです。 バッハは安定した生活の中で、この5年間で実に多くの作品を書いています。「管弦楽組曲」「ブランデンブルグ協奏曲」「無伴奏チェロ組曲」「無伴奏ヴァイオリン・ソナタ」「平均率クラヴィーア曲集第一巻」などがその時代の代表的な作品です。今日の話題曲「ヴァイオリン・協奏曲」も同じ時期に書かれたと言われています。バッハはその生涯で3曲のヴァイオリン協奏曲を書いたと言われていますが、実際にはもっと多くの協奏曲が書かれていたのではないかと想像されているそうです。 それはチェンバロ協奏曲の数曲に失われたと思われている、ヴァイオリン協奏曲の編曲と考えられる作品があることから想像されているそうです。このホ長調の作品は、急ー緩ー急の3楽章形式で書かれていて、第1楽章の明るい主題がとても印象的で、バッハの作品中でも最も好まれている音楽だと言われる通り、演奏が始まると思わず体を乗り出してしまうほどの美しい音楽が展開しています。第2楽章も美しい旋律に溢れています。 繰り返し演奏されるバス音型に独奏ヴァイオリンが優美な旋律を歌っています。第3楽章は舞曲風の実に楽しい雰囲気・情緒の音楽です。秋本番の夜にでも聴く格好の曲だと思います。愛聴盤 ジェラール・ジャリ(Vn) ジャン=フランソワ・パイヤール指揮 パイヤール室内管弦楽団(エラート原盤 BMGビクター B15D-39182 1978年4月録音 廃盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1923年 誕生 スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ(指揮者)1931年 没 カール・ニールセン(作曲家)1967年 没 マルコム・サージェント(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 アレチヌスビトハギ長居植物園のツバキ園を歩いていますとこの花が道端に咲いていました。 ここは「ミソハギ」がまるで壁のように長く続いて遊歩道脇で咲いていますが、この「ヌスビトハギ」は群生でなくて、どこかから種が飛んできて咲いているような風情でした。撮影地 大阪市立長居植物園 2006年9月22日
2006年10月03日
コメント(6)
-

武満 徹の映画音楽/彼岸花
『今日のクラシック音楽』武満 徹の映画音楽 「鈴木大介~夢の引用」このディスクは武満 徹の映画音楽のスコア通りに演奏されたものでなく、鈴木大介(ギタリスト)が自分でイメージした武満 徹の映画音楽を好きなように弾いています。 収録曲は下記の通りです。1. 「太平洋ひとりぼっち」 1963年 市川 昆監督 石原裕次郎2.「伊豆の踊子」 1967年 恩地日出男監督 内藤陽子 黒澤年男3.「ヒロシマという名の少年」 1987年 菅田良哉監督 西村 学4. 「あこがれ」 1966年 恩地日出男監督 内藤陽子 田村 亮5.「素晴らしい悪女」 1963年 恩地日出男監督 団 令子 久保 明6.「狂った果実」 1956年 中平 康監督 石原裕次郎 北原三枝 7.「日本の青春」 1968年 小林正樹監督 藤田まこと 黒澤年男鈴木大介、ブランドン・ロス、ツトム・タケイシの3人が奏でるギターによる武満 徹の映画音楽の世界を甘く、切ないまでに愁いの帯びた音色で彩られており、上記の映画をすべて観ていますので、目をつぶれば懐かしい映画のシーンが目に浮かんできます。 秋も深まってきた夜に、ウイスキー・グラスでもいいし、珈琲カップでもいい、そういう空間にとても似合うお洒落な映画音楽のひと時が味わえる、そんなディスクです。ディスクのタイトルは武満 徹の2台のピアノとオーケストラのための「夢の引用~Say sea,take me!」(1991)から取ったそうです。このCDです。(Intoxicate レーベル INTD-1009 2006年6月録音)先月6日にリリースされた今年6月の新録音盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1913年 初演 ディーリアス 「春、はじめてのカッコウをきいて」「河の上の夏の夜」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 彼岸花彼岸花の季節ももう終わってしまったようです。 いまでも畑や田圃、公園の植え込み、道端などで咲いているのを見かけますが、すでに盛りを過ぎたものばかりです。 彼岸花のシベを狙って撮ってみました。撮影地 大阪市立長居植物園 2006年9月22日
2006年10月02日
コメント(2)
-

露草/新調だんじりの入魂式
ともの『今日の一花』 露草今までにも何度も掲載している「露草」ですが、群生しているところを見つけました。自宅から徒歩わずか3分という青空駐車場の隅の空き地に咲いていました。 あまり足の踏み入れるところでないので、今までに気づかずにいたようです。撮影地 大阪府和泉市 2006年9月26日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『新調だんじりの入魂式』町が新しい「だんじり」を発注したのがすでに入荷しています。 この新調の「だんじり」を町内でお披露目曳行する前に、神社でお払いを受けて「だんじり」に魂を入れる「入魂式」が今日神社で行われます。 もういつ「だんじり」が来てもいいように神社の準備は済ませてありますが、8時半から始まる「入魂式」に合わせて、私を含めた神社役員14名が今朝7時に集まります。「だんじり」の画像は帰宅してから追記掲載致します。町はもうすでに「秋祭り」の雰囲気が漂っていて、神社や目抜き通りには寄付された提灯がずらりと吊るされています。 入魂式の後に町内をくまなくお披露目曳行が行われ、午後は「試験曳き」という祭前に行われる恒例の曳行があります。今日は泉州一帯の町内で一斉にこの「試験曳き」が行われて1週間後の(10月7日ー8日)「本祭り」に備えます。 今年も泉州が燃える秋の季節がやってきました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1865年 誕生 ポール・デュカス(作曲家)1904年 誕生 ウラディミール・ホロヴィッツ(ピアニスト)
2006年10月01日
コメント(10)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- ☆モー娘。あれこれ☆
- 【村越彩菜・島川波菜(ロージークロ…
- (2025-11-25 13:10:04)
-
-
-

- 人気歌手ランキング
- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…
- (2025-11-15 04:58:28)
-
-
-

- 洋楽
- ジョ・ジョ・ガン 『ジャンピング・…
- (2025-11-25 04:17:42)
-







