2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年03月の記事
全32件 (32件中 1-32件目)
1
-
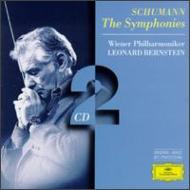
シューマン 交響曲第1番「春」/もうすぐ春爛漫/雪柳
『今日のクラシック音楽』 シューマン作曲 交響曲第1番 変ロ長調「春」ロマン派音楽の代名詞のような作曲家ロベルト・シューマン(1810-1856)は、紆余曲折、困難を乗り越えてクララ・ヴィークと結婚をしたのが1840年でした。 この1840年は、シューマンにとって「歌の年」と言われるほどに歌曲を数多く書いた年でもあり、2年後の1842年にはピアノ四重奏曲などの室内楽の名作を多く書いています。その「歌の年」と「室内楽の年」の間の1841年に書かれた曲に交響曲第1番「春」があります。 シューマンの功績は勿論自作の美しい音楽を遺していることなのですが、もう一つ、シューベルトの交響曲第9番を発見したことも挙げられます。 シューマンによって陽の目を見たこの曲は、彼自身に交響曲を書く意欲を与えたと言われています。そして、ドイツの詩人アドルフ・ベッツガーの「谷間に春が燃え立っている」という詩を読んで「春」というインスピレーションを得て、シューマンは交響曲第1番を書き、自ら「春」というタイトルを付けたと言われています。各楽章には春への想いを込めて、それぞれに「たそがれ」「楽しい遊び」「春たけなわ」などの楽想の言葉を書いていたそうです。第1楽章の序奏でホルンとトランペットがまるで「春の到来」を告げるようで、続いて春の暖かな空気を思わせる第1主題によって「春の気分」を漂わせており、この雰囲気が全曲を支配しています。シューマンの交響曲はベートーベンやブラームス、シューベルトなどに比べるとオーケストレーションに見劣りしていることは、聴いていても感じられることですが、シューマンのほとばしる情熱は楽想として感じられ、若々しい気分を湛えている佳品です。私が高校2年生の頃(1962年)にはハイドン、モーツアルト、ベートーベン、シューベルト、ブラームス、チャイコフスキー、ドヴォルザークやショスタコービチなどの交響曲を聴いており、シューマンのそれはこれら交響曲作曲家の曲に比べて劣るものと先輩から聴かされていましたので、聴きたいとは思っていてもLP盤の購入までに至らずに時間が経過して、1970年頃にやっとカラヤン/ベルリンフィルのLP盤を買うことによってシューマン体験をすることになりました。ロマンいっぱいの音楽に惹きこまれていきました。 今では古典派の交響曲よりも聴く機会が多い作曲家となっています。その交響曲第1番「春」が1841年の今日(3月31日)、メンデルスゾーンの指揮でライプチッヒ・ゲバントハウス管弦楽団によってライプチッヒで初演されています。愛聴盤 デビィッド・ジンマン指揮 トーンハレ管弦楽団 (Arte Nova 82876.57743 2003年10月録音 海外盤)鋭く情感豊かなフレージングと、躍動する生命力のある弾力的なリズムの扱い、平面的な部分がまったくなく、非常にテンションの高い演奏で、聴いていて実に爽快な気分になります。 最近のシューマンの交響曲のディスクでは、ジョージ・セルとベルリンフィルの2番のシンフォニーと共に特筆すべき秀演だと思います。 2枚組CDでシューマンの4曲が全部収録されていて1000円のお買い得盤です。↓ジンマンレナード・バーンスタイン指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団(ドイツ・グラモフォン 453049 1984年ライブ録音 海外盤)バーンスタイン特有の生命力にあふれた熱演で、どのフレーズにも生き生きとした爆発するような生命が宿る名演。 このディスクによってシューマンの素晴らしさを教えられた記念すべき録音盤です。 現在ではこの紹介盤が1500円で求められる廉価盤となっています。↓バーンスタイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1732年 生誕 ヨゼフ・ハイドン(作曲家)1794年 初演 ハイドン 交響曲第100番「軍隊」1841年 初演 シューマン 交響曲第1番「春」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『もうすぐ春爛漫』昨日、自転車にカメラを積んでソメイヨシノの開花状況のチェックを兼ねて近所の桜名所の公園に行きました(先日寒桜を撮影した画像をアップした公園)。 まだ蕾が固いのですが、もう開花する寸前でした。 今年は昨年に比べて1週間ほど開花が遅れているようです。 桜の開花のさきがけと言われる白木蓮や紫木蓮が満開で、花壇には色とりどりのパンジーやプリムラ、ストックなどが咲いており、気が付かずに見落としてしまう「仏の座」や「犬ふぐり」「姫踊子草」が雑草の中で満開になっており、垣根として植わっている「雪柳」の白い花も五分咲きで、木の頭部はすでに真っ白になっています。しかし「寒の戻り」でしょうか、気温10度、強い季節風が吹き渡っていて冬のように寒い一日でした。それでも「春の訪れ」はここかしこに見ることができます。畑には赤や白のエンドウの花が満開です。ソラマメの花も咲いています。 黄色い菜の花の傍で、珍しい紫花菜がひっそりと春を迎える準備のように、小さな紫の花を咲かせていました。 黄色いタンポポも「おらが春」と言わんばかりにお日さまに向かって精いっぱいの背伸びをしていました。これで桜が満開になれば、いよいよ「春爛漫」の季節になります。 桜満開を待つ、ともさんの「花便り」でした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 雪柳公園や家の庭などに白い花を咲かせています。これから4月下旬頃まで楽しめる花の一つです。 今日は木全体でなくて可愛い様子の一部分をマクロレンズで撮影した画像をアップしました。撮影地 大阪府和泉市 2006年3月24日
2006年03月31日
コメント(4)
-
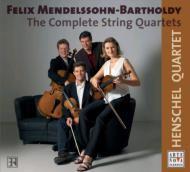
メンデルスゾーン 弦楽四重奏曲/オランダ耳菜草
『今日のクラシック音楽』 メンデルスゾーン作曲 弦楽四重奏曲メンデルスゾーン(1809-1847)と言えば、超有名なホ短調の「ヴァイオリン協奏曲」や「スコットランド」「イタリア」「宗教改革」などの交響曲、劇音楽「真夏の夜の夢」、ピアノ曲「無言歌集」などが浮かんできます。 それに「歌曲」、オラトリオ「エリア」などの声楽曲、大バッハの「マタイ受難曲」の初演、それにライプチッヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団での指揮活動などが挙げられます。彼は裕福な銀行家の御曹司として生まれ育った作曲家ですが、神さまは「人生」に長く留まることを許さず、わずか38歳で生涯を閉じています。その38年間の短い人生の中でメンデルスゾーンはこれらの音楽を作りだしており、抒情性にあふれた美しい旋律の音楽を書き残しています。特に彼が観た風景の描写はとても素晴らしい音楽として作られており、「音の風景画家」(ワーグナー)と呼ばれたほどでした。一方、メンデルスゾーンは数多くの室内楽作品も書き残しています。 弦楽八重奏曲やピアノ三重奏曲などが有名ですが、そのほかにも「チェロソナタ」や、「クラルネットソナタ」、「ヴァイオリンソナタ」、「ピアノ四重奏曲」、「弦楽四重奏曲」なども書いています。弦楽四重奏曲は、ハイドンやモーツアルトの時代には「サロン風」といったハウスムジーク(家庭音楽)の趣きのある音楽で、ベートーベンに至ってより明確に人間の心の叫びや魂の慟哭などが描かれるようになりました。その後、弦楽四重奏曲はシューベルトに代表されるように、ハウスムジークから解き離れたかのように、抒情性溢れるロマン音楽として結実しています。 ロマンの香りが濃厚で、音の色彩が豊かに書かれるようになってロマンが匂いたつかのように羽ばたいています。メンデルスゾーンの室内楽作品もそうして曲趣に入るもので、はちきれんばかりの「歌」に溢れ、色彩豊かに「ロマンの風」を運んでくるような音楽です。全部で6曲ありますこの弦楽四重奏曲もその例に漏れず、家庭のサロンから広い野原へと解放されて飛び出したのような、美しい「歌」と豊かな色彩の変化の妙を味わえる傑作の一つです。先日近所の友人から紹介盤が届きました。 この曲・演奏で楽しんでくれたらいいという意味だと思います。まだ全曲を聴いていないのにこれを書くのは乱暴な話ですが、この3枚組CDによって私の耳がまたメンデルスゾーンの室内楽の世界を求め出したのは間違いのないことだと感じています。このCDです。 ヘンシェル弦楽四重奏団(ARTE NOVA 82876640092 2002-2041年録音 海外盤)第1番から第6番全曲を3枚のCDに収録されて1,370円とはお買い得です。↓ヘンシェル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1879年 没 テオドーロ・コットウラ(作曲家 サンタ・ルチアで有名)1941年 初演 ブリテン 「戦争レクイエム」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 オランダ耳菜草先日アップしました同じ花が開花しました。 今日はもう一度その花をアップします。撮影地 大阪府和泉市 2006年3月28日なでしこ科 学名 オランダ耳菜草 ヨーロッパ原産で帰化植物です。 道端・畑や空地でよく見かける雑草花です。 「はこべ」や「ペンペン草」と一緒に咲いているのをよく見かけます。 花は小さい5弁花です。 葉が「ねずみの耳」に似ていて、食用にもなるところから「耳菜草」と呼ばれているそうです。
2006年03月30日
コメント(0)
-
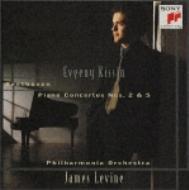
ピアノ協奏曲第2番/はこべ
『今日のクラシック音楽』 ベートーベン作曲 ピアノ協奏曲第2番変ロ長調ベートーベン(1770-1827)はピアノ協奏曲を5曲書き残していて、そのうち第3番から第5番までは演奏される機会が初期の第1番、第2番より多いのは否めない事実です。 彼のピアノ協奏曲のディスコグラフィを見てもやはり3番から5番が圧倒的に多く録音されています。この第2番は作品番号19で初期の作品ですが、彼が一番最初に書いたピアノ協奏曲で後に書いた第1番の方が先に楽譜出版されたので、順番が入れ替わっています。 またこの第2番はベートーベン自身が初めて公開演奏会でピアノを弾いた曲として記録されているそうです。第1番もそうですが、この第2番もいかにも「青春の息吹」といった感のある曲で、ピアノは軽く響き繊細な音色が特徴のように聴こえてきます。3楽章という伝統的な協奏曲形式で書かれており、オーケストラ編成は大きな規模でなく室内管弦楽団のような編成で、金管はホルンだけ、クラリネットもトランペットも、ティンパニーの使用もない編成になっています。一方、ピアノは上述のように繊細な響きと即興的な雰囲気があります。 まだ耳の病気もない頃に書かれていて「青春」が曲想から匂い立ってくるような音楽です。 リズミカルな主題と旋律的な主題から成る協奏風の第1楽章はいかにも若書きといった軽い感じにまとまっています。 第2楽章はピアノに技巧を感じさせる幻想的な気分の音楽となっています。 この曲の白眉は第3楽章だと思います。 ピアノ独奏でロンド主題が愛らしく奏でられるのは、とても可愛いと感じています。 続く副主題はまるでメルヘンを想わせるような旋律で可憐です。1795年の今日(3月29日)、このピアノ協奏曲第2番がベートーベン自身のピアノ独奏でウイーンで初演されています。愛聴盤 エフゲニー・キーシン(P) ジェームズ・レヴァイン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 (SONYレーベル ソニー・ミュージック SRCR2616 1997年録音)キーシンのピアノがとても美しい演奏で清々しいほどのベートーベンが聴ける録音盤。↓キーシンクラウディオ・アラウ(P) サー・コリン・ディビス指揮 シュターツ・カペレ・ドレスデン(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP3211 1987年録音)アラウの武骨なスタイルとドレスデンの純ドイツ風の重厚な響きが溶けあったアラウ最晩年の名演盤で、第1番~第5番までお薦め録音盤。↓アラウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1795年 初演 ベートーベン ピアノ協奏曲第2番1877年 初演 スメタナ 弦楽四重奏曲第1番「わが生涯より」1979年 初演 チャイコフスキー オペラ「エフゲニー・オネーギン」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 はこべ春が来て嬉しいのは畑の畦道、野原、空き地、道端、公園などに咲いている可憐な小さな雑草花を観ることが出来ることです。 この「はこべ」もよく目を凝らして見ないと見過ごしてしまう、ほんとに小さな花の一つです。自宅近所の畑の畦道にひっそりと群生して咲いていました。撮影地 大阪府和泉市 2006年3月28日なでしこ科 ハコベ属 春の七草(せり なずな ごぎょう はこべら ほとけのざ すずな すずしろ)の一つ。 小さく白い5弁花を咲かせています。
2006年03月29日
コメント(10)
-
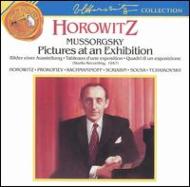
組曲「展覧会の絵」/寒桜
『今日のクラシック音楽』 ムスルグスキー作曲 組曲「展覧会の絵」モデスト・ムソルグスキー(1839-1881)の代表作として最も有名な曲が組曲「展覧会の絵」です。ムソルグスキーはロシアの色彩濃厚な民族的音楽を書き残しています。彼の音楽のどれを切っても「ロシアの大地」があふれ出てくると表現してもいいほどに、最もロシア的な旋律と色彩を塗りこめた音楽に満ちています。42歳という若さで生涯を閉じたムスルグスキーは、晩年はアルコール中毒となり、貧困と精神錯乱状態にあえぎながら亡くなったと言われています。 そうした悲惨な晩年を支えてくれた友人が一人いました。ヴィクトル・ハルトマンというムソルグスキーと同年輩の芸術家で、建築や絵画で認められていた人だそうです。ムソルグスキーとハルトマンの親密な交友期間はわずか4年間だったそうですが、生活苦の中にいるムソルグスキーに手を差し伸べていた貴重な友人だったようです。そのハルトマンが心臓病のために37歳で急死したのです。 友人たちによってハルトマンの遺作展覧会が1874年に開かれて、それを観たムスルグスキーが亡き友人の思い出のために個々の絵画を観た印象を書いたのが組曲「展覧会の絵」です。10枚の絵を採り上げているのですが、曲の冒頭に「プロムナード」が置かれており、今から絵を鑑賞しますよといった意味のテーマが演奏された後に第1曲へと移っていきます。 絵から絵に移るたびにこの「プロムナード」が効果的に表われてきます。私が最も好きな部分は「古城」の侘しげな表情を伝える旋律、目の前を通りすぎていくかのような描写の見事な「牛車」それに最後の壮大な伽藍を思わせる「キエフの大門」です。10枚の絵の印象をピアノで多彩に描いており、実に個性的な作品です。ピアノで紡ぎ出される1枚、1枚の絵の印象を頭の中で「どんな絵なんだろう」と想像することはとても楽しいひと時です。しかし、この曲はムスルグスキーの生前には公開で演奏されることなく、彼の死後6年を経て楽譜が出版されたそうです。現在最も人気のある曲の一つに数えられていますが、20世紀になってモーリス・ラヴェルやストコフスキーなどによって、このピアノ曲を管弦楽演奏用に編曲されていっそう華麗な色彩の音楽となって生まれ変わったからでしょう。特に「オーケストラの魔術師」と言われたラヴェル編曲版が最も有名で編曲版として定着しているようです。1881年の今日(3月28日)、ムスルグスキーは42歳で亡くなっています。愛聴盤 ウラディミール・ホロヴィッツ(ピアノ)(RCAレーベル 09026.60526 1947年録音 海外盤)原曲版ではなくて、ラヴェルの管弦楽版をホロヴィッツがピアノ版に編曲して弾いているので、原曲ピアノ版よりも色彩豊かに鳴り響いている音楽です。エフゲニー・キーシン(ピアノ)(RCAレーベル 09026.63884 2001年録音 海外盤)オーケストラ版(ラヴェル編曲)ではアルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団(RCAレーベル 60321-2RG 1943年録音 海外盤)シャルル・デュトワ指揮 モントリオール交響楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD5037 1985年録音)ヴァレリー・ゲルギエフ指揮 ウイーンフィルハーモニー(Philipsレーベル 468526 2000年録音 海外盤)オーケストラ版(ストコフスキー編曲)では、オリヴァー・ナッセン指揮クリーヴランド管弦楽団(ドイツ・グラモフォン 457646 1995年録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』 1801年 初演 ベートーベン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」1871年 誕生 ウィレム・メンゲルベルグ(指揮者)1871年 初演 チャイコフスキー 弦楽四重奏曲第2番 (アンダンテ・カンタービレが有名)1881年 没 モデスト・ムスルグスキー(作曲家)1903年 誕生 ルドルフ・ゼルキン(ピアニスト)1943年 没 セルゲイ・ラフマニノフ(ピアニスト・作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 寒桜この桜には名札がかかっていて「寒緋桜」と書いてありますが、私にはこれは「寒桜」だと思います。 「緋」の薄い色かと思っていましたがやはり「寒緋桜」はもっと「緋色」の強い色の桜なので、「寒桜」と訂正しておきます。撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2006年3月24日
2006年03月28日
コメント(8)
-

組曲「グランド・キャニオン」/寒桜
『今日のクラシック音楽』 グローフェ作曲 組曲「グランド・キャニオン」テンガロンハットを被り、鹿皮服を着た粋なクリント・イーストウッドが、馬上で短くなった細い紙煙草を口の端に咥えている。彼の足元には断崖が鋭く切り立っていて、遥か下にはコロラド川の急流が流れている。空はどこまでも澄んで青く、朝の太陽の陽射しが深い渓谷を光と暗を分けている。陽射しの当たる渓谷は金色に輝き、その反対側は暗い闇の様。馬上のクリント・イーストウッドのシルエットが美しい。アメリカの作曲家ファーディ・グローフェ(1892-1972)の書いた組曲「グランド・キャニオン」の第1曲「日の出」を聴くたびに、こういう西部劇シーンを想い起こします。 アメリカを代表するアメリカらしい風景に、ナイヤガラ瀑布とコロラド峡谷のグランド・キャニオンがあります。 グローフェはそのコロラド峡谷を音楽で描いたのが組曲「グランド・キャニオン」です。アメリカ南西部アリゾナ州にある国立公園。 世界の七不思議の一つ。ロッキー山脈から流れ出たコロラド川が数百万年の長い間侵食作用を起こして出来た峡谷です。 長さ450キロ、深さ1500メートル、幅は6km-28kmまである、とてつもない自然が創り上げたスケールの峡谷。 地層は堆積年代ごとに色が変わり、陽射しによって輝くさまは神秘的です。 30年ほど前に訪れてその途方もない規模と美しさに声も出なかったことが思い出されます。この曲は、その大峡谷を5つの風景で紹介しています。 順番に「日の出」「赤い砂漠」「山道を行く」「日没」「豪雨」という風景です。 これらを色彩豊かに描いています。 ガーシュインの「ラプソディ・イン・ブルー」をオーケストラ版に編曲したグローフェ。 ここでも変わりいく風景を、色彩感と迫力いっぱいに描いています。 「豪雨」では、多彩さ、迫力の凄さで、昔からステレオ録音の優秀さを競う格好の音楽となっています。 実にアメリカ的な風景を音楽で書いたグローフェは1892年の今日(3月27日)生まれています。 グローフェの誕生日にちなんで、この「グランド・キャニオン」を聴いてしばし大峡谷に遊ぶことにしましょう。愛聴盤 アンタル・ドラティ指揮 デトロイト交響楽団 (DECCA原盤 ユニヴァーサルクラシック UCCD5049 1981-82年録音)DECCA特有のピラミッド型に広がるダイナミックレンジがひろく、奥行き感も深い超優秀録音盤で、移り変わる大渓谷の表情を見事にとらえています。↓ドラティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1892年 生誕 ファーディ・グローフェ(作曲家)1927年 生誕 ムスティスラフ・ロストロポービチ(チェリスト・指揮者)1927年 初演 コダーイ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 寒桜市内有数の桜の名所公園で早咲きの「寒桜」が満開の花びらをつけています。 3月24日の晴天に誘われてカメラ持参で出かけました。 この公園内には遊歩道が回りに設けられています。 その遊歩道を早足で散歩を楽しむ人たちの中に、小学校の同級生たちもいて撮影の合間に言葉を交わすことが出来て、気分のいい撮影日和でした。 撮影はすべて逆光からの影を使った画像となりました。(追記)以前から疑問に思っていたのですが、この桜は「寒緋桜」でなくて「寒桜」だと思います。 寒緋はもっと「緋色」が濃い桜なので、この木にかかっていた名札は間違いだと思いますので訂正しておきます。 撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2006年3月24日
2006年03月27日
コメント(10)
-
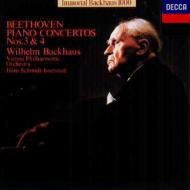
ベートーベンの命日/オランダ耳菜草
『今日のクラシック音楽』 ベートーベン作曲 ピアノ協奏曲第4番ト長調1827年の今日(3月26日)、ルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーベンがウイーンで57歳の生涯を閉じています。 それから57年後の1880年の同じ日にドイツで20世紀を代表する偉大なピアニスト、ウィルヘルム・バックハウ(1880-1969)が生まれています。ベートーベンのピアノソナタや協奏曲を最も得意にしていたバックハウスは、16歳でコンサートピアニストとしてデビューして以来、85歳で最後の演奏会となったオーストリアのケルンテン音楽祭ステージまで、弟子を採ることもなく、教職に就くこともなく、舞台と録音一筋のピアニスト人生を貫いた演奏家でした。バックハウスの演奏は、完璧にマスターしたピアノ技巧を基に(ピアノを弾く人の言葉ですが)、正確無比なピアノタッチと武骨とも言えるほど純ドイツ風のゴツゴツとした、男性的な逞しさと彫りの深い造型表現による曲・音楽の美しさを際立たせるピアニストでした。彼のレパートリーもこうした表現をいかせるベートーベン、ブラームス、シューベルトやモーツアルトのようなドイツ・オーストリアの作曲家の音楽を得意としていたようで、録音も数多く残されています。バックハウスは、ベートーベンの第4番のピアノ協奏曲についてこういう言葉も残しています。 「私は、この曲があらゆる音楽のなかで一番好きなんです。 第1楽章の清らかな喜びはことに素晴らしい。 第2楽章は神への静かな祈りであり、心の底からの訴えがあります」「一番好き」だと断言するだけあって、彼は最晩年には協奏曲ならこのベートーベンの第4番とブラームスの第2番を頻繁に弾くようになったと言われています。 ベートーベンの命日とバックハウスの誕生日にちなんでバックハウス自身が一番好きだったピアノ協奏曲第4番を、もう一度じっくりと聴いてみようと思います。尚、バックハウス最後の演奏会となった1969年の6月26日と27日のケルンテン音楽祭のリサイタルがCDで復刻されています。愛聴盤 イッセルシュミット指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD9165 1958年録音)LP時代も含めて何度再発売を繰り返してきたでしょうか。 現在はこの曲が第3番とカップリングされて1,000円盤としてリリースされています。クナッパーツブッシュ指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団(TDKコア TDBA0016 1962年収録)夢の共演とも言うべき演奏家たちの出会いがDVD映像としてリリースされています。「バックハウス 最後の演奏会」(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD9185 1969年ライブ録音)↓バックハウス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1827年 没 ベートーベン(作曲家)1884年 誕生 ウィヘルム・バックハウス(ピアニスト)1905年 誕生 アンドレ・クリュイタンス(指揮者)1925年 誕生 ピエール・ブーレーズ(作曲家・指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ともの『今日の一花』 オランダ耳菜草この花も春の空き地・野原・畑・道端・公園などに、「ナズナ」や「ハコベ」「仏の座」「犬のふぐり」などの傍で咲いています。 小さな、背丈の低い雑草の一つです。撮影地 大阪府和泉市 2006年3月24日
2006年03月26日
コメント(8)
-
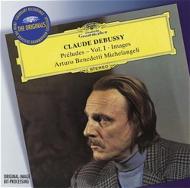
交響詩「海」/前奏曲集/姫踊子草
『今日のクラシック音楽』 クロード・ドビッシー作曲 交響詩「海」音楽家にはいつまでも語り継がれる夫婦愛を貫き通した人がいます。 一番いい例がロベルト・シューマンとクララ・シューマン。 一方、道ならぬ恋に生きた人もいます。 ワーグナーがその例ですが、今日の話題の作曲家クロード・ドビッシー(1862-1918)もその一人です。 妻を捨てて富裕な未亡人エンマと駆け落ちをして同棲生活を送り、一大スキャンダルを提供しています。そのドビッシーが、駆け落ちした1940年(43歳)に作曲された曲に交響詩「海」があります。 初演時の音楽の評価は、スキャンダルによって随分と歪曲されてしまったために不評だったそうですが、今ではドビッシーの代表作となっています。ドビッシーと言えば「フランス印象派音楽」で、対象物を音の印象ととらえる、という印象主義音楽手法を創った人で、和声が重要視されており、つかみどころのないような情緒的な音の響きがする音楽を生み出した人です。 すでに「牧神の午後への前奏曲」や「夜想曲」などを発表しており、この曲で印象主義を更に明確に進めています。副題として「交響的素描」と付けられているように、「より構成的、交響的な形の中に、流動的な海の姿をとらえようとした」(ドビッシーの言葉)音楽で、彼自身が葛飾北斎の浮世絵「富岳三十六景」を観て霊感を得て書いたと言われています。 彼が誕生してから5年後の1867年のパリ万国博覧会にはこの浮世絵が出展されていますから、実際に絵を観る機会があったのでしょう。曲は3つに分かれており、「海の夜明けから真昼まで」、「波の戯れ」、「風と海の対話」というサブ・タイトルが付けられており、刻々と変化する海の表情を、彼独特の色彩感と動きで見事に描ききった名品です。 演奏時間は約30分。そのドビッシーが1918年の今日(3月25日)亡くなっています。 今日は命日、それにちなんでこの交響詩「海」を聴こうと思います。愛聴盤 カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 (SONY レーベル SRCR9882 1989/1994年録音)カップリングはドビュッシー:牧神の午後への前奏曲、ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ、ラヴェル:組曲「マ・メール・ロワ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ピアノ曲集「前奏曲集」ドビッシーは数多くのピアノ作品を書き残しています。 「月の光」が含まれている「ベルガマスク組曲」、「版画」、「子供の領分」、「12の練習曲」、それに2つの「前奏曲集」などがあります。ドビッシー自身が10歳で早くもパリ音楽院でピアノと作曲を勉強するほどに、子供の頃からピアノにかけては卓抜した能力を持っていたそうです。上述の「海」で書きましたように、ドビッシーは「印象派」と言われる音楽を確立しています。 その最もいい例がこの「前奏曲集」だと思います。ショパンやリストといったピアノの名手も数多くのピアノ曲を書き残していますが、彼らとドビッシーのピアノ曲には大きな違いがあります。ショパンやリストのロマン派ピアノ音楽は、旋律が深く刻み込まれていますが、ドビッシーのピアノ曲は旋律よりも音そのものが重要で、ハーモニー(和声)や音色をとても大切に扱っています。この「前奏曲集」は、ドビッシー自身が観たり、読んだりした絵画・風景・文学作品などの印象を綴っています。 それぞれの曲に副題がつけられていて、ドビッシーが何から受けた印象なのかをピアノを弾く人や聴く人にわかるようになっています。この曲集には「亜麻色の髪の乙女」や「沈める寺」、「花火」などの単独で演奏される有名ピアノ曲が含まれています。ドビッシーのピアノ技巧が散りばめられた音色や色彩の豊かさでは、聴く者を夢幻の世界に誘ってくれるような曲ばかりです。各集とも12曲から構成されていて、ショパンの「24の前奏曲」と同じ構成です。愛聴盤 アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェロ(ピアノ)第一集(ドイツ・グラモフォン 4775345 1978年録音 海外盤)第二集(ドイツ・グラモフォン 427391 1988年録音 海外盤)消え行くピアノの音色の響きが例えようのない美しさです。 各曲とも濃厚な色彩に彩られている演奏で、各曲のイメージが彫りの深い表現で圧倒されています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1881年 誕生 ベラ・バルトーク(作曲家)1918年 没 クロード・ドビッシー(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 姫踊子草いつ開花するかと春の代表花「桜」ばかりに目がいきますが、今の時期には色々な花が咲き乱れてきます。 まさに「百花繚乱」。 でも道端や空き地、野原、公園の遊歩道などにひっそりと咲いている雑草のようでもある、小さな可憐な花たちもあります。 「寒緋桜」満開の公園の隅でひっそりと咲く「姫踊子草」を見つけました。 マクロレンズで覗いてみると可愛い表情をして、「春がきた~!」と喜んでいるようでした。撮影地 大阪府和泉市 2006年3月24日紫蘇科 オドリコソウ属 開花時期 2月中旬~5月下旬葉は五重塔のような段々状になっています。 雑草の一つですがたくさん集まるととても可憐です。「仏の座」という雑草のような花に似ています。
2006年03月25日
コメント(6)
-

桜とメジロ
ともの『今日の一花』 寒緋桜とメジロこの画像は昨年の3月21日に撮影したものです。 早咲きのこの桜はよく知られている「緋」の色が濃くない桜で、寒桜かなと思うほどの少し繊細な「寒緋桜」です。撮影場所は市内の公園。自宅から自転車で5分という絶好のロケーションで、毎年ソメイヨシノが満開になると市民がハイキング気分で集まる市内の桜名所の一つです。毎年この画像の桜が先陣を切って開花・満開となり、散っていくころにソメイヨシノが咲き始めます。 昨年も散歩に出て満開を確認してからカメラを持ち込んで撮っている枝に、一羽のメジロが飛んできて桜の花びらにくちばしを突っ込み始めました。その時のショットのうちの2枚をもう一度アップします。 今日は快晴との予報です、カメラ片手に1年ぶりの満開を撮ってこようと思っています。「お~い、君~!」 「何だよ~?」 撮影地 大阪府和泉市 2005年3月21日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1868年 初演 ブラームス ピアノ五重奏曲1916年 没 エンリケ・グラナドス(作曲家)1952年 没 ガブリエル・ピエルネ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』は休みます。
2006年03月24日
コメント(10)
-
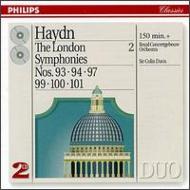
「偉大な芸術家の思い出」/「驚愕」/椿
『今日のクラシック音楽』 チャイコフスキー作曲 ピアノ三重奏曲「偉大な芸術家の思い出」作曲家にとても親しい友人や先輩、師匠がいて、その人たちが亡くなると作曲家がその人の思い出をこめて音楽を書くということがよくあります。 そういう曲の中でも有名な1曲があります。チャイコフスキーが作曲しましたピアノ三重奏曲イ短調 作品50「偉大な芸術家の思い出」です。チャイコフスキーにとって「偉大な芸術家」とは、モスクワ音楽院の設立者であり、ピアノの名手だったニコライ・ルビンシテインのことです。 チャイコフスキーが音楽院の教授として迎えられてからその親交が始まったのですが、彼の曲の初演や音楽への助言などもおこなっていたそうです。ところが、チャイコフスキーが書いた「ピアノ協奏曲第1番」については、ルビンシュテインに助言を求めなかったことで、この親友はへそを曲げてしまい、完成後に楽譜を親友に見せに来たチャイコフスキーに散々な酷評を述べたために、さすがのチャイコフスキーも怒ってしまい不仲となりました。実は、このピアノ協奏曲はルビンシテインに捧げるつもりで書かれていて、楽譜にもそう書くつもりだったそうです。その後この協奏曲はまったく手を加えることなく出版されて、曲は名指揮者ハンス・フォン・ビューローに捧げられてニューヨークで初演されました。しかしその後二人は元の仲に戻り、再び親交を深めるようになりました。再び戻った友情でしたが、そのルビンシュテインが46歳の若さでフランス・パリで亡くなり、チャイコフスキーはその死を嘆き悲しみ、その死を悼んで書いたのがこの曲です。ピアノ三重奏曲というジャンルは、モーツアルトの時代でさえも「ハウスムジーク」という雰囲気で書かれており、家族や親しい人たちが家庭のサロンで演奏するというような音楽でしたが、ベートーベンによってより芸術的な作品に昇華されて、あの偉大な「大公トリオ」が書かれています。その後シューベルトの2曲に代表されるように、ロマンの香りいっぱいの抒情的な曲が生まれて、ピアノ三重奏曲は独自の芸術性を確立していました。ところがチャイコフスキーはあまり数多くの室内楽を書き残していません。今でも頻繁にコンサートや録音に採り上げられるのは、後期の3曲の交響曲、ヴァイオリンやピアノの協奏曲、3大バレエ音楽に代表されるオーケストラ作品、ピアノ小品集、それにオペラです。彼の室内楽作品として今日でも演奏されているのが弦楽四重奏曲が筆頭でしょう。しかし、ピアノ三重奏曲としてはベートーベンの「大公トリオ」と並んで最も人気の高い、また優れた作品として挙げられるのがこの「偉大な芸術家の思い出」です。私の勝手な想像ですがニコライ・ルビンシュテインの追悼曲としては、弦楽四重奏・五重奏ではなくてやはりピアノが活躍するジャンルとして三重奏曲を選んだのだと思います。この曲を初めて聴いた時のことを今でも鮮やかに覚えています。高校2年生の音楽授業で、非常勤の女性教師が授業でこの曲を聴かせてくれたのが最初の出会いで、聴き終わって波のように押し寄せる感動に浸っていて、授業が終わってからそのLP盤を貸して欲しい、もう一度聴きたいからと教師に頼み込んでいました。そのLPは学校のライブラリーに備えられていたものではなく、その教師のプライベートの持ち物でした。次の音楽授業がやってくるまで1週間の間自宅で毎日聴いていました。日に3度聴く日もありました。 演奏はロストロポーヴィチ(チェロ)、スヴィアトスラフ・リヒテル(ピアノ)、レオニード・コーガン(ヴァイオリン)という1960年代の旧ソ連を代表する演奏家の夢のトリオでした。曲の冒頭、ピアノの分散和音に乗ってチェロが奏でる深い悲しみに溢れた旋律が流れると、そこはもうチャイコフスキーの世界で、ルビンシュテインを思う気持ちが切々とあふれ出ています。 曲は2楽章構成で、第1楽章はこのチェロで流れる旋律がヴァイオリン、ピアノに引き継がれて連綿と悲しみを歌い上げています。この曲の白眉が第2楽章で、民謡調の旋律がピアノ独奏で流れ出し、ヴァイオリン、チェロを交えた11の変奏が繰り広げられます。 最も活躍するのはピアノで、多彩な音色の変化に満ちた音楽で、ここにもピアノの名手ルビンシュテインへの想いが溢れているのでしょう。第2楽章は2部構成となっており変奏の終曲と終結部が第2部で、これまで親友の死を悼み悲しみながらも静かに思い出に耽っていたチャイコフスキーが、なりふり構わず泣きじゃくっているかのようで、第1楽章の主題がヴァイオリンで奏されてクライマックスを迎えるところなどは、泣きに泣くヴァイオリンに胸をしめつけられます。 そしてやがて静かに、静かに、ピアノとチェロが消え入るように音を刻みながら曲が閉じています。1882年の今日(3月23日)、ルビンシュテインの1周忌にこのピアノトリオが初演されてます。愛聴盤 スークトリオ(DENON CREST1000シリーズ COCO70528 1976年録音)↓スークトリオスケールの大きさではモノラルの名盤 ロストロポービチ、コーガン、リヒテルの演奏に匹敵する録音で、第1楽章の迫力には圧倒されます。 深い哀切を刻んだ第2楽章がとりわけ共感を呼ぶ名演だと思います。 他にデュ・プレ、バレンボイム、ズーカーマンのモノラル録音も見事な演奏を繰り広げていますし、チョン・トリオのデジタル録音も美しい演奏を繰り広げていますが、このスークトリオに愛着があります。現在CREST1000シリーズで1000円盤として再発売されています。上述のロストロポーヴィチ、リヒテル、コーガンのLP盤以来、5年後に買ったのがスークトリオの旧録音LP盤でした。 これで76年録音盤まで繰り返し聴いていましたので、スーク・トリオに愛着を覚えます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ハイドン作曲 交響曲第94番ト長調 「驚愕」フランツ・ヨゼフ・ハイドン(1732-1809)は1790年に、1761年(29歳)から30年間仕えたハンガリーの貴族エスターハージー侯爵の許を去ることになりました。ハイドンを手厚く扱ったニコラウス侯爵の死に伴って音楽に理解のないアントン侯爵から去って、イギリスの興行師ザロモンの招請を受けてドーヴァー海峡を渡ってロンドンに赴きました。ハイドンはその新天地イギリスを2度訪れていますが、そこで彼は12曲の新作交響曲を書き残しています。 この12曲が「ザロモンセット」と呼ばれている傑作揃いの交響曲で第94番「驚愕」、第100番「軍隊」、第101番「時計」などが含まれています。「驚愕」という副題の付いている第94番は、ハイドンが付けたものではありません。 ロンドン時代のハイドンは絶大な人気を誇っていて新作交響曲は評判となり、彼の人気が輪をかけるようになりました。ところが人気があっても演奏会では婦人たちの居眠りが見られて、ハイドンはこれを苦々しく思っていました。 そこで新作第94番の第2楽章に仕掛けを用意しました。 この第2楽章は親しみのある主題で始まり、じつにたおやかな情緒の美しい旋律が繰り返されます。 誰もがこのまま楽章が静かに終わるものと想っていると、突然全オーケストラの強奏が鳴り響きます。 これがハイドンの仕掛けで、眠っている婦人たちを驚かせて目を覚まさせようとしたので、この副題「驚愕」とか「びっくり」が付けられたと言われています。ユーモアに富んだハイドンらしいエピソードですが、ほんとにそういう意図だったのでしょうか?ハイドンらしく端正で流麗な旋律に溢れた古典交響曲の美しさに満ちた音楽が展開されていて、こういうエピソードを忘れて聴きほれてしまう傑作です。この「驚愕」が1792年の今日(3月23日)、ハイドン自身の指揮でロンドンで初演されています。愛聴盤 サー・コリン・ディビス指揮 アムステルダム・コンセルトへボー管弦楽団(Philipsレーベル 442614 1981年録音 海外盤)↓ディビス ディビスらしい実に端正な音楽をコンセルトヘボーの美しいサウンドで描いています。 春の午後のティータイムにぴったりのディスクだと思います。トーマス・ビーチャム指揮 ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団(EMIレーベル 5857702 1958-59年録音 海外盤)↓ビーチャムLP時代を含めて数え切れないくらい再発売を繰り返しています。 エレガントで実に温かみのこもった表現で、ハイドンの美しさと魅力を伝えてくれる稀有の演奏です。もうこういう演奏ができる指揮者がいなくなってしまいました。それだけに貴重な録音盤です。 現在はこの番号でリリースされていて2枚組で1,200円です。 ステレオ初期の古い録音ですが、演奏がそれを忘れさせる名盤だと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1873年 初演 モーツアルト 交響曲第35番「ハフナー」1792年 初演 ハイドン 交響曲第94番「驚愕」1881年 逝去 ニコライ・ルビンシュテイン(ピアニスト・指揮者)1882年 初演 チャイコフスキー ピアノ三重奏曲「偉大な芸術家の思い出」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 椿椿は4月上旬頃まで咲いているのもあります。 この椿の名前はわかりません。 ご存知の方がおられましたら教えて下さい。撮影地 大阪府和泉市 2006年3月17日
2006年03月23日
コメント(4)
-

あせび(馬酔木)ピンク
ともの『今日の一花』 あせび(馬酔木)今年の「あせび」は早くから咲いていました。長居植物園でも開花しているそうです。 この画像の「あせび」は近所のおうちの門扉横に地植されていたすごく背の低いもので、三脚を使うのが難しい位置でしたが何とか撮れました。 今度は長居植物園で白い「あせび」を撮ってアップするつもりです。撮影地 大阪府和泉市 2006年3月15日つつじ科 アセビ属 開花時期 3月初め~4月中旬 「あしび」とも呼ばれています 壷形の花をいっぱい咲かせています 色は、うす紅色のものと白の2種類があります 枝葉に有毒成分を含んでいて馬が食べると酔って足がなえることから「足癈(あしじひ)」と呼ばれ、しだいに変化して「あしび」そして「あせび」となったそうで、「馬酔木」もその由来によるそうです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1976年 没 藤原義江(テノール)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』は休みます。
2006年03月22日
コメント(2)
-
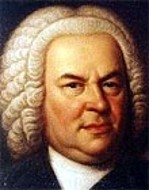
バッハ ブランデンブルグ協奏曲/花ニラ
『今日のクラシック音楽』 J.S.バッハ作曲 「ブランデンブルグ協奏曲」ヨハン・セバスチャン・バッハ(1685-1750)は、65歳の人生で教会音楽と呼ばれる「宗教」の行事に使われる音楽と、「世俗曲」と呼ばれる教会で演奏されるものと関係がない2つの音楽ジャンルの作品を書いています。 前者が「カンタータ」や「ミサ曲」、「オルガン曲」などで、後者には「管弦楽組曲」、「ヴァイオリン協奏曲」、「無伴奏チェロ組曲」、「無伴奏ヴァイオリンソナタ」、「平均律クラヴィーア曲集」、それに「ブランデンブルグ協奏曲」などがあります。バッハには「ワイマール時代」とか「ケーテン時代」とか「ライプチッヒ時代」とか呼ばれている時期があります。 それは彼がいち時期を過ごした場所を示す時代を表しています。 それぞれの時代にその場所の王侯・貴族に遣えて「音楽長」なる職務を与えられていたことを表す言葉です。「ワイマール」では9年半の間、「宮廷オルガニスト」「宮廷楽員」としてつかえて、最後には「楽士長」となっています。 その「ワイマール」の後バッハは紆余曲折を経て、ケーテン公レオポルドに熱心に請われて公の宮廷楽団の楽長のポストに就いて約5年半を「ケーテン」で過ごしました。 1717から1723年のバッハ32歳から38歳の時期です。 ケーテン公は非常に音楽の好きな人だったそうで、バッハを手厚く扱っていたためにバッハ自身も自分の書きたい曲を思う存分に書いていたそうです。上記の「世俗曲」はほとんど「ケーテン時代」に書かれたと言われており、バッハ65歳の生涯で「最も幸せな時代」であったと言われています。その「ケーテン時代」に書かれた作品の中に「ブランデンブルグ協奏曲」(全6曲)があります。 イタリアのヴィヴァルディ(1678-1741)に代表されるイタリア・バロック音楽に「合奏協奏曲」(独奏楽器群と合奏楽器群の競演)という音楽スタイルがあり、ラテン特有の華麗な音楽に人気がありました。 バッハはその「合奏協奏曲」スタイルに、よりがっしりとした骨組みを作ってドイツ精神のようなものを吹き込んだ作品に書き上げています。使用される独奏楽器群は6曲それぞれに異なっており、曲自体に様々な彩りを与えています。 各曲の独奏楽器群は、「第1番」 ホルン2本と3本のオーボエ「第2番」 トランペットとリコーダー、オーボエ、ヴァイオリン「第3番」 独奏と合奏の区別無く、弦楽器のみ「第4番」 2本のリコーダーとヴァイオリン「第5番」 フルートとヴァイオリン、チェンバロ「第6番」 独奏と合奏の区別なく、弦楽器での演奏となっており、ヴィヴァルディ・スタイルを踏襲しているのは「第2番」「第4番」「第5番」と言われています。 他の3曲はバッハ独自のスタイルとなっているそうです。音楽は華麗さとドイツ音楽の重厚な構成による骨太の音楽となっていて、それぞれの曲の多彩な曲趣を味わえる作品です。この曲は、「ケーテン時代」に書いて宮廷演奏会で演奏されていた作品から6曲を選び出して、1721年にルードヴィッヒ・ブランデンブルグ辺境伯に献呈されています。 この曲の名前はこのルードヴィッヒ伯爵に献呈されたことに由来しているそうです。私がこの「ブランデンブルグ協奏曲」を初めて聴きましたのが高校1年生の時で、今では何故この曲を選んだのか理由は定かではありませんが、カール・ミュンヒンガー指揮 シュトットガルト室内管弦楽団の録音したLP盤から第2番のみをプレスしたEP盤を買って聴きました。 トランペットの華やかな音色に魅されて毎日この「第2番」を聴いて楽しんでいました。1685年の今日(3月21日)、J.S.バッハが生まれています。 彼の誕生日にちなんで、今日はこの「ブランデンブルグ協奏曲」を聴こうと思います。愛聴盤(1) ルドルフ・パウムガルトナー指揮 ルツェルン弦楽合奏団(DENONレーベル COCO78379-80 1978年録音 廃盤)ヨゼフ・スークのヴァイオリン、オーレル・ニコレのフルート、ギィ・トゥーヴロンのトランペット、クリスティアーヌ・ジャコテ(チェンバロ)などをソリストに迎えた、少しの遅めのテンポでゆったりとした素朴なドイツ・バロック音楽といった感のある、聴くほどに味のある演奏です。 このディスクを多くの人に聴いてもうらためにも再発売して欲しいCDです。愛聴盤(2) ジャン=フランソァ・パイヤール指揮 パイヤール室内管弦楽団(DENONレーベル COCO70618 1973年録音)以前2枚のCDでリリースされていたのを聴いています。パウムガルトナー盤のような重厚さはありませんが、フランス・サロン音楽風のバッハでランパルのフルート、モーリス・アンドレのトランペット、ジャリのヴァイオリンなどの独奏者を迎えての名人芸を楽しめるディスクで、現在はDENON CREST1000シリーズで1000円盤として再発売されています。第1番を除いて5曲収録されています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1685年 誕生 J.S.バッハ「大バッハ」(作曲家)1838年 初演 シューベルト 交響曲第9番「グレート」1839年 誕生 モデスト・ムスルグスキー(作曲家)1936年 没 アレクサンドル・グラズノフ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 花ニラ 撮影地 大阪府堺市 大仙公園 2006年3月15日ゆり科 イフェイオン属 南アメリカ原産 開花時期 2月中旬~5月中旬。 星型をしたうす紫色の小さな春の到来を告げる花の一つです。葉をちぎるとニラの匂いがします。 花はとても可憐で美しく、葉がにらに似ていることから花ニラと呼ばれています。 昨年の春に初めてこの花を見て魅せられて、今年も開花を待ちかねていました。植物園やフラワーセンターなどで群生して咲いている様はとても美しい姿です。
2006年03月21日
コメント(10)
-
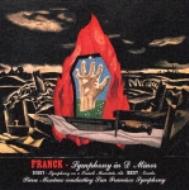
ダンディ 「フランス山人の歌による交響曲」/ムスカリ
『今日のクラシック音楽』 ダンディ作曲 「フランス山人の歌による交響曲」フランスの作曲家ヴァンサン・ダンディ(1851-1931)はよほど「山」が好きだったのか、それにまつわる曲がいくつか書き残されています。 交響的伝説曲「幻惑の森」、交響的三章「山の夏の日」やピアノ曲集「山の詩」などがあり、彼の作品中最も有名で今尚演奏会や録音などにたびたび採り上げられている曲が「フランス山人の歌による交響曲」があります。ダンディは3曲の交響曲を書き残していますが、この曲は交響曲第1番にあたる曲です。交響曲と言っても協奏曲というスタイルで書かれている曲もあります。 有名なのがラロ(1823-1892)の書いた「スペイン交響曲」で、これは実質ヴァイオリン協奏曲として書かれています。また協奏曲かな思って聴くと独奏曲であったりする曲もあります。 これも有名なのが大バッハ(1675-1750)の書いた「イタリア協奏曲」というピアノ独奏曲があります。この「フランス山人の歌による交響曲」は、ピアノとオーケストラのために書かれた交響曲で、ピアノ協奏曲風のスタイルで書かれています。ヴァンサン・ダンディは、フランスの作曲家セザール・フランク(1822-1890)の弟子で、リストやワーグナーとも親交があったそうです。 しかし彼の名前は日本ではこの曲の作曲家としての名前が残されている程度の知名度ではないでしょうか。 私も実は彼の曲はこの第1番の交響曲を聴いているだけで、他の室内楽作品や教会音楽、それに第2番、第3番の交響曲は随分昔にNHKFM放送で聴いただけで、今ではその音楽の感想を書けないほどに覚えていません。しかし、このピアノとオーケストラによる交響曲はLP時代に買った紹介盤や、FM放送で流れた他の指揮者の演奏を聴いてきた曲です。この曲の音楽は、ダンディが深く愛していたと言われるフランス・ヴィヴァレー地方の民謡が使われているそうです。 ヴィヴァレーとはフランス中央の山並みの一つで、セヴェンヌ山脈にあり風光明媚なところだそうです。曲の構成は3楽章で、伝統的な4楽章構成ではありません。 当初ダンディはこの曲をピアノとオーケストラによる幻想曲とする意図だったのが、交響曲として書き上げたそうです。 この3楽章形式がピアノ協奏曲風となったのかもしれません。民謡を用いているためか、音楽はのどかな山の風景・雰囲気をうまく醸し出していて、牧歌的な旋律が散りばめられた傑作です。 手法としては、フランクの弟子だけあって師匠が創り出した「循環形式」が用いられていて有機的に、効果的に使われています。ピアノ協奏曲風と言っても何度も聴き込んでいますと、ピアノがオーケストラの楽器の一つのように溶け込んでいるようにも聴こえてきます。この「フランス山人の歌による交響曲」は1887年の今日(3月20日)、フランス・パリで初演されています。愛聴盤 ピエール・モントー指揮 サンフランシスコ交響楽団(RCA原盤 BMGジャパン BVCC38319 1952年録音)モノラル録音でフランクの「交響曲ニ短調」とカップリングされています。上に書きましたLP盤がこの曲で、オリジナルはこのカップリングでなかったように覚えています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1887年 初演 ダンディ 「フランス山人の歌による交響曲」1890年 誕生 べりアミーノ・ジーリ(テノール)1914年 誕生 スヴャトスラフ・リヒテル(ピアニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ムスカリこれも春を呼ぶ、春を告げる花の一つです。 可愛い小さな花びらが顔を寄せ合って咲いています。 畑や野原ののどかな風景を運んできてくれるような春の花の一つで、今年も桜の開花に間に合うかのように地面からにょっきりと顔を出しています。撮影地 大阪府堺市 大仙公園 2006年3月15日ゆり科 ムスカリ属 開花時期 3月中旬~4月末 地中海沿岸または南西アジア原産 葡萄に似ていることから別名「グレープヒヤシンス」とも呼ばれています。 3月22日の誕生花 花言葉は「寛大なる愛」
2006年03月20日
コメント(7)
-
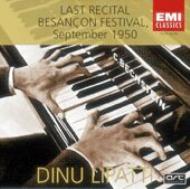
ディヌ・リパッティのピアノ
花画像日記(ともの『今日の一花』 沈丁花はこちらをご覧下さい。↓沈丁花・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ディヌ・リパッティ1917年3月19日、ルーマニア生れの天才型ピアニスト、ディヌ・リパッティ(1917-1950)が生まれています。彼の生涯は白血病のため、わずか33歳で閉じてしまいました。 今から45年前のことですから、私がクラシック音楽に興味を持って3年経った頃で、勿論生演奏や生前中の演奏をラジオなどで聴いた経験はありません。 確か16歳のころだったと思いますが(確かな記憶ではありませんが)、NHK放送から流れてきた、曲名は覚えていませんがモーツアルトのピアノソナタを聴いてハッとする美しいピアノの音色に魅せられたのを鮮明に覚えています。まるで鍵盤上を蝶々が舞うかのごときに聴こえたピアノの音色に驚きました。 それまで数少ない経験でバックハウスの重厚な音楽や、ルービンシュタインの華麗なピアノを聴いた経験とは次元の違うピアノでした。 当時はLP盤1枚買うにも小遣いが足りず彼の遺した録音盤を買う余裕がなくて、専らNHKや民放のクラシック音楽番組でたまたま流れる演奏を聴いた経験しかなかったのですが、聴くたびにすごいピアニストだなと感動していたのを思い出されます。 グリーグやシューマンの協奏曲などでした。ピアノを弾く人に聞いたのですが、ピアノ演奏技術は完璧だそうです。 リパッティの演奏の良さはピアノを弾く指による奏法の完璧さから来るものと、ペダリングを抑制したことによるものと教えてくれました。 肩、肘、手首などを最小限の動きにして、指の加減のみによって弦を叩くことから出てくる自然な美しさを追求しているからだと語っていました。 それがピアノという楽器の持っている美しさを表現できる弾き方だそうです。さらにペダルの使用を抑制しているので、ピアノの響きに純粋さ・透明さがより深く表現されているのだとも語っていました。適切な言葉で表現ができないもどかしさがあるのですが、独特の感性を持ち、それを余すところなく聴かせてくれた、ピアノの天才ではなかったかと思います。リパッティは亡くなる前のいわゆる晩年は、持病の白血病と闘いながらの演奏・録音であり、まさに「ピアノ」が彼の命を削るカンナであったのかも知れません。 しかし、病の苦悩を微塵も感じさせないのは、再現芸術家として神さまから遣わされた自分の使命を果たすべく強さを持っていたのだと思います。エルネスト・アンセルメがリパッティとの共演でシューマンの協奏曲をコンサートで演奏した時は、リパッティは死相と思われる表情を浮かべながらも、その苦しさを微塵も出さずにピアノに向かい、紡ぎ出す美しい音色に指揮をしながら涙を流していたというエピソードもあるほどです。有名な最後の演奏会となりました1950年の「ブザンソン・ピアノリサイタル」でのライブ・録音は、医師までもが止められなかったリパッティの精神的な強さを感じます。 予定していたプログラムのショパンのワルツ集の最後の1曲が弾けないくらいに、体の苦痛と闘っていたのでしょう。 この時の録音盤に書かれている夫人のその時の演奏会の模様は、何度読んでも涙が浮かんでくる言葉であり、そして演奏です。愛聴盤 ブサンソン音楽祭における最後のリサイタル(東芝EMI TOCE59180 1950年9月16日録音)シューマン/グリーグ ピアノ協奏曲 カラヤン/アルチェオ・ガルエラ指揮 フィルハーモニア管弦楽団(東芝EMI TOCE59176 1948年録音)今日は、私たちに神さまからディヌ・リパッティを与えられた日です。 じっくりと彼の演奏を聴き直してみようと思います。『今日の音楽カレンダー』1859年 初演 グノー オペラ「ファウスト」1917年 生誕 ディヌ・リパッティ(ピアニスト)
2006年03月19日
コメント(8)
-

沈丁花
『今日のクラシック音楽』はこちらをご覧下さい。↓デイヌ・リパッパティのピアノ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 沈丁花甘い香りが町内のそこかしこで漂うようになりました。 秋の金木犀や初夏の「くちなし」と並ぶ香りの花、沈丁花。 これが咲き始めますと春本番の趣きとなります。 撮影地 大阪府堺市 大仙公園 2006年3月15日沈丁花科 ジンチョウゲ属中国原産で室町時代に日本に渡って来たそうです。 開花時期 3月初め~4月上旬春の訪れを花の一つで、甘い香りのする花で秋に咲く「金木犀」や初夏の「くちなし」同じように、この匂いが遠くからでも相当強く漂ってきます。花芽がついてから開花まで3ヶ月くらいかかると言われていますから、12月に花芽がつくのですね。白い花もあります。沈香(じんこう)という香りに似ているのと、葉の形が丁子(ちょうじ)という植物に似ているので「沈丁花」と言う名前がつけられたそうです。3月23日の誕生花花言葉は「優しさ、おとなしさ」
2006年03月19日
コメント(0)
-
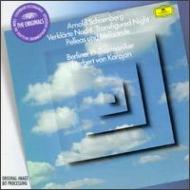
シェーンベルグ 「浄められた夜」/サンシュユ
『今日のクラシック音楽』 シェーンベルグ作曲 「浄められた夜」(弦楽合奏版)今日は現代音楽を1曲。 アルノルト・シェーンベルグ(1874-1951)は「12音技法」という斬新な音楽スタイルを生み出して確立した作曲家です。12音技法とは、1オクターブの12音をどれと偏らずに使うことで、「調」を作ることができないような特殊な音を作り上げる技法だそうです。シェーンベルグ以前の作曲家は誰も書かなかった音楽技法です。実際に書かれた音楽を聴きますと、「あ~、美しい!」と手放しで音楽にのめり込んでいける、あるいは音楽が勝手に心の中に入り込んできて居座ってしまい、いつも、或いは時々その旋律が心の中に浮かび上がってくるような音楽ではないと言えます。表現を変えると、この「12音技法」音楽は感情のない、まるで無機的な響きを持つ音楽のように感じます。 クラシック音楽好きには個人の好みがありますが、一般的に「美しい」音楽と言われる曲などをお好きな方には親しみにくい技法であることは間違いがないようです。そうした彼の音楽の中で、演奏会や録音で人気のある作品が初期に書かれた「浄められた夜」です。最初は室内楽(弦楽六重奏曲)として書かれていましたが、のちに弦楽合奏曲版に編曲されましたこの作品は、まだ「12音技法」を確立する前の音楽でドイツの詩人デーメルの詩を音楽に表現したと言われています。情景描写という音楽で、月夜の林の中を歩くある一組の男と女の会話姿を印象的な手法で描いています。 特に難解な音楽でもなく、後期ロマン派の色彩が濃厚に描かれており、少し暗い音色と厚めのサウンドが夜の情景と雰囲気を見事なまでに醸し出した音楽・作品で、明晰な音楽が耳に心地よく、現代音楽特有の「響き」と美しさに魅せられる曲です。1902年の今日(3月17日)、この「浄められた夜」(弦楽六重奏版)がウイーンで初演されています。愛聴盤(1)ズービン・メータ指揮 バイエルン国立管弦楽団 (Farao Classics B108042 2003年3月ー4月録音 ドイツ輸入盤)メータの36年ぶりの再録音で、甘美な色彩に溢れており、バイエルン国立管弦楽団の弦楽が豊かな情感を醸し出しています。 最新の超優秀録音も手伝っての美しい響きで、カラヤン/ベルリン・フィルに匹敵する秀演です。愛聴盤(2) ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリンフィル(ドイツ・グラモフォン 45771 1974年録音 海外盤)もう30年以上前の録音ですが、カラヤンとベルリンフィルが最も輝いていた時代と言われている時期で、カラヤン美学によって磨きぬかれた現代オーケストラが奏でる美しさを表現した端的な例かもしれません。 分厚い弦楽合奏の音色が聴く者に有無を言わさない美しい演奏です。カラヤンの演奏をあまり好きでない私でも、彼のオペラ録音同様に脱帽といった素晴らしい演奏です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1844年 生誕 リムスキー=コルサコフ(作曲家) 1902年 初演 シェーンベルグ 「浄められた夜」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 サンシュユ もっと近くで花びらを見ると撮影地 大阪府堺市 大仙公園 2006年3月15日
2006年03月18日
コメント(4)
-
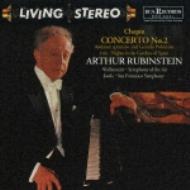
ショパン ピアノ協奏曲第2番/ナズナ(ペンペン草)
『今日のクラシック音楽』 ショパン作曲 ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調フレデリック・ショパン(1810-1849)は39歳の短い生涯に2曲のピアノ協奏曲を書き残しています。 これら2曲は1829-1830年に書かれていますから、非常に若い間に書かれていることになります。この第2番は、もうすでに有名なエピソードのように、第1番より先に書かれています。 これは楽譜出版が1番と2番が逆になったことから発生しています。ショパンがこの曲を書いた当時に片想いの恋をした女性(ワルシャワ音楽院卒業のコンスタンティア・グラドコフスカ)への思慕から、第2楽章「アダージョ」を書いたことで有名です。音楽は典型的なロマン派ピアノ協奏曲のスタイルで書かれており、ショパンのロマンティックな資質が泉のように湧き出た、甘く美しい旋律が全編に包まれています。 ショパンのピアノ協奏曲は、オーケストレーションのまずさとか下手だとか指摘されていますが、その下手くそと言われる管弦楽伴奏が、よりいっそうピアノ旋律・音楽の魅力を引き立てているようです。この曲の白眉は第2楽章「アダージョ」だと思います。まるで片想いへの恋しい女性に「恋文」でも書いているかのように、熱い想いが甘く美しい旋律で書き連ねられた、豊かな抒情的な雰囲気いっぱいの、ショパンの「青春の息吹」のような音楽に溢れています。グラドコフスカは幸せな人だと思います。 これほどの名曲を書くきっかけが彼女にあって、その想いが第2楽章に込められているのですから。しかし、この曲は片想いの当の本人にではなくて、後にパリで親交のあったデルフィナ・ポトッカ伯爵夫人に贈呈されたそうです。1830年の今日(3月17日)、このピアノ協奏曲第2番がショパン自身のピアノで初演されています。愛聴盤(1) ルービンシュティン(P) アルフレッド・ウオーレンシュタイン指揮 シンフォニーオブジエアー(RCA原盤 BMGジャパン BVCC37173 1958年録音)ほんとに古い、ステレオ初期の録音ですが、風格豊かに堂々と弾いているピアノだと思います。ピアノタッチの腰が強く、スケールが大きくて、明るく健康的で、情緒豊かに歌う演奏は今でも色あせない魅力です。愛聴盤(2) クリスティアン・ツィマーマン(Pと指揮) ポーランド祝祭管弦楽団(ドイツ・グラモフォン 459584 1992年録音)あらゆる機会に論じられた稀有の演奏。ツィマーマンの弾き振り。オーケストラまで新編成して自分のやりたいこと徹底的に語っています。 第1番とのカップリング、1番から順番に聴いたのですが、冒頭のオーケストラでの演奏から「ちょっと待ってよ!」と思い、使用楽譜に新版が出たのかと想ったほど、従来の演奏スタイルとは全く異なる濃厚なロマン情緒がどこを切っても表れる素晴らしい演奏です。 強弱の対比が鮮明で、強靭なピアノタッチ、蕩けるような甘さ、豊かな艶のある表現、もう無類の音色の変化にただただ呆然と聴いていたものです。しかし、この曲を初めて聴く方には是非この盤以外で聴いて欲しいと思います。 そのあとにこのツィマーマン盤を聴かれたほうがより凄さを理解できると思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1830年 初演 ショパン ピアノ協奏曲第2番1846年 初演 ヴェルディ オペラ「アッティラ」2005年 没 ガリー・ベルティーニ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ナズナ(ペンペン草)空き地や野原、畑・田んぼの畦などに見かけるナズナです。 これからしばらく楽しめる小さな花です。撮影地 大阪府和泉市 2006年3月11日
2006年03月17日
コメント(8)
-
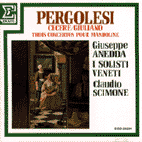
ペルコレージ 「マンドリン協奏曲」/スターバト・マーテル/寒桜
『今日のクラシック音楽』 ペルコレージ作曲 マンドリン協奏曲/「スターバト・マーテル」イタリアの作曲家ジョバンニ・バティスタ・ペルコレージは、モーツアルトにも較べられるほどの有り余る音楽の才能を持ちながら、わずか26歳という若さでこの世を去った作曲家だったそうです。 しかも26年という短い人生で、作曲活動を行なったのは5年間だけだったと言われています。劇音楽や宗教音楽、室内楽に多くの曲を書残しているそうです。 歌劇「奥様女中」や宗教曲「スターバト・マーテル」などは今尚演奏されている傑作です。ところが、その死後に彼の人気は急騰して、色々な偽物作品まで彼の作として出版されたために、後世では彼の音楽の年譜も作成することが難しくなり、謎の多い作曲家となってしまいました。今日はそのペルゴレージが1736年に亡くなった日で、それにちなんで、彼の作曲しました「マンドリン協奏曲 変ロ長調」を聴くことにします。実際には、この曲も確かに彼の作品であるという確証がないそうで、楽想からそうだろうという憶測が定説となり、今では彼の曲となっているそうです。3つの楽章からなる伝統的な協奏曲スタイルで、マンドリンの魅力がふんだんに味わえる音楽です。 明るく、典雅な第1楽章、シチリアーナと呼ばれる情緒いっぱいの第2楽章、マンドリンの独奏がきらびやかな第3楽章の、20分ほどの音楽です。愛聴盤 ジュゼッペ・アネッダ(マンドリン) クラウディア・シモーネ指揮 イ・ソリスティ・ヴェネティ(エラート原盤 BMGビクター B15D-39204 1971年録音)カップリングはC.チェチェレーレ(18世紀)とG.ジュリアーノ(18世紀)のマンドリン協奏曲です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・もう1曲はこれ! 「スターバト・マーテル」「悲しみの聖母」と訳されている「スターバト・マーテル」は、イエス・キリストが十字架にかけられたときの聖母マリアの悲しみを歌ったラテン語の詩に音楽をつけた曲で、、キリスト教会では「聖母の七つの悲しみの日」(9月15日)のミサに歌われています。この「スターバト・マーテル」は数多くの作曲家が音楽として書いています。 頭に浮かぶだけでもヴィヴァルディ、ハイドン、ボッケリーニ、ロッシーニ、ヴェルディ、ドヴォルザーク、シマノフスキ、プーランク、あ、それにドメニコ・スカルラッティがいます。ペルゴレージの曲として残されている中で、「スターバト・マーテル」は彼が書いた作品中で最高傑作と言われています。 ソプラノとアルトの二重唱と弦楽器による演奏スタイルですが、非常に美しい旋律に溢れており、極上の和声が心を癒してくれる流麗な音楽です。現在発行されているCDカタログを眺めてもペルゴレージの項には、この「スターバト・マーテル」がずらっと並んでおり、多くの名指揮者が録音していることがわかります。 それほどにこの曲には魅力があるからだと思います。「癒しの音楽」としては、筆頭に挙げられるべき音楽ではないでしょうか。それほどにこの曲の持つ魅力は例えようのないほどの天国的な美しさで、まるでオペラを聴いているかのようなイタリア音楽の魅力に溢れています。宗教音楽を敬遠される方には是非聴いていただきたい曲で、大バッハのようなドイツ音楽のゴツゴツとした、いかにも教会で演奏される曲といった感がなくて、まるでムード音楽と呼んでもいいほど流麗な旋律で、聖母マリアの悲しみを表現しています。私のペルゴレージ体験は、先に紹介しました「マンドリン協奏曲」が初めてですが、のちにこの「スターバト・マーテル」を聴いて、すっかりペルゴレージのファンになりました。愛聴盤 クラウディオ・アバド指揮 ロンドン交響楽団(ドイツ・グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG7137 1992年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1736年 逝去 ジョバンニ・ペルゴレージ(作曲家)1870年 初演 チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」1886年 初演 マーラー 歌曲集「さすらう若人の歌」1924年 生誕 クリスタ・ルードヴィヒ(メゾ・ソプラノ)1935年 生誕 テレサ・ベルガンサ(メゾ・ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 寒桜堺市の公園で「寒桜」が咲いている聞いて出かけてきました。今が見頃の花をつけていました。撮影地 大阪府堺市 大仙公園 2006年3月15日
2006年03月16日
コメント(6)
-

金のなる木
ともの『今日の一花』 金のなる木自宅の庭で小さな鉢植えの「金のなる木」が開花を始めました。これも春を告げる花の一つです。 マクロレンズで撮ってみました。 撮影地 自宅庭 2006年3月13日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1807年 初演 ベートーベン 交響曲第4番1865年 初演 リスト 「死の舞踏」1908年 初演 ラヴェル スペイン狂詩曲1929年 誕生 アントニエッタ・ステルラ(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』は休みます。
2006年03月15日
コメント(4)
-

訃報 アンナ・モッフォ/仏の座
『今日のクラシック音楽』 訃報 アンナ・モッフォ(ソプラノ)新聞報道で知ったのですが、1932年アメリカ生れの美貌のソプラノ歌手アンナ・モッフォが3月10日に亡くなったそうです。 死因については報道されていません。 享年74歳。 アンナ・モッフォは、今売り出し中のアンナ・ネトレプコ(ロシア出身のソプラノ)と同じく舞台姿が輝くように映える美貌と容姿に恵まれた歌手でした。1960年代~1970年前半に最盛期を迎えていた歌手で、「蝶々夫人」「椿姫」「ラ・ボエーム」「ルチア」「リゴレット」「セビィリアの理髪師」などに出演して、美貌と共にリリカルな美しい歌声を披露しており、LPにこれらのオペラを数多く録音しています。私が高校生時代にNHKイタリア歌劇団の公演をTV放映や実際の舞台を観て、オペラ好きとなってアリア集などをLPで聴き漁っていた頃に出会ったソプラノでした。 まだ10代の私にはモッフォの美貌が魅力でした。 美人で容姿も美しく、その美貌によって2~3本のイタリア映画に出演したほどでした。 「ローマのしのび逢い」という映画を映画館で観ましたが、音楽とは関係のない物語で、有閑夫人役で若きツバメとの恋愛劇でした。この映画の中でモッフォは大胆にもフルヌードを演じて話題になりました。言葉にならないくらいの美しい姿でした。 おそらくオペラ歌手でヌード姿を披露したのは、モッフォだけではないでしょうか。彼女の声はニルソンのようなドラマティックな声ではなくリリカルな声のソプラノで、テバルディのような澄んだ清らかな声でもなく、どこか翳りや影のある声が特徴で、愛聴しています紹介盤でもその魅力を充分に伝えており、DVD映像の「椿姫」は息を呑むような美しさに圧倒されています。レナータ・テバルディ、ビルギット・ニルソンなどに続くこのアンナ・モッフォの訃報は、私の心の中で一つの時代が終わったような寂しさを覚えています。安からに眠り給え。合掌愛聴盤(1) 「宝石の歌」~アンナ・モッフォ オペラアリア集 トゥリオ・セラフィン指揮 ローマ歌劇場管弦楽団 (RCA原盤 BMGジャパン BVCC37319 1960年録音)収録曲宝石の歌~「ファウスト」から私の名はミミ~「ラ・ボエーム」から影の歌~「ディノラ」何を恐れることがありましょう~「カルメン」から麗しい光が~「セミラーミデ」からお聞きください王子さま~「トゥーランドット」から氷のよな姫君の心も~「トゥーランドット」から鐘の歌~「ラクメ」から愛聴盤(2) オペラ「椿姫」(ヴェルディ)DVDモッフォ、ボニゾッリ、ベッキ、パターネ&ローマ国立歌劇場 (VIDEO ARTISTS INT'L VAIDVD4233 1968年制作)愛聴盤(3) オペラ「ランメルモールのルチア」(ドニゼッティ)DVDモッフォ、コズマ、カルロ・フェリーチェ・チラリオ指揮 ローマ交響楽団(VIDEO ARTISTS INT'L VAIDVD 4211 1974年制作)愛聴盤(4) オペレッタ「美しきヘレナ」(オッフェンバック) DVDモッフォ、ルネ・コロ、フランツ・アラーズ指揮 シュトットガルト放送響 (ドイツ・ユニテル原盤 ドリームライフ DLVC1120 1974年制作)(2)~(4)は全てオペラ映画としてスタジオ制作されており、モッフォの魅力を最大限に生かした秀作揃いです。 特に、「美しきヘレナ」では完熟女性の官能美を見事に演じている稀有な映像作品だと思います。しばらくはモッフォの歌声がオーディオ装置から、TV画面から聴く毎日となりそうです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1681年 誕生 ゲオルク・フィリップ・テレマン(作曲家)1821年 初演 シューベルト 弦楽四重奏曲第13番「ロザムンデ」1852年 初演 シューマン 「マンフレッド」序曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 仏の座この花も春を告げる草花の一つです。 小さな花ですがレンズの中では可愛い表情をしている被写体です。撮影地 大阪府和泉市 2006年3月13日しそ科 オドリコソウ属 開花時期 2月上旬~5月末ごろ半円形の葉が茎を取り囲んで付くようすを蓮華座に見立てたことからこの名前が命名されているそうです。
2006年03月14日
コメント(11)
-

桜草
ともの『今日の一花』 桜草春らしい清楚な花の一つで、町内の花好きのおうちには必ずと言っていいほどプランターに植えて楽しまれています。撮影地 大阪府和泉市 2006年3月11日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1845年 初演 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲1860年 誕生 フーゴー・ヴァオルフ(作曲家)1883年 誕生 エンリコ・トセリ(作曲家)1985年 没 ユージン・オーマンディ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』は休みます。
2006年03月13日
コメント(4)
-

ヒマラヤユキノシタ
ともの『今日の一花』 ヒマラヤユキのシタ11日の日記に掲載しましたのと同じ被写体です。小雨まじりの曇天に咲く花と快晴下に咲くのと、花の表情がこんなにも違います。微笑んでいるようです。11日の曇天下で撮影した画像です撮影地 大阪府和泉市 2006年3月9日快晴下で撮影した同じ被写体です撮影地 大阪府和泉市 2006年3月11日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1888年 誕生 ハンス・クナッパーツブッシュ(指揮者)1954年 初演 ブリテン チェロ協奏曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』は休載します。
2006年03月12日
コメント(12)
-

オペラ「ドン・カルロ」/ヒマラヤユキノシタ
『今日のクラシック音楽』 ヴェルディ作曲 オペラ「ドン・カルロ」イタリアの作曲家ジュゼッペ・ヴェルディ(1813-1901)は「リゴレット」「トロヴァトーレ」「椿姫」「運命の力」「仮面舞踏会」「アイーダ」「オテロ」など数多くの名作オペラを書き残していますが、それらヴェルディの作品の中でも、パリ開催の第2回万国博(1867年)のために書かれた「ドン・カルロ」は約3時間を要する大作で、彼のオペラの中でも一番長い作品で、劇的緊張力が最終幕の幕が下りるまで持続されて、しかも輝くような美しい歌にあふれていて、人々の心を深く感動させる力をもつ最高傑作ではない でしょうか。登場するドン・カルロ、フィリッポII世、その王妃、エボリ公女、ロドリーゴらのそれぞれの思い-嫉妬・疑惑・愛憎などの複雑な想いが絡み、政治や宗教の対立なども織り込んで、ドン・カルロとロドリーゴの友情等々を、重厚な音楽と劇的表現力によって描き出された悲劇が展開します。物語の時代は1560年代のスペイン。 先帝カルロ五世の墓のある、マドリッドの修道院の早朝に、スペイン王フィリッポ二世の王子ドン・カルロが親友のロドリーゴに、婚約者であったエリザベッタが父と婚姻して王妃となったことへの悲しみと憤りをぶちまけるところから始まります(4幕版)。ドン・カルロに想いを寄せる王妃付き女官のエボーリ公女は、彼が王妃を恋していることを知って妬み、王と密通して王妃エリザベッタのドン・カルロとの不貞を教えます。 このスペイン王は旧教徒で、新教徒が多いフランドル地方を弾圧しているの対して、ロドリーゴは王に諌言を行います。 ドン・カルロはロドーリゴに賛同して父を諌めたために、逆に投獄されています。 それを知ったロドリーゴは責任を感じてドン・カルロを助け出そうとしますが、王の手の者に殺されてしまいます。 ドン・カルロはロドリーゴが息絶える前に、彼からフランドル地方の解放を託されます。ドン・カルロは、エリザベッタに最後の別れを告げてフランドルに旅立とうとしているところに、父、国王と宗教裁判長らが現れて不貞の現場を取り押さえたとして、ドン・カルロを処刑しようとします。 その時、先帝の墓の扉が開いて、王冠を着けた修道士が現れてドン・カルロを連れ去っていくところで幕となります。ヴェルディ作品中、最大規模の長時間オペラですが、超絶技巧を要する《ヴェールの歌》、熱く盛り上がる《誓いの二重唱》、独奏チェロが非常に印象深い国王の嘆きの歌《一人寂しく眠ろう》、王妃による祈りの歌《世のむなしさを知る神》などのアリアが連なる密度の濃さのおかげで、時間を忘れてオペラの醍醐味に酔える作品です。1867年の今日(3月11日)、このオペラ「ドン・カルロ」はパリ・オペラ座で初演されています。愛聴盤 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウイーンフィルハーモニードン・カルロ : ホセ・カレーラス(T)ロドリーゴ : ピエロ・カプッチッリ(Br)エラザベッタ: イッツオ・ダミーゴ(S)フィリッポ国王 : フルラネット(Bs)エボーリ公女 : アグネス・バルツァ(Ms) カラヤンが亡くなる3年前のカラヤン自身の演出で行われたザルツブルグ音楽祭の上演ライブで、カレーラス、カプッチッリの当たり役、バルツァの公女、フルラネットの長いアリア「一人寂しく眠ろう」が聴きもの。 それに若干22歳のダミーゴのエリザベッタの初々しいデビュー、凝った舞台演出などヴェルディ最高傑作のオペラを満喫できるDVD。 私が持っているのはこのDVDではなく、17年前にNHK教育TVで放映された番組のVHS録画ですが、映像はこのDVDと同じものです。(ソニークラシカル SIBC14 1986年 ザルツブルグ音楽祭1986年ライブ映像)CDもやはりカラヤン指揮 ベルリンフィルの1976年のスタジオ録音で、ホセ・カレーラス、ミレッラ・フレーニ、ピエロ・カプッチッリ、ニコライ・ギャーロフ、アグネス・バルツァ、ホセ・ファン・ダム、エディタ・グルベローヴァ、ルッジェーロ・ライモンディ、バーバラ・ヘンドリックスなど、録音当時の最高の歌手を集めた、まさに帝王カラヤンの黄金時代の産物で、豪華な歌手の声の競演のみならず、カラヤンによって磨き上げられたベルリンフィルの完璧・怒涛の美しく、素晴らしいサウンドとアンサンブルに酔えるディスクです。歌手の競演も素晴らしいのですが、ここに刻印されているカラヤンとベルリンフィルの1970年代の最も充実したオーケストラサウンドを楽しんでいます。 まさにシェフ・カラヤンが手塩にかけて研磨技術のごとく磨き上げたベルリンフィルという「楽器」が、分厚い弦の響き、圧倒的な金管の咆哮、そして怒涛のような全オーケストラのフォルテッシモが、私の部屋を揺るがすほどの迫力と説得力で迫ってきます。歌手ではカレーラスの十八番のドン・カルロが生気あふれる誠実で情熱的な性格を歌い上げており、これまた最高と言っていいほどの、ビロードのようなバリトンを聴かせるカプッチッリのロドリーゴ、そしてバルツァのエボーリ公女が素晴らしい。艶があってメゾ・ソプラノ特有の力強い声がたまらない魅力です。もう30年前の録音ですが、非常に優れた音質でDレンジが広く、奥行き感もあり、合唱などでも混濁せずに舞台いっぱいに広がる臨場感が素晴らしい録音で、現代オーケストラの極上の響きがカラヤン美学となって私の部屋を満たしてくれます。(EMIレーベル 7694032 1976年録音 輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』1791年 初演 ハイドン 交響曲第96番「奇蹟」1830年 初演 ベッリーニ オペラ「カプレーティとモンテッキ」1867年 初演 ヴェリディ オペラ「ドン・カルロ」1917年 初演 レスピーギ 交響詩「ローマの泉」1976年 逝去 ジュラデイン・ファーラー(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ヒマラヤユキノシタ小雨の降る日で、空は暗く、咲いている場所が庭の植え込みの下、岩間でしたので、雨が止むのを待ってから「シャッター優先」でISO800で撮ってみました。 今日は快晴の予報なので、もう一度撮ってみて仕上がりを比べてみようと思っています。撮影地 大阪府和泉市 2006年3月10日
2006年03月11日
コメント(4)
-
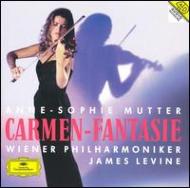
サラサーテ 「スペインの熱い血と香り」/しだれ梅
『今日のクラシック音楽』 サラサーテの「スペインの熱い血と香り」サラサーテ(1844-1908)はスペインの超絶技巧ヴァイオリニストとして活躍したと音楽史に名を残しています。 12歳でパリ音楽院に入学して15歳で卒業するという天才少年ヴァイオリニストで、音楽院卒業後に演奏活動を始めたそうです。ヴァイオリン演奏技巧として有名なパガニーニに例えられて「パガニーニの再来」と言われています。 その演奏技巧の素晴らしさに、当時の作曲家はサラサーテにヴァイオリン曲を献呈しています。 ラロの「スペイン交響曲」、ブルッフの「ヴァイオリン協奏曲」、サン=サーンスのヴァイオリン協奏曲第3番、「序奏とロンド・カプリチオーソ」などが挙げられます。パガニーニ(1782-1840)が自分のヴァイオリン技巧を表現するために「24の奇想曲」や「ヴァイオリン協奏曲」などを書き残しています。 或いはリストのピアノ演奏技巧が「超絶技巧練習曲」というピアノ曲を生んだのと同じように、サラサーテも自分のヴァイオリンの技巧を示すために、「アンダルシアのロマンス」「カルメン幻想曲」や「ツィゴイネルワイゼン」などの技巧曲を書いています。スペイン生れのサラサーテは、ヴァイオリン超絶技巧曲を書くにあたってスペイン音楽を題材にしているのが多いのです。 「アンダルシアのロマンス」を含む8曲の小品集「スペイン舞曲」やスペインを背景としてビゼーが書いたオペラ「カルメン」の音楽を題材にした「カルメン幻想曲」、それにスペイン音楽ではありませんが、スペイン・ジプシーの生まれる起源となっているハンガリー・ジプシー音楽を題材にした「ツィゴイネルワイゼン」がヴァイオリン音楽の魅力をたっぷりと引き出しています。「ツィゴイネルワイゼン」は、ドイツ語の「ツィゴイナー」から由来しており、これは「ジプシー」を意味しています。 「ジプシー」はインドのアーリヤ民族を起源としており、その後ハンガリーからスペインへと「ジプシー民族」が生まれていきました。この曲はハンガリーのジプシー音楽や民謡を素材にしています。 大きく分けて前半の「ハッサン」と後半部の「フリスカ」で構成される「チャルダッシュ」というハンガリーの舞曲形式をとっています。前半の「ハッサン」は2部構成で、緩やかな哀愁に満ちた憂いいっぱいの旋律で彩られた第1部、弱音器を付けて甘く、美しく奏でられる旋律の第2部で、ヴァイオリンのむせび泣くような音色に胸をしめつけられるような魅力がありあます。後半は速いテンポの「フリスカ」で、ヴァイオリンの目の覚めるような技巧が華麗に繰り広げられています。 ジプシーの熱い血のたぎる音楽が親しみやすい旋律で全編に刻み込まれている、ヴァイオリン曲の名曲中の名曲です。この曲を初めて聴いた中学生の頃は夢中になって聴いていたものです。「カルメン幻想曲」の原題名は、「オペラ<カルメン>の動機による演奏会用幻想曲」でビゼーのオペラ「カルメン」の音楽を題材にして序奏と4つの小品から構成されています。 オペラの中の「ハバネラ」や「セギディーリア」、「ジプシーの歌」などが採り上げられており、オペラの舞台を飛び出した「カルメン」が、スペインの熱い血と香りを運んできてくれます。サラサーテは1844年の今日(3月10日)、スペインのパンプローナで生まれています。 彼の誕生日にちなんでこうしたヴァイオリン名曲をもう一度聴き直してみようと思っています。愛聴盤 アンネ=ゾフィー・ムター(Vn) ジェームズ・レヴァイン指揮 ウイーンフィルハーモニー(ドイツ・グラモフォン 437544 1992年録音 海外盤)↓ムター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1785年 初演 モーツアルト ピアノ協奏曲第21番1832年 没 ムツィオ・クレメンィ(作曲家)1844年 誕生 パブロ・デ・サラサーテ(作曲家・バイオリニスト)1892年 誕生 アルテュール・オネゲル(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 しだれ梅ようやく町内でも梅の見頃がはじまりました。 今日はしだれ梅の画像です。 曇り空と陽が射しているときの違い明確に表われています。曇り空 快晴撮影地 大阪府和泉市 2006年3月9日
2006年03月10日
コメント(2)
-
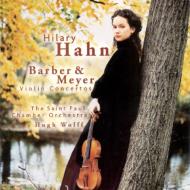
バーバー ヴァイオリン協奏曲/梅 ピンク
『今日のクラシック音楽』 バーバー作曲 ヴァイオリン協奏曲アメリカの作曲家サミュエル・バーバー(1910-1981)の書き残した作品といえば、私は「弦楽のためのアダージョ」と「ヴァイオリン協奏曲」の2曲を聴いたのみですが、これら2曲はとてもわかり易い曲で、現代音楽の特徴である難解さがありません。その2曲のうち、今日は「ヴァイオリン協奏曲」を聴いてみようと思います。書かれているのは1939年で、伝統的な3楽章形式で書かれており、楽想は叙情性豊かでしっとりとした趣きのある旋律に彩られています。 特に、最初の2つの楽章にその情緒が色濃く刻み込まれています。 「20世紀の音楽はわかりにくい」という一般的に定着しているイメージを払拭する作品と言えるでしょう。第1楽章は、甘く美しい旋律の主題で開始されており、ここでもうすでに「わかりにくい現代音楽」という概念から解放されてしまいます。 甘く美しいと言っても、当然メンデルスゾーンやチャイコフスキーの協奏曲などの楽想とは異なり、どこか「影」を落とした感の趣きがあり、しかも牧歌的なおおらかさもあります。 中間部でピアノの打鍵が打楽器的に表われてくるとこなどはそうした「影」のような情緒をただよわせています。第2楽章のオーボエの奏でる主題がとても優しく響き、やがて表われてくる独奏ヴァイオリンは切なさを訴えてくるかのようで、美しい中にも哀感を切々と歌っているようです。 どこか「はかなさ」といった情緒に包まれている楽章です。第3楽章は、前の2つの楽章に比べるとテンポの速い音楽となって、叙情的な楽章とは対照的です。 短く寸断されたような音が続く不安な情緒いっぱいの音楽が展開されています。 牧歌的な前の2つの楽章と比べると雑踏の都会に放り出された感のある音楽と例えられるでしょうか。独奏ヴァイオリンの奏でる音楽は、いかにも超絶技巧が要求されると思われ「都会の雑踏」の感をいっそう深めています。 まるで唐突といった感じでこの楽章を終わっています。 1939年と言えば第2次世界大戦が始まる「不安の時代」という時代背景を表しているような楽章・音楽です。やはり叙情的な音楽が美しいので、私は初めの2つの楽章だけを聴くことが多い曲です。1910年の今日(3月9日)、このヴァイオリン協奏曲の作曲家サミュエル・バーバーが生まれています。愛聴盤 ヒラリー・ハーン(Vn) ヒュー・ウルフ指揮 セントポール室内管弦楽団(SONY CLASSICAL SK89029 1999年録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1842年 初演 ヴェルディ オペラ「ナブッコ」1849年 初演 ニコライ オペラ「ウインザーの陽気な女房たち」1877年 初演 チャイコフスキー 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」1910年 誕生 サミュエル・バーバー(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 梅 ピンク長居植物園の梅もようやく見頃を迎えたようです。撮影地 大阪市長居植物園 2006年3月5日
2006年03月09日
コメント(11)
-
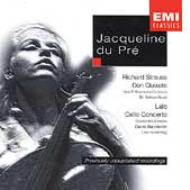
R.シュトラウス 交響詩「ドン・キホーテ」/サンシュユ
『今日のクラシック音楽』 R.シュトラウス作曲 交響詩「ドン・キホーテ」オーストリアの作曲家リヒャルト・シュトラウス(1864-1949)は、自分の曲に注目を集めるためか、と思うほどに絶妙なるタイトルを付けています。 自身を描いた「英雄の生涯」、プレイボーイの代名詞「ドン・ファン」、どんな悪戯をするんだろうと思わせる「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」、ニーチェの名著そのままの「ツァラトゥストラはかく語りき」、 シェイクスピア悲劇そのままの「マクベス」。 まるで文学作品そのままの、聴く者の気をひくネーミングはしたたかな計算があってのことだったのでしょうか?今日の話題の交響詩「ドン・キホーテ」の原作は、スペインの作家ミゲル・セルバンテス(1547-1616)がその円熟期に書き上げた長篇小説です。 映画やミュージカルでも「ラ・マンチャの男」として採り上げられ、作家セルバンテスの裁判の劇中劇としてこの「ドン・キホーテ」が演じられています。 ミュージカルでは特に「見果てぬ夢」が有名で、今ではスタンダード・ナンバーとしてミュージカル以外のポピュラー音楽としても愛され続けています。ラ・マンチャの田舎貴族ドン=キホーテと従者サンチョ・パンサの物語をシュトラウス独特のロマンティックで、豊穣な旋律、巧さの極みのヴァリエーション、そしてフランスのラヴェルと共に、近代音楽史上最高といわれる豊かな色彩に彩られたオーケストレーションで描き出していきます。この曲はドン・キホーテの主題を独奏チェロで表し、掛け合いのように従者サンチョ・パンサの主題(独奏ヴィオラ)による変奏曲の形を取っています。 この有名な物語を変奏曲形式で描いています。 「騎士的な主題を持つ幻想的な変奏曲」という副題が付けられていて、全体が序奏と終曲を含む12曲の場面から構成された、非常に大規模な変奏曲です。 しかし、主役ドン・キホーテの出番が多く、チェロ協奏曲のような趣のある変奏曲です。聴いていて楽しい曲です。 レコード、CDには大概この物語の進行と変奏曲が何を描写しているかを説明していますから、それらを読みながら変奏を聴いていますと面白く、聴く側も空想の世界をさ迷うかのような錯覚を覚えることがあります。 前述のように豊かな色彩感のあるオーケストレーションが、まるでメルヘンのようなヴァーチャル空間に誘ってくれているようです。私が一番好きなのは、非常に短い(1分くらい)第7変奏「ドン・キホーテの空中飛行」です。 目の前でドンキホーテが空中を飛んでいるような錯覚におちいるような音楽です。 題材が題材だけにR.シュトラウスの交響詩の中で「面白い」という角度から評すると、一番面白い曲ではないでしょうか。1898年の今日(3月8日)、この交響詩「ドン・キホーテ」がシュトラウス自身の指揮で初演されています。愛聴盤(1) エドリアン・ボールト指揮 ニューフィルハーモニア/ジャクリーヌ・デュプレ(チェロ)(EMI原盤 5555282 1968年録音 輸入盤)デュ・プレの力強いチェロの技巧が変奏の妙味を堪能できる稀有の演奏です。 ラロのチェロ協奏曲とのカップリングです。↓デュ・プレ愛聴盤(2) アンドレ・プレヴィン指揮 ウイーンフィルハーモニー(TELARKレーベル CD80262 1990年録音 海外盤)R.シュトラウスの色彩豊かな、豊穣な音楽を楽しむにはどうしても優秀録音が要求されます。 「録音のテラーク」というキャッチフレーズそのままの、ウイーンフィルの極上のサウンドが楽しめる超優秀録音で、私はモニター用としても使っています。 カップリングは「ドン・ファン」。↓プレヴィン(これは日本プレス盤です)愛聴盤(3) ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリンフィルハーモニー(ドイツ・グラモフォン 439027 1986年録音 海外盤)R.シュトラウスとなればカラヤンを聴かずにはおれないでしょう。 自身が磨き上げたベルリンの豊穣なサウンドをフルに駆使して、色彩豊かにR.シュトラウスのオーケストレーションを見事に美しく表現しています。 録音も非常に優秀な、カラヤンが亡くなる3年前の最晩年の遺産です。 カップリングは「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」です。↓カラヤン(これも日本プレス盤です)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1858年 生誕 レオンカヴァルロ(作曲家)1869年 逝去 エクトール・ベルリオーズ(作曲家)1898年 初演 R.シュトラウス 交響詩「ドン・キホーテ」1902年 初演 シベリウス 交響曲第2番1961年 逝去 トーマス・ビーチャム(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 サンシュユこれも「春の訪れ」を伝えてくれる嬉しい花です。 これが満開になってやっと桜が開花してきます。 「桜を呼ぶ花」とでも言ってもいいでしょう。撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月12日
2006年03月08日
コメント(8)
-
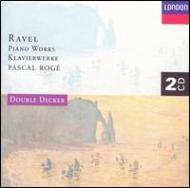
ラヴェル「夜のガスパール」/マンサク
『今日のクラシック音楽』 ラヴェル作曲 「夜のガスパール」フランスの作曲家モーリス・ラヴェル(1875-1937)は、「水」についてよほど音楽で表したかったのでしょうか、「水の戯れ」や「海原の小舟」(「鏡」の中の1曲)、「夜のガスパール」の第1曲「オンディーヌ」(水の精)などのピアノ作品がそれを物語っています。ラヴェルは、その「夜のガスパール」を33歳の1908年に書いています。 この時期の作品を調べてみますと、ピアノ曲「鏡」「ソナチネ」「マ・メール・ロア」やオーケストラでは「スペイン狂詩曲」などを書いていて、気力充実した時期であったと推測されます。この曲には「アロイジス・ベルトランによる3つの詩」という副題がラヴェル自身によって書かれています。 ベルトランとは私はどういう人なのか知らず、またそれがどんな詩なのかも知りませんが、おそらくその詩を読んでその心象、またはそのイメージをピアノで表現したかったのだろうと思います。 以下の内容はCDの英文解説を読んだことからの自分なりの解釈です。第1曲「オンディーヌ」(水の精)「水の精」が人間の若者に恋をします。 そして彼に結婚して欲しいとプロポーズしますが、断られてしまいます。 そして「水の精」は強く降る雨の中に消えていくという詩に基づいて書かれているそうです。序奏は水の囁きのような、さざ波を立てているかのようなピアノの音色が幻想的に描かれています。 また「水の精」を表現してのでしょうか、優美なピアノの旋律が美しく輝いています。 ラヴェルが描いた「水」の様子を伝えるピアノ曲の中でも実に美しい1曲です。第2曲「絞首台」鐘が鳴り響くかのようなピアノの音が繰り返されています。 死刑執行前の様子を幻想的に描いているかのような響きです。 鬼気迫るような感じの響きさえ感じられます。 しかし、聴いていますとピアニストには大変な演奏技巧を要求されてことがわかるようなパッセージがたくさんあります。 技巧を要求されてしかも表情豊かに描かなければならない、演奏技巧の難しい曲なんだなと思います。第3曲「スカルボ」この「スカルボ」とは小妖精のことだと解説には書かれています。 3曲中で最も長い曲でスケルツォ風に描かれており、小妖精が飛び回っているような雰囲気の軽妙な音楽描写が素晴らしい曲です。 第2曲が陰気であるので余計に効果的に感じます。この曲も弾く人は大変だろうと思わずにおれないほど、難度の演奏技巧が要求されているような曲ですが、こんな曲を弾きこなせば胸のすく思いになるどろうと想像されます。 小気味のいい、そしてラヴェル特有の精緻な表現の美しさがたまらない魅力の曲です。モーリス・ラヴェルは1875年の今日(3月7日)、フランスで生まれています。愛聴盤 「ラヴェル ピアノ作品全集」 パスカル・ロジェ(P)(DECCAレーベル 440836 1974年録音 海外盤 2枚組)もう1枚 「ラヴェル ピアノ独奏曲全集」 ペルルミューテル(P)(Nimbusレーベル N17713 1973年録音 海外盤 2枚組)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1875年 誕生 モーリス・ラヴェル(作曲家)1981年 没 キリル・コンドラシン(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 マンサク春の訪れを伝える花の一つで、この時期に咲く「サンシュユ」と共に大好きな早春の花の一つです。撮影地 大阪府和泉市 2006年3月02日
2006年03月07日
コメント(6)
-
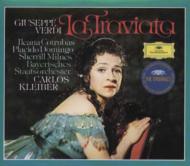
「椿姫」/プリムラ・シネンシス
『今日のクラシック音楽』 ヴェルディ作曲 オペラ「椿姫」私はジュゼッペヴェルディ(1813-1901)です。 今日は私が書いたオペラ「椿姫」の記念日なので天国から降りてきました。この「椿姫」は、初演では大不評でした。 しかし、あれほど精魂傾けて書いた曲ですから私はいつかはこのオペラが大衆に受け入れられると確信がありました。 「初演の失敗は、私の罪か歌手たちの失敗か、時代が語ってくれる」と当時は思っていたものです。あの初演で歌ったヴィオレッタ役のソプラノ歌手は肥満女性で、とても薄幸の弱々しい女性を演じる歌手ではなかったのです。 ミス・キャストが初演失敗の理由だと思っています。あれは1851年の暮れだったか、私はジュゼッピーナとフランスに逃げたことがありました。 彼女は当時イタリアでは最高のプリマドンナでした。 私はオペラ「ナブッコ」で、アビガイッレ役を彼女に歌ってもらうために書いたものです。 それほどに私の気に入ったオペラ歌手でした。ジュゼッピーナは舞台から引退してパリへと旅立ち、そこで音楽教師をしていました。 その頃には、私の妻であったマルガリータはすでに亡くなっていました。 マルガリータは、当時私の支援者でもあったバレッツィの娘でした。私とジュゼッピーナが「恋に落ちる」まで時間はかかりませんでした。 ドイツの詩人ハイネは「恋に狂う!とは言葉が重複しています。 恋そのものがすでに狂気なんです」という言葉を残していますが、私とジュゼッピーナにぴったりとあてはまる言葉でした。 私は彼女の魅力に燃え上がりました。 そして同棲生活を始めました。 それが1849年でした。 場所は前妻と住んでいたブッセートでした。しかし、あの地は閉鎖的な考えの多い人が住むところでもあり、ジュゼッピーナ自身も結婚せずにテノール歌手や指揮者との間に子供も生むと言う、当時では奔放な、恋に生きる女性であったことから、私を支援してくれていた義父と私に確執が生まれており、そのわづらわしさから二人でパリに逃げました。そして二人は1852年の2月に、パリで上演されていましたデュマ・フィス(三銃士やモンテ・クリスト伯などで有名なアレクサンドル・デュマの息子)の小説[椿姫」を基にした演劇を観劇しました。高級娼婦マルグリット・ゴーティエが金持ちのパトロンを持って社交界で人気のある女性でした。 娼婦とはいえ、芸術・文学・音楽・文化・歴史などに造詣の深い女性でした。 その彼女が青年アルマン・デュバルをパーティで会って恋に落ちて、彼とパリを離れて生活を始めますが、この青年の年収では家計は火の車で、彼女は「売り食い」生活を始めていました。 そこへアルマンの父デュバルがやってきて自分の栄誉ある家名を重んじて欲しい、息子と別れてくれと説得されたマルグリットはアルマンと別れて、ある貴族の情夫となります。その彼女の変心を知ってアルマンは激怒して、面前で彼女を罵倒して姿をくらましてしまい、とうとう行方知らずのままになります。一方マルグルットは結核がひどくなって、最後は貧困生活の中で血を吐いて死んでいくという舞台でした。愛しながらも「家」の名誉を守ってあげるために身を引いたマルグリットに、私もジュゼッピーナも芝居を見ながら涙しました。 昔、日本の大衆に受け入れられた「近松世話物」か、あるいは昭和の世に人気のあった「新派大悲劇」のヒロイン像と重なり合います。この芝居は私の愛人ジュゼッピーナに深い感銘を与えたようです。 私自身敬虔なカソリック信者でもありましたから、彼女の奔放な恋の生き方には疑問を感じながらも、彼女の魅力に引きずられていることを彼女も知っており、同棲生活に悩んでいたようです。彼女は我が身をマルグリットに置き換えて想ったのでしょう。 当時私が「イル・トロヴァトーレ」の作曲中にも関わらずこの「椿姫」を是非オペラ化して欲しいと、私に懇請する始末でした。 私も自分をアルマンに置き換えて、義父からジュゼッピーナとのことで責められる日々でしたし、これをオペラにすることに決めました。二人で「椿姫」を観た9ヵ月後の1852年の11月から「トロヴァトーレ」を書き始めて4週間で書き上げたものです。 そこへジュゼッピーナの願いもあり、オペラ劇場からの新作オペラの委嘱もあり、私は「椿姫」を「トロヴァトーレ」完成後にすぐに書き始めました。 こんなことは私の作曲家生活の中でもなかったことで、それほど私はこの原作に心を打たれて書いたものです。 そして「トロヴァトーレ」初演2ヶ月後には完成させました。当時は「トロヴァトーレ」の稽古もあり、ほんとに忙しい時期でしたが私には非常に充実した時でした。オペラでは最終幕でアルマン(アルフレード)を登場させて彼の胸の中でマルグリット(ヴィオレッタ)が息を引き取るという筋書きに変えて、オペラらしい物語に脚色しています。今でも世界のオペラ劇場で最も上演回数の多いオペラなっていることを知って、私の確信に間違いがなかったと喜んでいます。「第1幕への前奏曲」「乾杯の歌」 ヴィオレッタのアリア「ああ、そはかの人か~花から花へ」、ジェルモンのアリア「プロヴァンスの海と陸」、ヴィオレッタとアルフレードの二重唱「パリを離れて」などが、特に力を入れて書いた音楽なので、是非聴いて欲しいと思っています。ところで私はこのオペラには「ラ・トラヴィアータ」と名付けました。 これは「道を踏み外した女」という意味です。 ヴィオレッタの社会的な身の上を指しているのです。ジュゼッピーナが私の耳に「オペラ化」を囁かなければ、いや、彼女と恋に落ちていなければ1852年にパリでの「椿姫」の舞台鑑賞も無かったかもしれません。 そんなことを考えると、私とジュゼッピーナのパリでの再会は運命付けられていたのだろうと思います。その彼女との同棲生活を10年送ったあと、二人はやっと結婚してその後終生一緒に暮らしました。1853年の今日(3月6日)、私のオペラ「椿姫」がヴェネツィアで初演されたのです。 その記念日に皆さんどうぞ「椿姫」を聴いて下さい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・愛聴盤 カルロス・クライバー指揮バイエルン国立管弦楽団・合唱団イレアーナ・コトルバシュ(S)プラシド・ドミンゴ(T)シェリル・ミルンズ(B)(ドイツ・グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG30149 1976-77年録音)クライバーの凄まじいまでのダイナミックな表現と精緻な音楽作りは、今聴いても新たな感動を覚える素晴らしい演奏です。映像ではこれ!↓(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POBG1017 1982年制作)テレサ・ストラータス(S) プラシド・ドミンゴ(T) コーネル・マックネイル(Br) ジェームズ・レヴァイン指揮 ニューヨーク・メトロロポリタン歌劇場管弦楽団・合唱団舞台映像でなく、オペラ映画。 ゼッフィッレリの演出が秀逸な作品で、ストラータスの美貌と容姿が美しく、映像なら断然このDVDに限るとまで断言できる素晴らしいオペラ映画です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1831年 初演 ベッリーニ オペラ「夢遊病の女」1853年 初演 ヴェルディ オペラ「椿姫」1903年 誕生 ロリン・マゼール(指揮者)1914年 誕生 キリル・コンドラシン(指揮者)1933年 誕生 ジョン・フィリップ・スーザ(作曲家)1944年 誕生 キリ・テ・カナワ(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 プリムラ・シネンシス撮影地 大阪府堺市 大仙公園 2006年2月28日
2006年03月06日
コメント(2)
-
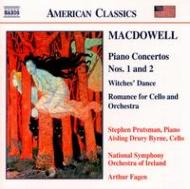
マクダウェル ピアノ協奏曲第2番/マツムシソウ
『今日のクラシック音楽』 マクダウエル作曲 ピアノ協奏曲第2番エドワード・アレグザンダー・マクダウェル(1860ー1908)はアメリカを代表するロマン主義音楽の作曲家・ピアニストでした。 数多くののピアノ曲や2つのピアノ協奏曲を書き残しています。マクダウェルは少年の頃からピアノの音楽教育を学んでおり、17歳でフランスに渡ってパリ音楽院に入学するほどの秀才だったそうです。 その音楽院の同級生にはクロード・ドビッシーがいたり、また音楽院在学中にはリストにも面会しているそうです。 リストが音楽院訪問の際には、リストが作曲した交響詩のピアノ版を演奏したというエピソードも残っています。パリ音楽院では作曲も勉強しており、少しずつ曲を書いていきました。28歳になった1888年にアメリカに戻り、ボストンで音楽教師やピアニストとして活動を続けています。 忙しい学校での生活のかたわら作曲を続けていたようです。マクダウェルの少年期から青年期にかけてのヨーロッパ生活と受けた文化が、彼の作風に何らかの影響を与えているように思えます。 精神的には新天地アメリカの風土を基盤とした心象・文化でなくて、ヨーロッパ文化・精神文化が影を落としているように思えます。例えば彼のピアノ協奏曲第1番は、ノルウエーのエドアルト・グリーグ(1834-1907)が書いたピアノ協奏曲の影響が多分に見られます。 作曲家名を知らずに聴いていると、グリーグの曲なのかなと思うほどです。またピアノ作品だけでなく歌曲にも多くの作品を残しており、最も有名なのが「野ばらに寄す」で昔から日本でもポピュラーな歌曲の一つです。今日の話題曲、ピアノ協奏曲第2番は、華麗なピアノの技巧と紡ぎ出されるような、こぼれるような詩情にあふれており、私のようにロマンティックな音楽を好きな者にはたまらない魅力に満ちた協奏曲です。 この曲がどうしてもっと演奏会でとりあげられないのか、録音ではマイナーな曲の扱いを受けているのか不思議なくらいです。抒情的で哀感を滲み出した本格派ロマン音楽としてのピアノ協奏曲。 是非一聴をお薦めします。このマクダウェルのピアノ協奏曲第2番が1889年の今日(3月5日)、アメリカで初演されています。愛聴盤スティーヴン・プルッツマン(p)/ アイリング・ドルリー・バーン(vc)/アーサー・フェイゲン指揮/アイルランド国立交響楽団(Naxosレーベル 8.559049 1999年11月録音)代表作の2曲のピアノ協奏曲が収録されています。 今ならHMVで790円の廉価盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1867年 初演 ボーイト オペラ「メフィストーフェレ」1887年 誕生 エイトール・ヴィラ=ロボス(作曲家)1889年 初演 マクダウェル ピアノ協奏曲第2番1953年 没 セルゲイ・プロコフィエフ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 マツムシソウ撮影地 大阪府堺市 都市緑化センター 2006年2月28日松虫草科 マツムシソウ属 秋の草原に群生しています。 紫色の美しい花で、この画像花は園芸品種です。 「松虫草」の名は、花の終わったあとの坊主頭のような姿が仏具の伏鉦(ふせがね:俗称「松虫鉦(名前は虫の音に由来)」)に似ているところから命名されているそうです。 別名 「スカビオサ」 園芸品種もこの名前で呼ばれています。 4月26日の誕生花。 花言葉は「感じやすい」
2006年03月05日
コメント(6)
-
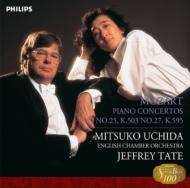
モーツアルト ピアノ協奏曲第27番/ヒマラヤユキノシタ
『今日のクラシック音楽』 モーツアルト作曲 ピアノ協奏曲第27番変ホ長調ヴォルフガング・アマデウス・モーツアルト(1756-1791)がわずか35歳という生涯で、ピアノ協奏曲を全部で27曲書き残しています。 その最後の協奏曲がこの第27番です。モーツアルトは、残されている彼に関する記述では、底抜けに明るく天真爛漫な性格の持ち主であったようです。 いつも上機嫌で、楽しいことも悲しいことも臨機応変に応える性格だったそうです。数多くの手紙が今でも保存されているそうですが(この功績は、悪妻と言われているモーツアルトの妻コンスタンツェが彼の死後にまとめたことによると言われています)、32歳頃からお金に苦労し始めたそうで、借金の申し込みの手紙が増えているそうです。 昔、雑誌「レコード芸術」だったと記憶していますが、この第27番を書き上げた1791年の1月の寒い日に暖房用の薪さえ買うお金に窮しており、妻と寒さをしのぐために二人でダンスをしながら体を温めあったというエピソードを読んだことを覚えています。第27番はこうした悲惨な貧乏生活の中で1791年の1月5日に書き上げられています。しかし、この曲にはそうした暗い生活の翳りが微塵も感じられません。 あくまでも明るさを湛えた音楽が紡ぎ出されています。 そうした明るい情緒の中でも、曲全体に「諦観」に境地が達しているように感じられます。 言葉で表現することが難しいほどに「澄み切った諦観」というものを感じます。明るさはありますが、第26番「戴冠式」のような華麗な気分は全くなくて、まるでモーツアルトが「瞑想」に耽るような楽想は、その年の12月5日にこの世を去ることを予感していたような想いになってしまいます。第2楽章「ラルゲット」で、ピアノとオーケストラが淡々と演奏される音楽は、まるで「対話」のようで「協奏的な詩」のように感じます。 貧乏に追い立てられているモーツアルトが「死」を予感したかのような「諦め」の境地のような感さえあります。ハイドンがモーツアルトの死の前年にロンドンに旅行をする時に、モーツアルトは「先生と二度とお会いできないかもしれません」と言ったエピソードが残っているそうです。 こうしたエピソードを聞くと、余計にこの曲全体に滲んでいる「澄み切った美しさ」が「死」を予感していたのかなと思ってしまいます。第3楽章「ロンド」は、この第27番の書かれたすぐあとに作曲された、有名な歌曲「春へのあこがれ」がそのまま転用されていて、春が訪れるのを待ち望む気分を歌った「春へのあこがれ」。 モーツアルトには、もう二度と「春が来る」こと叶わずに彼岸に旅立ったことを思わずにおれない想いでいつもこの曲を聴いています。ピアノ協奏曲第27番は1791年の今日(3月4日)、初演されています。愛聴盤(1) 内田光子(P) ジェフリー・テイト指揮 イギリス室内管弦楽団(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7053 1987年録音)何よりもピアノの音色がとても美しく響いています。ドラマティクな強い音と豊かでありながら孤独さを感じさせる柔和な弱音の響きがとても美しく感じられるピアノです。↓内田光子 愛聴盤(2) クリフォード・カーゾン(P) ベンジャミン・ブリティン指揮 イギリス室内管弦楽団(DECCAレーベル 4677092 1970年録音 海外盤)以前POCL9417としてリリースされていた盤(20番とのカップリング)で聴いていますが、現在入手できるのが25番とのカップリングのこの盤になります。 この曲の内面的な哀感を見事に表現しています。↓カーゾン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1678年 誕生 アントン・ヴィヴァルディ(作曲家)1791年 初演 モーツアルト ピアノ協奏曲第27番1929年 誕生 ベルナルト・ハインティンク(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ヒマラヤユキノシタ撮影地 大阪府和泉市 2006年2月26日雪の下科 ベルゲニア属 開花時期 12月中旬~4月下旬ヒマラヤ地方原産。明治初期に渡来したそうです。 きれいなピンク色の花で長い間咲いています。 名前は、ヒマラヤ、シベリア地方に多くて、寒さに強く、冬でも常緑の葉を雪の下から花が咲くことから命名されているそうです。 最近は園芸種として育てられています。この画像も園芸種です。
2006年03月04日
コメント(10)
-
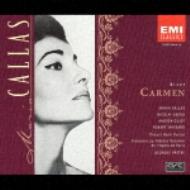
オペラ「カルメン」/椿(伯洲)
『今日のクラシック音楽』 ビゼー作曲 オペラ「カルメン」プッチーニ(1858-1924)の「蝶々夫人」と共にオペラ作品の代名詞のようなジョルジョ・ビゼー(1837-1875のオペラ「カルメン」。 強烈なスペインの雰囲気を情熱的に表現したこのオペラは、クラシック音楽やオペラを聴かない人でも多分この題名だけは知っているだろうと思われるオペラ。音楽は親しみやすい、美しい旋律に満ち溢れており、ドラマは男と女の情念が生々しく描かれていて、非常にわかり易いオペラです。1920年頃のスペイン・セヴィリアを舞台に、奔放に生きるジプシー女カルメンと、彼女への恋心から軍隊を逃げて彼女と盗賊の群れに身を落とし、許婚のミカエラの必死の説得にも関わらずカルメンに従いていき、やがてカルメンが闘牛の花形スターエスカミリオへ走ったことで、闘牛で沸き立つ闘牛場の外でカルメンを刺して殺してしまうホセ。 どの時代にも、どの国にでもある男と女の恋情のもつれの哀れな結末を題材にしたドラマが、ビゼーの美しい音楽・旋律によって生々しく表現されています。「第1幕への前奏曲」「衛兵の交代」カルメンのアリア「ハバネラ」「ジブシーの歌」「セギディーリャ」、「アルカラの竜騎兵(第2幕への前奏曲)」「闘牛士の歌」、ドン・ホセのアリア「花の歌」、「第3幕への間奏曲」「ミカエラの詠唱」「蜜入者の行進」、「アラゴネーズ(第4幕への前奏曲)」などスペイン情緒いっぱいの旋律が聴く者を魅了してくれるオペラの「名品」の一つです。この「カルメン」は1875年に作曲されたオペラですが、同じ年に初演された3ヶ月後にビゼーは36歳という若さでこの世を去っています。有り余る才能を持ちながらの、あまりにも早く逝ってしまいました。 彼がもっと長生きしてくれていれば、私たちには今以上に素晴らしい音楽を聴けたかもしれません。ところでこのビゼーには「3」という数字に不思議な因縁のある人なんです。このオペラ「カルメン」の初演が1875年3月3日、その3ヵ月後に36歳で亡くなっています。 その日がこの「カルメン」の33回目の上演が行われていたそうです。 ビゼーが亡くなった日の33回目の上演舞台の第3幕の「カルタ占いの場」でのこと。 カルメン役がカードを並べていると、何度やっても不吉なカードばかりが出てきたそうです。 このカルメン役のガリ・マリエというソプラノは胸騒ぎを覚えたという後日談が残っています。ビゼーが亡くなったのは、その第3幕から数時間後だったそうです。「カルメン」はそのシーズンに37回上演されており、その1875年10月23日にウイーン初演でされて初めて大成功を収めているそうです。そして1878年の、やはり記念すべきウイーン初演と同じ10月23日にニューヨーク初演が行われているそうです。こうしてみると、ビゼーには「3」という数字がまるで「運命的」とさえ思えてくるエピソードです。オペラ「カルメン」は1875年の今日(3月3日)、パリで初演されています。有名オペラで歌手なら誰もが外題役を歌いたいという「オペラ」ですから、素晴らしい演奏・録音が多く遺されています。愛聴盤(1)マリア・カラス(ソプラノ) ニコライ・ゲッダ(テノール) ルネ・デュクロ合唱団 他ジョルジュ・プレートル指揮 パリ国立歌劇場管弦楽団 (EMI原盤 東芝EMI TOCE49503 1964-7年録音)↓カラス愛聴盤(2)アドリアーナ・マリポンテ(S)、マリリン・ホーン(Ms)ジェイムズ・マクラッケン(T)、トム・クラウセ(B))、他メトロポリタン歌劇場管弦楽団、マンハッタン・オペラ・コーラス指揮: レナード・バーンスタイン(ドイツグラモフォン 471750 1973年録音)↓ホーン愛聴盤(3)ジュリア=ミゲネス・ジョンソン(ソプラノ)プラシド・ドミンゴ(テノール) ルッジェーロ・ライモンディ(バリトン) 他フランス国立放送管弦楽団・合唱団(エラートレーベル R30E-1008/10 廃盤)愛聴盤(4)フィオレンツア・コッソット(Ms)マリオ・デル・モナコ(T)レナーと・ブルゾン(Br)マリア・キアーラ(S)ペーター・マーク指揮 フィレンツェ歌劇場管弦楽団・合唱団(MONDO MUJICAレーベル MFOH10031 1971年4月ライブ録音 海外盤)まるでイタリアオペラを聴いているような声の競演が繰り広げられている稀有な演奏記録です。 ペーター・マークも「どうぞお好きなように歌って下さい」と言わんばかりの指揮で、これはコッソットとモナコ、ブルゾンの声を聴く「カルメン」。 まさに異色の演奏です。 万人にお薦めはしません。映像ソフト(1)上記(3)の映像でオペラ映画として制作されています。 スペインの熱い血と砂埃が舞い上げる、劇場を飛び出してスペインの大地が迫る凄まじいほどの激情の物語として描かれており、ジョンソンのかつてない官能的・扇情的な「カルメン」で、ホセを誘惑する場面などは官能映画と見間違えるほどの衝撃的な体当たりでの演技に脱帽です。 今のところ「カルメン」に限らず、全オペラ映像の最高傑作だと思っていますが、紹介盤はVHSですでに廃盤となっています。 画質に優れるDVDでのリリースが待ち望まれる作品です。(RCA COLUMBIA PICTUARES CVS 10530 1987年制作)映像ソフト(2)マリア・ユーイング(M:カルメン)バリー・マッコーレイ(T:ドン・ホセ)マリー・マクローリン(S:ミカエラ)デイヴィッド・ホロウェイ(Br:エスカミーリョ)、他ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団ベルナルト・ハイティンク(指揮)演出:ピーター・ホール (WANER CLASSICS 4509994992 1985年グラインドボーン音楽祭ライブ)ユーイングの「カルメン」も個性的でその官能性は美しく、歌唱も素晴らしく、ハインティンクの指揮は彼らしく端正で、少し物足りなさもありますが、カメラアングルが美しいまるでオペラ映画のような感さえある秀逸の映像作品です。↓ユーイング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1842年 初演 メンデルスゾーン 交響曲第3番「スコットランド」1875年 初演 ビゼー オペラ「カルメン」1899年 初演 R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 椿(伯洲)椿の最新画像です。撮影地 大阪府和泉市 2006年3月2日
2006年03月03日
コメント(8)
-

「トゥーランドット」/梅一輪
『今日のクラシック音楽』 プッチーニ作曲 オペラ「トゥーランドット」昨日大阪市内に出かけて一つの驚きがありました。 HMV、タワーレコードや他の大手CDショップから流れ出てくる音楽がどれも「トゥーランドット」なのです。 これも「荒川効果」なのかなあと思い、今日は以前にも話題にしましたオペラ「トゥーランドット」を採り上げました。ジャコモ・プッチーニ(1854~1924)はオペラ作曲家として不動の地位を築き、今や世界中のオペラ劇場で彼の作品が上演され続けており、イタリアオペラではヴェルディと人気を二分する人です。 彼のオペラで目を見張る特徴は、イタリアやヨーロッパの歴史・土地を舞台にした作品に限らず、外国の物語や歴史などを題材にして書かれた作品が少なくないことと、それらの作品が異国情緒をたっぷりとたたえた音楽で今でもオペラファンを楽しませてくれています。日本を背景にした「蝶々夫人」、アメリカのゴールドラッシュ時代を描いた「西部の娘」などがあり、今日の話題のオペラ「トゥーランドット」は中国を舞台にした作品です。物語は中国を舞台にしており、美しい「トゥーランドット」姫が彼女に心を寄せ、結婚を望む外国の王子たちに「謎」をかけて、それが解けた者とだけ結婚するが解けない者は死刑という極刑を課する冷たい心の姫君がいました。そこへタタールの没落・放浪王子カラフがやって来て、離れ離れとなっていた父・国王と世話をする女奴隷リューと再会するも、美しい姫を垣間見て心を奪われてしまい、この謎解きに挑戦して見事その謎を解いて姫と結婚するという、ちょっと荒唐無稽な粗っぽい筋書きの物語です。音楽は中国風の旋律が随所に散りばめられており、アリアも「泣くなリュー」(カラフ)、「千年の昔」(トゥーランドット)、「氷のような冷たい姫君さま」(リュー)、「誰も寝てはならぬ」(カラフ)などの聴かせどころがあります。私が最も好きなのはリューが自殺前に歌う「氷のような姫君さま」で、リューが自分の命を捨ててまでも王子カラフを守ろうとするアリアです。 この場面になると何度聴いてもリューの女心に心を打たれて、涙なしに聴けない音楽です。実はこの作品は、プッチーニが1924年に亡くなる直前まで書かれていたのですが、ついに完成することなく、リューが亡くなるところまで書いてプッチーニは逝ってしまいました。 残りは弟子のアルファーノがスケッチを基に完成させています。この「トゥーランドット」が1926年の4月25日に、名指揮者アルトゥーロ・トスカニーニによってミラノ・スカラ座で初演されました。リューが亡くなった場面が終わるとトスカニーニは聴衆の方を振り返り、「プッチーニ先生はここで作曲を中断されました」と言って、彼もここで指揮棒を置き初演を終えたそうです。 これがトスカニーニが聴衆に向かって語った最初で最後の言葉だそうです。その初演の翌日に現在上演されています形でやはりトスカニーニの指揮で演奏されたそうです。愛聴盤 ビルギット・ニルソン(S) フランコ・コレッリ(T) レナータ・スコット(S) モリナーリ・プラデリル指揮 ローマ王立歌劇場管弦楽団・合唱団(EMI原盤 東芝EMI TOCE6461/2 1965年録音)ニルソンにより、最高のドラマティック・ソプラノの醍醐味を味わえる盤です。 トゥーランドットとの謎解きに勝っても結婚を嫌がる彼女に王子カラフは「私の名前を言い当ててみなさい、そうすれば私はあなたのことを諦めよう」と言ったことに対して、姫は「この王子の名前がわかるまで、誰も寝てはならぬ」と命令します。王子カラフは、民衆が名前を知ろうと躍起になっている時に歌うアリアが「誰も寝てはならぬ」です。 トリノ・オリンピック開会式でパヴァロッティが歌ったのがこの場面のアリアで、荒川静香選手のフリー演技での滑りの最後にドラマティックに流れていたのもこの場面のアリアを基にした旋律です。 そのあとに姫が現れます。彼女にはリューがどうして死をかけてまで、カラフの名前を言おうとしなかったのかわかりません。 そんな姫をカラフは「あなたは人の心がわからないお人だ」と責めて、姫を抱き寄せて強引に口づけをします。舞台上ではしばらくの沈黙。 この口づけのあとで「氷のような姫君」が「一人の女」に変身します。 そのあたりの声での使い分けが、ニルソンの歌を聴いていますと、非常によくわかります。 「冷たい姫君」から「愛を知った女」に変わる重要な場面での声のコントロールと表情付けに、いつ聴いても私は身震いを覚えます。 それほどにこのニルソンの「トゥーランドット姫」は凄いのです。下記に紹介しますニューヨーク・メトロポリタン上演でのエヴァ・マルトンも80年代の第一級のドラマティック・ソプラノで、このトゥーランドットを当たり役としていましたが、ウイーンでのマゼール盤も含めてこのニルソンのような素晴らしい歌唱には一歩及んでいません。私にはこのビルギット・ニルソンの「トゥーランドット」がまるで永遠・不滅の歌唱に思えてなりません。ひょっとして近い将来にネトレプコの外題役を聴けるかなと楽しみにしています。映像はエヴァ・マルトン(S) プラッシード・ドミンゴ(T) レヴァイン指揮 メトロポリタン歌劇場管弦楽団・合唱団(ドイツグラモフォン原盤 ユニヴァーサルクラシック UCBG9012 1987年ライブ映像)ゼッフィレッリ演出の有名な豪華絢爛の舞台を楽しめます。↓ゼッフィレッリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』1795年 初演 ハイドン 交響曲第103番「太鼓連打」1824年 誕生 ベドルジーハ・スメタナ(作曲家)1873年 初演 ビゼー 小組曲「子供の遊び」1900年 誕生 クルト・ヴァイル(作曲家)1910年 初演 ドビッシー 春のロンド(管弦楽のための映像~第3曲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 梅一輪 撮影地 大阪府堺市 大仙公園 2006年2月28日
2006年03月02日
コメント(12)
-
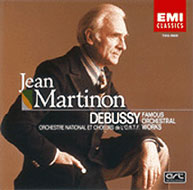
指揮者 ジャン・マルティノン/梅 ピンク
『今日のクラシック音楽』 指揮者 ジャン・マルティノン私がまだクラシック音楽に出会う3年前に、凄いフランスの指揮者が来日してN響と共演して、ほぼ2ヶ月にわたり東京、名古屋、京都、大阪でコンサートを開いていました。 フランスの指揮者ジャン・マルティノン(1910-1976)がその人です。 (ジャン・マルティノン 未購入CDジャケットから)1953年10月13日から12月9日までの演奏会のプログラムがあります。下記がそれです。 プログラムはベルリオーズ、ドビッシー、ラヴェルなどのフランス音楽、ベートーベンの第9、ストラビンスキーの3大バレエ音楽などを振っています。1953年 NHK交響楽団10月13-14日:日比谷公会堂 ベルリオーズ/幻想交響曲 ドビュッシー/牧神の午後への前奏曲 ラヴェル/スペイン狂詩曲10月28日:日比谷公会堂 ベルリオーズ/ローマの謝肉祭 メンデルスゾーン/ヴァイオリン協奏曲(VN/アイザック・スターン) ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲(VN/アイザック・スターン)11月8日:日比谷公会堂 グルック/アウリスのイフィゲニア、序曲 ラロ/スペイン狂詩曲交響曲(VN/諏訪根自子) マルティノン/交響曲第3番 ルーセル/バッカスとアリアーヌ、第2組曲11月17-18日:日比谷公会堂 ストラヴィンスキー/ペトルーシュカ ストラヴィンスキー/火の鳥、組曲 ストラヴィンスキー/春の祭典11月23-24日:日比谷公会堂 チャイコフスキー/交響曲第6番 フランク/交響的変奏曲(P/長岡純子) ファリャ/三角帽子、組曲11月27日:名古屋市公会堂 ストラヴィンスキー/ペトルーシュカ ストラヴィンスキー/火の鳥、組曲 ストラヴィンスキー/春の祭典11月28日:名古屋市公会堂 ベルリオーズ/幻想交響曲 ドビュッシー/牧神の午後への前奏曲 ラヴェル/スペイン狂詩曲11月30日/京都劇場 ベルリオーズ/幻想交響曲 ドビュッシー/牧神の午後への前奏曲 ラヴェル/スペイン狂詩曲12月1日:大阪産経会館 チャイコフスキー/交響曲第6番 フランク/交響的変奏曲(P/長岡純子) ファリャ/三角帽子、組曲12月2日:大阪産経会館 ストラヴィンスキー/ペトルーシュカ ストラヴィンスキー/火の鳥、組曲 ストラヴィンスキー/春の祭典12月8-9日:日比谷公会堂 外山雄三/小交響曲 ベートーヴェン/交響曲第9番10年後の1963年とその後の70年にも来日しています。 その時の演奏会プログラムは下記でご覧下さい。↓ジャン・マルティノン来日公演1953年(昭和28年)といえば、まだ戦後復興の途上でこれだけの都市を回るのも大変だった頃の演奏会です。勿論日程は詰まったものでなくて、リハーサルなどに時間をかけていたのか、コンサートからコンサートへの間が長い時もあります。私が驚いたのは10月28日の演奏会(メンデルスゾーンとベートーベンのVn協奏曲)でアイザック・スターンと共演していること、11月17-18日のストラビンスキーのバレエ音楽「ペトルーシュカ」「火の鳥」「春の祭典」の一夜です。スターンがすでにマルティノンとこんな早い時期に日本で共演していたのですね。 日本のクラシック音楽の土壌はやはり歴史があるんだなと改めて感じています。そしてストラビンスキーの一夜。 何と53年にはすでに「春の祭典」が演奏会で採り上げられていたのですね。 私は自分がクラシック音楽に興味を持って聴き始めてから1961年だったか62年だったか、日本フィルハーモニーをイゴール・マルケビッチが指揮してこの「春の祭典」をTVで観て、音楽の凄さを知ったのですが、それが日本における「春の祭典」元年だと信じ込んでいました。 それほどに強烈なインパクトを音楽ファンに印象付けた演奏会でした。 そしてその後、日本でも徐々にコンサートで採り上げられるようになり、LP盤での録音・演奏が増えていき今や現代音楽の古典となっていますが、そのきっかけはマルケビッチと日本フィルとのこの演奏会だと言われているくらい、伝説の名演として演奏会史上に刻まれています。しかし、その7-8年前にすでにマルティンがN響と演奏していた、これに驚きました。 しかもそれを東京・名古屋・大阪で4夜にわたって演奏してることに驚いています。 自分の勉強不足をまざまざと見せ付けられました。ジャン・マルティノンの名前を知ったのは、中学3年生の頃だと記憶しています。 英デッカにウイーンフィルと録音したステレオ録音初期のLPで、チャイコフスキーの「悲愴」交響曲が話題になってました。しかし、彼の演奏を録音で聴くようになったのは70年代になってからでした。 RCAに録音した「フランス音楽集」で、当時彼がシカゴ交響楽団の音楽監督を務めている頃の録音です。 その頃には私にも指揮者の表現する音楽を聴いていて違い(他の指揮者・演奏家との)がわかり、言葉で表現することが出来るようになっていましたから、アンセルメの指揮するフランス物とは違う音楽に魅了されていました。LP盤に刻まれたマルティノンのドビッシーやラヴェルの音楽は、「スコアが透けて見える」という表現があてはまるような、実に透明性豊かな音楽でした。 アンセルメのような精緻な音楽作りとは異なる、リズム一つをとっても非常に繊細な感覚で刻み付けられており、感情をあまり表に出さずに情緒的に音楽が流れているのですが、彼特有の透明な響きが「知的な」美しさを湛えています。シカゴ交響楽団ではむしろ不遇な時代を過ごしたと言われていますが、この演奏を聴く限りではシカゴ響の美しいサウンドを十全に引き出している、美しい音楽を表現していると感じています。フランスに帰ったあとはEMIレーベルにフランス国立放送管弦楽団と残したフランス物が、今尚ファンを魅了しているそうです。これら70年代にEMIに遺した録音では「幻想交響曲」だけを聴いていて、ドビッシーやラヴェルの音楽を聴いていません。 これを機に聴いてみたいと思うのですが、現在所有するRCA盤に収録された曲と重なっているのが躊躇う理由です。そのジャン・マルティノンが1976年の今日(3月1日)、66歳という現代では早過ぎるくらいの年齢で亡くなっています。 もう少し彼の演奏を出来れば日本で聴きたかったと願うのは私だけではないと思います。愛聴盤 マルティノン・フランス音楽作品集 シカゴ交響楽団(RCAレーベル 09026・63683 1964-68年録音 海外盤)↓フランス音楽・シカゴ響もう1枚 マルティノン指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7021 1958年録音)↓悲愴・ウイーンフィル両盤とも何度再発売されたかわかりませんが、とにかく再発売の数でも群を抜く回数だと思います。 ウイーンフィルとの「一期一会」の録音で「悲愴」とは。 美しい演奏の「悲愴」です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1810年 誕生 フレデリック・ショパン(作曲家)1867年 初演 シューベルト 弦楽四重奏曲第12番「四重奏断章」1869年 誕生 ディミトリ・ミトロプーロス(指揮者)1924年 初演 ショスタコービチ 交響曲第7番「レニングラード」1976年 没 ジャン・マルティノン(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 梅 ピンク昨日堺市の大仙公園に咲く「梅」を撮ったのをアップします。 梅の見頃はまだまだのようです。撮影地 大阪府堺市 大仙公園 2006年2月28日
2006年03月01日
コメント(6)
全32件 (32件中 1-32件目)
1
-
-

- 今日聴いた音楽
- ☆乃木坂46♪奥田いろは、本日『バナナ…
- (2025-11-25 12:14:27)
-
-
-

- プログレッシヴ・ロック
- Steve Hackett - The Lamb Highlight…
- (2025-11-22 00:00:10)
-
-
-

- オーディオ機器について
- 試作スピーカー31.9(アルマイト処理…
- (2025-11-24 21:13:19)
-







