2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年09月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

サルヴァトーレ・リチートラ/シラサギスゲ(白鷺菅)
『今日のクラシック音楽』 サルヴァトーレ・リチートラを聴くソニーからリリースされました新盤「禁断の恋~サルヴァトーレ・リチートラ」を今夜聴きました。 サルヴァトーレ・リチートラはパヴァロッティの継承者とも言われている今年37歳のイタリアのテノール。 彼の2002年5月のアメリカ・ニューヨークでのパヴァロッティの急な休演の代役デビューはあまりも有名で、一夜にして世界的な名声を得た純正のイタリアの声を聴かせてくれるテノール歌手です。 性質はリリコですが、アリアによってかの有名な故マリオ・デル・モナコを彷彿とさせる声の持ち主です。 ドラマティコと呼んでいいほど強靭な声で表現をするアリアもあります。 このCDで録音されたアリアはテノール歌手なら誰もが歌ってみたい、まるでオペラの「紅白歌合戦」のようなアリアをずら~と並べています。 聴き終わったあとは満腹といった感のある聴きごたえのある声です。昨年は確か5月に大阪にも来演して関西フィルだったと思うのですが、共演して大成功を収めたように聞いています。明るく輝きを失わない歌唱は、「これぞ、イタリア・オペラ!」という感があります。 性格描写では右に出る者がいないほどに、実に巧みに表現しており、そこへイタリアの太陽のように明るく輝く声ですから、「純正イタリア歌手」と言われるのが頷けます。まだ37歳。 これからも活躍が期待されるテノールです。「禁断の恋」 サルヴァトーレ・リチートラ(テノール) プリニョーリ指揮 ジュゼッペ・ベルディ交響楽団↓(SONY CLASSICAL 8287678852 USA輸入盤)日本盤はこちら(収録曲も出ています)↓日本盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』 1791年 初演 モーツアルト オペラ「魔笛」1908年 誕生 ダヴィッド・オイストラフ(ヴァイオリニスト)1935年 初演 ガーシュウイン オペラ「ポーギーとベス」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 シラサギスゲ(白鷺菅)以前からこの花を撮っていましたが、天候が良すぎた日が多くていつも「白飛び」現象が起こって白地部分がはっきりとしない写真ばかりでしたが、白地部分が完全な白にはなっていませんが、写真撮影をはじめて3年でやっと何とか撮れた花です。 撮影地 大阪市立長居植物園 2006年9月22日かやつりぐさ科 ディクロメナ属 北アメリカ地方原産 水生植物で夏に開花します。 白鷺が飛んでいる姿に似ていることから命名されているそうです。 「白鷺蚊帳吊(シラサギカヤツリ)」 とも呼ばれているそうです。
2006年09月30日
コメント(4)
-

念仏奉仕から帰りました/ニラの花
『念仏奉仕から帰りました』京都・西本願寺への1泊2日の念仏奉仕活動から帰ってきました。 この西本願寺は親鸞聖人が開祖の浄土真宗の総本山で、毎年1回念仏奉仕に出かけています。 南大阪(泉州一帯)の浄土真宗の寺で「三郡組」という組織を組んで、今回は総勢206名でこの念仏奉仕をおこなってきました。昨日は総御堂と呼ばれる金堂にあたるお勤め場所(650畳敷き)の畳を乾いた雑巾でから拭きを何度も何度も行っていました。今日は朝6時からのお勤めに参加してきました。 総本山門主自らお仏飯を阿弥陀如来にお供えする儀式があり、その後40分間お経を唱えてきました(テキストはその場で借ります)。 このお仏飯の1つの大きさに驚きました。 なんと約1升もの米が一つの什器に供えられているのです。正確には9.3合です。 とても大きなお仏飯でした。それが終わってから朝食となって、9時から境内の庭園の落葉集めや草抜きなどを2時間ほど行い、奉仕は終わりました。とても清々しい気持ちで帰ってきました。 両手を合わせて念仏を唱えることが心を落ち着かせるとてもいい経験です。 年に一度のお勤めで、来年も行きたいと思っています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ニラの花自宅近くの畑の土手で赤い彼岸花が咲いていて、それを撮りに行ったのですが見事に失敗しました。 そのヒガンバナの傍でニラの花が咲いているのを撮ってみました。 撮影地 大阪府和泉市 2006年9月26日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1918年 初演 ホルスト 組曲「惑星」(非公開初演)1920年 誕生 ヴァツラフ・ノイマン(指揮者)1930年 誕生 リチャード。ボニング(指揮者)
2006年09月29日
コメント(6)
-

念仏奉仕/時計草
『念仏奉仕』今日は朝から1泊2日の京都・西本願寺へ「念仏奉仕」に出かけます。 南大阪のお寺の檀家とバス3台を連ねて西本願寺にお参りして、雑巾がけや境内の清掃と翌日(29日)早朝5時からのお勤めをおこなってきます。 28日・29日の両日は音楽記事は休みます。 両日共、花画像だけの日記となります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 時計草長居植物園入り口付近に毎年咲く秋の定番のような花です。撮影地 大阪市立長居植物園 2006年9月22日
2006年09月28日
コメント(8)
-
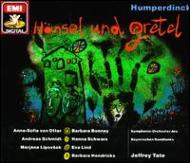
オペラ「ヘンゼルとグレーテル」/ススキ
『今日のクラシック音楽』 フンパーディンク作曲 オペラ「ヘンゼルとグレーテル」エンゲルト・フンパーディンク(1854-1921)は実に楽しいオペラを書き残してくれました。 グリム兄弟の童話を原作にしたオペラ「ヘンゼルとグレーテル」がそれです。ドイツの森が舞台で、おとぎ話の世界の出来事です。 箒作りのペーターの妻ゲルトルートは家の中で遊んでいるヘンゼルとグレーテルの兄妹を叱り付けて、森の中へ野いちごを籠いっぱいに採りに行くように送り出します。帰ってきた亭主のペーターはこれを聞いて驚きます。 それもそのはず、その森には子供を食べる魔女が住んでいたのです。 すぐに助けに森へと走ります。一方、兄と妹は森の中で遊んでいるうちに道に迷ってしまいます。 あたりは暗くなってくるし途方にくれる二人の子供の前に「眠りの精」が現れて、二人は眠ってしまいます。やがて「暁の精」に起こされた二人の前にお菓子が出現して喜んでいると、魔女がしのび寄って来て魔法の杖で二人を捕らえてしまいます。 魔女は二人を焼いて食べてしまおうと準備をしているうちに、二人の知恵で逆に竈に入れられてしまいます。喜ぶ二人の前で竈が爆発して魔法でお菓子にされていた大勢の子供たちが現れます。 そこへペーター夫妻が着いて幕となります。音楽は平明で流麗、イタリア・オペラのようなドロドロした人間関係もなく、兄が妹を励ます姿も微笑ましく、また魔女が魔法の杖で空中を飛ぶような場面もあり(これはDVDなどの映像でないとわかりませんが)、童話のおとぎ話の世界に遊ぶような楽しいオペラで、家族で楽しめる趣向の作品です。オペラ「ヘンゼルとグレーテル」を書き残したエンゲルト・フンパーディンクは1921年の今日(9月27日)、67歳の生涯を閉じています。愛聴盤(CD) ジェフリー・テイト指揮 バイエルン放送交響楽団 アンネ=ゾフィ・フォン・オッター(Ms)、バーバラ・ボニー(S)、バーバラ・ヘンドリックス(S)他 (EMIレーベル 754022 1989年7月録音 海外盤)愛聴盤(DVD) ゲオルグ・ショルティ指揮 ウイーンフィルハーモニー、ブリギッテ・ファスベンダー(Ms)、エディタ・グルベローヴァ(S)、ヘルマン・プライ(Br)(グラモフォン・レーベル 0734110 1981年録音 海外盤)アニメーションも交えた幻想的な映像とショルティ指揮のウイーンフィルの豊かな響き、ファベンダー(ヘンゼル役)、グルベローヴァ(グレーテル役)の美しい声、どれをとっても一級品の仕上がりです。 これでCD1枚分の価格です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1880年 誕生 ジャック・ティボー(ヴァイオリニスト)1921年 没 エンゲルト・フンパーディンク(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ススキもうすぐ「仲秋の名月」となります。 最近は見られなくなりましたが、子供の頃はお月様が上がって来る頃には東の部屋に月見団子を置いた「三方」を据えて、その横に「ススキ」を鎮座させていました。 そうしたことで四季の喜びを表していましたが、最近はそういう四季感がなくなってきましたね。秋らしく「ススキ」の画像を掲載します。撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2006年9月19日
2006年09月27日
コメント(6)
-

「ランメルモールのルチア」/マツムシソウ/丹波哲郎逝く
『今日のクラシック音楽』 ドニゼッティ作曲 オペラ「ランメルモールのルチア」ガエタノ・ドニゼッティ(1797-1846)は弦楽四重奏曲などを書いていますが、何といってもオペラ作曲家として名を成しており、オぺラ「愛の妙薬」「連隊の娘」「ドン・パスクワーレ」などを書き残しています。 それらのオペラ作品の中でも最高傑作として今でも舞台や録音などで頻繁に採り上げられているのが「ランメルモールのルチア」です。17世紀のスコットランドを舞台に豪族レーヴェンストック家とアシュトン家の争いに巻き込まれて非業の死を遂げる若き男女の悲恋物語で、オペラ特有の物語の図式です。 これは東西南北、世界のどこにでもあるような「家」同士の拮抗中にその両家の男女が恋に落ちて、愛し合いながら結ばれることがないというシェイクスピアの「ロメオとジュリエット」の物語の図式です。アシュトン家の娘ルチアとレーヴェンストック家のエドガルド当主が愛し合っていましたが、ルチアは意に沿わない政略結婚をさせられることとなり、結婚誓約書を書かされているところにエドガルドが現れて、ルチアを罵ります。ルチアは婚礼の夜に花婿を殺して、狂気を帯びて現れてエドガルドとの愛を語り(狂乱の場)、その場で発狂して亡くなります。 それを知ったエドガルドはアシュトン家との決闘の前に、彼女への弔鐘が聞こえる中で、自刃して果てます。このオペラはベルカント・オペラの最高傑作と言われているだけに、旋律はどこをとっても美しく流れており、「歌」を聴かせてくれるイタリア・オペラの醍醐味を味わえる作品です。 とりわけ聴き所は「狂乱の場」のルチア(ソプラノ)の長大なモノローグです。恋人エドガルドと引き裂かれて、意に沿わない結婚を強いられて夫を殺し、発狂して現れる場面は何度聴いても観ても感動させられるコロラトゥーラ・ソプラノの最高の見せ場となっています。1835年の今日(9月26日)、このオペラ「ランメルモールのルチア」が初演されています。愛聴盤 マリア・カラス、ジュゼッペ・ディ・ステファーノ、ティト・ゴッビ、 トリオ・セラフィン指揮 フィレンツェ五月祭管弦楽団・合唱団(EMIレーベル 5627642 1953年録音 海外盤)かつて東芝EMIからAngel盤でTOCE3901-2として発売されていたのと同じ音源で、この録音盤は何度も再発売を繰り返しています。 Naxosからも2005年4月に8.110131-2として復刻されて2000円という廉価でリリースされています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1835年 初演 ドニゼッティ オペラ「ランメルモールのルチア」1877年 誕生 アルフレッド・コルトー(ピアニスト)1898年 誕生 ジョージ・ガーシュウィン(作曲家)1945年 没 ベラ・バルトーク(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 マツムシソウ花の写真撮影の条件の一つに天気の具合があります。 曇り空であまり暗くてもいけないし、かと言って快晴が必ずいいとは限りません。 勿論撮影する被写体にもよりますが。 やはり「花曇り」が最適の条件かと思います。 そういう意味ではこの画像被写体の撮影時の快晴は、この花の魅力を全て伝えてはいません。 あまりの快晴下での撮影が影響しています。 撮影地 神戸・六甲高山植物園 2006年9月8日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『丹波哲郎逝く』 個性的な脇役で数多くの映画に出演して、TV時代劇やドラマ「Gメン」などでその名を高めた映画俳優・丹波哲郎が亡くなりました。 享年84歳。神東宝映画で1952年にデビュー。その頃は陰気な悪役を演じていましたが、TV時代劇「三匹の侍」でニヒルな役で脚光を浴びて一躍人気スターになったように覚えています。 デビュー後50年を超える俳優生活を続けており、出演作品は500にも及ぶそうです。私には何と言っても松竹映画「砂の器」(松本清張原作 野村芳太郎監督 橋本 忍脚本 芥川也寸志音楽監修)の刑事役が忘れられない思い出です。 演出もいい、脚本もいい映画でしたが、丹波のぶっきら棒な台詞回しがぴったりとあてはまった名演技でした。 ソナタ形式で言えば「コーダ」にあたる部分の捜査会議で、事件の解明を説明していく場面は迫真の演技で、この刑事役は彼しかいないと思わさせる演技でした。それと鶴田浩二や高倉 健の東映ヤクザ映画路線全盛の時代に演じた侠客やギャングのボスなどもこの人独特の風情があり、侠客役での眉毛をキュッと寄せた着流し姿は背が高いために絵になる俳優でした。昔ながらの映画俳優といった感のある人で、新劇の俳優のような演技・台詞回しではなくて、むしろ大根役者のような感さえあった俳優で、それは最後まで続いた人でした。 彼の口癖のような言葉「それはだなあ」が映画・TVドラマの中でも頻繁に聞かれました。彼の代名詞のような言葉でした。得意の英語・英会話を駆使してショーン・コネリーと「007は二度死ぬ」で共演するなど、国際的映画俳優としても活躍した人でした。長い俳優生活、ご苦労さまでした。 霊界でごゆっくりおやすみください。合掌
2006年09月26日
コメント(12)
-
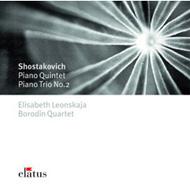
ショスタコービチ ピアノ三重奏曲第2番/イヌタデ
『今日のクラシック音楽』 ショスタコービチ作曲 ピアノ三重奏曲第2番今年はモーツアルト生誕250年にあたり色々なコンサート・リサイタルなどが開催されたり、演奏家によるモーツアルトの作品の新録音事業が行われていますが、その陰に隠れてシューマンの没後150年と同様に盛り上がらないのがショスタコービチ生誕100年の事業です。 今日がショスタコービチの生誕100年の節目の日になりますので、彼の書いた「ピアノ三重奏曲ホ短調 作品67」を採り上げました。 ディミトリ・ショスタコービチ(1906-1975)は2曲のピアノ三重奏曲を書き残していますが、第1番は17歳のときに書かれた習作のようなもので、現在はほとんど演奏される機会がないようで、彼のピアノ三重奏曲と言えば、1944年8月13日に完成された第2番を指しているようで、演奏会や録音でもほとんどこの第2番が採り上げられています。この作品は、ショスタコービチ以前のチャイコフスキー、ラフマニノフ、アレンスキーといったロシアの作曲家が、自分と何らかの関わり合いのあった故人を追悼して書いたピアノ三重奏曲と同じように、ロシアの音楽学者ソレルチンスキーの死を悼んで書かれています。 どうもロシアでは故人を追悼する曲としてはピアノ三重奏曲を選ぶ伝統みたいなものがあるようです。作品全編に悲痛な感情が色濃く影を落としていて、故人を悼むショスタコービチの心情が痛切に音楽に表現されています。第1楽章の弱音器をつけたチェロの悲しげな旋律がまるで挽歌のように聴こえてきたり、第3楽章ラルゴでの痛切な悲しみを歌う、ヴァイオリンとチェロの旋律は悲しみの心情が極限までに歌い尽くされているように聴こえます。第4楽章では、第1楽章の主題が再現されて徐々に壮大な緊迫感のあるクライマックスを築き上げて、やがて静かに消え入るように終わっていて、ショスタコービチの悲しみを窺えます。神社役員で私の幼馴染でもある人が先日亡くなったこともあって、今日はこの曲を聴いています。1906年の今日(9月25日)、ディミトリ・ショスタコービチが生まれており、今年が生誕100年のメモリアル・イヤーとなっています。愛聴盤 エリザベート・レオンスカヤ(P) ボロディン四重奏団メンバー (Teldec原盤 Elatusレーベル 2564.60813 1995年4月録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1906年 誕生 ディミトリ・ショスタコービチ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 イヌタデ 撮影地 神戸・六甲高山植物園 2006年9月8日蓼(たで)科 タデ属 7月半ばから10月末ごろまで開花しています。 辛味がなく食べられない蓼、の意味で命名された名前だそうです。
2006年09月25日
コメント(8)
-
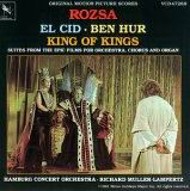
ミクロス・ローザの映画音楽/都草(ミヤコグサ)
『ミクロス・ローザの映画音楽』私は中学生の頃から映画と映画音楽が大好きでした。 1957年ごろから興味を持ったのですが、同居していた叔父がとても映画好きで、映画館へよく連れて行ってもらいました。 また叔父は映画音楽も好きで、ラジオ放送でもLP盤でもよく聴いていましたから、その影響も大いにあります。今日は映画音楽の巨匠ミクロス・ローザの作品を聴いています。 映画「ベン・ハー」「エル・シド」「キング・オブ・キングス」のオリジナル・スコアで演奏されたディスクです。ミクロス・ローザは1907年ハンガリーの首都ブダペストに生まれ、ライプツィヒ大学で本格的に音楽の勉強に専念し才能を開花させたようです。映画音楽は、仕事で訪れたパリでフランス六人組の1人オネゲルの影響を受けて、当時活躍していた監督ジャック・フェデーの下で初めて映画の曲を書いたのがきっかけだと言われています。1940年「バグダッドの盗賊」でハリウッドに移って以来、ハリウッドの大作物には欠かせない存在の大物作曲家として大活躍。特に史劇ものにはクラシック音楽を超えた素晴らしい音楽を書いています。その代表作が上記の3作品です。絶対的強みを発揮。 特に「ベン・ハー」の壮大・雄渾な旋律は1960年に映画を観て以来、私の好きな音楽の一つになっています。 「序曲」の壮大な音楽の流れ、「愛のテーマ」の抒情的な美しさ、「戦車競争」の迫力ある描写などは特に人気のある音楽となっています。 この「ベン・ハー」だけでも3枚のディスクで聴いていますが、今日はそのうちの1枚を聴いています。 もうこれほど壮大で抒情に溢れた映画音楽を書く人がいなくなってしまったことは寂しい限りです。愛聴盤 リヒャルト・ミューラー=ランパーツ指揮 ハンブルグ・コンサート・オーケストラ(Varse Sarabande Rcords VCD47268 1962年録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 名前不詳の花昨日掲載の龍舌蘭のすぐ近くに一輪だけ咲いていました。 どこからか種が飛んできて花が咲いたのでしょう。 あまりに可愛いので撮ってみましたが、名前がわかりません。 おそらくマメ科の花だと思いますが、どなたかご存知の方は教えて下さい。撮影地 大阪府和泉市 2006年9月19日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1922年 誕生 エットーレ・バスティアニーニ(バリトン)
2006年09月24日
コメント(8)
-

龍舌蘭その後
ともの『今日の一花』 龍舌蘭の実(種?)先日この日記で掲載しました「龍舌蘭」が1ヶ月経って実になってしまったと自衛官から聞いて、早速観に行きました。 話の通りに見事に実がなっていました。 この実を植えるとこんな立派な木のような花が咲くのでしょうか? 不思議なサボテン科の花です。実になってしまった龍舌蘭撮影地 大阪府和泉市 2006年9月19日威風堂々の龍舌蘭(約7メートルあります) 花がこれです。 撮影日付はいずれも2006年8月3日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1835年 没 ヴィンチェンツォ・ベルリーニ(作曲家)
2006年09月23日
コメント(10)
-

ツリフネソウ
『長居植物園』今日は長居植物園に花の撮影に行ってきました。 朝9時半の開門を待ちかねたように入って、午後1時まで秋の花たちを撮ってきました。 時計草、ヌスビトハギ、コスモス、名前のわからないキク科の白いヒメジョオンのような花、赤と白の彼岸花、ミソハギ、女郎花、シラサギスゲなどを撮ってきました。 後日これらの花たちを掲載しようと思っていますが、まだPCに取り込んでいませんので、はたしてどんな画像が飛び出してくるやら。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ツリフネソウ六甲高山植物園のいたるところに咲いていました。 今が旬の花の一つですね。撮影地 神戸・六甲高山植物園 2006年9月8日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1869年 初演 ワーグナー 楽劇「ラインの黄金」1916年 誕生 ヘンリク・シェリング(ヴァイオリニスト)
2006年09月22日
コメント(4)
-

カノコユリ/シャーリー・バッシー
ともの『今日の一花』 カノコユリこの花は以前にも掲載しましたが、あまりにきれいに咲いていましたので、シャッターを切っていました。 この花は傾斜のきつい場所に咲いていましたので、こういうアングルでないと撮れなかったのが残念です。 もう少し右か左に寄って撮ればもっといい構図になったはずですが。 撮影地 神戸・六甲高山植物園 2006年9月8日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『シャーリー・バッシー』私の永遠の歌姫、イギリスのシャーリー・バッシー。 気分が落ち込んでいる時には彼女のゴージャスな歌声を聴いてみたいと思っています。映画007シリーズの主題歌「ゴールドフィンガー 」、「ダイアモンドは永遠に 」の大ヒットで世界的な大スターとなった英国の国民的歌手。007の主題歌でものすごいパワフルな歌を披露するかと思えば、ビートルズのジョージ・ハリソンのSomethng、カーペンターズの「ふたりの誓い」などのしっとりとした歌唱、イタリアのミーナも顔色なしと思われるカンツォーネの激情、またミュージカルナンバーでのコケティッシュな歌唱と、まさに声の七変化のような素晴らしい伸びのある声で楽しませてくれる、1937年生れの本物のエンターテイナーです。大阪フェスティバルホールでの歌唱ではまるで腰を抜かしたように聴いていました。そして10分間に渡る聴衆総立ちのスタンディング・オベーション。母国の英国で、男性のナイトに相当する女性の敬称、デイムを受勲。底知れぬ歌唱力とゴージャスなコスチュームで観客を魅きこむカリスマ的エンタテイナーです。15歳からクラブ歌手として下積みから鍛え上げられた、叩き上げの職人ににでも似た本物の歌手とはこういう人を指して言うのでしょう。LP時代にはこの人のレコードを20枚近く持って聴いていました。 おそらく1枚だけ私のライブラリーから取り出せと言われると、大バッハ、ハイドン、モーツアルト、ベートーベン、ブラームス、シューベルト、シューマン、ブルックナー、マーラー、ワーグナーや数々のイタリア・オペラでなくて、この1枚を選ぶかもしれません。 それほどにこの人の歌唱は聴く人の心を打つ素晴らしいエンターテイナーです。今日は久しぶりに彼女の歌を堪能しようと思います。(EMI原盤 東芝EMI TOCP65656)1 ダイアモンドは永遠に 2 ヒストリー・リピーティング 3 ビッグ・スペンダー 4 キス・ミー・ハニー・ハニー(キス・ミー) 5 ムーンレイカー 6 サムシング 7 ふたりの誓い 8 愛に生きて 9 ハートに火をつけて 10 何もない私 11 ある愛の詩 12 永遠の愛 13 アイル・ゲット・バイ 14 すべての山に登れ 15 アズ・ロング・アズ・ヒー・ニーズ・ミー 16 ユール・ネバー・ノー 17 ホワット・カインド・オブ・フール・アム・アイ 18 行かないで 19 そして今は 20 ゴールドフィンガー 21 生命をかけた愛 22 私の人生 ↓(シャーリー・バッシー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『長居植物園』7月に花蓮を撮りに行って以来ご無沙汰しています長居植物園。 気分もすぐれない数日を過ごしていますので、今日はこの長居植物園に撮影に行こうと思っています。ヒガンバナやコスモス、萩などが見頃だという情報です。 うまく撮れたらここに掲載いたします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1874年 誕生 グスターヴ・ホルスト(作曲家)
2006年09月21日
コメント(16)
-

キレンゲショウマ/神社役員逝く
ともの『今日の一花』 キレンゲショウマこれも秋を彩る花の一つです。撮影地 六甲高山植物園 2006年9月8日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『神社役員逝く』この町の神社役員の一人が9月5日に入院して検査を受けていましたが、去る17日(日)の早朝に亡くなりました。 前日の16日の午後2時半頃に他の神社役員たちと見舞った時は、黄疸症状は出ていたものの元気にベッドから起き上がって座って話をしていたのですが、私たちが帰って15分後に喀血して、翌朝になくなったそうです。まるで私たちのお見舞いを待ってくれていたかのようです。 十二指腸の傍でリンパ腫の大きなのが出来ていたそうです。 それが破裂したようです。私より2歳年上で数軒先に住んでいて、小さい頃から野球などをして遊んでくれた人でした。62歳まで単身赴任で働いた後に完全に退職して、これから余生を奥さんと共に楽しもうとしていた矢先です。17日以来私はショックに見舞われており、昨日葬儀が終わったのですがまだ引きずっています。 そのために音楽記事を書けない状態になっています。自分と同じ年、あるいはそれに近い年の方が亡くなりますと、ほんとにその死がこたえてきます。
2006年09月20日
コメント(14)
-

サワキキョウ
ともの『今日の一花』 サワキキョウ涼しげに咲く初秋の花です。撮影地 神戸・六甲高山植物園 2006年9月8日ききょう(桔梗)科 ミゾカクシ属 湿地に群生するようです。 青紫色が鮮やかです。 「ベニバナサワギキョウ」 という紅色もあるようです。 花は下から上へと咲いていきます。キキョウに似ているところから命名されているようです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』 1908年 初演 マーラー 交響曲第7番「夜の歌」1912年 誕生 クルト・ザンテルリング(指揮者)1972年 没 ロベール・カサドジュ(ピアニスト)
2006年09月19日
コメント(2)
-
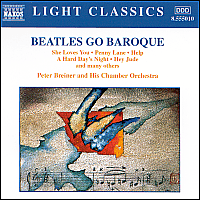
ビートルズ合奏協奏曲集/キイジョウロホトトギス
『今日のクラシック音楽』 ビートルズ合奏協奏曲集2003年にNaxosからユニークなディスクがリリースされています。 曲はすべてビートルズナンバーですが、演奏はバロック音楽風合奏協奏曲スタイルに編曲されています。第1集~第4集まであり、どの曲もいかにもバロック音楽を聴いているかのような、実に巧みなアレンジが施されています。 ヘンデル風コンチェルト・グロッソスタイルの第1集、ヴィアヴァルディ風、大バッハ風、コレルリ風と続く第2集~第4集。第1曲のShe Loves Youなどどこを切ってもバロック音楽といった感じで、まづこのディスクの素晴らしさに驚嘆させられているうちに、ビートルズのヒット・ナンバーの旋律がバロック・スタイルのなかで浮かび上がり、それが実に自然に溶け込んでいると手法です。編曲の妙なる技法によってバロック音楽を聴く楽しみを味わえて、しかも全20曲のビートルズ・ナンバーを味わえるという、癒し系音楽の典型のようなディスクです。編曲はこのCDの指揮を執っているペーテル・ブレイナーによるものです。このCDです。 「Beatles Go Baroque」ペーテル・ブレイナーと彼の室内オーケストラ↓ (Naxosレーベル 8.555010 1992年2月ー3月録音)収録曲1.ビートルズ合奏協奏曲 第1番(ヘンデル・スタイル) シー・ラヴズ・ユー/レディ・マドンナ/フール・オン・ザ・ヒル/ハニー・パイ/ペニー・レイン2.ビートルズ合奏協奏曲 第2番(ヴィヴァルディ・スタイル) ビートルズがやってくるヤァ!ヤァ!ヤァ!/ガール/アンド・アイ・ラヴ・ハー/ペイパーバック・ライター/ヘルプ3.ビートルズ合奏協奏曲 第3番(J.S.バッハ・スタイル) ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード/エイト・デイズ・ア・ウィーク/シーズ・リーヴィング・ホーム/恋を抱きしめよう/ヘイ・ジュード/イエロー・サブマリン4.ビートルズ合奏協奏曲 第4番(コレルリ風) ヒア・カムズ・ザ・サン/ミッシェル/グッド・ナイト/キャリー・ザット・ウェイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1974年 没 斉藤秀雄(音楽教育者・指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 キイジョウロホトトギス秋を彩る花の一つですが、なかなかお目にかかることのない花の一つでもあります。 私が訪れた時にはまだ蕾で開花していませんでした。 上の写真は私の撮ったものですが、開花している写真は他の人が昨年撮った写真です。蕾 撮影地 神戸・六甲高山植物園 2006年9月8日開花したところです。
2006年09月18日
コメント(16)
-

サワフジバカマ
ともの『今日の一花』 サワフジバカマこの花は「サワフジバカマ」かもしれませんが、お判りになる方がおれれましたら教えて下さい。撮影地 神戸・六甲高山植物園 2006年9月8日
2006年09月17日
コメント(9)
-

永遠のマリア・カラス/チングルマ
『今日のクラシック音楽』 永遠のマリア・カラス今日は久しぶりにマリア・カラスの世界に浸ってみようと思っています。1960年初頭にNHKの招聘で来日したイタリア歌劇団公演をTVで観て、オペラへと傾倒していったのですが、このブログでも何度も書いていますように、この時のマリオ・デル・モナコの「道化師」とシミオナートの「カヴァレリア・ルスティカーナ」を客席で聴けたことは、今でも私の大事な宝となっています。その来日公演の大きな目玉演目が、モナコとテバルディの「アンドレア・シェニエ」であり、テバルディの「トスカ」でした。どちらもNHK音源のDVDで当時の舞台公演を観ることが出来ますが、何度観ても「アンドレア・シェニエ」の終幕の幕切れの2重唱、「トスカ」の「歌に生き、恋に生き」には鳥肌立って観ています。「歌に生き、恋に生き」の歌唱後の客席の興奮と熱狂ぶりは大変なものでした。確か15分間は拍手が鳴り止まず、テバルディも困惑している表情がありありと見えたものでした(DVDではそのところが割愛されています)。そのテバルディと当時は人気を二分していたソプラノ歌手にマリア・カラスがいました。当時私はテバルディに夢中になっていてカラスの声をあまり聴いた覚えがないのですが、それから3年後くらいして大学生の頃にLP盤で「カルメン」を聴き、「トスカ」を経験して、「ノルマ」でぶったまげた思い出が残っています。テバルディの声は美しく澄んでいて、「声」で勝負すれば間違いなくテバルディに軍配が上がると思います。片やカラスは、美しい声ではないのですが、潤いがあり、少し鼻にかかった声は魅力の一つでした。そして、カラスを語る時に必ず形容される言葉ー「激情」という感情表現の巧さは抜群でした。恐らく現在でも彼女の右に出る者がいないほど、演技力は抜群のものがあり、映像でなくてCDで聴いていても感情の入れ込みと、表現の多様性は容易に聴き取れる「激しさ」がありました。 この点ではテバルディをはるかに凌駕するソプラノでした。ディ・ステファーノのカヴァラドッシ、ティト・ゴッビのスカルピア、デ・サバタ指揮の演奏・録音の「トスカ」は、今尚私の心を揺さぶる永遠の名演奏で、テバルディとはまた違った「トスカ」の魅力を聴かせてくれます。(Naxosレーベル 8.110256 1953年録音 2枚組で2000円です)↓トスカカラスの名唱をダイジェストのような形でリリースされているアリア集のCDがあります。時間のない時はこのCDを愛聴しています。↓(EMI原盤 東芝EMI TOCE55183 1954年ー1965年録音)↓カラス1 ハバネラ(恋は野の鳥)歌劇「カルメン」第1幕より2 セビリャの城壁の近くに 歌劇「カルメン」第1幕より3 わたしは夢に生きたい(ジュリエットのワルツ)歌劇「ロメオとジュリエット」第1幕4 ある晴れた日に 歌劇「蝶々夫人」第2幕より5 わたしのお父さん 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より6 お仲間の方々~気もはればれと 歌劇「夢遊病の女」第1幕より7 亡くなった母を 歌劇「アンドレア・シェニエ」第3幕より8 さようなら、ふるさとの家よ 歌劇「ワリー」第1幕より9 春はめざめて 歌劇「サムソンとデリラ」第1幕より10 さようなら、私たちの小さなテーブルよ 歌劇「マノン」第2幕より11 ああ、そはかの人か 歌劇「椿姫」第1幕より12 さようなら、過ぎ去った日よ 歌劇「椿姫」第3幕より13 この柔らかなレースの中で 歌劇「マノン・レスコー」第2幕より14 わたしの名はミミ 歌劇「ラ・ボエーム」第1幕より15 今の歌声は 歌劇「セビリャの理髪師」第1幕より16 清らかな女神よ 歌劇「ノルマ」第1幕より17 私の生まれたあのお城 歌劇「アンナ・ボレーナ」第2幕より18 苦い涙をそそいで(狂乱の場)歌劇「ランメルムーアのルチア」第3幕より19 氷のような姫君の心も 歌劇「トゥーランドット」第3幕より20 歌に生き、恋に生き 歌劇「トスカ」第2幕よりこれ1枚からでもカラスの凄さがわかるお買い得アリア集です。そのマリア・カラスが1977年の今日(9月16日)、フランス・パリで54歳の生涯を閉じています。マリア・カラスについてはこのサイトで非常に詳しく語られています。↓私のマリア・カラス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1977年 没 マリア・カラス(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 チングルマこの花は今回初めて観ました。 今までに一度も観たことのない花です。 おもしろい形状の花です。 これも六甲で撮ったものです。 上の画像が私が撮りました「チングルマの実」です。花が散ってしまうとこういう形になるそうです。花は下の画像ですが、この写真はネットから拾ってきました。 無断借用転載です。 オーナーさん、ほんとにごめんなさい。 申し訳ありません。 撮影地 神戸・六甲高山植物園 2006年9月8日花の画像 バラ科 ダイコンソウ属主に高山で咲く花だそうです。
2006年09月16日
コメント(7)
-
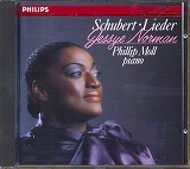
大歌手ジェシー・ノーマン/ゲンノショウコ
『今日のクラシック音楽』 大歌手 ジェシー・ノーマン(ソプラノ)アメリカの名歌手ジェシー・ノーマン(1945~)は、すでに60歳を過ぎていますから引退をしていると思います。 彼女は黒人歌手なのでオペラを舞台で歌うのに制約があったろうと思いますが、レコードやCDで聴く限り、その歌唱は心地よさ、快さが聴いている者の心の琴線に触れてくる歌手でした。オペラでも歌曲でもノーマンの歌唱は「自然体」を思わせるような、ヒロインでも歌曲の中の人物の感情をストレートに表現しているかのような、喜びや悲しみがごく自然に表現しているかのような歌い方でした。 極めて冷静に人物の表現を琢磨して歌っているようなシュワルツコップ(ソプラノ)とは対極にある歌手だろうと思います。別な表現で言うならば、ノーマンの歌にはフィルターがなく人の感情が息づいていて、それが格調の高い表現でなされている、とことが一番感じる特徴です。ノーマン自身が語った言葉として「そもそもの初めから私がしてきたことは、ごく自然に歌うということだった」という表現が彼女の歌唱の全てを語っていると思います。音域の広さとそれをまるで自在にコントロールしているような歌唱。 透明な感じの声は、陰影の深さを伴っているし、声の中に色彩を感じることさえあります。 声は大きく、透明感があり、それも深さを伴って聴こえてきます。 一体どうすればあんな美しい声になるのか、と聴くたびにそう思います。実にほかに例のない大歌手の一人だろうと思います。ジェシー・ノーマンは1945年の今日(9月15日)アメリカ・ジョージア州で生まれています。愛聴盤 「シューベルトを歌う」 ジェシー・ノーマン、フィリップ・モル(P)(Philipsレーベル 4126232 1984年4月録音 海外盤)もう1枚 「おもいでの夏~ジェシー・ノーマンmeetsミシェル・ルグラン」ジェシー・ノーマン、ミッシェル・ルグラン(P)、ロン・カーター(ドラム)、グラディ・テイト(ベース) (Philipsレーベル PHCP11193 ユニヴァーサル・ミュージック 1997年10月録音)クラシック最高のソプラノ歌手と映画音楽・ジャズピアニストのミッシェル・ルグラントのコラボレーション・アルバムです。ルグランのピアノ、ロン・カーターのベース、グラディ・テイトのドラムというピアノ・トリオをバックにジェシーが歌うこのアルバムは、ムーディーでジャずっぽく、そして何よりもロマンティックなムードいっぱいのディスクです。ジェシー・ノーマンがオペラの世界から飛び出して、ポップス・ジャズ・シンガーとして全くこれまでになかった新しい魅力を発揮しています。 オペラ・アリアやドイツ・リートもいいのは当然ですが、こういうポップス調の音楽でも素晴らしい歌唱の世界を覗かせています。収録曲1.夏は知っている(映画《おもいでの夏》主題歌)2.瞳の中に3.アイ・ウィル・セイ・グッバイ 4.これからの夏(映画《ハッピー・エンド》主題歌)5.アイ・ウォズ・ボーン・イン・ラヴ・ウィズ・ユー(映画《嵐が丘》主題歌)6.愛のささやき(映画《水のなかの小さな太陽》主題歌)7.嘆きの子供たち8.月と私(新曲)9.セ・リュイ・ラ10.風のささやき(映画《華麗なる賭け》主題歌)11.ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプ(映画《ロシュフォールの恋人たち》挿入歌)12.リラのワルツ13.アフターソーツ(新曲)14.シェルブールの雨傘(映画《シェルブールの雨傘》主題歌)15.ビトゥイーン・イエスタデイ・アンド・トゥモロウ16.夏は知っている17.愛の閃く時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1867年 誕生 ブルーノ・ワルター(指揮者)1945年 誕生 ジェシー・ノーマン(ソプラノ)1945年 没 アントン・ヴェーベルン(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ゲンノショウコこれも小さな花ですがレンズを通して覗いてみると、とても可愛い表情をしています。 こういう表情の花がとても好きです。撮影地 神戸・六甲高山植物園 2006年9月8日
2006年09月15日
コメント(7)
-

秋の鰻つかみ
昨日の朝から雨が降り続いています。 「秋の長雨」とはよく言ったものです。 おかげで気温はぐっと下がっています。 昨日の大阪の最高気温は23度。 朝から仕事で大阪市内に出かけるのに、久しぶりにスーツにネクタイという姿でした。 もうこれで完全に秋の気候になるでしょう。これからは一雨ごとの涼しさになるはずです。 体調も快復しました。 明日あたりから音楽ブログ記事を書いていきます。年を重ねるごとに暑さ、寒さがこたえます。 これからも充分に体調を保持して貴重な毎日を過ごしていきたいと思っています。 体調を崩した時にいただきました、皆様方の温かい激励のお言葉にほんとに感謝致しております。 ありがとうございました。 また頑張ってクラシック音楽について書いてまいりますので、皆様どうかよろしくお願い申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 秋の鰻つかみ体調を崩す原因となりました神戸・六甲への撮影時に撮りました花です。 撮影地 神戸市六甲高山植物園 2006年9月8日たで科 タデ属 湿地や水辺に群生しています。 茎と葉の部分にとげがあって、うなぎをつかみやすいところからこの名前がついているそうです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』 1760年 誕生 ルイジ・ケルビーニ(作曲家)1954年 初演 ブリテン オペラ「ねじの回転」
2006年09月14日
コメント(10)
-

萩の花
ともの『今日の一花』 萩の花今まで見慣れていました「ヤマハギ」とは違う花びらです。 萩にも数種あることは知っていますが、こんな花びらの萩を見たのはおそらく初めてだとおもいます。公園の駐車場フェンスに群生して咲いていました。 撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2006年9月7日マメ科 ハギ属・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1894年 逝去 エマニュエル・シャブリエ(作曲家)1977年 逝去 レオポルド・ストコフスキー(指揮者)
2006年09月13日
コメント(4)
-

キンエノコロ
ともの『今日の一花』 キンエノコロこれも公園の植え込みに数多く生えていました。 通称「猫じゃらし」と呼んでいますが、エノコログサは種類も多くあります。 「エノコログサ」「ムラサキエノコロ」「ハマエノコロ」「アキノエノコログサ」「キンエノコロ」などですが、この画像は多分「キンエノコロ」だろうと思います。 撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2006年9月4日イネ科 エノコログサ属「キンエノコロ」は付け根が金色に輝いています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1764年 逝去 フィリップ・ラモー(作曲家)1910年 初演 マーラー 交響曲第8番「千人の交響曲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『神社の寄進集め』一昨日から神社からの寄進集め、つまり神社への寄付金を集める作業が始まっています。 神社は町の「氏神さま」ですから町内の皆さんに寄付金を募って、それを神社の維持費としています。体調が悪くて今年は控えめにしようと思っていましたが、役員2人が病気でまわれなくなっていますので、私も10日(日曜日)から町内を歩いてまわっています。 今日で3日目になりますが、疲れがあってきついのですが会計係として動かないわけにはいかないので、今日も町内を歩いてきます。
2006年09月12日
コメント(8)
-

水カンナ
『今日の一花』 水カンナこれも同じ公園の池の畔で群生している花ですが、まだこんな時期にでも咲いているのかと驚きました。 7月ごろから咲いています。 撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2006年9月4日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1840年 完成 シューマン 歌曲集「ミルテの花」1907年 初演 アルベニス 組曲「イベリア」第2集
2006年09月11日
コメント(6)
-

ヒナタイノコズチ
ともの『今日の一花』 ヒナタイノコズチこれも先日来掲載しています雑草が生えています公園にたくさん生えていました。 ところが野草の本で調べても名前がわからなかったのですが、「ヒナタイノコズチ」と0722よしさんに教えていただきました。 ありがとうございました。 撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2006年9月4日ヒユ科 イノコズチ属道端や荒地、野原などの生えている多年草。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1838年 初演 ベルリオーズ オペラ「ベンヴェヌート・チェッリーニ」1941年 誕生 クリストファー・ホグウッド(指揮者)
2006年09月10日
コメント(6)
-

ヤマホロシ
『今日のクラシック音楽』は体調不良のためしばらく(と言ってもそんなに長くはないと思います)休みます。 元気になれば、また書いてみるつもりです。 当分の間花画像の掲載と「音楽カレンダー」のみの日記とさせて下さい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ヤマホロシこれも昨日の画像と同じく公園の池のそばに咲いていました。 茎に棘がないところから悪茄子ではないと思います。 自生の「ヤマホロシ」だと思います。 撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2006年9月4日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1902年 誕生 レオポルト・ウラッハ(クラリネット奏者)1960年 逝去 ユッシ・ビョリンク(テノール)
2006年09月09日
コメント(10)
-
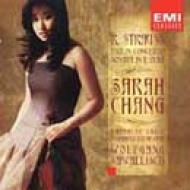
R.シュトラウス 「ヴァイオリン協奏曲」『四つの最後の歌」/ヤブガラシ
今日は神戸の六甲山へ撮影に出かけて来ました。 このところの秋らしい涼しさに慣れてしまっていたのか、今日の残暑の厳しさに軽い熱中症にかかってしまったようです。 今日はR.シュトラウスの命日なので、何か書いてみようと思っていましたが体がだるくて重いので、書く意欲もありません。 そこで昨年の同日に掲載しました記事をそのまま転載しておきます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 R.シュトラウス作曲 ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品8 及び 「4つの最後の歌」このブログを始めてから一日一曲を原則として今までに紹介してきましたが、今日はその原則を破って2曲紹介することにしました。 その意味は最後まで読んでいただくとおわかりになると思います。1.「ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品8」R.シュトラウス(1864-1949)と言えば交響詩に多くの名作が書き残されています。 今日も実は、先に彼の「アルプス交響曲」について書いていたのですが、この曲はあまりにも有名なので、今日はシュトラウスがただ一曲だけ残したヴァイオリン協奏曲について書いてみることにしました。この「ヴァイオリン協奏曲 二短調 作品8」は、作品番号からもわかりますように彼の初期の作品で、1881年から書き始めて翌年1882年に完成しています。シュトラウス18歳の時の作品です。 この曲の一番の特徴は、ブルッフ、ヴィエニアフスキーなどの濃厚なロマン主義の音楽を受け継いでいるかのような作風ですが、「カデンツア」が書かれていないということに尽きると思います。 こういう協奏曲はちょっと珍しいですね。のちのシュトラウスの音楽を予感させるような、第1楽章は華麗に彩られた、劇的な旋律で始まり、そこへドラマテイックに独奏ソロが浮かび上がってきます。「あ~、やっぱりシュトラウスだ!」と想わせるに充分な音楽の始まりで、その気分がこの楽章の最後まで持続されて、濃厚なロマンテイックと劇的緊張を味わえる音楽となっています。「レント」の第2楽章は、非常に旋律的なメロディで書かれており、瞑想的な気分が支配する美しい音楽が展開していきます。ヴァイオリンの旋律的な美しさを見事に表現しています。「ロンド」の終楽章は、独奏ヴァイオリンもオーケストラも熱狂的に歌い上げており、旋律をたっぷりと歌う部分もあり、最後は第1楽章の主題が戻ってきて劇的に音楽を盛り上げて終わります。それにしても、この見事な曲を18歳で書いたとは。初めてこの曲を聴いた時には、やはりR.シュトラウスは凄い作曲家だ改めて思ったものでした。この曲は1882年の12月5日にウイーンで初演されています。 シュトラウスの作曲家としての旅立ちでした。愛聴盤 サラ・チャン(Vn)、サヴァリッシュ指揮 バイエルン放送交響楽団(EMIレーベル 558702 1999年4月録音 USA輸入盤)↓(サラ・チャン)2.「4つの最後の歌」管弦楽に独自の書法を確立しているシュトラウスは、歌曲にも素晴らしい作品を残しています。おそらくロマン派歌曲としては最後の作曲家となったのではないでしょうか? 彼の歌曲には濃厚な後期ロマン派の音楽が受け継がれているものの、感情表現などに近代的なものを感じます。それは洗練された情緒の表現に最もよく表われていると思います。 人工的とさえ思われる美しさが今までの歌曲になかった新しい情緒表現が表われているからです。人間のぬくもりを感じさせる情感が、一種独特の抒情を醸し出しているように思えるのです。「4つの最後の歌」は、1948年に書かれたシュトラウス最後の作品で、文字通り「白鳥の歌」となった曲です。ここではシュトラウスは、伴奏をピアノでなくてオーケストラに授けています。 歌はソプラノによって歌われます。オーケストラ伴奏によって、歌曲の持っている性格が広い空間に放たれて、幅広い、しかも色彩豊かな情感を引き出すことに成功しています。説得力がピアノ伴奏よりも、より普遍的になっているのです。マーラーもこうしたオーケストラ伴奏での歌曲を書き残していますが、マーラーのそれは交響楽的な発想から来ているのに対して、シュトラウスのは歌の伴奏の域を出ないものでありながら、ピアノで表現できない情緒をより多彩に、色濃く表現した伴奏であることに、両者の違いが明白に表われているように思えます。この「4つの最後の歌」は、ヘルマン・ヘッセの詩に3曲、アイヒェンドルフの詩に1曲、歌が付けられています。 生の疲れと死の予感を匂わせた詩でありながら、音楽はあくまでも瑞々しさにあふれた歌曲集です。「春」「九月」「眠りにつこうとして」「夕映えの中で」の4曲ですが、ドイツの詩では「眠りにつく」は「死」と同じ意味に扱われており、4曲目の「夕映えの中で」には、こういう言葉が綴られています。・・・・・こっちへおいで、ひばりがさえずるにまかせてーじきにもう眠りの時間がくる、この二人きりのさびしさの中でぼくらははぐれないようにしよう。おお、この広々とした静かな平和!こんなに深々と夕映えに染まって。旅の疲れが重くぼくらののしかかっているーひょっとしたら、これが死だろうか? (アイフェンドルフ 詩) (西野茂雄 訳) シュトラウスの死の前年に書かれたこの曲は、まるで彼自身の「告別の歌」のようです。 そのリヒャルト・シュトラウスは1949年の今日(9月8日)、85歳の生涯を閉じています。 愛聴盤 エリザベート・シュワルツコップ(S) ジョージ・セル指揮 ベルリン放送交響楽団(EMIレーベル 5669082 1965年9月録音 輸入盤)↓シュワルツコップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1841年 誕生 アントニン・ドヴォルザーク(作曲家)1949年 逝去 リヒャルト・シュトラウス(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ヤブガラシこれも公園の植え込みに生えていました。 これは非常に繁殖力があって瞬く間に繁殖していくので「ヤブカラシ(藪枯らし)」という名前が付けられているそうです。 道や空き地などの野原でよく見かける雑草です。 開花したところです。 撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2006年9月3日ぶどう科 ヤブガラシ属 つるでどんどん伸びていきます。 近くにある植物を薮状にして枯らしてしまうほどの繁殖力のためこの名前が付けられているそうです。 茎の先端に小さい花を密生して咲かせています。 別名 「貧乏かずら」
2006年09月08日
コメント(5)
-

シマスズメノヒエ
ともの『今日の一花』 シマスズメノヒエ先日公園に出かけますと雑草のような細い草類がたくさん生えていました。 これもその中の一つです。 多分「シマスズメノヒエ」だと思います。 画像の右上に見えるのは「萩」の蕾です。 撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2006年9月4日
2006年09月07日
コメント(7)
-

交響組曲「シェラザード」/カゼグサ
『今日のクラシック音楽』 リムスキー=コルサコフ 交響組曲「シェラザード」リムスキー=コルサコフ(1844-1908)は「ロシア5人組」という作曲家の一人で、この「5人組」とは当時のロシア音楽界の若手たちが集まって、ロシアの国民の生活・感情・精神などを民族的色彩の濃い音楽で描こうと結成されたグループでした。その5人とはバラキレフ、キュイ、ムソルグスキー、ボロディン、リムスキー=コルサコフでした。しかし、お互いに人間的に成長いていくにつれ芸術がそれぞれに確立していったのでしょうか、意見の異なることが多くなり、1881年にムソルグスキーの死と共にこの「5人組」は解散しました。この5人組の中でも、一番若く華やかだったリムスキー=コルサコフは、その後富裕家の支援を借りて、ロシア国民主義音楽をさらに進めて行き、彼の「傑作の時期」と言われた1887~1888年に、「シェラザード」「スペイン奇想曲」序曲「ロシアの復活祭」などが書かれています。交響組曲「シェラザード」は、アラビア語の説話文学で、世界の国の言葉に翻訳された親しみ深い物語ですが、リムスキー=コルサコフはその中の序章にあたる部分を音楽で描いたのです。アラビア王シャリアールは名君の誉れ高い王様でした、ある日彼の愛妃が奴隷とベッドを共にしているのを見つけて即座に二人の首をはねてしまい、以降毎夜にわたり生娘を呼んで愛欲に耽り、朝になればその娘を殺してしまうという日を繰り返す暴君に変貌します。ある日、大臣の娘シェラザードが夜伽に呼ばれます。彼女は一計を案じて床に臨み、諸国の冒険談、好色談などをおもしろおかしく王に話して聞かせると、王は話の続きを聴きたくなって朝には彼女を殺さず、また次の夜に語らせるという日が続き、それが千夜一夜も続いてとうとう王はシェラザードを王妃に迎えたという有名な物語です。「海ととシンドバッドの船」「カランダール王子の物語」「若い王子と王女」「バクダッドの祭りー海ー青銅の騎士の立つ岩での難破ー終曲」という4楽章形式の組曲です。シャリアール王の登場を表す荒々しい冒頭の音楽に続いて、「むかし、むかし・・・」と語り始めるシェラザードの旋律は独奏ヴァイオリンで、エキゾチックな東洋風の艶麗な旋律で始まります。 このシェラザードの主題が全ての楽章で表され、彼女の物語が始まることを表しています。 ヴェールを顔にかけ、シースルーの薄物をまとったシェラザードが目の前に表れるかのような実に美しい魅惑的なメロデイーです。曲全体に東洋風のメロデイーが色濃く溢れており、色彩豊かに繰り広げられ、あなたをアラビアン・ナイトの世界に導いてくれます。1929年の今日(9月6日)、ロシアの「爆演」指揮者と呼ばれたエフゲニー・スベトラーノフが生まれています。BBC交響楽団に客演してこの「シェラザード」を振っていますが、実に個性的な演奏です。 私はカラヤンとベルリン・フィル、ストコフスキーとロンドン交響楽団の演奏したCDを最もよく聴いていますが、このスベトラーノフの演奏も個性的でおもしろいディスクの一つです。 徹底的にロシア色に染め上げた、極彩色の大伽藍絵巻のような、スペクタクルな表現を聴く者を圧倒してきます。 彼の誕生日に因んで、今日はこの曲を採り上げました。エフゲニー・スベトラーノフ指揮 BBC交響楽団↓ (BBCレーベル BBCL4121 1978年ロンドン・ライブ録音 輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1791年 初演 モーツアルト オペラ「皇帝ティートの慈悲」1864年 初演 ヨゼフ・シュトラウス ワルツ「オーストリアの村つばめ」1929年 誕生 エフゲニー・スベトラーノフ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 カゼグサ(風草)名前のわからない雑草でしたが、「日本の山野草」という本で調べますと「カゼグサ(風草)」でした。 別名 ミチシバ(道芝)。 「ジュズダマ」「パンパスグラス」と同じ公園にありました。 空き地や公園、道端などでよく見かける雑草です。 多分イネ科だと思うのですが、検索しても出てきません。 あまりにありふれた草だからでしょうか? 撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2006年9月3日イネ科 イヌガヤ属道や公園空き地など、どこにでも生えている細い草です。 8-10月に開花するようです。
2006年09月06日
コメント(5)
-
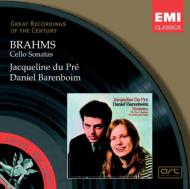
ブラームス チェロ・ソナタ第1番/パンパスグラス
『今日の音楽カレンダー』 ブラームス作曲 チェロ・ソナタ第1番9月になりますとさすがの猛暑も影を潜めて涼しくなりました。 特に朝夕はめっきり秋らしい気候になりました。 夜に冷房で過ごすことも無くなりました。 窓を開けていますと秋らしい涼気を伴った風が部屋を吹き渡ってきます。 こんな時に聴く格好の曲があります。ヨハネス・ブラームス(1833-1897)が書いた「チェロ・ソナタ 第1番 ホ短調 作品38」がそれです。私は「ブラームス大好き人間」で、おそらくベートーベンよりも好きだと思います。 何故? ブラームスのくすんだ、翳りのある、分厚く、渋い音色に魅かれるのでしょうね。 交響曲、ヴァイオリン協奏曲、ピアノ協奏曲、ヴァイオリン・ソナタやチェロ・ソナタなどの室内楽、ピアノ曲、どれを採ってもこれらの形容詞があてはまる曲ばかりです。 日本のお寺で言えば、奈良や京都の観光客がいつも訪れる有名なお寺でなく、名刹ではあるけれどどこか寂れた趣きがあり、壁などの漆喰にくすんだ風情のあるお寺。 ブラームスの音楽にはそういう、くすんだ名刹の風情がオーヴァーラップしてきます。 そういう趣きの音楽に魅かれます。さて、今日の話題曲のチェロ・ソナタ 第1番ですが、これはもう「渋い」としか言いようのない曲で、まさに上に書いた情緒そのままの音楽です。 第1に、楽器がチェロですからヴァイオリンに比べると、一段と渋い音色になります。 そこへ北ドイツのようなくすんだ色彩に溢れた音楽が展開するんですから、渋さに渋さを重ねたような趣きです。 しかし、ブラームスのどの音楽にも言えることですが、「渋さ」の中にブラームス特有の熱いたぎりが秘められていて、そこが彼の音楽のたまらない魅力になっています。 クララ・シューマンへの密かな想いが影響していると言う人もいますが、私はブラームスが北ドイツの生まれであることが、彼の音楽の特質に多大の影響を与えていると思います。曲の冒頭第1楽章で、第1主題が独奏チェロで歌い出されると、もういきなりメロメロの状態になってしまいます。とても穏やかで、たおやかな情緒でありながら、もの寂しさいっぱいの情感に包まれており、ピアノに受け継がれて音楽が昂揚していきます。心に染み込んでくるような抒情的な旋律とその展開に酔ってしまいます。第2楽章は、哀愁のただようメヌエットで、侘しさや寂しさを湛えた音楽で、これは1865年2月2日に亡くなった母への哀悼の歌とされています(この曲は1865年夏に完成しています)。第3楽章は、フーガ構成のような音楽が展開していきます。第1主題はバッハの「フーガの技法」から採られていると言われています。劇的に昂揚しながら、チェロとピアノが熱いたぎりをみせて燃焼していく様は感動的です。このチェロ・ソナタ 第1番は、完成18年後の1883年の今日(9月5日)、ウイーンで公開初演されています。愛聴盤 ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) ダニエル・バレンボイム(ピアノ)(EMIレーベル 5627582 1967年録音 輸入盤)↓デュ・プレもう1枚 ロストロポーヴィチ(チェロ) ルドルフ・ゼルキン(ピアノ)(ドイツ・グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・クラシックス POCG1119 1982年録音)↓ロストロポーヴィチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1791年 誕生 ジャコモ・マイヤベーヤ(作曲家)1857年 初演 リスト 「ファウスト」交響曲1883年 初演 ブラームス チェロ・ソナタ 第1番1892年 誕生 ヨーゼフ・シゲティ(ヴァイオリニスト)1997年 没 ゲオルグ・ショルティ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 パンパスグラス昨日の「ジュズダマ」と同じところに生えていました。 この「ススキ」は群生で出穂するのが特色のようです。 撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2006年9月3日稲科 シロガネヨシ属 南アメリカ原産。 ススキを大きくしたような形です。 アルゼンチン辺りの草原を「パンパ」と呼んでいて、そこに生える「グラス」ということからこの名前になっているそうです。
2006年09月05日
コメント(4)
-
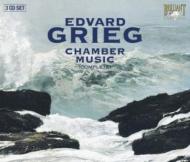
グリーグ チェロ・ソナタ/ジュズダマ
『今日のクラシック音楽』 グリーグ作曲 チェロソナタ イ短調 作品36今日は北欧ノルウエーに飛んでみました。 ノルウエーといえばエドヴァルド・グリーグ(1843-1907)の名前が真っ先に挙がるほどの、ノルウエー国民から今なお愛され続けている作曲家の生まれたところです。ノルウェーの南西部、北海に面したフィヨルド地帯にある都市ベルゲン。もう25年くらい前になるでしょうか、私は仕事でノルウエーに行った時にこのベルゲンにも立ち寄りました。 そこからそれほど遠くない郊外のトロールハウゲンと呼ばれる丘にグリーグの家がありました。 作曲家所縁の地を訪れて、生家や住居や楽譜、使った楽器などを見ると、よりいっそうその人の音楽が身近に感じられます。ベルゲンやオスローで会った仕事の関係者とも音楽の話をしましたが、やはりグリーグはノルウエー国民にとって永遠の祖国の大作曲家であるようです。グリーグの作品リストを眺めてみると、隣国フィンランドのヤン・シベリウス(1865-1957)のように交響曲などの大作を書かずに、ピアノ協奏曲は別として、ピアノ曲など小品を抒情あふれる作品を多く書き残しています。今日は、そうした彼の作品の中から「チェロ・ソナタ イ短調 作品36」を聴いてみることにします。この曲は1883年、グリーグ40歳の時に書かれた作品で、ちょうどヴァイオリン・ソナタ3曲の中間にあたる頃の曲です。 第1楽章から美しい旋律がピアノとのかけ合いでチェロで奏されます。チェロという渋い音色の楽器ですが、歌謡性豊かな旋律が美しい抒情の世界へ運んでくれます。同時に劇的緊張もはらんでおり、ベートーベンの第3番のチェロソナタを想い起こさせるような楽章です。第2楽章は、一日の終わりを窓辺で回想している婦人を想い起こすような、抒情たっぷりの豊かな情感がチェロとピアノで紡ぎ出されていく楽想はとても魅力的です。 私はよくこの第2楽章だけを聴いていることがあります。それほどに魅力あふれる音楽です。第3楽章は、リズミックでノルウエーの舞曲をモチーフにして快適なテンポで音楽が綴られていきます。この曲が何故、演奏会や録音などにもっと採り上げられないのか不思議なほど、魅力にあふれた室内楽作品の名品です。この「チェロ・ソナタ」や有名な「ペール・ギュント」「ピアノ協奏曲」「抒情小品集」などを差作曲したグリーグは1907年の今日(9月4日)、64歳の生涯を閉じています。愛聴盤 ロバート・コーエン(チェロ) ロジャー・ヴィニョレス(ピアノ)(CRDレコード原盤 Briliant Classics 921761 1980年-95年録音 輸入盤)グリーグの弦楽四重奏曲(2曲)、ヴァイオリン・ソナタ(3曲)など全室内楽作品を3枚のCDに収録されていて、1,500円でおつりがきます。↓グリーグ室内楽作品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1824年 誕生 アントン・ブルックナー(作曲家)1892年 誕生 ダリウス・ミヨー(作曲家)1907年 逝去 エドヴァルド・グリーグ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ジュズダマ今日は朝から自転車で10分くらいのところにある公園にカメラ持参で行ってきました。 しばらくの間は猛暑のために撮影を自粛していたのですが、掲載する画像が底をついていましたので、公園内に咲く野草などを撮ってきました。 その内の1枚で「ジュズダマ」です。 子供の頃には女の子がこの実を採って布で編んだ袋に入れて「じゅず玉」として遊んでいました。 撮影地 大阪府和泉市 黒鳥山公園 2006年9月3日
2006年09月04日
コメント(10)
-
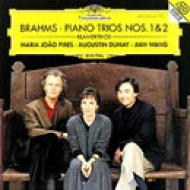
ブラームス ピアノ三重奏曲第1番/ルドベキア
『今日のクラシック音楽』 ブラームス作曲 ピアノ三重奏曲第1番 変ロ長調 作品8マーラーの重い交響曲を聴いた昨日と打って変わって、今日は室内楽作品を聴いてみようと思います。ヨハネス・ブラームス(1833-1897)の初期の作品で「ピアノ三重奏曲 変ロ長調 作品8」です。 実はこの曲との触れ合いはまだ新しく、下に紹介しましたCDを買って聴いたのが初めてですので、まだ10年にも満たないこの曲との付き合いです。ブラームスは4曲のピアノ三重奏曲を書き残していますが、普通は作品番号の付された第1番~第3番までが彼の三重奏曲と呼んでいます。これらの3曲は初期、円熟期、晩年の3期にわたって1曲ずつ書かれています。今日の話題曲の第1番はブラームス22歳の1855年に完成している、青年ブラームスの覇気の伝わってくる曲で、いかにも北ドイツの生まれと連想させるほどに雲の垂れ込んだような、渋く、くすんだような北ドイツの色彩と厚い和声に包まれたほの暗い情緒が特徴の音楽です。 曲は4楽章で構成されています。ピアノソロが抒情的で豊かな響きで奏でる旋律のあとのチェロ、そしてヴァイオリンが加わって進んでいく、明るく、若々しさに溢れた豊かな抒情性の第1楽章は、まるで一日の終わりの夕暮れの、のどかさを感じさせるロマンティックな音楽です。親しみやすい旋律と魅力ある楽想のスケルツォの第2楽章。宗教的とさえ形容できそうな神秘的なアダージョの第3楽章。ピアノが華麗に、輝くように音楽を盛り上げる第4楽章。9月になった途端に夜はエアコンも必要のない涼しさを楽しめる秋の訪れを感じますが、好きな珈琲を味わいながら聴くこのブラームスも、いつも秋の夜長の静けさを演出してくれます。 演奏時間は約38分の大曲です。初演は1854年3月26日に、クララ・シューマンのピアノで非公開で行われ、1855年11月27日にニューヨークで公開の初演が行われています。愛聴盤 ピリス(P)、デュメイ(Vn)、ワン(チェロ)(ドイツ・グラモフォン 447055 1995年4月録音 輸入盤)カップリングはブラームスのピアノ三重奏曲第2番です。↓ ここで参照できます。ピリス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』特記事項はありません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ルドベキア撮影地 大阪府和泉市 2005年8月9日菊科 オオハンゴンソウ属 北アメリカ原産で明治中期に渡来したそうです。 夏から秋にかけて開花しています。 よく見かけるのは、花びらが8枚で真ん中がこげ茶色の花です。
2006年09月03日
コメント(2)
-

ノイマンの「白鳥の歌」/キンミズヒキ
『今日のクラシック音楽』 マーラー作曲 第9交響曲~ノイマンの白鳥の歌ヴァーツラフ・ノイマン。 チェコを代表する指揮者ヴァーツラフ・ターリッヒ、カレル・アンチェルの後を受け継いでチェコフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督・指揮者。 1920年9月29日生まれで、1995年9月2日ウイーンで74歳の生涯を閉じた名指揮者。 今日はそのノイマンの命日。ここにノイマンが亡くなる5日前に録音を終えたディスクがあります。 1995年8月21日から8月28日にかけてセッション録音されたマーラーの交響曲第9番。 まさにこれがノイマンの「白鳥の歌」となりました。 生涯マーラーの曲を愛したと言われるノイマンらしい最後の演奏曲目です。第1楽章最初のバイオリンの旋律から、天国的な美しさに包まれています。 この楽章は時折激しい高揚を見せるのですが、決して暴力的に響くことは無く、音楽そのものの美しさを見事に表出しながら、マーラーが描こうとした「死の境」を表現しています。弦楽器も管楽器もノイマンの整理された意図に基づいて見事なバランスを保ちながら、複雑なスコアを複雑と感じさせない美しさで表現しています。第2楽章のレントラーは、グロテスクな気分にさせる音楽ですが、そういうグロテスクスさが充分に表現されていて、その上に嫌味な感じがありません。特に弦のアンサンブルの見事さは特筆ものです。素晴らしい演奏を繰り広げています。第3楽章も、決して暴力的な音楽になっていません。もっと迫力のある表現を好む人もいるかも知れませんが、私はこういう演奏・表現が好きなんです。 どこを切り取っても美しい音楽が表現されていると感じています。そして第4楽章。ノイマン自身が「これ以上の第4楽章は無い」と言ったと伝えられている終楽章。非常に美しく素晴らしいサウンドです。 ここに至ってはこれ以上の終楽章は無いとさえ感じさせてくれる美しい演奏が繰り広げられています。 これほど美しい演奏を他に探すとなると60年代のバルビローりとベルリンフィルの演奏か、バーンスタインがイスラエルフィルを率いて演奏した東京公演の放送をFMで聴いたときくらいでしょうか。チェコフィルの弦楽器が、マーラーの「死の世界へ導く」さまを壮絶に美しく奏でています。金管とのバランスも極上のサウンドを生み出しており、この終楽章を初めて聴いたときには、あまりの素晴らしさに涙を浮かべました。 この演奏5日後に向こうの世界に逝ってしまったノイマンを想って涙を浮かべたこともありますが、仮に彼がまだ存命であっても同じことだったと思います。大向こうを唸らせる演奏とは程遠い、真摯に温かく誠実にこの曲に向かったノイマンの音楽性が、生涯変わらずにマーラー音楽を愛し続けた集大成が、そのまま出ている演奏ではないでしょうか。 この第9の録音された1995年6月にマーラーの第7交響曲をセッション録音する予定だったのが、首席管楽器奏者の入院で中止となり、8月に録音の予定がなかったところに、ノイマン自身の強い要請でこの第9が録音されたそうです。「ノイマンよ、この世を去る日が近づいた。 お前の一番好きな曲を現世で最も愛するオーケストラで、心残りなく演奏したまえ」と、神さまが降臨して囁いたかのような、そんな気がしてなりません。愛聴盤 ヴァーツラフ・ノイマン指揮 チェコフィルハーモニー管弦楽団 (キャニオン・クラシックス PCCL00305 1995年8月21日ー8月28日録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1995年 逝去 ヴァーツラフ・ノイマン(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 キンミズヒキ朝から友人の車で和泉市・河内長野市との境にある槙尾山へ行ってきました。 自宅から車で35分~40分かかる15KMくらいのとところにある標高600mくらいの山で、昼食時には家に戻っていなければんらないので、山頂までは行かずに戻ってきました。その登山途中で見つけた「キンミズヒキ」です。 撮影地 大阪府和泉市 槙尾山 2006年9月2日
2006年09月02日
コメント(6)
-
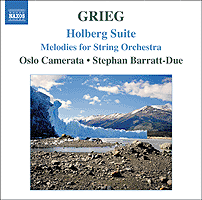
グリーグ「弦楽オーケストラのための音楽」/ミニ睡蓮
『今日のクラシック音楽』 グリーグ作曲 弦楽オーケストラのための音楽イタリア・オペラやモーツアルトのオペラ、ワーグナーの楽劇、大バッハの受難曲など長時間にわたって聴かねばならない曲が数多くあり、そういう音楽を聴く時はディスクをプレーヤーに載せる前から意気込んでいます。 「さあ、聴くぞ!」という調子です。 でないと最後まで聴き通せることが難しいのです。聴き終わったあとに必ずということではありませんが、オーケストラやピアノ・ヴァイオリン・チェロやギターなどの器楽曲や、短い曲室内楽曲などを聴いていることがあります。 いわば「お茶漬けの味」のような曲を選んでいます。先日このページで紹介しました11組のCDを順番に毎日聴いているのですが、この暑さですから聴き終わったあとは疲れます。 そんな折に聴きたいと思って先月の新譜としてリリースされましたNaxosレーベルのグリーグが書きました「弦楽オーケストラのための音楽」というディスクを1枚買いました。勝手から1週間経ちますがまだ聴いていなくて、昨夜初めてプレーヤーに載せてみました。 折からの篠つく雨で空気は涼しく、窓から入り込む雨粒を気にもせずに久しぶりの涼気を味わいながら、この音楽を楽しみました。収録曲1.組曲「ホルベアの時代より」作品402.2つの悲しき旋律 作品34~第2番 晩春3.2つのメロディ 作品534.抒情小品集 第9集から 第1番「傷ついた心」5.2つのノルウエーの旋律 作品636.「オーゼの死」~ペール・ギュント」第1組曲からこのラインナップから想像できるのは感傷たっぷりの北欧情緒だったので買ってみたのですが、涼気が運んでくれる秋風と共に、実にロマンティックで感傷的で、また躍動するノルウエーの民族的な色彩を散りばめた音楽が部屋を満たしてくれました。美しい旋律は複雑さがなくて実に平明に書かれており、ロマンの薫りがいっぱいで、その平明さが余計に聴く者の心を捉えて離さないという、どこか「やるせなさ」を伝える音楽ばかりです。昨夜は特に2回目となるワーグナーの楽劇「ワルキューレ」全曲(カイルベルト指揮 バイロイト祝祭管 1955年ライブ)を聴いたあとでしたので、余計に爽やかさを感じたのかもしれません。最近はますますNaxosから目が離せなくなりました。このCDです。 オスロ・カメラータ (Naxosレーベル 8.557890 2005年8月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1653年 誕生 ヨハン・パッヘルベル(作曲家)1876年 誕生 トリオ・セラフィン(指揮者)1935年 誕生 小澤征爾(指揮者)1953年 逝去 ジャック・ティボー(ヴァイオリニスト)1957年 逝去 デニス・ブレイン(ホルン奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ミニ睡蓮 撮影地 大阪府和泉市 2004年9月3日
2006年09月01日
コメント(2)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- 楽器について♪
- 2025年冬のハープコンサートのお知ら…
- (2025-11-23 00:18:07)
-
-
-

- 好きなクラシック
- ベートーヴェン交響曲第6番「田園」。
- (2025-11-19 17:55:25)
-
-
-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…
- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…
- (2024-08-17 21:14:58)
-







