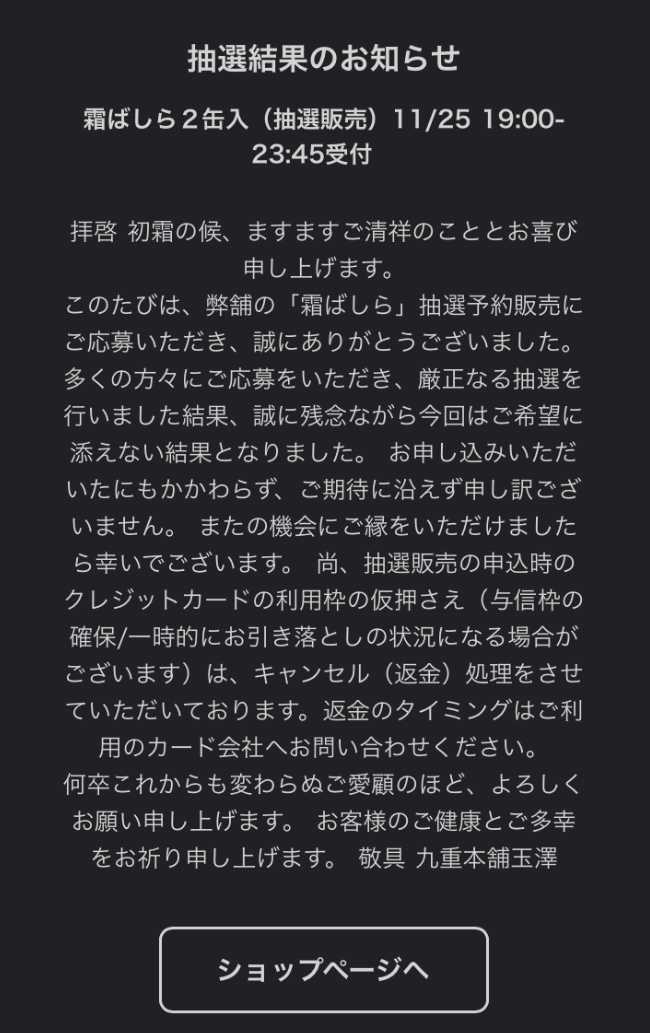2014年07月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
ホット古武道
もう八月に入るというのに、何なの、この忙しさは!? 昔は大学といえば、7月上旬には授業も終って夏休み態勢。そこから2ヶ月というものはスッコーンと仕事がなく、リラックスした中で、自分の勉強、自分の研究に思う存分打ち込めたものですよ。 それが今はどう? もう私なんて、あまりに忙しすぎて、あまりに仕事が多すぎて、逆にどれから手を付けていいかすら分からないという。 もし私が私の奥さんだったら、私は私のために泣くね。外ではこんなに身を粉にして働いているのかと。 そんな中、今日は夜、道場に行ってきました。(道場に行く暇はあるんだ!) しかし、何しろこの暑さ。道場の中も蒸し風呂状態で、まだ体を動かす前から流汗リンリですよ。「ホット・ヨガ」というのがあると聞いてはいますが、これはまさに「ホット古武道」だ。 で、今日はA師範とS師範から三段技の「雅勲」を伝授していただきました。 雅勲というのは、実にこの不思議な技で、経絡と呼ばれる線状のツボを瞬間的に圧迫を加え、それによって相手を内臓から崩すもの。これ、受けると冷たく凍らせた刃物で痛打されたようなペパーミント系の激痛が走るので、実に掛けてみたい技ではあるものの、実際に掛けるとなると難しいんですわ。 無論、私だって10回くらい試すと1回くらいうまく掛けられるのですが、成功した時と失敗した時の感覚にあまり差がないので、どうして成功したのか、どうして失敗したのか、よく判らないという・・・。 で、今日はA師範からは相手の手の上に自分の手を乗せる角度や場所を、そしてS師範からは手の力だけでなく、身体全体の構えと言うか、動かし方によって効率よく圧迫を加えるコツのようなものを伝授していただき、ちょっとだけ精度が上がったような気になれたという。しかし、10回かけたら10回、うまく技が入るようになるまでには、まだまだ練習が必要でしょうな。 しかし、あまりの忙しさに頭がバクハツ寸前だったので、1リットルくらい汗をかくような稽古をして、少しスッキリしたかも。頭ばかり疲れると眠れなくなりますが、こうやって身体を疲れさせてバランスをとると、それなりに熟睡できるので、今日は稽古に出て良かったかな。 まあ、これも古武道の効用ということでございましょう。
July 31, 2014
コメント(0)
-
病膏肓に入る
「病膏肓に入る」。老婆心ながら、「こうこうにいる」と読みます。「こうもう」じゃないよ! いやあ、このところ恩師が書いた雑誌記事・新聞記事を探し出してはパソコンに打ち込むという作業を続けているのですが、こういう作業って、やり始めると中毒になるというか、まさに「病膏肓に入る」という感じになってきますなあ。 というわけで、最近では暇があれば図書館の地下書庫に籠り切り、ひたすら記事を探しているのですけど、宝探しと同じで、徒労の比率が多い割に、一つでも未知の記事が見つかった時の歓びは大きく、やったー! って感じです。 で、今日は調子が良くて、一日で2つの記事を探し出しちゃった! 一つは、日外アソシエーツの雑誌記事索引(冊子体の奴)をこまめに引いているうちに見つけたのですが、何と『国文学』という雑誌に、先生が書いた文章が載っていたの。 さすがにアメリカ文学の専門家が、『国文学』に寄稿するとは思わないよね~! いやはや、びっくりよ。 で、もう一つは、ヘンリー・ミラーという作家の書誌を見ていて、見つけたんです。 これ、記事というより、座談会の様子を記事にしたものなのですが、その座談会を仕切っている三人の司会者のうちの一人が我が恩師だったというね。しかし、座談会の記録というのは、「特定の誰かが書いたもの」ではないので、恩師の名前が大きく特記されているわけでもなく、普通に探していたのでは見つかるはずもなし。 しかも、我が恩師は、特にヘンリー・ミラーを愛読していたわけでもないので、なおさら、普通に探していたのでは見つからない。 でも、それでこうして見つかったとなると、先生が愛読していたかは別として、主だったアメリカ作家の書誌は一通り見ておかないと、見落とすことがあるかも知れないということですな・・・。 ますます、ファイトが漲ってくるぜ! それにしても、こうして恩師の足跡をたどっていると、先生と同時代に活躍した人たちが書いた記事も、結構沢山目にします。 たとえば由良君美とか。 事実、今日私が探し出した『国文学』という雑誌の同じ号に、由良さんの「総論・70年代なかばに立って」という記事が掲載されておりました。 そして、これだけでなく、結構あちこちで、由良さんの文章を見かけるんですよね。 だから、由良さんの弟子筋の人で、由良さんが昔書いた記事を集めて本にすれば、結構、部厚いボリュームの本ができるはずですけど、さあて、その労を執る人がいるかどうか・・・。 弟子じゃなくてもやっていいなら、私がついでにやってもいいんだけど、そういうわけにもいかないのかな。それともいくのかな。どうなんだろう? ま、それはともかく、とにかく、広大な海の中から一粒の砂をつまみ出すがごとく、メディアという大海の中から恩師の書いた記事を一つ一つつまみ出すという気の遠くなるような作業に没頭しながら、つくづく、こういう作業に向いてるな、自分、と思うのでした、とさ。
July 30, 2014
コメント(0)
-

ループタイの評判
小学生ですら夏休みに入ったというのに、大学はまだ前期が続いているという・・・。当然、全館でエアコンをオンにしているわけで、省エネという観点から言えば、完全に逆行しているよね・・・。 とはいえ、そろそろ期末試験の時期になり、ようやくゴールが見えて参りました。 で、昨日、今日と私も自分の授業の期末試験を実施しているわけですが、専門の授業なんかですと、受講生の大半が自分の科の所属学生ですから、若干なりとも気安いところがある。 で、「解答を終えた者は、答案用紙を提出して帰ってもよろしい。しかし、もし時間が余ったのなら、答案用紙の余白に、授業の感想とか、なんか面白いことを書きなさい」ってなことを言っておくわけ。 すると、学生ってのは面白いもので、なんだかんだ面白いことを書いてくる。 で、答案を採点しながら、そういう学生からの一言を読み、それで退屈な時間を少しでも紛らすようにしているのですけど、今回、学生からの一言の中に、私のファッションについて言及しているものがありまして。 曰く、「夏場、先生がしていらっしゃる首飾りのようなもの、とってもオシャレでステキだなあといつも思っていました」ですと! この学生の眼に止まった「首飾りのようなもの」というのは、「ループタイ」のことでございます。私はここ数年、夏はループタイと決めて、数種類のループタイをとっかえひっかえ身につけているのですが、これの評判がいいと。 ループタイは、普通のネクタイとは比べものにならないほど涼しいし、といって、ネクタイを締めないよりはフォーマルな感じがするし、夏は絶対これがいいと私は思っているのですが、同僚たちは「ループタイは爺臭いからイヤ」とかいって、なかなか賛同者が出てこないんですわ。だから、私一人、ループタイで頑張っているわけですけれども、ほーれ、学生からの評判もいいじゃん。 ループタイは爺さんだけのものではございません。若い連中だって「おシャレでステキ!」って言ってくれるのですから、ネクタイ派やノータイ派のご同輩たち、偏見を棄てて、是非ループタイをしましょう! 教授のおすすめ!です。これこれ! ↓当店人気上位!希少なピックループタイ!メール便 送料無料 ループタイ ピック ブラック アンテ...価格:1,798円(税込、送料込)
July 29, 2014
コメント(1)
-

齋藤兼司著『留学しないで英語の頭をつくる方法』を読む
さてさて、風邪を引いて寝ていた間に読んだ英語習得本の最後を飾るのが齋藤兼司さんの書かれた『留学しないで英語の頭をつくる方法』です。 この本、冒頭のところを読むと、「誰だって母語は完全に習得しているのだから、それと同じ方法で英語も習得すればいいのだ」というようなことが書いてあって、おやおや、この本もまた「ナチュラル・スピードの英語を浴びるように聞けばいい」式の本かな?と、一瞬、危ぶんだのですが、よくよく読んで見ると、どうもそういう感じではないようなんですな。 で、本書の最初の方に、「高級レストランでコース料理をオーダーしたとき、スープはスプーンをお皿に当てずに飲み、ワインはボトルの口をグラスに当てずに注ぐ。またステーキは、ナイフとフォークを使い、小さくカットしてから口に運ぶ。それがよいテーブルマナーだ」という一文が書いてある。で、普通の日本人ならこの文をざっと読んで、別になんということもなく理解できるでしょ?と。 まあ、できますな。 だけど、よく考えてみると、この文の中には「レストラン」「コース」「オーダー」「スープ」「スプーン」「ワイン」「ボトル」「グラス」「ステーキ」「ナイフ」「フォーク」「カット」「テーブル」「マナー」と、相当数の英語が交っているわけです。だけど、それを我々はすんなり聞き取り、一瞬で理解してしまった。 ということは、日本人の頭の中にもすでに部分的に英語脳が出来ているわけで、それをほんの少し拡充すればいいのだと。 なるほどー。うまいこと言うじゃないですか。 で、齋藤さん曰く、必死にならずとも、すんなり頭に入ってくる、という状態は、耳で聞いた言葉が映像として頭の中に映じている状態のことだと。音とイメージが結び付いてないと、何語であろうとそんなにすんなりとは理解できないはずだと。 そういえば、先ほどの文章にしても、モノの名前(スプーンだとかワインだとか)は勿論のこと、「カット」とか、「オーダー」とか、そういう動詞にしても、カットなら切る動作、オーダーなら注文する動作を、映像としてイメージしようと思えばできるし、実際、瞬時にイメージしているのかもしれない。 で、だからこそ、「文字を目にしたり、音声を耳にした時に、それらが語っているものが頭の中に映像として出てくる状態にする」というのが、英語を(母語のように)学ぶ最大のコツであると、齋藤さんは喝破するんですな。 で、その手始めとして、まず単語をイメージとして覚えようと。 齋藤さんがそこで勧めているのは、『Longman Children's Picture Dictionary with CDs』という単語集。800語ほどの英単語が映像や絵などと共に紹介されている本なので、先ずはこれを使って基礎単語800語を、すべて、それを見た・聞いた瞬間に、頭の中に映像が結ぶまで覚えろというわけ。この時重要なのは、日本語による解釈を差し挟まずに、単語を映像・絵のみによって頭に叩き込むということ。 この練習によって単語レベルの映像化が完成したら、次は文レベルの映像化に取り組みます。それには『Just Look'n Learn English Picture Dictionary』を使う。で、この本に出てくる英文を自分で録音し、今度はその録音を聞いて、その内容を(日本語訳ではなく)映像として、一枚の絵として、頭に思い浮かべる練習をする。「Daddy is reading a story about a duck.」という文章であれば、先頭の「Daddy」という言葉が出たところで、優しそうなお父さんの姿を思いうかべる。そして「is reading a story」のところで、そのお父さんが何か本を読んでいる映像を思いうかべ、最後の「about a duck.」のところで、お父さんが持っている本の表紙にアヒルの絵が付いている、そんな状態を思いうかべる。そうやって、一文まるごと、映像として頭の中に描け、というわけ。 で、この練習を飽きるほど繰り返し、例文をチラッと見ただけで、それが語っている状況が映像として頭の中に浮かび、逆にその映像を思いうかべた状態で、元の例文が口をついて出てくるくらいまでにする。 で、これができたら、次の段階として・・・と、齋藤さんの指示が続くのですが、とにかく、この一連の方法を1000時間くらいかけて勉強すれば、英語は出来るようになりますよと。だから、1年でマスターしたかったら、一日3、4時間勉強すればいいし、2年でマスターするなら、一日1、2時間の勉強を2年間続ければいい。 ま、そんな感じでこの本は、英語マスターまでの段取りをつけてくれる。 で、4冊立て続けに英語習得本を読んだ中で、説得力があったのは、この本だけですな。ちゃんと、しっかり、「メソッド」というものを確立している感じがする。私が知りたいのは、まさにそういうメソッドなものでね。 ということで、この本、なかなかいいです。もし、英語を勉強し直したいと思っておられる方がおられましたら、私だったらこの本をお勧めします。私も、単語の映像化のレベルから、もう一度英語を勉強しなおそうかな!これこれ! ↓【楽天ブックスならいつでも送料無料】留学しないで英語の頭をつくる方法 [ 齋藤兼司 ]価格:1,404円(税込、送料込)【メール便送料80円】Longman Dictionary【ロングマン辞書】Longman Children's Picture Dictio...価格:3,056円(税込、送料別)【送料無料選択可!】アメリカンキッズえいご絵じてん / 原タイトル:Just Look’n Learn ENGLIS...価格:4,104円(税込、送料別)
July 28, 2014
コメント(0)
-
『世界の非ネイティヴエリートがやっている英語勉強法』を読む
3番目にご紹介しますのは、斎藤淳さんが書いた『世界の非ネイティヴエリートがやっている英語勉強法』という本。著者の斎藤さんは、上智大からアメリカの名門イェール大学の大学院に行き、イェールで助教授をやっていたのに、なぜか帰国して中高生向けの英語塾を始めた、という、やっぱり「なんじゃそりゃ」系の経歴の持ち主。多いですね、この手の英語習得本を書く人に。 で、本書を読んで、まず何が書いてあるかといいますと、著者が在籍していたイェール大がいかに語学教育に力をいれているか、ということ。日本だと、東京外国語大学ですらそこで学べる言語が28個なのに、イェール大では50もの言語を教えている、というのですな。しかも50分の授業を週5ペースで受講するシステムになっているので、この大学に3年くらいいると、大概の言語は習得できると。 でまた、院生がチューターになってくれたり、レベル別クラス編成になっていたり、発音矯正のための専門の知識と技術をもったスタッフが徹底的にコーチしてくれたり、ランチタイムのカフェテリアには言語テーブルというのが設置されていて、そのテーブルに行けば自分が習得中の言語で誰彼と話ができるようになっていたり、とにかく至れりのつくせりの言語習得環境らしいんです。 そうなんですか。羨ましいですなあ。 で、さんざん羨ましがらせた後、どうなるかというと、斎藤さんなりに、英語習得のやり方としてああすればいい、こうすればいい、と、色々やり方を伝授してくれる。 が! やり方といっても、特に目新しいことはなく、「発音はフォニックスで勉強しろ」「シャドーイングしろ」「前置詞はイメージで理解しろ」「文法は重要」「英語で文章を書く時は、英語流に、冒頭にトピックセンテンスをもってこい」「リスニング力アップのために英語の動画ニュースを書き起こせば、同時にライティング力もアップできる」云々かんぬんといったところ。 まあ、この手の本では多いのですが、こういうのって相当な英語上級者が、さらなる実力アップのためにやるべきことであって、こういうことができるくらいだったら、もともと苦労しないよ、という感じのものですな。 ところで、本書ではそれぞれの章の終わりに、おすすめの教材が紹介されておりまして、それは親切というか、参考にはなるので、興味が湧いたらそこで紹介されている教材を買えばいいと思うのですが、しかし、逆に言いますと、「こういうことが勉強したかったら、次に紹介する本読んで」というのだったら、楽だよねと。だって、それは他人のふんどしで相撲をとるようなものでしょ? それだったら、誰にだって言えるわけですよ。「英語では単語力が重要。○○出版社の単語集を買って、勉強して下さい。それから発音も大事。○○出版社の本を読んで勉強して下さい。それから文法も大事。○○出版社の本を買って全部読んでください。それから動画もいい勉強になります。○○出版社から出ている英語の動画DVDを買って勉強して下さい。それからディクテーションも大事。NHKの英語ニュースを毎日ディクテーションして下さい。これら全部やれば、きっとあなたも英語が上達します」って、言っているようなもんですから。 ということで、本書を読んで私が学んだのは、「イェール大学って、スゴイな」ということだけだったのでありました。残念!
July 27, 2014
コメント(0)
-
多田佳明著『英語は日本語で学べ!』を読む
昨日ご紹介した本とはちょうど対照的に、今日ご紹介します多田佳明著『英語は日本語で学べ!』は、日本人が英語を勉強するなら、日本語を軸にして勉強するのが一番効率的、と主張している本。当然と言えば当然なのかもしれませんが、所変われば品代わる。著者が変われば、その主張するところも180度違うという、そこが面白いところと言えば面白いところ。 ところで『小川式勉強法』の小川仁志さんが、「日本語で英語を教える日本の英語教育なんて全然役にたってない!」という実感をご自身の英語習得法の立脚点に据えているのと同じく、多田佳明さんもご自身の実体験から「英語で英語を教えるなんて、全然ナンセンス!」という立脚点を得ているんですな。というのは、多田さんが通っていた中学では、世間に先だって「英語で英語を教える」というシステムを取り入れていて、そのような形で英語を習い始めたために、あやうく英語落第生になりかけた、という実体験が、多田さんにはあるから。 実際、英語のえの字も知らない中学生にとって、先生が英語で何かを説明しても、何を言っているのかまったく分からないわけですよ。それで多田さんも、他の同級生たちと同じく、どんどん英語が嫌いになって、なーんも勉強しないようになってしまった。 しかし、それではいかんと一念発起した多田さんは、夏休みに本屋に行き、市販の英語の参考書を買って読んでみたと。 すると、今まで分らなかったことが立ちどころにどんどん頭に入ってくる。例えば、それまで「どうしてある場合には動詞に s がつくのに、別な場合にはつかないのかなあ??」と悩んでいた多田さんですが、その参考書に「主語が三人称単数現在の時には動詞に s がつく」と書いてあるのを読んで疑問が氷解。そこで多田さんは、「なあんだ! そんな簡単なことだったのか!」と感激するわけ。 と同時に、「だったら、最初から日本語でそう教えてくれよ!」という反感をもった。 また、長じてから、英会話教室などでネイティヴに英語を習った人が、挨拶など最初のふた言三言はまるでネイティヴと同様の素晴らしい発音で言えるのに、そこから先、ちょっとでも込み入った話になるとまるで手も足も出なくなるのを数多く見る一方、自分の言いたいことをまず日本語で考えて、それを一生懸命英訳して、下手な英語ながらも必死に自分の言いたいことを英語にしている人は、相手のネイティヴからも一目置かれるのを目撃し、日本人の英語力なんて、これでいいじゃないかと考えるようになるわけ。 つまり、「やっぱり英語は英語で勉強しなきゃ」とか、「まずは英語で発想することが重要」などという、実現可能なのかどうかわからないことに振り回されることなく、日本語を軸にして地道に英語を勉強すりゃーいいんだ、という確信を得るわけですな。 そして、たとえ「日本語で考え→頭の中で英訳し→発話する」という複雑な作業をすることになろうと、この作業のスピードさえあげればいいじゃないか、と考える。 ということで、多田さんの英語勉強法は、地道です。 たとえば、多田さんは、他の英語習得本の著者がよく言うように、「ナチュラル・スピードの英語を浴びるように聞け」などとは言いません。たとえば百パーセント知らない言語の発話を百時間聞き続けたところで、何一つ頭に残らないように、英語だってただ聞き流しているだけでは、何にも頭に残らない。聞く前にまず、ボキャブラリーを増やして、リスニングのとっかかりになるような足場を築かないとダメ、というわけ。 で、じゃあ、どうやってボキャブラリーを増やすか、というと、大学受験とかの時に使うような、英単語の意味を日本語で書いてあるような単語集を使えばいい、と。他の英語習得本著者とは違って、「英々辞書を使え」などとは言わないわけ。 ただ、英単語を見た瞬間、日本語の意味が出てくるくらいまで暗記しろ、とは言っています。「あー、これなんて意味だったっけなー。えーっと・・・。そうそう、確かこんな意味だった」というようなのでは、それこそ役に立たないと。 また、熟語とか英語特有の言い回しなど、「あ、これは使えそうだ」と思うようなものに出くわしたら、自分でノートを作ってそこに書き込み、そうやって自作のノートを作って勉強した方が、市販の熟語集を使うよりも効果的、なんていうアドバイスもしています。 その他、発音は重要なので、よく勉強しろ、とか、文法は理屈で覚えて行けとか、色々アドバイスはしているのですが、それは要するに万遍なく勉強しろ、ということを言っているのであって、そうなってくると、要するに「英語習得に王道なし、地道に、時間をかけてやれ」と言っていることになり、それはもちろん百パーセント正しいけれども、「それは最初から分かっていることだよね」と言われてしまえばそれまで、ではあります。 というわけで、本書は、「コレを読んだら、眼からウロコがボロッと取れる」という類の本ではありません。ただ「地道に時間をかけて一生懸命勉強して、ようやく少し英語が使えるようになる」ということが分かるだけ。本書に一つ取り柄があるとすれば、「英語は英語で勉強しなきゃ」というような、一般人からすればハードルの高いことを言われても、そんなことにビビることなく、日本人は日本語を軸に勉強すればいいんだよ、と、少しホッとさせてくれるところがある、というですな。 ま、そんな感じです。
July 26, 2014
コメント(0)
-
英語習得本4連ちゃん(その1)
風邪で伏せっていた間、まあ、縦になってする仕事ができなかったので、横になっていてもできることとして結構沢山の本を読んだのですが、その中で、こういう時しか読むチャンスがなかろう、というような本として、英語学習法関連の本を立て続けに読みました。 ということで、読んだ分だけ、1冊ずつコメントしていこうかなと。 で、第一日目として、小川仁志さんという方が書かれた『「小川式」突然英語がペラペラになる勉強法』をご紹介しましょう。 この方は京大を出て名古屋市立大大学院を出て、商社に勤めたり、公務員をやったりした後、プリンストン大学の客員になり、今は哲学者として商店街で哲学カフェを主宰する(なんじゃそりゃ)という異色の経歴の持ち主。 で、この方が英語習得は日本人にとって必須だなと感じるようになったのは、プリンストン大に居た時、韓国や中国の留学生に比べて日本人の英語力は全然ダメだなと痛感したことが元になっているようなんですな。つまり、英語という言語で勝負せざるを得ない国際的な場で、日本人の英語力は全然通じないと。 で、振り返ってみれば、結局、日本の英語教育のやり方が全然間違っているのだから、公教育に頼ってはいられない。世界の舞台から取り残されないための自衛手段として、自分で英語力をつけるしかない、と、まあ、小川さんはそう考えた。 ここまでは、よく言われていることを小川さん流に言い直しているだけだから、多分、誰からも異論はないでしょう。 で、じゃあ、どうやって英語を自習するか、という方法の話になるのですが、小川さんは5つの方法を提案しています。その5つというのは、・話すための「ハーフ&ハーフ・スピーキング」・聴くための「ナチュラル英語シャワー・リスニング」・書くための「添削フレンドリー・ライティング」・読むための「アウトプット式リーディング」・考えるための「直接英語シンキング」 です。 し・か・し。 この辺りから、私としては「ん?」となってくるんだなあ。 例えば「話すための『ハーフ&ハーフ・スピーキング』」って何かというと、日常生活中の会話の半分を英語にしよう、というもの。 たとえば会社だったら会社の同僚の中から同志を募って、昼休みの会話は英語で行うようにする、とか。家でも奥さんと英語で話すとか。もしそれがダメならスカイプを使って外国の人と話すとか。とにかく、そうやって一日の中で英語で話す時間を増やせばいい、と。 次に「聴くための『ナチュラル英語シャワー・リスニング』」って何か、というと、映画のDVDを借りてきて、英語音声を英語字幕付きで見まくれ、と。 「添削フレンドリー・ライティング」は、というと、仕事上のメモとか、趣味上のブログとか、そういうのを全部英語に変えろ、と。そうやってとにかく沢山書いて、それを英語の上手な人、もしくはネイティヴに添削してもらえと。 「アウトプット式リーディング」というのは、英語の新聞や雑誌を読むだけでなく、読んだ内容を英語で表現しろと。 「直接英語シンキング」というのは、日本語で考えて英語に訳す、というのではなく、直接英語で考えろと。 で、上のようなことをすれば、日本人の英語力は各段に上がる、というのですけど、どうなんでしょうか。 私の個人的な読後感から言いますと、小川さんが言っているのは、「既に相当な英語力を持った人で、しかも短期間程度なら外国で暮らしたこともある、というような人が、英語を忘れないようにするためにやればいいこと」であって、そのレベルの素養のない人に言っても仕方がないことなんじゃないかと。 「言葉は使わなくちゃ上達しないのだから、使えばいいんだ! そうだ、明日から英語しゃべろう!」って言って、明日から英語をしゃべれるなら、誰も苦労しないのであって。「サッカー上達したいのなら、メッシみたいなプレーをすればいいんだ! じゃあ、明日からメッシみたいなドリブルしよう!」というのが、サッカーの初心者にはまったく意味を成さないのと同じで。 それに、「昼休みの会話は英語でやりませんか?」という提案が気軽に出来る、という環境に身を置いている人は、日本広しと言えどもすごく少ないと思うんですな。それならば、せめて奥さんとは日ごろ、英語で話せばいい、と言うかもしれませんが、それもどうかな~!? 今までそれなりに会話のあった夫婦も、それを英語で、となったら、会話のない夫婦にならないかなあ?! とにかく、小川さんのご提案を明日からガンガン取り入れられる人というのは、極端に少ないと思うので、ということは、この小川さんのご提案は、ほとんど意味がない、ということになるんじゃないでしょうか。 日本の英語教育はダメだけど、それに比べて小川さんの方法ならバッチリだ、とは、少なくとも私は思わないな。 少なくとも、この本の表題である『「小川式」突然英語がペラペラになる勉強法』というのは、まったくもってこの本の内容を正しく伝えていないと思います。この本を読んだからといって、突然英語がペラペラになんてならないですよ。 ということで、この本、私にはあまり響いてこなかったし、どうやって英語を教えるのが一番いいのか、という私の長年の疑問を一部でも解いてくれるものではなかったのでありました。残念!
July 25, 2014
コメント(0)
-

復活
はーい! 釈迦楽先生復活~! 2週間ほども前に「風邪引いた」の一言を残してそのままブログ更新をしなかったので、ひょっとして重病なのではないかとか、身内に不幸があったのではないか、など、様々な憶測を呼んでしまったらしく、とうとう心配して電話してくれたりする人も出てきたので、さすがにこれではいかんと、復活することにいたしました~。 実はですね、確かに季節外れの風邪が重かったんです。っていうか、今でもまだ百パーセントの体調ではないという・・・。もう、自分でも「本当に治るのか?」と心配になるほどでありまして。 しかし、所詮風邪ですから、死ぬほどのもんじゃない。 実を言いますと、2005年からこのブログを続けて参りまして、殆んど毎日更新していたものですから、それが習い性になってしまって、ブログを書かない日々というのがどんなだったか忘れかけていたわけ。 で、風邪を口実に、ブログをしばらく書かないでいたら、ブログを書かない日々というのも案外楽しいなと。忘れかけていた楽しみを思い出した、みたいな。 というわけで、ある意味では意図的に休暇を取っていたわけですな。 だけど、それももうそろそろおしまいにすることにいたしまして、また今日からブログを書き続けることにいたしました。prodigal son のご帰還でーす! 温かく迎えてね! さて、ブログ更新をさぼっていたとはいえ、人生そのものをさぼっていたわけではないので、この間、大分、本も読みました。ということで、この間に読んでいた本の紹介などをぼちぼちしていきましょう。 その第一弾がコレ。『おざわせんせい』です。【楽天ブックスならいつでも送料無料】おざわせんせい [ 博報堂「おざわせんせい」編集委員会 ]価格:1,404円(税込、送料込) これ、広告代理店「博報堂」の名物クリエイター、小沢正光氏の語録でありまして、猛烈上司たる「おざわせんせい」からつきつけられた様々な理不尽な言葉の数々を、それが発せられたシチュエーションともども、彼の部下たちが紹介している本なんですな。 で、これを読むと、おざわせんせいの部下になると、とんでもないことになるんだ、というのがよく判る。 例えば冒頭からして「世界中さがしたのか?」ですからね。CMの参考になるような写真や資料を探すことは、CM作成の第一歩なわけですが、インターネットなどがない当時、資料探索は手間のかかる仕事だった。で、そういう時、おざわせんせいは常にこの言葉を発して、「本当にとことん、もうこれ以上ない、というところまで探したのか?」という要求を、部下につきつけると。 この言葉一つからもわかるように、おざわせんせいは中途半端はぜったいに許さないわけ。たとえばNASAの写真が必要だということになったとき、注文を出した下請け制作会社の担当者が「ちょっとむずかしい」という返事をしてきた。その時におざわせんせいが発した言葉は「じゃあ、今そこでNASAに電話して」。「どうもむずかしいようだ」とか、そんな憶測で自ら限界を作ることは許さないわけですな。 また夜中の1時にスタッフミーティングをすることになり、スタッフ全員集めるということになったとき、部下が「この時間だとさすがに・・・」と躊躇った時のおざわせんせいのひとことは「つべこべ言わずに、俺が呼んでいるって言やいいんだよ」。同趣旨の発言としては、「俺への返事は、大きい『ハイ!』か、小さい『ハイ…』だけだ!」「これ以上言ったら、殴るぞ。」「言葉で殺されたいか、それとも拳で殺されたいか?」(おざわせんせいは空手部出身) VHSで資料をつくってクライアントにプレゼンしようとしたら、クライアントにあったデッキがベータ方式だった。そんな時のおざわせんせいの一言がこちら。「いいから、入れろ」。 取引先制作会社に電話して仕事をオーダーしたところ、あいにく担当者が出払っていて、電話番しかいなかった。で、その電話番がその事情を伝えて断ろうとしたところ、おざわせんせい曰く「お前がいるだろ」。かくして電話番がその作業をするはめに・・・。 まあ、そんな理不尽な一言満載で、第三者としては笑えるのだけど、直接の部下だったらしんどいだろうな!と思わされることばかり。 でも、おざわせんせいはただ単に理不尽なのではもちろんなく、その理不尽な一言の背後には、深い仕事の哲学がある。それが部下たちにもわかっているからこそ、彼の一撃を受け止める。そこがいい。 たとえば「天才でない限り、階段は一段ずつしか上がれない。でも、ちゃんと一段昇ったら、もう下に降りることはない」とか。 「広告は、最大の社内広報だ」とか。 「代案がない奴に、企画を否定する権利などない」とか。 「評価は厳しく! 査定は甘く!」とか。 「誰よりも考えていれば、そうは負けない」とか。 結局、博報堂で誰よりも仕事をしているのは自分だという強烈な自負、そして自分は天才ではないから、一つの仕事をするにもちゃんと手順を踏み、かつ各手順の一つ一つに集中し、考え抜き、もうこれ以上は出来ないというところまで努力をしているからこそ、それを背中で部下に示しつつ、同じことをしろと要求しているわけ。企業人として、これを正しい姿と云わずしてなんと言えばいいのか。 とにかく、そういう深いところまで含めて、笑いながらも考えさせられる本でございます。巻末のおざわせんせいインタビューもすごくいい。 で、私は最近、自分のゼミでもおざわせんせいの語録を使うことにしています。ゼミ生が「調べたんですけど、なかなか資料がなくて・・・」とか言うと、すかさず『世界中、探したのか?』と。 「お前はこの企画書(卒論)に、自分の名前をサインできるのか?」とか。 「根っこから考えろ、根っこから!」とか。 もちろん、自戒の意味も含めて、ね。 というわけで、本書『おざわせんせい』、教授の熱烈おすすめ!です。
July 24, 2014
コメント(2)
-
風邪ひいた~
夏風邪引いてしまいました・・・。今日は、第三校を終了させ、出版社に返送したところで力尽き、終了~って感じ。これからぐっすり寝て、明日は復活したいと思います。それでは、お休みなさーい。
July 11, 2014
コメント(0)
-

木全信著『ジャズは気楽な旋律』を読む
最近、なかなか暇がなくて、ジャズ関連の本を読んでいなかったのですが、そういう意味では久々にそっち系の本を読みましたので、ちょいと心覚えを書きつけておきます。 読んだのは木全信という方の書かれた『ジャズは気楽な旋律』(平凡社新書)という本なのですが、著者の木全さんという方は、ジャズのプロデューサーとして、数百枚のジャズ・アルバムをプロデュースした業界人。で、その仕事の過程で知り合った数多くのジャズマンたちの思い出を絡めながら、ジャズという音楽の気楽な楽しみを語っているんですな。 思うに、今まで私が読んできたジャズ関係の本というのは、ジャズ評論家、あるいは熱烈なジャズファン、あるいはプレイヤーの方が書いたものばかりで、プロデューサーが書いた本というのは、本書が初めてかも。 で、プロデューサーの書いた本だからこその美点はどこにあるかと申しますと、実際に仕事で付き合ったからこそ分かるジャズマンたち一人一人の個性とか、人柄とか、そういうのが書かれていることです。 たとえばベニー・ゴルソンというサックス・プレイヤーの温厚かつまじめな人柄とか、フレディー・ハバードというトランぺッターのやんちゃぶりとか、ケニー・ドリューというピアニストに感じられるそこはかとない「華」とか、そういうものを、実際に彼らをよく知っていた木全さんの口から語られると、やっぱり非常に興味深いわけですよ。 その他、楽譜は必ず手書きで書き写してくるピアニストのジャッキー・バイアードの真面目さとか、奥さんにマネージメント方面をすべて託し、演奏のことしか頭にないトミー・フラナガンの神秘性とか。出てくるミュージシャンが有名どころばかりなので、面白くて仕方がない。また逆に、今まで知らなかったジャズマンについても、「そういう人なんだ・・・」というのが分かると、アルバムを聴いてみたくなったりして。 その他、本書には「ジャズをプロデュースする」とは一体どういうことなのか、ということや、木全さんの体験的ジャズ観も披瀝されていて、うなずくことが多かった。やっぱり、そういう点では、評論家がすごくマニアックなアルバムについて、重箱の隅をつつくようなことを書いているのを読まされるのより、よほど面白いかも。 ま、それを言ったら、私だってアメリカ文学について評論家的なことをやっているわけで、作家でもなければ、編集者でもない立場からアメリカ文学を云々したって、読んでいる人は面白くないのかもね・・・。 そんな反省も促されつつ、とにかく、面白いのは人間だなと。ジャズが面白いのは、そのジャズを演奏している人間が面白いからだな、なんてことも感じさせられるこの本、私としてはおすすめ!です。興味のある方は是非!これこれ! ↓【楽天ブックスならいつでも送料無料】ジャズは気楽な旋律 [ 木全信 ]価格:864円(税込、送料込)
July 10, 2014
コメント(3)
-
恩師の足跡
恩師の書いたものをすべて集めようと決意し、着々とその計画を進めつつあるのですが、まあ楽しい、楽しい! 何が楽しいって、文献を探索するのが。 通常、雑誌記事とかを探すとなりますと、我々が普通使うのは「Ci-Nii」(サイニー)というサイトでありまして、これに著者名を打ち込んでサーチをかけますと、一瞬のうちに文献リストが上がってくる。非常に便利なものであります。 が! 本気になって、ある特定の人物が書いた記事をすべて集めようとすると、この「Ci-Nii」がいかに穴だらけの杜撰なものであるかがよく判る。例えば私がある記事の存在を知っていて、実際、それを持ってすらいるのに、その記事がCi-Niiからは検索できない、なんてことがよくある。要するに、本気で探そうと思ったらCi-Niiなんてまるで頼りにはならないということですな。 その点で言えば、国立国会図書館のサイトも全然頼りにはなりません。 また逆に、思わぬ収穫があるのが「日本の古本屋」をはじめとする古本屋さんのサーチ・エンジンで、これで探した結果、Ci-Niiも国立国会図書館も把握していない文献を購入することが出来たこともしばしば。 つまり、ありとあらゆるサーチ・エンジンを十字砲火的に使用して、探していかないといかんわけですよ。 でも、それにも限界があるので、最終的には過去の新聞・雑誌を40年分くらい、1ページずつチェックするとか、そういうレベルまで行かないとダメでしょうな・・・。 だ・け・ど! そういうの、私、決して嫌いじゃないの。「探す」という行為が、割と好きなんですよね~。恩師の足跡を求めて、ひたすらページをめくるとか、そういうのって、探偵になったみたいで実にスリルがあって面白いんですわ。 というわけで、今日も今日とて、図書館に籠って雑誌の目次を数十年分にわたってめくっていた私なのでございます。そういうの、分っかるかな~、分かんねえだろうなあ・・・。
July 9, 2014
コメント(1)
-
号泣県議×半沢直樹
誰が考えるのか知りませんが、すばらしい組み合わせを考える人がいるもので、例の号泣県議と半沢直樹を掛け合わせ、すばらしい動画をアップしている人がおります。その完成度たるや! 一見の価値がありますので、是非!これこれ! ↓号泣県議×半沢直樹
July 8, 2014
コメント(0)
-
いい気分
今日、アメリカ映画論の授業を終え、後片付けをしていると、大柄な男子学生が近づいてきて、何か質問かと思ったら、大学院の進学相談だったという。映画が好きなもので、映画に関する修士論文を書くとしたら、私に指導教授になってもらえるか、とのこと。 ほう! そうですか! まあ、大学院というところは、修了した先のことを考えておかないと、進学することがその人にとってどれほど役に立つか分らないところがあるので、その辺、どれくら明確な計画があるかどうか、もう少し詳しい話を聞かないとどう答えていいか分からないのですが、それにしても、指導教授を頼んでくるということは、私の授業を聴いて面白いと思ったからでしょうから、頼まれて嬉しくないこともない・・・というか、めちゃくちゃ嬉しいね! ま、実現するかどうかは別として、実にいい気分でございました。 そしてその後、今度はゼミの時間にゼミOBのM君が遊びに来てくれて、後輩の指導を手伝ってくれた他、ゼミの後に少し話したところによると、就職先で順調に出世している様子。そこはそれ、私の教え子ですから、出世して当然なのですが、持ち前の能力がしかるべく評価されているというのはいいことでありまして、本人にとっても張り合いのあることでしょうし、私としても鼻が高い。 ということで、今日は愉快なことが続いて、とても気分のいい一日だったのでありました。大学に行くと、たいがい、嫌なこと・面倒なことに出くわすことが多いのですけど、たまにはこういう日があっていいよね~!
July 7, 2014
コメント(2)
-
第三校
近日発売予定(希望的観測)の拙著の第三校が出てきたので、今日は一日中、校正作業に没頭しておりました。 三校ですから、もうほとんど間違いはない・・・と思いきや、まだあるんだなあ・・・。自分のことながら、「いい加減にしてくれ!」と言いたくなります。それでも、今回数カ所の直しを入れたことで、その分、また一歩完璧に違づいたわけですから、良かったとしましょう。 今回のゲラは、表紙以外はほぼリアルな感じで出てきたので、ああ、実際に本が出ると、こういう感じになるんだなあ、というのが分かって、モチベーションは上がりましたね。今回も才能豊かな若い女性の装幀家、Sさんが担当して下さっているので、デザイン的にはすごく凝っていて、自分の本ながらステキです。 ということで、これが最後の山場だと思って、あと数日、校正作業に打ち込む予定。頑張ります。
July 6, 2014
コメント(0)
-
長浜&彦根へ
ちょいと野暮用があって、姉一家の住む彦根に行って参りました。 が、そこはそれ、せっかくそちらの方に行くならば、少しは観光もしようということになり、まず彦根のお隣、長浜に向います。 琵琶湖畔の小さな観光地である長浜。私はそれこそ二十年ぶりくらいに訪れるのですが、かつては観光地とはいっても閑散とした町だったのに、今は大河ドラマの影響でスポットを浴びているようで、なかなかの人出でありました。 で、まずは腹ごしらえということで、名物の「のっぺいうどん」を食すべく、「茂美志屋(もみじや)」さんへ。有名な店らしく、店内には有名人の色紙がわんさと貼ってある。で、初めて食べる「のっぺいうどん」とは、汁がものすごくねっとりと葛でとじられたうどんのことで、大きな椎茸の煮たのがでーんと上に乗っている。ま、特別旨いかと言われると、それほどでもないような気もしますが、まあ、普通においしくいただきました。名物ですから、一度は食べてみないとね。 そしてその後、「黒壁スクエア」周辺を1時間ほど散策しながら、ガラス細工の店を冷やかしたり、骨董の店を冷やかしたり、小さいけどこだわりの古本屋を冷やかしたり、芋金つばの店で金つばを買ったりしたという。まあ、こんなもんでしょう。 で、久々の長浜散歩を適当なところで切り上げた我ら夫婦は、そこからクルマで小一時間彦根方面に走って、姉の家に到着。2年ほど前に新築した姉の家のハウスツアーをしてもらって、建築フェチの私としては大満足。注文建築なもので、内部の間取りは言うまでもなく、外壁の色やデザイン、各部屋の壁紙や床材、二階への階段の傾斜を急にするか緩やかにするか等々、ありとあらゆる部分を自分たちで選ばなければならないため、全部を決めるまで相当な時間が掛かったとのこと。そんな苦労話を聞きつつ、春休み以来久々に会う姉と、しばし歓談して楽しい午後のひと時を過ごしました。 で、夕方の6時くらいに姉の家を辞した我らが次に向かったのは、竜王アウトレット。せっかく近くまで来たので、ちょいと買いものでもしようかと。 しかし、「30分くらいで着くよ」と姉に言われたものの、一本道の国道8号が結構渋滞したおかげで、アウトレットに着いたのは7時過ぎ。結局、実質1時間半ほどしか見て回れなかったという・・・。収穫もゼロでしたが、まあ、買い物っていうのは、買うばかりが楽しみではないですからね。「ああ、こういうところか」というのが分かっただけでも楽しかったです。 で、アウトレット内にある近江牛の店で遅めの夕食を取り、それから帰宅。竜王から自宅まで、名神高速を使って1時間半ちょいですかね。 というわけで、時間的にはあまりゆったりは出来ませんでしたが、内容盛りだくさんの週末となったのでした。
July 5, 2014
コメント(0)
-
顔芸と泣き芸
『ルーズヴェルト・ゲーム』最終回、録画したまま見ていなかったのですが、ついに見てしまいました。そして、ネット上でも騒然の、あの香川照之さんの「顔芸」をついに見ることができて感動! もう、あんまりスゴイので、巻き戻しては見、巻き戻しては見、10回くらい連続して見ちゃった! もう、この回は永久保存版にして、ビタミン剤みたいな感じで、仕事に疲れた時とかに見直そうっと。 しかし、昭和の頃はいざ知らず、現代のテレビで、あんな顔芸をする俳優なんて他にいないわけで、香川さんはなんかこう、余人にはまねのできないレベルまで、突き抜けてしまった感がありますな。素晴らしい。どんな職業でも、「これをやらせたら一番」というものを掴んだ人というのはスゴイですよ。私も香川さんの顔芸に匹敵する芸を、文学研究の世界で培いたいものでございます。 その一方、どこぞの県議かなんかの泣き芸、あれは別な意味ですごいですな。世の中には、いろんな人がいるもんです。ビックリだね・・・。
July 4, 2014
コメント(0)
-
促音便
今日も今日とて、古い新聞・雑誌記事のパソコンへの打ちこみに精を出しておりました。 ところで、古い記事を打ちこんでいて違和感があるのは、促音便についてでありまして、ある時期以前の記事を打ち込んでいると、促音便の表記として小文字が使用されないので、すごく打ち込みにくいんです。 つまりですね、現在の表記であれば、「あって」となるところ、「あつて」と打ち込まないといけないわけ。 で、特に面倒臭いのは、「戻って」とかいう場合。これ、「もどつて」と打ち込んで変換キーを押すと、「盛度つて」とか、変な変換になってしまうので、一度「もどって」と普通に打ち込んで、「戻って」と変換させ、あとから「っ」と「て」を消去して、それからあらためて「つて」と打ちこまなくてはならない。これが面倒臭いわけ。 で、いつ頃まで「戻って」ではなく「戻つて」という表記が使われているか、と言いますと、大体1960年代初頭くらいまでは、「戻つて」が主流のような気がする。要するに今から50年前までは普通にこういう大文字だけの表記が使われていた、ということになりますかね。 そういう意味では、促音便の表記に小文字を使うようになつたのは、わりと最近になつてから、といつていいでしよう。 ぎやくに言えば、ちよつと前までは、こんな感じの表記で人々は文字をつづつていたということになるわけですな。 あれ? なんだか、はまつてきた。 これ、けつこう、おもしろいんじやない? ひやー。めつちやくちや、おもしろいわ。 これから、昔ながらの、こんな書き方でこのブログもかいちやおうかな?! やつつぱ、しようしよううざいか!
July 3, 2014
コメント(0)
-
知性はどこに消えた?
ザッケローニ監督離日に際して、長谷部選手と内田選手が見送りに現れ、監督も感激していたとのこと。まあ、しかし、浪花節思考の私からすれば、結果はどうあれ4年間世話になった人が国に帰るのに、見送りがたった二人だけかぁ・・・って印象を受けますなあ。それぞれ、忙しいのではありましょうけど、それにしてもねえ。逆に、見送りに来た長谷部さんと内田さんはいい人だなって思います。特に長谷部さんは、ますますファンになっちゃうぜ。 さてさて、今日は退屈な退屈な教授会だったのですが、私は内職に勤しみ、スペンサー・ジョンソン著『チーズはどこへ消えた?』という、ひと昔前の世界的ベストセラーを熟読しておりました。 ちなみに本書の日本語版が出たのが2000年、今日私が読んでいた本は2014年版ですけど、この14年間になんと64刷。日本語版だけでもどのくらい売れているんだって感じ。ですから本書を読んだことがあるという方も多いのではないかと思いますが、一応、内容を説明しますと、登場人物は二匹のネズミと二人の小人。で、ネズミチームと小人チームがそれぞれ、チーズステーションという名の迷路のどこかに隠されているチーズを探すわけ。 で、ネズミは馬鹿なんですけど、馬鹿な分、戦略もシンプルなので、迷路の中でチーズを探すとなれば、とにかく試行錯誤を繰り返しながら、ひたすら迷路を走り回って探すわけ。無駄も多いので時間は掛かるけど、結局は目的のチーズに辿り着いて幸せになる。 一方、小人チームも最初は頑張って八方手を尽くして迷路を探し回り、ようやくチーズを見つけて、ネズミチーム共々ハッピーになると。両チームとも、しばらくの間、戦利品をむさぼって満ち足りた日々を過ごします。 ところが、ある日、チーズが忽然と姿を消すんですな。 ネズミチームは、単純なので、「チーズがなくなっちゃった。じゃ、次の探そう」って感じで、何のためらいもなく新たなチーズを探しに迷路を走り回ります。ところが小人チームは、もう少し逡巡することになる。 小人チームの二人は、まず、チーズという既得権を失ったことに呆然とするわけ。そして、嘆き悲しみ、ここで待っていれば、ひょっとして次の日には消えたチーズが戻ってくるのではないかと、はかない期待を抱いたりする。要するに、ネズミチームと違って、さっさと次のチーズを探す行動に出られないんですな。で、とにかく絶望を自分たち自身で増幅させてしまって、身動きがとれなくなる。 ところがそんな無為な日々が続いた後、二人の小人のうち、一人が「こんなことじゃ、いかんのじゃないか?」という自問自答を始めるわけ。で、この小人は、色々悩んだ挙句、ついに別のチーズを探すため、迷路の探索を始めることにする。しかし、もう一方の小人は、がんとして行動を拒否し、この場に居残ると宣言。仕方なく、先の小人は一人で別なチーズを探すため、迷路の探険に向います。 が、迷路の中でも、彼は悩むわけ。やっぱり、友だちと一緒に元の場所で待っていた方が良かったのではないか? 迷路に探しに出たのは間違っていたのではないか? と。なかなか次のチーズが見つからないことも、彼の不安と苛立ちを募らせることに資するばかり。 しかし、それでも彼は思い直し、「ただ手をこまねいて現状にいるより、その現状を棄てて、あらたな冒険に出たほうがずっといい」ということに気づく。それで希望を胸に探し続けた結果、遂に彼は新しいチーズにたどり着くんですな。 とまあ、要するにこれは寓話で、人間は一度成功すると、その成功に安住してしまって、仮にその成功が効力を発揮しなくなった後でも、いつまでもそれにしがみつこうとする。しかし、それをやっていると、本当にダメになってしまうので、そういう場合は、「別のチーズ」をもとめて行動する方がいいし、また新たに行動を起しつつ、なぜ前の成功がダメになったのかを分析して、次に成功した時の心得にする、というようなことをした方がよほど建設的である、というようなことが言いたいわけですな。 実はこの話は二重構造になっていて、この寓話を知った人間の大人たちが、それぞれの人生を振り返りながら、自分も成功に安住して、それがダメになった後までしがみついていた小人にそっくりだ、ってな反省をし、一つ賢くなりました、みたいなオチが付くのですけれども、とにかく、基本的な部分としては、「人生、うまくいかなくなったら、うまくいっていない状況にしがみつくのではなく、積極的に行動して、新しい人生を切り開いていった方がよほど得よ」という話であるわけですよ。 ちなみに、この本を内職で読んでいる間、教授会が進行していたわけですけれども、そこでは来たるべき改組に向けてどうすべきか、なんてことが議論されている。 で、その改組というのは、文科省主導の改組であって、私としては、一体全体、今うまく行っている組織をなぜ変える必要があるのかさっぱり分からないところがある。故に、私自身はこの件に関しては保守派でありまして、基本的な立場としては改組反対なんです。 が! 『チーズはどこへ消えた!』というのは、保守派を批判し、「こういう時は、とにかく積極的に行動でしょ!」とけしかける本であるわけで、何だか読んでいるうちに、自分自身のことを批判されているような気になり、何だか居心地が悪くなってきたというね。 どうなんだろう、文科省は、またいつものその場その場の適当な思いつきで「今のままじゃダメ」とか、訳のわからないことを言っているだけだと思うのですが、それでも、どうあがいたって結局は文科省の言うなりになるしかないのであれば、改組に積極的に取り組んだ方がいいのですかねえ・・・? どうなのかしら。 ま、タイミングがタイミングだっただけに、この本を読んでそんなことを色々考えさせられたわけでございます。 しかーし! 冷静になってこの本を評価するとなると、私に言わせれば、この本、驚愕の本でございますよ。 驚愕というのは、どうしてこれほどア○みたいな本が、これほど売れるのか、という意味で。 寓話っていったって、ひねりもなければ、作意見え見えで、この寓話について話し合いを行う大人たちの会話も、わざとらしいというか、泣きたくなるほど下らなくて、ほんとにこんな本をお金だして買う奴いるのかよって感じ。まあ、私自身買っているわけで、人のことは言えませんが、それでも私は仕事で買っているので、プライベートでは絶対に買わないよね・・・。 チーズがどこへ消えたか考える前に、著者の知性は一体どこへ消えたのか、私は断固尋ねたい。というわけで、この本、教授のおすすめ!は、なーしよ!
July 2, 2014
コメント(0)
-
なっちを見直す
今日のことではなく、昨日のことなんですが、昨夜、NHKのBS放送で、『ダイ・ハード』(日本語吹き替え版)をやっていまして、それ、つい見てしまったんです。 私はこの映画が好きでね。完璧な脚本! どの一部をとっても、面白くないシークエンスがない! だけど、百回くらい見て見慣れているはずのこの映画を見ていて、どうもピンとこない。アレ? 変だな? と思ったら、日本語吹き替えの声優さんが違う。そして、日本語訳が違う。 私が見慣れているのは、民放版の吹き替えで、その場合、声優は野沢那智、そして訳は「なっち」こと戸田奈津子。しかし、昨日見たNHK版では声優も訳も違う人。 で、思うにやっぱりブルース・ウィルスの日本語版吹き替えは、野沢那智じゃないのかなと。(村野武則でも、まあ、いいけど)。 そして、訳はなっちかなと。 例えば、足にガラスが刺さった状態で、アルと無線でしゃべるシーンで、アルの哀しい過去を聞かされたマクレーンがつぶやく台詞がある。 これ、うろ覚えですけど、なっち訳では「何だか気が滅入ってきた」なんですよね。 ところが、昨日見たNHK版では、「嫌な気分になってきた」みたいな訳になっていた。 この一箇所を比べただけでも、なっち訳の方がいいんだよなあ・・・。 一事が万事でありまして、なんだかしっくり収まらない日本語訳の吹き替えを、聴きなれない声優さんの声で聴かされて、イマイチ、「いつもの『ダイ・ハード』じゃない!」的な思いを抱かされたのであります。 戸田奈津子訳。いいのか、悪いのか、私には必ずしもわかりませんが、少なくとも『ダイ・ハード』に関する限り、なっちはいい仕事をしているのではないか。私はその点、なっちを少し見直してしまったのであります。
July 1, 2014
コメント(0)
全19件 (19件中 1-19件目)
1