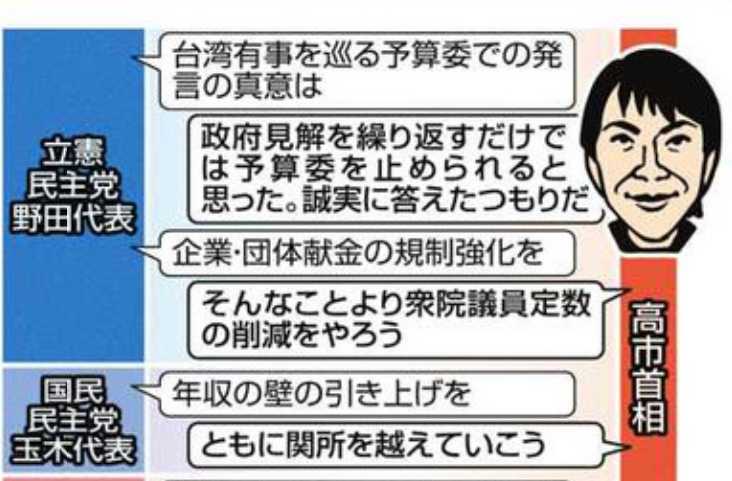2016年03月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
角川映画やらルパンやら
先日、1977年前後のアメリカ映画のヒット作の話を書きましたが、当時、日本映画はどうなっていたのか。今日はその辺のお話を。 1970年代って、まず大映がつぶれ、日活はロマンポルノ路線に転向、東宝はそれでも『日本沈没』とか『八甲田山』、あるいは三浦友和&百恵の「ゴールデンコンビ映画」で気を吐くものの、東宝は寅さん頼み、東映は実録やくざ路線頼みと、日本映画界は総じて暗黒時代なんですけれども、その中で異様に目立っていたのが角川映画。いわゆる「読んでから見るか、見てから読むか」の時代でございます。 丁度私が中学に上がった頃、1976年ですかね、まず『犬神家の一族』の映画版がどーんと出た。原作の方も横溝正史の作品が角川文庫でずらり揃って、空前の横溝ブーム。映画版では石坂浩二が金田一役でしたが、翌年から始まったテレビ版横溝シリーズの古谷一行バージョンの金田一も良かった。 そして、『人間の証明』ね。森村誠一。ドゥー・ユー・リメンバー? ついで『野生の証明』、ここで薬師丸ひろ子登場。これまた私とほぼ同世代の少女が映画界に彗星のように現れたことで、強く印象に残っております。それから松田優作の『蘇える金狼』。そして『戦国自衛隊』。この時期、横溝正史とか、森村誠一とか、大藪春彦とか、半村良とか、角川映画がらみでどーんと売れたミステリー/ハードボイルド系の一郡の作家というのがおりましたねえ。 もっとも、ほれ、多くの人がわーーーっともてはやすものに対して、極端に「アンチ」な態度を取る私、こういう系のものは一切見ておりません。現象としては角川映画の隆盛ぶりを目撃したけれども、私自身はその中に入って行かなかったという。 だから、中学校時代、友人たちが競って角川文庫の横溝正史ものを読み漁っているなあと思いつつ、私はまったく、一冊も読んでないの。今思うと、自分に対して「そういうところだよ、お前のダメなとこ」とダメ出ししたいところですけど、過ぎちゃったことは仕方がない。でも、ま、とにかく、当時角川映画の勢いがすごかった、というのは、はっきり覚えております。 それから、やはり私の中学時代のことだと思うのですけれども、もう一つ覚えているのは、この頃、二つのアニメ作品が我々の世代で人気があったということ。 一つはね、『ルパン三世』。もちろん、第1シリーズのこと。 もともとこのアニメは1971年に放送されていたのですが、最初に放送された時はほとんど話題にもならなかった。ところが、何度か再放送されているうちに人気が出てきたんですな。何を隠そう、かくいう私もその何度目かの再放送ですっかり魅了されてしまった口。私の「今まで見た中で素晴らしかったアニメ」ランキングでも、『妖怪人間ベム』『サスケ』『アルプスの少女ハイジ』などと並んで、常に1位か2位を争う作品でございます。 しかし、その人気にあやかってか、1977年から第2シリーズが始まるでしょ。赤いジャケットを着たルパンが登場する奴。これには本当にガッカリさせられたものでございます。あのルパンなんだから面白いはず、と思って、期待マックスで見るのだけど、その都度、ガッカリという。第1シリーズとは雲泥の差でした。第1シリーズは大人の鑑賞にも耐えるけれど、第2シリーズ以後は、レベルの低い子ども騙しですな。 それからもう一つ、ルパンと同じ様に再放送によってじわじわと人気が上昇し、最終的には国民的アニメになってしまったものとして、この時期、『宇宙戦艦ヤマト』がありました。 それ以前のアニメといえば、敵と味方の二項対立で、敵は100%悪い、というのが常識だったと思うのですけど、『宇宙戦艦ヤマト』の場合、二項対立は二項対立ではあるものの、敵であるはずのガミラス星人にも地球を乗っ取る大義名分というのがあって、向うの連中だって可哀想なんだよな、というところがある。しかも、敵には敵の名将というのがいて、尊敬できるところもある。そういう、単純な勧善懲悪でないところがすごく新鮮でしたねえ。 ま、その後、宮崎駿が『風の谷のナウシカ』で三項対立アニメってのを編み出し、さらに『もののけ姫』になると四項対立くらいになってどんどん対立項が増え、それに比例してストーリーがとめどもなく難解になって行くのですけれども。 それはさておき、出版社が母体の角川映画にしろ、再放送がきっかけのアニメ人気にしろ、今までとはちょっと異なる経緯をたどって一連の作品が話題になるという、そんなことが1970年代後半にはありましたね。
March 31, 2016
コメント(0)
-
スーパーの宅配サービスと「ラッタッタ!」の時代
私の実家は、スーパーマーケットまで歩いて5分、というような感じで、日頃の買い物の便はいい方なのですが、それは若い者の考え方であって、80代の母からすれば、行きはまあいいとして、買ったモノを両手にぶら下げて5分の道のりを歩くのはそれなりに骨。これからますます歳をとっていくことを考えると、買い物もままならない、なんてことにもなりかねません。 で、今テレビで宣伝しているイトーヨーカドーの「ネットスーパー」でしたっけ? あれを利用したらどうかと思ったのですが、あれはその名のごとく、インターネットでの注文になるので、母には無理か・・・。 で、あれこれ調べてみたのですが、生協にしても「らでぃっしゅぼーや」にしても、帯に短し襷に長しって感じで、どうも我が家のニーズには合わない。うーむ、意外に難しいもんだなあと思っていたら、なんと灯台もと暗し。いつも使っているスーパーに宅配サービスがあったのでした。買い物をして、5000円以上だったら無料で、それ以下だったら200円くらいの配送料で家まで持ってきてくれるというシステム。これならば、重い荷物を下げて歩かなくて済むので、それだけでもかなり楽。 しかも、同じ系列の別のスーパーでは、300円の配送料を払えば電話注文で買い物が出来るらしく、これなら、例えば体調が悪い時など、外に出ることなく買い物を済ますことができる。いやあ、調べてみるもんですなあ。 これからは年老いた両親にとって、色々な意味でサバイバルの時期。利用できるサービスは何でも利用しないとね。 さてさて、「昭和の男」シリーズ、1977年頃の話が続いております。 昨日、この頃の日本が、ディスコのビートに乗ってなんとなく浮かれていたという話をしましたが、ビートと言えば、もう一つ、この時代にはエンジンのビートも軽やかに轟いていたのでございます。 まずね、この頃、日本で「原付自転車」のブームが来るんです。 一番印象的だったのは、ホンダが売り出した「ロードパル」ね。1976年の発売。これ、CMにあのソフィア・ローレンが登場して、「ラッタッタ!」とか言いながらエンジンをかけるという。この「ラッタッタ」が流行ったのよ。で、翌1977年にはヤマハが「パッソル」を、1978年にはスズキが「ユーディーミニ」を発売して、原付人気が沸騰。もっとも、原付の人気が高かったのは数年のことで、1980年代に入ると各社ともステップスルー(両足を揃えて乗れるタイプ)のスクーターに販売の主力を移すことになるのですが、とにかく、1970年代末には、原付自転車の軽やかなエンジン音が日本中に響いたわけですよ。 そして、同じ頃、自動車の分野でも新顔登場。ホンダの「シビック」ですな。シビックの発売は1972年ですが、翌1973年に「ホンダマチック」という自動変速機付きのものが加わり、さらに当時世界一厳しかったカリフォルニア州の排ガス規制を初めてクリアした「CVCC」エンジン付きのものが売り出されると一気に人気上昇。1970年代後半には、このコンパクトなハッチバック車が日本中の道路を席巻し、バイクメーカーだったホンダの四輪車部門進出への決定的な足がかりとなったのでした。 で、思い出すのですが、私が中学校に上がった頃、そこの先生方の多くがこのシビックに乗っていたんですわ。だから職員用の駐車場なんてシビックだらけ。特にまだ若くて、それほど月給も多くなかったであろう先生方も、シビックなら買えたんでしょう。そういう若い先生方がみんなシビックを乗り回していた。そういう意味で、日本のモータリゼーションってのは、1970年代半ばに一気に成熟したんじゃないでしょうかね。 原付自転車とか、自動車とか、庶民にとっては大きな買い物であるはずのモノに関して、この頃、どんどん画期的な商品が売り出され、さかんにCMが流され、それを皆が買った。そういう景気の良い時代、それが1970年代後半だったのではないかと。 それにしても、若者や若い奥さん方が原付自転車を乗り回し、若いサラリーマンたちがシビックを買って乗り回していた時代。やっぱり「ラッタッタ!」のかけ声の似合う時代でした。
March 30, 2016
コメント(0)
-
ロッキーとディスコブームと未知との遭遇
昨日、父の米寿記念で句集を出す、という話を書きましたが、今日は早速その作業に取りかかり、父がこの10年ほどの間に作った写真俳句の一覧表を作っていたのですが、さすがに10年分となると相当な分量があって、結局一日仕事になっちゃった。もちろん、素人の作る俳句ですから、どうしようもないものも多いのですが、やはりこういうのは経験がものを言うのか、ここ数年の作品は、時々(ほんの時々ですけど)、おっ、と思うような出来のいいものもある。下手な鉄砲も数打ちゃ当たるといいますが、やっぱり下手でも打ち続けることが大事なんですなあ。大したもんだ。 さて、このところ1970年代後半の話に差し掛かっておりますが、今日は1977年〜78年頃の話。 1977年というと、例えばサダト大統領のイスラエル訪問とか、歴史的なトピックもあるのですけど、ま、当時中学生の私にはそれほど重要なことにも感じられず。それより、この辺りの時代で鮮明に覚えているのは、アメリカの映画のヒット作の数々のこと。 まずね、『ロッキー』ですよ。1976年の作品ですが、日本公開は翌1977年だったような。言うまでもなく、シルベスタ・スタローンの出世作。「エイドリアーン!」が感動的で。しかも、この映画が封切られた頃に中学2年に進級した私は、たまたま所属したクラスが「ロッキー組」(私の通っていた中学では、各クラスに山の名前がついていた)だったこともあり、この映画、なんとなく「我がクラスのテーマ映画」的なところがあって、一層、印象に強く残っております。 で、1977年の映画と言えば、『サタデーナイト・フィーバー』の人気がすごかった。こちらはジョン・トラボルタの出世作。そしてビージーズの音楽が素晴らしかった。これがきっかけで、日本ではその後、ディスコ・ブームにつながって行ったのではなかったかと。 それにしても、ビージーズのディスコ・サウンドはビックリでした。というのは、当時の日本人にとって、ビージーズと言えば『小さな恋のメロディ』の音楽担当として印象づけられていたからで、「若葉の頃」とか「メロディ・フェア」など、繊細で美しいメロディが売りのグループだと思っていたのに、それがいきなりドンスカドンスカのビートに乗せたファルセットの炸裂でしょ。このサウンドの大転換、まさに「山本リンダ級」でしたね。 「山本リンダ級」といえば、この頃、もう一つビックリさせられたのは、オリビア・ニュートン=ジョンの大変身。「そよ風の誘惑」で我々日本人を魅了したたおやかな女性歌手と思っていたら、1978年にトラボルタと組んでディスコ映画『グリース』に出演、その後レオタード姿で「フィジカル」などという破廉恥な歌まで出しちゃって。 とにかく、やがて来るバブルの時代を予感させるイケイケの感じが、これらヒット映画からも窺えますなあ。 それから、もう一つ、この時代のアメリカ映画の傾向としては、「宇宙」を扱ったものが立て続けに出たということですな。 まず『未知との遭遇』。これも、スピルバーグの意欲作ということで、えらい前評判だった覚えがある。巨大なマザーシップの圧倒的な映像と、例の「ティラリラリー」の音階。めちゃくちゃ流行った。 そして、1978年の夏にはかの『スター・ウォーズ』が上陸。映画的な面白さという意味では、『未知との遭遇』どころの騒ぎではなかった。しかもあの迫力の映像は、とても邦画が太刀打ち出来るものではなかったのではないかと。 でまた、それからさほど時間を置かず、『エイリアン』がやって来るのですけど、まあ、このあたり、宇宙映画全盛ですよ。そして、この空前の宇宙ブームに乗ってピンクレディーが「UFO」を出す(1977年)。焼きそばも「UFO」が出る(1976年)。そして街の喫茶店では「インベーダーゲーム」が大流行。 ディスコと宇宙モノで、上を下への大騒ぎ、それがこの時期の日本だったのではないかと。なんか、当時のことを思い出すと、沸き立つような明るさを感じますけど、実際、そんな感じだったんじゃないですかね。
March 29, 2016
コメント(0)
-

米寿記念
私の父が今年米寿を迎えるもので、何か記念になることをしようと考えていたのですが、出版マニアの私が出来る最大の親孝行としては、父の本を出版してあげることであろうと思い、ここ数年「写真俳句」に熱中している父のために、写真俳句の句集を編集・出版することにしました。昨年、先輩同僚の本を編集・出版した経験があるので、要領はもう分かっておりますからね。 計画としては、春・夏・秋・冬、それぞれ22句ずつ秀句を選び、全部で88句の本にして、88歳の記念にしようかなと。頭良いね、わし。 で、最初は父に「我ながらよくできた」と思う句を選んでもらおうかとも思ったのですが、それだとちょっとつまらないので、父だけでなく、母と姉と私も選句に参加し、父を著者に、我々を編集協力者にして本を出そうと。というわけで、今、その選句のための準備中でございます。 ところで、写真俳句ですから、写真と句がセットになるわけなんですが、これの編集方法をどうしようか、それが現在の悩みの種でして。 で、参考になるかなと思い、朝日文庫から出ている森村誠一氏の『写真俳句のすすめ』という本を買ってみたと。【中古】 森村誠一の写真俳句のすすめ /森村誠一(著者) 【中古】afb価格:198円(税込、送料別) で、これを読みますとね、右のページに句が一つ、左のページにその句にまつわる写真が一点、という具合になっている。基本的にそのパターンは変わらないわけ。 だけど、それがずっと続くと、ちょっとね、こう、ワンパターンな感じがする。 で、写真俳句ではないのですが、参考までに角川文庫から出ている銀色夏生さんの詩集を書店でパラパラ見ていたのですが、こちらは編集が洒落ていて、写真が上にあって詩が下にあったり、写真が右ページで詩が左ページにあったり、時には写真の上に詩の言葉が印刷されていたり、とにかく変化に富んでいて面白いというか、とにかく美的な意味でセンスがある。 うーむ、そこが朝日文庫と角川文庫の差か? それとも森村誠一と銀色夏生の差か?? それとも装丁担当者の腕か??? でも、両方を比べてしまうと、それはもちろん銀色の方がカッコいいわけで、私も父の句集をそのようにしたい。しかし、銀色さんの詩集に使われている写真はどうせプロが撮ったものだろうし、父の写真俳句の場合は、父自身が撮った写真ですから、写真そのものの出来だって正直、大分差があるといえば差がある。そこがね、また悩ましいところでありまして。 ということで、ひょっとすると、私の場合も森村本と同じく、右ページに句、左ページに写真のワンパターンになってしまうかもしれませんが、ま、まだ時間はありますから、そこはもう少し悩むことにしましょうかね。 でも、ま、とりあえずそういう本を出すということを伝えたら、父も嬉しそうにしていましたし、良かった、良かった。 さて、「昭和の男」シリーズですけれども、1975年とか1976年頃の話をしていたら、その頃のファッションについてあれこれ思い出してしまったので、ちょっとだけ書き付けておきましょう。 小学校高学年から中学生になりたての頃、私が普段、どんな恰好をしていたかと言いますと、これがね、バリバリ「パンタロン」スタイルだったのではないかと。 そう、1970年代前半、ジーンズといえば、「パンタロン」でした。っていうか、正式には「ベルボトム」というべきか。でも、当時の言葉遣いとしては、「ベルボトム」ではなくて「パンタロン」だったよなあ。 で、それは、今でいう「ブーツカット」どころの騒ぎではないほど、裾がどーんと広がっていて、今から考えるとかなり滑稽な感じがする。だけど、当時はそれが恰好よかったんですよね。大学生くらいのお兄さん、お姉さんだって、当時は大抵パンタロンのジーンズを穿いていたのではないかと。例えば前に言及した『俺たちの旅』なんてドラマを見れば、カースケ役の中村雅俊さんなんて、ばっちりパンタロン姿ですからね。 で、私もまたこの時代にはパンタロンを穿いていたのよ! 当時住んでいた東林間には、西口を出たところにある商店街の片隅に、「テキサス」という、いかにもジーンズ屋さんっぽい店名のジーンズ・ショップがあって、ほんの小さなお店なんですけど、行けば不思議と自分に合うジーンズを店の親父さんが出してきてくれるという。その親父さんも、当然下はジーンズ、上もデニムのシャツという、いかにもサラリーマンには向かなそうな、一目見てジーンズ屋の親父って感じでね。 で、大概そのお店で買ったのですが、銘柄はね、リーバイスとかリーとかもあったのだろうけれども、痩せっぽちの私には合わず、結局買ったのはエドウィンか、ビッグジョンだったような。 だけど、ここで私の特異なファッションセンスがしゃしゃり出て来る。 新品のブルージーンズを買って来るじゃない。で、それを穿く前に、風呂場かなにかに持ち込んで、裾の辺りに漂白剤をですね、びや〜っと引っ掛けるわけ。アクション・ペインティングの要領で。すると、びちゃっと漂白剤が引っかかったところだけ白く漂白されるので、ブルー・ジーンズに偶然性がもたらす白い模様が浮かび上がる。で、それを一度洗濯してもらってから穿くのよ。 要するに、自己流に加工したわけですな。誰に教わったわけでもなく。 で、友人からは「釈迦楽、それ変だよ」とか言われながらも、「わかってねえな、そこがいいんじゃん」とか言って、全然恥ずかしげもなく、むしろ得意になって穿いていたのですから、私も相当な変人だったんですかね。 ま、もっとも今だって、ほとんど誰もしていないのに自分だけはこだわってネクタイピンをし続けるとか、夏場は絶対にループタイの方が楽だからという理由で、ループタイをし続けるとか、変なところで「我が道を行く」ところがありますけれども。 とにかく、1970年代半ば、日本の若者は、こぞってパンタロンだった、ということは、懐かしく覚えておいていいことなのではないかと思う次第なのであります。
March 28, 2016
コメント(0)
-
中学生進学の儀式
ひゃー、昨夜、東京の実家に戻って参りました〜。新東名の豊田・いなさ区間、初めて走ったけど、やっぱり快適。岡崎周辺のノロノロ区間を通らなくていい分、スムーズよ〜。だけど、その先、大井松田・町田間で事故渋滞があり、結局、結構な時間が掛かってしまいましたが。 家に帰ってみると、二階への階段とか、風呂場/トイレなどにがっしりした手すりが付けられておりまして。段々、足腰が弱ってきた父のための措置なのですが、ううむ、いよいよこういう段階に入ってきましたか・・・。今はまだ何とかなっていますが、これから先、介護問題が他人事ではなくなって来るのかもね。 さて「昭和の男」シリーズ、いよいよ1976年あたりの話になっておりますが、この年、私は中学生になる。と、学校生活も大分変わって参ります。 私が通っていた小学校はランドセルを採用していなかったので、それぞれ適当に手提げ鞄を提げて通学していたのですが、中学に入ると、いわゆる「学生鞄」というのを持つことになる。 今、アレですかね、学生鞄ってスタンダードなのかしら? なんか、今時の中学生って、リュックみたいなの背負ってたりしない? でもね、昭和の中学生は、やっぱり学生鞄なんですよね。あれを持つようになることが、「もう小学生じゃないんだ」という自覚を促す一つの契機になっていたような気がする。 で、もちろん私も買ってもらったのですけれども、やっぱり嬉しかったですね。 それからね、当時の感覚ですと、子どもが小学生から中学生に上がる時に、もう二つ買ってもらえるものがあった。時計と万年筆ね。 時計をそれぞれ身につけるというのは、象徴的な意味で、「これからは自分で時間を管理するんだよ」というメッセージにもなっているのであって、なかなかいい風習ではないかと思うのですけれども、とにかく、私も中学に上がる少し前に親に時計を買ってもらった。人生初の時計はシチズンの「セヴンスター」という機種。フェースがちょっと紫がかった青でね、なかなかカッコ良かった。それ、今でも大切にとってあります。これを買ってもらった時は嬉しかったなあ。 それから万年筆。これも、「もう大人なんだから、鉛筆じゃなくて、万年筆を使いなさい」という意味合いがあるわけで、当時は中学生(=大人)になるために必要な儀式的なモノでしたね。例えば、旺文社が出していた『中1時代』とか、学研の『中1コース』とか、いわゆる「学年雑誌」と呼ばれるものがありましたけど、これが3月頃になると、定期購読者獲得のために「4月号からご予約の方には、もれなく万年筆プレゼント!」とか、そういうキャンペーンをやっていて、「万年筆は中学生の必需品」的な概念をさらに強化していたようなところもありましたし。 で、そういうこともあって、私も中学生になる13歳の誕生日に、プレゼントとして万年筆を買ってもらったのでした。セーラー万年筆で、皮巻の豪華版。当時の万年筆って、ある意味、今より豪華なところがあって、ペン先なんか14金よ。これも嬉しかった。 というわけで、学生鞄、時計、万年筆、この豪華3点セットを携えて、後期昭和の子どもたちは中学生に、大人に、なっていったのでございます。 ただ、この3点の中では、万年筆だけが宝の持ち腐れ、ってとこがあったんじゃないかな。やっぱり中学生くらいだと、筆記具の中心は鉛筆・・・いや、シャープペンだったかな。 私の通っていた小学校では、一応、学校ではシャープペン禁止で、鉛筆仕様がマストだった。で、黄色い箱に入った緑色のトンボ鉛筆がスタンダードで、たまに黄色いコーリンなんかを使っている子もいたかなと。だけど、上級学年になると段々贅沢になってきて、より滑らかに書ける鉛筆が人気の的になってくる。で、三菱の「ユニ」とか「ハイユニ」派と、トンボの「モノ」派に分かれるというね。私は、「ハイユニ」派だったかな。 そこへ持ってきて、小学校6年生くらいの時に、だから1975年か、三菱から「BOXY」という鉛筆が出まして。これが爆発的な人気よ。「O」のレタリングの真ん中の空洞のところが星形になっていてね。私も使いましたよ。でまた、金属製の缶ケースみたいなのもあったりしてね。 小学生にとって、鉛筆箱の中は魅惑の空間だからね。そこに何を入れるかってのは、結構、重要なセレクションだった。 そう言えば、消しゴムにも凝ったなあ。 だって、小学校低学年の時の消しゴムって「ねり消しゴム」しかなかったのですが、その後、「プラスチック消しゴム」というのが登場した時は感動したもんね。あまりにも消し易いので。 それで、一番スタンダードだったのはやっぱり三菱の「モノ」シリーズだったような気がしますが、私はね、シードが出してた「Radar」というブランドの消しゴムが好きだった。 ハイユニやボクシーの鉛筆、そしてRadarの消しゴム。思い出すなあ、我が鉛筆箱。そう、それで、そこに「ボンナイフ」が入っていたら完璧だよ。 「ボンナイフ」懐かしいな! 今、売っているのかな、ボンナイフ。年に一度くらいは、クラスの誰かがあれで流血の惨事になるという奴。カッターナイフの登場で、絶滅したのかな。 そう、それで、小学校までは鉛筆主体だったけれど、中学生になってシャープペン解禁となり、私もシャープペンを愛用したような気がします。 で、その際、私が一番愛用したのが「ぺんてる」が出していた「メカニカル・ペンシル」という奴。確か100円で安いのですけど、芯のところにスプリングが仕掛けてあって、強い筆圧をかけるとそのスプリングが縮んで芯が折れるのを防ぐという機構付き。今もそうですけど、私は筆圧がものすごく強いので、これじゃない普通のシャープペンだと、芯をボキボキ折っちゃうのよ。 なんか話がそれてしまいましたが、昭和の昔には、中学生になるにもちゃんと儀式的なモノがあったってこと。今はそれが「スマホ」に変わったとか、そういうことなのかも知れませんけどね。それだと、なんか可愛くないな。やっぱり、学生鞄とか、時計とか、万年筆とか、そのレベルがいいんじゃないかな。
March 27, 2016
コメント(2)
-
王貞治と野球の時代
昨日、1976年のコマネチの話をしましたが、翌1977年にはまたスポーツ関連の偉業がありました。そう、巨人軍の王貞治選手が756本目のホームランを打ち、当時の世界記録であったハンク・アーロン選手のメジャー・リーグでの記録を抜いて、文字通り世界のホームラン王となったのでした。 ま、今はね、日本人選手がじゃんじゃんメジャーに行く時代ですし、当時とはまた大分事情が変わるでしょうけれども、当時としてはあの、野球発祥の地アメリカの一番スゴイ記録を、王選手が抜いたってんで、それこそ国を挙げての大騒ぎでしたよ。実際、これで王選手は1977年に初の「国民栄誉賞」に輝くわけですし。 で、それで思い出すのですけれども、この当時はもちろんJリーグなんてのはないわけで、日本で「プロ」としてやっていけるスポーツって、相撲・プロレス・ゴルフ、それに競輪・競馬・競艇等々の他には野球くらいしかなかった。運動の得意な子どもにとってプロ野球ってのは、今以上に大きな夢の一つだったんじゃないでしょうかね。 で、我々の世代が子供の時と言えば、まだファミコンとかの時代ではないし、少なくとも男の子が集まればキャッチボールとか、三角ベースとか、野球がらみの遊びを外ですることが多かった。 大体、キャッチボールって、別に点数を競い合うわけでもなし、ただボールを投げ合っているだけで、よく考えてみると何が面白いのか分らないものですけれども、あれ、実際やってみると楽しいんだよね! 自分が投げる時は、なるべく相手が捕り易いように、相手の構えているグローブ目がけて投げるわけで、それが上手くいって友人が「ストライク!」なんて言ってくれると嬉しいし、逆にボールが逸れて相手が捕球できず、ボールを取りに走らせてしまったりすると申し訳なくて「ごめん、ごめん!」なんて言ったりして。たかがボールの投げ合いでも、相手を思いやる心ってのがあるわけよ。また友人が投げたボールを受けるというのも楽しくて、何て言うんだろう、一種無言の会話みたいなところがある。 それで、集まった友達が3人以上になるとバッターを立てることもできる。そうするとゲーム成立だから、これはまたこれで面白い。一人がピッチャー、一人がキャッチャーで、一人がバッター。3ストライク交代制で、ヒットを打ったら「透明ランナー」を想定し、ヒットが続いて透明ランナーがホームインすれば得点というね。 もちろん、もっと人数が集まれば、三角ベース(2塁を想定せず、1塁の次が3塁という奴)で試合をやったり、もっと人数が集まれば正式な草野球となる。子どもの対応力ってのは大したもので、人数に応じてそれなりに野球を楽しむ術を持っていたわけですよね。 だから、後期昭和の男の子の家には必ずグローブとバットと軟式のボールの一つや二つは必ずあったものですよ。今はどうかわからないけど。軟球にはA球とかB球とかC球とか、いくつか種類があって、我々が子供の頃は、たいていC球を使ったものでございます。C球が一番小さいのかな? もっとも、友達と二人だけでキャッチボールする時は、グローブを使わずに、ゴム製のカラーボールを素手で投げ合ったりもしましたっけ。 ちなみに私は運動神経が全然ない方なのですが、野球に関して言えば、投げるのも打つのも、まあ、人並みには出来る方で、皆とまざって野球をするには困らなかったのですが、一つ、難点があったのは、バウンドボールの捕球が苦手だったこと。よくトンネルとか、取り損なって弾んだボールを顔面に受けるとか、そういうドジを踏んだ苦い思い出があります。それで、少しでも上手くなろうと、壁にボールを投げてバウンドして戻ってくるボールを捕球する練習とか、一人で黙々としたこともありました。真面目かっ! だから、今でこそプロ野球にはまったく興味のない私も、子どもの頃はそれなりに興味があって、それなりに応援したりしたものでございます。どの球団を? いや、もちろん巨人を。なにしろ「巨人、大鵬、卵焼き」世代、巨人軍のV9が続いていた頃ですから、東京近郊の普通の子なら巨人を応援するものだったんですよ。ま、たまに阪神ファンとか、ヤクルトファンとか、いましたけど、ごく少数派で。もっとも当時阪神には田淵が居たし、ヤクルトには若松が居たし、それぞれのチーム・カラーは今以上に鮮明で、面白かったんじゃなかったかな。 で、巨人ファンとしては、長島派と王派に別れるわけで、私は華やかな長島派ではなく、努力の人・王派だったかな。あの一本足打法というのは、独特でしたからね。やっぱり、当時から「人と違うことをやる」人に惹かれていたんでしょうな。 だから、その王さんが一本足打法でホームラン記録を塗り替えた時は、やっぱり嬉しかったことを覚えていますよ。 だけど、その王さんも、そろそろ引退の時期を迎えていたし、王・長島が欠けた後を埋める選手としては、例えば淡口だとか、色々いたけれども、やっぱり王・長島の時代と比べると小粒感は否めず、1980年に彼が現役を退いた頃には私も高校生になっていて、そろそろ野球なんかしている場合じゃなくなってくる。私もまた野球卒業の時代を迎えていたのでしょう。 だけど、こうして子供の頃の野球の思い出を振り返ると、やっぱり王・長島が現役で活躍しているのをリアルタイムで見ていて、それに刺戟されて自分も原っぱに飛び出していった経験を持っているんだから、いい時代をだったんだなと思いますね。
March 26, 2016
コメント(0)
-
妖精コマネチの1976年
本来であれば、今日あたり、実家に帰ろうと思っていたのですけれども、私も家内も風邪でダウン。ということで、ここは無理をせず、帰省を一日延ばすことにして、今日は家でゆっくり休むことにしました。・・・といっても、私は結局、あれこれやらなきゃいかんことをしていたのですが。 さてさて、「昭和の男」シリーズ。今日は1976年頃のお話。 1976年と言いますと、私は中学に上がった年ですか。いよいよ「ティーンエイジャー」となった私は、この年、一体何を見たのか。 まず政治的なことから言いますと、「ロッキード事件」で田中角栄元首相が逮捕されるというのが、世間を一番騒がせていた事件だったんじゃないでしょうか。賄賂の単位を表す「ピーナッツ」なる隠語とか、田中角栄氏が例の口癖「よっしゃ、よっしゃ」を連発しながら、ロッキード社のために飛行機購入を取り計らったんだとか、まあマスコミの田中金権政治に対する批判のかまびすしかったこと。ちょっと前まで「コンピュータ付ブルドーザー」とか、「今太閤」とか、さんざん持ち上げていたのに。 私には田中元首相がらみで思い出すことが一つあって、それはロッキード事件の最中、家族で雑談していた中、私が「でも田中角栄って、割と好きだな」と発言したところ、両親からさんざん叱られたこと。私は「清廉潔白で無能な首相(まあ、三木さんのことですな)と、金権政治家だけど実行力のある首相を比べた場合、政治家としては後者の方が優れている」と論陣を張ったのですけれども、そこは両親と中1の論戦ですから、こちらに分がないのも当然。 だけど、没後、続々と出版される「田中角栄本」の数々はもちろんのこと、かの石原慎太郎氏が田中角栄に成り代わって一人称で書いた自伝小説(?)『天才』が、今日、ベストセラーまっしぐらの状況を見ても、田中角栄という人の人間としての抜群の面白さや魅力は疑い得ないわけでありまして、中1の頃の私の見立てもさほど間違ってはいなかったのではないかと。田中さんが地元での人気とりのために新潟に新幹線を引っぱって行ったことが随分批判されましたが、今はやれ北陸新幹線だ、北海道新幹線だと、新幹線の延伸ブームでありまして、上越新幹線を批判した人たちはどうしたんですかね。あれは駄目だったけど、これはいいんですかね。 さて、しかし、そういった政治がらみのスキャンダルの他に、もう二つ、日本人を騒がせた「事件」が1976年にはありました。覚えてます? そのうちの一つは、モントリオール・オリンピックの開幕。と言えばお分かりでしょうが、そう、妖精コマネチが華々しく登場したのがこの年なのでございます。 ルーマニア女子体操チームとして出場したコマネチ選手ですが、彼女はこの時14才。見ていた私は13才。年齢的にはほとんど変わらない、同年代の女の子が、世界中の人々が見守る中で「10点」の演技を連発するというね。まあ、衝撃的でした。 だって、それ以前の女子体操といえば、チャスラフスカでしょ。ずっしりとした、大人の女がやるものと相場が決まっていた。そこへ持ってきて、突然、まるで体重を感じさせない、まさに妖精としか言えないようなコマネチが登場してきて、とても幅10センチの平均台の上とは思えないようなアクロバティックな演技を、まったくミスなく、完璧にこなすわけじゃん? これはもう完全に事件ですよ。 その可憐な美しさと演技の妙、そして自分とほぼ同年だということで、驚異と憧憬と羨望と嫉妬と、この4つの感情がグルグルと渦巻くのを感じながら、私はコマネチの一挙手一投足から目が離せずにいたのでした。 だからね、私にとってコマネチは、ある意味、神なの。 それゆえ、と言いますか、後にビートたけしが「コマネチ!」というギャグを編み出した時、私はまったく笑えなかったし、今も笑えません。ビートたけし氏の世代の人たち、そしてそのギャグを笑った私より年少の人たちにとってはギャグの対象になるのかもしれないけれど、私にとってコマネチはギャグの対象にしてはならないものなのよ。(私と同世代の皆さん、そうですよね?) とにかく、コマネチの登場は衝撃的でございました。 さて、もう一つの事件は何かと申しますと、「ミグ25事件」でございます。 1976年というと、南北ベトナムが統一した年でもあって、冷戦のもやもやがまだまだくすぶっていた時期。そうした時期に、ソビエトの最新鋭戦闘機ミグ25に乗ったベレンコ中尉が函館に亡命してきたのですから、まあ、びっくりよ。 でまた、その東側の最新鋭機ミグ25が、実は真空管だらけの旧式なものだったと判って大笑いっていうね。 ま、それはともかく、ミグ25に乗ったソビエト軍中尉の突然の函館飛来で、ただでさえ緊張状態の続く東西状況の中に期せずして日本が巻き込まれるという、そんな大騒ぎがあったのが1976年という年でしたねえ。
March 25, 2016
コメント(0)
-
結婚記念日
昨日、卒業式で、学年の行事をすべて終了したわけですから、少し休みたいところだったのですが、事務の方から「先生宛てに大きな荷物が届いていますから、なるべく早く取りに来て」というメールが入り、結局、今日も大学に行くことに。 荷物ってのは、アメリカ文学会の機関誌だったのですが、和文号・英文号とも200部ずつありますから、大きな段ボールで3箱、これを自分の研究室に運び込むのにまあ、大汗かかされました・・・。 でも、今回の号には、私の著書に対する書評も掲載されているので、ちょっと楽しみ~。 その他、大学に行ったら行ったで仕事が追いかけてくるもので、あれやこれや事務的な仕事をこなして、一日暮れてしまったという。いやはや、安月給で働かせてくれるねえ・・・。 ところで、今日は我々夫婦にとって18回目の結婚記念日。ということで、帰宅してから急いで支度をし、夕食を外食することに。向った先は、尾張旭にある「菊花」という中国料理のお店。 このお店、中国料理とはいえ、ちょっと和のテイストも入ったヌーベル・シノワという感じで、脂っこかったりしつこかったりすることなく、コースを通して工夫を凝らしたそれぞれの料理を堪能できました。素材もよく吟味されていて、完全予約制ということもあり、ゆったりと過ごせたのもグッド。このお店、教授のおすすめ!です。 それにしても18年、早いものでございます。あっという間の、しかし楽しいこと満載の18年でした。これからも二人で力を合わせて、私の甲斐性が許す最大限の範囲で、人生を楽しみ尽くしたいと思っております。まだまだ、お楽しみはこれからよ!
March 24, 2016
コメント(0)
-
卒業式&修了式
今日は勤務先の大学で卒業式と大学院の修了式がありました~。 今年のゼミ生3人は、これぞ「釈迦楽ゼミ生」って感じで、私の秘蔵っ子たちでしたし、修士論文の面倒を見た大学院生2人も良かったので、今日は彼ら/彼女らの門出を見ながら、嬉しくもあり、寂しくもあり、って感じでしたね。 でもまあ、社会人になってもきっと連中は節目節目に私のところに戻ってきて、その時々の報告をしてくれることでしょう。ゼミ生の連中は、早くも夏前には全員で集まろうとか計画していましたし。 でも、やっぱり寂しいな・・・。私は直接の教え子たちのことは極端に可愛がるからね。子離れできない親みたいなものですわ。 別れが辛くないような人間関係なんて意味がないと思っているし、でも、いざ別れなければならないとなるとやっぱり辛いし。その堂々巡りの中で、私は毎年、この別れの日を悶えるように苦しみ抜いているのでございます。
March 23, 2016
コメント(0)
-
加藤有希子著『カラーセラピーと高度消費社会の信仰』を読む
加藤有希子さんの『カラーセラピーと高度消費社会の信仰』(サンガ)という本を読みましたので、心覚えを。 この本、タイトルからだと何が書いてある本なのか、とっても分かりづらいと思うのですけれども、簡単に言えば自己啓発本に対する批判の書です。 で、加藤さんはもともと美術史とか表象文化とか、そういう方面がご専門なので、自己啓発のジャンルの中でも特に「カラーセラピー」とか「オーラソーマ」とか呼ばれるジャンルに興味を持たれたと。で、そういうセミナーみたいなのに実際に参加したりしながら、カラーセラピーとは何か、そういうものに救いを求める人々ってのはどういう人たちなのか、というようなことを調べ始めたわけですな。 で、私も「カラーセラピー」とか「オーラソーマ」というものについてはほとんど無知だったので、どんなものかと思って読み始めたのですけれども、「オーラソーマ」というのは1980年代にヴィッキー・ウォールという人が考案したものらしく、色のついたオイルの入った瓶をですね、被験者に自由に選ばせる。で、その人が選んだボトル、というか「色」をもとに、その人の心の状態なんかを分析していく、的なものらしい。 と言うと、ほとんどカード占いですよね・・・。 でまた、このカラーセラピーがさらに進化したのが「オーラソーマ」らしくて、これの発案者はC・W・リードビーターとかいう人だそうで、この人によると、人の身体には「チャクラ」というツボのようなものが7つあって、これが虹の7色に対応していると。だから、被験者が赤いボトルを選んだとしたら、それは赤のチャクラである下半身に対応するので、その赤いオイルを足に塗る。そうすると・・・よく分からないけれどもなんか効能があるんでしょ。 ま、とにかく、カラーセラピーとか、オーラソーマの先生になると、そんな感じで被験者の心を分析したり、オイルを塗ったりして、6日間のセミナーで14万円くらい取る。だけど、被験者はそれで「本当の自分」を見出してハッピーになれるのだから、全然OKというシステムらしい。 で、まあ、悩んでいる被験者がそれでいい気分になれるのであれば、第三者としては別に構わないわけですけれども、常識的に言えばこんなの詐欺に見える。で、加藤さんも、どうして人はこういう噓臭いものに簡単に引っかかるのか、そのメカニズムを究明したいと思われたんでしょうな。で、本書第二章以降は、自己啓発とかスピリチュアルとかニューエイジとか、そういうものについてあれこれ考察を巡らせるわけ。 で、加藤さん曰く、現代人が罹っている病とは、「自分とは誰か?」を問うことであると。現代人の誰もが「自分を知ること」が一番大事と信じてしまっている。いわゆる「自分探し」ですな。本当の自分を見出したいという願望。我々が生きている現代というのは、そういう「ミーイズム」の時代であると。しかし、そのような問いを発するということは、「自分とは誰か?」という問いに対する答えが存在すると信じていることが前提だし、またその答えさえ見つかればすべての悩みが解決すると信じていることになる。 だけど、加藤さんご自身は、「自分とは誰かを問うことは、狂気への入口」だと思われているらしいんですな。確固不動の「自己」を探せば探すほど、脆弱な自分しか見いだせないという悪循環に巻き込まれてしまうと。加藤さんご自身の文章を引用しましょう。「ミーイズム、そしてそれを支える個人主義の勃興――その背後には、自己の強化ではなく、自己の脆弱化が見て取れた。自己はゆさぶられるほどに、その不安を打ち消さんがために、自己に拘泥するのである。グローバリズム、自由にともなう物語の個人化、画一的な自己像、他者の肥大化、不安とリスクの増大・・・かつてないほどに自己像の確立が求められる現代、それは同時にかつてないほどに自己が危機に瀕している時代なのである」(80頁) で、そんな時、自己啓発本とかスピリチュアルとかニューエイジとかがしゃしゃり出てきて、「自分を信じるのです」的なことを言う。「自分自身が積極的なことを考えれば、すべて上手く行くようになりますよ」と。 要するに、自分探しの不安の渦中にあった人に、「大丈夫ですよ~」と声を掛けてくるのが自己啓発本であり、だからこそ現代人はこの安易な慰めにコロッと引っかかってしまうというわけ。根本的な解決ではなく、そこそこの解決、だけど、非常に明瞭な解決法を提供してくれるので、誰もがこれに飛びついてしまう。 その一方、「積極的な思考」というのは、自分さえ積極的に考えて行動すれば物事は上手く行く、と教えるので、逆にもしそれでも物事が上手く行かなかった場合は、自分が十分に積極的ではなかったからということになってしまう。つまり、成功の原因も自分だけれど、失敗の原因も自分ということになってしまう。頑張っても出来なかったのは、頑張りが足りないからだ、ということになってしまう。その意味で、頑張れば上手く行く社会的強者にはいいけれども、頑張っても上手く行くことが少ない弱者には非常に厳しい側面もある。 だから、自己啓発本という安易な解決法は、両刃の剣なのだ、と加藤さんは警告するんですな。そして、このことこそ、村上春樹の『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』という小説の中で、村上が自己啓発セミナー主催者の「アカ」を批判的に描いていることの理由であろうと加藤さんは喝破する。 ま、私流にまとめるならば、本書の内容はざっとこんな感じです。 さ・て・と。 で、加藤さんのお説、説得力あります? 私には全然ないね(爆!)。 大体、現代人は皆「自分探し」していて、その結果「脆弱な自己」しか見いだせず、狂気へのスパイラルまっしぐら、っていう前提からして全然受け入れがたい。私、現代人ですけど、全然そんなこと考えてないもんね。「脆弱な自己」とか、そんなのインテリの言葉遊びにしか見えない。その辺のおばちゃん捕まえて聞いてごらんなさいよ、「あなた、ひょっとして脆弱な自己に遭遇して狂いそうになったことありませんか?」って。 なんかね、加藤さんの問いの立て方とそれへの答え方が、独り相撲みたいなんですよね。勝手に「現代はこういう時代で、人々はこういう問題を抱えている」という仮説を立て、それに対して自己啓発本はこういう解答を寄せるから無責任だ、と批判するのだけれど、その仮説に賛同できない人間からすれば、「この人、何言っているの?」って感じになってしまう。 それに、そもそも自己啓発本って、「自分さえ信じればいいんです」的なものばかりじゃないですよ。もっとはるかに健全なものだ。 例えば最近読んだ『バビロンの大富豪』にしたって、その言わんとしているところは、成功したければまず仕事を好きになって一生懸命働き、稼いだお金の1割を自分の将来のために健全な投資に回しなさい、という、ごく常識的なことですから。これ以上ないほど健全な提案。自己啓発本って、基本そうですよ。給料分よりちょっとだけ多く働きなさい、とかね。 もちろん、いわゆる「引き寄せ系」の自己啓発本の場合は、「宇宙に向かって強く念じたことは必ず実現する」的なことが書いてありますが、これもね、歴史的に見れば、それ以前の常識、すなわち「すべては神様の決めたことだから、人間がどう考えようが、どう行動しようが、何一つ人間の思い通りにはならないよ」という常識へのアンチ・テーゼとして出てきたものですからね。そこを理解しておかなと、まったく意味がない。 昔の「士農工商」の時代みたいに、農民に生まれついたらどうあがいても一生農民として過ごす以外ない、という時代の方がいいというなら別、そうでなければ、自分のやりたいことができる社会の方がいいわけでしょ。「引き寄せ系」が主張する「なんでも自分の望み通り」というのは、「あなたの運命は、他人(or神)に定められたものではないのだから、自分で決めていいんですよ」ということを比喩的に言っているだけですから。 だけど、加藤さんの本にはそういう歴史的経緯の部分が欠如しているので、引き寄せ系の言説が単なるオカルトとみなされてしまっている。それじゃ、本当の意味で、自己啓発思想の何たるかなんてわかりませんよ。 また加藤さんは、自己啓発思想のスタート地点として、アメリカの思想家エマソンを持ち出すのですけれども、エマソンについての理解もかなり怪しい。加藤さんの理解では、エマソンが自己啓発的な思想を持っていたみたいに考えておられるようですけれども、そうじゃないからね。ただ、エマソンの言葉を著作物の文脈から切り離してそれだけ見ると、まるで現代の自己啓発本の言説そっくりに見える。だから、彼の言葉は歴代の自己啓発本作家たちから引用され続け、その結果、まるで彼が自己啓発思想の産みの親みたいに見えてしまう、というところが面白いのに、その辺、全然ノーチェックという感じがする。っていうか、そもそも加藤さんはエマソンがいつの時代の人かも知らないようで、エマソンの言葉を引用しながら、「これは七〇年前の言葉だが・・・(60頁)」とか書いていますけれど、一七〇年前の間違いでしょ。百年も違うじゃん。 あ、それから加藤さんが本書の中で使うキーワードの一つ「ミーイズム」という言葉の使い方も、ちょっとおかしくないか? 加藤さんは「自分は誰か」という問いにこだわる精神状況のことを指してこの言葉を使うのだけど、本来、「ミーイズム」って、自分の幸福や満足だけに関心を持つ自己中心的な心情のことを言うのでしょ。意味内容が大分違うじゃん。 ま、そういう個々のこともそうなんですけど、私がこの本について一番感心しないのは、加藤さんが「自己啓発本」なるものを「面白い」と思っていないことですね。最初から批判の対象としてしか見ていない気がする。 だけどね、例えば「クルマが欲しい」と強く心に念じれば、その思いが宇宙空間を伝って行って、宇宙空間を満たすエーテルに働きかけ、それがクルマの形に固まり、念じた者のもとにやってくる、などという突拍子もない自己啓発本の言説に触れて、これを「面白い」と思えない人に、自己啓発思想について云々する資格はないのではないかと。 だって、この考え方、面白いじゃん! こんなことを大真面目に論ずる人がいるということ、またそれを大真面目に信じる奴がたーくさんいるということは、すごく面白い。びっくりするぐらい面白いと思わない? で、面白いなあ! 一体全体、どうしてそういうことになっちゃうんだろう? という素朴な疑問から出発しなかったら、この思想の妙味には届かないですよ。そして、その妙味に届かないのだったら、批判なんかできるはずない。 加藤さんのこの本読んで、「自己啓発本とか、自己啓発思想って、奇天烈で面白いなあ!」と加藤さんが面白がっているところが想像できない。むしろ加藤さんは「自己啓発本って胡散臭いなあ」と思っていて、その胡散臭さを暴露してやろう、というのが本書の執筆意図と見た。そこがね、本書をつまらないものにしている一番大きな原因ではないかと私は思うのであります。愛がないよ、愛が。 というわけで、私はこの本から色々学ぶところはあったのですけれども、人におススメはしません。だから、「教授のおすすめ!」はなーしーよ。
March 22, 2016
コメント(0)
-
散骨ブーム、からのアグネス・ラム
イギリス人同僚のR先生のお母様が亡くなられたことで、にわかにイギリスでの葬儀のあるあるを知ったのですけれども、イギリスのお葬式ってのは、すごく時間が掛かるんですってね。 これが日本ですと、御当人が亡くなられてから、どうですかね、二、三日後くらいには告別式になるじゃないですか。色々事情が重なったとしても、四日目、五日目にはどうしたって荼毘に付されることになる。 ところがね、イギリスだと亡くなられてから告別式まで3週間とか、そういうのが普通なんですって。 第一、検死に時間が掛かるというのですが、おそらく、最近の日本と違ってご自宅で亡くなるということも多いのでしょうな。 で、R先生のお母様の場合も、亡くなられてから告別式まで3週間くらいあったのですが、故人の意志なのかファミリーの意志なのか、お墓は作らず火葬して散骨されたとのこと。 ふーむ。散骨か。 で、そんな話を伺っているうちに、このブログにもしばしば登場する「アニキ」ことK教授も、「僕も散骨するもんねー」と。 え? そんなこと、もう決めたんですか? で、私が「それ、奥様もそれでいいとおっしゃっているのですか?」と尋ねると、「勿論。っていうか、妻も散骨するもんね」ですって。 ひゃー、そうなの? うーん、そうなのか・・・。 いや、実は私もね、散骨を考えなくもない。だって、お墓なんか入ったって面白くないじゃん? それより、好きな山、好きな海にでも散骨してもらって、たまにその山とか海にドライブするようなことがあったら思い出して、みたいな風にしておいた方がいいかなと。 樹木葬も含め、そういう風に考える人が、今、日本で着実に増えているようですけれども、そうなると「祖先の墓を守る」的な発想ってのが無くなって、従来のお墓は廃れる一方、またそれを管理するお寺さんも収入が無くなって廃業に追い込まれ、その反対に海や川や山は人骨の灰だらけ、ってなことになるのかしら。 山に行って、「ああ、いい空気だ」とか言って深呼吸したら、隣で撒いていた誰かさんの灰を思いっきり吸いこんじゃった、とか、そういうことになったりして。 さてさて、「昭和の男」シリーズも、そろそろ1970年代半ば、昭和で言えば50年代に突入しようかという頃ですけど、この頃に何があったか。 その頃、私は小学生から中学生に上がる頃ですけど、そうなりますと、少しは色気づいてくると言いますか、ちょっと性差を意識し始め、以前ほど気楽にクラスの女子と戯れられなくなってくる頃ですなあ。ちょっと女の子と長くしゃべっていたりすると、後で「釈迦楽君、○○さんのこと好きなんでしょ」とか冷やかされたりして、面倒臭いような、ちょっと嬉しいような。 と、同時に、そこには触れてはいけない何かがあるような、そんなことにも気が付き始める頃でございます。思春期ですなあ。 で、そんな折も折、ドドーンと登場してきたものがある。『エマニエル夫人』でございます。1974年ですか。 こちら小学生ですから、この映画を観たとか、そういうことは当然ないわけですけれども、世間の大人たちが何やら騒いでいることには気づいた。テーマ音楽も、フランス語で、なにやら淫靡な感じがしてね。 またこの頃、くだらないクイズが小学生の間で流行っていたこともあって、『エマニエル夫人』もクイズになった。「エマニエル夫人は、将来、太るでしょうか、痩せるでしょうか」っていうの。答えは「太る」。なぜなら、「今にL〈サイズ)」だから。しょーもないよね。でも、そういうクイズが流行った位だから、小学生の間でもこの映画のことが何となく意識されていたことの証拠にはなるでしょう。 1974年と言いますと、例えば小野田寛郎少尉がフィリピンから戻ってきた、とか、春闘で空前の国鉄ストがあったとか、ニクソン大統領がウォーターゲート事件で失脚とか、佐藤栄作元首相がノーベル平和賞とか、田中角栄首相辞任とか、割とあれこれあった年なんですけど、そろそろ「政治の季節」が収束し始めた感じもあって、そういう大きな物語ではなく、もっと身近な話題に目が行くような、平和な時代が来ていたのでしょうな。 そもそも『エマニエル夫人』って、外交官の妻が平凡な毎日に飽き飽きして、それでちょっとした性的冒険を試みるって話でしょ。日本も、結局、そういう状態だったんじゃないでしょうかね。政治の季節も終って、退屈だから、ちょっとエッチなことに興味が出てきました、みたいな。 だけど、小学生から中学生になりかけの我々の世代にとって、そういう「アンニュイ」な性なんて分かるはずない。やっぱり、もっと溌溂とした、健康的なものの方がいいわけですよ。 で、そこへやってきたのがアグネス・ラムです。1975年。最初はエメロン(懐かしいね、この名前! 昔はシャンプーといえばエメロンだったのに)のCMか何かで日本のお茶の間に登場してきたのではなかったでしたっけ。 アグネス・ラムさんはね、シルヴィア・クリステルとは対照的というか、健康的に日焼けして、愛嬌があって、グラマラスなんだけど淫靡さのかけらもない。ハワイのお日様を日本にそのまま連れてきたような感じでしたね。でまた、外国人なんだけど、顔立ちにどことなく東洋的なところもあって、それが一層、日本人(男性)には親しみが持てたというか。 で、アグネス・ラムが日本に来た頃に、小学館が『GORO』という雑誌を創刊(1974年)したでしょ。篠山紀信さんがグラビアを担当して。だから、アグネス・ラムなんて、恰好の被写体ですよ。もちろん、その前からある『平凡パンチ』とかにも載ったでしょうが。 とにかく、アグネス・ラムの登場は、グラビア界の黒船みたいな感じだったのではないかと。 もっとも我々の世代からすると、そんなアグネス・ラムさんは「きれいなお姉さん」って感じで、その健康的な肢体にうっとりとしたまなざしを向けただけですけどね。 ところで、アグネス・ラム画像を懐かしく見ながら思うのですけれども、この頃の女性美の一つの基準は、「こんがりと健康的に焼けた肌」だったのではないかと。特に、夏場はね。だから、夏になると、肌をきれいに焼くためのオイルや、肌を小麦色に見せるためのファンデーション(?)のCMがガンガン流れていた。 この系統でよく思い出すのは、ちょっと先の話になっちゃうけど1979年の資生堂のCM、「燃えろいい女」ね。世良正則がテーマソングを歌った奴。あと、「ナツコの夏」ってのもあったなあ。 まあ、これは私の個人的な嗜好かも知れませんが、70年代後半から80年代初頭にかけての化粧品のCMって、私は好きなんですよね。この頃って、四季それぞれに化粧品のテーマが決まっていたじゃないですか。春は口紅のCM、夏はサンオイルなどのCM、秋はアイシャドウのCM、冬は・・・ってな具合に、四季に応じて宣伝するものが決まっていた。 その中で、特に春と夏が印象深いのですが、例えば76年、カネボウの「銀座レッド」のCM、覚えています? デイヴという歌手が歌ったフレンチ・ポップス「銀座レッド・ウィウィ」ね。デイヴのこの曲もそうですけど、この頃って、たとえばミシェル・ポルナレフとか、フランスの歌手の歌が結構日本でも流行っていましたよね。 それから、77年春、資生堂の「マイ・ピュア・レディ」(尾崎亜美)。77年夏の資生堂の「サクセス」。78年春の資生堂の「春の予感」(南沙織)。78年夏、資生堂の「時間よ止まれ」(矢沢栄吉)。78年秋、資生堂の「君の瞳は百万ボルト」(堀内孝雄)。79年春、カネボウの「君は薔薇より美しい」(布施明)。79年春、ポーラの「私のハートはストップモーション」。79年秋カネボウの「セクシャル・ヴァイオレットNo.1」(桑名正博)等々。ガンガン思い出せる。 この頃って、こういう化粧品のCMソングで、季節の移り変わりを知るってこと、ありましたよね。 で、傑作揃いの化粧品のCMソングの中で、どれか(誰か)一つを選べと言われたら、私なら尾崎亜美を取る。「マイ・ピュア・レディ」、そして南沙織に曲提供した「春の予感」。この二曲は、70年代後半の春を思い出す上で、絶対に欠かせないものでありまして、それらを作った尾崎亜美さんのことは、私は重視するんですなあ。 今日は東京で桜の開花宣言もあったようですが、私の思春期の始まりの頃、春に流れていた尾崎亜美の曲は、今でも私の心に春を呼ぶ曲でもあるのでございます。
March 21, 2016
コメント(0)
-
先輩のブログ本、そして私の新宿
日本アメリカ文学会での先輩で私の兄事する本城誠二先生がこの度『Crossing Borders ジャズ/ノワール/アメリカ文化』(英宝社)という本を上梓されました。 この本、本城先生が2008年から続けられている「越境と郷愁」というブログから生れた本でありまして、ブログに綴られた様々なトピックの中から特に先生のお好きな映画やジャズ、そしてもちろんアメリカやイギリスの小説、とりわけミステリーなどについて書かれたものを一冊にまとめられたもの。先生のお人柄のよく表れた穏やかな文体で綴られたエッセイ集ですが、実は相当年季の入った映画・ジャズ・文学の見巧者ならではの鋭い観察と、アメリカ文化の様々な側面を横断し、結びつける巧みな手腕が発揮された、素人から通まで等しく唸らせるアメリカ文化論となっております。 私も長年ブログをやってきて、ブログを通じて何が出来るのか、自分はブログを書くことで何をやろうとしているのか、ということを意識してきましたし、実際、ブログに書いたことを本にしたこともありますが、この度、本城先生のこの本を読ませていただいて、先生が私とほぼ同じ感覚でブログを続けられていることを確信し、非常に面白かった。アマゾンでももう間もなく販売が始まるようですので、興味のある方は是非。教授のおすすめ!です。 映画・ジャズ・アメリカ文学と、テーマ的にも私の好きなものばかり、そしてブログから生み出された本という点も興味津々。本城先生に負けず、私も頑張って、本にまとめてもおかしくないような内容のあるブログを作っていかないといけませんな。ますます、やる気が出て参りました。 さてさて、「昭和の男」シリーズのつづきですが、今日は昭和40年代の新宿のお話。 と言ってもね、「二丁目の青線地帯が・・・」とか、「ションベン横丁が・・・」とか、「西口地下広場でフォークゲリラが・・・」とか、そういうお話じゃないの。そういうのが出来るのは、団塊の世代以上なので、昭和40年代初頭にようやく幼稚園に行き始めた子どもの目には、そういうものは入ってこないのよ。 1960年代半ば過ぎ、幼かった私の目に映った新宿というのは、小田急百貨店や京王百貨店がまだ真新しく、西口地下広場が完成したばかりの頃。西口と言えば、京王百貨店があるばかりで、その先にはまだ何もなかった。当然、高層ビルなんてのもなくて、京王プラザホテルの完成がようやく1971年、それから住友三角ビルが出来るのが1974年。そのあたりから徐々に、という感じでしたね。 一方、東口側には既に色々ありましたが、我が家に関係するところと言えば、東口地下通路沿いの施設、例えば紀伊国屋書店であったり、中村屋であったり、三越であったり、伊勢丹であったりといったところ。伊勢丹より先は行ったことがなかった。要するに、小田急百貨店や京王百貨店や三越や伊勢丹など、大型デパートが沢山ある街、というのが新宿という町に対する私の最初の印象でございます。 あ、そう言えば、新宿には丸井もあったけれど、当時丸井は月賦で物を買わせるという、クレジット社会の現在では当たり前だけど、当時としては斬新な商売をしていて、そこが母の気に入らないところだった。「他人にお金を借りてまで物を買うというのは浅ましい」というのが母のモットーでしたから、丸井なんて、てんで軽蔑して行ったこともなかった。それに昔の人は、物を買うにも、名前を重視しましたからね。三越とか、高島屋とか、そういう格式あるのがいいわけですよ。 ま、とにかく子供の頃の私にとって新宿はデパートの街。それも、普通の買い物ならば町田で済むので、新宿のデパートに行くとなると、ちょっとスペシャルな感じが伴う。 じゃ、スペシャルというのは何かと言いますと、例えばクリスマスの買い物とかね。 今、街が一番盛り上がるのは、ひょっとしてハロウィンの渋谷、だったりするのかも知れませんが、昭和40年代って言ったら、やっぱりクリスマスだったんじゃないかと。 今、クリスマスって、どうなんだろ。盛り上がっているのかなあ。一応、クリスマス・セールとかはあるのだろうけれども、街全体がハイになっている感じはありませんよね。 だけど、私が子供の頃のクリスマスなんてのは、もう、誰も彼もみんな浮かれてましたよ。サラリーマンのお父さんが、会社のクリスマス宴会かなんかで酔っ払って、頭には円錐形の帽子をかぶって、手には寿司折かなんかを持って、千鳥足で歩いているという、漫画みたいな光景が実際にありましたからね。で、大きな街の繁華街はもとより、小さな街の商店街だって、ジングルベルの曲がけたたましく鳴り響いていて。 高度経済成長期だったし、各家庭の懐具合も全般的に良かったんじゃないですかね。だから子どもにとっては、クリスマスってのは誕生日と並んで、欲しかったものがプレゼントされる一年でも最高の一日。 で、釈迦楽家では当時、この日をどんな風に過ごしたかと申しますと、12月24日に家族揃って新宿のデパートに買い物に行くわけ。 で、家族のメンバーそれぞれにプレゼントを買うのだけど、例えば父にプレゼントを買う時は、父に何処かで待っていてもらって、母と姉と私で父へのプレゼントを買いに行く。 万事この調子で、母にプレゼントを買う時は、母に何処かで待っていてもらって、父と姉と私で母へのプレゼントを買う。姉へのプレゼントを買う時は、父と姉がどこかで待っていて、母と私で買いに行く。私へのプレゼントを買う時は、母と私がどこかで待っていて、父と姉で買いに行く。 そうして家族分のプレゼントを買って帰るわけ。 そうすると、どうなるかと申しますとね、もう楽しくて仕方がないのよ。父に何を買ってあげたか、私は知っているけど、父は知らない。母に何を買ってあげたか、私は知っているけど、母は知らない。姉に何を買ってあげたか、私は知っているけど、姉は知らない。その状況が可笑しくて仕方がないわけ。ついうっかり、手袋を買ったんだよ、とか、ブローチを買ったんだよ、とか、セーターを買ったんだよ、とかバラしたくなってしまうのだけど、それをじっと我慢するのがめちゃくちゃ楽しい。 それでまた、自分に何を買ってもらったかは自分には分らないわけで、これは早く知りたくて仕方がない。 それでクリスマスの買い物を済ませた我が家一同は小田急線に乗って帰宅するんですけど、姉と私はクスクス笑ってばかりだし、父も母も楽しそうで。 他愛ないクリスマスの一コマですけど、今から考えると、我が家のメンバー全員が一番屈託なく人生を楽しんでいたのは、この頃だったのかもしれません。 とにかく、こういう家庭の幸せの背景にあったのが、新宿のデパート群だった。だからね、あれから幾星霜が過ぎましたけれども、私は新宿という町には、今でも愛着があるのでございます。 だけど、その一方、例えば東口地下通路なんて、当時はもっと暗くて、あまりぞっとしないところでもありました。何せ通路の脇には、今で言うホームレス、当時で言えば乞食の皆さんがずらっと坐っていたり寝転んでいたりしましたからね。あと、クリスマスとか年末の頃になると、傷痍軍人が坐って募金を訴えていたり、救世軍が「社会鍋」と称してやはり募金を促していたり、あるいはまた懐かしい赤尾敏が辻説法をしていたりする。 当然、そういうのを見れば、子ども心に「あれは何をやっているのだろう」と思うし、親に尋ねたりもしましたが、その返答の何となく曖昧なところからして、何か尋ねてはいけない種類のことなのかなと思ったりして、世の中には口籠るべきものがあるのだ、ということを最初に学んだのも新宿だったかも知れません。 私にとっての昭和40年代の新宿というのは、そういう光と影の交錯する、魅惑の異空間だったのであります。
March 20, 2016
コメント(0)
-
ナイト・ミュージアムを楽しむ
現在、愛知県美術館で開催中の『ピカソ、天才の秘密展』、前から見たい見たいと思いつつ、ピカソだとどうせ混むのだろうなあ、人の頭越しに見てもあんまりおもしろくないなあと、ぐずぐずしている内に、会期末目前となってしまったという。 そこで意を決して見に行くことにしたのですが、金曜の夜は美術館が8時までオープンしていると聞き、ならば7時頃に入ったら空いているのではないかと、昨夜、行ってみました。初のナイト・ミュージアム体験でございます。 すると! ひゃー、空いているじゃん! ガラガラとは言わないまでも、いい感じで空いている。なるほど~、人気の展覧会でも金曜の夜に見れば、ラクラク見られるわけね~! いや~、いいことを学びました。 というわけで、じっくりピカソ展を見て廻ったのですが・・・。 今回の展覧会はピカソの若い頃の絵、特に「青の時代」が展示の中心になっているというようなことだと思って見始めたのですけれども、実はそうでもなかったというね。 もちろん、ピカソが14~15歳くらいの時の習作から展示が始まって、青の時代の展示があるのですが、割とすぐに「ばら色の時代」の絵の展示になり、「アレ? 青の時代はもう終り?」と思っているうちに、今度は「キュビスム時代」の絵の展示になって、「は? 結局、キュビスム時代の展示もあるの?」と思っているうちに、出口に出る、という。え? 何? もう終り? って感じ。 そんな調子ですから、どの時代もみんな中途半端に終わってしまうんですよね。どこか食い足りないというのか。ピカソ展なんてのは何年かに一回どこかの美術館がやるのだから、ここは特色を出して、初期から青の時代までに限定して、その分、その時代の絵をたっぷり見せてくれればいいのに。 ま、もちろん、そうは言ってもピカソはピカソですから、初期の『宿屋の前のスペインの男女』とか1901年の『母子像』、『道化役者と子ども』、『魚、瓶、コンポート皿(小さなキッチン)』等々、感銘を受ける絵も何点かありました。だけど、やっぱり数が少ないですな。ピカソ展は、やっぱり物量でも圧倒してほしいのに。 それから、一つ意外だったのは、ピカソの少年時代の習作を見て、あまり感銘を受けなかったこと。割と平凡じゃない? もちろん上手いのですけど、「あら、お上手」っていう感じのレベル。ピカソなんだから、もっとぶっ飛んで尋常じゃない才能を感じさせるかと思いきや、それほどではない。ピカソが天才になるのは、やっぱり青の時代が始まってからじゃないですかね。つまり、自分のスタイルを見つけてからのピカソが凄いということですな。 ま、そんなことを思いつつ、でも、とにかく、ピカソ展をこれだけゆったり見られたことに感動。金曜の夜に美術館を楽しむってのは、すごくいい思い付きでした。 で、夜に美術館に行くという裏ワザを楽しんだ後、家内と私が向かったのは、栄プリンセス大通り近くにある「勝牛」というお店。 京都のお店の名古屋支店なんですけど、牛肉のカツを色々なタレで味わわせてくれるお店で、ソース、塩、わさび醤油、温泉卵、カレー・ダレが付いてくる。で、どれで食べてもおいしいのですけど、わさび醤油で食べる牛カツの旨いこと! しかも最後は麦飯に温泉卵をかけたり、カレー・ダレをかけたりしてかっこんだりしても楽しめるというね。それで1380円とか、非常にリーズナブルな値段なんだからもう言うことなし。「勝牛」、教授の熱烈おすすめ!です。栄で食べることがある人なら是非! というわけで、夜のピカソ展、そして「勝牛」の牛カツを満喫した昨夜のワタクシだったのであります。
March 19, 2016
コメント(0)
-
志摩旅行
ひゃーー、志摩ドライブ旅行から戻って参りました~! もっともたった1泊の旅行だったのですけど、帰って来た途端、大学の仕事が山積みでなかなかブログを更新するヒマもなく、ちょっと遅いご報告となった次第。 で、旅行初日はまず伊勢湾岸道をかっ飛ばして一足飛びに伊勢神宮へ。まあ、既に何度も訪れている場所ではありますが、こちらの方に来るというのにここをスルーするというのも日本一の神社に対して申し訳ないかなと。そして最近、足が痛くて歩くのがつらくなってきたという父のために、足が良くなるようお祈りし、健康のお守りをゲット。 で、昼食はおかげ横丁・おはらい横丁で。 いつもですと、「すし久」で「手こね寿司」を食べるところなのですが、今回はここで変化球を入れまして、おはらい横丁にある「豚捨」さんで、牛丼をいただくことに。と、これが実に正解でありまして、ちょっと甘目のタレがお腹に優しい、おいしい牛丼でした。1000円というコスパもいいし、店の雰囲気も良かった。1階のコロッケ売り場は観光客でごった返していますけど、2階のレストラン部は意外にひっそりと空いていて、居心地良し。このお店、教授のおすすめ!です。 そしてお腹も一杯になった我らは一路、志摩へ向かい、目指すは西山慕情ヶ丘。英虞湾を見下ろす夕日がきれいということだったので。 ところが。 カーナビに途中で案内を放棄され、道路上に道案内もないもので、グルグル回った挙句辿りつけず・・・。仕方なく、行き先を「ともやま展望台」に変えることになる始末。いやはや。でも、ともやま展望台からの眺めだって、なかなかのものでございました。 で、今日のところは旅程終了で、この日の宿となります「プロヴァンス」ホテルへ。 このホテル、賢島のほんのちょっと手前にある割とこじんまりしたホテルで、ホテルの周辺は別になんの洒落たところもなく、ちょっと失敗だったかなと危惧したのですけれども、これが実は大当たりだったのよ。 「美食の湯泊り」をキャッチフレーズにするだけあって、まず食事がいい。量的に圧倒するのではなく、ごく常識的な分量の、しかし一品一品おいしい料理を、気取らずに提供してくれるところがとてもいい。翌朝の朝食も、すごくおいしかったですしね。 それで、食後のデザートは、場所を変えて、6階にあるカフェ・バーみたいなところでいただくようになっているのですけど、そのデザート自体が美味しかったということに加え、そこに天体望遠鏡が据えてあって、専門の係の人がいる。で、その人に誘われて、夜空を見たら、まあ、星がきれいに見えて。で、望遠鏡も見せてもらいましたが、木星のシマシマや、月のクレーターもクッキリと。ちょっと面白い体験でした。 で、ここはちゃんと温泉が出るのですけど、夜10時過ぎに行ったら誰もいなくて、大浴場独り占め。いい気分。 それで、チェックアウト時にプロヴァンス産のワインをボトルでプレゼントしてくれて(たまたまそういう宿泊プランだったらしい)、それもなんだか得した気分でしたけれど、とにかくホテルの方のサービスが、おしつけがましくなく、かつ、親切気があって、すごく良かった。この辺に旅行にいらっしゃる予定があるならば、プロヴァンス、おすすめですよ! ってなわけで、快適な一夜を過ごした我らが翌日向かったのは、地中海村。宿泊施設もあるので、最初ここに泊ろうかと思っていたのですけど、予約が取れなかったんですよね。 ここ、スペインかポルトガルあたりの港町を再現したようなリゾート施設なんですけど、まあ、別にアトラクションがあるわけでもなし、行ってみたら、それほどのこともなかったかな・・・。その割に、お土産はしこたま買い込んじゃいましたが。 で、その後、安乗の灯台へ。映画『喜びも悲しみも幾歳月』にも登場する四角い灯台ですよ。私たちは意外に灯台フェチで、灯台が近くにあると聞けば、とりあえず行ってみたくなるもので。前に大王崎の灯台は見たので、今回はこちら。灯台からの眺めはやっぱり良かったです。観光客は他に誰も居ませんでしたけどね。 で、次は浦村へ。昨年、浦村の牡蠣小屋で食べた牡蠣の味が忘れられず、今回もここで牡蠣を食べるのがメインの目的ですから。 で、今年も「英治丸」という焼き牡蠣専門のお店へ。昨年学習しているので、今回は前もってコンビニで買ったオムスビ持参ですよ。で、このオムスビを食べながら、1個100円の丸々と太った超大ぶりな焼き牡蠣を次々とお腹に納めます。うまーい!! こんな豪華な牡蠣を遠慮なく食べられるのって、ちょっと他ではないですよね。 で、今年も念願の牡蠣で満腹した我らは、最後、鳥羽の水族館に向います。 多分、スタート当時はすごくモダンな新タイプの水族館だったであろうここ、今ではさすがにちょっと古い感じがしなくもないですけど、それでも魚だけでなく、セイウチやイルカやアシカなどの海獣もいるし、結構楽しめました。それに、ここには「スナドリネコ」がいるんですよね。山猫フェチのワタクシとしては、スナドリネコが見られるだけでも、来て良かった。 で、ここを観終わった段階で、今回の旅程の大半が終了。後は伊勢の方に戻りながら「二軒茶屋」で二軒茶屋餅をゲット(これめちゃくちゃ旨い)し、伊勢外宮周辺で簡単に夕食を済ませて帰路についたのであります。 昨年・今年と二年連続でこの時期、伊勢・志摩を旅しましたが、大体、見るべきものは見たかな~って感じ。でも、浦村の牡蠣は美味しいし、今年行ったプロヴァンスはいい宿だったし、どうしようかな、来年ももう一回くらい行こうかな。 とにかく、1月、2月、3月と多忙な日々を過ごして私には、ちょっといい息抜きになりました。
March 18, 2016
コメント(4)
-
クルマ・デザイン論
クルマのデザインを論じた本を書いちゃった。 ま、これまで何十年もの間、クルマの雑誌に費やしてきた膨大なお金、そしてそれを読んできた膨大な時間を考えれば、私にはクルマのデザインを論じる資格が十分にあると思うのですが。 だけど、本は書きあがっても、出版してくれるところがないんだよね! これからそれを探すので右往左往するのかと思うとウンザリだけど、書いちゃったものは仕方がない。のんびりやりますよ。 さて、私は明日から春休みを楽しむべく、ちょっと伊勢・志摩の方にドライブ旅行をして参ります。浦村で牡蠣を食べるんだ。去年、初めて行ってあまりの美味しさに感動したもので、今年もう一回行ってやろうと。 ということで、また帰ってから旅のご報告など。それでは、その時までご機嫌よう!
March 14, 2016
コメント(0)
-
「町田」今昔
町田。小田急線ユーザーにとって、新宿に次ぐ都市にして、東京でも23区、八王子市に次ぐ人口を誇る大ベッドタウン。 群馬の絹が八王子で織物となり、それを鎌倉に運ぶ道が鎌倉街道であるわけですが、その関東シルクロードの道筋に栄えた宿場町が元。それが1960年代あたりから山崎団地・木曽団地といった大団地群を擁する東京のベッドタウンとなり、今日に至る、みたいな感じの町ですな。我が東林間からすると、電車で二駅しか離れていないのですから、東林間で事足りないけれども新宿まで行くほどではないといった買い物は、とりあえず町田で済ますというのが通例でありました。 だけどね、あそこはもともと「町田」ではなかったんだよね。覚えています? あそこは小田急線と横浜線が交差するところなのですが、横浜線の駅が「原町田」で、これに対して小田急線の方の駅は「新原町田」でした。だから、私が子供の時は「新原町田」だったんですよ、あの町は。で、私がまだ小さすぎて「しんはらまちだ」と言えず、「ちんからまちだ」と言っていたというのが、我が家で私をからかう時によく出るエピソードなのでございます。 だけど、どういうわけかその区分が無くなり、横浜線も小田急線もいつのまにか「町田」になっちゃった。 ま、言語学的には面白い現象で、これに似た現象としては英語の「napron」という言葉がある。今で言う「エプロン」ですよ。だけど、英語には冠詞が付きますから「a napron」ですな。それがいつの間にか、「an apron」と分けるのではないかと誤解され、「n」の字が単語の方ではなく、冠詞の方に移っちゃった。こういうのを言語学的には「異分析」というのですが、それで今では「apron」の方が一般になってしまったわけ。これと同じで、「新・原町田」と分けるべきところ、「新原・町田」と異分析され、「新原」がとれて「町田」が単語として残ったと。 どうでもいいか。 で、新原町田時代の町田は、今と比べるとずっと素朴な町でありまして、今の駅ビル、すなわち小田急百貨店なんかなくて、駅の脇に平屋だったか、あるいは二階建てくらいの小田急ストアがあった。屋上にちょっとした遊園地があったんじゃないかな。その小田急ストアの向いに不二家があって、ペコちゃんが立ってたのを覚えております。 この当時、町田にあったデパートは「さいか屋」だけ。まあ、南口の東っ側に「長崎屋」ってのもありましたけれども、大したことはなかった。だから、我が家はちょっとした買い物にはなにかとさいか屋に行ったんですよ。あ、あと、国鉄の原町田の駅前にダイエーがあったか。でも、当時ダイエーのイメージって「安物売り」というものだったので、お金はないけど心の貴族だった我が家はあまり行かなかった。 この当時の町田って、ザ・昭和って感じの町で、バラック建ての小店舗とか、鰻の寝床状の闇市的なマーケットみたいな「都南商店街」なんてのがありまして。その当時の雰囲気は今でも「仲見世商店街」に残っております。さいか屋の前に、小さな緑色の噴水のある自転車屋とかあったなあ。 あと駅前には、本屋の久美堂があり、これは今も同じ場所にありますね。それから同じ南口には、楽器とレコード屋さんがあって、ここでわが家はレコードを買ったものです。そう「鈴木楽器店」か。あと、南口といえば忘れられないのはジーンズの「マルカワ」。敷地は超狭いのだけど、6階建てだったか7階建てだったか、全フロアがジーンズ売り場でね。これも今もあるんじゃないかな。 あと大きな文房具屋さんの「なかじま」というのがあって、文房具なら何でも揃うという。ここにも随分お世話になりました。 それからさいか屋から道路を隔てた西側に宝永堂という宝飾店があって、これも今もあるんじゃないかな。 だけど南口も境川を越えた西側となると、これまたちょっとヤバい感じの場所がありまして、千寿閣とか町田ボウリングセンターとか家具の大正堂まではまだいいとして、その先となるとラブホテルがあったり、もっと露骨な売春街があったり、怖くて子どもが足を踏み入れることのできない場所でしたね。今は、JRの町田駅に隣接してヨドバシカメラができましたが、私なぞは昔のイメージが焼き付いているので、ヨドバシ以外には今でもこちら方面に足を向けたくないという。 で、駅の北側、特に今西友がある辺りは何もなかった。北口では、新宿よりに「ミドリ屋」というデパートが一軒あるきりでしたけど、我が家の電気製品はすべてミドリ屋で買ったという記憶がある。特にカラーテレビを買った時のことはよく覚えておりますよ。嬉しかったものね。ちなみにミドリ屋はかなり前に撤退して、当時の建物は今雑居ビルになっていますね。一時期、古本屋の高原書店がこの雑居ビル内にあった時期もありましたが。 そんなもんよ。 それが1971年でしたか。南口に隣接したところに大丸百貨店が出来た。また北口に西友が出来たのも同じ年だったかな? この頃から町田の大発展が始まるわけ。 大丸が出来た時はすごかったですよ。オープンの日に電車で町田駅を通過したのですが、店を取り巻く十重二十重の人の列が電車からも見えた。 そして1976年、小田急線の駅舎の建て替えに伴って小田急百貨店町田店が出来た。これで、それまで町田のデパートとして長年栄えてきたさいか屋がたまらず閉店して「ジョルナ」という専門店モールに業務転換してしまった。長年、さいか屋に親しんできた者としては寂しい限りでございました。そして1980年に東急百貨店がさいか屋の隣に出店。いつの間にやら、町田はデパートの町と化したのでございます。今では東急百貨店も二棟に増え、JR駅にも駅ビルとしてルミネや丸井があり、今は無くなりましたけど東急ハンズがあった時代もありましたしね。 だけど、その割にまだ旧態依然とした個人商店が残っていたりして、大店舗と小店舗が混在しているという点では、ちょっと吉祥寺に似たところもあり、また昼と夜の顔がまったく異なるという点では、あまり例のない町でもあるのかな。夜は結構、こわい場所ですからね。 で、そういう町田の進化をずっと見守ってきたわけですけれども、私から見てやっぱり懐かしいのは、せいぜい大丸が出来た頃までの町田かなあ。日曜日に家族で出かけて、さいか屋の地下のお好み食堂でミートソースとソフトクリームを食べて、それで十分に幸せだった時代。 子どもの頃の私は、今と違って、人ごみとかもあまり嫌いではなかったし、むしろ大勢人がいて楽しいな、くらいの心持だったんですよね。だから、町田に行って、デパートに行って、人が沢山いて、それで楽しかった。 そういう意味から言いますと、私にとって町田よりももっとステキなところがあった。小田急線のターミナル、新宿でございます。 で、そんな新宿のお噂については、また次回のこころだ~!
March 13, 2016
コメント(2)
-
昭和40年代の食生活
昭和40年代、すなわち私が小学生の時代に何を食べていたかを思い出しております。 まず自宅での朝・昼・晩の食事のことを考えてみると、もちろんそれほど洒落たものは食べておりませんでしたが、かといって、現代の食生活といかほど違ったかと考えてみると、それほどの違いはないかなと。 ただ、小学校3年生まではそれこそ畳の部屋で、一家4人ちゃぶ台を囲んで、という、典型的な昭和の風景が我が家でも見られて、そこが一番の違いかなと。 で、今もよく思い出すのは、この平屋の借家に住んでいた頃、母ご愛用の料理本がありまして。時々、この料理本のレシピでなにかご馳走を作ってくれたこと。 例えばプリンとかね。 だけど、その料理本のレシピによるプリンは、今我々が食べているようなカスタード・プリンではなくて、なんか、食パンをベースにしたもので、蒸かしたフレンチトーストのようなものだった。多分、当時の日本では各家庭にオーブンなんかなかっただろうし、フライパンと蒸し器と、そんなものだけで西洋のお菓子を作るにはどうしたらいいか、知恵を絞って方法を案出していたんでしょうな。 そういう、ちょっとこう涙ぐましい文化があったのよ、昭和には。 でも、今になってみると、そういう時代のことが懐かしくて、古本屋さんとかでこの母愛用の料理本が売りに出てないかな、なんて探してみたりするんですけど、そういうものって案外残ってないんだよね。古本好きには男が多いから、料理本というジャンルまで目が届かず、消失するに任せてしまったのではないかと。 ま、それはともかく、1973年、私が小学校4年生の時にマンションに引っ越してからは、わが家も大分、文明化し、ダイニング・ルームでテーブルに椅子という生活になり、オーブンもあったし、オーブントースターもあったので、食生活も大分モダンになって、それこそ今とあまり変わらない感じになってきた。 それに付けて言えば、マンション時代に入ってからは、冷蔵庫が二段式というか、冷蔵室と冷凍室が別になりましたから、それに伴ってこの頃から「冷凍食品」がわが家に導入され始めたのではなかったかと。わが家に限らず、昭和40年代後半から末頃にかけて、日本中でそんな感じになっていたのではないかと思いますねえ。 いや、冷凍食品のみならず、インスタント食品も普通のものになったかなあ。日曜日の昼とか、袋もののインスタントラーメンとか、インスタント焼きそばとかで済ませてしまうことも多かったし。ちなみに明星ラーメンが1962年発売でしょ。日清のインスタント焼きそばが1963年。私と同い年。1968年には「ゴマラー油入り」が売りの「出前一丁」発売。これ、よく食べたなあ。そしてカップヌードルが1971年発売となると、まさに私の世代はインスタント・ラーメンと一緒に育ったと言ってもいい。 あと、食に関するもう一つの側面として「外食」ということがあるわけですけれども、私が住んでいた当時の東林間には、そんなに洒落たレストランなんてものはなくて、外で食べると言えば、例えば蕎麦屋とか、中華そば屋とか、そんな感じ。具体的には、今も東林間に残る蕎麦屋の巴屋さんとか、ラーメンの三福とか、あるいは今は無き東珍軒とか、そんなところに行きましたね。あと、これらのお店から店屋物を取る、ということもよくありました。店屋物といえば、たまにお寿司も取ったかなあ。吾妻寿司。あと駅前に鰻屋さんもあって、たまに行ったけれど、ここは数年前に潰れたようですね。 で、それよりももう少し洒落た・・・というか、洋食が食べたい時などによく行ったのは、町田ね。 で、町田で食べるという時、我が家がよく行ったのは、昔の「さいか屋」(今の「ジョルナ」ですな)の地下にあった「お好み食堂」。食券を買って空いているテーブルにつくと、係の人が券をもぎりに来るの。半券をもぎって行って、料理を出す時に残りの半券を持って行くシステム。ここではよく「スパゲティ・ミートソース」を食べたものですよ。そう、さいか屋には3階にも洋食レストランがあって、そこではスパゲティ・ポロネーズをよく食べました。後、グラタンも食べたか。 あと、これはもう少し後になってからですけど、やはりさいか屋の中にステーキの店の「ズム・ズム」というのが出来た時代があって、ここで「ランプ・ステーキ・セット」というのを食べるのは、地下のお好み食堂でミートソースを食べるよりぜいたくな気がして嬉しかったことを覚えております。 町田での外食でもう一軒思い出すのは、もっと駅に近いところ、たしか久美堂書店の近くの地下にあったのですが、「山のグリル」というお店ね。ここのハンバーグがめちゃくちゃ美味しかった。ソースに独特の風味がありましてね。で、店が地下にあるし、照明もわざと落としていて全体的に暗いのですけど、一つの壁に大きな、多分スイスあたりの山の写真のパネルがあって、そのパネルを内側から蛍光灯でバックライト的に照らしていて、これが暗めの店内ですごく目立つわけ。そうした店内のしつらえが、なんだかすごく高級感があったんですわ。ここで食べるのは、ちょっと奮発したご馳走、という感じがしたものです。 外食と言えば、ファースト・フードが登場したのも昭和40年代後半、すなわち1970年代初頭でしたねえ。マクドナルドが銀座1号店を出したのが1971年。 ちなみに私が最初に食べたハンバーガーは、マクドナルドではなくて、ロッテリアだった気がする。ロッテリアも創業は1972年で、マクドナルドにそれほど遅れを取ってないですからね。やはり町田のロッテリアで食べた。その時の印象では、ハンバーガーもさることながら、「シェーキ」ってのはとんでもなく旨いなと思ったことをよく覚えております。 それからね、ファースト・フードで言えば、ピザのこともよく覚えていて、私が最初にピザという食べ物を食べたのは小学校6年生の時、つまり1975年ですよ。これは神戸で食べた。この頃、神戸でピザを食べさせる店が出来たってのが評判になって、京都の親戚の家に行った時に、従姉のお姉さんが大騒ぎして、彼女に引っ張られるようにみんなで食べに行ったので、多分、日本でのピザ普及のごく初期のことだったと思います。そう、それでその時に初めて「タバスコ」の存在を知ったのよ。で、最初のピザ体験の時にタバスコをかけてしまったので、私のDNAの中でピザとタバスコはペアになっているわけ。その意味で、私のピザ概念はどうあがいたってアメリカ風なんですよね。ピザの本場イタリアにタバスコなんかないって言うじゃない? とにかく食文化全般を通じて一つ言えるのは、日本の食卓の西洋化とインスタント化、冷凍化、ファーストフード化は、すべて私の世代から始まったってことですよ。それが良いことか悪いことかは別として、その変化の波を目撃し、それに最初乗ったのは我々昭和後期の世代なわけ。 すごくない? すごいかどうかはアレですけど、変化に立ち会ったっていう意識、それはありますね。こんなに沢山、変化に立ち会った世代って、我々の世代以外にないと思うしね。 さて、食文化の話の中で、「町田」という都市に言及しているうちに、この面白い町のことについても書き残して置きたくなってきました。ので、次回は町田について語りましょうか。
March 12, 2016
コメント(0)
-
それ以外の音楽
先日、小学校時代の歌謡界の話を書きましたが、ああいうアイドル系・演歌系以外に、日本の歌謡曲界には何かこう、別な種類の音楽、いわば「それ以外の音楽」的な流れがあったような気がします。それは、ある面では人をおちょくったような、というか、反抗的なものを笑いに変化させたものであったりもするし、あるいは社会に背を向けて自分たちの世界だけを見つめたようなものもあるし、それらをもっと昇華させて新しい価値観を提示しようとしているものもある。具体的に言えば、ギャグ・ソングであったり、「(四畳半)フォーク」であったり、「ニュー・ミュージック」であったりっていうね。 例えば私がかなり幼かった頃のヒット曲に「帰って来たヨッパライ」がある。1967年末。これはまあ、純粋なギャグ・ソングですけれども、酔っ払いが一度死んで天国に行くものの、そこから追放されてまた現世に戻ってくるという人を食ったような歌。 それから「走れコータロー」、これもヒットしましたなあ、1970年ですか。もちろん、この曲にも取り立てて何か反抗的なメッセージがあるというわけではないのでしょうけれども、曲の合間に入る競馬の実況、あれは当時公営ギャンブル廃止を訴えていた美濃部都知事の口調を真似たものでしょ。さらにこの曲を歌っていたソルティー・ジュガーのメンバー山本厚太郎氏は、後に地球環境保護を訴えて参議院選挙にも打って出ている。やっぱり、どこか既成のものに対する政治的批判ってものはあったんでしょうな。 あとね、この種のギャグ・ソングとして記憶に焼き付いているのは、「老人と子供のポルカ」ね。これも1970年。左卜全とひまわりキティーズ。これは「やめてけれゲバゲバ」ですから、ゲバ棒を振るう学生運動への明確な批判。結構政治的であります。学生運動自体が社会体制への批判ですから、その批判に対する批判。おちゃらけた歌の中にも、なかなか深い事情がありそうです。 で、おそらくこのギャグ・ソングの延長線上に、例えばあのねのねの「赤とんぼ」とか、所ジョージの「正気の沙汰でないと」とか、そういうのが来るのでしょう。あるいはとんねるずの「ガラガラ蛇がやってくる」とか。 一方、四畳半フォークでは、何と言ってもかぐや姫の「神田川」でしょうなあ。1973年。同棲する若い男女が一緒に銭湯に行くという渋いシーンを歌ったものですが、なんで女より男の方が長風呂なんだっていうファンダメンタルな疑問はおくとして、高度経済成長の日本でガンガン仕事して出世してやろうという世界観からドロップアウトした若者たちの姿が見えて参ります。 また、あまり四畳半フォークという感じはしないですけれども、吉田拓郎の「結婚しようよ」が1972年。結婚する条件が「僕の髪が肩まで伸びて君と同じになったら」ですから、長髪の男の歌なのであって、やはり当時の日本のアングリー・ヤング・マンの歌なのでしょうが、怒っていてもロマンスはあるというね。前述したテレビドラマで言えば、『俺たちの旅』的な世界が、歌謡曲の世界にも存在していたと。 で、こういう系統の歌が色々あった中で、いよいよ井上陽水登場。『断絶』が1972年、『氷の世界』が1973年。フォークではないし、社会抗議でもないし、ギャグでもないという。だけど、もっとパーソナルな狂気みたいなものが表現されていて、衝撃的。「東へ西へ」の中で、「満員電車の中で床に倒れた老婆が笑う」とか歌われると、シュールでしたからね。「都会で自殺する若者が増えているけど、自分にとって問題なのは、雨なのに傘がないこと」とかね。 で、陽水恐るべしと思っていると、今度は荒井由美の『ひこうき雲』(1973年)が出てきて、これまた独自の哀しくも美しい世界が提示されて。荒井由美が出たことで、審美的かつ非論理的な若い女性の感性というものが初めて世に出たと言ってもいいのではないかと。 で、陽水と荒井由美が出たことで、日本で初めて「アルバム」というものが認識されたのではなかったでしょうかね。それ以前、ヒット曲というのは「シングル」を意味したわけですが、陽水とユーミンは「アルバム」が売れた。レコードの売り上げなんかでも、中三トリオや新御三家がいくらヒット曲を連発してみても、最終的に蓋を開けてみると、陽水かユーミンか、そのどちらかが歌手部門の長者番付一位を確保しているというね。 そしてユーミンあたりから「四畳半フォーク」とはベースとなる世界観が異なる「ニュー・ミュージック」がバーッと出てくる。山下達郎の「Ride on Time」とかね。もちろん、ニュー・ミュージックの中にも温度差はあって、より一般のポップス寄りのところにはハイ・ファイ・セットとか原田真二が居たり。だけど、思うに、ニュー・ミュージックの真ん中の人たちってのは、テレビではなくラジオをベースにしている人たちっていう感じがしますな。それは単にラジオで彼らの曲が掛かるという意味ではなく、ラジオを通じた人脈とか、あるいはアーティスト自身がDJをやるとか、そういう意味でラジオの中にこそ彼らのベースがあった。 だから当時、ラジオとかFMエアチェックにうつつを抜かしていた私の世代にとって、ニュー・ミュージックというのは、より一層身近だったわけだよね。 で、それが1970年代後半のこと。 これが1980年代に入るとね、またガラッと変わるわけ。まずジョン・レノンが殺されるでしょ。やっぱりそれは「何かの終り」を意味するわけで。それから日本ではYMOが出てくる。テクノ・サウンド登場。 だけど、その辺のことは先の話なので、また後日。
March 11, 2016
コメント(0)
-
名古屋古本屋ツアー
今日は同僚2人と共に、春休み記念「名古屋古本屋ツアー」という企画をやってきました。 今年度新しく同僚になった若いF先生は、珍しく古本好きで、同好の士を求めていた私にとっては渡りに船。いつか、名古屋の古本屋を一緒に歩いて回ろうと約束していたのですが、それがこの度、ようやく念願かなったという次第。 で、そんな計画を立てていた時に、アニキことK教授が「僕も行きたいけど、ほんとに古本屋だけ回るの? もっと面白いことしないの?」というので、「面白いことって何?」と尋ねると、「たとえば美味しいもの食べるとかさあ」と。 ということで、今回の古本ツアーにはK教授もまぜてあげて、お昼を3人で食べるということにしたわけ。 で、お昼前に名古屋は大須観音前に集合し、ピザで名高いチェザリでランチと相成ったのであります。 で、私は颯爽とマルゲリータを注文したのですけれども、アニキもFさんも「じゃ、パスタで」ですと。え゛ーーー、ピザ世界一と銘打っている店で何でパスタ食べるのよ! わけわかんねーな! ま、いいけど。 で、実際食べてみたところ、世界一の味だったかというと、まあ、どうかな。不味くはなかったけどね。普通よ、普通。 で、お腹が一杯になったところで、大須観音から上前津まで徒歩で移動。三松堂書店と海星堂書店〈南店)へ。私は三松堂で池田満寿夫の画集をゲット。そして海星堂でちょっと珍しいものを発見。 何を見つけたかと言いますと、山田隆著『プロレス入門』。これね、私が子供の時に愛読した本なのよ。引っ越した時に処分してしまったのですけど、後になって後悔して、もしどこかで見つけたら買い直そうかなと思っていた奴。 だ・け・ど! 2500円だったんだよね! うーん、ちょっと高いなあ! これが1500円だったら間違いなく買うんだけれど・・・。 で、散々迷った挙句、ひょっとしてネットでもっと安く買えるかも知れないと思い、今日のところは保留。 そして、次、今度は鶴舞の古書店をみるべく、鶴舞までさらに地下鉄一駅分徒歩で移動! で、鶴舞では三進堂書店、ネットワーク、山星書店に見参。今日は大学堂が休みだったのですが、今回初めてネットワークという古書店に行ってみて、ちょっと面白かった。いかにも古本屋さんのニューウェーヴっぽいお店でしたね。で、ここでも池田満寿夫関係2点ゲット。もっともこれは既に持っているもので、ただ100円とか150円で売っていたので、文化財保護した次第。どちらも初版だったしね。 てなわけで、ここで本日の古本屋ツアー終了! 今日はちょっと寒かったので、鶴舞駅前のドトールでコーヒーを飲んで、冷えた体を温めてから解散となりました。 私以外の二人は、F先生が1冊ゲットしたのみであまり収穫は無かったようですけれども、古本屋めぐりの楽しみは、釣の楽しみに似て、収穫があればよし、無ければ無しで、それはまたそれで楽しいというところがありますからね。 それに、別れ際、アニキがポツリと「今日は案外楽しかったな・・・」と言っていたので、これも良かった。最初、アニキは上前津まで付き合う、みたいなことを言っていたのですけれども、結局鶴舞まで我々に付き合ったわけですから、マジで結構楽しかったのでしょう。 というわけで、初の試み、名古屋古本屋ツアーは成功裏に終わったのでした。アニキも古本屋めぐりが楽しかったようだし、次はまた三人で「地下鉄東山線沿い古本屋ツアー」でも企画しようかな。 あ、それから帰宅してからネットで調べたのですけれども、例の『プロレス入門』は、子ども向けの本とはいえ、大人の鑑賞にも耐える名著とされているようで、ネット上では3000円程度で取引されている模様。なんだ、2500円というのは、むしろ良心的な値段だったのか・・・。やっぱり、古本は一期一会、ケチケチしないで、出会った時に奮発して買わないとダメですな。そんなこと、厭というほど知っているはずのワタクシなのにね。
March 10, 2016
コメント(0)
-
『ヘイトフル8』を観た
昨夜、レイトショーでタランティーノ監督の『ヘイトフル8』を観てきました。以下、ネタバレ注意! 時は南北戦争の数年後という頃。賞金稼ぎの男ジョン・ルースが、札付きの悪女ドメルグを捕まえ、レッドロックの町まで連行し、そこで絞首刑にしようと真冬のワイオミングを馬車で進んでいく途中、吹雪に遭遇して、「ミニーの洋品店」で吹雪をやり過ごすことに。 ところが途中で同じく賞金稼ぎの黒人マーキス・ウォーレンと、レッドロックの新しい保安官だと名乗るクリス・マニックスがこの馬車に同乗することになるわけ。で、一行はミニーの店に着く。 ところがミニーは母親に会いに出かけたとのことで、留守を見知らぬメキシコ人の男(ボブ)が店をあずかっていたばかりか、先客としてレッドロックの死刑執行人モブレー、母親とクリスマスを過ごすために故郷に帰ってきたカウボーイのゲージ、それに元南軍の将軍だというスミザーズなる老人がいた。 吹雪によってミニーの店に吹き寄せられたこの8人、どうも、誰もが皆腹に一物ありそうな連中ばかり。そもそも黒人のマーキスは、南北戦争では北軍で活躍し、南軍に参加したスミザーズ将軍や南軍兵士のクリスとはうまが合わなそうだし、さらにマーキスは北軍の白人も大分殺しているので、必ずしも北部人からもよく思われてはいなさそう。また札付きの悪、ドメルグには手下が沢山いるようで、ドメルグの配下の者たちが彼女の奪還を企んでいるという可能性もある。 さてさて、誰もが怪しく、互いに一触即発になりそうな8人が一つ屋根の下に集まっている状況下、果たしてルースは無事、ドメルグをレッドロックに連れていって賞金を稼げるのか? ってな話。 で、この映画に対する私の点数は・・・ 「83点」でーす! 合格。 まあ、私はタランティーノには甘いからね。でも、とにかく、いつものタランティーノ組の面々が揃い、いつも通りの血みどろ状況が、いつも通りユーモラスに進行して、一応、払ったお金の分だけは楽しめますから、いいんじゃないでしょうか。ワタクシ的には前作の『ジャンゴ』より笑えたな。もっとも、私がタランティーノの神髄と信じる『レザボア・ドッグズ』や『パルプ・フィクション』を越えるものではないとは言っておきましょうか。 さて、「昭和の男」シリーズの続き。 前回、ラジカセだの短波ラジオだののお話をいたしましたが、自分の好みである洋楽はさておき、一般の歌謡曲の世界はどうだったか。今日はその辺のことを思い出してみようかなと。 まず私が記憶する限り、「あ、これは芸能界が少し変わったな」と思わされたのが、天地真理の登場。それ以前の歌手と比べて圧倒的な素人感。だけど、その素人っぽさを逆に売りにするというその戦略が新しかった。でまた、若い男性のファンの応援がすごくて、今のアイドルの走りだったんじゃないでしょうか。 で、この辺りからガラッと芸能界が若返りまして、たとえば「花の中三トリオ」として桜田淳子、山口百恵、森昌子が出てくる。そして男性陣でも「新御三家」と称して西城秀樹、野口五郎、郷ひろみが登場。 でまた登場の順番は忘れましたけれど、南沙織が出てきて、麻丘めぐみが出てきて、アグネス・チャンが出てきて、城みちるがイルカに乗って登場して、あいざき進也が出てきて、キャンディーズが出てきて、伊藤咲子が出てきて、太田裕美が出てきて、浅田美代子が出てきて・・・みたいな感じ。とにかく、私よりも10才くらい年上の若い連中がバーッと出てきた。登場の時からそれほど若いという感じではなかったけれど、小柳ルミ子も年齢的にはこの辺と同世代かな? それが1970年代前半って感じ。そして、圧倒的な歌唱力で岩崎宏美が出てきて、そしてこれまた圧倒的なブームとなったピンク・レディーが出てくるのは1970年代後半、すなわち昭和50年代ということになります。 そう言う意味で、私が小学生の頃ってのは、年端も行かぬ若い子たちが芸能人としてしゃしゃり出てきた最初の時代であり、私はそれを確かに目撃した、という意識がある。 で、そういう若いのがうじゃうじゃ出てくる一方、もうちょい年上の、しかしまだ若手というのがいて、例えばにしきのあきらだったり、沢田研二だったりするわけですが、中でも沢田研二の人気はすごかった。中三トリオや御三家に伍して3カ月ごとに大ヒットを飛ばすというのを何年も続けていましたからね。 で、そんな感じで人材豊富でしたから、この頃の『平凡』とか『明星』みたいな芸能情報雑誌は、毎号、新御三家や中三トリオやジュリーあたりまでのアイドルの情報を盛り込んで170万部越えですよ。この頃のこの二誌の表紙の屈託のない・・・というか、突き抜けた明るさというのは、今眺めても目が眩みます。 しかし、その一方で、森進一と五木ひろしといった演歌系の中堅どころも健在で、特に森さんは『襟裳岬』とか『冬のリヴィエラ』的な、新感覚の演歌が素晴らしかった。 で、これに加えて、さらに年長の北島三郎さんとか橋幸夫さんとか青江三奈さんとか、そのさらに上の美空ひばりさんとか三橋美智也さんとか春日八郎さんあたりも元気でしたから、昭和40年代の大晦日の紅白歌合戦の豪華だったこと。ほんとに若い世代から、大人世代、そしておじいさん世代まで三世代の家族全員が楽しめる一大イベントでしたよ。 で、この頃の紅白は、ガチでその年の大ヒット曲につぐ大ヒット曲の応酬でしたからね。通して聴いていると、その一年のことが走馬灯のように思い浮ぶという。だから、本当に一年の総まとめとして大晦日に楽しむべきものだったわけですよ。 だからさ、こういうのを子どもの時に体験しちゃっているもので、我々の世代は今の時代の紅白に対しては忸怩たる思いがあるわけなんだよね! もう紅白なんか止めちゃえばいいのに、意味ないじゃん、って一番強く言っているのは、我々の世代じゃなかろうか。こんなもん、紅白じゃねえよって。 ま、とにかく、そういうね、歌は世につれ、世は歌につれって言葉の意味が分かる最後の世代、それが昭和40年代の人間だよ。 だけど、それだけじゃない。アイドル歌手の活躍とか演歌歌手の活躍とか、そういうのはまだこの時代の歌謡曲界の表っ側の一部であって、さらにその下にもう一層があった。それが「ニューミュージック」というジャンル。我々の世代は、紅白には決して出てこない井上陽水とか、ユーミンとか、そういう連中すらも擁していたわけですからね。その豊穣たる世界はどうよ。 ま、その辺のお話はまた後日。
March 9, 2016
コメント(0)
-
ソニー信奉と電波ジェネレーション
昨日、江本勝氏の『水は答えを知っている』という本を読んでいたのですけど、これは聞きしに勝る本でしたね。 大体、冒頭から江本氏は駆っ飛ばしておりまして、「人間はそもそもこの世に誕生する前、受精卵のときは九九%が水です。そして、生れたときは体の九〇%が、成人になると七〇%が水で、おそらく死ぬときになってやっと五〇%を切るのでしょう。すなわち、人間は一生を通じてほとんど水の状態で生きているといってもいいのです。」(14頁)と語り、その帰結として「物質的にみると、人間とは水です。」(15頁)と喝破する。 強引! そうでしたかぁ! 人間とはすなわち水であると! この辺からすでに「アレ?」って感じですけれども、ここからさらに江本氏は水の神秘に突入していきます。 氏によれば、水は人間の言葉とか音楽に反応すると。だから「ありがとう」という紙を貼った瓶に入れた水を凍らせるときれいな結晶ができるのに、「ばかやろう」と書いた紙を貼っておいた瓶に入れた水は、ぐちゃぐちゃな結晶しかできないと。 あ、ちなみに瓶に紙を貼る時は、瓶の中の水に読めるように、ちゃんと裏返して、水の方に表が見えるように貼らないとダメですよ。 で、水は音楽も解するので、ベートーヴェンとかモーツァルトを聴かせると、それぞれの曲調にあった結晶を作るらしい。 それからショパンの「別れの曲」を水に聴かせてみたら、なんと結晶が二つに別れてしまったと。曲のタイトルまで水は理解するらしいんですな。 だけど、そもそもショパンのこの曲にはもともと「別れの曲」なんて名前はついてなくて、どこぞの日本人が勝手にそういう名前を付けたわけですよ。だからショパンの曲を水が聴いて、「これは別れの曲だから」ってんで分裂した結晶を作ったなんてはずがない。 普通はそう思うわけですが、江本氏は違います。「水はすごい! ショパンの曲に『別れの曲』と名前を付けた日本人の心まで汲みとったんだ!」と、感動する。そして、水は人間なり生物の思いを全部汲み取るので、海の水なんか、そこに生きた何十億年分の生命の記憶に満ちているはずだと。 だからね、薬を水に溶かすじゃん? その水を希釈して希釈して、ほとんど薬の分子が残らないほどに希釈したとしても、水は薬の記憶を保持しているので、その水には通常の濃度の薬と同等の薬効が残ると江本さんは豪語しております。ルルドの泉が病人を癒す、なんてのも、この原理によるらしいし。 あ、それから、人の願いだけで水を浄化することも可能で、琵琶湖の水を浄化しようと三百五十人ほどのボランティアで「宇宙の無限の力が凝り凝って、真の大和のみ世が生り成った」と断言したら、琵琶湖の水も澄んでしまったとのこと。 ひゃーーーーー! あ、あと、江本さんは、地球に水があるのは、宇宙から飛んできた水の塊が今もなお日々、地球を潤しているからであって、このままだと地球は水浸しになってしまうかもしれないことを本気で心配なさっています。 ま、この本はそんなことを述べている本でございます。 一言で言って、やばいな。この本はやばい。とはいえ、この本、世界31カ国で180万部が売れたんだけどね。 自己啓発本の言説にはまともなものとそうでないものとありますが、「そうでない」方も、この本あたりが極北であってほしい。そうじゃないと、これ以上、この研究続けていく自信が無くなってくるよーーー。 さてさて、昨日、ラジカセの話をし始めましたので、その続き。 そう、昭和四十年代末に、日本では一大ラジカセブームが起ったのでした。 この時、何がウリだったかというと、まず「ステレオ」っていう部分。それ以前のラジオって、大体「モノラル」でしょ。それが「ステレオ」になった。当然、音の質が全然違う。右の音は右から、左の音は左から聴こえるわけですから。それはスゴイことだった。 それから、スピーカーも、高音用のツィーターと低音用のウーハーに別れていたりして、見た目的にもド迫力。いわゆる「2ウェイ4スピーカーシステム」って奴。でまた、高音・低音、それぞれ別々に調整できるタイプもあったりして、好みの音質に変えられるものもあったりしてね。 そして、なんといってもカセット付っていうね。これが魅力だった。なにせ、ラジオの音声をそのまま録音できるんだもの。ほんとの「エアチェック」時代の到来ですよ。 でまた、録音用のカセットテープがまた、色々あるんだ。 最初の内はそれほど種類も無かったですけど、しばらくしてから「クロムテープ」が、そしてその後さらに「メタルテープ」が出た。「クロムって何? メタルって何??」という素朴な疑問はさておき、とにかく「メタルにすると音質がいいらしい」ってことになって、普段は普通のテープでも、ここぞと言う時にはちょっとお値段高めのメタルテープを奮発する、みたいな。 カセットテープって、もう、我々の世代にとっては本当に素晴らしいものだったのよ。だから、TDKとか日立マクセルとか、ソニーとか、それぞれのメーカーが趣向を凝らしたテレビコマーシャルを打ち出しててね。 特によく覚えているのはたしか加藤和彦が歌ったのだったかなあ、「富士フイルムのカセットに、一杯音楽あれば、後はどうにか、なってゆきます」って言う奴。ほんとにそうだったんだもん。カセットがあれば、後はどうにかなる、っていう時代が確かにあった。今だったら「スマホがあれば・・・」ということになるのだろうけれども。 で、日本中のティーンエイジャーが自室でラジカセをセッティングしてエアチェック準備万端なものだから、特にFM番組は花盛りでね。となると当然、FM雑誌というのも花盛りになる。『FMファン』『週刊FM』『FMレコパル』『FM STATION』等々。懐かしいね。 さてさて、世の中がそんな風になっている中で、私もラジカセ買ってもらって。本当はソニーのが欲しかったのだけど、ちょっと値段が高かった。で、結局、アイワのラジカセを買ったの。妥協して。 そう、この頃ね、音質に関してはさておき、デザイン面ではこの種の製品ではソニーのデザインがダントツでさ。私たちの世代は、ソニーを中心に世界が回っていたわけよ。我々の世代のソニー信奉ってすごいからね。子どもの時から植えつけられているのでなかなか抜けない。 ま、それはともかく、アイワでもいいよ。とにかく自室にラジカセがあるってことが重要だったんだから。今でも思い出すけど、自分の部屋の勉強机の両端にZライトとラジカセがあるってことが、どれだけ幸せなことだったか。部屋の灯りを消し、Zライトだけにして、それでラジカセでFMを聴く、なんてのはさ、ホントに至福の時でしたよ。 大人になると、その程度のことで至福を体験できるってことがなくなって、ホントにつまらないよね・・・。 ところで、私の場合、ラジカセに加えてもう一つ、大きな宝物がこの時期にありました。それはね、「短波ラジオ」。これもまたね、この時期流行ったんだ。 で、私が小学校6年生の時だけど、誕生日だったか、親にねだってついに買ってもらったの。秋葉原まで行ってね。 買ってもらったのはソニー(ついにソニーだよっ!)の「スカイセンサー5900」って奴。これ、めちゃくちゃカッコよくてさ。 短波放送だと、世界中のラジオが聴ける。例えば、当時人気だったのが「ラジオ・オーストラリア」で、夜7時だったかにダイヤルを合わせると、笑いカワセミの声で始まる日本語放送が聴ける。今聴いているのは、オーストラリアで発信された電波なんだ、っていうのが、子どもにとってはロマンでね。番組自体は別に特に面白いものでもなかったんだけど、とにかく、電波が世界を経巡って今、自分の手元に来たというところが何ともいえず楽しかった。 だから、結局、私たちの世代の青春時代の入口って、「電波を通じて世界に開いていた」っていう感覚なんだよね。 ひょっとすると、我々の一回り上、団塊の世代の連中って、もっと生身の世界体験をしていたのかもしれない。だから学生運動とか、デモ参加とか、しちゃうんじゃない? だけど我々の世代は、そこに電波が一つ挟まる。その意味で、「メタ体験」なんですよね、なんでも。テレビ世代ってこともあるけど。 ともかく、そんな感じで、私の小学校高学年時代には、ラジオ&ラジカセがすごく大きな比重を占めていたのでございます。
March 8, 2016
コメント(0)
-
ラジオ・洋楽・ラジカセの時代
紀要の件も片付いてようやく少し本が読めるようになりました。 で、昨日読んでいたのはマーク・ジョイナーの『オレなら3秒で売るね!』と、ジョージ・S・クレイソンの『バビロンの大富豪』。ジョイナーは、ジョー・ヴィターリの弟子。ヴィターリってのは『ザ・キー』の著者として有名な人。 ヴィターリは「引寄せ」の人ですから、その弟子が「引寄せ」をマーケティングに応用するとどうなるのかと思ってジョイナーの本を読んだのですけど、これはもろにマーケティングの話だったので、ちょっと期待外れ。だけど、この本を読んでいたら、ドミノ・ピザが始めたという「30分以内にお届け出来なかったら、代金は頂きません」という宅配ピザのマーケティングがいかにすごいか、というのがよく分かりました。 で、もう一方のクレイソンの『バビロンの大富豪』ですが、これは1921年出版の本で、100年近いベストセラーでございます。 で、これは大富豪になるにはどうしたらいいかということを、古代バビロニアの大富豪の経験談という形で描いた、小説仕立ての自己啓発本。 だけど、そのキモは何かというと、「1.労働を友と思い、一生懸命に働くこと」、「2.稼いだお金の十分の1を使わずに取っておくこと」、「3.そうして貯まってきたお金を、安全な投資によって増やすこと」の3点。つまり、しごくまともな、当たり前のことを言っているわけで、富の蓄積に王道なし、コツコツやれ、と、そういうことを言っている本でございました。 ま、そうだよね。 さて、昨日まで、私が小学校中学年くらいに観ていたテレビ番組などの話をしてきましたが、そろそろ高学年くらいの話に移ろうかなと。 私が小学校5年生になった頃、私にとってにわかにブームとなったのが、「ラジオ」でございました。 どうして急にラジオに興味を持ったのか、その辺はよく覚えていないのですが、とにかく、この世には「電波」っていう面白いものがあって、ラジオがあればそれを受信できるし、それは非常に面白いことだ、っていうことに、何故か急に気が付いてしまったんですな。 もちろん、父には愛用のラジオがありましたけれど、そうなってくると自分用のラジオが欲しくて仕方がない。それで、まずは携帯用の、ごく安いラジオ、たしか1000円くらいで買えるものだったと思いますが、そういうラジオをゲット。それで聴き始めた。 で、そこで出会ったのが、いわゆる「洋楽」って奴。 私がラジオにかじりつき始めた時、洋楽で何が流行っていたかっつーと、まずスタイリスティックスね。「You Make Me Feel Brand New」とか「Can't Give You Anything」とか。それからキャプテン&テニール。「Love Will Keep Us Together」ですよ。この辺がバンバン掛かっていた。 今思い出してみると、この頃って、「洋楽」人気は大したもので、洋楽だけの「電リク」(うわ、久しぶりに使ったわ、この言葉!)番組とかありましたからね。 それで、洋楽にすっかりはまり出した頃、1975年だったかなあ、ポール・マッカートニー&ウィングスが「あの娘におせっかい」(すっごくダサい邦題だけど、原題は「Listen to What the Man Said」)が大ヒット。私はこれに完全にやられてしまった。この曲を聴いて以降、もう洋楽以外聞くまいと。 だけど、これもいわば象徴的なことでありまして、ウィングスがヒットしていたということは、つまり、ビートルズはもう解散しているわけ。私はビートルズによって小学校1年生の時に洋楽の洗礼を受けてはいるのですが、完全にはまったのはビートルズ後、ということになる。私たちの世代は、その意味で「ビートルズに間に合わなかった世代」と定義することもできましょう。 ま、とにかく、この頃から洋楽とラジオの虜となった私、洋楽の電リク番組を散々聞きましたっけ。 たとえば「土井まさるのポップス・ナンバーワン」とかね。FMだと、「ダイアトーン・ポップス・ベスト10」とか。 そう、それで、先にも言いましたが、この頃、日本では結構な洋楽ブームで、例えばダニエル・ブーンの「ビューティフル・サンデー」とか、めちゃくちゃ流行っていた。田中星児さんがカバーしたりして。それから、あれですよ、「ベイシティー・ローラーズ」の「サタデー・ナイト」とか。 もっとも私は「サタデー・ナイト」的なものは割と軽蔑していて、「何コレ? クイーンの『キラー・クイーン』の方がよっぽどいいじゃん」みたいに思っていた。 小学生にして、本質を見抜いていたのよね~。 そして、洋楽聞きたさに、私は米軍放送FENの深みにはまっていくのでございます。土曜日の午後にやっていたケーシー・ケイサムの「全米トップ40」ですよ。土曜で午前中で学校が終って、急いで家に帰って、FENで洋楽を聴く楽しみったら、なかったね。 ところで、こうやって本格的に洋楽を聴き出すと、さすがに携帯ラジオじゃどうしようもなくなってくる。我が家の音楽環境改善時代の到来でございます。 まずね、ついに我が家にステレオがやってきた。 前に昭和40年代世代にとって「ピアノ」は文化生活の象徴だった、的なことを書きましたが、昭和50年が近づくにつれて、次の第一歩として「ステレオ」がやってくる。 で、この方面、凝り出すと大変で、例えば「サンスイ」がいいんだとか、「マランツ」がどうだとか、色々あるのでしょうが、その辺、まだ我が家はそこまでのレベルではなくて、結局、ソニーのステレオセットを買っちゃった。でも、大きさから言えば堂々たるもので、それが我が家のピアノの隣に鎮座した時には、「ついに、こういうことになったか」と言う感慨がありましたねえ。 それで、ステレオを買った以上、レコードも買わなくちゃならないってわけで、その選択は私と姉に任されたと。 で、すっごく恥ずかしいのですが、我が家で最初に買ったLPレコードが、ポール・モーリアのベスト盤ですよ。今考えると、「なぜ?」って思うのですけど、当時、ポール・モーリアのイージー・リスニング系の曲って流行っていたのよ。「エーゲ海の真珠」とかそう言う奴。 ま、とにかくね、ステレオセットが家にやってきたというのは、一つの時代の象徴的出来事ではありましたね。 とはいえ、当時LPは高かったからね、おいそれとは買えないし、やはり、我ら子ども世代の音楽生活の基本は「エアチェック」ですよ。(「エアチェック」という言葉も久しぶりに使ったなあ) でまた、この頃なんだ、「ラジカセ」が登場してくるのが。「カセット文化」ですよ。 私が小学生2年の時、音楽の授業で、自分の歌声を録音する、というのがあって、その時に使ったのはオープンリールデッキでしたし、記念に頂いたのもオープンリールのテープだった。私の父は英語の先生でしたから、家にオープンリール・デッキがありましたからね。 だから、カセット・テープなるものが登場してきたのは、私の小学校時代の後半なわけ。まあ、びっくりしましたよ、こんな小さくて持ち運びし易いものに録音できるんだ、と知った時には。 で、そのカセットとラジオが合体した「ラジカセ」なるものが登場してきた時、まさにラジオ・ブーム真っ只中だった私にとって垂涎の的となったことは言うまでもないでしょう。 だけど、もうだいぶ長くなってしまいましたので、そんなラジカセのお話はまた後日。
March 7, 2016
コメント(0)
-
刑事コロンボとプロレス中継
なんとなくナンが食べたくなって、今日のお昼は家の近くにある「ニュー・バンチャ」というカレーのお店に行ってきました。カレー2種、マトンカレーとチキンチーズカレーなるものを食べたのですが、美味。そして念願のナンは「チーズナン」というのを注文したところ、これまた美味。おいしかったです。でも、チーズ入りのナンはボリュームがあって、全部食べたらお腹いっぱいになり過ぎちゃった。 で、帰りには本屋さんに寄ってあれこれ立ち読みしていたのですけれども、文房具も売っているこの本屋さんの入口のところに5冊パックのノートが山積みされていて。 いやあ、中学生とか高校生の頃、春休みにこの種の5冊パックノートって買ったよなあ! なんか新学年に備える的な心構えからか、つい買っちゃうんですよね。そんなことを思い出して、ちょっとテンション上っちゃった。 真新しいノートって、なんか、いいですよね! さてさて、昨日、子どもの頃に観ていた刑事ものの話を書きましたが、一つ忘れていました。『刑事コロンボ』のこと。1972年の大晦日から、日本での放映が始まったのでしたっけ。 これ、結構鳴り物入りで始まった記憶があって、そんなに面白いの~? ほんとに~? 的に、半信半疑で観始めたら、鳴り物以上に面白かったっていう。だから余計インパクトがあった。 第一、通常の刑事ものとは全く逆に、最初にテレビを観ているお茶の間の人たちの前で犯罪が行われ、それを後からコロンボが突きとめていくという、その逆転の発想がすごかった。それからこのドラマの場合、犯罪者がセレブであることが多く、プール付の大邸宅とか、リッチなクルマとか、そんなのを持っている知的な人たちの犯罪というところも面白かった。今だってそうですけど、当時ではなおさら、自分たちの住宅事情とドラマの中のセレブ犯罪者たちの生活ぶりのレベルが違い過ぎて、ひゃーって感じがした。 だからこそ、そんなセレブとは好対照の、よれよれレインコートのコロンボがネチっこく捜査していって、最後には真相を突き止めるところが、庶民の側からすると爽快なところがあったのでしょうな。そしてもちろんコロンボのキャラクターと、「うちのかみさんが・・・」、あるいは「あ、それからもう一つ・・・」という口癖の面白さ、そして小池朝雄さんの吹き替えの見事さもあったしね。あと、テーマ音楽も良かったんだよね~。あれ、ヘンリー・マンシーニでしょ。超一流の映画音楽の作り手ですよ。 それから、これは日本ではコロンボほど称揚されていませんが、『刑事コロンボ』のシリーズが終った後に、その後釜として始まった『警部マクロード』、これもね、私は案外好きだった。西部のカウボーイみたいなマクロードが、どういうわけかNY市警に配属されることになり、カウボーイ的に破天荒な手法で犯人を追いつめるもので、上司のクリフォード部長がいつも苦い顔、という奴。これもマクロード演じるデニス・ウィーヴァーの声を宍戸錠さんが吹き替えて、ちょっと上ずったようなところがマクロードっぽくてすごく良かった。これもテーマソングがヘンリー・マンシーニだったような気がします。 この頃NHKが放送していた洋モノドラマ、例えば『大草原の小さな家』とかもそうだけど、質が良かったねえ。 ところで、1973年、私が小学校の4年生頃と言いますと、私の個人的な年代記からすると、「プロレス時代の幕開け」なんですよね。 今、プロレスって社会的な認知が低いような気がしますけれども、ジャイアント馬場とアントニオ猪木が活躍していた1970年代の始め頃なんて、プロレスは全盛期ですよ。 っていうか、それ以前の力道山の時代こそ全盛期だって説もあるでしょうけれども、力道山と街頭テレビの時代まで行っちゃうと、さすがに私の世代ではカバーできない。私の世代だと、やはり馬場と猪木の時代という感じがする。 で、プロレス中継なんて、花形番組だからね。確か馬場の全日本プロレスの中継が土曜の夜8時、猪木の新日本プロレスの中継が金曜の夜8時だったのではないかと、どっちにしても週末のゴールデンタイムど真ん中でしょ。それから、この二つと比べるとちょっと地味だけど、国際プロレスってのもあって、これは月曜の放送だったかな。 でまた、どういうわけで私がプロレスに夢中になったのか、きっかけは覚えていないですけれども、お正月とかに父方の祖父の家に遊びに行った時に、祖父が割と好きで、よく中継をテレビで見ていたからかなと。それで興味を持った私は、俄然、プロレスの本を数冊入手して、熱心に研究し始めた。 ま、ここに既に私の性格が表れております。格闘技好きの性格と、まず何はともあれ関連書を読み漁ることから始めるという辺りがね。今の私そのままじゃん。三つ子の魂なんとやらだ。 で、研究を始めてたちどころに世界の有名なレスラーや、そのレスラーの得意技なんかを覚えてしまい、予習は完了。毎週のプロレス中継が楽しみで、楽しみで。 でね、当時のプロレスがいい時代だったのよ。キャラの濃い人たちばっかりで。 例えば長身のロシアからの刺客、モンスター・ロシモフとかね。後のアンドレ・ザ・ジャイアントですよ。カナダの怪力男、カナディアン・バックブレーカーの使い手ブルーノ・サンマルチノとか。重量級で言えばヘイスタック・カルホーンとか。リンゴを握りつぶす握力を持つフリッツ・フォン・エリック、キチン・シンクのジン・キニスキー、全然ハンサムじゃないハンサム・ハリー・レイス、試合に出れば必ず流血の惨事になる噛み付き王フレッド・ブラッシー、回転トウホールドで名高いドリーム・ファンク・ジュニア、エアプレーン・スピンなる大技を得意としながら小技も冴えるドン・レオ・ジョナサンも好きだった。頭突きで有名なボボ・ブラジルとか、大木金太郎とかも居たなあ。 覆面レスラーも人気で、足四の字固めのザ・デストロイヤー、千の顔を持つ男ミル・マスカラスとかね。マスカラスの空中殺法、フライング・クロス・チョップとかカッコ良かった。ジグソーの「スカイハイ」が入場のテーマソングで。あと、包帯だらけで登場するザ・マミーとか、ケンドー・ナガサキなんかも面白い存在でね。ケンドー・ナガサキって、日本人の方じゃなくて、イギリス人の方ですよ。 日本の方だと、馬場、猪木はもちろん、ヤマハブラザーズとかね。覚えています? 山本小鉄と星野勘太郎ですよ。小兵ながらメキシコレスラーのような空中殺法で、回転エビ固めとかやっちゃうの。あと、坂口征二とかね。国際プロレスの方には、ちょっと毛色の変わったのがいて、サンダー杉山とかグレート草津とかストロング小林とかラッシャー木村とか。あと、国際プロレスの方には、スープレックスという技の生みの親たるビル・ロビンソンがよく来日していたんじゃなかったかな。 で、こういうのを観てエキサイトした私は、自分でも体を鍛えることに熱中。親にねだってエキスパンダーを買ってもらったりして。だけど、当時はどんなに食べてもガリガリのやせっぽちだった私に、筋肉がつく様子は一向になく。 それで、今あるかどうかわからないのだけれど、当時、「ブルワーカー」っていうのが話題でね。少年漫画雑誌とかの広告欄に必ず載っているの。まあ、トレーニング機器なんですけど、「キミもブルワーカーで、筋骨隆々になろう!」的なキャッチコピーが躍っていた。これさえあれば、自分も将来、プロレスラーになれるんじゃないかと思ってかなり欲しかったのですが、たしか1万円位するもので、さすがに親にはねだれなかった。でも、私の世代の男は、少なくとも一度は「ブルワーカー」を欲しがった時があると思います。 で、とにかくプロレスに夢中だった私は、自分でチャンピオンベルトを工作して作って、友人とプロレスごっこをしては、このベルトを守ったり、取られたりしたものでございますよ。 ま、私のプロレス時代は2年くらい続いたのかな? でも、その後プロレスは私の好むところとは別な方向に進化していくんですな。 まず最初の兆候は、「嫌な反則ブーム」ね。アブドラ・ザ・ブッチャーとか、タイガー・ジェット・シンなんかが登場してきて、可愛げのない反則をし、敵味方とも大流血の惨事、みたいになっちゃうのが流行るようになってくる。確かに昔から反則はプロレスにつきものでしたけど、昔の反則は、もっとお茶目なものでね、ブッチャーみたいに「こいつほんとに何するか分からない」というようなのはなかった。 で、こういうのヤだな、と思っているうちに、今度は、「ガチンコ・プロレス」の時代がやってくる。確かアントニオ猪木の打ち出した方向性だと思うのですが、ショー・アップしたのではない、真剣勝負のプロレスみたいなのが求められるようになってくるわけ。「格闘技の中で一番強いのは何か、白黒つけよう」的な方向性といいますか。猪木がモハメッド・アリと対戦して、床に寝転がってばかりいた試合なんかも、この方向性の必然ですな。 だから、スタン・ハンセンとか、その辺りが出てきた頃はもう、なんかほとんど本気の喧嘩じゃん、みたいな感じがして見ていられなかった。だから、そこから先のレスラーたちのことは私はまったく興味がない。ハルク・ホーガンとか長州力とか藤波辰爾とか、橋本真也とか、そういう人気レスラーのこともほとんど知らない。それから、私よりも一世代後の連中が夢中になった「ビューティー・ペア」的な女子プロレスについても、私はほとんど知らない。 そう言う意味で、私にとってのプロレスってのは、ある意味、ジャイアント馬場に尽きるわけ。馬場さんが足を上げて待っているところに、ちゃーんとロープから跳ね返ってきた相手選手がぶつかっていって、まともに16文キックをくらってくれるような、そしてあの効いているのかどうなのかよくわからない「ヤシの実割」なんて技でギブアップしてくれるような、そういう古き良きプロレスが好きだったんです。 そしてそういう私の中のプロレス・ブームが終った時、私の中でまた別なブームが始まって行く。ま、その辺についてはまた後日ということで。
March 6, 2016
コメント(2)
-
『俺たちの勲章』など
今日は紀要原稿を印刷に回すため、担当の出版社の方と打ち合わせがあり、いつものように竹の山にある「イースト・パラダイス」というカフェで落ち合う・・・予定だったのですが、なんとイースト・パラダイス閉店。しかも昨年10月に。 え゛ーーーー。うそ~ん。結構お客さん入ってたと思うけど。そうなの? 夜遅くまでやっているのも便利だったし、ここのフレンチ・トースト好きだったのに~。私が好きな店って、たいてい潰れるんだよなあ。なんで? で、仕方なく急遽お隣のコメダへ。打合わせは無事終了しましたが、イーパラ潰れたのは残念だなあ。 さてさて、昨日のつづきですけど、1970年代前半から半ばのテレビ番組というと、もう一つ、「青春もの」ってのがありましたね。 そして「青春もの」と言えば、やっぱり「おれは男だ!」ですな。青春の元祖・森田健作ですよ。早瀬久美演じる「吉川操」、っていうか「吉川くーん」との掛け合いが良かった。高校生の男子が同じクラスの女子のことを「さん」ではなく「くん」づけで呼ぶというところが新鮮で。 だけど、これも強い女に対して押され気味な男たちのドラマで、その押され気味なのを善しとしない男一匹が頑張るという、そういうタイプのドラマですな。 そしてこの辺りから「学園もの」ってのが色々出てくる。昨日言及した『おくさまは18才』も学園ものですが、やっぱり決定的だったのは『飛び出せ! 青春』ですな。こちらは「レッツ・ビギン」が極め台詞の村野武範さんが主演で。 この系統では、若い新任教師と不良の多い生徒たちとのぶつかり合いという側面と同時に、新任の先生と古株の教頭先生(およびその腰巾着)との攻防も見せ場で、そういう場合の教頭先生って大抵穂積隆信、腰巾着が柳生博だという。 とにかく、海岸をマラソン、夕日に向かって青春を叫ぶというパターンは、この時代からですよ。我々のものだ。 そして刑事もの。『太陽にほえろ!』。 だけど、私はこのドラマを最初から見ていたわけではないんですな。最初は、それほど人気なかったんじゃないですかね。ただ、「マカロニ刑事」ことショーケンが殉職した辺りから段々人気が出てきて、「ジーパン刑事」こと松田優作が出てきた頃から私も見始めたのではなかったかと。 で、例の「なんじゃこりゃー!」でジーパンが殉職する頃にはもう国民的番組ですよ。私もテキサス刑事(勝野洋)の時代くらいまではよく見ていましたからね。その後、ボン、スコッチ、ロッキーくらいまでは見たり見なかったりで、その先はちょっと飽きた、みたいな。 でも、『太陽にほえろ!』は、石原裕次郎のボスをはじめ、七曲署の面々がそれぞれ個性的で良かったし、聞き込みをするシーンなんかもリアリティがあってよかった。音楽の使い方も斬新だったしね。聞き込みシーン、悪い奴が悪いことするシーン、犯罪の実態が分かったシーン、逮捕シーン、とか、それぞれのシーンごとにテーマ音楽が決まっていたのなんて、このドラマからじゃない? ところで、私にとって印象的な刑事ものと言いますと、実はもう一つ、『俺たちの勲章』が忘れられないんですわ。 松田優作と中村雅俊、両方とも背が高くてカッコいいんだけど、松田優作の方が暗くてやばい感じがし、中村雅俊の方がまっとうな正義漢という、そんな二人の若い刑事の物語。これは良かった。 でまた、特によく覚えているのが、水谷豊が孤独な殺し屋を演じた回。当時の水谷豊って、孤独なチンピラみたいな役をさせるとものすごくリアリティがあってね。それは、『傷だらけの天使』でショーケンの子分の「アキラ」役にも通じるんだけど、寂しくて寂しくてしょうがないから、自分のことをかまってくれる「アニキ」とか「親分」に着いて行っちゃうタイプの役柄をやる時の水谷豊は素晴らしかった。 とにかく、この時代の松田優作も中村雅俊も、売出し急上昇って感じでしたねえ。 で、ここから中村雅俊は『俺たちの旅』で更に売り出していくんじゃなかったかしら。そう言えば、『おれは男だ!』の森田健作もそうだけど、『俺たちの旅』の中村雅俊も、主演ドラマの主題歌を歌いましたよね。そういうのが流行る時代だったんですなあ。 でまた、『俺たちの旅』は、今、出演したメンツを眺めると、まあ、豪華なもんで。 これは大学を卒業したはいいけれど、そこから先、どうするか、って話で、登場人物の中でもちゃんと就職するのもいれば、まだ現実になじめなくてぶらぶらしている奴もいる。ぶらぶらしながらバイトしたり、自分でジーパン屋を開いてみたり、色々試行錯誤するのですが、そういうのを現実逃避だとか就職した先輩に叱られて殴り合いの喧嘩をするとか、ま、そういうタイプの青春群像ですな。 結局、『俺たちの旅』でそういうことをやっている連中というのは、団塊の世代、学生運動なんかやっていた世代の人たちで、私よりも一回りほど年上なわけですよ。だから当時の私は、私よりも一回り年上のお兄さんたちの青春の蹉跌を、小学生として見つめていたと。ああ、大学生になるっていうのはこういうことをすることなんだ、そしてその大学を卒業した後はこういう風になるってことなんだ、というのを、小学生の時に見て学んでいたと。 でまた、当時はフォークソングっぽい歌とかも色々あって、例えば「南こうせつとかぐや姫」が歌った「神田川」とかね。これなんか、やっぱり当時の世相を反映していたわけで、大学生とかになると、同棲とかしちゃうんだ、みたいな。そういう、ちょっとこう、淫靡なところもあるような、ないような、そういうことを、自分も大学生になったらしちゃうのかしら、みたいな、そういうことを思いながら、小学生の私はこの手の青春ドラマを観ていたという。 で、中村雅俊なんかは、そういうドラマの中で、「ジーパンに下駄」というスタイルを貫くわけですけれども、結局、私がジーパンに下駄で大学に通うことは、なかったですなあ。12年くらいの時間差で追っかけるとなると、時代にはとても追いつけないわけですわ。同棲もしなかったしね。 でも、とにかく、そういうテレビドラマを観ながら、私は小学生も上級生になっていくわけです。
March 5, 2016
コメント(0)
-
『パパと呼ばないで』の時代
毎年私が単独で担当しているうちの科の紀要ですが、ようやく今日、校了となり、明日入稿の運びとなりました。同僚の論文原稿を編集しつつ、自分でも論文を書くという、いわば綱渡り的な作業だったわけですが、それもようやく終了。一仕事終わったって感じですね。意外に時間が掛かってしまいましたが。 また、ちょうどその仕事が終った頃、今年度のゼミ生3人が研究室に遊びに来てくれました。ガールズは昨日、北欧旅行から帰ってきたということでお土産持参。北欧なら、趣味のいい置物があるだろうから、そういうのがあったらお土産に買ってきてと頼んでおいたのですけれども、私の好み通りの可愛い、そして色使いのいい水鳥(?)の妖精みたいなのを買ってきてくれて感謝感激。土産話を聴いているうちに、私も北欧に行ってみたくなっちゃった。 一方、白一点のキング君は、アカペラ・サークル部活の追いコンが大感激だったらしく、号泣したとのこと。帰宅部だった私の学生時代とはまた異なる青春を過ごしたようで、それも良かった。彼は作家志望ですから、卒業式まで頑張って書き進めるとのこと。 彼らと次に会うのは、卒業式かな? そう考えると今から少し寂しいですな・・・。 さて、先日は私が小学校低学年くらいの時によく食べていたお菓子の話を書きましたが、今日はその頃観ていたテレビの話を一つ。 1972年とか1973年頃に観ていたテレビと言いますと、何と言っても思い出すのは『パパと呼ばないで』なんですよね。石立鉄夫と、そして天才子役時代の杉田かおるさんが出ていた奴。 特に杉田かおるさんと私はほぼ同年代で、その同年代の子がテレビで活躍していることに妙に嫉妬したというか。ちなみに私は皆川おさむさんと同い年で、「黒ネコのタンゴ」が流行った時もちょっと嫉妬したことを覚えております。子ども心にライバル心ってのがあるんですよね。 しかしね、杉田かおるさんってのはね、あれは天才ですよ。『パパと呼ばないで』の「チー坊」役の杉田さんは、ほんとに魅力がありましたから。今時の子役なんて束になってもかなわないんじゃない? で、ドラマも良かったんだよね。死んだ姉の子であるチー坊を引き取ることになった「右京さん」こと石立さんが、下宿した先に松尾嘉代さん演じる「園ちゃん」という娘さんが居て、ことある毎に右京さんとぶつかって喧嘩するんだけど、ドラマの進行と共にこの二人の関係が少しずつ近づいていって最後にはチー坊も含めて右京さん、園ちゃん、チー坊の三人が家族として一つに収まるって話でね。 この時代、こういう「一つ屋根の下で暮しているうちに・・・」っていう話はテレビドラマの設定としてよくあったのだけど、それは要するに「下宿」というシステムが普通にあったからなんですよね、この時代。今、アパートを借りるというのはあるけれど、他所様の家に下宿するということってないでしょ。でも昭和にはあった。だからこそ生まれる設定なわけよ。 平成の今だと「シェアハウス」なんてものもありますが、昔は田舎から上京する=下宿だからね。その時点でシェアハウスですよ。 それからさ、『パパと呼ばないで』もそうですけど、この時代のテレビドラマって、1年続くのが普通で、もっと長く続くドラマなんていくらでもあった。1年4クールとか、そういう忙しないアレじゃないわけ。だから、我々お茶の間でテレビドラマを観ている側も、右京さんと園ちゃんとチー坊が、少しずつ、1年かけて互いに馴染んでいくのをゆーーーっくり見守っていられた。彼らと春夏秋冬を一緒に過ごせたわけですよ。そののんびりした感じが、良かったんだよね~。 それにしても、この時代の石立鉄夫のモテぶりはどうよ。『パパと呼ばないで』の前に岡崎友紀と組んだ『おくさまは18才』も面白かったしね。決してハンサムではないのだけれど、コミカルなシチュエーション・コメディをやらせたらピカイチだった。 で、また『パパと呼ばないで』の後の『雑居時代』も、いいドラマだったんだよね。これにも杉田かおるさんが「あまり」ちゃん役で出ていて。石立さんは「十一」という名前のカメラマン役で、トランプになぞらえて「ジャックさん」とも呼ばれるのだけど、このドラマのヒロイン役が若き日の大原麗子だったんだよね。十一の写真道の師匠が川崎敬三さんで、山が好きで山ばかり撮っている気の弱いカメラマン役を好演していたのも懐かしい。 『パパと呼ばないで』の園ちゃんも気の強い女でしたが、『雑居時代』となると、冨士真奈美さんを筆頭に、大原麗子、川口晶、山口いずみ、そしてあまりちゃんまでの5姉妹が石立さんを圧倒する、というシチュエーションがドラマの見せ場なんですけど、この時代、「強い女」ってのが「下宿」と並ぶキーワードだったのかもね。男は下宿している時点でそもそも立場が弱いわけで、その立場の弱い男が強い女に押されまくるという、その面白さがこの時代のテレビを面白くしていたのかもしれません。 ところで、この時代のテレビドラマは、まずは時代劇。そしてファミリー向けのコメディがあって、もう一つの柱が刑事もの。 刑事ものでは『7人の刑事』ってのが人気でしたけど、これはね、私には少し時代がずれていて、あまり覚えていないの。私にとって刑事ものといえば、やはり『キイハンター』からですね。もっとも、これも子供向けのものではなかったし、子どもが見る時間帯のものではなかったので、内容についてはあまり覚えていない。 その意味で、やはり私の世代の刑事ものといえば、『太陽にほえろ!』なんですな。 だけど、その話をし出すとまた長くなるので、その辺りの話はまた後日。
March 4, 2016
コメント(0)
-
梅見
午前中から会議。 だけど、今日は久し振りに暖かい、春らしい日となったので、お昼を食べに出がてら、ちょっと足を延ばして同僚3人と知多の佐布里に梅を見にいくことに。 行ってみたらちょうど満開で。香しい梅の香りが漂って、食後の散歩をするにはちょうどよい気候でございました。 もう、うちの大学もあちこちギスギスしてますからね。こんな時に梅見をしようなんて挙に出る風流さが残っているだけ、さすがうちの科だなと。そのくらいの心の余裕がなければ、学問なんかできまへん。 で、仕事帰りには道場で一汗。 三好の道場は改修工事が終了して、やたらに明るくなり、畳も一新。目にもまぶしい位。そんな新しい畳(といってもイグサの畳じゃないけどね)の上で気分よく稽古。今日の稽古のポイントは、ある部分に一定の圧をかけながら、そこは放っておいて、別な箇所を動かすという意識で技を掛けるというもの。と、口で言っても何のことやら、という感じでしょうが、人間の身体の生理学的な反応を逆手に取り、それを騙すような術理というのは面白いものでね。 さて、明日はそろそろ紀要原稿の校了へ向けて最後の作業。頑張ります。
March 3, 2016
コメント(4)
-
『オデッセイ』を観た
映画ネタ連続ですけれども、マット・デイモン主演の『オデッセイ』を観てきました。以下、ネタバレ注意です。 マット・デイモンと他の5人のクルーは火星でなんらかのミッションをしていたのですが、そこで嵐に遭遇し、急遽脱出せざるをえないということになる。で、急いで宇宙船に乗り込もうとするのですが、嵐で飛んできたアンテナに直撃され、デイモン演じるワトニーが吹っ飛ばされてしまう。もちろん仲間は彼を助けようとするのですが、猛烈な嵐でワトニーの姿は目視で確認できず、宇宙船も倒壊の危機に。仕方なく船長の判断でワトニーは死んだものとし、5人で火星から脱出してしまう。 ところが、ワトニーは生きていたんですな。 で、彼は火星基地に避難するものの、食料も水も酸素も限りがある。しかも次の火星ミッションは4年先。このままではいずれ死ぬしかない。 しかし、ワトニーは科学者・植物学者としての知識を総動員して、基地にあるものを利用して科学反応で水や酸素を作り、ジャガイモを栽培し、なんとか生き延びようとするわけ。 で、やがて地球との交信方法も見つけ出し、自分がまだ生きていることが地球にも伝わると。 で、大騒ぎになった地球では、彼を救出する方法が案出されるのですが、急ごしらえの支援物資運搬ロケットは発射直後に爆発してしまい、残された手段は、既に地球に近づいていたワトニーの同僚5人の乗った宇宙船をもう一度火星に向かわせるしかないということになる。 で、途中で中国のロケットから支援物資なども受け取るなど、ことはアメリカのみならず世界中の注目の的となるわけですが、まだ問題は山積み。 火星に向かっている宇宙船には着陸用のロケットがないので、火星の別なベースに残っているロケットを使用しなければならない。それには、ワトニーに数千キロもの移動を要請しなければならないし、仮にそのロケットで宇宙空間まで来たとしても、それを無事、宇宙船が回収できるかどうかはやってみなければわからない。 さて、ワトニーは何カ月もかけて別なベースまで無事移動し、ロケットを稼働させられるのか? そして宇宙船は彼を無事回収できるのか? ・・・ってな話。 宇宙でのサバイバルものとしては割と最近『ゼロ・グラヴィティ』ってのがありましたし、もうちょい前には『アポロ13』がありましたが、今回はワトニーが火星でサバイバルする、その部分をじっくり描くというところに焦点が当てられていて、孤独な状況の中、絶対に生還してやるという目標を頼りに如何に生きていくかということを、ワトニーの身に自己投影しながら見られるのが良かった。つまり、危機的状況に自己投影するのではなく、一人の人物に自己投影できるところが良かったかなと。 で、点数をつけるとするならば・・・・ 「74点」! 合格。ま、私はマット・デイモンに甘いところがありますけどね。 ところで、これは映画とは関係が無い話かも知れませんが、この映画観ていると、如何にハリウッドが人種問題とか女性問題とか政治問題に神経過敏か、ということがヒシヒシと感じられる。 NASAを描く時も必ずいいポジションに女性や黒人をつけるし、救出ミッションの最終案を考案したのも若い黒人青年という設定。重要な役どころであるロケットのエンジニアはアジア系のおデブさんが演じていたし、宇宙船の船長も女性。あ、それから宇宙船スタッフにはメキシコ系のお兄さんも。そして、救出ミッションに中国が全面バックアップという筋書きには中国(アジア)に対する配慮が。 そういうのがあまり見え見えなので、なんだか鼻白むというか。不自然ですらあるっていうか。 先日のアカデミー賞の際、2年連続で黒人のノミネート者がいないじゃないかってんで色々取沙汰され、それに対応して授賞式でも気の毒なくらい黒人に対する配慮がなされていましたが、私が思うに、今の時点でもうやり過ぎなくらい配慮しているのに、これ以上配慮されたらたまらんなと。「アカデミー賞にノミネートする際は一定の割合で黒人俳優を混ぜること。何年かに一度はアジア人俳優も混ぜよ」なんて暗黙のルールとかできたらどうなのよ。そんなアファーマティヴ条項でノミネートされた黒人俳優は嬉しいの? スパイク・リーよ。四の五の言ってないで、自分でいい映画作って、誰の目からもあんたが一番と言われて監督賞・作品賞・主演/助演/俳優/女優賞獲りなさい。
March 2, 2016
コメント(0)
-
『博士と彼女のセオリー』を観た
WOWOWが今、アカデミー賞特集をやっていて、昨年の受賞作をばんばん放映してくれるもんで、ロードショーの時に観そこなっていたこの作品を観てしまいました。ネタバレ注意ということで。 といってもストーリー的にはそんな大したことはなくて、例のALSの天才物理学者スティーヴン・ホーキング博士の人生をドラマ化したというもの。 若き日の博士は、ケンブリッジ大学の博士課程で頭角を現し始めるのですけれども、その時点でALSの症状が出始め、余命2年と診断されてしまう。で、もちろん博士は絶望するわけですが、当時付き合い始めていたジェーンという女の子が博士を励まし、たとえ余命2年でもいいわ、ってな感じで二人は結婚。で、子ども3人に恵まれるのですが、やはり身体の自由がどんどん利かなくなっていく。 で、子育てと博士の世話で手一杯になってしまったジェーンは、ちょっとヒステリックになりがちで、それで少しでも気分転換になればってことで、母親に勧められて町の聖歌隊に入ってみた。 ところがこれが運命のいたずらというのか、そこでジェーンは聖歌隊の指導者だったジョナサンと恋に落ちてしまう。で、博士もそれに気付きながら、ジェーンの辛さも理解してその状況を受け入れる。 だけど、結局、世間体もあって、ジェーンは泣く泣くその男性と別れるんですな。 ところが、そのうちに今度は博士の方が、新しい介護士として博士の面倒を見ることになったエレインという女性と恋に落ちてしまうと。 そんなこんなで博士とジェーンは別れることになるわけ。 だけど、まあ、それも仕方ないことだったのかなと。人生予測不能だからね・・・。 ・・・みたいな話。 筋書きだけ書くと、何だソレ?、って感じの映画ですな。 実際、この映画、そんなに面白くないのよ。点をつけるとしたら、「53点」くらい。不合格なので、教授のおすすめ!は、なーしーよ。 ただ、ホーキング博士を演じたエディ・レッドメインがあまりにも迫真演技で、本物のホーキング博士みたい。そこはマジでお見事。 見どころとしてはそこだけですね。 それにしてもハリウッドってすごいなと思うのは、実在の人物を俳優が演じる場合、ほんとにその人になりきる人材を連れてくるじゃない。たとえば『レイ』でレイ・チャールズを演じたジェイミー・フォックスとか。『ジェームズ・ブラウン 最高の魂を持つ男』でJBを演じたチャドウィック・ボーズマンとか、『マルコムX』でマルコムXを演じたデンゼル・ワシントンとか、『カポーティ』でカポーティを演じたフィリップ・シーモア・ホフマンとか。もう、本物以上に本物っぽいもんね やっぱり、その辺は、層の厚さって奴ですかねえ・・・。 そこへ行くと日本はどうだろう。実在の人物を、本物以上に本物っぽく演じた例ってどのくらいあるのかしら? あんまりないような気がする。 ・・・・・ あ! 一つ思いついた! 山下清役の芦屋雁之助だ! 「ぼ、ぼ、僕は、おにぎりが好きなんだな」って奴。 それだけかいっ!
March 1, 2016
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1